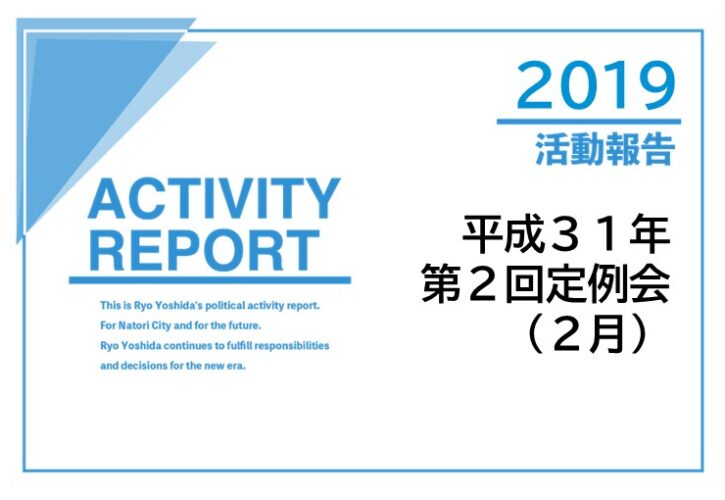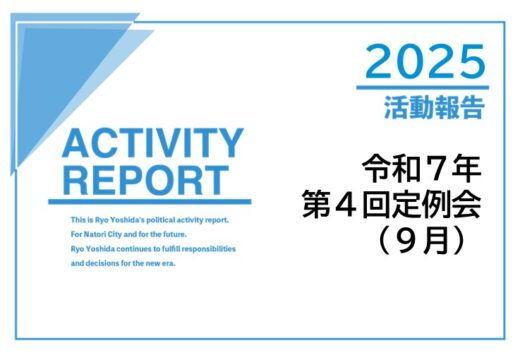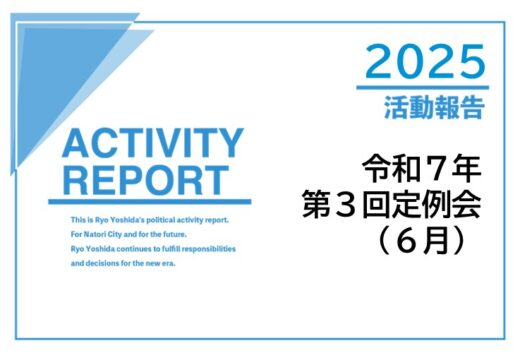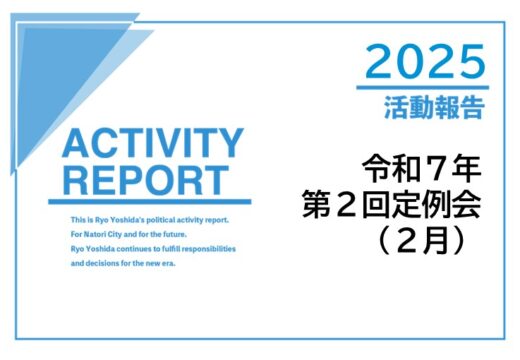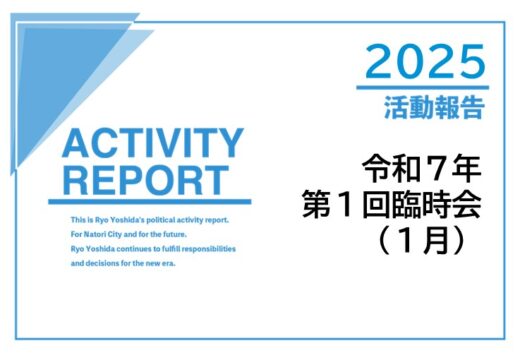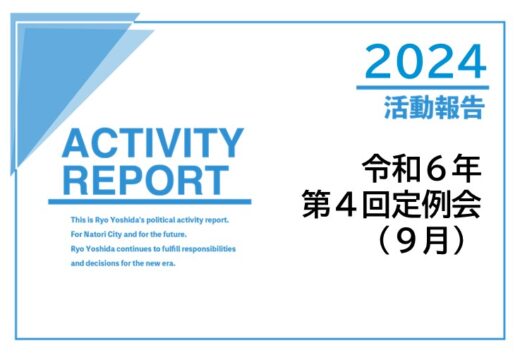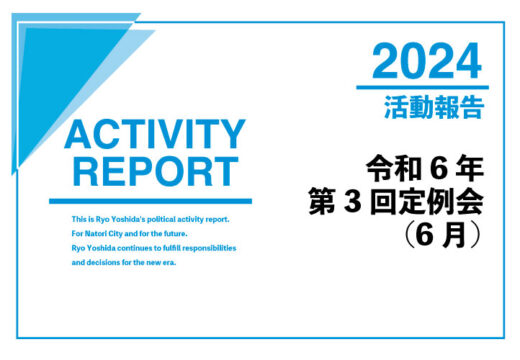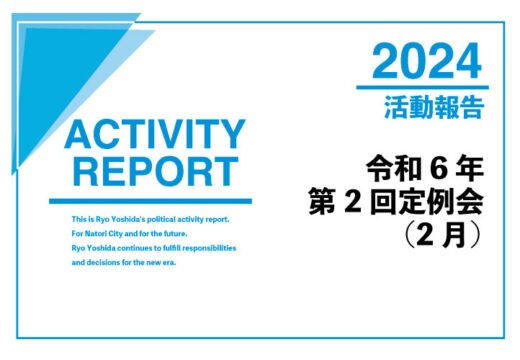本会議
(議案第17号 名取市都市公園条例の一部を改正する条例)
吉田
都市公園法の改正に基づいて、公募対象公園施設の建蔽率が引き上げられたと理解しているのですが、市内に公募対象公園施設があるのかどうか。そういうものを建てることが可能な公園はどこにあるのか。もし数が少なければ、具体的に名称まで教えてください。
都市計画課長
公募施設管理制度に伴う建物は、今、本市にはありません。大小にかかわらず全公園が対象となります。
吉田
都市公園法の改正の趣旨は、民間の力を利用することで公園の維持管理の費用を下げていくことに主眼が置かれていると思います。本市はこうしたものを民間に提案していくという具体的な計画は、閖上地域も含めて何かお持ちかどうか確認します。
都市計画課長
今のところ具体的にこことは決めておりませんが、実際設置するとなると、本市で整備方針やどういうものを整備していくかをまず決めていかないと進まない話です。今回公募設置の建物ができることによって、便益施設は2%しか建てられなかったものが、10%まで上積みできるということで、より多くの便益施設ができるようにという意味を込めて、今回法律の改正に伴って一緒に条例改正したものです。
(議会案第1号 宮城県上工下水一体官民連携運営事業について、慎重な対応を求める意見書)
吉田
宮城県のコンセッション方式については物議を醸しているところではないかと思いまして、私もいろいろと心配している点はあります。この意見書の提出者に伺いたいのは、大きく2つの措置を講ずるように要望されていて、2番目は慎重に対応することと結ばれているわけですが、宮城県のコンセッション方式を進めることに関しては、基本的に賛成の立場と捉えてよろしいのでしょうか。
小野寺美穂議員
基本的に賛成の立場ではありません。
吉田
そうすると、賛成ではない理由がいろいろあると思います。恐らく1番目の、全ての情報を公開することと書かれている部分かと思いますが、現在も宮城県からさまざまな資料が公開されています。その資料を全部読み込むだけでも大変な分量で、私も非常に苦労しているところです。これだけ情報が出ている中で、さらにこれ以上の情報は例えばどのような部分を求めているのか、全てのというところに現在不足している情報があるのであれば、どの部分が不足と捉えているのか、伺います。
小野寺美穂議員
現在公開されているものが全てではないかという質疑者の発言は、何をもとにしているのでしょうか。「みやぎ型管理方式」についてはホームページにも出ておりまして、平成30年12月21日付で出されています。宮城県が出している資料は、ほかにも例えば市町村別の覚書水量が、例えば大崎広域水道事業、仙南仙塩広域水道事業、仙台北部工業用水道事業等々、対象が9事業ありまして、それぞれが県水を買っていたり、市町村としての覚書水量等があります。
これは独自に入手したものですが、そういった水量予測表や導入可能性等調査業務などがさまざま出ているわけです。そういうものも出すべきですし、県が言っている、こうしないと水道事業はパンクしますよということのみならず、県が知り得ている、例えばヨーロッパでの水道サービスは誰が担うべきなのか、水は商品あるいは人権なのか、民主主義自治は機能しているのかといったような、既に一旦民営化して再公営化をしている世界の情勢というものもあります。そういった県が今の水道事業として出している資料のみならず、県が把握している世界の趨勢、動向、そういったものも全て出した上での判断を仰ぐべきという考え方です。
吉田
さまざまな世界の国々で、完全に民営化をした事例、そこからまた公営に戻した事例等、そのようなものに関しても県で資料を出していることについては把握しているのですね。全ての情報となりますと、例えば今後の県の水道事業の経営、その収支を予測していく際に、支出と収入と両方を見比べていかないと、将来的な収支の見込みは立てられないと思います。そうなると必然的に、入ってくるお金がどのくらいあるのか、大口の企業の企業名まで含めて情報を出していけというようにも捉えられます。現在、県から出ている大口事業者のデータに関しては、会社名は伏せられてA社とかB社となっていますが、そのようなものも含めて全て情報として公開しなければならないというように、この案文からは捉えられますが、そのあたりの整理についてはどのようにお考えですか。
小野寺美穂議員
いかなることを意見書に求めようとも、それには基づく法令や政令などがありまして、それに抵触するようなことは可能ではないと考えています。ですから、全てというところだけに重きを置くのであれば、解釈の違いだと思いますが、情報公開請求でとれるようなものであればとれるでしょうし、それもできないという理由があって、情報公開の審議会等でこれは出すべきでないと伏されているようなものであれば、それはとれないでしょうし、そこはその時々の判断だと思います。
また、全てと言っても、何が全てなのか、結局のところ私たちにはわかりません。これが全てと言われたら全てということになるかもしれないし、ほかのところから持ってきた資料に基づいて、いや、こういうことがあるのではないかというような局面は、ほかのケースでもあるわけです。対県とか自治体。名取市が相手でもそうですが。名取市がこれだけですと言っても、いや、こういうのがあるんじゃないですかということは、調査研究していって調べるものです。しかし、それが法に抵触するということであれば、出せないというのはあると思います。しかしながら、県民の権利として知っておくべき情報は出すべきだという意味です。
吉田
もちろん情報公開請求で出せないものは出せないということになれば、あえてここに全ての情報公開するということを求めなくても、県としてはもう全て情報公開しているというスタンスではないのかと捉えられると思うのです。必要なのは、情報そのものの取り扱いではないかと思うのです。今後の将来的な予測を立てて、宮城県は今危機的な状況にあると。今後かなり赤字がかさんでいくという予測を立てているわけですが、その数字が本当に正しいかどうかということは、もとの数字が正しくても扱い方が違ってくると、いろいろな結果が出てくると思うのです。そういった意味では、情報の公開はもちろんですが、情報の取り扱いの部分を盛り込んでいくことも必要ではなかったかと思うのですが、提出者のお考えを伺います。
小野寺美穂議員
今は意見書の取り扱いについての審査なので、そこまで言って、ここで変えるとか変えないとかいうことになるのか運び的にわかりませんが、提出者としては県民に対して情報を公開することが大前提だと考えているわけです。その過程で、それが出せる、出せないとか、県はこれで全部だと言っているのにといっても、その担保はないわけなので、そういうことも含めて対応していきなさいということです。私は全部出していると思っていないので。
しかも、全県民に対してだから、我々がつかんでいるとか、私が知っているとかではなく、県民に広く全てを明らかにして出していき、判断材料となるものは示すべきだということです。その過程において、先ほど全部出すということで取り扱いだということでしたが、それはその先の話であって、この意見書の趣旨としては、情報を公開して慎重に対応すること、それに尽きるわけです。事細かに、実際この官民連携運営事業についてどうなのかという審査については、付託された委員会でどこまでやるかわかりませんが、意見書を提出する段階で捉え方が違うと言われてしまえばそれまでですが、とにかく県民に情報を出せと、それが言いたいことです。
一般質問
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、通告に従いまして私の一般質問を始めさせていただきます。
初めに、大項目1 給与水準の適正化についてお伺いいたします。
お断り申し上げておきますが、現在の給与の水準というのは額ではなく、決定のプロセスについて、きょうは市長と議論させていただきたいと考えております。
現在、国家公務員の一般職職員の給与の改善については、中央人事行政機関として設置されている人事院が、国家公務員給与と民間給与の実態を調査比較した結果として、毎年8月に俸給表や各種手当等の改定を国会や内閣に勧告しております。一般的に人事院勧告と呼ばれるものです。9月、内閣は人事院勧告の取り扱いについて閣議決定を行い、10月に給与法改正法案が国会に提出され、11月以降に改正法案が審議され、そして成立、公布、施行という流れとなっています。
地方公務員はどうかと申しますと、人事委員会を設置している自治体では、人事院勧告の内容と自治体内の民間賃金動向等を総合的に勘案して人事委員会が勧告を行い、人事院勧告の取り扱いに関する閣議決定を受けて、具体的な給与改定方針が決定されます。本市のように人事委員会を設置していない自治体では、国の取り扱いや都道府県の人事委員会勧告等を受けて、具体的な給与改定方針が決定されています。いずれの場合でも、議会の議決により給与条例を改正することとなっております。
なお、特別職についてもおおむね人事院勧告の趣旨に沿って取り扱われておりますが、手当の引き上げに対し、お手盛りという批判は絶えません。
ほとんどの自治体における職員給与は国に決めてもらっているに等しい状態であり、自立的に決定するという責任を負わなくてよいのと同時に、批判が上がればほかも同じだからという口実にできるわけです。私はこうした状況を改善する必要があると思いますが、市長のお考えを伺いたいと思います。
小項目1 一般職及び任期付職員の給与等の改定が、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じている現状をどう捉えているのか、市長にお伺いいたします。
市長
地方公務員法第24条第2項で、地方公務員の給与について「生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」と規定されております。
また、人事院は毎年8月に民間準拠の原則にのっとり国家公務員の給与等について勧告を行い、その後に国家公務員に係る一般職及び任期付職員の給与に関する法律等が改正されております。
本市においては、この内容に準じ、議会に給与条例改正の提案をし、御承認をいただいているところであり、今後も人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて改定をしていきたいと考えております。
吉田
人事院勧告の中身、職種別民間給与実態調査の範囲を調べてみたところ、全産業の企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の全国の民間事業所がその範囲とされています。平成30年は5万8,351事業所でした。そこから1万2,479の事業所を無作為に抽出し実地調査が行われ、実際に調査が完結したのは1万896事業所でした。
なお、平成28年の経済センサスによると、国内の事業所総数は約558万事業所に上ります。少し時期的なずれがありますが、民間給与実態調査の範囲となる事業所は、全国の全事業所の100分の1程度しかないという状況です。
中小企業という定義は業種によって異なっているようですが、従業員数50人以下の企業は、どの業種でも中小企業として位置づけられていると伺っています。これは企業全体の99%、そして働く人の約70%は中小企業で働いていると言われています。しかし、この職種別民間給与実態調査は初めから中小企業を除外して行われています。人事院勧告は、こうした99%ある中小企業を存在しないものとして出されているものと捉えられます。
中小企業の経営者や従業員の方にも税を負担していただいている行政のトップとして、市長には少なくとも現状を改善する意思をお持ちになっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
市長
企業規模50人以上の企業となぜ比較をするのかと。これは公務と比較をする上で、課長や係長など公務同様に役職の段階があるからです。中小企業ではそうした役職がない部分もありますので、そういう意味で公務と民間の役職段階上の比較ができるということ。それから、民間企業の正社員という部分で見たときに約6割がカバーできるというようなことで進めているものと承知しているところです。
吉田
民間と行政の一番の違いは、行政には倒産のリスクがないということです。ですから、その辺も含めて、民間の特に大企業と比べていくのはいかがなものかという議論は尽きないわけですが、次に移りたいと思います。
これまでの本市の給与等の条例改正に対する審議において、職種別民間給与実態調査の範囲となる事業所の数を私から質問させていただきましたが、把握していないという理由で具体的な数は示されておりません。職員の給与の改定を人事院勧告に準拠しなければならないという事情については、私も一定の理解は置くべきものと捉えております。ただ、準拠しなければならないという今の事情においても、その根拠となったデータ、本市の状況を知らないという姿勢は、やはり捉え方によっては無責任なものではないかと映りかねないと思います。
そこで、小項目2 人事院勧告のもととなる職種別民間給与実態調査において調査対象となる、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の民間事業所が市内にいくつあるのか、把握すべきについて、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
人事院は、給与勧告に当たり、公務員給与との比較対象となる民間給与について基礎資料を得るため、都道府県、市、特別区人事委員会と共同で職種別民間給与実態調査を毎年実施し、平成30年度の調査では、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の全国の民間事業所約5万8,400のうち、無作為抽出した約1万2,500の事業所を対象としていることは承知しております。
本市においては、人事院の調査内容と多少捉え方は異なりますが、税の概要において法人市民税の納税義務者数を公表しているところであり、市内で従業員が50人を超える事業所が、平成29年7月1日現在、97事業所あることは把握しているところです。
吉田
初めてお聞きしました。平成29年7月1日時点で97事業所ということです。市内にはさまざまな事業所が置かれていると思いますが、この97という数は、その全体に対してどのぐらいのパーセンテージなのか。それを市長としては多いと捉えるか、少ないと捉えるか、その考え方をお伺いしたいと思います。
市長
市内の事業所が1,978事業所ですので、事業所割合としては4.9%になりますが、そこで働く方が先ほど申し上げた正社員かどうか、また役職別の段階といった捉えが必要であろうと思っておりますので、この数字だけをもって一概に多いとか少ないということではないと思っております。
吉田
先ほど紹介したとおり、国の職種別民間給与実態調査の対象企業の割合は1%ということでしたので、市の捉え方では約4%ですから、本市は国全体と比べると、中小企業ではない、50人以上の事業所の割合が多いのかなという捉え方もできようかと思います。ただ、いずれにしても、そのような国の捉えてきた調査に準拠しなければならないというよりは、やはり名取市は名取市で自治体ごとに決める考え方がよろしいのかなと私は思いますので、きょうはそういう議論にさせていただきたいと思います。
それで、仮に本市が独自にこのような調査を行うことを考えると、例えば公務員と同種同等のもの同士による調査が可能な市内事業所となると、今市長のおっしゃっていたことはまさにそのことだと思いますが、事業所規模1,000人以上というものがもしそこにあったとすると、実際の経済状況の中でそこの企業だけを抽出するとなるともちろん正しくないということになろうかと思います。
この人事院勧告の調査対象とされている事業所が一体どのぐらいの数なのかを見ると、やはりこれも規模ごとに分けられておりまして、先ほどの1万896事業所の規模別の内訳を見ますと、50人以上100人未満が1,903事業所、100人以上500人未満が4,642事業所、これが一番多いようです。500人以上1,000人未満が1,266事業所、1,000人以上3,000人未満が1,255事業所、そして3,000人以上が1,830事業所ということで、事業所規模が1,000人以上の事業所がこの調査対象の約3割を占めているという結果になっています。1,000人以上となると、市内では相当厳しい状況になってくるかと思います。私は思いつかないのですが、あるかどうかわかりませんが、相当な大企業になってくるわけです。しかし、人事院勧告は、そういう1,000人以上の規模の企業が調査の約3割ということで大きな割合を占めているということだと思います。
こうした地域の実情と人事院勧告の調査対象がかけ離れている状況があり、給与の改定が本当に適正であるということを理解していただくには、まだ少し無理があるのではないかと思うところです。
それで、具体的に改善策を示していかなければならないと私は個人的には思うのですが、どのような方法があるかといろいろと考えてみたところ、次の小項目3に移っていきますが、人事委員会というものを置いている自治体があると。これは都道府県と政令指定都市には義務づけられていて、この人事委員会は人事院と共同で民間給与の調査を行い、情勢適応の原則、均衡の原則にのっとって給料表、手当の改定勧告内容を決定し、人事委員会勧告を行っているということです。
そして、仙台市ではどのぐらい予算がかかっているのかを確認したところ、当初予算ですが、1年間で約1億8,000万円が計上されていました。これは、もし本市で人事委員会を設けるとなると、費用に見合うだけの市民福祉につながるかといえば、さすがにそれは少し違うのではないかということで、なかなか人事委員会を設けることは予算の面からも難しいことが理解できると思います。それでも、やはり独自に第三者という中立の機関を置くことで公務員給与と民間給与の実態について調査比較を行い、そしてその地域の身の丈に合った内容に改定していくのが本来あるべき姿ではないかと思います。
そこで、例えば環境や規模が似ている自治体が共同で人事委員会を置くことはできないものかどうかと考えてみました。前例は今までないと捉えておりますが、研究していく価値はあると思います。
そこで、小項目3 広域連携による人事委員会の設置について研究してはどうか、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
地方公務員法第7条では、都道府県及び政令指定都市は条例で人事委員会を、政令指定都市以外の人口15万人以上の市及び特別区は人事委員会または公平委員会を、人口15万人未満の市町村及び地方公共団体の組合は公平委員会を置くものと規定されております。
本市においても、昭和34年から公平委員会を設置してきたところではありましたが、公務員制度改革や職員からの要求の多様化等もあり、また、事案も少ない中では高度な専門知識を維持するのが難しいことから、地方公務員法第7条第4項の規定に基づき、平成21年4月から宮城県人事委員会に事務を委託したところです。
広域連携による人事委員会の設置についての御質問ですが、地方公務員法上、本市においては単独でも広域連携でも人事委員会を設置する要件を満たしておらず、設置はできないものとなっていることから、現時点では設置について研究を行う予定はありません。
吉田
その設置できないというのは、法的に禁止されているわけではなくて、設置することをどう捉えるかだと思います。確かに公平委員会の事務は今県に委託をしていますが、例えば上乗せ条例という考え方もあり、しっかり要件を満たした上で、さらにそれ以上に厳しい規制をかけていくようなことが、例えば環境問題などに関しては認められています。国よりも厳しい基準ということです。そういうものが広域連携による人事委員会の設置に当てはまるかどうかということです。これは、結論を導くのはまだ早いのではないかと思って、私も個人的に総務省に電話をかけて聞いてみたのですが、担当の職員の方は、個人的に今お答えできませんということで、絶対できないとは言ってきませんでした。ということなので、可能性としては、無理ではないのではないかと思いますが、ただ、市長の御答弁がそのようなことですので、この問題は一旦置いて、最後の質問で、別の形で人事委員会を求めていきたいと思います。
今、市長から御答弁があったように、人口15万人以上の一般市は、公平委員会か人事委員会のどちらかを設置する定めとなっています。そこで要件を満たす市はまず公平委員会を置いていますが、ただ、唯一、例外として、和歌山市だけは、本当は公平委員会でもいいのですが、人事委員会を置いている現状となっています。その和歌山市の人事委員会が行う民間給与調査では、和歌山県人事委員会とは異なる結果が出ています。人事委員会勧告の内容が市と県で異なるということは、給与水準に地域経済がより強く反映していることのあらわれではないかと評価したいと思います。
公平委員会にはない事務はほかにもたくさんあり、その中には、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修及び勤務成績の評定、厚生福利制度その他職員に関する制度について、絶えず研究を行うことというものもあり、これは人事委員会が置かれていることによって職員が受けることができるメリットではないかと捉えているところです。
以上のことから、やはり人事委員会は設置するのが望ましいと私は思いますが、しかし、今市長から御答弁があったように要件を満たしていないということもあります。それでも実現可能な方法はないわけではないと思います。多少強引かもしれませんが、人事委員会を置く政令指定都市と隣り合っている本市であれば、仙台市と合併すれば、人事委員会を置くことと結果としてつながってくると捉えています。
小項目4 専門的・中立的な立場から給与などに関し講ずべき措置について勧告する機関が置かれていない問題を解消するために、仙台市との合併を検討してはどうか、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
仙台市との合併については、これまで何度も答弁申し上げているとおり、本市独自に持続・発展し続けるまちをつくっていきたい、まずは模索していきたいと考えております。
宮城県内の市町村において仙台市のみが人事委員会を設置していることは承知しておりますが、議員御質問の問題を解消するためだけの理由で合併を検討することは考えていないところです。
吉田
合併すべき理由として今までいろいろなことを言ってきたので、これもそのうちの一つとして捉えていただければと思います。
今の市長からの御答弁で、やはり現状のまま人事院勧告準拠という方針でしばらくいかなければならないということかと思います。今いろいろと指摘してきた問題、人事院勧告に準拠しなければならないという市としての主体性のなさ、それから、大企業のみを対象としているために地域の経済状況が反映されにくい職種別民間給与実態調査のあり方、そのようなことを解消するために何か別の手だてとして市長は妙案をお持ちかどうか、お伺いしたいと思います。
市長
できる限り地域の民間企業の実情を反映した形にということをおっしゃる議員のお考えもよくわかるところはありますが、現状、市としては、この人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じるということ以外の妙案はまだ持ち合わせていないところです。
吉田
名取市を活性化させて人口を15万人以上にふやして人事委員会を置くというのも一つの手かと思いますが、そういう未来も模索しながら、よりよい制度の運用の仕方を常に検討していただきたいと思います。
続いて、大項目2 地方公務員制度の見直しによる影響についてお伺いいたします。
平成29年5月17日、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が公布されました。その内容についてはこの議会でも取り上げられた議員がいらっしゃいますが、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度へ必要な移行を図るものとされています。あわせて、会計年度任用職員に期末手当の支給が可能となると伺っています。
法律の施行による自治体運営への影響は多岐にわたるものがあると思います。その中でも今後の地域づくりへの影響が特に大きいのが、公民館長の選出方法と区長制度の2つではないかと思います。この法律の施行を約1年後に控え、市はどのようにその影響を分析しているのか確認させていただきたいと思います。
小項目1 平成32年4月、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、特別職非常勤となる対象の要件が厳格化される。本市の区長制度及び公民館長推薦制度にどのような影響があると捉えているのか、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
議員御指摘のとおり、改正地方公務員法の施行に伴い特別職非常勤職員の任用要件が厳格化されるため、特別職非常勤職員の運用を抜本的に見直す必要があると捉えておりますが、制度上のさまざまな課題があることから、他の自治体同様、意思決定には至っていない状況です。その中で、区長制度の部分について答弁いたします。
現在、本市では、区長について、町内会等の地域から推薦いただいた方を、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職非常勤職員として任用しております。改正地方公務員法の施行に伴い特別職非常勤職員が限定列挙されることにより、区長は除かれることになると承知しているところです。
今般の改正は、任用方法、服務、勤務条件など、あらゆる面に影響が及ぶことから、早急に新たな制度設計を行う必要があると捉えています。
教育長
公民館長推薦制度の部分について答弁いたします。
現在、公民館長の任用については、各地区の公民館運営協力委員会から推薦していただいた公民館長候補者を教育委員会で承認し、特別職の非常勤職員として任用しております。
改正地方公務員法の施行後の公民館長の任用のあり方については、総務省が作成した会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルにおいて、「美術館や公民館などにおいて特別職非常勤職員として任用されている館長についても、一般職に移行する必要があるか」との質問に対し、「原則として一般職に移行することが適当である」と回答しています。
現在、教育委員会では、総務省の回答から、公民館長候補者の地域推薦は難しいものと捉えておりますが、市長部局と調整しながら、引き続き検討を進めていきたいと考えております。
吉田
まだ完全に固まったわけではないので、これから具体的に取り組んでいかれるかと思いますが、こうした非常に重要な内容について、議会側に対しての説明が全くされていない状況に今あると思います。私も地域の方から、何か公民館大変そうだよという話を伺ったのですが、議会側への説明を今後どういうスケジュールで考えていらっしゃるのか、市長と教育長にお伺いしたいと思います。
市長
この制度改正については、総務省から会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルは出されていますが、例えば選考方法の問題ですと、これは基本的には推薦ではなく原則公募による選考、そして試験を行うこと、また、職務専念義務という部分から勤務時間や場所、報酬にかかわってくる問題、整理しなければならない課題がさまざまあります。そういう意味で、今後の方向性について市として方針を定めるに足りるだけの必要な指針までは示されていないところです。今後示されるということですが、そうしたことを踏まえて、その後、市としての考え方をまとめた上で、当然、議会や関係者にもしっかりと周知を図っていきたいと思っています。まだそこに至る段階ではない状況ですが、早急に取りまとめが必要だという認識は持っております。
教育長
ただいまの市長の答弁と同じような内容になりますが、現在、検討を進めている段階で、教育委員会としては市長部局と緊密に情報交換をして調整しながら検討していくということで進めておりますが、具体的にこういう形でというところまではまだ固まっていない状況にあります。公民館長のあり方については非常に大きな問題だと捉えていますので、方針が固まった段階で議会等への説明は必要であろうと考えております。
吉田
マニュアルの今後のスケジュールの中には公募制度にするに当たっては条例改正が必要になるということがあり、新しい制度の中で区長や公民館長を募集するときに、やはり条例の改正が必要になってくるかと思います。できれば2月の議会でそれを行うべきだということがマニュアルの中に書いてあったのではないかと思います。現状として市の取り組みは少しおくれていると捉えるべきかと思いますが、そのあたりの御認識はいかがでしょうか。市長にお伺いします。
市長
例えば区長業務について、委託できる部分と、それから、その受け皿となる地域でなかなか受けられないような地域の実情によって変わってくる部分とがあります。委託も可能ではないかというようなマニュアルでの書きぶりですが、では、この業務はどうするのか、こちらの業務はどうか、また、区長制度そのものも自治体によってあり方が少し変わってきている。いわゆる地域の実情を必ずしも網羅した形で示されていないのが現状であり、これは全国のほかの市町も同様に抱えている大きな課題ではないかと思っております。
吉田
ということは、スケジュールとしては今は市としてはもっとスピードを上げていかなければいけないという認識でよろしいのですか。
市長
平成32年4月からとなりますと、その数カ月前には任用というか更新というか、いろいろな動きが出てくると思います。その前に制度設計をしなければいけませんので、その制度設計の前に必要な指針などの取りまとめをすることになります。そういったことを踏まえると、やはりなるべく早くお示しいただいた上で進めていきたいという気持ちでおります。
吉田
条例の改正が必要になってくるということもありますので、これから議会側にも説明をいただきたいと思います。我々も地域住民の方々に説明していく務めがあると捉えておりますので、できる限りスピード感や内容などを十分に考慮して進めていただきたいと思います。
次に、具体的な内容について、まずは区長制度に絞ってお伺いしていきます。
総務省のホームページから、今おっしゃっていた会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルを閲覧することができます。そのQ&Aの中の55ページに、「区長など勤務時間の把握が困難である職について、引き続き特別職非常勤職員として任用は可能か」という問いがありました。その答えとして、「単に勤務時間の把握が困難であるという理由のみで特別職として任用することは適当ではない」「区長について地方公務員として任用するのであれば一般職とすべきであるが、地方公務員として任用するのではなく、文書の回覧・配布などといった業務について委託することも考えられる」との回答が示されています。先ほど市長が御説明なさったとおりのことです。
この点で、小項目2 区長を一般職として任用する考えはあるのか、市長の御見解をお伺いしたいと思います。
市長
任用、服務規律等の整備を図るという改正地方公務員法の趣旨を踏まえると、特別職に適合しないとされた者は、今回創設される一般職の会計年度任用職員への移行等を図る必要があると考えており、区長の任用についても同様に考えているところです。
なお、総務省は、会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルにおいて、「区長について地方公務員として任用するのであれば一般職とすべきであるが、地方公務員として任用するのではなく、文書の回覧・配布などといった業務について委託することも考えられる」として、一般職である会計年度任用職員への移行と、町内会等への委託への移行の2通りの方法を例示しております。
区長制度の運用方法の転換については全国の自治体から問題が提起されており、総務省が改めて方針を示すとしていることから、本市としては、国や他自治体の動向を注視しつつ、引き続きあらゆる方向性について検討していきたいと考えております。
吉田
総務省がまたこれからそういう新たな考え方を示すということも、時間的に非常に詰まってきている中でどうなのかという思いもありますので、市としてはやはり一定の方向性をしっかり定めて、その上で、新しい法の趣旨にのっとった制度のつくりかえが必要になるのではないかと思います。今のマニュアルをそのまま解釈すると、一般職として任用することは恐らく厳しいのではないかということで、そうなると区長制度そのものが、やはりもうなくならざるを得ないと。筋としては、今まで続いてきた区長制度を廃止していく方向に進んでいくべきではないかと思われます。
そして、今、市長も一つの可能性として区長業務を町内会等に委託していくことを示されました。こうしたことを私も随分以前から提案してきていましたが、市からは、区長制度については、平成32年度の閖上の復興事業の落ちつきを待って、その後、見直しを検討するという答弁がずっと続いてきました。今回、国の法律改正があったとしても、こうやって方針が180度と言ってもいいくらい変わってしまうことについて、市長としてどう考えていらっしゃるか。もう少し早くそういう問題を捉えて、やはり区長制度も、国から言われたにしろ言われないにしろ、本当にやろうと思えばできるわけですから、もっと早く取り組んでおくべきではなかったかと私は思うのですが、市長はいかがお考えでしょうか。
市長
区長制度のあり方については、これまでも検討、研究を続けてきました。今般、平成32年4月からの制度改正が示されたわけで、これはもう喫緊の課題として検討せざるを得ない状況であると捉えているところです。本質的には、区長制度そのものをやめるということではなく、現状区長が担っている業務をどういう形で残していくのかということがまず1点だろうと思っています。広報や市のチラシ等の配布については委託という方向性も不可能ではない、いわゆる検討の俎上にはのせられると思っておりますが、さりとて、例えば住民からの相談の問題とか、それから、例えば行政サービスの漏れなどを防ぐためにこれまで住民の異動の把握もしてもらってきた、こういったものについては、地域に任せるには非常に困難を伴う部分もあるのではないかと思います。どういう形でこれまでやってきていただいた業務を残していくのかということが非常に大きな視点になるかと思いますので、この辺のことについて、考え方を取りまとめていく必要があるだろうと思っています。
もう一つは、コスト見合いということで、現在130人を超える方が区長として働いています。勤務時間等いろいろなことが固まって一般職で給与ということになったときに、それはやはり非常に大きなコストとなりますので、その辺のいわゆる業務とコストといった視点からも検討が必要かと思っております。
吉田
ポスティングについては委託という方法もあるということで、過去にもいろいろと検討されてきた経緯があると伺っていますが、住民リストについても以前指摘させていただきました。行政区長はその行政区内の住民の氏名、住所、生年月日等が書かれている住民リストを自宅で保管しているという問題です。こちらについては、このように区長が特別職非常勤職員でない新しい形になったときに、委託して続けていくのかどうか。あるいは、それをなくしていくことになれば、別の形でどうやって住民の状況を把握していくのか。そのあたりの考え方は今どこまで固まっているのかお伺いしたいと思います。
市長
繰り返しの答弁になりますが、区長が行っている業務をどういう形で残していくのかということがこれからの大きな検討課題だと思っております。まだ具体に住民異動の把握はどうするかとか、チラシ等の配布をどうするかといったところまでは詰めていないところです。
吉田
では、次に、公民館長の選出についてお伺いしたいと思います。
会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルのQ&Aの54ページに、「公民館などにおいて特別職非常勤職員として任用されている館長についても、一般職へ移行する必要があるか」という問いがあり、「原則として一般職に移行することが適当である」という回答となっています。これまで公民館長は地域からの推薦によって選ばれてきており、名取市公民館の将来像もその前提で策定されました。
そこで、小項目3 平成30年3月に策定された名取市公民館の将来像を見直す考えはあるのか、教育長の御見解をお伺いいたします。
教育長
平成30年3月に教育委員会が策定した「名取市公民館の将来像」は、これからの公民館がどのようにあるべきかについてまとめたものです。その中で、これからの公民館に必要な機能として、「学びあいを支援する」「地域を繋ぐ」「住民自治の力を養う」の3点を挙げており、住民主体による機運の醸成を図っていこうというのが基本的な考え方です。
地方公務員制度の見直しがこの将来像の基本的な考え方に影響するとは考えておりませんが、職員体制のあり方に触れている部分などに修正が必要になる場合には、対応を検討していきたいと考えております。
吉田
大変長い時間をかけて、そして多くの市民の方の協力もいただいて策定された名取市公民館の将来像ですので、その大きな変更は難しいというか、するべきではないというお考えかと思います。ただ、今教育長がお示しになったように、例えば名取市公民館の将来像の17ページには「公民館の管理者は、現在、地域から選ばれた立場で」という部分もありますが、これが今後は地域から選ばれるのではなく、あくまで公募で公平にという形になってきますので、そういった部分の細かい修正は必要になってくるのではないかと思うところです。
ただ、もう少し根本的な問題として、今回の会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルのQ&Aについては、国からはあくまでも「原則として一般職への移行が適当」と示されています。この「原則として」、しかも「適当」という部分に関しては、必ずそうしろと捉えないこともできるのではないかと思います。公民館長を平成32年度以降も特別職のまま据え置くという検討についてはこれまでなかったのかどうか、お伺いしたいと思います。
教育長
地方公務員制度の改正に伴って将来の公民館長をどのようにするかということについては、あらゆる可能性について検討してきました。その中には、制度上このまま残せないのかという議論も当然ありましたが、総務省からの回答としては、原則として一般職への移行が適当ということですので、具体的に今、現状のままの制度を維持することについて積極的に取り組んでいるということではありません。先ほども答弁したように、これについてはただいま検討中ですので、市長部局とも調整しながら早急に方向性を示したいと考えております。
吉田
「原則として」という言葉がつくと、私などは原則があるなら例外もあるのではないかと捉えてしまいたくなるのですが、現在公民館長を務めている方々にもいろいろと意見を聞いたり説明をしたりということもこれまで踏んできていらっしゃるようですので、区長制度もそうですが、少しでも早くしっかりとした制度を示していただくことをお願いしたいと思います。
この大項目2の最後の質問ですが、こうして公民館長の身分や区長制度が変更されていくことになると、公民館の運営そのものに大きな影響を及ぼすことが考えられると思います。これまで地域課題への取り組みは、私としては区長と公民館とが強く連携して行っているものであると。もちろん行政もそうなのですが、地域という観点で見ると、この両者は本当に車の両輪のような関係ではないかと思っていました。この両輪のあり方が変わってくることで、これまで公民館としても区長を頼りにいろいろと行ってきた事業や取り組みが、風通しが少し厳しい状況になるのではないかという懸念もあります。そして、今後、区長としての立場の変化を模索していけば、ポスティングの際にやはり町内会などの自治組織が非常に重要ではないかと思います。
この自治会の組織は任意団体ではありますが、これまでも行政の手の届かないさまざまな地域課題に対して活動をお願いしてきている状況です。そして、他の自治体で既に取り組みが始められているように、自治会組織と行政の間での役割分担を明確にして、その自治会の組織に活動資金を交付するという新たな制度を導入していくべきではないかと私は思っています。
そこで、小項目4 区長業務を含む地域課題を住民みずからが事業化して解決する、公民館地区単位による小規模多機能自治制度を導入すべきについて、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
議員御提案の小規模多機能自治制度については、おおむね小学校区程度の小規模で、目的型組織や地縁型組織等のあらゆる団体が結集し、地域のさまざまな課題を地域住民みずからの自治で担っていくという仕組みと捉えているところです。
この小規模多機能自治の考えが出てきた背景には、平成の大合併が行われ自治体の区域が拡大し広域となったことで行政が遠くなったことと、急激な人口減少と高齢化が進んだことで従来の体制の維持ができなくなったことがあり、新しい形として多様な主体による参加、協力が必要とされたことが挙げられます。
本市においては、平成の大合併を行っていないこと、人口が増加を続けていること、高齢化が進んでいくものの緩やかな変化であることなどから、小規模多機能自治制度に取り組んでいる自治体とは置かれている状況が異なっていると捉えています。
また、小規模多機能自治制度の仕組みについては、既存の制度での運用には多くの課題が指摘されていることや、行政区域内のいわゆる分権化であり、市民の負担も相当大きいと捉えていることから、現段階において小規模多機能自治制度を導入することは考えていないところです。
教育長
教育委員会は、地方自治の本旨にのっとり、地方自治制度を尊重し、さまざまな教育上の課題に対応しております。しかしながら、自治制度そのものや自治組織について言及する立場にはありませんので、答弁は差し控えさせていただきます。
吉田
今市長が小規模多機能自治制度が導入されてきた背景として挙げられた2つの点、大合併と人口減少については、もちろん今の本市は該当しませんが、小規模多機能自治制度が導入されている背景にはもう一つの点があると私は思っています。それは、自治会組織そのものの活動がだんだん厳しくなっている。これは人口減少ではなくて、どちらかというと高齢化の観点かと思いますが、そして、一部の方に負担がどんどんかかっていって、1回役員を引き受けるとなかなかやめられないという状況をいろいろな自治会から伺っているところです。
ですから、小規模多機能自治制度を導入しないのは住民の負担が大きくなるからということを理由の一つとして挙げておられましたが、実際にもう住民の負担は大きいのです。そして、それをどうやってこれから解決していくかといったときに、先ほどおっしゃったように、市の中で分権化をしていって、そして市が今まで行ってきたことも住民の方々に責任を持って行っていただくと同時に、そこに交付金もつけると。交付金の使い方は全部委ねましょうと。そのようにして市の中で分権をしていくというあり方なのです。そうなると、これは新しい自治のあり方ということで、名取市では今までもちろん取り組んだことがありませんが、私は、町内会としては逆に活性化していく方向につながることが可能性としては高いと思います。市は何かやってくれるけれども大変なところは自治会におりてくるな、それで負担だけは高いなという状況から変えていくためには、やはりこういう大きな制度の変更が必要だと思います。そこで今回の地方公務員制度の見直しというのが一つの転機になってくると思います。そうすると、公民館は今は社会教育の場ですが、そうではなく、地域づくりの一つの拠点として、例えば健全育成にしても交通安全にしても、さまざまな地域課題を全て社会教育として捉えて、公民館を拠点として地域づくりをしていく形をとるという意味では、この小規模多機能自治制度は調査すべきであり、本当にいろいろなヒントを与えてくれるものかと思いますが、市長と教育長にその考え方をぜひお伺いしたいと思います。
市長
市民ニーズが多様化する中で、行政だけでは手が届かない地域の課題、きめ細やかなサービスなどについて、地域の方と一緒にというか市民協働で取り組んでいくという方向性は同じだと思っております。
今回御提案いただいた小規模多機能自治制度については、ある意味、究極の姿なのだろうと思っています。これは、地域に権限もお金もおりていくかわりに、責任と負担も当然おりていく。例えば地域の中で決めるときにも当然議会のような議決の機関が必要になってくるということで、より強固な組織や制度設計が求められ、住民の負担や責任も出てくる中で、地域を元気にしていこうとか、地域をどうやって活性化していこうかという方向性は一緒ですが、ここに一足飛びに行くには、私は課題が非常に多いのではないかと思っています。ただ、方向性として、行政と地域、行政と市民が一緒になって地域課題を解決したり、きめ細やかなサービスをしていくという方向性については、私は意見を同じくしているものと思っているところです。
教育長
公民館のあり方については、地域における地域コミュニティーの拠点として、先ほど議員から御指摘があった地域課題についても当然取り上げて、住民の方々と話し合ったり、ともに考えていくということは、現在でも行っております。そういった意味で、学びあいを支援する、地域を繋ぐ、住民自治の力を養うという3点を大事にしながら住民主体による機運の醸成を図るというのはこれからの公民館に必要な機能であるということで、教育委員会としては将来像をまとめたところです。先ほどの答弁の繰り返しになりますが、地方公務員制度の改正が、この基本的な考え方そのものに大きく影響するものではないと捉えていますので、教育委員会としては、引き続きそのような公民館を目指して取り組んでいきたいと考えております。
公民館にさらに自主的な機能もという先ほどの御質問については、そこまで私が言及する立場にはありませんので、控えさせていただきたいと思います。
吉田
高齢化ということを考えていくと、自治会そのものの存立も大変危機的な状況に立たされているところが多くなってきています。ですから、町内会を逆に活性化させていくためには、何か新しい制度をつくっていかなければならないと。今ある制度が100%正しいと思っているわけではないと思いますが、常にその時代に合った新しい制度にしていくという意味では、この小規模多機能自治制度はまさしく今、日本の地方自治を考える上で大変重要なことではないかと。みんなで決めるというのは確かに大変な面がありますが、それは今までみんなで決めてこなかったということではないのかと。やはりお金と責任などが全部ついて一緒に考えるということをこれから一つの方向として、ぜひ深く検討していただきたいとお願いいたします。
最後の大項目3に移ります。にぎわいの創出についてです。
本当はこの項目だけでも40分かけて質問したいところですが、残された時間に凝縮して質問していきます。
仙台市の人口減少が拡大しているという報道が先日ありました。東北の自治体は、本市などごく一部を除いて、ほとんど人口減少にあえいでいます。仙台市もいずれ総人口が減少に転じ、本市もその後を追うと予測されています。人口減少の原因はもちろん少子化もありますが、社会減という意味で、若者世代が首都圏など大都市へ流出し続けていることがあります。もはや地方都市は今の若者の夢をかなえるための機能を失いかけていると言っても過言ではありません。
そこで、東北で若者の首都圏流出をとめられる都市というのは仙台しかないというのが現状です。秋田県や山形県の方はこうおっしゃるそうです。東京に出ていった若者は帰ってこない。でも仙台に出ていった若者は帰ってくると。だから、仙台というのは人口のダムになる。若者流出の防波堤になっていかなければならない。ただ、私が申し上げている仙台というのは、あえて仙台市と言っていないのですが、本市も含めた仙台都市圏としてそこは捉えていかなければならないと思います。
スケールメリットという言葉がありますが、やはり大きな組織、自治体の枠を広げていくことによって、これまでできなかったさまざまな事業もその地域の中で行っていける。そういった意味でも、仙台市との合併は今必要な課題であると申し上げたいと思います。
また、市長の仙台市地下鉄の南進の公約ですが、こちらもやはりそのような、より広い視点で捉えていただきたいと思います。名取市民の足を確保することももちろん市長の一つの思いかと思いますが、それ以上に大きな都市としてどういうものをつくっていくのかと、そこまで視野を広げていただきたいと思います。
これから提案する、にぎわい創出の3つの具体案があります。これは、本市と仙台市がもし一体であれば、どれもスピード感を持って進めていける、あるいは実現可能性が高まるものと私は思っておりますので、本市独自のまちづくりをこれからも続けるという市長でしたら、ぜひこの政策も音頭をとって前に進めていただきたいとお願いいたします。
まず、1つ目は、広浦から名取川を挟んで北側にある藤塚・井土浦地域との連携です。藤塚・井土浦地域にある東谷地地区は、東日本大震災の津波の影響により干潟を形成する汽水域の状態となり、一度は生態系が破壊されてしまいましたが、間もなく多様な動植物が生息する自然豊かな領域として再生しようとする兆しが見えてきました。そこで、県による堤防復元工事でもし汽水域が閉塞すれば干潟が陸化して生物多様性が失われてしまうことから、仙台河川国道事務所が井土浦環境懇談会を設置して、堤防復旧に当たっての環境保全対策を検討しました。また、仙台市議会の有志は、干潟の環境保全に配慮して堤防の復旧を行うよう申し入れを行いました。これらを受けて、県では復旧される堤防に3カ所の通水口を設置し、その結果、干潟の環境は守られ、今では自然愛好家を初め多くの人が訪れる憩いの場所となっています。ここの位置関係を見ますと、国土交通省が名取川に設置した船着き場から舟を使って直接アクセスが可能と思われます。
そこで、小項目1 舟運事業において仙台市の藤塚・井土浦地域をコースに組み入れ、魅力を高めるべきに対する市長の御見解をお伺いいたします。
市長
平成30年度の舟運事業については、8月11日から9月2日までの土日、うち、台風の影響で1日欠航しましたので、定期運航としての実績は、延べ7日間の運航で28便、227人となりました。平成31年度以降は、7月から9月までの土日に運航していただくことで運航事業者と協議が調っております。
新たな運航ルートの拡充という御提案ですが、運航事業者の公募の際、将来ルートも含めた事業提案を受けておりますが、仙台市の藤塚・井土浦地域までのルートは含まれていない状況です。また、平成30年度の運航を踏まえ、運航ルートの水深確保や取り切れない瓦れきの対応など、新たな課題も見えてきたところです。
舟運事業の魅力を高めるべきという視点については全く同意見ですが、新たな課題への対応、運航事業者の人的あるいは資機材の充足状況、さらには事業の採算性など、今直ちに運航事業者と運航ルートの拡充について協議をする状況にはないことを御理解いただきたいと思います。
吉田
貞山運河にある瓦れきがまだ撤去されていなくてしゅんせつが必要だとお伺いしたことがありますが、そういうことも、もし仙台市と連携ができれば進みぐあいにスピード感が出てくると思います。やはりそういうところは大きい都市の力をかりていくことも必要かと思います。もちろん運航事業者がもうルートを決めているということですから、すぐに変更はできないと思いますが、こういう話を持ちかけてみることは決してお互いにとってマイナスになることではありませんので、進めていただければと思います。
次に移ります。
ことしは熊野那智神社の御創建からちょうど1,300年の年に当たっています。この節目の年に、閖上のまちびらきが行われるのに合わせて、約20年間途絶えていた民俗行事お浜降りを復活させる計画が進められています。伝統文化の次世代への継承のために尽力されている関係者の皆様には、深く敬意を表したいと思います。
このことにも関連して、小項目2ですが、熊野信仰にゆかりの深い地域との間で観光振興のための連携を進めるべきに対する市長の御見解をお伺いいたします。
市長
熊野信仰にゆかりの深い地域との観光連携については、本市に熊野三社があるといった御縁から、熊野信仰発祥である紀伊の熊野三山の一つ、熊野速玉大社のある和歌山県新宮市と平成20年10月に姉妹都市の盟約を結んでおり、ふるさと名取秋まつりにおける物産品販売や、平成30年9月の熊野三山シンポジウムの開催などを通じ、交流や連携を図っております。
全国には熊野三山の祭神を勧請された神社が3,000社を超えると言われています。このように熊野信仰は全国津々浦々に広がっておりますが、あくまで中心地は紀伊の熊野三山であり、それ以外の地域との観光連携については、名取の熊野信仰とのかかわりを見きわめた上で考える必要があると捉えております。
吉田
今市長がおっしゃったように、熊野という名前をつけた神社は全国に本当にたくさんあります。その中でも今の紀伊の熊野三山のほかに島根県に熊野大社というのがありまして、市長は御存じかと思いますが、こちらは出雲国風土記という昔書かれた書物にも名前が載っているほどの非常に歴史のあるところで、観光客も大変多く訪れている状況です。幸いなことに出雲空港と仙台空港が直行便で結ばれ、アクセスが非常によくなっています。そこで、出雲空港などで名取にも熊野三社があるということをPRするのは、島根県の方にも興味を持っていただくという点で大変有効かと思いますが、そういった取り組みはいかがでしょうか。
市長
議員から今御提案いただいた中身について、直行便ということですので、向こうに行く、向こうから来ていただくという相互の交流がより深まればいいと思っております。そういう観点では一つの大きなヒントではないかと思います。ただ、まず、本家といいますか、紀伊の熊野三山とのパイプをより太くしていくことに重きを置きたいという気持ちはあります。
吉田
紀伊の熊野三山に行くパイプは、今、非常に細いのです。交通アクセスが非常に悪いので。ただ、熊野古道の分岐点にある和歌山県田辺市に南紀白浜空港がありますが、そちらと仙台空港が直行便で結ばれたら大変行きやすくなります。そういうことを市長として何か提案していただくということはありませんでしょうか。
市長
以前、私が別の仕事をしていたときに、和歌山県に行くときに利用させていただいたことがあって、大変便利に思ったことがあります。ただ、今、市長の立場として、そうしたことについて言及していくことはどうかと。なかなか言いづらいところです。そういった御縁があればいいと思いますが、それを市として積極的に推進していくのは少し早いのではないかと思います。
吉田
市長はいろいろなPRが非常に上手なので、こういったことに積極的に取り組んでいただきたいと、私は個人的に期待をしております。
また、熊野というと、秋保にもかつて熊野神社だった神社があり、今は秋保神社となって、羽生結弦さんが参拝して非常に有名になっていますが、そういうところとも熊野つながりで何か連携していけるのではないかと思います。私は、名取の熊野三社から秋保まで歩いていけるトレイルの道をつくって、これを例えば熊野古道ではなく熊野新道と名づけたり、そういう案を持っています。こういったことは個人的な趣味のような面もありますが、今後、市長にもぜひ検討していただきたいと思います。
小項目3です。仙台空港アクセス線に隣接する空港周辺地域に大規模集客施設を誘致できる環境を整えるべきに対する市長の御見解をお伺いいたします。
市長
北釜地区については、移転元地を利用して防災公園や防風林などの整備を進めておりますが、現在、土地利用事業化検討業務で、段階整備計画の策定に向け、企業ヒアリングによる企業の進出条件等の把握などを行っており、それらをもとに土地利用の計画策定を行いたいと考えております。
また、宮城県においては、将来の定住人口の減少を交流人口で補うべく、仙台空港の運用時間延長の取り組みを進めています。宮城県による地元への説明会では、空港の運用時間延長で期待される効果として、周辺地域の開発促進、航空機関連産業の集積、宿泊施設等の集客施設を含む企業立地の促進、物流拠点の形成、雇用の増加及び地域交通網の充実を掲げており、いずれは運用時間延長に伴う具体な地域振興策として空港周辺の環境整備を提案されるものと見込んでおり、本市では現在、県の動きを注視しているところです。
吉田
北釜に限らず、空港線の沿線にはまだ農地が広がっており、そこに大規模な施設をつくると数万人集まります。そういうスケールの大きい夢をぜひ描いていただきたい。例えば宮城球場は昭和25年に完成してから間もなく70年。これは老朽化が激しいために補修も間もなく限界が来ますので、東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地を空港の近くに誘致するというようなことをしていただきたい。それは東北楽天ゴールデンイーグルスにとってもそうですが、ファンにとっても鉄道で通えるなどのメリットがあります。また、御存じかと思いますが、北海道日本ハムファイターズは、自前で本拠地を札幌ドームから移して、北広島市に新しい駅をつくって球場をつくる計画も進めています。そういうことも可能性としてはどんどん広がっていきます。仙台空港を含めて、そして閖上の復興をかなえていくために、こういうスケールの大きなことを行っていただきたいと思います。市長の御意見をお伺いします。
議長
吉田議員、時間です。
本会議
(議案第21号 工事請負契約の変更)
吉田
工事の施工手順が変わると捉えたのですが、資料で黄色で示されている今回減工となる部分については、改めて発注をかけ直す形になるのでしょうか。
復興まちづくり課長
震災復興部長からの補足説明にもありましたが、今後、舗装工事の発注を予定しており、その中にこの部分を含めて発注したいという考えです。
(議案第22号 工事請負契約の変更)
吉田
資料の下にある閖上東地区Aゾーン盛土造成断面図で、今回変更追加工事の部分と平成31年度発注予定の部分があります。平成31年度発注予定が4万4,900立方メートルで今回の購入分よりも量が多いのですが、断面図では今回の変更のほうが盛り土の高さが高いように見えるので、平成31年度発注する予定の範囲といいますか、今回の追加工事以上に広がって次回は盛り土を行うということでよろしいのですか。
復興区画整理課長
断面図を見ていただくと、確かに高さとしては宅盤が4.1メートルということで平成31年度の発注分が多くなっています。この平成31年度分については、盛り土として必要な土量は1万3,000立方メートルほどですが、その上に宅造の地盤の圧密沈下を促進するための載荷盛り土を施工します。その載荷盛り土の分も含めると4万4,900立方メートルが必要ということです。
吉田
契約の手続など詳しくわからない部分があるので変なことを言っていたら申しわけないのですが、今回は変更追加ということで金額が増になるわけですが、次回の平成31年度は発注ということで別の施工業者を考えているのかと思うので、なぜ追加と新規の発注に分けたのかお伺いしたいと思います。
復興区画整理課長
今回の変更は、既に発注している断面図の黒い部分についての追加の変更となります。これはどういうことかというと、この断面図を見ていただくと区画道路が4カ所あり、その舗装の厚みが30センチメートル程度あります。それで、段階的な施工を考えておりまして、まずは赤い部分を盛って道路の面下まで仕上げたいと。それを施工基面と考えていますので、まずはここまで仕上げて、そして、平成31年度に道路の部分と一緒に宅地造成を行うということで、そこは新たに発注することになります。
(議案第23号 和解及び損害賠償の額を定めること)
吉田
経緯がよくわからなかったので確認したいのですが、医療支援対象者の方が東北大学病院で装着して自宅に戻り、その後、保健センターの職員がそれを取り外して専用ケースにしまったということでしたが、職員が取り外すのは病院からの指示だったということでよろしいのですか。
保健センター所長
まず、この心電計は24時間測定のものでした。平成30年11月26日に東北大学病院に医療支援対象者の方と保健センターの保健師が行きまして、その方に心電計を装着して24時間データを測定しました。翌日に保健師が医療支援対象者宅を伺って、心電計を取り外して専用ケースに収納して持ち帰ってきたわけですが、健康福祉部長の補足説明にあったように、その方が糖尿病性網膜症のため失明の危険性がかなり高く手術を必要としているといったこともあり、管理については、その後の通院の際に返すことを東北大学病院と約束し、その間の保管に関しては保健センターで行ったということです。
吉田
それは保健センターとして厚意で行ったわけであって、本来の貸し借りについては、あくまでも病院側と患者側、医療支援対象者との関係ではないかと思うのですが、そのあたりの整理をもう少し具体的にお伺いしたいと思います。
保健センター所長
議員御指摘のとおり、借り受けの話になりますと、あくまでも所有者は東北大学病院、借りる側は当該医療支援対象者となります。もちろん借受書の取り交わしもその場で行い、本来であれば借受者であるその方が署名しますが、目が不自由で署名がかなわなかったため、一応代理人ということで同行した保健センターの保健師が署名しました。ですから、本来は借りた方が保管しますが、先ほど御説明したとおり目の病気で失明の危険性があって物を見るのもなかなか難しいということで、保健センターの保健師が保管したということです。
(議案第24号 平成30年度名取市一般会計補正予算)
吉田
8ページ、9ページの13款1項4目土木使用料の2節駐車場使用料が減額となっていますが、駐車場ごとの増減の内訳をお伺いしたいと思います。
土木課長
今回の駐車場使用料の減額158万4,000円の内訳として、名取駅東口駐車場が254万8,200円の減額、名取駅西口駐車場は93万円の増額、館腰駅西口駐車場は3万4,700円の増額、合計158万4,000円の減額となります。
吉田
名取駅東口駐車場が大きく減額になっているのは、複合ビルの建設時に駐車場が一部閉鎖されたためなどではないかと思うのですが、逆に名取駅西口駐車場のほうは大きく増額になっていたり、全体的な増減をどのように分析しているのかお伺いしたいと思います。
土木課長
名取駅東口駐車場は254万8,200円の減額と金額が大きいのですが、内訳を調べると、議員がおっしゃったとおり駐車場の利用制限期間があったことが理由として1つあります。それから、当初予算において前年度実績をもとにして算定しますが、前年度実績として平成28年10月から平成29年9月までの1年間の実績をもとにしたところ、その期間は増田の名取駅前地区市街地再開発事業が工事の時期に入っており、その作業員等も含めて駐車場を多く使っていて、臨時的な利用まで含めて実績として見たために過大な積算になり減額の幅が広がったということです。
吉田
8ページ、9ページの13款1項4目土木使用料の4節住宅使用料で復興公営住宅の現年度分があります。平成30年12月に全ての復興公営住宅が完成し、その後、一般募集も開始しているということですが、一般の方の使用料もこれに含まれていると捉えてよろしいのでしょうか。
復興まちづくり課長
議員おっしゃるとおり、復興公営住宅に若干空室がありますので、今、その空室解消のために一般募集という形で入居者を募集しております。今回は、一般募集の一番最初の10月募集の方が1月から入居できたので、その分についての補正計上です。
吉田
そうすると、平成31年1月の段階で空室は何戸として計算したのでしょうか。
復興まちづくり課長
空き戸数ということではなく、今回入居された16戸分の増額計上となっています。
吉田
14、15ページの14款2項2目民生費国庫補助金3節家庭児童福祉費の児童虐待・DV対策等総合支援事業費について、恐らく当初予算にはなかったと思うのですが、この支援の内容をお伺いしたいと思います。
こども支援課長
内容は家庭児童相談員の人件費になります。家庭児童相談員3名中、2名分を計上しています。
吉田
家庭児童相談員の報酬のようですが、最近、悲惨な児童虐待のケースなどが全国から聞こえてきているところですが、これは相談を受ける側であり、そのようなことを未然に防止するといった趣旨の事業として捉えてよろしいのですか。
こども支援課長
主には相談を受ける側の人件費の補助金となっております。
吉田
22、23ページ、15款2項6目教育費県補助金の3節社会教育費です。当初予算額から大幅に減となっているコミュニティ復興支援事業費補助金の減額の理由をお伺いいたします。
生涯学習課長
コミュニティ復興支援事業費補助金の内容ですが、平成30年度においては、地域学校協働活動について、地域の方々や団体、その他住民の方々の参画を求めながら本部設置に向けて取り組み、地域と学校の連携として組織づくりを主に行ってきました。本部設置について地域並びに学校から理解を求めるべく整理してきましたが、検討だけに終わりました。具体的には、教育委員会内部で、市内の小中学校の校長、教頭を含めて地域学校協働活動の本部設置に係る検討委員会を立ち上げ、全5回会議を行いました。その中で、平成31年度以降、モデル校を指定して本事業を進めることになりました。
吉田
現状でも、本部を設置しなくても学校と地域との連携が非常にうまくいっているケースもあります。本部を設置するということで、平成31年度に課題が先送りされたような内容かと思うのですが、平成30年度中に事業がうまく回らなかったことに鑑みて、どのような点を次に生かしていくといいますか、教訓にしていこうと捉えているのかお伺いしたいと思います。
生涯学習課長
本部設置に向けて検討してきたと答弁しましたが、まずは平成31年度ではモデル校を設置し、その中にコーディネーターを配置し、学校と地域を結びつけられるよう決定したものです。
吉田
28、29ページです。31ページも関連するかと思いますが、20款5項2目雑入の2節違約金として工事請負契約の解除に伴う違約金とあります。念のために、相手方も含めてこの違約金の内容をお伺いします。
財政課長
御指摘の違約金と、次のページの20款5項2目雑入12節返還金の工事請負契約の解除に伴う前払金返還金は同じ要因となっています。中身は、平成29年度に株式会社エムテック仙台支店と広浦北釜線(仮称)仙台空港線鉄道横断橋梁工事(上部工)を契約しましたが、その後、契約解除となりましたので、29ページの違約金はそれに伴う違約金として契約金額2億4,300万円の30%相当額を受け入れるものです。31ページの前払金返還金については、契約金額の40%相当額9,720万円を前払金として支払っていましたので、その返還を受けるという内容です。
吉田
金額的に大型の倒産であったと記憶していますが、この違約金について、今の説明の算定で確かに金額はそうなるのでしょうが、実際に返還される見込みというか、現状で期限が設定されているのかなど、どのような形で返還を求めるのか具体的にお伺いしたいと思います。
財政課長
違約金については、契約の際に三井住友海上火災保険株式会社の工事の履行保証を取りつけていますので、そちらと協議し、平成31年3月15日までの納期限で納めていただく予定です。前払金の9,720万円については、平成30年11月末に入金済みとなっています。
吉田
36、37ページの2款1項18目空港対策費19節負担金補助及び交付金の仙台空港国直轄事業負担金の国直轄事業の内容をお伺いいたします。
政策企画課長
この国直轄事業負担金は国が行う仙台空港B滑走路の耐震改修に係る工事に対する負担金です。
吉田
仙台空港の国の直轄事業を本市が一部負担するという考え方の根拠はどういったところにあるのでしょうか。
政策企画課長
まず、国直轄事業負担金の3分の1については都道府県が負担するとの規定が空港法にあり、宮城県が3分の1を負担することになっています。また、県の負担金については、所在市町村を含め県内の関係自治体に負担させることができるとなっております。この県から市町村への負担金に関しては、昭和62年に仙台市、名取市、岩沼市でそれぞれの負担割合について取り決めを行っておりまして、県負担分の2.7%に相当する額を本市で負担するものです。
吉田
42、43ページの2款5項2目諸統計調査費の8節報償費、住宅・土地統計調査協力記念品とあり、金額としてはそれほど大きくはないのですが、当初で計上された分が全額減となっている理由をお伺いいたします。
市政情報課長
報償費ですが、記念品ということで、住宅・土地統計調査に御協力いただいた方へ粗品を差し上げるという趣旨で1万5,000円を計上していたところです。これは前回の調査を参考にしたわけですが、実際には調査対象者が2,500件を超えることになり、謝礼の意味をあらわす粗品を用意できる状態ではないということで、要は贈呈を取りやめたため減額を計上しています。
吉田
ただいまの説明で理解できない部分があるのですが、2,500件の調査について担当している方がいて、その2,500件は全てしっかり調査されていて、それだけの調査であれば粗品ではなくて別な形で何かお礼をするということなのか。なぜ粗品を差し上げないことになったのかもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。
市政情報課長
この調査に限らず粗品を差し上げる場合、一般的に例えばウエットティッシュや台所用品程度をかつて差し上げていた経過があります。ただ、前回は1,960件だったと思いますが、件数がふえたことと、件数で割り算をしますと金額が10円に満たないことになって、なかなか準備が難しいというのが実情です。
吉田
58、59ページです。4款1項4目健康増進費の22節補償補填及び賠償金で先ほど議題となった医療機器紛失賠償金が計上されているわけですが、この件で賠償金の金額を決定する際に法律の専門家の御意見はどのぐらい聞いたのか、その経緯をお伺いしたいと思います。
保健センター所長
額の決定について専門家の意見というお話ですが、金額そのものに関して専門家の査定等は市ではお願いしていません。ただ、和解を結ぶに当たり、金額というか要求されるものについて、例えば、物品のレンタル料や損害額などのほかに、その間にかかる人件費分等の請求もあるのかという点については顧問弁護士に相談をして、そういったものはないと確認させていただいています。
吉田
顧問弁護士への相談で済んだのであれば、弁護士への報酬のような形で別に支払うものはなかったということでよろしいですね。
保健センター所長
議員お見込みのとおりです。
吉田
64、65ページ、7款1項2目商工振興費22節補償補填及び賠償金で宮城県信用保証協会損失補償金とあります。これは、中小企業振興資金融資などを利用した方が実際に信用保証協会に損失を発生させた場合に市でも負担するらしいのですが、今回の件数をお伺いしたいと思います。
商工観光課長
今回、損失補償金の対象になったのは1件です。
吉田
現状では、全体の損失の中で本市が負担するのは何%ですか。
商工観光課長
損失補償金については、計算がいろいろとあるのですが、代位弁済が生じる場合には、まず80%は日本政策金融公庫が保証します。残りの20%分のうちの20%を金融機関が保証することになります。その残りの分についてを宮城県信用保証協会が40%と市が60%の保証を行うという形になっています。
吉田
70、71ページの8款6項1目住宅管理費13節委託料の市営住宅跡地利活用調査委託料が減額になっている理由をお伺いいたします。
都市計画課長
委託料の額が確定したために、差額を減額補正するものです。
吉田
額が確定しても調査が終了したわけではないと思うのですが、調査としては平成30年度にはどのあたりまで進捗するのでしょうか。
都市計画課長
業務の内容としては、跡地の利活用の方針の検討と、入居者の移転方針の検討という2本柱で調査を進めています。住民アンケートや庁内関係部署にもアンケートをとりまして、利活用の調査を行っております。あとは、入居者については移転先等の意向を聞いたり、それに伴う移転補償の考え方等を検討しました。
吉田
70、71ページの8款6項1目住宅管理費15節工事請負費の名取団地空家解体工事の減についても内容をお伺いします。
都市計画課長
これも工事請負金額が確定したための減額補正ですが、当初の見込みでは9棟を解体する予定でしたが、平成30年度末で11棟解体することができました。
吉田
そうなると、この補正予算が可決した段階で残りは何棟になるのでしょうか。
都市計画課長
残りは15棟となっております。
吉田
78、79ページの10款2項2目教育振興費19節負担金補助及び交付金ですが、小学校体育連盟助成金が当初76万円から大きく減額になっている理由についてお伺いいたします。
学校教育課長
小学校6年生が一堂に会して行う陸上競技大会について、平成30年度は予備日も含めて雨天のため中止になったことから、バスの輸送費を減額したものです。
吉田
そうすると、これは初めから用途が決まっている助成金であって、小学校体育連盟としてストックしておくことはできない種類のものと捉えてよろしいですか。
学校教育課長
おっしゃるとおりです。
吉田
82、83ページの10款5項3目社会教育振興費13節委託料、体験学習等機会提供委託料が全額減となっておりますが、内容をお伺いいたします。
生涯学習課長
午前に申し上げた内容と関連しますが、平成31年度に向けて地域学校協働事業が始まるということで本部を設置するわけですが、それに伴う支出額として関連する8節報償費から13節委託料までが減額となります。
吉田
84、85ページの10款5項4目図書館費19節負担金補助及び交付金の名取駅前市街地再開発組合事務費等負担金です。ここは図書館費の費目ですが、公民館費のほうにはこの負担金は計上されていないようです。また、88、89ページの災害復旧費のほうには計上されていますが、どのような考え方で費目を分けて計上しているのですか。
生涯学習課長
議員からお話がありましたが、図書館費に計上されているのが図書館分となります。また、増田公民館の分については、御指摘のあった88ページ、89ページの11款6項2目社会教育施設災害復旧費の19節負担金補助及び交付金に計上されています。
吉田
そのほかに駐車場があったと思いますが、名取駅前市街地再開発組合の負担金としては駐車場の分は入っていないのでしょうが、平成30年12月に竣工して、名取駅前市街地再開発組合関連の負担金は今回のこの補正予算をもって全て清算終了と考えてよろしいのですか。
生涯学習課長
説明不足だったと思いますが、今回計上しているのは登記費用の負担分ということで、今回、土地、建物の登記が終了し、その分に対する事務費の負担金と捉えております。
総括質疑
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長より発言のお許しをいただきましたので、名和会を代表して、事前の通告に従い総括質疑を行います。
ことしは平成31年、平成最後の年です。間もなく第126代の天皇へと皇位継承が行われる予定となっています。思えば昭和という時代から2つ先の時代と、時代の変化を非常に感じております。昭和の時代には当たり前のようにあったことが今はなくなっていたり、逆に昭和の時代には想定もしていなかったさまざまな問題が現在私たちの目の前に横たわっています。そのようなことを地方自治体としても今後重要な課題として捉えていかなければならないことは自明のことです。
そして、この平成という30年間を振り返ってみますと、やはり日本列島が大きな災害に見舞われてきたということを感じます。こうした大きな災害を日本人全体が一緒になって力を合わせて乗り越えてきた、この経験を次の世代へとしっかり残して伝えていかなければなりません。
その意味では、この平成31年度の予算は、名取市として震災復興計画の最終年度、そして閖上のまちづくりという意味でも、次にしっかりつなげていけるものとして捉えていきたいと思います。それと同時に、今私たちの新しい課題となっている少子高齢化と日本全体の人口減少という問題は、本市としても決して人ごとではありません。
そのようなことを考えていくと、何が大切なのか、やはり人づくりであると。次の世代を担っていく子供たち、そしてその子供たちを育てている保護者の世代に対する手当てが、今回の予算の中に色濃く反映されている部分があるという意味では、山田市長のカラーがようやく見えてきた気がします。ただ、それと同時に、財政上の厳しさなどさまざまな問題もありますので、そうした部分も含めて、この平成31年度の予算の審議の中で市長の思いと議会側の思いを交わすような審議にしていきたいと考えております。
では、具体的な内容に進んでいきたいと思います。
まず、大項目1 財政運営について、中項目1 財政運営についてお伺いいたします。
小項目1 財源不足との説明が毎年続いているが、財政運営の現状と目指すべきあり方をどのように捉えているのかお伺いいたします。
次に、小項目2 財政調整基金繰入金における通常分と復興分の内訳と、それぞれの残高を伺う。また、復興事業の完了が迫る中、通常分の事業についてどのような見通しを持って繰り入れを行ったのかお伺いいたします。
次に、小項目3 基金の運用による収入と利回りをどの程度と見込んでいるのかお伺いいたします。
続いて、大項目2 震災復興事業について、中項目1 震災復興事業についてお伺いいたします。
小項目1 閖上地区まちびらき事業は、住民や支援者が中心となり実行委員会形式で行われるが、市としてどのような構想を抱いているのか。また、市民全体で祝うという考え方は反映されるのかお伺いいたします。
最後に、大項目3 通常事業について、中項目1 総務費についてお伺いいたします。
小項目1 新たに始まる「こどもファンド事業」では、どのような人材を育成することを目標に、どのような方法で取り組むのかお伺いいたします。
次に、小項目2 名取市情報化基本計画の最終年度として、情報化推進重点項目の総仕上げにどのように取り組むのかお伺いいたします。
小項目3 年度内に3つの選挙が行われる予定だが、投票率向上と経費削減にどう取り組むのかお伺いいたします。
続いて、中項目2 民生費について。
小項目1 子供たちの健やかな成長を支える保育の運営者側にとっての現場の課題をどのように捉えて取り組むのかお伺いいたします。
小項目2 増田児童センターが小学校の教室を借用するに当たっては、小学校教職員とセンター職員との連携をどのように進めるのか。また、小学校の学習活動に対しどのような配慮を行うのかお伺いいたします。
次に、中項目3 土木費について。
小項目1 都市計画道路見直し検討は、市の道路交通網の将来像をどのように描いて取り組むのかお伺いいたします。
小項目2 名取団地空家解体計画はどこまで進捗する予定か。また、遅滞なく進めるためにどのような点に配慮するのかお伺いいたします。
次に、中項目4 消防費について。
小項目1 平成32年度からの救急車4台による救急救助体制の確立に向けて、職員や資機材の配置など消防組織機構の見直しにどのように取り組むのかお伺いいたします。
小項目2 新年度の女性消防吏員の採用は何名か。また、女性消防吏員が働くための環境整備にどのように取り組むのかお伺いいたします。
最後に、中項目5 教育費について伺います。
小項目1 教育振興基本計画策定事業は、これまでの方針と異なる狙いを持つのか。また、策定に当たっては本市の実情をどのように捉え、目標をどこに定めて取り組むのかお伺いいたします。
以上で総括質疑とさせていただきます。
市長
5番吉田 良議員の総括質疑に答弁いたします。
初めに、大項目1 財政運営について、小項目1 財政運営の現状と目指すべきあり方についてお尋ねをいただきました。
平成31年度予算の編成に当たっては、通常分、震災分の合計で18億3,500万円の財源不足額が生じ、同額を財政調整基金から取り崩し、対応を行ったところです。
市町村の財政運営においては、収支のバランスを適切に保ちつつ、将来世代に過大な負担を残さないことはもちろんですが、限られた財源を最大限有効に活用し、市民の皆様の負託に応えていくことが何より重要と考えており、常にそのような視点に立って持続可能な市政運営に取り組んでいるところです。
次に、小項目2 財政調整基金繰入金についてお尋ねをいただきました。
財政調整基金繰入金の内訳としては、通常分が9億7,629万1,000円、復興分が8億5,870万9,000円、合計では18億3,500万円となっており、また、平成31年度末時点における見込み残高は、きのう可決いただいた2月補正後の残高を期首残高とした場合、通常分が19億9,776万円、復興分が12億8,854万6,000円、合計で32億8,630万6,000円になるものと見込んでいるところです。
財政調整基金のうち震災分については、復興事業の進展に伴い、いずれかのタイミングで全額を執行する性質のものと捉えておりますが、通常分については、今後とも持続可能な財政運営を進めていく上で一定規模の残高を保持していく必要があるものであり、中期的な財政収支見通しを念頭に、年度間のバランスに配慮した基金管理に努めていきたいと考えているものです。
小項目3 基金の運用による収入と利回りについてお尋ねをいただきました。
基金運用に係る収入については、予算編成時点(平成30年10月末現在)における各基金の平成30年度末現在高見込額に定期預金利率0.01%の利子収入を見込み、一般会計においては、財産運用収入として143万4,000円を見込んでいるものです。低金利の状況の中、基金運用に係る収益増を図るため、安全かつ効率的な管理運用の方策について検討していきたいと考えているところです。
次に、大項目2 震災復興事業について、閖上地区のまちびらき事業についてお尋ねをいただきました。
閖上地区まちびらきは、本市の復興に御支援をいただいた全ての方々に感謝する機会であり、市を挙げて実施すべく、各種団体、学校、企業などから成る実行委員会を組織して検討しております。
まちびらきの実施内容については、市民団体や地元小中学生、市内高校生などが参加するプレゼン大会を行ったほか、実行委員会に参加を希望する団体を随時受け入れるなど、広く参加と提案を募りながら、より多くの市民に参加いただけるよう検討を進めております。
現時点におけるまちびらきの概要は、メーン会場となる閖上公民館において式典を行い、その後、隣接する中央公園のステージにおいて演奏や演舞などを行う予定となっております。また、サブ会場として、かわまちてらす閖上、水産加工団地、震災メモリアル公園、ゆりあげ港朝市など7カ所を予定しており、それぞれの会場の特色を生かしながら、飲食・物販、施設見学、パネル展、スタンプラリーなどを行いたいと考えております。
市では、今後、各地区の公民館で説明会を行い、広報なとりやパンフレットなどによりまちびらきについて広く周知し、多くの市民と一緒にまちびらきを祝いたいと考えております。
次に、大項目3 通常事業について、中項目1 総務費中、小項目1 「こどもファンド事業」についてお尋ねをいただきました。
新たに取り組む「こどもファンド事業」は、「自分の住んでいるまちは自分たちで考える」をコンセプトに、子供のときから主体的にまちづくり活動へ参加することでまちづくりの楽しさ、大切さを学び、将来の活動へとつなげることを狙いとし、創造力や行動力、郷土愛を兼ね備えた人材を育成することを目標としております。また、この活動に大人の協力を組み込むことで、地域活動に対する大人の関心も高まることを期待しているものです。
「こどもファンド事業」の仕組みですが、事業を提案するのも審査するのも18歳未満の子供が行い、20歳以上の大人が活動をサポートするものとなっています。提案者の要件は、市内に在住または市内の学校に通学する子供3人以上のグループで、大人が2名以上サポートすることとしており、1グループ10万円以内で交付する補助金により事業を行うこととしております。
次に、小項目2 名取市情報化基本計画についてお尋ねをいただきました。
名取市情報化基本計画の情報化推進重点項目のうち、「ICTを利活用した行政サービスの向上」に掲げた26項目の具体的施策に関しては、その約8割に当たる21項目について業務運用を開始しております。
平成31年度については、この業務運用を開始しているものについて、安定的な稼働の維持、機能の強化に努めるほか、新たに情報取得環境充実の一環として、増田、閖上を除く各公民館と市民体育館に公衆無線LANの整備を計画しているところです。
一方で、平成26年度から27年度にかけて関係自治体と検討協議を重ねたものの、結果として、その枠組みでの導入をしないこととした自治体クラウドなど業務運用に至っていない項目や、ICT環境の変化により見直しを要する項目などについては、研究・検討を継続するよう努めていきます。
また、「行政事務の効率化」に掲げた「住民情報系、内部情報系システム」の運用、「人材育成と情報セキュリティ対策の強化」の項目については、引き続きシステムの安定稼働やセキュリティー対策に努めるとともに、eラーニングを活用した職員研修などに取り組んでいきます。
次に、小項目3 選挙の投票率向上と経費削減についてお尋ねをいただきました。
平成31年度に任期満了を迎える選挙については、国及び県からの委託費に基づいて執行するもの、または経費の全額を市費により執行するものであり、投票率向上に向けた選挙啓発などの取り組みは、その執行費用を負担する主体が中心となって推進するものと捉えております。
本市の選挙管理委員会では、投票率向上のため、市内大型ショッピングセンターでの街頭啓発や、前回の選挙より開始した市内高校における若年層をターゲットとした啓発活動等を継続していく予定です。また、閖上地区においては、平成31年7月に執行予定の参議院議員通常選挙より、新たに閖上公民館及び高柳地区集会所の2つの投票所を設けることとしております。
各種選挙の執行においては、大前提として、ミスのない公正公平かつ迅速な選挙執行が求められるものです。一概に経費削減を図ることは難しい状況ではありますが、可能な限り経費削減には意を用い、他自治体の動向も注視しながら、今後も適正な選挙執行に取り組んでいきたいと考えております。
次に、中項目2 民生費中、小項目1 保育の運営者側にとっての現場の課題についてお尋ねをいただきました。
子供たちの健やかな成長を支える保育の運営者側にとっての現場の課題は保育士の確保であり、このことが安心・安全な保育の提供につながるものと捉えております。保育士の確保については、民間事業者の責任で対応していただくこととなっておりますので、市としては、民間事業者に対し、国や県で取り組んでいる保育士の確保を図る事業等について、引き続き情報交換や情報提供を行っていきたいと考えております。
なお、公立保育所における保育士については、人材紹介手数料を昨年度に引き続き予算措置し、保育士の確保に努めていきます。
次に、小項目2 増田児童センターが小学校の教室を借用することについてお尋ねをいただきました。
増田放課後児童クラブでは、平成31年4月からの利用登録児童数が急激に増加したことにより、増田児童センターのみで受け入れることが困難となったことから、平成31年度より増田小学校1階の図工室をお借りして事業を実施いたします。
図工室は授業で使用する教室でもあることから、利用に際しては、学校と定期的に連絡調整を行うことにより、増田小学校の教職員と増田児童センター職員とで学校行事や活動内容の情報の共有化を図り、連携を進めていきたいと考えております。また、利用する時間帯は放課後ですが、学習活動を実施している際には室内で静かに過ごすような活動内容とし、学習活動の妨げとならないよう配慮していきます。
次に、中項目3 土木費中、小項目1 都市計画道路の見直しについて御質疑をいただきました。
都市計画道路は、交通機能や防災機能の役割を担い、都市の将来像の実現のために必要な重要な都市施設です。しかしながら、都市計画道路の中には、都市計画決定以降、長期間未着手となっている路線も多く、社会情勢やライフスタイル等が大きく変化していることなどを踏まえ、本市の都市計画道路網のあり方について、見直しの作業を進めているところです。
本市の都市計画道路の将来像については、先般策定した名取市都市計画マスタープランにおいて、高速道路インターチェンジへのアクセス道路や産業立地を促進する交通基盤の整備等と位置づけており、飛躍する力を生み出す高い広域交通利便性を創出していくものです。
なお、業務については平成31年度完了予定で、見直し方針案が確定しましたら、説明会を実施し、市民との合意形成を図っていきたいと考えております。
小項目2 名取団地の解体についてお尋ねをいただきました。
名取団地の空き家解体については、平成30年度中に11棟の解体を完了しております。残りは15棟と集会所になりますが、平成31年度において現在入居者のいない3棟を解体、平成32年度に残る12棟と集会所を解体し、解体事業を完了する予定としております。
なお、平成32年度解体予定の12棟には現在入居者がおり、平成31年度中の移転をお願いすることとしておりますので、解体スケジュールに影響が出ないよう、円滑な移転手続に努めていきたいと考えております。
次に、中項目4 消防費について、小項目1 救急救助体制の確立に関するお問い合わせをいただきました。
先般、提案理由で申し上げたとおり、平成32年度からの救急車4台による救急救助体制の確立を目指していくために、隊員の確保に加え、新たに高規格救急自動車1台と、あわせて高度救命処置用資機材の整備を進めていきます。
また、救急救命士の新規養成と救急現場の実践的な教育指導体制の充実、さらに地域医療機関との連携強化・円滑化を担うため、新たに指導的立場の救急救命士を養成し配置することで、救急業務全般の質の向上につながるものと考えております。
次に、小項目2 女性消防吏員の採用と環境整備についてお尋ねをいただきました。
平成31年度の消防職員の新規採用はありません。
女性消防吏員が働くための環境整備については、初めて女性消防吏員を採用した平成30年度において、当直勤務をする際の施設として、消防署に女性用の仮眠室、シャワー室を整備しました。平成31年度については、設備の充実を図っていきたいと考えております。
また、名取市特定事業主行動計画に基づき、女性消防吏員が働きやすい環境を整備し、ワーク・ライフ・バランスのとれた職場環境の整備に取り組んでいきたいと考えております。
次に、中項目5 教育費中、小項目1 教育振興基本計画策定事業についてお尋ねをいただきました。
教育振興基本計画策定事業については、平成27年度から平成32年度までの計画期間としている「教育等の振興に関する施策の大綱」の内容を基本とし、長期総合計画と同様に1年間計画期間を前倒しし、平成31年度から計画策定作業に着手するものです。
策定に当たっては、第五次長期総合計画で掲げた教育分野の施策や大綱に掲げた施策の評価を行い、ただいま策定している第六次長期総合計画の教育施策の各項目と整合を図ることとしております。これまでの方針と異なる狙いを持つのかとの御質疑ですが、大綱のかわりとなるものですので、異なる狙いを持つものではないと伺っております。
また、教育委員会では、学校教育の分野において教育に関する意識調査を小学校、中学校、義務教育学校の保護者等を対象に実施し、その結果を計画に反映させるとのことです。
具体的な目標設定については、策定の段階において外部委員を含め検討していきますが、アンケート結果や国の教育振興基本計画を参酌した上で、長期的な視点での目標設定となると聞いております。
以上、5番吉田 良議員の総括質疑への答弁といたします。
財務常任委員会
吉田
6、7ページの1款1項1目個人分ですが、現年課税分の均等割で前年度に比較して153人の増を見込んでいるということです。この153人という考え方についてお伺いします。
税務課長
市民税個人分の均等割の納税義務者の見込み数ですが、平成29年9月末現在の人口と平成30年度の当初課税の納税義務者数により、人口に占める納税義務者の割合を算出しております。また、平成30年度の当初課税の納税義務者と平成30年9月末での納税義務者数により、納税義務者の伸び率を算出し、平成30年9月末の人口に占める納税義務者の割合と伸び率を乗じて納税義務者を見込み、均等割の納税義務者数について153人の増を見込んだところです。
吉田
人口の伸び率を予測してということかと思いますが、人口としては全体でどのぐらいの伸びを予測されているのでしょうか。
税務課長
人口の伸びではなく現在の時点を捉えておりますので、人口対人口の伸び率ではなく、人口に占める納税義務者の割合の伸び率を勘定しているということです。
吉田
先日、報道で知ったのですが、岩沼市でスマートフォン決済による市民税等の徴収が平成31年4月から開始されるということでした。平成31年度は本市においてそういう取り組みはあるのでしょうか。
税務課長
内部的には検討しているところですが、平成31年度はこれまで同様の納付手法でお願いするということで考えております。
吉田
納付のチャンネルをふやしていく必要性は随分前から議論になっているようですが、今回の報道では岩沼市のほかに亘理町、山元町、涌谷町、七ヶ浜町などでも4月から開始するということで、やはりいろいろと検討を前向きに進めていくべきときではないかと思います。例えば市民税個人分の現年課税分では調定見込みは98%となっております。チャンネルをふやすことによって直ちにこれが上がることにはつながらないかもしれませんが、今回98%として残りの2%、これも100%に近づけていく努力が必要かと思いますが、そういった意味で、調定額をふやしていくための新たな取り組み、あるいは強化すべきと捉えている取り組みが何かあったらお聞きしたいと思います。
税務課長
収納率の向上のために滞納整理なども行っております。また、納期内納付をお願いしており、平成31年度においてもこれまで同様の取り組みとなりますが、こちらの予算上の係数の掛け方については、あくまでも調定見込額ということで、予算を見込むときの考え方として仮に個人市民税については98%の係数を掛けているということです。これを初めから100で計上するのも一つだとは思いますが、現実には決算の際に歳入欠陥になりますと、これはまた別の問題も生じますので、このような数字を使っているということで御理解を賜りたいと思います。
吉田
先日の一般質問の際に、人事院勧告の件で、名取市内の50人を超える従業員を抱える法人数が97と御答弁いただきました。地方税法の第312条の第1号から第9号までの法人の中で、2・4・6・8・9号法人がそれに当たると理解していますが、実際に正規職員だけでなくパートなどの非正規職員も算定の仕方によってそこに人数として含まれていくような考え方があろうかと思いますが、そのあたりはどのように事務処理をされているのかお伺いします。
税務課長
法人税の均等割については、その区分が資本金と従業員数によって決められています。お尋ねの従業員数の捉え方ですが、その法人が賃金、手当、賞与等の支払いを受けている者を従業員数に算定するということで、1日アルバイトであっても1人とカウントされてくると。あくまでも基準になる日にちに支払ったのであればカウントされると捉えております。
吉田
例えばパートで3時間だけ働いた方も正社員で一日中働いている方も同じ1人として扱うというのは、この法の考え方からいうと少し疑問があるのですが、余り予算から離れてもよくないので、この6、7ページの市民税法人分の均等割の部分で、実際には今回法人数がプラス13法人となっていますが、パート従業員や正規の従業員の数が企業ごとにどのように増減しているかというところまでの把握はされていないということでよろしいですか。
税務課長
委員お見込みのとおりです。
吉田
6、7ページ、1款2項1目固定資産税の現年課税分で、家屋の新築を450棟と見込んでいるという説明でした。この450という棟数の考え方についてお伺いいたします。
税務課長
これまでの経過、新築家屋の傾向を捉えて棟数を見込んだところですが、見込む時点で既に建築確認をとって建築に着手し未完成であったところだけでなく、当然、年度中にも建築を始めて竣工するところがありますので、これについてはあくまでも見込みで、このくらいは見込めるだろうというところの棟数ということです。
吉田
例えば家屋といっても戸建て住宅なのか集合住宅なのか、あるいは地区別にどういった地区に多く新築されるとか、そのような見通しなどを何かお持ちでしたらお伺いしたいと思います。
税務課長
仮に今マンションをつくっていて竣工まで2年かかるというところが見えれば、その部分はまさに見込むところですが、地域の個別状況を鑑みてというのではなく、市域を面として見たときにこのくらいは見込めるだろうと。どこの地区で何棟、どこの地区で何棟と積み上げたものではなく、面として捉えていると御理解いただきたいと思います。
吉田
8、9ページの1款3項1目軽自動車税ですが、市制施行60周年記念事業でカーナくんのナンバープレートを新たに作成しました。あのナンバープレートをつけて走ってもらえればそれなりに市のPRにもつながるかと思いますが、平成31年度、あのナンバープレートを利用してくれる方の見込みは何か考えていらっしゃるでしょうか。
税務課長
市制施行60周年記念事業ということでオリジナルナンバープレートを作成しました。その数は、50cc、90cc、125cc、それぞれ300枚、100枚、100枚ということで500枚作成したところです。今後とも市のホームページ等を通じてのPR、また、バイク販売店もしくは所有者が希望されればということで、あくまでも従来型とオリジナルナンバープレートが並行していますので、そちらをお勧めしながらやっていきたいと考えております。
吉田
町なかを走っていても余り見かけないのです。それで、今、新年度の見込み数をお伺いしたのですが、明確に見込みは立てていないということかもしれませんが、平成30年度の実績をどのように反映させていくというか、平成30年度の時点でわかっている件数があれば、お伺いしたいと思います。
税務課長
トータルで133台です。
吉田
14、15ページの8款1項1目自動車取得税交付金ですが、自動車税の税率などが変わったり環境性能割が導入されるということで、影響額2,000万円の減と。そして、その減額の割合が28.6%ということがきのうの補足説明であったと記憶しています。この28.6%というのは全国のどの自治体も同じような計算をすれば必ずこういう数字になるということで、名取市だけ特別な事情があるわけではないということでよろしいですか。
財政課長
もともとは自動車取得税交付金からスタートすることになりますが、自動車を取得する段階で課税されるものです。ほかの市町村でも台数、割合等が本市と同じであれば同じようなことがあるかもしれませんが、市町村ごとに取得台数が違っていますので、同じような割合で減になることは考えられないところです。
吉田
20、21ページの13款2項2目衛生手数料の墓地管理手数料ですが、昨日の御説明で、8カ月分を4,000円で200基と見込んでいるということで、これは8月から徴収するということであろうかと思います。ということは、8月の段階では200区画にお墓を設置していただくということかと思いますが、この200という数字は全体の受け入れ可能な数からすると少ないのかなという気がしますが、その後ふえていくこともしっかり見越した上で、そちらについては補正で処理するという考え方でよろしいですか。
クリーン対策課長
委員お見込みのとおりです。
吉田
もともと利用したい方がどのぐらいいるかという調査に基づいて区画数を決めておられると思いますので、順調に使用者がふえてくるものかと思います。ただ、なかなか待てずに既にお墓をつくってしまった方もいるかと思いますので、実際、全部が埋まるということは難しいかと思います。そうした被災者等で埋まらなかった部分を一般の方が前倒しして申し込みができるようなことについての検討はあったのでしょうか。
クリーン対策課長
こちらの市民墓地の被災者の部分の取り扱いですが、一般市民墓地分の応募自体が平成32年7月から開始ということで、まだそちらの実績も見えていない状況ですので、そちらの応募などの状況も加味しないと、例えば一般市民墓地分である程度不足が生じる見込みが出てきたとか、そういったことも、被災者墓地分で埋まらない部分があったときの取り扱いについて検討するときに考えなければいけないと思っています。今後の推移を見ながら、一般墓地の利用については検討したいと考えているところです。
吉田
40、41ページの14款3項1目総務費国庫委託金4節統計調査費でお伺いいたします。国勢調査が平成32年度に予定されているということで、今回、国勢調査調査区設定委託金が含まれているようですが、調査区設定というのはどのように進んでいくのか、内容をお伺いしたいと思います。
市政情報課長
国勢調査調査区設定委託金ですが、2020年に国勢調査が実施されます。この前準備として、具体的に平成27年度の実績でお答えすると、調査区を530ほど設定しております。それから、調査区要図という図面を542枚ほど作成しております。この実績をもとに、同様の事務を平成31年度に行っていくということです。
吉田
平成32年度ということですと、行政区長が一般職になるのか住民に委託になるのかまだ決まっていないようですが、こういう国勢調査に実際に当たってくれていた行政区長も結構いたかと思います。そのあたりの制度変更に関しての対策として、平成31年度中に何か取り組むことがあれば教えていただきたいと思います。
市政情報課長
国勢調査については調査員を多数必要とします。現在のところ、登録調査員は79名となっています。国勢調査に向けて調査員の確保を図っていくことになりますが、行政区長についての何らかの対策は特別考えておりません。
吉田
50、51ページの15款1項3目消防費県負担金で、宮城県林野火災防ぎょ訓練負担金ですが、平成31年度は名取市が会場だという御説明を受けました。今回計上されている金額は、全体でかかる費用のうちの、割合としてはどのぐらいということなのでしょうか。
防災安全課長
宮城県林野火災防ぎょ訓練については、平成25年度より消防の単位として県内12ブロックで輪番制で実施しているものであり、平成31年度は名取市で行います。この負担金については、訓練に要した経費の2分の1に相当する分の金額を県が負担するもので、限度額が150万円と決まっております。歳入は県負担金として150万円の予算を要求しておりますが、歳出としては550万円ほど予算計上しております。
吉田
訓練の2分の1ということで、訓練以外にもいろいろと費用がかかるということで550万円ほどになっているようですが、最終的に事業が終わった際には、当初の予算の枠の中で少し縮小になったとしても県にお返しする必要はないという認識でよろしいですか。
防災安全課長
これについては、2分の1で150万円限度ということですので、例えば300万円を割った場合については少なくなるという形になります。
吉田
50、51ページの15款2項1目総務費県補助金の2節総合振興費の宮城の松林健全化事業費、こちらは補足説明では松くい虫の防除や薬剤注入ということでした。松くい虫の被害は非常に大きく広がっていて深刻化していると伺っていますが、今回のこの補助金を防除などで使うために、被害のレベルなどに何か基準はあるのでしょうか。
農林水産課長
今回の宮城の松林健全化事業は、松くい虫防除のために樹幹注入剤を注入するという事業です。この松については、松くい虫の被害木ではなく、まだ松くい虫の被害を受けていない松を対象とした樹幹注入剤の注入事業ということです。
吉田
本数としておおよそ何本分ぐらいになるのでしょうか。
農林水産課長
今回の事業の本数としては39本を見込んでおります。この39本については、実は5年前に実施した十三塚公園内の松39本と同じものに、再度、松くい虫の防除のために樹幹注入を行うものです。
吉田
58、59ページの15款3項1目総務費県委託金の1節総務管理費の県広報配布委託金です。計算してみると、年4回発行で世帯数で考えると単価として5円を少し超えるぐらいかと思います。これも区長制度の話で申しわけありませんが、5円とか6円で普通の紙1枚を配ってもらうのが普通のポスティング業者でやっとのところかと思いますが、こういう冊子のようになっている行政の広報紙などを配っていただくとなると、民間であればかなりお金がかかるところではないかと思います。今後の区長制度の見直しに向けて、平成31年度中にこの県の広報紙の扱い方についてはどのように検討されていくのかお伺いいたします。
総務課長
まず、こちらの委託金の金額の中身ですが、こちらは1回につき1世帯当たり配布手数料が7円、それから事務費として1円50銭ということで、1世帯当たり8円50銭での計算になります。平成32年度から毎月発行が奇数月発行の年6回に変わっておりますので、その回数と世帯数を掛けた金額が予算額となっているところです。また、この金額については県から示されている金額ですので、それをもとに今回予算を計上したということです。
吉田
58、59ページ、15款3項1目総務費県委託金の2節に知事権限移譲事務費というのがあります。こちらの内容と、前年度から増額になった理由についてお伺いいたします。
政策企画課長
こちらの知事権限移譲事務交付金については、条例によって県知事の権限を市町村におろして市町村が実施した事務に対する事務費相当の交付金となります。
この交付金の仕組みですが、対象となる年度の前々年度、ですから平成31年度で申し上げると平成29年度の実績の処理件数に県が定める単価を乗じて概算の交付額を算出して、それを交付するというのが1つです。それから、同じく前々年度ですが、平成29年度当時は概算で交付しておりますので、それをその平成29年度の実績に応じて精算します。この精算をした上で、項目ごとに精算の額がプラスになれば追加の交付、マイナスになれば歳出で返還をするといった中身になっています。ですので、今回、平成31年度予算の中で大きく増加するのは、平成29年度の概算の際の件数が、精算したことによって、それよりも件数が多かったことが増額の理由になるものです。今回200万円ほどの増額になっていますが、この主な要因としては、農地の賃貸借契約の解約に係る事務が、いわゆる農業の担い手の集約ということで法人に集約されたということで、賃貸借契約の解除件数が平成29年度に多かった、つまり平成28年度に比べて多かったということになりますが、そういったことによって今回交付額が増になったものです。
吉田
条例によるという御説明でしたが、それは県条例ということでしょうか。済みません、私も勉強不足でこれからもう少しそういう勉強をしていかなければいけないと思いますが、例えば道路標示で警察が引かなければならない白線などが消えていたとしても、警察にお願いしなければ引いてもらえないと。何かの工事のついでに市として引ければスピード感を持ってできるようなことも、県が動いてくれなければできないので大変時間がかかるような部分があります。名取市から、そういうものの権限を移してくれというようなお願いはできないものなのでしょうか。
政策企画課長
今お尋ねにあったのは施設の管理権限の話かと思いますので、この歳入の中にある知事の権限移譲、条例によって移譲するという中身とは異なるものと理解しています。先ほど答弁の中で平成28年度に比べてと申し上げましたが、あくまで平成29年度の概算と精算の差によって今回の金額になっているということです。
吉田
70、71ページの20款5項2目雑入9節の学校給食費実費徴収金ですが、滞納繰越分をこの金額に設定した考え方についてお伺いいたします。
学校教育課長
給食の現年度の収納率は、平成27年度99.43%、平成28年度99.57%、平成29年度99.68%と、平成27年度から大変高い収納率の推移となっており、99%の後半をキープしているところです。今年度と過年度の滞納分についておよそ2,165万6,000円と見込んでいるところであり、それに目標の収納率30%を掛け、滞納繰越分について649万6,000円と計上した次第です。
吉田
順調に収納率が100%に近づいて伸びてきているということで、教育委員会の努力のたまものかと思います。2,165万円ほどが未納としての今までのトータルで、その30%ということですが、これは何年前ぐらいからの金額か、わからなければいいですので、わかる範囲でお願いいたします。
学校教育課長
今年度については把握しておりますが、何年度前からの分の滞納がそのような形になっているのかについては把握をしておりません。
吉田
72、73ページの21款1項1目総務債です。1節通信設備整備債で公衆無線LAN整備事業に対する起債とありますが、こちらは総括質疑の際に増田、閖上を除く公民館と市民体育館に整備していくという答弁がありましたので、恐らくそのための財源かと思いますが、なぜ起債という形での財源確保となったのか。750万円という金額ですので、大小さまざまな事業がある中で、何か手当てすることは十分できるのではないかと思いますが、ここで起債とした理由をお伺いします。
財政課長
公衆無線LAN整備事業に対する起債については、緊急防災・減災事業債のメニューの中で対応できる部分でしたので、今回こちらを活用したところです。
吉田
その起債をすることによって、例えば何割かが国庫で賄われるとか、何かそういうメリットがあるということでよろしいですか。
財政課長
委員御指摘のとおり、こちらの緊急防災・減災事業債については交付税措置があり、元利償還金の70%が後年度交付税で見られるという内容のものです。
吉田
80、81ページの2款1項1目一般管理費13節委託料で、会計年度任用職員制度導入支援委託料の内容をお伺いいたします。
総務課長
これについては先般の2月補正の債務負担行為でお認めいただいた内容です。中身としては、来年4月から始まる会計年度任用職員制度をスムーズに進めるために、見識のある業者にお願いして、職員の研修や関連例規の整備、そして内部調整に係る方針決定のアドバイスなどをいただく意味での委託料です。
吉田
見識のある業者とおっしゃいましたが、制度の導入に当たって、業者を使わずに、外部に依存することなく、市の組織の中でしっかり検討しながら進めていくといった考え方はなかったのでしょうか。
総務課長
確かに市の内部でもそのような検討はしましたが、なかなか広範囲にわたる例規の改正や中身の調査など専門的な部分もありますので、ここは先ほど申し上げたような実績のある業者にお願いしたいという考えで計上したものです。
吉田
82、83ページ、2款1項1一般管理費18節備品購入費の公用自動車購入費についてもう少しお聞きしたいのですが、自動車の車種や仕様について現時点で検討している内容がありましたら教えていただきたいと思います。
政策企画課長
現在検討している車種という御質疑ですが、発注の関係もありますのでタイプということで答弁いたします。ミニバンタイプの多人数乗車、7名程度の定員の車両で、環境に配慮したハイブリッド車両ということで検討しております。
吉田
現在の普通の乗用車タイプからより多くの人が乗れるタイプに変わるようですが、その理由をお伺いします。
政策企画課長
市長公用車の運行に際して、市長が1人で乗車する場合もありますが、職員と一緒に乗車して車中で事務の打ち合わせ等が行えるようにということを踏まえて、現在のセダンタイプではなくミニバンタイプでの更新を考えているところです。
吉田
84、85ページの2款1項2目文書費13節委託料、住民リスト印刷等委託料は、平成30年度から庁舎内の印刷機ではなくて外部に委託を始めたと平成30年度予算審査の際にも御答弁いただいていますが、これについても委託先の決め方をお伺いしたいと思います。
総務課長
取り扱うデータが住民データですので、本市の住民基本台帳ネットワークシステムデータを管理している業者です。
吉田
昨年の御答弁でもそのような説明でしたが、住民の情報、個人情報ということで取り扱いには細心の注意を払わなければいけないと思います。情報の保護については契約の中身で決めているという御答弁でしたが、住民情報、個人情報の保護をどのように確保していくかということについて、契約の中身をもう少し詳しく伺いたいと思います。
総務課長
個人情報保護対策については、委員御指摘のとおり契約の中できちんと明記されていますが、そのほかにシステム上でも、本市と委託業者を物理的に閉鎖した専用回線で結んでおり、市でつくった異動データはほかの誰にも見られない独立した回線で委託業者のサーバーに行くようになっております。そこから委託業者が出力をするという形で、物理的にも守られているところです。
吉田
90、91ページの2款1項7目財産管理費で、13節委託料に契約システム導入委託料、14節使用料及び賃借料に契約管理システム利用料とあります。これは関連があるのかと思ったのですが、契約システムの導入の内容をお伺いいたします。
財政課長
契約システム導入委託料については、平成31年度で新たに計上しております。これは発注から契約まで一連の事務手続を行えるシステムです。工事の例を挙げますと、現在、まず担当課で起工伺を行って、その後、契約担当課ということで財政課に依頼が来ます。そこから指名委員会であれば業者選定、一般競争入札であれば条件設定といった手続を行い、指名委員会の資料を作成します。その後、確定したら、選定業者の指定、指名通知の打ち出し、入札公告の打ち出し、そして入札執行となります。入札執行に当たりましても、予定価格調書の作成や入札調書、入札結果、そういったものの事務手続等を経て、最終的にようやく契約を締結できるという流れです。現在、それぞれエクセルなど別々に管理をしていますが、今回このシステムを導入することによってこの一連の流れを全部できるという内部事務のシステムとなっています。
契約管理システム利用料については、このシステムはクラウドを考えておりまして、そのシステム利用料、またLGWANを使いますのでその利用料となっています。
吉田
発注から契約に至るまでの一連の流れが迅速化するのだと思いますが、具体的に何日分ぐらい、何カ月分ぐらい早くなるのか、それは細かいので持ち合わせていなければ結構です。
それから、入札する業者のメリットとしてはどのような点を捉えているのかお伺いしたいと思います。
財政課長
まず業者のメリットですが、先ほど御答弁申し上げたとおり、あくまで内部事務の簡素化というか省力化に寄与するシステムですので、それは特にないものと考えております。
それから、どれほど省力化できるのかということですが、現在、契約については職員2名体制で事務を行っています。入札日が近づけば入札関連の事務にそれなりの時間を費やしているところですので、担当の考えからしますと、かなり事務は省力化できるのではないかと期待しております。
吉田
同じく新たな都市交通システム導入可能性調査委託料についてお伺いします。平成30年9月定例会に一般質問で市長に地下鉄に関して今後の見通しと仙台市側の考え方を確認させていただいたところ、その時点では、仙台市に対して事務レベルでの協議の場の設置をお願いしているという御答弁でしたが、もうそのときから調査委託料を次年度に計上しようという考え方は持っていたのでしょうか。
政策企画課長
仙台市側とは具体的に延伸についての協議というところまでを行っているのではなく、あくまで事務レベルでの勉強会ということで、今後どのように進めていくのがいいのかということで相談を申し上げているといった内容です。その中で、今回計上している調査委託料については、仙台市に対して具体的にこういったもので進めていくと御相談しているものではなく、そのような整理をしていくのにどういったことを今後進めていくのがいいのか、そういったアドバイスをいただいた際に、富谷市でもこのような調査をされているので参考にされではどうですかというアドバイスをいただいたわけです。この調査費の予算化等について仙台市と具体的に意見交換を行っているということではありません。
吉田
それは先ほども御答弁の中にあったのでわかっているのですが、前述の一般質問の際、市長からは、宮城県が仙台市などと一緒に取り組んでいるパーソントリップ調査の結果を見ながら検討するということでした。この平成31年度の本市の調査が、パーソントリップ調査として宮城県が行っている部分とどのように関連づけられるのか。もしパーソントリップ調査で同じようなことを調査しているのであれば、あえて本市独自の調査をしなくてもいいのではないかと思うのですが、そのあたりの整理をお伺いしたいと思います。
政策企画課長
パーソントリップ調査については、仙台都市圏の中の人あるいは物の移動等に着目しての調査と理解していますが、この調査の中では、現在走っていない交通体系を前提とした結果が得られるものではないと理解をしておりますので、各自治体間の移動等の数字等がパーソントリップ調査で明らかになれば、それらをこの調査検討の中に取り入れて、その上で可能性等について検討をお願いするということで考えております。
吉田
同じく新たな都市交通システム導入可能性調査委託料です。可能性調査となっていますので、調査の結果は、可能性ありとかなしとか、ありとしたら何%など、どのような形の結果を求めていくのかまだ少し見えないのです。先ほどからの御説明だと、どこに駅を設置したら何人利用して、どのルートを通ればどのぐらいの費用がかかる、そのようなイメージを持っているのかと思いますが、実際に可能性が本当にあるのかないのかという部分まで調査の結果としてどのようにあらわそうと考えているのでしょうか。
政策企画課長
具体的な整備あるいは運行に係る運営費用等についての調査委託を考えています。ただ、可能性について具体的に何%と示すのではなく、例えば、こういった条件が一番可能性が高いとなった際に、その条件として例えば運行区間がどのぐらいの距離であるとか、あるいはそれに並行してまちづくりもこういった規模で行われないと採算的に厳しいなど、そういった条件をつけて可能性が示されることはあるかと思いますが、具体的に何%の確率で可能性があるといったような結論は難しいと考えております。
吉田
調査するまでもなく、可能性はゼロ%だと思うのです。というのは、まず仙台市の持ち物ですし、調査の結果、予算が何百億円という数字が必ず出てきます。それは調査をしなくても誰でもわかることだと思うのです。どのルートを通しても結局そのぐらいお金がかかるわけです、地下でも地上でも。そうなったときに、ではどのようにその何百億円の財源を確保するのかということまで考えなければ、可能性とは言えないと思います。お金をどこから調達してくるのか。仙台市が出すなりいろいろな方法があるのでしょうが、それらも可能性の中に含まれると思います。例えば、先ほど政策企画課長からは第三セクターという話もありましたが、市長は平成30年9月定例会の一般質問では第三セクターは考えていないと、あくまで仙台市が主体になってと答弁していますので、そのような結果になるのかと思いますが、何百億円というお金をどのように用意するのかという部分の調査もこの中に含まれていると捉えてよろしいのですか。
政策企画課長
委員からお尋ねのあった事業を行うための財源をどこが負担するのかということについては、この調査には含めないと現時点では考えております。
吉田
102、103ページの2款1項17目市民活動促進費19節負担金補助及び交付金、こどもファンド事業補助金についてお伺いします。コンセプトが非常におもしろいと個人的に思っていますが、確認したいのが審査するのも18歳未満の子供だという点です。先ほどのスケジュールで審査会を7月に開く予定ということで、恐らくここで事業の審査が行われると思いますが、審査をする子供を選ぶ方法をどのように考えているのかお聞きしたいと思います。
男女共同・市民参画推進室長
審査員については、事業と同様に公募の形で審査員になる児童生徒を募集するということで考えております。
吉田
公募によって応募した方の中から選ぶことになるわけで、その選ばれた審査員としての子供がこの事業に申請したグループのいろいろな企画の審査を行いますが、審査の段階で、選ばれた審査員は、全く市の職員などの影響を受けずに、本当に自分たちの考えだけ反映させて審査するという流れになるのですか。
男女共同・市民参画推進室長
子供審査員になった方については、事前に研修を行いまして、事業の審査についての基準といったものを子供の中で話し合いをして決めていただき、その審査基準に従って審査を行うという流れを考えています。その際にアドバイザーとして入っていただく早稲田大学の先生を今想定していますが、その方にそういった流れについてレクチャーをしていただきながら、進め方については指導をしていただきますが、基本的には子供たちがみずから考えることを大事にしていますので、その点で市の職員が関与するといったことは直接的にはないと考えております。
ただ、実際の審査会の中では、子供の視点での審査に加えて、大人アドバイザーの方を委嘱し、審査とはまた別に、その方から大人の視点として事業に取り組む上でのアドバイスをもらうことは考えています。
吉田
同じ改製原戸籍廃棄委託料ですが、紙から電子化されたということで、戸籍は一つの重要な文化遺産とも定義できる面もあるかと思うのですが、電子化に漏れている部分はないのですか。4万枚保管されている分の電子化はどのように行われたのですか。コピー的な形で丸々書面を写真のように写したのか、それとも数字や文字だけをデータ化、デジタル化しているのかお伺いします。
市民課長
中身については、原戸籍を1枚ずつスキャナーで読み取って、現在戸籍システムにおいて運用しています。全部、原戸籍は戸籍システムに現物と同じ形で保管されている状態ですので、紙のものとデータ化されてシステムに入っているもの、同じものが2つ保管されているのが現在の状況です。
吉田
スキャンしているということであれば現物の状態についてわかるかと思いますが、そのスキャンしたデータの保管の期限といいますか、今後どのぐらい確実に保管されるのか。将来的に年月がたつとそれが消えていく可能性はないということでよろしいですか。
市民課長
戸籍システムの中に取り込まれているデータなので、消えてなくなることはないと捉えております。
吉田
114、115ページで、2款4項1目選挙管理委員会費13節委託料の選挙システム改修委託料の内容についてお伺いします。
選挙管理委員会事務局長
これは元号改正に伴うシステムの改修です。
吉田
116、117ページ、2款4項3目参議院議員通常選挙費12節役務費の投票用紙計数機等点検調整料です。この計数機は本市の持ち物でしょうか、そのあたりの内容をお伺いしたいと思います。
選挙管理委員会事務局長
これは本市の備品になりまして、内容として、投票用紙の自動交付機34台ほか、開票のときに必要となる読取分類機といったものの点検の経費です。
吉田
平成31年度に選挙が3回立て続けにありますので、点検はその都度必要になるのでしょうか。近く行われるので、1回点検して次までもたせるようなことはやはり計数上不都合があるのか、考え方を確認させてください。
選挙管理委員会事務局長
これは選挙のたびに点検を行うものと認識しております。
吉田
144、145ページの3款3項1目児童福祉総務費14節使用料及び賃借料で子育て支援拠点施設テナント借上料ですが、何カ月分で、家賃のほかに含まれているものがあれば御説明をお願いします。
こども支援課長
借上料については4月から来年3月までの12カ月分です。
吉田
そうすると、4月1日からもう運営できる状況と捉えていいのか、もう一つ、敷金のようなものは発生していないのかお伺いします。
こども支援課長
開設時期は平成31年4月19日です。敷金については今回は発生しておりません。
吉田
155ページの3款3項5目児童措置費20節扶助費、母子生活支援施設入所措置費の内容をお伺いいたします。
こども支援課長
これは、DV被害者の入所施設、母、子供2人分の措置費です。
吉田
今回、どのような考え方でこの金額を見込んだのかお伺いいたします。
こども支援課長
この施設は年間の運営費、生活費を入所世帯数で割って負担するようになっています。今回、本市分として1世帯分を負担するものです。
吉田
162、163ページ、3款3項11目幼児教育振興費19節負担金補助及び交付金の被災幼児私立幼稚園就園奨励費補助金が平成30年度に比べて減となっています。幼児教育の無償化などの影響を見込んだのかと思うのですが、この補助金の対象者数なども含めて減の理由をお伺いいたします。
こども支援課長
人数については47名分です。これは、ふたば幼稚園が子ども・子育て支援新制度に移行するということで減額となっております。
吉田
この制度そのものがよくわからないのですが、被災幼児の被災というと震災に遭った方かと思いますが、震災からもう8年経過していますので、震災以前に生まれた子供で幼稚園児はいないのではないかと思うのですが、47名の対象者の定義をお伺いします。
こども支援課長
被災した親の子供ということになりまして、これについては県からの補助が10分の10入ってくることになっています。
吉田
176、177ページの19節負担金補助及び交付金で歯と口と健康のつどい助成金とありますが、この集いの内容をお伺いいたします。
保健センター所長
歯と口と健康のつどいについては、岩沼歯科医師会と自治体の共同主催の形で開催するイベントでして、岩沼歯科医師会の管轄が岩沼市、名取市、亘理町、山元町の2市2町になります。2市2町で2年ずつの持ち回りで開催しており、本市の開催が平成31年度、平成32年度の2カ年になります。イベントの内容は、6月4日が過去に虫歯予防デーとされていたこともあり、口内ケアの大事な点を皆さんに周知を図る月間ということで、それに合わせて開催時期を6月に設定しています。今年度は6月1日に名取市文化会館で開催しまして、自治体の負担金については2市2町とも30万円を基準にしていますので、本市においても平成31年度は30万円を計上しているところです。
吉田
これは岩沼歯科医師会と自治体の共同主催ということで、あくまでも歯科医師のための会ではなく、一般の方を対象に虫歯予防の考え方を周知するということかと思いますが、この会についての周知の進め方をお伺いしたいと思います。
保健センター所長
周知方法については、既にホームページにもイベントの一部である例えば川柳などの作品募集を掲載し、また虫歯がない方の表彰を考えています。あとは簡単な寸劇のようなものをお見せして口内ケアの大切さをPRしたいと考えており、いろいろなイベントを当日詰め込んで皆さんにお見せしようと考えております。
先ほど作品の募集をお話ししましたが、開催のお知らせについても、広報なとり、ホームページ、またポスターも作成して市内の関係機関に張って周知に努めたいと考えております。
吉田
180、181ページ、4款1項8目環境保全対策費1節報酬で環境審議会委員報酬(11名)となっています。平成29年に選出された委員数はたしか今13名いると思いますが、ここで11名となっている理由をお伺いいたします。
クリーン対策課長
委員おっしゃるとおり、環境審議会の委員は現在13名で構成しています。ただ、そのうち公務員であるため報酬を出さない委員が2名いますので、予算上、報酬をお支払いするのは11名となります。
吉田
平成31年度中に改選を迎えますので、もしかすると定数15名いっぱいにまでふえることも見込まなければいけないのかと思うのですが、ここで11名となっているのはその分の見込みがないということかどうか伺います。
それから、報酬の額については、例えば専門的に研究している方は現在は入っていませんが、そのような方に委嘱する際に報酬額が人によって変わることはあるのか、特定の資格を持った方は少し高い金額になることはあり得るのかお伺いしたいと思います。
クリーン対策課長
環境審議会では平成31年度においては、予算書の同じページにありますが、第二次環境基本計画の策定の2年目です。2年目の主な活動内容としては、いろいろな調査の結果を踏まえた素案を作成して、その内容についてお諮りいただきます。そのため、現在11名で予算措置しているところですが、定員15名以内で人数に余裕があるので、必要に応じて補正等で増員も検討する可能性はあると考えております。ただ、今のところ決定事項ではありませんで、一応検討していきたいというところにとどまっているところですので当初予算には反映しておりません。
吉田
184、185ページ、4款1項14目墓地運営費13節委託料、墓地管理等委託料です。実際の墓地の管理体制について、何名で管理するのか、また、以前に議員協議会でも一部御説明があったかと思いますが、例えば何時から何時まで職員をどのように配置するかなど、決まっていることがあったら教えていただきたいと思います。
クリーン対策課長
運営時間については細部はまだ決まっていないところもありますが、管理にかかわる人の配置としては、平日においては1人、日曜祝日は2人、そしてお盆、お彼岸といった繁忙期は3名を現在考えております。
吉田
188、189ページ、4款2項2目リサイクル推進費19節負担金補助及び交付金、生ごみ堆肥化容器購入費補助金です。金額は変わっていないので、補助の上限の台数や補助の金額なども恐らく変わっていないと思いますが、毎年どうしても残額が出てしまうということで、新年度の普及に向けての取り組みをどのように考えているのかお伺いしたいと思います。
クリーン対策課長
平成31年度予算のこの補助金については、委員お見込みのとおり内容は平成30年度と変更はありません。ただ、周知については、確かに委員御指摘のとおり、なかなかふえている傾向とは言いがたい状況です。当然、広報周知をより強化しなければならないと考えていますが、今のところ、ホームページや広報なとり等で周知していますが、アピールが足りないところはありますので、この制度についてより理解していただいた上で何かできるようなことを考えていきたいと思います。
吉田
さきに一般質問でお伺いした際に、平成31年度は補助の額は据え置くが、平成32年度以降の引き上げに向けての検討を平成31年度中に行うというお話でしたが、いつごろをめどに結論を出すスケジュールかお伺いします。
クリーン対策課長
この補助金の単価の値上げについては平成32年度を目標にということですが、先ほどの答弁でも申し上げたとおり、近々の状況と他市町村の金額といった状況を踏まえながら見直しを検討していきます。一応予定としては、平成32年度当初予算に計上できればという目標で検討を進める考えです。
吉田
192、193ページ、5款1項1目労働諸費の(公社)名取市シルバー人材センター補助金ですが、こちらは前年度に比較して増となっています。この理由についてお伺いいたします。
介護長寿課長
(公社)名取市シルバー人材センター補助金は、まず、国と同額であることが基本です。平成31年度のシルバー人材センターにおける国の関連予算について、高齢者活用・現役世代雇用サポート事業の交付基準が見直され、今回、平成31年度予算が大きく増額しているものです。今まで高齢者活用・現役世代雇用サポート事業の就業延べ人員により交付額が示されておりましたが、平成31年度は会員数の実績と就業延べ人員から算出することとなり、さらにはその会員数の増加割合に応じた加算、それから女性会員の増加割合に応じた加算が加わることになったものです。
吉田
では、新年度の会員数の見込みについて、今おっしゃった女性会員の数なども含めて、現時点で捉えているところをお伺いしたいと思います。
介護長寿課長
見込み数については名取市シルバー人材センターから伺っておりませんが、先ほど申し上げた会員数の増加割合を申し上げます。平成29年11月現在と平成30年11月現在の人数を比較した増加率になります。平成29年11月現在、男304人、女101人、合計405人です。平成30年11月現在は、男314人、女111人、合計425人です。これにより会員の増加割合は4.9%ということで、加算額が45万円となります。それから、女性会員については9.9%の増で、加算が20万円ほどついております。
吉田
202、203ページ、6款1項10目災害対策費の委託料、被災区域ほ場整備農地集積調査・調整委託料とあります。平成30年度から進められている事業かと思いますが、こちらの今後のスケジュールについてお伺いいたします。
農林水産課長
この事業については、圃場整備の関連で農地集積事業の管理表作成の委託料が主な内容となっています。こちらは歳入でも御質疑をいただいていますが、平成31年度は担い手の大幅な見直しを行うことから予算の増額を見込んでいるところです。平成30年度に引き続き農地の集積を図るということで、こういった管理表の作成業務を継続していきたいと考えております。
吉田
前年度から増額になっているということですが、平成31年度の課題をどのように捉えているのか、もしあればお伺いできればと思います。
農林水産課長
圃場整備もそうですが、やはりこれからは効率的な農業をいかに展開していくかということが課題になっています。そういった意味から、区画の整理をすることが一つですし、また、担い手に集積を行って効率的な農業経営をしていくということです。その一つの基礎となるのがこの管理表の作成ですので、これらを活用しながら進めていくことが課題の解決に結びついていくのではないかと思っております。
吉田
206、207ページの6款3項2目水産業振興費で、先ほどからのろ過海水供給施設のことでお伺いします。13節の委託料の中でお聞きしたいのですが、保守点検ということで、この空気だまりの状況などについても点検していくことになろうかと思いますが、このような構造になっているということは、当初これを設置する段階で見込まれていたつくりなのですか。それとも後になってそういう空気だまりが発生するという問題が発生したのか。そのあたりを御説明いただけないでしょうか。
農林水産課長
ろ過海水供給施設の配管の構造についての御質疑と捉えてお答えします。現場は南防波堤の外洋側から取水していると先ほどお答えしましたが、外洋側から取水しますと、一旦防波堤を越えて、その防波堤に沿って配管を敷設しておりますので、一旦高く上げて低いところに配置をするという設計でした。ポンプの能力等を考慮しますとそれでも取水可能だというものでした。当然現在も取水をしておりますので、能力的には十分そういった設計も見合っていたわけですが、結果的にはそのような事象が発生したということで、当初の設計段階ではなかなかそこまでは想定できなかったという状況です。
吉田
実際に設計の段階で想定できなかったことが出てきているようですが、これからも末永くこのろ過海水供給施設を使っていくに当たって、そのあたりの根本的な対処の進め方をどのようにお考えなのか、お伺いしたいと思います。
農林水産課長
今後、施設を稼働、運営していって、例えばポンプ等の交換が必要になったり空気だまりが出たりといったいろいろな課題がありますので、抜本的な改善が必要になってくるのかなとは考えております。当然、平成31年度予算の中には盛り込まれていないところですが、そのような計画や準備なども考えていかなければいけないと思っております。現状としては今の施設をいろいろと工夫し、また保守管理を徹底しながら、やはり水産業の振興という面では非常に重要な施設となっておりますので、今後も安定したろ過海水を供給できるように努めていきたいと考えております。
吉田
208、209ページの7款1項2目商工振興費、ふるさと寄附金の関連ですが、13節の委託料のふるさと寄附金特産品取扱委託料です。こちらについては、以前の質疑の中で、窓口となっている業者が4つあって、それぞれの手数料の割合が決まっているという説明があったと記憶しています。今回増額になっているのは利用する方がふえるということもあると思いますが、詳細にどの事業者、どの窓口がどのぐらいふえるとか、そういう見込みは何か立てていらっしゃるのでしょうか。
財政課長
こちらのふるさと寄附金特産品取扱委託料については、一般社団法人名取市観光物産協会に返礼品の発送などを委託しているものです。平成30年度に比べての増要因については、寄附金の受け入れ額を平成30年度は2億円としていたところですが、平成31年度では3億円と見込みを上げております。それに伴って委託料がふえているという内容のものです。
吉田
では私の勘違いなのか、インターネットサイト等によるふるさと納税の申し込み窓口に対しての手数料のようなものは、ここには含まれていないということですか。
財政課長
ただいま委員御指摘のポータルサイトの利用料については、87ページ、2款1項総務管理費の財政管理費の中の役務費、ふるさと寄附金代理納付手数料等に含まれております。209ページの委託料については、先ほど申し上げたとおり、一般社団法人名取市観光物産協会への委託料となっており、積算については月額は基本分と従量分で算定しておりますが、寄附金の受け入れ額がふえたことに伴う増となっているところです。
吉田
212、213ページの7款1項4目観光費の19節負担金補助及び交付金で、お浜降りイベント助成金についてお伺いいたします。こちらは総括質疑の際に市の未指定無形民俗文化財というお話がありました。長年途絶えてしまっていたものが、平成31年度、関係者の方の御努力で復活するということですが、この事業が行われることによって、本市の観光振興という意味でどのくらい効果があると捉えていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。
商工観光課長
こちらについては今回21年ぶりに開催することになりますが、熊野那智神社創建1300年、加えて閖上のまちびらきということで行うことになっております。その効果については、今も実際にイオンモール名取の中でみこしを披露していますが、市民の方々に知っていただくということもありますし、今回お浜降りを閖上のまちびらきと同じ日に行いますので、今まで復興に携わってきた方々も参加して見ていただけるということで、名取熊野三社について皆さんに認知していただけるという効果があると考えているところです。
吉田
いろいろな観光資源がある中で、こういう動きのあるものは人を呼び寄せる可能性を大きく持っているものではないかと思います。今後もこういう事業が続いていって、一番望ましいのは、市の補助なしに自立していくことであろうと思いますが、そういうところに向けて、平成31年度に限らず、市としての今後の見込みというか、取り組みの理想的なあり方とか、そういう部分をどう考えていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。
商工観光課長
このお浜降りについては、総括質疑でも説明しましたが、これまでも市制施行の節目などの機会に実施してきた経緯があります。本来であればどこまで市が補助するかについて考慮しなければならないということもありますが、今回21年ぶりということで、前回のことを覚えている方がなかなかいなくて、やはり10年に1回ぐらいは何とかしてほしいというお話をいただいています。その辺も含めて、基本的には市がイニシアチブをとって行うことではありませんので、そういった状況を踏まえながら検討していきたいと考えております。
吉田
212、213ページ、7款1項4目観光費の負担金補助及び交付金、なとり春まつり助成金、なとり夏まつり助成金、前のページにある7款1項2目商工観光費のふるさと名取秋まつり助成金も関連しているので一緒に質疑させていただきたいのですが、こういうイベントでたくさんの物販、食品の販売、またセリ鍋を初めとしておいしいものをたくさんいただくことができて、とても充実したお祭りですが、実際に物を売った後で問題となるのがごみです。出てくるごみに関して、恐らく分別をして回収していると思いますが、分別して集めた後の処理については、本当に分別をしっかり守って処理されているのかどうか、把握されていたらお伺いしたいと思います。
商工観光課長
ごみの処理については、基本的には分別をしていただくということで、特に秋まつりはエコステーションを設けて尚絅学院大学の学生の協力をいただきながら行っているところです。その後の処理については、その分別に沿ってごみ収集業者が処分をしているものと捉えています。
吉田
収集の際にせっかく分別していたものが、回収していく段階でみんな一緒になってしまっているのではないかという指摘を受けたことがあります。せっかく分別しているのに余り意味がないのではないかと受けとめられたのですが、そのあたりの徹底という面に関して、市の主催でないので何とも言えないかと思いますが、どの程度まで声がけをしていけるのか、その取り組みの考え方をお伺いしたいと思います。
商工観光課長
基本的には事業用ごみとして分別を行っていますが、それを収集する事業者については、分別されたごみの種別に基づいて処理をしていると捉えているところです。
吉田
220、221ページ、8款2項1目道路橋梁総務費で名取中央スマートIC関連調査委託料とありますが、この調査の中身についてお伺いいたします。
土木課長
今回、新たに名取中央スマートIC関連調査委託料を計上しています。これについては、名取中央スマートインターチェンジが平成29年3月に開通しましたが、運用開始後の社会便益や安全性、採算性、管理及び運営形態等について調査及びフォローアップを行い、名取中央スマートIC地区協議会を開催して報告、検証を行うための準備をするということで、今回委託料を計上しているところです。
吉田
報償費には名取中央スマートIC地区協議会委員謝礼も計上されていますので、その関連のようですが、大変多岐にわたる調査を行うように受けとめられました。開通後、これまでの利用者数の実績をどのように捉えての調査なのか、把握されている部分で教えていただきたいと思います。
土木課長
まず、開通後の交通量の台数ですが、計画交通量は1日当たり2,800台としておりましたが、平成31年2月の1カ月間の1日当たりの平均台数は3,300台で、約18%増になっているところです。
平成30年12月4日に第4回名取中央スマートIC地区協議会を開催しましたが、そこでは事業の経過や交通量の推移、事業関係の効果を説明しています。次回は平成31年度に開催する予定ですが、イオンモール名取も平成31年4月にリニューアルグランドオープンしますので、その後の交通量の推移や、インターチェンジをつくるときに整備効果を4つほど挙げていますので、それらの検証などを第5回の名取中央スマートIC地区協議会に報告したいということで、今回この委託料を計上しています。
吉田
230、231ページ、8款4項1目都市計画総務費の13節委託料、都市計画道路見直し検討委託料です。総括質疑でお伺いしたところ、「長期間未着手となっている路線も多く」という御答弁でしたが、未着手となっている路線の具体的な部分、どういったところを想定に入れての見直し検討と捉えていらっしゃるのでしょうか。
都市計画課長
歳入の質疑でも9路線と答弁していますが、仙台市と本市の市境にある中田線、中田南線、館腰駅箱塚線、愛島東部線で未整備の部分があると捉えております。
吉田
見直しというのは、具体的に都市計画道路ではない道路にするとか、どういう見直しになっていく可能性があるのか、そのあたりをお伺いしたいと思います。
都市計画課長
本市独自でできるわけではないので、長年未着手の部分などをピックアップして、宮城県や仙台市など関係機関に聞き取りをして意向を確認していく中で、そういったところを残すのか残さないのかということがわかってくると思います。それから、本市独自で整備を行っている館腰駅箱塚線や愛島東部線などは、せんだって名取市都市計画マスタープランもできましたが、20年後にはどうなっているのかというところも考えながら都市計画道路網図をつくっていくということで、見直していきたいと考えているところです。
吉田
232、233ページの8款4項3目県営事業負担金の負担金補助及び交付金の植松田高線県営事業負担金です。県の事業ですので把握されている範囲で結構ですが、平成31年度までの事業期間らしいのですが、その中でももう少し詳細なスケジュールなどがあれば教えていただきたいと思います。
土木課長
この負担金の中には、大手町下増田線と植松田高線の2つの都市計画道路の路線名が入っています。まず、大手町下増田線については、平成31年度は4号バイパスとの交差部であるせきのした交差点の改良工事などの工事費になります。植松田高線については、道路用地に係る物件補償費の再算定の費用ということで負担金を計上しております。
吉田
せきのした交差点というのは、例の1車線になってしまってそこがネックになって詰まってしまうところですが、そこが2車線になるということで、非常に多くの要望があった点です。
植松田高線のほうで特にお聞きしたいのですが、この路線が開通することによってさまざまな影響が出てくると思います。いい影響ももちろんですが、一つの例として、大手町下増田線のときにあったのですが、もともとごみの集積所だったところが道路になってしまったことにより集積所が置けなくなってしまい、非常に不便な思いをしているということで、事前にもう少し説明が欲しかったという地元の声も聞いております。この植松田高線についてはそのようなことがないように、住民の方への説明や意見の収集などについてどのくらい実施されているのか、どう把握されているのか、お伺いしたいと思います。
土木課長
この事業については、県の仙台土木事務所が事業主体となって工事を進めています。市としては、地元からのそういうお話はまだ受けておりません。ただ、受けた場合は、県の仙台土木事務所とその辺は調整しながら、地元等も含めて調整して、いい方向に持っていきたいと考えております。
吉田
232、233ページの8款4項5目コミュニティプラザ等管理費です。名取駅コミュニティプラザは、図書がたくさん置いてあったり新聞が置いてあったりしてミニ図書館のような位置づけで使う方が多かったかと思いますが、すぐ近くに名取市図書館がオープンしたこともあり、利用者の数などに影響が出てきているのではないかと思います。平成31年度の名取駅コミュニティプラザの運用について、何か変更点などがあったらお伝えいただきたいと思います。
都市計画課長
現在のところ、特別な変更点はありません。
吉田
立地もとてもいい場所ですので、今後そういう検討は必要になってくるのではないかと思いますが、今のところそういう検討を進めていくような流れはないのでしょうか。
都市計画課長
今のところ考えていないところですが、名取市図書館を利用する方と名取駅コミュニティプラザを利用する方そのものが少し違うのかなと思っています。名取市図書館は時間をゆっくりかけたい方だと思いますし、名取駅コミュニティプラザは電車の待ち時間などに使う方が主なのかなと思っています。新図書館ができてからの影響は今後4月以降に出てくるのではないかと思っていますので、そうなった時点で、指定管理をしている名取まちづくり株式会社と協議していきたいと考えています。
吉田
238、239ページの8款6項1目住宅管理費22節、移転補償金の内容について、件数なども含めてお伺いいたします。
都市計画課長
名取団地は現在解体しているわけですが、17世帯が入居しております。その方々の移転に伴う補償費として、1世帯当たり50万円の17世帯ということで850万円計上しております。
吉田
平成31年度中に全世帯に移転していただくことを目標として掲げていらっしゃるということでよろしいですか。
都市計画課長
移転期間としては平成31年4月から平成32年3月ぐらいまでということで、平成31年度内に何とか移転していただければと考えております。
吉田
244、245ページ、9款1項1目常備消防費の9節旅費です。新年度は新規の採用はないと総括質疑で答弁されたのですが、ここに計上されている消防学校等入校旅費はどのような方が入校されるのか、伺います。
消防本部総務課長
新年度の消防学校入校については、10名を予定しております。9専科、専科と申しますのは例えば火災調査といった専門業種に特化した専門的な学科ですが、9専科に10名を予定しております。
吉田
10名の方の研修期間はどのくらいなのか、伺います。
消防本部総務課長
専科の科目によって期間が違いますが、4泊5日もしくは1週間、2週間となっておりまして、科目ごとに期間が設定されております。
吉田
242、243ページ、9款1項1目常備消防費の全体的なことで伺います。先ほど病院搬送時間の短縮に向けて、タブレットによる県統一の病院検索の仕組みを導入するということでしたが、このために新たに必要となる予算については、今回どのようになっているのでしょうか。
消防署長
県とのタブレットを利用した医療機関の選定、県内各地の共通した認識をとるということで、現在検討の段階ですので、予算措置等々まではまだ至っておりません。
吉田
では、いつごろその検討の結果がはっきりしてくるのか、今わかっている範囲で結構ですので伺います。
消防署長
今、県が県内各地の消防本部を回っておりまして、医療機関の情報をこれから皆さんと共有しようという段階です。いつから始めるということはまだ決まっておりません。
吉田
250、251ページ、9款1項3目消防施設費の18節備品購入費で、小型動力ポンプ付積載車購入費、こちらの台数と配備される部について伺います。
警防課長
配備数は2台で、配備される部は増田分団7部、以前は村区と言っていましたが、今は杜せきのした一丁目と、愛島分団第1部、北目に小型動力ポンプ付積載車を更新します。また、増田のものは救助資機材搭載型の車両です。
吉田
この配備状況を見ると、平成9年式のポンプ車が3台、そのうちの1台が今回愛島1部ということで、その後も平成10年が4台、11年が3台と、ちょうどこの時期に一気に導入されてきたようです。今後の更新のスケジュールについて、今何か検討されているものがあれば伺います。
警防課長
更新計画に基づいて更新をしています。増田分団には救助資機材搭載型の車両が入っていませんでしたが、今回前倒しで増田分団第7部に配備しまして、配備する予定だった車が後になったということです。
吉田
250、251ページ、9款1項4目防災費の1節報酬、国民保護協議会委員報酬で伺います。前も指摘したのですが、この国民保護計画は平成19年に策定されたままでありまして、第四次長期総合計画当時の地図が残っていたり、人口が6万人台だったりということで、大分現状と差が出てきているのですが、新年度はこの見直しの検討はいかがでしょうか。
防災安全課長
委員御指摘のとおり、内容的には昔のままでありまして、平成31年度に見直しをしたいと考えております。
吉田
その見直しの内容や分量によっては、議会に諮らなければならないような規定もあったかと記憶しているのですが、そのあたりの進め方、内容や分量、議会に諮るのかどうか、今の時点で方針が決まっていれば伺います。
防災安全課長
担当課としては、国、県の計画と整合を図りながら平成31年度の見直しを進めていきたいと考えております。
吉田
254、255ページ、10款1項2目事務局費の1節報酬、子どもの心のケアハウス支援員報酬で伺います。子どもの心のケアハウスについては、新規の事業ということでいろいろ御説明いただいたところですが、もう少し詳しく、利用する子供さんの立場に立って、例えば実際にどういうサービスをその中で受けることができるのか、またその期間など、何かイメージがありましたら伺います。
学校教育課長
この事業は、登校が難しい状況にある児童生徒及びその保護者を支援するために、平成31年度から名取子どもの心のケアハウスといったものを設置し、不登校傾向にある児童生徒への初期対応や自立支援を、学校、関係機関と連携して行いながら、児童生徒の学校復帰支援を行っていくものです。総括質疑の答弁でもお話ししているところですが、具体的には3つの中身で考えております。
1点目は、心のサポート事業です。教育相談窓口としての機能、必要に応じて学校での別室登校児童生徒の学習支援や家庭訪問による支援を行います。
2点目は、適応サポート事業です。不登校傾向にある児童生徒の早期学校復帰のための教育相談活動などを行います。
3点目は、学びサポート事業として、心のケアハウスや学校において児童生徒の学習支援を行うものです。職員としては、スーパーバイザー1名、心のケアハウス支援員3名を配置し、各学校との連携を密にしながら、児童生徒の学校復帰を目指すものと捉えております。
吉田
不登校になる児童生徒にはもちろんそれぞれの背景があるわけで、今の説明ですと、どちらかというと早期に改善して登校に結びつけていくというところに重きを置いているようです。中には親御さんとして長年子供の不登校に悩んでいる方等も相談したいケースもあるかと思うのですが、そうした部分についても対応できる体制になると考えてよろしいでしょうか。
学校教育課長
初期対応だけではなくて、親御さんが長い間お子さんのことで悩みを抱えている場合にも対応する、そういった組織をつくろうと考えております。
吉田
256、257ページ、10款1項2目事務局費の19節負担金補助及び交付金で、仙台地区教科用図書採択協議会負担金があります。本市内の小中学校の教科書は、仙台教育事務所の管内ということで、そちらの代表者が採択審議会の委員だったと思うのですが、その審議会に出る方の構成を把握されていたら、伺います。
教育長
仙台地区教科用図書採択協議会は、仙台教育事務所管内の13の市町村で構成されています。委員のメンバーは、13市町村の教育長が13名、そのほか直接教科書の採択に利害関係を有しない者という位置づけで、各市町村のPTAの代表者を3名委員として加えて、合計16名で構成しております。
吉田
教科書は長年同じ会社の教科書が採択されているという現状もあって、採択の過程についてより高いレベルの情報公開が求められていると思うのですが、平成31年度は次の採択に向けた作業について何かスケジュールがあれば伺います。
教育長
教科用図書については、原則小学校用、中学校用、おおむね4年に1回教科書の内容が改訂されています。それに合わせて採択が行われておりますが、平成32年度から小学校の学習指導要領が改訂になりますので、平成32年度から使用する教科書については、各教科書会社でつくる教科書の内容が変わるものと見ております。平成31年度は、平成32年度から使用する小学校の教科用図書の採択が主な内容となります。そのほかにも特別支援学級で使用する教科用図書の採択も、これは毎年行われますが、来年度6月から7月、8月にかけて各学校あるいは市町村において、平成32年度から使用する教科書の採択に関する事務が進められる予定となっております。
なお、情報公開については、仙台地区教科用図書採択協議会の事務局、これは平成29年度から平成30年度にかけては本市が事務局になっておりますが、事務局の所在する市町村のホームページにおいて審議過程等を公開しております。ただ、性格上まだ公開できない時期もありますので、常時公開しているわけではありませんが、既に終わっている採択事務については公開しております。
吉田
256、257ページ、10款1項2目事務局費の教科書採択について、もう一度伺います。小学校の教科書に限ってですが、これまでの採択結果を確認しました。平成23年、27年、31年からという3つの資料が県のホームページから確認できたのですが、全ての教科において、全ての教科書の会社が全部一致しているということで、10年以上同じ教科で同じ会社の教科書が採択され続けている状況にあります。宮城県の教育委員会から教科書採択に係る基本方針が示されておりまして、4番目の項目として「教科書の選定の過程においては、保護者等の意見が反映されるように配慮し」とあります。先ほど協議会の構成を伺ったところ、保護者等の意見の代表と思われるPTAの方が16名中3名しか入っていません。この状況で次年度の採択に当たって、保護者等の意見が反映されるための努力はどのような形で行っていくのか、伺います。
教育長
宮城県内において10年近く同じ教科書が使われているという御指摘でしたが、教科書採択の流れをお話しします。まず、新しい教科書採択の年には、各学校ごとに新たに教科書会社が発行する教科用図書の教科書展示会に行くなどして、学校としてどの教科書を採択したいかという希望を、各市町村の教育委員会に出します。各市町村の教育委員会では、市町村の学校の希望を受けて、今度は教育委員会内で、教育委員会としてどの教科書の採択を希望するか協議をして1つに絞り込みます。その場合の教育委員会というのは、教育委員4名に私も含めた5名から成る教育委員会で協議をします。教育委員会としても教科書展示会にもまいりますし、教科書会社から審査用の見本が5組来ますので、それぞれの教育委員にお渡しして、その上でどの教科書にするか、教育委員会としての意思決定を行います。
13の市町村から各市町村の教育委員会で採択したい教科書が出て、それをもとに16人の委員で決定するという流れになっておりますが、結果的に同じものが採用されてきていると認識しております。保護者等の意見の反映については、前に述べた学校、教育委員会で採択する時点において、保護者等の意見を反映させるのは非常に難しいものと思っておりますが、仙台地区の採択協議会の中で、保護者の方3名が入っているというところで、その中で反映されるものと思っております。これまで以上に保護者の意見を反映させるための新たな取り組みについては、現時点では特に考えてはおりません。
吉田
それだけ多くの方がかかわって1つの教科書に絞っていくということですから、今のは名取市内のことですが、それが仙台教育事務所管内13市町村の各教育委員会で同じように学校からの意見を吸い上げてくる中で、やはりいろいろな意見が出てくると思うのですが、必ず同じ結果が出てくるのはなぜなのかと非常に疑問を感じます。それはただ名取市だけの問題ではないので、ここでそこまでお話しするレベルではないと思いますが、以前、仙台市などでは教科書を採択する段階で、図書館などに全ての教科書を展示して、図書館で教科書を見た方が、こういう理由でこの教科書がいいと思いますのように、意見を書いて、より保護者等の意見を反映させるような取り組みをしていたというケースもあります。なぜそのようなことに今回取り組まれないのかについて伺います。
教育長
先ほど教科書展示会という話をしましたが、これは県の教育委員会が行っているものです。宮城県内の何カ所かで検定済みの教科書を全て見ることができるような、教科書展示会を行っております。それは学校の先生方あるいは教育委員会の教育委員、職員が行くことが多いわけですが、一般の方が見ることができないわけではありません。名取で近いところというと、美田園の総合教育センター内にある教科書センターで教科書展示が行われております。ただ、先ほどどうして同じ教科書なのかということでしたが、それは結果として同じ教科書が採択されているのであって、恣意的に最初から特定の教科書を採択するということで、そういう結果になっているのではないと認識しております。
保護者の意見の反映については、先ほどの繰り返しになりますが、これまでと同じように仙台地区教科用図書採択協議会の中で、保護者の方も委員として入っている中で、意見の反映ということで考えていきたいと思っております。
吉田
小学校中学校全体で聞きたいので、252、253ページの教育委員会委員報酬ということで、教育委員会の捉え方として伺います。大阪市では小学校中学校の児童生徒に対して、学校へのスマートフォンの持ち込みを認める方向で検討されているということです。災害が頻発する中で、保護者との連絡手段として非常に有効だという判断だと伺っていますが、本市の教育委員会においてはそういう検討は、平成31年度どのように進められるか、もしありましたら伺います。
教育長
今、委員から御紹介があったスマートフォンの持ち込みについては、防災面、子供たちの安全・安心の面からと私も聞いておりますが、現在は名取市内の小中学校、義務教育学校では、原則としてスマートフォン、携帯電話の持ち込みは禁止しております。ただ、家庭の事情等でどうしても必要な場合には、学校に申請して許可を得て持ち込みを認めておりますが、授業中は職員室等で預かる形をとっております。文科省でも大阪市の対応を受けて検討するという話も出ておりますが、まだ現時点では本市としては従来の方針で各学校に指導してまいりたいと考えております。今後、大阪市、国の動向を見て検討はしていきたいと思います。
吉田
災害のときに役に立つということもありますし、またそれ以外にスマートフォンを持つ年齢がだんだん下がってきて、小学生への普及率も上がってきていると言われています。そんな中で、スマートフォンの危険性などもいろいろ指摘されているところで、そういう内容の教育も含めた本市としてのスマートフォンに関しての教育方針の必要性は捉えてはいないでしょうか。
委員長
吉田委員に申し上げますが、予算の質疑ですから余り広げないようにしていただければと思います。
吉田
266、267ページ、10款2項2目教育振興費19節負担金補助及び交付金で伺います。平成30年度の2月定例会の補正で、体育連盟助成金が陸上競技大会中止の影響で減額になったのですが、平成31年度にはその金額そのものが計上されていません。この小学校体育連盟助成金は、平成31年度は発生しないということでよろしいですか。
学校教育課長
平成31年度から名取市陸上記録競技大会は廃止することが、今年度小学校体育連盟で議決協議がなされ、平成31年度からはとり行わないことになりました。さまざまな理由を踏まえての結論に至った次第です。
吉田
さまざまな理由に、何か主なものがあれば教えていただきたいのと、それにかわる形での教育活動をお考えであればお示しください。
学校教育課長
まず1点目は、児童数の増加による課題があります。名取市内の6年生の児童数は、平成29年度783人から平成30年度840人を超えるという形で、大分人数が増加しております。全ての子供たちがこの陸上記録会に参加しますので、多くの子供たちが100メートル走にも参加することになります。当然人数がふえれば、競技時間が延びるという問題もあります。
また、学校の人数の差が大きくなってきました。大規模校と小規模校の差です。大規模校では子供たちがそれぞれの競技に出なければいけないこともありますので、100メートル走に多くの子供たちが参加しますが、逆に小さい学校ですとほかの種目もありますので、自分の種目が終われば自校の生徒の応援ではなく、ほかの学校の競技をずっと一日見ているという状況になっているということで、学校間の児童数の乖離による課題が一つの要因です。
もう1点は大会運営にかかわる課題です。小学校6年生の児童が800人以上集まっての大会運営ですので、当然担任だけでは賄い切れませんから、ほかの学年の教員もこの大会にかかわることになります。自分の学級あるいは学校の業務を置いて、こちらの大会の運営に参加するわけですので、その負担も大きいということがあります。
それから、実際に何も練習しないで大会に参加するということはありませんので、夏休み前、陸上の練習を大会に向けて行っております。ただ、小学校の学習指導要領の範囲でできるのかというとそうではなく、やはり放課後の練習であったり、体育の時間に陸上にだけ時間を費やすという問題もあります。とすると、ほかの種目、ほかの体育の授業の中身にも影響があるということも要因の一つです。また、バスに関しては、予備日を含めて2日間バスの予約をしております。従来ですと、予備日当日雨でもバス代のキャンセル料は発生しなかったのですが、何分今の時代ですとキャンセル料が発生するので、2日間の予算を計上しなければならないということ。この課題は平成30年度だけではなく、長年小学校陸上記録会にかかわる課題として、小学校体育連盟の中で話し合いがなされてきて、平成30年度結論を見出したところです。
ただ、代替案としては、名取市体育協会の陸上競技協会で主催している陸上記録会のようなものがありますので、それには従来も全学年の児童が参加しておりました。陸上競技協会主催の大会に教員が引率して子供たちの陸上への気持ちを高めるといったことも行っておりましたので、今後はそちらの大会への参加を促しながら、発展的な解消を図るという意味で、平成31年度からの陸上記録会の廃止に至った経緯となっております。
吉田
286、287ページ、10款5項2目公民館費19節、それから291ページの19節もそうですが、再開発ビルの管理組合負担金、平成30年に完成して平成31年4月1日からということで1年分になるのかと思いますが、この金額を決める際に以前は規約がまだはっきり定まっていないという御説明でしたが、改めて今規約は定まった状態なのか。
また、以前説明いただいたところから何か変更点がなかったかどうかの御確認をお願いします。
生涯学習課長
今回お願いする北棟管理費は、全体の共有部分の管理費を管理会社で算出して、その総額を北棟の総面積分で除して平米当たりの単価を算出しています。それに公民館、図書館、店舗それぞれの専有面積を乗じて、全体の共有部分の管理費となります。さらに、そこに専有部分、公民館でいえばグリーストラップ等の専用費用がありますが、管理費を足したものを北棟管理費としております。
また、駐車場棟の管理費の考え方ですが、これについても駐車場全体に係る管理費と時間貸しの持ち分に応じて案分しております。時間貸しに係る管理費を、時間貸しに参加している所有者ということで、その分を共有者持ち分で案分したものが駐車場棟管理費となっております。
3つ目ですが、駐車場棟の修繕積立金の考え方ですが、これについては駐車場棟の長期修繕計画に基づいて、将来にかかる費用をあらかじめ積み立てしているものです。駐車場の持ち分に応じて管理会社が算出しておりまして、それに基づく積立金を行うこととしております。今回は12カ月分で算出しているということです。この決め方ですが、組合の中に管理会社があります。管理会社から算出していただいて、管理組合でおのおの決定して、それに基づいて本市に請求が来るという形になっているところです。
規約については組合の中で定めているものです。
吉田
規約そのものがもう既に完璧にでき上がっているというように捉えてですが、今回は12カ月分ということでしたので、その規約の中の考え方はまだ中身を読んでいないのでわからないのですが、12カ月分としての定額が毎年これから同じだけかかって、プラスそこにその年度に必要となる臨時的なものがあるかと思うのですが、今回の平成31年度予算の中でその内訳を伺います。
生涯学習課長
今回12カ月分で算出しておりますが、北棟管理費と駐車場棟の管理費については、改定の予定はありません。駐車場棟の修繕積立金のみ5年目に改定が計画されているということです。
吉田
306、307ページ、11款3項1目観光施設災害復旧費15節工事請負費で、サイクルスポーツセンター災害復旧工事が計上されています。平成31年度は全体の予算ベースでいうと何%まで進むのでしょうか。
商工観光課長
率は捉えていませんが、今回ここに計上しているのは建築工事になりますので、このほか今後必要なものは什器備品を改めて予算計上したいと考えております。基本的にはそれで全体の費用は終了になると捉えています。
吉田
多分ないと思うのですが、建物の部分ができたら、その部分だけ先に利用できるという計画はありませんか。
商工観光課長
基本的には、供用開始は一体的にすることを想定しています。
吉田
308、309ページ、11款5項1目消防施設災害復旧費の15節工事請負費で、高舘分団第6部ホース乾燥塔災害復旧工事とあります。こちらの災害に遭った内容、どの程度の被害であったのか伺います。
消防本部総務課長
これは平成30年10月、市内全分団の施設点検中に、高舘分団第6部のコンクリート製のホース乾燥塔にひび割れを発見しました。専門的な調査が必要と判断して、設置業者に点検を依頼したところ、通常設置している状況ではひび割れはなかなか発生しないので、東日本大震災により許容荷重以上の力がかかったことによって乾燥塔を傷めた可能性が高い。さらにさびが浮き出ているので、建てかえを勧めるという報告を受けました。これにより復旧工事をお願いしているものです。この設置年は、平成20年度製のコンクリート製ポールとなっています。
吉田
東日本大震災から結構時間がたっての発見でしたので、こういうものは早目に発見することが望ましいと思います。似たような施設においての同じような被害がないかどうかの点検は、もし済んでいれば結構ですが、平成31年度中にもしあれば伺います。
消防本部総務課長
先ほどお答えしたとおり、全6分団34部の点検をして、コンクリート製のポールは市内21カ所あります。これを全部点検したところ、高舘分団第6部にひび割れを発見したということで、今回の復旧をお願いしているところです。
吉田
323、324ページの1款1項1目一般被保険者国民健康保険税でお聞きします。4節医療給付費分滞納繰越分、5節後期高齢者支援金分滞納繰越分、6節介護納付金分滞納繰越分は滞納繰越分の調定見込額が計上され、いずれも平成30年度に比べて額が減っていますが、これはその分しっかりと回収できると捉えての見込み額なのか確認したいと思います。
税務課長
この金額の考え方ですが、これまでの滞納整理や滞納処分によって年々収納率が向上しています。それに伴い滞納繰越額が減少していますので、基本的にはこの金額は見込みとなりますが、現実にはそれ以上の収納率もありますので、予算計上している額は確保できると捉えております。
吉田
今おっしゃったように、納付額が努力によってだんだん増加しているのであれば、調定見込額の10%よりも実際には数字は上がっているのではないかと思いますが、さらに収納率を上げるための取り組みを新年度について何か検討していたらお伺いしたいと思います。
税務課長
これまでと同様となりますが、滞納整理と滞納処分を適正に行っていくということで、現実には決算で収納率も向上していますので、これを継続していくという考え方です。
吉田
343、344ページの5款2項1目保健事業費1節報酬でレセプト点検員報酬(2名)です。レセプト点検の1年間の件数の見込みがもしあれば伺います。それから、点検方法について、紙ベースや電子データなどいろいろとあると思いますが、中身をお伺いいたします。
保険年金課長
レセプト点検の総数は、平成29年度の実績では28万6,122件でした。平成31年度の見込みですが、30万件を見込んでいるところです。点検方法は、今は電子申請になっていますので、パソコンの画面で確認しております。具体的には、月をまたぐような長期間にわたる治療や投薬といったものに対して適正かどうかという点検を主に行っています。
吉田
その中で今の説明のように月をまたぐような部分に焦点を当てながら、何とか全体をチェックしていると思うのですが、この点検を2名の体制で、しかも、非常に重大な仕事でありながら、報酬額として1人当たりにすると年間で百何十万円という金額なわけで、レセプト点検の適正さの確保のためにはどのようなことに取り組むべきと捉えているかお伺いします。
保険年金課長
人数については御指摘のとおり2人でお願いしているところです。先ほど申し上げたように、月をまたいで長期間同じ薬をずっと処方されている、また病名に対してその薬を使うのが適正か、毎月検査しているが過剰な検査ではないか、そういったところを重点的に点検を行っています。実際点検した結果、平成29年度の実績として5,500件ほど再審査の請求を行いました。
2人で実際にできるのかという御指摘もありましたが、先ほど申し上げたものを機械的に抽出することも可能なので、現在2人で実施しているということです。
吉田
27ページの資本的収入及び支出の支出で建設改良費に含まれると思いますが、水道管の更新や新規に布設する際に、ポリエチレン管は平成31年度ではどのぐらいの布設が見込まれているのでしょうか。
水道事業所長
更新については、基幹配水管には従来の耐震性能を有したダクタイル鋳鉄管を使おうと思っていますが、御質疑にあった配水用ポリエチレン管、HPPE、ハイポリと言われるスペックダウン的なものも、一部配水枝管的なところで施工する予定です。それについては、現在、管の更新事業を行っている大手町地区で2,000メートル弱予定していて、あわせて耐震性を持ったダクタイル鋳鉄管の部分も610メートルほど計上しています。
吉田
平成31年度の予算の範囲から外れたら恐縮ですが、ポリエチレン管を今後進めていく方針かどうか、平成31年度では全体として広げたい枠の中の何割ぐらいまで達するなどといった見込みがあったら伺います。
水道事業所長
その検討についてはさきにアセットマネジメント業務の中で行ってきたところです。スペックダウンについては、基本、口径75ミリメートル未満の部分は今おっしゃるハイポリ、要は比較的資材単価が安いものを採用しようと思っていますが、いかんせん、耐震性を有しているとメーカーは言っていますが、耐震性能において、あるいは経年化に対抗するのはやはりダクタイル鋳鉄管のほうがまさっていると思っていますので、おおむね口径75ミリメートル以上の耐震性を備えたダクタイル鋳鉄管を採用していこうと考えております。ただし、ハイポリ管と呼ばれるスペックダウンした管材を全く使わないわけではなく、ケース・バイ・ケースになると捉えております。
吉田
34、35ページ、下水道の年間総処理水量が802万3,772立方メートルとあります。水道の契約の際に水道と下水道を一緒に契約し、下水道の料金は水道の使用量に応じて設定されていたと記憶しています。家庭で水を10立方メートル使ったら、下水道も10立方メートルとして計算されているかと思うのですが、先ほどの水道事業で年間の総給水量が約929万4,000立方メートルとなっており、給水と下水の処理水量に大きな差が出ていますが、この差の分の水はどこに行ったと捉えているのでしょうか。
下水道課長
水道事業における水量は市全体に給水されるものであって、下水道事業においては、公共下水道と農業集落排水とそのほかに浄化槽というものもありまして、全ての水道水が公共下水道で処理されるわけではありませんので、イコールにはならないということです。
吉田
そうすると、年間総処理水量は公共下水道で処理する量であり、差の分は今答弁した浄化槽などで全て処理されているということでよろしいのか。というのは、その差については、負担する側にとっては、使った水の分に加えて本来払わなくてもいい分の処理費用まで払っているのではないかという単純な疑問を持っていたのですが、そのような計算にはなっていないということでよろしいのですか。
下水道課長
先ほども答弁しましたとおり、水道で使われる水が全て公共下水道で処理されるわけではなく、今回、下水道事業で処理水量として押さえている数量は、公共下水道から流域下水道のほうに処理する汚水量として計上しています。ですから、御存じのようにいろいろな使われ方をするので、水道が全て公共下水道に入ってくるわけではありません。
本会議
(議案第38号 名取市放課後児童クラブ実施条例の一部を改正する条例)
吉田
今回の条例改正では、市長が特に必要があると認めるときということで、例外的な規定を置くということであろうかと思います。具体的にどこに場所を置くかということがもう決まっているのでしたら、かえってその表の中にそちらも含めて正式な形で条文化してはどうかと単純に思うのですが、なぜこうした例外規定という形で今回条例改正となったのか、伺います。
こども支援課長
今後、ほかの児童センターにおいても定員を相当オーバーするケースも考えられますので、今回はこのような規定とさせていただいたところです。
吉田
これからもそういうケースがふえるのであれば、なおさら条文の中に児童センターの名前として明記しておくべきではないかと思うのです。では今後いろいろと事情が変わってくる中で、いつまでもこうした例外的な規定という形で残していくのか。それとも、どこかの時点でやはり児童センターが1つの小学校区に2つになったりという場合も、両方明記するのか、そのあたりの見通しはどう考えているのですか。
こども支援課長
放課後児童クラブの登録数が多いのは、増田児童センター、増田西児童センター、下増田児童センター、愛島児童センターが相当多くなっております。これらの施設については、今後児童センター以外の場所で実施する可能性もあり、また場所についてはマンションの空き室や貸し家等いろいろと考えられますので、今回はこのような改正とさせていただいたところです。
(議案第39号 工事請負契約の締結)
吉田
資料3の左のページの一番下ですが、側道橋側面図、赤い部分を撤去するという説明がありましたが、その下にあるくいの部分、長く掘り下げてある部分は残すように見えるのですが、堀の部分の一番下、底面から飛び出た状態で残ってしまうようにも見えるのですが、実際どうなっているのか御説明ください。
復興まちづくり課長
側道橋の側面図ですが、くいを確かに黒く着色しておりまして今回の工事からは外しております。このくいの長さが16メートルから24メートルとなっておりまして、これを撤去するとなると相当な工事となります。それが一つと、基礎が川底よりも深い位置になっております。今回は基礎まで撤去して、それに伴って若干くいの頭は撤去しますが、そこまで撤去すると川の機能に支障がないということで、くいは残すということで協議は調っております。
吉田
確認ですが、将来的に貞山運河を何か別な形で活用していくこともあろうかと思いますが、そういうことも見据えた上で残すという判断でよろしいですか。
復興まちづくり課長
管理者である宮城県と協議して、この形で支障がないという回答を得ているところです。
(議案第40号 工事請負契約の締結)
吉田
以前にも御説明いただいたことをもう一回確認します。資料の4ページの3人用宿泊室、ここは自転車を持ち込める部屋になっているということで、壁に自転車をかけるようにして置くという説明が以前ありましたが、その構造や、ベッドと自転車のすき間の見込みをどのようにお考えか、伺います。
都市計画課長
部屋の構造ですが、普通の壁に合板のようなものを張って、傷がつかないように保護しながらフックで自転車をかけるのですが、2台は置くことができます。もう1台は通路の廊下に置くようになります。
吉田
傷がつかないようにというのは、実際の壁に傷がつかないように、壁にもう1枚合板を張るということなのか、自転車をかけても傷がつかないほど頑丈な壁になるのか、よくわかりません。
それから、こうした狭いスペースに自転車をかけることによって、災害が起きた際など避難の妨げになるのではないかという点についても明確に防止策が示されていませんが、そのあたりはどのようにお考えなのでしょうか。
都市計画課長
自転車をかけるフックは、よく台所などに張ってある汚れと傷を防止して補強する合板につけます。有事の際は、避難の妨げにならないように自転車は置いて、まずは自分の命を守っていただくということになると思います。
(議案第41号 工事請負契約の変更)
吉田
資料の下の段の濃い赤色の部分が今回増工となる部分という御説明でしたが、この舗装する部分も最初の契約をした際の工事の中に含めなかったのは、今話されたほかの事業との調整という面だけの理由ということでよろしいですか。
復興まちづくり課長
軟弱地盤対策として、盛り土をして落ちつくまで待っていなければならなかったという事情がありました。
吉田
上の平面図にも濃い赤と薄い赤の着色部分があって、薄い赤の着色部分もこれから新しく増工する部分があるということで、着色されているのですか。この図の読み方がよくわからないので、そこを教えてください。
復興まちづくり課長
中央部の薄い赤の着色部分は、当初発注分です。今回の濃い赤の着色部分は増工としておりますが、薄い赤の着色部分は今後増工する予定は今はありません。
(議案第44号 平成31年度名取市一般会計補正予算)
吉田
12、13ページ、4款1項3目一般予防費の13節委託料、麻しん風しん抗体検査委託料で伺います。大変流行しているということで、予算がついたことは非常にありがたいと思うのですが、その検査や接種の対象となる方の枠について伺います。
保健センター所長
国から示されている対象者は、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性になります。この事業は、来年度から3カ年に分けて実施することになっておりまして、初年度は昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の方にまず通知を差し上げて、抗体検査、予防接種を実施することになっております。
吉田
3年に分けてということで、もし1年目の対象の方が1年目にこの検査、接種を逃してしまった場合に、翌年度以降に受けることができるかどうか。それから、これは補助という形になると思うのですが、実際にかかるための費用のうちどのくらいの補助があって、それは割合なのか金額なのか、その2点について伺います。
保健センター所長
接種を逃した場合ですが、2年目以降の方法については国からまだ正式に示されていないところですが、対象年齢としては昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性なので、その期間中に抗体検査を受けていない方がいれば、受けられる方向で国から通知が来るものと理解しております。
補助金については、事項別明細書の7ページの14款2項3目衛生費国庫補助金、4節の一般予防費が国庫補助金になるのですが、この対象が抗体検査にかかわるものの事業費の2分の1となっておりまして、12、13ページに戻ると、項目として上がっている13節の麻しん風しん抗体検査委託料、電算委託料、これは電算システムの改修費用になります、その下、19節の麻しん風しん抗体検査助成金、この合計額の2分の1を国庫補助金として国から補助されることになっております。残り2分の1は、特別交付税措置されるということで国から通知が来ております。
吉田
12、13ページ、7款1項4目観光費13節委託料、仙台空港周辺地域活性化インバウンド事業委託料、財源は5分の4が国の交付金のようです。この事業内容に広域観光連携とありますが、広域連携の枠組みと内容を伺います。
商工観光課長
この交付金は平成29年度からありまして、ことしが3年目となります。枠組みとしては、名取市、岩沼市、亘理町、山元町の2市2町で、広域連携としてこれまでも取り組んでいたものになります。今回、平成31年度では、今国に申請を上げていて、内示はまだですが、事業を先に進めるために今回補正でお願いしているところです。
今回の主な内容については、台湾のFIT、いわゆる個人や少人数の旅行者をメーンターゲットにする事業として、これまで2年間築き上げてきた基盤と観光資源をもとにしています。一番大きいのは受け入れ環境整備事業で、訪日外国人に対して、昨年ジャパン・エコトラックというルートを設定して、それぞれの地域の資源に案内表示や協力店をもらっているのですが、そこにQRコードをつけて、スマホで情報をすぐ入手できるようにします。また、バーチャルリアリティーを活用して、機器を10台予定していますが、それで多言語化ツールの活用事業を行うということです。そのほか、受け入れ環境については、地域事業者、団体等と連携してツアーを造成する中で、観光ガイドを活用したモニターツアーを行うことを主に進めるようなことで、今国に申請を行っているところです。
吉田
都道府県別で海外からのインバウンドが宮城県は特に伸びていることもあって、大変ありがたいことですし、せっかく空港が立地しているという好条件がありますので、海外からの観光客に仙台や松島に行かずに本市にぜひたくさん来ていただきたいというのは、共通した願いであると思います。今、御説明の中にQRコードをつけるとか、VRというものがありました。そのほかに、例えば通貨が違うというのが海外旅行者にとってはいろいろと不便な部分ですが、スマートフォンを持っている方が登録しておけば、スマートフォンで決済できる仕組みも大分進んできています。そういったものの促進はここには含まれていないのでしょうか。
商工観光課長
スマートフォンでの決済機能については、国あるいは県が進めると伺っていますので、今回の事業の中ではその分は取り入れておりません。