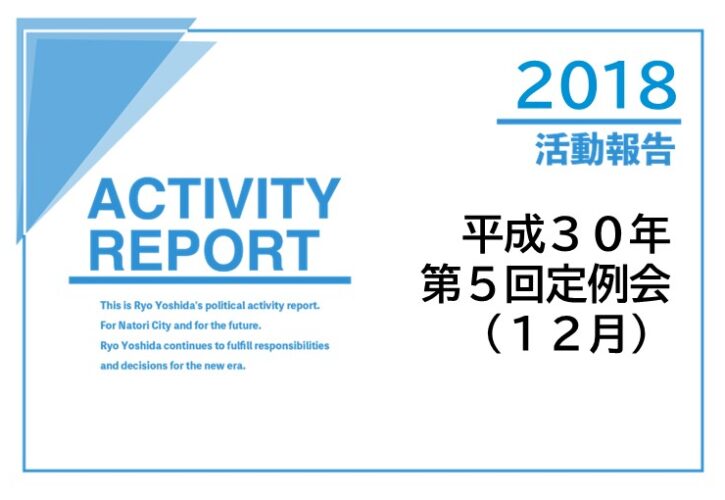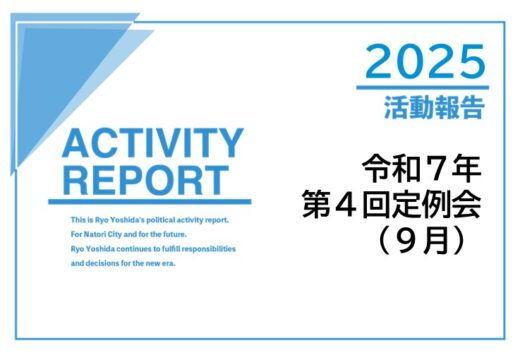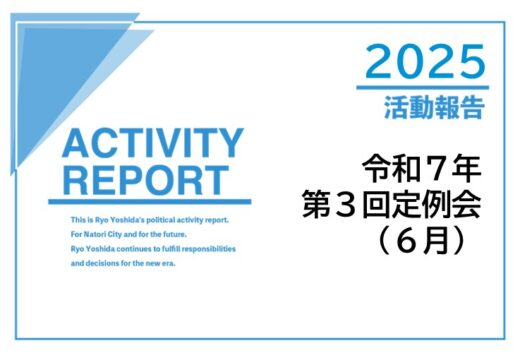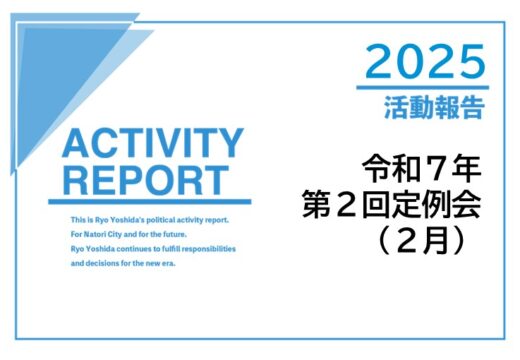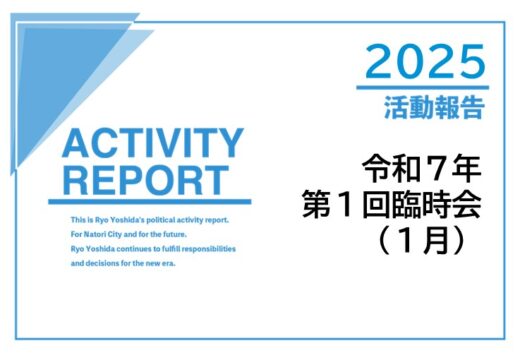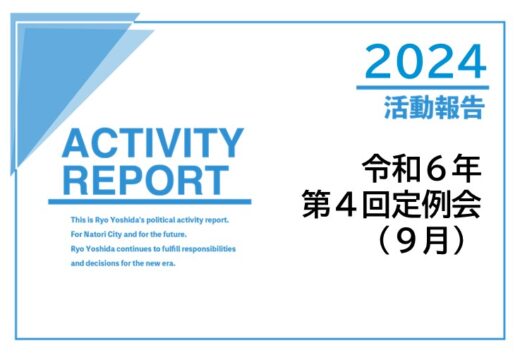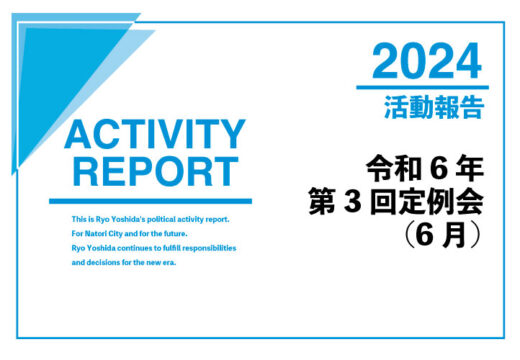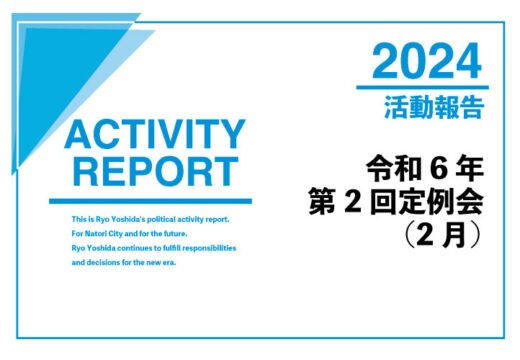本会議
(議案第122号 名取市議会議員及び名取市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例)
吉田
公職選挙法の改正で市議会議員選挙についてもビラの配布が認められたことから今回の条例改正になったかと思いますが、条例の第8条で、ビラの作成に公費負担が適用される上限額は1枚当たり7円51銭とされています。この金額については今回特に変更はないということですが、どのような検討を経て金額を据え置いたか、お伺いしたいと思います。
選挙管理委員会事務局長
この公費負担の金額は、国からの通知によって決定されている額です。地方選挙においては国政選挙に準じて行うこととされていますので、市として金額の検討は特にしておりません。
(議案第128号 工事請負契約の締結)
吉田
今回落札した加賀田組という会社についてお聞きします。自転車のコースの工事の実績として、これまでどういったものがあったのかについてお伺いしたいと思います。
財政課長
今回の入札参加条件の中においては、特に自転車走路にたけたということではなく、過去10年間において国または地方公共団体が発注した1ヘクタール以上の造成工事または1ヘクタール以上の公園工事を元請として施工した実績がある者であることという要件を付しています。この要件に従って、一般的な舗装工事となりますので、特に加賀田組が自転車走路にたけているというものではないと認識しております。
吉田
たけている、たけていないではなく、その工事の実績があるかないかをお聞きしたのですが、ないということでよろしいですか。
財政課長
先ほども答弁申し上げたとおり、過去10年間の実績ということで条件を付しているところです。実際に自転車の走路について工事実績があるかどうかについては確認をしておりません。
吉田
自転車は車と違って生身の人間が運転するものですから、実際にかなりのスピードを出して競技を行ったりするとなると、その道路のコンディションは非常に重要な要素だと思います。そういうことを全く想定しないで今回入札を実施したということでよろしいですか。自転車の競技が行われるような施設であるにもかかわらず、自転車の道路の工事をした実績があるかどうかが業者を決める際の一つの参考として加味されなかったということでよろしいですか。
都市計画課長
サイクルスポーツセンターの走路の設計については、サイクル協議会などの専門家に聞き取りをしながら行ってきました。工事の種類としては、標準横断図にもあるとおり普通のアスファルト舗装の工事と捉えております。それを設計どおりに施工していただくということです。
吉田
先ほどの御答弁で、設計どおりに施工されるので問題がないと受けとめました。その自転車の走路のアスファルト舗装ですが、資料4の標準横断図を見ると、カラーアスファルト13とかアスファルト13と書いてあります。いろいろなアスファルトの種類があろうかと思いますが、その種類を指定しているということで、その指定するアスファルトは、もちろん自転車が走行しやすいアスファルトを選んで指定をしたということでよろしいですか。
都市計画課長
舗装については、カーブのところはカラー舗装で注意喚起をすることにしており、一般のところは普通の黒舗装としています。今回、競技だけではなく、一般の方のほうがどちらかというと多いのではないかと思っていますし、通常の道路などもいろいろとありますが、走りやすい舗装材で、それから排水についても考慮して透水性のものを使いますので、そういったことで走りやすさはあるのではないかと考えています。
吉田
私もアスファルトの専門家ではないのでよくわからないのですが、資料を見るとアスファルト13とアスファルト20というのが主にあるようで、今調べたら、20のほうが滑りどめが強いというかスリップしづらいということが載っていました。今、答弁されたように、一般の方の利用が大半であろうというのはもちろんそうだと思いますが、やはり本格的な自転車のコースということで、ここで自転車の競技などを行って、それが人を呼び込むような効果も非常に期待できるのではないかと思います。今回の業者は自転車の道路の施工実績は確認していないという話でしたが、実際にある程度スピードが出るような競技を行いたいと言われた場合、しっかりと責任を持って貸し出すことができると主催者側に言い切ってよろしいですね。
都市計画課長
安全施設という意味では、カーブについては転落防止柵も設置しますし、転落防止柵にクッション材をつけることも考えていますので、ある程度スピードを出した場合でも対応できる構造になっていると思います。舗装については、通常の舗装であれば対応できるのではないかと思っております。
(議案第131号 工事請負契約の変更)
吉田
歌碑設置工事についてお伺いします。歌碑の裏面のことが何も書かれていませんが、裏側にどういう説明文が載るのかということ。それから、この図ですと歌の文句がそのまま活字で書かれていますが、実際はどなたが揮毫するのか。その2点をお伺いいたします。
復興調整課長
今のところ、裏面に何を刻むかということについて具体的な検討はしておりません。ただ、この歌碑の設置目的とか、なぜ設置をしたかということをお示しするために、イメージ図の行啓記念碑の前にある四角い石碑にいろいろな説明を記す予定です。
それから、歌碑の揮毫については、現在、市内の中学生から上手な方を2名選んで、そちらの方にそれぞれ書いてもらうということで、大分スケジュール的には厳しいのですが、そういうことで、今、教育部と調整をしております。
吉田
地元の特に中学生の揮毫ということで、大変すばらしいお考えかと思います。ただ、その説明板を行啓記念碑の前に置くということですが、恐らくこれは金属板にプリントか何かをするのかと思います。こういうものを各地で見かけますが、やはり10年20年と時間がたつと、かなり劣化して見るも無残になってきます。やはり石に刻めば永久に残りますので、せっかくの歌碑があるわけですからそちらに刻んだほうがいいのかなと思いますが、今後のそのあたりの検討をお伺いしたいと思います。
復興区画整理課長
こちらの説明板については、今、ステンレスのエッチングということで考えています。ただし、やはりステンレスといえども、だんだん劣化することも考えられますので、その辺についてはこれから検討していきたいと思っております。
(議案第132号 土地の取得)
吉田
道路の構造について一部お聞きしたいのですが、中央部あたりを見ると、片側2車線の車道、その外側に恐らく自転車道、歩道があって、さらにその外にも道路らしき部分をとっているように見えるのですが、この一番外側にある部分はどのような理由でこのようにつけられたのかお伺いいたします。
土木課長
本路線は、交通量の関係から片側2車線ともう一つの片側2車線の間に中央分離帯を整備することとなっています。道路を横断する箇所が交差点部に限られるため、農地への乗り入れ関係ができなくなることや、本線部の交通量が多く予想されるため通行及び乗り入れが危険になることから、機能補償として側道の整備をすることとしています。そこを通って農地などに行くための側道になります。
吉田
将来的な話ですが、この地図でいうと東側の仙台市域のところで市街化区域が途切れていて、名取市側は市街化調整区域ということで、住宅は建っていないと思います。将来的にここに用途変更ということが起きてくるような前提は考えずにこういう設計ということでよろしいですか。
土木課長
この地区は市街化調整区域になっており、この本線部についても市街化調整区域です。やはり今現在農作業で使うという地権者からの要望がありましたので、現在のところは農作業という考えで側道をつけることとしています。
一般質問
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問を行います。
初めに、大項目1 良好な環境の保全についてお伺いいたします。
本市は平成15年3月に名取市環境基本計画を策定しました。前の前の市長、石川次夫市長の時代のことです。この計画には、良好な環境の保全と創造に関する施策の実現に向けて、長期的な具体的目標値や環境に配慮した施策の大綱などが定められています。当初の計画期間は平成24年度まででしたが、東日本大震災の影響などにより、平成32年度までの18年間という非常に長い計画期間となって、ようやく今年度の当初予算に第二次名取市環境基本計画の策定に向けた予算が計上されました。
8月30日に開催された環境審議会では、18歳以上の市民2,000人、市内事業者400社、小学5年生と中高生2年生おおむね2,000人を無作為に抽出し、市民意向調査を行うことなどが決定されたと伺っております。工程表のとおりに進んでいるのであれば、意向調査は10月までに終わり、現在は現況評価と課題抽出に進んでいるはずです。第二次計画は、第一次計画の策定時と異なり、補助金等の措置は厳しいと伺っていますが、どのような内容にするにしても、第一次計画の総括は欠かせません。
そこで、小項目1 名取市環境基本計画に掲げられる12の目標値と63の行政の役割(施策の実施)のうち、これまでに達成または実施されたのはどの項目か。また、最終年度とされる平成32年度までに達成または実施されると見込まれるのはどの項目か、市長にお伺いいたします。
市長
名取市環境基本計画は、名取市環境基本条例の目的である現在と将来の市民の健康で文化的な生活の確保を実現するため、環境の目標及び施策の大綱を定めるとともに、取り組みを総合的かつ計画的に推進するための計画です。
平成29年度の実績は「なとりのかんきょう」でまだ公表に至っておりませんので、平成28年度実績で公表している名取市環境基本計画の12の目標値と63の行政の役割(施策の実施)達成及び実施されているものとして答弁させていただきます。
目標値で達成しているものは2つあり、1つ目は、基本目標の水質汚濁防止に掲げてある増田川中流のBOD値、2つ目は、交通による公害防止の二酸化窒素濃度年平均値が目標値を達成しております。
次に、公表している市の役割の実施状況については、実施しているのは10項目あり、主なものとしては、自然観察会の継続と充実で自然観察会を実施しています。また、公共施設へのソーラーシステムの率先導入で、学校、公民館等に太陽光発電を導入しております。
名取市環境基本計画の最終年度までの見込みについても、第二次名取市環境基本計画の策定の中で、市民、事業者のアンケート調査や庁内ヒアリングを実施し、目標値及び市の役割などの現況評価に取り組んでいるところですので、御理解いただきたいと思います。
吉田
目標値で達成が2項目、行政の役割で実施しているのが10項目ということで、全体に占める割合が非常に低いと捉えました。
この目標は当初は平成24年度まででしたが、それがこれだけ延びているにしても達成できていない要因について、市長はどのように分析されているでしょうか。
市長
1つには、やはり東日本大震災による影響が非常に大きいのではないかと思っております。もう一つは、12項目の目標値については、例えば苦情件数がゼロなどそもそもハードルが非常に高いと感じられるものもありますし、また、国道4号の二酸化窒素の濃度のレベルといった本市単独ではなかなか達成が困難と感じられる項目もあります。さらには、家庭のCO2排出量云々ということで、統計による推計値でしか把握できず、計測が困難な部分もあろうかと思います。いずれ平成15年に策定された計画でもあり、今後を見据えてということで、第二次の計画として、より実情に合った、そして実効性のある計画をしっかりとつくり上げていきたいと考えております。
吉田
非常にハードルが高いなどの理由については理解できますが、やはり高い目標を掲げたことそのものに価値があるのではないかと思うのです。それを達成できなかったのは結果であり、その達成に向けて市として取り組みをしっかり行ってきた経過があるのであれば、そこは評価すべきかと思います。
ただ、1点、一番最初に理由として挙げた震災によって困難であったということについては、震災は平成23年3月に発生したので、計画期間10年間の8年ぐらいの時点で起きたわけです。この8年間の取り組みは本当に目標達成のために努力したのかどうか、そこは市長はどのように捉えていらっしゃるでしょうか。
市長
当時現職ではありませんでしたが、計画に掲げたことについて職員それぞれ精いっぱい頑張ってきたものと捉えております。
吉田
市長はその当時執行部ではなく議員側にいたので、恐らく計画の策定からいろいろとお感じになった部分もあろうかと思いますので、それらをこれからどう施策として実現していくのか、この後議論させていただきたいと思います。
次に移りますが、ここで全ての項目を取り上げることは時間的に不可能ですので、幾つかの項目に的を絞って質問したいと思います。
行政の役割の41番をクローズアップして、「ポイ捨て禁止条例(仮称)」の制定とあります。これまでの会議録からこのポイ捨て禁止条例についての発言を拾い出してみたところ、環境基本計画が策定される前から一般質問などで議員から何度も提案されていたことがわかりました。環境基本計画が策定された直後になりますと、平成15年12月定例会において、佐藤賢佑議員から罰則つきのごみポイ捨て禁止条例の制定が提案されました。その際、石川市長から、ボランティアによる啓発活動による成果を見きわめながら、次の段階としてポイ捨て禁止条例を制定する取り組みに着手したいと答弁がありました。
その2年後の平成17年12月定例会で、菊地 忍議員がポイ捨て禁止条例制定の取り組みを質問したのに対して、佐々木市長が関係する市町との整合性を図った上で条例化を検討してまいりたいと答弁されました。菊地議員からごみ処理の問題とポイ捨て禁止の問題は別であろうと指摘があったものの、それについて答弁は求めないということでしたのでコメントもありませんでした。
その後、平成18年9月定例会において、相澤祐司議員が市民の協力による環境美化活動には限界があることを指摘し、たばこポイ捨ての禁止条例のような罰則規定を設けた取り組みの検討を求めています。ただ、こちらも具体的な答弁はなかったようです。
この平成18年を最後にしてポイ捨て禁止条例を求める質問はぱたりとやみ、条例は制定されることなく現在に至っております。検討したいという答弁があってから非常に長い期間が経過していますが、なぜ制定できていないのか、小項目2 ポイ捨て禁止条例の制定が見送られ続けている理由を市長にお伺いいたします。
市長
ポイ捨て禁止条例の制定については、平成15年3月に策定した名取市環境基本計画において、規制を取り入れた手法による問題解決を目指すとして条例の制定を挙げておりますが、現在も制定しておりません。
その理由は2点あります。1点目は、罰則規定を備えた条例を制定した場合、取り締まるための監視体制を整えることが人員や費用の点で困難であり、実施に時間がかかること、2点目は、名取市環境美化の促進に関する条例第2条第1項に同様の条項が既にあることから、条例制定の手法について検討が必要であることです。
環境基本計画においてポイ捨て禁止条例の制定を明記していますが、名取市環境美化の促進に関する条例を現状に合わせて改正することも検討可能であると捉えております。
現在、本市で実施しているごみのポイ捨て禁止に向けた対策を充実させるためにも、問題を整理し、検討していきたいと考えております。
吉田
罰則を設けると取り締まるための人件費等の課題が生じることはもちろんわかりますが、実際に罰則を設けている自治体もあります。実効的な力があるかどうかという点ではなかなか難しいのですが、そのことによってポイ捨てをさせないという気持ちに住民がなっている部分もあり、その意味で効果が全くないわけではないと評価されていると思います。
そして、市長から御答弁があったように、確かに名取市環境美化の促進に関する条例に同じような趣旨で条文が組まれていますが、もう一つの手法として、ごみを捨てさせないためには、ごみが行く場所を用意する、ごみ箱を市内にもう少し整備すべきではないかと思っております。ポイ捨て禁止条例の制定はあくまでも手段であって目的ではない。目的は、まちを美化する、ごみが散乱しないようにするということです。
そのために、小項目3 ポイ捨てを禁止するばかりではなく、抑止する手法もある。市は、屋外へのごみ箱設置を積極的に進めるとともに、ごみ箱の設置を推進する制度の創設を検討すべきについて、市長にお伺いいたします。
市長
屋外へのごみ箱の設置については、かつて、市内各所にごみ箱を設置した結果、粗大ごみや危険物などの不法投棄の誘発が見受けられ、地域の環境衛生の悪化を招くとして、現在ごみ箱の設置を控えている状況です。
屋外に設置されたごみ箱は、住宅地内のごみ集積所と異なり、住民のかかわりが薄い分、無責任かつモラルの低い行為を誘発し、かえって環境衛生の悪化をもたらす原因になりかねません。本市の現状より、屋外へのごみ箱設置及びこれを推進する制度の創設は難しいものと捉えております。
現在、本市のポイ捨て防止に係る施策として、注意喚起の看板や監視カメラの設置、市内パトロールの実施、不法投棄物の早期発見、早期回収を行っております。また、各地区での環境美化活動の実施により、住民の皆様より市内の環境美化の推進に御協力をいただいている状況です。 今後、さらに有効な手段を調査研究しながら、引き続きポイ捨て防止に取り組んでいきたいと考えております。
吉田
不法投棄があったという理由でごみ箱の設置を控えたということでしたが、ではそのように捨てられていたごみは一体どこに行ったかと考えると、ごみをごみ箱に捨てていた人たちが自分の家で処理したかといったら、必ずしもそうではないと思います。結局は増田川や山林に捨てられる状況になっていると思うのです。そこで、市は監視カメラの設置やパトロールを行っているということですが、それもやはり限界があります。コンビニエンスストアから出たような小さなごみについては、パトロールしても拾い切れないと思います。
そして、もう一つごみ箱の設置が一斉に取りやめられた理由として、当時、オウム真理教のテロ事件があり、駅のごみ箱に危険物が仕掛けられたことから、まず駅においてごみ箱を一斉に撤去した。全国的にそれが広がって、各自治体でも公園などからごみ箱を撤去したという背景があったと見ております。オウム真理教事件は首謀者たちの刑の執行でもう解決しましたので、これを機会に、市としてもう一度ごみ箱を公共施設に設置して、ごみはごみ箱へという施策をとっていただければと思うのですが、そのあたりの御検討はいかがでしょうか。
市長
以前、各地区の公園にごみ箱を設置して、公園の維持管理を委託された地元の自治会等が排出されたごみを処分して維持管理を実施していたわけですが、先ほど申し上げたとおり、粗大ごみの不法投棄、それから犬のふんを捨てるなど問題が発生して、地元の自治会からごみ箱の撤去要請が相次いだという実情もあったように伺っています。そうしたこともあって、基本的には、自分のごみは自分で持ち帰ることが基本であり、それをしっかりと啓発することに力を入れていきたいと考えております。
吉田
結局、ごみ箱に捨てられていた犬のふんなどが今路上に散乱していたりします。昔に比べたら随分マナーはよくなっていますが、いまだに犬のふんが放置されている事例は増田川の近辺などは特によくあります。ごく一部の例外的な方によるかと思いますが、ほかにも散歩コースになっているところでは必ずそういう事例は見られます。
ですから、そのような理由でごみ箱が設置されなくなったのは非常に残念だと思うのですが、もう一つ別な観点で、業者によるごみ箱設置も考えていきたいと思うのです。名取市環境美化の促進に関する条例には、自動販売機の設置者、環境美化促進重点地域内で自動販売機により容器入り飲料を販売しようとする者に対し、自販機ごとに空き缶等回収容器の設置と管理を義務づけていますが、ほかのごみが捨てられるなどの懸念は全くないわけですか。
市長
いわゆる環境基本条例の中に事業者の責務という規定があり、その中で回収等それぞれの責務を果たしていると思います。当然、空き缶や空き瓶の回収容器については投入口の形が少し変えてあるなど、それ以外のものが捨てづらいように、そしてそれぞれの業者が定期的に回収するということで進めているかと思います。したがって、先ほどの公園内等市内各地へのごみ箱の設置とは少し異なる部分があるのではないかと考えております。
吉田
自動販売機から販売されて空き缶となったものをその場で捨ててもらうというのが恐らく回収容器等の設置の一番の目的ではないかと思いますが、実際、全ての方がそうしているのではないと思うのです。家に持ち帰る人がほとんどだと思いますが、路上でジュースを飲んでごみ箱を探したら、たまたま別の自動販売機のごみ箱があってそこに捨てた。だから、必ずしもコカ・コーラの販売業者で設置したごみ箱にコカ・コーラの容器だけがごみとして入っているわけではなくて、ほかの業者の容器も入っていると思います。そもそもそういったことを前提として置いているわけですから、ある程度設置者のごみ以外のものが捨てられることも想定のうちにあると思うのです。であれば、地域に置くごみ箱に本来そこに捨てるべきものではないものがある程度入っても、それは市の責任で回収することもできなくはないと思うのですが、そのような必要性は感じておられないでしょうか。
市長
何度も申し上げますが、自分のごみは自分で持ち帰るのが基本であり、それをしっかりと市民の皆さんにもわかっていただけるように進めていきたいと考えております。
吉田
その大原則はほとんどの方は守っているのです。啓発にはやはり限界があって、どうしても一部マナーの悪い人がいてごみが散乱している。ここにごみを捨てないでくださいという看板があっても、すぐ近くに捨ててある状況です。増田川の清掃活動をしていますと、コンビニから出たと思われるごみが非常に多いのです。なぜわかるかといいますと、買い物袋にコンビニのロゴが入っています。お握りはコンビニによって包装が違うのでわかりますし、パンや菓子、そして、まちのたばこ屋はどんどんなくなっていて、たばこも現在はほとんどコンビニで買われています。ただ、そのコンビニにおいてこれまで屋外に設置していたごみ箱を屋内に移している状況で、例えば車で来た方が、別な店で買い物をして出たごみをコンビニのごみ箱に捨てられない。そのごみはどこに行っているのか。やはり一部はその辺にポイ捨てされたりしているのではないかと思います。
コンビニの店舗数も、最大手のセブンイレブンでは、昭和59年度に2,299店舗、平成29年度の最新のデータでは約10倍の2万260店舗出店しています。環境美化の促進に関する条例ができた当時と比べて10倍ぐらいにふえているわけです。コンビニという社会にこれだけ浸透している事業形態の中で、事業者間において自分の店から出たごみは自分で回収するという意識が必要だと思うのです。これは市に対して言うわけではありません。ただ、市で環境美化条例の中に自動販売機だけではなくてコンビニも位置づけることによって、屋外にごみ箱の設置を義務づけられるかと思いますが、そのようなことは法的に可能かどうかお伺いしたいと思います。
市長
法的に可能かどうかと言われるとなかなか難しい問題ですので、要請をすることになろうかと思います。いずれ御提言いただいている条例制定等の中でどういったことが可能か、十分検討していきたいと考えております。コンビニがなぜごみ箱を中に入れたかというと、恐らく家庭ごみを含めてコンビニで買ったもの以外が捨てられるので、その防止で店内に設置されているという実情もあるわけですので、そうしたことも踏まえてもろもろ検討していきたいと思います。
吉田
それはそもそも事業者側の言い分でしょうが、先ほどの自販機のごみについても同じことが言えるわけです。自販機についてはできるわけですから、コンビニに対しても同じように条例の中に位置づけて、やはり事業者間でごみを自分たちで処理するという意識をきちんと持っていただくと。ある意味では条例にそれを規定することも今後の課題ではないかと思いますので、御検討をお願いしたいと思います。
次に移りまして、生ごみの堆肥化促進について質問いたします。
平成28年度における家庭から排出されたごみの量は、1人当たり1日平均約760グラムでした。これは名取市環境基本計画が目標とする710グラムよりも50グラム多くなっています。家庭から出る燃えるごみのうち、約4割が生ごみというデータもあります。もし生ごみを減らすことができれば、ごみの焼却炉の長寿命化や温室効果ガスの排出抑制などにつながります。
そこで、生ごみを有効活用する一つの方法が堆肥化です。これについては環境基本計画の行政の役割46番に書かれています。生ごみ堆肥化容器購入のための補助金制度については、1年前の平成29年12月定例会で菊地議員が取り上げています。そのときの提案を受けて、周知についてはホームページの内容の更新などで改善されていると受けとめていますが、補助の上限額は2万5,000円に据え置かれたままです。
同様の質問になって恐縮ですが、小項目4 生ごみ堆肥化容器購入費補助金の交付上限額を引き上げるべきについて、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
御承知のとおり、生ごみ堆肥化容器購入費補助金の交付上限額については、現在、販売価格の2分の1で、上限を2万5,000円としているところです。
議員御質問の購入費補助金の交付上限額の引き上げについては、現在、制度の見直しを含めて検討を進めている状況です。引き続き県内各市町村の状況等を把握しながら判断していきたいと考えております。
吉田
検討を進めているということですが、いつまでに検討の結論を出すのか、期間についてと、それから、上限額のほかに補助割合もあります。本市の場合は2分の1までですが、仙台市は5分の3までの補助と記憶しています。この2点について再度お伺いいたします。
市長
できるだけ早期にということで、可能ならば平成31年度中に結論を出したいと思っております。 検討の内容としては、補助額、それから、今、市内業者育成の観点で販売登録店制度をとっていますが、これについては、業者育成の観点と、逆に使う側からすると大手量販店で買えないといったこともあります。また、機種選定の幅についても縛りがあり、どうすれば地域経済の振興に寄与し、そしてまた使う側の利便性を向上させて、よりよい中身になるかといったことを検討しているところです。
吉田
生ごみ堆肥化容器の普及が進んでいない状況だと思うのですが、念のために、平成30年度の現在までで結構ですので、生ごみ堆肥化容器30基と電気式生ごみ処理機の25基という枠の中で、補助が認められた件数についてお伺いしたいと思います。
クリーン対策課長
平成30年度の名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金のうち、平成30年12月3日現在で申請者数は25名、内訳は、生ごみ堆肥化容器の申請が15基、電気式生ごみ処理機については10基です。
吉田
まだまだ余裕がある状況ですが、年度内に予算額の全て補助が認められるかどうかとなると、12月も半ばですのでちょっと難しいのかなということで、やはり普及が進んでいかないという状況かと思います。
普及が進まない事情には、まず、補助が認められても結局3万円ぐらいの出費があるわけで、そのようなそこそこ高い金額であることが1つあろうかと思います。もう一つ、生ごみ堆肥化容器を使ってせっかく堆肥化しても、その堆肥の行き場所が余りないという事情があると思います。自宅で家庭菜園などをやっていればそこで利用できますが、それにしても1年間で大量に出る生ごみを全て堆肥化しても使い切れるものではないと思います。このような行き場のない堆肥を市で有効活用を図れれば、補助制度を使って堆肥化を進めたいという方もふえるのではないかと思います。
そこで、小項目5 家庭の生ごみ堆肥化容器によって作られた堆肥を有効活用できる仕組みを構築すべきについて、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付制度は、堆肥化容器を使用することで、一般家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化に対する意識の高揚を図ることを目的としております。
堆肥を有効活用する仕組みの構築ということですが、各家庭から堆肥を収集し管理するには、専用の施設や人手、費用が必要となります。
堆肥化容器でつくられた堆肥については、各家庭にて無理のない量で生成し消費することを想定していますが、議員御指摘のとおり、どのような活用方法があるのかを今後調査研究していきたいと考えております。
教育長
小中義務教育学校あるいは公民館において、家庭の生ごみ堆肥化容器によってつくられた堆肥を有効活用できる仕組みを構築することについては、堆肥の収集と管理、学校や公民館が必要とする量の調整、学校、公民館への堆肥の搬入等に課題があることから、教育委員会といたしましては考えておりません。
なお、公民館などにおいて環境学習のメニューの一つとして取り上げるなど、効果的な活用につながるような取り組みについて検討していきたいと考えております。
吉田
今、シニアの方などで、趣味で畑を借りて野菜をつくっている方がふえています。農家や本格的にやっている方に生ごみ堆肥を使ってもらうのはなかなか厳しいかと思いますが、趣味でやっている人の中には使いたいという方もいると思いますので、そういう方の手にうまく渡る仕組みについて、例えば公民館などを拠点にすることは答弁では余り前向きではないようですが、今後、一つの課題として進めていただければと思います。
では、次にまいります。第二次環境基本計画の策定に向けた取り組みです。 実施計画書の工程表によると、平成31年2月から基本理念及び基本目標の設定と第二次計画の素案作成が始まるとあります。その環境基本計画に関することについて、市長の諮問に応じ、調査、審議するのが名取市環境審議会です。名取市環境審議会委員の任期は2年間ですが、現体制は平成29年9月に発足しています。委員の選任は市長の権限であり、人選には市長の環境に対する考えが反映されるはずですが、前任委員の再任が7名、そして、再任ではないものの同じ所属団体からの新任が6名となっています。つまり、13名全員について構成が前任者とほとんど変わっていない状況です。
そこで、小項目6 市の環境に対する市長の思いが、平成29年度の名取市環境審議会委員の選定にどう反映したのか、市長にお伺いいたします。
市長
名取市環境審議会は、名取市環境基本条例で定めてあります。平成29年度の名取市環境審議会委員の選定については、学識経験を有する者を8名、関係行政機関の職員を2名委嘱しております。
その他市長が必要と認める者については、一般公募として3名選考していますが、選考に当たりましては、環境審議会一般公募委員選考要領により、地域活動の理解、学歴職歴等、環境への関心度、動機・意見・人柄を基本として選考しております。
私は、環境審議会委員の選定について、これらの内容を確認し、委嘱をしております。
吉田
市長が就任されて最初の環境審議会委員の改選でしたが、そこで前任者と構成がほとんど変わっていないということは、市長は前職の市長が進めてきた環境政策を是とすると捉えてよろしいのですか。
市長
現在の委員については、計画の推進に重点を置いている委員とも捉えております。今後具体的な計画策定に入っていきますので、現在、環境審議会の委員が15名の枠に対して13名ということもありますので、早速、より高度な学識経験をお持ちの方の補充も含めて検討していきたいと考えております。
吉田
小項目7に対する御答弁のようになってしまったので少し聞きづらいのですが、やはりおっしゃったように、第1号委員、学識経験を有する者ですが、現在、学者の方、研究を専門にしている方が3名です。それ以外の分野での学識経験者もいますが、環境の分野で研究、そして実績を出している研究者の割合をもう少しふやすべきと考えております。念のため、小項目7としてお伺いします。
小項目7 来年9月の環境審議会委員の改選に当たっては、名取市環境基本計画の理念を前進させるよう考慮すべきと考えますが、市長にお伺いいたします。
市長
来年9月の環境審議会委員の改選の時期については、今年度より着手いたしました第二次名取市環境基本計画の策定の最終年度に当たります。
第二次名取市環境基本計画策定に当たり、より専門的な見地から御意見をいただくことが重要であると捉えておりますことから、委嘱に当たっては趣旨に沿った人選を行い、環境基本計画の理念を前進させるよう取り組んでいきたいと考えております。
吉田
ぜひ市長の環境に対するといいますか、子供たちの未来、20年、50年先の子供たちの未来に対しての思いが反映された人選を行っていただきたいと思います。
続いて、大項目2に移ります。温室効果ガスの排出抑制についてです。
これも広く捉えれば大項目1に含まれる内容ですが、ことしの夏の異常高温、そして、現在ポーランドでCOP24、国連気候変動枠組条約第24回締約国会議が開催されているタイミングを考慮して、あえて別枠として質問することといたしました。
温室効果ガスの大部分を占める二酸化炭素の量は200年前と比べて約30%増加し、西暦1880年から2012年においては、地上における世界平均気温は0.85度上昇したと言われております。このまま世界中の人々が何も対策をとらなければ、21世紀末には地球の平均気温は最大で4.8度上昇すると予想されています。
以前にも指摘しましたが、この地球温暖化を防ぐためには国際社会の連携が不可欠です。しかし、国ばかりでなはく、自治体の行動も重要です。アメリカでは、昨年6月、トランプ大統領がパリ協定からの離脱を表明しましたが、カリフォルニア州前知事のアーノルド・シュワルツェネッガー氏は演説の中で、「米国の指導者は首都ワシントンの指導者だけではない。州や市、地方政府レベルでは、温室効果ガス排出削減へ向けた動きが続いている」と述べています。日本の各自治体にも率先して行動することが求められております。
本市の環境への取り組みを調べる過程で、温室効果ガスの排出抑制等のための実行計画があることを知りました。これを読んで、ここまでやっているのかと大変市の姿勢を見直したところです。考えられるあらゆる場面において、温室効果ガスの排出抑制に取り組んでいます。そして、その取り組みの結果については、毎年「なとりのかんきょう」で報告されています。「なとりのかんきょう」は毎年年末に発行されていますが、ことしはまだ入手できていませんので、ここで確認したいと思います。
小項目1 名取市温室効果ガスの排出抑制等のための実行計画に基づく平成29年度の取り組み結果への評価を市長にお伺いいたします。
市長
平成29年度における名取市温室効果ガスの排出抑制等のための実行計画の結果等については、「なとりのかんきょう」で公表するものとなっていますが、現在、精査中であり、年度内に作成する予定で進めております。したがって、現段階としましては、公表されている平成28年度分で答弁させていただきます。
平成28年度の名取市温室効果ガスの排出抑制等のための実行計画に基づく温室効果ガスの総排出量は、二酸化炭素換算値で4,162トンであり、評価といたしましては、平成21年度比で6.4%削減してあり、目標としている5%削減を達成しております。 なお、今後も引き続き温室効果ガスの排出抑制に努めていきたいと考えております。
吉田
平成29年度の「なとりのかんきょう」はほぼでき上がっているかと思いまして、その中身を聞きたいと思ったのですが、御答弁がなかったので仕方がありません。次に移ります。
名取市温室効果ガスの排出抑制等のための実行計画には6つの目標が掲げられ、それぞれの目標を達成するための具体的な取り組み事項が定められています。昼休みの消灯など、本当にさまざまな取り組みが行われていると感心いたします。このように非常に意欲的な実行計画ですが、ここに掲載されていなくても実現できることがあるように思います。その一つになとりん号のアイドリングストップが挙げられると思います。バスターミナルとも言える名取駅には、毎日かなりの数のなとりん号が発車時刻を待って待機していますが、アイドリングストップをしている様子を見たことはありません。担当課に確認したところ、委託業者に対しアイドリングストップの指示や呼びかけは行っていないということでした。この状況を市長はどう思われますでしょうか。
小項目2 なとりん号の運行による温室効果ガスの排出に対し、市が関与していない現状をどう捉えているのか、市長にお伺いいたします。
市長
名取市温室効果ガスの排出抑制等のための実行計画において対象としている事務事業の範囲は、市の全機関において市が実施する全ての行政事務事業としていますが、基本的には地方公共団体が所有または賃借している全ての施設・設備になります。
なとりん号の運行による温室効果ガスの排出については、市が所有または賃借していないことから、受託者の事業活動によるものとして捉えているところです。
なお、温室効果ガスの削減等の措置が可能なものについては、受託者に対して必要な措置を講ずるよう働きかけていきたいと考えております。
名取市環境基本条例には、事業者の責務として、環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に積極的に努めるとありますので、それに基づき事業者がみずからの責任で積極的に取り組むべきことと考えております。
吉田
事業者が積極的に取り組んでいれば、駅前で夏と冬以外の気候の温暖なときにはアイドリングストップをしてもいいのではないかと思いますが、駅前でそのような様子を見たことは一回もありません。それは、事業者側は、市からある程度の助言といいますか、そういったものが全くないので気づいていないのではないかと思うのですが、この点は市長はどのように分析されますか。
市長
先ほど御答弁申し上げましたが、必要な措置を講ずるように働きかけを行っていきたいということです。現状、もしそういったことが日常的に行われるのであれば、不要のアイドリングはできる限りやめていただくということだろうと思います。
吉田
あくまでも実行計画の中に書くか書かないかという問題であり、行おうとしていることは同じかと思います。アイドリングストップはどのぐらいの時間で効果があるか実験した方がいて、5秒間エンジンをかけている状態と、エンジンをオフからオンにスタートするときに使用するガソリンの量は大体同じだそうです。だから、停車して5秒以上エンジンをかけたままにしていれば無駄になる。5秒以内の停車であれば、エンジンを切ってかけ直すほうが逆にガソリンを多く使うらしいです。これは大型車にも言えるかどうかはわかりませんが、ぜひその辺の検討も含めて調査していただきたいと思います。
そこで、小項目3 バス停車時におけるアイドリングストップの条件の基準を定めるなど、公共交通対策事業での温室効果ガスの排出抑制に取り組むべきと思いますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
温室効果ガスの排出抑制の取り組みとしては、名取市温室効果ガスの排出抑制等のための実行計画において、公用車の運転に際し、暖機運転の抑制、急発進、急加速、不要なアイドリングをしないこと等を明示し、環境に優しい運転に努めて温室効果ガスの排出量の削減に向けて取り組んでいるところです。
なとりん号に関しての温室効果ガスの排出は、受託者に対し温室効果ガスの排出抑制に取り組むよう働きかけをしていきたいと考えております。
吉田
働きかけをしていくということで、市は規制をかけるところまでは考えていないと思うのですが、温室効果ガスだけではなく、排気ガスはいろいろと非常に有害な物質を含んでいるので、駅前でバスを待つ方に対する健康被害なども考えなければいけないと思います。事業者といっても、市で委託をしているということはある意味で市と一つといいますか、そこまでは言えないかもしれませんが、ぜひこれは市で、例えばいつからいつまでとか何秒以上、太陽の出ている時間など、少し詳しく基準を設けたほうが事業者もやりやすいと思いますが、市長はどのようにお考えでしょうか。
市長
事細かに規定、決まり等で事業者に対して縛りをかけることはなかなか難しいかと思います。ただ、先ほど申し上げたとおり、環境の保全及び創造に積極的に努めるとなっていますので、事業者の責務としてしっかりと果たしていただけるように、条例等の趣旨をしっかりと把握して進めていただきたいということは申し上げていきたいと思います。
吉田
ぜひそのようにお願いしたいと思います。
次に移ります。
平成30年9月定例会で市内小中学校へのエアコンの設置が決まりました。子供たちの学習環境として大変結構なことですが、これは全国的な流れとなっており、真夏にはさらに多くの発電量が必要となるため環境への負荷の増大が懸念されるところです。
ことし10月28日の河北新報の朝刊に、仙台市泉区在住の12歳の小学生の投書が掲載されていました。一部を抜粋して読み上げます。学校にクーラーをつけたらもっと温暖化が進んでしまう。クーラーがあれば部屋が涼しくなって過ごしやすいと言われる。だが、その分、外の環境が悪くなる。温暖化を防ぐためには、クーラーを設置するのではなく、緑のカーテンを普及させたほうがいいと思う。
大変意識の高い投書であると思います。この子が提案している緑のカーテンは、建物の外側に植物を生育させることによって、建物の温度上昇抑制を図る省エネの手法です。窓の外側に網を張ってアサガオやゴーヤーなどを育てている一般住宅を見かけたことがあるかと思います。これは、もちろんエアコンのある部屋でも効果を発揮します。窓の外に緑のカーテンを設置すれば直射日光が入り込む量が少なくなるため、エアコンの運転による消費電力を抑えることができます。また、植物は光合成によって二酸化炭素を分解しますので、まさに一挙両得であると思います。
そこで、小項目4 学校へのエアコン設置に伴い、児童生徒を活動の主体とする「緑のカーテン」事業を推進すべきと考えますが、教育長の御見解をお伺いいたします。
教育長
夏の学校の暑さ対策として、御紹介がありましたように、現在、教室へのエアコン導入を進めているところです。緑のカーテンを設置することは教室内の温度上昇を抑える効果もあることから、エアコンの電気使用量も削減され、結果的に二酸化炭素の排出を抑制する効果も期待されます。
緑のカーテンについては、現在、市内小学校、義務教育学校のうち6校が取り組んでおり、理科の授業等で教材として活用している学校もあり、児童もその世話にかかわっております。
緑のカーテンの設置は温室効果ガスの排出抑制と環境教育にも役立つものであることから、今後も継続して行っていくことと、あわせて取り組んでいない学校へも紹介していきたいと考えております。
吉田
もう6校で実施しているということですので、これから広がっていくことを期待します。さらに、緑のカーテンといっても植物であり、植物を育てるためには肥料が必要です。そこで、生ごみ堆肥化容器でできた堆肥を学校で使用すれば、市民にもプラスになりますし、学校にとってもプラスになります。みんな無駄にしないで有効に使うという循環型の学校教育になるのではないかと思いますので、そのようなこともぜひ今後検討していただきたいと思います。
次に移ります。
地球温暖化防止のための取り組みは、住民一人一人の意識が高まり、行動に移すことが必要です。温暖化による自然災害の大規模化、食料生産量の縮小、不可逆的な生態系へのダメージ、命を脅かす疫病の発生、そして国が失われる小さな島国の人々の存在などについて、日本で話題に上ることは余りありません。温暖化による影響の周知、温室効果ガス排出抑制についての啓発もやはり行政の役割の一つであると考えます。名取市環境基本計画には、行政の役割として、60番に体験型の環境学習プログラムの開発、61番に環境学習出前講座の充実が定められています。
そこで、小項目5 環境保護団体と連携し、市がかかわるイベントにおけるブースの設置や教育施設における公開講座等の開催を通し、温室効果ガス排出抑制を啓発する機会を拡大すべきと考えますが、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
環境保護団体と連携して温室効果ガス排出抑制を啓発するブースの設置等は現在行っていない状況ですが、情報を収集し、実施に向けて検討していきたいと考えております。 また、公開講座といたしましては、出前講座の「なとりのかんきょう」において、温室効果ガス排出抑制の内容も取り入れたものとなっておりますので、教育委員会を通し学校等にPRすることで、啓発する機会を拡大していきたいと考えております。
教育長
公民館などの社会教育施設が主催する講座についてですが、環境保護団体と連携し、直接、温室効果ガス排出抑制をテーマとした講座は行っていないのが現状です。
しかし、公民館講座全体の中で地域課題を捉えたとき、「環境」というキーワードは大切なテーマの一つであり、環境に関する講座は幾つか開催されております。また、生涯学習推進事業として、市長答弁にもありましたように、市職員が直接出向いて行う出前講座のメニューとしても取り入れているところです。
今後、環境に関する市民の学習要請を踏まえ、それぞれの地域課題を捉えながら学習機会の提供を図っていきたいと考えております。
吉田
まず市長に、これから実施の方向で検討ということですが、市の主催するイベントにはいろいろとお祭り的なものがありますが、自治体の中では、環境フェスタや環境フェアなど環境に絞ってイベントを行うところもふえています。七ヶ浜町ではしちがはま環境フェスタ、亘理町、わたり環境フォーラム、石巻市、環境フェア、大崎市、おおさき環境フェア、利府町、りふ環境まるごとフェア、角田市、角田市環境フェスティバルと、どの自治体もやって当たり前のような状況です。市の行事として今後そこまで拡大できたらさらにすばらしいと思うのですが、お考えをお聞きしたいと思います。
それから、教育長には、あくまでも生涯学習ということでしたが、学校の教育の中でも、地域における地球温暖化防止促進活動など、環境保護団体が学校に出向いて行っている取り組みがあります。例えば、県内に本部を置くある団体の報告書を見ると、平成29年度の小学校における環境出前講話は、利府町では何と4回も行われています。仙台市が3回、そして大崎市、栗原市、加美町、美里町、多賀城市、登米市と、本当に多くの自治体で子供たちを対象とした出前講座が行われています。授業そのものへの講師の派遣も、数は多くないようですが行われています。こういったことの今後の検討について、お考えをお伺いしたいと思います。
市長
環境については大変重要なテーマの一つであると考えておりますので、まずは秋祭り等の人が集まるところでブースを出すというようなことから始めていけたらと思いますし、次のステップとして、環境フォーラム等についても検討課題の一つになろうかと思っております。
教育長
学校現場におきましては、総合的な学習の時間などにおいて、環境を一つのテーマとして取り上げて学習している学校がかなり多くあります。環境のうち何を取り上げるかということは、それぞれの学校の地域の実情やそれまでの学習の成果などを踏まえて学校ごとに検討しており、さまざまなテーマに取り組んでいるものと思っております。議員から御紹介のあった取り組みなどについても、機会を見て各学校に紹介していきたいと思っております。
吉田
ありがとうございました。ぜひそのように進めていただきたい、また、今後の課題として考えていただきたいと思います。
最後の質問に移ります。
本市では、名取市温室効果ガスの排出抑制等のための実行計画にのっとって温暖化防止の取り組みが行われています。これは大いに評価されるべきだと思いますが、ほとんどの市民は、この行政による具体的な取り組みを知らないのではないかと思います。年1回発行される「なとりのかんきょう」は、全世帯に配布されているわけではありません。そもそもこのようなものが発行されていることをほとんどの方が知らないのではないかと思います。これは、やはり知られないことには幾ら努力しても伝わるわけがない、まず知ってもらうことが最初だと思います。このように本市が努力していること、そして努力から生まれた結果を広く知ってもらうことにより、行政がそこまでしているなら私たちもというぐあいに、市民の意識もより高まることが期待できようかと思います。
そこで、小項目6 温暖化防止のための取り組みについて、ホームページやSNSを活用し、広く周知すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
温暖化防止のための取り組みについては、市のホームページに「なとりのかんきょう」やみやぎ環境交付金事業で実績を掲載しております。今後、広報、ホームページ、フェイスブック等により、さらに広く周知をしていきたいと考えております。
吉田
SNSについてはいかがでしょうか。本市でも、水道事業所や防災安全課のようにツイッターのアカウントを持っている部署がありますが、クリーン対策課でもアカウントを取得して独自に情報発信を行うと、年に1回などの長いスパンではなくもう少し短い間隔で、その都度発信できると思いますが、市長はどのようにお考えでしょうか。
市長
現状の取り組みについて、市民を含めて広く理解していただくことは大事なことだと思っております。先ほどフェイスブック等と申し上げましたが、ツイッターも含めてどういった形で周知を図ればいいのか考えていきたいと思います。
吉田
いろいろなツールがありますので、どれがいいか選ぶのではなく、あらゆるものを使う、使えるものはできるだけ使うといった方向で進めていただきたいと思います。
最後に、蛇足になるかもしれませんが、残りの時間でブータンという国の国王が1970年代に提唱した国民総幸福量を紹介したいと思います。
国民総幸福量は4つの柱から成っております。1、持続可能で公平な社会的・経済的開発、2、自然環境の保護、3、伝統文化の保護と発展、4、よりよい統治の促進です。そして、大事なことは、1番の社会的・経済的開発は、ほかの3つの要素があって初めて人々の幸福に資するものだと考えられています。江戸時代の末期に日本を訪れた外国人の多くが、「人々は貧しい。しかし幸せそうだ」という内容の感想を残していますが、いつのころからか、この日本は「人々は豊かだ。しかし幸せそうではない」という社会になってしまったように思われます。ブータンの国民総幸福量からいいますと、1番を追求する余りに2番から4番をないがしろにしてきたのがその原因ではないかと私は思います。
本市は住みよさランキング上位としばしば聞きます。大変結構なことですが、国民総幸福量のような考え方もあることを御承知おきいただき、環境政策も含めた今後のまちづくりを進めていただきたいと思います。 以上で私の一般質問を終わります。
本会議
(議案第121号 名取市墓地公園条例)
吉田
第17条に「市長は、第11条第1項の規定により使用許可を取り消したときは、焼骨を一定の場所に改葬することができる」とあり、その第11条第1項は第7号まであります。それぞれケースによってさまざまかと思いますが、もしこういう事態が起きたときに、「市長は」となっていますが実際に市長自身がお骨を改葬するわけではないと思いますが、市の職員がお骨を移すようなことをするのか、あるいはそれなりのお坊さんとか宗教関係の方にお願いするのか、そのあたりはどのように想定されているのでしょうか。
クリーン対策課長
そちらに当たっての具体なところはまだ想定していないところです。その区画から移すに当たっても、そういった区画が何件か出てから対応するのか、それとも1回ずつ生じた際に対応するのかということもあります。その場合、焼骨になった方に敬意を表するために宗教的なものを取り入れるかどうかについては、政教分離などの問題もありますし、そこは現在検討しているところです。
吉田
それからもう一つですが、そのように改葬したとして、その後、また遺族の方が第11条第1項に該当しなくなった場合、その際にまた自分でお墓を戻したいと言ったときに、名取市の墓地公園に再契約し直すことは難しいのかもしれませんが、改葬についていま一つイメージが湧かないのです。骨つぼそのものを移すのか、それとも骨つぼの中を一緒にしてしまったりするのか。またもとに戻してほしいと言ったときにそれにきちんと対応できる形で考えていらっしゃるということでよろしいですか。
クリーン対策課長
こちらの対応をする場合、改葬する先の種類としては、例えば合葬墓のような形になるかと思います。そちらの焼骨というか遺灰については、お寺や墓地によって対応はさまざまです。ただ、今議員がおっしゃったようなことも想定されますので、そちらの管理については、どういった手法でするのか、骨つぼの状態でおさめて並べていく形になるのか、ただ、余りにも数が多くなって対応できない場合については、ある程度になったらやむを得ない措置として骨つぼをあけて遺骨をまぜてしまうことも将来考え得るかもしれません。ただ、今回どのような対応にするかについては、まだ具体の検討中です。一応そういうことも検討していることは申し述べておきたいと思います。
(議案第133号 平成30年度名取市一般会計補正予算)
吉田
8ページ、9ページ、14款2項1目総務費国庫補助金の社会保障・税番号制度システム整備費補助金の内容についてお伺いいたします。
市政情報課長
こちらの国庫補助金の中身ですが、住民票に旧姓を併記するという制度の改正が今進められております。その旧姓を住民票に併記するためのシステムの改修に用いる財源です。
吉田
12、13ページ、18款2項7目ふるさと寄附基金繰入金ですが、どの項目からの繰り入れで、どういったことに充当されるのかお伺いいたします。
財政課長
ふるさと寄附基金繰入金の中身について説明させていただきます。充当先としては、1つ目として、都市計画の道路網の見直し事業の市負担分に充当していた分ですが、こちらは歳出で事業費が減となっていることから247万9,000円の減としています。2つ目として、若竹園の備品購入ということで、ウッドチェア、木製デスク等の備品整備をしています。こちらは七十七銀行の七十七愛の募金会から寄附をいただいたもので、17万3,000円充てています。3つ目として、閖上小中学校の遊具の設置、備品購入に2,000万円を充てているところです。閖上小中学校については、寄附者から閖上小中学校へという意向がありましたので、今回そちらに充てているところです。
吉田
16、17ページ、2款1項6目企画費の自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金とありますが、この市区町村長の会の内容についてお伺いいたします。
政策企画課長
この自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会は、北海道・東北といったような全国のブロックごとの設立の発起人の首長の方々の呼びかけによって今回設立されたものです。内容としては、住民の健康増進や観光振興、環境への負荷の低減といった自転車の効用を増すための施策についての関係機関への要望、あるいはそういった観光施策について各自治体での振興等を目的に情報交換等を進める会ということで設立されたものです。
吉田
大変有意義なことだと思います。念のために確認しますが、この会に所属している市区町村の数とか、全体に占める割合がわかればお伺いしたいと思います。
政策企画課長
全国の市区町村のうちの294の自治体が現在加入していると聞いております。
吉田
32、33ページの4款2項1目清掃総務費の委託料、ごみ分別促進アプリ設定委託料についてです。先ほどクリーン対策課長から製品化されているものを使うというお話がありましたが、OSは何か、お伺いします。
クリーン対策課長
こちらのアプリは、スマートフォンを対象としているものです。アンドロイド、iOS、どちらでも対応できるソフトアプリとなっているところです。
吉田
アプリは会社がつくったものですので、例えば途中で会社の判断によって更新をやめてしまうこともケースとして想定されることかと思います。この契約の内容ですが、最低何年間は使えるとか、そういうところが決まっていればお伺いしておきたいと思います。
クリーン対策課長
例えば今後5年間とか、そういった形の契約ではなくて、毎年更新という形で契約するものです。
吉田
38、39ページの8款2項3目道路新設改良費の15節工事請負費について伺います。浜街道線待避所設置工事とありますが、まず、こちらの内容についてお伺いしたいと思います。
土木課長
浜街道線待避所設置工事については、浜街道線のJR西側の本線部の狭隘部において、車両交通量が多い上に自転車や歩行者も多くすれ違いが困難なため、待避所の設置を要望されていることと、また、沿道の宅地開発が実施されることから同時に水路整備を施工することにより効果的な整備ができることから、工事請負費を補正するものです。
吉田
大変狭い道路で、これまでもたくさん要望があったかと思いますが、まず、今後の待避所の設置の完成までのスケジュールと、その後の道路そのものの拡幅の見通し、この2点についてお伺いしたいと思います。
土木課長
今回設置する待避所は、水路側、要は道路の南側になりますが、そちらにVS側溝の400型を2カ所、合計68メートルほど設置します。それで車や自転車、歩行者がすれ違える場所を2カ所設ける計画で、これについては今後工事を進めていくことにしております。
それから、改良計画については、地元の町内会長の方々と話し合いをしましたが、まずもって官地幅内の改良を進めていただきたいという要望のようです。ですから、まず待避所をつくって、それで車と自転車、歩行者のすれ違いの交通量を見て今後進めていきたいということで、今のところは改良ではなく、既存の官地幅内で整備を進めたいと考えております。
吉田
44、45ページの9款1項3目消防施設費の18節備品購入費、人員輸送車購入費とありますが、こちらの内容についてお伺いいたします。
消防本部総務課長
人員輸送車については、消防車仕様の29人乗りのマイクロバスです。この消防車仕様というのはLED散光灯、いわゆる回転灯、サイレンアンプ、それから消防カラーといって赤色に塗ったものです。こちらの購入費となっております。
吉田
消防車と見た目が似ているマイクロバスと理解したのですが、今この補正で提案されている理由というか、何か緊急性が出てきたものなのでしょうか。そのあたりの経緯をお伺いしたいと思います。
消防本部総務課長
まず、なぜこの時期に補正で消防車仕様のマイクロバスをお願いしているかということですが、こちらに関しては44ページの特定財源に700万円計上しております。こちらは、名取市の消防施設の復旧に役立ててほしいということでサントリーレディスオープンゴルフトーナメントのチャリティー収益金をいただいたもので、今までも消防団車両等を購入させていただいておりました。しかし、今年度は6月に大阪北部地震、7月に西日本豪雨、そして8月に台風20号被害等があり、本市としても復旧のためにいただいているところではありましたが、そういった被害のあるところに寄附をということで辞退させていただきました。サントリー側からは検討させてほしいということでしたが、その後、9月末にサントリーから本市に寄附をいただくことになり、今回、この消防車仕様のマイクロバスの購入に充てさせていただきました。
なぜマイクロバスかというと、名取市消防本部のマイクロバスは平成23年の東日本大震災の津波によって全損しました。それで、同年11月に鹿児島県の妙見温泉観光協会から寄贈していただいたマイクロバスを消防本部で使用していましたが、平成5年式で25年経過しており、走行距離も25万5,000キロメートルということで、最近は故障が多発して修繕費もかさんでおりました。そういったことからマイクロバスの購入に充てさせていただくということです。
吉田
44、45ページ、9款1項4目防災費の河川洪水ハザードマップGIS設定委託料についてお伺いします。先ほどの御答弁ではGISの内容の更新ということだったかと思いますが、現在のこのハザードマップは平成7年10月作成のものではないかと思いますが、そのあたりの確認をお願いしたいと思います。
防災安全課長
現在のハザードマップのデータについては、昭和61年8月5日、平成6年9月22日の2つの洪水の実績と浸水予測結果に基づいてつくられたものです。
吉田
平成6年の水害ということで、平成7年に作成されたものかと思います。それで、県のホームページに各自治体のハザードマップが一覧で載っているのですが、本市のハザードマップだけが、拡大しても画質が粗いというか、非常に見づらいとよく指摘されます。今回GISにこのハザードマップを設定することによって、県のホームページからのリンクもそこにつながるように設定し直されると捉えてよろしいでしょうか。
防災安全課長
こちらについては、本市のなとりマップだけでの更新ですので、県にはリンクしないということです。
吉田
50、51ページと52、53ページの両方ですが、名取駅前再開発ビル管理組合負担金が10款5項2目公民館費と10款5項4目図書館費に計上されています。これは当初でも金額が出ていますが、そのときには規約がまだ完全に決まっていないという答弁だったと記憶しています。まず、この管理組合の負担金について、これはあくまでも北棟の部分の管理組合なのか、それとも駐車場棟の管理組合も入るのか、その内容を詳しくお伺いしたいと思います。
生涯学習課長
今回お願いしている部分ですが、北棟のところに駐輪ラックを設置していますが、違法駐車防止用の利用料の集金システムを追加で整備することに伴い、今回、経費を新たにお願いするものです。
吉田
その新しく必要になったというのはわかりますが、必要になる都度、このように求められて、それをそのまま認めていいのか、少し疑問に思うところがあります。その駐輪ラックに市として負担するのは、全体のうちの何%の金額になるのですか。
生涯学習課長
今回の負担金の算定方法ですが、共有部分の全体の面積を案分して、それに基づいて算定しています。全体から見ると、図書館と公民館を合わせると大体81%ぐらいになります。
(議案第140号 名取市職員の給与に関する条例及び名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例)
吉田
人事院勧告そのものが調査対象としている企業として、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の全国の民間事業所となっています。これだけの規模の事業所といえば、やはりそれは会社の分類としては大きな会社かと思います。ちなみに全国に5万8,004カ所ほどあるということらしいのですが、名取市内でこの規模の事業所に当たる事業所の数を把握されていればお聞きしたいと思います。
総務課長
特に把握しておりません。