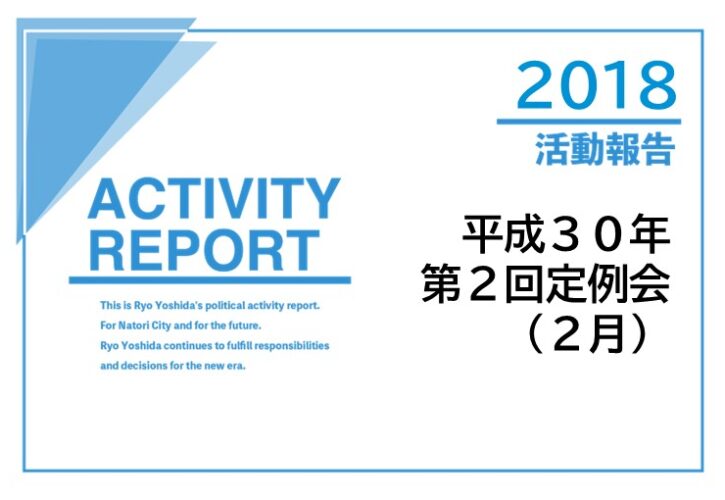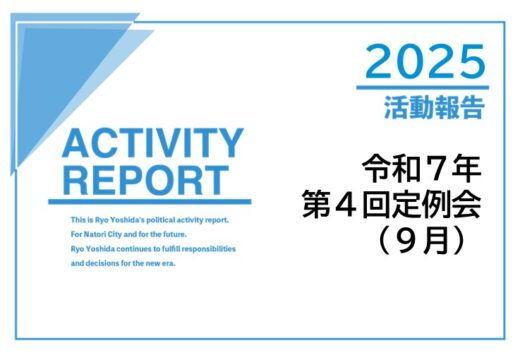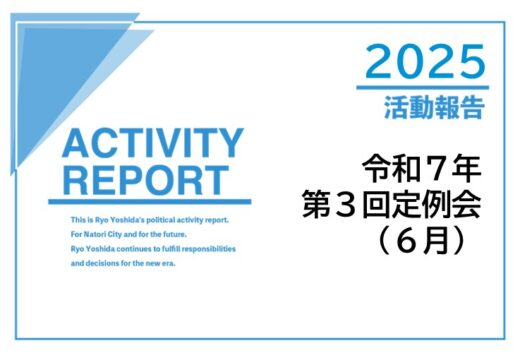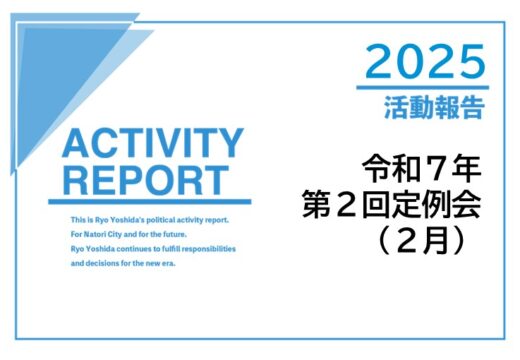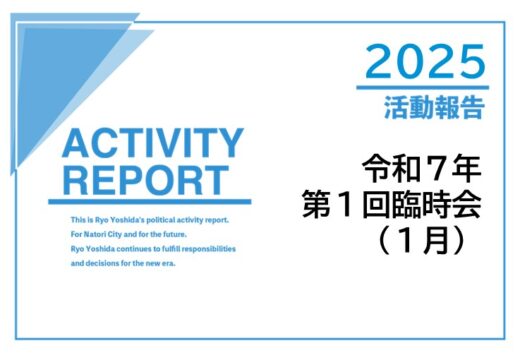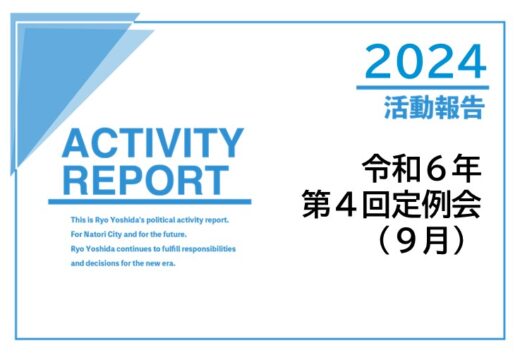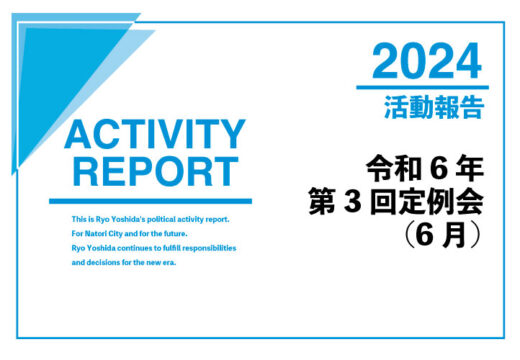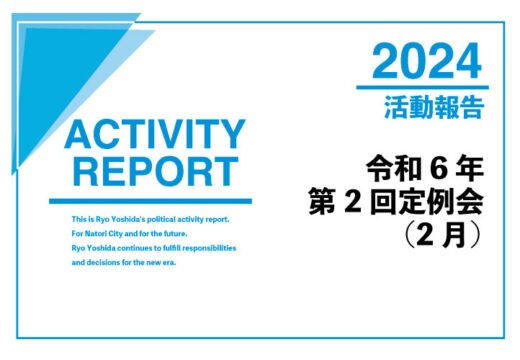本会議
(議案第28号 財産の取得)
吉田
資料の1ページに案内図がありますが、W-37とW-41は一度整備が取りやめとなっていたような記憶があります。また、E-35街区は、1区画だけがなしということで、それ以外9つのスペースがあったと思いますが、こちらも変更になっているようですので、そのあたりの経緯についてお伺いいたします。
復興まちづくり課長
まず、閖上小中学校の南側の件ですが、ここが29区画ありました。それに対して25区画の契約を行い、間もなく完成の運びとなっています。そこの4区画が残っておりましたが、そちらの2区画に今回整備するという形です。その2区画がふえた理由ですが、今回整備する右下のほうにある街区公園-5の付近で、戸建て住宅4戸の整備の計画がありましたが、こちらの4戸のうち1戸の辞退がありました。残りの2戸については、団地の集約を図りたいという市の意向を伝えて、この閖上小中学校の南側に移動していただくことを承諾いただきました。もう1戸については、医療福祉施設の街区に移っていただくことで承諾いただきました。その医療福祉施設のほうの計画ですが、17戸で進めておりましたが、こちらで4戸の辞退を受けています。そのあいた街区に先ほどの1戸の方に移動をお願いして了承いただきまして、閖上小中学校の南側で2戸、医療福祉施設側で14戸、合わせて16戸の建設を今回行うということです。
吉田
よくわかりました。ということは、最終的に戸建ての整備はこれで全てということでよろしいのでしょうか。
復興まちづくり課長
戸建て住宅については、この16戸をもって完了と考えております。
(議案第38号 市道路線の廃止及び議案第39号 市道路線の認定)
吉田
議案第39号の資料の1ページでお伺いいたします。増280の名取駅東口自由通路線が新しく認定されるということですが、こちらは階段部分も市道に含まれるのでしょうか。
土木課長
階段部分についても市道認定されます。
一般質問
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、通告に従い一般質問を行います。
まずは、大項目1 名取市文化会館の施設及び設備の充実についてお伺いします。
文化会館は、平成29年に開館20周年を迎えました。記念事業として企画された復曲能「名取ノ老女」の上演は、盛会裏に終わりました。少し気が早いようですが、10年後の30周年も視野に入れて文化会館の施設や設備について御一緒に考えていただきたいと思います。
名取市文化会館条例には、市民の文化の向上及び福祉の増進に寄与するため、文化会館を設置すると明記されております。ここに示される向上させるべき文化には、大きく2つの方向性があると考えます。1つは、音楽や舞踊、絵画や写真など作品を鑑賞すること。もう一つは、作品をみずから表現することです。
鑑賞については、文化会館が主催する公演を初めさまざまな催しが行われており、充実していると感じます。また、表現についても、発表や練習のためのスペースが十分に備わっており、多くの利用者から高い評価を受けております。しかし私は、文化会館の表現施設としての役割に、さらなる充実を求めたい。まずは、楽器の貸し出しです。
文化会館には、ピアノ4台と太鼓1台が備品として整備されております。また、音楽練習室2には、ドラムセットが置かれております。使用頻度の高い楽器から優先的に選ばれていると思いますが、これで十分と考えるべきではないと思います。文化のさらなる向上のためには、使用頻度が余り高くない楽器も徐々に充実させていくべきではないでしょうか。文化の向上には、地域の文化資源を生かすという視点が大切です。
では、本市が持つ文化資源とは何か。その一つとして吹奏楽が盛んであることが挙げられます。文化会館を拠点に活動している名取交響吹奏楽団は、これまで全国大会に21回出場し、うち7回金賞を受賞しております。また、市内の学校も吹奏楽部の活動が盛んです。市民にとっては演奏を聞ける機会に恵まれており、気軽に楽器を体験できる環境が加われば、ますます吹奏楽の文化は広がっていくものと期待されます。
そこで、小項目1 市民の貸し出しの要望に応えられるよう、特殊楽器を初めとする吹奏楽の楽器を備品として購入すべきについて、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
名取市文化会館では、ホール等を含め各施設において、施設の利用目的に合わせ必要な設備、備品等を備え、利用者に提供しているところです。
御質問にありました特殊楽器を初めとする吹奏楽の楽器類の備品については、利用頻度や必要性、また保管場所を考えますと、市の備品として購入し、市民に貸し出すことは難しいものと考えております。
教育長
文化会館では、各ホールにピアノを備えておりますが、吹奏楽等でホールを利用する際は、ピアノ以外は個人の所有する楽器を持ち込み、利用していただいているところです。近隣自治体等の公共文化ホールの状況を見ますと、ピアノ以外に吹奏楽等の楽器を備えている施設はない状況となっております。
このようなことから、市長の答弁にもありましたとおり、特殊楽器を初めとする吹奏楽の楽器を購入し、備品として貸し出しすることは考えておりません。
吉田
このような質問をするに至ったことについては恐らくお察しかと思いますが、平成29年12月定例会で齋議員からも質問がありましたが、市内中学校の部活動、吹奏楽部の所有している楽器の不足の状況があることを、まず1点目に挙げさせていただきたいと思います。平成29年12月定例会の際の市長の御答弁の中で、やはり現場の部活動用の楽器の購入は非常にハードルが高いと、予算のつけ方には制限がありますので、そのように感じました。そこであえて今回は、一般貸し出しと、市民全体向けということで整備をしていく。もちろん使用頻度は先ほど申し上げたように高くはありませんが、低いものでも整備をしていくということが、これからの文化の発展には必要なのかなと思います。
また、同じく教育長も、吹奏楽連盟の補助金をもって各学校の楽器修繕費などに充てて利用しているという御発言をされました。ただ、その助成金は、本市としては年間27万円という額で、もしこれが全額助成されたとしても、楽器を購入するのは1台がやっとというものでありまして、実際にはメンテナンス費用にほとんど消えていく、それでも足りないという状況です。やはり学校単位ではなく、文化振興のための備品として整備していくことが、施設と同様に、学校からの要請に対して貸し出しを行えることにつながっていくのではないかと思いますが、市長と教育長のお考えをお伺いします。
市長
吹奏楽を本市独自の文化と位置づけての御質問ですが、その点については一部うなずけるところもあると感じてはおります。ただ、現実問題、その使用頻度のことで言えば、本当に文化会館にそれを配置することが部活動の利用に実際につながるのかどうか。どういった楽器が必要なのか。そういったマッチングが本当にうまくいくのかということもありますし、また楽器によっては保管場所も相当とってしまうこともあります。また、一つ一つの楽器は非常に高価なもので、財源の問題もありますし、そもそも吹奏楽にある程度集中してやっていくことについての考え方も含めて、整理をしていく必要があるのではないかと考えております。
教育長
議員から御指摘がありましたように、文化会館において本市の文化を発展させていく、そういったさまざまな活動が行われていることについては、あるいはまたいろいろな意味で高く評価していただいていることは、私も聞いております。
御指摘のあった中学校の部活動、吹奏楽との関連について、いろいろ御指摘もいただきましたが、中学校の場合、練習場所はほとんどの場合それぞれの学校で行っております。そういったことも考えると、仮に文化会館に吹奏楽用の楽器があったとして、それを十分にそれぞれの学校で利活用できるかどうかという課題もあろうかと思います。また、確かに吹奏楽の楽器は高価なものですので、なかなか学校で配当されている予算等で購入することが難しい。それは体育で使用するいろいろな用具類や、教科の学習で使用するものについても同様のことは言えるかもしれませんが、文化会館で仮に準備したとしても、中学校の部活動の吹奏楽で楽器を利用することについて、現実的にどうかなということも感じております。
そのようなことから、現時点で文化会館に吹奏楽用の特殊楽器等を含めて準備することは考えておりません。
吉田
なぜ吹奏楽なのかというお話もありましたが、例えば旧中新田町にはバッハホールがあり、パイプオルガンがあります。県内で唯一公的施設にパイプオルガンがあるところですが、実際にパイプオルガンを備えてから相当使用頻度が上がっていると。そのように整備をしてから頻度が上がってくるというケースもあります。そして、そのパイプオルガンのある中新田バッハホールは、これまでの地域づくりが認められて、財団法人地域創造大賞というものも受けております。
このようなこともありますので、本市はやはり吹奏楽が盛んだという環境を大いに生かして、私は個人的に合唱愛好者ですが、吹奏楽がもし盛り上がるのであればそれも大歓迎です。市長としても、子供ミュージカルを育てられたこれまでの経験もありますので、そういった観点から表現活動をさらに深めていくために必要になってくるのではないかと思いますが、もう一度そのあたりのお考えについてお伺いします。
市長
本市の文化芸術がいろいろな形で振興していくことについては、私としても精いっぱい応援していきたいと思っております。ただ、吹奏楽も確かにそういった一つの重要な要素ではあると感じておりますが、そこにある程度集中して投資をしていくということ、またその必要性等、先ほどるる申し上げたような中身については、考え方の整理が必要だと現段階では考えております。
吉田
先ほど財源の問題もお話しされましたが、ほかの自治体で、例えば北海道赤平市や愛知県尾張旭市などで、吹奏楽の楽器を学校で整備するためにふるさと納税が活用されているという例があります。このようなことも検討に値すると思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
市長
それも一つのアイデアかと思いますが、ふるさと納税についてはやはり本市独自のといった切り口もあって訴える力が出てくると思いますので、そうしたことも考慮しながら進めなければならないのではないかと思います。
吉田
では次に、大ホールの舞台の利便性についてに移ります。
大ホールを音楽用として使用する際は、ステージ上に反響板を設置するのが一般的です。反響板は設置されると客席の壁と一体的となります。音響にすぐれた空間になりますが、一方で舞台袖と舞台上の間を移動するために、上手と下手のそれぞれに設けられた幅約80センチの出入り口を通らなければなりません。この幅は人が一列で通るのがやっとであり、同時にすれ違うことができません。出演者が大人数であったり、舞台道具を配置転換したりする場合、移動が終わるまでかなりの時間を要します。また、マリンバなど大型の楽器は通すことができません。1,350名の観客を収容できるすばらしいホールでありながら、こうした構造であることなどが理由で、吹奏楽コンクールなどに利用されることがありません。せっかくの大規模なホールですから、これまで以上に多様な発表の場として使用していただきたいものですが、そのためには改修が必要です。
そこで、小項目2 大ホールの反響板にある出入り口の幅を、1,000人規模の客席を持つ県内の音楽ホールと同程度に広げるべきについて、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
名取市文化会館の大ホールは、構造や機能にすぐれたメーンホールとして多くの方々に文化芸術の創造や発表の場として利用されており、また大ホールに設置する反響板は県内で例のない自走式の本格的な設備と言われております。
反響板を舞台に設置した場合、扉の出入り口幅が90センチメートルで、それを超える大型楽器等を持っての出入りが困難となる状況は承知しておりますが、反響板の構造上の問題等があり、改善には課題が多いと認識しております。
教育長
大ホールの自走式の反響板については、開館当初より出入り口の幅が90センチであったことから、これまで音楽公演等で大きな楽器を使用する際は、最初からステージに楽器を備えるか、舞台正面側からステージに上げる方法で利用いただいているところです。
先ほどの市長答弁にもありましたとおり、大ホールの反響板の扉の幅を広げることは構造上の課題もあることから、教育委員会としても特に考えておりません。
吉田
私も舞台の後ろ側から見ましたところ、やはり鉄骨がしっかり組んであるので、非常に大きな工事になるかと思います。ただ、県内の1,000人規模のほかの施設を見ますと、宮城県民会館の大ホールでは上手下手に約180センチと、名取文化会館の2倍の広さの扉を持っています。仙台市民会館は扉がついていない、スペースがあいているものでした。イズミティ21の場合は110センチ、岩沼市民会館は扉がない状態で上手下手に大体100センチのスペースがあるということです。
もちろん改修にはさまざまな問題があるかと思いますが、先ほど申し上げたように、今後次の10年間を見据えて、ぜひ利便性を高めていただきたいと思います。せめて下手側だけでもという考え方はないか、市長にお伺いしたい。
それから、教育長には、これまで反響板の出入り口が今の広さであることによって、使用に至らなかったケースや、あるいは使用契約を結んだものの、実際に使用した際にいろいろと障害になったケースがなかったかどうか、そのあたりをお伺いします。
市長
ただいま議員もおっしゃったとおり、裏面が鉄骨構造になっておりまして、やるとすればかなり大がかりな工事になるであろうと想定されます。出入り等でかなり不便な場合もあるという問題は認識しておりますが、解決にはなかなか高いハードルがあるなと思っております。気持ちとしては、何とかできるものであれば何とかしたいと思いますが、ハードルも高いというのが現状です。
文化・スポーツ課長
反響板の扉の大きさで契約等に至らなかったケースということですが、文化会館の貸し出し等は、公益財団名取市文化振興財団に指定管理でお願いしているところですが、具体的にそういったケースがあったかどうかについては、教育委員会としては現段階では捉えていないところです。
吉田
捉え切れていない部分が必ずあるはずですので、今後の課題としてぜひお考えいただきたいと思います。
次に、バリアフリーについて考えていきたいと思います。
大ホール1階の後方には、車椅子スペースが8台分設けられております。大ホール入り口から客席の車椅子スペースまで、扉さえ開かれていれば車椅子の方でも自力でたどり着くことができます。しかし、出演者側に車椅子利用者がおられる場合、舞台までの経路に階段があることから、自力でたどり着くことができません。
そこで、小項目3 屋内の空間から大ホール舞台までの経路をバリアフリー化すべきについて、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
文化会館の屋内の空間から大ホール舞台までの経路を、大ホール舞台への出演者等が利用する経路と捉えてお答えいたします。
文化会館の大ホールは半地下式であることから、舞台に1階の廊下やホワイエ側から移動する際は、構造上、階段が伴う通路を使用する以外はありませんが、特に足の不自由な方等が大ホール舞台に移動する場合は、文化会館の南側の外入り口からの平たんな通路を案内し、利用いただいているところです。
なお、大ホール舞台までの経路全体のバリアフリー化は、階段をスロープに改修する必要がありますが、通路の長さや幅はもとより、ホール内外を含めた施設全体に影響する問題もあることから、現実的には難しいと考えております。
教育長
屋内から大ホールまでの経路全体をバリアフリー化することについては、ただいまの市長答弁にもありましたとおり、建物の構造にも影響する大規模な修繕となることから、実施は難しいものと考えております。
吉田
大規模なものになるとのことですが、不可能であるとは今の御答弁からは捉えられませんので、やはりこれも長期的な計画の中でぜひ考えていただきたい。
それから、南側外入り口からの通路について話もありましたが、雨が降っているケースももちろん考えられますし、このまま車椅子を利用される方、特に足の不自由な方にとって使いづらい文化会館の大ホールのままであってはいけないと思いますので、ぜひこれから検討を重ねていただきたいとお願いします。
続いて、大項目2 区長制度の見直しについて。
平成29年12月定例会で、市長は現状では区長制度を廃止する考えは持っていないと答弁されました。率直に申し上げて、私はこの御答弁に不服な立場です。本日は区長制度の問題点、不備な点を幾つか指摘し、段階的な廃止へつなげていきたいと考えております。
区長制度の歴史を調べたところ、昭和52年発行の名取市史426ページにこう書いてありました。「明治22年4月に、市町村制を実施して以来、(中略)市町村の地域内を幾つかの行政区域に区分し、その区分した地域に区長を配置して、行政事務を補助させ」云々、「当名取市においても、旧町村このかた市制施行後も引き続きこの区長制を継続して実績を上げている」云々とのことです。
ことしは市制施行60周年、市になるよりはるか以前の2町4カ村の時代から区長制度があったことがわかります。人口の急増や、各地区で自治組織が設立された時点で、区長制度は役割を終えておくべきであったと私は思います。しかし、実際には区割りなど軽微な変更が行われてきてはいるものの、さまざまな矛盾をはらんだまま今に続いていると認識しております。
まずは、広報紙等の配布業務についてお伺いいたします。
ごく一部の例ではありますが、広報紙等の配布を地域住民が代行している行政区があると聞いております。区長と自治組織、または個々の住民との間で合意形成されているとしても、重大な問題が残ります。それは代行者の災害補償です。
小項目1 区長から依頼を受けて広報紙等の配布を代行する住民が交通事故などに遭遇した際、公務災害として補償を受けられない現状をどのように捉えているのか、市長にお伺いいたします。
市長
広報の配布は、市としてはあくまで区長に依頼している業務ではありますが、地域によっては長年のさまざまな経過がありますので、配布の方法が異なる場合があることは認識しております。区長本人が配布する場合のほか、双方合意の上で区長が町内会等に配布を依頼している場合、町内会等が伝統的に自主的に配布を手助けしている場合などがあり、各地域ごとの取り組みの中、御対応いただいているところです。 そのため、区長以外で対応いただいている方々については、公務災害の対象とはなっていないところです。
吉田
公務災害の対象となっていないことをどう捉えているかについて質問しましたので、もう一度そのあたりをお願いします。
市長
これまでの長い歴史や地域の実情があって、今の姿になっていると捉えております。ただ、広報配布はあくまで区長にお願いしているのが市の立場でありまして、公務災害補償となりますと、公務員が公務執行中に労働災害に遭った場合に限定されますので、厳密に言えばそういった適用には入らないというのが現実です。
吉田
現実の問題はそのとおりで、よく認識しております。そこで、もし代行している住民が事故に遭った際、恐らくそのけがは個人で手当てしていかなければならないと思いますが、そういう現状でいいのかどうかについてお伺いします。
総務課長
市長も答弁したとおり、あくまで公務員が公務執行中に労働災害に遭った場合が公務災害ということで、それ以外の方が配布した場合の代案ですが、基本的に例えば町内会なり自治会、契約会などで入っている保険等で対応していただくものではないかと捉えております。
吉田
自治組織向けの保険はいろいろあると思います。私が所属している自治会にもありますが、その規約の中には、自治組織が企画立案し、総会や会則などによる手続を経て決定された行事を対象とするという一言が書かれております。この広報紙配布代行が、そうした自治会の総会で議決されている、あるいは会則に明記されていることをしっかり確認されているのでしょうか。
総務課長
そこまでの確認はしておりません。
吉田
ということは、保険が適用されないことがあるかもしれない。保険会社の対応次第だと思いますが、絶対に大丈夫だという状況ではありません。非常にこれは問題であろうと考えます。
そこで、小項目2 業務を代行する住民に対し損害補償を担保するとともに、世帯割分の報酬を支給すべきについて、市長にお伺いします。
市長
先ほどの答弁で申し上げたとおり、広報配布等の業務を各地域ごとの取り組みの中で御対応いただいている場合、その方々に市が損害補償を行うことは困難な状況です。
また、現在の区長報酬の世帯割については、おのおのの受け持ちの行政区の世帯数をもとに算定しているところではあります。しかし、区長は行政と地域のパイプ役として、日ごろから地域内の相談業務など多様な業務を行っておりますので、その報酬は世帯割といっても広報配布数だけで決められるものではないと捉えております。
このことから、一部の業務を切り取って報酬を算定したり、一部の業務を切り取ってほかの者と業務委託契約を結んだりということは、現在想定していないところです。
吉田
そうなのです。代行される住民の方は公務員ではないのです。ですから、もちろん公務災害にはならない。そのとおりです。ただ、実際にしている仕事は区長の業務の中の一部である。これは公務なのです。区長がすれば公務であるし、区長から代行を依頼されれば公務にならない。そして、結果として、万が一の際にそのような大きな差が出てしまう。それなら市がその状況を把握しているのであれば、せめて代行する住民に公務ではない普通の労務災害という形で保険をかけていくことはできないのでしょうか。
総務課長
公務の契約を結んでおりませんので、それはできないと解しております。
吉田
では、万が一、市民の方が今後もその代行をすることによって事故が起きてしまった場合は、市としては何もできないということでよろしいのですね。
市長
議員御存じのとおり、区長御本人による配布はあくまで公務ですが、町内会等のお手伝いになると、これは厳密に言えば公務とはなり得ない状況です。ただ、現状、長い歴史、それから地域の実情があって、今の姿になっているということもありまして、そのことは課題としては捉えておりますが、現状そういった形になっているとしか、今はお答えできないということです。
吉田
そのような事故が起きないことが一番なので、気をつけて対応していただくことになろうかと思いますが、ただ絶対に起きないとは誰も保証できません。やはり市民に業務を代行させるということは、そういう危険もあることをしっかり周知して、区長御本人にも代行している住民の方にも理解していただくことが必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長
何度も同じ話になりますが、長い歴史と地域の実情があって今の姿になっております。その地域の実情に市がどこまで立ち入るかということにもなりますが、どのようなことができるかについては考えてみたいと思います。
吉田
区長制度そのものが非常に長いものですので、時代の変化にまさに合わなくなっているというのがまず1点かと思います。
次に移りますが、住民異動の配布業務というものがあります。区長推薦の際に送られる区長についてという文書に、職務内容として区域内の住民異動の把握と明記されております。転入、転出者の把握のことであると思われますが、内容をより詳しく調べたところ、行政区に住む全市民の個人情報が記載される紙媒体の台帳を、区長が自宅に保有しているということでした。非常に驚きました。
私は実物を直接見たわけではありませんが、どうやらこれには住民の氏名、住所、生年月日、そして家族構成がわかる内容が含まれているということです。個人情報の保護のために庁舎における情報管理は非常に高いレベルが設定されていると思いますが、約140名おられる区長の御自宅は一般の個人住宅でありまして、無防備な環境にあると言えるわけです。個人情報流出のリスクが極めて高いと言わざるを得ません。
そこで、小項目3 区長が住民異動を把握するために、住民の個人情報が書かれた文書を自宅で保管する現状をどのように捉えているのか、市長にお伺いいたします。
市長
区長は非常勤特別職の市の職員であり、市の規則で守秘義務を定めております。また、個人情報は、区長業務を行う上で必要最小限のものにとどめており、第三者の目に触れぬよう運用・保管するよう指導しているところです。
住民異動の把握は、原発避難者等、住所を置いていない方への各種検診のお知らせや、防犯上問題のある空き家の把握など、区長業務遂行に必要なものです。
名取市個人情報保護条例の趣旨に基づき、今後とも個人情報を適正に取り扱うよう指導していきたいと考えております。
吉田
もちろん守秘義務は当然あるものですし、第三者の目に触れないようにというお達しでしょうが、その保管の方法はどのように指導されているのか、具体的にお伺いします。
総務課長
区長をお引き受けいただいた際に、各業務の内容等の説明の中で当該リストについての説明もしております。保管についてもお願いはしているところですが、今議員御指摘のとおり、個人情報の最たるものが入っておりますので、できれば金庫や施錠ができる場所に保管していただくのが一番いいとお願いしておりますが、ただ個人のお宅にそういったものが全てそろっている状況ではないと思います。その場合は、先ほど市長が答弁しましたが、第三者の目に触れぬようなところに確実に保管、そして運用をお願いしているところです。
吉田
これも非常に大変な問題で、実際に職員は庁舎から個人情報を外に持ち出すことはできませんね。それはなぜかといえば、外に出せば出しただけリスクがあるからです。守秘義務はもちろんですが、ほかにも個人宅ですから泥棒が入らないとは限りませんし、いろいろなケースが想定されるかと思います。これまでそうした盗難や紛失の事例はなかったのかどうか、今後も絶対にないと言い切れるかどうか、そのあたりの確認をお願いします。
総務課長
盗難等の報告はいただいておりません。それから、今後絶対ないのかというところについては、申し上げるのは難しいと思います。区長には、守秘義務ということで、できる限り保管についても厳重にすることを今後ともお願いしていきたいと思います。
吉田
例えば市として金庫を貸し出すとか、そういうことがあればまだ少しはリスクは低くなるのかと思いますが、もし今後今のような状況を続けていって、盗難や紛失が起きた際は、一体誰がどのような責任を負うことになると考えるのか、そのあたりについてお伺いします。
総務課長
最終的には名取市長ということになります。
吉田
当然そうだと思います。ただ、いずれにしても、このような大事な個人情報を自宅で預かっていることについて、区長御本人たちの精神的な負担になっているのではないかと思いますが、そのあたりの区長のお考えの把握はいかがでしょうか。
総務部長
議員からも区長制度は長い歴史があるというお話をいただきました。区長をお受けいただく場合に、そういったことも含めてお受けいただいているということで御理解をいただいていると認識しております。
吉田
わかりました。ただ、リスクが完全に排除できたわけではありません。もし個人情報が一度でも漏れ出してしまえば、それが名簿業者などによって電磁記録に残される、そして以後完全に消去することはできなくなる、御承知のとおりであると思います。
このように漏れた個人情報は、特殊詐欺などに悪用されたりすることで、市民の安全や財産を脅かします。また、そうでなくても、特にひとり暮らしの若い女性にとっては、幾ら守秘義務があろうと、公的な業務であろうと、個人情報を見られることには抵抗があると察せられます。こうした明治時代から時間がとまってしまっているような情報管理のあり方は、即刻改めるべきであろうと考えます。 小項目4 少なくとも第三者のアクセスを防ぎ、業務上のアクセスは記録が残るシステムを導入すべきであり、それができないのであれば住民異動の把握業務を廃止すべきについて、市長にお伺いいたします。
市長
第三者のアクセスですが、第三者からの悪意のある接触と捉えて答弁をいたします。
住民異動の情報は紙ベースで必要最小限のものにとどめており、先ほどの答弁の繰り返しになりますが、区長には第三者の目に触れぬように運用・保管するよう指導しております。また、セキュリティーの面から紙ベースとしているところであり、現状では御質問のようなシステムの導入については考えていないところです。
住民異動の把握は、住民サービスに漏れがあってはならないとの考えから行っている必要不可欠な業務であり、滞れば市政の推進に影響が及ぶことが懸念されます。一定のセキュリティーは担保されており、必要な業務であることから、現時点の廃止は難しいと考えているところです。
吉田
紙ベースということで、実際にデータ化するよりは流出の危惧のレベルは少し低いと言っておられると理解しました。
ただ、いずれにしても区長の御自宅で市民全員の個人情報、先ほど必要最低限、最小限とおっしゃいましたが、そこには氏名もある、住所もある、そして生年月日があるということは年齢もわかってしまう、家族構成もわかってしまう。これが万が一流出しないという保証はどこにもないわけです。もちろん守秘義務を守った上でも、別な危機が起きるということは想定しておくべきことであろうと思います。
その点も含めて、区長制度は見直しは行うということで、今後震災復興事業が落ちついてきたときに検討するという答弁が前回ありましたが、そのあたりで区長業務の中からこの住民異動の把握を外していくということについて、現状ではどのようにお考えでしょうか。
市長
住民異動の把握については、住所を置いていない方への各種検診の通知や空き家の把握等、防犯上欠くことができない中身となっておりますことから、これまでその業務としてきたわけですが、これまでの経過も含めて、副市長から答弁をいたさせます。
副市長
区長制度については、先ほどから答弁しているとおり、長い歴史のもとに現在の姿があるわけですが、その経過の中では区長制度についてもいろいろな見直しの論議等が行われたのは事実です。ただ、震災以前にはポスティングで広報の配布等、その配布の仕方も検討したことはありますが、震災を受けて、区長制度については当面現在のとおりということで現在もあるわけです。
区長制度の長い歴史の中で、区長業務についても各種変遷をしておりますので、区長に対するデータの提供の仕方についても、現在の方法がいいのかどうかも含めて検討はしてみたいと思います。
吉田
長い歴史があるということで、先ほど御紹介申し上げたように、名取市史によれば明治時代からあるということが恐らく真実であろうと思います。そのような時代から恐らく個人の名前など、個人情報が書かれたものを紙ベースで自宅で保管していたのではないかと思われます。その経緯についてまでは名取市史にはこれ以上詳しくは書かれておりませんでしたが、今は明治時代と違って、もう電話もあるのです。インターネットもあるのです。区長が御自宅でいろいろ業務をする中で、住民の何か心配な点があったら、一々自分のところに台帳を置いておかなくても、すぐに役所に連絡をして何らかの対策をとってもらえるような、そういう世の中になっているのです。いつまでもこのことを明治時代のまま残しておくのは、やはりいかがなものかと思いますが、もう一度その点について、市長からも御答弁をいただきたいと思います。
市長
ただいま副市長から御答弁申し上げたとおり、御質問の点については、そのあり方も含めて検討はしてみたいと考えているところです。
吉田
では、次に移ります。区長制度と自治組織との関係について掘り下げていきたいと思います。
平成30年は区長の改選の年です。区長の選出まで幾つかのプロセスがあり、まず副市長から公民館長宛てに、区長推薦委員の選考について「依頼」という文書が届きます。そこには推薦委員の選考基準として、町内会、契約会等の会長、副会長など、住民の総意をまとめ得る者との記述があります。
そこで、小項目5 区長推薦の内申に必要な「住民の総意」をどのようなものと捉えているのか、市長にお伺いいたします。
市長
地域の主権者である地域住民が、自己責任のもとで自己決定することと捉えております。具体的には、地域住民の比較多数の意思となろうかと思われます。この意味において地域をまとめ得る団体として、町内会等の自治組織に区長推薦の内申をお願いしているところです。
吉田
全員が一致した意見ではなく、比較多数として捉えているということでした。ただ、その比較多数というのも、実際には本当に住民の意見が反映されているかどうかという点について、非常に疑わしいと私は思います。まず、区長推薦委員の選考に関する規則がありましたら、それについて詳しくお伺いしたいと思います。
総務課長
規則は特にありません。
吉田
区長を推薦する人を誰にするかについては規則がないので、現状では自治会の会長にお願いしているということですが、まずこの規則がない中で区長の選考が始まっていくという、その一番スタート地点に大きな問題があるのではないかと感じます。
そこで実際に、副市長の名前で公民館長に対して区長推薦委員の選考についての依頼があるわけですが、そこに区長推薦委員の選考基準として、町内会、契約会と先ほど言いましたが、これをもとに公民館長が区長推薦委員を選んでいくことになろうかと思います。ただ、これはあくまでも町内会などがあることを前提にしておりまして、現在、町内会の加入率が100%ではないことも、以前この議会で発言がありました。町内会に入っていない方の総意はどのように考えているのか、その総意の中に町内会に入っていない方を含まないということでよろしいのでしょうか。
総務課長
結果的にはそのような形になるものと捉えております。
吉田
となると、比較多数という考え方も、町内会の中ですら本当に多数がとれているかどうかもわかりません。例えば、現状で区長の人選に不服がある方が町内会にいる場合、これは総意と言えないのではないかと思いますが、区長を決める段階でそういう方の意見がどのように反映されるのかについてお伺いします。
総務課長
繰り返しになりますが、こちらとしては選考する際に、町内会、契約会等の会長、副会長等、地域住民の総意をまとめ得る方にお願いしておりますので、そういった形でお願いしているところです。
吉田
そもそも町内会は任意の団体であると、何度もこの場で皆さんから答弁いただいております。そうした任意団体から始まって区長を選んでいくと。しかもその中で、任意団体の全体の意思をしっかり確認できるような手順をとっているかどうかもわからない。総会での議決があるかどうかも把握しないままに、一部の役員の署名をいただければ、それだけで区長が選ばれることに関しては、果たしてそのようなことでいいのかと非常に疑問です。
その総意というものを考えていく際、できれば一番理想的なことは選挙することだと思います。投票によって選んでいく。ただ、これは区長に関しては費用の面からもいろいろな面からも現実問題不可能ですので、そうなるとやはり町内会、自治組織が根本に来るのは仕方がないと思います。
ですが、町内会がスタートにあるのであれば、もともと今区長にお願いしている業務を先に町内会にお願いしてしまえばいいのではないですか。何でそこに区長という立場を一つ上に置いて、さらに区長に市の業務をお願いしていくと。なぜ任意団体とはいえ、町内会に委託などの形で事業を進めていくことをお願いできないのか、非常に疑問です。市内一律で区長制度がありますが、やはりこれから見直しの話も進んでいくかと思いますので、そうした際に地域ごとに事情があることもよく理解しました。地域ごとに変えていける、区長のあり方を選んでいける、そういう余地をこれから検討していただきたいと思います。
小項目6 総会の議決などの手続を経れば、広報紙等配布の業務委託や区長への個人情報提供の拒否を自治会組織に認めるべきについて、市長にお伺いいたします。
市長
広報配布については、市が区長に依頼している業務です。また、区長への情報提供は、区長業務遂行に必要なものとして非常勤特別職の市の職員である区長に提供しているものであり、区長は一般の職員に準じた職責や守秘義務があり、職務上必要な情報を得て業務を遂行する責任と義務があるところです。
このことから、市が町内会等の自治組織に直接依頼したり、その業務委託導入の判断を個々の自治組織に委ねたりすることは、現段階では考えていないところです。
吉田
現段階ではということですから、これからお考えいただきたいと思います。ほかの自治体では実際そのように区長制度を廃止するところが出てきておりますので、そのようなところを参考に今後御検討をお願いしたいと思います。
最後の質問事項に移ります。
大項目3 中学校制服の価格についてです。
もうすぐ入学、進学のシーズンです。銀座の公立小学校で、海外一流ブランドの標準服が採用されたことが話題になりました。こちらは一式そろえた価格8万円以上ということで、成長期の小学生に着せることはいかがかという疑問の声も上がったと伺っております。このケースと比較すると、本市の場合かすんでしまいますが、本市の中学校制服ももう少し価格を抑えられるのではないかと私は思います。
平成28年6月定例会一般質問で、制服の価格について保護者の負担軽減を求めましたが、教育長からは、現在適切な価格であるとのお考えを示されました。その約1年半後の平成29年11月29日、公正取引委員会が公立中学校における制服の取引実態に関する調査報告書を発表しました。
そこで、小項目1 公正取引委員会が平成29年末に発表した、公立中学校における制服の取引実態に関する調査結果をどのように受けとめているのか、教育長にお伺いいたします。
教育長
ただいま議員からも御紹介がありましたが、平成29年11月29日に公正取引委員会から公表された、公立中学校における制服の取引実態に関する調査では、学校と制服メーカー及び販売店との関係、制服の販売価格、制服の取引における公正な競争の確保がポイントとして示されました。
販売価格は、最も多い販売価格帯が3万円から3万5,000円であることが示されております。市内の中学校の制服販売平均価格は、男子が3万4,000円、女子が3万3,000円であり、全国と比べても平均的な価格であると認識しております。
市内中学校の制服は、名取衣料店会を通して制服メーカーから購入しております。販売価格については、かなりの間ほぼ据え置きとなっております。原料として使う生地などを一定程度まとめて用意し価格を抑えるなど、衣料店会や制服メーカーの努力があるものと捉えております。
吉田
平成28年12月定例会の質問の答弁では、制服の価格が据え置かれて、男子Mサイズ3万4,000円、女子Mサイズ3万3,000円ということでした。公正取引委員会の調査結果によると、10年前の平成19年ごろは男子が2万8,000円、女子が2万7,000円で、そこから徐々に制服価格が上昇してきたという傾向がありました。本市の制服価格については、平成19年までさかのぼってとは申しませんが、価格の変更についてデータが残っていればお伺いしたいと思います。
教育長
中学校の制服は、基本的に各学校で業者と契約を結んで購入しておりますので、詳細な価格の推移までは把握しておりませんが、価格の推移の一つとして、消費税率が8%に上がったときは、それに合わせて制服の価格も上昇していると把握しております。それ以前のかなり前までさかのぼっての制服価格の推移までは把握しておりません。
吉田
税率が上がらないで価格が上がらなければいいのですが、今後のこともありますので、もう少しお聞きしたいと思います。
先ほど申し上げた調査報告の中で、制服販売店が保護者に対して制服の案内をする際に、指定販売店とする、取扱販売店とする、それとも案内をしないという3つのパターンがあります。本市には5校の中学校がありますが、どの形に当たるのですか。
学校教育課長
市内5校の中学校において指定しているのか、取扱店なのかということは、教育委員会としては把握していないところですが、採寸等を衣料店会により学校で行い、納入も学校を通しているところです。また、その際に制服を準備できなかった場合、もしくはサイズが大きくなって制服が着られなくなった場合には、市内の複数店舗で購入できることは確認しているところです。
吉田
指定か取り扱いかの違いですが、取り扱いの場合は学校の制服の仕様を満たすのであれば、学校が案内する販売店以外で制服を購入してもよいと案内していると定義しているのです。そのようなことは、本市の学校では認められているのですか。
学校教育課長
制服についてはそれぞれの学校でデザイン等を決めておりますし、それを複数のお店で買うことができるということです。
吉田
では、今おっしゃった学校の制服の仕様を満たすという、その仕様というのははっきりと保護者に明示されているということでよろしいのですか。
学校教育課長
仕様と申しますのは、デザインがそれぞれの学校で決まっているわけで、そのものが仕様になるのかと思っています。
吉田
ということは、公正取引委員会の定義の中では、取扱販売店ではなく指定という形で、必ず決まった仕様のものということになろうかと思います。その際、指定販売店ですと、先ほど名取衣料店会ということでしたが、そこに新たに指定販売店として案内をしてほしいという、新たな業者の申し入れはこれまでどのくらいあったのか、把握している範囲でお願いします。
学校教育課長
教育委員会としては把握していないところです。
吉田
ちなみに、指定販売店によって同じ制服、同じサイズ、同じ性別で価格が異なる例はありますか。こちらの販売店では3万2,000円だが、こちらは3万2,500円とか、そのように異なっているケースは現在把握されているでしょうか。
学校教育課長
具体的に把握はしておりませんが、同一価格で販売されているものと思っております。
吉田
制服の価格が同一になるというのがよくわからないのです。公正取引委員会の報告書に戻りますが、自治体内で制服の仕様の共通化を行っている場合、案内する指定販売店等が多い場合、それから学校が販売価格の決定に関与している場合に、平均販売価格が安くなる傾向が見られると言われております。そして、制服メーカー間及び販売店間の競争が有効に機能するよう、取り組みが行われていることを学校に期待すると言われているわけです。
競争が有効に機能する取り組みへの期待というものは、これこそ消費者の期待と重なる部分であると思います。
そこで、小項目2 学校は、制服メーカー間及び販売店間の競争が有効に機能するよう取り組むべきについて、教育長にお伺いいたします。
教育長
公正取引委員会の調査結果には、コンペ等により有効な競争を確保することが示されております。今後、新たに制服を選定する場合には、コンペ等による選定を促していきたいと考えております。
吉田
本市では閖上小中学校が開校になりますが、こちらの制服についてはどのように決まっていったのか、そのあたりの経緯についてお伺いします。
教育長
閖上小中学校は、新しい小中一貫校となるのを機会に制服も変えてはどうかという意見も一部にありました。それで、教育委員会と学校と連携して、小学生中学生全員、それから閖上小学校、中学校の保護者にアンケートを実施しました。そうしたところ、現在の中学校の制服、それから小中学校の運動着について、現在のものに対する愛着が非常に強いということで、今後未来永劫同じ制服を使うということではありませんが、学校とも相談して従来の制服を使用するという方針が決定したと把握しております。
吉田
そうなると、コンペが行われるのはまだ少し先なのかなと思いますが、調査報告書でコンペ以外にも、指定販売店をふやすことが望まれていますが、指定販売店をふやすことに関して今後具体的に取り組んでいく方策はお考えでしょうか。
教育長
先ほど学校教育課長が申し上げたとおり、市内の5つの中学校の制服については、それぞれデザインも違っております。また、校章が制服に入っているなど、その学校独自のデザインとなっております。現時点において、教育委員会として新たに指定販売店をふやすことは考えておりません。
吉田
指定販売店がふえることによってより競争が生まれて、消費者にメリットが生まれてくるという考え方だと思うのです。指定販売店と学校との関係の中で、学校がいろいろ依頼することによって独占禁止法上に問題になるというケースが、今回この報告書で8つ例示されています。一つ一つ言うと長くなってしまうので、資料を御参照いただきたいのですが、この制服メーカー及び販売活動等に対する学校の関与について、留意する必要がある行為について、教育委員会としてしっかり学校を監督できていると考えてよろしいのですか。
教育長
現在、各中学校において、名取衣料店会と契約を結んで制服の販売を行っていると考えておりますが、公正取引委員会で指摘しているような不適切な形で行われているとは考えておりません。
吉田
名取衣料店会の位置づけですが、こちらは販売店の任意組合ということでよろしいですか。
教育長
名取市内の衣料店の組合と認識しております。
吉田
そうなると、組合と学校との間のやりとりの中でも、一番最後の例ですが、独占禁止法上問題になるというケースがあり得るということですので、そこのところはしっかりとそうならないように監督をしていただきたいと思うのですが、この報告書の最後のほうに、販売店が共同して販売価格の決定を行うことは、独占禁止法違反であると書いてあります。このようなことはないと、話し合いが行われていないと、それでも自然に価格が一緒になっていると捉えてよろしいのですか。
教育長
個々の学校の詳細な契約の内容まで把握しているわけではありませんが、今手元にある学校の制服に関する契約書では、名取衣料店会を通して納入はしていただいておりますが、ある衣料服の株式会社と中学校の間で契約を結んでおります。その契約に基づいて衣料店会を通して制服を提供していただいている、という契約書の内容となっております。
吉田
そうすると、学校とメーカーとの間でのやりとりと、学校と販売店との間のやりとりというように3者の間で価格が決まっていっていることになりますが、こちらについても2つの例を挙げて、気をつけなければならない点を挙げられております。そのことについてもしっかりと監督を行った上で、現在の価格設定があるということで間違いないということを、もう一度御確認をお願いします。
教育長
最初に申し上げたとおり、生地を大量に確保することで価格を抑えるとか、そういう企業側あるいは店側の努力がなされ、価格が消費税が上昇したときは別ですが、据え置かれていると。そういう努力をしていただいていると認識をしております。
吉田
値段についてではなくて、一律で同じ額が設定されていることについての監督といいますか、捉え方をお聞きしたかったわけです。いずれにしても制服を着る期間は3年間で、中学生にとっては成長期でもありますし、成長が早ければ途中でサイズが小さくなってしまうケースもあると思います。初め少し大き目のサイズを買っておくかと思うのですが、想定以上に子供さんが大きく成長された場合は、買いかえないとかわいそうだなというケースも出てくると思うのです。そうした際に、やはり同じように金額を支払うのは保護者にとっても負担になってきますから、ここで学校ごとに取り組まれているバザーをもう少し活用していただきたいということで、最後の項目です。
小項目3 バザーなど制服再利用の取り組みを積極的に支援、紹介すべきについて、教育長にお伺いします。
教育長
ただいま議員から御提案がありましたが、現在市内のほとんどの中学校ではバザーで制服の提供を呼びかけて販売を行っております。また、制服ではありませんが、運動着等同様の取り組みをしている小学校もあり、再利用が進められております。今後も再利用できるように各学校に促していきたいと考えております。
吉田
ぜひその周知も含めて広げていただきたいと思います。バザーとなると年に一度ぐらいでしょうか。回数はそれぞれだと思いますが、もちろん全部売れなくて残ってしまったりもするかと思うのです。そういう場合に、ことしは残ってしまったが、来年もう一回バザーに出せるようにということで、例えば教育委員会として空き教室などを利用して保管しておくとか、そういうことまで協力していただくというのはできないものでしょうか。
教育長
バザーは御承知のとおり、各学校でPTA等が中心となって行われているものだと考えております。バザーに提供したもので販売に至らなかったもの等については、それぞれの学校あるいはPTAで適切に判断をして取り扱っていると考えております。教育委員会で預かるとか、そこまでは考えてはおりません。
吉田
実際にバザーを行っている方たちに、より容易な仕組みを教育委員会としても協力していただければ、こういう取り組みがもう少し進んでいくかなと思います。
一つの例ですが、栃木県足利市に視察に行ってきまして、こちらでは制服のリサイクルをボランティアの方たち、消費者団体の方たちが行っていました。人口約15万人のまちで本市の約2倍あるのですが、約20年間で制服類合わせて累計で2万4,000着ほど再利用されているという数字が出ております。このような取り組みは大変すばらしいものだと思いますので、できるところから進めていただきたいと思います。
これで私の一般質問を終わります。
本会議
(議案第27号 工事請負契約の変更)
吉田
一部の用地の取得が困難になったという御説明でしたが、困難になった理由についてお伺いいたします。
復興まちづくり課長
所有者となかなか接触がとれない状況があり、いろいろと手を尽くしたのですが、取得には至らなかったためです。
吉田
接触がとれないということですが、設計を行った段階では用地取得の見込みをはっきりつけないままに設計したという経緯だったということでよろしいのですか。
復興まちづくり課長
当然取得を前提で考えていましたが、残念ながらこのような結果になってしまったということです。
吉田
また同じ質疑になりますが、所有者と接触がとれないということでしたが、当初から現在まで一切接触できなかったのか、それともどこかで接触が途切れてしまったのか、そのあたりについて御説明をお願いします。
復興まちづくり課長
当初から接触がとれないような状況にありました。
吉田
駐車場が減工になっている部分があり、ここが広場になるということですが、広場の地面はどのようになるのか、例えば芝生あるいは土なのか、整備の内容を伺います。
復興まちづくり課長
現在の防災公園の整備計画については、復興事業として整備を行っています。ただ、平成30年度において、公共土木施設災害復旧事業としてこの公園内に遊具整備を行う計画が出ました。それに伴って土地利用の内部調整を行い、この部分については駐車場ではなく、現状の土のままの仕上げとする形で今回は考えています。
吉田
土のままそこに遊具を設置するということなのかよくわからないのですが、いずれにしても、駐車場が狭くなるというか、台数が減ることによる影響などについてはどのようにお考えでしょうか。
復興まちづくり課長
今、遊具と申し上げましたが、遊具もしくは広場の整備ということで、一旦整備したものをさらに手をかけることのないように、手戻りのないように土で整備するという考えです。
なお、スペースが減少した駐車場については、台林線の左手のほうに駐車場があり、区画線は入れていますが、そのほかにも平地が少しありますのでこちらの利用等を考えています。
(議案第29号 平成29年度名取市一般会計補正予算)
吉田
6、7ページの1款6項1目入湯税についてお伺いします。市内の宿泊施設に天然温泉が備わったのかと思いますが、150円掛ける5,898人というこの人数の考え方についてお伺いいたします。
税務課長
具体的には1業者が対象で、平成29年11月から天然温泉を利用し始めている法人です。今回の補正予算を計上する際に、平成29年12月分までの入湯税について申告と納税がありました。その現況を踏まえて年度末までの入湯税額の見込みを立てたところです。
吉田
年度末までということで今月いっぱいまでだと思いますが、恐らく事業者で整備した温泉は個室ではなくて大浴場系かと思うのです。それを利用しない宿泊者もいると思いますが、そのような宿泊者からも入湯税が取れる規定になっていると捉えてよろしいのですか。
税務課長
当該事業者にどのような形でカウントするのかという点も確認させていただきましたところ、大浴場のドアの開閉でもって人数を把握しているということです。それによって人数掛ける1人1日150円という形で計算して毎月の入湯税を申告納税していただいています。
吉田
26、27ページの16款2項2目土地建物売払収入で、土地売払収入の内容をお伺いいたします。
財政課長
これは財政課を含めて3課で担当しています。内容としては、水路などの用途廃止に伴う払い下げ5件分で396万円ほど、南貞山運河災害復旧事業用地などの県施行の事業用地が5件あり、合計で2,340万円ほどとなっております。また、資材置き場、代替地等の普通財産の払い下げが2件で5,100万円ほどです。復興区画整理課で、防災集団移転先団地の4件とそのほか公募など全部で20件の売り払いがあり、合計1億3,040万円ほどになっています。復興調整課で、美田園北団地の宅地貸付者への土地の売り払いが2件あり、合計で2,853万円ほどです。
吉田
35ページの2款1項1目一般管理費の全体的なところで、行政不服審査法第三者機関事務が40万円の減となっていますが、これは当初予算で幾ら計上したうちからこれだけの額の減になったのでしょうか。
総務課長
当初は1件20万円の3件ということで60万円の予算措置でした。
吉田
行政不服審査は恐らく市民から申し立てというかそういったものがあると思うのですが、市民に対する周知は何か進めているのでしょうか。
総務課長
周知という点では特に行っていません。
吉田
88、89ページの10款4項4目図書館費です。19節負担金補助及び交付金で名取駅前市街地再開発組合事務費等負担金とありまして、事務費等と「等」がついているのでいろいろな解釈ができるのですが、この事務費等の詳しい内容についてお伺いします。
生涯学習課長
負担金の内容ですが、駅前ビルに入る図書館の水道開発負担金や水道加入金、また保留床の売買契約締結によって生じた平成29年度の固定資産税相当分が発生したことから、今回増額補正を計上しています。
吉田
固定資産税は市が徴収するものですから、市が課税して市が納付するという中身も一部あるかと捉えられるのですが、負担金の計算の仕方といいますか、組合の負担する全体の額の中の何%を本市で負担するのですか。
生涯学習課長
まず水道加入金については、図書館占有部分のメーターということで、そのものということでの負担金です。水道開発負担金については、図書館の全体共有持ち分が56%あり、それに応じて案分した負担金です。固定資産税については、平成29年1月1日現在の地権者所有の建物、土地の固定資産税総額に市の持ち分比率を掛けて固定資産税の額を算出しています。
(議案第33号 平成29年度名取市後期高齢者医療特別会計補正予算)
吉田
143、144ページです。1款1項2目普通徴収保険料の滞納繰越分ですが、当初予算では調定見込み額として七百四十何がしの25%という見込みでしたが、今回の減ということで実際の調定率は何%になるのでしょうか。
保険年金課長
今回の滞納繰越分については、調定見込み額を325万8,600円と見込んでおり、実際収納できる率を20%と見込みまして、その差額120万6,000円を減額計上しています。
吉田
20%とは、もともとの見込みの25%が20%になったということではなく、25%の中の20%となるのか、答弁でわかりづらかったのですが、どちらにしても大きく減額になっていますが、収納についてどのような取り組みを行ってきたのかお伺いします。
保険年金課長
当初予算は収納率25%、これが実際は20%になるであろうということで見込んでいます。それから、滞納整理ですが、保険年金課の職員が随時滞納整理にお伺いして収納に努力しているところです。
(議案第36号 市の境界変更について及び議案第37号 境界変更に伴う財産処分に関する協議について)
吉田
議案書の71ページ、協議書の最後のほうの3番の境界変更にかかわらず名取市が所有する土地というところです。地目の中で公衆用道路はわかりますが、田となっているのは田んぼも本市が所有しているということでよろしいのですか。
総務課長
確かに議員御指摘のとおり地目は田となっていますが、現況は公衆用道路になっております。所有が行政ですので、登記はそのままにしている形です。
吉田
そうすると、今は田んぼとしては使われておらず、実際は道路ということですが、これらについても道路としてのままいずれ登記の手続により仙台市に移されるということでよろしいのですか。
総務課長
議員御指摘のとおりです。
財務常任委員会
(議案第2号 平成30年度名取市一般会計予算)
吉田
6ページ、7ページ、1款1項1目個人分でお伺いいたします。昨日の補足説明で、1節現年課税分の均等割で1,051人の増の見込み、所得割で1,172人の増の見込みという御説明がありましたが、今実際に本市の人口が順調に伸びている中でこのような課税対象の方の数を割り出していった、その算定の仕方について、詳しく御説明をお願いしたいと思います。
税務課長
新年度予算を立てる場合には、その前年の9月末の調定の状況を見ながら予算の編成を考えることになっています。平成30年度当初予算については平成29年9月末の調定をもとにしており、均等割の納税義務者が3万7,848人、所得割の納税義務者が3万5,581人ということで、その伸び率などを見て今回の当初予算に計上しているところです。
吉田
前年9月末の時点からの算定ということでした。人口がこれからもこのように伸びていけば市にとっては大変歓迎すべきことかと思いますが、その人口の予測ということで、かつて名取市地方創生総合戦略の人口ビジョンを策定しましたが、その際に算定された人口の増と比べて、現状はどのようになっているのかお願いします。
税務課長
そこまで個人分の住民税の伸び率等には反映させていないというか、そこまで比較していない状態です。
吉田
滞納繰越分についてお聞きします。滞納している方が実際に納税する際に、分割払いなどを市と約束することもあると聞いています。例えば市民税の個人分ですと調定率が12%と設定されていますが、そのうちの大体どのくらいが既に約束されている部分に当たると考えてよいのでしょうか。
税務課長
滞納者の方で分割納付をしている方というのは、市と滞納者の間で納税交渉をして分割納付をしてもよい状況の方、条件はいろいろあるのですが、そういった方に対して、分割納付の誓約書を取り交わして分割納付をしていただいています。ただ、滞納額の中で分割納付をしている方が何名ぐらいいるかについての把握まではなかなか進んでいないところですが、滞納額全体の中で分割納付の誓約まで進んでいる方の人数は、半分まではいないのではないかというところだと思います。
吉田
滞納している方全体の中で半分に満たない方しか分割の誓約ができていないと捉えてよいのでしょうか。半分というとそれなりに大きい値ではないかと思いますが、そうした分割払いを誓約している方が今回の予算の中でこの12%の中にしっかり反映された形で額があげられているのか、確認したいと思います。
税務課長
まず、分割納付の話ですが、滞納者の方と納税交渉した上で分割納付を認めて誓約書の取り交わしまでできる方が、先ほど言ったとおり半分までは多分いないだろうと理解しております。今回の滞納繰越分については、そういった方も含めて滞納繰越額全体に見込みの収納率を掛けた形で調定をしていますので、今委員から話があったとおり、そういった方も含めてそのような調定をあげていることになります。
吉田
6ページ、7ページ、1款1項1目個人分でお聞きします。滞納繰越分ということで、滞納した方にはその月数などによって延滞金が生じることになっているかと思いますが、その延滞金も含めてこの見込み額と考えてよろしいのでしょうか。
税務課長
予算上の調定額については全て本税です。
吉田
12ページ、13ページの6款1項1目地方消費税交付金についてお伺いいたします。こちらは、制度が変わったということで、8%の消費税全体の中から都道府県分が1.7%、さらにその2分の1が市町村に配分されるという御説明がありましたが、その配分は完全に人口に比例するということでよろしいのですか。
財政課長
平成30年度から、国から都道府県に払い込む際の都道府県間の清算の方法が変わりました。これまでは、商業統計に基づいた小売年間販売額と経済センサス活動調査に基づいたサービス業対個人事業収入額の合算額が全体の75%で、そのほかに国勢調査に基づいた人口が17.5%で、経済センサス基礎調査に基づいた従業員数が7.5%でそれぞれ案分して配分されていましたが、平成30年度からこの清算方式が変わり、商業統計の小売年間販売額と経済センサス活動調査のサービス業対個人事業収入額が75%から50%に改められました。そのほかに国勢調査に基づいた人口は17.5%から50%に引き上げられ、経済センサス基礎調査の従業員数割については算定から外されることになりました。ということで、きのうの歳入の補足説明でもあったように、首都圏から地方に配分が強く来るということで、平成30年度当初予算については見込みよりは少し強目に見ているところです。
吉田
首都圏から地方により温かい制度になったことは、きのうの御説明でも少し理解できたところですが、県におろされてきた分の半分が市町村に配分される中で、今回県内の市町村の中で本市にはこの額が配分されたのだと思います。その配分額の決定の仕方、算定の仕方、何かもとになるものがあってこの数字になったのかと思いますが、実際、県から配分される際、今回のこの額は1,000万の位で端数を処理していますが、何円単位くらいまで県が決めて配分されることになっているのですか。
財政課長
まず、都道府県間の清算の後に県から市町村に交付される際の算定方法については、平成30年度以降も特に変更はありません。宮城県にこれまでよりもパイとなります配分額が多くなるということなので、人口増でもある本市としては、少し強目に見ることはできるだろうと考えております。従前分と社会保障財源分とあり、従前分については、2分の1を市町村の人口割、2分の1を経済センサスに基づいた従業者数割で案分して交付されます。その後、社会保障財源分については、全額を人口で案分して交付されることになっております。都道府県からの配分方法については変更はありません。
吉田
18、19ページです。13款1項4目土木使用料の2節駐車場使用料として、館腰駅・名取駅西口自転車等駐車場使用料が平成29年度当初予算に比べて減額を見込んでいますが、この減の理由についてお伺いいたします。
土木課長
館腰駅・名取駅西口自転車等駐車場使用料については149万6,000円の減となっていますが、これについては利用件数が約3,734件減になっています。その減の理由を調べたところ、平成29年度の上半期が平成28年度の上半期に比べて1,527件の減になっており、平成28年度の下半期が平成27年度の下半期に比べて2,343件減になっています。また、平成29年4月1日から使用料を値上げしていますので、その辺の影響があるか確認したところ、4月1日からの使用料によって1,527件の減、そして、使用料を上げる前から利用件数が2,343件減っていましたので、使用料を上げたことによる影響は少なからずありますが、上げる前から件数は減っており、利用者が減少したことが主な要因と考えられます。
吉田
使用料が上がったことも利用者が減った理由の一部に含まれるという分析をされたということですから、使用料を上げて本当によかったのかと、当時反対した私としては今になって感じるところもありますが、利用者が減になっているということは、実際に自転車には乗っていても本市の駐輪場を利用しない方がいるということだと思います。自転車の利用そのものをやめて徒歩にしたとか車にしたという方も中にはいるかもしれませんが、自転車を利用しているままで、市の駐輪場を利用していない方がいると思います。では、その方たちはどこに自転車をとめていると分析していらっしゃいますか。
土木課長
市としても、できれば駐輪場にとめていただきたいと思っているところですが、仮に公共施設の道路とかに置いてあるのであれば、ここに置かないようにという張り紙を張って、それでも置いている場合は撤去するような形をとっております。ただ、ほかに民間の駐輪場もありますので、そちらを利用しているのではないかとも思いますが、そこまでは実態を把握しておりません。
吉田
18、19ページの駐車場使用料についてもう一度お伺いしますが、今度は名取駅自動車駐車場についてです。今、名取駅東口に新しく建設されている複合施設の北側にも駐車場が完成すると伺っていますが、それはこの名取駅自動車駐車場の中に含まれると捉えてよろしいのですか。
土木課長
名取駅自動車駐車場には含まれておりません。
吉田
駐車場として料金も徴収していくという説明も以前あったように記憶していますが、その駐車場料金の収入については、今後の補正予算で対応されることになりますか。
建設部長
名取駅前地区市街地再開発事業の駐車場については、管理組合をつくって料金徴収をすると伺っております。
吉田
20ページ、21ページ、13款2項2目衛生手数料の中で、2節清掃手数料の廃棄物処理手数料が昨日の御説明ですと動物火葬が減少することを見込んだということでしたが、そのように見込んだ理由について御説明をお願いいたします。
クリーン対策課長
廃棄物処理手数料はペットの火葬ということになります。これが大きく減額になっている理由ですが、例年、市外の動物火葬を含めた数を捉えていますが、今回は平成30年5月に岩沼市にできる新斎場に動物火葬炉ができることから、その影響が大変大きいと考えています。これまでの市外の動物火葬のほぼ7割方が岩沼市、亘理町、山元町、柴田町などとなっていますが、その地区の方たちが岩沼市の新斎場に行くことが見込まれますので、その分を想定して減額したということで、このように3分の1ぐらいとなっています。
吉田
相当広い範囲の方がこれまで本市の斎場をペット火葬で利用してきたということで、岩沼市に動物火葬炉ができることによる影響が非常に大きいと感じたところですが、本市在住の方が岩沼市の動物火葬炉を利用するような想定はしていないということでよろしいですか。
クリーン対策課長
これまでなかったので、本市の動物火葬炉は重宝されていました。大分、料金的な差も影響するのではないかと思いますが、岩沼市の動物火葬炉もほぼ同額で対応するようです。なかなかこちらにどうぞと言えることでもありませんし、近いところに行くのではないかと思いますが、そのような状況で推移するのではないかと捉えております。
吉田
62、63ページです。18款2項1目財政調整基金繰入金ですが、この中の復興事業分と通常事業分のそれぞれの額についてお伺いいたします。
財政課長
財政調整基金の通常分と震災分ということですが、22億7,500万円の取り崩しの中で通常分としては7億760万6,000円、震災分としては15億6,739万4,000円となっています。
吉田
通常分が7億何がしということですが、このような取り崩しをした後の残高では復興分としてどのくらい残っているのかお伺いいたします。
財政課長
2月9号補正後の基金残高で答弁させていただきます。財政調整基金の残高は44億212万2,000円となっており、そのうち通常分としては21億7,231万2,000円、震災分は22億2,981万円となっています。
吉田
66、67ページ、20款1項1目延滞金です。先ほどの御答弁の中で滞納繰越については延滞金を含まないということでしたので、その分の延滞金がここに計上されているのかと思います。前年度と同じ金額になっていますが、この考え方について、市税にはいろいろな税目があろうかと思いますが、例えば市民税は何%とか、そういう割り当てというか、そのあたりの考えがあるのかどうかお伺いいたします。
税務課長
延滞金については、基本的には前年度以前の本税を納めた場合に、その納期限から実際に納めた日までの日数をもって延滞金額を計算し、本税と合わせて納付する形になっております。延滞金については、滞納繰越の本税がどの程度納められるかがなかなか見込めませんので、科目設定のような形で基本として100万円という額を毎年計上し、あとはその年の実際の収納額に合わせて増額補正をさせていただくということで考えているところです。
吉田
延滞金そのものの全体のうちのどのぐらいを今回、平成30年度で納めていただくかという数字が見えてこないのですが、実際に延滞されているその延滞分として平成30年度の当初の時点でどのぐらいあるのでしょうか。
税務課長
本税の何年度のどの分を納めるかによって延滞金額も変わってきます。例えば平成28年度の国民健康保険税の何期分を納める場合と平成25年度の国民健康保険税の何期分を納める場合とでは、その期別ごとに納期限があって、納期限と実際に納めた月日との間で延滞金の計算をしますので、実際にどこの分をどのように納めるかによって延滞金は変わってきます。そのためなかなか読み切れないところがありますので、先ほど御説明したような形で当初予算として計上させていただいているところです。
吉田
68、69ページの違約金です。公正取引委員会から指摘があったという御説明でしたが、これが発覚した経緯というか、市のほうにはどの程度説明があったのかについてお伺いいたします。
財政課長
本市においては、平成29年2月2日に公正取引委員会から通知が来たことで初めて発覚したもので、それ以前についてはこちらとしては特に情報はありませんでした。
吉田
済みません、質疑が広がり過ぎるかもしれませんが、今回は予算の出どころが国ということで公正取引委員会なのかもしれませんが、例えば市が単独で行う事業などの場合でも、こういう公正取引委員会からの指摘などが入る可能性はあるのでしょうか。
財政課長
理論上はあり得ると思います。
吉田
80、81ページ、2款1項1目一般管理費、荒川委員の質疑と同じく委託料ですが、身分証明証の名札についてはデザインを刷新するのは、職員の方の中でもどの身分の方でしょうか。合計で何名分かということです。
総務課長
対象は一般職員、任期付職員、派遣職員、非常勤職員、そこに特別職も入りますが、全部で850名で見積もっております。
吉田
現在、名札に顔が入っている方と入っていない赤い名札の方と、いろいろな名札の方がいます。あるいはつけていない方もいるのかもしれませんが、例えば行政区長の名札を作成する等のお考えはなかったですか。
総務課長
名札は我々のほか臨時職員の方の分は顔写真のない臨時職員という形の名札で、基本的にはつけていただくことにはなっています。それから、区長については今回の対象には入っていません。
吉田
82、83ページの2款1項1目一般管理費19節負担金補助及び交付金の職員退職手当組合負担金、これはここだけでなく全体で大きく減額になっておりますが、その理由と、もし捉えていれば全体の額として平成29年度との比較の金額を伺います。
総務課長
退職手当組合負担金が、平成29年度は7,000万円強が1,700万円に大幅に減っている理由ですが、これは職員の退職金に係る負担金、いわゆる積み立てをしているための支出になります。仙台市を除く県内の自治体事務組合水道企業団等で入っている宮城県市町村職員退職手当組合がありまして、本市もそこに入っているわけですが、平成29年9月に組合から積立金が大分あるということで、減額の協議の話がありました。今後の退職者並びに新規採用のプラスマイナス等の数値を計算したところ、3年間一般職員の分の負担金をゼロにしても相当余裕があるという判断がありまして、それで平成30年度は一般職員の分については負担金はゼロという形で、組合とも調整して、その関係で今回このような減額になったものです。
平成29年度との比較については捉えておりません。
吉田
平成29年度の7,000万円から平成30年度は1,700万円というのは、総務管理費の部分だけということであって、本市の予算全体から見たら、もっと桁が恐らく違ってくるのかと思います。組合のホームページも拝見したのですが、どういう制度で積み立てがどのくらいあるか、一般の我々にははかり知れない部分があると思うのですが、このように急に減額しても大丈夫だという話があるということは、これまでの組合の中でどのように積立金が管理されていて、それを本市ではどのように把握されていたのか。
というのは、今後このような逆のパターンで、急に負担額をふやしてくださいなどということがないのかどうか、そのあたり本市としてはどのくらい把握できるのかについてお伺いします。
総務課長
組合から、逐次積み立ての残高等の情報は受けております。今後急に負担額がふえるような話はないかということですが、平成28年度末の積み立ての残高が16億3,000万円となっています。そういった数字をもとに計算していって、逆転になるような状況はないと捉えております。
吉田
82、83ページの2款1項1目一般管理費18節備品購入費です。公用自動車購入費とありますが、金額が少し小さいようですが、予定している自動車の仕様について伺います。
総務課長
こちらの公用自動車は、日産自動車株式会社から平成28年3月から3年間の期限で無償で貸与されている電気自動車です。その買い取り費用と、車両整備に係る備品の購入費となっております。
吉田
今初めてお聞きしたので、電気自動車なのですね。お借りしていた期間が満了になって、残った分をこちらでお支払いして買い取るという形でしょうか。主にどのようなところで今後使われていく予定でしょうか。
総務課長
電気自動車ですので、ガソリン車と違って1回の充電での走行距離が限られているということで、現在は公民館の毎日の文書送達に使っておりまして、今後もその用途と考えております。
吉田
84、85ページ、2款1項2目文書費13節委託料で、住民リスト印刷等委託料ということですが、区長に行政区の住民リストを管理していただくことについて一般質問でも取り上げました。これまでもずっとそうだったということで、今回見える形で計上されてきたようですが、区長も市の職員ではありますが、同じ住民に個人情報をお預けすることに関して、リストに書かれている地域の方たちの同意をとろうとか、そういう検討は今までなかったのでしょうか。
総務課長
特に検討してはおりません。
吉田
同意なく庁舎の外に住民の個人情報を出すことについて、いろいろ考え方があるのかと思いますが、それは区長ならよくて、ほかの一般の職員はだめだという分け方の考え方について伺います。
総務課長
区長も職員でありまして、その職員がよくて、庁内の職員は自宅には持ち帰れないという線引きですが、区長の業務上、基本的に地域の見守り、それから市とのパイプ役という位置づけの職員でありまして、リストがないと広報の配布等にも支障を来すことから、配付をしているところです。
吉田
90、91ページ、2款1項7目財産管理費14節使用料及び賃借料のところで、工事実績情報システム利用料とありますが、こちらの内容について伺います。
財政課長
こちらはサービスの提供元としては、一般財団法人日本建設情報総合センターというところが運営するシステムです。国、都道府県、市区町村948の自治体が導入しているもので、公共工事500万件以上のデータが蓄積されているもので、発注者、受注者、場合によっては現場代理人、そのようなデータを検索することができるシステムです。
こちらのシステムを利用しますと、業者の手持ちの工事の量や発注予定の類似工事の実績、そういったものを把握することができるため、本市として例えば指名競争入札をする際に、実績のある業者を指名することもできるというメリットがありまして、今回お願いするところです。
吉田
そうしますと、あくまでも市の業務にとってのメリットということでよろしいですか。
財政課長
委員お見込みのとおりです。
吉田
98、99ページ、2款1項13目電算運営費で伺いますが、13節委託料が大幅に増になって、14節使用料及び賃借料が減になっています。この辺の相関関係が何かあるのかどうかと、この金額の根拠について伺います。
市政情報課長
13節委託料の金額の増加と14節使用料及び賃借料の金額の減ですが、この理由は、私どもで基幹系と呼んでいる住民情報系システムと、財務会計などを処理する内部情報系システムとがありますが、その保守経費を13節で見込んだため増加したということです。この中身は、基幹系と内部情報系システムについては、長期継続契約を締結して、システムの機器とソフトウエアを借り上げて運用しておりました。これまでそのシステムの保守費用を含めた形で、14節の賃借料の科目で予算をお願いしていたものです。このシステムについては、長期継続契約の期間が終了しております。この基幹系と内部情報系システムは、賃貸借契約期間の満了後においても、当面運用を継続する計画としております。この2つのシステムについて、長期継続契約の満了時点で、システム自体は無償譲渡されることとなっておりますので、借上料、賃借料は発生しないわけですが、運用を継続するということで保守委託は継続しなければなりません。したがいまして、保守委託料を13節でお願いするということです。
吉田
譲渡されるということ、その分の保守に費用がかかってくるということですが、この基幹系システム、内部情報系システムということで、電子化を進めていく中で平成30年度新たなシステムを何か導入、つけ加えていくといいますか、そのような部分の検討についてはいかがでしょうか。
市政情報課長
平成30年度は、現在使用しております基幹系システムと内部情報系システムについては、継続して使用していきます。また、使用料の関係になりますが、内部情報系システムの主な業務システムは財務会計システムで、現在の財務会計システムについては、平成31年5月まで運用する計画としております。したがいまして、平成31年度の新年度予算編成については、新しいシステムでもって処理していくことになり、その半年以前からシステムを稼働させる必要があります。
吉田
102、103ページ、2款1項19目市制施行60周年記念事業費で、いただいた資料で伺いますが、13節委託料に記念コンサート等開催委託料とあります。これはコンサートの運営の委託料なのかと思いますが、コンサートの中身は今後どのように決めていくことになっているのでしょうか。
文化・スポーツ課長
現在のところ、文化振興財団に委託を考えているところです。現在、中身で検討しているものは、5月4日に開催されますArt for Kids@なとりわくわくパビリオンがまず1つです。2つ目として、11月に開催される名取ミュージックガーデン。3つ目として平成31年年明けになるかと思いますが、お笑いライブの開催を計画しているところです。
吉田
3つのそれぞれ特色ある企画ということで、大変楽しみです。これらの企画を行うということですが、5月のものも11月のミュージックガーデンとか、名前を聞くと市民も気軽に参加できるのかなという気もしてくるのですが、そのあたりの考え方は現時点でどのようになっているのか、伺います。
文化・スポーツ課長
2番目と3番目がコンサート等の公演になりますので、聞いたり見たりするものです。1つ目のわくわくパビリオンについては、子供から大人まで楽しめる参加型の企画ですので、こちらのほうはそういった方々が参加できるものと考えております。
吉田
103、104ページ、2款1項19目市制施行60周年記念事業で、いただいた資料ですが、予算計上なしとなっている部分でも伺いたいのですが、下から2番目の熊野三山シンポジウム開催事業について伺います。三山一寺ということで、熊野三山と青岸渡寺の宮司と住職が来てシンポジウムを開くのかと思いますが、このあたりの現時点での内容、決まっている部分について伺います。
商工観光課長
こちらは熊野三山協議会という形で、今委員話されたように、熊野速玉大社、熊野那智神社、熊野本宮大社、あと青岸渡寺の方々が入った上に、新宮市、田辺市、那智勝浦町の方で構成されている協議会です。会長が新宮市の市長で、平成29年9月に、もともと熊野三山協議会でPRする機会ということで、講演会やシンポジウムをこれまでも行ってきました。
その中で平成30年度が本市の市制施行60周年、また姉妹都市締結10周年になるため、これをお祝いしたいというお話をいただきました。それを受けていろいろと調整した中で、記念式典の当日に基調講演、内容は熊野とヤタガラスとか、熊野信仰と名取の老女とか、防災の観点からの姉妹都市の協力あたりをキーワードにということと、パネルディスカッションということで熊野三山協議会と名取熊野三社の関係者ということで、テーマは今から検討していきたいと思います。そのほか、両方の熊野のPRということで、パネル展などを実施していきたいという内容で、今後先方と詰めていきたいと考えております。
吉田
開催時期が9月ということで、台風が来る季節かと思います。あの地域は非常に雨が多く降ることがあって、私も昔訪れたとき、車の通行どめになった経験がありました。取り越し苦労に終わればいいのですが、そのような大雨に遭ってしまうと、参加される方皆さんが足どめになってしまって、空港までもたどり着けないとかなってしまうことも考えておかなければいけないのかなと。そういうことも含めて、お招きする方々の今後の日程の調整など、そのあたりの考え方について伺います。
商工観光課長
日程については、市制施行60周年の記念式典の日に合わせて名取市文化会館を使って実施したいと考えております。宿泊するかどうか、前泊から入るかということについては、先方の事情もありますので、飛行機で来るか、新幹線を使って来るかというのは、こちらではわかりかねるところがあるので、御理解いただきたいと思います。
吉田
118、119ページの2款5項2目諸統計調査費1節報酬のところで、住宅・土地調査員報酬が平成29年度に比べて大きくふえておりますが、この理由について伺います。
市政情報課長
住宅・土地統計については、平成29年度は調査区の設定業務だけでしたが、平成30年度は本調査になりますので、調査員の数が増加しております。
吉田
その80名の方たちの調査に当たる体制をどのように組んでいくのか、伺います。
市政情報課長
80名の内訳ですが、指導員が15名、調査員が65名で、具体の調査の割り振りなどについてはこれからの作業となります。
吉田
130、131ページ、3款1項5目知的障害者福祉費15節工事請負費のみのり園照明設備改修工事について、内容を伺います。
社会福祉課長
みのり園の建物は、昭和62年に建てられております。これまで何か破損があればその都度ごとに修繕はしてきているところですが、照明器具についてはこれまで蛍光灯だったのですが、さすがに中で作業するには暗いこともありまして、今回予算をお願いしているものが内部のLEDの照明工事になります。場所は、調理等を行っている場所をLEDの明るい照明に切りかえて作業をしやすくしたいということで、お願いしているものです。
吉田
明るくなることで作業がやりやすくなるということだと思うのですが、実際LED化するのにそんなに大規模な改修というほどではないのかなと思うのですが、工事の期間や、その期間中の利用者の利用に際してのケア等、そのあたりの考え方について伺います。
社会福祉課長
実際には予算をお認めいただいて、年度当初すぐにそのような対応をということになりまして、業者が確定してからスケジュール等が確定できると思っております。それに合わせて、その期間、仮に1カ月とか2カ月という時間がかかるものなのか。そうであれば、その代替施設、場所をどうするか、そういう期間が確定したところで対応を考えたいと思います。
吉田
148、149ページ、3款3項3目児童館・児童遊園費、15節の工事請負費ですが、児童センター空調設備設置工事ということで、名取が丘と増田西と館腰の児童センターの3カ所のことかと思います。この空調設備の仕様といいますか、どのような規模のものになるのか、台数等について伺います。
こども支援課長
こちらの空調設備については、事務室に業務用のエアコンを設置する工事となります。
吉田
業務用ですと、天井に埋め込むようなものになるのかなということですが、その際の工事の期間をどのくらい見込むのかについて伺います。
こども支援課長
工事の期間については、できれば長期休業に入る前にと考えておりますが、いずれにしても工事事業者が決まってからの調整となるところです。
吉田
154、155ページ、3款3項9目母子・父子家庭医療対策費で、20節扶助費に母子・父子家庭医療費があります。母子家庭、父子家庭のお子さんということかと思いますが、実際に戸籍上の母子関係、父子関係だけでなく、内縁関係の同居の方がいるケース等、そのあたりの把握はいかがでしょうか。
こども支援課長
母子・父子家庭医療費の申請を受けて支給認定する際ということで答弁しますが、住民登録のデータで同居者がいた場合は、その状況を確認してから支給対象とするかどうかを判定しているところです。
吉田
ですから、本来母子家庭や父子家庭、やはり子育ても含めて大変だという中で、こういう制度があるかと思うのですが、実際に結婚という形でなくても、内縁関係にあって同居している方がいて、その家庭に子供がいる場合でも、支給されているケースがあるのではないかということが考えられるかと思いますが、そのようなことは市でどの程度把握に努めているのかをお聞きします。
こども支援課長
医療費助成の申請をしていただいて受給者証を発行しておりますので、申請していただいた場合には、住民登録の情報で同居者がいないかどうかを確認しているところです。
吉田
172、173ページ、4款1項6目環境衛生費の中で8節報償費とあります。薬剤散布協力謝礼ということで、地域の薬剤散布に協力してくれている団体へ配分しているのかと思いますが、その謝礼の交付先と、配分の考え方、どのような計算で配分されているのかについて伺います。
クリーン対策課長
薬剤散布協力謝礼182万円の考え方ですが、まず市内の環境衛生協力会に加入する町内会に対して、衛生害虫の駆除運動の協力の謝礼ということでお支払いしているもので、この考え方は世帯割としてまず1世帯に対して55円、行政区割ということで1行政区当たり5,000円という考え方で、平成30年度の予算については2万1,000世帯に対して、行政区133区に対して、182万円のお支払いをするという計算です。
吉田
今の御説明ですと、町内会に環境衛生協力会があって、そこにお支払いしていくと。ただ、行政区割ということで、必ずしも行政区と町内会の区域は一緒ではないということが、これまで何回も指摘されてきたところです。そのあたりの整理を1点伺います。
もう一つは、薬剤が散布されたかどうかの状況の把握、町内会に来た薬剤が、市で思っているほどしっかり散布されているのかどうかの把握を、どのように取り組んでいくのかについて伺います。
クリーン対策課長
必ずしも行政区が全てイコール町内会ではないのは、御案内のとおりだと思いますが、考え方としては、町内会が環境衛生協力会に加入しているとは限らないのですが、行政区単位でまずはお支払いしているのが現状です。 それと、実際に薬剤が散布されたのかについては、年度の終わりに報告書、春と秋、主に秋に散布していただいていますが、その報告書を年度内にいただいて取りまとめをして、そこで実態を把握しながら地域の実情を把握し、また地区との情報を共有して、地区の事情を把握しながら取り組んでいるということです。
吉田
182、183ページ、4款2項3目ごみ処理費19節負担金補助及び交付金の亘理名取共立衛生処理組合ごみ処理負担金ですが、現状で焼却灰の最終処分を市外に委託している状況が続いているようですが、これは平成30年度もその状況が続いていくという見込みでよろしいですか。
クリーン対策課長
焼却灰の処分は、昨年度から市外に処分を委託しているということですが、これは最終処分場で処分できないという現状ですので、最終処分場ができるまで、これが当分続くということを組合からは聞いております。
吉田
最終処分場ができるまでの限定ということですが、では最終処分場がいつできるかについて、本市だけでなくこれは2市2町の問題ですが、組合と本市とお互いどういう関係の中で今後検討していくのか。現時点である程度、最終処分場の選定の見込みが進んでいるのであれば、現在の状況についてお伺いします。
委員長
ただいまの吉田委員の質問は予算から外れておりますので、予算の項目に限っての質問をお願いいたします。
吉田
では、この負担金の中には、最終処分場を選定していくためのいろいろな協議の場に係る費用は含まれないということでよろしいですか。
クリーン対策課長
負担金の中には、これは入っておりません。負担金は亘理名取共立衛生処理組合の経常経費の中での負担割での負担です。
吉田
184、185ページの5款1項1目労働諸費19節負担金補助及び交付金の中でシルバー人材センターの補助金が今回も計上されています。現在の事務所の施設が相当老朽化していると前々から指摘がありますが、平成30年度中の事務所移転の動きなどについて市で把握している情報はあるのでしょうか。
介護長寿課長
シルバー人材センターの事務所の建てかえについては、公益社団法人ですのであくまでも主体はシルバー人材センターと考えております。ただ、やはり高齢者の就業確保という点においては、本市としてもある程度の支援は考えなければならないと思います。平成29年1月に施設の老朽化による建てかえについての協議書が提出されています。それに対して本市として一定の案をシルバー人材センターへ示しているところですが、いまだお互い合意には達していない状況です。今後もシルバー人材センターと話し合いを持ちまして検討していきたいと考えています。
吉田
移転ではなく建てかえのための協議が進められているが、まだ合意に立っていないということで、市としては平成30年度中に具体的にどのようなところまで進めていければと考えているのでしょうか。
介護長寿課長
建てかえか移転かも含めての検討ですが、やはりそれなりの資金が必要になると思われます。平成30年度内に話し合いが合意に達するかどうかは担当課としても見通せない部分がありますが、今後も話し合いは重ねていきたいと思っております。
吉田
194、195ページ、6款1項10目災害対策費19節負担金補助及び交付金の下堀及び矢野目堀用排水施設整備事業負担金ですが、平成29年度は7目農業土木費に計上されていたのが今回は10目災害対策費に費目が変わったことについて、何か内容の変更があったのかお伺いいたします。
農林水産課長
事業内容としては平成29年度と同じです。今回の目の移動は、内容をさらに検討した結果、10目の災害対策費のほうがより適切であるという判断で移動したものです。
吉田
実際に水害の対策だと思いますが、これは昨年も指摘したことですが、工事の範囲には希少生物が生息している部分があり、地域で保護活動に取り組んでいる方もいるわけです。平成30年度の取り組みの中で、工事における保護の配慮などそのような点について把握していることをお聞きしたいと思います。
農林水産課長
下堀及び矢野目堀の中には確かに委員のお話のとおり希少生物が生息しており、そのために工事の中では環境配慮対策として3つ掲げています。1つは、昨年も委員会でお答えしましたが、自然の状態を保つために、未装工とし水路の底の面の土を残します。2つ目として、護岸のブロックの形状として魚巣型ブロック、植生型ブロックといった魚が巣をつくりやすいように配慮した製品を使用します。3つ目については、もともとの水路、蛇行したところをほぼ真っすぐに整備するわけですが、カーブの曲がったところをそのまま残して、そこに魚がすむような水たまりといったもの、ワンドを設置して希少生物を保護するといった配慮をして工事を進めると伺っております。
吉田
196、197ページの6款2項1目林業費ですが、13節委託料の森林情報管理システム整備委託料の内容についてお伺いいたします。
農林水産課長
森林情報管理システム整備については、森林法が改正され、これまで宮城県が窓口となっていた林地台帳について、平成31年度からは各自治体において備えつけ、運用を行うことが義務づけられました。そのため平成30年度において管理システムの整備を行うものです。
吉田
平成30年度は整備を行い平成31年度から本格的な運用となり、市町村に移管ということですが、こうしたシステムは市町村単独での運用という形でいいのですか。これまで県がやってきたのを細かく分けることになれば、その分コストが余計にかかってしまうのではないかという単純な考えですが、これまでの県での取り組みに比べて、本市としての負担のあり方はどのように捉えているのか伺いたいと思います。
農林水産課長
森林情報管理システムについては現在宮城県で運用しており、今後も、窓口となる市町村、それから当然管理する宮城県と情報共有を図る意味からも、宮城県で現在使用しているシステムを本市においても導入したいと考えております。そういった意味では、一からの開発ではなく、宮城県の林地台帳のシステムと共有していく方向で整備するものです。
吉田
202、203ページの7款1項2目商工振興費8節報償費、先ほど菊地委員からも質疑がありましたが、閖上地区商業施設について、株式会社伊藤チェーンとの立地協定が締結され進出ということでオープンが非常に待ち遠しいところです。先日いただいたこの施設に関する資料に施設の概要図が載っていましたが、平家か2階建てかなど詳細を把握していたらお聞きしたいと思います。
復興調整課長
建物としては今後いろいろと御検討いただきますが、今のところは平家です。
吉田
平家ということは、やはり万が一の際の利用者や従業員の避難誘導などが気になりますが、今回のアドバイザーに対してはその点に関してのアドバイスなども求めると捉えてよろしいのですか。
復興調整課長
避難を意識した建物の構造など、避難誘導についてはこのアドバイザーに対しては想定しておりません。
吉田
206、207ページの7款1項4目観光費14節使用料及び賃借料でお伺いします。観光パンフレット用モデル更新料とありますが、そのモデルの内容について、契約期間やどのようなものとして捉えているのか、また、パンフレットも名取市観光物産協会のパンフレットなのかなど御説明をお願いいたします。
商工観光課長
現行の「ぷらっとなとり」というパンフレットの制作に当たり、掲載モデル2名が写真使用に係るということで、当初からその使用料を含めて作成をしていました。今在庫が少なくなって、一部修正をしてこれから増刷する予定ですが、増刷となると、モデルの契約条件に更新料をうたってあるために、印刷会社に支払う義務があるということで今回予算計上しているものです。
吉田
では、大体同じような内容で増刷をかけると思いますが、モデルということで専門の方だと思いますが、例えば市の職員をモデルにするような考えはなかったのでしょうか。
商工観光課長
そういった考え方もあると思いますが、やはり専属のモデルですとシチュエーションに応じて見ばえがすることもあってモデルをお願いして取り組んできたところです。
吉田
210、211ページ、8款1項3目公共物管理費15節工事請負費の増田西小学校周辺水路整備工事です。毎年計上されているようですが、内容をお伺いいたします。
土木課長
増田西小学校周辺水路整備工事ということで、確かに毎年継続事業として工事を進めているところです。これは土側溝に排水フリュームを整備する工事になります。延長は7メートルで、水路脇ということでフェンスを32メートル予定しています。
吉田
7メートルは長さなのですか。平成30年度は水路を7メートル工事するということだと思いますが、周辺で大雨が降ったときなど非常に水はけが悪いと指摘されていると思うのですが、その改善は平成30年度ではどの程度行うのか伺います。
土木課長
今回の水路整備を行って、平成30年度でこの場所については工事完了予定になっています。水路がコンクリート構造物になりますので以前より流れがよくなり、環境上はよくなると思われます。
吉田
224、225ページの8款4項4目駅前広場等管理費の全体的なことでお伺いいたします。先ほど、歩行すべきではないところを歩行する方に注意を促すために看板の設置、そして植栽というお話がありました。駅前の広場については、名取駅の利用者が非常にふえていることもあると思いますが、問題はほかにたくさんあるのです。例えばロータリーに入ってきたバイクがそのまま自転車置き場のほうへ歩道を突き抜けていったり、バスがとまる場所に車が何台もとまっている。あるいは、駐車場に入るためには1回ぐるっと回って生協側から入らなければいけないのが、直接バス停側から入ってしまう車があり、この間はそこでトラブルも起きていました。本当に利用者がふえている、そしてまた、なとりん号が今度増便されますからますますごちゃごちゃしてくると思います。そうした中で、そのような状況をどこまで把握して今回優先順位として植栽を選んだのか、検討の経緯について御説明いただきたいと思います。
土木課長
ロータリー内を歩行者が通らないように植栽と注意喚起看板を設置したことについては、一般質問でも話があり、確かに担当でも朝と夕方に行って現場を見てみました。そうすると7割から8割ぐらいの方がロータリーを横断するような状況でしたので、これはやらないとだめだということで設置しました。委員御指摘の件については、今後現地を確認して、危ないところがあるのであれば確かに改善も必要になりますので、今後検討していきたいと考えております。
吉田
植栽があることによってのメリット、そして看板の設置によって注意喚起ということで、実際今までそういうことをしていた方が考え直すこともあるかと思いますので、効果については、数字であらわすようにとまでは申しませんが、一定程度あると思います。ただ、優先順位のつけ方といいますか、いろいろな要望や危険度の高低がある中でなぜそこから進めるのかという部分が、今の御説明では一般質問があったからと。では、一般質問で取り上げれば何でも先にやってくれるのかといえばそうでもないと。ですから、そこに至った経緯をもう少し具体的にお伺いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。
土木課長
先ほど確かに一般質問と言いましたが、委員御指摘の件については担当でも把握していない点もありました。その中で植栽と看板に決まったものですから、私たちも現地を再度確認して、改善すべきところがあれば今後改善していきたいと考えております。
吉田
226、227ページの8款4項5目コミュニティプラザ等管理費11節需用費で修繕料が計上されていますが、この内容をお伺いいたします。
都市計画課長
名取駅の東西の男女トイレの便器や水の入るタンクの修繕、また名取駅東西自由通路の照明灯の修理を考えています。
吉田
名取駅コミュニティプラザではないようですが、そこに防犯カメラが設置されていると伺っていまして、警察からの照会が非常に多いと。やはり人がよく集まる場所なので、指名手配の人が来たのではないかなど警察からの問い合わせがよくあるという話を伺っておりますが、平成30年度について防犯カメラの充実に係る検討はなかったのでしょうか。
都市計画課長
平成30年度については今のところそこまで考えておりません。
吉田
238、239ページ、9款1項1目常備消防費12節役務費に電話料等とあります。救急隊員が搬送先の病院を調べるためなどに携帯電話を利用しているということですが、この電話料の中に業務で使用する携帯電話の料金も含まれるということでよろしいですか。
警防課長
委員おっしゃるとおりです。
吉田
何台使っているのか。また、携帯電話の会社もいろいろとありますが、どのように決めているのか、選定の仕方をお伺いしたいと思います。
警防課長
携帯電話に関しては、救急車が3台、各出張所のポンプ隊に1台ずつで3台、隊長と指揮隊で2台、通信に1台で計9台、そのほかに救急車にスマートフォンが3台です。
吉田
240、241ページの9款1項2目非常備消防費です。消防団の制度が変わって学生消防団員や市外から通勤する方の消防団への入団が可能になって間もなく1年ですが、それらの方々の入団促進の取り組みとして、平成30年度についてはどのようなことを考えたのかお伺いいたします。
消防本部総務課長
現在、学生消防団に2名が入っておりますが、これは市内の大学校、専門学校に伺って勧誘を行いました。新年度についても、同じく市内の大学校、専門学校等に直接出向いて説明をし、チラシの配布やポスターの掲示など入団促進について依頼したいと考えております。
吉田
学生消防団はそのような形でますますPRが進んでいくと思いますが、市外からの一般の方についての取り組みも確認したいと思います。
消防本部総務課長
市外から市内の企業や事業所にお勤めの方がその勤務地の分団に入団するという勤務地団員も、平成29年度の改正で同じく条例に加えました。こちらに関しても、消防署で実施している予防査察の機会を利用したりホームページへの掲載、また消防団協力事業所等に周知して入団促進に努めていきたいと思います。
吉田
246、247ページの9款1項4目防災費15節工事請負費、全国瞬時警報システム改修工事についてお伺いします。先ほど機器の更新でカテゴリーの種別がふえるという答弁がありましたが、主な部分で結構ですので、変更になるカテゴリーについて伺いたいと思います。
防災安全課長
国ではどの部分のカテゴリーがふえるとは示していませんが、考え方としては、これまで緊急地震速報、火山情報など幾つもあり、それを再分類といいますか、もう少しふやすことができるということで種別がふえると聞いています。
吉田
以前に鳴らなかった事例があり、現在運用している受信機で一部使いづらい部分があるのではないか考えました。そのような点について、新しい受信機は市で再設定しなければいけない部分が結構あるのか、あるいはほとんどそのままで国から配信された情報は受信できるように改善されているのか、把握していればお伺いしたいと思います。
防災安全課長
新型受信機を購入し、本市において防災行政無線に自動起動機を介して接続して、そして子局においてアナウンスをすることになります。新型受信機のインターフェースとして接続の部分に関しては特に調整は不要ではないかと思っていますが、どうしても自動起動機で外へアナウンスすることになりますから、この部分の調整はあるものと捉えています。
吉田
250、251ページ、10款1項2目事務局費19負担金補助及び交付金に仙台地区教科用図書採択協議会負担金が計上されています。教科書の採択が平成29年度に行われたと思いますが、教科書が選ばれた経緯などについて、平成30年度はどのように市民に対する説明というか周知を考えているのかお伺いします。
教育長
教科書採択については教育長が直接かかわっておりますので、私からお答えいたします。
仙台地区教科用図書採択協議会は、宮城県内に8つある共同採択地区の1つで、仙台管内の13の市町村がこの協議会に入っています。ここで小学校、中学校で使用する教科用図書の採択を行いますが、その採択結果、理由についてはホームページを通して公表しております。
吉田
ホームページで確認したところ、主要教科について出版社が全部同じでした。いろいろな出版社があり、選定する会議において内容をよく比べて決めたと思いますが、そうした実態があるわけです。他自治体の中には、いろいろな教科書がある中でなぜこの出版社に決めたのかということを図書館などに展示して市民に見てもらい、一緒に考えていただく取り組みをしているところもあると認識していますが、そのような取り組みは平成30年度は行わないということですか。
教育長
今御紹介があったような形での取り組みについては考えておりません。
吉田
252、253ページの10款1項3目生涯学習推進費8節報償費、生涯学習振興計画策定懇談会委員謝礼とあります。この生涯学習振興計画の策定のスケジュールについてお伺いいたします。
生涯学習課長
生涯学習振興計画のスケジュールですが、平成7年に策定した名取市生涯学習推進基本構想に基づいて、5年ごとに生涯学習振興計画を策定しており、現在、第3次名取市生涯学習振興計画があるのですが、当初の計画期間は平成21年度から平成25年度で、期間が過ぎています。生涯学習に関する考え方等が変わってきたということで平成30年度に市民意識調査を行いますが、その前に、先ほどの生涯学習振興計画策定懇談会委員を4月に選出して、策定検討委員会を行った後、生涯学習市民意識調査を7月ごろに予定しています。そして、意識調査の結果を踏まえて課題整理等を行い、平成31年度いっぱいかけて新たな生涯学習振興計画を策定したいと考えております。
吉田
現在の第3次の計画から生涯学習に関する考え方が変化しているという答弁でしたが、具体的に教育委員会としてはどのように変化していると捉えているのでしょうか。
生涯学習課長
平成7年に策定した生涯学習推進基本構想と比べますと、社会環境が変わってきて、また行政機構も大きく変化しており、それにより市民の学習環境も変わったと認識しております。その認識に基づいて新たに意識調査を行い、生涯学習振興計画を策定したいと考えております。
吉田
252、253ページ、10款1項3目生涯学習推進費で生涯学習振興計画についてもう一度お聞きします。先ほど答弁で市民意識調査については18歳以上の市民を2,000名抽出するとありましたが、アンケート調査の内容によって答え方が変わってくると思うのです。といいますのは、現在、生涯教育とは何かということ自体が広く浸透しているとは言いがたい状況だと思うので、意識調査の方法についてもう少し具体的に考えていたらお伺いしたいと思います。
生涯学習課長
意識調査に関しては、平成30年度に向けて行うということで、詳細についてはまだ決まっていませんが、アンケート調査の内容の骨格として、1つは市民の学習活動の有無と将来の学習意欲、また学習情報の収集の場、学習の場、あるいは地域への愛着度などを盛り込めればと思っているところです。
吉田
公民館の将来像を考えるワークショップなども行われている中で、それらとの関連もいずれ出てくるかと思います。生涯学習というと、今の枠組みの中では中等、高等教育を終えた年齢の方と捉えるのが一般的だと思いますが、世代交代がうまくいっていないという公民館運営の問題などがある中で、世代間の交流が今後の考え方に含まれるのかなと。先ほど生涯学習の考え方が変わってきているという御説明があったので、その辺を期待したのですが、今そうではないような気がしました。意識調査にしても、18歳以上ということですが、なぜそう限るのか。例えば小さいお子さんをお持ちの保護者に対しては、18歳以下の子供も含めての生涯学習を今後どのように考えていくのかという点についての検討はありませんか。
生涯学習課長
現在、平成30年度に向けて進めているところで、対象者を18歳以上の市民と答弁しましたが、過去に同様の意識調査を行った際にこのような形をとりました。委員の御指摘については今のところは考えておりませんが、どのようにできるか考えさせていただきたいと思います。
吉田
280、281ページです。10款5項2目公民館費19節負担金補助及び交付金に名取駅前再開発ビル管理組合負担金とあり、4目図書館費にも同じ項目が計上されています。事務費ではなく管理組合の負担金とすると、共同で建物を使う方たちが管理組合を設立して、その中での負担金として本市の分ということだと思いますが、この金額の算定根拠を伺いたいと思います。
生涯学習課長
名取駅前再開発ビル管理組合負担金の内容ですが、公民館や図書館が入っている北棟の共有部の管理費です。これについては、建物全体に関する消防設備点検業務や入退室管理システムなど、また公民館施設に関するエレベーター点検、フロン排出抑制法に基づく点検業務等が含まれている負担金です。それから、駐車場等管理費ということで負担金が発生しています。駐輪場の管理費も同様に負担金が発生しています。そして、修繕積立金ということで、これは駐車場等ですが、竣工後に突発的な修繕が必要となった場合を想定して新築時にあらかじめ積み立てておくもので、この4つの部分が今回負担金ということで予算計上しているところです。
吉田
私が知りたかったのは、金額をこのように設定した根拠です。組合となると、マンションの方まで含むのかどうかここではわかりませんが、多数の団体や個人で構成される中で、本市として、教育委員会としてこの金額を負担すると。これだけではなく、公民館、図書館とそれぞれ同様に求められています。なぜこの金額に定められているのか、誰が決めたのかわからないのでもう一度お聞きしたいと思います。
もう一つですが、修繕などが必要になってくるための積み立てもあるということでした。今後必ず老朽化しますからいつかはあり得ることだと思うのですが、いろいろな団体や個人が参加している組合の中で物事を決定する際に、やはり総会のようなものが行われることになると思います。そうした際に、本市あるいは教育委員会として、表決権といいますか、多数決を行う際に市としてはどの程度の発言力があるのか。その点は平成30年度においてどのように決めてこの金額を設定したのでしょうか。
生涯学習課長
まず負担金積算基礎ということで、管理費の算定と捉えて答弁いたしたいと思います。北棟と駐車場棟と2つありますが、北棟は名取市外1名と、駐車場棟は名取市のほか店舗やマンション入居者が入ります。それぞれ管理組合を設立して、管理組合が管理会社を決定する方法をとっています。管理組合が管理会社と協議の上、施設の維持管理に係る経費等を試算して、所有者の占有面積に応じて算出しているところです。
次に、議決権に関してですが、北棟の所有者については名取市外1名と2名であることを考慮して、北棟に関する決め事については随時もう1名と協議して決めています。北棟の議決権についての規約はまだ作成されておらず、夏ごろにできるという話を伺っております。駐車場棟の議決権については規約ができており、公民館が137分の17、図書館が137分の40です。
吉田
一部規約がまだない状況でこうして提案されていますので、そのあたりをどう判断していいのか難しいという印象を受けております。
管理組合の負担金の中で処理されるのが、先ほど言った北棟の共用部、駐車場棟に係る部分ということですが、管理組合と管理会社はまた別にあるわけですし、本市の負担分の算定も規約に盛り込まれると思いますが、この規約は議会で確認することは今後可能なのですか。
教育部長
先ほど生涯学習課長から夏ごろに規約ができるということでした。それが確定すれば、積極的に公表するということではなく、お尋ね等がありましたら組合で規約を示すことは可能だと思っております。
吉田
280、281ページ、10款5項2目公民館費、もう一度名取駅前再開発ビル管理組合負担金についてお伺いします。ほかにも287ページと305ページの計3カ所で同じ名目で計上されていて、先ほどの答弁からは、規約が幾つかあり、1つはできていて、まだできていないものは5月にできる予定と読み取りましたが、規約が幾つかあるということは組合が複数あると捉えられる気もするのですが、組合の構成についてお伺いしたいと思います。
生涯学習課長
管理組合については、南棟もあるのですが、本市としては北棟と駐車場棟ということで、北棟は本市とほか1名、駐車場棟については、南棟も北棟も利用しますので、本市と店舗、マンション入居者で構成しています。
吉田
そうすると、この負担金は今言った幾つかの組合を全部一まとめにして、その中で負担金をそれぞれ分けたというあらわし方なのですか。北棟管理組合があり、また駐車場棟管理組合があるとなると、説明にはそれが別々に出てくるべきではないかと思うのですが、実際は一つにまとめてこの数字で計上されているということですか。
生涯学習課長
名取駅前再開発ビル管理組合負担金の中身ですが、それぞれ駐車場棟負担金と北棟負担金が含まれており、一本で負担金として表示しています。先ほど委員から予算措置が3つに分かれているとありましたが、市として、図書館と公民館が施設ごとで負担していることと、公民館は災害復旧事業で整備している関係上、分けて計上しているところです。
吉田
そうすると、管理組合は1つの組合ということでよろしいのですね。北棟の組合があって駐車場棟の組合があるのではなく、1つの管理組合で、その中で本市から北棟の分と駐車場棟の分として負担し、そして組合の中でそれぞれに充当するということかと思うのです。管理組合は普通の住居用マンションなどにもあります。マンションの入居者が1世帯ごとに加入し、修繕費等を積み立てて、何十年かに1回それを使って修繕を行ったり、また日常の管理をする。恐らくそれと同じ考え方だと思うのです。そうすると、この管理組合には、名取市教育委員会以外にもマンションを含めた複合施設の住人や店舗のオーナー等も加入しているはずです。
そうした中で、今後建物の修繕等を行う際に、本市も管理組合の一員ですから、話し合って決めていく際に本市として意見を申し上げることもできるし、決定権の一部を持つと思います。その場合にどのぐらい本市の言い分が通るのかということを知りたいのです。お金だけたくさん負担させられて、実は1票しかなかったといった取り決めになっていないのかどうか。きちんと負担金に比例する形で表決権を与えられているのかどうか。その点について把握しているのかお伺いします。
生涯学習課長
管理組合は1本ではなく、北棟と駐車場棟の管理組合は別です。
そして、所有者の負担割合に応じた議決権、言い分が通るような形になっているのかということですが、先ほど駐車場棟についての議決権は公民館が137分の17、図書館が137分の40と答弁しました。残りは店舗やマンション入居者になると捉えています。北棟については、本市のほかは1名なので、規約がまだできていないこともありますが、2名の構成であることを考慮し、今のところ、決め事については随時ほかの1名と協議して決めています。ただし、持ち分比率でいえば本市のほうが議決権が多くなると考えます。
(議案第3号 平成30年度名取市国民健康保険特別会計予算)
吉田
319、320ページの1款1項1目一般被保険者国民健康保険税の滞納繰越分について、ここに3つあるわけですが、その滞納されている方の滞納期間はどのくらいになっているのか。1年未満の方は何%とか、ある程度の期間ごとに捉えているものがあれば教えてください。
税務課長
滞納額や滞納者の傾向の把握については、1年間未納だとか2年間未納だとかという捉え方はしていないところです。
吉田
調定見込み額全額であったとして、それに対して見込みが10%ということで例年そのような見込みを立てているということですが、これを10%そのまま納めていただいたとして、残り90%がまだ滞納中ということになりますが、これが平成30年度中に不納欠損になる部分はどのくらいと見込んでおられるのですか。
税務課長
不納欠損の見込みですが、不納欠損になる事由が3通りありまして、例えば執行停止後3年たっても納められない状況の方、あとは滞納者が亡くなって、その方の相続人も財力がなくて納められずに相続放棄するなど、そのような事情があって不納欠損になるものです。ですから、不納欠損の見込みは、当初ではなかなか見込めないのが現状です。
吉田
341、342ページですが、5款2項1目保健事業費1節報酬でレセプト点検員報酬とありまして、平成29年度3名から2名に減らされて、その際に県単位化による共同実施が検討されているということで、今後状況を見てという答弁だったと記憶しているのですが、この平成30年度のレセプト点検の体制について伺います。
保険年金課長
レセプト点検の体制ですが、平成30年度はこれまでどおり市で行うことで考えております。人数は平成29年度と同数になりますが、2人でレセプト点検を実施するということで考えております。
吉田
平成29年度と同じ2名ということですが、3名から2名に減った仕事内容を見ながら、平成30年度もこの2名で十分対応できるという見込みでよろしいのですか。
保険年金課長
お見込みのとおり2名で対応していきたいと考えております。
(議案第4号 平成30年度名取市土地取得特別会計予算)
吉田
353、354ページ、4款1項1目土地開発基金借入金です。一般会計と比べまして、実際には市民墓地の事業等になってくるのかと思ったのですが、今回このように土地取得会計から計上されているということですが、市民墓地の計画について、今土地の取得は100%完了していると捉えてよろしいですか。
生活経済部長
市民墓地ですが、用地取得については今進めている最中です。全てが終わったということではありませんが、大区画の土地などもありますので、今鋭意用地買収については進めている最中です。
吉田
美田園の空港のところの公園で用地取得できなかったという例が、一部契約の変更ということで先日審議されました。そういうことがないようにお願いしたいと思うのですが、実際に連絡がとれないで今に至っている方は、この件の中ではそういう例はないと捉えてよろしいですか。
委員長
吉田 良委員に申し上げます。少し広がり過ぎておりますので、土地取得会計についての質疑でお願いします。
吉田
平成29年12月定例会の補正のときに、同じように1億何がし計上されておりますが、今回このように分けて計上している理由について伺います。
財政課長
今回、こちらで措置しております1億6,860万円の借入金については、平成30年度の市民墓地の事業分ということで計上しているものです。
(議案第6号 平成30年度名取市介護保険特別会計予算)
吉田
387、388ページ、4款1項3目任意事業の12節役務費、成年後見制度申立鑑定手数料等とありまして、認知症などによって自分でいろいろ決定することができなくなった方のために成年後見人を立てる制度かと思いますが、本市でどのようなケースがあって、それから何件と想定されているのか、伺います。
介護長寿課長
この成年後見制度利用支援事業ですが、これは主張申し立ての部分です。現在1人の方がいます。平成30年度の予算では、3名の方を見込んで予算を計上しているところです。
吉田
こういったケースが全国的にふえてきている傾向があるように伺っております。これは3件と見込んでいるという御説明でしたが、実際にこの制度が利用されていく中で、行政で実際の業務上、そのような方が出ているという実感、この制度の今後の拡大の見込み等、その捉え方は今どのようにお持ちでしょうか。
介護長寿課長
成年後見制度については、高齢者がどんどんふえていく中で今後ふえていくものと思われます。まして、主張申し立ての部分についても、困難事例が多数あります。例えば、離れて暮らす家族がいるにもかかわらず、自分の父や母の面倒は見ないというような家族関係も多々ふえております。そのような困難事例が上がったときに、包括支援センターや市役所に相談があって、それで主張申し立てということで順を追って支援をしていくというような形になっております。
本会議
(議案第2号 平成30年度名取市一般会計予算)
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長より発言のお許しをいただきましたので、名和会を代表して、議案第2号 平成30年度名取市一般会計予算について、賛成の立場から討論を行います。
名取市震災復興計画の期間が残り2年となった今、ハード面の復興事業を確実に進めるとともに、地域コミュニティーが自立して活動できる体制を築いていくことも課題として捉える必要があります。地域づくりは全ての住民が当事者であるという意識を醸成することが重要であり、地域コミュニティーの育成にプラスとなる施策をどう打っていくのか、市民の知る権利にどう応えていくのか、行政の手腕はこのようなところにも問われております。
復興計画期間の終了後に対しても、本格的に視野を広げていく段階に差しかかっております。新たに編成された平成30年度予算は、そうした求めを十分に満たすものとは言い切れない部分はあるものの、これまで行われてきた事業の継続性に配慮しながら、市長が目指す市内の均衡ある発展に向けた方向性を示している点で、評価すべき内容であるとの結論に達しました。
以下、事業の効果を最大限に発揮していただきたいとの思いから、何点か注文を申し添えたいと思います。
歳入の部では、市税とりわけ個人市民税の伸びが予測されており、順調に人口が増加することを見込んでの算定であろうと思います。本市の人口増だけを見れば確かに喜ばしい状況ではありますが、まだまだ伸びしろがあると考えられます。空港や高速道路など交通インフラが充実している恵まれた立地を最大限に生かし、さらなる税収増をもたらす企業誘致と定住促進に、より積極的に取り組まれることを期待します。
また、市の独自色を発揮できるふるさと寄附金ですが、各市町村によってさまざまな返礼品が考案されており、本市では寄附金額が頭打ちとなった感があります。平成30年度はPRを強化することなどにより、予算計上した額を確保することはもちろんのこと、より大胆で話題となるような取り組みを市としても模索されるよう望みます。
次に、歳出の部、震災関連事業のうち、生活再建支援事業では前年度に引き続き伴走型支援のための経費が計上されました。平成30年度中に3カ所の仮設住宅の閉鎖が予定されておりますが、具体的な生活再建策を決められずにいる被災者の方がいまだに多くいらっしゃいます。一日一日と時間が経過するごとに、その方たちにとって不安は募るばかりです。個々人の置かれる状況や希望にはそれぞれ差があり、多様な対応が求められるという厳しさがありますが、行政の英知を結集し、最良の支援を提供されることを望みます。
通常事業のうち総務費では、市制施行60周年記念事業における取り組みが具体的に示されました。記念コンサートの一部、市民提案事業、市民参画型地域イベント事業などで、行政から市民への一方通行としてではなく、市民の発想力や発信力を生かそうという方向性は、市民協働によるまちづくりを進めていくための基礎を形成する意味でも、非常に有意義であると考えます。事業主体となる市民団体には、イベント等の開催実績が余り多くない団体もあろうかと思われますので、事業を成功に導くための助言を惜しまぬようお願いしたいと思います。
土木費では、名取団地の空き家解体の費用が計上されたことにより、長年指摘され続けてきた安全面での不安材料を軽減させるばかりでなく、市内で最も高齢化が進む地域に活力を生み出すことも期待されます。ただ、現在26棟ある管理棟数のうち、平成32年度までに14棟の解体が計画されていますが、残り12棟については今の時点では見通せない状況にあります。約1万4,000平方メートルという広大な土地を一体的に活用できてこそ、土地の用途変更は最大の効果を生むものと捉えられます。今後、入居中の方々と丁寧な対話を進めることにより、転居への理解につなげていくことと、跡地利活用調査においては市全体の課題でもある高齢化への対応として、一つのモデルを示すことを目指していただきたいと願います。
消防費では、初めて女性消防職員を採用するに当たっての庁舎修繕費が計上されました。男女共同参画が一層進むと同時に、女性ならではの活躍が大いに期待されるところです。将来的には女性消防職員を5名にまでふやす目標とのことですが、たった1名でのスタートですので、女性であることを理由とする負担が、物理的なものはもちろんのこと精神的にも生じないよう、雰囲気づくりなども課題として捉えておいていただきたいと思います。
教育費では、第4次生涯学習振興計画策定のための費用が計上されました。本来であれば、第3次計画は平成25年度までであり、既に第4次計画は実施されてしかるべきところですが、ともあれ平成30年度中に第4次計画策定に着手できることは評価すべきところです。策定に際しては、市民意識調査の結果を反映させることはもちろん、これまで実施してきた事業の成果や課題を踏まえ、新しい時代にふさわしい計画となることを期待します。
教育費ではほかに、平成30年度中に復旧が完了する図書館と増田公民館が円滑に事業を開始するための経費が計上されております。中心市街地の活性化と生涯学習のさらなる進展に、各施設がその役割を大いに果たすことが期待されます。特に図書館では、ボランティアの方々の協力体制を構築していくなど、ソフト面の充実を図ることを望みます。
なお、図書館と増田公民館が入ることになる複合施設、北棟と、居住者や利用者のための駐車場棟については、本市にとって初めてとなる区分所有による管理運営が行われることが決まり、管理組合の負担金が計上されました。区分所有は、立地のよい場所に商業施設と同居することによるメリットがある反面、施設が高層化複合化することにより、維持管理費が高くなりやすいデメリットもあります。他の権利者がかかわることから情報公開が進みにくく、高コスト体質になることが見過ごされやすい傾向があることも指摘されております。
駐車場管理組合において、3分の1以上の議決権を保有していることは確認できました。今後の協議において、組合理事会の役員に市長の代理として本市職員を置き、施設管理に対する意思を反映させる機会を確保することを望みます。さらに、市民に対し、意思決定のプロセスを説明する場の設置を検討していただきたいと思います。
以上で私の賛成討論を終わります。
(議案第61号 平成30年度名取市一般会計補正予算)
吉田
6、7ページの16款2項2目土地建物売払収入となっていますが、この土地売り払いの場所についてと、金額の算定の根拠についてお伺いします。
復興まちづくり課長
売り払いの場所は、下増田の屋敷と広浦になります。売り払い金額は、地目が田、畑、雑種地とありますので、それぞれの地目に合った単価で算出しているところです。
吉田
今、国のほうで国有地の売り払いの経緯についていろいろもめているところですが、一般論でお聞きしたいのですが、土地を売り払う際に、相手方との交渉の中で金額が変わったりすることはあるものなのでしょうか。
復興まちづくり課長
不動産鑑定の結果に基づいて単価を決定しております。
吉田
11ページの2款1項28目震災復興費の東日本大震災復興交付金返還金となっておりますが、この返還金が生じた理由についてお伺いします。
財政課長
先ほど歳入で土地売払収入の部分がありましたが、こちらは2次防御ラインの用地買収に伴う代替地の提供ということです。こちらには復興交付金が入っておりましたので、4,492万8,000円に対する復興交付金分、補助率でいいますと0.875を掛けた3,931万3,000円を返還するものです。
吉田
そのようなケースは今まで記憶にないのですが、今後ももし生じた際には、やはりその都度返還金という形になるのか。それともある程度ためておいて、どこかで一度に返すのか、そういう考え方はいかがでしょうか。
財政課長
事業が進行しているものについてはやりくりの部分はあるかと思いますが、今回こちらは防災集団移転促進事業ということで、事業そのものとしては土地を買った段階で終了しているため、終了した事業にこのようなことが発生した場合には、その都度返還していくものと考えております。