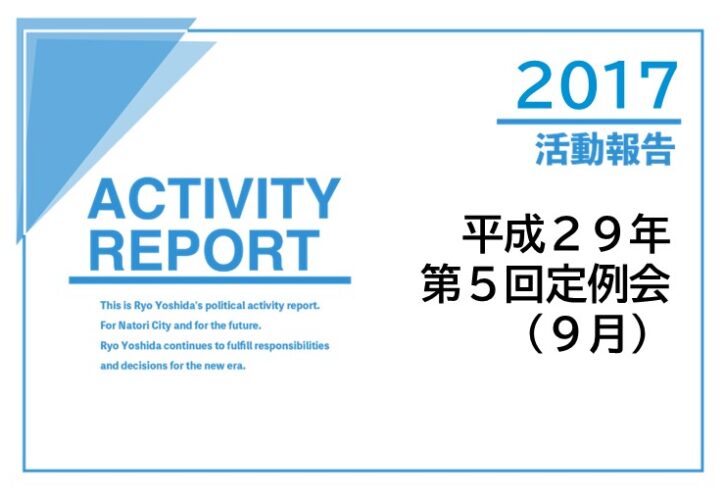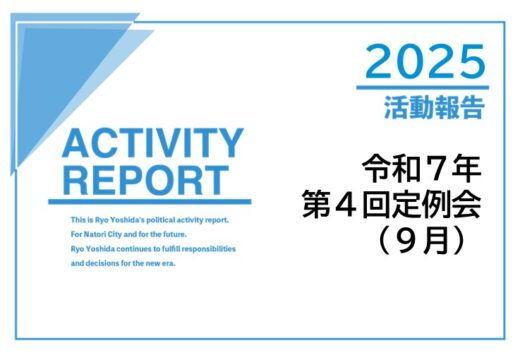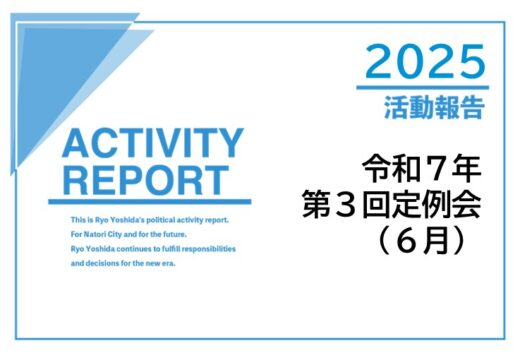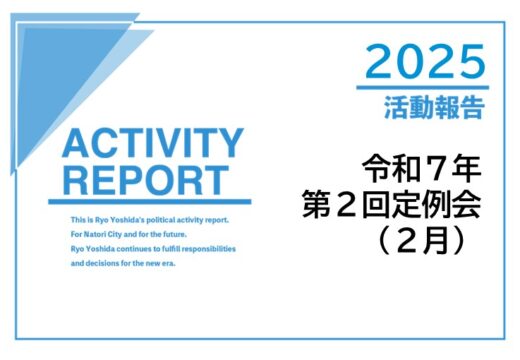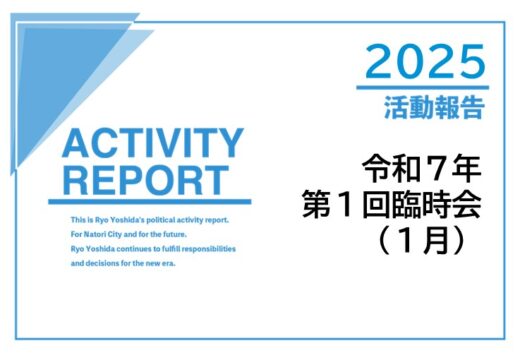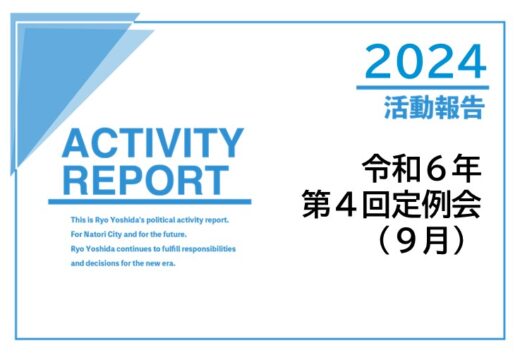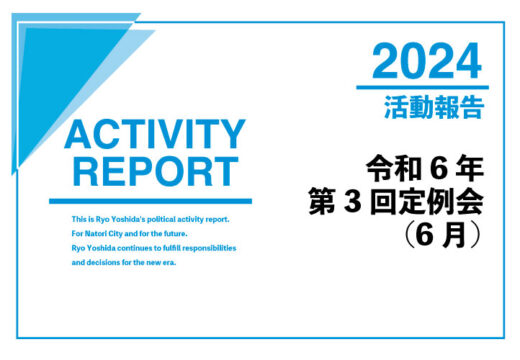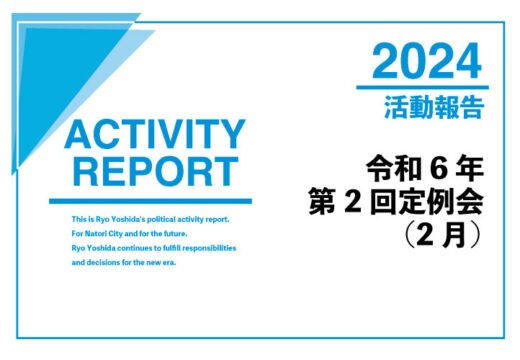本会議
(議案第100号 市道路線の廃止について及び日程第25 議案第101号 市道路線の認定について)
吉田
昨日、議員協議会で環境省のみちのく潮風トレイルの説明をいただき、コースに閖上も含まれるということで全体的な地図を見せていただきましたが、今回廃止される市道の中でそのコースにかかっている部分はあるのでしょうか。
土木課長
お尋ねの路線は閖24と捉えてお答えしますが、この路線は今回廃止しませんので、既存の道路をそのまま使う形を考えております。
吉田
すると、みちのく潮風トレイルは平成30年度までに整備し、始まるのが平成31年度以降になるかと思いますが、区画整理事業が始まっていても、実際に利用者の通行という面では影響はないと考えてよろしいのでしょうか。
震災復興部長
今説明させていただきました閖24については、閖上東地区の区画整理事業にあわせて一部若干のかさ上げが必要になる道路であり、工事中は通行、また当然歩行者の安全も確保しながら、代がえの路線を用意するなどして工事を進めていきたいと考えております。
一般質問
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長より発言のお許しをいただきましたので、通告に従い私の一般質問を行います。
まず、大項目1 他国によるミサイル発射等に対する市民生命の保護についてお伺いいたします。
去る8月29日火曜日、日本時間の午前5時58分ごろ、北朝鮮から弾道ミサイルが発射されました。日本政府は、午前6時2分、北朝鮮西岸から東北地方の方向にミサイルが発射された模様との情報を全国瞬時警報システム、Jアラートで伝達しました。伝達対象地域は宮城県を含む12道県に上りました。市内では、携帯端末に緊急速報エリアメールが配信されたほか、市の防災行政無線からは国民保護サイレンが吹鳴され、市民に避難を呼びかける放送が繰り返し流されました。弾道ミサイルは午前6時6分ごろに北海道上空を通過し、午前6時14分ごろに太平洋上に落下したと推定されます。幸いなことに人的、物的被害はありませんでしたが、新幹線や在来線などの一部で運転が見合わされるなど、市民生活への影響は決して見過ごせるものではありません。
さらに、9月3日には6回目の核実験が強行されました。北朝鮮による軍事的挑発は今後もますますエスカレートすることが予想される一方、アメリカ大統領は全ての選択肢がテーブルの上にあると発言するなど、日本を含む東アジアの情勢は、朝鮮戦争の休戦後、最も緊迫した状況にあると言っても過言ではありません。事態がこれ以上悪化しないことを願いながら、本市としても定められた国民保護の体制を万全のものにしていかなければなりません。まず、このたびの危機に対し本市がどう対応したのかを確認させていただきたいと思います。
小項目1 北朝鮮によるミサイル発射・通過という8月29日早朝の政府発表を受けての対応を、市長、消防長、教育長にそれぞれお伺いいたします。
市長
8月29日早朝のミサイル発射・通過に伴う対応としては、Jアラートの受信により防災行政無線での周知を行っております。また、名取市国民保護計画の参集基準に基づき、担当課体制として防災安全課職員が自主参集し、その後、情報収集に当たっております。当該情報収集により得た情報については、ホームページに掲載し、情報発信を行ったところです。
消防長
8月29日早朝の消防本部の対応については、担当課の警防課員が参集し、緊急情報ネットワークシステム等からの情報で宮城県に対して着弾の可能性が低くなったことから、情報収集活動を行ったところです。
教育長
教育委員会では、情報収集に努め、対応を検討しました。その後、児童生徒の登校に際し、差し迫った危険はないと考え、通常の登校と判断いたしました。
吉田
まず、市長にお伺いします。新聞等の報道で、Jアラートの情報が自動的に流れるはずだった登録制のなとり防災メールで、そのメールが届かなかったという事例があったということでした。また、ツイッターの防災情報アカウントでも同様の事案が起きているということで、その原因と再発防止策についてお伺いしたいと思います。
次に、消防長には、やはり消防はいざとなったときに一番に市民の生命を守らなければならない立場ですので、まず守る立場の方たちが最初に自分たちの身を守らなければなりませんが、そのときに、今政府から伝達されている、実際に警報が鳴ったときに物陰に隠れるとか、そういうことについてどのように御自身の身を守る体制をとってきたのか、その点についてお伺いしたいと思います。
また、教育長には、今、小中学校は特に危険がないという判断で通常どおりの登校としたとの答弁でしたが、その休校しないという判断をしたプロセスについてもう少し詳しくお聞きしたいと思います。
市長
当日、防災メールとツイッターがJアラートに連動して配信されなかったことに関しては、運用設定上の問題ということもありましたので、具体的な経緯について担当より答弁をいたさせます。
防災安全課長
Jアラートによる情報のなとり防災メール等への未配信に係る経緯について御説明いたします。
去る8月29日火曜日、国からJアラートにより情報伝達がありました。午前6時2分に、ミサイル発射情報として、関係する北海道、東北地方、長野までの北関東地方に対し情報を配信し、午前6時14分にミサイル通過情報を関係する12道県に伝達されています。
本市においてもJアラート情報を受信し、防災行政無線の屋外拡声子局とFM放送局への割り込み放送、そして防災ラジオでの自動放送は行っております。しかしながら、新たな伝達手法であるなとり防災メールによる、登録した市民宛てのメールでは、情報伝達には至っておりません。
今回の情報伝達に関しては、登録市民メールなどへの関連づけ、設定の際の認識不足に課題があったと捉えております。国からのJアラートの情報は、カテゴリー別に大分類されており、国民保護関係情報、緊急地震速報、地震情報、津波情報、火山情報、気象情報などの大分類が、さらに中分類、小分類の情報種別に区分されています。今回のような弾道ミサイル情報についてはカテゴリーの大分類、国民保護関係情報のうち、小分類の情報種別がゲリラ情報、航空攻撃情報、ミサイル情報、大規模テロ情報として配信されるものと認識し、この場合には登録市民メール等へ連動して情報提供するよう、連動システムを「有」と関連づけておりました。しかしながら、今回の情報種別の即時音声合成情報については、市民メールへの連動システムでは「無」として、関連づけておりませんでした。基本的にミサイル情報は小分類の情報種別にあるミサイル情報により配信されるものと認識しており、即時音声合成情報での情報配信を想定、認識しておりませんでした。このことから、今回のJアラートの情報はなとり防災メールの登録市民に対し、お届けしておりません。
8月29日の事象確認後、Jアラート情報の即時音声合成情報となとり防災メール等への連動に関しては関連づけをしたところです。今後、同様のJアラート信号の受信後は、防災行政無線を通じての屋外拡声子局での放送を初め、なとり防災メール登録者への情報配信など、多様な情報提供に努めていきます。
消防長
消防本部としては、Jアラート警報に伴う弾道ミサイル飛来の初動対応についてという取り決めをしております。具体的には、Jアラート警報の発令と同時に、窓、車庫を閉鎖、本署の来庁者及び職員、当時は早朝でしたので来庁者はいませんでしたが、1階の待機室、旧ボイラー室などに避難する、それから、通信係による関係機関との情報収集と共有及び通信機器の点検、また、災害の大規模化が予想されるため全職員、団員の招集の準備という内容になっており、当時はこれに従って初動対応を行ったところです。
教育長
差し迫った危険がないと考えた経緯ですが、先ほど議員からも御紹介があったように、午前6時2分にJアラートが作動し、その後、早い子供たちが登校を始める時間帯、午前6時半から7時ぐらいには、既に北海道上空を通過し太平洋に着水した模様という情報が流されておりました。そのようなことから、登下校には支障がないと判断したという経緯です。
吉田
今回はこのように大きな被害が出ませんでしたが、これからどのようなことが起きるかまだわからない状況ですので、常に最悪の想定をしておかなければならないと言えるかと思います。
今御答弁いただいたことを広げて、次に移らせていただきたいと思います。
市内の一時避難場所についてお伺いいたします。
政府は、弾道ミサイルの発射から到達までの時間を10分足らずとし、落下する可能性がある場合は行政からの指示に従うよう広報しています。しかし、いざエリアメールが受信され国民保護サイレンが聞こえても、とっさに行動することは難しいものです。
8月29日の場合、ミサイル落下の可能性を警告する放送が防災行政無線から流れているにもかかわらず、ふだんと何も変わらずに犬を連れて散歩している市民の姿もありました。その背景には国民保護サイレンが周知されていないという問題がまず挙げられると思いますが、それ以前に、ミサイル落下から身を守ることができる場所が市内のどこにあるのか、どのくらいの人数が避難できるのかが知られていないのが実情です。
そこで、小項目2 市内で一時避難に利用できる主な場所と、その総面積・収容人数を市長にお伺いいたします。
市長
国では国民保護の避難施設をコンクリートづくりの建物としており、市内の一時避難に利用できる避難施設としては、指定避難所のうちコンクリートづくりの26カ所と捉えております。
ミサイル発射等の場合の一時避難については、当該避難施設の近くにいる方のみが避難することになるため、施設での面積的な部分での受け入れは十分可能と考えており、施設の総延べ面積、避難収容人数は捉えていないところです。
吉田
市で指定しているのは26カ所ということですが、もう少し具体的にその26カ所の内訳についてお伺いいたします。
防災安全課長
小学校、中学校、公民館をもって26カ所と答弁申し上げています。
吉田
そうかと思いましたが、今回のこの事態は御存じのように早朝に起きた事例でした。この早朝の時間に、小学校、中学校、公民館に実際に避難することができる状況であったのかどうか、そのあたりの把握はいかがでしたか。
防災安全課長
学校や公民館が開所前であれば、その施設の中に入ることは、入り口を壊すなど特別な環境の中でだけ対応できるかと思います。その対応に関しては市でも内閣官房から出されている部分でお知らせをしています。屋内にいる場合、屋外にいる場合でその対応を周知しておりますが、情報伝達されて10分足らずで速やかに近くに避難ということになると、基本はお近くのところになるかと思います。公的な施設の部分で避難施設を申し上げていますが、一方で民間のマンションなどもその場面によっては避難する先になろうかと思います。
吉田
今、民間のマンションという話も出ました。それは1つ後に置いておきたいと思いますが、実際に小学校、中学校、公民館は施錠されていますので、まさかそれを壊して入るなどということは、本当にミサイルが落ちてくるかどうかがわからない状況の中でできることではありません。ということは、このような早朝を想定すれば、鍵がかかっていて避難できない場所を一時避難所に指定していることになってしまいますので、この辺はもう少し詰めていかなければならないと思います。
それで、今おっしゃったマンションですが、現在、鉄筋コンクリートづくりのマンションが市内各所にありますが、新しいマンションはほとんどオートロックがかかっている現状だと思います。本当にミサイルが落ちてくるかどうかわからないというときに、そのロックを破って入るなどということはできないわけです。ですから、今後、そういう際は管理組合などに協力をいただくなどして、例えばサイレンが鳴ったときは自動的にあけていただくというような協定を結ぶべきかと思いますが、そのような考えについて市長はいかがでしょうか。
市長
午前5時58分にミサイルが発射され、午前6時2分にJアラートが発動し、午前6時6分に日本の上空を通過しております。そういう意味では、四、五分という本当に限られた時間で自分の身を守ることになろうかと思います。そんな中でできることは非常に限られているのかなと。堅牢な建物にいればいいですが、外にいるときに、また、今おっしゃっているように早朝や深夜などであれば、自分の身は自分で守るということに基づいて対応するしかないだろうと思っています。ミサイルが発射されJアラートを受信したときに、例えば学校施設を自動で開錠できるようにするとか、民間のマンションなどのロックを解除して入れていただく体制をつくることについては、現実的に非常に難しい問題だろうと考えております。そのようになれば命を守るという意味ではいいかもしれませんが、現実問題を考えたときにさまざまな課題があって、実現するのは非常に難しいと感じております。
吉田
市長のおっしゃることももっともだと思います。何といっても、こういう危機が迫ってくることがこれまで想定されずに来ており、地下に避難する場所も全くないという状況が、全ての原因になっていると思います。
そこで、行政の機能の確保についてに移らせていただきたいと思います。
東日本大震災において、庁舎が被災し住民記録が消失するなど行政機能を失った自治体の例が報告されています。本市庁舎は激しい揺れに耐え、津波が到達することもなかったために、行政機能が失われることはありませんでした。しかし、弾道ミサイルという新たな脅威の高まりとともに、行政機能が維持できなくなるほどの大きな被害を想定し、代替施設の手はずをとっておくことが次なる課題であろうと思います。
さきに平成27年第4回定例会において、佐々木哲男議員が一般質問で、万が一を想定し、災害対策本部の充実及び機能確保について提言されました。それに対する御答弁は、例えば直下型の地震で庁舎の機能が確保できない場合については、例えば消防庁舎や市民体育館など安全な場所を確認して、そこを代替として一時的に利用する方法も検討しなければならないという内容でした。その具体的な検討がそれからどのぐらい進んでいるのか、恐らく進んでいるかと思いますが、今回はその延長線上にあるものとして、復旧までに長時間を要するほどの大規模な損害を受けた場合の行政機能の確保についてお伺いしたいと思います。
小項目3 攻撃等により庁舎が行政機能を果たせなくなった場合の仮庁舎の位置をあらかじめ設定し、市民に周知すべきについて、市長にお伺いいたします。
市長
ミサイル発射等による被害想定を市としてどう考え行動するかについては、非常に難しい問題だと捉えております。攻撃等により庁舎が行政機能を果たせなくなるような事態が発生している状況では、市全体に甚大な被害が発生していることが予想され、方針決定などについては国レベルでの対応になろうかと思います。
また、市庁舎が行政機能を果たせなくなるような攻撃等の中では、市内に必ず安全が保障される場所はなく、当該状況の中では、国、県と協議しながら、比較的安全な公共施設などを選択し、仮庁舎として使用するものと現時点では考えております。議員御紹介のとおり、自然災害等であれば消防本部が災害対策本部の設置場所となることが考えられますが、ミサイル発射等の場合に関しては、状況に応じて国、県と協議していくことになろうかと思います。
吉田
本当に何が起こるのかわからない状況の中で、それを予測していくのは非常に難しい作業であると思います。ただ、先ほどから申し上げているように地下に避難できる空間がないと。一番安全なのはやはり地下だと思うのです。もちろんその整備は今すぐできることではありませんが、NPO法人日本核シェルター協会が調べた核シェルターの普及率を見ると、日本は0.02%で、世界的に見ても非常に低い普及率です。ほとんどないと言える状況です。地下空間が全て核シェルターになるとは言えませんが、これからいろいろなことに備えていかなければなりませんので、そういうものの普及ももう少し啓発していかなければならないことだと思います。
行政としても、もちろん今すぐにということではありませんが、今後、将来的にこの庁舎を例えば何十年後かに建てかえるとか、いろいろな機会があると思いますが、地下の空間を確保していこうという対策をするお考えはないでしょうか。
市長
いずれ国レベルでの対応になろうかと思います。例えば核シェルターについても、国で推進していくという方針が示され、その財源についてもしっかりと示されて、その中で市としても考えていくことはあろうかと思いますが、現時点で市が先行して進めていくという状況にはないと考えております。
吉田
地下室といっても核シェルターとは限らず、例えば地下を駐車場にしている施設などは幾らでもありますので、地下を設けていくことは、これから新しい建物を設置していく上で、一つ、検討の過程の中に入れていくべきではないかと考えます。
次に移らせていただきます。
消防の装備と体制の強化について、こちらも非常に難しい課題ではありますがあえて申し上げますと、市民の生命を守るために最前線で職務に当たっているのが消防の職員の方々です。火災や救急救助という日々の御活躍はもちろんですが、日々訓練にいそしまれていることに心より敬意と感謝を申し上げます。
弾道ミサイルなどの脅威が高まるにつれ、自衛隊だけで国民の生命を守り切ることがますます厳しくなってきていると感じます。いざ危機が現実となった際、市民が真っ先に頼りにするのは、やはり近い存在である消防ではないかと思います。消防組織法によると、消防の任務は「国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うこと」とされております。
ここに災害とあるのは、自然現象はもちろんですが、人為的な原因によるものも含まれると捉えられます。平成7年に起きた地下鉄サリン事件では、東京消防庁が多数の部隊を出動させて救命救助に当たりました。しかし、原因物質不明のまま初動の活動を行い、結果として職員に被害が出るなど数々の課題を残しました。このため、東京消防庁は化学テロも踏まえた装備や資機材、教育訓練、活動体制等の強化を図るとともに、その後も茨城県での臨界事故や米国での同時多発テロ等を踏まえてさまざまな対策を講じているとのことです。
東京都のような大都市であればともかく、本市のような規模では、消防に大規模破壊兵器などに対するものを求めるのは非常に難しいことは存じています。しかし、例えばクアラルンプール国際空港でのVXガスによる暗殺事件とか、あるいは北朝鮮が大量の化学兵器を保有しているという事実を鑑みても、大量破壊兵器等を用いたテロが国内で発生する危険性は短期間で飛躍的に高まっていると考えるべきだと思います。
そこで、小項目4 化学防護服などの装備を充実させ、生物化学兵器による攻撃に即応できる体制を整備すべきについて消防長にお伺いいたします。
消防長
他国によるミサイル発射等により市内に災害が発生した場合、名取市消防計画及び名取市消防本部NBC災害活動計画に基づき、弾頭の種類が判明するまでは、危険度の高い最高レベルの装備で災害活動を実施したいと思います。なお、関係機関と連絡調整を図りながら、災害活動を実施いたします。
吉田
最高の装備と今答弁されましたが、そのあたりを具体的に、わかる範囲でお示しいただければと思います。
消防署長
化学防護服の中には、毒性が強く原因物質がわからない場合の装備として陽圧式化学防護服というものがあります。これは内部の空気が一定になっていて、外部から侵入できないようになっており、その最高のレベルで毒性やガスをはかって危険かどうかを確認しながら活動できる防護服です。2番目には、危険な地域からすぐ近くで活動する場合のB防護服というものがあり、汚染されていないところはC防護服ということで、3つの防護服を名取市消防本部では所有しております。
吉田
3つの種類の防護服を使って救助活動に当たる訓練も日々行っているかと思いますが、例えば生物化学兵器のみならず、今回、北朝鮮の弾道ミサイルの燃料が固体化されたと報道されていますが、液体の燃料を使用した際にはかなりの毒性を持っているとも言われています。このようなことについて対応できる装備であると考えてよろしいのでしょうか。
消防署長
そのような弾頭が着弾した場合にあっては、あらゆる防護服を着て、住民の避難誘導に当たるしかないと思います。
吉田
承知しました。
では、次に、小中学校の対応について、さらに詳しくお伺いしていきたいと思います。
8月29日のミサイル発射は午前5時58分ごろのことであり、午前6時14分ごろに太平洋上に落下したと推定されます。市内小中学校は非常変災その他窮迫の事情としての対応はとらず、全校で通常の授業を行ったと御答弁いただきました。もしミサイルの発射時刻があと一、二時間おくれていたとしたら、登校させるべきか、臨時休校とすべきか、判断に苦しむことになったのではないかと思います。Jアラートだけでは、ミサイルが飛行する方角や距離、弾頭に何を積んでいるかを正確に知ることはできません。ミサイルが市内の通学路に落ちることで児童生徒が被害を受ける確率は、交通事故に遭う確率よりもずっと低いかもしれませんが、子供たちの絶対の安全確保のためであれば、学校を休業するという選択肢を責める市民はいないと考えます。
ただ、もし臨時休校にするとしても、Jアラートで伝達される時刻がちょうど登校時刻に重なっていれば、全家庭に休校を知らせることは困難になると思います。ミサイル発射を受けて臨時休校とするのであれば、保護者や児童生徒本人がはっきり判断できる基準をあらかじめ示しておく必要があろうかと思います。
そこで、小項目5 小中学校を臨時休校とする基準を設けるべきについて、教育長にお伺いいたします。
教育長
臨時休業については、学校教育法施行規則や名取市立学校の管理に関する規則の中に、「非常変災その他窮迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる」と定められております。今回のミサイル発射の対応につきましては、臨時休業の措置をとった学校はありませんでした。 ミサイル発射等により臨時休業とする際の基準については、さまざまな状況に応じた対応が必要となることから、一定の基準を設けるのは難しいと考えております。教育委員会としては、学校、校長と連絡をとり合いながら、状況に応じた対応を行っていきたいと考えております。
吉田
ということは、ミサイル発射の報道が流れている、サイレンも鳴っている、そしてエリアメールも鳴った、テレビでも緊急の放送が流れているという状況がまさに通学中に起きたとしても、教育委員会や学校としては、そのときにならないと対応することができないと、そのように捉えてよろしいでしょうか。
教育長
今回のミサイル発射の事態を受けて、教育委員会では、校長会とも協議をして、先週、それぞれの学校長を通して各学校の保護者にお知らせを出しています。Jアラートが作動する時間帯によって、その対応はさまざまなケースを考えていかなければならないと感じておりますが、今回、大きく4つのケースについて校長会と協議をしました。
1つは、先日のように登校時間前にJアラートあるいはミサイル発射の情報が流れた場合。その場合は、原則として情報は各家庭において入手し、登校はさせずに自宅待機にしていただくと。これについては、そのお知らせの文書の中で、そのように保護者にお願いをしております。問題は自宅待機から通常登校にしてよいという判断ですが、それについては、教育委員会で名取市あるいは国の情報等を十分に検討した上で、8月29日のように差し迫った危険がないと判断した場合、教育委員会から各学校宛てに通常登校というお知らせをするというのが1つのパターンです。
それから、朝夕の登下校の途中に作動した場合については、学年の発達段階によって理解度は違いますが、まず防災行政無線の放送をよく聞くこと。そして、自分のいる場所によって、学校に戻る、自宅に戻る、あるいは近くに身を隠すところがあれば身を隠すなど、そういう臨機応変な対応がとれるように子供たちに指導するというのが2つ目のパターンです。
3つ目のパターンとしては、子供たちが学校にいる時間帯に作動した場合は、当然、学校の中で比較的安全な場所に児童生徒を移動させることになりますが、一定の安全が確認できるまでは学校にとめ置くことになろうと思います。安全が確認された以降、通常下校させる、場合によっては保護者に引き渡しをする。
4つ目として、休日や夜間の時間帯であれば基本的には各家庭の判断で対応していただくと。被害状況によって、翌日何らかの措置をとることもあるかもしれませんけれども、ただ、今申し上げた4つのパターンではないケースもさまざま想定されますので、やはりその都度、情報をきちんと収集して検討した上で判断していくしかないかなと考えております。
吉田
さまざまなケースがあり、その中で判断していかなければならないと。今の教育長の答弁では、大きく4つのケースで捉えているということでした。それをこれから周知して、もう周知はされていると思いますが、いざというときのために保護者や児童生徒自身がいつでも対応できるようにしておかなければならないわけです。そういった訓練についてはまた後ほどお聞きしたいと思いますが、今の教育長の答弁の中に、一旦児童生徒を自宅待機させた後、学校に登校させるかどうかの判断をするとありましたが、私は今回のケースでここが一番問題ではないかと思っています。それについて質問を進めさせていただきたいと思います。警戒の解除についてです。
8月29日、エリアメールや国民保護サイレンなどで、ミサイル発射に関する警報が市民に知らされました。その後どのように推移したのかを振り返りますと、危機的な状況が過ぎたことを知らせる公的な知らせが一つもなかったのが現状ではないかと思います。安全を確認する知らせがなかったために、いつまで避難、警戒を続ければよいのか、この部分で戸惑った市民がいたかもしれないと考えます。
国民保護法の第44条から第47条に、武力攻撃から国民の生命、身体または財産を保護するための緊急の必要があると認めるとき、内閣総理大臣である対策本部長から都道府県知事、都道府県知事から市町村長、そして市町村長から住民に、警報の通知、伝達が行われるということが規定されています。特に第47条では、市町村長は、通知を受けたときはその国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちにその内容を住民などに通知、伝達しなければならないとあります。また、第51条では、警報の必要がなくなったと認めるときの通知、伝達について、今申し上げたような手順で行うことが定められています。
そこで、名取市国民保護計画における通知の解除の項目を見ますと、警報の解除の伝達については、原則として警報の発令の場合と同様の方法で周知を図ると書かれています。発令の場合と同様の方法ということであれば、今回は防災行政無線を通じて知らせるのが原則だったはずです。しかし、実際は警報の解除の伝達はありませんでした。このように原則のとおりに進まないことも想定しておかなければならないと思います。
そういうことも含めて、小項目6 安全宣言の時期と発表の方法を検討すべきについて、市長にお伺いいたします。
市長
他国によるミサイル発射等に係る安全宣言については、市として判断できるものではなく、国が行うものと考えております。国が発表した場合の広報については、ホームページ、ツイッター、なとり防災メール、エフエムなとりなど、多くの媒体を活用して周知を図っていきたいと考えております。
今回のミサイルの発射については2発目、3発目があるのかということもあり、相手の意思があるものですから、国としても判断がなかなか難しかったのではないかと捉えているところです。
吉田
経緯をもう一度確認させていただきますと、まず、国からの解除の通知が県になかった、そして県からも市に対してなかったと。大もとの原因は国にあると捉えてよろしいのでしょうか。
市長
答弁申し上げたとおり、判断については国がしていくものと考えております。
防災安全課長
国から安全宣言の時期、収束の時期という知らせはありませんでしたが、県からは、時間が経過したところをもって、ここで警戒態勢を終えるという情報提供がありました。市としては、日本上空を通過して落下した模様ということを受けて、市のホームページに、被害はないと捉えていますが何かあったら情報提供をお願いしますということで掲載したところです。
吉田
名取市国民保護計画では、原則として警報の発令の場合と同様の方法で周知を図るとなっています。ただ、警報については、ホームページでミサイルが発射されたというお知らせは恐らくなかったと思います。逆に防災行政無線でお知らせがあったと。ですから、その部分で警報の発令と解除についての方法が食い違っているわけですが、そのあたりについては今回は仕方がなかったという認識でよろしいのでしょうか。
防災安全課長
警報の発令については、Jアラートによって信号を受信し、防災行政無線の屋外拡声子局から配信するという自動的な手続の中でアナウンスをしております。一方、2発目、3発目云々ということもあり、国や県から収束の情報提供がない段階では、なかなか市の判断だけではできないと。
一方、防災行政無線の屋外拡声子局でのアナウンスについては、名取市国民保護計画の中では警報の発令と同じ方法ということで解除の伝達について記載しているところですが、やみくもにはできませんので、そちらは今後検討していかなければならないと捉えています。
吉田
防災行政無線で解除されるという放送が流れても、それがまた次の混乱に結びついてしまってもいけませんので、そのあたりの周知の仕方はこれから慎重に検討していかなければならない部分であると思います。例えば、なとり防災メールのようなものであれば登録している方には確実に伝わっていきますので、今、Jアラートと連動して自動的にというシステムのようですが、今後、国や県から警戒解除の通知が来たときにこういうものに手動でお知らせすることをつけ加えていくというお考えについてはいかがでしょうか。
防災安全課長
なとり防災メールについては手動で配信することも可能ですので、情報を読み取ってそれを配信することは現段階においても可能だと認識しているところです。
吉田
では、今後検討されることを期待しております。
今、いろいろな問題点を指摘させていただいた中で、このような想定を超える事態が今後また続いていくことが考えられます。あらゆる事態に対し、行政もそうですが、もちろん市民一人一人も自分の力で自分の身を守っていかなければならない。第一にはそこから始まっていくと思いますが、そのための政府からの避難の方法などもいろいろと示される中で、それだけでは今後、行政と市民の立場や市民同士の助け合いなど、いろいろな課題がまた出てくると思います。これは通常の支援災害とはまた違った観点になってくるのではないかと思うところです。
そこで、次に、国民保護の訓練について移らせていただきたいと思います。
国民保護サイレンがなかなか周知されていないことや、避難の呼びかけに対し適切な行動をとることになれていないなどによって、不測の事態が起きた際に多くの市民が犠牲になるおそれがあります。身を守るための知識を持っていたとしても、いざ行動するとなると迷いが生じるものです。そこで、適切な頻度で訓練を実施し、とっさのときに全ての市民がより適切な行動をとれるように備えておかなければならないと思います。
名取市国民保護計画には、「市は、近隣市町村、県、国等関係機関と共同するなどして、国民保護措置についての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る」と書かれています。しかし、現実問題として、他自治体等との共同訓練は規模が非常に大きくなるため、予算や団体間の調整など、さまざまな課題があります。そこで、当計画に、留意事項として「国民保護措置と防災上の措置との間で相互に応用が可能な項目については、国民保護措置についての訓練と防災訓練とを有機的に連携させる」とあります。そこで、市の総合防災訓練にメニューを加えるなどの方法を検討するのも一つの手ではないかと考えています。
小項目7 総合防災訓練や小中学校における避難訓練に、ミサイル発射等を想定した訓練を追加すべきについて、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
ミサイル発射等における避難と自然災害時における避難では、とるべき行動が異なります。また、市、市消防本部、警察、自衛隊等、公助の活動内容についても、ミサイル発射時と自然災害時では大きく異なるものがございます。このことから、総合防災訓練においてミサイル発射等を想定した訓練を追加することは非常に難しいものと捉えております。
防災訓練時とは別の、単独でのミサイル発射等の避難訓練については、今後、国、県と協力して行う機会などを捉え、実施できるよう検討していきたいと考えております。
なお、小中学校では、他の避難訓練等にあわせ、ミサイル発射等を想定した訓練を行っている学校もあると伺っております。
教育長
ミサイル発射等に対する避難行動については、平成29年4月に県教育委員会から通知があり、それを各学校に周知し、学校の実情に合わせた対応について指示しております。
ミサイル発射等の避難行動の場合、通常行われている避難訓練の行動とは逆の屋外から屋内への避難となります。この避難行動については、現在まで全ての小中学校で全校あるいは学年、学級ごとに指導しており、避難訓練を実施している学校や予定している学校もあります。今後もミサイル発射等を含めたさまざまな非常事態に応じた指導や訓練を行い、災害や危機に備えたいと考えております。
吉田
まず、市長にお聞きしますが、私もそのように思います。通常の自然災害とは全く違うというのはおっしゃるとおりですが、ただ、今おっしゃったように国や県と一緒に訓練を実施できるタイミングをこれから図っていくとなると、かなり時間がかかってしまうと思います。そうやって時間を無為に過ごすのか、それとも、次の総合防災訓練で例えば防災行政無線から国民保護サイレンを鳴らすだけとか、そういうちょっとしたことでも、国民保護とはこういうことなのだということを知らせていけるいい機会になるのではないかと思います。そういうタイミングでも図らない限り、こういうことを周知していくのは難しいかと思いますが、そのあたりについて、もう少しお考えをお聞きしたいと思います。
それから、教育長にお伺いします。屋外から屋内へという方針は、もちろんそのとおりだと思います。学校内での避難訓練として、そういう形でこれから行われていくこともあろうかと思いますが、先ほどの4つのケースの中で、やはり登校途中、あるいは今は塾や習い事に行く子供も多いので、そのように学校外にいる場合についても、自分の身の守り方を教育の中である程度教えていく、訓練しておく必要があると思います。その際、一つの方法として、児童生徒の通学路のルートとか、あるいは何時にどこの塾に行くとか、日々のスケジュールは児童生徒個々人で別々ですから、それぞれ自分のスケジュールに合わせて、こういう場合はこういう避難をするということを想定させて、授業の中で自分の避難行動マニュアルというか避難計画をつくらせるということも考えられると思います。そのような教育の必要性についていかがお考えかお伺いいたします。
市長
ミサイル発射等に対する訓練ということで言えば、やはり国、県との広域的な訓練が前提になると思います。市単独で行ってどれだけの効果があるかということもありますので、基本的には国、県と連携しながら訓練に当たりたいと思っています。現状については非常に憂慮しておりますので、できるだけ早い機会を捉えて行っていきたいと考えております。
教育長
学校において、子供たちの生命と安全を守っていくという観点から想定しなければならない災害等は本当に各種あります。火災、地震、津波、土砂災害、洪水、それから不審者の問題、交通事故の問題、そして今話題となっているミサイル発射の問題、そういったさまざまな問題がある中で、子供たちに全ての場合を想定した避難訓練を詳細に実施することは、現実的には非常に難しい問題もあろうかと思います。
先ほど申し上げた屋外から屋内に避難することについてですが、今回のような場合だけでなく、校地内に不審者が侵入した場合についても、各学校では校庭にいる子供を屋内に入れます。ただ、校舎内に不審者が侵入した場合は、また別の対応になります。そういったさまざまな場合を想定して行っておりますので、今回のようにミサイルが発射された場合の訓練についても、ミサイル発射に特化した避難訓練ではなく、ほかの避難訓練等とあわせて、こういう場合もあるということを各学校では指導しているのが現状です。
9月8日付で文部科学省から、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に係る対応について」という通知が来ています。内容については今まで答弁申し上げたような内容ですが、留意事項として、保護者、児童生徒を必要以上に不安にさせることがないよう十分配慮するということも述べられています。もちろんいろいろなケースを想定して子供たちに自分の命を守る、安全を守るということについて指導することは必要だと思いますが、今回のミサイル発射を受けて、それに特化した訓練等を殊さらに実施することは、各学校での対応としては現実的に難しいと考えております。
それから、後段で議員から御提案のあった通学路での対応ですが、東日本大震災後の津波で本市でも多くのとうとい命が失われました。その後、登下校時に地震が起きたらどうするかということについて、各学校でも、どの場所にいたらどうするかということを子供たちと話し合ったり、指導をしたりしています。
ただ、Jアラートが作動したらどうするか、先ほど申し上げたように放送をよく聞いて、どう行動するか、学校に戻る、自宅に戻る、近くに身を隠す、そういったことについての指導は行っていますが、ミサイル発射に特化した登下校中の訓練を実施することは、現時点では考えておりません。
吉田
訓練というよりは、いざとなったときに動けるようにいつでもシミュレーションしておくことも訓練の一つかと思います。必要以上に恐怖をあおらないようにするというのは確かにそのとおりかと思いますが、必要以上の必要をどこのラインとするのか、これも考え方かと思います。実際にこういう問題が起きて、何が起きるかわからないという状況の中で、警戒をして、し過ぎだということはないと思います。そのあたりは恐らく同じお考えではないかと思いますが、学校もそうですし、行政、市でも、市長がおっしゃったように国、県と連携した広域の対策ももちろんそうですが、そうした中でも、機会を待たずに、少しでも何か周知できる部分があればしていくことが必要だと思います。今回の教訓は、まさにここから出てきた課題を一つの踏み台にしてよりよい体制をつくっていくことにつながっていくと思いますので、そういう作業の検討をぜひとも進めていただくようお願いいたします。
大項目1の最後になりますが、名取市国民保護計画の見直しについてお伺いいたします。
平成19年4月に作成された名取市国民保護計画には、市国民保護計画については、国における研究成果や新たなシステムの構築、県国民保護計画の見直しなどを踏まえ、不断の見直しを行う旨が示されています。作成されてから10年以上が経過し、県はこれまでに平成22年、平成26年、平成28年と合計3回、見直しを行っていますが、本市は一度も行っていません。煩雑な手続を必要とするものならともかく、軽微な変更については市国民保護協議会への諮問と知事への協議は省略できるものとされており、市議会への報告と公表だけで手続が完了します。まずは今後の見直しの意思を確認させていただきたいと思います。
小項目8 新たな脅威に備えるため、宮城県国民保護計画の見直しなどを踏まえ、名取市国民保護計画を改定すべきについて、市長にお伺いいたします。
市長
名取市国民保護計画については、平成19年4月に策定され、その後、改定されることなく現在に至っております。武力攻撃事態等の危険性が高まっていることもあり、名取市国民保護計画の改定について、市として早急に検討していきたいと考えております。
吉田
10年たっていますから早急に進めていただきたいと思いますが、具体的にどのあたりを見直すか、現時点でのお考えをお聞きしたいと思います。
市長
平成19年のときとは、もちろん道路事情も違いますし、仙台空港アクセス線もまだ供用開始直後だったということもあります。また、実際にミサイルが発射されたという緊迫感も全く違います。
具体的には初動体制の見直しが必要ではないかということで見直しの指示をしているところですが、今考えている具体の内容については担当より答弁をいたさせます。
防災安全課長
計画の中で、前段の市の概況等を取りまとめたところから、人口規模なり招集体制なり、るる入っていくところです。先ほど申し上げた収束、安全宣言の部分も関連があるので、全体的に見直しをしたいと思っています。
吉田
宮城県国民保護計画の見直しなどを踏まえてとなっていますが、例えば宮城県国民保護計画にも、ほかの都道府県と比べたときに少し足りないと思われる部分があるのではないかと思います。私は、実際に見て、具体的には申しませんがそのように感じた部分がありましたが、宮城県国民保護計画をさらに超えるような部分は検討されないことになりますか。
防災安全課長
基本的に県の国民保護計画の中で考えていくものですが、不足している部分があるのであれば、その部分を組み入れることが可能かどうか、それらも県の担当に確認しながら進めていきたいと思います。
吉田
県に確認したところ、宮城県内の市町村で国民保護計画を平成19年以降一回でも改定した自治体は、現時点では恐らく3自治体しかないのではないかということでした。こういう事態になって、ようやく見直しということに気持ちが向いていくのかなと思います。恐らく県も問題点を踏まえてさらに見直ししていく部分があると思いますし、県外のほかの自治体でもいろいろな先行する事例がありますので、ぜひともそのあたりも検討していただき、より安心できる国民保護計画にしていただきたいとお願いいたします。
続きまして、大項目2 ポケットギャラリーの使用許可についてお伺いいたします。
ポケットギャラリーは本市庁舎1階にあり、市内に住所を有するか勤務している個人、またはその個人を含む団体などが、市長の許可を得て、連続5日間まで無料で使用できる部屋のことです。ポケットギャラリー使用許可基準は平成19年9月5日に施行され、現在に至っています。本日も、閖上が復興していく様子を描いた油彩画の個展が開かれています。小さなスペースではありますが、市民に利用されることにより、文化振興や市民同士の交流などが促進されることが期待されています。 このポケットギャラリーにて先月上旬に行われた催しにおいて、政治的主張と解釈できる内容が含まれる文書が掲示されていました。催しの終了後、私は、所管課に現場の写真を提出し、事実関係を確認するように申し入れを行っています。このことについてお伺いいたします。
小項目1 8月上旬に行われた催しで、会場内に「政府は核兵器禁止条約締結促進を」「安倍総理は条約を否定」との旨が書かれた文書が掲示されていたが、このことについて事実確認の現状と御見解を市長にお伺いいたします。
市長
議員御指摘の催しは、8月7日から9日まで市役所1階のポケットギャラリーで行われた原爆写真展のことと思われます。
ポケットギャラリーの使用については、その使用状況が使用許可基準に沿ったものになっているかの確認をしなければならないところではありますが、これまでは使用者の裁量に任せていたところもあり、全ての使用状況を確認してはおりませんでした。
今回の催しについても、実際の使用の状況を直接確認はしておりませんので、現場でどのような文言がどのように掲示されていたのかを把握していないことから、議員御質問の見解を述べることはできない状況にありますので、御理解いただきたいと思います。
吉田
あらかじめそのことについて申し入れていたのですが、例えば主催者側に、私が言ったことは本当かどうかという事実確認もされていないということでよろしいのでしょうか。
財政課長
ただいま議員から御指摘のあった申し入れの後に、使用者の方に事実関係の確認は特に行っておりません。ただその文言、記事等が一部に掲示されていたということだけをもって、議員御指摘のような政治的主張とまで捉えられるかどうかは非常に難しいところがあります。ポケットギャラリーの使用許可基準では、政党や政治団体の使用については許可しないという文言はありますが、単純に記事が書かれていた、張られていたということだけをもって政治的主張、政治的活動と判断するわけにはいかないと考えております。そういった行為に該当するかしないかについては、実質的にどういう目的でどういった内容がどのように掲示されているのか、そういったことを全て総合的に判断して政治的主張と捉えるべきと考えているところです。
吉田
市民の方に多く利用していただくためには、なるべく制限をかけ過ぎないとか、余りチェックを厳しくし過ぎないとか、そういう方向性ももちろん理解できます。私が今回この件を申し上げているのは、そこに書かれていることについて賛成とか反対とか、そういう立場からではなく、こういうものは、見る方によっては、一方的ではないか、市の庁舎で行うことが果たして許容されるのかと。それに、もっと多面的に見ることができるのではないかとか、そういう方法であればまた一緒に考えようという意味で意義があることかと思いますが、少なくとも私が調査したところでは、写真も全部持っているので見せることもできますが、この文書については某政党の機関紙だったことが明らかになっています。それを調べていく過程でほかにもさまざまな全国紙などを調べたら、同じ件に関して、例えば朝日新聞は「核兵器禁止「橋渡し」を 広島市長、政府に訴え」、読売新聞は「広島原爆忌 核廃絶訴え 平和宣言橋渡し政府に求める」というように橋渡しを求めると。あるいは産経新聞だと「被爆72年広島、原爆の日 首相「核兵器なき世界主導」」と。やはり同じ一つの事象についても見方によってさまざまな捉え方ができるわけです。申すまでもありません。
しかし、市の庁舎を無料で貸し出すという中で、その中の一つだけの意見がぽんと出るということは、もしかすると、今度は逆の側から別の主張を持っている方々が市の庁舎を同じように使わせてほしいと。極端な何かそういう考えかもしれません、あえてどうとは言いませんが、そういう方に対しても皆お貸ししなければならないと。一つ認めれば、そのようにどこまでも広がっていく可能性があるのです。そのあたりの線引きについて、行政側ではどのように考えていらっしゃるのでしょうか。
財政課長
先ほどの答弁の繰り返しになるところはあろうかと思いますが、単にその記事を掲示しただけで、どこか特定の思想なり宗教なりを助長しているとか促進しているとかということにはならないかと思っております。使用される方の思想、信条の部分もありますので、特に市が、ここからここはよい、ここからここはだめと単純に判断するような基準をつくるのは難しいと考えております。全体の中で、どういう目的でどの程度のものがあったのか、社会通念にのっとって客観的に判断すべきものと考えているところです。
吉田
まず、今回はその判断をすべき現場の確認も行われていないわけですから、判断のしようがないわけです。また、どのような政治思想を持とうと、それは思想、良心の自由が保障されていますから自由なのです。しかし、市民全員の財産である市の庁舎が特定の主張を宣伝するために使われていると思われてしまっていのかどうかと。あれもこれも制限しろと言っているのではありません。ほとんどの場合は、きょうの油彩画展にしても、あるいは生け花にしても、文化的なものであると思います。ただ、そういう中で、政治的なメッセージが含まれることが想定される場合については、ある程度確認をすべきではないかと思います。
そこで、小項目2 特定の思想や組織の宣伝となっていないか、展示内容の確認を徹底すべきについて、市長にお伺いいたします。
市長
現在、ポケットギャラリーは、絵画やポスター、写真の展示など、文化活動や各種推進運動などに伴い使用されている状況にあります。絵画やポスター、写真には少なからずテーマに関する思想が含まれているものと考えられますし、各種推進運動などに伴うものとしては、むしろ組織の宣伝を目的としたものもあります。したがって、そういったものまで一概に否定されるものではないものと捉えております。
しかしながら、庁舎内の秩序の維持または災害の防止のためにその使用を制限しなければならないこともあると考えられることから、今後については使用基準に沿った使用状況になっているかどうかについても、できる範囲で確認していきたいと考えております。
吉田
使用基準に沿った形になっているかどうかをいずれかのレベルで判断しなければならないわけです。ほとんどの場合は大丈夫ですということになると思いますが、ちょっとこれはいかがなものかというケースも必ず出てくるかと思います。そのような際の判断をしていくための、もっと細部にわたった捉え方を市がある程度準備をしておかなければ、先ほど申し上げたように、例えばもっと過激な思想の団体が、これは宣伝ではないとか、これは事実なのだとか、いろいろな理由をつけて展示することができるわけです。例えば写真にもそういうものを一部つけ加えて、自分たちはそういう思想ではないと言って宣伝することも、やり方によってはできることになります。非常に線引きが難しい中で、それを最終的に責任を持って行政は、これはちょっとまずいのではないか、これはいいと決めていかなければなりません。そういう責任を負っているわけです。そのあたりについて、市長として、これまでできるだけ市民に広く開放してきたということも維持しつつ、もう少し今までよりも確認のレベルを高くしていくべきではないかと思いますが、お考えを伺いたいと思います。
市長
先ほど担当からも答弁いたさせましたが、使用許可基準の中に政党または政治団体の使用は認めないという文言があります。ただ、今回の件については、大々的に全面的に特定の政党なり政治団体なりを宣伝しているのではなく、原爆の悲惨さを通じて世界の恒久平和を願うという趣旨で開催されたものと捉えており、その中の一部に、ちょっと確認はできていませんが、問題となる部分があったというだけをもって、例えば中止にしたり、以後貸さないという措置までとれるかというと、それは少し違うのではないかと思います。基本的には市民の方に広く利用していただきたいと考えております。
また、その確認についても、検閲をするというような考え方ではなく、庁舎内で行われる市民の方の活動について、こちらでも拝見させていただきながら、基準に沿った使われ方がされているかどうかという確認をできる限りしていきたいということです。
吉田
何も私は検閲を推進しているわけではありません。思想・信条の自由は誰にでも認められています。先ほどから申し上げています。ただ、それは例えば自分たちの活動資金などで行っていくことであって、市民全体の持ち物を使ってそのようなことが行われるということについて、果たしてどうなのかと申し上げているわけです。
この使用許可基準は平成19年に作成されたもので、10年間そのまま継続しているものです。一般の市民の表現活動をこれからも推進していく、どんどん進めていただく、それと同時に公平性を確保していくためには、今の使用基準では少しわかりづらいと思います。行政側の裁量に任される部分が非常に大きいと思うのです。例えば、政党はわかります、政治団体にも制限をかけるというのもわかりますが、その政治団体というのはどこまでを言うのかと。選挙管理委員会に申請されているものだけが政治団体なのか、あるいはそれよりもっと広い意味での政治団体があるのか、そういう部分についても曖昧なままです。そればかりではありませんが、こういった面も含めて、やはり今後改定を検討すべきかと思います。
小項目3 使用許可基準第5条(使用許可の制限)に政治や宗教の宣伝活動を追加し、違反した個人や団体に対して以後の使用を認めないなど罰則を設けるべきについて、市長にお伺いいたします。
市長
現行の使用の制限に関する規定の仕方については、本市においては一般的な規定の仕方であると考えておりますが、他の自治体では宗教活動等を制限している団体もありますことから、今後、実態を見きわめながら十分研究していきたいと考えております。
また、違反した個人や団体に対してのペナルティーについては、以後使用を認めないというペナルティーを検討する以前に、使用する方々へ、ポケットギャラリーの使用に当たってのルールを十分に御理解いただいて、そういった状況にならないように周知徹底を図っていきたいと考えております。
吉田
他市の議員とこの件について話したときに、その市ではこれはあり得ないことだと言われました。やはり政治にかかわっているからと。もちろんそういう線引きは自治体ごとに決めていくことだろうと思いますが、10年たって今の使用許可基準が見直しの時期に来ていることは市長も認識されているということですので、どうかこれについてはおっしゃったとおり進めていただいて、みんなが納得できる、そしてみんなで安心して使っていけるようにしていただきたいと思います。啓蒙活動にしても、市長からも原爆展というお話がありましたが、やはり原爆の恐ろしさ、悲惨さはしっかり次の世代に引き継いでいかなければならない、そういう気持ちについては全く同じです。そういう純粋な気持ちをそのような場で提示していただいて、その一方で公平性が疑われるようなことにならないように、そういう点について誰が見ても一目瞭然の判断基準を目指して、今後使用基準の改定を進めていただきたいと思います。
これをもって私の一般質問を終わらせていただきます。
本会議
(議案第92号 平成29年度名取市一般会計補正予算)
吉田
9ページの16款2項2目土地建物売払収入1節土地建物売払収入について、具体的な場所をお伺いいたします。
財政課長
今回の土地建物売払収入は名取駅前の市街地再開発に伴う代替地6区画分の売却収入です。
吉田
6区画の具体的な場所と金額の算定方法をできる限り詳しく御説明願います。
財政課長
6区画については、事業区域の東側、増田四丁目の5区画と旧増田公民館駐車場のところの1区画です。面積は、事業区域の東側5区画がトータルで1,263.65平方メートル、旧増田公民館駐車場が264.47平方メートルです。売却価格については、事業区域の東側5区画分で合計7,591万1,000円、旧増田公民館駐車場で1,904万1,840円です。
吉田
11ページ、18款2項7目1節ふるさと寄附基金繰入金について伺います。ふるさと寄附は6項目の寄附金の使い方の中から選択する形で今進められていると思うのですが、今回はどの項目に幾らなのか、繰入金の内訳をお伺いします。
財政課長
今回のふるさと寄附基金繰入金は、平成28年度で使用したふるさと寄附金特産品取扱事業の特産品代と送料、そして、観光物産協会への委託に係る委託費について、平成28年度においては一般財源で立てかえていたこともあり、平成28年度分の確定に伴って基金から繰り入れたもので、議員御質疑の目的に関しては特に想定していません。
吉田
ということは、用途が選択されて寄附されているわけですが、その部分については手をつけていないという解釈でよろしいのでしょうか。
財政課長
今回繰り入れているのは経費というか事務費の分で、強いて6つの項目のどこから充てているかと申しますと、「元気な都市(まち)づくり【市長にお任せ】」の項目から充てていると考えられるかと思います。
吉田
20、21ページの8款1項3目公共物管理費19節負担金補助及び交付金の私道等整備補助金についてお伺いします。当初予算で200万円が計上されたと思いますが、私道に関してはやはり多くの方からいろいろと整備の要望が上がっていると思います。今回追加された中で要望に対して適用されるのは何件分の補助になるのでしょうか。
土木課長
今回の補正ですが、補助金交付要綱の要件の緩和を行い、また、交通安全施設の設置を補助対象に追加したため、当初予算額では不足することから補助金の増額補正を計上しました。その内訳は、現在、申請予定件数は4件で、そのうち、舗装要件の緩和で1件、新たに補助対象になった交通安全施設の照明灯関係が2件、合計3件が今回の改正により追加されました。
吉田
要望している方からするとこのような形で補助がおりることはありがたいのかと思いますが、そもそもこの金額が小さいのではないかと思います。当初予算の200万円プラス今回73万2,000円ですが、金額について今後拡大していく必要性は感じていないのでしょうか。
土木課長
毎年200万円ずつ予算計上していますが、過去5年間で申請なしが2回、それから1件が2回で、それは舗装で約100万円ぐらいでした。今回改正したのは、申請がなかったり、あっても申請額が少ないということで、より多くの方に使っていただきたいということで利便性向上を図ったものです。舗装に関しては、当初予算200万円というのは、1件当たり100万円で、通常年2件分と考えています。ですから、今後改正によりふえると思われますが、その時々に合わせて補正等で対応していきたいと考えております。
吉田
22、23ページです。8款7項3目復興まちづくり事業費で13節委託料と15節工事請負費にある名取駅東口歩道橋整備工事についてお伺いします。資料を見ますと、まず橋脚を全部で4本設置して、その橋脚の上に歩道となる部分を載せるのかと思いますが、橋脚の場所を見ると、一番名取駅舎側とその次の橋脚が現状のアーケード、雨よけの屋根のかかっている部分に重なっていると思うのですが、現在のアーケードは設置したままで、そこに穴をあけるような形で橋脚を設置するのか、詳しい施工方法を説明願います。
増田復興再開発推進室長
歩道橋の工事で一番駅舎側と橋脚についてですが、ここには現在アーケードということで歩廊が設置されていて、橋にぶつかる部分は撤去となります。
吉田
ということは、歩道橋の下側にあるアーケードの部分は撤去するという考え方ですね。名取駅から南側におりてくるほうもバス停に現在アーケードがかかっていますが、それも撤去し、そこに橋脚を打ってその上を通すということで、その撤去費についても含まれていると思います。また、P3の橋脚は視覚障がい者のための点字ブロックにもかかっていると思うのですが、これらも全部含めた上での今回の工事の予算という考え方でよろしいのでしょうか。
増田復興再開発推進室長
平成29年度9月補正で計上している予算は橋脚の設置分となります。まず今年度において橋脚を敷設した後、一時的に舗装の撤去等もあります。そして、平成30年度に視覚障害者用誘導用ブロック等の復旧を行いたいと考えております。
吉田
今回の予算は橋脚のみでそれ以外は新年度でと聞いて少し驚いたのですが、幾らぐらいさらに必要になるのか。図面を見ただけではわかりませんが、橋脚を認めればその上の部分も認めなければならなくなると思いますので、全体の工事費の現在の見込みをお聞きしたいと思います。
増田復興再開発推進室長
全体の歩道橋の整備費は、現在のところ、上部工と下部工を合わせて2億8,000万円と見込んでおります。
吉田
22、23ページの8款7項3目復興まちづくり事業費13節及び15節の名取駅東口歩道橋整備工事についてですが、工事費が合計で2億8,000万円と先ほど御答弁があり、非常に大きな額だと感じました。これを設置しなければならない理由が果たしてそれほど大きなものかどうか、もう一度考えてみたいと思うのです。例えば仙台駅のような車が多く人通りも多いところでしたら、1階は車、2階は人と分けなければ事故が起きやすくなってしまいます。ただ、名取駅の場合はさほど車の通行も人通りもなく、交差点も少なく、必ずこれを設置しなければいけない理由は私にはどうしても見当たらないわけです。今回の計画決定に当たって、メリットはどのようなところだと捉えているのか、あわせて1日当たりの利用者数の見込み等があればお示しいただきたいと思います。
増田復興再開発推進室長
歩道橋の整備効果と捉えて御答弁いたします。
再開発ビルと名取駅東西自由通路を直結する歩道橋ということで、駅の利用者、また、新しく整備される再開発ビルの施設を利用する方にとっては非常に有効度の高い歩道となると考えております。再開発ビルは種々の施設が入る複合ビルとなります。施設の高度利用の観点から、ビルの立体的な空間を有効に利用するために、再開発ビルの施工区域の中で2階に公共的な歩廊を設置するという整備計画で今進めています。これは、再開発ビルの2階に入居する図書館、生活利便施設、これらをつなぐ道路、歩廊ということで名取駅前地区市街地再開発組合で整備します。この歩廊と名取駅東西自由通路を接続することによって、ビルのさらなる利用を促進できることになります。そして、駅の西口を利用する方にとっても、1階におりずに図書館等の公的施設を利用でき、非常に利便性が高いと考えています。特に、2階が図書館となりますが、ここと駅の改札が直結されることで新たな利用者の拡充につながると考えます。また、災害など有事の際には電車が運休する場合があります。このときに一時的に再開発ビルの中の施設に休憩または避難することも想定できます。これによって駅前広場の中で電車を待つ方々がスムーズに施設に移動できる、わかりやすいということで、防災上の機能も確保できるのではないかと考えております。 それから、利用者数の想定については、今手元に資料がありませんのでお答えできません。
吉田
今言ったさまざまなメリット、効果については、本当に歩道橋を設置しなければ得られないものなのか非常に疑問です。例えば電車が運休の場合も想定されて、非常によく考えていると思いますが、では、ビルの中に電車を待つ方々が一時的に移動したとして、電車が今から出発するという知らせがそこに届くのかといえば、やはりそれは個人で確認しなければなりませんから、歩道橋の有無にかかわらず個人の問題になるわけです。それから、1階におりなくても利用できると。これも1階におりないことによって一体どのぐらいのメリットがあるのか。駅から1階におりない、何か1階におりてはそんなに都合の悪いことがあるのか。私はそこまでとは思わないのですが、直接2階から2階にというのは、確かに歩く歩数がその分何歩か減るのでしょうが、それをメリットと言えばメリットかもしれませんが、そのことに対してこの2億8,000万円は余りに大きいのではないかと感じているところです。例えば仙台駅のような大きいペデストリアンデッキだと、その部分を使ってイベントの開催や市民が集って交流できるといったこともあるかと思うのですが、ここの場合は、ビルのほうにはそのようなスペースがあるという話でしたが、歩道橋にはないと思います。そういう中で本当にここに歩道橋をつけなければいけないという理由が私は大変疑問なのですが、今回の件に関して、利用する市民の方、駅の利用者あるいは複合施設を今後利用する周辺の方々への聞き取りはどの程度行ったのか、その内容と結果をお伺いいたします。
増田復興再開発推進室長
再開発ビルと歩道橋をつなぐ施設については、名取駅前地区市街地再開発事業の地元説明会として増田地区の説明会、また工事説明会を行い、この中で、当然駅からの直接の接続歩道橋も整備するということで、歩道橋の平面図等をお見せしながら事業を説明しております。その際に異論はありませんで、ある程度の御理解をいただいているものと思っております。
吉田
繰り返しになりますが、同じく名取駅東口歩道橋整備事業です。先ほどの御答弁では地元説明会の中で異論はなかったということでした。手続を踏んでいるということで一つ安心はしたのですが、恐らく金額がどのぐらいかかるかまでについては説明していないのではないかと思うのです。ですからそういうことも、市民から見れば、どんな施設でもやはりできたものはありがたいですが、ただ、そこにどのぐらい税金が投入されるかとなったときに、ほかのところで先にやってもらいたいということもたくさんあるわけですので……
そこで、少し視点を変えて、今回の補正予算は橋脚部分だけなのでまだ計上されていない2階の歩道ですが、視覚障がい者のための誘導用ブロックは設置する予定と考えてよろしいのでしょうか。
吉田
まだ今回は橋脚部分ということで、そこから始まっていくわけですから、今後さらに議論していかなければならないことで、あらかじめ知っておかなければ私も賛否を示すのは難しいと考えて今申し上げたのです。できれば市長に直接お伺いしたいのですが、この計画は市長に就任してからより具体化されてきたかと思うのですが、具体的な計画の中身、金額等についてもお知りになってから、何かこれを見直しするような手続といいますか、検討は行われたかどうかお伺いいたします。
吉田
今、駅の清掃を行っているのはJRの方と、市の土地は恐らくシルバー人材センターの方かと思いますが、このような施設をつくってこれから維持管理をしていくとなったときに、年間どのぐらいの維持管理費がかかると見込んでいるのかお伺いいたします。
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、議案第92号 平成29年度名取市一般会計補正予算について反対の立場から討論をさせていただきます。
反対の理由はただ1点です。先ほどから何度も質疑させていただきましたので御理解いただけたかと思いますが、このたび名取駅東口に整備が計画されている歩道橋について、御答弁で全体での金額が2億8,000万円に上ると確認し、反対させていただく決意をしました。
ここまで整備を進めるに当たって大変な御苦労があったかと思いますので、その点については大変心苦しく思いますが、本市の現状を考えた際に、それだけの金額の予算があるのならば、ほかにも手をつけてほしい部分、地域課題はたくさんあるわけです。そうした中でそれを一つ一つ比べていくのも大変な作業ですが、優先順位から考えた際、駅前東口の整備は今ここでしなければならないのか、しかもこれは震災復興事業とはまた別ですから、国からの交付金もない中で進めるのは難しいのではないかと判断しました。また、やはり新しいものをつくるとなれば将来にわたってそれなりの負担が毎年かかるわけですが、今、市内のさまざまな道路等についても、区画線が消えているなどいろいろな市民からの声にも応え切れない中で、新たなものをそれだけの予算を使って整備することに関し大変疑問を抱いた次第です。
この件に関してだけということで反対いたしますが、どうかよりよいまちづくりのために総合的に判断していただきたいとお願いいたしまして、私の反対討論とさせていただきます。
(議案第107号 区域外における公の施設の設置の協議について)
吉田
バス停を置くことになるのかと思うのですが、もちろんバス停はバスがとまるために道路にあるもので、交通量の多い道路等に関しては、側道に少しバスが寄せられるようなスペースを設けているところが見られると思います。今回、2番の国道4号は交通量が相当多いと思いますが、岩沼市がバス停の設置を希望する具体的な場所に係る協議が詰まっていたら、そこについてバスが脇に寄せられるスペースが現在あるのかどうかお伺いいたします。
防災安全課長
バスベイを設置してそこにバスをとめるのかというお尋ねだと思いますが、2番の路線についてはここをバスが通るということでの手続です。今回の公の施設の設置の申し入れですが、バスの運行について申し上げますと、その許可については東北運輸局宮城支局に許可申請を行うことになり、その際、運行路線とダイヤということで運行時間、そして始点終点がどこになるのか、この3つが要件になります。今回は名取市域を岩沼市のバスが運行するということで、この3路線となります。申し上げたとおり2番にはバス停はありません。1番は仙台空港のバス停が1カ所、総合南東北病院の北側のいわゆる堀内南に関しては道路の北側に1カ所、そしてもう少し東側に行った市境に1カ所のトータル3カ所になります。
財務常任委員会
吉田
7、8ページ、1款市税全体でお聞きします。不納欠損が前年度に比べて926件増加しており、その内容は生活困窮、所在不明、無財産、死亡が主なものとなっていますが、その他として367件あります。この分の、その他に分類された主な内容をお伺いしたいと思います。
税務課長
主なものとして、例えば会社の倒産案件等で、倒産してすぐ処理できるものについては即不納欠損に落とすケースもあります。もしくは、一時的に執行停止にした後、3年たって状況が変わらない場合に不納欠損にするケースもありますので、そういったものが主な案件と御理解いただければと思います。
吉田
7、8ページ、1款1項1目市民税個人分の1節現年課税分で、不納欠損として2万4,915円と記載されていますが、これが収入未済ではなく不納欠損になっている理由を教えていただきたいと思います。
税務課長
先ほど不納欠損の処理の関係でお話ししましたが、該当条文に基づいて該当した案件が、個人市民税の不納欠損については2万4,915円であったということです。
吉田
17、18ページ、10款1項1目地方交付税についてお伺いいたします。昨日の説明の中で、普通交付税など内訳について金額をお示しいただきましたが、それぞれ前年度と比べての増減のパーセンテージをお伺いしたいと思います。
財政課長
地方交付税の内訳のそれぞれの増減についてです。まず普通交付税ですが、額にして1,904万円の増、伸び率としては0.8%増、特別交付税については3,205万7,000円の減、伸び率としては5.9%の減、震災復興特別交付税については12億1,074万9,000円の減、伸び率としては13.9%の減となっています。
吉田
普通交付税の部分は0.8%の増ということでふえています。これも算定の方法が非常に複雑なものだと思いますが、算定していった中で、増になった要因というか、市としてこういう部分が成果が出たので変わったとか、そのようなところの捉え方についてはいかがでしょうか。
財政課長
普通交付税の算定に当たって平成27年度と平成28年度を比較しますと、まず、振りかえ前の基準財政需要額についてはほとんど差はありません。平成28年度でいうと、約243万9,000円の減になっています。そのほかに基準財政収入額は、平成27年度と比べると8,425万5,000円ほどふえています。これにより、財源不足額については対前年度で8,669万4,000円減っているところです。財源不足額が減っていますので、それに連動して普通交付税が算定されます。その際に財源不足額と連動する臨時財政対策債は連動して増減しますが、例えば平成27年度、平成28年度、基準財政需要額、基準財政収入額が同じであったとしても、普通交付税の原資、また全国自治体の財源不足額の合計の状況によって大きく変わるものです。平成28年度については、基準財政収入額がふえており、財源不足額そのものについては圧縮される形になっていますが、それ以上に臨時財政対策債が減っているということで最終的に普通交付税の交付額としては1,904万円の増となったところです。
吉田
25、26ページ、13款2項4目消防手数料で、当初予算額と補正予算額を合わせて77万円という金額になっていますが、平成27年度はこれが98万4,000円でした。見込みをそこまで下げていたわけですが、実際に決算で今回出てきている額は、昨年度を上回っています。このあたりの見込みが変わって額が大きくなった要因をどのように捉えているかお伺いします。
予防課長
手数料については危険物と火薬の手数料をいただいていますが、ただ単に件数がふえたということです。件数は多いときもあれば少ないときもあってなかなか読めないので、予算という形で出してはいますが、決算で金額がふえたのは危険物や火薬の手数料の件数がふえたことによるものです。
吉田
前年度と同じくらいと見込まずに、先に低く見積もって実際は大きくなったということなので、そのあたりの理由というか、なぜあらかじめ前年度と同じくらいを見込んでいなかったのか、その辺を詳しくお伺いしたいと思います。
予防課長
低く見積もっているわけではないのですが、件数がどのくらいになるかわからないので、平均的に約70件ということで予算を組んでいます。
吉田
20款5項2目雑入9節学校給食費実費徴収金ですが、給食費の支払いの方法として口座引き落としを行っている学校はあるのでしょうか。
学校教育課長
ほとんどの学校が口座振替という形で行っています。
吉田
そうなると、収入未済となっている分は口座から引き落とせなかったというケースが相当含まれているのかと考えられますが、口座引き落としを実際していない方というか、現金で集めているケースはどのぐらいの割合になるのですか。
学校教育課長
現金で集めているというのは、市内ではありません。
財務常任委員会第一分科会
吉田
市政の成果の136ページ、常備消防費の民間協力団体の育成の中で幼年消防クラブについて伺います。平成27年度に比べて会員数がふえていますが、主な入会の動機をお伺いします。
予防課長補佐
幼年消防クラブについては、市内12カ所の幼稚園、保育所の4歳児、5歳児が対象で入会します。園の入所者がふえたので会員数が若干の増加となりました。
吉田
保護者等も含めて、その子供たちが卒園後の次なる効果につながったような事例は何か把握しているでしょうか。
予防課長補佐
幼年消防クラブは幼稚園、保育所が対象で、卒園すると小学生になるわけですが、どういった効果があったのかというところまでは担当では把握しておりません。
吉田
市政の成果137ページ、常備消防費の5の消防活動力の充実・強化の(2)委託料についてお伺いします。総括質疑でもありましたが、多言語通訳コールセンター業務委託ということで、具体的にどの言語を利用したのか、また通報から搬送までに要した時間について詳しくお伺いしたいと思います。
警防課通信指令係長
多言語コールセンターの使用は1件のみで、救急現場において傷病者から症状を直接聞くために使用しています。使用した言語は英語です。搬送先までは把握しておりません。基本的に外国人から外国語で119番通報があったときに使うという考え方ですが、119番での使用は現在のところありませんので、救急現場で1件利用したという状況です。
吉田
電話の通報に対する多言語コールセンターの利用ではなく、現場での通訳の形で使ったと認識しましたが、担当としてどのように評価しているのでしょうか。
警防課長
指令時間が午後6時51分で、車内収容を経て病院を決定し、午後7時50分から午後8時2分、約12分で病院には到着しております。なお、この事案は交通事故でしたので、外国人とのコミュニケーション、どこが痛いかなどの把握に時間をとったものと思われます。
吉田
市政の成果138ページ、常備消防費の消防活動の成果の1番の表で、放火・放火の疑いが平成27年はゼロ件だったのが平成28年1月から12月で3件とふえています。3件のうち何件が確実に放火とはわからないということで放火の疑いに分類されているのかお伺いします。
消防署警防係長
放火と放火の疑いについてですが、放火と断定できるものを放火と限定しており、これが2件です。放火の疑いは、調査した結果、断定まではできませんが、推定として放火だろうという事案について放火の疑いと表現していて、1件です。断定2件、推定1件の合計3件となっています。
吉田
1件は思い当たる件があるのですが、放火の疑いの2件では実際にどのようなものが燃えたのでしょうか。
消防署警防係長
放火の疑いについては、遊技場内のトイレに火をつけられたのではないかと、断定までできずに推定ということで判定しました。
吉田
市政の成果139ページ、常備消防費の救急活動の表で、搬送人員が2,997名、出場件数が3,227件ということです。詳しい内訳が消防概要に載っているかと思いますが、確認のため、この中で手倉田出張所管内でどのぐらい救急出動件数があったのかお伺いしたいと思います。
消防署救急救助係長
手倉田出張所管内への救急出動件数は1,145件となっています。
吉田
件数にすると全体の3分の1ぐらいになるのかと思いますが、先日、手倉田出張所を現地調査して、かなり老朽化していることも含めて、救急車が配備されていないということで今後の課題かと思ったところです。ほかから救急車が回ってくるのかと思いますが、今の1,145件についてほかの地域との通報から到着までの所要時間の差をもし把握していたら伺います。
消防署救急救助係長
地区別の到着平均時間は把握していません。
吉田
市政の成果145ページ、防災費の防災対策事業の委託料の防災ラジオ販売業務委託について、平成28年度末時点で売れ残りがあれば台数をお伺いいたします。
防災安全課長
残台数という質疑ですが、まず引き渡した台数が平成27年度は3,632台、平成28年度は812台です。そして、公的施設として学校や公民館など、岩沼警察署も入っていますが53台で、引き渡し累計は4,497台となります。5,000台からこの分を引いて503台が平成28年度末で残っています。
吉田
順調に購入されていると捉えられるかと思います。現在、原則1世帯に1台となっていると思いますが、例えば2台購入したいという方がいたのかどうか、その辺の検討や対応についてお伺いします。
防災安全課長
1世帯で2台を希望する方もいますが、大まかに申し上げますと、世帯、事業者を含めて市内に3万世帯あるとすると5,000台でもまだ少ないわけです。1世帯1台もしくは必要な方という部分でまだ購入していないところもありますので、現段階においては基本的には1世帯1台ということで制限をかけております。
吉田
市政の成果140ページの非常備消防費の全体的なことについてお伺いしますが、平成28年度末時点の消防団員の平均年齢を伺います。
消防本部総務課総務係長
消防団員の平均年齢は44.7歳です。
吉田
訓練や出動等1年間の活動の中でけがなどをした方はいなかったのでしょうか。
消防本部総務課総務係長
平成28年度中における消防団員の労災事故はありませんでした。
吉田
1ページの企画費の地方創生事業で婚活支援事業補助金についてお伺いいたします。さきの総括質疑でも結婚に至るケースもあったという御答弁があり、成果が見られたと評価しているかと思いますが、例えば交際に至る方たちの傾向のようなものは分析していますか。
政策企画課政策係長
傾向については担当で捉えていませんが、先日も答弁したとおり、なとコンについては12組、イモナコンについては7組のカップルが成立ということで、アンケートなどをとっているようですが、カップル成立の経緯等は捉えていないところです。
吉田
カップル成立後の追跡調査というか、そのあたりはどのようにしたのか伺います。
政策企画課政策係長
最終的には結婚が大きな目標と答弁しましたが、そこまでの追跡は個人的な話でもあり少し難しいということで、主催者側と今後も相談させていただきながらそういった形で何かできないかとは考えていますが、正直なところ難しいのではないかという捉え方です。
吉田
市政の成果の2ページ、財産管理費で財産管理事務の2 財産保険加入ですが、平成27年度も質疑がありましたが、市民総合賠償補償保険で適用があったのかどうか、もしあれば件数をお伺いいたします。
財政課管財係長
市民総合賠償補償保険の平成28年度の対象となった件数は17件、保険金額は112万7,693円となっております。
吉田
平成27年度は16件で42万5,000円で、件数はほとんど変わらないのに平成28年度は額が大きくなっていますが、対象となった事例の内容の主なものについてお伺いします。
財政課管財係長
平成27年度は市内の体育行事等ということで、対象はほぼ変わらないのですが、大きなものとして、建物に被害を与えた案件が発生して対物賠償が増加したことが大きな要因となっています。
吉田
市政の成果の4ページ、庁舎管理費の光熱水費等の表の電話料でお伺いいたします。電話としては、庁舎内に設置されている業務用の電話と公衆電話、それから職員が携帯電話を持っているのかどうかわからないのですが、その内訳と、契約方法について、法人向けの契約などを利用していたら詳しく教えていただきたいと思います。
財政課長
電話料の内訳ですが、庁舎の電話料として430万296円、そのほかにファクス料金等が17万1,634円、公衆電話料が3万6,984円、レタックス公用電報が2万2,262円です。契約の方法は、フレッツ光分で1万6,524円、東日本電信電話が6万7,392円、合計461万5,092円となっております。
吉田
庁舎内で業務に使っている分で金額としては410万何がしということでしたが、詳しい台数と、今固定電話を使っているとのことですが、契約内容で例えば電話会社によっては使い放題のプランなどがあるところもありますので、経費削減に向けた取り組みをこれまで行ったのかどうか伺いたいと思います。
財政課長
台数は捉えていません。携帯電話等については、この中には入っていませんが、一般管理費で秘書係が持っているものがあります。
吉田
事項別明細書109ページから112ページまでの2款4項選挙費で、平成28年度に行われた参議院議員通常選挙と市長選挙の内容をお伺いします。今回の選挙に限りませんが、例えば町内会で持っている施設を投票所などに借りる際の借り上げ料の決め方についてお伺いいたします。
選挙管理委員会事務局長
投票所の借り上げ料ですが、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律がありまして、それを準用して1投票所当たり5,000円の借り上げ料をお支払いしています。
吉田
1投票所当たり、投票日当日のみで5,000円ということだと思います。その金額の多寡についてはいろいろと議論があるかと思うのですが、今回はダブル選挙として行われましたので、このあたりは国とどのように分けて考えたのかお伺いします。
選挙管理委員会事務局長
県からの指導もあり、国政選挙、参議院選挙の分は案分いたしまして3分の2、市長選挙の分は3分の1ということで算出して、3目参議院議員通常選挙費と4目名取市長選挙費のどちらの科目からも支出し、合わせて5,000円を支出しました。
吉田
市政の成果の14ページ、市民活動促進費の市民協働提案事業についてお伺いします。平成28年度は前年度に比べて1団体1事業ふえて2団体2事業になりましたが、応募数はどのぐらいあったのかお伺いいたします。
男女共同・市民参画推進室推進係長
協働提案事業については、平成28年度では委託が1団体、もう1団体が補助ということで採択されておりますが、応募は3団体からありました。
吉田
応募に必要な書類の作成等にもいろいろとお手伝いいただいて、利用したいという方は本当にありがたいと言っているところです。今回応募が3団体で採択されたのが2団体ですが、選考方法といいますか、基準についてお伺いします。
男女共同・市民参画推進室推進係長
平成28年度に予算執行した団体は平成27年度中に応募があった方々となります。平成27年度中に3団体の応募があり、名取市協働事業審査会設置要綱に基づいて、まずは協働したい課と情報交換会などを行い、書類と話し合いによる1次審査を経て、プレゼンテーションのもと、要綱にある審査会で審査委員によって審査がされて採択されます。