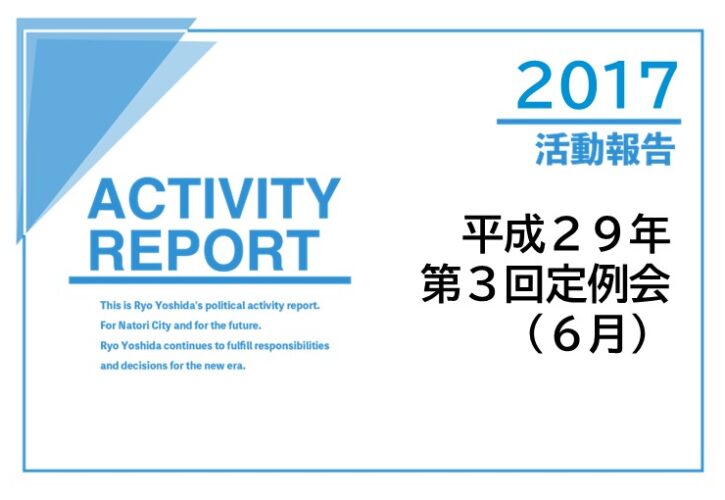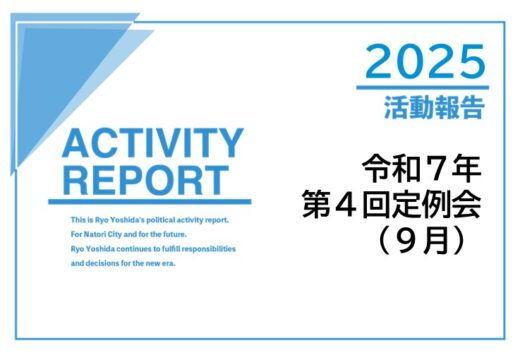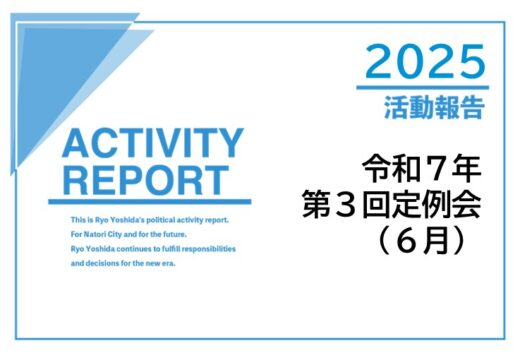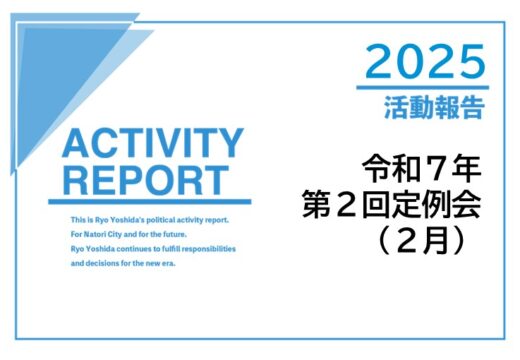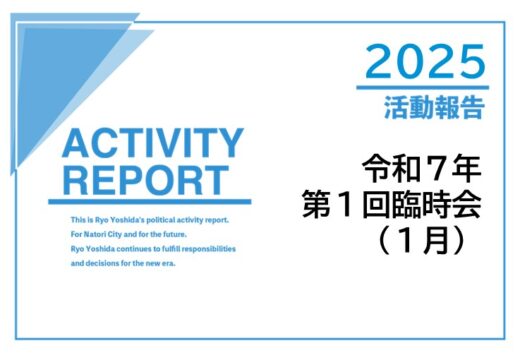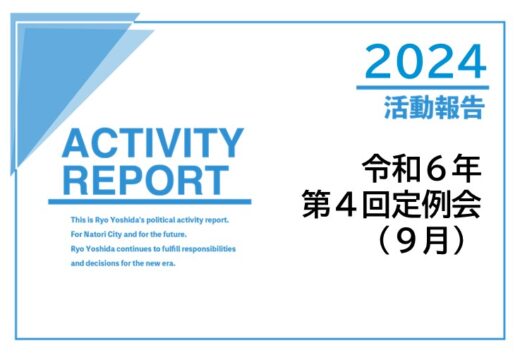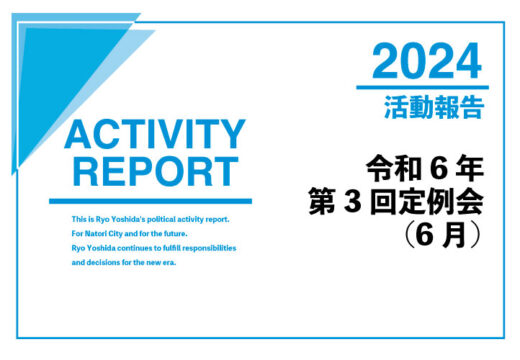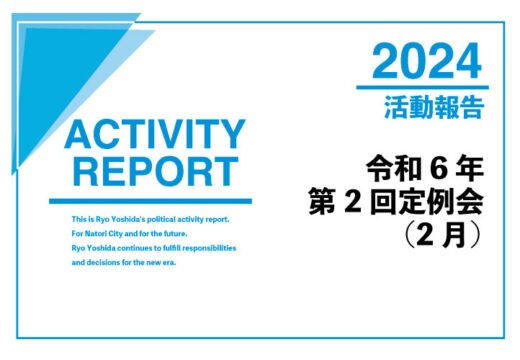本会議
(議会案第2号 国民の議論のもと平和主義の理念を堅持し社会情勢の変化に即した憲法改正の発議を行うことを求める意見書)
日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、今日に至るまでの70年間、一度の改正も行われていない。このことは先進国の中でも極めて異例なことであるが、その理由は憲法改正の手続きが衆・参両院での3分の2以上の賛成によって発議され、国民投票において過半数の賛成により成立するという高いハードルがあるからである。このことからこれまで70年間、我が国では憲法改正を行わず法律の制定・改廃などで社会情勢の変化に対応してきた。
しかし大規模災害の発生時に一人でも多くの被災者の生命を救うため、重大な危険を伴う任務にあたってきたのは自衛隊であり、憲法制定時には存在しなかった自衛隊が今日では、その活動を多数の国民によって高く評価されていることから、その存在を憲法に明記すべきであるという声がある。また憲法施行時には予測されなかった高等学校の進学率や環境権、性的少数者への理解、地方分権の進展など社会情勢や国民意識の変化に対応することも求められている。
憲法は国の最高法規であり、その改正については、主権者である国民みずからが幅広く参加し、十分な国民的議論を尽くしたうえで進めていくべきものである。
よって国会においては、国民の議論のもと平和主義の理念を堅持したうえで、社会情勢の変化に即した憲法改正の発議を行うことを要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年 月 日
名取市議会議長 郷内 良治
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
小野寺美穂議員
委員会の審査もあるのですが、全体の中でお伺いしておきたいのです。
まず冒頭、今日に至るまでの70年間一度も改正が行われていない。その理由が、改正のハードルが高いと述べられていますが、一度も改正が行われていないのは異例といっても、日本国憲法は硬性憲法ですから何回も何回も改正するというものではないのです。これまでハードルが高いから改正されていないというように読めるわけですが、国民の議論を経て改正したいという状況になったにもかかわらず、ハードルが高いから改正できなかったという具体的事実経過はいつなのかを示してください。
吉田
こちらで案文として今回明記しておりますことは、議員御指摘のとおり高いハードルがあるために、これまで成立することがなかったということです。実際に国民の議論がどのくらい高まったかというのに関しましても、さまざまな新聞等のアンケートですとか、いろいろな捉え方ができるかと思いますが、この国会、衆参両院で3分の2以上の賛成によって発議されるという、このハードルに関して国民の大多数が望んでいるかどうか。そのアンケート結果などがどの程度まで進み、それがハードルとなっているのか。国会がハードルになっているのかということに関して、具体的にそれがいつのことであったかに関しては、私はそこまで想定はしておりません。
小野寺美穂議員
想定ではなくて、変えられていないことが異例だと。その理由はハードルが高いからだと書いてあるわけです。しかしながら、先ほどお聞きしましたように、国民が求めているのに、3分の2以上の賛成が得られなかったから改正ができなかったということになるわけであって、そういう具体的事実経過はいつなのかと伺っています。改正されていない理由に、ハードルが上げられているので、それによって改正できなかったというのはどのことを言っているのかと伺っているのです。
吉田
あくまでこれは、今の憲法の制度の中での改正の条項についてのことを申し上げております。
高いハードル、それが高いか低いかということに関しては、それぞれの個人の見解があろうかと思いますが、先ほど議員が話されたように、確かに日本国憲法は硬性憲法であると。そして、戦後70年間さまざまな問題がある中で、いろいろなハードルのあることにより今まで改正がなされてこなかったと。そろそろそのことについて国民的な議論のもとに考えていってもいいのではないでしょうかという意味で、このように掲げさせていただきました。
齋浩美議員
本文の5行目のところ、このことからこれまで70年間、我が国では憲法改正を行わず、法律の制定、改廃などで社会情勢の変化に対応してきましたと書いてあるのですが、これは少し矛盾しているのではないかと思います。結局、法律の制定と改廃や改定などで十分に対応できているのに、何でここに憲法を変えるのかという話が出てくるのかなと思います。
憲法を変えないと対応できなかったという事例があったのかについて、具体的な事例でお答えいただければと思います。
吉田
憲法を変えないことによって、何かを果たすことができなかった、問題を解決することができなかったということに関しては、事案として例をあえて挙げるとすれば、やはり今自衛隊の存在が違憲の存在であると多くの憲法学者がみなしている。そのことが一つ挙げられるのではないかと考えております。
そのような状況の中で、不安定な中で活動しなければならないことについて、しっかりと憲法に明記した上で、みずからの職務を果たしていただけるような環境を整備していく、これはあくまで一つの例として挙げますが、そのようなことが考えられるかと思っております。
齋浩美議員
今、自衛隊のお話も出てきたのですが、今お話ししたのと少し矛盾していると思うのですが、仮に自衛隊は憲法に違憲だとあっても、自衛隊法という法律には従って出ているわけですよ。その存在はどうあれ、自衛隊法という法律があってきちんと活動している。この前、我々も東日本大震災などでお世話になっています。憲法改正したからといって自衛隊が現状ある中で、それで憲法を改正するという、十分法律で対応できている、そして今お話しした内容というのは、やはり少し矛盾しているのではないかと思うのですが、その辺について伺いたいと思います。
吉田
自衛隊法という法律があるというのもそのとおりです。しかし、その法の根拠となっている憲法、憲法は日本の最高法規ですから、全ての法律の根拠になるわけですが、そこにおいて明記されていないということが今後、最高裁判所の判断等いろいろあるかと思いますが、そのような疑いといいますか、そのような経緯をたどらないということを完全に排除することはできないというのが、現状の問題ではないかと認識いたしております。
小野泰弘議員
憲法改正はこの意見書にあるとおり、国民みずからが幅広く参加し、十分な国民的議論を尽くした上で進めていくべきものという点では、異論のないところです。しかし、市議会からこのような意見書を提出するとなれば、我々議員は市民の憲法改正に対する議論に耳を傾ける必要があるのではないかと思います。しかし、どれほどの名取市民が、憲法改正の議論に参加しているのか。どれほどの議論がなされているのか。少なくとも私は耳にしたことがありませんので、市民が憲法改正を望んでいるのかどうか大変疑問に思うところです。
提案者及び賛同者は、市民の憲法改正に対する議論や考えをどのように聞き、そしてそれをどう理解して意見書の提出に至ったのか、その点についてお伺いします。
吉田
決して現段階で、そこまで憲法の議論が深く進んでいるというところまで至っていないのが現状であろうかとは認識いたしております。
しかし、一方で、やはり憲法のことに関しては、非常に関心を持たれている市民の方がいらっしゃることは、私の通常の活動の中でもよくそのような話をされる方も多数いらっしゃることから、恐らくは市内にはそれだけではなくおられることは確実であろうかと思われます。また、先ほども申しました新聞等の各社のアンケート調査などによりましても、現在改正を求める声が非常に高まっているということは、これは全国的に見てそのような流れにあり、名取市もその一部であろうということは容易に想定できますので、このような形で今回提出させていただいた次第です。
小野泰弘議員
では、別の観点からもう1点。国会法によりますと、議員が憲法改正原案の発議をするには、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要するとあり、よく知られているように、その後、両院でそれぞれ総議員の3分の2以上の賛成をもって可決されて、ここで初めて憲法改正の発議となりますが、この意見書の宛先については衆参両院議長となっております。議長は憲法改正原案の発議をすることはできません。しかも議長みずからは慣例に従い、憲法改正発議の採決に加わらないことになっております。したがって、衆参両院議長宛てに憲法改正の発議を求める意見書には、大変違和感を覚えるところです。提案者と賛同者はどのように考えて、衆参両院議長宛ての意見書としたのか、その理由をお尋ねいたします。
吉田
議員お話しのように、衆参両院の中での手続が決められているという中で、衆議院と参議院それぞれの多数の議員の代表であるのが議長です。宛先としてはそのような形で、両院の議員の方たちに見ていただくために、そのトップとしての議長宛てにこのような形で送らせていただきたいと考えている次第です。
大沼宗彦議員
いろいろあるのですが、あとは常任委員会で審議されることですので、私は最後のところにある、憲法施行時には予測されなかった高等学校への進学率や環境権、性的少数者への理解、地方分権の進展、社会情勢や国民意識の変化に対応することも求められていますということで、この意見書の説明の中にあるのですが、現在の憲法の中にある中身でも十分酌み取れるのではないか。例えば憲法第26条に、全ての国民は法律に定めるところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有すると。ですから、次の第2項は義務教育についてうたっていますが、こういうふうにして能力に応じて享受できるということが書かれています。
環境権についても、基本的人権、性的少数者ということでも、第97条の基本的人権の尊重で、これは侵してはならないと述べてありますし、地方分権に至っては、8章に第92条、93条、94条、95条ということで、選挙で直接選ぶことができるなど、いろいろな条例をつくることができるということで書かれていますので、なぜここに地方分権の進展などということがあるのか。そして、最後に、社会情勢や国民意識の変化に対応することが求められていると言っているのですが、実際は憲法に合わないような現状が、今社会通念であると、非正規の問題だったり、環境問題だったり、原発の問題だったり、そういうことがあるということで、本来ならば現実の社会を憲法に合わせなければならない、そういう発想をすべきであるのに、この認識はどうなのかと思うのですが、いかがでしょうか。
吉田
こちらに挙げさせていただいたそれぞれの例については、ほかにもさまざまな議論がありますが、特に今回私はあえてこのように載せましたのは、国民の生活で直接の結びつきの度合いや、あるいは世界的な潮流を踏まえて、このようなものを例として挙げた限りでありまして、それはやはりその人、その人の立場においていろいろな問題点、改正すべき点というものはお考えの方もたくさんいると思います。ただ、どのような形かで一つの意見書としてまとめなければいけない中で、今回案としてこれらのものを挙げた次第です。
憲法を変えないでも対応できるのではないかということも、確かにお話のとおりで、先ほどからそのような議論にもなってきているところです。ただし、法律は国会の手続でより簡単に改正することができる一方で、憲法は改正するのが非常に難しい。それはやはり国のこれからの方向をより明確に、絶対にこれは国の基本方針として今後も守っていく、この方針でいこうというものについては、法律にその文言を書くよりも、憲法に書くことによって、よりそれがこの基本として今後の法整備につながっていくと。
ですから、憲法に書かれなくても、何もかも法律で対応できるということになれば、それは今話された例えば小学校中学校義務教育の無償化にしても、憲法ではなく法律の中で処理することだって可能であるわけです。しかし、それをあえて憲法にのせるというのは、やはりそれを今後も長くその方針を守っていこうと、そのことが理由として挙げられるかと思います。そのような理由において、今回はこのような案文としました。
大沼宗彦議員
私はそうでなくて、憲法に合わない現実、今の社会状況があると。それを正していくことこそが必要であって、憲法を変えるということは、では非正規等も認めるような、そういう社会にするのですか。そうではないでしょう。朝日訴訟というのがかなり前に私の学生時代にありましたが、生活保護者、こんな金額では暮らせないということで憲法違反の訴訟を起こしました。憲法違反のいろいろな実態がある、それを訴えて直していくということが大事であって、これに今お話しされたような、対応できるのではないかではなくて、対応できない状況が今あるということの認識が、私は必要ではないかと思っています。
だから、私は今の回答を聞きながら、今の社会状況で憲法からかけ離れた実態をどう考えているのかなということを聞いてみたいというか、答弁いただければと思います。
吉田
日本国憲法に掲げられているさまざまな条文には、これからますますそれを実現していくために、国民の福祉をより拡充していくという意味においては、残すべき部分がたくさんあるかと思います。
ただ、その一方で、やはり国の最高法規というものは、その時代に合わせ国民がみずからの手で議論し、そして決めていくものであるのが本来のあり方ではないか。そして、そのことをもって世界の諸国は、先進国もそうですが、憲法の改正を繰り返してきた。それは日本と同じ敗戦国であるドイツやイタリアにおいても同じことです。そのような意味で、いいところはいいとして残す。そしてまた、時代の流れに合わせて変えるべきところは変えるという意味におきまして、今回はあくまでこのような例を挙げましたが、さまざまな議論があるかと思いますので、委員会でもその点については深く審議をしていただきたいとお願いしたいと思います。
小野寺美穂議員
今、答弁の中で話されましたが、日本国憲法は国家の方針を決めるものではありませんよ。日本国憲法は、国の行く先や国の方針を決めるものではない。英文でも書かれているから、英文で読まれたことがあると思いますが、We Japanese peopleです。日本国民は、というところからこの前文が始まります。国の行く末や国家の方針をあらわすのが日本国憲法ではなく、日本国民が国家権力に対してこのようにしなさいと言っているのが憲法です。そこを間違わないでほしい。そこから違ったのでは、もう議論する何もない。よって、我々は今ここでなぜ地方議員としていられるかというと、憲法第93条に、地方議会を置いて、地方議会の長、その議会の議員及び法律が定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると、日本国憲法に定められているからこそ、我々は今ここに議員としています。
先ほどいいものはいいとして残す、だめなものは変える。そんなことで変えられる憲法ではないのです。また、これについておわかりになって出されているからあれですが、再び言いますが、憲法第99条に、我々はこの憲法を尊重し擁護する義務を負っているのです。あだやおろそかに変えろと言うことは、許されていない。意見をするということはあるかもしれない。しかし、先ほど国民が議論を尽くすということをしたかという小野議員のお話がありましたが、国民が議論を十分尽くした結果、変える必要はないという結論が出る可能性もあるのに、なぜ改正ありきなのですか。まず日本国憲法を国家の方針なんて言ってもらったら困りますよ。これは憲法学者の一部の人の認識など、そういう問題ではありません。これまで長い間培われてきた大事な理念です。そこをどう捉えていますか。
そして、結果として、改正は必要ないという可能性もあるのに、なぜ改正の発議ありきなのか。ここで伺っておきます。その後は常任委員会で伺います。
吉田
国民の議論を尽くした上で、その改正をするべきでないという結論が出るということも、もちろん一つの想定としてはあり得るかと思います。
しかし、この議論そのものを今後より深めていくと。それはやはり今の憲法の中にあるさまざまな規定の中で、時代に沿わなくなってしまった部分、それはともに考えていくべき内容ではないか。そして、必ず全ての条文、一文字一句変えずにこの先永遠に続けていくのかといったときに、それはどの法律についても、憲法についても、先ほどから申し上げておりますのでまたお叱りを受けるかもしれませんが、必要なところは改めていく。大事なことは憲法の条文の文字を守るのではなく、市民の国民の福祉と、そして日本の世界との信頼関係、このようなものを守っていくことが大事なわけでして、その意味では憲法の改正を求めると、発議を行うことを求めると、今回このような形で衆参両院の議長に送付させていただきたいと考えました。
また、その前にあった御質疑ですが、憲法は国の方針を決めるものではなく、権力を縛るものであると、それもおっしゃるとおり、そのような憲法の教科書には書かれております。それは私も認識をいたしております。ただ、権力を縛るという意味におきましても、今その権力の縛りというものが足りない部分があるのかもしれない。足りない部分をつけ足すということに関しては、やはりこれも改正が必要となってくるわけです。そういう意味では、このような議論を行っていく、それを国会に届けていくということは、地方議会としても十分に一つの議論をしていくべきことなのではないかなと、そのように考えているところです。
(議会案第3号 日本政府に核兵器禁止条約のための行動を求める意見書)
吉田
似たような意見書案が昨年も同じ6月の議会で審議されまして、可決されたという経過があったことを記憶しております。今回その文言とは中身が微妙に変化しているものですが、この3行目にあります核兵器禁止条約についての交渉を行う国連会議の第一会期とありますが、この会議の正式な名称、外務省が使用しているものとしての正式な名称について教えていただきたいと思います。
大沼宗彦議員
正式名称ということですが、その正式名称がわからなければ議論できないということでしょうか。2015年の第70回国連総会の決議で行われて、5月及び8月に15日間ジュネーブでこの会議……
吉田
質疑に答えていただくようにお取り計らい願います。
議長
ただいまの吉田議員の議事進行に関しまして、答弁者の答弁をしっかり聞いてから考えていきたいと思いますので、そのまま続行いたします。大沼議員、続行してください。
大沼宗彦議員
多国間核軍縮交渉の前進に関するオープンエンド作業部会というのがあって、それで作業部会では国連加盟国、多いときで100カ国以上が参加して、市民それから国の代表が集まって議論して、そして最終的な報告書を受けて賛成68、反対22、棄権13ということで採択されてきているということです。今回、この準備期間を経て3月の国連の会議、そして6月末から7月にかけて、この条約の締結に向けた国連の会議が開かれるということです。正式な名称かどうか少し自信ありませんが、経過としては以上です。
議長
大沼議員に申し上げます。正式名称ということでよろしいのですね。
大沼宗彦議員
正式名称は保留、なし、自信がありませんので。
議長
わかりませんということですね。
大沼宗彦議員
わかりません。
吉田
現実に今、外務省が取り組んでいることに関して、そうではないのだ、別の方針をとるべきだというような意見書ですから、当然今外務省が現状どのような対策をとっているのかについて最低限の調査を行うことは、これから審議していく上での私たちの務めではないかと思います。
今回のこの会議につきましては、外務省側では核兵器禁止条約交渉第1回会議という名称をつけていると。これはインターネットでも閲覧することが可能なものです。当然この資料につきましてもお読みかと思いますが、今回の議会案のこの意見書案について、被爆国にふさわしい役割を発揮されるよう強く求めますというのが1ページ目の真ん中から少し上あたり、3段落目にあります。となりますと、これまでの日本国の政府の、あるいは外務省の取り組みというものが、被爆国にふさわしい役割をまだ発揮していないのかというように受けとめられかねないと感じますが、なぜ今回日本政府側がこのような会議におきまして参加しなかったか、その理由について高見沢軍縮代表部大使という方がステートメントを発しております。それについてはお読みになったことはあるのでしょうか。
議長
吉田議員に申し上げますが、この意見書案の内容について質疑をしていただければと思います。余りにも拡大し過ぎていますので、その辺のところを配慮してお願いします。
吉田
今申し上げたステートメントによりますと、日本政府としてはあくまでも核保有国と非保有国との間で核軍縮を目指していくという大きな方針があるわけです。それに対し、今回国連で始まったこの会議というものは、あくまでも核を保有していない国の間だけのもので、提案者の議員がおっしゃるように、それでは意味がないだろうと。日本もそこに参加して、核兵器廃絶に向けてより加速させていくべきだろうという思いであろうということは重々理解しているところですが、このようなことがこれまでの日本政府の取り組みと矛盾する、あるいはこれまで積み重ねてきたさまざまな成果を一気に崩してしまうおそれもあるのではないかということについて、今回高見沢代表はこのことを言っているわけです。
そのようなことについて、日本は今後この意見書案に書かれているように、被爆国としてのふさわしい役割ということですが、ほかの国々、日本の同盟国であるアメリカ等との連携といいますか、そのようなことについては全く想定をされずにこのような意見書の案になっているのかということについて、お伺いします。
大沼宗彦議員
この核保有国と核を持っていない国、それの対立をさせるための取り組みではない。国連の会議などでも結果的には核を持っていない国々が会議を開き、そして煮詰めていって、6月の下旬から7月にかけて成案をつくろうとしています。そこには核を持っている国々も、核を廃絶するという取り組みまでは、まだそこに踏み込んでいない中間的な中身ですから。ですから途中からでも入ってこられるということです。ただ、特徴的だったのは、やはり世界の多くの国々が、この核というのは化学兵器と同じように悪なのだと。これを製造も移動も開発も全て禁止するとした画期的な内容を持っている、そういう中身なのです。ですから、対立させるわけではなくて、今まで部分確定の核不拡散条約というか、実際核を持っている国々に、ほかの国々はつくってはだめだ、持つのは私たちだけ、そして核の傘にということがずっと今まで世界で通用してきて、そこが核兵器廃絶までつながらなかったという経験を世界の国々は持っているわけなのです。
だから、特徴的だったのは3月の国連の会議で、核保有国の大国が本来ならば市民団体などいろいろな人たちが国連に対して外から抗議や要請をしている光景が当たり前だったのですが、今回の場合は国連の中にいる、核を持たない国々が一生懸命話をする。その会議の外で、核保有大国が抗議行動をするという、これは日本のマスコミでは少し紹介されたくらいですが、だから核保有国がもう核というのは世界の悪なのだということを共通認識にしていく。そして、核を持っている国々も製造、開発、そして廃棄に向けた取り組みを今後していくということでは、一緒に共同歩調ができると、そういう門戸も開いているような会議ですので、私は今後この一つの中間の会議としては意味があると思っています。
一般質問
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、通告に従い私の一般質問を行います。
まず、大項目1 選挙事務についてお伺いいたします。
本年11月に宮城県知事の任期が満了することから、年内に県知事選挙が行われることは確実です。投票の意思があっても投票所へ行きづらい方に投票の機会を拡大することが本市の課題であると認識しております。そのためには、期日前投票所を市役所以外に設置することが一つの有効な手だてであると考えます。期日前投票所増設のためには通信環境の整備や人員の確保などの課題があり、新たな財源が必要となることでしょう。これまでの選挙事務に係る経費の使われ方に見直しをかけることも、財源確保のための手段の一つではないでしょうか。
そこで、まず、投票所入場券の配付方法についてお伺いします。
公職選挙法施行令第31条に投票所入場券交付の努めが定められていますが、配付方法や様式についての規定はなく、自治体の裁量によって決められるものとなっています。本市選挙管理委員会が交付する投票所入場券は、有権者1名に対し1枚の郵便はがきで送付されています。それに対し、封書などで同一世帯の複数の有権者宛てにまとめて送付する自治体がふえています。この方法であれば、個人単位に比べ、郵送料の総額を低く抑えられます。
そこで、小項目1 個人単位で行っている投票所入場券の配付方法を封書などによる世帯単位に変更すべきについて選挙管理委員会委員長にお伺いいたします。
選挙管理委員会委員長
投票所入場券を世帯単位で郵送することにより、郵送コストなど一部経費の削減につながるなどのメリットはあるものと捉えております。
しかしながら、入場券を世帯単位で封入する場合、封入までの業者委託料、封筒購入料、はがきから封筒に変更することで郵送料の増額分が新たに発生します。さらに、封入とした場合、郵送直前まで、転出者、死亡者、DV被害者等の入場券を抜き、最終的に職員の手作業による封緘作業が生じてきます。
以上のことから、郵送料等の経費と人的経費を総合的に勘案すると、現段階においてすぐに世帯単位に変更することは難しいと考えており、今後十分に検討する必要があるものと考えております。
吉田
私も試算をしてみたところ、郵便はがきの代金が6月から1枚当たり62円に引き上げになったことを勘案しても、本市の有権者数で見れば、実際は大体100万円の削減にしかならないという試算結果でしたので、おっしゃったように封筒の印刷代などを含めれば、それほど大きな削減にならないことは認識していました。ただ、封書ではなく別の方法でも入場券について削減していく手段があるかもしれませんので、いろいろと検討を重ねていただくようお願いしたいと思います。
次に、期日前投票の事務の簡略化についてお伺いします。
公職選挙法施行令第49条の8として、期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書の規定があります。本市では、期日前投票所において宣誓書を記入し、提出することとしています。しかし、投票所入場券に宣誓書記入欄を設け、あらかじめ自宅で記入できるようにしておくことで、投票の際の受け付けに係る事務の簡略化と、障がい者など字を書くことが苦手な方への配慮を進めるべきではないでしょうか。
このことは既に平成23年に先輩議員が一般質問で取り上げており、平成26年には宣誓書をホームページからダウンロードできるようになっています。しかし、ダウンロードの利用者の割合は低水準にあります。今では多くの自治体で入場券への記載という形が取り入れられています。
そこで、小項目2 期日前投票の受付事務の簡略化のため、投票所入場券に宣誓書記入欄を設けるべきについて選挙管理委員会委員長にお伺いいたします。
選挙管理委員会委員長
本市の投票所入場券ははがきサイズであり、裏面には注意事項を記載しているため、スペースの関係上、宣誓書の印刷までは現状では難しいと考えております。仮に宣誓書を裏面に印刷したものに選挙人が記入して投票に来られたときに、宣誓書を記入する時間が短縮される一方で、投票用紙交付受付の前に行列をつくることが想定されます。
これらの問題と、入場券レイアウト変更の経費について解消できれば、宣誓書記入欄を設けることは可能であると考えており、もう少し検討する時間をいただきたいと考えております。
吉田
御存じのように、多くの自治体の選挙において取り上げられていますので、ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。
ここでお聞きしたいのですが、もし投票所入場券に宣誓書の欄を設けた場合、宣誓書の欄にあらかじめ名前や住所を印字して送付することについては、今の法整備ではいかがなっているのでしょうか。
選挙管理委員会事務局長
宣誓書の欄にあらかじめ印字をして投票所入場券を送付することについては、印刷業者、関係者の方々との協議が必要と思われますので、経費などを十分に研究して、今後検討する必要があると考えています。
吉田
もともと投票所入場券には宛先があり、有権者の方一人一人の住所と氏名が印字された状態で郵便局から発送されますので、同じものを2回印字することで済むかと思いますが、ただ、法律上、自分でサインしなければならないとか、その辺の取り決めがあるかと思います。私、今回そこまではっきりと確認することができませんでしたが、もしそういう取り決めがないようでしたら、そのあたりまで利便性を高めていただいて、特に高齢者や障がい者の方がなるべく手間をかけずに投票所に行ける形にしていただきたいとお願いいたします。
次に、期日前投票所の増設についてお伺いいたします。
投票率の低下の現状ですが、世代別に投票率を分析しますと、70歳以上の方を別として、年齢が低いほど投票率が低くなる傾向が見られます。若い世代、働き手世代がより投票しやすい環境を整えていくためには、学生や勤め人の平日の行動範囲にある駅や大型商業施設などに期日前投票所を設けることが有効であろうと考えられます。近年、駅や商業施設はもちろんですが、大学などにも期日前投票所を設置する自治体があらわれてきています。本市における期日前投票所は市役所1カ所だけであり、投票時間も午前8時半から午後8時までに限られています。もし期日前投票所がふやされれば、投票の機会が広がり、若い世代ばかりでなく、全ての有権者にとっての利益となることでしょう。
そこで、小項目3 有権者の投票の機会を広げるため、期日前投票所をふやすべきについて選挙管理委員会委員長にお伺いいたします。
選挙管理委員会委員長
期日前投票所の増設については、近年の期日前投票の投票率の上昇傾向から早急な判断が求められるところです。課題として、二重投票防止のためのオンラインによる投票管理システムの構築や、個人情報の流出防止のためのセキュリティー対策、期日前投票所の安定的な確保、増設する期日前投票所の箇所数に比例して事務従事者も増員しなければならない等の事情があり、期日前投票所の増設は非常に難しい状況ではありますが、どのようにしたら実現できるのか、今後も研究していきたいと考えております。
吉田
委員長のただいまの御説明にもあるとおり、大変コストがかかるということは事実であると思います。今回私が提案したのは本当にささいな部分であり、実際にコスト削減につながるかといえば、そう簡単に進まないと思いますが、それ以外にもいろいろな面で選挙に係る事務には削減できる部分があろうかと感じています。そこも含めて今後検討を進めていただきたいとお願い申し上げます。
ここからは、県知事選挙に向けた対応ではなく、市で行われる今後の選挙の事務負担の軽減について提言させていただきます。
まず、投票方法についてです。
現在、市議会議員選挙及び市長選挙において、投票用紙に候補者の氏名を自書する記名式投票が行われています。この方式は、疑問票が多くなることや開票作業の時間が長くなるなどの傾向があります。
一方、あらかじめ候補者名が印刷された投票用紙に丸印を記入または押印して投票する記号式投票は、疑問票の減少や開票作業時間の短縮のほか、みずから文字を書くことが困難となっている高齢者や障がい者の投票の秘密を守る利点もあります。ただし、候補者数が多い議会議員選挙で記号式投票を行うと、最初に名前が書かれている方が有利になる順序効果が発生することが考えられるため、記号式投票を行っている自治体の多くは首長選挙だけにこれを導入しています。
そこで、小項目4 市長選挙で記号式投票を導入すべきについて選挙管理委員会委員長にお伺いいたします。
選挙管理委員会委員長
記号式投票を実施するためには、公職選挙法第46条の2第1項の規定により、条例で定める必要があります。
市長選挙に記号式投票を導入することで疑問票を少なくできる等のメリットはありますが、最初に名前が書かれている方が有利になる順序効果が発生する可能性があるといったデメリットもあると伺っております。
また、導入した場合、期日前投票の仕方や投票用紙の印刷方法の課題があると捉えており、ほかの自治体の状況も参考にして、今後十分な研究が必要であると考えております。
吉田
その十分な研究をぜひ重ねていただきたいと思います。やはり文字を書くことが苦手な方は実際にいらっしゃるわけです。そういう方たちがスタンプを押すだけ、丸印となるとまたこれも疑問票が出てくる可能性がありますが、そういう形で、できるだけ選挙に行ってストレスを感じないという方式を今後は目指していくべきではないかと思います。そしてまた、選挙に当たる事務の方たちの労力の面でも、疑問票があると大変時間がかかりますので、それを少なくしていくために、記号式はとても効果があろうかと考えます。いろいろな課題があるかと思いますので、その点についてぜひ検討を進めていただきたいとお願いいたします。
最後に、投票の通知についてお伺いいたします。
昨年の本市議会議員選挙では、開票が終わって当選人が確定すると、夜明けを待たず、直ちに担当職員が当選人の自宅や事務所に当選通知を届けておられました。御存じのように、市議会議員選挙の季節は真冬でした。通知を配達して回る職員の安全と健康状態が気がかりでしたし、私自身も早く休んで翌朝に備えたいというのが本音でした。担当の方から通知が届いたのは深夜1時半ごろだったと記憶しています。
通信技術の未発達な時代とは異なり、候補者は小さい時間差で開票速報を知ることができます。そして、夜が明けてから配達しても結果が変わるわけではありません。私は、個人的にこの通知のあり方はいささか古めかしく、職員が労力を削るのであればより生産的なことで削るべきであろうと考えています。
そこで、小項目5 当選者への通知は深夜に行わず開票翌朝に行うべきについて選挙管理委員会委員長にお伺いいたします。
選挙管理委員会委員長
職員への御配慮、本当にありがとうございます。
公職選挙法第101条の3第2項の規定により、当選人が定まったときは「選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない」と明記されていることから、選挙管理委員会では、従来、当選人に対し、直ちに告知をしている現状です。
吉田
直ちにという言葉も、もちろん直ちになのですが、翌朝は、直ちには含まれないのかなと、その辺ももう少し柔軟に捉えていただければいいのではないかと思います。ほかの自治体の例などもいろいろと検討しながら、今後課題として捉えていただきたいとお願いいたします。
続いて、大項目2 閖上小・中学校の教育計画についてお伺いいたします。
閖上小中一貫校の開校まで残り1年を切っています。校舎の建築は予定どおり進捗し、教育計画の策定も順調に進んでいるようですので、仮設校舎で学ぶ児童生徒たちが新築の校舎で学べる日が来ることを私もわくわくしながら待っています。
ただ、さきの2月定例会でも御指摘があったように、心配されるのが児童生徒数です。このことは、私も昨年の2月定例会の一般質問で取り上げました。その際、児童生徒が充実した学校生活を送れるだけの人数確保が困難であることを理由に、人口分布と児童生徒数の長期的見通しを踏まえた上で計画を見直すべきという提案をさせていただきました。この質問に対し、当時の佐々木市長と瀧澤教育長から、計画の見直しは考えていないとの御答弁をいただきました。そして、その際の説明に基づき熟考を重ね、小中一貫校の校舎建設のための経費を含む平成28年度予算に賛成した次第です。
そこで、賛成した以上は市内全域から児童生徒が安心して通えるための具体的な提案を行わなければならないと悩みながら約1年、先日、教育委員会から、平成30年度閖上小中学校入学希望者・検討者人数一覧が示されました。入学希望者は、1年生から6年生までが56名、7年生から9年生までが33名、合計89名とのことです。2月定例会で御説明のあった合計84名からふえており、喜ばしく感じています。
また、それ以上に注目すべきが入学検討者数で、こちらは9学年を合計すると171名とのことです。この方たちが今、入学検討で踏みとどまり、入学希望までまだ至っていない理由としては、通学の問題、生徒数の問題、部活動の問題など、さまざまな要因が挙げられることでしょう。これら要因を除去することは非常に難しく、これから申し上げる私の提案は突拍子もないものと受けとめられるかもしれませんが、閖上小・中学校を活気あふれる学校にするために御検討いただければ幸いです。
では、まず、一貫校の生活時程についてお伺いいたします。
一貫校の教育計画によると、登校は午前8時15分までと定められています。これは全国の一般的な小中学校の登校時刻と大きく異なるものではありません。しかし、例えば相互台地区から公共交通機関を使って通学する場合、名取駅までなとりん号で約1時間かかります。今年度の時刻表を参考にすると、始発便が名取駅に到着するのは午前8時18分となっており、名取駅から学校に向かうスクールバスどころか、登校時刻にも間に合いません。来年の時刻表改定でこれが改善されるかどうかは見通せない状況です。そこで、発想を逆転させ、バスの時刻を登校時刻に合わせるのではなく、始業時刻を遅くしてはいかがでしょうか。
小項目1 遠距離通学者への配慮として登校時間をおくらせ、年間計画の工夫等により授業時数を確保すべきについて教育長にお伺いいたします。
教育長
多くの児童生徒が閖上小中学校に通うことができるような条件整備については、非常に大事なことだと感じております。
ただ、始業時刻をおくらせることにより、共働きの家庭においては、保護者の出勤後に児童生徒が家庭で1人、あるいは子供だけになることが想定され、安全面では好ましいことではないと考えます。
また、始業時刻をおくらせることは、1日当たりの授業時間が圧迫されることになります。現在も年間を通しての授業時間の確保は非常に厳しく、長期休業中に授業日を設定する場合には、学校外の行事との調整も困難が予想されます。
以上の点を考え、始業時刻をおくらせることは考えておりません。
吉田
本当にほかに前例がないような提案なので、そのような御答弁になることは予想していました。ただ、あえてもう一度お伺いしたいのですが、児童生徒が始業時刻前に学校に行ってはいけないということはないのですね。家が近い児童生徒は始業時刻前に行ってしまう、午前8時前には学校に行ってしまうと。1時間目が始まるのがただ遅くなるだけで、それまでの間、いろいろな学校内の活動はできると思うのです。
そして、学校の先生方の勤務時間について確認すると、出勤時刻は午前8時15分、退勤時刻は午後4時45分となっていますが、多くの先生方は出勤時刻以前に学校に来られているのが現状のようですので、先生方の勤務時間については大きな変更は必要ないかと思います。
今、夏休みなどに塾に通う児童生徒も多くなっている社会状況ですので、夏休みについても教育委員会で日程を変えることで、夏休みに授業を行って、わざわざ塾に行かなくても学校に行って先生に勉強を教えてもらえるというような形で1年間のスケジュールを調整していくことについては、いかがお考えでしょうか。
教育長
ただいま幾つかの点をお話しいただきました。
まず、決められた登校時刻、今は午前8時15分始業ですが、児童生徒がそれより早く来ることを制限しているわけではないのではないかという趣旨のお話がありました。現在、多くの学校では始業は午前8時15分前後ですが、登校時刻をおおむね午前7時半以降としている学校が多いかと思います。ただ、実態として、保護者の方が両親とも仕事で家をあけるという場合、早目に登校する児童生徒がいるという実態があります。それが、登校時刻が遅くなれば遅くなった分、多くの時間、家庭で1人で待っているか学校に早く来て過ごすということになろうかと思います。
それから、先生方の勤務時間についてもお話がありましたが、午前8時15分から午後4時45分という基本的な勤務時間になっています。確かに先生方はもっと早く来ていますし、遅くまで残っています。ただ、それは正規の勤務時間以外に仕事をしているということで、そこを前提として児童生徒の活動を設定することはできないものと私は考えています。
また、夏休みの活用についての御提言もありましたが、今、小学校、中学校の年間の授業日数は200日前後となっています。卒業する小学6年生、中学3年生は200日を若干下回りますが、そうすると、始業時刻をおくらせることによって1時間目の授業ができなくなった場合、年間200時間を新たにどこかに生み出さなければならないことになります。その場合、現在、夏休みは、曜日の関係もありますが実質的には36日から38日程度になっています。土日を除くと約25日です。1日5時間、授業をすると125時間の授業ができますが、夏休み全てをお盆も含めて授業日にしたとしても200時間は生み出せません。冬休みと春休みも全て授業日にしても確保できるかどうかという状況にあります。さらに、平成32年度からは、小学校の3年生以上で週1こま、授業がふえます。年間で35時間です。
そういったことも考えると始業時刻をおくらせて年間の教育計画等で工夫をすることは現実的に無理ではないかと考えています。基本的には現在の始業時刻をベースに、閖上小・中学校においても教育計画を作成することが妥当ではないかと感じています。
吉田
私も無理であろうという前提でいろいろと頭をひねって考えた結果でした。1時間、授業がなくなってしまうと捉えるか、あるいは6時間授業を午前3時間、午後3時間とし、一番最後の時間を例えば体育の時間にすれば、そのまま部活動ができると。いろいろな意味で時間の調整はできるかと思いますが、無理というお話ですので、これ以上粘らずに次に進みたいと思います。
小中一貫校の修学旅行についてお伺いいたします。
昨年6月定例会の一般質問で、格安航空を利用した修学旅行の実施が可能となるよう関係機関との間で必要な調整に取りかかるべきと提案しました。ちょうど1年が経過しました。
閖上小中一貫校の教育計画には、修学旅行について、首都圏での研修を通して日本の政治、経済、文化についての見聞や理解を深めるとの記載があります。国会議事堂などは確かに首都圏にしかなく、中学生の段階で訪れることに意義があることも理解できますが、修学旅行で絶対に首都圏を訪れなければならないという法の定めはありません。大人数であればさまざまな制限が生じますが、少人数は小回りがきくという利点もあります。教育旅行という本来の趣旨に沿った上で、特色ある修学旅行を計画し、新たな魅力に加えてはいかがでしょうか。
小項目2 修学旅行を首都圏方面に限定せず、飛行機の利用等特色ある行程の設定を認めるべきについて教育長にお伺いいたします。
教育長
学習指導要領では、旅行・集団宿泊的行事の狙いを「平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこと」としております。
来年度開校の閖上小・中学校では、自主研修を通して自分の設定した学習テーマについて主体的に学び調べ、現地調査や見学、聞き取りを通して課題解決する力を身につけること、また、集団生活・行動を通して、友情を深め、集団生活のルールやマナーを学ぶこと、さらに首都圏での研修を通して、日本の政治、経済、文化についての見聞や理解を広めることを目的として、関東方面への修学旅行を実施する計画を立てております。
中学3年の社会科公民的分野においては、政治、経済、社会生活にかかわる学習をしております。政治や経済の中心である首都圏には関連する施設等も多く、体験的に学習することが期待できます。また、社会科だけでなく、9年間で学習してきた事柄についても見聞できるものもあります。
修学旅行を含めた教育課程の編成は校長の職務権限で行われており、教育委員会で旅行地を限定しているものではありませんが、修学旅行先として首都圏を設定していることは適切であると捉えております。
吉田
特色を求めていくのはなかなか難しいものだと実感しています。
次に、小中一貫校の部活動についてお伺いいたします。
部活動は教育課程外であるものの、生徒にとっては学校生活の中で特に比重の大きい活動です。また、高校入試の選考においても部活動の成績が評価される場合があることから、好きな種目に安定して取り組めることが学校においての安心の一つにつながるのではないかと考えます。このことに配慮してか、小中一貫校の教育計画には、市内の他の中学校と合同チームをつくり大会に参加との記載があります。
そこで、小項目3 部活動における他校との合同チームを想定しているとのことですが、具体的な方法を教育長にお伺いいたします。
教育長
合同チームについては一つの選択肢として教育計画にも載っていますが、それを必ず推進するということではないことをまずお断りした上で答弁させていただきたいと思います。
他校との合同チーム編成については、「宮城県中学校体育連盟主催大会における複数校合同チーム参加規程」により条件が定められております。
合同チームが承認される種目は、バスケットボール、サッカー、ハンドボール、バレーボール、軟式野球、ソフトボールの6種目となっております。
合同チーム編成は、同一郡市中体連において、部員数が試合人数に満たない単独チーム編成が困難な2校以上で編成する合同チームや、単独校でのチーム編成が可能な学校が試合人数に満たない学校を吸収して編成する準合同チームがあります。合同チームは、当該種目の専門部と相談した上で、それぞれの校長が認め、定められた手続が行われての編成となります。
部活動の種目は学校で定めるものですが、来年度開校の閖上小・中学校では、現在ある種目を基本としながら、在籍数等を考慮して種目を決定していくこととなります。閖上小・中学校では、市中総体終了時点の部員数により合同チームの編成も想定していますが、さきに述べた条件を踏まえ、定められた手続が必要となります。
吉田
その定められた手続を進めて合同チームが編成されたとしても、やはり違う学校の生徒同士が同じ場所で練習するとなれば、移動のための時間、あるいは指導する顧問の先生が生徒全員の性格や特性を把握できるかどうか、そのような問題点も考慮していかなければならないと思います。やはりできるだけその学校単独でチームをつくっていけることが一番望ましいのではないかと思います。それでも、どうしてもだめなときは合同チームという手段もあろうかと思いますが、そのような観点で考えていきたいと思います。
中学校の学習指導要領の第1章総則の4の2には、「生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、(中略)地域や学校の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすること」とあります。ことし4月に文部科学省によって制度化された部活動指導員を活用することで、この運営上の工夫が行えるのではないかと考えています。
一般的に部活動指導員は外部コーチのように捉えられていますが、私が提案したいのは、高い技術を持っているようなコーチではなく、自分の特技を生かして地域の子供たちを育てていきたいという住民の方が参画できるような部活動の姿です。学校という枠を超えて地域住民が老若男女問わずにスポーツや文化をともに楽しむという意味で生涯学習に近いかもしれませんが、大会に出場できるだけの部員数を確保できない部がもしあったとき、また、遠距離通学の生徒、時間的に制限される生徒についても、部活動指導員の活用方法によってさまざまな支援ができる可能性が見えてくるのではないかと考えたところです。
そこで、小項目4 部活動指導員に係る規則等を整備し、指導員の活用によって、生徒が部活動を通じ自己実現を果たす機会を広げるべきについて教育長にお伺いいたします。
教育長
ただいま議員御指摘の部活動指導員については、私も中学校の先生の負担軽減などの観点からも非常に注目しているところです。部活動指導員は、平成29年4月1日施行の学校教育法施行規則の一部改正により、学校における部活動の指導体制の充実が図られるように、その名称と職務が明示されました。
改正された規則では、部活動指導員は、校長の監督を受け、技術的な指導に従事することが職務とされており、部活動の教育的意義と学校や各部の活動の目標や方針を熟知すること、指導や事故対応に当たっては顧問や指定された教諭と連携することが求められています。また、学校の設置者が部活動指導員に係る規則等の整備をすることとされております。
部活動指導員ではありませんが、運動部に限ると、現在、県教育委員会の運動部活動外部指導者派遣事業の外部指導者を本市においても活用しております。平成29年度は、運動部活動外部指導者派遣事業の外部指導者は、市内で9名認定されています。ほかにも学校で指導していただいている指導者がいます。
教育委員会としても、文部科学省や県の教育委員会の動向を注視しながら、有意義な部活動となるよう対応していきたいと考えております。
吉田
今の御答弁では、県の外部指導者が平成29年度は市内で9名ということです。外部指導者は県の事業ですので、市から県にお願いする形で県で認められなければならないので、人数については制限があり、範囲がかなり狭くなっているのが現状ではないかと思います。この範囲をもう少し広げて、より多くの方に学校の部活動に参画していただくためには、市として単独で新たな部活動指導員という形で進めていくことが今後の望ましい対応ではないかと考えます。ただ、今の御説明の中で、学校の教員と同じくらい詳しく、さまざまな知識を持っていなければならない、責任も生じてくるとなると、そう簡単に名乗りを上げられないという現状もあるかと思いますので、今後、その点も含めて検討を進めていただきたいとお願いいたします。
続いて、大項目3 職員と利害関係者等との接触についてお伺いいたします。
今、国会では、学校法人森友学園や学校法人加計学園と政権との関係について激しい議論が繰り広げられています。この動きがなかなか収束しない理由には、公の財産の管理において公平性と透明性が確保されていないのではないかという国民の疑念に対し、政権が説明責任を果たし切れていないこともあるのではないかと個人的に捉えています。
公の財産を扱うという意味では、規模の違いこそあれ、自治体にも国と同様に公平性と透明性の担保、そして説明責任を果たすことが求められています。当然、本市にも公金の支出や公有財産の管理・処分において同じことが言えるはずです。本市職員の皆様が高い倫理意識をお持ちであることは承知していますが、もし利害関係者等から飲食の提供などを呼びかけられたとき、どのような行動をとればよいのか、あるいはとってはいけないのか、判断に苦しむこともあろうかと察せられます。行動を一つ誤ることが、公平性が損なわれた、密室で物事が決められたと批判され、市民の信頼を失うことにつながりかねないと考えられます。まずは現状を確認させていただきたいと思います。
小項目1 職員が利害関係者等と接触することに関する規定の整備状況を市長にお伺いいたします。
市長
職員が利害関係者等と接触することに関する規定については、市独自の規定は設けていない状況です。 地方公務員法及び名取市職員服務規程に基づき、市民全体の奉仕者としての自覚と常に公正な職務の執行に当たるよう指導してきました。毎年年末には、綱紀の厳正な保持について、職務上利害関係にある者との会食、贈答品の授受等、市民の疑惑や不信を招くような行為は厳に慎むよう、全課に対し通知をし、全庁的に徹底を図っているところです。
吉田
今の答弁ですと、疑念を招くかどうかを職員は御自身で判断していかなければならないと捉えられます。国家公務員倫理規程などもありますので、恐らくそれに準じた形での行動規範になるのかと思いますが、先ほど申し上げたように、本当にどうしたらいいのかわからない、きわどいケースの場合、例えば国家公務員倫理規程では、倫理監督官に相談してその指示に従うことになっています。本市において、もしそういう事例があった場合はどなたに相談することが考えられるのでしょうか。
総務課長
基本的には所属長が判断することとなっています。
吉田
所属長に相談して判断を仰ぐということで、承知しました。
そのように実際に規程に抵触しない場合でも、市長にとって職員は頭脳であり手足ですので、そのような方が利害関係者と接触した場合、市民から説明責任を求められた際に、それにしっかり応じられるよう備えておくことが必要ではないかと考えます。
そこで、小項目2 管理職と利害関係者等との接触について、上司に報告する範囲を明確にすべきについて市長にお伺いいたします。
市長
先ほどの答弁でも申し上げたとおり、本市において職員が利害関係者等と接触することに関する規定は設けていない状況です。
議員御指摘の職務の執行の公正さに対する疑惑や不信を招かないように努め、公務に対する市民の信頼を確保することは、公務員として当然あるべきものです。御提案の部分については、他自治体を参考にしながら調査研究を行っていきたいと考えております。
吉田
実際にこういう規程がつくられる自治体は何か問題が起きてから取り組むのが多いかと考えられますが、行政として、市民に対しての説明責任は一番大事にしていかなければならない部分であると思いますので、そのあたりは今後検討していただきたいと考えているところです。
実際にこういう規程がつくられる自治体は何か問題が起きてから取り組むのが多いかと考えられますが、行政として、市民に対しての説明責任は一番大事にしていかなければならない部分であると思いますので、そのあたりは今後検討していただきたいと考えているところです。
利害関係者等の中にどういう人が含まれるのかについて、例えば__はどうなのか、あるいはいろいろな団体に所属する人はどうなのか、こういうことも何かしら規程の中に盛り込んでおかなければならないのではないかと感じます。____________________________________________________________________________________________________。そのあたりも御検討いただければと思うところです。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
小野寺美穂議員
__がどうして出てくるのかわかりません。国家公務員の倫理保持のためのルールで利害関係者というのは明確に示されていますし、______は利害関係ではありません。___________________________________________________________________________________、そこをきちんとしていただけませんか、議長。____________________。
議長
ただいまの小野寺議員の議事進行に対して見解を申し上げます。
確かに小野寺議員のおっしゃるとおりでありますので、その辺のところについて取り消しして、質問を続行していただきたいと思います。議長権限で取り消しさせていただきたいと思います。
吉田
では、最後に、大項目4 いじめの現状と対策についてお伺いいたします。
隣の仙台市において、わずか3年余りの間に3名もの中学生がみずから命を絶つという痛ましい事件が続きました。いずれも学校におけるいじめが自殺の引き金になったと指摘されていると伺っています。いじめを根絶することは非常に難しい、いじめはいつどこででも発生する可能性があるという前提で、教育現場は常に対策を講じておかなければならないと思います。もちろん本市もその例外ではないはずです。
平成28年9月の財務常任委員会において、平成27年度のいじめの状況は認知件数で小学校20件、中学校62件であり、小学校の20件中19件と中学校62件中48件が解消、残る小学校1件、中学校14件については見守りを継続している状況であるとの御説明がありました。また、いわゆる重大事態に該当する事例はなかったとのことです。その後、半年以上が経過しています。見守りを継続するとしていた案件の経過も含めて伺います。
小項目1 市内小中学校におけるいじめの現状把握について教育長にお伺いいたします。
教育長
いじめの現状把握の方法として、各学校においては月1回のアンケート調査を全小中学校で行っています。担任や教職員の日常的観察のほかに、個別面談、個人ノート、家庭訪問等を活用し、いじめの把握を行っております。
次に、平成28年度における市内小中学校のいじめの概要について御説明いたします。まず、いじめ防止対策推進法に示されている重大事態はありませんでした。また、いじめの認知件数については、小学校では30件、中学校では50件、計80件でした。うち、解消しているものは70件、解消に向けて継続指導しているものは10件です。いじめの態様については、小中ともに冷やかしが多く、全体の半数以上に当たります。
いじめの認知については、小さないじめも見逃さず認知することで、早期発見・早期対応につながるよう今後とも努めていきたいと考えております。
吉田
教育現場では、先生方が非常に努力されて、いじめの問題に取り組んでおられることかと思います。ただいまの御答弁に小学校、中学校のいじめ認知件数が合計80件とありましたが、その中で、特別支援学級に通うような生徒がかかわる件数は報告があるのでしょうか、お伺いいたします。
学校教育課長
特別支援学級に在籍している児童生徒の数についてはっきり把握しているところではありませんが、ここに上げられている80件については、一件一件、全て個別の名称で教育委員会では把握しているところです。その中で、大半は通常の学級に通っている児童生徒と捉えています。
吉田
なぜそのようなことを伺うのかというと、今、文部科学省では、インクルーシブ教育システムの構築を推進していると伺っています。以前であれば学校生活のほとんどを特別支援学級で過ごしていた児童生徒に、通級によって通常の学級で指導を受ける機会をふやし、障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒ができるだけ同じ場でともに学べるようにすることを理想とするという考え方だと思います。一方で、障がいを持っている児童生徒に対しての差別や偏見などが生まれ、それがさらにいじめに移ってしまうことがないかということが懸念として拭い去れない部分ではないかと思います。もちろんそのような偏見をなくしていくことこそがインクルーシブ教育の推進の目的であろうと捉えられるところですが、やはり障がいのある児童生徒も含めて全ての児童生徒を守るための対策を、それぞれの現場に合わせてとっていただきたいとお願いさせていただきます。
今御答弁にあった認知件数についてはもちろん把握されている分ですので、把握できていない部分、漏れている部分、認知されていない部分がないかということが懸念されます。現場がつかみ切れない部分があることも想定しておく必要があると考えるところです。
次に、いじめも含めた教育現場の責任の所在についてお伺いさせていただきます。
仙台市の事例で、当初教育委員会がいじめの事実を認めなかったことが、その後のいろいろな混乱につながっていったと伺っています。このような混乱を招いてしまった要因の一つに、学校現場における最終的な責任の所在が、今の法整備ではどうやら不明確ではないかということが挙げられると私は感じています。いじめなどの深刻な事態を予期するためには、まずは責任の所在を明らかにしておくことが一定の効果を持つものと思うところです。
そこで、小項目2 いじめによる自殺事案等の問題に対し、誰が最終責任者であると捉えているのか、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
いじめ問題に対する市の方針として、教育委員会と連携して、名取市いじめ防止基本方針を平成26年3月に策定しております。その中で、「市長及び市教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずる」とありますが、私としては、最終的に責任を負う覚悟を持って取り組んでいるところです。
今後も、教育委員会と協力し、いじめや自殺の防止に努めるとともに、いじめ問題等への適切な対応をしていきます。
教育長
いじめ防止対策推進法においては、国、地方公共団体、学校の設置者、学校及び学校教職員、保護者、それぞれの責務が示されております。
いじめによる自殺事案等の問題についても、各立場、組織において、それぞれ果たすべき役割と責任があると考えます。それぞれが連携しながら、いじめや自殺防止に努めるとともに、万が一自殺が起きた場合は、法令の趣旨を踏まえ、その対応を確実に丁寧に行いながら、その責任を果たしていくことが大切であると考えます。
教育委員会としては、市長と連携しながら、最後まで責任ある対応をとっていきたいと考えております。
吉田
今の御答弁ですと、市長も教育長も、それぞれ最終的に責任を果たしていきたいということで捉えたところです。
平成27年9月定例会において、私はこのときはまだ議員ではありませんでしたが、会議録を読ませていただき、いじめによる自殺事案等の問題に対し、国が最終的な教育行政の責任を果たせるという御答弁があったと確認しました。その点については、国に最終的な責任があるのではなく、やはり市長と教育長それぞれ、御自身に最終的な責任があると捉えてよろしいのでしょうか。お二人にお伺いいたします。
市長
私の気持ちを申し上げたわけですが、前段申し上げたとおり、まず、いじめ防止対策推進法には、地方公共団体、学校の設置者、学校及び学校教職員、保護者の責務がそれぞれ定められており、それぞれがその責任と権限の中でしっかりと対応していくことが基本になっていると捉えているところです。
教育長
国に責任があるというのは、例えば国家賠償法等で考えれば、国や地方公共団体が賠償責任を負うという法的な定めはあるかと思います。ただ、仮に本市において児童生徒がいじめを一つの要因としてみずから死を選ぶという行為があった場合には、まず、国とか何かというより前に、それぞれの立場においてきちんと責任ある対応をとることが大事だと思いますし、私としては、教育行政を預かる教育委員会の代表者として最後まで責任を持って対応していきたいという思いでおります。
吉田
非常に力強いお言葉であると思います。今の市長、教育長の思いをもって、リーダーシップをもって、学校教育現場も含めて、児童生徒全員、一人一人の命をしっかり守っていくように、これからも取り組みを続けていただきたいと思います。
そこで、具体的にいじめ防止の体制についてお伺いしたいのですが、昨今ではインターネットの発達とスマートフォンの普及がいじめのあり方に大きく影響してきているのではないかと感じられるところです。インターネットは便利で楽しい道具である反面、保護者や教師の目が届きにくい世界がそこにあります。ネット上で集団からおとしめられる、あるいはグループから排除されるということが実際に起きています。これは大人でも恐怖を感じることだと思います。人生経験の少ない児童生徒にとってはなおさらのことであると察せられます。これからのいじめの防止対策には、やはり児童生徒たちがインターネット上でどのような行動をとっているのか、これはプライベートな空間でもありますから非常に難しいかと思いますが、学校や保護者が積極的に関与しながら把握に努めることが欠かせないものになるのではないかと考えています。
そこで、小項目3 児童生徒によるSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)等のインターネット利用について、情報収集と指導の現状を教育長にお伺いいたします。
教育長
平成28年4月、小学校6年生、中学校3年生を対象に行われた全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙の結果によると、本市の児童生徒の携帯電話やスマートフォンの所持率は、小学校6年生では全体の約6割、中学校3年生では7割5分という結果でした。また、インターネット、メールや通話の時間については、小学生も中学生も30分より少ないと回答した児童生徒が一番多く、それぞれ全体の約2割近くになります。
これは一つのデータですが、このような利用状況も踏まえ、各学校においては、情報教育を推進する中で、情報モラルについても指導するように努めております。担任による指導のほか、NTTや岩沼警察署などから外部講師を招いて児童生徒、保護者に情報モラル教育を実施したり、お便り等で家庭にも呼びかけたりしている学校もあります。
SNS等がきっかけでトラブルやいじめにつながることもあるので、今後も情報モラル教育の推進に一層努めていきたいと考えております。
吉田
やはり学校の取り組みだけではどうしても賄い切れないのがこのインターネットの問題だと思います。家庭の協力なしには児童生徒の状況の把握は大変困難です。そのようなことで、今、保護者の協力を得ながら進めている学校も実際にあると伺いましたが、今後、市全体としてそのようなことを進めていくという方針はお考えではないのでしょうか。
教育長
基本的には各学校の計画に基づいて、ただ、情報モラル教育にきちんと取り組んでほしいということは、常々、校長会、教頭会等でも申し上げています。ただいま御指摘がありましたように、保護者にも御理解をいただくという意味で、ある学校では、中学校入学を機にスマートフォン、携帯電話等を利用する生徒も多いことから、小学校卒業が間近になった時点で、保護者と児童に情報モラルの指導をしています。そういった例なども紹介しながら、各学校での取り組みを推進していただきたいと考えています。
吉田
いじめがなるべく起きないようにということで、今のインターネットの利用も含めて、今後も取り組みを進めていただきたいとお願いいたします。
そこで、最後の質問として、実際いじめが起きてしまったときの対処についてお伺いいたします。
いじめの根絶は非常に難しいと考えています。教師の目が届かない場所で行われるケースもあれば、解決したと思われる事案が再発するケースもないわけではありません。教師や、例えば警察などが介入したとして、その場で解決したと処理されても、事態がより悪化するケースは幾らでも考えられます。いじめに苦しむ児童生徒を救うために、いじめから逃げるということを自然に受け入れられるような雰囲気と制度をつくっていくことが必要ではないでしょうか。
今、欠席数が入試の合否判定にどの程度影響を及ぼすのかということも、保護者はよくわかっておりません。余り欠席し過ぎると入試に影響があるのではないかと感じている方もおられます。本当のところどうなっているのか、私も存じておりません。このようなこともあり、実際にいじめを受けていて、逃げたくても逃げられない児童生徒がいることも考えられます。
念のために申し上げますが、私は不登校を推奨しているわけではなく、無理をして登校するよりも、まず命を守ることが最優先であるという観点で捉えていただきたいとお願いいたします。
ここで、平成28年7月28日の産経新聞「朝の詩」に掲載された、当時本市在住13歳の女子生徒による「逃げ」という詩の全文を読み上げます。
逃げて怒られるのは
人間ぐらい
ほかの生き物たちは
本能で逃げないと
生きていけないのに
どうして人は
「逃げてはいけない」
なんて答えに
たどりついたのだろう
小項目4 いじめから身を守るための欠席は、一定の条件を満たせば出席扱いとすべきについて教育長にお伺いいたします。
教育長
いじめも含めて、児童生徒の生命、身体を守ることを最優先という認識は、私も同じです。
いじめにより登校が困難な児童生徒については、学校、保護者、関係機関と連携しながら問題解決を行い、児童生徒が安心して登校できるよう努力していくことがまずは大切であると考えております。いじめにより登校できない場合の出席扱いについては、一定の要件で認めることができますので、事案に応じて対応していきたいと考えております。
吉田
その一定の要件については、実際にそのようなケースがあった際に、本人や保護者がしっかり把握できるような体制ができているのでしょうか。
教育長
教育委員会に相談があった場合には、もちろんこういった取り扱いもできるということは周知しています。
また、文部科学省等でもいろいろなサイトやパンフレットの中で、いじめに限ったことではなく、どうしても学校に行けない児童生徒がいる場合に、学校復帰を前提とはしつつも、一定の条件、例えば保護者と学校がきちんと連絡をとり合っているとか、あるいはきちんとした計画のもとに学習が行われているとか、最低週1回程度教師が面談をしているとか、幾つかの条件はありますが、そういった中で、指導要録上、出席扱いにするという取り扱いはできます。
一方、いじめる側の児童生徒についても、その児童生徒が登校している状態でどうしてもいじめが解消できない場合には、いじめている側の児童生徒を出席停止にするという取り扱いをすることも可能です。
吉田
いじめている側もいじめられている側も同じ児童生徒であり、先生方にとっては皆かわいい子供たちです。私も教員経験がありますので、その気持ちは理解しているつもりです。先生方の仕事は、いじめられている生徒がいる、あるいは出席できない不登校の生徒がいるということで、これまで以上に仕事量がふえてくることになるかと思いますが、先生方の健康状態や精神状態も児童生徒に影響してくるところもあるかと思います。その管理の面も含めて、児童生徒一人一人の安全をこれからも確保していただきますように強くお願い申し上げ、私の一般質問とさせていただきます。
本会議
吉田
17ページ、7款1項2目商工振興費24節投資及び出資金に(仮称)閖上地区まちづくり会社出資金とあります。この内容をお伺いいたします。
復興調整課長
現在、閖上地区の名取川沿いに商業施設や飲食店などのにぎわい拠点を整備するということで、参加意向を持つ皆さんで設立準備会を立ち上げていろいろと検討を行っています。この施設の整備については国の補助金を財源として見込んでいるわけですが、交付の条件として実際の運営を行うまちづくり会社に対して補助をするという要件となっており、夏に向けて設立準備会をそのまま会社として設立します。それに対して設立準備会から市に出資要請があって、今回300万円の出資を計上しています。
吉田
300万円という金額は、あくまでも設立準備会からの要請にそのまま市で対応したということでよろしいのでしょうか。
復興調整課長
300万円は設立準備会からの要望金額です。にぎわい拠点は被災した方々の本格再建の場であり、閖上地区にお住まいの方の買い物の場にもなります。また、他の自治体においてはいわゆる交流人口拡大の機能も担っていますので、市としてもこのまちづくり会社が担う役割なども勘案して要望金額が妥当ということで計上しました。
吉田
17ページの7款1項4目観光費13節委託料で、先ほど貞山運河シンポジウムと御答弁の中にありましたので、それについて少し詳しくお聞きしたいと思います。先ほどの御答弁では7月29日開催の予定で1日のみという話でしたが、現時点で決まっている範囲で結構ですので、例えばどのような方々がパネラーで参加する見込みなのか、また会場、そして、もっと広くどのような組織を巻き込んでいくのか、そのあたりについて説明をお願いします。
復興調整課長
この予算を認めていただいた後にいろいろと詳細は動くと思いますが、現時点では、貞山運河研究所という貞山運河の研究を行っている団体があり、そこといろいろと連携を図っていきたいと考えております。それから、シンポジウムについては、基調講演とパネルディスカッションなどを名取市文化会館の小ホールを会場に考えていますが、学識経験者や旅行会社の方、地元の産業の方、そういったいろいろな識者の皆さんに集まっていただき貞山運河の活用等について議論をしていただければと考えているところです。
吉田
貞山運河は歴史的に非常に貴重な地域資源ですが、仙台市より北側にもずっと続いています。そちらの町や市で、やはり貞山運河を観光資源として有効に活用していくということで連携が随分進んでいると聞きました。今後、そのようなところとの北と南という形での連携はどのようにお考えでしょうか。
復興調整課長
まだ具体的な連携ということではありませんが、貞山運河の活用については宮城県が挙げて音頭をとっていて、平成28年ぐらいから貞山運河に関係する市町村会議のようなものが開催されるようになり、各自治体の取り組み事例などの発表や意見交換の場もできています。いずれこういった機会を捉えて連携が図られていくのではないかと思います。
吉田
資料1に街区公園6カ所とポケットパーク7カ所と2種類の公園の計画が示されています。それぞれの公園の役割の違いというか、例えば防災倉庫を設置するとすればこのような配置にするといった方針について現在何かありましたらお知らせください。
復興区画整理課長
まず公園の配置の考え方ですが、緑で示している街区公園については、6カ所設置する予定ですが、公園の基準がありまして、誘致距離が250メートルと地区の方々が歩いて利用できるような距離に設置することになっています。こちらは通常の街区公園ですから、子供からお年寄りまで利用できる遊具やベンチを置いたり、木陰をつくるといった整備になると思います。それに加えて、青い部分のポケットパークについては、過年度に閖上地区まちづくり協議会から、街区公園だけでなく、それを補完する意味で近隣の方がコミュニケーションをとるための井戸端会議程度ができるようなものをところどころにつくってもらいたいという話がありましたので、それを受けて整備を行うものです。ポケットパークは街区公園とは活用方法が違ってくると思いますので、ベンチ、また木陰をつくるような植栽程度を整備したいと考えています。
吉田
やはり公園は町内の行事等で拠点になる場所ですので、非常に重要な位置づけにあると思います。例えば町内の清掃活動などを行う際や芋煮会などの行事で水道があると非常に便利です。公園によってはトイレが設置されているところもありますが、そのような点についての現在の方針を伺います。
復興区画整理課長
公園のレイアウトについては、実施設計において精査を行う考えです。それから、かわまちづくりのにぎわい拠点等が出てきますので、そういった他事業との関連で、例えば近くに公園があるので水道やトイレが欲しいという要望が出てきた場合に、どの公園にどのような施設を配置するのかということについては今後関係者の皆様と協議して決めたいと思っていまして、現在案は持っておりません。
(議会案第3号 日本政府に核兵器禁止条約のための行動を求める意見書)
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長より発言のお許しをいただきましたので、議題となっております議会案第3号 日本政府に核兵器禁止条約のための行動を求める意見書に対し、反対の立場から討論を行います。
核兵器のない世界が戦時下の核兵器使用による惨禍を経験した我が国の願いであることは論をまちません。世界には、核を保有する国と保有しない国、みずからは保有しないが保有国に守られている国があることから、核兵器のない世界に向けたプロセスはいずれの国もが参加可能な実効性を持つものであることが必要と思います。日本政府は、核兵器保有国と非保有国の双方を巻き込んだ、現実的で実践的な措置を積み上げることを一貫して主張しています。この基本的立場のもと、国連総会において核廃絶決議を23年間連続で提出し、圧倒的多数の支持を得てきたことや、包括的核実験禁止条約の早期発効に向けて地道な外交努力と技術面、財政面での積極的貢献を尽くしてきたことは、唯一の戦争被爆国による対応として評価に値します。
核兵器保有国の協力なくして核軍縮の進展は不可能と思われます。日本政府は、新たな条約の作成については、NPT(核兵器拡散防止条約)等既存の核軍縮・不拡散体制を強化するものでなければならないとし、現実的な核廃絶に向けての貴重なバランスや土台を保持することが大切であるとの立場を示しています。しかし、本意見書は、日本政府が示す核保有国が参加しない形で条約をつくることは、保有国と非保有国の亀裂など国際社会の分断を一層深め、核兵器のない世界を遠ざけるものになるとの見解に対し、より説得力のある論理を展開できているようには思えません。
唯一の戦争被爆国に生まれた一人の人間として核兵器の廃絶を望む気持ちは、私も本案提出者と異なるものではありませんが、NPT体制の強化という現方針こそが、市民の生命と安全を守り続けるために今後も進むべき最善の道であると考えます。
以上、本案に対する私の反対討論とさせていただきます。