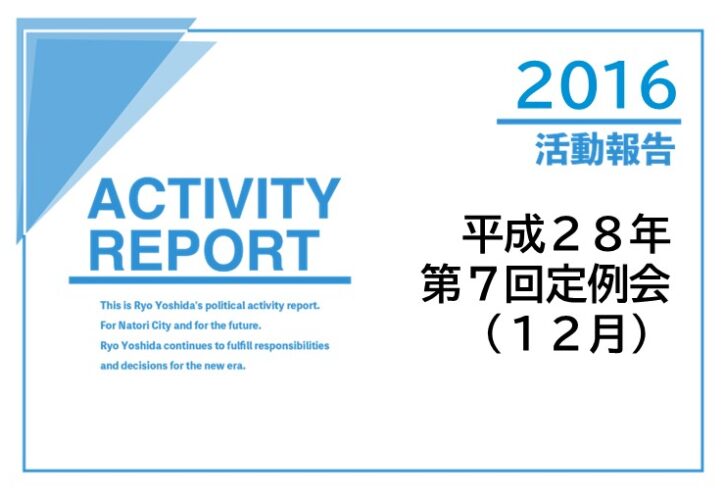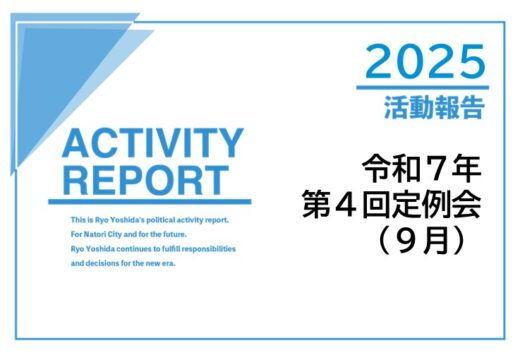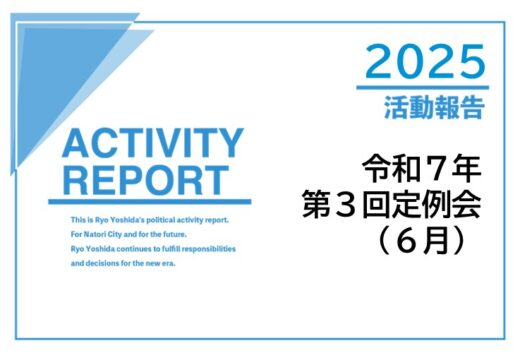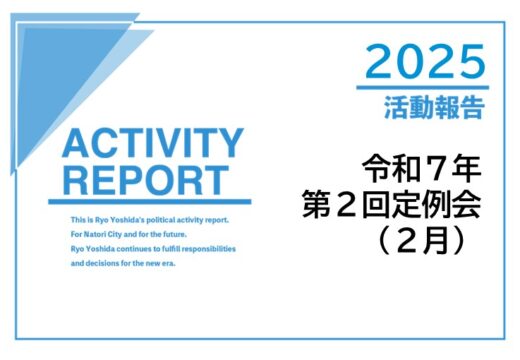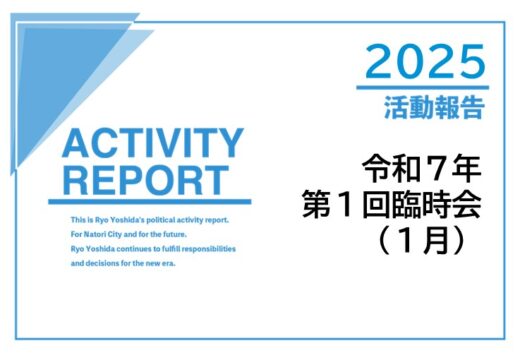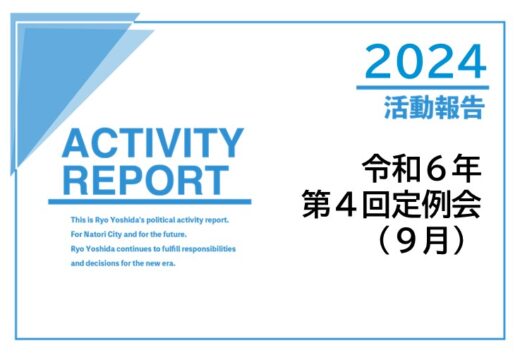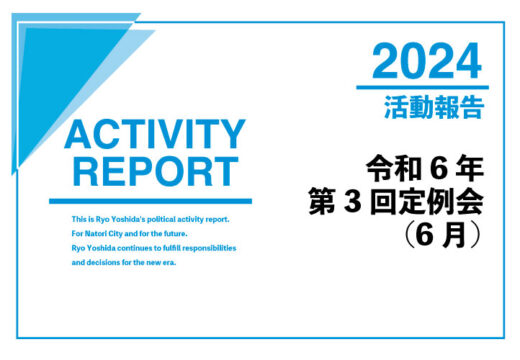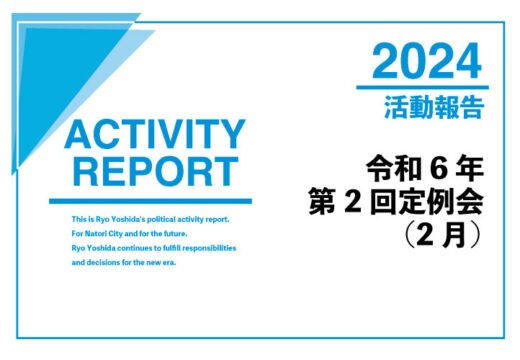一般質問
吉田
まず、大項目1 児童生徒の食育についてお伺いいたします。
国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことを目的として、平成17年に食育基本法が制定されました。その後、同法に基づき第1次食育推進基本計画及び第2次食育推進基本計画が策定され、10年にわたって食育が推進されてきました。その結果、家庭、学校、保育所等における食育は着実に進展してきております。しかし、若い世代では健全な食生活を心がけている人の割合が少なく、他の世代と比べて健康や栄養に関する実践状況に課題が見られます。また、大量の食品廃棄物が発生することによる環境への負荷も問題となっており、食品ロスの削減と環境にも配慮する必要があります。
本市の学校給食における食品ロス、つまり残食の割合は平成27年度は重量ベースで約2割に上るとのことです。汁物の重量が含まれているとはいえ、食育の観点からは改善を目指すべき数字であろうと考えます。
そこで、小項目1 給食の残食を減らす取り組みを行うべきについて教育長にお伺いいたします。
教育長
学校給食法の中には、学校給食の主な目標として、適切な栄養摂取による健康の保持増進を図ること、学校生活を豊かにし明るい社交性を育てること、給食を支えている方々や自然の恩恵について理解を深めること等が挙げられております。
これらを踏まえ、各小中学校では給食指導を計画に基づいて行っております。残食に関しては各校で減らす取り組みを行っていますが、具体的には、食べ物やつくった方への感謝の気持ちを育て、残すのがもったいないという心を持たせる、嫌いなものや食べなれていないものを一口でも食べ、食の幅を広げる、栄養について学び、バランスよく食べることの大切さを理解させる、栄養士や栄養教諭による食育の授業を通し、残さず食べることは元気につながることを理解させるなどの取り組みを行っています。
また、給食センターにおける残食を減らす取り組みとして、栄養士、栄養教諭が学校訪問し、食の傾向等の実態を把握すること、バイキング給食を行い、食べられる量やバランスを判断させること、小学5年生全員を対象にセンター見学を行い、食への理解と感謝の気持ちを育てることなどを行っております。
今後も学校や給食センターと連携しながら、給食を残さず、楽しく、バランスよく食べる指導を含めた食に関する指導を行い、給食の残食を減らす取り組みを行ってまいります。
吉田
ただいま教育長から御答弁がありましたが、各学校で具体的に、感謝する気持ち、もったいないと思う気持ちなどを育てたり、給食センターでも栄養士などが学校訪問等を行って、それぞれ取り組みが進められているということです。
しかし、その取り組みによって成果がどの程度上がっているか、いま一つ見えてきていないことが問題ではないかと思います。給食が残される理由は、今教育長もおっしゃいましたが、主なものとしては時間内に食べ切れないこと、好きではない、食べなれないなどということがあるかと思います。これらは児童生徒の成長とともに改善させることが学校に求められているのではないかと思います。小中学校それぞれの学習指導要領には、学級活動の内容として食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成という項目があります。この望ましい食習慣とは、規則正しい時間に食べることのほかに、栄養バランスや分量についても適切に食べることや、準備、後片づけを協力して行うことなども含んでいると解釈できます。こうした食習慣は児童生徒の成長とともに伸ばしていくべきものでありましょう。
そこで、児童生徒が給食に関するみずからの成長や課題を知るきっかけにするために、定期的に学校ごとの残食率を公表すべきではないでしょうか。給食センターの委託業者からは市に対し毎日業務日報が提出されて、学校ごと、品目ごとの残食の量が記載されていると伺っております。ホームページや給食だよりなどで残食率を公表することで、児童生徒が他校と比較し、残さず食べる努力に結びつくものと期待されます。そして、1年間の残食が最も少なかった学校を表彰したり特典をつけてあげたりしてもいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
教育長
子供たちに正しい食習慣を身につけさせ、食についての考え方をより深く認識してもらうことが大事であるということについては私も認識は同じです。
ただ、まず本市で把握している残食率についてお話をさせていただきますと、PFI事業者である株式会社名取学校給食サービスで毎日残ってきた残食を計量しています。残食率を計算する方法としては、提供した食事の重量からそのときに欠席した児童生徒の分を除いて計算するのが一般的ですが、本市の場合は欠席した子の分の把握までは行っていないのが現状です。それから、インフルエンザや台風等により臨時休業になって給食停止が間に合わなかった分の提供できなかった給食なども残食に含めて計算しています。そのようなことから、一般的に言われている残食率と同じように比較して考えることはできないものと思っております。
学校ごとの数字の公表という御提言ですが、先ほど議員からも御紹介がありましたが、残食率は前述した計算で本市では約20%弱という数字が出ています。ただ、例えば30人学級で1人欠席者がいた場合、本市では20%と出しますが、その1人の分を除くと残食率が約3%減ります。20人の学級の場合は約4.2%、10人学級で考えると約9%減ります。したがって、小規模校であればあるほど、本市ではかっている残食率に欠席者の与える影響が大きくなってしまいます。もちろん教育委員会あるいは給食センターでは、先ほどお話しした方法による残食率を学校ごと、献立ごとに把握していますが、どうしても大規模校ほど残食率が低くなる傾向があります。欠席者の影響が相対的に低くなることも関係しているかと思います。また、残食率自体を正確に出すことはかなり難しいということが1つあります。
それからもう一つ、残食を減らすことは私も非常に大事だと思います。ただ、残食を減らす、その数字を減らすことだけを考えると、本末転倒になってしまうようなことも起こりかねないという危険性を感じております。どういうことかと申し上げますと、ある栄養士といろいろとお話をしている中でその栄養士が話したことですが、残食を減らすには子供が好きなものを毎日出せば簡単に減らせる。例えばハンバーグやカレーライスなど。ただ、今家庭ではなかなか味わえないような、日本の伝統的な食文化も含めた豊かな食生活を子供たちに味わわせることも学校給食の大事な役割の一つであると。したがって、そういったものもあえて出して一口でも子供たちに味わわせる。そのような経験を通して子供たちの食生活を広げていくことも学校給食の大きな役割だろうと考えております。
ただ、先ほど申し上げましたように各献立ごとの詳細な残食率は把握しています。多く残った献立について、なぜ子供たちが食べなかったのかということはかなり分析をして、味つけを変えたり組み合わせを変えたりして少しでも多く食べてもらう努力は行っております。ですから、残食率という数字だけを重大視して考えることには私は少し問題があろうかと思っております。したがって、先ほど答弁したように感謝の心を持たせることやバランスよく食べることの大切さを今後も繰り返し指導し、そのことを通して少しでも残食を減らす取り組みは行っていきますが、学校ごとの残食率の数字の発表は考えておりません。
吉田
私も、教育長がおっしゃったように、子供の好きなメニューだけを出せばいいなど、そのような形での残食率の減少を申し上げているのではありません。今、給食センターのほうで、決められている枠の中で、メニューの中で子供たちに少しでも多く食べてもらうと。そして、今の御答弁では欠席の児童生徒の分については把握していないということでしたが、それも取り組もうとすればできることですので、ぜひ進めていただきたいと思います。残食率を短い周期で公表することは、給食費の納入者である保護者に対して学校の食育に対する取り組みの成果を知らせることにつながりますので、ぜひとも実現されるようにお願いしたいと思います。
では、次に移ります。学校給食の残食の処理についてです。
内閣府がことし策定した第3次食育推進基本計画には今後5年間に特に取り組むべき5つの重点課題が掲げられており、その4番目に食の循環や環境を意識した食育の推進とあります。本市では以前は給食残食のリサイクルが行われていましたが、東日本大震災以降は全てごみとして廃棄されています。学校で残食を少なくする取り組みを進めたとしても、ゼロにすることは困難です。やむを得ず発生してしまう残食を有効に処理することも重要な課題の一つであると考えます。
そこで、小項目2 給食の残食を有効活用するために、生ごみ処理機を導入すべきについて教育長にお伺いいたします。
教育長
学校給食センターの維持管理・運営はPFI事業者に委託しております。その業務の中に給食の残食も含めた廃棄物の処理業務も含まれています。
残食については、現在、水分を抜いて圧縮し可燃物として処理されています。調理後の食品のリサイクルは、塩分や油分、糖分等を含んでおり、肥料や飼料への転用が難しく、コスト面も含めて適当な処理業者が見つからないと聞いております。
生ごみ処理機を導入し有効活用をとの御提案ですが、導入にかかる費用の問題や発生する堆肥等の利活用方法など課題が多くあります。
市といたしましては、現在の委託先であるPFI事業者に対し、残食も含めた食品廃棄物のリサイクル推進について引き続き働きかけをしていきたいと考えております。
吉田
処理機の財源などの問題もあるかと思いますが、平成26年10月の中央環境審議会意見具申「今後の食品リサイクル制度のあり方について」を受けて環境省は、学校給食の実施に伴い発生する廃棄物の3R、つまり発生抑制のリデュース、再使用のリユース、再生利用のリサイクルの促進を図るとともに、食育、環境教育の観点から、学校における学習教材としての利用を促進するためのモデル事業を実施しています。これは学校給食の実施に伴い発生する廃棄物の3R促進モデル事業というもので、平成27年度は北海道札幌市、長野県松本市、岐阜県恵那市、平成28年度は京都府宇治市と千葉県木更津市が選ばれ、最大で300万円の補助を受けています。
これら紹介した自治体のうち札幌市では、平成18年度から給食ごみを堆肥にした野菜づくりを進めており、平成23年度から今日までの給食の食品廃棄物のリサイクル率は100%、残食率はここ数年間1割を下回っているということです。また、木更津市では、御提案している生ごみ処理機を補助金で導入し、処理によってつくられた液肥を市内の農場で土壌づくりに活用しています。
環境省に問い合わせたところ、平成29年度も同事業は行われる予定とのことでした。本市もこの事業に応募し、生ごみ処理機の導入を目指すべきではないかと思います。給食センターは確かに施設の問題があります。もし設置が難しいのであれば、いずれかの学校の敷地内に置いてもよいと思います。むしろそのほうが子供たちの食への関心を高めることにつながると思いますが、いかがでしょうか。
教育長
先ほども御答弁申し上げたとおり、PFI業者、株式会社名取学校給食サービスに処理については委託しております。議員から御提言のありましたモデル事業、またそのほかにも独自に飼料化や肥料化に取り組んでいる給食センターがあることは私も承知しております。本市において生ごみあるいは残食をもっと有効に活用できないかということについては、議員からの御提言も含めて今後研究させていただきたいと思います。
吉田
ぜひとも研究を進めてよりよいまちにしていただきたいと思います。
では、次に移ります。こども食堂についてです。
私は2月定例会の一般質問において、朝食を食べられない児童生徒に対する支援を行うべきと提案させていただきました。その際、教育長から朝食提供などの支援については考えていないとの御答弁をいただきました。確かに朝食を食べている児童生徒の割合は本市は全国平均よりも高いかもしれません。しかし、その食事の中身を考えた際、また、朝食に限らず全ての食事に見方を広げた際、食育の観点から望ましい食事をしているかどうかは疑問です。現実には、共働き世帯の増加や調理済みの商品がコンビニエンスストアなどで簡単に手に入るといった社会状況であることから、孤食いわゆる1人での食事や偏食、偏った食事が子供たちの間で常態化している、そのような子供の数がふえていると思われます。この問題は既に全国的に表面化しており、地域社会が子供の食を支援するこども食堂が全国各地で次々に始められております。
そこで、小項目3 こども食堂の開設に向けて必要な整備を始めるべきについて、本来であれば教育長に質問すべき内容ですが、未来を担う子供たちの食の問題に関して市長の姿勢をお伺いしたいと思います。
市長
県内でもこども食堂が幾つか開設されており、孤食への対応や食育の推進を目的とするもの、あるいは学習支援の場とあわせて実施しているところもあると聞いております。
運営については、NPO法人や民間団体、住民有志、個人などが行っており、その運営費用については寄附金や民間企業の助成金などで賄われているようです。
近年、核家族化やライフスタイルの多様化による家族団らんで食事をとることができないといった孤食や、不規則でバランスのよい食事をとることができないといった食の問題に対して、こども食堂はその解決に向けた一つの手法と考えられています。
平成28年3月に策定された第3期宮城県食育推進プランでは、家庭での食事は心身ともに健やかに生涯を送るための基本とされ、特に子供の食育では家庭が重要な役割を担うとされております。
当市においても、「元気なとり」食育プラン(第2次)に沿って、市民一人一人が自立して健康的でよりよい食生活を目指せるよう食育の推進を図っているところです。
このようなことから、当市としましては児童生徒の食育にかかわるこども食堂の開設については今のところ考えておりません。
吉田
行政としては考えていないということかと思いますが、こども食堂は、進め方によるかと思いますが、子供が友達や地域の大人とともに食事をする機会をつくり、バランスのとれた食事を安心してとることを可能とします。朝日新聞社の調査によると、平成28年5月の時点で全国にあるこども食堂の数は319カ所に上るとのことでした。
こども食堂は、先ほどの御答弁のとおりNPO法人や民間団体などによって運営されているものがほとんどですが、寄附や持ち出しで費用を賄っている団体、また公的な補助を行っている自治体も少なくありません。または公民館や児童センターなどの公的施設が利用されている例も見られ、一部では学習支援団体と連携して学校の勉強を教えるような取り組みも行われています。地域において多種多様な人々が交流できる新たな場としても、こども食堂は多くの可能性を持っていると思います。本市ではまだ例のない取り組みですから、公と民間との役割分担など明確なイメージを持つことは難しいと思いますが、市長の姿勢としては、今後このような支援が必要かどうか、どのようにお考えでしょうか。
市長
先ほども申し上げましたとおり、社会の中で一定の役割を果たしているものと捉えております。ただ、これは、いわゆるやる気のある民間の方が自分たちの地域の課題として主体的に取り組んでいくものと捉えています。行政が主体的に取り組むというところまでは考えていませんが、今後、民間との連携、また支援のあり方について研究していきたいと考えております。
吉田
民間との連携ですね。やはり市が主導するのではなく、民間でそのような声が上がってきたときに市としてもバックアップしていただきたいと、そのような御答弁として認識しました。そうであれば、このような考えがある方にとって進めやすくなってくるのではないかと感じた次第です。
では、続いて大項目2 公共施設の運用についてお伺いいたします。
去る9月定例会において、施設使用料や各種手数料が平成29年4月に改定されることが決まりました。ほとんどの施設や区分で値上げとなります。私は採決に先立ち反対討論を行い、その際、市民負担の引き上げから入る改革は本当の改革ではなく、コストカット、経営者感覚、そして施設の価値の向上を実現するよう要望しました。この中でコストカットや経営者の感覚を取り入れることはすぐには難しいかと思いますが、施設がそれぞれサービスを拡充することでその価値を高めることは可能であると考えます。そこで、今回は3つの施設についてサービスの拡充を具体的に求めてまいります。
まずは小項目1 名取駅コミュニティプラザは主に観光客向けの荷物無料預かりサービスを始めるべきについて市長にお伺いいたします。
市長
名取駅コミュニティプラザでは、地域の活性化に資するとの目的で平成22年度からレンタサイクル事業を実施しており、レンタサイクル利用者に限りますが、無料で御利用いただけるコインロッカーを6台設置している状況にあります。また、本市管理ではありませんが、JR名取駅構内に有料のコインロッカーも12台設置されています。
名取駅コミュニティプラザには荷物の預かりの問い合わせ等もいただいていないことから、今のところ観光客向けの荷物無料預かりサービスに取り組むことは考えておりませんが、観光客の誘致に向けた今後の研究課題としたいと考えております。
吉田
まだそのような問い合わせがなく、今後の課題ということでした。その今後がいつなのかということでお聞きしたいと思うのですが、本市の地方創生総合戦略においては、施策の基本的方向として地域資源を生かした観光振興が盛り込まれています。駅などの交通拠点の近くに宿泊施設がない土地では、観光客はコインロッカーに入らないような大きな手荷物は持って移動するほかなく、目的地として設定できる場所は限定されてしまいます。仙台空港に到着した観光客が市内の名所を目指そうとしても、大きな荷物を預けられる場所がないために、宿泊施設のある仙台市などに流れてしまうおそれがあります。
しかし、もし市の玄関口である名取駅で大きな手荷物を預けられるとなれば、身軽ないでたちで市内を観光することが可能になります。名取駅コミュニティプラザは、平日は午前7時半、土日祝日は午前9時に開館し、午後8時まで職員が常駐しています。手荷物を保管できるスペースも十分あるように思われます。これは今すぐにでも始められるサービスで、新たにお金をかける必要もありません。もちろん、さらにサービスを広げて、一般市民が利用することを妨げる理由もないと思います。できるだけ早期、遅くとも名取駅コミュニティプラザのホールの使用料が引き上げられる平成29年4月までにこのサービスを始めるべきではないでしょうか。お伺いいたします。
市長
確かに観光客が来られたときの一つの拠点として名取駅、そこからいろいろと市内をめぐっていただく、名取駅にはそのような拠点としての機能があると考えております。ただ、荷物を預かる際、仮にそれがロッカーではなく人的なサービスとしたときに、まず観光客であるかどうかの見きわめや人的な配置の問題もあります。そして、保管するスペースはあるとおっしゃいましたが、本当にその保管スペース等が確保できるのかということもありますので、もう少し時間をかけて研究していく段階だと捉えております。
吉田
平成29年4月までは十分時間がありますので、ぜひそれまでに御検討をお願いしたいと思います。
では、次に移ります。
斎場で犬や猫などペットの火葬を行う際の手数料についても、このたびの改定で1.5倍に引き上げられました。ペット火葬についてもサービスの内容に充実が可能な部分があるのではないかと思います。
今日、ペットを家族の一員として非常に大切に扱う方がふえていると言われております。そのような飼い主の方にとって、何年間もともに暮らしてきたペットが死んでしまうことは家族を失うことに等しいものです。できるだけ丁重に送ってあげたいという飼い主の気持ちを行政は決してないがしろにしてはなりません。現在の斎場が完成するまではペットの死骸は一般ごみとともに焼却されていたそうで、そのころに比べてサービスが格段に上がっていることは事実です。しかし、最近、実際にペットの火葬を利用された方から、担当職員の方が作業着で対応されたこと、また受付に使われる部屋がまるで倉庫のようであることなど、改善すべきではないかという御意見をいただきました。
そこで、小項目2 斎場はペット火葬において利用者の心情に寄り添った対応をとるべきについて市長にお伺いいたします。
市長
斎場は生命の終焉の儀式を行う場として、その業務に当たっては身だしなみや言葉遣いは重要であり、ペット火葬も人間火葬と同様に利用者の心情に配慮した対応が必要となります。
本市のペット火葬業務は、業務委託により3名の従事者が人間火葬と兼務で行っています。火葬は動物専用の火葬炉を使用しますが、ペット火葬専従の者はおらず、人間火葬を優先に業務を行い、その合間にペットの火葬を受け入れて対応しているのが現状です。
ペットも家族の一員であるという認識を持って、常々利用者の心情に配慮して業務に当たってはおりますが、そのような中でも利用者から要望をいただいた際は、その内容を速やかに検証し、その後のサービスの向上に生かせるよう日々努めているところです。
なお、今お話し申し上げたとおり、人間火葬の業務で実際に火葬する際に作業服で対応している合間に対応させていただいていることから作業服での対応となっていますが、この点については委託業者と服装に関して協議をしていきたいと考えております。
吉田
作業着での火葬炉の運転ということで、恐らく通常のスーツなどを着ていてはなかなか難しいと思いますが、そのような作業にも対応できる丈夫なスーツなども実際にあると思いますので、そのようなものも取り入れながら、やはり使用される方の気持ちを考えていただきたいと思うのです。それはまた服装に限らず受付の場所についても同様で、倉庫のような部屋が今受付として使われていますが、やはりペットを失った飼い主の気持ちを考えると余りにわびしい印象です。こちらの内装についても、最小限のもので結構ですから改善すべきと思いますが、いかがでしょうか。
市長
先ほどの答弁の繰り返しになりますが、いずれ委託業者とも協議をしながら検討していきたいと考えております。
吉田
先ほど御答弁ありましたように、もちろん斎場は人様の火葬が主の目的の施設ですから、人様の尊厳を守ることが第一であり、ペットと人様との間に線引きをすることは必要です。しかし、ほかにもペット火葬についてサービスを拡大できる余地があるのではないか。例えば仙台市ではペット斎場の受付で骨つぼや位牌の販売を行っています。本市では骨つぼ等は飼い主が持参することになっていますが、火葬の日までに用意できない方、また、いざ火葬する段になって急に気が変わる方などもいらっしゃるかもしれません。そのような方たちのために本市斎場においてもペット用の骨つぼの販売を検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。
そのようなことも含めて、ペットのためにそこまでするのかという批判的な考え方も確かにありますが、むしろペットを失った市民のために行政が真剣に取り組んでいるという姿勢をとることは、ペットロスに苦しむ飼い主の方の精神的負担を和らげることにもつながる、ひいては住民福祉の増進として理にかなっているのではないかと思うところです。ぜひとも前向きに検討をお願いしたいと思います。
次に移ります。
このたびの改定においては文化会館の使用料もほとんどの区分で引き上げとなっています。文化会館は市民の文化活動の中心的施設ですから、使用料の改定が文化活動の縮小につながらないか危惧するところです。ほかの施設についても申し上げているように、新たな経費をできるだけかけず、可能な範囲でサービスを拡大することが求められます。文化会館を使用する個人や団体の多くは、音楽や舞踊、公演などの催しにたくさんの観衆を集めることを目指しております。会場の所有者や管理者はこれまで、みずからが主催する行事以外、観衆を集めるための支援は最小限にとどめていますが、使用料引き上げに見合うだけのサービス向上を実現するのであれば、ここにもその余地があるのではないかと思います。
そこで、小項目3 文化会館は使用者の集客の増強につながる支援を行うべきについて教育長にお伺いいたします。
教育長
当市では、文化会館の管理運営を公益財団法人名取市文化振興財団に指定管理者の指定をし、施設を拠点に文化芸術の振興に努めております。
このような中、文化会館を使用し開催される主な事業については、広報なとりへの掲載、市のホームページに文化会館のホームページをリンクさせるほか、催事のポスターやチラシを庁舎等に掲示や配架するなど、催事を含め施設の周知を図り、集客の増強に努めているところです。
今後はさらなる使用者の集客の増強につながるよう、開催される催事の情報発信の拡充に努めるとともに、エフエムなとりの活用を含め支援方策について研究していきたいと考えております。
吉田
また具体的な提案をさせていただきますので、もし御答弁が無理でしたら結構ですが、例えば、ホームページというお話がありましたが、文化会館が管理しているホームページを確認したところ、催しのスケジュール一覧は確かにあります。ただ、主催者の名前や、なぜか電話番号にはリンクがついているのですが、主催者のホームページに対するリンクがありませんでした。これは、もちろん求めない方についてそこまでする必要はありませんし、ホームページを持っていない団体が主催者になることもあるかと思いますが、ただ、やはりそれがあることによってより周知が広まるという考え方もあると思いますので、申請書にURLを記入していただくようにすればすぐに対応できるかと思います。
また、同じくインターネットを使った広報としては、文化会館はツイッターの運用も行っています。議会のツイッターもいよいよ正式に運用が始まりましたが、ツイッターは今重要な情報発信のツールですので、文化会館としても会館主催以外の行事についてもぜひ積極的にインターネットで発信していただくべきかと思いますが、いかがでしょうか。
教育長
先ほどのリンクの問題については、状況を把握して、改善できないかどうか文化振興財団と話をしてみたいと考えます。
なお、先ほども申し上げましたが、今議員から御提言のありましたようなことも含めて、今後さらに集客増につながるような支援ができないか、研究、検討していきたいと考えております。
吉田
ただいまは宣伝の面での集客の増強の支援ということでしたが、それ以外にもあるかと思います。例えば、現在、文化会館の使用者、主催者から依頼があれば会館の受付で入場券の販売を代行しています。現在のところ販売総額の10%を手数料として徴収しています。しかし、この制度を利用している使用者の割合は2割から3割程度と伺っております。窓口で購入されたチケットの手数料は、今の計算からするとさほどの金額になっているとは思えません。平成29年4月の料金改定を機に思い切ってチケット販売代行に係る手数料を廃止して、より多くの催しのチケットが受付で購入できるようにすると。そのことによってさらに利用者や観衆の方の別の催しに対する興味も広がっていくかと思います。チケット販売の手数料について廃止すべきと思いますが、いかがでしょうか。
前向きに御検討いただきたいと思います。
施設の価値を高めるためのサービスの拡充は、当然、以上申し上げた3つの公共施設に限った目標ではありません。今の3施設以外の公共施設においても同じように目指すことが求められると思います。これ以外の施設についても、今後時期を見て質問させていただきたいと思います。
最後に、大項目3 市の組織と人事制度についてお伺いいたします。
全ての職員がやる気と使命感を持って職務に当たり、市民の福祉をみずからの喜びとして捉えられるようになるためには、業務の公平な配分と正当な人事評価が最低限の条件であると考えます。よって、管理職のマネジメント能力の向上が職員全体の意識を高め、結果的に住民福祉の一層の増進につながるものと思われます。
管理監督職の皆様は、部下育成能力や組織管理力などを高めるため、日ごろから研修にいそしんでおられることと存じますが、庁舎内でみずからのマネジメント能力を多面的に評価される機会は余りないのが現状ではないでしょうか。本市の人事評価マニュアルによりますと、評価は常に上司から行われることになっているようです。経験、知識ともに豊富な上司からの評価が最も信頼できるものであることは当然ですが、上司の背中を常に見続けている部下からどのように評価されているのかを知ることも、人事評価制度の客観性をより確保するために有効ではないかと思います。
そこで、小項目1 人事評価制度の充実のためマネジメントサポート制度を導入すべきについて市長にお伺いいたします。
市長
本市における人事評価制度については、東日本大震災を受け、本格施行に移行する前に平成23年度より一時中断をしておりましたが、平成26年度の地方公務員法改正を再開の契機と捉え、平成27年度中に中断期間も長かったことから再度試行を行い、今年度より本格実施しているところです。
本市の制度は、国で先行して実施されていました人材育成に主眼を置いた、他の職員との比較ではなく、評価項目や設定され目標に照らして、職員一人一人の職務遂行能力や勤務実績を客観的に把握して評価する制度としております。
人事評価制度におけるマネジメントサポート制度は、管理職が自分のマネジメントを部下がどのように見ているかを知ることで、みずからのマネジメント能力の向上と意識変革を促進し、組織全体の活性化を図ることを狙いとして導入している自治体もあると認識しています。
今後、本市の人事評価制度の熟度を見ながら、また、他自治体の人事評価制度を参考にしながら、人事評価制度におけるマネジメントサポート制度について研究していきたいと考えております。
吉田
今後住民にとってより住みやすいまちにしていくために、職員の方たちのますますの働きに御期待するところですが、このマネジメントサポート制度は確かに現在導入するには課題がいろいろとあるかと思います。例えば、部下に評価されることによって、上司が部下に気を使ってしまうのではないかという懸念も実際に挙げられています。しかし、そのような懸念ついては、部下からの評価はあくまで上司、部下双方に気づきを与えるためのものとして捉え、職員間における目標の共有化を進めるためのフィードバックにとどめるということで払拭できるかと思います。先ほど市長もおっしゃいましたが、既にマネジメントサポートを導入している自治体があります。上司の意識変革の促進、上司と部下のコミュニケーションの円滑化などについて成果が出ていると伺っています。また、民間企業においても試行錯誤の上で導入が進んでいると伺っています。今後、課題かと思いますが、ぜひ市長には、市政に新たな風を起こすため、早期に導入に向けて具体的な検討に入っていただきたいと思いますが、市長のお考えをもう一度御確認させていただきたいと思います。
市長
この制度を導入するに当たり、やはり幾つかの課題と他の事例で成果も上がっていると思いますが、いずれ本市の人事評価制度そのものが、先ほど御答弁申し上げたとおり、平成28年度に本格実施されたばかりですので、まず現制度の熟度を見ながらよりよい人事評価制度に進化させていく形をとっていきたいと捉えております。
吉田
新しい人事評価制度は確かに内容が非常に充実していると思いますので、それを進めながらぜひ今後の課題としてマネジメントサポート制度も考えていただければと思います。
では、次に移りまして区長制度についてお伺いしたいと思います。
本市では、市の行政事務を補助させるため、原則として行政区ごとに区長を1人置くこととしています。区長については、平成18年3月に策定された名取市集中改革プランにおいて制度のあり方の検討が目標とされ、その後、平成23年2月には制度見直しのスケジュールが示されました。しかし東日本大震災の発生で中断し、その後も先輩議員からの一般質問や、また市民からの陳情で見直しを求める声がたびたび上がっていますが、それにもかかわらず何も進まないで今日まで至っております。
私は、平成28年6月定例会の会期中、総務消防常任委員会の委員として区長業務の現状確認と職務見直し改革についての陳情の調査に加わりました。その際、当局からの説明を受けて、市内全域の区長業務をすぐに統一することは難しいと認識しましたが、いずれは見直しが必要であろうと考えました。そしてまた、当局から震災復興事業が落ちつくまで保留とするとの説明がありました。しかし、市長が交代した今こそ見直しの作業に着手するときではないかと考えるに至った次第です。
そこで、小項目2 区長の業務内容と報酬の見直しを検討すべきについて市長にお伺いいたします。
市長
区長の業務内容としては、広報紙の配布、名取市及び名取市の附属機関等が発行する通知文書等の配付、地域内の住民からの相談などがあります。
この区長の業務内容の見直しについて、平成22年度には、広報紙等のポスティングによる配布など、より具体的に時代の流れに合った業務内容の見直し、報酬の見直しを検討しておりました。そのような折、東日本大震災が発生しまして、区長においては、本来の業務を超えて、地区住民の安否確認、在宅避難者への支援物資の配付、混乱している地域のまとめ役など多くの困難な役割を引き受けていただきました。
区長制度の見直しについては、以前の答弁でも申し上げていますように、震災復興業務が落ちついた時点においてよりよい方向に向けて再度検討していきたいと存じます。
吉田
確かに震災時の区長の働きは、私は実際に目で見たわけではありませんが、大変一生懸命住民のために動いていただいたことはお聞きしております。震災復興業務の落ちつきを見てという答弁ですが、どこで復興事業が落ちついたと見ればいいのか、具体的にスケジュールを切ることはできないと思いますので、できるだけ早期に検討に入るという姿勢を示していただきたいと思います。
ここで報酬の金額に触れるのもいかがかと言われるかもしれませんが、あえて今その点について指摘させていただきますと、区長の報酬は月当たり均等割額で1万300円、世帯割額が1世帯当たり150円となっており、これらの額をもとに年間の区長報酬総額を計算すると市全体で約7,000万円という大きな金額となります。これを1人の区長が年間に受ける報酬額として平均を出すと約55万円です。この額を多いと見るか少ないと見るか、私は多いのではないかと感じます。
先ほどの御答弁にあった集中改革プランではより効率的でスリムな自治体経営、これは経常経費の削減を目指すものと思いますが、この経費がかかること、そればかりではなく、町内会等が広報紙等の配布をかわりに行っている行政区も29行政区あることが先ほど申し上げた総務消防常任委員会で御答弁がありました。一方で区長の高齢化も実際に見られる現象で、高齢の区長が夏の炎天下で広報なとりの配布を行っていた最中に倒れてしまったという事例も伺っています。行政区ごとにいろいろな事情があると思います。また、経緯もあるかと思います。海側、内陸部とそれぞれ環境も異なります。しかし、本来、市としては同じ目的のために支出されている税金です。それが区長の裁量によって使い方に違いが生じている現状について市長はどのように捉えておられるのかお伺いいたします。
市長
区長の皆さんには行政と地域の橋渡しとしての役割も担っていただいていると捉えております。地域との橋渡しということであれば、当然その地域ごとに地域のあり方というか実情が違ってくるのだろうと思います。それぞれの地域ごとの実情に合わせた形で区長の皆さんにはお働きをいただいていると捉えております。
吉田
区長の職務について定めた資料があり、その中には明確に広報紙を配布するという内容が書かれているわけですが、それが実際に行われていない行政区があると。そのような中でも、区長が町内会に対して配布をしていただいている分の謝礼を渡している区が18行政区ある一方で、謝礼もない行政区が9つあるということも先日の御答弁の中であったと記憶しています。やはりこのような地域ごとのばらつきもあります。また、行政区長それぞれ地域の橋渡しという市長のお考えというか、それが市の捉え方だと思いますが、そのような役割も当然負っておられると思います。ただ、それにしても、平成23年に一度は作成された区長制度の見直しがあり、そしてその内容は、全てそのとおりとは言えないかもしれませんが、やはり今の官から民へ、民間へという流れの中で非常にすぐれた内容ではないか、また、その見直しについて再びスケジュール化するために内容の一部手直しなども含めて早期に着手すべきではないかと思いますが、もう一度市長のお考えをお伺いしたいと思います。
市長
最初に御答弁申し上げたとおり、まず復興の事業、業務が落ちついた時点に改めて業務内容や報酬等について見直しも含めて検討していきたいと考えておりますが、具体的な検討内容等について担当より答弁をいたさせます。
総務課長
ただいま市長が御答弁申し上げた内容に尽きるわけですが、平成23年の見直しでは、広報紙やチラシの配布については民間のポスティング業者を使う、それ以外は全部郵送という取り扱いを考えており、それに合わせて報酬も見直すという内容でした。ただ、現在同じような内容でできるかと申しますと、少し状況が変わっているところがありまして、平成23年には市内全域をポスティング業者が配布可能ということでしたが、現在、市域全体をカバーしている状況ではないという話も伺っています。そういった点で議員御指摘のとおり同じ内容ということは難しく手直しをせざるを得ないかもしれませんが、いつの時点ということも含めて、今後、震災復興業務が落ちついた段階でスケジュールを出していきたいと考えています。
吉田
ほとんどの区長の方は定められた職務を遂行されて正当な報酬を受け取っておられて、地域活動にも積極的に参加されている。また、地域の行事などに頻繁に顔をお出しになって、その都度、御祝儀を送っておられるような方もたくさんいらっしゃるということで、月によっては報酬よりも交際にかかるほうが上回ってしまうのではないかと思われますが、報酬がなくても、ボランティアとしてでも地域の橋渡しはやってくれる、そのようなすばらしい方が本市にはあちこちにいらっしゃるのではないかと思います。ぜひスケジュール化を進めていただきたいと思います。
では、次に移りまして社会福祉調査員についてです。
本市では、社会福祉に関する各種調査を行うため、民生児童委員を社会福祉調査員に充てています。民生児童委員には報酬は支給されていませんが、本市においては社会福祉調査員に対するものとして報酬を支給しております。しかし、その額は1人当たり年間7万円程度と、責任の重さに比べ微々たるものと言わざるを得ません。そして、社会福祉調査員の設置について定めた要綱を確認すると、施行された昭和57年から一度も改正されておらず、身分や報酬について明文化されておりません。今後ますます進むと思われる高齢化、貧困世帯、ひとり親世帯の増加、障がい者支援ニーズの高まりに対応するには、社会福祉調査員の担い手を安定的に確保する必要があります。
そのためにも、小項目3 名取市社会福祉調査員設置要綱を改定し、調査員の待遇や職務環境の改善を図るべきについて市長にお伺いいたします。
市長
名取市社会福祉調査員は、名取市社会福祉調査員設置要綱に基づき、地域福祉のさまざまなニーズを捉えるため、本市が民生委員・児童委員に委嘱しております。
現在、社会福祉関係の法律改正等による文言の整理を含め、要綱については改正の手続を進めているところです。
また、社会福祉調査員に対しましては、報償費として年間1人当たり7万円を予算措置しておりますが、民生委員・児童委員としては、宮城県の非常勤特別職であることから、その活動に伴う災害の際には地方公務員災害補償制度の適用を受けることになっています。
なお、民生委員・児童委員には給与を支給しないと民生委員法第10条で定められており、民生委員に関する費用は県が負担することとされ、現在は予算の範囲内で国が補助することとされております。
今年度は県負担の民生委員・児童委員活動費が増額されていることを踏まえ、現在のところ、市の社会福祉調査員報償費の額の改定については考えておりません。
吉田
要綱の改正手続を進めているとの御答弁でしたが、少なくとも調査員の身分と根拠となる法令を明示した上で明文化し、報酬についても記載するのが正しいあり方ではないかと考えます。
その上で、現在の報酬額について市長からも御答弁がありましたが、それが本当に適正であるのかどうか。先ほどあったように区長の報酬は平均すると1人当たり年間約55万円、それに対して調査員は7万円でおよそ8分の1です。両者の職務内容と報酬額、そう簡単に比較できるものではありませんが、バランスがとれているのかどうか、市長のお考えはいかがでしょうか。
市長
これは報酬ではなくあくまで報償ということです。まず考え方そのものに区長制度と少し違いがあることは御理解いただければと思います。
吉田
報酬と報償ということです。報償というのは要綱に定めはありませんので、市としての解釈という捉え方でよろしいですか。
市長
簡単に言うと謝礼という捉え方だろうと思います。
吉田
確かに報酬と謝礼では全く性質の違うものですが、どちらにしろ、まちのため、そして地域住民のために働いておられる方たちですから、謝礼のあり方も含めて改正手続の際はよりよい制度にしていただけるようお願いしたいと思います。
社会福祉調査員の職務環境の改善が今後さらに進みますように、報酬の面も含めて行政側にはしっかり取り組んでいただきますようお願い申し上げまして、私の一般質問とさせていただきます。