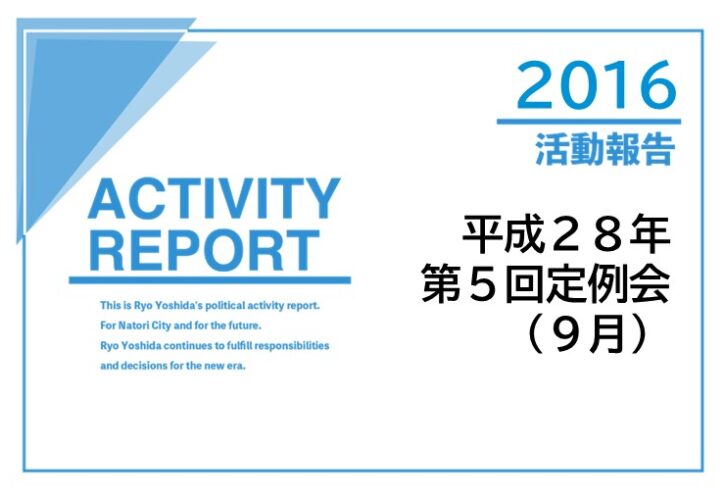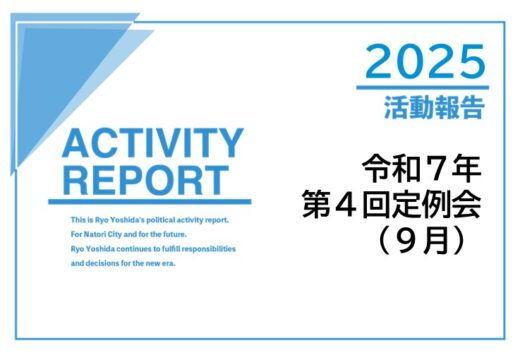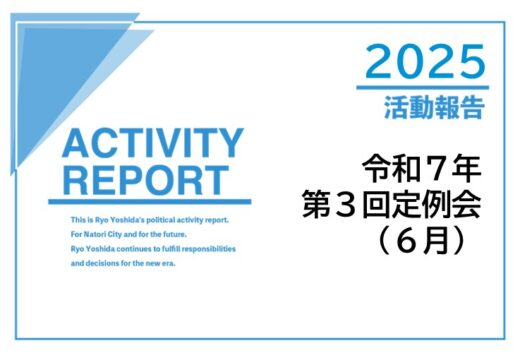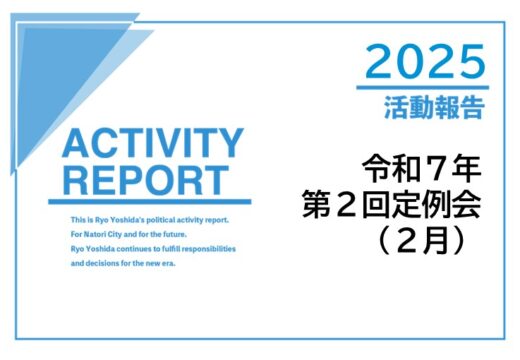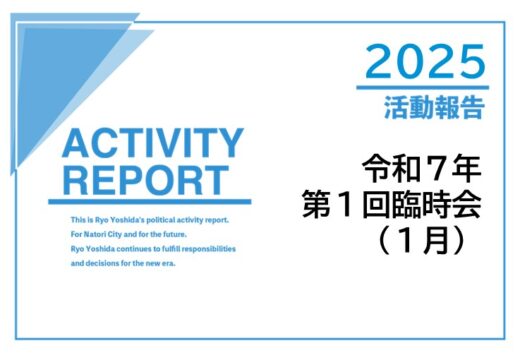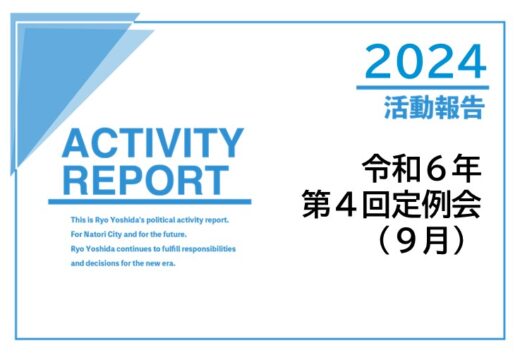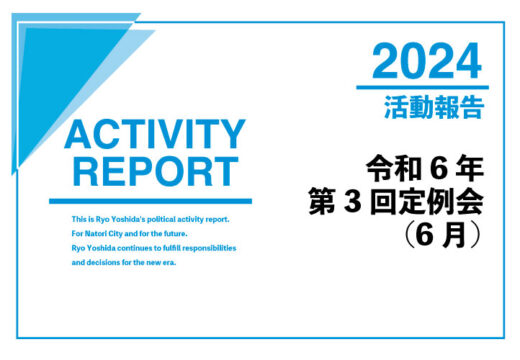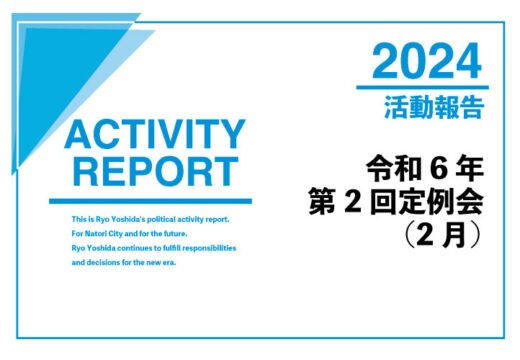一般質問
吉田
初めに、大項目1 広域連携と市町村合併についてお伺いいたします。
平成28年2月定例会の一般質問におきまして、前市長に仙台市などの周辺自治体と将来的に合併すべきではないかと申し上げました。それに対し前市長は、市民に対し正しい判断をしていただくための情報提供や課題提起を行う必要があると考えているが、現在、私の耳に合併を望む声は聞こえてきていない状況であると答弁されました。私には聞こえている声が市長には聞こえていないのかと残念に思ったことを記憶しています。
このたび新たに市長に就任された山田市長は、聞く耳と対話を重視するという姿勢で選挙に臨み、現職候補に6,000票以上の差をつけて当選されました。山田市長を支持する方の中には仙台市との合併を望んでいる方も実際におられるはずでしょうし、市長もそのような声を直接お聞きであろうかと推測されます。
時代の流れとともに市民の活動範囲は広域化しており、それに伴って、広域的な交通体系の整備や公共施設の一体的な整備、相互利用などの必要性が高まっていることから、市長は選挙公約に「広域連携の強化」という文言を盛り込まれたものと思われますが、広域連携によっても解消されない課題があることもまた事実であり、それらを前へ進めるためには市町村合併という選択肢も考慮する必要があるはずです。昭和33年に市制へと移行して以来、本市においても市町村合併の機運が高まったことがありましたが、市の枠組みは変わらないまま現在に至っています。当時の地域住民による選択を重く受けとめながらも、私は時代の要請にしっかりと耳を傾けるべきであると考えます。
そこで、小項目(1)本市を対象としたこれまでの合併議論と、今後の広域連携及び合併の展望について市長のお考えをお伺いいたします。 いて市長にお伺いいたします。
市長
本市を対象としたこれまでの合併議論については、平成7年ごろの仙台市との合併議論、平成15年ごろのいわゆる平成の大合併時の合併議論があったとことについては承知しているところですが、いずれも広く市民の合意形成までには至らなかったものと認識しております。
今後の合併の展望については、当面は本市独自により持続・発展し続けるまちづくりを目指していきたいと考えています。
広域連携については、これまでもごみ・し尿処理の一部事務組合、後期高齢者医療の広域連合、周辺自治体との広域行政協議会の設置、広域観光の連携など、積極的に取り組んできているところですので、今後とも連携を図っていきたいと考えております。
吉田
ただいま御答弁がありましたが、私も過去を振り返ってみたいと思います。本市では、先ほどおっしゃったように平成6年に市民有志によって仙台名取合併推進協議会が設立され、そして、明くる平成7年に改正合併特例法に住民発議の制度が創設されたことを受けて、仙台市を合併対象市町村として全国初となる合併協議会設置の直接請求が行われました。同年8月、本市と仙台市、それぞれの議会で合併協議会設置議案が採決され、仙台市議会では賛成多数で可決されましたが、本市議会では賛成4、反対21の賛成少数で否決されました。明くる平成8年、今からちょうど20年前に当たりますが、その年に行われた市長選挙において合併賛成派が擁した新人候補者が敗れ、事実上、本市と仙台市との合併論議は幕引きされることとなりました。
いわゆる平成の大合併により全国的に市町村合併の流れが加速してきた平成15年、名取市・岩沼市合併問題調査研究会が設置され、当時の宮城県知事や副知事が本市と岩沼市の市長を相次いで訪問し、合併特例法の期限を踏まえた具体的な検討を要請しました。これを受けて岩沼市が実施したアンケートでは、回答者の多くが両市の合併に関心を持ち必要性を感じているという結果が出ました。しかし、住民全体の機運が高まらなかったことや、行財政基盤が確立している、あるいは今後確立可能であるなどの理由により、両市の合併は実現しませんでした。
さらに、平成18年に県が策定した市町村合併推進構想に、前年に施行された新合併特例法のもとでの合併が望ましい市町村の姿として、名取市、岩沼市、亘理町、山元町の2市2町を構成市町村とする案が示されました。この合併により議会議員定数51人の削減、職員数285人の削減、人件費20億円以上もの削減が見込まれるなど、さまざまな効果が示されました。しかし、このときも合併の実現には至らず、現在のところ、この2市2町では広域連携という形にとどまっています。
ただいまの御答弁では当面は独自のまちづくりを行っていくということですが、ここで改めて市長にお伺いします。もし今後、市町村合併を求める市民の声が高まりを見せた際、これまで進めてきた2市2町の広域連携の枠組みが、それ以外の枠組みでの合併の選択肢を妨げる要因となることは考えられるのでしょうか。広域連携の実績がある2市2町以外の枠、例えば仙台市との2市による合併やそこに旧名取郡の一部である岩沼市を含む3市による合併など、2市2町にとらわれない枠組みによる合併を排除しない考え方をすべきであろうと思いますが、いかがでしょうか。
市長
県の構想の中に、仙台地域広域行政圏ということで南部地域の中で2市2町による合併が望ましいのではないかという取りまとめをしていることは認識しています。ただ、先ほど申し上げたとおり、当面は本市独自でとにかく持続・発展可能なまちをつくっていきたいという思いを最優先に進めていきたいと考えていますので、今議員のお話にあった仮定の話について判断する状況ではないと考えております。
吉田
ということは、合併に関しては2市2町の枠組みも含めて現在白紙の状態だと認識させていただいてよろしいのかと思います。そこで、次に移ります。
御存じかと思いますが、今月1日、愛知県北名古屋市長は、隣接する名古屋市との合併について本格的な検討に入る旨、市議会定例会の一般質問で明らかにし、市役所内に検討会を設ける考えを示しました。参考までに北名古屋市の概要を説明しますと、平成18年に2町の合併によって誕生した市で、現在の人口は約8万4,000人、名古屋市という大都市のベッドタウンとして発展し、平成20年から5年間の合計特殊出生率は愛知県の平均を上回る1.65、市の人口は増加傾向にあります。ちなみに議会議員定数21は本市と同じです。
なぜあえて名古屋市との合併に前向きな姿勢をとるのか、その理由について北名古屋市長は、多様化する住民サービスへの対応を名古屋市と一緒に解決していくことが自然な流れ、今の財政規模ではできない災害時のきめ細かな支援などが期待できるなどと述べられたと報道されています。また、聞くところによると、それ以外にも両市の間ではごみ処理や消防などにおける広域連携が進み、衆議院選挙区も一体であるなどの理由が挙げられるということです。ベッドタウンとして単独で自治体経営を続けるのではなく、大都市と名実ともに一つとなって住民福祉の向上を目指し、人口減少時代に備えるものと思われます。合併特例債のような大きいメリットがない中で、地域の未来を見据えて自主的に市町村合併を目指す姿勢は、同じ規模の人口を預かる本市も参考にすべきと私は考えます。
現行の合併特例法第1条には、自主的な市町村の合併の円滑化並びに合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図り、もって合併市町村が地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とすると明記されております。
そこで、小項目(2)現行の合併特例法の目的を受け、本市でも自主的な市町村合併の検討に移るべきについて市長にお伺いいたします。
市長
市町村の合併の特例に関する法律の第1条では、地方分権の進展並びに経済社会生活圏の広域化及び少子高齢化等の経済社会情勢の変化に対応した市町村の行政体制の整備及び確立のため、合併について関係法律の特例など必要な措置を講ずることにより、合併市町村が自主的かつ総合的に行政運営の役割を担うことができるようにすることを目的としております。
確かに経済社会生活圏の広域化、少子高齢化といった経済社会情勢の変化への対応は、今後の行政運営に求められる重要な課題であると捉えていますが、現在のところ、これらの課題の対応策として合併の検討を行っていくという段階ではないものと考えております。
先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、合併については、当面は本市独自による持続・発展し続けるまちづくりを目指していきたいと考えていますので、自主的な市町村合併の検討という形ではなく、広域連携の強化により対応していきたいと考えております。
吉田
広域連携の強化、確かにそれは現在取り組んでいることと存じますが、先ほど申し上げたとおり広域連携だけでは解決できない課題がさまざまにあることも事実です。
宮城県は、東日本大震災後の平成24年に、市町村の行政機能の向上、震災からの復興に向けた施策の展開、地方分権型社会における責任と判断によるまちづくり等を支援する目的で「宮城県市町村行財政運営支援方針~震災復興に向けて~」を策定しました。その中で、震災からの復興と地方分権型社会の中核的な担い手となる市町村に対し、行財政基盤の強化と地域の実情や住民ニーズを踏まえた施策の展開に向け、さらなる行財政改革と限られた人員による対応を求めています。県は、地域の実情を踏まえながら自主的な合併を目指す市町村に対し、関係市町村の要望に応じて可能な限り必要な支援を引き続き行うとしています。
この地域の実情を本市において考えたとき、大きなものの一つとして大都市仙台のベッドタウンであるという特性に思い至る、私はそう感じます。本市から仙台市へ通勤通学で移動する方は非常に多くいらっしゃいます。本市は独自に乗合バスを運行していますが、現在のところ必要な地域に必要な本数を確保できているとは必ずしも言えない状況にあります。しかし、もし仙台市営バスが本市に乗り入れることになれば、本市から仙台市中心部へのアクセスを初め、地域住民の足の問題も改善が見込まれるでしょう。さきに紹介した北名古屋市の事例でも、名古屋市営バスの乗り入れが一つのメリットとして考えられています。仙台市の敬老乗車証を本市民が利用できないという問題等、本市の地域の実情の一つである大都市との間の交通の課題を踏まえ、今こそ市町村合併の検討を始めるべきではないかと思いますが、市長のお考えをお伺いいたします。
市長
先ほどの県が取りまとめた構想の中で、最も効率的な行政運営が可能とされる人口規模が16.5万人ということで目標となる都市の規模を20万人としていますが、人口規模とその効率性において遜色のない7万人から8万人程度の規模も当面の目標とするということで、いわば今の本市の規模がそのような意味ではある程度バランスがとれているのではないかと考えております。
また、交通アクセス、また別の議員の御質問の中でもあったとおり、文化面や医療圏など相互利用しながら、いわゆる大都市に隣接しているメリットをしっかりと共有しながら持続可能なまちをつくっていきたいということが今の私の思いであります。
吉田
1つの自治体における人口の適正規模にはさまざまな考え方があると思いますが、今申し上げた交通の問題としてほかにも取り上げたいと思います。
本市と仙台市とをつなぐ鉄道は東北本線しかないことがまず挙げられると思います。仙台空港アクセス鉄道や常磐線などが乗り入れされているため、本数こそ少なくはありませんが、事故などによって一たび運行が停止すれば非常に多くの利用者が影響を受けることになります。当然、本市の市民もその中に含まれます。このような現状の打開を目指すために、恐らく市長は選挙公約の中で仙台市営地下鉄の南進を打ち上げたのではないかと推測しているところです。しかし、仙台市営地下鉄は文字どおり仙台市の財産であることから、本市が単独でこれをどうこうしようと努力したところで、実現する見込みは皆無に近いものと思われます。また、仙台市が名取市民のために新たなリスクを背負うことは考えにくいと思います。
しかし、ただ一つ地下鉄南進の可能性があるとすれば、本市と仙台市との合併がその前提になるのではないでしょうか。もし合併したとしても、結果として地下鉄南進は実現しないかもしれません。それでも本市側が一方的に夢を描いている現状から一歩進み、少なくとも議論の土俵に乗せることは可能となるはずです。地下鉄南進という公約が実を結ぶかどうかは未知数ですが、市長が責任を持って公約実現を目指すのであれば、その第一歩として仙台市との合併の検討に踏み込むべきではないでしょうか。市長にお伺いいたします。
議長
吉田 良議員に申し上げます。合併議論については市長が再質問の中で十分に答弁をされていると思われますので、角度を変えて質問してください。
吉田
わかりました。では、次に移りたいと思います。
現在、市長の考えは今すぐに合併の議論に移るものではないということがはっきりしましたが、市長のお考えがどのような形であるかにかかわらず、選挙公約に地下鉄の南進が掲げられたことで、仙台市との合併が進んでいくのではないかという期待やあるいは不安が市民の中で広まっていくものと想定する必要があるかと思います。
合併の是非について議論がなされる場合、感情論による批判合戦が繰り広げられることを回避するよう努めるべきだろうと考えます。市を二分するような感情のもつれが生じることは誰のためにもならない悲しむべきことでありましょう。だからこそ、市民の客観的な思考を助けるために、可能な限り正確な情報の発信が必要ではないでしょうか。仙台市と合併することにより、先述のバスや地下鉄など公共交通、道路、保育所、病院などの社会インフラ、庁舎や議員定数、また職員数、国民健康保険や介護保険などの保険料負担、水道料金、そしてまた消防や警察の管轄、小中学校の学区などを含め生活環境がどう変わるかは、事実に基づいてある程度は予測が可能だと思います。それらの予測によって得られたデータを用い、広域連携と合併それぞれの効果や変化を比較して公表することで、冷静に議論できる環境が生まれるものと考えます。
そこで、小項目(3)広域連携の拡大や市町村合併による効果、変化などを調査研究する部門を市役所内に設け、地域の将来を判断するための情報を市民に提供すべきについて市長にお伺いいたします。
市長
先ほどから申し上げておりますとおり、当面は本市独自によるまちづくりを推進していきたいと考えておりますので、市民に対し合併に関する積極的な情報提供を行うべき状況にはまだないと捉えています。
また、合併について調査研究する部門の設置についても、現時点では必要性のないものと捉えていますが、なお、現在の所管課において引き続き情報収集等を行っていきたいと考えております。
吉田
市長の選挙公約には、新産業エリアの整備と企業誘致という項目も盛り込まれていました。本市内に働く場がふえれば、地域経済の活性化や定住人口の増加などが見込まれると考えられます。実効性を持って企業誘致を進めていくには、他の自治体と比較して魅力が感じられるよう本市のメリットを示す必要があると思います。
その一例として税負担の面でのメリットを挙げるとすれば、例えば仙台市では事業所税が事業者に対して課されるのに対し、本市ではそれは課されません。確かにこれだけを見ると、仙台市よりも本市に事業所を置いたほうが税の負担が軽くなりそうな感じがしますが、実際はそうとばかりは言い切れません。法人市民税の法人税割について仙台市は、資本金または出資金の額が1億円以下の法人に対し、本市より2.4ポイント低い税率を設定しています。事業所税の課税対象とならない小規模事業者は、本市より仙台市内に事業所を構えたほうが税負担の面では軽くなることを意味しています。多くの事業者に仙台市内に事業所を置くほうが税の面で低負担だと判断されれば、本市が全力で企業誘致を行ったとしても、その成果は限定的となってしまうことが考えられます。
しかし、仙台市との合併を視野に入れて調査研究部門の設置に踏み切れば、事業者の中には本市の将来的な成長を見越し、地価の高い仙台市域ではなく、名取市域に事業所を構える方があらわれないとも限りません。事業者にとっても未来を見据えて入念な計画を立てることが可能となるよう、何度も申し上げて恐縮ではありますが、今こそ市が独自に市町村合併の効果を調査研究し、公表すべきではないでしょうか。
市長
先ほど来申し上げているとおり、合併について調査研究する専門の部署の設置は現時点では必要がないと考えております。企業誘致等については政策企画課が担当していますので、今のお話も含めて本市でそのようなことができるようにいろいろと今後検討していきたいと考えます。
吉田
では、現在のところはまだ検討段階にないということですが、今後もしっかりと聞く耳を大事にしていただきまして、住民の中からそのような声が上がってきましたらまた先へ進めていただきたいと思います。
次に、大項目2 歴史・文化的資源の保存と活用についてお伺いいたします。
郷土にはそれぞれ先人が培ってきた固有のすばらしい文化があります。しかし、生活様式の変化などによって、文化の中でも特に無形民俗文化財は後継者不足に瀕し、日本全国で消滅の危機に直面していると指摘されています。
本市には、県指定3件、市指定6件の無形民俗文化財がありますが、保存会で活動する市民の中からは、会員の高齢化が進みいつまで続けられるかわからない、または次の時代を担う人材が不足しているなどの声が聞かれます。このままでは郷土の大切な財産が失われてしまうおそれがあります。
そこで、小項目(1)地域の先人が守り継いできた貴重な無形民俗文化財を今後どのように後世に継承していくべきかについて、市長のお考えをお伺いいたします。
市長
市内には先人たちが守り伝えてきた多くの有形・無形の文化財があり、その中の無形民俗文化財には県や市の指定を受けた9件があり、各保存団体による保存、継承のための活動に対し助成を行っているところです。
しかしながら、近年の地域社会の変化に伴い担い手や後継者が少なくなり、今後の保存、継承が難しくなってきている現状もあります。
このような無形民俗文化財は、本来、その地域や保存団体の自主的な活動により保存、継承されるべきものではありますが、それぞれの団体の状況や意向なども踏まえながら、次世代を担う子供たちが民俗芸能に触れる機会や理解を深めることができるような支援について、教育委員会と協議をしていきたいと考えております。
吉田
教育委員会と協議をされるということですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律によると、文化財の保護に関することは教育委員会の職務権限と定めがあります。ただ、市長部局が教育委員会との連携を今後工夫していくことによって、より効果的な保存、継承へ進展することが見込めるのではないかと感じています。
市は現在もさまざまな事業を行っていますが、事業そのものの目的を果たすことに加え、無形民俗文化財の継承という相乗効果が期待されるような事業について、ぜひ教育委員会と連携のあり方を模索していただきたいと思いますが、いかがお考えでしょうか。
市長
先人たちが守り伝えてこられた有形・無形の文化財をしっかりと未来に引き継いでいけるように、教育委員会と協議、連携を図っていきたいと考えます。
吉田
市長から教育委員会との協議をしっかり行っていきたいという御答弁をいただきましたので、次へ移ります。次は教育長にお伺いいたします。
我が国において無形の文化財が次の世代へと継承されていくための場は、多くの場合、1次産業を中心とする地域コミュニティーによって担われてきたものと考えられております。よって、国全体で進んでいる1次産業従事者の減少が無形の文化財にも存続の危機を及ぼしていると捉えられますが、かといって、将来、産業構造が大きく変わることは考えられず、本市においても無形の文化財を次へつなぐための場を考え直さなければならない時期に来ていると思います。その新たな場として期待されるのが学校ではないでしょうか。
そこで、小項目(2)郷土にゆかりのある無形民俗文化財に触れる機会を各小中学校で拡大し、児童生徒の郷土への愛着と知識を一層向上させるよう取り組むべきと思いますが、いかがでしょうか。
教育長
郷土を愛する心や態度を育てる指導については、文部科学省が示す学習指導要領や宮城県教育委員会が示す学校教育の方針と重点の中にもその重要性が示されております。また、本市の教育基本方針の中にも、ふるさと名取を愛する心情を育むことを具体的施策の一つとして位置づけており、市内の児童生徒に郷土を愛する心や態度を育むことは、地域の復興や発展に貢献できる人材育成の観点からも重要な教育の一つであると考えます。
市内の小中学校においては、ふるさと教育の一環として、各学年の発達段階に応じて、地域の素材や人に触れながら地域への愛着を育む学習を行っています。
その中の地域素材の一つとして、本市の無形民俗文化財を取り上げている学校もあります。各地域にゆかりのある神楽、舞、踊り等について調べたり、踊りや舞の体験を行ったりしながら、無形民俗文化財に触れる学習を行っております。また、保存会の方々の協力を得て踊りや舞を学び、それを運動会や学習発表会などで発表している学校もあります。
ほかの学校についても、地域の実態に応じて、地域の素材や人に触れながらふるさと教育を行っています。今後も各学校の実践を情報交換しながら、無形民俗文化財も含めたふるさと教育の充実に取り組んでいきたいと考えております。
吉田
このことについては2月定例会でも少し質問させていただき御答弁をいただきましたが、ふるさと教育に取り組むことにより有形・無形の文化財を次の世代に継承し、若者の首都圏への流出に歯どめをかけることは教育委員会も重視しておられることを私も認識いたしております。「ふるさと名取の歴史展」や歴史講座、そして小学校社会科の副読本の「わたしたちの名取市」等の活用も確かに意義のある取り組みですが、無形の文化財は座学による継承は難しく、実技を拡充することが効果的であろうと考えています。
ただいま御答弁にありましたが、市内小学校では館腰小学校と増田西小学校で既に行われている無形民俗文化財の体験学習は非常に価値のある取り組みであると思っております。これら先行事例を参考とすることで、ほかの学校がこれらを導入する際に、カリキュラムの編成や学校と保存会との連携など課題の解消へ進むことも期待できるかと思います。本市の無形民俗文化財は9件ありますが、小学校は11校あります。保存会の協力を得ながら全小学校で体験学習を導入し、無形民俗文化財の継承の場を確保することを目指すべきではないでしょうか。
教育長
先ほど答弁しましたように、各小中学校においてふるさと教育を推し進めることは非常に大事であると考えております。ただ、ふるさと教育を考えた場合に、それぞれの地域によって地域性もあり、地域の自然、歴史、文化、伝統等について、それぞれの学年の発達段階等に応じてそれらに触れたり体験していくものだと考えています。ですから、その中の一つとして無形民俗文化財があるという認識です。
したがって、教育委員会として、無形民俗文化財の体験学習を全ての小学校あるいは中学校において取り入れるよう働きかけることは考えておりません。それぞれの学校の実情に応じてふるさと教育の充実をさらに図っていくことはもちろん大事ですが、だからといって無形民俗文化財についての学習を全ての学校で取り入れることについてまでは考えておりません。
吉田
確かに地域ごとにいろいろな実情、事情があるかと思います。今後ぜひそれらを課題にしていただきたいという思いをお伝えするのみかと思いますが、館腰小学校、増田西小学校において郷土芸能を学んだ児童たちについて少し角度を変えて考えたいと思います。
この児童たちは、校内の発表会で体験学習によって覚えた実技を発表することになっているかと思います。これをさらに市の行事など学校を離れた場で発表できれば、彼らにとってさらに有益な経験になるのではないかと考えます。また、彼らが中学校へ進学すれば、郷土芸能の体験授業は思い出として残ることにはなりますが、それだけで終わってはいかにも残念ではないかと思います。さらに社会に出た後を考えても、やはり事あるごとにその経験を、覚えたことを発揮できる場があれば、たとえ本市を離れて首都圏で働くようになったとしても、何かの機会にふるさとに戻って伝統芸能にもう一度触れようと、そのような気持ちが働くことにつながるのではないかという期待も少しは持てるのではないかと思います。
そこで、先ほど市長から無形民俗文化財の継承のためには教育委員会と必要な協議などを行っていきたいという御答弁をいただきましたが、同じ目的を持って市と連携することについて、教育委員会、教育長としてはどのようにお考えでしょうか。
教育長
教育委員会といたしましても、無形民俗文化財の保存、継承が大事な課題であるという認識については同じ思いです。議員から御紹介のありました、館腰小学校で花町神楽、増田西小学校では手倉田枡取り舞を地域の方から教えていただいて学習発表会等で発表することは、私も館腰小学校に勤務していましたのでよく承知しています。ただ、先ほど申し上げましたように、無形民俗文化財についてはふるさと教育の一環として取り上げております。それで、結果的に子供たちが無形民俗文化財に興味を持って将来やってみようという気持ちになってもらえれば、それは本当にすばらしいことだと思います。ただ、学校教育の中で無形民俗文化財の保存、継承を第一義の目的として活動を行うことには少し無理があるのではないかと思います。
ですから、館腰小学校の例で言いますと、学校の学習発表会で発表するほか、私が勤務していたときには館腰神社で子供たちが披露したという事例もあります。そのような形で、子供たちが学校だけではなくいろいろな場面で発表する機会があったり、そういったところでさらに無形民俗文化財に興味を持って将来これを保存していこうという気持ちを持ってもらえればいいなと、学校としてはそのような気持ち、態度、心情も含めて育てていきたいと考えております。
吉田
ただいまの御答弁で、無形民俗文化財の保存については、学校という場に限定するのではなく、市と教育委員会が共通の認識で今後連携をとりながら保存に向けて取り組んでいきたいという考えであると認識いたしました。
そこで、次に移りまして改めて市長に御質問いたします。
小項目(1)の議論の続きとして、無形民俗文化財の保存のために、教育委員会と連携することにより観光資源としての活用を提案したいと思います。これも2月定例会で申し上げましたが、本市の地方創生総合戦略には地域資源を生かした観光振興が盛り込まれており、無形民俗文化財という誇るべき地域資源を生かすことは観光振興に大いに寄与するものと思われます。これらが観光資源として確立し、観光客の増加によって地域経済が潤えば、市民による保存活動は経済的に自立を果たし、努力が成果に結びつく仕組みが構築されるものと期待が持てます。こうした仕組みは一朝一夕に整うものではありませんが、粘り強い取り組みによって実現を目指すことが行政に求められるのではないでしょうか。
そこで、小項目(3)無形民俗文化財を観光資源として活用する未来像を描くとともに、保存活動が経済的に自立できる支援のあり方を検討すべきについてお伺いいたします。
市長
地域の歴史や魅力を物語る無形民俗文化財は、歴史的な価値を有するほか、地域づくりや観光資源として生かすことができるものです。
活用に当たっては、名取市観光物産協会等との連携を図りながら、それぞれの伝統芸能が持つ歴史的な価値や特徴を市内外へ積極的に情報発信するとともに、他の文化財との一体的な観光資源としての活用について教育委員会と協議していきたいと考えます。
このほか、保存団体に向けては、無形民俗文化財の保存、活用に対する民間団体の助成金制度や、イベント出演情報などの提供も行いながら、引き続き支援のあり方について教育委員会と協議していきたいと考えております。
吉田
市長も無形民俗文化財は観光振興に活用できると考えるという御答弁でしたので、具体的な御提案をさせていただきます。
無形民俗文化財を観光資源として活用している自治体の中には、観光客の方たちに実演の体験をしてもらう取り組みを行っているケースがあります。例えば、徳島の夏の風物詩、阿波踊りは全国的にも有名なイベントですが、この郷土芸能を期間外にも観光資源として活用しているのが徳島市内にある阿波おどり会館という施設です。館内のステージでは、休日、祝日はもちろん、平日も1日数回の公演が行われ、入場者が簡単な指導を受けながら実演体験をすることができる時間が設けられています。同じような取り組みは島根県安来市でも、いわゆるどじょうすくいとして知られる安来節を活用して行われております。これらで上演に携わっているのは地域の踊り手の方たちです。特に阿波おどり会館では30を超える連と呼ばれるグループが日がわりで出演し、地域ぐるみでこの事業を支えています。
本市の無形民俗文化財は阿波踊りやどじょうすくいほど有名ではありませんが、旅行者は必ずしも有名なものだけを目的に観光しているわけではなく、その地域にしかない珍しいものに触れることも重要な要素の一つであると考えられることから、活用の仕方によっては観光資源になり得るものと考えます。しかも、この取り組みに地域の子供たちを参加させることで、自分たちも文化の担い手であるという自覚が芽生えるきっかけにもなると思います。地域経済の活性化、無形民俗文化財の保存、若者の市外流出の抑制という3つの効果が生まれる可能性を秘めていると思います。このために新しい建物が必要であるとは思いません。市が保有する既存の施設の一部でも結構です。拠点となる場を設けるとともに、これまで培ってきた市民との信頼関係や豊富な情報をもとに組織づくりの検討を始めてはいかがでしょうか。
市長
観光客が実演体験をしている事例の御紹介をいただきました。子供たちと連携したり観光資源として生かせばいろいろなメリットがあるのではないかということで御提案いただきましたが、拠点づくり、また組織づくりまでは現在考えていませんが、観光資源としても含めて無形民俗文化財をどのように内外に情報発信できるのか、観光物産協会と連携を図りながら、また教育委員会としっかり協議をしながら今後検討していきたいと考えます。
吉田
市民の方からも時々指摘を受けますが、本市には観光の分野にまだまだ成長の余地があると思います。そこで、例えばですが、先ほど先輩議員からも質問がありました、今後新たに整備されるであろう歴史民俗資料館に、保存会の活動拠点となり、また観光客が実演体験できる適切な規模の体験スペースの設置も検討していただきたいと思います。市民はもとより、観光客にも愛される施設になり得ると考えます。観光客による実演体験というユニークな取り組みが本市でも始められるように、ぜひとも市と教育委員会には、観光物産協会との連携なども模索しながら、開館後のビジョンについても考慮していただきたいと思っております。
では、最後の大項目3 道路の安全性と利便性の向上についてお伺いいたします。
多数の市民が利用する公の道路は、行政が常に責任を持って維持管理に努めなければなりません。昨日、ニュース番組で報じられていましたが、名取が丘に住む女子中学生が9月8日の大雨の際に転んで側溝に落ち、25メートルほど流されてしまったとのことでした。幸い軽傷で済みましたが、一つ間違えば大事故につながるところでした。この事故を受けて市では現場の側溝に鉄製のふたを設置するとのことですが、事故が起きてから対応するのでは遅く、危険に先回りして誰もが安心して利用できる道路の整備を進めていただきたいと思います。
側溝についてはいずれ改めて質問することとし、現在、市内に張りめぐらされている市道の中に、白線が消えかかっている箇所や視線誘導標、いわゆるデリネーターが曲がっていたり破損していたり、あるいはポールだけを残して欠損している箇所が多数見られます。
そこで、小項目(1)白線やデリネーターを計画的に点検し、補修が必要な箇所は順次対処すべきについて市長にお伺いいたします。
市長
市は、1,302路線、約500キロメートルの市道を管理しており、日ごろから職員による道路パトロールを実施し、道路施設の目視点検等を行っているところです。
道路附属施設の区画線やデリネーターは、道路照明のない区間や曲線部において道路線形を明示し、運転者の視線誘導を行い、交通の安全と円滑化を果たしています。
道路附属施設の補修については、地域からの通報や道路パトロール中に破損等を見つけた場合、早急に対応しているところです。
御質問のデリネーターについては、破損のほとんどは接触事故等が原因であり、市への届け出がなく道路や歩道に倒れかかっているものなどについては職員で補修をしています。また、区画線については、センターラインや交差点付近の中央線、矢印の表示など消えている箇所を優先に工事を発注し、修繕を行っているところです。
今後も日常的に道路パトロールを行い、道路施設の安全確保に努めていきたいと考えております。
吉田
区画線といいますか白線の長さ、またデリネーターも相当な数に上るかと思いますので、ぜひ計画的に点検を行い適切な維持管理をしていただきたいと思います。
では、次に移ります。市内の住宅地は造成された時期やその他さまざまな要因により、それぞれ特徴や課題を持っています。宅地が誕生したころには予想されなかったたぐいの問題が、時代の変化とともに少しずつ生活に影響を及ぼしている事例が見られます。その一つとして、歩道が車道よりも標準で15センチ高いマウンドアップ方式の歩道について指摘させていただきます。
マウンドアップ方式の歩道は、車道を走行する車両が運転操作の誤りなどによって歩道に乗り上げようとしても、その段差によって歩行者を守る効果があります。一方、歩道に面した土地に住宅と駐車スペースを持つ住民にとって、車両の乗り入れは非常に不便です。歩道の乗り入れ部に傾斜をつければ車両の出し入れの問題は解消されますが、そのための費用の負担を避けたい世帯は、段差部分に市販のスロープや鉄板などを置いて段差をなくす工夫をしています。しかし、これらスロープや鉄板は車道の隅に置かれているために、自転車の利用者にとっては通行の障害となっております。自転車がスロープを避けて蛇行することで、後ろから来る車両との事故にもつながりかねません。また、車椅子の利用者にとって、段差の高いマウンドアップ方式は転落の危険と常に隣り合わせとも言えます。
そこで、小項目(2)自転車や車椅子の利用者も安全に通行できるようにするため、マウンドアップ方式の歩道がある地域の現状を調査し、改善を図るべきについて市長にお伺いいたします。
市長
6月定例会において同様の一般質問をいただいたところであります。 本市では、道路を新設する場合、名取市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例の規定により、歩道部はセミフラットタイプとして整備しております。
御提案いただいておりますマウンドアップ方式の歩道改修については、歩行者通行の多い市道植松田高線や名取が丘中央大通り線で実施しており、平たんに近い形状のセミフラットタイプへ改修を進めているところです。
昔からの基準での歩道が残っている路線としましては、土地区画整理事業や開発行為で行われた大手町地区や名取が丘地区の一部の歩道になります。市にはまだまだ歩道の狭いところやマウンドアップの形状などの歩道が残っていますので、段差解消を図るべく、できるところから取り組んでいきたいと考えております。
吉田
できる限り早くということですので、ぜひ地域の安全のため、住民の方たちの利便性のために取り組んでいただきたいと思います。本市は某経済誌が実施した住みよさランキングにおいて上位にランクインしていますが、本当の住みよさを実感できるまちとは、やはり高齢者や障がい者などの社会的弱者の視線を反映できるまちであろうかと思います。マウンドアップ方式の歩道は高齢者が多い地域の実情によっては多くの危険が潜む場所となり得ます。さらなる住みよさを実現するために、社会的弱者の視線で歩道の現状をしっかり把握し、早目の対策を打っていただきますようお願いしたいと思います。
それでは、最後の質問に移ります。
車両と歩行者がともに行き交う交差点において、歩行者側が弱者であることは申すまでもありません。車両の運転者は歩行者保護に努めなければなりませんが、残念ながら最近ではスマートフォンを操作しながらの運転による死亡事故も、本市内ではありませんが、発生しています。運転者の安全意識の向上が求められますが、啓発活動は効果に限界があります。かといって、全ての交差点に信号機や標識などを設置することも、予算などの面から現実的ではありません。
そこで、現実的な方法で運転者の注意喚起を促すために、小項目(3)歩行者事故の危険性が高い交差点は、路面のカラー化や段差舗装の設置を進めるべきと思いますが、市長、いかがでしょうか。
市長
議員御指摘の歩行者事故の危険性が高い交差点とは、交通量が多く、交差点の構造上の問題があり見通しの悪い交差点や信号機及び歩道のない交差点と思われます。
これまでも、交通量の多い道路の交差点や通学路の指定になっている歩道のない道路などについて、段差舗装や歩道スペースを路面に着色して区別をしています。
今後とも、歩行者事故の多い交差点の現場状況等を勘案しながら、路面表示や着色等の対策を講じて歩行者の事故防止に努めていきたいと考えております。
吉田
昨年、平成27年の1年間に市内で発生した人身事故は456件と聞いていますが、道路形状別の発生状況を見ますと、全件数の半分以上にもなる237件が交差点または交差点付近で発生しています。やはりできるだけ早く交差点における人身事故の発生を抑えていく対策をとることが求められているかと思います。それぞれにメリットとデメリットがあるかと思いますが、今後、カラー化あるいは段差舗装等さまざまな取り組みを地域住民の方たちの声なども聞きながらできるだけ早く進めていただきたいとお願いいたしまして、私の一般質問とさせていただきます。
本会議
(議案第83号 名取市使用料及び手数料の改定等に関する条例について)
吉田
別な場でもお聞きしたことですが、もう一度確認のためにお伺いしたいと思います。使用料を改定した後、使用者等の数が同じ実績と仮定すると、使用料と手数料それぞれについてどのぐらい増収が見込まれるのか御説明をお願いします。
政策企画課長
使用料については、平成26年度の決算額から算出しまして差額として1,130万円ほど増になるという見込みを立てています。手数料も差額として1,189万円ほどの増と見込んでおり、合わせて2,319万円ほどの増という見込みを立てております。
吉田
特に使用料についてですが、使用料金が引き上げとなると、市民の方の中には例えばこれまで利用していた回数を減らすなど、利用頻度が低くなることが想像されるかと思います。今回全ての施設において改正ということで一括で上げられていますが、全体的にで結構ですので、どのぐらい使用頻度が抑えられると見込まれるのか、金額ベースで幾らぐらい考えられるのか、その見込みを教えていただければと思います。
政策企画課長
使用頻度が落ちるのではないかというお尋ねですが、前にも御説明いたしましたが、この点については減る推計は立てておりません。あくまでもこれまで利用された金額によって見込み額を算出しています。
吉田
議題となっております議案第83号 名取市使用料及び手数料の改定等に関する条例について反対の立場から討論を行います。
使用料、手数料見直しにおいて受益者負担の原則と算定方法の明確化という2つの考え方を取り入れたことは、いずれも市民に対する説明責任を果たす上で意義のあることだと認識いたしております。しかし、この基本的な考え方による今回の改定は、結果的に公民館を除く施設における使用料の多くの区分で最大1.5倍の料金引き上げとなっています。料金引き上げの結果どうなるか。市民が施設の利用回数を減らすことにつながり、住民福祉の増進という自治体の目的そのものを遠ざけてしまうおそれがあることが、私が本案に反対する最大の理由であります。
先ほどの御答弁によりますと、今回の改定が実施された上で利用の実績が前年度と同じであれば、使用料は金額にすると約1,100万円の増収が見込まれるとのことでした。しかし、使用料が上がることで、日常的に利用されている方が利用の回数を減らすことは容易に想像できます。また、イベント等で施設を利用する各種団体は使用料の引き上げ分を会費の増額で補うことも考えられます。このことは会員となっている一人一人の負担が増すことに等しく、最悪の場合、活動への参加そのものをやめてしまうケースもあり得なくはないと思われます。市民の文化・スポーツ活動への参加を消極化させてしまうことは、市として歓迎すべきことではないはずです。
こたびの改定は第五次名取市行財政改革大綱実施計画によるものであると伺っております。行財政改革を加速化すべきは私の個人的な信念です。しかし、市民負担の引き上げから入る収益向上は一面的な改革と言わざるを得ません。まず先に行政が身を切る形でコストカットを実行し、経営者としての考え方を取り入れ、施設の持つ価値を最大限に活用することで、利用者の増加による収益向上を図ることがあるべき改革ではないでしょうか。
いずれにしても市民負担の引き上げは最後の最後の段階と考えます。したがって、施設にネーミングライツを導入することや利用率の向上につながる取り組みを行うなど、収益を上げる具体的な方策を検討、実施されることを求めたいところではあります。ただし、今は大綱の内容について議論するべきときではありません。これ以上の言及は避けますが、議題となっている料金の改定については手数料と公民館の使用料にとどめ、それ以外の施設の使用料の改定はほかに必要と思われる対策がなされるまで据え置くべきと考えます。
以上で本案に対する私の反対討論とさせていただきます。
財務常任委員会
吉田
21、22ページ、13款1項4目土木使用料の4節住宅使用料ですが、先日の御説明ですと、収入未済の件数701件ということで金額が1,000万円を超えておりまして、平成26年度に比べて約300万円ふえているかと思うのですが、これについてはどのような要因が考えられるのでしょうか。
都市計画課長
収入未済額の増については、総括質疑のときにも滞納者の対応及び要因をお答えしておりますが、短期の滞納者については高額所得者の方がおりまして、その方が職をやめたということで、なかなか納入ができなくて金額が張ったということと、一括納入が難しい長期滞納者がなかなかお支払いしていただけなかったということで、滞納額がふえたと捉えております。
吉田
不納欠損は平成27年度は発生しておりませんが、今後も不納欠損とならないために、どのように対策をとっていかれるおつもりでしょうか。
都市計画課長
市営住宅については、私法上の債権ということで時効が5年となっております。相手方から時効の援用ということで、時効ですよという申し出がない限りは最大10年の時効期間とい、納入については古いものから納入していただいておりますので、今まで不納欠損というのは生じていなかったところです。
吉田
恐らくこのような事案は本市以外にも各地で相当起きているかと思いますが、ほかの自治体の情報についてどの程度把握していますか。
吉田
23、24ページの13款2項2目衛生手数料の1節飼犬登録手数料についてお伺いします。先日の御説明ですと、新規に307頭の登録があって、総数3,883頭ということでした。それは予防接種ですか。この登録というのは、その仕組みですが、あくまで申請する飼い主側からの申請があっての登録という形になっているのでしょうか。それによって、申請漏れのようなものがないのかと気になるのですが、御説明をお願いします。
クリーン対策課長
新規登録は、あくまでも平成27年度新規に登録した件数、全体で新規ということで捉えておりまして、件数は307件ありました。登録漏れというのは、飼い主からの申請ですので、特に漏れとかいう考えはありません。ないということで捉えております。
吉田
ということは、あくまで登録されている分だけが登録ということで、登録されていない部分はあってないもののような、そういう扱いなのかなという気がするのですが、こちらの金額を見ますと、予算のほうで310万円ほど計上されていますが、今回の調定額がそれよりも下回っておりまして、これはなぜその予算から下回ってしまったのかということについてお伺いします。
クリーン対策課長
当初予算は平成25年、26年等の実績を踏まえて予算化していたところです。実際、ふたをあけましたら、登録件数が新規の分として少なかったという実績ですので、この差が出たということです。
吉田
同じく54ページの18款2項3目有価証券売払収入のところですが、平成27年度にこの2億4,000万円という株を売ったことで、恐らくこの収入になったと思うのですが、418ページを見ますと、有価証券の内容が2億3,502万5,000円からこれだけ今回現金化したということで、残り1,000万円少ししか残っていないわけですが、このタイミングでこれを現金化した理由についてお伺いします。
商工観光課長
こちらについては2月定例会の8号補正で上げているのですが、仙台空港の民営化に伴いまして、今回新たな運営権者ということで市のほうで持っていた仙台空港ビルの株券、こちらの分が1億9,000万円、それから仙台エアカーゴターミナルの株券が5,000万円ということで、この価格で2億4,000万円、それを売却したということで、こちらの金額に載っているものです。
吉田
ということは、株を購入したときとの差額というのは、どの程度発生しているのでしょうか。
商工観光課長
株の取得というか出資価格については2億2,500万円、譲渡のほうが2億4,000万円ということで、差し引き1,500万円の売買の増があったということになります。
吉田
65、66ページの21款1項市債ですが、1目総務債の2節情報システム整備債、これは1億4,600万円ということで調定額になっておりますが、これが全額収入未済となった理由についてお伺いします。
財政課長
こちらの情報システム整備債については、先ほど国庫の補助の収入未済のところで、市政情報課長からも答弁しましたが、番号カード交付関連のシステム改修に係る整備債ということで充当しているものですので、平成27年度に歳出がなかったということで、平成28年度に全額財源を繰り越すということになっているものです。
財務常任委員会第1分科会
吉田
市政の成果の73ページ、4款1項13目の委託料、工事請負費についてお伺いします。消防本部の屋上に太陽光発電設備を設置したということですが、この仕様や発電量などの規模についてお伺いします。
消防本部総務課企画管理係長
まず、導入設備の活用について答弁いたします。通常時は太陽光により発電した電力を照明、通信施設等に使用するとともに蓄電に活用します。また、余剰電力で通常の使用電力を賄います。災害時については、昼間は太陽光による発電を利用し照明、通信、冷暖房施設等に使用するほか、蓄電池に充電いたします。夜間は蓄電池に充電した電力を照明、通信、冷暖房に使用します。基本的に消防本部設置の自家発電設備の補助的な役割となります。
次に、充電量についてお答えいたします。昼間、午前6時から午後6時まで発電量は28.8キロワットアワー、夜間は午後6時から午前6時までということで、充電した28.8キロワットアワーを夜間に使用することになります。夜間の使用量については、内容として、一部制限がありますが、照明、消防本部照明、情報収集のためのテレビ、パソコン、冷暖房設備に使用するということで13.5キロワットアワーを想定しています。
吉田
13.5キロワットアワーですと、最大限に充電して28.8キロワットアワーですから、今の御説明では大体2日間は夜間を通して使用できるのかと思いますが、例えば曇りや雨の日が続く時期に当たって十分な発電量を賄えないような場合、夜間の電力の使用をどのようにコントロールして時間をもたせようとお考えでしょうか。
消防本部総務課企画管理係長
基本的に停電の際は消防本部設置の自家発電設備を使用して、こちらがメーンとなります。自家発電は満タン状態で、本部庁舎関連は72時間、119番等の通信施設についても同じく72時間供給できるように設置しています。その中で今回設置した太陽光発電設備によってその分を補完するということで、自家発電は随時燃料を補給しながら稼働しますので、あくまでも自家発電設備の補完という扱いです。
吉田
市政の成果の138ページに戻りまして、予防活動の(4)民間協力団体の訓練指導の回数で、町内会における防災訓練が33回から26回と平成26年度に比べてかなり減っていますが、この要因についてはどのように捉えているでしょうか。
予防課長補佐
26回はあくまでも消防職員が立ち会った回数です。その他、自主防災組織、町内会で独自で行っているところもかなりありまして、そこは消防署にある水消火器などの資機材をお貸しして訓練をしていただいております。
吉田
消防署の職員が立ち会っての防災訓練の回数が減っているということは、すなわち町内会の中で自分たちで防災訓練ができるというようなことで、町内会の技術や意識の高まりがこの結果としてあらわれているのかと思います。今後この回数はもしかすると今の状態でいけば減っていくかもしれませんが、例えば防災訓練の中身がもう少し充実されれば、もう大丈夫だと捉えられている町内会へもまた新たに行くこともあるかと思います。そのようなことについての今後の計画をお聞きしたいと思います。
予防課長補佐
件数がだんだん減っているのはある意味いい面だと思いますが、立ち上げから数回までは消防署でも立ち会っていろいろな訓練を御提示しています。ただ、いつまでも消防職員が行きますと消防職員の訓練になってしまいますので、自分たちでやってみてくださいと、あくまでも町内会、住民の方が自主的に行えるような指導にだんだん変えています。また、新しい訓練の内容がありましたら御提示するようにしております。
吉田
市政の成果の140ページです。消防活動の成果ということで、火災発生状況と防御活動の表の中の車両の火災4件が損害額が大きくなったことにもつながっていると事前の御説明でありました。この車両火災の4件の中身というか、どのような経緯で発生したかお伺いします。
消防署警防係長
車両の荷台でてんぷらを揚げていたら車両が燃えたという火災が1件。原因は不明ですが、エンジンルームから出火した車両火災が1件。車軸のベアリングの摩擦熱で発生した車両火災が1件。車両の単独事故の衝突事故により発火した1件の合計4件です。
吉田
てんぷらというのは多分御家庭での使用の範囲かと思いますが、それとは違って、エンジンルームからの出火やベアリングの摩擦による出火は、やはり日ごろから持ち主が車をしっかりと維持管理、メンテナンスすることによって防ぐべきものだと思います。このような事例に関して、火災が起こらないように車両の管理についてもいろいろと働きかけをしていかなければならないのではないか。無理して長く乗ったりする方や、必要な整備点検がなかなかできないような状態の方もいらっしゃるかと思いますので、そのような点に対する後の働きかけといいますか対策についてのお考えをお伺いしたいと思います。
消防署長
やはり個人の車は個人で管理するのが一番メーンだと思います。ただし、本市にも観光バスが134台ありますが、それらは、消火器を設置しているか、危険物持ち込み禁止の表示があるか、非常口がスムーズにあくかなど、バス査察で年1回立ち入りをしております。
吉田
今回の市政の成果の表に入っていないのでお聞きしてよろしいのかどうかわからないのですが、平成27年度の通報から駆けつけまでの平均的な所要時間を把握されていたらお知らせいただきたいと思います。
消防署救急救助係長
救急関係については、119番通報から現場到着までの平均所要時間は市内では8分24秒となっています。
消防署警防係長
火災関係に関しては、平成27年度は事後聞知火災の3件を除くと20件出動しており、平均して6分18秒です。
吉田
非常に素早い御対応をいただいて本当にありがたいところですが、この値は平均ということで、例えば極端に時間がかかってしまった事例などはなかったでしょうか。
消防署救急救助係長
救急関係について、入電から現場到着までに30分以上かかった事案を御説明いたします。平成27年度中2件あり、1件目が、酩酊されている方が119番をしてきて内容が不明ということで、警察官と同時に現場に向かいました。これは現場到着まで37分かかりました。この事案に関しては傷病者不搬送となっています。もう1件は、加害事件発生ということで入電しています。この場合も警察官と合流して現場到着まで31分かかっています。この場合も傷病者は不搬送となりました。
消防署警防係長
火災出動についてお答えします。火災出動でも最長で出動から現場到着まで21分かかった事例がありました。これは警察からの入電で警察官の方も場所が特定できないということで受けて、警察官と一緒に探したという事例です。
吉田
先ほどの119番通報から到着までの平均時間に関連した質疑です。例えば酩酊状態で内容が不明などとなると、通報電話とのやりとりで相当時間がとられたりもしたのではないかという気もするのですが、このように時間がかかってしまった事案によって、ほかの本当に救助を必要とされている方の救助に支障になったような事例はなかったでしょうか。
消防署救急救助係長
119番通報が長くなり手間取ったことによる救急出場の遅延に伴って違う隊が出られなかったという事案はありませんでした。
吉田
ただいまの防災ラジオについてお聞きします。平成27年度末の時点で具体的に何台残っているのでしょうか。
防災安全課長補佐
3,632台の引き渡しができたということで、製造数が5,000台ですから、引き渡しをした数を引いて1,368台が残りました。
吉田
その残った台数もこれから購入されることになるかと思いますが、特に市街地など住宅がある部分や今後住宅がふえていきそうな区域で、現時点で防災ラジオの電波が届かないところは市内にあるのでしょうか。
総務部長
高舘の山手3団地、具体的には相互台、今成地区、愛島の方面で一部電波が入らない地区があるということで、平成27年度において中継局の整備を行いましたので山手に関してはかなり改善されたと思っています。ただ、カーラジオは比較的入りやすいのですが、屋内にポータブルラジオがある場合は、それ自体のアンテナの伸ばし方や性能によって入りぐあいに若干差があるようですので、どのようにして聞こえるようにするか、難聴区域がどのような実態かさらにいろいろと調査を行い、個別にお声などをいただきながら、できるだけ難聴区域が出ないよう改善に向けて今後も努力していくように考えているところです。
吉田
市政の成果145ページの防災費です。目標の2行目に「災害時に備え生活必需品及び食料の備蓄を行う」ということで、昨年の決算審査では市内33カ所あるいは学校4カ所などの具体的な数字が説明されましたが、平成27年度の備蓄の状況をお伺いします。
防災安全課長
平成27年度については、品名ですが、災害救助用ハーベストという食料品を買いました。これはお菓子ですが、各避難所によって賞味期限が切れる箇所があります。その賞味期限が切れる年については特に学校で防災訓練に使用していただき、不足したところについて随時補完しながら配備している状況です。
吉田
保存食以外で、例えば毛布などについて、もしふえたものがありましたらお願いします。
防災安全課長
平成27年度については先ほど申し上げたとおり非常食を買いました。そのほかに毛布を20枚買いました。今、具体的な配備については把握していませんが、避難所の一覧表を作成して随時同じような形で配備しています。
吉田
2款1項6目企画費についてお伺いします。市政の成果の1ページに地方創生事業の委託料で地方創生総合戦略策定支援委託料がありますが、支援された範囲をお伺いします。
政策企画課政策係長
策定支援委託料の中身についての御質疑だと思いますが、審議会の会議に同席していただき内容の把握をしてもらう、策定に係る基礎資料の提供、それからアンケート調査も実施していまして、そういった内容が委託料に含まれています。
吉田
市政の成果の3ページ、2款1項8目庁舎管理費で庁舎管理事務の1番、庁舎の維持管理の内容の庁舎清掃等管理業務に電話の取り次ぎということで2名とあります。この2名の勤務の状況というか、交代や日程などどのように組まれているのか、毎日2名が常に張りついているのかなどその辺の説明をお願いします。
財政課管財係長
毎日2名張りついて対応しています。
吉田
平成27年4月からダイヤルインが導入されていると伺っていますが、そのことによって電話の取り次ぎの方の対応する電話件数が平成26年度と比べてどのぐらい減っているのか、具体的な数字でお願いします。
財政課長
平成27年4月1日からダイヤルインを開始し、毎月の1日当たりの受ける電話件数を捉えています。4月は平成26年度は1日最大977件、最小で661件、平均して842件受けていました。これがダイヤルインを導入した直後については最大で823件、最小が591件、平均で683件となり、平均の数字で申し上げると導入当初は19%程度件数が減っています。これを年度末の3月で比較すると、平均の数で申し上げますが、平成26年度は887件、平成27年度は546件で39%減となっています。導入によってオペレーターの方の負担が軽くなったこともありますが、直接担当課につながるということで、電話をかけていただく市民の方の利便性も向上したものと捉えております。
吉田
市政の成果3ページ、2款1項8目庁舎管理費で、先ほどは電話交換手のことをお聞きしましたが、警備についてお伺いします。これを見ると警備は2名ということで契約していると思います。警備員がどのような仕事をするかはしっかり契約書の中で業務の範囲が決められていると思うのですが、聞くところによると、市庁舎の国旗ポールに掲げる日の丸と市章旗の掲揚と降納については警備員が行っているという話だったと思いますが、これについては業務の規定の中に盛り込まれているのでしょうか。
財政課管財係長
契約の中の業務の一部で、晴れの日に掲揚する形になっています。
吉田
そうすると、晴れた日は恐らく夜中に警備をされた方が帰るときに国旗、市章旗を掲げてそのまま帰られるような形だと思うのですが、例えば掲げた日にお昼ごろになって雨が降ってきたと。その場合は恐らく職員がおろすと思うのです。しかし、逆に警備の方が朝方に雨が降っていて掲げず、昼になって晴れた場合、きょうも駐車場から見たら空は晴れているのですが上がっていなくて寂しい気持ちになったのですが、そのあたりについて、警備の方が残していった仕事の一部として職員でこのようなことをしましょうなどということは平成27年度の中ではあったでしょうか。
財政課管財係長
申しわけありません。先ほど契約の仕様の中に明記されていると申し上げましたが、実は特記事項の中で、適宜職員の指示で揚げることになっています。その都度、職員の指示でという形をとっております。
今の御質疑のケースについては、職員のほうで揚げることは今までしておりませんで、朝の状況で警備員が国旗、市旗を揚げるか揚げないか判断をしていました。
吉田
市政の成果7ページ、2款1項10目交通防犯対策費でお伺いします。交通安全事業の2番の交通指導隊の活動について、事前説明で出動延べ回数が3,987.5回にふえた、隊員数も42名から43名と増員されたということで大変ありがたいと思いますが、実際にこの数を1人当たりの出動延べ回数として割り算すると、平成26年度の3,369回を42名で割ったら1人当たりおよそ80回ですが、平成27年度の数で割り算しますと1人当たり90回を超えると思います。増員は1人で出動回数がこれだけふえたというのは釣り合わないような印象ですが、そのあたりの詳しい事情について御説明お願いします。
防災安全課生活安全係長
4月と9月に春と秋の交通安全運動がありますが、平成27年度については4月に統一地方選挙があるということで、4月に行っていた春の交通安全運動を5月に1カ月延ばしたことによるものです。というのは、春休みなど休み明けの登校の際には指導員も出て街頭指導を行うことになっており、その時期と同時に交通安全運動もあるものですから指導員としては重複した形で出てもらっていたところが、平成27年度については、春休み明けの街頭指導と1カ月おくれで行った春の交通安全運動の2回となったため出動が多くなったことが大きな要因の一つです。
防災安全課長
今係長が答弁したことが1つ要因ですが、平成26年度末で隊員の中でいろいろと都合があり退会したいという方が何名かおりました。我々もそのため新しい指導隊員を探していましたがなかなか見つからずに、とりあえず籍を置いていたということで先ほど部長が申し上げた43名でしたが、最終的に出動がゼロ回という方もおりました。平成27年度においては新しい方が4名入り、その方には通常どおりの回数を出ていただきました。そういった要因と先ほど係長が申し上げた要因で今回の指導回数の増となっています。
吉田
ゼロ回の方もいらっしゃったというのは平成26年度の1年間ということだと思いますが、今回の決算の平成27年度1年間を見て、隊員の方はやはりそれぞれ生活をされているわけですから活動の回数はいろいろだと思いますが、一番多く活動された方と一番少なかった方の年間の回数を教えていただきたいと思います。
防災安全課長
この回数については4時間を超えると2回とカウントします。それから、午前中に朝の交通指導に出て、午後からまた1時間出た場合は1.5回となります。特に多かったのは、教育班の班長が交通安全教室を大変数をこなしており、228回です。平成27年度では途中から入った方がいまして、その方が最終的には8回となっています。平成28年2月1日に入隊された方は、当然活動月数も少ないので9回となっています。また、先ほど申し上げたとおり、どうしても仕事上できないということでゼロ回という方も1名います。
吉田
今、教育班という聞きなれない言葉が出てきました。228回ということでかなり頑張っていらっしゃると思うのですが、教育班の具体的な活動の内容の定めがありましたらお願いします。
防災安全課長
市内の保育所、幼稚園、その他子供を預かる場所等に、市から交通安全教室について御案内申し上げます。その中には、春に施設に入ったばかりの方に対して1回、夏の街頭指導、そして秋に再度もう1回ということで3回行う施設もあります。あるいは子供の安全を守ってほしいということで施設から要望があり、それに全て対応しております。それから、春まつりや秋まつり、また地域のお祭りや行事についても交通指導隊の要請、あるいは小学校の安全教室等いろいろな教室が要請されますので、それに対応しており、毎年開催日数はふえている状況です。特に教育班については、非常に熱心な方で、いろいろな器具をそろえて、逆に東京でも発表するぐらいにいろいろなノウハウを持った方ですので、施設からは来ていただきたいということで要請が非常に多い状況になっています。
吉田
そのように大変実力のある方がいらっしゃることは本当に心強いと思いますが、教育班の方は平成27年度では何名いらっしゃったのか。そして、教育班の方に限っての出動延べ回数について御説明をお願いします。
職員防災安全課長
平成27年度で教育班に所属している方は5名です。先ほど言いましたとおり一番多い方で228回、少ない方、これは急に仕事の都合が入って出られなくなった方で、そのしわ寄せが特に班長に行ってしまったのですが、50.5回の方もおります。それ以外の方は170回近く出ています。
1人ずつ言いますと、166.5回、228回、50.5回、196回、169.5回であり、その合計が延べ回数になります。
吉田
市政の成果7ページの2款1項10目の交通防犯対策費でもう一度お伺いします。先ほど隊員として活動されている方には活動の回数や時間に応じて手当が支給されているということでしたが、支給のされ方というか、どのような申請を行ってどのように渡すのか、その手順をお伺いします。
防災安全課生活安全係長
各隊員に出勤表が渡されており、それを毎月各地区の班長に提出し、班長が確認、取りまとめの上、市に提出という流れです。
吉田
例えば何名もの方に指導に当たっていただくということで、特に交通安全運動の期間なども多くの方が活動されていると思います。その活動の内容といいますか、例えば交差点1つ当たりに何名も張りついて1日だけ行うよりも、人数を分散させたほうが子供たちの安全のためにはより効率的であるなどいろいろな考え方があると思うのですが、活動の内容についての把握、それからこのように行ったほうがいいなどの指導はどのように行われたのでしょうか。
防災安全課長
指導隊については基本的に年間の出動カレンダーをつくっております。春の交通安全運動や子供たちの春休み、夏休み、冬休み明けの1週間、あるいは夕暮れ時期の運動など決められた出動カレンダーがあります。そのほかには、先ほど申し上げたとおり要請に基づいて出ることがあります。その場合は団体から場所を指定されて要請があるので、そのもとに指導しています。出動カレンダーに基づくものについては、学校あるいは各地域によって指導隊の人数も若干違いますが、特に子供たちの通学路の交差点に立っていただいているのが実情です。地域によって先ほど申し上げたとおり人数が違いますので、指導隊のほかに地域の安全協会あるいは父兄の方にも御協力いただきながら、特に朝の交通安全についてはいろいろな関係団体と連携をとって指導しているところです。
吉田
市政の成果14ページの18目の地域情報化推進費です。先ほどの御説明によると、平成22年度に開始した双方向型のシステムについて平成27年度で終了したということでしたが、廃止された背景について御説明をお願いします。
政策企画課政策係長
いわゆる市民の広場と呼ばれる情報提供事業ですが、冒頭に部長が説明したとおり平成27年度で廃止となりました。一番大きいのは、やはりスマートフォンを使った情報ツールといいますか、そういった環境が5年前と比較してかなり変わってきていることもあり、今のシステムではなかなか機能がカバーし切れないため一旦廃止とさせてもらったということです。