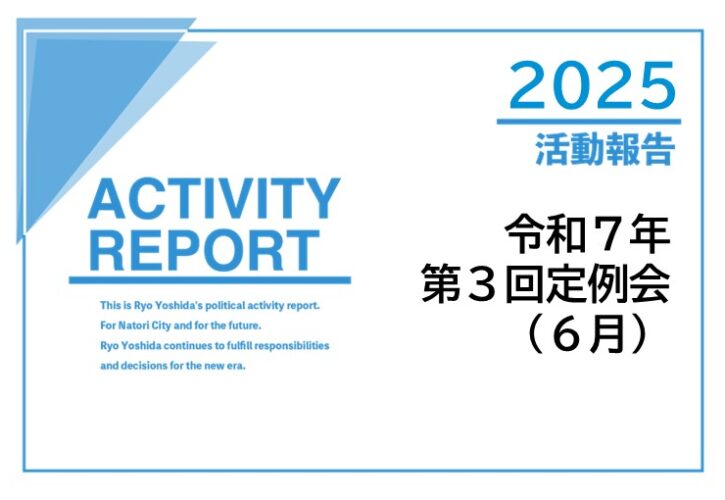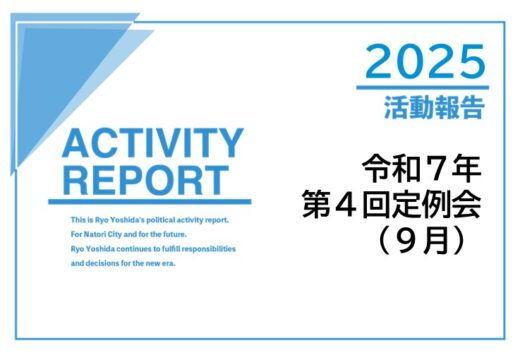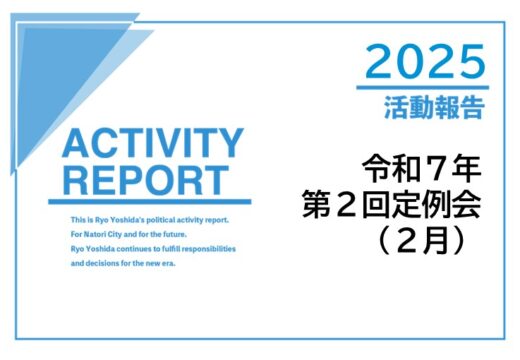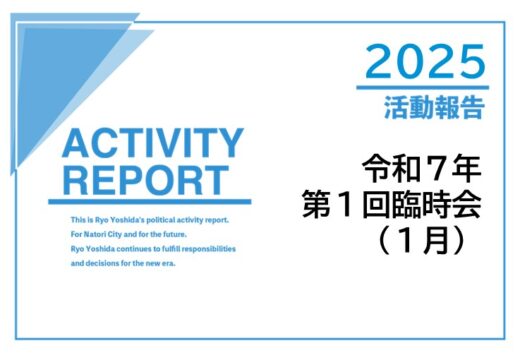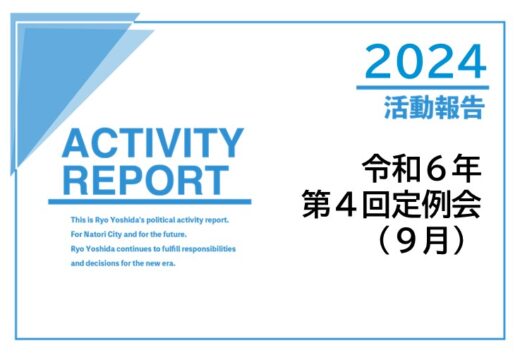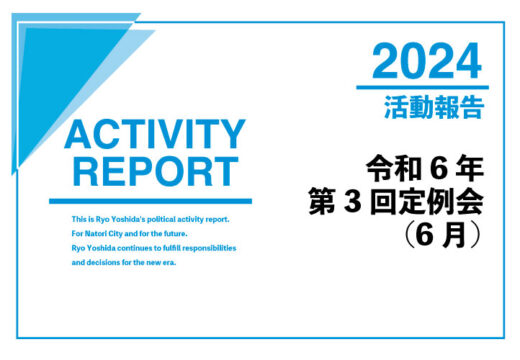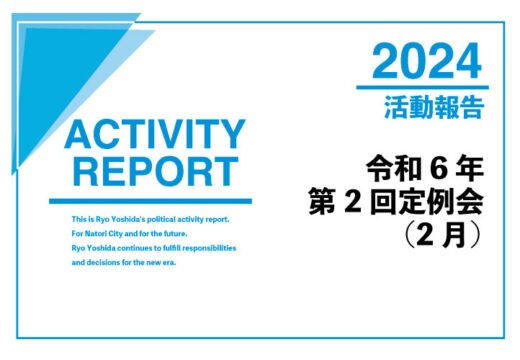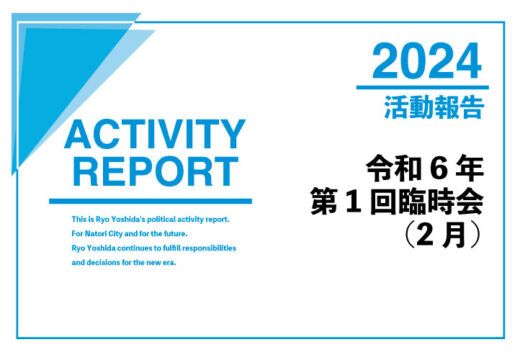本会議
(議案第46号 専決処分の承認)
吉田
令和7年度の国の税制改正に伴う今回の条例改正ということですが、その税制改正の部分で、市がどのぐらい把握されているのかお伺いしたいことがあります。所得税の控除の範囲が広がっていくということは、単純に言えば納税者の所得税の納付額が減っていくことになると思います。令和7年度の所得税額によって令和8年度の市民税などが決まっていくと思うので、所得税の納付額が減れば市民税もそれに影響されて、一般論としては市に納める額が減っていくという考え方でよろしいのですか。
税務課長
所得税との関連というよりは、このたびの税制改正で、特定親族特別控除の新設、あるいは給与所得控除の最低保障額の引上げ等がありまして、所得控除の市全体の総額が増える分、そのことによる一定の減収はあるのではないかと捉えているところです。
吉田
仮に減収があるとして、現時点で国から、その補填の在り方のようなものについては何か示されているのでしょうか。
財政課長
控除額が増えることによって税収が減る分の補填についてですが、市に影響が出てくるのは令和8年度以降と捉えております。現時点においては国から何も示されていない状況です。
(議案第49号 専決処分の承認)
吉田
18、19ページ、13款2項1目土地取得費、財源更正についてですが、第1号補正で病院用使用貸借用地取得費として減額補正されたものの財源更正だと思います。第1号補正のときには地方債とその他、両方とも減額となっていましたが、今回、改めて財源更正する理由をお伺いいたします。
財政課長
病院用使用貸借用地取得費については、18億4,900万円の財源について、起債75%、13億8,670万円、ふるさと振興基金繰入金4億6,230万円を見込んでいたところですが、今般、県より市町村振興資金貸付金として15億円借入れすることができたため、起債額を1億1,330万円増額し、ふるさと振興基金繰入金を1億1,330万円減額するものです。
吉田
その借入れは、12、13ページ、歳入の22款1項9目諸支出金債の起債が恐らく充てられると思いますが、こちらについては交付税措置みたいなものはなく、元金は全額返さなければならないというものでしょうか。
財政課長
議員お見込みのとおり、交付税措置はないものと捉えております。
(議案第58号 名取市サイクルスポーツセンター条例の一部を改正する条例)
吉田
上限額の設定という形に変わったということですが、今、下限というか、最低限の額は設定されていませんので、市長の承認が要るとはいえ、指定管理者側が現行の使用料よりも低い金額で宿泊料金を設定することは想定されるのでしょうか。
商工観光課長
現段階で指定管理者がどのように設定するのかということは、私もなかなかお答えできないのですが、当然、繁忙期であれば現行の料金より上がったり、例えば閑散期などはもう少しリーズナブルな価格設定も十分考えられるかとは思っております。
吉田
安い金額でも、たくさんの方に利用してもらえて売上げとして上がっていけばそれにこしたことはないと思いますが、あまり安売りし過ぎてしまって事業者側の赤字が増えてきたりしてもいけないと思います。仮にそういうケースが起きた際に、市が指定管理料以外に、そこの部分の穴埋めをするようなことはあり得るのでしょうか。
商工観光課長
そういった部分の穴埋めは考えておりません。あくまでも指定管理料の中で行っていただくと。我々としても、そうならないように承認のプロセスを取っていますので、その辺は十分注意しながら進めていきたいと思っています。
吉田
第12条第3項です。これはさきの議員協議会でも質疑が出て、その段階では検討中ということでしたが、事業費全体を超過した場合、超過額の一部を納付金として市が徴収するとされております。この条文を読んでも、市長は必要と認めるときということと利用料金の一部ということで、どのぐらいのボリュームなのかが分からないところがあるのですが、今申し上げた2点について、現時点でどの程度まで固まっているのかお伺いいたします。
商工観光課長
まず、納付金については、指定管理料と利用料金の収入から実際にかかった経費を差し引いた余剰分を利益として、その中の一部という形で市に納付いただくという制度になります。
その一部がどのくらいの割合なのかというと、まだ我々もそこまでほかの事案をいろいろ把握しておりません。同じように利用料金制度で運営されている事業者などにも聞いてはおりまして、その事業者は10%だという話を聞いておりますが、まだそこしか聞いていないので、今後、募集をかけるまでに、類似施設であったり、市町村であったり、いろいろ情報収集をしていきたいと思っております。
吉田
「必要と認めるとき」ということで、では必要があると認めなければ徴収しないのかということにもなりますので、この「必要と認めるとき」というのがどういうときに当てはまるのかということと、その金額の割合については、仕様書にしっかりと明記しなければいけないと思いますが、その辺のお考えはいかがでしょうか。
商工観光課長
その必要と認める場合、またその割合については、しっかり提示しないと、逆に手を挙げる方がちゅうちょする可能性もありますので、その辺も含めて、いろいろ近隣の類似案件などを調査させていただいた上で、公募に向けて取り組んでいきたいと思っております。
(議案第67号 訴えの提起)
吉田
先ほどの御説明ですと仙台地方裁判所にまず訴えを起こすということで、相手方は遠方の方ということですが、今回これが可決されたと仮定して、裁判のスケジュールをどのように考えているのかお伺いいたします。
社会福祉課長
この議決をいただきましたら、裁判所に書類を提出して、その後、何度か出向いて公判などがあると思います。その後、1年ぐらいで終結して、債務名義取得に至るかと考えております。
吉田
その相手方が今どういう経済状況なのかも分からないので、仙台地方裁判所でその裁判が進んでいくというときに、こちらまで出向いてくることはなかなか難しいのかなと思ったりします。もちろん、この災害援護資金はしっかり返している方が大半ですから、公平性、平等性からいっても借りたものは返してもらうのが当然だと思いますが、裁判の判決が出て、時間ばかり経過して結局何も得られるものがなかったみたいなことにならないのかなということも少し心配なのですが、その辺どのように考えておられますか。
社会福祉課長
これまで行っていた支払い督促の申立てなどで、裁判になったのをきっかけに連絡が取れるようになる方が多くいらっしゃるので、この方からも、裁判所から書類が行くことで市に連絡があればと期待しております。
あとは、この裁判で債務名義を取得して、その後も音信がなかった場合ですが、それでも、債務名義取得によって時効が延び、こちらで債権を放棄することがなく済むので、そこだけでも実施したいと思っております。
一般質問
吉田
14番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、事前の通告に従いまして一般質問を行います。
初めに、大項目1 名取市環境美化の促進に関する条例の運用についてお伺いします。
昭和60年4月、本市では、市民、事業者、土地または建物の占有者、市等が一体となってごみの散乱を防止するとともに、散乱ごみの清掃を行うことにより環境美化の促進を図ることを目的とする名取市環境美化の促進に関する条例が施行されました。制定・施行からかなりの年数が経過していることもあり、まずは確認させていただきたいと思います。
小項目1 条例を制定する背景となった課題と、現在までの課題解決状況を市長にお伺いします。
市長
昭和60年4月に施行された名取市環境美化の促進に関する条例は、缶飲料の自動販売機の普及等に伴う空き缶、空き瓶等のごみの散乱が全国的な社会問題となり、地域の環境美化の促進を図るため本条例の制定に至ったものと捉えております。
現在まで、市民、事業者、市等が一体となり、町内会等による地域清掃活動や、環境美化看板の設置によるポイ捨て禁止などのマナー向上の啓発等に継続して取り組んでおり、地域の環境美化が一定程度保たれていると捉えております。
吉田
地域の環境美化が一定程度保たれているということですが、もう既に30年近く経過をしていますので、制定当時といろいろと比較をしてみたいと思います。まず、比較の材料として、第二次名取市環境基本計画を策定する際に行われたアンケート調査を取り上げます。こちらによりますと、前計画策定時、散乱ごみが少ないと思う人の割合は39.0%でした。しかし、第二次名取市環境基本計画では、まちのきれいさの満足層が62.0%と、設問が異なるので単純に比較することはできませんが、満足度が上昇傾向にあると言えると思います。
しかし、別な見方をすると、自然環境と生活環境を合わせた身近な環境8項目の中で、まちのきれいさの満足層の割合は最下位となっています。また、改善したい環境として、30.5%の市民が「まちのきれいさ(ポイ捨て、ごみの散乱)」を挙げており、14項目中第3位となっています。なお、こちらの場合ですと、第1位は「公共交通の便」、それから、第2位は「道路環境(道路渋滞など)」となっていまして、いずれも身近な環境には含まれない、いわゆる環境美化の範疇ではないといった項目です。改善したい身近な環境という観点では、まちのきれいさ、ポイ捨て、ごみの散乱が引き続き第1位であると言えると思います。まず、この点について認識を確認したいと思います。
市長
アンケートをどう読むかということだろうと思います。先ほど一定程度と申し上げたとおり、完全によくなったとは捉えていません。
一方で、他市から本市に来られた方に、結構きれいなまちですねというお話をいただくこともありますし、不法投棄はまた別の問題として、ごみの散乱等に対する苦情についても、あまりないというのが現状です。
吉田
今、市民意向ということで主観的な見方だと思うのですが、これを客観的に捉えるとどうなるかということで、例えば、ポイ捨てされるごみの量を客観的な数量として捉えているのかどうかお伺いします。
環境共創課長
ポイ捨て等されているごみの量を客観的に捉えているものはありません。
吉田
環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課が令和6年3月に公表した令和5年度「ポイ捨て」に関する調査報告書によりますと、ポイ捨てされたごみの量を調査していると回答した市区町村数は154、有効回答数1,741の約9%でしたが、本市はこの9%に含まれていないということでよろしいですか。
環境共創課長
町内会清掃等で集められたごみの袋の数等は捉えていますが、量としては捉えていません。
吉田
いろいろな捉え方がありますし、国で全体を統一する基準がないのでほかと比較するのは難しいと思いますが、ごみを取り巻く状況ということで見れば、ポイ捨てされることが多いものの種類や場所も先ほどの環境省の調査に示されています。そうしたことについて、条例制定当時と比べ、今、社会情勢がどのように大きく変化していると捉えているのか、お伺いします。
環境共創課長
条例の制定当時は昭和60年ということで、市長が答弁したように自動販売機ができ始めたときでした。現在、自動販売機は当たり前のものになっているので、そこについての状況は変化してきていると捉えています。
吉田
ほかにも、例えばコンビニエンスストアの数がかなり増えたとか、あるいは最近ですと新型コロナの影響でマスクをする人が増えて、マスクのごみが多く見られるということもあって、いろいろ状況は変わってきていますので、やはり今の状況に合わせた形での対策は常に模索をしていかなければいけないと思います。
それでは、次に移ります。条例の運用状況についてです。
令和7年4月、増田神社の例大祭の前日に、みこしの担ぎ手の有志と共にみこし渡御のルート周辺でごみ拾い活動を行いました。本市のシンボルである衣笠の松付近に20個を超える空き缶やペットボトルが散乱していたのは非常に残念でした。もちろん、これは全部回収しました。そして、そのすぐそばに自動販売機が置かれているのを確認しましたが、空き缶を回収するための容器の姿はありませんでした。
本条例によると、環境美化促進重点地域では回収容器の設置が義務づけられているはずです。衣笠の松がある増田防災広場では市が関与するイベントも多く開かれており、重点地域に指定されていて当然と思っていたため、自動販売機の設置者に回収容器を設置させるよう担当課に対応を求めました。ところが、当該場所は重点地域には指定されていないとの返答でした。それでは、重点地域としてどこが指定されているのかを尋ねると、驚いたことに重点地域は指定されていないとの答えが返ってきました。
改めて条文全体を読むと、守られていない規定がほかにもあることに気づかされました。その全体を把握するために、ここで確認させていただきます。
小項目2 遵守されていない規定があることについて、どのように捉えているのか、市長にお伺いします。
市長
条例で規定されている地域環境美化促進計画の策定、環境美化促進重点地域の指定、環境美化推進員の選定など、一部形骸化しているものがあり、早急に現行条例の課題を整理し、条例の改正に向けて見直しを検討したいと考えております。
吉田
その見直しの検討ですが、過去にどういう議論があったのか、私も市議会のホームページで会議録を検索しましたが、名取市環境美化の促進に関する条例が守られていない問題は、平成8年3月の予算特別委員会から指摘をされています。平成8年というのは、現在インターネットで公開されている会議録の最も古い年で、その発言をされた議員は、3年か4年前から度々言ってきて、もう3回目だ、とそのときにおっしゃっています。また、平成8年9月定例会では、別の議員からの一般質問に対し、当時の石川市長は、前々から指摘があるので、一部見直しなどの検討もしながら実効性のあるものにしたい、と答弁しています。さらに、平成9年12月定例会の一般質問では、一部改正を現在検討中と当時の市長が答弁しています。このとき、今回在職25周年の議員の方々が表彰されましたが、その方々が議員になる前からそういう問題が指摘されてきて、今もなお条例が改正されていない、適切に運用されていない状況が続いています。なぜ、今に至るまで条例の運用の部分が改善されていないのかお伺いします。
副市長
名取市環境美化の促進に関する条例が制定され、それに取り組んできたことは議員御指摘のとおりですが、その後に名取市環境基本計画を策定しました。そして、様々な要因があるとは捉えていますが、名取市環境基本条例を制定し、名取市環境基本計画を策定する中で、様々な施策、事業を展開してきたところです。また、地球環境を含めて取り巻く環境、取り組むべき課題が目まぐるしく変化するなど、その対応を優先してきたところもあります。
環境美化については、啓発活動のほか、名取市環境衛生組合連合会をはじめ地区のボランティアや様々な団体の皆様がごみ拾い、美化活動などその実施を推進してきたことなどがあります。
そういったことがありまして、なかなかその条例を改正し、具体の取組まで至らなかったところが背景にはあると思いますが、そうであるから条例を改正しなくていいということではありません。御指摘をしっかりと受け止めて、整理し、対応していきたいと考えています。
吉田
刻々と状況は変わっていますので、その対応が遅れてきたことは紛れもない事実だと思います。やはり今回市長が検討していきたいとおっしゃいましたが、早急に進めていただきたいと思います。ただ、その進め方にもいろいろありますので、その部分について、これから確認していきたいと思います。
まず、具体的に今おっしゃったところで、御答弁の中では指摘されていませんが、本条例の第4条第3項では公園、広場、駅等の公共の場所の管理者にはごみを回収する容器の設置が義務づけられているはずです。こちらについては設置されていない場所があると思います。逆に設置されている場所等があれば、お伺いしたいと思います。
環境共創課長
屋外ということでお答えしますが、公共施設等で自動販売機の飲料の空容器回収以外のごみ箱については、現在設置していません。
吉田
次に、第6条の地域環境美化促進計画です。こちらが策定されていないのは、恐らく環境基本計画と重なるところがあるからだと思うのですが、環境基本計画を策定する際にそのあたりの整理はされなかったのかどうかを経緯として伺います。
環境共創課長
第二次名取市環境基本計画については令和2年度から取り組んでいます。その際に、第一次名取市環境基本計画の整理をしました。第一次名取市環境基本計画ではポイ捨て禁止条例の制定について検討すると整理をしていましたが、ポイ捨てよりも大規模な不法投棄が多くなってきている現状に合わせ、制定を見送ったと整理をしています。
地域環境美化促進計画については、第二次名取市環境基本計画の中に地域の美化活動を促進します、と明記をしています。そこに包含をしているというところまでは整理していませんが、計画の中で着実に遂行しているということで、現在取り組んでいます。
吉田
具体的な対応は後でもう一度振り返りたいと思います。
次に、第7条です。環境美化促進重点地域は、なぜこれまで指定されてこなかったのでしょうか。
環境共創課長
環境美化促進重点地域については、指定をすることができるという条文になっていますので、必ず指定しなければならないわけではないと整理をしています。どこを指定すればよいのかについての整理はなされなかったと捉えています。
吉田
確かにできるとはなっていますが、条例をつくったのは市ですので、市がその重点地域を指定しなければ、その以下の条文の有効性がないわけですから、指定するという前提の下につくられたはずですよね。それがされていないというのは、やはりおかしいのではないかと思います。
そして、先ほど市長から、今後のことについても検討していくという答弁がありましたが、もし条例を改正するとなったときに、将来的にどういう方向性での改正が考えられるのかお伺いします。
生活経済部長
本条例の目的は、まちを美化する、ごみの散乱のないまちにしていくことが趣旨です。その目的を推進するために、他自治体の環境美化の促進に関する条例やごみの散乱防止に関する条例を参考にしながら、現在のごみを取り巻く情勢に合った条例の改正に向けて検討していきたいと考えています。
具体にどういった規定を設けるのかまではまだ至っていませんので、今後検討していきたいと考えています。
吉田
大事なのは、その条例の文章を守るとかではなくて、やはりその目的や趣旨を守っていくこと。そして、それを深めていくことだと思います。改正そのものに私は必ずしも反対するわけではありませんが、この趣旨が後退するような形での改正にはならないように、そこはくれぐれもお願いしておきたいと思います。
それでは、次に移ります。空き缶等回収容器の設置についてです。
現在、自動販売機のある市内多くの場所には空き缶等回収容器も設置されています。重点地域の指定がない現状では、事業者に設置と維持管理の義務はないはずですが、協力していただいているのであれば大変ありがたいことです。事業者の環境美化に対する意識も変わってきていると思われますし、回収容器の設置箇所が増えれば、ポイ捨ても減ることが期待されます。
そこで、小項目3 第7条で市長が指定することができるとされている環境美化促進重点地域を市内全域に指定し、空き缶等回収容器の設置を原則とすべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
環境美化重点地域の指定の在り方については、現行条例の見直しの際に検討したいと考えております。なお、空き缶等回収容器については、市から小売業者へ、設置及び適正な維持管理について協力依頼をするとともに、ごみの持ち帰りについては改めて市民に周知をしていきたいと考えております。
名取市環境美化の促進に関する条例施行規則の中で、重点地域の指定については、ごみの散乱の状態であるとか地域の実情等に合わせて指定をしていくということになっています。
また、先ほど個別具体の自動販売機の話もありました。そういった個別の事例については、販売元も含めて善処していきたいと考えています。
吉田
確かに施行規則の第2条にごみの散乱の状態及び地域の特性を勘案してとは書かれています。しかし、第3条で定める自動販売機を除く自動販売機の設置状況については、重点地域の指定がない中で、市として市内全体の把握ができているのかどうか。第3条で定めるものを除く自動販売機の設置状況について、現状をお伺いします。
環境共創課長
自動販売機の設置台数は捉えていません。
吉田
かなり多くの自動販売機があるので、全部捉えるのは大変なのかなとも思ったのですが、他自治体の事例を見ますと、必ずしも捉えていないわけではなくて、例えば、東京都町田市、大阪府枚方市、静岡県伊東市などでは、条例に基づいて自動販売機の設置の届出を義務づけています。他自治体でできることを本市が行わないのは怠慢ではないかと私は思います。条例までつくっていますので、本市も、設置や管理の状況を正確に把握するため、条例第8条以下の届出に関する義務を適正化すべきと考えますが、いかがでしょうか。
市長
ただいま御指摘いただいた点も踏まえて、現行条例の見直しの際に検討したいと思います。
吉田
見直しもどのぐらいのスケジュールで考えておられるのか、お伺いします。
市長
現行の条例と地域の今の実態、世の中の流れに必ずしも合っていない部分があるということは感じておりますので、できるだけ早く改正に向けて動いていきたいと思っています。
吉田
平成8年からそういう答弁が続いてきているので、また令和が終わっても同じことを引き続きということはないように、必ず市長の代で実行してください。よろしくお願いします。
それでは、次に移ります。次は、ごみを回収する容器、一般的にごみ箱と呼ばれる容器の設置についてです。この設問については、平成30年12月定例会及び令和元年9月定例会の一般質問で取り上げた経緯があります。市は様々な理由を並べて屋外への設置をしていません。ところが、条例を読むと、市や市教育委員会がごみを回収する容器を設置する義務があるとしか読み取れない部分があります。
そこで、小項目4 第4条第3項で、公共の場所の管理者に設置と維持管理が義務づけられているごみを回収する容器を、多くの人が利用する市の管理施設に設置すべきと考えますが、市長と教育長の御見解をお伺いします。
市長
過去に設置しておりました公園のごみ回収容器では、粗大ごみや危険物などの不法投棄の誘発が見受けられ、地域の環境衛生の悪化を招くとして、設置を控えたという経過があり、今後、現行条例の見直しを検討したいと考えております。
また、自ら生じさせたごみは持ち帰ることが基本であり、ポイ捨て禁止などのマナー向上と併せて啓発していきたいと考えております。
教育長
文化会館や市民体育館などの施設においては、屋内外の自動販売機の空き缶等を回収する容器を除き、ごみ箱は設置しておりません。
市民からの要望もなく、施設の敷地内においてごみが散乱している状況が見受けられないことから、現時点において新たに設置することは考えておりません。
吉田
施設の全部に設置しろということではないと思います。今の御答弁に対するこちらからの考え以前に、第4条第3項がいうところの管理者に市と市教育委員会が該当する施設はあります。公園や駅前の広場などが該当すると思いますが、そのあたりはどのように捉えているのかお伺いします。
環境共創課長
今、議員御指摘のとおり、公園等この条文に該当する公共施設はあると捉えています。
なお、一方、市長が答弁いたしましたように、ごみは持ち帰ることが基本ということもありますし、以前設置したものを撤去して以降、新たにごみ箱を設置してほしいという直接的な要望は、最近は寄せられていません。
吉田
市長も課長も御答弁されたように、自分のごみを自分で持ち帰るということが基本というのは当然だと思います。ただ一方で、残念ながら持ち帰らないでポイ捨てする人がいるのも現実です。また、そうではなくても、ごみを誤って落としてしまい、そのことに気づかないようなケースもあり得るわけです。私も市内を歩いていると、お菓子の包装ですとか使用済みマスク、また、ちり紙などが道端に捨てられているのを見かけることは珍しくありません。ごみを回収する容器が設置されていれば拾って捨てたいのですが、屋外に置かれていないという事情があります。自宅に引き返して捨てるような時間の余裕もありませんし、また、レジ袋などを持ち歩いて、それを入れて持ち歩くのも抵抗があります。やはりそのために見て見ぬふりをせざるを得ず、とても嫌な気持ちになります。公共の場に、もしごみを回収する容器が置かれていれば、拾ったものを捨てて、手を洗って心もすっきりすると思いますので、場所によっては条例のとおり設置すべきと考えますが、市長はどのようにお考えでしょうか。
市長
この問題は非常に難しい問題をはらんでいます。過去において、条例に定めているとおり設置した結果、かえって本来の目的である地域の環境美化の促進が損なわれる事態に発展してしまったことがあります。公園のごみ箱の中に犬のふんが捨てられていたこともあったと伺っています。ですので、議員おっしゃっているような良識ある方が拾って捨てておきたいという気持ちと同時に、地下鉄サリン事件等があって、ごみ箱の設置の話もいろいろと難しい問題が出てくる中で、必ずしも設置することが環境美化、そして安全につながらないというところがあったものですから、慎重にならざるを得ないと思っています。ただ、全く設置しないということではありませんので、個別の実情に応じて、御指摘等があれば、市の内部で検討して、必要に応じて設置をすることはやぶさかではないということです。
吉田
不法投棄の誘発も確かに考えられます。その対策もないわけではありません。平成30年に施行した頃に比べると、防犯カメラが大分普及してきていることもありますから、テロ行為も含めて、防犯カメラを設置し、録画中であることが見えるようにごみ箱に表示しておけばよいのではないかと思います。そして、これは各種犯罪の抑止にもつながりますから、決して方法がないわけではないと思います。
このように防犯カメラの性能やコストは条例制定時よりも格段に向上していますので、まずは多くの人が利用する管理施設1か所で実証実験を行ってみてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
市長
防犯カメラの設置についても、プライバシーも含めたガイドラインがあります。今御指摘いただいたことについては、内部で検討させていただきたいと思います。
吉田
次に移ります。事業者等への対応についてです。
本条例第2条には市民等の責務、第3条には事業者の責務、第4条には土地又は建物の占有者等の責務が書かれています。責務とは一般的に責任と義務のこととされ、責務規定は努力義務より強い規定と言えます。本条例制定時の強い意気込みを感じさせるものでありますが、現状は形骸化してしまっているものがあることは否めません。本市の環境美化が一層促進されるためには、それぞれの責務が自分事として捉えられ、実践につながっていくことが必要であり、条例を制定した名取市は率先して役割を果たしていくことが求められます。
そこで、小項目5 市は条例を遵守した上で、第2条から第4条までの責務が守られていない事例に対し、必要に応じて助言または指導するとともに、第5条に規定される必要な協力要請を行うべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
多くの市民、事業者、土地または建物の占有者は環境美化の促進に取り組んでいただいていると捉えておりますが、個別、具体な事例があった場合については、市として必要に応じて個別に指導、助言を行うとともに、協力要請を行ってまいりたいと考えております。
吉田
そういう個別な事例がもしあったとしても、まず、市が自分でつくった条例を自分で守れていないという現状は大問題ですので、そこを解消しないとなかなか本質的な話には進んでいかないと思います。まずこれを喫緊の課題として全体的な見直しは進めていただきたいと念を押してここで申し上げておきたい。
また、例えば、矛盾点を解消するために条例を改正するとした場合に、現実路線として、第6条の地域環境美化促進計画を名取市環境基本計画の中で整理することや、あるいは第18条の環境美化推進員については清掃推進員と置き換えて運営するということもあり得ると思います。全部一気に変えるということではなくて、できるところから進めていってはどうかと思いますが、進め方の考え方をお伺いします。
市長
議員御指摘のとおり、環境基本計画や清掃推進員制度で読替えができる部分については早急に対応していきたいと思いますし、フレキシブルに対応していきたいと思います。条例制定まで全てのことを今のままにしておくのではなくて、できるところから進めていきながら、最終的には現行条例の見直しにつなげていきたいと思います。
吉田
それでは、次に大項目の2 ウエルビーイングの推進と指標の活用についてに移ってまいります。
ウエルビーイングとはそもそも何か。その定義については、ここでは文部科学省が2023年に策定した第4期教育振興基本計画から引用しておきます。どのようなことが書かれているかといいますと、身体的・精神的・社会的によい状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念であり、また、多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、個人を取り巻く場や地域・社会が幸せや豊かさを感じられるよい状態にあることも含む包括的な概念とされます。以上は個人のウエルビーイングですが、集団・組織のウエルビーイングというものもあります。
ところで、国際社会における豊かさの尺度として、1930年代から経済成長率、GNPやGDPが用いられてきました。その価値基準は、言わば量的拡大というものでありました。GDPを尺度とする経済発展において、世界が大きな進歩を遂げたことは確かです。しかし一方で、環境破壊や格差など新たな危機に直面しているという世界的な認識が広まり、2010年頃を境に豊かさを示す新たな指標づくりは急速に進められるようになりました。それらが目指す共通の概念がウエルビーイングです。2015年に国際目標とされたSDGsについても、3番目の項目の原文にウエルビーイングが含まれています。GDPに代わる指標としてのウエルビーイングの取組は、日本ではなく、諸外国や国際機関が先導しているのが実情です。
日本では、2011年に民主党政権の下に幸福度指数試案が作成されましたが、政権交代後の第2次安倍内閣は、アベノミクスを掲げ、GDP路線へと回帰し、ウエルビーイング路線は後退しました。その後、2019年の経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針で、初めて「人々の満足度(Well-Being)」という用語が用いられるという経緯です。
日本社会においても、近年、ウエルビーイングが注目されるようになりました。そうなったのには幾つか理由があります。その一つに、デジタル庁が2024年に、地域幸福度(Well-Being)指標利活用サービスを公開したことが挙げられます。また、民間では2021年にウエルビーイング学会が設立されました。当学会は日本初、世界初のウエルビーイング研究に関する学会誌の創刊を令和7年10月に予定をしています。政府や民間団体によりウエルビーイングに関する様々なレポートの公表が進む中、本市の実情を確認したいと思います。
小項目1 地域幸福度などと訳されるウエルビーイング指標について、本市の実情をどのように把握しているのか、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
令和6年度デジタル庁が実施したWell-Being全国調査において、名取市の幸福度や生活満足度は全国平均を上回っているという結果が出ております。
また、名取市第六次長期総合計画の見直しに伴い、令和5年度に実施した市民意識調査でも、名取市に住み続けたいと回答した方の割合が約8割と、前回調査から大きく伸びており、現状、名取市での生活に幸福感、満足感を感じている市民の割合が多い状況と捉えております。
デジタル庁調査における個別のカテゴリーについても、多くの項目において、住民アンケートから算出した主観指標が、関連施設の整備状況などの客観指標を上回っているなど、当市の生活環境に満足いただいている割合が高いと認識をしております。
教育長
教育委員会では、教育に関する基本的な方針として教育振興基本計画を定め、各分野において生涯学習振興計画などを策定しております。このことにより子供たちの健やかな成長を支える環境づくりや、市民の生涯学習の推進に努めているところです。
ウエルビーイング指標につきましては、現時点では本市の教育行政において直接的な活用は行っておりませんが、幸福度や生活満足度を把握することは、教育施策の充実において重要な要素であると認識しております。
教育委員会では、各分野の計画策定に当たり、市民を対象に意識調査などのアンケートを実施し、その結果を踏まえてよい点をさらに伸ばすことや課題改善につながる取組を計画に反映させることにより、幸福度や生活満足度の向上に努めているところです。
吉田
現状の認識についてお伺いしましたが、今、急にこういう話が出てきて、何のことだか分からない方もたくさんいらっしゃると思うので、もう少しウエルビーイングについて話をします。そもそも個人のウエルビーイングが高いとどういう効果が生まれるのか、これがある一定の研究から明らかになっています。例えば、先進国を対象とするある調査によると、幸福度が高い人はそうでない人より7年から10年くらい長寿になるという結果が出ています。また、会社組織において、幸福度の高い社員は、そうでない社員に比べて、創造性が約3倍、生産性が31%、売上げが37%高く、また、欠勤率は41%、離職率は59%、業務上の事故は70%低いという調査結果もあります。こうしたことを自治体に置き換えれば、住民のウエルビーイングが高まることで、よりよいまちになっていくことにつながっていくと私は思います。
先ほど御答弁の中でもおっしゃっていましたが、このウエルビーイングの現状、実情を的確に把握して、それを施策に活用すること、最低でも指標をしっかり意識していくことは必要だと思いますが、その点についてお二人の御見解をお伺いします。
市長
先ほども御答弁申し上げたとおり、名取市第六次長期総合計画の見直しに際しての市民意識調査の項目が、このウエルビーイングの項目と重複しているところもあります。ウエルビーイングの指標が今後の政策を生かしていく上で大切になるだろうということは実感をしているところです。どう生かしていくかまでは、まだ至っていないところです。
教育長
先ほど申し上げましたように、現在、教育委員会でウエルビーイング指標そのものを意識して計画の策定等はしていませんが、文部科学省ではウエルビーイングに関する分析を公表しています。毎年行われている全国学力・学習状況調査において、幸福度に関係する児童生徒質問紙の項目などを変えていると述べられています。その中で、例えば、学校に行くのは楽しいと思いますか、ふだんの生活の中で幸せな気持ちになることはどれくらいありますかというような幸福感を尋ねる設問などもあり、幸福感が高い子供あるいは自己有用感が高い子供については、学力との相関関係もありますし、あるいはいじめや不登校などの問題行動との影響なども指摘されているところです。ですから、ウエルビーイング指標で言われているような幸福感等について、きちんと把握し施策に反映していくことは重要だと思っていますが、現時点で文部科学省でもウエルビーイング指標に当てはめていくような考え方や、それを意識した取組ではないので、今後、教育委員会でもどの程度ウエルビーイング指標を意識した取組ができるかについては、検討していきたいと思います。
吉田
まず市長に確認します。デジタル庁の「地域幸福度(Well-Being)指標利活用サービス」で、本市のカテゴリー別レーダーチャートは今、お手元に配付しました資料1のとおりになっていまして、先ほどの市長の御答弁のとおり、本市は比較的主観的なウエルビーイングが高いという非常にいい結果が出たと捉えています。ただ、アンケート回答数が102しかないということには留意が必要ではないかと思いますが、全体的に興味深い傾向が見られると思います。また、こちらのサービスでは、RAIDAとかRESASといった客観データの基となるデータベースも公開されていまして、そちらにも有意義なデータが豊富に収められています。先ほど、名取市第六次長期総合計画の後期基本計画見直しにおいて活用されたということですが、どの程度反映されたのか、どのような検討の経過だったのかを確認させていただきたいと思います。
また、教育長には、全国学力・学習状況調査について御答弁がありましたが、令和5年度からウエルビーイングに関係が高い質問調査項目が追加されています。この結果が出ているはずですので、本市の児童生徒はこのウエルビーイングの観点からどういう状態に置かれているか、そうした分析がもう既に行われているのかも含めてお伺いします。
市長
このウエルビーイングの指標については、私、尚絅学院大学の外部評価委員をしており、その中で詳しい委員の方が本市のことを独自に調べてくださいました。そして、その状況を教えていただき、庁内で調べてみようということで指示を出したところです。
先ほど申し上げたのは、名取市第六次長期総合計画の見直しに伴って市民意識調査を行ったということで、ウエルビーイング指標で何かを反映したということではありません。
教育長
全国学力・学習状況調査における児童質問紙、生徒質問紙の項目の捉え方についてですが、本市の子供たちに関連する項目として、自分にはよいところがあると思いますか、については、小学校、中学校もほぼ全国並みの数値だと捉えています。それから、将来の夢や目標を持っていますか、という項目については、小学校はほぼ全国並みですが、中学校においては全国よりも高い傾向が見られています。これは長年取り組んでいる夢サポート事業なども影響しているのかなということも感じています。また、ふだんの生活の中で幸せな気持ちになることはどのくらいありますか、については、小学校では90.7%の子供が、よくある、時々ある、という回答をしています。同じ質問で中学校では86.6%とやや低い傾向にあります。そうしたことも踏まえると、比較的いい傾向にはあるものの、完全というわけではありません。例えば、宮城県教育委員会では、学校教育で子供の学びを支援する5つの提言を出しており、子供を褒めること、認めることでやり抜く力を育てましょうといったことを一つの柱に掲げています。また、いじめや不登校の防止という視点から、子供たちが行きたくなるような学校づくりを日常的に行うということを掲げていますので、名取市教育委員会でも常に各学校にそうした視点を指導、助言し、そういう雰囲気をつくり出すような取組をしているところです。
吉田
それでは、次に移りたいと思います。小項目2 本市におけるウエルビーイングの向上に関する施策の実施状況と、その効果をどのように捉えているのか、市長と教育長にお伺いします。
市長
デジタル庁の調査と、市民意識調査における分野別の傾向を見ていくと、防災や自然の豊かさ、子育て環境に関する評価が共通して高いという傾向になっております。
これらの評価につきましては、本市がこれまで力を入れて取り組んできた施策がウエルビーイング向上にも寄与しているものと捉えております。
現時点において、ウエルビーイングの向上そのものを目指した施策の実施には至っておりませんが、これまでも市民意識調査の結果を踏まえ、市民の皆様の満足度向上を意識しながら各種施策に取り組んできたところであり、今後も、そのような取組を継続してまいります。
教育長
前に述べたように、教育委員会では計画策定に当たり、市民意識調査等による実態把握に努め、計画を策定しているところであります。
生涯学習を例に申し上げると、市内各施設での多様な教室・講座の開催や、生涯学習グループによる自主企画講座の支援に加え、家庭教育支援事業、青少年健全育成事業、地域学校協働活動など、幅広い世代やライフステージに応じた事業を展開しています。
こうした学習活動への主体的な参加や、協働の機会を得ることは、市民一人一人の幸福感の向上につながるものと考えております。
なお、現時点でウエルビーイング指標自体を直接活用してはいませんが、今後、教育委員会の計画策定や取組に活用できるかどうか調査研究してまいります。
吉田
デジタル庁の指標を使用する際の注意事項として、自治体間の優劣の比較やランキングづけなどをデジタル田園都市国家構想の目的以外に利用する行為を禁止しています。先ほどの答弁の中で全国平均を上回っているという言葉があり、そこに気になりました。上回っていることはいいことなのですが、そういう形ではなく、あくまでも名取市の中での課題として見ていくべきではないのか。そうしないと、あそこの自治体よりうちがいいとか、うちが悪いとか、そういう比較になってしまうので、本来の趣旨と外れてしまうと思いますが、その点について市長のお考えをお伺いしたいと思います。
また、教育長には、今、生涯学習のほうで幸福感の向上に沿った内容を実施しているということですが、小中学校の学校単位で子供たちのウエルビーイングを高めていこうという取組を進めている他自治体も出てきています。まだ本市ではそこまでの取組は行っていないと思いますが、今後、他自治体の個別の学校の状況について、どのように情報収集していかれるお考えなのかお伺いします。
市長
先ほど全国平均との比較ということで御答弁申し上げましたが、他市と比較して優劣というような考え方は持っていません。大切なことは、市民の方それぞれの満足度が徐々に上がっていくということだろうと思っています。ただ、それぞれの項目別に見ていく際に、全国的に見たときと比べてどうなのかという比較は、内部においてはしていきたいと思っています。
教育長
全国的に見ると、市町村で教育振興基本計画にウエルビーイング指標の考え方を生かして策定している自治体もあることは承知しています。本市ではそこまでは行っていませんが、各学校においては、年度初めに校長を中心に学校経営方針を定め、年度末に学校評価を行います。その際に、子供たちに、例えば、あなたは学校に来るのが楽しいですかとか、授業が分かりますかとか、友達と仲よく過ごせていますかなど、いろいろなアンケートを行います。その数値を基に、年度当初には目標を決め、年度末にはどこが学校としてよくできていないのかという学校評価を行い、次年度の計画に反映させることは、大分前から行われています。ウエルビーイング指標そのものの考え方ではありませんが、それに近いような取組は行われています。学校評価の結果については、毎年、教育委員会にも報告していただいていますので、今後もそのような取組をきちんとできるように各学校に働きかけていきたいと思います。
吉田
教育長にお伺いします。全国調査の中には、教師との関わりについての質問もあります。教師と児童生徒のウエルビーイングは相互に影響し合うということも複数の研究で報告されています。本市の学校の組織と運営において、全ての教職員にとって働きやすいウエルビーイングな職場をつくっていくことは必要だと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
教育長
ただいま議員から御指摘いただきましたように、児童生徒の幸福感等と先生の関わりには相関関係があるということを、文部科学省でも分析しています。そういった意味で、先生方がきちんと子供たちの話を聞き、寄り添い、向き合って仕事をしていくことが大事だと思います。そのためには、十分に行われているとはまだ言えませんが、先生方が子供と向き合う時間を確保するための働き方改革として、例えば、令和6年度から全校で校務支援システムなども導入しており、かなり業務量に影響があるという先生たちの声もあります。それだけではありませんが、今後、先生方が子供たちと向き合い、子供たちが幸福感を得られるような取組を継続して行いたいと考えています。
吉田
全国調査の質問は市町村別では公開されていないと思いますが、その確認をさせてください。
教育長
全国調査の質問は、市町村別では公表されていません。
吉田
自治体間の競争につながらないようにデジタル庁が注意しているのと同じように、やはり教育の分野でも学校間の過度な競争にならないように公表されていないと思いますが、実情をしっかり捉えてそれに対応していく。オープンデータはみんなの財産ですので、学力の部分はいいとしても、今の質問紙の部分の公表を検討課題としてもいいのではないかと思いますが、教育長はどのようにお考えでしょうか。
教育長
学力と同様に児童生徒質問紙についても、文部科学省から教育委員会に市内の全学校分のデータと本市の平均データ、県、全国の平均データが届きます。学校ではそれを基に、全国、県の平均等と比較し、自分の学校が、例えば幸福度が低いとなれば、何が原因なのだろうかということを考え対応する、そういう分析に生かしています。本市としても、先ほど申し上げましたような大まかな傾向にはあります。そういった傾向については、公表することはやぶさかではありませんが、数値で公表することによって、議員も懸念されているような過度の競争につながるということもありますので、現時点では数値の公表は考えていないところです。
吉田
広い考え方の中でウエルビーイングというのは人と比較しないことによっても幸せになっていくというのがありますので、そういう意識が全体的に広がっていったらもっといい社会になるのではないかと思いますが、課題があることは承知しています。
それでは、次に移ります。本市職員による実践の提案です。
ウェブ上で利用できる無料のウエルビーイング診断が複数確認されています。その中でも、日本におけるウエルビーイング研究の第一人者である前野隆司氏が開発に関わった幸せの見える化サービス、幸福度診断Well-being Circleは、現時点で延べ42万人を超える個人を診断したほか、企業などの組織を幸せにするためのサービスも行っています。私もこのサービスを無償で個人診断として利用してみました。メールアドレスを登録して72問のアンケートに答えることで、34項目にわたって多面的に個人のウエルビーイングを調べることができます。平均値と比較できるレーダーチャートで表示され、個々人の特徴や課題が分かりやすく把握できるほか、AIが結果を分析し、幸福度向上のためのガイドをします。資料を用意したかったのですが、印刷がうまくいかず、今日は提出できませんでした。誰でも無償で簡単に利用できるため、ウエルビーイングとはどういうものかを知る導入には最適な手段だと思います。まさに百聞は一見にしかずです。
そこで、小項目3 本市職員を対象に、個人が特定されない形で無料のウエルビーイング診断を実施し、職場環境の課題を分析することにより、その改善を図るとともに、職員にウエルビーイングへの理解を促進すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
令和5年8月の人事院勧告において、ウエルビーイングの実現される公務を目指すとして、人材確保の取組や環境の整備について示されていることは存じ上げているところです。
本市におきましては、職員のストレスチェックを毎年実施し、職員個人がストレスを認識するとともに、検査結果を所属ごとに集計・分析を行い、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげているところです。
現在、ハラスメント防止やメンタルヘルス研修の実施に加え、超過勤務の縮減や年次有給休暇の取得促進など、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでおります。
今後も、職員のウエルビーイング向上を図りながら、併せて、その理解促進につなげてまいりたいと考えております。
吉田
こちらは、単純に自分のウエルビーイングがどういう状況かというのが分かるので面白いです。定期的に自分の身体的・精神的な健康状態をはかることで、自分をよく知ることにもなると思います。実際に使ってみると、いろいろな観点から自分自身の特性が分かってくるので、私は個人的にお勧めをしています。
先ほど教育長への質問で、教師と児童生徒のウエルビーイングは相互に影響し合うということを紹介しました。大都市は別としても、小さい町であれば公務員と住民のウエルビーイングも相互に影響し合う部分があるのではないかと思いますが、市長はどうお考えでしょうか。
市長
職員がいい仕事をして、結果、まちづくり含めて市内の環境がよくなってきて市民の満足度も上がってくるという比例関係みたいなことは、一部あるのではないかと思っています。
吉田
それでは、次に移ります。本市におけるウエルビーイング政策の推進についてです。
地方自治体におけるウエルビーイング指標の活用と促進については、2023年の骨太方針に記述が盛り込まれました。なお、2023年10月の段階で何らかのウエルビーイング政策に取り組んでいる都道府県は18あり、現在までにそれ以外の都道府県や市町村にも取組は広がりつつあります。デジタル化の進展により膨大な情報がデータベースとして蓄積され必要なデータへのアクセスが容易になったことで、自治体単独の予算の範囲内でウエルビーイング政策を進めることは今後一層容易なものになると予想されます。
そこで、小項目4 将来的に、庁内横断的にウエルビーイング政策を推進する体制構築を目的とする部署を設置すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
市民意識調査においては、防災や子育て、公共交通など分野別の満足度についても調査を行っており、調査の目的は、ウエルビーイングの考えとおおむね一致するものと捉えております。
当該意識調査の結果を踏まえ、昨年度に後期基本計画の策定を行ったところですので、当面は本計画に基づいた施策の推進により、市民満足度の向上を図ってまいりたいと考えております。
そのため、ウエルビーイング政策の推進につきましては、新たな部署を設置するということではなく、まずは現在取り組んでいる名取市第六次長期総合計画の進行管理の中で、ウエルビーイング指標の活用や推進について検討してまいります。
なお、新たな部署の設置につきましては、次期長期総合計画の策定に当たって組織体制についても検討していくことになると捉えています。
吉田
もちろん今すぐにということではなくて、将来的な課題ということです。これから人口減少、少子高齢化といろいろな課題がある中で、幸福の実感度を高めていくことは個人としても、組織としても本当に大事な課題だと思うので、本市としてそこをどのようにしていくのか。福祉向上とよく言われますが、福祉だけではなく、もっと広い概念でのウエルビーイングにつながるような形での組織運営についての検討を今後進めていただきたいと思います。
それでは、最後の質問に移ります。名取市第六次長期総合計画も折り返し地点を経過しました。少し早いと思われるかもしれませんが、次期計画の策定を視野に入れて、小項目5 次期名取市長期総合計画においては、ウエルビーイングの向上を主要な柱とすることを検討すべきについて、市長の御見解をお伺いします。
市長
ウエルビーイングの向上を目指した考え方や取組については、今後、広がっていくものと捉えておりますが、一方、ウエルビーイングの考え方そのものも、社会の変容に合わせ、変化と発展を続けていくのではないかと考えております。
現在の長期総合計画は、令和12年度までの計画となっているため、次期計画の策定時期までにどのような考え方を採用していくべきか、時間をかけて研究を重ねてまいります。
吉田
私、令和2年6月定例会の一般質問で、数値に表せない幸福感について質問したことがあります。これを数値として表そうという試みが、まさに今話題としているウエルビーイングなのですが、その際、幸せリーグという市町村の団体を紹介しました。ウエルビーイングの個人診断を開発された前野隆司先生は、幸せリーグの令和6年度の実務者会議において講演を行っています。その講演も、日本の置かれた状況と世界が進んでいく方向なども含めて大変勉強になります。令和2年6月の段階で、この幸せリーグへの加入について、市長からは団体の取組や成果をさらに調査した上で検討していきたいという答弁がありました。現状で検討された経過などがもしあれば確認させていただきたいと思います。
政策企画課長
ただいま御紹介いただきました幸せリーグに関する講演等について、市の担当で講義を聞いたりということで具体的な検討を行った経過はありません。
吉田
講演を聞くことではなくて、参加をしてはどうかという提案に対して検討するということだったので、まだしていないのであればしていないでいいです。市長も尚絅学院大学の組織に所属されており、いろいろな情報が入ってくると思いますので、そうしたものをより一層広げていただきたい。これは日本だけではなく世界の潮流としてこれから間違いなくその方向に進んでいくと思います。SDGsが今まさに一番の課題ということですが、このSDGsの次にはGDW、Gross Domestic Well-being、国内総ウエルビーイングになっていくと思います。先ほど申し上げたウエルビーイング学会がそれをしています。2030年頃には世界的な共通の概念として計算式なども考案されるのではないかという予測もされています。本市もこれだけ住みよいまちで、いろいろなウエルビーイングが高い要素がありますから、それを生かして、他の自治体に先駆けてウエルビーイングを高めるという目標を掲げて施策を展開していただきたいと思いますが、市長はどのようにお考えでしょうか。
市長
尚絅学院大学の外部評価委員会でお話を伺ったときに、やはりこれは今後の流れになるなと思ったものですから、政策企画課で今種々その分析や生かし方について検討しているところです。
ただ、世界的な指標については、今SDGsというお話がありましたが、その前がMDGsでした。そして、SDGs。2030年からSWGsもしくは議員おっしゃったようにGDWになるのか分かりませんが、世界的な潮流は変わってきます。その流れもしっかり捉えながら、どういった方向に行くのかも俯瞰しながら、次期長期総合計画については、その柱をどうしていくかということについて考えていきたいと思っています。
吉田
ウエルビーイングは、あくまでも個人の感覚なので、人によって様々です。一つのことについても、それをいいと捉える人もいれば、不快に思う人もいたりすることもありますし、また、面白いという言葉一つとっても、ゲラゲラ笑う面白い、趣深い面白いなどいろいろあります。一概に決めつけることはできないのですが、ただ、向上心や新しいことに取り組んでいくなど、おおむね同じ方向性を向いた幸福感、幸福の実感の在り方というのは、もう既に日本国内でも研究成果が発表されていますので、そういうことを一人一人が感じていけるような社会になっていけばいいのではないかと思います。名取市の強みというのは、先ほど市長がおっしゃったことはもちろんそのとおりで、これまで防災ですとか子育て政策に取り組んできたこともあると思うのですが、他の自治体に比べて、市民の様々な分野での活動が厚いものがある。ここがほかの自治体に比べて特徴的だと思います。1個1個の数値を比較するのではなく、本市の特色はそこにあるのではないかと思います。そうしますと個人個人が幸せになっていくウエルビーイングの考え方を深めて展開していくには、とてもいい環境が今既にできているのではないかと思います。ただ一方で、これから少子高齢化など、ますます個人個人のつながりが薄くなっていく中で、せっかくのこういう強みが損なわれてしまうことも懸念されるわけです。ですから、今こうした状況にあるときに、市として一つの大きな目標として、市全体が豊かに幸せになっていこうという方向性をぐっと掲げ、そしてそちらの方向へ進んでいっていただきたい、そして日本を引っ張っていってもらいたい、そのぐらいの意気込みでやっていただきたいと、私は期待をしています。
以上で私の一般質問を終わります。
本会議
(議案第62号 令和7年度名取市一般会計補正予算)
吉田
8、9ページ、15款2項7目商工費国庫補助金1節観光費のブルーツーリズム推進支援事業費でお伺いいたします。国の補助金を申請する際はKPIの設定が求められると思いますが、具体的にどのような項目にどのような数値を設定しているのか、お伺いします。
商工観光課長
KPIについて、まずSUPによる名取川周遊コンテンツでは、参加者数20名以上、PR動画の再生回数1,000回を設定しています。海鮮ナイトバーベキューについては、利用者数を令和6年度より多い240名と設定しています。また、新たな事業として開催予定の閖上の魅力を発信するフォトコンテストでは投稿件数240件、ゲーム感覚で海岸清掃を行うイベントの参加者数を60名と設定しております。
吉田
これまでのブルーツーリズム推進支援事業の実績を踏まえて今回新たにKPIを設定したと思うのですが、令和6年度と比べてどの程度増加させたのか、お伺いします。
商工観光課長
例えば海鮮ナイトバーベキューの利用者数については、令和6年度より約30%増の値を設定しております。また、SUPによる名取川周遊コンテンツでは、倍以上の参加人数を見込んで設定しております。
吉田
12、13ページ、22款1項6目教育債5節小学校情報機器整備債、6節中学校情報機器整備債、7節義務教育学校情報機器整備債ですが、これは歳出の財源更正によりタブレット端末の整備に充てられるものだと認識しています。この起債を行うことで、将来的に交付税措置される部分はあるのでしょうか。
財政課長
交付税措置については、現時点では詳しい情報は示されておりませんが、県からは、単位費用で措置されるのではないかとの説明を受けているところです。
吉田
今の御説明だけでは少し理解しづらいのですが、これはほとんどの学校で義務的に整備が求められる端末であり、国としても何らかの手当てがあってしかるべきものだと思います。現時点で詳細は決まっていないとのことですが、今後どのようなスケジュールで進んでいくのか、見通しをお伺いします。
財政課長
現在、普通交付税の算定が行われており、令和7年7月初旬には交付額が決定される見込みで、その時点で詳細が明らかになる予定です。なお、今回の予算措置については、起債のみで対応しているわけではなく、補助金も含まれております。
吉田
14、15ページ、2款1項11目公共交通対策費18節負担金補助及び交付金で、デマンド交通に関してお伺いいたします。先ほどの御答弁で、想定収入見込額に対して実際の運賃収入が下回ったとのことでした。1,000万円を超える収入を想定していたとのことですが、乗車率など、様々な計算によって算出されたものと思います。ただ、実際には利用者それぞれに異なる利用の仕方があり、ルートの組合せなどがうまくいかずに効率が悪くなっている部分があるのではないかと感じています。ルートはAIを活用して決定していると思うのですが、その仕組みに関する課題や問題点を把握している部分はないのでしょうか。
防災安全課長
運賃収入が想定を下回った要因ですが、想定収入見込額1,170万円の積算根拠として、利用人数2万9,250人掛ける客単価400円という見込みでしたが、実際の利用実績としては、利用人数2万937人掛ける客単価289円でした。利用者数が想定の約7割にとどまったことに加え、小学生は半額、未就学児は無料、障がい者やその介護人も半額、さらに免許返納者は1年間半額といった割引制度が大きく影響したものと捉えております。
また、AIの仕組みに関する課題ですが、現在、データの分析を進めております。以前も質疑がありましたが、立ち寄りやすくするために余裕時間を長めに設定するなど、様々な研究をしておりますので、今後、これらを踏まえて最適化を図っていきたいと考えております。
吉田
割引については、市として必要があって実施しているものなので、客単価が低い点についてはやむを得ない面もあると受け止めていますが、利用者数が想定の7割程度にとどまっている状況については改善する必要があると思います。デマンド交通運行業務欠損補助金で全て賄えるという甘い認識を持たれては困ります。今後、できるだけ想定収入見込額に近づけるため、企業としてどのような取組や努力が期待できるのか、また、企業側の考えを把握しているのであれば、その点についてお伺いします。
防災安全課長
企業側での改善はなかなか難しい面もありますが、現状では予約状況が可視化されていないため、それを改善し、空いている時間帯の予約を促すことで利用者の増加につなげていきたいと考えております。ただ、そのためにはシステム改修が必要となるため、費用対効果も踏まえ、導入に向けて検討を進めていきたいと考えています。もちろん、受託業者である大新東株式会社にも、企業努力を促していきたいと考えております。
吉田
14、15ページ、2款1項24目諸費18節負担金補助及び交付金の集会所建設補助金ですが、この集会所の場所と補助率をお伺いいたします。
市民協働課長
こちらの建設補助金の対象は、高舘吉田第二区生活センターの改修工事です。当該センターは築22年が経過し、屋根や外壁等の老朽化が認められたことから、該当する高舘第二区町内会の会長から、市に対して集会所補助金の交付申請が提出されたものです。補助率としては工事費の2分の1で、改修の場合の上限額は180万円ですので、工事費の2分の1の額から1,000円未満を切り捨てた金額が今回の計上額となっております。
吉田
16、17ページ、2款2項2目賦課徴収費21節補償補填及び賠償金の滞納管理システムパソコン賃貸借契約解約料について、当初予算が皆減となっておりますが、こちらの内容をお伺いいたします。
税務課長
こちらについては、13節使用料及び賃借料、21節補償補填及び賠償金のいずれも滞納管理システムのリース契約に関するものです。当初は令和8年9月までの長期継続契約で実施していましたが、国が進めている基幹業務システムの統一標準化に伴い、本市でも令和8年2月以降は現行の滞納管理システムを使用しない予定です。そのため、契約期間が短縮となりますが、リース契約であるため、令和8年2月から令和8年9月までのリース料については支払う義務があります。当初は、この費用を中途解約による損害賠償に類するものと捉え、21節補償補填及び賠償金として措置していました。しかし、契約の実務を進める中で支出の性質を改めて精査した結果、これはあくまで契約に基づき発生するリース料の支払いであり、本来の支出科目である13節使用料及び賃借料で処理することが適切であるとの認識に至ったことから、予算科目の組替えをしたものです。
吉田
国の制度がいろいろと変化していることが根本的な原因であることは理解しますが、将来的な見通しをもう少し早い段階で立てておけば、リース契約期間の設定を短縮できたのではないかとも思います。私も詳細までは分かりませんが、今回の支出は避けられないものと捉えてよろしいでしょうか。
税務課長
当初のリース契約は、令和3年10月から5年間の契約として締結しておりました。システム標準化の流れについては、当時の段階ではそこまで見込めていなかったことから、今回、当初予算編成時点で契約期間が短縮される見込みとなり、当初は21節補償補填及び賠償金で措置したものです。
吉田
22、23ページ、10款2項2目教育振興費、また、3項中学校費及び4項義務教育学校費も同様に財源更正となっています。先ほど歳入ではタブレット端末の整備に一部補助金を充てるとのことでしたが、不足分を単費で対応し、今回起債するとのことです。このような財源措置については、国からの指示によるものなのか、市が独自に判断したものなのか、お伺いします。
財政課長
今般、起債の申請に当たって、県と相談し、デジタル活用推進事業債を活用できることが確認できたため、今回、財源更正を行うものです。
吉田
厳密には歳入に該当する質疑かもしれませんが、地方債の償還期間をどのぐらいと考えているのでしょうか。
財政課長
デジタル活用推進事業債の償還期間については、5年と捉えております。
(議案第68号 工事請負契約の締結)
吉田
議員協議会の資料に基づいてお聞きします。今回の大きな変更点としてはホールのエアコン設置だと思いますが、それに伴って断熱効果なども考慮する必要が出てくるのではないかと思います。その場合、工事費用にどの程度の影響が生じるのか、お伺いします。
都市計画課長
エアコン導入に伴う断熱材の金額の変更についてですが、もともと断熱材の使用は計画に含まれておりますので、今回のエアコン設置による金額や資材の変更等はありません。
副市長
工事関係ですので、私から若干補足をさせていただきます。このような公共構造物、公共施設の場合は標準仕様が決められており、所要の断熱効果が得られるような断熱材は当然入れることが前提になっております。したがって、今回も冷暖房施設を導入するわけですが、従前の標準仕様を超えてまで断熱効果を得られるような仕様にはなっていないということで御理解をいただきたいと思います。
吉田
従来の施設と大きく変わらないものと理解しました。エアコンは今後、どの施設にも標準的に整備すべき設備になると思いますし、設置する以上、効率よく運用できることが重要で、稼働させてもなかなか室温が変わらないようでは困ります。そのため、断熱材に限らず、特に南側や西日の影響を受けやすい箇所について外からの光を抑えるためにガラス窓を減らすなど、改善の余地があるのではないかと思いますが、今回の工事ではそうした変更も含めて行わないという理解でよろしいでしょうか。
都市計画課長
例えば断熱のためにペアガラスの中にガスを封入する対応などもしておりますので、変更は考えておりません。
(議案第69号 工事請負契約の締結)
吉田
このたび、随意契約とした理由についてお伺いします。
警防課長
令和6年度、部分更新を行った通信指令装置は沖電気工業株式会社の機器で、今回、無線装置及び付随する設備、車両動態管理装置(AVM)間の通信データ形式は沖電気独自のシステムとなっております。そのため、ほかの業者では完全な制御及び工期内の施工は困難であることから、随意契約となった次第です。沖電気以外との契約になった場合、接続するには新たに共通のインターフェースを製作することとなり、多額の開発費用と製作期間を要することから、工期内の施工は困難となります。以上のことから、随意契約となりました。
吉田
いろいろ事情があることは理解できますが、最終的に適正な金額であるかどうか、消防本部としてはどのように金額の算定に取り組んだのか、お伺いします。
警防課長
先ほど申し上げたように、他社のメーカーを接続する場合、指令装置と無線基地局それぞれに開発費用として約4,000万円必要になるため、計上した費用については適正と考えております。
吉田
今回、様々な機器の更新により機能が強化されるとのことですが、新しいシステムへの切替えは一度に全て変更されるのか、それとも機能ごとに段階的に更新するのか、全体の完了時期も含め、今後のスケジュールについてお伺いします。
警防課長
議案をお認めいただいた後、速やかに業者と打合せを行い、年度内に整備が完了するように進めていきます。導入については、機材がそろい次第、随時更新する形となります。
吉田
随時更新とのことですので、順次切り替わっていくものと思います。従来の機器と操作性が異なる部分もあるかと思いますが、新しい機器に対応するための職員の体制については、どのようにお考えでしょうか。
警防課長
現在の設備に搭載されている無線機の型式や仕様については、ほぼ変更はありません。変更点としては通信先選択機能(セレコール)の機能ですが、これは通信指令室で選定することとなっており、担当職員が十分な訓練を行った上で対応していきます。
(議案第70号 財産の取得)
吉田
バスケット付ブームについて伺います。先日の総合防災訓練では、民間業者の同様の車両を使用して訓練が行われましたが、今回導入する車両も、放水だけでなく、高所から救助者をバスケット部分に乗せて降ろすといった運用も可能なのでしょうか。
警防課長
議員お見込みのとおり、この高所作業車は高さ13.7メートル、建物の5階相当まで延びるため、高所からの救出活動も可能な仕様となっております。
(議案第72号 令和7年度名取市一般会計補正予算)
吉田
10、11ページ、3款1項1目社会福祉総務費19節扶助費の定額減税不足額給付金について、先ほど令和6年度の定額減税による不足分との説明でした。今回の給付件数と、全件数に対してこの給付が占める割合をお伺いします。
社会福祉課長
今回、対象人数は1万1,000人を見込んでおります。全体数は捉えておりません。
吉田
1万1,000人というのは相当な人数だと思いますが、こうした事態は当初から想定されていたのか、それとも何か想定外の理由があるのでしょうか。
社会福祉課長
国の制度設計上、前年度の給付額に対し、例えば所得の減少、あるいは出産など扶養親族の増加による給付金増額の場合は次年度支給となっているため、今回の件は当初の想定どおりと認識しております。
吉田
10、11ページ、3款1項1目社会福祉総務費19節扶助費の定額減税不足額給付金に関して、1目全体の定額減税不足額給付金給付事業としてもお伺いしますが、この給付金は全て書面で周知し、申請を受ける形になるのでしょうか。
社会福祉課長
申請方法は3通り考えております。まず、令和6年度の定額減税調整給付金の対象者については、口座情報があるため、プッシュ型で支給を行う予定です。口座情報がない対象者には、確認書の提出を求めます。さらに、転入などで税情報がない方については、申請書の提出により給付を行う予定です。
吉田
今後のスケジュールをお伺いします。
社会福祉課長
現時点で担当課としては、書類の発送を令和7年7月下旬に行い、同時に電話対応の受付も開始します。振込開始は令和7年8月中旬から下旬を予定しております。申請受付期限は国によって令和7年10月31日金曜日までと定められておりますが、今後、契約事業者との調整により変更の可能性はあります。