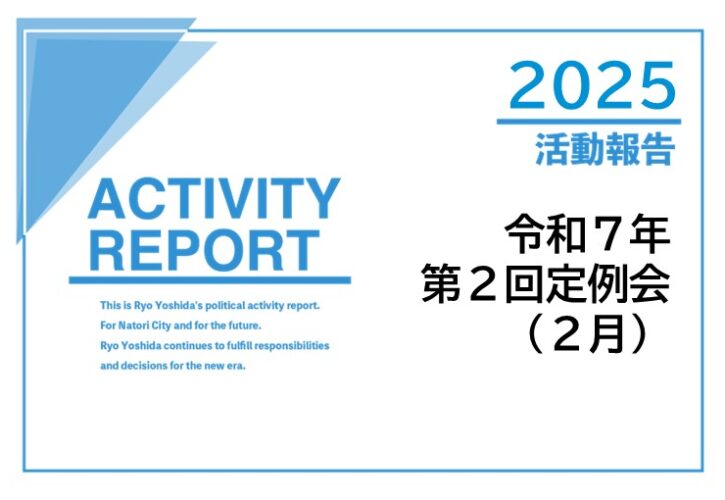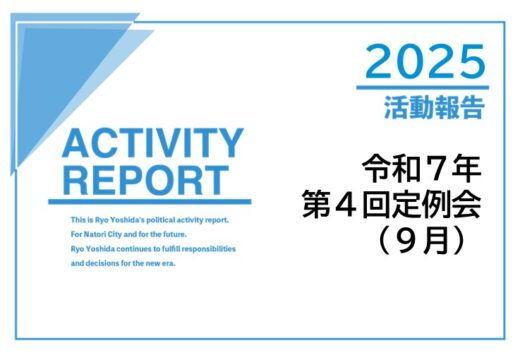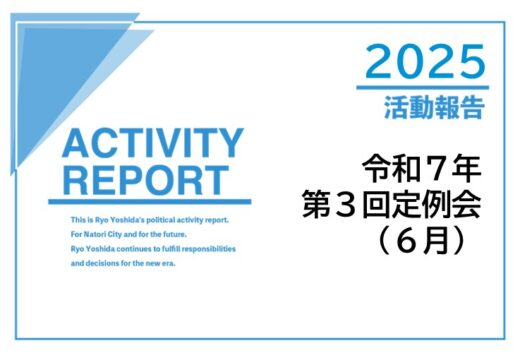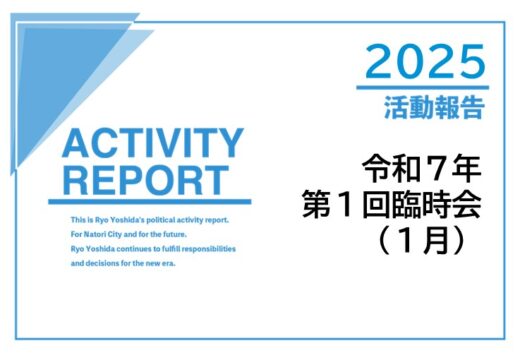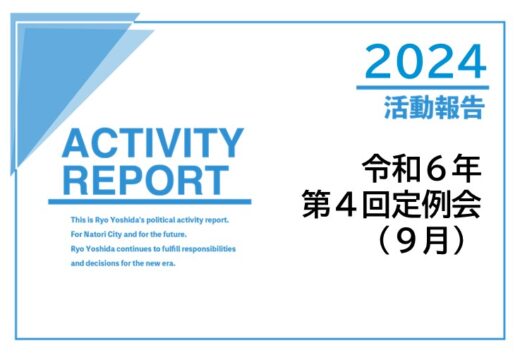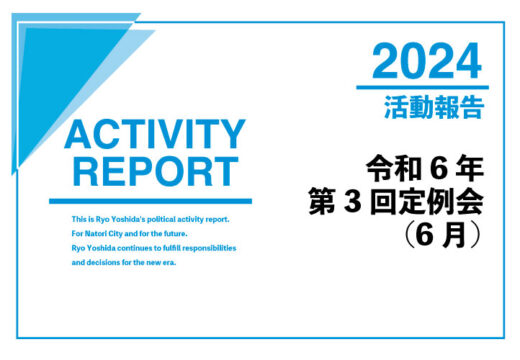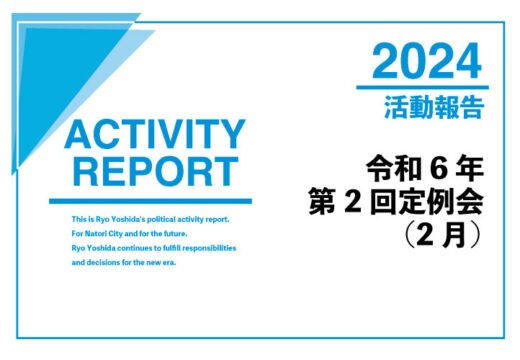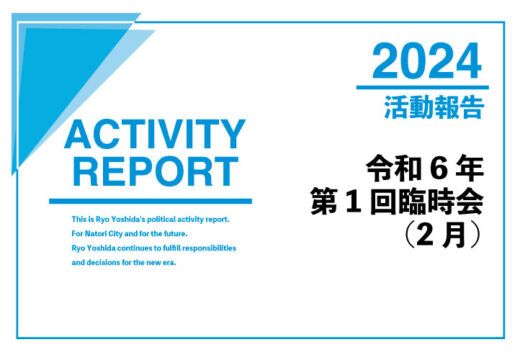本会議
(議案第14号 名取市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例)
吉田
第10条の5通勤手当でお伺いします。通勤手当の一月当たりの支給限度額が大きく引き上げられることになりますが、現行、最大5万5,000円とされています。現時点で、市役所職員で満額での交通費支給を受けている人はいるのかどうか。もしいるならば人数をお伺いします。
総務課長
現在の限度額は5万5,000円になっていますが、この満額に達している職員はいません。
吉田
今回改正した場合、現在の5万5,000円を超える方は想定されていますか。
総務課長
この改正によりまして、いろいろな支給の条件等が変わってきます。高速道路の通行料金なども改正により支給しやすくなります。実際には通勤届を改めて出してもらい算定しないと分からないのですが、高速道路も含めた場合に5万5,000円を超える人が出てくる可能性はあると考えています。
吉田
第10条の5通勤手当、高速道路を使った分が算定に含まれてくるというお話でした。私も身近なところで覚えがあって、例えば、市外に職場があるような、名取市だと仙台市から通ってこられる人がいると思いますが、高速道路はもちろんありますし、一般道もあります。高速道路を使えるルートの人は必ず高速道路を使うようなことに当てはまっていくのかどうか。交通費として高速道路を利用することが認められる要件をお伺いします。
総務課長
改正後の要件でお答えします。採用時から支給可能となっていまして、新幹線等を利用しない場合に通勤距離60キロメートル以上または通勤時間90分以上となる職員に支給します。育児、介護等のやむを得ない事情により転居して新幹線等による通勤を必要とする職員で、異動等により新幹線等による通勤を行う職員と同様に取り扱う必要がある者に対しても支給することとなるものです。
吉田
こちらは月額なのか、それとも高速道路を利用した都度、高速道路料金として支給されるのか。月額だと結構な額になると思うのですが、例えば高速道路を利用しなくても帰ってこられたりすると思いますが、そこはどうやって線引きされるのかお伺いします。
総務課長
基本的には月額で支給することになります。通勤届において主たる交通経路を届出してもらい、それに基づいて計算をし、月額で支払うものです。
吉田
高速道路を利用したかどうかについては、通常であれば、ETCだと1回ごとに料金を取られますが、それを電車の定期券のような形で月額で契約を結ぶことが必要になってくるのかどうか。そういう契約があるかどうか分かりませんが、そうでないと、支給を受けるだけ受けて高速道路を使わないというようなこと、不正に高速料金分を使用することができてしまうことが考えられるので、そこはどうやって防いでいくのかをお伺いしたいと思います。
総務課長
基本的には高速料金については月額で払うことが基本ですが、これまで高速料金を支払った職員がいませんので、細かい支給の方法等については、今後検討したいと思います。
吉田
附則第33項です。地域手当が今回廃止されるということですが、それに対しての代替の措置ということだと思います。100分の3を乗じた額を支給するということですが、給与全体の額は従前と変わらないという理解でよろしいでしょうか。
総務課長
議員お見込みのとおりです。
吉田
附則第33項の部分は経過措置なのか、それとも、今後恒久的に続いていくのか、伺います。
総務課長
こちらは当分の間ということで規定しています。従前ですと10年で地域手当の見直しがなされていましたが、今後、期間を短縮して行うということも示されていますので、それより短い期間で見直しがなされると思います。そこのタイミングでまた検討するものと捉えています。
(議案第23号 土地の取得)
吉田
私も以前、予算措置されたときにいろいろ質疑させていただいて、そのときの判断は時期尚早ではないかということでしたが、その後また少しずつ状況が変わってきましたので、今回は病院の建設のための費用の面からお聞きします。仙台赤十字病院と県との間での負担の在り方は示されていると思います。その額は幾らなのでしょうか。
病院立地環境整備推進室長
令和6年11月に公表されました基本構想の中の資金計画において、建設費、いわゆるイニシャルコストの部分についてですが、建築の事業費が約210億円、その他医療機器情報システム整備費が51億円、そのほかが39億円で、合計300億円を見込んでいるところです。それに対して財源として補助金が約200億円。この内訳は、地域医療介護総合確保基金、医療提供体制施設整備交付金、そして、県による財政支援です。この補助金の200億円以外に借入金として100億円で、300億円の財源を見込んでいると公表されています。
吉田
最近は資材が高騰していて、まだ天井が見えないような状況の中で、他の自治体では庁舎の建て替えなども断念するところが出てきている状況にあるというのは御承知だと思います。今予定されているこの300億円という建設費が、実際に建設が始まって完成するまでにはまだ相当な費用が上乗せされなければいけないという予想は容易に立つと思います。そうした際に、現在の基本構想の中で示された経営のランニングコストになってくると思うのですが、当然、仙台赤十字病院としては、この建設費で借り入れた分は返済をしていかなければいけませんので、相当経営のほうに負担が大きくなってくると思います。そうした部分までの予測がはっきりついて、その上で持続可能な医療を提供できると、民間で、あくまでも今のこの日本赤十字社が経営の主体で継続して医療提供できるということでなければ、なかなかその後のことが見えないと今判断するのは難しいと思うのですが、今後そのランニングコストの部分での経営、現時点では赤字体質ということが言われていますが、どの程度、新病院の経営の収支については予測が示されているのか、お伺いします。
病院立地環境整備推進室長
まず初めに、建設費の上振れについてですが、確かにここ最近、資材価格や人件費が高騰しているということは承知しています。ただ、この建築費などのイニシャルコスト部分については、先ほど申し上げました基本構想の中で県が中心に財政支援を行うと理解しています。そのようなことから、この建設費高騰に対して本市から支援するということは、現時点では考えていないところです。
それから、ランニングコストの予想額ですが、運営支援については国の特別交付税制度に基づきながら、これまで行ってきています総合南東北病院への支援の枠組みを参考にしながら検討していきたいと考えているところです。額については、まだ正式に要望を受けていませんので、検討している段階ではありません。
吉田
持続可能な経営かどうかというところを私一番気にしていまして、現時点で県では、運営していく上でもし補助が必要となったときは、ランニングコストの部分についても補助が出るような可能性について言及されていたとは思います。
さらに、最近気になった事案は、例えば、国立仙台医療センターでは看護師不足で一部病棟が閉鎖されているということもあって、様々な観点から医療の在り方の環境が非常に厳しくなってきているという気がしています。そういう中、今後補助が必要となった場合、県のほうで運営費も出してくれるということであれば、全部それを負担してもらえればいいのですが、現時点で本市としては二次救急医療の補助を行うという先ほど室長御答弁のとおりだと思うのです。仮に、県あるいは新しい病院のほうから運営費の補助もしてもらいたいと、利用されている患者が多い自治体、特に仙南区域になってくると思いますが、本市はじめそういうところで補助してもらいたいとなったときは、それは協議の場を設けるのか、それとも、いやそれは話が違うからその話は聞き入れられないというような態度になるのか、現時点で対応をどのように想定しているのか、お伺いします。
企画部長
宮城県あるいは日本赤十字社からそういった協議のお話があれば、当然協議については受け入れるということで考えています。
吉田
地元の医療を支えていくために必要な措置とも捉えられると思うのですが、その一方で、やはり、そのような部分でお金を取られれば、ほかの行政サービスを削らざるを得ないということもありますので、どのぐらいの額かということもとても問題になってくるかと思います。ただ、やはりこれは民間の病院ですから、民間の医療機関に、ただでさえ現在二次救急のところで補助しているのに、現時点でさらに補助が必要になったら協議に応じるみたいなことを言うのは、サービスがよ過ぎるのではないのかなと。民間は民間で、今、設置する段階での決められた枠組みの補助の中で持続的に経営していくことが当然の努力すべきものだと思うのですが、もう少しその部分は県のほうにもしっかり本市から伝えていくべきではないですか。何もかも県から言われたら全部のみ込むみたいな対応あるいは病院からお願いされたらそのとおりになんていうのでは、税金を預かっている側としてあまりにも甘いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
企画部長
先ほど申し上げましたのは、協議の場にはつくということで申し上げたわけでありまして、提示された分を青天井に受け入れるという趣旨で答弁したものではないところは御理解をいただきたいと思います。
また、日本赤十字社の病院については、民間病院とは一線を画した公共的病院という認識を持っているところです。
吉田
私も内心ではすごく揺れているのです。病院が来てくれるのは本当にありがたいことなのですが、まだ判断できる材料が十分にそろっていないということです。
病院の用地の取得について、引渡しは明日という唐突な印象は拭えません。いろいろ事情があって急いでいるというのは分かりますが、例えば、県と協議するような場面が今後出てきたりすることもあると思います。今回の取得に関しても、例えば、固定資産税の部分で何かしらの措置をするなど、所有者にもう少し待ってもらうようなことはできなかったのか。県のほうから新しい病院の内容、特に県立がんセンターの機能がどのぐらいまで残るかということがはっきり示されるまで。これは1回進めてしまうともう後戻りできないですから、そういう協議が必要だったのではないかと思うのですが、そういうものはなかったのでしょうか。
病院立地環境整備推進室長
これまでも答弁申し上げてきていますが、地価の上昇基調があることを背景に、加えて、令和6年11月には令和5年12月に締結されました基本合意をさらに具体化したものも公表されていますし、令和12年度中の開院を目指していることから逆算しても、決して土地取得のタイミングが早いとは市としては捉えていないところです。
吉田
今、基本構想まで出ていますが、基本計画が今後示されるということですから、そちらのほうが先なのではないのかと思います。県議会でも、県立がんセンターが実質廃止されるわけですから、それでいいのかという議論がされている中で、仮に本市がここで公金を入れて土地を購入してしまえば、ここにまたもう一つの既成事実ができますので、県ではがんセンターの廃止は止めようがないということになります。県議会がどんなに頑張ろうと、もう名取市が土地を購入していますから、この話を進めるしかありませんとなるのではないかと。そうなればむしろそれこそが県議会の軽視に当たるのではないのかなと。県議会でこのことについてしっかり合意がなされていない中で本市は先走っているのではないかという気がするのですが、どのように捉えていらっしゃるでしょうか。
企画部長
本市としては、基本合意の後の基本構想の締結、それから、現在は基本計画の策定ということで、新病院立地に向けた手続が日本赤十字社と県との間で協議が進んでいるものと理解をしていますし、基本合意を締結されたときにもお話をしたことではありますが、これが法的拘束力を持つ合意だということであって、現時点でも日本赤十字社としてもこの計画に沿って進めていくという考え方に変わりはないというお話もいただいているところです。
一方で、本市としては、県に対して新病院の誘致を進めてきた中で、場所としてここが適地であるということを提案している経過もあります。そういったことを考えますと、現時点で本市として判断する材料としては、土地を取得するということで動いていくべきではないのかと考えているところです。
(議案第24号 財産の取得について(追認)及び議案第25号 財産の取得について(追認))
吉田
取得の相手方は隣の市の事業者ということでよく分からないのですが、市内には教科書を扱う事業所はないということでした。こちらとの取引はいつから始まっているのでしょうか。
教育長
まず、今回、小学校の教師用教科書、指導書について、本来、議会の議決を得るべきところ議決を得ずに購入してしまい、このような追認をお願いするような形になってしまったこと、教育委員会として大変申し訳なく思っております。申し訳ございませんでした。
教育部長
教科書の取次店については、先ほど、議案書にありますとおり渡藤書店ですが、過去ずっと担っているようです。
また、市内の取次店ということですが、かつて1社ございました。
吉田
デジタル関連の指導書ということもあって非常に金額が莫大で、しかも、これは上のほうから恐らく配分されて決まってくるものでしょうから、どちらの書店から購入したいということもなく、また競争の原理も働かないので、決まった額を決まったところにと、そういうことがいまだに続いているということについて私は違和感しかありません。制度上そうなっているのは仕方がないということです。参考までに、仮に今後市内で教科書を扱う事業者が名のりを上げようとしたときは、国の審査を受けるなどすれば可能な制度になっているのですか。
教育部長
教科書については教科書発行法という法律がありまして、その中での縛りがあります。県では1社、宮城県教科書供給所というところがありまして、そことの契約で申請して認められれば取次店になる可能性はありますが、こちらではコントロールができない部分になっています。
一般質問
吉田
14番吉田良です。ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、事前の通告に従い一般質問を行います。
まず初めに、大項目1 虚偽の住民登録に基づく就学の件についてです。
この件については、令和7年1月24日に開かれた臨時会において市長から一般市政報告がなされ、経緯と対応が説明されました。最低限の必要な対応は取られることと理解したところではありますが、事の重大さに鑑みると、ほかにも解明が必要と思われる不確かな部分が残されておりますし、再発防止策についても踏み込んだ説明が求められます。まずはいま一度、経緯を振り返りたいと思います。
小項目1 これまで届いた全ての投書について、受け取った時期と内容、その都度の対応を教育長にお伺いします。
教育長
初めて教育委員会に匿名の投書が届いたのは、令和6年2月でした。内容は、知人の住所を使って名取市に転居し、市内中学校の部活動に通っている生徒がいるというものでした。確証はないという内容でした。教育委員会では、適正に転入や入学が行われているか確認をしましたが、その時点で問題は確認できませんでした。
令和6年4月に宮城県教育庁教職員課から匿名の投書があったとの連絡がありました。内容は、名取市内中学校のある部活動に所属する複数の生徒の保護者が、子が所属する民間のクラブチームの監督の自宅住所等を借りて住民票を市内中学校の学区内に異動して、この中学校の運動部に入部させていることを指摘するものでした。
これを受け、教育委員会では、当該中学校の校長に聞き取り調査を行い、正規の手続で転入・入学はしているが、住所だけを移し、学区内には居住実態のない生徒が複数いることを確認しました。教育委員会は当該校長及び部活動の顧問に対し、中学校の部活動として不適切であること、二度とこのようなことがあってはならないことについて指導を行いました。また、当該中学校の校長はクラブチームの監督に対し、住所を貸して転入させるようなことは二度としないこと、学校としては初心者であっても入部しやすい部活にしていきたいことについて話をし、理解を得たとの報告を受けております。
教育委員会としては、当該生徒が現にこの中学校で学校生活を送っていることから、年度途中に大きな環境の変化を与えることは好ましいことではないと考え、今年度末までに是正をしていくという方針を持ちました。
その後、令和6年9月に名取市教育委員会に、令和6年11月には県中体連に、令和6年12月には宮城県教育庁教職員課に、また、令和7年1月には、新聞報道を受け、名取市教育委員会にそれぞれ匿名の投書が届いております。
投書の内容は、部活動のための越境入学、部活動の私物化、違法性などを訴え、是正を求めるものでした。教育委員会では、11月下旬から年度末に向け是正をしていくための検討を行い、その後、顧問弁護士への相談や、市長部局との調整、関係する保護者やクラブチームの監督、部活動顧問、住所を貸した者などの関係者への聞き取り調査等を行ってまいりました。
吉田
まず、情報開示請求を行ったことで、学校名や部活動名、それから、個人が特定される文言が書かれた部分を黒塗りとする6つの投書が開示されています。私の手元にその写しがあります。これら投書に書かれた内容の中で、要望や感想を除く事実関係の指摘のうちで、認識が誤っているとする部分があるのかどうかお伺いします。
教育長
投書で指摘された事実関係は、おおむね教育委員会で確認した内容と合致しているものと思っています。
吉田
市教育委員会だけではなく、県教育委員会や中体連にも投書があったということですが、それらの扱いの中で気になったことがあります。令和6年2月16日の一番最初の投書には、教育委員会のそれぞれの職員の呈覧の印鑑が押されているのですが、同じ市教育委員会宛ての令和6年9月26日、令和7年1月9日の投書には呈覧の印鑑が押されていません。なぜ扱い方が異なっているのでしょうか。
教育部長
開示文書の中身において呈覧の在り方が違っているという御指摘だと思います。
その文書ごとに呈覧する位置を変えている部分がありますので、令和6年2月の投書については、文書上呈覧をそこに押していました。その後のものについては違う扱いで、決裁については全て教育長まで上げています。
吉田
令和6年2月16日段階で、学校にそのような事実がないことを確認したというところが、まずこの不手際の発端だと思います。そこについてさらに進んでいきたいと思います。
次に移ります。実効性のある対応が遅れた理由についてです。
これまで説明があったように合計で6回も投書があったにもかかわらず、虚偽の住民登録を是正するための対応を取ることが決まったのは、入試や卒業が迫る令和7年1月になってからのことでした。最初の投書があったのは令和6年2月ですから、その時点で迅速かつ適切に対応していれば、令和6年度の違法な入学は回避できたはずです。そうすれば、もともと学区に住んでいる新入生が希望する当該部活動に入り、ごく当たり前に活動に取り組んでいたとも考えられます。また、令和6年4月から越境通学してきた生徒たちも、本来入学すべき中学校で問題なく学校生活を送っていたはずです。しかし、教育委員会が適切な対応を取らなかったことで、人生が変わってしまった生徒もいることが投書の中からも読み取ることができます。教育委員会の初動における判断が誤っていたと言わざるを得ません。その理由がどこにあるのか。
小項目2 明白な違法行為であるにもかかわらず、速やかに実効性のある対応を取らなかった理由を教育長にお伺いします。
教育長
先ほどの答弁でも申し上げましたが、令和6年4月の投書の後に行った学校への調査の中で、住所だけを移し、学区内には居住実態のない生徒が複数いることを確認はしましたが、現に生徒がこの学校において教育活動や部活動を行っている中で、大きな環境の変化を与えることは好ましくないと考え、今年度末に向けて是正しようという方針により、この時点では直接的な対応は取っておりませんでした。
その後、今年度末に向け是正を図っていくために、先ほども申し上げましたが、顧問弁護士への相談や、関係する保護者、クラブチームの監督、部活動顧問、住所を貸した者といった関係者への聞き取り調査、そして、市長部局との調整などを行ってまいりました。
吉田
年度途中の大きな環境の変化が起きることは好ましくないというのは理解できるところです。ただ、その前の令和6年2月はまだ年度が替わっておりませんから、その時点での投書を受けての判断に誤りはなかったのかということを私は申し上げたいわけです。
それで、この虚偽の住民登録は、一般的に違法行為であることを教育委員会として認識したのはいつの時点なのでしょうか。
教育長
令和6年4月にこのような状態であることを確認して、これが中学校の部活動としてあってはならない、部活動の趣旨から大きく逸脱したものであるという認識は持っていました。ただ、具体的に今回の行為が住民基本台帳法あるいは公正証書原本不実記載という法に触れるという認識を持ったのは、顧問弁護士に相談をした令和6年12月のことです。
吉田
1回目の投書に確かに「確証はありませんが」とありますが「犯罪だと思います」と、ここで既に犯罪の指摘があります。1回目の投書のこのことを受けて、なぜそこで本当に犯罪かどうかを確認しなかったのでしょうか。
教育長
先ほども冒頭で申し上げましたが、議員からも御紹介がありました確証はないという内容で、教育委員会で確認できる範囲で転出入の事務手続について確認を行ったところ、特段そこの時点で問題は確認できなかったということで、その時点での対応は取らなかったということです。
吉田
今おっしゃった令和6年2月時点での確認について、どのような確認をして、なぜ問題がないと判断をしたのか、詳細を伺います。
学校教育課長
転入手続の申請書の書類、そして住民票の住所が合致しているかどうかといったものの確認をしました。
吉田
学校現場には確認しなかったのですか。
学校教育課長
書類上の確認を行ったということです。
吉田
学校の当該部活動の顧問や教員への聞き取りを行わなかったのか伺っています。
学校教育課長
その時点では、聞き取り等は行っていません。
吉田
それを確認したとみなすことについては、一体教育委員会のどのレベルで決定したのか。教育委員会は、本来決定する際はいろいろな規定に基づいて合議であるはずですが、そこに至らなくても、教育長なのか、部長、課長、事務局なのか、どこの判断で問題ないという決定をしたのでしょうか。
教育長
開示した投書の写しにも教育長印まで押してあると思います。教育委員会で情報を共有し、先ほど課長が申し上げたように、学校教育課内で書類等の確認をしたけれども、問題は確認できなかったということから、私の判断でこれ以上の対応は取らなかったということです。
吉田
それでは、次に移ります。市長部局との情報共有についてです。
住民登録の事務は、本来、生活経済部の市民課、つまり市長部局の所管です。そして、虚偽の住民登録という違法行為が行われている疑いが濃厚である場合、直ちに法的責任を問うことまではしなくとも、せめて担当課に相談し、どのように処理するのが適切であるのか、正しい判断をしなければならないはずです。ところが、先ほど来の御答弁によれば、令和6年暮れに教育委員会から市長部局へと、虚偽の住民登録がなされた疑いのある旨の情報提供があり、令和7年1月に入ってから市民課として書面上の住所地を訪問して実態調査を行ったということでした。
教育委員会はこの1年に近い間、しかるべき部署に相談もせず、虚偽の疑いを隠すことに手を貸してきたも同然の対応を取ってきたと言わざるを得ません。しかし、この部分の説明にはいまだ違和感が拭い去れないものもあります。これは本当に教育委員会だけで決定されたことなのか、改めて説明を求めたいと思います。
小項目3 市長と教育委員会との間における情報共有と、対応等の協議に関する経緯を、市長と教育長にお伺いします。
市長
事実が発覚した令和6年4月以降、教育長より口頭で報告を受けておりましたが、私としては、名取市内の問題であるとの認識を持っておりました。その後、令和6年12月に報告を受けた際に、市外から複数の生徒が当該中学校に不正に転入・入学しているという実態を知りました。
対応についての市長部局と教育委員会の間での協議は、これまで4回行ってまいりました。内容につきましては、住民票の職権消除について、生徒の学籍について、返還金について、そして、住民基本台帳法違反に対する対応及び公正証書原本不実記載に対する対応について協議してまいりました。
教育長
経緯につきましては、ただいま市長から答弁があったとおりです。
市長には当初、口頭で報告してまいりましたが、十分な詳細についての説明が不足していたことにつきましては、深く反省をしております。
吉田
市長は口頭で説明を受けて、今のお話ですと、市内の問題ということは転入ではなくて転居、不正の転居の届出ということになろうかと思うのですが、なぜその際にもう少ししっかり適正な判断に向けての対応にならなかったのか。どういう判断だったのかお伺いします。
また、教育長、今反省されているという御答弁でしたが、本来はどのような対応を取っておくべきだったと今になって考えておられるのか、お伺いします。
市長
市内の問題というのはあくまで小学校の指定校変更のことですが、おじいちゃん、おばあちゃんが近くに住んでいる場合は、そこで面倒を見てもらえるから指定校変更が認められるといった教育委員会内部のルールが少し曲がった形で運用されているのかなという認識を持っていました。
もう一つは、そのことについて、学校等に対して、二度とあってはならないということの指導があったという報告や、年度途中であるために、今ここで動かすのではなくて令和6年度末に向けて解決を図っていきたいという報告を受けたところです。
教育長
市長への報告が口頭であったために、先ほど市長答弁にもあったように、十分に市長に今回の事実関係が伝わっていなかったということがありましたので、その時点できちんと、どういう形で当該中学校に不正な形での転入が起きていたのかを、もう少し具体的かつ詳細に報告をして、対応を検討していくべきだったと反省していると申し上げました。
吉田
実際、より詳細な真相が分かるまで時間を要したということで、市長ももっと早く知りたかったという思いは当然持っておられると思います。そのような長い時間がかかってしまったことに対して、教育委員会への何か御見解をお持ちであれば伺いたいと思います。
また、教育長には、実際に今回は虚偽ということですが、これまで私も市内の児童生徒の保護者から、人間関係などの理由によって転校したいという相談を受けた際に、教育委員会にそのことをお願いしたことがありました。しかし、そういう理由では受けられないと、かたくなに学区を守らなければいけないという対応を取られてきました。そういう子供たちや保護者の方に対して、今改めて、虚偽があったのをその年度の終わりまでは認めるみたいな形、それも理解できなくはないのですが、そういう部分で生徒の扱いにかなりの差が出ているというのが実際だと思いますが、その部分についてはどのようにお考えなのかお伺いします。
市長
教育委員会とは、これまで以上に情報共有を密に図りながら事務に当たっていきたいと考えています。
教育長
まず、今回の対応については、該当する生徒に全く非がないとは申し上げませんが、子供にしてみれば、純粋にそのスポーツをクラブチームと同じメンバーで同じ指導者に教えてほしいという思いから、強く保護者や監督に訴えたということで、そういった生徒たちに年度途中で大きな環境の変化を与えることは好ましいことではないのではないかと。ただ、ずるずると引き延ばすことはできないので、令和6年度末を一つの区切りとして適正な形に戻していきたいという考えで対応を取りました。
一方、ただいま議員から冒頭に御紹介があったケースですが、いろいろな事情があって転校したいという場合には、教育委員会では、指定校変更あるいは市をまたぐ場合は区域外就学について一定のルールを決めて対応しています。その中には、教育的配慮ということでこれまでも何件か、具体的な話ではなく例えばということでお話ししますが、友達との人間関係がこじれたり、あるいはいじめを受けていたり、どうしてもなじめず不登校状態にあるという場合に、状況を聞きながら指定校変更を認めることがあります。ただ、先ほどのお話で、もう少し具体的に内容をお聞きしないと判断できませんが、仮にそういう相談を門前払いをしたことがあるとしたら、それは教育委員会として大変落ち度があったと思いますので、今後、絶対そういうことがないようにしていかなければならないと思います。
吉田
分かりました。
次に移ります。住民基本台帳の事務は適正に行われたかどうかについてです。
住民基本台帳法第3条には、市町村長等の責務が規定されています。同条第2項に「市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない」とあり、第3項に「住民は、常に住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない」とあります。
このたびの事案で問題となっている転入届は、同法第22条に規定されています。すなわち、転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く)をした者は、転入した日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならないというものであります。
そして、またこの同法第52条には、第22条の規定、ただいまのこの転入の規定ですが、これに関し虚偽の届出をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処するとあります。こちらについては行政罰でありますが、先ほど教育長からも御紹介あったように、刑法上の公正証書原本不実記載罪に当たるとも思われます。
自治体の職員が住民基本台帳事務の処理を進めていく上での指針、基準を定める行政機関の内部規律が住民基本台帳事務処理要領です。これを独自に制定している自治体もあるようですが、ほとんどは総務省の事務処理要領を基に事務が行われていると思われます。本市は独自の事務処理要領を制定していないようです。こちら一般公開もされていません。現時点でその内容を私のほうで把握することはできていません。
今回の事案の転入届には、既存世帯の世帯員の一部が他の既存世帯の住所へ転入するという不自然な点があることから、事務処理要領上の審査によって届出の虚偽を把握することが可能ではなかったのかと思われます。
そこで小項目4 住民基本台帳事務処理要領にのっとった審査が行われていたのかを市長にお伺いします。
市長
転入する住所に既に住所を有する住民がいる場合の転入手続について、住民基本台帳の事務処理要領では「必要に応じその状況を聞き取り、当該住民の承諾を得ているかどうか確認することが適当」とされております。
本市においては、別世帯での届出か、同一世帯での届出かを確認する過程で、その必要性を判断してきており事務処理要領に沿った対応であると考えております。
今後も基本的にはこれまでと同様の対応を考えておりますが、市民課の受付事務は、会計年度任用職員も含め対応していることから、今回の件を踏まえ、名取市としての「必要に応じ確認する基準」を定めた上で、聞き取りする内容、問いかけする言葉の表現など、そのマニュアル化について検討してまいりたいと考えております。
吉田
事務処理要領のさらに下にマニュアルがつくと理解しました。先ほどの御答弁で、単純に事務処理要領だけを見ると、既存の世帯に転入する場合は転入先の世帯に確認をすると載っているとおっしゃいましたが、それを今回しなかったということですね。
生活経済部長
必要に応じ確認ということですので、今回については確認はしていません。
吉田
従来「必要に応じ」の「必要」というのはどのように想定されていたのでしょうか。
生活経済部長
事務処理要領では、必要に応じて、あるいは記載されている届出内容が疑わしい場合にはということがありまして、私どもとしては、届出人の本人確認、提出された書類の内容に間違いがないかどうか、添付すべき転出証明書が添付されているかどうか、そのやり取りの中でその必要性があるかどうかを判断してきました。直近の例では、そのやり取りの中でその必要性があると判断するような疑わしいものまでは実態としては捉えられなかったということです。今申し上げたような確認を行って、問題がなければ転入届を受理するという処理を行ってきたものです。
吉田
市民課の事務は大変な労力を必要とされていること、私も理解しています。そこにまた新たに煩雑な確認が増えてしまえば、それこそ今の職員の体制ではパンクしてしまうでしょうし、そこの部分に難しさは確かにあると思います。しかし、こういう事案があり、令和6年2月の段階で虚偽の部分がしっかり把握できていればこうはならなかったはずなので、厳格なというところまではいかなくても、適度な形で虚偽を見抜けるような仕組みをぜひつくってもらいたいと思います。それは、次の再発防止のほうで改めて伺っていきたいと思います。
次に移ります。市内学校では令和7年2月28日付で文書が配付されたようです。
それも含めて、小項目5 同様のことが起こらないよう、本市は部活動を目的とするいわゆる越境通学を認めておらず、虚偽の住民登録は法令違反となることを広報するほか、防止策を講ずるべきと考えますが、市長と教育長に御見解をお伺いします。
市長
このような事態の再発防止のため、令和7年2月17日開催の総合教育会議において議題とし、話合いを行いました。また、教育委員会では、再発防止のため、保護者への周知、ホームページへの掲載等の対応を取ったと伺っております。
教育長
教育委員会では、再発防止に向け、市内保護者に対し、居住実態のない住民票の異動は違法になることや、指定校変更、区域外就学の要件について、令和7年2月28日付で文書で周知を行うとともに、ホームページにも掲載をいたしました。
また、校長会等において、部活動の在り方について何回か指導もしております。
今後とも、引き続き広く周知を図り、二度とこのようなことが起こらないよう徹底してまいります。
吉田
まず、市長にですが、令和7年2月17日の第22回総合教育会議で、部活動目的の区域外就学についてを議題にしています。こちらで協議された内容、調整された内容について詳細をお伺いします。
また、教育長には、今ホームページで周知しているということですが、虚偽の住民登録を部活動を目的とするものとして行わないよう注意喚起を行っている自治体、ほかにも自治体として確認されているものが確かにありまして、私もそれを幾つか把握しましたが、その中で、例えば福島県白河市では、ホームページだけですが、刑法違反に当たる可能性があるということも示されています。また、埼玉県上尾市の文書、こちら配布文書だと思いますが、こちらには学区外から通学が認められる場合についても書かれています。認められないケースだけではなくて、認められるケースはこうだということ。また、東京都小平市の文書には、学校及び教育委員会が予告なく不定期に居住調査をする場合があるということが書かれています。今回の文書は、取り急ぎということもあろうかと思いますが、今後も注意喚起を行っていく上で、もう少しブラッシュアップできるのではないかと思いますが、御見解をお伺いします。
市長
令和7年2月17日の総合教育会議の中で、教育委員から幾つか意見をいただきました。再発防止に向けてということで、居住実態なく住民票を異動することが違法であること、条件を満たせば指定校変更ができることについて周知が必要であるという意見。また、教育活動の一環としての部活動の在り方等も含め校長会等で指導するなど学校に対しても改めて周知が必要であるという意見。また、少子化や部活動の地域移行を踏まえ、将来的には部活動を目的とした指定校変更等についても検討する必要があるというような意見をいただきました。特に周知について、早速動かなければいけないという認識を共有したところです。
教育長
令和7年2月28日付で発出した文書については「指定学校への通学について」というタイトルで、虚偽の住民登録は住民基本台帳法違反になることも含めて、具体的には知り合いの家の住所を借りて住民票だけ動かすことなど具体例を挙げて、そういう行為は違法となるため、行わないようにと載せています。
それから、認められるケースも載せている自治体があるとの御指摘でした。当日発出した文書そのものには詳しい内容は載せておりませんが、指定校以外の学校に通う指定学校変更や区域外就学も一定の条件で認めているので、ホームページを参照してくださいということは書いてあります。そこに触れてあることとしては、居住地以外から通学している場合、登下校の途中に事故に遭っても日本スポーツ振興センターの保険適用外になる場合があるということも書いてあります。
ただ、抜き打ちで居住実態の調査をするというところまでは書いてはいません。
今後、この文書によって、おおむねこういったことは起こらないとは思っていますが、今後も、再発防止にはどういった対応が必要かについては、引き続き検討をしていきたいと思います。
吉田
まず市長には、住民基本台帳事務処理要領の扱いのマニュアルをつくるということでしたが、これまでも慎重な審査が行われる決まりがあったはずです。今回のようなケースは年にどのぐらいあるのでしょうか。かなり細かいのですが、お聞きしておきたいと思います。
また、教育長には、仮に今後、令和6年2月の1回目の投書のような匿名で真偽が不確かな投書があった場合はどのような対応を取っていくお考えなのかお伺いします。
議長
吉田議員、最初の質問ですが、小項目4に戻っているのではないかと判断しますが、内容を変えて質問していただけませんか。
吉田
では、結構です。
教育長
仮に投書があった場合、速やかに事実関係の確認をしたいと思います。
吉田
最初の投書の際にも確認をしていたはずです。ということは、確認というのは、庁内でというか、現場への確認は今回なかったのですが、同じような形での確認をこれからも取っていくという考え方でしょうか。
教育長
今後の仮定の問題ですので、投書の内容にもよりますが、仮に同じような、ある学校に不正な転入学が行われているという学校名などを挙げた投書であれば、今回は教育委員会の内部で転出入の書類の確認にとどめましたが、可能な範囲で、学校名などが特定できるのであれば、当初から学校にも確認をするということも含めて対応していきたいと思います。
吉田
生徒たちが部活動に本当に一生懸命取り組んでおられる。そういう実情の中で起きてしまったことで、今回の件は本当に残念だなと思います。議会でもこれまでたくさん議論されてきた部活動の地域移行、地域展開とおっしゃっているのですが、やはりこれは生徒たちの一番教育的な観点から、そして彼らの夢をどう実現していくか、そういうことにしっかり資するような形で早急に議論を進めて、加速していただきたいということは申し上げておきたいと思います。
また、それと同時に、今回は、その子供たちには非はないとおっしゃいましたが、分からないですよね。どれが犯罪で、何をやっていいか悪いか、こういう細かいことになると分からない。確かにそれはあると思います。ただ、やはり、不正があった、違法があったということが実際には結果として認められてしまっているということは、教育上、私はよくない効果を生んでしまっているのではないかと。やった者勝ちみたいに捉えられるようであってはいけないなと、教育現場にいた人間として、この甘い対応について思います。こういう言葉を言った人がいます。小善は大悪に似たり、大善は非情に似たり。今回は大悪に近いような対応を取ってしまったのではないか。ただ、私ももし教育長の立場だったら同じようなことになったかもしれません。これは1人を責められることではないと思いますが、様々な教訓を得られる事例だと思います。今後の改善に、市長部局と教育委員会と連携しながら取り組んでいただきたいと思います。
それでは、大項目2に移ります。本市の人口動態と空き家対策についてお伺いします。
厚生労働省によると、令和6年1年間に生まれた子供の数は、日本で生まれた外国人を含む速報値で、前年から約3万8,000人の減となる72万988人でした。また、出生数から死亡数を引いた自然減は89万7,696人となり、過去最大の減少となりました。宮城県内の令和6年の出生数は、一昨日の読売新聞の県内版によりますと1万1,630人で、前年より7.8%の減となったとのことです。
国立社会保障・人口問題研究所が2023年に公表した将来推計人口、その中位推計によりますと、外国人を含む出生数が72万人台に落ち込むのは2039年と見込まれており、少子化は想定より15年早いペースで進んでいると言えます。
日本における少子高齢化・人口減少の流れは止めることが極めて難しい状況にあり、子供を産み育てやすくするための施策に力を入れることはもちろん重要ですが、それと同時に、人口減少を見据えた社会づくりへの転換も避けられず、将来世代にかかる負担を少しでも減らすために取組を取捨選択していく必要があると考えます。
まずは、本市の人口動態について幅広く確認したいと思います。
小項目1 名取市第六次長期総合計画の初年度から現在までの人口動態について、自然増減、社会増減、転入元・転出先の傾向及び在留外国人数の推移を市長にお伺いします。
市長
計画初年度の令和2年10月1日から令和6年10月1日までの人口動態は、自然増減についてはマイナス817人、社会増減についてはプラス1,064人となっており、自然減を社会増が補い、全体としては微増となっている状況です。
転入元・転出先の傾向といたしましては、3割から4割程度が隣接する仙台市との間での移動でありますが、宮城県全体や仙台市の転入元・転出先を見ますと、東北6県から宮城県、仙台市へと集まり、関東圏に転出していくという構図となっております。
在留外国人数については、令和2年4月の437人から、直近の令和7年1月末には641人と、204人増加しております。
吉田
自然減を社会増で賄っているということで、これは大変ありがたいことであることは間違いないと思います。
また、関東圏に転出していく流れ、これはやはり止めることができていないと。これは本市に限らず、宮城県含めて東北全体の問題だと思いますが、このあたりが本当に一刻も早く、もっと効果のある手を打っていかなければいけないと思います。
今、最後に在留外国人の数について御紹介いただきましたが、確かに令和2年4月末は437人、令和7年1月末は641人で204人増加しているということで、この期間、日本人と外国人の増加の数を比べると、実は313人の全体の増加の中で、外国人が204人、日本人は109人ということで、増加分の3分の2が外国人の増加になっています。ですから、もしかすると8万人達成記念も外国人の方に受けてもらうことになるかもしれません。
確かに手っ取り早く人口を増やすには、国外から労働者を積極的に受け入れるのが最も近道だと思います。本市は積極的に外国人労働者を受け入れている実態があるのでしょうか。
市長
詳細については把握していませんが、外国人数が増えていることについては、企業での受入れが増えているのかなと思っています。
市としても、ホームページも含めて表記の多言語化や、海外出身の方々ができるだけ暮らしやすいような施策については今後とも取り組んでいきたいと考えています。
吉田
人口が微増しているという陰にそのような実態があるということはあまり知られていないと思います。ですので、人口が増加していく中で、その実態は慎重に見ていかなければいけないと思います。
そこで、次に移りまして、本市の目標人口についてです。
小項目2 名取市第六次長期総合計画の中間年である令和6年度において、本市の人口は見込みより約2,400人少ないとされています。最終年度の令和12年度に8万5,000人の目標は達成が極めて困難であると思われますが、どのように実現を図る考えなのか、市長にお伺いします。
市長
議員御指摘のとおり、中間年の目標人口には約2,400人及ばない状況となりました。
しかしながら、令和5年12月に公表された直近の国立社会保障・人口問題研究所による人口推計において、名取市は2030年人口が7万8,883人、2040年人口が7万8,952人と、現状の人口から大きく減少はしないと推計されております。これは、宮城県内で一番人口が減少しないまちであると示されたものであります。
これを前提に、令和12年度までの間に、既に販売が始まっている愛島台地区の第2期分譲事業や、今後、計画されている増田西地区、名取中央スマートインターチェンジ地区、高舘熊野堂・吉田地区、上余田地区の4つの土地区画整理事業による人口増加を見込むとともに、移住支援金やマイホーム応援補助金などの移住定住施策による人口増を図りながら、人口8万5,000人の目標実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
吉田
人口を目標として定めていますが、それがそもそも違うのではないかと、私は違和感を覚えます。人口の増減というのは、結果として何らかの指標にはなるかもしれませんが、本来は結果として捉えるべきものではないかと。人口を目標とすると、それに行政が引っ張られて、そして政策が誤っていってしまうおそれがあるというのが私の考え方です。名取市第六次長期総合計画にそれが書いてあって、中間見直しでも引き継いでいくお考えのようですが、人口を目標として定めるのではなく、別なところに定める方向に転換していくお考えはないでしょうか。
市長
議員がおっしゃっていることはよく分かります。人口の8万5,000人というのは、企業に置き換えると営業予算の売上げに当たる部分です。売上げが上がるということは、市でいうと税収が上がるというところもあります。予算なので達成に向けて最大限努力をしていきます。
一方で、経営は営業と違うということで、売上げに多少のぶれが発生しても経営に影響を及ぼさないように、最終利益が確保できる組立てをしていくのが経営だと思っています。
いろいろな指標の推移がありますが、名取市第六次長期総合計画の前と後で比べてみますと、人口は0.7%の微増ですが、市税については約118億円から約127億円で約7.6%増加しています。一方で、地方債の残高は約1.6%の減。年間商品販売額については約9.3%の増、観光客の入り込み数については約26.5%の増ということで、これに加えて直近の市民満足度のアンケートの調査では、本市は住みよい、住み続けたいという方が約8割ということで、これも名取市第六次長期総合計画が始まるときに調べた調査から大きく改善しています。
大事なことは、自治体の経営者として、このような様々な指標を総合的に勘案しながら、これからも本市が持続可能なまちであり続けられるようにいろいろな施策を打っていくということになろうかと思います。
吉田
もちろん成果が出ている部分については評価したいと思います。
次に進みまして、新たな宅地造成の計画について考えていきたいと思います。
令和5年11月12日、河北新報が報じたところによりますと、宮城県は、本市や仙台市など12地区400ヘクタールの市街化区域編入を認めたということです。うち4地区が、先ほど市長から御紹介のあった名取中央スマートインターチェンジ地区、増田西地区、上余田市坪地区及び高舘熊野堂・吉田地区とされています。そして、想定人口については、仙台市が2,565人としているところ、本市は5,774人としています。随分と大胆で強気な想定だという印象です。そのような数字を示す以上は、何らかの根拠がなければならないと思います。
そこで小項目3 報道によると、本市では5,774人の人口増を想定し、4地区を市街化区域に編入する案が進行しているとのことですが、需要予測の根拠を市長にお伺いします。
市長
宮城県では、令和6年6月7日に策定した仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において、令和12年の目標年次における仙塩広域都市計画区域内の市街化区域の将来人口を142万2,000人と推計し、このうち、新規開発による人口フレームを9,000人と設定いたしました。
本市においては、この人口の範囲内で、かつ総合計画における目標年次の推計人口である8万5,000人を視野に入れ、事業実施希望がある4地区から出された各土地区画整理事業における計画人口を基本に、約5,800人と設定をし、この内容が県に認められたものであります。
吉田
今の御説明ですと、県に引っ張られてのことということですか。そこの部分が分からないです。市長は、この計画に対して、そもそも推進されている立場なのか、それとも慎重な立場なのか、二者択一でお伺いします。
市長
本市が持続可能なまちであり続けるために、人口については少しずつ増えていくという形を何とかつくっていくことが大事だろうと思っています。
土地区画整理事業は、御存じのとおり様々な課題があって、これが直ちに夢のようにぱっと進むかというと、そうではないことは十分承知しています。しかし、少なくともそれぞれの地区で土地区画整理事業を進めたいという地元の熱意があり、本市の発展にとってそれが必要であると認識したため県に計画を上げ、県においても様々な角度から検討されて認められたということです。
吉田
持続可能なまちづくりは当然大きな課題ですので、誰も異論はないと思いますが、田んぼを潰したりするような土地区画整理を、そもそも市長として推進をしているのか、それとも慎重になるべきと考えているのかをお伺いしています。
市長
議員にも賛同いただいた、名取市第六次長期総合計画、それから名取市第五次国土利用計画の中に、この4地区については破線ではありますが計画に含まれています。地元の熟度が高まれば開発をしていくという内容でして、私としてはその計画を策定した者として、熟度が高まったということで県に上げたということです。
吉田
推進されていると理解しました。私はどちらかというと慎重な立場です。これだけの宅地開発を行えば、潰される農地は当然広大になります。主食である米の値段が1年で2倍にも跳ね上がるという状況の裏には、実は米の生産量が減っているのではないかという指摘もあります。安易に潰した田んぼは元に戻すことはできません。食料の安定供給という課題より人口増加が優先するとは私には思えません。
ところで、仮にこの4地区の全ての計画が遂行された場合、新たに敷かれる市道や上下水道の延長はどの程度になると見込まれるのか。一般的な土地区画整理を準用した形でお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
都市計画課長
今回4地区のまちづくりの面積は約140ヘクタールですが、その中で、水道・下水道延長については、今後、設計を行っていく中で決まるものです。今の時点では出ていません。
吉田
現時点でそこまで見込むのが難しいのは確かに理解できますが、それができた後も本市として維持管理をしていかなければいけない課題であることは認識しているはずだと受け止めています。
確かに、今、駅から近い地域については住宅の需要が高いと見られます。例えば、増田西地区、田高南地区は、一戸建てが解体された後に3戸の新規住宅が建築されている風景も見ることができます。こうしたことについては駅から徒歩圏内ではない地域でも言えるのかどうかということです。例えば、車がなければ町なかに出ていけないような地域が市内にもたくさんありますが、そうした地域でも不動産の売行きは好調であると言えるのか、お伺いします。
市長
4地区の計画を認めていただく中で、例えば、名取中央スマートインターチェンジ地区については、特定保留ということで、より実現性が高まっていると認められたということ。一方、ほかの地区については、一般保留という形で、もう少し熟度を上げていく必要があるという評価を受けた上で計画として認められたということです。
今の住宅需要については、詳細は把握していませんが、全体的に以前よりは住宅の着工のペースが落ちてきていると感じています。
吉田
そこが私も非常に気がかりです。これから先を予測すると、間違いなく日本全体で人口減少していきますので、本市だけの視野で見たら、確かに宮城県内で一番人口を維持できる自治体であることは間違いないですが、別なところの影響が本市に出てくることもありますので、今からそれを考えていきたいと思います。特に空き家問題として考えていきたいと思います。
空き家と一言で言いましても、実態は様々です。その全てが問題だというわけではありません。総務省は、空き家を、賃貸用、売却用、二次的、そして、その他、4つのタイプに分類して集計してきましたが、令和5年度の統計から、その他については、定義はそのままに名称を賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家と変更しました。これが個人所有で住人のいなくなった住宅を示すもので、いわゆる迷惑空き家になりやすい空き家のことです。
令和5年の総務省の住宅・土地統計調査によると、全国の空き家の内訳は、賃貸用が約49.3%と最も多く、続いて、賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家が約42.8%でした。売却用と二次的はそれぞれ4%程度です。なお、この二次的というのは別荘などのことを表します。前回調査の平成30年と比較すると、全体の空き家率は13.6%から13.8%へ0.2ポイント増加。うち、賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家の割合は5.6%から5.9%へ0.3ポイント増加しています。
また別の視点で見ていきます。野村総合研究所によりますと、全国の空き家率について、2028年には15.5%、2043年には25.3%になると予測しています。今から約20年後、日本国内で4軒に1軒が空き家になるということで、これは非常に深刻な将来が待っているということにほかなりません。
さて、本市では、令和4年3月に名取市空家等対策計画が策定されました。計画の最終年は令和12年と定められ、将来推計人口を8万5,000人としています。人口は予測している一方で、空き家数や空き家率についてはこれまでの推移しか示されていないと理解しています。
そこで、小項目4 本市における空き家数及び空き家率の将来予測を市長にお伺いします。
市長
令和5年住宅・土地統計調査では、市内の空き家は2,470戸、空き家率は7.6%という結果となっております。
本市における空き家数及び空き家率の将来予測は行っていないところでありますが、本調査の結果によれば、本市の空き家総数及び空き家率は減少傾向にあること、また、全国や宮城県と比較しても空き家率は低いことを踏まえると、空き家の利活用数については堅調に推移しているものと捉えています。
吉田
その堅調な推移はいつ頃まで続くとお考えでしょうか。
なとりの魅力創生課長
いつ頃まで続くかということですが、今後の住宅需要の状況にもよりますので、捉えていないところです。
吉田
あくまで予測なので、どういう未来が来るかは分からないわけですが、ただ、その予測をある程度立てておかなければ、まちづくり全体が間違った方向へ行きかねないので、そこは重要だと思います。人口の予測だけではなくて、空き家数、空き家率の予測については、何らかのものを持っていたほうがいいのではないかと私は思います。
ここで東京都のことを考えていきたいと思います。空き家率は10.9%、都道府県別で全国で4番目に低い値ですが、空き家数で見ると89万6,500戸で全国トップです。この数字は、秋田県の全県民が移住しても余るだけの空き家が東京にはあるということを表しています。今後、少子高齢化によって東京都で空き家の増加が進めば、不動産の価格が下がり、今より手に入れやすくなるということが考えられます。また、少子化が進むことで地方の魅力が低下していく中、東京都内で住むところが確保しやすくなり、若者が東京へ流れる傾向がますます強まることも十分に考えられます。そして、首都圏全体で見ますと、神奈川県、千葉県、埼玉県も空き家数のワーストテンに入っています。東京近郊であっても、不動産が投売り状態になることは決してあり得ない話ではありません。
こうした状況の下、本市で5,000人規模の新たな住宅地開発を行い、人口が減っていく中で新しい住宅が売れるとなると、既存の住宅地はどういう方向へ進んでいくと考えられるでしょうか。
市長
まずは宮城県の計画に認めていただいているということもありますが、宮城県とすれば、人口が伸びる部分は新規開発も含めて伸ばしていく、これはきちんと精査をした上で計画にのせているということです。
一方で、新たな開発をしながら人口を少しずつ増やしていくという方策を取りつつ、既存市街地をどうしていくかというのは、まさに同じ土俵で考えなければいけないテーマです。以前の中心市街地活性化基本計画や、今の名取駅東地区にぎわい再生計画、また、今、名取が丘を中心に、以前の一戸建ての土地に2軒か3軒ずつうちが建っているという新たなモデルも出てきています。そうした民間の動きも把握をしながら、官民合わせて、どういう形で新たな開発をするかということと、既存の市街地をどうしていくかということについて、同時進行で考えていかなければいけないと思っています。
吉田
国立社会保障・人口問題研究所の予測で、本市の人口は7万8,000人台をしばらく維持していくと。仮に、本市の人口が当面横ばいで推移するとしたときに、新たに5,800人規模の住居が増えるということは、当然、新規で住宅を買って定着した人口分、既存の住宅地から人口が減るということになります。両方増えていったら人口も増えるわけですから。新規で建てた家が全部埋まっていけば、その分、全体として人口が変わらなければ既存の住宅地の人口は減っていくわけです。ここは認識されていますか。
市長
今議員がおっしゃっているような流れも一つあると思います。
逆に、市外、県外から本市に移ってこられる方もいると思うので、図式的に完全にそのようになるということではないのではないかと思います。
我々が期待しているのは、外から転入していただくこと、しかも、できれば若い世代の方に転入してきていただき、そこで家庭ができて、年少人口も少しずつ増えていきながら、人口全体も増えてくる。その結果、税収が安定してくるといった構図をつくっていきたいということです。
吉田
いい部分ばかり考えていますが、都合の悪い部分が全然見えていないのではないかと思います。先ほど申し上げましたが、新しい住宅ができると、その分インフラも整備しなければいけない。そうすると、今、下水道管の事故が全国で話題となっていますが、本市もそうした修繕、維持管理に相当お金がかかっていますし、管理しなければいけない部分が増えていくわけです。仮にどこかの住宅地の一つの区画から一斉に人がいなくなって、その分、別な住宅地で一斉に増えていく。こちらはインフラは全部捨てていいと思います。できると思います。しかし、市内各住宅地から人口がまるで歯が抜けるように減少していくような状況では、使う方がいる以上、インフラは全部維持していかなければいけない。人口が維持されたとしても、その維持すべきインフラが増えていったら市の財政負担はどんどん増えてしまうのではないか。ここのところを非常に危惧しているわけです。
次に移ります。空き家対策についてお伺いします。
小項目5 既存住宅地の人口の維持に向けた空き家対策に取り組むべきと考えますが、市長の御見解を伺います。
市長
空き家の有効活用に向けた取組として、市が指定する特定エリアにおいて、新築・中古を問わず住宅を購入した世帯を対象としたなとりマイホーム応援補助金や、空き家を改修して起業する方を対象とした空き家有効活用支援事業補助金を支給しており、これらの事業により、既存市街地への移住・定住を促進することで人口の維持に向けて取り組んでいるところです。
なお、空き家の有効活用に向けた取組として、空き家の売却や貸出しを希望する所有者と空き家の利用を希望する方とをつなぎ、有効活用を促進することを目的に令和4年度から空き家バンクも運営しております。
吉田
分かりました。今の取組の成果を聞く前に、空き家となる原因はいろいろあると思いますが、最も多い原因は何であると認識されているでしょうか。
なとりの魅力創生課長
空き家となる要因で一番多いのは、相続と捉えています。
吉田
国土交通省の令和元年空き家所有者実態調査によりますと、空き家を所有することになった理由のうち最も多いのが、今課長がおっしゃった相続、こちらは54.6%に上ります。今後、高齢化から、つまり最も人口が多い年代が終えんを迎えていく時代が到来していくわけですから、親が所有する空き家を相続するケースはますます増えるものと思われます。しっかり管理されているのであれば問題は少ないのですが、既存住宅地の人口が減れば、活気が失われ、魅力のない土地となるばかりです。物置として使用されるケースも実際には多いようですが、人が居住していない家屋は劣化も早いと言われています。住み続けてもらうこと、住む人がいない家は所有者に適切に管理してもらうこと、所有の意思がない場合は手放しやすくすること、迷惑空き家を是正させること等、空き家対策といっても課題は多方面にわたっています。現在の本市の体制や取組で深刻化する空き家問題に対応するのは難しくなるのではないかと思いますが、その体制の部分でのお考えをお伺いします。
企画部長
庁内の体制ということでは、なとりの魅力創生課、それから、関係する部署で空き家対策は進めているところです。しかし、空き家の流通となりますと庁内の体制だけでは不十分ですので、全国宅地建物取引業協会連合会等に、物件の紹介あるいは中古物件の仲介等、様々な御協力をいただいていますし、最近は宮城県司法書士会とも連携協定を締結しました。空き家の原因となっている相続に関する相談会等もこの前開催しましたが、外部の力も借りて空き家対策については行っていきたいと考えています。
吉田
私からの提言をさせていただきたいと思います。
まず、相続などで得た空き家を所有者に適切に管理してもらう課題。特に所有者が遠方に住んでいる場合のことですが、民間企業、特に不動産業者などが優良の空き家管理サービスを行っています。こちらプランによって金額が変わりますが、月1回60分程度、巡回サービスで月1万円程度の金額が一般的なようです。こうした民間サービスをふるさと納税、ふるさと寄附の返礼とするように取扱業者に促してはどうかと思いますが、いかがお考えでしょうか。
企画部長
まずは、そういった業務を取り扱う業者が市内にあるかどうかということもあるかと思います。もちろん、適正な管理をしていただくということが迷惑空き家発生の防止にもなりますし、その後、市場に流通をさせるということにおいても、適正に管理を続けていただくということは重要かと思います。そういった業者がいるかどうかということも含め、今後の空き家対策の中で実施可能か研究していきたいと思っています。
市長
企業版ふるさと納税の件で、先日、小学生を招待したチャーターフライトなども行っていまして、様々な形で財源を確保しながら事業を推進していくという立場から、議員御提案いただいた件についても検討はしていきたいと思います。
吉田
ただ、幾ら業者に管理してもらっても、常態的に居住するよりは早く傷むということで、これは空き家の根本的な解決にはならないと考えられます。現状の空き家バンク等の政策を進めながら、不動産の所有を継続する意思がない場合に、相続した方が手放しやすくするため、遺贈や相続土地国庫帰属制度などの選択肢もあるということを周知してはいかがかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
なとりの魅力創生課長
相続を機に、そのことも含め、活用できる制度については周知したいと思いますが、所有者の意向もありますので、御案内を行いながら相談に乗っていきたいと思っています。
吉田
そして、迷惑空き家が増えていってしまった際に、それを是正させるための実効性ある対策が求められると思います。その際、空き家の除却費の補助、空き家の家財道具処分費の補助、また、空き家解体時の固定資産税の減免など、こうしたことについて他自治体の取組を参考に導入を検討したらどうかと思いますが、いかがお考えでしょうか。
なとりの魅力創生課長
空き家の除却に伴う税制関係については、私どもでも対応はさせていただいておりまして、その事業の中で周知を行っているところですが、なお分かりやすい周知を心がけていきたいと思っています。
吉田
そして、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正により、管理不全空家に認定されると固定資産税の減免が受けられなくなりました。また、特定空家は、市が所有者に代わって空き家を撤去する行政代執行の対象となりました。本市では改正前の特定空家に認定したケースはありません。迷惑空き家の周辺住民からは、市の消極的な態度に不満の声も上がっています。長期間にわたり所有者から是正に向けた協力を得られない場合、管理不全空家や特定空家への認定も必要ではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。
なとりの魅力創生課長
ただいまの議員から御紹介ありました管理不全空家等々については、法改正に伴う見直しが主になりますが、令和6年度、空き家対策の見直しを行っています。計画の中でもうたっています。実際に実施するかどうかは慎重に判断していかなければならないと思っていますが、計画の中で位置づけていますので、ケース・バイ・ケースで対応について検討していきたいと思います。
吉田
地域が魅力的であるということは、ある一定の人口規模をしっかり住宅地が保っているということ、そして、管理されているということが必要条件だと思います。これから既存住宅地の状況をしっかり見極めながら、本当に住宅の需要がある際に、それ以上の住宅が必要なときの開発ということ、そういう方向で慎重に取り組んでいただきたいと申し上げまして、私からの一般質問を終わりにします。
本会議
(議案第19号 名取市環境基本条例の一部を改正する条例)
吉田
その名称のことについては私も少々疑問があります。今、国際化が進み、本市に在住する外国人が増加する中で、ごみの問題は国ごとに制度が異なるため、日本の制度を理解してもらうのに時間がかかることがあります。その場合、窓口となるのは現在のクリーン対策課で、今後は環境共創課になるわけですが、この課の名前は英語ではどうなるのでしょうか。
政策企画課長
環境はenvironmentになると思いますが、共創の部分についてはco-creationになると思っております。
吉田
今後、外国人向けのパンフレットなどを作成するときは、今の名称をそこに載せる形になってくるのでしょうか。
政策企画課長
今、環境と共創を直訳するとそのような言葉になると答弁しましたが、外国の方にお示しする際にどのような名称がよりふさわしいかという部分については、なお確認の上、対応していきたいと思います。
(議案第22号 工事請負契約の締結)
吉田
今の御説明の最後に、これまでストックされていた土を使うため、新たな購入等はないとのことですが、そうすると、資料2に書かれている盛土工9万4,200立方メートルから掘削工2万4,800立方メートルを引いた分がこれまでたまっていた土の量となるのでしょうか。
都市開発課長
議員お見込みのとおり、これまで残土をこちらにストックしていましたが、それ以外にもストックとして今後の住宅用地建設等に用いる残土があります。
吉田
そうすると、ここの工事を進めていく上で、それらの残土は今後進める住宅地エリアに仮置きしていく形になるのでしょうか。
都市開発課長
議員お見込みのとおりです。
(議案第26号 令和6年度名取市一般会計補正)
吉田
12、13ページ、15款2項1目総務費国庫補助金の5節物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金について、減額の内容をお伺いいたします。
財政課長
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の減額ですが、歳出の42ページから45ページ、3款1項1目社会福祉総務費中、低所得世帯等物価高騰重点支援給付金・定額減税調整給付金給付事業の事業費確定に伴い、歳出見合いの額を全額減額するものです。
吉田
歳出について示していただいたのですが、当初の見込みより減額になったのは、予算を十分使い切って支援が必要なところにしっかり給付できたかどうか、よく見極めた上での減額なのでしょうか。
社会福祉課長
対象となる方は令和6年度新たに住民税非課税世帯、新たに住民税の均等割のみ課税世帯、子育て世帯への加算給付金、そして定額減税にかかる調整給付金についてであり、該当する方全員にお知らせを送付して申請を促し、期間中に申請がなかった件数分を減額しているものです。
吉田
14、15ページ、15款2項4目土木費国庫補助金の1節社会資本整備総合交付金で、空き家再生等推進事業費の当初予算額が皆減になっている理由をお伺いいたします。
企画部長
歳出では32、33ページ、2款1項6目企画費18節負担金補助及び交付金の空き家有効活用支援事業補助金に該当します。この中の地域活性化支援タイプで、空き家を活用して地域活性化につながる取組をする個人や企業・団体に対する補助ですが、これまでも補助金の応募者がいなかったことによって今回減額するものです。
吉田
当初予算を見ると、補助基本額は500万円の2分の1の補助となっていて、歳出は600万円減額補正となっていますが、この250万円の減額は500万円の事業の半分で、今回、補助金の該当者がいなかったということでよろしいですか。
企画部長
当初予算で計上していたものの中には、そのほかに起業支援タイプとして1件当たり100万円の補助があります。歳出の当初予算上は700万円の予算で、1件は今後の申請に備えて保留しておりますが、残る1件を今回減額するということです。
吉田
18、19ページ、17款1項1目財産貸付収入1節土地建物貸付収入で、土地貸付収入の増額について、当初予算の際には令和6年度420件とメモしていたのですが、これは件数が増加したのか、それとも内容が変わったのか、お伺いいたします。
財政課長
土地貸付収入の増額ですが、年間455件を見込んでおり、その件数の増加も要因の一つです。また、令和6年度から路線価の評価替えが行われておりますが、令和6年度当初予算ではその分が見込まれていないこともあります。増額の内訳としては、面積貸し20年超の新規貸付けが10件増で2,960万2,000円の増額、また、先ほど申し上げた路線価の改定等で、防災集団移転先団地、閖上地区、美田園北地区が評価替えの影響でトータル227万6,000円の増額を見込んでいるための増額となっております。
吉田
22、23ページ、17款2項2目土地建物売払収入ですが、件数と主な内容をお伺いいたします。
財政課長
土地売払収入ですが、件数は普通財産の土地9件分の売払収入の見込みです。内訳としては、防災集団移転先団地が2件、貸付けしている土地もしくは未利用地等の部分が7件で、合計9件となっております。
吉田
その金額を決定する際には、評価替えされた後の額が適用されているということでよろしいですか。
財政課長
売払いをする際は、不動産鑑定評価等の対応をしております。また、鑑定評価しない比較的小さい土地などについては、近隣の現状の路線価の評価額から計算しております。
吉田
32、33ページ、2款1項6目企画費18節負担金補助及び交付金で、買い物機能強化等支援事業補助金が133万3,000円の減額です。当初予算では、この金額は市の負担という説明だったと記憶しているのですが、皆減ではなく100万円残している理由をお伺いいたします。
政策企画課長
こちらの買い物機能強化等支援事業補助金については、当初予算において継続事業分として50万円分を2件、新規事業分として、県が行っている同様の補助事業のかさ上げ補助分として1件を見込んでおりましたが、今回新規事業分として見込んでいた経営補助へのかさ上げ補助に該当する事業者がいなかったため、その分を減額しております。
吉田
継続事業分はあるが、新規事業分がなかったということですか。
政策企画課長
議員お見込みのとおりです。
吉田
42、43ページ、3款1項1目社会福祉総務費、先ほど歳入でお聞きした定額減税調整給付金給付事業と低所得世帯等物価高騰重点支援給付金について、期間中に申請がなかった分の減額との御答弁でしたが、それは想定していた申請数そのものが多過ぎて実際に給付を受けた方が少なくなったのか、それとも、要件を満たしている人数の見込みは合っているが、実際の申請が少なくてこのような減額になったのか、どちらの要因が強いと捉えていらっしゃるのでしょうか。
社会福祉課長
予算案を作成したときに多く見込んでいたことが減額の大きな理由です。この予算については、令和6年2月専決と6月定例会の3号補正で予算を認めていただいたのですが、市民税の確定が5月から6月であるため、令和6年6月の時点で未申告の方もいる可能性もあり、多めに見込んだところです。また、定額減税調整給付金について、所得税減税に対する給付は今回初めてだったので見込みが難しかったこともあります。さらに、令和5年度の所得税から令和6年度の所得税を推測するという不確かな部分もあり、多めに見込んだ結果、申請が下回ったと捉えております。
吉田
それでは、給付金の対象者数と、実際の給付件数も捉えていると思いますが、要件を満たしていながら給付を受けなかった件数はどのぐらいになっているのでしょうか。
社会福祉課長
まず、低所得世帯等物価高騰重点支援給付金ですが、対象者と思われる方に発送した件数が1,116件で、返送率は約89%です。もう一つの定額減税調整給付金は、発送した件数が1万5,068件で、返送率は約92%でした。
吉田
54、55ページ、4款1項3目一般予防費の特定財源のその他で4,971万7,000円の減額となっており、これが先ほどの26、27ページ、歳入21款5項2目雑入16節雑入の(一社)新薬・未承認薬等研究開発支援センター助成金と額が一致するのですが、まずこの部分に該当するということでよろしいですか。
財政課長
議員お見込みのとおり、歳入の雑入の(一社)新薬・未承認薬等研究開発支援センター助成金がこの特定財源のその他の内容です。
吉田
歳入の際の御答弁ですと、新型コロナワクチン接種者の減少によりこの助成金が減額になったという説明だったと記憶しています。接種者が減少すれば費用も減るように思いますが、歳出のワクチンの事業費を見ると、国へ返還する金額の増加など、余計に支出が多くなっているように見えるのですが、どのような仕組みなのか、お伺いします。
保健センター所長
一般予防費の内容で、特定財源のその他については歳入の(一社)新薬・未承認薬等研究開発支援センター助成金に一致するものですが、それ以外にほかの予防接種の増減や令和5年度の返還金も入っておりますので、全体的に増加しているわけではありません。
吉田
60、61ページ、6款2項1目林業費12節委託料で、ナラ枯れ被害木対策委託料300万円減額の内容をお伺いいたします。
農林水産課長
ナラ枯れ被害木対策委託料については、これまでと同様に、地域森林計画区域対象森林や公園等において倒木の危険がある場所での駆除を進めてきたところですが、対象となる木の本数が減少したことに加え、作業条件によって委託単価が変動するため、不用額が生じ、減額補正を計上しております。
吉田
当初見込んでいた本数と実際に作業した本数、そして単価変更の部分についても詳細をお伺いいたします。
農林水産課長
当初は100本程度を見込んでおりましたが、令和6年度は現在において29本でしたので、減額となりました。処理方法としては、切った木を薬剤等で薫蒸処理してその場に置くものと、切り出した木をチップ加工して処分するものがあります。
吉田
62、63ページ、7款1項2目商工振興費21節補償補填及び賠償金で、宮城県信用保証協会損失補償金の内容をお伺いいたします。
商工観光課長
宮城県信用保証協会損失補償金については、中小企業振興資金制度を利用して融資を受けた市内の中小企業のうち、倒産等によって返済ができなくなった企業があったことから、宮城県信用保証協会と取り交わしている契約に基づき、信用保証協会が代位弁済した分について負担割合に応じて市が補償するものです。今回、2事業者が対象となっており、その合計が73万3,000円となっております。
吉田
その負担割合は会社や規模によって違うものなのか、負担割合の取決めの部分をお伺いしたいと思います。
商工観光課長
まず、代弁済額の8割は日本政策金融公庫から保険金という形で補填されることになっております。残り2割のうち、本市が負担するのは48%という取決めとなっております。
吉田
72、73ページ、10款1項2目事務局費1節報酬のいじめ防止対策調査委員会委員報酬について、令和6年11月臨時会で条例改正になったと思いますが、そのときの御説明では、たしか委員が5名に減って、その委員の職業や専門分野なども大体見込みがついたとのことでしたが、改めて決定した委員はどのような専門分野の方なのか、また、これまでの会議の経過についてお伺いいたします。
学校教育課長
新しい委員は、法律分野として弁護士、教育福祉が専門の大学教授、医療分野として医師、心理分野として大学の助教、教育心理が専門の大学教授、以上の5名となっております。新しい委員となってから、これまで委員会を令和6年12月21日、令和7年2月1日、3月1日の3回実施しております。第1回の委員会では、委員長、副委員長の選出等が行われました。第2回の委員会では、当該生徒の保護者であるお母様と代理人弁護士への聞き取りを行っております。第3回の委員会では、今後の聞き取りについての方針等が話し合われております。
吉田
今後、3月に開かれるかどうかは分からないのですが、令和7年3月1日の会議で今後の方針等が協議されたとのことですから、その際、今後のスケジュールをどのように組まれたのか、現時点で決定している内容をお伺いいたします。
学校教育課長
次回は令和7年3月30日を予定しております。内容や日程についてはまだ決まっておりませんが、今後、生徒と当時の学校の教員に対しての聞き取りを行っていく予定で調整をしていくところです。
財務常任委員会
(議案第4号 令和7年度名取市一般会計予算)
吉田
12、13ページ、1款2項1目固定資産税の1節現年課税分でお伺いいたします。先日の一般質問で、空き家などの対策として税制関係で既に取り組んでおられるという御答弁がありましたが、実際に空き家の所有権が別の人に移るとか、そうしたときの税制上の何かメリットになるような制度というのは、令和7年度どういったものがあるのでしょうか。
税務課長
空き家関連については、管理不全空家に指定されると固定資産税の住宅用地特例が解除されるとか、そういった制度はありますが、今の御質疑にありましたような特例的なものは特にないところです。
吉田
現状では特定空家も管理不全空家も指定されているものはないと思いますが、令和7年度は、そうした部分についての見込みはこの中に含まれているのかお伺いいたします。
税務課長
御指摘にありましたとおり、現在そういった状況は把握しておりませんので、新年度予算においても織り込んでいないところです。
吉田
12、13ページ、1款2項1目固定資産税の1節現年課税分で、土地についてお伺いいたします。令和6年度予算でも同じ質疑をして、対象となる土地の面積が令和6年度の見込みでは6,517万9,900平方メートルということでしたが、令和7年度の対象となる土地の全体の面積をお伺いいたします。
税務課長
地積についてお答えいたします。令和7年度の見込みですと、6,508万9,435.97平方メートルとなっております。
吉田
新たに課税対象となる土地もあれば、対象から外れる土地もあって、トータルすると令和6年度よりも面積は9万平方メートルぐらい減っていますが、対象から外れる要因としてどういうところが大きいのか、どう分析されているのかをお伺いいたします。
税務課長
全て詳細に捉えているわけではありませんが、代表的な例として区画整理などで地積が整理されて減少になったとか、そういったことなどがあると捉えております。
吉田
12、13ページ、1款2項1目固定資産税1節現年課税分でお伺いいたします。こちらについては以前から確認してきましたが、疑義が生じている学校法人、活動の実態の部分で疑義が生じているということで令和6年度に調査をされているはずです。その調査結果を受けての令和7年度の取扱いについてお伺いいたします。
税務課長
新年度予算の算出においては、予算編成時点の状況で見積もっておりまして、今回、提起された疑義に対しての判断の結果は織り込んでいないところです。
吉田
判断に何か結果があっての新年度予算なのか、判断の結果がまだ何も確定したものがない中での今回の御提案なのか、そこをお伺いいたします。
税務課長
繰り返しの答弁になってしまいますが、予算編成時点というか、令和6年度の課税実績の状況で積算しておりますので、そういった疑義に対する判断の結果は特に入っていないところです。
吉田
14、15ページ、1款3項2目種別割の1節現年課税分でお伺いいたします。補足説明より、今回は台数が2万9,007台とのことですが、その中で、古い車の税金が高くなっているという、平成27年3月31日でなのでしょうか、年度が変わるとどこが基準になるか分からないのですが、古くなって金額が変わる台数は何か捉えているものはありますか。
税務課長
厳密ではありませんが、今御指摘いただいたとおり、自家用軽四輪車については、旧税率と新税率で出入りがありました。見込みとしては、旧税率が837台減少、新税率が849台の増加となっております。ですので、こちらは推測になってしまいますが、買換えなどがあったのかなとは捉えているところです。
吉田
その見込みというのは、やはり前年度の実績などから導かれるものなのですか。それとも、何か別の方法で予測が立てられる部分があったりするのでしょうか。
吉田
16、17ページ、1款7項1目都市計画税1節の現年課税分です。令和6年度中に市街化区域に編入された土地はあったのでしょうか。市街化区域に新たに編入された分をどう反映しているのかをお伺いします。
税務課長
令和6年度中に市街化区域に編入した区域はないものと捉えております。
吉田
22、23ページ、11款1項1目地方交付税です。その内訳の中で特別交付税が令和6年度比で2割増となっておりますが、これは国からそのように示された根拠のようなものがあるのでしょうか。
財政課長
特別交付税については、省令で定めているルール分と災害発生等によるルール分以外の要素が含まれておりますが、実際、ルール分以外については、災害が全国で発生している状況等により、配分が変わってくるという状況です。国から何か示されたのかというお尋ねですが、そういうことではなく、本市における直近3か年の平均を見ますと、6億1,400万円程度の交付実績があります。地方財政対策においては、地方交付税が全体で1.6%の増ということが示されておりますので、最低でも6億円程度は交付いただけるのかなということで増額をしているところです。
吉田
24、25ページ、14款1項2目衛生使用料1節環境衛生使用料の墓地使用料です。補足説明によれば令和7年度は87基ということで、既に申込みがある部分ということだと思いますが、区画ごとの内訳と、さらに、区画ごとの受け入れられる空きの数、どのぐらい空いているのかをお伺いいたします。
クリーン対策課長
まず、87基の内訳ですが、墓地は区画ごとに大きさが変わっておりまして、一般墓地ですとA区画、B区画、C区画と分かれていますが、一般墓地についてはまとめてお答えさせていただきます。一般墓地全体で37基、そのうち市内の方が12基、市外の方が25基です。続いて、芝生墓地は50基を見込んでおり、市内の方が22基、市外の方が28基です。
残基数ですが、市民墓地の総区画数2,438基に対し、令和7年2月末現在で956基が使用済みですので、残りが1,482基です。その内訳ですが、一般墓地が678基、芝生墓地が352基、被災者墓地が452基です。
吉田
傾向として恐らく芝生墓地の人気があるのかと思います。この残基数が令和7年度中に全部契約になるとはなかなか考えられないところだと思うのですが、今後の増設等についての令和7年度中の考え方をお伺いします。
クリーン対策課長
令和7年度中に新たに増設する予定はありません。今、吉田委員がおっしゃったとおり、芝生墓地の人気があることについては認識しているところです。今のペースで芝生墓地の販売をしていった場合という仮定の話になりますが、令和13年度頃に芝生墓地の残がなくなる見込みです。したがって、それまでの間に、今はまだ今後整備可能な区画が残っていますので、その区画をどのように活用していくかについて、検討していきたいと考えております。
吉田
26、27ページ、14款1項3目農林水産業使用料の2節ろ過海水供給施設使用料です。令和6年度の当初のときも、軽減措置が令和5年度まであって、それが下がるというような御答弁があったと思いますが、もし令和7年度の軽減措置があるのであれば、その内容をお伺いします。
農林水産課長
このろ過海水供給施設使用料については、令和6年度から令和8年度までの部分が、経過措置として23.5%から25%の軽減となっていますので、今回もそれを使用しております。また、若干令和6年度より増えているところについては、使用する量が増えているということで使用料を上げさせていただいたところです。
吉田
その軽減分を含まない単価は変わらないということですよね。このろ過海水供給施設は修繕等でかなりお金がかかっておりまして、この現在の単価の在り方、計算の仕方で果たしてどうなのかなと正直思うところがありますが、令和8年度までは軽減があって、その先のことについての検討などが令和7年度のスケジュールに入っているのかをお伺いいたします。
農林水産課長
確かに軽減の関係については令和6年度から令和8年度までということで、それを今後見直すというところについては、令和8年度あたりに時期的に見直すかどうかを検討していきたいと考えております。
吉田
30、31ページ、15款1項1目民生費国庫負担金4節教育・保育給付費中、上から2つ目の地域型保育給付費(小規模保育事業等分)です。予算資料を見ますと、令和6年度が12施設だったのが、令和7年度は11施設で、1施設分、減となっています。この減というのが、補助金の対象から外れたのか、それとも施設が閉鎖されたのか、そうしたことも含めて、この増減の内容の部分をお伺いいたします。
こども支援課長
地域型保育施設1施設が閉園する見込みになりまして、ただ、系列の認可保育所がありますので、そちらで継続して、お子さんは受入れ等をしていただく方向で調整していますが、1つ閉園になることによる施設数の減になっております。
こちらの給付費については、第13号補正のときにもお話ししましたが、給付費の算定の基礎となる公定価格という単価が、人事院勧告での人件費増の分で価格自体が大きく上がっておりまして、令和7年度もそちらの公定価格を参照しておりますので、給付費が大きく増になる形になっております。
吉田
閉園ということですが、影響は極力少なく抑えられそうだということは分かりました。実際にこれまで受け入れられていた定員数、実際に利用されていた利用者の最終的な人数、実際に今回影響が及ぶと思われる人数についてと、また、子供さん方が移ることによる、そちらの施設への補助の額がしっかり手当てされているのかどうか、お伺いいたします。
こども支援課長
新しく移行する園の補助の額については、利用する人数に基づいてしっかりと給付費は算定させていただきますので、そちらについては影響はないと捉えております。
何人移行するかについては、今手持ちの資料がなく、お答えすることができませんので、答弁保留とさせていただきます。
吉田
38、39ページ、15款2項2目民生費国庫補助金3節家庭児童福祉費の母子家庭等対策総合支援事業費の中で、令和6年度に日常生活支援事業費として計上されていた分が今回皆減となっておりますが、それがどこに行ったのかお伺いします。
こども支援課長
委員御指摘の母子家庭等対策総合支援事業にあった日常生活支援事業費については、2節児童福祉費の子育て世帯日常生活支援事業費で拡充して取り組む事業として予算を見込んでおります。38、39ページの中段です。
吉田
この国庫補助率が2分の1から3分の1に縮小されているように見えるのですが、それから、子育て世帯日常生活支援事業費では月当たりの人数を今回新たな制度の下で見込んでいるようですが、そのような部分での影響は何かないのかお伺いします。
こども支援課長
まず、国の補助率ですが、国の補助は3分の1、同じく県の補助も3分の1ありますので、全体としては3分の2の補助を受けられることになりますので、拡充されていると捉えております。
月当たりの人数ですが、積算の根拠としては、1回当たり2時間、週2回ヘルパーを派遣し、その1か月当たりの見込みを立てまして、それに12か月を掛けたという積算になりますので、延べの世帯という形で捉えていただければと思います。
吉田
40、41ページ、15款2項3目衛生費国庫補助金1節母子保健衛生費の産婦健康診査事業費、令和6年度よりも対象者数を減として見込んでおりますが、どのような見込みで少なくしたのか、前年度実績に基づいた数値なのか、その辺についてお伺いいたします。
保健センター所長
産婦健康診査事業費ですが、こちらは実績に基づき、産婦が減少しているということで、令和7年度は対象者数を減らして算出したものです。
吉田
これは基本的に全員が受ける健康診査ということで、対象者数をそのままここに見込みとして費用を充てているということですか。受けない人がいるという想定ではなくて、全員が受けるという考え方でよろしいですか。
保健センター所長
母子手帳の交付数なども参考にしながら、全員が受けるような形で人数を出しております。
吉田
44、45ページ、15款2項5目教育費国庫補助金1節教育総務費、特別支援教育就学奨励費とありまして、こちらは資料によると188人ということですが、これは特別支援学級の在学生、小学1年から中学3年までの9学年の全員の数を見込んでおられるということでよろしいですか。
学校教育課長
こちらについては所得区分がありまして、支給できる品目などもそれによって3つに分かれております。1区分としては生活保護基準の1.5倍までの所得、2区分としては2.5倍までの所得、そして3区分としては2.5倍を超える所得ということで3つの基準に分かれています。
吉田
その3つの区分のどれにも入らないような特別支援の生徒は何人くらいいるのでしょうか。
学校教育課長
3つの所得区分について、生活保護基準の1.5倍までの所得、2.5倍までの所得、2.5倍を超える所得ということで説明をさせていただきましたが、生活保護基準の1.0倍については生活保護を受給していただくと。1.3倍については就学援助を受けていただくということで、こちらは併給はできないことになっておりますので、それを受けていただくということで、この3つを合わせて特別支援学級に在籍する全ての児童生徒について、その対象になるということです。
吉田
56、57ページ、16款2項2目民生費県補助金、一番下に産後ケア事業費とありまして、人数は600人を見込んでいるということです。先ほどの40、41ページ、15款2項3目衛生費国庫補助金の産婦健康診査事業費は、基本的に全員対象で500人を見込んでおられるということで、もし産後ケアを全員受けたとして600人で、こちらの産婦健康診査が500人となると、100人のずれがあると思うのですが、まず、この600人という人数を見込んだ理由についてお伺いいたします。
健康福祉部長
衛生費国庫補助金の産婦健康診査事業費の500人は、実人数で見込んだ500人です。民生費国庫補助金の産後ケア事業の600人については、延べで計算した人数で、宿泊型、通所型、訪問型をそれぞれ計算して足し上げたのが600人となっております。そこで500人と600人の差が出ているところです。
吉田
58、59ページ、16款2項2目民生費県補助金3節児童福祉費の一番下にある子どもの貧困対策支援事業費、令和7年度は8団体ということで令和6年度から2団体増えているようですが、こちらはその団体から正式に申請等があって、令和7年度は8団体体制でスタートできるということでよろしいですか。
こども支援課長
子ども食堂を運営している団体への補助8団体を見込んでいるところです。今、実際動いているのは7団体で、1団体は今後開設されるだろうと見込んでいる団体になります。
吉田
その見込みの団体は間もなく子ども食堂の運営が始まることが年度内にはほぼ決まっているという情報を得た上での、今回のこういう数字ということでよろしいですか。
こども支援課長
当初予算を算定したときはまだお話はなかったのですが、今の段階でこども支援課に2団体ぐらい、令和7年度開設したい旨の相談は来ています。ただ、令和7年度にしっかり開設できるかどうか、まだはっきりとは見込めていない状況です。
吉田
66、67ページ、17款1項財産運用収入で、3目以下の基金収入のところでお伺いいたします。資金の運用については、定期預金のほかに地方金融機構債、国債、都市再生債など、債権での運用が増えてきていることによって利子も上がっているところがある反面、今、長期金利が上昇していることから、債権そのものの評価額が下がる傾向にあるのではないかと思いますが、その評価額については捉えておられるかお伺いします。
会計管理者
評価額については、年に一度、取引の会社からその時点での評価額が示されておりますので、その時点での評価額は捉えているところです。
吉田
令和7年度のこの予算には直接その数字は出てきませんので、別な観点からしますと、恐らく令和7年度中にもその評価額の報告があるわけですよね。今、長期金利が0.15%という中で、現状のまま推移したときに令和7年度中の評価損がどのぐらいになる見込みなのか、そうした予測は立てておられるでしょうか。
会計管理者
予測は大変難しいものと捉えております。現在の状況を見てみますと、例えば金融機構債や国債、そのほか都市再生債などを購入しているところですが、その債権の種類によっても違いますし、購入した年度によっても評価が下がるその率が違っているようなので、見込みは立てられないところです。
吉田
92、93ページ、2款1項1目一般管理費の18節負担金補助及び交付金、宮城県市長会特別負担金について伺います。台湾訪問は何を目的としているのか。経済界なら経済交流などでお互いの製品を売ったり買ったりするという意味で分かります。ただ、行政ということならば、行政として市民全体に広くメリットがなければいけないと思いますが、そういう意味で何を目的に行かれているのか、令和7年度は何を目的に行く予定なのかお伺いします。
政策企画課長
委員御指摘のとおり、主な目的としては経済交流や観光交流、インバウンド促進などが大きな部分を占めるものです。当然、民間同士の交流ももちろん成果としては期待できるものですが、そこに行政も含めて、とりわけこちらは宮城県内の市長が全員参加して日本の中の東北の中の宮城県をPRするというトップセールスです。台湾の行政のトップの方々との会談等も行われますので、今後の経済発展あるいは観光の交流という意味で大きな成果が上げられる、期待できるものと考えています。
吉田
おっしゃりたいことは分からなくはないのですが、数を連ねていくということに意味があるのでしょうか。市長会としてなのか。どこの市が一体主体となってこういうことを言い出して始めているのか。恐らくは、政令指定都市あたりかなとも思いますが。結局、今回予定されている台湾訪問、相手方の台湾のどういう方たちとどういう日程でお会いして、そこにまた、それこそトップセールスならトップセールスで直接会話ができなければいけないですが、間に恐らく通訳の方が入ったりすると思います。台湾の方の声を聞いたりこちらの声を伝えたりするのに、どのように意思疎通を十分に図っていく考えなのかをお伺いします。
政策企画課長
台湾訪問の企画そのものについて、例えばどこどこの首長が強いリーダーシップを持ってこれを始めたということではなくて、最近の台湾などアジア圏からのインバウンドの高まり、あるいは、現にそちらの地域から東北に来られる方も大分増えていることを踏まえて、市長会全体として、ぜひ、首長が一団となってそういった企画に取り組んではどうかということになったものと承知しています。
今手元に詳細の名簿などを持ち合わせていなくて申し訳ないのですが、例えば、台北市長や在台北の経済関係のそれなりのポストの方と直接意見交換を行い、今後の取組につなげていくものです。
吉田
94、95ページ、2款1項2目文書費12節委託料の例規集更新データ作成等委託料について、例規集の冊子についてお伺いします。令和5年度の質疑で126冊と御答弁があったかと思いますが、令和7年度の冊数とその金額の契約の在り方、1冊当たりの契約なのか、違う形になっているのかをお伺いします。
総務課長
例規集の紙のものは、これまで126冊ということで加除を行ってきました。令和6年度中に事務改善という内容で職員から提案があり、外部施設などでは特に紙の例規集を使わないことと、加除のたびに持ってくる手間もかかるということで、事務改善を行った結果、102冊になる予定となっています。庁舎内分は残す予定です。
こちらはデータの更新なども含めまして一括で委託しているものです。
吉田
我々も年に4回ほど加除で重いものを事務局まで持っていくのですが、議会としても恐らくデータで処理できるのではないかと思います。職員の皆さんも必要とされているところがあると思いますが、実際その差し替えの作業がこの委託料の中に含まれているのか、それとも職員が手で差し替えているのか。もし手で差し替えているとすれば、その作業に年間何時間ぐらいの時間が取られるのか伺います。
総務課長
例規集の紙の加除については業者に委託していまして、一括して行っていただく内容です。
吉田
令和7年度の区分とそれぞれの単価、そして、もし分かれば、見込みの時間数を伺います。
防災安全課長
現行4時間未満1回2,500円を、3時間未満1回2,500円に変更する。続いて、4時間以上、これは2回分とカウントしますが5,000円と決めていたものを3時間以上2回5,000円ということで変更しています。それから、同日に複数回の出動があった場合、今まで1.5回で3,750円としていましたが、こちらについては2回で5,000円、3回で7,500円と考え方を変えています。
それから、街頭指導分については、朝晩については変わりなく1回2,500円ですが、施設等において実施している交通安全教室については、今まで2,500円でしたが、3,500円に変更しています。ただし、交通安全教室を実施するに当たっては事前の打合せの時間が必要になってきます。今まではそれを別に計算していたのですが、今回は研修打合せの時間をこの3,500円の中に含めて考えることにしています。
その他行事等の出動単価2,500円は変わりありません。
吉田
162、163ページ、3款2項1目老人福祉総務費12節委託料に増田西老人憩の家解体設計委託料があります。底地は借りているということで、所有者の方の御事情ということもあろうかと思いますが、後継施設をどのように検討していくのか、令和7年度中のスケジュールをお伺いします。
介護長寿課長
今後の増田西老人憩の家の在り方について、まだ方針が決まっていません。現存の施設は令和7年度いっぱいは使えることになっていますので、令和7年度の中で今後の方針について、いろいろな可能性を探りながら検討していきたいと考えています。
吉田
令和7年度いっぱいは使えますが、令和8年4月からは使えなくなるということです。すぐに新しい施設とはなかなかいかない事情は分かります。当面の間は、代替の施設で継続して、活動している方が分散されるということはあろうかと思います。しかし、ある程度道筋が示されない以上は、不安なこともあったり、あるいは住民の間で不確かな情報も流れたりということもあります。できる範囲で市のほうから今後の道筋を示していただいたほうがいいのではないかと思いますが、今の御答弁だと令和7年度中に何がどう進むのか分からないので、現時点での方向性、示せる部分でお伺いしたいと思います。
介護長寿課長
先日、地元の町内会の理事会、連合町内会の会長の集まりに出席して、現時点では既存の公的施設で活動の場所を分散していただくことをまず考えていただきたいということをお話ししました。
吉田
196、197ページ、4款1項2目感染症・結核予防費で伺います。これまで13節に感染症情報配信アプリ使用料が計上されていましたが、今回見当たりません。皆減かと思いますが、そのあたりの事情をお伺いします。
保健センター所長
感染症情報の発信の必要性は高いということでこれまで実施してきましたが、新型コロナウイルス感染症の流行から5年間経過したということもありますので、アプリの当初の目的は達成されたと考えて見直しを行ったところです。その財源を他の感染症対策に充てていきたいと考えています。
吉田
いろいろなアプリがあって、5万ライセンス分の予算を確保した中で登録者数が伸び悩んでいたという実情があったので、致し方ないことではあるとは思いますが、実際にプレサインを使っておられた方々が同様の情報を得たいという場合に、ナトぽたで代替できるような仕組みになっているかどうかお伺いします。
保健センター所長
現在想定していますのは、ホームページで、これまでの感染症情報配信アプリの情報の内容を参考にしながら、公的機関、県、保健所、国の感染症情報を周知していきたいと考えています。
吉田
206、207ページ、4款1項8目環境保全対策費の7節報償費の中でお伺いします。自然体験事業で、ここは協力者謝礼ですが、ほかのところにもいろいろ出てきています。総括質疑で、対象年齢、時期、行き先などをお伺いしましたが、対象者をどうやって決めるのか。また、人数はどうなのか。また、この事業そのものが環境保全事業ということで、その啓発も事業の中に含まれていると思います。一定の効果を得るためには振り返りが必要になってくるのではないかと思いますが、この計画の中でどのように検討されているのかお伺いいたします。
クリーン対策課長
募集について、詳細は今後詰めていくことになりますが、7月下旬を予定していますので、6月の広報なとりで周知をするとともに、各小学校に御案内したいと考えています。人数は20人を考えています。
その効果については、子供たちが実際に自然と触れ合う中で環境保全意識の啓発につなげていきたいと考えていますが、事後のアンケートを取る形で今後つなげていきたいと考えています。
吉田
これも教育分野ではないのかなというような気がしなくもないですが、それは置いておいて、実際に参加される方々の自己負担はどうなっているのかお伺いします。
クリーン対策課長
宿泊場所は岩手県陸前高田市の岩手県立野外活動センターを想定しています。宿泊代、食事料金分は実費負担で、1人当たり6,000円程度を想定しています。
吉田
194、195ページ、4款1項1目保健衛生総務費18節負担金補助及び交付金の二次救急医療運営補助金についてです。これは若干金額が下がっています。要綱の中での算定式が変わったのか、それとも、実際の利用者数の見込数なのか、この金額の根拠をお伺いします。
保健センター所長
算定基準が変更になったということではありません。2市2町の人口、受診者数での案分で若干下がっています。
吉田
具体的に根拠となった数字の受診者数はどのように予測されているのか。令和6年度との比較での減だと思いますが、いかがでしょうか。
保健センター所長
令和5年10月から令和6年9月までの期間で、本市は268人となっています。比較は持ち合わせていませんでした。
吉田
212、213ページ、4款1項12目みやぎ環境交付金事業費10節需用費の修繕料です。実施計画には市庁舎と名取駅東西自由通路で照明をLED化と書いてありますが、具体的な場所と基数を伺います。
財政課長
市庁舎においては、市役所1階、2階の大部分の箇所、各事務室、1階の更衣室、合計で429本のLED化を見込んでいます。
名取駅東西自由通路については、自由通路の入り口の天井照明11台、案内板の照明16台を予定しています。
吉田
LED化というのは、土台となる機材の部分の工事も含めての金額ということですか。
財政課長
委員おっしゃるとおり、機材一体として蛍光灯仕立てのものからLEDのものに変えるということです。
吉田
188、189ページ、3款4項3目中国残留邦人等支援給付事業費の中国残留邦人の人数ですが、歳入の資料だと延べ数なのか月21人となっていて、住宅支援給付費のほうが月5人となっています。そうでないところだと6人と書いてあるところや3人と書いてあるところもありますが、その5人は間違いないですか。
社会福祉課長
現在は5世帯5人で間違いなく、最後に亡くなられた方が令和7年1月なので、その分が予算要求の時点とずれていると思います。
吉田
これは国に申請する補助金ですので、きちんと根拠があるはずです。21人となっているのはどういうことですか。5人とはかなり差があるのではないかなと思いますが。延べだとしても、項目ごとに数字がばらばらなので。6人となっているところは1人亡くなって5人になったということですか。
社会福祉課長
生活支援給付費の一番上の段の6人は、この後1人亡くなっています。
住宅支援給付費は1世帯に対して1人なので5人。介護支援給付費は介護を利用する方を対象としています。医療支援給付費は、この時点で6人ですが、今は亡くなって5人です。
吉田
230、231ページ、6款1項7目農業土木費15節原材料費の田んぼダム原材料についてお伺いいたします。田んぼダムの取組については総括質疑でも御答弁いただいておりますが、原材料に関して、今回対象となる田んぼに対して、市からどのようなものをどのような形で配分していくのか、お伺いいたします。
農林水産課長
田んぼに調整堰板を設置し、水田の雨水貯留機能を強化していくことになります。設置を予定している法人等に対して、購入した調整堰板を配付し、設置箇所については法人と市が場所等を選定し、調整しながら設置していきたいと考えております。
吉田
堰板の枚数については後で御答弁いただきたいのですが、市から対象となる農家に一定程度配分して、場所等は決めながらということかと思います。
令和2年9月定例会の一般質問で、取組の一例として、新潟県見附市において、田んぼダム事業に参加する農家の方に対し、協力に対するお礼のような形で、あぜ道の草刈りの作業日当を支給しているという事例を紹介しました。田んぼダムは農家の方々の協力によって成り立つものですが、現在の農業の非常に厳しい経営環境を踏まえ、作業に対する市からのお礼やメリットとなるようなことは考えていないのか、お伺いいたします。
農林水産課長
堰板の枚数は概算で約300枚あります。委員御紹介の件については、この区域は多面的機能支払交付金の対象区域になりますので、田んぼダムを設置した農地の面積数によって多面的機能支払交付金の加算が増えると伺っております。これを活用できるかどうか、その団体とも協議しながら鋭意進めていきたいと思っております。
吉田
238、239ページ、6款3項1目水産業総務費18節負担金補助及び交付金で、広瀬名取川水系さけます増殖協会負担金の内容についてお伺いいたします。
農林水産課長
こちらについては、市が事務局になっている広瀬名取川水系さけます増殖協会の運営費に係る補助金になります。
吉田
増田川は入っていないのですか。増田川では、令和5年にはサケが一匹も確認されず、令和6年には1匹の遡上が確認されております。このように川の豊かな生態系を守るという観点もこの協会においては重視すべき点だと考えますが、増田川のサケについて、令和7年度はどのような取組を予定しているのか、お伺いいたします。
農林水産課長
あくまでも、こちらの補助金は広瀬名取川漁業協同組合に係るものですので、増田川は入っておりません。
吉田
238、239ページ、6款3項2目水産業振興費12節委託料、ろ過海水供給施設保守点検委託料でお伺いいたします。さきの補正予算で前倒しされた抜本的改良と令和7年度の保守点検の時期が重なるかと思いますが、それぞれの作業は対象となる機器や部位が異なるのか、また、場所を調整して並行して実施するのか、あるいは時期を調整するのか、伺います。
農林水産課長
今回の保守点検は、取水施設と給水施設の稼働に関する補修料となっております。工事については、その影響を受けない時期に進めていきたいと考えております。
吉田
恐らく異なる委託先になるのではないかと思うのですが、現時点では具体的な時期は決まっていないのでしょうか。
農林水産課長
取水施設の保守点検については、予算成立後すぐに入札で委託を進めていきますが、工事についてはその保守点検の結果を踏まえて令和7年度に入ってから実施する予定です。
吉田
266、267ページ、8款4項1目都市計画総務費12節委託料の立地適正化計画策定検討業務委託料についてお伺いいたします。総括質疑に対する答弁で、社会資本整備総合交付金の重点配分一律化のための策定と理解しましたが、市街化区域編入予定の広いエリアとの整合性についてまだ疑問が残ります。立地適正化計画の制度の概要について、総括質疑で答弁のあった住宅ローン減税は具体的にどの区域に適用されるのか、お伺いいたします。
都市計画課長
まず、立地適正化計画の概要ですが、今回、市内において居住誘導区域と都市施設の誘導区域を定める予定で、これらの区域内で住宅ローン減税などの優遇措置を講じます。また、区域外には緩やかな規制を設けて人口を誘導区域内へと誘導し、人口密度や都市サービスの維持を図ることが目的となっております。住宅ローン減税の具体的な対象区域については、今後の検討によって決定するため、現時点では未定となっております。
吉田
これから策定するため詳細は決まっておらず、まずは策定を進めていく方向性であると理解しております。国土交通省が示している資料などを見ると、居住誘導区域については人口密度を確保することが明記されており、今後の人口推移を踏まえながら、できる限り人口を集約していくという考え方ですので、新たに造成される地域が増えると人口密度が分散することになります。その点を踏まえると、今後、市街化区域への編入が予定されている地域については、居住誘導区域には含まれないのかと思いますが、見解をお伺いします。
都市計画課長
今回の4地区についても市街化区域に編入予定ですので、居住誘導を図っていく考えです。
吉田
266、267ページ、先ほどの8款4項1目都市計画総務費12節委託料の立地適正化計画策定検討業務委託料について、再度伺います。
市街化区域の中に都市機能誘導区域があり、その中に居住誘導区域を設定するという区域分けが国から示されていますが、そうなると誘導区域はさらに狭くなると思います。国立社会保障・人口問題研究所の人口推計では、本市の人口は今後7万8,000人から7万9,000人台とされている中、市街化区域を広げるほど人口密度は下がり、矛盾が生じます。実際に人口を誘導できる現実的な計画として整理できていて、国に認められる見込みはあるのか。実際、国立社会保障・人口問題研究所の資料にも、現実的でない案であるとか実現不可能な案である、あるいは人口密度の低下などと記載されていますが、実現可能な数字はしっかり設定できるとお考えなのでしょうか。
都市計画課長
現在、まだ策定は行っておりませんが、予算成立後に検討を進めます。居住誘導区域は市街化区域内で、都市機能誘導区域は駅周辺など交通利便性の高い地区を想定し、進めていく予定です。
吉田
どこかの住宅地をその区域から外して人口を持ってくるわけではないとは思いますが、これから策定段階なので具体的なことは未定だとしても、補助金の重点配分を受けるためだけに策定を進めるのは本末転倒だと考えます。実現可能な立地適正化を進めるための計画として、これからどのような方々の意見を取り入れて策定を行うのか、そのプロセスについてお伺いします。
都市計画課長
今後の進め方については、国土交通省のガイドラインに従い、県の助言などを受けながら策定していきます。また、策定に当たっては、関係各課などと内容調整を密に行い、説明会やパブリックコメントなどを実施して住民の意見を反映させ、名取市都市計画審議会への意見聴取及び諮問を行った上で進めていきたいと考えております。
吉田
266、267ページの8款4項1目都市計画総務費、もしくは268、269ページの8款4項4目コミュニティプラザ等管理費で、名取駅コミュニティプラザのレイアウト変更の予算は1目都市計画総務費17節備品購入費の施設用備品購入費になるのでしょうか、まずお伺いします。
都市開発課長
名取駅コミュニティプラザのレイアウト変更については、266、267ページの8款4項1目都市計画総務費で措置しております。なぜ268、269ページの8款4項4目コミュニティプラザ等管理費ではないのかという御質疑かと思いますが、今回のレイアウト変更は名取駅東地区にぎわい再生計画に基づくもので、中心市街地活性化推進事業に位置づけられたため、こちらで措置しております。また、備品購入費のほか、需用費でも措置しております。
吉田
レイアウト変更に関しては、図書館の混雑などの理由で個人用学習スペースの設置が検討されているのだと思いますが、以前、アイスクリームやコーヒーなどの軽食提供の検討についても説明がありました。今回のレイアウト変更をきっかけに、そのような飲食スペースも設置する予定があるのか、もし設置される場合、その内容についてお伺いいたします。
都市開発課長
自動販売機については、市の事業ではなく、名取まちづくり株式会社による設置となります。現時点では未設置ですが、令和7年3月末までにアイスクリームの自動販売機を東西自由通路側に設置予定となっております。
吉田
278、279ページ、9款1項1目常備消防費で職員全体のことでお伺いします。令和7年度の職員の体制、人数と、現時点で育児休業の対象となると見込まれる男性職員の数、そしてどのぐらいの取得率を目指すのかということももしあればお伺いいたします。
消防本部総務課長
令和7年度の消防職員の体制については104名となり、そのほかに定数外で初任科入校者が5名おります。育児休業については、現在1名が取得予定と見込んでいるところです。
委員
どの部署も同じですが、今、女性だけではなく男性職員も育児休業を取りやすくするという流れで全国で取り組んでいると思います。この1名はあくまで申請ということだと思うのですが、令和7年度内にもし新たに申請者があった場合に、どのような形で育児休業を取りやすくしていこうとしているのか、組織としての考え方をお伺いします。
消防本部総務課長
育児休業については、現在、100%取れるように調整しているところです。令和7年度以降についても、申請があれば調整して、100%取得を目指して実施していきたいと考えております。
吉田
278、279ページ、9款1項1目常備消防費で令和7年度の救急車の配備等についてです。令和6年末に完成した手倉田出張所、手倉田字山の新しい出張所への救急車の配備のスケジュールとそこに配置される人員の体制についてお伺いいたします。
消防長
救急車は令和7年4月1日から配備する予定です。人員については、救急隊増隊分8名がプラスになりまして16名体制となります。
吉田
このことによって消防力の強化につながると思うのですが、線路から西側や南側の地域で救急車の到着までの所要時間がどのぐらい短縮される見込みか、何か捉えていればお伺いいたします。
警防課長
以前、手倉田出張所の配置の検討に当たり、消防力適正配置等調査を業者に委託し算出したときには、たしか1分程度は現場到着が早くなるであろうという結果でしたが、実際に運用してその辺がどのようになるか見ていきたいと考えております。ただ、早くなるのは間違いないのではないかと考えているところです。
吉田
286、287ページ、9款1項3目消防施設費14節工事請負費の消防救急デジタル無線システム更新工事です。性能が上がるということで大変な安心材料だと思いますが、金額がかなり高額で、お荷物になりかねないといったこともよく言われると思います。今回、このシステムの更新に必要となる財源については、それこそ緊急防災・減災事業債で全て充てるという考え方でよろしいですか。
財政課長
委員お見込みのとおり、システム更新の工事費に関しましては緊急防災・減災事業債を100%充当します。
吉田
結構な額がかかるということで、通信指令業務の一元化のような話も以前ありましたが、やはり本市単独で運用できるというのは現時点ではベストな選択だと思うところです。
緊急防災・減災事業債であれば、交付税措置されるのは元利償還金の70%という理解でよろしいですか。
財政課長
委員お見込みのとおり、元利償還金の70%が交付税措置ということです。
吉田
296、297ページ、10款1項2目事務局費18節負担金補助及び交付金の中で外国人児童生徒受入拡大対応事業負担金です。総括質疑でもお伺いしましたが、対象となる外国人児童生徒の定義が分からないのでお伺いいたします。
学校教育課長
日本語や教科の学習をする際に、言語について支援が必要なお子さんと捉えております。
吉田
例えば外国籍を持っているなど、そのようなことを聞きたかったのです。日本人の親が外国に長く住んでいて、外国で生まれたけれども国籍は日本であるなど、そのあたりが曖昧なので詳しくお願いします。
学校教育課長
対象の範囲については、まず外国籍で日本語指導が必要な児童生徒、そのほかに、日本国籍で日本に住んでいたことがある場合でも、外国に長期間滞在した結果、日本語指導が必要となる児童生徒も対象になります。
吉田
先ほど令和7年度の対象児童生徒数の見込みが6名と御答弁がありましたが、外国籍か日本国籍か、内訳は把握しているでしょうか。
学校教育課長
全て外国籍の児童生徒となります。
吉田
308、309ページ、10款2項2目教育振興費17節備品購入費です。この中にはGIGAスクール構想で導入したタブレット端末の更新が含まれていると思うのですが、小学校分の台数をお伺いします。
学校教育課長
児童用と予備用で4,844台、教職員用で318台、合計5,162台を見込んでおります。
吉田
さきの2月定例会初日に、教師用の指導書などの物品購入の件で議決に付すべきだったとありました。2,000万円以上の場合は議決が必要で、このGIGAスクール構想のタブレット端末の更新については合計すれば2,000万円を超えると思うのですが、議決を必要としない理由はどのようなことでしょうか。
学校教育課長
こちらについては、令和7年6月定例会で議案を上程し、承認を得てから本契約を行うというスケジュールになっております。
吉田
314、315ページ、10款3項1目学校管理費12節委託料の第二中学校駐輪場改築設計委託料です。学年ごとに雨漏りが生じていて、1年生の部分は改善したそうですが、今回は雨漏りも含めての改築か、詳しい内容をお伺いいたします。
教育総務課長
今回改築するのは第二中学校北側の駐輪場です。昭和55年建設で老朽化による雨漏りがあり、劣化も激しいということで、改修のための設計業務委託です。工事は令和8年度を予定しております。
吉田
場所は北側と分かりました。2・3年生の部分が雨漏りしているという話ですが、学年で何学年かは把握していないでしょうか。
教育総務課長
学校で駐輪場のどこを何年生という割り振りをしているかまでは把握しておりませんでした。
吉田
338、339ページ、10款5項4目図書館費1節報酬の司書報酬です。令和6年度当初では12名だったところ、11名と1人少なくなっている要因をお伺いいたします。
生涯学習課長
司書報酬については会計年度任用職員の分で、令和6年度当初は12名でしたが、実際、正職員との配置の関係で令和6年度は11名体制で行っており、その継続ということで令和7年度も11名で予算を計上しています。
吉田
令和6年度は正職員を含めて12名だったのですか。図書館そのものの職員の配置、体制は令和6年度と全く変わらないという理解でよろしいですか。
生涯学習課長
予算としては令和6年度現在の職員配置と同様の人数で計上しています。この11名は全員が会計年度任用職員で、図書館に6名、そして中学校5校にそれぞれ配置しているという内容です。
吉田
348、349ページ、10款5項7目文化振興費18節負担金補助及び交付金に各種大会出場助成金が計上されています。教育委員会の会議録によると、文化芸術に関し、全国大会だけでなく国際大会への出場者に対する助成も令和7年度当初予算で措置されると教育委員会定例会で説明があったようですが、まず助成金の要件についてお伺いいたします。
文化・スポーツ課長
この助成金については、文化芸術について、おっしゃったとおり従前は国際大会に関して規定がありませんでしたが、令和7年度から、スポーツと同様、国際大会に出場した場合にも交付するということで決定しています。条件については、スポーツと同じ考え方で、予選などを勝ち抜いて国際大会に出場することで、団体、個人ともに対象となります。
吉田
金額も聞きたかったのですが、国際大会の範囲としてどの程度まで認められるのかという点が一つ議論になるかと思いますので、その辺の整理はついたのか、国際大会とはどのように定義づけられての今回の予算計上かお伺いいたします。
文化・スポーツ課長
まず予算については、今のところ見込みがあるわけではありませんが、団体で出場した場合を30万円として1団体を見込み、令和6年度より30万円増額しました。
それから、国際大会の定義についてはなかなか整理が難しく、想定されるものとして、例えば一般的にテレビなどで見られるものであればピアノコンクール等があるかと思いますが、どういったものが出てくるかは全く想定しておらず、申請を受けて一つずつ検討していきたいと考えております。
(議案第5号 令和7年度名取市国民健康保険特別会計予算)
吉田
396、397ページ、1款1項1目一般被保険者国民健康保険税1節医療給付費分現年課税分です。県の推計値という説明がされているところですが、令和6年度の当初と比較すると、世帯数は増加して被保険者数は減少しています。これはあくまで当初との比較ですが、県全体で見たときもそういう傾向があるということですか。
保険年金課長
県全体の数値の増減については把握していないところです。本市の数を示されたということで把握しているところです。
吉田
例えば現時点での本市の被保険者数、世帯数の最新の数字があると思いますが、そちらと県の示している推計値との違いはどうなっているのですか。現時点で把握している本市の被保険者数、世帯数の最新の数字をお伺いしたいと思います。
保険年金課長
本市の直近の世帯数と被保険者数ですが、令和7年2月末日時点での世帯数は8,122世帯、被保険者数は1万2,226人となっております。
吉田
398、399ページ、4款1項1目保険給付費等交付金の1節普通交付金、こちらは令和6年度よりも減額となっています。こちらの県からの交付金の算定については、先ほどの納税義務者の世帯数、被保険者数、あるいは調定見込額とか、そうしたところがどのように影響しているのかをお伺いいたします。
保険年金課長
普通交付金は、医療にかかった医療給付費をお支払いするために、県から基本的に全額来るものです。具体的に申しますと、支出項目でいうと408、409ページの2款1項療養諸費、410、411ページの2款2項高額療養費、2款3項移送費、この3つの項目を支払うために全額県から交付されるということです。普通交付金の金額については、予算の算定に当たり、そもそも支払う対象としてこちらで予算を組んでいる各項の療養費が令和6年度よりトータルでは減となっているので、つまり支払うものが少なくなる見込みのため、普通交付金も減となっているという仕組みです。減となっていることの影響としましては、県で推計した被保険者数、世帯数は直接こちらの計算で使うわけではありませんので、そちらの影響は直接はありません。医療費の減というところが直接的にこちらの普通交付金の減に影響しているところです。
吉田
そうすると、県からの交付金として現時点でこの金額を示しているのは、あくまでも本市としての見込み、本市行政として組んだ歳出に基づいて、そちらの見込額ということであれば、これは仮に今後増減していったときに、県から入ってくる額は実際にそれに伴って変わってくるということになるのですよね。そうすると、先ほどの408、409ページの療養諸費の額を予測する基準というか、その予測の根拠に、こちらの納税義務者数が関わっているのですか。それとも、あくまでも前年度までの実績に基づいてということなのでしょうか。
保険年金課長
こちらの療養諸費のうち、408、409ページの2款1項1目一般被保険者療養給付費と2目一般被保険者療養費、410、411ページの2款2項高額療養費の1目一般被保険者高額療養費については、計算方法が、令和6年度中の1人当たりの平均医療給付費に、先ほどあった県から示された被保険者数の推計値1万2,149人を乗じて算出する形になりまして、ここの時点では県の推計値を使います。直接、普通交付金の計算という形ではないのですが、その前段としての歳出のところでは先ほどの県の推計値を使いますので、そういった意味での影響はあります。
吉田
400、401ページ、6款1項1目一般会計繰入金1節保険基盤安定繰入金が、令和6年度当初と比較して増となっています。令和6年度の質疑の中で県からの推計値を基にということで、その際、被保険者数の減が要因ということで、令和6年度も令和5年度に比べてやはり減額になっていましたが、今回も同じ計算式を用いてということなのでしょうか。
保険年金課長
委員おっしゃるとおりです。
吉田
令和6年度は、最新の令和7年2月4号補正で増額になっていて、それを足すと大体今回の令和7年度の当初の額になるのですが、実際には今後県との調整がいろいろ生じてきて、実際に被保険者数が減っているわけですから、年度途中で減額の補正がかかる可能性もあると思いますが、その辺の見込みはどうなっているのでしょうか。
保険年金課長
当初予算においては、県から示された計算方式でこちらの金額とさせていただきました。ただ、委員おっしゃるとおり被保険者数もどちらかといえば減少傾向が続いています。こちらの金額、計算式においても被保険者軽減世帯数なども使いますので、それに比例して減っていく可能性もあり得ます。あるいは所得がなかなか厳しいということであれば、軽減していない世帯から軽減世帯になることでの増減もあり得るかと思います。一般論的な見解になってしまいますが、被保険者数の減少傾向に伴って、こちらのほうももしかすると減る可能性はあるとは思いますが、現時点ではまだ何とも言えないところです。
吉田
400、401ページ、8款1項1目一般被保険者延滞金の1節保険税延滞金と、396、397ページの1款1項1目一般被保険者国民健康保険税の滞納繰越分は、どういう違いがあるのですか。
税務課長
保険税延滞金については、滞納税額に対して、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、その税額に法律で定められた割合を乗じて算定されるものです。
吉田
では、この保険税延滞金は、令和7年度の当初時点で件数はどのぐらいあるのでしょうか。あるいは延滞額の総額はどのぐらいでしょうか。
税務課長
延滞金については歳入見込額算出が困難なために、令和7年度予算では350万円増額ということにしておりましたが、例年ですと、当初予算にて科目設定的な意味合いで50万円を措置して、実績に応じて補正予算で対応していたところです。ただ、今回、令和7年度の要求については、過去の歳入実績と令和6年度の見込額で確実に見込める額として400万円を当初予算で要求するものです。
吉田
400、401ページ、8款1項1目一般被保険者延滞金ですが、先ほどの御答弁にあった令和6年度の科目設定的なところから、2月4号補正で350万円増となっておりました。同じような徴収の進め方などで恐らく確実に見込める額ということだと思いますが、令和7年度の徴収の仕方とか延滞金の集め方の取組について、令和6年度から引き続きという部分も含めてお伺いします。
税務課長
延滞金の取扱いについてですが、こちらは法律にのっとって算定するものですので、特に取扱いについては従前と変わることはないものです。
吉田
根拠となったのが令和6年度の実績ということなので、令和6年度なぜそのような額に大きく変わったのか。毎年度補正で対応してきたものをなぜ今回当初で大きく出たのかというところが違いだと思うのですが、その部分はどのようなお考えなのでしょうか。
財政課長
予算の編成方針として、当初予算で見込める歳入についてはでき得る限り当初予算に盛り込むという方針を掲げております。それに基づいて編成した結果ではありますが、先ほど税務課長が答弁したとおり、例年、ルールで計算した延滞金については400万円を超える金額を収入しているという状況がありますので、方針に基づいて当初から組ませていただいたということです。
吉田
396、397ページ、1款1項1目一般被保険者国民健康保険税ですが、もう1回改めて見比べてみたら、令和7年2月末の実数である8,122世帯というのは、令和5年度の当初の数字と大体同じくらいです。何かそのあたりの県の推計の方法で、令和6年度が一気に減って令和7年度が減ったままの数字で推計しているのに、実数は随分とそれよりも大きいというところについては、どういった理由があるのでしょうか。
保険年金課長
県の推計値に関して県から説明を受けているのは、被保険者数に対してはコホート方式、場所を決めてそこの移動を考慮した推計の方法を使っているということで、それ以上の説明は県からいただいていませんので、県の推計値の計算の方法、基準になっている数値等については、市では把握していないところです。
吉田
基本的な考え方とすれば、世帯数、被保険者数が増えれば、その分、こうした県からの補助金の部分も増えてくるような形に、比例するわけではなくても関連しているというか相関している部分はあると思うので、県が小さく見積もっているということは、本市に入るお金もその分小さく見積もられてしまっているのかなと思います。令和6年度の補正でも、この1款1項1目の一般被保険者国民健康保険税は減額補正になっています。でも、世帯数の部分の実数は増えているということですから、補正でも増額されていなければいけないのではないかと思います。仮に令和7年度この実数の部分が今後影響してくるというか金額に反映するとなると、大体いつ頃の段階で補正が増となってくる見込みなのでしょうか。
保険年金課長
令和7年度、改正後の税率による計算は、7月の本算定で初めて計算されるものですので、そこの時点での直近の世帯数、被保険者数を用いて計算することになりますので、そこの時点から本市の実際の世帯数、被保険者数に基づいた計算が始まっていくというところです。
(議案第8号 令和7年度名取市介護保険特別会計予算)
吉田
488、489ページ、4款1項3目任意事業の11節役務費、成年後見制度申立鑑定手数料等とあります。令和6年度は5名見込みということで、令和7年度も同額ですので恐らく同じ件数かと思いますが、この5名として見込んでいる考え方についてお伺いいたします。
介護長寿課長
委員お見込みのとおり、件数としては5名を見込んでいます。最近になりまして、そういった相談件数が少しずつですが増加傾向になっておりますし、独り暮らしの高齢者が増えていくことなども加味して、5件としたところです。
吉田
相談が増えてきているなら見込みも増えるのかなと思いますが、年間で5名で間に合うということなのでしょうか。
介護長寿課長
こちらは主に、裁判所に申立てをする際に申し立てる親族がいないために市長が申立てをするケースになる場合について予算化しているものです。そんなに件数が多くなるとは見ていないのですが、不足になることがありましたら必要に応じて補正なりをしていきたいと考えております。
吉田
488、489ページ、4款1項3目任意事業の19節扶助費、在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業についてお伺いいたします。令和6年度も見込数と1人1か月当たりの金額を伺っていますが、令和7年度、同様に見込数と月当たりの金額をお伺いいたします。
介護長寿課長
延べの件数でお話しします。見込んでいる延べ件数は1,332件となっています。そして、1人一月当たりの単価は、およそ8,700円と見込んでいるところです。
吉田
令和6年度は143人の見込みという御答弁があったような気がするのですが、もし捉えていれば見込人数もお聞きします。こうした御時世で、自宅で最期をみとりたい、みとってもらいたいという人が増えてきている中で、こうしたおむつも在宅で寝たきりの方が対象ですから、何かしらそういう傾向みたいなものを令和7年度に反映したものがあればお伺いします。
介護長寿課長
令和6年度の延べで見込んでいた件数が1,740件でした。令和6年度から令和7年度にかけて人数や件数が大分減っていますが、はっきりした要因は分からないところです。実績を基に見込みを出しているところではありますが、在宅であっても、長期で入院したり施設の入所になったりして、在宅ではなくなってしまっているところが要因となっているのではないかと捉えているところです。
(議案第10号 令和7年度名取市被災市街地復興土地区画整理事業特別会計予算)
吉田
530、531ページの歳出の1款1項1目総務管理費10節需用費、消耗品費です。具体的に予算措置されているのはこの項目だけなのですが、この消耗品費の内容をお伺いいたします。
都市開発課長
まず、こちらの事業については、歳入の2款1項1目雑入の1節清算徴収金が事業費になります。それを、徴収金に当たる割賦の送付は郵送費で措置し、残額について消耗品として事務費という形で取っているということです。
吉田
こちらの会計に基づいての年間の事務のスケジュールはどういう内容になるのかお伺いします。
都市開発課長
こちらの事業ですが、清算金に伴う対象者が2名いらっしゃいます。2名について徴収金を徴収するわけですが、今回の令和7年度で完了という形になりまして、おのおの2名に対して1回納付書を送付し、納入を受けるというのが事務です。
(議案第11号 令和7年度名取市宅地造成事業特別会計予算)
吉田
546、547ページ、歳出の1款1項1目愛島台地区造成事業費14節工事請負費の愛島台造成工事でお伺いいたします。令和6年度に測量と実施設計がされて、第2期は430戸分で、そのうち完成済み143戸という御答弁がありましたが、令和7年度についての完成の見込みをお伺いいたします。
都市開発課長
こちらの工事請負費の4億円については、令和6年度・令和7年度で債務負担行為を設定している令和7年度分の予算です。今議会において議案第22号で議決をいただいた7.8ヘクタールの産業用地の工事請負費をこちらで措置しているということです。
吉田
そうすると、その7.8ヘクタールを合わせて、全体で430戸程度建つ広さということなのですか。
都市開発課長
こちらについてはあくまでも産業用地です。住宅用地については、令和8年度の工事を予定する見込みとしております。こちらは産業用地ということで、430戸というのは住宅用地全体の計画戸数ですので、その数字とはリンクしないということです。
吉田
546、547ページ、1款1項1目愛島台地区造成事業費、今の上の12節委託料の用地測量委託料の内容についてお伺いいたします。
都市開発課長
先ほど説明しました工事請負費で造成工事をします7.8ヘクタール分の産業用地に係る確定測量ということで、工事完成後に測量を行う業務です。
(議案第12号 令和7年度名取市水道事業会計予算)
吉田
予算書27ページ、1款1項1目拡張費の30節工事請負費、上余田地区配水管布設工事等2件ということですが、もう少し詳細に場所をお伺いいたします。
水道事業所長
場所ですが、上余田字市坪地内での配水管布設工事となっております。もう1件に関しては農道愛島120号線で、令和6年度で配水管の工事をしておりましたが、舗装復旧がまだでしたので、令和7年度に舗装復旧ということで考えております。
吉田
市坪となると再開発というか区画整理の区域かと思うのですが、市坪の区域においての総延長はどのぐらいになるのでしょうか。
水道事業所長
区画整理とは関係ありません。その中での延長に関しては、124メートルを予定しております。
吉田
22ページ、1款1項2目配水及び給水費13節備消品費のスマート水道メーター対応無線端末機についてお伺いいたします。この端末は、設置から次の交換までの目安は何年間ぐらいになるのですか。
水道事業所長
端末機の交換時期は検満と合わせますので、8年が検満になりますが、本市の場合は余裕を持って7年で交換ということで考えております。
吉田
検針業務のコストで考えていきたいのですが、現在人が回っているところをこのように機械化することで、今回の増田西や愛島で4,400戸をスマート水道メーターに替えた場合に1年間で削減できる検針業務の費用はどのぐらいになるのでしょうか。
水道事業所長
試算等はまだ行ってはおりませんが、スマート水道メーターであれば機械類の計上もありますので、検針員より割高にはなっております。
(議案第13号 令和7年度名取市下水道事業会計予算)
吉田
24ページの1款2項1目支払利息及び企業債取扱諸費の48節企業債利息です。令和6年度と比べると相当な額に膨らんでおりますが、こちらの要因についてお伺いいたします。
下水道課長
償却が満了した部分の差になるわけですが、令和6年度償却満了分と令和7年度の償却開始分、その差分が今回の減額分になっております。
企業債利息については、令和6年度当初予算ベースで公共下水道1億3,521万3,000円、農業集落排水事業587万8,000円、合計1億4,109万1,000円に対し、令和7年度1億2,921万8,000円(「1億2,921万7,000円」に発言訂正あり)で、旧農業集落排水事業を含めての額では、全体として減になっております。
吉田
25ページの1款1項企業債のところでお伺いしたいのですが、支出でも企業債の償還金ということで同じぐらいの額が計上されていて、そんなに違わない額が出て入ってくるわけです。今回はその他の企業債というのも新たに措置されて起こされていますが、こちらの償還期間と利息、固定なのか変動なのか、そういった内容をお伺いします。1目建設改良費等の財源に充てるための企業債、2目その他の企業債、両方についてお願いします。
下水道課長
2目その他の企業債で計上している予算については、27ページの1款2項1目企業債償還金にある企業債元金償還金から、24ページの1款1項7目減価償却費を差し引き、長期前受金戻入を差し引いて、そもそもの不足分を対応するという形で考えておりますが、令和6年度から資本費平準化債を含んでもいいという形になりましたので、保険的にその1億5,000万円相当分を今回計上しております。ただし、それが必ず必要になるというものではなく、予備という形として計上しております。
吉田
今のは2目のその他の企業債の御説明ということで、1目の建設改良費等の財源に充てるための企業債についても、今回起こす理由と、償還期限、期間、利息をお伺いします。
下水道課長
理由としては支出の平準化を図るためのものでして、期間については30年、利率については2.0%と見込んで計上しております。
吉田
26ページの1款1項1目管渠建設費の30節工事請負費の小山調整池築造工事で、先ほど詳細の御説明がありましたが、この小山調整池は、そこにつながる小山幹線の設計などとしっかり連携させて進めていくという流れだったと思います。そちらの小山幹線の現状について、設計等がどこまで進んでいるのかお伺いします。
下水道課長
調整池から上流部分の水路整備ですが、ヒューム管1,350ミリメートルから、ボックスカルバートの900ミリメートル掛ける900ミリメートルから1,200ミリメートル掛ける1,200ミリメートルを用いまして、300メートルの整備を令和6年度の実施設計で進めております。工事に関しては、調整池が完了した後という形で進めております。
本会議
(議案第4号 令和7年度名取市一般会計予算)
吉田
14番吉田良です。ただいま議長から発言のお許しがありましたので、名和会を代表し、議案第4号 令和7年度名取市一般会計予算に対する賛成の討論を行います。
新年度の歳入のうち、市税を129億9,683万1,000円と過去最高額で見込み、総額は365億8,500万円と、大がかりな復興事業が行われていた時期を除いて最大規模となりました。しかし、決して喜んでいられるだけの状況ではなく、大幅な財源不足が解消できない状況は継続しており、市民の日常生活に目を向ければ、物価高の影響が様々な面に暗い影を落としています。市民から集めた税金が市民の福祉増進を図るために適切に使われようとしているのか、限られた予算の中で最大限に効果を発揮できる事業運営が可能かどうか、議会にはこれまで以上に高度なチェック機能が求められていると感じます。
本議案には賛成の立場ではありますが、何点かを抽出し、指摘や要望をしていきたいと思います。
まずは歳入について。疑義が生じている学校法人に対し固定資産税を課税するかどうかの判断については、明確な答弁はありませんでしたが、これまで行われてきた聞き取りや現地調査などの税務調査により、賦課するかどうかの判断の材料は整っていることと思います。新年度は、関係法令に基づき適切に徴税事務が遂行されることを求めます。
次に、歳出に移り、総務費中、交通指導隊員謝礼について。謝礼の単価を1回当たり2,500円から3,500円へ引き上げるなど変更することを評価します。さらに、出動要請に基づかない事前打合せ等が1回として計算される運用が、事前打合せを含めて1回として数えることに改められるとの説明がありました。このように変更されることで、隊員間の年間支給総額に大きな差が生じている現状も改善されることが期待されます。名取市交通指導隊は、市の交通安全を保持し、交通事故防止を図ることを目的とする、交通安全に対する深い関心と熱意を持つ方々によって構成される重要な組織です。隊員が誇りを持って業務を続けられるよう、処遇等の改善に向けた検討が継続されることを願います。
次に、民生費中、なとりっこすくハピ応援事業について。特に0歳児と3歳6か月の健康診査の対象児に絵本を贈呈することを評価します。昨今の物価上昇が家計を圧迫し、各家庭において、児童の情操、心を育てるための支出が後回しにされることが危惧されます。そうした状況の中、子育て世帯への応援の一環として絵本が贈られることは、子供が愛され保護されることや、その健やかな成長や自立を図ること、また、その保護者が家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できることを基本理念として定める、こども基本法の趣旨に沿った有効な施策と考えます。
次に、衛生費中、自然体験事業について。子供たちの自然や環境への関心と理解を深めるという趣旨には大いに賛同するものではありますが、教育委員会の職務権限に当たる内容ではないのかの疑問を覚えます。学校教育法には義務教育として行われる普通教育の目標の一つとして、学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うことが規定されています。提案されている自然体験事業は、本来は学校教育の中で行われるべきものであり、そうしたことを教育課程の中で学ぶための体制の充実を図るのが本来の行政の役割ではないでしょうか。対象者の人数を限定したり家計への負担を求めるような形を取れば、経済的に余裕のある家庭の児童しか参加できず、体験活動の実績が受験において評価されるような形で教育格差が一層固定化することへとつながりかねません。市内全ての児童生徒に平等に機会が与えられる形となるよう、次年度の見直しを求めます。
次に、農林水産業費中、田んぼダムについて。市内の農業法人等30団体及び名取土地改良区に対する説明と協議を経て田んぼダムの取組の開始にこぎ着けたことを評価します。70ヘクタールの田んぼダムが十分に機能することで、水害による被害の軽減が期待されます。農業者の本業に支障を来さないよう、今後も対話を継続しながら、田んぼダムの機能の向上に努められるよう求めます。また、ほかにも有効と思われる農地がある場合、連携の輪がさらに拡大されることは本市にとって歓迎すべきことです。協力を得られた農業者に対し、あぜ道の草刈りの作業日当を支給するなど、追加の支援についても検討されることを求めます。
次に、商工費中、観光大使について。令和6年12月、本市で初となる観光大使に宝塚歌劇団花組トップを務めた仙名彩世さんが委嘱されました。令和7年度は活動が本格化し、本市の魅力と観光情報の発信力が大きく向上することが期待されます。御本人の個人的活動が展開されることで本市のアピールという相乗効果につながるため、その人気にあやかって成果を得ようとするだけではなく、活動の場が拡大するよう、可能な範囲で支援することも必要ではないかと思います。一例としては、総務費で提案されている台湾への訪問は観光大使が担うことが望ましく、そうなれば現行の宮城県市長会よりも格段に注目を集めると思われます。本市の認知度、好感度が上がり、民間レベルでの交流が深まるよう、適材適所による運用を求めます。
次に、土木費中、立地適正化計画の策定について。これまでのまちづくりでは、人口の増加や経済の成長・拡大を前提として、土地利用の規制や都市インフラの整備が進められてきましたが、人口減少が進むことが確実であることから、持続可能なまちづくりを進めるためには、量ではなく質の向上を図り、都市をマネジメントするという新たな視点を持って取り組む必要があるとされます。そこで各市町村には、都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加え、住居や都市機能の誘導により、コンパクト・プラス・ネットワークの形成に向けた取組を推進するための立地適正化計画が求められています。本市も名取市第六次長期総合計画策定当初の予測ほどには人口が増加していない現状に鑑み、背伸びをするのではなく現実に即したまちづくり、量より質を重視した課題解決につながる計画の策定を願います。
次に、消防費中、消防事務及び救急救助事務について。令和7年4月1日からの消防署手倉田出張所への救急車の配備を評価します。令和4年2月時点では、救急車の配備計画について、移転改築した消防署手倉田出張所が業務を開始してから、改めて消防車を含めた出動体制や管轄区域を十分に検討した上で配備を検討したいとされていましたが、その後の議会からの強い要請により職員定数条例が改正され、令和6年4月1日から消防職員数が109名に引き上げられたことで、令和7年度からの配備が実現することとなりました。それに加え、救急デジタル無線システム更新による通信指令機能の強化、また、バスケット付ブームを搭載した水槽付消防ポンプ自動車への更新と、市内の消防機能強化及び適正配置への効果が期待されます。
次に、教育費中、芸術・文化振興事業について。新たに文化芸術賞顕彰が設けられたことと、各種大会出場助成金が文化芸術分野の国際大会にも拡大されたことを評価します。顕彰については、多くの自治体がスポーツ分野のみに設けており、文化芸術分野における顕彰が行われるのは非常に珍しい先進的な取組と言えるかと思います。文化芸術分野はスポーツ分野よりも多岐にわたる種目があり、どこまでを顕彰の対象とするのかの基準を設けるのは非常に難しかったのではないかと思料します。スポーツ分野においても、eスポーツやアーバンスポーツなど、定義は時代の流れとともに変化しています。こうしたものも取りこぼさないことを願います。そして、スポーツと文化芸術のさらなる振興と、それらにおける市民の活躍が一層可視化されることで、多くの市民が文化・スポーツを実践する機会の拡大につながることを期待します。
令和7年度が本市にとってさらなる飛躍の年度となることを願い、私から賛成の討論を終わります。
(議案第43号 令和7年度名取市一般会計補正予算)
吉田
10、11ページ、歳出2款1項6目企画費、10款6項2目体育振興費、なとりスーパーキッズ育成事業委託料について伺います。今回の判決によって、事業そのものの市長部局による管理執行、それから、業務委託契約の締結が違法であるということが認められましたが、市ではほかにも様々な事業を行っている中で、教育に関することに当たるのかどうかという線引きがなかなか難しい事業があろうかと思います。先ほどの討論でも一部そうしたものについて指摘をさせていただきましたが、現時点でそのあたりをどのように整理されているのか伺います。
総務部長
個別に全ての事業について再度見直してはいませんが、先ほど議員から御指摘いただいた点も踏まえて、今後、教育に関することなのかといった疑義が生じているようなものがあった場合には個別に検討して対応したいと考えています。
吉田
ここにいらっしゃる皆さん全員御存じだと思うので、隠す必要もないので申し上げますが、私がこの訴訟の原告です。弁護士をつけずに本人のみで争ってきました。私のような者からしても、法律等の条文を見て、明らかにこれは教育、そしてスポーツに関することであると見えるもので、この議場でも、なとりスーパーキッズ育成事業が予算化されたときに予算執行留保を求める附帯決議を提案いたしました。その一番最初には、住民の理解を得ることが留保を解くための条件として盛り込ませていただいた経緯があります。これほどの、誰がどう見てもスポーツに関すること、教育に関することと分かるようなことであれば、もっと市民の意見を聞いていれば、まずいのではないのかと。そして、そこで一旦立ち止まって、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条に基づく条例をしっかり整備するなど必要な対応を取ってからであれば、この事業がもっと軌道に乗ってうまくいっていたかもしれない。そのことを思うと、全然検討する時間が足りていなかったのではないか。それが一番の要因だと思います。
教育委員会としても、この事業を見て、これは教育ではないのかなという認識は持たれなかったのでしょうか。
教育長
教育委員会が所管する教育、文化、スポーツ、生涯教育、それらに関わる様々な事業がありますが、一つスポーツを取ってみても、いろいろなスポーツに関する事業があります。スポーツだけを狙いとする事業というのは少ないと思います。ほかにも様々な狙いを持ったものがあり、線引きはなかなか難しいのではないかなと感じているところです。
今回のなとりスーパーキッズ育成事業については、先ほど市長の提案理由説明にもありましたように、教育委員会が所管すべきという判断が下されたということで、教育委員会として関わっていくという認識は持っていますが、一概にスポーツが含まれるものが全て教育委員会が所管すべきかというと、なかなかその辺の判断は難しいのではないかと感じているところです。