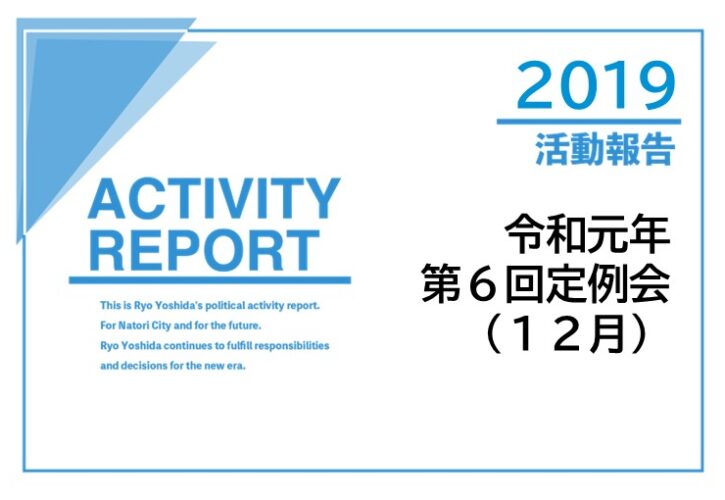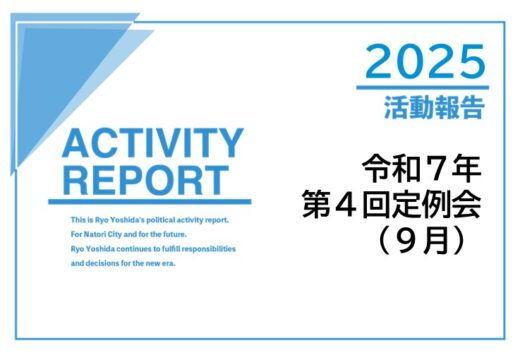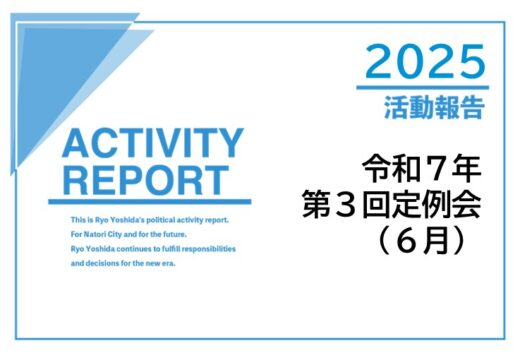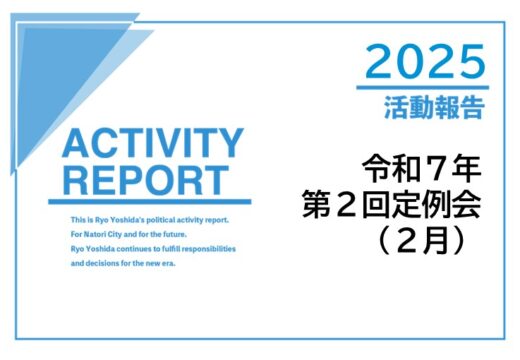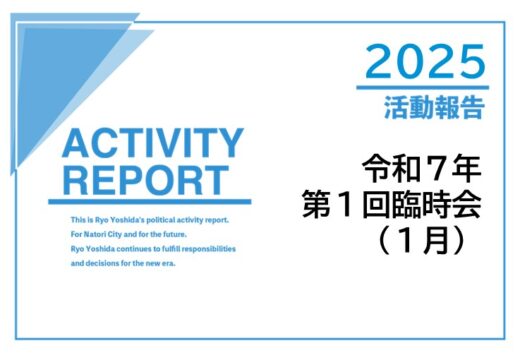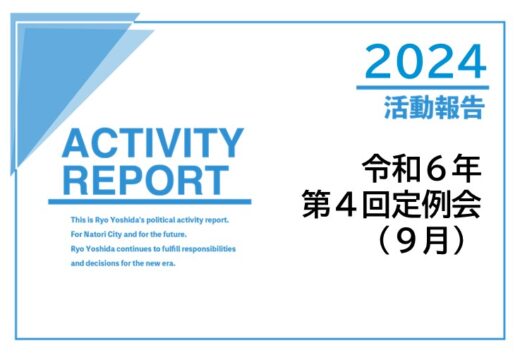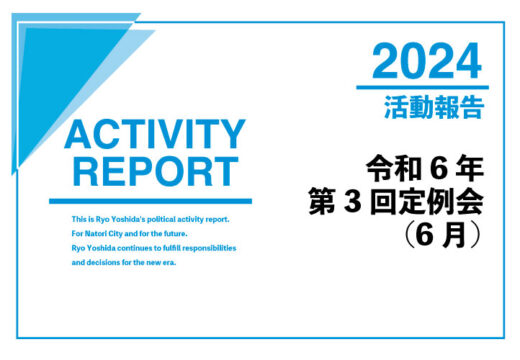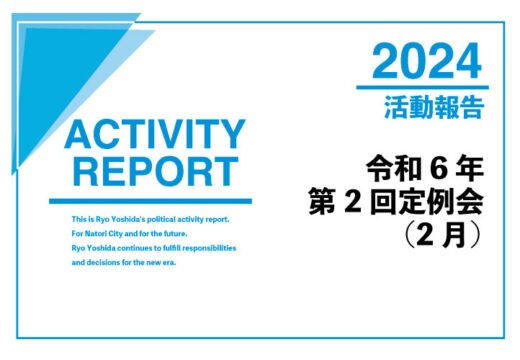本会議
(議案第106号 名取市都市計画税条例の一部を改正する条例)
吉田
被災市街地復興土地区画整理の区域内は、まだ市街化区域と市街化調整区域が混在しているという説明がありました。この区域で全体が市街化区域に編入される時期の見込みはどのようになっているのでしょうか。
建設部長
市街化区域への編入については、宮城県とも調整し、令和3年5月を予定しております。
吉田
令和3年5月に予定どおり完了したとして、この都市計画税を課さない期間は令和何年度までになるのですか。
税務課長
令和3年5月ということが明確になれば、令和4年の賦課期日、1月1日には編入されていることになりますので、結果的には令和3年度までは課税免除するということになります。
吉田
令和3年度中に課税することが実質できないとわかっていて、今回、令和元年度を令和2年度に改めるということで1年間だけ延ばしたことについては、何か理由があるのでしょうか。
税務課長
建設部長が予定として令和3年5月と説明申し上げましたが、その時期が明らかではないというところがあります。来る令和2年1月1日時点では編入されないと見込めますが、令和3年5月というのはその時期が不明確というところがありましたので、結果的には課税免除を1年間延長させていただくと。その後、時期が明らかになるところまで、仮にまた1年延ばすということもあり得ます。先ほどの令和3年5月というところが明確であれば今回の条例改正において2カ年の延長も起こり得ますが、当方としては、それが明らかではないことをもって1年間の延長をお願いするものです。
吉田
明確でないのはそのとおりだと思います。ただ、市としての考え方の中で、市街化区域へ全域が編入される時期を少しでも早めて、令和3年度から課税できるようにしたいという市の意向はないのでしょうか。
総務部長
本市としては、その時期によって適正に課税をするというスタンスは変わっておりませんが、建設部長が申し上げたとおり、県の都市計画審議会という手続を経なければいけないということで、その調整がありますので、そのことについては見守らなければいけないという立場であるということです。
(議案第107号 名取市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例)
吉田
少し細かいことになりますが、審査委員会の委員の任期はどのぐらいの期間と定める予定なのでしょうか。
社会福祉課長
これはまだ内部での検討の段階ですので、具体の年数についてはこの場ではなかなか申し上げにくいところですが、複数年と考えております。
吉田
その複数年の任期中に災害弔慰金や災害見舞金等が発生するような事案がないこともあろうかと思います。この委員の方たちには報酬等をお支払いするかと思いますが、それは任期に応じてお支払いするのか、それとも会議が開かれた際に日当のような形でお支払いするのか、そこの部分をお伺いします。
社会福祉課長
今回御提案している改正条例の中にも含んでいるところですが、日額という形で、そのような事案が発生したときにお支払いするという考え方でおります。
(議案第115号 指定管理者の指定)
吉田
管理の期間を5年間に設定したということですが、今回の更新前は3年間でしたが、3年から5年に今回変えた理由についてお伺いいたします。
男女共同・市民参画推進室長
先ほど補足説明で総務部長が申し上げたように、3年間の指定管理の前には業務委託という形で実質的な運営の部分を担っていただいておりました。そういった実績を鑑みて、当初は3年間の指定管理期間でお願いしたところです。通常、指定管理者の指定についてこのように業務委託の後に指定管理を行ったような施設については、その3年間の業務実績を見ながら、次は5年間とするのが名取市としては通例の取り扱いになっております。5年とする理由については特に制度上の制約があるわけではありませんが、団体の運用の安定といったようなことも考慮して、期間を5年として今回お願いするものです。
吉田
5年間という長い期間の中で、いろいろと社会情勢の変化などが生じることがあろうかと思います。この指定管理料なども今回5年間の債務負担行為でということでしたが、その社会情勢の変化等によって5年間の間に管理料が変更される可能性、それができるかどうかということについて確認させてください。
男女共同・市民参画推進室長
指定管理料については、今回の補正予算の中で債務負担行為ということで5年間をお願いしているところです。指定管理料の支払いについては、年度ごとの協定を結ぶ中で、それを上限として指定管理料をお互いに取り決めをすることにしております。
先ほど議員から御指摘のあったような大きな社会情勢の変化等に伴って指定管理料を変更するようなことが生じた場合は、予算措置をした上で、この年度協定の中で変更していくことになろうかと思います。実際、消費税の増税等に伴って指定管理料の増額をしておりますので、そのような変化があった場合には適切に処理をしていきたいと考えております。
(議案第116号 指定管理者の指定)
吉田
大泉議員への答弁の中で、事務局体制を今の閖上さいかい市場の建物から移っていただくということでした。名取市観光物産協会の事務局というか拠点をどこにするかということは、これまで幾つか経緯があってなかなか安定してこなかった中で、新しい施設がそうした拠点になることは組織として大変ありがたいことであろうかと思います。ただ、その一方で、やはり外部の団体、組織である以上は、このように一つの市の施設を借りて、そこに事務局を置くとなった際に、逆にそれは市に対して賃貸料のようなものを支払うべき立場になってしまうのではないかと思います。そのあたりはどのように処理をされるのでしょうか。
復興調整課長
震災伝承業務に支障のない範囲あるいは支障のない時間帯に、そこで名取市観光物産協会の業務をとっていただくということで、あくまでも震災復興伝承館の業務が主でありまして、それに支障のない範囲で行っていただくということで考えております。
吉田
随分都合のいい考え方なのではないかと捉えられます。名取市観光物産協会に対しては、私は大変お世話になっておりますし、評価をしているわけですが、ただ、公平性という観点から見たときに、特定の団体が、施設を管理するという名目で、その中で自分たちの別の事業に対する業務も邪魔にならない範囲でできるというのは、ちょっとこれはいかがかなという気がします。
それで、今申し上げたいのは、震災復興伝承館にこうして団体の本部を置くことになろうかと思いますが、契約書に団体の名前や本部の住所も書かなければいけないと思います。その際には、名取市観光物産協会としては、本部の住所も震災復興伝承館として、管理するのも震災復興伝承館ということで、本部の場所と管理する場所、両方同じ住所をそこに明記することになるのですか。
復興調整課長
団体の定款などにおける所在地とか、そういった手続は今後になろうかと思います。今のところは事務局機能を震災復興伝承館に移転するのであろうという判断で、定款上の移転などの手続については承知をしていない状況です。
吉田
今後のことが見通せないというのはもちろんわかります。ただ、1つ、指定管理者制度の市の運用の中で確認したいと思います。幾つかの施設で指定管理者制度を行っていると思いますが、その指定管理者の主たる事務所が管理している施設と同一になっているケースは、何件中、何件ですか。
副市長
漏れたら申しわけありませんが、現在、名取市文化会館、市民体育館において、指定管理者が内部に事務所を構えていると捉えております。市民体育館については、名取市体育協会の本拠地をどこに置いているか確認しなければなりませんが、名取市文化振興財団については名取市文化会館に置いています。ただ、それは本来の指定管理の業務に加えて、名取市文化振興財団が自主事業でいろいろな事業を展開しますので、そこに置いたほうがより効果的な運営ができるのではないかという判断もありますし、市が名取市文化振興財団の出資者として全て出資しているという公益性もありますので、そういう取り扱いをしているということもあります。一件一件こういう場合はこうするという取り決めはありませんが、そういう全体の総合的な判断から行っております。もう1件、名取駅コミュニティプラザの指定管理者である名取まちづくり株式会社もそうなっているかと思います。そこも本拠地は確認しなければいけませんが、民間の場合は民間の事業所があって指定管理を受けて業務を行っておりますが、公益性など総合的な判断で、先ほど申し上げた名取市文化振興財団のようなケースもありますので、その中に置くのが全てだめだという判断はしておりません。
吉田
何でもかんでも事務所を置いてはいけないということではありませんが、今、副市長が御紹介された施設は、その施設の中でほぼ指定管理者の行う事務が完了するものかと思います。名取市文化振興財団でしたら名取市文化会館の中での事業ということで、名取市文化振興財団が外でふるさと納税の返礼品などを扱っているわけではないのです。ですから、これはやはりその施設の中で行われるような場合はもちろんその施設に事務所を置くというのが、管理していく上で、そして運営していく上でプラスになるというか一番やりやすいやり方だということは理解します。
ただ、今回のこのケースにおいては、震災復興伝承館の指定管理という枠だけではなくて、名取市観光物産協会はそれ以外にもいろいろな事務を行っています。そのそれ以外の部分の事務もこの建物の中で行うことに対する妥当性が問われていると思うのです。副市長の説明ですと、この名取市観光物産協会が閖上さいかい市場を出た後の事務所についてはまだ明らかではない、今の時点ではまだ見通せないということでしたが、この指定管理をお願いするとなれば、やはり私は、まず主たる事務所はここに置くということがはっきりわかった上でなければ、それ以外の事務はそちらで行っていただき、震災復興伝承館の事業については震災復興伝承館の中でやっていただくというようなすみ分けができないと思います。このまま名取市観光物産協会の事務所が次にどこに移るかが全く見通せない中で指定管理者を指定してもいいと認識されているのですか。
副市長
まだはっきりしない部分がある中で明確な回答はできませんが、ただいまの御意見等も踏まえて、要するに団体が自立するかどうかという問題だと思いますが、一気に自立まで早急にできるかどうかも含めていろいろな角度から検討せざるを得ないと思っております。
(議会案第3号 小・中学校全学年での少人数学級実施並びに特別支援学級の基準を8名から6名にすることを求める意見書)
吉田
少人数学級については、児童生徒に対して目の行き届く教育にしていくという意味では私も重要な課題だと思っておりますが、この案文の中で少しお聞きしたいところがあります。本文の下から4行目ですが、「東北6県の中では本県が一番遅れた状態になっています」とあります。この東北6県の中でのほかの県との比較についてもう少し具体的に教えていただければと思います。
大沼宗彦議員
東北6県を全部網羅して調べているわけではありませんが、ちなみに紹介しますと、この特別支援学級の基準を8名から6名にするというところですが、きめ細かな教育をしていくために、この子は情緒障害である、この子は多動性障害であると決めることが難しい複合的な障害があることをまず認識していただければと思います。ちなみに、山形県では、平成25年に8名から6名にしています。仙台市では、30人学級にして支援員や時間講師を置いたりして対応しています。やはり一人一人いろいろな個性と障害の特徴がありますので、先生が一人の子供につきっきりになって別の子供が置き去りにされることをなくすためには、やはり子供の人数を少なくして、先生方が目の行き届いた教育をしていくことが重要なことではないかと思います。
吉田
ここに「東北6県の中では本県が一番遅れた状態」と明記されていて、そしてこれを県知事に届けるのですよね。あなたの県はおくれていますよと県知事に言って指摘をするのに際し、ほかの自治体の状況を把握できていないというのはどういうことなのでしょうか。それはやはり知事に対して、私は少し失礼なのではないかと思います。少なくとも宮城県はほかの5県に比べてこういうところがおくれているということをはっきりと根拠として示すことができなければ、ただこのように「遅れた状態になっています」では、ただのイメージというか、ぼんやりとして中身が全く見えない状態です。これはぜひ委員会の中でそうしたことも深く議論していただきたいと思います。
また、この8名から6名という特別支援学級の編制標準についてですが、私は大変不勉強で特別支援学級の編制の基準がわからないのですが、現在、先生方の手が行き届かない8名から7名で実際に教室を運営している学級が県内にどのぐらいあるかについてはお調べでしょうか。
大沼宗彦議員
済みません、県内がどういう状態なのかということまでは捉えていません。
一般質問
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長より発言のお許しをいただきましたので、事前の通告に従い一般質問を行います。
初めに、大項目1 災害に強いまちづくりについてお伺いいたします。
まずは、台風第19号の被害に遭われた皆様に対し、謹んでお見舞いを申し上げます。台風第19号は、日本においては観測史上最大級の台風であったと言われております。全国各地で河川氾濫や崖崩れなどが発生し、幾つものとうとい命が奪われ、多くの家屋が被害を受けました。
この規模の台風は、これまでであれば50年に一度とか、100年に一度というレベルのものであったと思われます。しかし、昨今、台風の規模が巨大化しております。一説には、地球温暖化が原因ではないかと言われております。台風第19号と同規模の台風は、来年もこの地を襲うかもしれません。できることから対策をとっていく必要があります。
そして、今回はまず道路の冠水についてから取り上げさせていただきます。
小項目1 冠水しやすい公道の把握及び冠水対策の現状を市長にお伺いいたします。
市長
市内の冠水しやすい公道については、過去の大雨から大手町の植松田高線、増田四丁目の市道沢目1号線、三日町熊野堂線のアンダーパスなど、20数カ所について把握をしております。 冠水対策としまして、今年度は7カ所において側溝や排水管の敷設、土砂や落ち葉詰まり防止などの対策を行っております。また、短時間の豪雨で冠水する公道は、通過車両の安全を確保するため、通行どめの対策を行っております。
市街地の冠水対策としましては、齋 浩美議員の一般質問でも御答弁申し上げましたが、公共下水道区域内において平成9年8月から、管渠や調整池の整備を行っております。
現在は、平成30年3月に策定しました既成市街地における名取市雨水対策基本計画に基づき、雨水幹線管渠等の整備や、流下能力不足箇所の小規模管路の改修を進めているところです。
吉田
非常に多くの箇所で道路の冠水が起きておりましたが、その原因としては、やはり内水氾濫であったと見なされるかと思います。国土交通省では、平成21年に内水ハザードマップ作成の手引というものを示しております。この手引では、内水ハザードマップを作成するようにということが書かれておりますが、本市ではこの内水ハザードマップ作成に着手されているのか、現時点での対応を伺います。
下水道課長
本市の雨水対策基本計画を作成するに当たりまして、既成市街地における降雨強度によるシミュレーション、いわゆる内水ハザードマップは作成しておりますが、市内全域にわたってのものについては、下水道課では作成しておりません。
吉田
既成市街地のほうはもう作成されているということでした。ということは、こちらは公開もされていて、どなたでも見ることができる状態であるということでよろしいですか。
下水道課長
開示については、基本計画を作成するに当たって既成市街地というある限定した地域での作成に当たっておりまして、全体的な関係は防災安全課のほうでもいろいろ調整を図っているということなので、現在は公開しておりませんが、条件をつけて既成市街地ということで、今後開示に向けて調整していきます。
市長
少し複雑なので補足します。
雨水対策基本計画の作成時に、10年、30年の確率で既成市街地の浸水シミュレーションは行っております。これを今公開できるように、既成市街地という条件つきで行っていくという考え方なのですが、今国から水防法上で求められているのは、想定最大規模降雨における想定です。既成市街地等に加えて、市街化調整区域を含めた市内全域の想定最大規模降雨における想定のもとで、内水浸水想定区域図と洪水ハザードマップを作成しなければなりません。
この件につきましては、専門的な知見によるデータの解析、分析も含めて取り入れていかなければいけないということから、時間、労力、費用というようなこともありまして、少し時間を要するということです。
吉田
冠水しやすい場所がどこかということをはっきり示していくためには、公開が必要だと思いますので、今後そのまま続けていただきたいと思います。
そして、もう一つ御提案がありますが、増田川への排水口が低い位置にあるために、増田川の水位が上がることによって雨水の行き場がなくなってしまうというケースが今回もあったと思います。そうした部分の道路の冠水を防ぐために、市街地においていろいろな対策をこれまでもとってきたということですが、排水ポンプを市街地に設置することも必要ではないかという部分もあります。そういった検討について、お考えはいかがでしょうか。
市長
増田川について言えば、9・22の水害がありまして、それによって改修がされ、今回そのようなこともあって決壊にまで至らなかった部分もあると思っております。ただ、実際には2.5メートルの危険水位を超え、最終的には3メートルのハイウオーターも超えた状態でありまして、そういう状況の中でポンプを使っても何しても、結局下のほうに流していけないという状態が一緒になりますので、そういった方法ではない形も含めて、どういう対策があるかということは講じていかなければいけないと思っております。
吉田
さまざまな対策の仕方があると思いますので、今後御検討を進めていただきたいと思います。
次に移ります。指定避難所の場所についてです。
このたびの台風は、愛島小学校のように指定避難所さえも駐車場が冠水するほどの豪雨をもたらしました。安全であるはずの避難所が危険にさらされてしまったわけです。避難所の設置場所について、再検討する必要が生じているところもあろうかと思います。
そこで考慮していただきたいのが、道路が冠水することで避難所までたどり着くことが困難になるケースがあるということです。以前から指摘されておりますように、増田西地区、特に大手町や八幡地区の住民にとっては、県道仙台館腰線から増田西小学校へつながる場所が冠水することによって、増田西小学校に避難することが難しくなります。大手町の五丁目には市民活動支援センターもあります。こちらも市の施設です。避難所に指定してほしいという声が、一部の住民から聞こえてきております。
そこで、小項目2 市民活動支援センターを避難所に指定すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
名取市市民活動支援センターについては、大手町五丁目にあり、増田川が近隣していることから、大雨のときに避難所に向かう途中で被災する可能性があり、避難所開設には一定の注意が必要な施設となっております。
しかしながら、建物が2階建てであり、2階部分に避難が可能な会議室を有することから、今後、災害リスクや避難所としての運用方法など、避難所として指定が可能かどうかさらに検討し、可能であれば指定をしていきたいと考えております。
吉田
安全を最大限に配慮しながら、検討を進めていただきたいと思います。
次に移ります。ペットを飼っている人のための避難についてです。
指定避難所へのペットの同伴は、現在市内では認められておりません。避難所はさまざまな方に利用されるため、ペットが持ち込まれることによるトラブルの発生を防ぐことが理由であろうと考えられます。しかし、ペットを家に残して避難することはできないと考える方がいることも事実です。不特定多数の方が利用する避難所にペットを同伴することができないのであれば、それらとは別に、ペット同伴者のための避難所を設置することも検討課題ではないかと思います。
小項目3 災害時に避難所が設置された際、ペットの同伴を可能とする避難所を設置すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
避難所においてペットの持ち込みを可能とするかどうかについては、ペットアレルギーを有している方の有無や、鳴き声を不快に感じる方の有無、ペット同行家族向けの専用スペースを確保できるかどうかなど、そのときの避難所の状況により判断されるものと考えており、あらかじめ持ち込みを可能とする避難所として避難所を開設することについては、難しいものと捉えております。
一方で、現在では、ペットを家族として考えるひとり暮らしの高齢者の方がいるなど、ペットをめぐる意識も変わってきており、ペットの持ち込みについて極力対応するよう、避難所配置職員向け研修でも説明をしているところです。
吉田
私は、現在の避難所体制をペット同伴可にしてほしいということを申し上げているのではなくて、現在の避難所体制は現在のまま、そこにプラスしてペットを同伴できるものを市内で1つでも設置することができれば、ということを提案させていただいております。
それで、環境省で策定した「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」というものに、こうあります。災害時のペットの同行避難を推進することは、動物愛護の観点のみならず、放浪動物による人への危害防止や、生活環境保全の観点からも必要な課題である。避難をする際には、飼い主はペットと一緒に避難する同行避難が原則であると記されております。
このように策定されたガイドラインがありますが、本市ではペットの避難所がないという状況です。そのことについて、市長は率直にどのように感じられるでしょうか。
市長
先ほども申し上げたとおり、できる限りペット連れの方も受け入れられるような体制については考えていきたいと思っておりますが、例えば先ほど御提言あった1カ所ということになりますと、市内の端から来るとなると最大やはり20分くらいはかかると思うのです。そういう中で、そういった場所を仮に中心部に持ってこられたとしても、そういった時間的なこと、刻一刻を争う中でそういうことが本当に可能かどうか、できればやはり身近なところに逃げたいと思うのが心理ではないかと思います。 いずれ課題を整理して考えていかなければいけないことだろうと思います。
吉田
市長が今おっしゃったのは、市内に何十カ所もあるものを1つにしろと、減らせというのだったらそういう問題が出てきますが、ゼロのものを1にするときに、どこから文句が出てくるのでしょうか。私はそうは思いません。まずは1カ所でもいいから、市内1カ所でもいいから設置するべきではないかということです。
ここでもう一つ例がありますが、西日本豪雨の被害を受けて、平成30年7月6日、岡山県総社市でペット同伴避難所を設置したという例があります。そこで設置された避難所は、市の職員だけではなくて、避難してきた飼い主の方々も協力的にいろいろ役割を負いながら、避難所の運営に当たられたと伺っております。このような飼い主の方にも一定の努力義務を負っていただくというような、そういう形で安全で清潔な避難所運営が行われるようなルールづくりを進めるべきと思いますが、いかがお考えでしょうか。
市長
当然といいますか、前提として自助的なことも含めて、災害対策については進めていきたいと思っております。何度も申し上げますが、ペット同伴の方についてもできる限り受け入れをできるような環境整備をしていきたいとは思っておりますが、現在、そもそも災害種別の避難所が現状のままで百点満点だと思っておりませんので、災害種別に避難所がまずどこにあるべきなのか。エリアによっては冠水するときに避難する場所が正直うまく見つかっていないところもありますので、そういった場所についてどうするかということも含めて、まず避難所についてどうあるべきかということを全市を見ながら、改めて決めていきたいと思っています。
そうした中で、仮に適切な場所があって、そういった箇所を設けることが可能であれば、それは場所の問題だけではなくて、受け入れる職員の体制の問題であるとか、近隣の理解も含めて総合的に判断していくことになると思っております。
吉田
わかりました。では、次に移ります。
樽水ダムの事前放流実施体制についてです。
樽水ダムは、平成6年の9・22豪雨の際に緊急放流を行ったことで、流域に多大な被害を及ぼしたという歴史があります。このたび台風第19号が襲来した10月13日の午前2時33分、緊急放流3時間前の通知が市に伝えられたとのことをお伺いしました。豪雨がもう少し長く続いていたら、9・22の二の舞となるところであったと思われます。
小項目4 樽水ダムの事前放流実施体制について、協議する場の設置を宮城県に求めるべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
ダムについては利水の機能を有しており、一定の貯水が必要であるという面を有しておりますが、一方でダムの事前放流については、大雨時のダムの貯水量を高めることになり、河川氾濫を防ぐ有効な手段であると考えております。
事前放流を含めたダムの実施体制等については、市として既に県に改善の働きかけをしており、協議する場の設置についても、必要に応じて県に求めていきたいと考えております。
吉田
市と県だけの二者の話ではなくて、いろいろな方に話が必要になってきますので、丁寧に進めていただくべきかと思いますが、現状これまでの宮城県に対する要望の経緯について確認させてください。
市長
ダムについては、緊急放流をする際に、一定のルールのもと数時間前にファクスが流れてきたりしますが、今回は本当に非常に短時間に水位が上がったりということで、緊急放流までには至りませんでしたが、それに近い状態まで来ていたということです。市としては、少なくともダム事務所と電話で、ホットラインでやりとりできるような形にしてほしいという要望はしているところです。
また、増田川、川内沢川の総合整備促進協力会で要望活動をする中で、先ほど来申し上げてきている川内沢川の越水の状況であるとか、具体的な応急的な措置であるとか、そうしたことも含めた中で、ダムについてもお話をさせていただいているところです。
吉田
おっしゃったのは、緊急放流の宮城県に対する要望ではないかと思うのですが、事前放流に対してはこれまで要望してきたということではなかったですか。そちらのことで、この間の経緯で何かありましたらお知らせいただきたいと思います。
防災安全課長
本市としては、仙台地方ダム情報伝達連絡会という会議がありまして、こちらの会議において樽水ダムについて、台風が来るなど降雨が予想される前に事前に水位を下げることはできないかということで、こちらからお話をしております。ただ、県からは、国の方向性が示されていないということと、国の動向に注意しながら今後対応を検討していきたいという回答をいただいているところです。
吉田
11月26日に国土交通省や経済産業省など関係省庁の局長などで構成される、既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議の初会合が開かれました。来年の夏までに、事前放流の導入を目指す方針案が示されたと伺っております。これで県も動きやすくなったと思いますので、市からもさらにもう一押し、協議の場を求めるための働きかけをしていただきたいと思います。何とぞお願いいたします。
では、次に移ります。今度は住民相互の情報共有について取り上げます。
災害の被害を最小限に食いとめるために最も必要なのは、正確な情報を早く知ることではないかと思います。住民の誰もが情報を必要とする立場であるのと同時に、いざ被害が自分の身に降りかかったとき、情報を発信しなければならない立場へと変わります。
そして、情報を広く、また即時に発信できるインターネットは、使いこなせば非常に便利なものですが、本市ではまだ限定的な使われ方しかされていないと私は捉えております。どこでもインターネットに接続できる携帯端末の普及率もかなり上がってきており、高齢者でも使いやすい機能を備えた機種もよく売れていると聞いております。端末上で作動するアプリケーションも、さまざまなものが開発されております。住民が相互に災害情報を共有できるアプリケーションはないものかと調べましたところ、既に商品化されているものがあるということを確認しました。ただ、内容はすぐれておりますが、利用登録にそれなりの額の負担が必要という仕組みになっております。
そこで、小項目5 災害安否確認と避難要支援者救済機能を備えた電子回覧板アプリを町内会等が導入する際の経費の補助制度を創設すべきについて、市長の御見解をお伺いします。
市長
電子回覧板は、周知したい情報の一斉配信ができ、町内会役員などにかかる負担の軽減や情報の遅延防止など、現状の紙媒体による回覧方式の短所を克服できる機能を持つシステムであると認識をしております。
一方で、災害時の安否確認機能や避難要支援者救済機能が装備されている電子回覧板の災害時の活用については、町内会長などの役員において通常の電子回覧板機能を緊急時のモードに切りかえる判断を行う責任や、安否確認のために必要な町内会等の構成員の氏名を初めとする個人情報を、個人情報取扱事業者の立場で安全に管理する義務を負うなど、町内会役員に係る負荷の問題を初め、携帯端末の操作に不安を抱える方への対応、町内会の予算を充てつつシステムの維持管理費を負担し続ける問題など、整理すべき課題もあるものと捉えております。
このようなことから、まずはシステムを導入している先進的な自治体や導入団体の取り組みについて、情報の把握を行いつつ、補助制度のあり方を含めて調査研究を行っていきたいと考えております。
吉田
これも新しいものを導入することに関しては、やはりいろいろな不安がつきまとうかと思いますが、実際に石川県の小松市などでもう既に導入の実績がありますので、調査をしていただきたい。あるいは、まずモデル地区をどこかの町内会につくってもらう、募集をするという形で、まず実験的な実施を行ってみてはどうかと思うのですが、そのようなことについての考え方は、市長いかがでしょうか。
市長
課題についてある程度整理ができれば、御提言いただいた内容について否定をするものではありません。もう少し時間をかけて調査研究をしたいというところが本音です。
吉田
ぜひ前向きに導入に向けての検討を進めていただきたいと思います。
次に移ります。行政による被害情報の発信についてです。
議員協議会やさきの臨時会の一般市政報告に対する質疑でも取り上げてきました。災害時における本市の情報発信については、SNSの活用が重要な課題であると私は認識しております。住民にとって、道路の冠水や崖崩れなどは現地へ行かなけれは発生そのものがわかりません。それが現在の体制です。しかし、ツイッターで、なとらじが今回台風第19号の被害の際に、いろいろと画像を発信しておりました。また、ユーチューブでも、匿名のアカウントで市内の被害状況を動画で発信していたという情報もあります。現在も幾つか閲覧できる状態であることを確認しております。
申すまでもなく、行政は住民のためにある存在です。行政が知り得た情報を一つでも多く、少しでも早く住民に知らせることは、少なくとも災害時には重要な課題であると考えます。携帯端末とインターネットを活用すれば、こうした課題を改善することが可能であると考えます。
そこで、小項目6 被害の発生状況を素早く周知するため、SNSによる情報発信力を強化すべきに対する御見解を、市長にお伺いします。
市長
現在、市としての防災情報の伝達については、防災行政無線、防災ラジオ、広報車、市ホームページ、エリアメール、なとり防災メール、防災ツイッター、フェイスブック、テレビのdボタンを活用した防災情報、テレビのテロップ情報、電話での問い合わせ対応を実施しており、台風第19号の対応として、新しく自主防災組織を通じた情報伝達を実施しているところです。
今後は、被害が収束した場合の発信情報の更新のあり方など課題を整理した上で、ツイッターへの災害発生現場写真や動画の掲載など、情報発信力の強化に取り組んでいきたいと考えております。
吉田
昨日の齋 浩美議員の質問の際に、そのひな形をつくって発信するというようなお話がありましたが、このひな形というのは本当に必要なものかどうか、私は少し疑問なのですね。職員の方は、採用試験の際にきちんと日本語ができて、そういう力を持っている方を採用しているわけなので、素早く情報発信してもらうためには、そういうひな形に必ず照らし合わせて、どこに何を埋め込んでみたいなことをしている時間はないと思うのです。ただ写真を上げるだけでも全然違うと思います。やはり迅速性に一番重要性を置いていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
市長
情報発信に当たりましては、今回の台風等に関する検証会議においても、迅速性のほかに正確性、そしてわかりやすさを兼ね備えた形で情報発信をしなければいけないと考えております。冠水などについては、本当にあっという間に冠水してしまうこともあることから、写真や動画を活用した形でツイッターで投げかけていくことも必要だろうと思っておりますし、同時に防災メール等で発信していく際には、やはりある程度の文書のひな形があって、その中にはめ込むことで、より早く処理ができると捉えているところです。
吉田
発信方法ごとにということであろうと思いますので、そのあたりは迅速性、そしておっしゃったように正確性も、災害のときにはデマ情報が出回るという実例もありまして、そういうデマを流させないためには、やはり行政が正確な情報をいち早く伝えることが大事かと思いますので、そこも含めての御検討を今後も重ねていただきたいとお願いします。
次の質問事項に移ります。
大項目2 学校給食費の段階的無償化についてです。
同じ質問事項で、昨日大久保議員も一般質問されていました。重複する部分もあるかもしれませんが、改めて確認させていただきます。
小項目1 選挙公約とした理由について、市長にお伺いいたします。
市長
学校給食費の段階的無償化を通して、子育て世代の経済的負担を軽減するとともに、市内外に対し、名取市が子育て・教育に力を入れて取り組んでいるという強いメッセージを発信できるものと考え、子育て・教育先進都市の実現を目指すものとして、選挙公約に掲げたものです。
学校給食費の段階的無償化については、県内の市部では初めての取り組みであり、この取り組みを通して真に名取市に住み続けたい、住んでみたいと思える愛されるふるさと名取をつくっていきたいと考えております。
吉田
子育て・教育先進都市というものを何回かお聞きしておりますが、こちらが実現できるかできないかということはまた別として、その全体的な都市のイメージは、市長どのようにお持ちなのか、それをお話しいただきたいと思います。
市長
他の議員の質問でもお答えしているところですが、これまでも取り組みとしては子育て支援拠点施設を新たに市として初めて設置したり、まだ待機児童が解消というわけではありませんが、保育所の定員を大幅拡充するために8施設、409名の定員増、これはいわゆる子育てしやすい環境づくりです。
また、子どもの心のケアハウスの開所についても、教育委員会と連携しながら進めてきたところでありまして、これはいろいろな心の悩みを抱えた子供たちが安心して通える、そんな環境づくりをしていきたいという思いからです。
また、突発的ではありましたが、災害とも言えるぐらいの猛暑、酷暑があった中で、全小中学校、義務教育学校にエアコンの設置も昨年決断したところです。また、子供たちには、国際空港があるまちとして、国際感覚のある人間に育っていただきたいという思いの一つとして、ALTの増員を図りながら、英語が話せるというよりは、外国の方と気兼ねなく会話ができるような、コミュニケーションがとれるような、そんな人材育成にもつなげていければと思っております。
また、子供たちの育ちや学びを地域全体で見守っていくような、地域学校協働本部にも、教育委員会と協働しながら取り組んでいけたらと思っておりますし、今後についてはICT教育、これは国のほうでやることで決断されているようですが、市としてもそこは従来の既定路線として、今後も力を入れていきたいと思っております。
さまざまな市政運営の中で課題がある中で、市政運営の大きなテーマは、私は持続可能なまちづくりだろうと思っています。その持続可能なまちをつくるために、いろいろな課題がある中で、柱として子育て、教育の施策の拡充、そしてまた誰もが安心して暮らせる、これは高齢者から障がいのある方からLGBT含めて、経済的な格差も含めてになりますが、誰もが安心して暮らせる共生のまちづくりということ、そしてまた地域経済の活性化という観点で、中小企業を初めとした地元の経済雇用を支えている方々に、どうやって振興していただけるかといったようなことがあろうかと思います。
そうした中でも、子育て・教育については、まちの未来を担う人材を育成していくという観点で、私は最優先の課題の一つだろうと思っております。その中の子育て・教育の施策の柱の中の一つとして、学校給食費の段階的無償化に取り組んでいきたいと考えたところです。
吉田
市長の1回の答弁で、これだけ長い御答弁をいただくというのは、私恐らく経験上初めてなので、相当やはりこのことについては強い思いを持っていらっしゃると伺います。今、市長は実績をおっしゃいましたが、私が聞きたかったのはそれだけではなくて、今後の展望なのです。先進都市、先進というのは先を行くわけですから、どのようにこの市を子育て・教育の豊かな材料がそろったまちとして、どこにもっていきたいのか。そういうイメージをお聞かせいただきたいと思います。
市長
イメージというと、非常に漠とした難しさがあると思いますが、私は持続可能なまちという意味では、誰もが夢や希望を持って暮らしていけるまちなのだろうと思っています。毎日、現実に向き合って、みんな大人も子供も暮らしておりますが、少しでも夢とか希望が持てることで、それは前に進んでいく大きな力になると思います。
そういう中でも、子供たちがいること、そして子供たち一人一人の可能性、勉強ができる子、数学が得意な子はそこで何か力が発揮できる可能性とか、歌やダンスが好きな子はそこで活躍できる可能性、スポーツができる子はそうした舞台があってそこで活躍できる可能性、その一つ一つを伸ばしてやれるような環境づくりをしていくことが、結果として子供たちの生き生きとした笑顔になって、それが我々大人にとっても生きる希望になってくるのではないかなと、そういうまちだと思っております。
吉田
市長の思いを確認させていただきましたが、学校教育において保護者の負担というのはさまざまな部分があります。その中で制服や修学旅行についても、私は以前に質問させていただいたことがありますが、今回こうしたさまざまの負担の中で、なぜ無償化のターゲットを給食費に絞ったのか、そこについてのお考えをお伺いします。
市長
学校給食費の無償化を公約ということで取り組んできて、給食費の無償化のことだけやってほかをやらないということではないというのは、先ほど申し上げてきた、これまで取り組んできた内容でおわかりいただけるかと思います。一つ、県内で取り組んでいるところはないということもありますし、やはり子育て・教育に対して本気で取り組んでいくのだということについて、これについてはある程度の大きな財源を伴うこともありまして、ほかで取り組みたくてもなかなかできずにいる政策だろうと思っております。
そこに目をつけて、名取であればそこに取り組んでいくことで、本気度というのがわかっていただけるかなと思っております。
吉田
今の御説明では、給食費にターゲットを絞った理由がよくわからないのです。市長がそれを選挙公約に掲げたというのが、こちらとしては説明としては一番そうなんだろうなというところですが、選挙公約に決める際、当時私も市長と行動をともにしたこともありましたが、こういう話をしたことがなかったので、きょうお伺いしたいのです。学校給食法の第11条第2項に、学校給食費は学校給食を受ける児童または生徒の保護者の負担とするという規定があるのです。公約を決定する際、市長はこの条文の存在については御存じだったでしょうか。
市長
残念ながら存じ上げておりません。
吉田
現時点で、この学校給食費無償化にするためにいろいろと調査されたと思いますが、現時点では条文の存在は御存じですか。
市長
担当と調整する中で、その条文であったかどうかはわかりませんが、法的な根拠についても確認をしているところです。
吉田
法律には何らかの法の規定の理由があるわけですね。理由がなく法律ができるわけはない。では、この給食費を児童または生徒の保護者の負担とすると規定している理由は、なぜだと思いますか。
市長
今お話しされているのは、給食費の賄い材料費だと思います。実費分について負担を求めるということでして、さきの議員協議会でも御説明申し上げたとおり、給食費はそれだけではありません。センターの維持管理費もありますし、運営費もあります。そのトータルの中で、ただ賄い費については保護者負担という原則になっているものですから、その部分について段階的に無償化をしていきたいということです。
吉田
もう一回、お聞きします。そのことは第1項で、施設と設備、運営については公費でと、そして第2項でそれ以外は保護者負担でと、それが給食費なのです。その学校給食費を保護者負担としているこの法律の規定の理由は、どこにあるとお考えでしょうか。
市長
法学者ではありませんので、法の規定の細かいところ、その背景まで熟知しているわけではありません。ただ、基本的には賄い材料の部分について受益者負担ということなのだろうと思いますし、給食について当市では完全給食でやっておりますが、そうでない地域もあるわけですので、全てを公費で賄うことについてはどうかということもあってなのだろうと推測いたします。
吉田
現段階では推測でもいいと思うのです。ただ、やはりこの法律ができた背景は、もう一度しっかりと経緯を調べ直して、そして説明できるようにしていただきたいと思います。
そういう実費負担にしている理由、私もいろいろあると思うのですが、本当にどこが正しいのかということについてはわかりません。ただ、そうした中でいろいろな想定をしていかなければならないということは確かだと思うのです。
そこで、無償化実施後の想定について、次に移りたいと思います。
近年、食品の価格は上昇傾向にあります。さまざまな要因がありますが、もし食材の価格上昇によって給食費を上げなければいけないとなった際に、給食費を上げるか、給食の中身の質を下げるかと、どちらかになってくると思うのですが、中身の質を下げるというか、現状維持とか、そういう形にはしてもらいたくないのです。予算を膨らませて質と量を維持するかなどいろいろ想定があるかと思うのですが、お聞きしたいと思います。
小項目2 材料費が高騰するなど1食当たりの単価が上昇した場合をどのように想定しているのか、市長にお伺いいたします。
市長
先日の議員協議会で御説明しているところですが、今回の学校給食費の段階的無償化については、設置者負担(免除)方式で実施することとしており、これは初めから給食費を保護者から徴収しないというものであり、1食当たりの単価が上昇した場合は、無償化の対象となる中学3年生の単価の上昇分は、そのまま市の負担として増加するものと見込んでおります。
吉田
恐らくそうではないかと思いました。今年度も学校給食費の値上げは実際にありまして、小学校は255円から10円値上げして265円と、中学校は310円から15円値上げして325円と、双方約5%値上げされております。これをもし無償化した際は、その都度対応することになると思うのですが、この予算の枠というのがやはりどうしてもあると思います。そう簡単に5%分ふやす、枠を広げるということはできるのかどうか。予算編成上、そこを膨らませた分どこか減らさなければいけないと思うのですが、柔軟に対応できると捉えてよろしいのですか。
市長
さきの他の議員への答弁でも申し上げたとおり、今回については中学3年生ということで進めていきますが、そうした変動値も含めてどういった推移になるのかを観察できるぐらいの余裕というか、財政的なスペースは持った上で進めていくということです。
吉田
今、提案されているのは中学校3年生だけですが、これが全学年9学年となりますと、計算上約3億5,000万円で、今回のように5%の給食費値上げだけでも相当な大きな値上げ額になると思うんですね。その都度市の負担をふやしていくことになっていくと思うのですが、1,000万円単位の金額がさらに必要になったとしても対応していけると、そういう担保がなければ、こういう大きな事業はそう簡単に取り組むことはどうなのかなと思うのですが、そのあたりの考え方はいかがでしょうか。
市長
段階的に引き上げていくというのはそういうことでありまして、まず取り入れてみて、その中でどういった変動値がある、また突発的な他の事業においても市全体の財政にかかわるようなことがないとも限りませんので、そうしたことを見きわめながら段階的に進めていくということです。
吉田
段階的にということも、今回はそういう形で中学校3年生という御提案ですが、段階的にもいろいろあるのではないかという議論も先日ありましたので、私も一つ提案をさせていただきたいと思います。
次の項目ですが、オーガニック給食について提案させていただきます。
ちょうどきょう、愛知県の東郷町という町の議会でも、オーガニック給食の推進について一般質問されているようです。まだ結果は知らないのですが、そちらよりもぜひ市長には踏み込んだ答弁をされることを期待いたします。
利府町では先日、小学6年生と中学3年生から給食費の段階的無償化が提案されたものの、議会で反対が賛成を上回りまして立ち消えとなってしまいました。私はこの給食費の無償化に対しては反対の立場ではありません。ただし、無償化による効果というものが、より広い形で及んでくるもの、少なくともその見込みが確実であることが、私が今回の提案に賛成できる条件ではないかと自分では考えております。
学校給食費の無償化は確かに保護者にとっては負担軽減となります。しかし、考えようによっては、現金による負担が少なくなることは、現金を給付するのと実質は変わらないとも捉えられる。これだけでは、やはりばらまき政策ではないかと思われます。ですので、そうならないためには、やはりより多くの効果を生み出すような施策にしていかなければならないと私は思います。
そこで、無償化によってどういう新しい効果を期待するべきかということですが、日本における食の現状をSDGsの理念に照らして考えますと、農薬による人体と自然界への影響を取り除くことがまず1点目、それから食品廃棄をできるだけ少なくすることが2点目、これらが私は優先課題として上にあるのではないかと考えております。
そして、これらの問題をできる限り解決に向かわせるための一つのアプローチとして、オーガニック給食というものがあります。
ここで、小項目3 無償化を負担軽減だけで終わらせるのではなく、安全で自然と調和したオーガニック給食の実施に結びつけるよう検討すべきに対する御見解を、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
本市では、平成22年度に現在の学校給食センターを整備し、安全・安心な学校給食の提供に努めております。学校給食の材料の選定、確保については、教育委員会が所管となっておりますので、詳細については発言を控えさせていただきますが、議員より御質問のありましたオーガニック給食については、特色ある教育、食育を進める上で非常に興味深いテーマであると感じるものの、さまざまな課題があり、現状では難しいものと認識をしております。
教育長
安全・安心な学校給食の安定供給は、学校給食関係者が一丸となって取り組んでいるところであり、通常の給食のほかに食物アレルギーを持つ児童生徒に対しては、アレルギー対応食を提供しております。
御質問のありましたオーガニック給食は、有機栽培で生産した農作物を材料に使用した給食と認識しております。本市の学校給食センターでは、1日に約8,000食の給食をまとめて調理しております。オーガニック給食を実施するためには、大きさや形、品質等規格に合った大量の食材を毎日確保する必要があるとともに、単価の問題も発生しますので、現状では取り組むことは難しいものと考えております。
オーガニック給食につきましては、全国的には一部実施している自治体もあるようですので、今後、調査研究していきたいと考えております。
吉田
今、教育長から単価の問題という答弁がありました。もちろんそのとおりだと思います。普通の今の給食に比べて、オーガニック化をすれば単価がその分上がるのです。こういう上がった分の単価について、私は無償化の一部をそこに充てていくというものが、自分としては理想なのです。
なぜこういうことを取り上げるかといいますと、今、給食の額が高くて払えないという声は、私は少なくとも余り耳にしてはおりませんが、社会問題として、給食をめぐる問題の一つとして、食材に含まれている遺伝子組み換え食品、そして残留農薬について、最近そのことへの関心の高まりを感じております。
令和元年9月定例会の一般質問でも、世界的に使用禁止が進むグリホサートについて取り上げました。ある団体が独自に行った調査では、給食のパンからグリホサートの成分が検出されていると言われております。これは調査の主体から明かさないでほしいと言われておりますので、あくまでも私が得た情報だとして捉えていただきたいと思います。ただ、一般に売られている食パン等のパンには、グリホサートは検出されております。これは公開されております。
日本で使われる小麦のほとんどは、海外から輸入されているのです。その海外でこうした遺伝子組み換えの作物、それだけではなく農薬を非常に多く使用されているものが、日本にどんどん入ってきているという現状があります。そしてまた、グリホサートに限らず、ミツバチの大量死の原因として指摘されているネオニコチノイドという農薬、こちらについては最近の発表では、これは島根県ですが、宍道湖のウナギやワカサギの激減の原因になっていることが指摘されております。
こうしたグリホサートやネオニコチノイドなど危険と言われている農薬については、先進諸国ではどんどん規制が強まっているのですが、日本は大変甘い状態にあるのです。日本における農薬の使用量は、中国に次いで世界第2位とも言われております。こうした食材を給食で普通に出して、子供たちに食べさせているのですが、やはり給食の安全性ということに関してもう少し気を配るべきではないか。少なくとも無償化という財源がせっかくあるのでしたら、そういうことも含めて解決していける道を示すべきではないかと思うのですが、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
先ほども申し上げましたが、学校給食の材料の選定、確保については教育委員会が所管となっておりますので、発言を控えさせていただきます。
教育長
先ほども申し上げましたが、名取市学校給食センター、平成22年8月から今の学校給食センターで給食の提供を行っておりますが、私としましては安全・安心に十分注意をしながら、子供たちにおいしい給食を提供できるよう努めているという認識でおります。
その中で、今吉田議員からいろいろな御紹介がありましたが、本市の学校給食センターで使用している食材については、当然国の基準を満たしている安全なものだという認識で使用しております。そういった中で、極力地元の農家の方がつくられた地場産の野菜等を活用するなどの取り組みを行っておりますので、現時点で御紹介のあった有機栽培による野菜を積極的に取り入れていくことについては、さまざまな課題があることから難しいのではないかと考えております。
吉田
その難しい課題をクリアするためには、財源が必要なのです。せっかく今回財源があるわけですから、そういう形で無償化と一体化して進めていくべきではないかと提案させていただいております。
地元の野菜などをなるべく使うことについては、今進められているということは確認しましたが、例えば野菜以外の加工品ですね、豆腐などにはやはりその原料となる穀物があるわけですが、日本の穀物の中で日本国内でつくられているものは大変割合が少ない。これは御存じかと思いますが、先月のある方の講演会の記録から取り上げるのですが、遺伝子組み換え作物の輸入国としては日本は世界一なのです。食卓に上るトウモロコシの何%だと思いますか。74%です。大豆は84%、ナタネは89%と、こうしたものが加工された後も食卓に上ってきているというわけなのです。
こうした穀物を多く海外から輸入しているのは、アメリカの企業の利益のために、こうして日本に輸入されているという現状があるのです。米なども今までの貿易協定などの中でこういう経過があるわけです。それがやはり給食に含まれている。海外でつくられて農薬がたくさん含まれているような食品が原料になっている。それが日本に入ってきているわけなのです。そして、給食にも上ってきている。一体給食で出されているパンなど、そうした加工食品の中にこういう外国産の遺伝子組み換えの材料がどのくらい含まれているかということに対して、これまで調査をした経緯はあるのでしょうか。市長と教育長にお伺いいたします。
教育長
先ほどとほぼ繰り返しの答弁になりますが、給食で使用している食材については、国の基準にのっとって安全な食材を使用しているものと認識しております。したがいまして、遺伝子組み換え食品等の使用については調査したことはありませんし、これからもそのような観点での調査については特に考えてはおりません。
吉田
給食を変えることによって、いろいろないい効果が出てきたという実例があるのです。先ほど大沼議員の質問の中で不登校の話がありましたが、これは長野県の真田町、現在は合併して上田市の一部になっていますが、そこで校長として中学校に赴任された方の実際の体験談です。
非常に学校が荒れていた、そこで子供たちといろいろ話をしていく中で、食事がやはり大変乱れている。家庭での食事が、まず乱れている。そこで、この校長は何に取り組んだかというと、給食を改善したわけです。全てパンを御飯にかえた。そして、無農薬の米を使い、発芽玄米を10%ほど配合する形にした。おかずは、小魚とか青魚が中心で、あとは旬の野菜。肉料理は一切出さない。これは家庭で食べているため、肉は出さない。それから、農薬、防腐剤、化学調味料を入れない。そうしたところ、毎年60何名あった不登校が1名か2名くらいまで減ったと。それから、いじめがなくなった。非行がなくなった。アトピー、アレルギーも改善された。やはり食を変えることによって、そうした成果が出てきたということがあるわけです。また、学力が上がったとも言われています。
私は、教育・子育て先進都市のイメージは、こういうものではないかと思うのです。本当の安心・安全というのはこういうことではないのかと。食というものは本当に大事なものではないかと思います。
市長と教育長から先ほど来、そうそうすぐには取り組めないということはもちろん理解するわけです。一つの例として、千葉県のいすみ市というところで、平成25年から有機米の栽培に力を入れてきて、平成27年から有機米を学校給食にも一部導入、平成29年11月から市内の小中学校の給食のお米を全部地元産の有機米にしたと。やはりこれぐらい、6年以上時間がかかっているわけです。まずできることから進めていかなければ、今1年目でなければ6年目はずっと先にいってしまいます。早く進めていただきたい。
韓国では、全国の学校給食のオーガニック化と無償化も進められております。韓国は国として、国策として進めているようです。そして、アメリカはゼン・ハニーカットさんというお母さん方の運動によって、スーパーなどで遺伝子組み換えを使っていない食品の売り上げが驚異的に伸びている。毎年約10%、こうした遺伝子組み換えでない食品の売り上げが上がってきております。そうしたものの市場規模は年間で約500億ドルと、アメリカもそういうふうに変わってきていることを申し上げたいと思います。
また、もう一つの情報として知っていただきたいのが、他の自治体でも水面下で学校給食の無償化の議論が進められ、その一部の議員からはオーガニック化を同時に進めるべきではないかという働きかけもあるようです。こういうことは、もし他の自治体で実現したら本市もということではなくて、やはり名取のほうで先に市長からのろしを上げていただきたい。そのように私は提案したいと思います。
このオーガニックの意味をもう少し広く捉えますと、これは単に有機栽培とか無農薬とかいうだけではなくて、動物や植物の生態系に配慮した持続可能な循環型手法を意味するそうです。先ほどイノシシがふえて困るという質問もありましたが、イノシシも何でふえたか、もとをたどっていくと、天敵がいなくなってしまったということがあるのです。イノシシの問題を解決する一つの方法として、天敵をまた復活させるということもあるそうです。実際に研究している方がいまして、ニホンオオカミをもう一回日本で復活させようという研究をしている方もいるようですが、それほどに生態系というものはやはり大事で、一度崩れてしまうと二度と修復が不可能であると言われております。
そしてまた、私が今回もう一つ提案したいのが、先ほど2点目として上げた食品のごみの問題ですが、新しい発電として、メタン発酵ガス化発電というものが、再生可能エネルギーとして今世界では主流になってきている。これは日本は研究が20年ほどおくれていると言われておりますが、給食の残飯も含めて発電に使うことができて、しかもCO2も発生しないという、大変有効な発電です。このようなことも含めて今後の検討に入れていただきたいというのが、私の考え方なのです。教育長にこのような総合してお考えというか、御感想をお伺いします。
教育長
今、多方面にわたる御提言を頂戴しましたが、冒頭でお話しいただいた校長が給食の改革に取り組み、学校が劇的に変わったという、それについては大変すばらしい出来事だと思いますが、それがオーガニック給食を取り入れることによってそういう変化が生じたのかということについては、私も詳細を経過を見ないと何とも言えませんが、お聞きする限りではその校長の熱意によるところが大きかったのではないかという感じもいたしております。
オーガニック給食について私も不勉強ですが、いろいろ議員のほうから御紹介いただいた幅広い見方なども含めて、今後研究していきたいと思いますが、今日本で有機栽培でつくられる野菜は、市場に流通している野菜の0.5%程度だとも言われております。現実的に本市の学校給食センターでそれを使用することについては、価格の問題だけではなく、安定的に納入する方がいるかどうかという問題もあります。現在、名取で使っている食材について、繰り返しになりますが、安全・安心に最大の注意をして食材を選定していると私は認識しておりますが、今後、国内あるいは世界の動向なども、もう少し私も幅広く見識を広めて見ていきたいと考えております。
吉田
有機農業を推進するところで、行政がいろいろと支援している自治体の例もありますので、そういうことも含めて今後より一層研究を進めていただきたいと思います。
では、最後の質問事項に移ります。
大項目3 第2期地方創生総合戦略についてです。
政府は平成26年から毎年、まち・ひと・しごと創生基本方針と総合戦略を策定しております。本市は、平成28年に名取市地方創生総合戦略を策定し、将来の人口減少に歯どめをかけ活力ある地域社会を維持していくために、必要な取り組みを進めてまいりました。その計画期間が今年度をもって終了いたします。
そこで、小項目1 地方創生総合戦略の計画期間が間もなく終了します。現行戦略の反省と次期総合戦略の課題をどのように捉えているのか、市長にお伺いいたします。
市長
現行の地方創生総合戦略の計画期間が満了しておらず、次期戦略につきましては国においても策定作業の途上ですので、現行戦略の進捗状況と課題につきまして答弁を申し上げます。
現行戦略では、3つの基本目標を掲げ、それぞれに数値目標を設定しております。まず、基本目標1、出生率の向上を目指す分野です。数値目標のいずれも目標値に達していない状況となっており、今後も本市における活力を維持、増大させていくためには、出生者数の増加、待機児童の解消、子育て支援施策に対する満足度の向上に向け、引き続き子育て支援策の充実を図っていくことが必要と考えております。
次に、基本目標2、働く場の確保を目指す分野です。この中で、15歳から24歳までの若い世代の流出を抑えようという数値目標を掲げておりますが、依然として若者の流出が続いている状況にあるため、地元企業などと連携しながら、働く場の確保に向けた取り組みを継続していく必要があると捉えております。
基本目標3は、本市に定住してもらうための魅力づくりを目指す分野です。定住人口については、平成30年度実績において目標値を達成しているものの、これからも名取に住み続けたいと考える市民の割合については目標値を下回った結果となっており、にぎわいの創出や定住促進に向けた取り組みが重要になると捉えております。
吉田
定住人口をふやしていくという目標の土台にあるのが、日本全体としてやはり人口減少していくということ、そして都市部に非常に人口が集中して過密化しているという、地方と都市部との人口格差の問題です。これを国全体として考えたときに、市町村ごとにどういうことができるか、都道府県もどういうことができるかというのが、この総合戦略であると思うのです。このような将来の国全体として人口減少に歯どめをかけて、活力ある地域社会を維持していくという目標に対して、本市としてはどういう位置づけにあると捉えておられるか、もしお考えがあればお伺いしたいと思います。
国としての大きな目標がある中で、やはり市町村ごとにさまざまな特色があるわけです。市町村ごとに、その大きな目標に対して何ができるかということを考えていかなければいけないということだと思うのですが、国として今申し上げたような人口の問題に対して、本市としてどういうところに位置づけられるというか、国全体の目標の中で本市は一体どういうことを果たしていけばいいのかということをお聞きしたいと思います。
市長
本市としては、東北の大きな都市である仙台市に隣接しているという地理的な条件、優位性、それから仙台空港を初めとして各道路網、鉄軌道、非常に利便性が高いまちであるという特徴を生かしながら、自然増の部分と、社会増の部分で若い方々の定住をいかに促進して、社会増がふえれば数年後に自然増がふえてくるという構図になりますので、そうした形で東京一極集中ということではなく、地方の中でそうした人口流出の受け皿になるような機能の一部を果たせればと思っております。
吉田
私も同じように思います。そういう名取市の特色がやはり強みですので、そこを生かしていくというのは必要だと思うのですが、そうした中で第1期のいろいろな反省があるということは先ほどお伺いしたのですが、今度第2期の具体的な施策について提案させていただきたいと思います。次の項目に移ります。
政府は、ことしの9月、まち・ひと・しごと創生基本方針2019を閣議決定しました。令和2年度から6年度までを第2期とし、自治体は国のビジョン、総合戦略を踏まえて、総合戦略を切れ目なく改定するとしております。本市の第2期総合戦略は、第六次長期総合計画の枠組みに落とし込む形で検討されているようです。国の基本方針のほうには6つの新たな視点が示されておりますが、そのうちの5番目として、誰もが活躍できる地域社会をつくることに対してのということがあります。このことに対し、私は長期総合計画の中でもう少し具体的な施策として見えてきてほしいという思いを持っております。
そこで、小項目2 第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略における新たな視点に、誰もが活躍できる地域社会をつくるとあります。多世代交流の場や生涯活躍のまちをつくるため、施策を具体化して示すべきに対する御見解を、市長にお伺いします。
市長
現在、国において、議員御指摘の誰もが活躍できる地域社会をつくるという視点を、次期戦略に追加するとの考えが示されていることについては承知しているところですが、詳細な内容についてはまだ示されていない状況です。
一方で、議員御指摘の多世代交流の場や生涯活躍のまちづくりという視点については、現在策定作業を進めている第六次長期総合計画において位置づけをしているところです。
具体には、多世代交流の場という視点では、重点政策のリーディングプロジェクトの中で、世代、地域を問わず交流し、つながりが生まれる仕掛けづくりを掲げておりますが、その中で例えば、地域と学校、家庭、活動団体との連携、交流により、子供の成長を支え合う体制の充実に努めるほか、市民協働提案事業において、多世代交流につながる取り組みの提案が出されてきていることから、これらを活用した取り組みを進めていきたいと考えております。
また、生涯活躍のまちという視点では、同じくリーディングプロジェクトの中において、高齢者や女性、外国人等の活躍の場の創出に向けた仕掛けづくりを掲げておりますが、その中で例えば、引き続きママインターン事業による女性の再就職を促進していくほか、市民活動団体の育成、支援により、そこに参画されている高齢者の方々が活躍できる機会の創出を図っていきたいと考えております。
吉田
それももちろん、そういう観点で考えれば枠の中に入ると思いますが、この閣議決定のあったものについては、もう少しまち全体の中で地域ごとに特色を持って、高齢者の方でも外国人の方でもそうですが、皆さんが集い交流できる場というものを求めている部分があります。少し今の内容だけでは、私は個人的にですが、足りないのではないかと。町なかにもっと誰もが交流できる、お互いに集い合えるような場所がこれからより必要になってくると思うのですが、そうしたあたりを本市で策定する第2期の総合戦略のほうに新たに盛り込んでいくことについてはいかがでしょうか。
市長
新たな拠点施設までは考えておりませんが、御指摘の内容については第六次長期総合計画の中に既に溶け込ませているものと捉えております。第2期地方創生総合戦略については、国の方針を踏まえて適切に対処していきたいと考えております。
吉田
拠点施設というだけではなくて、やはり地域としてそういうことができるように、ほかの事例などをいろいろと研究していただきたい。あと日本版CCRCなども研究していただきたいと思います。
以上で一般質問を終わらせていただきます。
本会議
(議案第97号 名取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び議案第98号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例)
吉田
議案書7ページの第21条でお伺いいたします。パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬についてですが、第2項で「規則で定める割合」という形で、規則がほかにあるということかと思います。この規則で定める割合について、具体的な内容をお伺いいたします。
総務課長
第21条第2項で定める規則ですが、これは新たにつくる規則としておりまして、名称はこれからですが、要は支給に関する規則というような形でつくる予定です。また、割合については、現在の給与に関する規則に準じて、(1)については100分の125、(2)については100分の135と考えているところです。
吉田
議案書12ページの第33条でお伺いいたします。ここに、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与とありますが、「職務の特殊性等を考慮し」というのは、具体的にどういうケースを想定されているのでしょうか。
総務課長
ここで定めているのは、別途給料が定められているような場合を想定しております。具体的には、今学校に配属されているALT、外国語指導助手ですが、こちらはJETプログラムで別途給料が事前に募集の際に各国に通知されておりまして、それを給料表に当てはめるのは困難ということで、今回、こちらの書きぶりに該当するものと考えております。
吉田
その際、任命権者が別に定めることになっておりますが、これはその都度定めるというか、ケースごとに定めていくことになるのでしょうか。任命権者のこの決め方について、どういう手続で進んでいくのかお伺いしたいと思います。
総務課長
その都度のケースになりますが、一定の基準の中で定めていくことになります。
(議案第100号 名取市歴史民俗資料館条例)
吉田
第5条、職員の体制についてお伺いいたします。「館長その他必要な職員」とあります。館長の身分は常勤となるのでしょうか。そして、館長も含めた全体的な職員体制をお伺いいたします。
文化・スポーツ課長補佐
名取市歴史民俗資料館の職員体制ですが、まず、館長については常勤の職員を予定しております。また、職員体制については、他の社会教育施設の一般的な職員体制と同様に、館長を初め、専門的な知識を有する職員、事務職員等を配置する予定です。配置する職員は市長部局との相談の上で決定されることになっておりますので、実際の人数等についてはまだ確定していないところです。
吉田
その職員体制にあわせて、1つ確認したいことがあります。たしかオリエンテーションルームを提案されていたと思います。以前の資料の中で、映像を見たりできる部分があるということでしたが、こちらの部屋を一般に貸し出す際の業務は、この歴史民俗資料館の中の職員が行うというお考えでよろしいですか。
文化・スポーツ課長補佐
考古資料展示室内のオリエンテーションルームについてですが、こちらは貸し出し等の予定はしておりません。基本的には名取市の通史映像などを見ていただくエリアとしておりますが、ただ、スペース的に有効活用できるように、設置する椅子等については簡単に動かせるものを配置する予定で考えておりますので、例えばその場所で市主催の興行を行ったりイベントを実施したりということで、スペースを活用していきたいと考えております。
吉田
第2条、設置で、保存及び活用と書かれております。この中で、いわゆる無形民俗文化財については、歴史資料とか民俗資料とかありますが、どこに含まれると理解したらよろしいのでしょうか。
文化・スポーツ課長補佐
第2条の中では民俗資料に含まれるという考えです。
吉田
第4条では民俗資料も含めて収集、整理及び保管となっておりますが、具体的に無形民俗文化財の業務としてどういった業務があると捉えているのかお伺いします。
文化・スポーツ課長補佐
実際は、映像など、そういった無形民俗文化財の資料関係を収集、保管し、後世に伝えていくということでの保管収集業務と考えております。
(議案第101号 名取市中小企業・小規模企業振興条例)
吉田
第12条の検証結果の公表についてお伺いいたします。この検証結果の公表は、施策の実施状況についてとありますが、何か施策を実施する都度、検証して公表するのか。それとも、例えば1年なら1年と期間を決めて、その中で実施された内容についてまとめて公表するということなのか、お伺いいたします。
商工観光課長
現在考えている案としては、その都度ではなく、ある程度まとまった期間で、例えば1年たってその施策が実施できているのかどうかなどについて検証していきたいと考えているところです。
吉田
その検証する対象となる施策は、この条例が今後制定されるとして、制定される前から行われていた中小企業等向けのいろいろな事業も含めてということなのでしょうか。それとも、新たに条例制定後に行われる事業についてだけということなのでしょうか。
商工観光課長
今まで行ってきた施策について、見直しを含めて実施していきたいと考えております。
(議案第108号 令和元年度名取市一般会計補正予算)
吉田
12、13ページの18款2項7目ふるさと寄附基金繰入金ですが、こちらはどういったことに充てられるものでしょうか。
財政課長
ふるさと寄附基金の充当先ということでお答えさせていただきます。今回、歳出で組んでおりますが、増田、下増田、愛島の各児童センターにエアコンを設置する分として充当しております。
吉田
児童センターへのエアコン設置3カ所分ということです。ふるさと寄附金をどういったことに活用するかは自治体の裁量かと思いますが、いろいろな課題がある中で、こういった形で今回エアコン設置に充てるという結果に至るまで、どういった検討が行われたのかお伺いいたします。
財政課長
ふるさと寄附金の充当の考え方については、これまで何度か議会の場で説明させていただいておりますが、いただいた温かい寄附を充当するに当たってはできるだけ目に見えるような形で充当したいと考えておりますので、今回についても各児童センターのエアコン設置に充当させていただいたところです。
吉田
12、13ページの18款2項10目東日本大震災復興交付金基金繰入金ですが、今回の補正後の基金の残高をお伺いいたします。
財政課長
今回の12月補正後の東日本大震災復興交付金基金の残高ですが、20億1,402万2,000円となっております。
吉田
10、11ページの14款2項8目商工費国庫補助金ですが、観光費の東北観光復興対策交付金の減額の理由についてお伺いいたします。
商工観光課長
歳出38、39ページの観光費にも関連しますが、平成31年度事業について平成31年1月に国に7事業を要望し、平成31年第2回定例会の新年度予算1号補正としてお願いしていました。その後、3月下旬に、7事業のうち1事業のみの採択の決定があり、内示を受けていたところです。今年度に入って、2次募集が6月にありまして再度挑戦しましたが、全て不採択という通知を受けましたので、今回予算を減額とするものです。
吉田
採択された事業とされなかった事業の中身をお知らせいただきたいと思います。
商工観光課長
採択された事業は滞在コンテンツ充実・強化事業で、これまで築いてきた観光資源をもとに、仙台空港と連携しながら、ステップアップを目指し、モニターツアーを企画し実施するものであります。
不採択のものについては、観光復興促進調査事業、プロモーション強化事業、受け入れ環境整備事業等になっております。
吉田
12、13ページの21款1項1目総務債の1節通信設備整備債、公衆無線LAN整備事業に対する起債ですが、これは当初予算で、起債をすることで70%が国の交付金ということをお伺いしました。今回減額になることによって、やはりこの減額の分もあくまで名取市分の30%ということなのでしょうか。
財政課長
今回、公衆無線LANの起債については減額をしておりますが、通常の起債と同様に、減額した後の起債の分については元利償還金の後年度の措置はあるものと捉えております。
吉田
その措置の分の最終的な部分は、あくまでも市としては30%の負担で、残り70%は国で負担していただけるということでよろしいですか。
財政課長
お見込みのとおりです。
吉田
24、25ページの3款1項5目知的障害者福祉費の需用費の修繕料の内容をお伺いいたします。
社会福祉課長
この修繕費については、みのり園の屋根修理ということで要求させていただくものです。
吉田
今後の工事のスケジュールを、完了予定も含めてお伺いいたします。
社会福祉課長
今議会においてこの補正予算案をお認めいただければ、この時期ですので、年明けの発注となります。屋根のふきかえとなりますので、その辺は工事契約を結ぶ段階で工期等が確認できるものと見込んでおります。
吉田
28、29ページの3款3項2目保育所費の賃金ですが、臨時保育士等賃金の増額の中身についてお伺いいたします。
こども支援課長
当初、調理員を含め臨時17名を見ていたところですが、補正後は調理員を含め30名と見込んだところです。
吉田
計算すると13名分の増ということかと思いますが、これはどちらの施設にどのぐらいの人数と捉えていらっしゃるのでしょうか。
こども支援課長
臨時職員の人数については、当初17名から補正後30名となったところです。その30名の配属先はどちらかということですが、増田保育所が10名、うち3名が調理員、名取が丘保育所が10名、うち3名が調理員、ゆりが丘保育所が7名、うち3名が調理員となります。残り3名については、募集はしていますがまだ確保できておりません。今後確保したいということで、3名分の予算を残しているところです。
吉田
28、29ページの3款3項3目児童館・児童遊園費15節工事請負費で、先ほど歳入の際にお尋ねした空調設備設置工事についてです。ふるさと寄附金を充てるということでしたが、数字的にはふるさと寄附金分が10分の9で、それ以外の10分の1が恐らく一般財源ということかと思います。このように財源を分けたのはどういう考え方に基づくのでしょうか。
財政課長
ふるさと寄附金を充当する際に、例えば物品の購入などに充当するときの割合については、基本的に90%を一つの目安として充当しております。ただ、それが全部ということではなく、物によっては10分の10を充てているものもあります。
吉田
38、39ページの7款1項4目観光費13節委託料、仙台空港周辺地域活性化インバウンド事業委託料です。採択されなかったことについて、基準が厳しくなったという御答弁がありましたが、逆に今回採択された事業、先ほどの御答弁ですと滞在コンテンツの充実などについて予算化できるということですが、これは内容がオリンピック・パラリンピックとか広域連携にどうかかわっているのかお伺いしたいと思います。
商工観光課長
採択の基準としては、オリンピック・パラリンピックに特化したもののほかに、広域連携によるものということもあります。今回採択された滞在コンテンツ充実・強化事業については、名取市、岩沼市、亘理町、山元町の広域でモニターツアーを企画し実施するということで、2市2町の広域連携というところで採択されたものです。
吉田
モニターツアーですか。余りよくわからない言葉なので、できればもう少し今後の連携のあり方などについて、今御説明いただける部分で結構ですのでお聞きしたいと思います。
商工観光課長
内容については、受託した事業者が海外に旅行業者を持っておりまして、ターゲットは台湾と中国ですが、そこの旅行会社を活用してモニターツアー客を呼んでくるというものです。空港周辺地域のモデルコースとして、例えばわたり温泉に1泊してイチゴ狩りをして、それから竹駒神社に寄って、仙台を周遊して帰るというようなツアーをつくっていただき、その中でアンケート調査等を行って、その結果をインバウンドに反映するということで事業を実施していただく予定となっております。
吉田
46、47ページの8款7項3目復興まちづくり事業費の震災復興伝承館についてお伺いいたします。こちらは指定管理が決まったわけですが、このホームページの作成という部分で、今後指定管理者との調整はどのように進められることになるのでしょうか。
復興調整課長
現在はトップページから2階層くらいで場所などをお知らせしているところですが、自主事業のお知らせなどのページをどのようにするかという部分については、指定管理者と今後詰めていきたいと考えております。
吉田
今後、震災復興伝承館がオープンしてホームページもいろいろと更新されていくことになろうかと思いますが、そういった維持管理に係る費用とか維持管理を行う主体というのは市なのか指定管理者なのか、そのあたりの考え方をお伺いします。
復興調整課長
指定管理者に今後いろいろと充実をしていただくことになると考えております。
吉田
46、47ページの8款7項3目復興まちづくり事業費の13節委託料で、震災復興伝承館警備委託料が計上されています。この警備の期間、いつからいつまでの分の委託料なのかをお伺いいたします。
復興調整課長
この施設については1月末に完成する予定で、その後、引っ越しなど開館準備をいたしますので、今回計上する委託料については2月、3月分の委託料です。
吉田
警備員は何名の体制になるのか。そして、閉館後の時間帯の警備ということなのか、それとも開館中も何かしらの形でかかわっていただくのか、そのあたりの体制についてお伺いいたします。
復興調整課長
これは警備会社に機械警備を委託して、何か発生した際に駆けつけていただくという内容です。
吉田
48、49ページ、9款1項5目水防費です。9節旅費の出動手当ということですが、水防訓練なのでしょうか、増額になった理由についてお伺いいたします。
警防課長
これは台風第19号と10月25日の大雨による警戒の出動手当です。
吉田
50、51ページの10款2項小学校費、52、53ページの10款3項中学校費、10款4項義務教育学校費の1目、先ほどの賃金ですが、実際、計画していた延べ日数よりも少ない日数だったという部分について、夏休み中の猛暑によってプールが使えなかったこともこの減の要因の一つになっているのでしょうか。
庶務課長
温度が低いというほかに、猛暑ということもあると捉えているところです。
吉田
そのように天候によってプールが使えなくなった際に、監視補助員はその日の予定をあけてくれているわけですが、やはり実際にプールが使えなかったということでそこはお支払いできないことになっているのでしょうか。
庶務課長
その部分については実働日数ということで支払いをしているところです。
吉田
58、59ページ、11款3項1目観光施設災害復旧費19節負担金補助及び交付金のサイクルスポーツセンター走路災害復旧負担金ですが、これは負担金となっております。これまでの工事については工事請負費という形で復旧費を計上してきていますが、ここで負担金となっているのはなぜでしょうか。
商工観光課長
サイクルスポーツセンターを復旧整備するに当たり、走路の一部区間について県が整備する自転車道路と隣接しているところがあります。そこの工事について、アロケーション、要するに配分によって整備するもので、県に依頼するものとなっております。
吉田
では、その県との配分の割合についてお伺いいたします。
商工観光課長
名取市は実費負担で、境界防護柵については2分の1となっております。
吉田
広報等配布手数料を計上されていますが、民間の業者を間に挟んで名取市から住民に広報紙等を配布するといったときに、どういう形で配達をしてもらうかをもう少し具体的に聞きたいのです。例えば、広報なとり何月号とそれに伴う公民館だよりなどを一まとめにしたものを封筒に入れて、それを一つの郵便物として、本市の職員が全世帯分のシールを張っていつでもそれを郵送できる形にして業者に持っていくのか、それともシールは業者で張ってもらうのか。シールなのか手書きなのかわかりませんが。もしくは住民のデータをまとめてデジタルデータとして配布業者に渡してしまって、それを参考にして配布業者に各世帯に運んでもらうのか、どのようにお考えなのでしょうか。
総務課長
まず、配布していただくものについては、現在は市の職員が庁舎内のスペースを使って1世帯ごとにまとめる作業をしておりますが、そういったところも全て業者にお願いすることになります。業者側で配布物は全てまとめて、一つの世帯分のパッケージをつくって配布するという形になります。配布先の情報をデジタルデータで渡すとか、そういったことは今後業者が決まった際にそこで調整をしていきたいと考えております。
吉田
それはこれからでは遅いと思います。それはあらかじめ決めた上で、こういった予算をつけていくことになるのではないかと思います。業者とはいえ、法律に基づいてそうした個人情報を扱うことにはなろうかと思いますが、これまで区長は市の職員ですから名取市と住民との間の直接の関係の中で広報の配布業務をしていたわけですが、間に民間の業者が入るということは、住民の個人情報を民間の企業に渡さなければならない、委ねなければならないことになります。これは今の名取市民一人一人にそれでよろしいかどうかをきちんとお聞きしなければいけないのではないでしょうか。そこまで名取市にお任せして民間業者に自分たちの個人情報が渡されることを何も問題がないと全ての住民が捉えていると、市としては今理解しているのでしょうか。
総務課長
説明が不足して大変申しわけありません。委託業者を公募する場合には当然仕様書をつくります。その業務の中に、今議員がおっしゃったところについての基本的な部分は当然掲載して、入札に進むことになると考えております。先ほど私が言ったのは、より具体的な細かいところの調整については、業者が決まってから調整させていただくということでした。
吉田
先ほどの続きになりますが、やはり住民からすると重要な住所と名前のデータが業者にどういう形で託されるかが今の御説明ではわかりませんし、それを本当にこのまま進めていくことに対して御理解をいただくのは難しいのではないかと思います。業者に個人情報を委ねることについて、住民に許可をもらうというか確認をしていくということはこれからしなくてよろしいのでしょうか。
総務課長
今後の進め方ですが、広報の配布方法が変わるということをホームページ、広報等で市民の皆様に周知していくことを考えております。
吉田
周知はもちろんわかりますが、ただ周知をするだけであって、あくまでも名取市としては個人情報を民間の業者に渡してしまうと。そして、そのことに対する住民の意見の聴取は行わないと。こういう言い方はあれですが私は非常に強引だと思いますが、そういう進め方でこれから取り組んでいくということでよろしいのですか。
総務課長
繰り返しの答弁になりますが、お認めいただければ、基本的にはこれから業者を公募して入札をして、市民の皆様には各媒体を使ってお知らせをしていくという考えです。
(議案第114号 町の区域を新たに画すること)
吉田
以前に議員協議会でも御説明いただいていましたが、そのときに確認できなかったのですが、今回、この区画整理事業の区域外の部分でこうして地名が変わることによって影響を受ける、例えばもともと町名がついていた部分があってそれが違う地名になったりという区域はないのでしょうか。
復興区画整理課長
区画整理事業区域外ということですが、この議案資料の2ページの赤い線のところが今回の区画整理の区域となりますので、漁港等について新たに町名を付するということが発生してきます。
吉田
新町界という青い線の外側の部分で、例えば旧閖上七丁目の南側の緑の線のあたりなどはどこに含まれるのかなと、ここに地名が書いていないところがあるのですが、こういった部分は旧地名のまま今後も続いていくということでよろしいのですか。
復興区画整理課長
議員お見込みのとおりです。