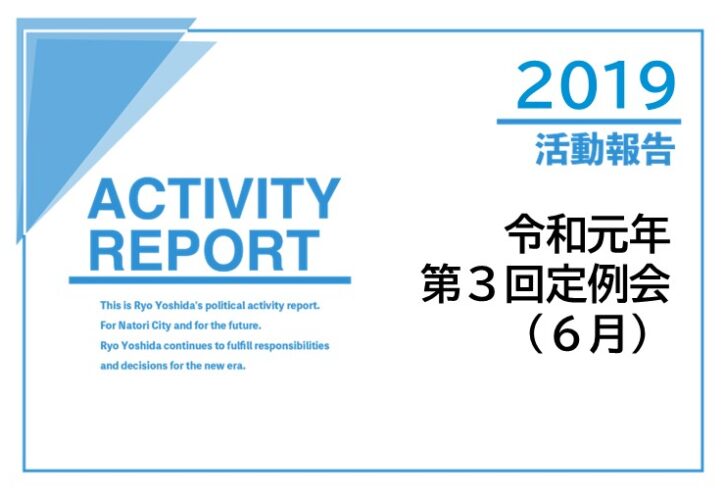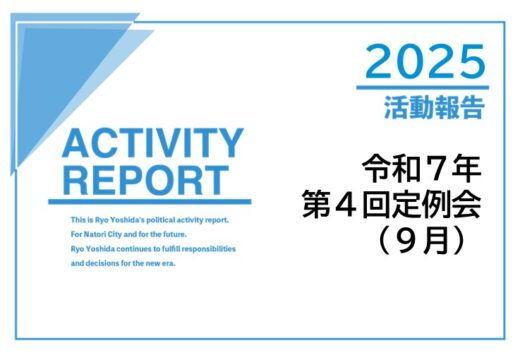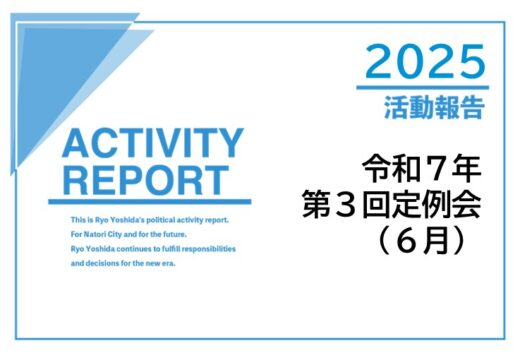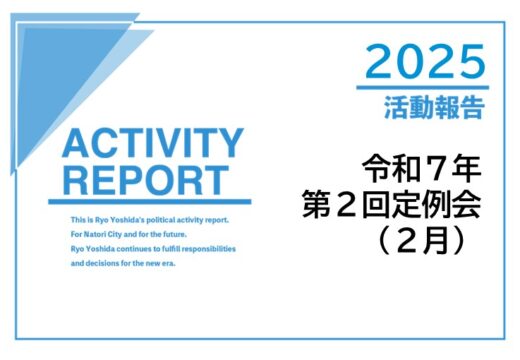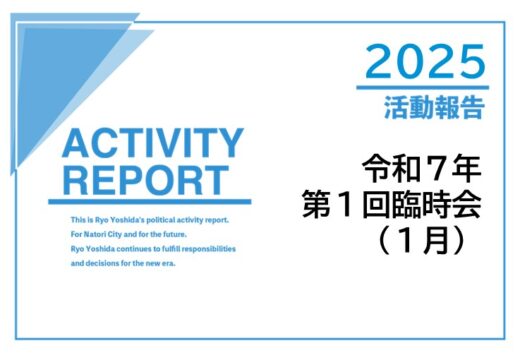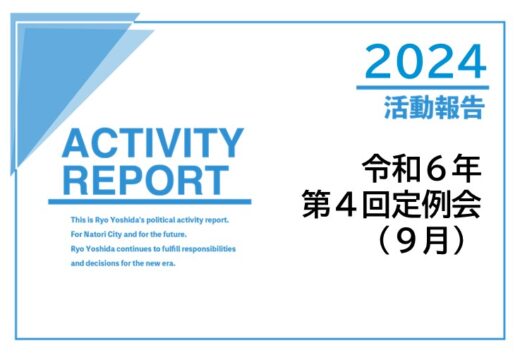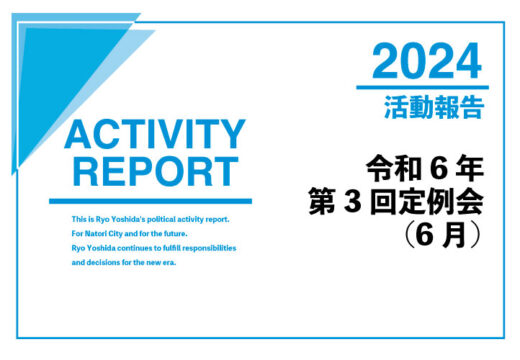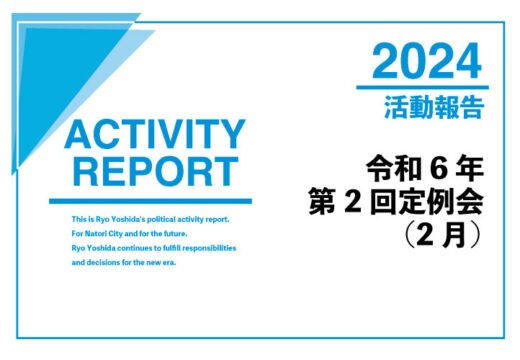本会議
(議案第49号 専決処分の承認)
吉田
歳入歳出全部ということなので確認したいのですが、歳入8、9ページの一番下の21款1項5目教育債、図書館建設事業に対する起債ということで、歳出のほうを見ると財源更正ということで、地方債のほかにその他として500万円計上されています。その他の500万円というのはどこから出てきたのかについて伺います。
財政課長
こちらは寄附金で、図書館の中の子供の部屋に使ってほしいということでいただいた寄附金を充てているものです。
吉田
それはこの歳入の部でいうと、6、7ページ、17款1項1目の一般寄附金になっていて、その中の一部ということでよろしいですか。
財政課長
8、9ページ、18款2項7目のふるさと寄附基金繰入金のほうに含まれております。
(議案第51号 名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)
吉田
報酬の額が変更になることとあわせて、立会人の確保がしづらい状況の中で、若い方にそういうことをやっていただく取り組みが始まっている自治体もあります。この改正は今年度からということで、例えば報酬を時給にして渡すとか、学生など丸々1日立ち会いも難しいと思うので、1日を何時間かずつに分けてお支払いするということも考えられると思います。そのような検討は今どのくらい進んでいるのでしょうか。
選挙管理委員会事務局長
時間給ということですが、現在条例では日額として規定していますので、時間で従事していただくのは難しいと考えています。ただ、ことしの夏の参議院議員の選挙から、市内の大学生を期日前投票の立会人として日額で、1日対応でお願いするということで、選挙管理委員会としては考えております。
吉田
新しい取り組みとして、大学生を立会人として1日お願いするということです。隣の岩沼市では18歳以上で募集していて、午前8時15分から午後8時15分までという1日の部分もあれば、午前8時15分から午後5時15分までなど、時間を幾つかに区切って、より応募しやすい内容となっています。本市はまだ条例などの整備が整っていないということでしたが、今後そういう検討についてはいかがお考えですか。
選挙管理委員会事務局長
選挙管理委員会としては、今のところ日額で日給として考えております。
一般質問
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問を始めさせていただきます。
初めに、大項目1 高齢者の自動車事故対策と外出支援についてお伺いいたします。
自動車は現代人にとって生活必需品となっていますが、便利である反面、操作を誤れば人の命を簡単に奪う凶器にもなります。自動車を運転する人は誰もが加害者になり得ますし、自動車社会で生きる以上は誰もが被害者になり得ます。その意味では、年齢を問わず全ての人が自動車事故の当事者にならないよう気をつけなければなりません。
交通事故の全体の件数は年々減少傾向にありますが、近ごろ高齢ドライバーによる死亡事故が全国で多発し、平成31年4月19日に池袋で起きた暴走事故では、幼い子供と母親が犠牲となったことで全国に悲しみが広がりました。飲酒運転やスマートフォン等を操作しながらの悪質な事故とは異なり、操作ミスや認知の欠如から発生する高齢者の自動車事故は事故そのものが悪質とは言えないことから、やりきれなさが残ります。被害者、そして加害者を出さないために何ができるのか、行政として考えていく必要があると思います。まずは現状を確認させてください。
小項目1 高齢者による自動車事故が社会問題となっている。本市における高齢者による自動車事故の発生状況と防止対策について、市長にお伺いいたします。
市長
高齢者の交通事故防止は、毎年、春と秋の交通安全市民総ぐるみ運動でも重点目標の一つとなっております。岩沼警察署によりますと、平成30年中の本市における高齢運転者の事故は、加害、被害合わせて57件、死亡が4人、負傷者が70人となっています。
対策といたしましては、高齢者に対する交通安全教育の推進として、岩沼警察署との共催や交通指導隊による高齢者交通安全教室の開催、啓蒙・啓発事業として、交通安全母の会による高齢者世帯訪問事業や高齢者に対する交通事故防止声かけ運動などを、交通安全運動期間を中心に展開しております。
また、ハード面においても、高齢運転者に限らず誰もが通行しやすい安全な道路を目指し、事故防止のための防護柵の設置、交差点へのカラー舗装の採用や破線誘導による明確化など、道路交通環境の整備に努めております。
高齢者の交通事故防止は喫緊の課題でもありますので、今後とも重点を置いて努めてまいります。
吉田
さまざまな対策を講じているということは確認できました。それらの対策がしっかりと効果を発揮しているかどうかはどのように検証しているのかお伺いいたします。
防災安全課長
全体としては件数が減少しているのは間違いありません。しかし、高齢運転者の事故については、平成29年、平成30年は、平成28年から比べると少し減っていますが横ばいであり、先ほど対策として挙げた高齢者交通安全教室や啓蒙・啓発事業を引き続き行っていくことが一つの対策ではないかと考えています。
吉田
検証は難しいのは確かだと思います。ただ、現在、法律上、70歳以上の人が自動車運転免許を更新する際には高齢者講習等を受けなければならないと定められています。つまり、法律上も、70歳以上の高齢者の中には正常な運転ができなくなっている人がいるかもしれないという前提に立っているということであり、認知能力や運動能力が衰えていく年齢の方には、極論すれば、運転そのものをやめていただく、運転免許証の自主返納が一番の事故防止ではないかと考えられると思うのですが、そのようなことについて市として取り組んでいる内容はあるのでしょうか。
市長
運転免許証の自主返納については御本人が判断することだろうと思っております。本市も比較的若いまちとはいえ高齢化が進んでいる現状があり、やはりそれぞれの方が生活の中で車を使わざるを得ない環境もあるのだろうと思います。市としては、高齢者の方の運転に対して、注意喚起や啓発などといった側面からしっかりと広報していきたいと考えております。
吉田
海外では国の法律で年齢の上限も設けているところもありますが、日本にはないので、今できることは何かといえば、心配になってきた方には自主的に返納していただくということかと思います。ただ、実際には、市長がおっしゃったように、免許証を手放して車が運転できなくなると買い物や病院などに行く手段が非常に限られるため、大変自主返納が進みづらい状況にあると思います。 先ほど菊地 忍副議長が福祉バス乗車券等の交付事業を取り上げていましたが、この事業に対する市の捉え方として、あくまでも社会参加という面だけなのか、それとも結果として免許証の自主返納につながることに期待を持っているのかどうかお聞きしたいと思います。
市長
福祉バス乗車券等交付事業については、高齢者による運転免許証の自主返納が世の中の大きな話題になる前から続けている事業であり、それだけを趣旨として進めている事業ではないと捉えております。
吉田
自主返納については小項目3で詳しく聞きますが、なぜこのようなことを聞いたかといいますと、次の項目に移りますが、ある書籍に書かれていた内容を紹介したいと思います。平成29年に交通死亡事故を起こした75歳以上のドライバーのうち、検査を受けた385人の49%に当たる189人が認知症や認知機能の低下があると判定されました。また、平成29年末の時点で75歳以上の運転免許証所有者は約540万人に及ぶそうです。これからますます高齢化が進んでいきますので、高齢ドライバーによる自動車事故のリスクは高まっていくと考えられます。自動ブレーキ機能がついた車種などもだんだんふえていますが、年金暮らしでゆとりのないような高齢者の方にとって、いつまで運転できるかわからない状況の中、新しい車に買いかえるなどの余裕はほとんどの方が持っていないと思います。
この問題に本気で取り組む姿勢が行政に求められますが、組織として現在の本市の組織機構がどうかといいますと、その課題に十分に対処できるような部分が物足りないのではないかと私には思えます。
そこで、小項目2 本市では現在、高齢者の社会参加は介護長寿課、交通安全対策は防災安全課が所管している。高齢者による自動車事故を防止するための関係事務を一元化すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
本市における高齢者関係業務として、社会参加については介護長寿課が所管しており、主な取り組みとしては、バス・タクシー券交付事業や通いの場、ふれあいサロン、生きがいづくり支援事業などがあります。
また、交通安全対策については、高齢者の自動車事故防止も含め防災安全課が所管しており、さきに述べたとおり、高齢者安全教室や高齢者世帯訪問等の事業を実施し、事故防止に努めております。
高齢者による自動車事故を防止するための関係事務を一元化すべきとの御質問ですが、現に自動車事故防止の観点では、防災安全課が一元的に事務をとり行っているところであり、現在の対応を継続していきたいと考えております。
吉田
防災安全課でまとめて行っているということですが、これから高齢者の運転についてより広く捉えていく中で、いろいろな策をこの後提案させていただくことになると思いますが、現在の本市の組織を見ると、いずれは震災復興部を廃止というか解体して組織改編が行われると思います。そういった今後の組織のつくり直しの際に、このような観点を取り入れて、より時代の変化に即した新しい組織機構にしていこうといった市長の思いについてはいかがでしょうか、確認させてください。
市長
組織機構の改編に当たっては、常に時代の要請に応えられる形で取り組んでいくべきという基本的な考え方を持っております。ただ、高齢者による自動車事故対策をどのような形で抜き出して、どこに張りつけていくかといったことについては、課題も多いのではないかと捉えております。
吉田
では、次に移ります。
先ほども指摘しましたが、運転能力に自信がなくなってきた高齢ドライバーに免許を返納していただくという一つの形があります。しかし、自動車は生活必需品となっていることから、高齢となって肉体的な衰えを感じたとしても、タクシーに自由に乗れるような人を別とすれば、自家用車に頼らなくては生活が成り立たないのが現状です。大抵の高齢ドライバーは、杉 良太郎さんのように免許証の自主返納を決断することはなかなかできない状況にあります。
現在、県内には免許の自主返納の支援に取り組む自治体があります。例えば大崎市は、ことし4月から、自主返納者に対し市民バスなどの運賃を1年間半額にする事業を実施しています。栗原市は、平成17年度以降に免許を自主返納した人に対し、公共施設の入館料が免除になるプラチナパスを交付しています。調べた範囲で、県内で18市町村が何らかの自主返納支援を行っています。また、民間企業でも宅配無料サービスや施設等の利用割引などの取り組みが広がっています。ただ、一方で、本市では自主返納の支援を行っているとは伺っておりません。
そこで、小項目3 運転免許を自主返納するなど自動車の運転資格を有しない高齢者を対象に、民間バスや公共交通を一部負担で利用できるパス券事業を実施し、外出を支援すべきと思いますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
高齢者による交通事故が大きく報じられる中、高齢者の運転免許返納の流れが全国的に広がっており、市といたしましても、返納後の生活に支障が出ないよう環境整備を行っていくことは必要と考えております。
本市では、現在、自動車の運転資格を有する、しないにかかわらず、満75歳以上の高齢者を対象にバス・タクシー券の交付事業を行っており、平成30年4月からは、なとりん号の充実等にも努めてきたところです。
御質問にあります高齢者の外出支援については、公共交通ネットワークのさらなる取り組みも含め、総合的に研究していきたいと考えております。
吉田
ですから、先ほど例に挙げた福祉バス乗車券等交付事業についてはあくまでも社会参加ということで、免許証の自主返納には直接つながっていないということで、やはりそこを全体的に一元化して捉える必要がどうしても出てくるのではないかと思うのです。
例えば、また別の例で特に運転免許の自主返納とは関係ないのですが、富谷市では、外出支援乗車証として「とみぱす」を発行している事業があり、70歳以上の人が年間1割の負担で2万円分まで公共交通を利用できます。これは、市民バスばかりか、仙台市営地下鉄も利用可能です。このように富谷市では免許を持っている方も持っていない方も対象にしていますが、例えばこれを免許証を所有していない方に限るとか、利用者負担率を1割ではなく2割、3割ともう少し負担してもらい支出を抑える形にして、本市として事業に取り組むことに関して市長のお考えをお伺いしたいと思います。
市長
住みなれた地域で安心して末永く暮らしていただくという観点から、高齢者の外出支援を行うことについては私は有意義であろうと思っております。ただ、その形として、より公共交通の中身を充実させていくほうが先なのか、それとも御提案のような優遇策を用いたほうがいいのか、財源の絡みもありますし、先ほども申し上げた外出支援のあり方についてはいろいろな形があると思いますので、そういったことを総合的に考えていきたいと思います。
吉田
ですから、どちらが先かという議論になりますと、やはり今のように所管が違う状況ではいつまでも議論が進まない、堂々めぐりのままですので、一元化はそういう意味でも大事かと思います。そして、今の市長の答弁によると交通そのものの充実も一つの課題と捉えていると思いますので、小項目4に進みたいと思います。
本市が手がけている公共交通として、なとりん号があります。大きな改定は5年に一度で、前回は昨年の4月でした。全体の利用者数は増加傾向にあるとはいえ、通勤通学の時間帯以外は相変わらず乗客数が少なく、本数や路線については改善の余地があります。路線バスはバス停の位置が決まっており、一定の間隔で設置されているため、歩いてバス停まで行くのも大変だという声が特に高齢者層から聞こえてきます。このような理由から、免許を返納しても、なとりん号があるから大丈夫と考える高齢者は少ないと思われます。
近年、路線バスとは異なる、新たな形態の乗合タクシーを導入する自治体がふえています。いわゆるデマンド型乗合タクシーです。岩沼市では平成30年2月から運用を開始しており、対象区域がその後拡大されるなど、利用者からの評判は高いようです。本市にも、震災前の平成22年にデマンド型乗合タクシーの導入を提案した、先見の明のある議員がいらっしゃいました。山田司郎さんという方です。路線バスの中で特に生活路線やコミュニティー時間帯の廃止や大幅な見直しを行い、その分の財源を高齢者の日常生活を支える足として注目されているデマンド型乗合タクシーに振り分けるべきというこの方の御意見に私は大賛成です。
そこで、小項目4 路線バスとデマンド型乗り合いタクシーの組み合わせによる新たな公共交通体系の確立に着手すべきと考えますが、市長のお考えをお伺いいたします。
市長
議員御提案の、高齢者の自動車事故対策と外出支援としてデマンド型乗合タクシーを導入することは、有用な手段の一つであると捉えております。
一方で、なとりん号については、平成30年度から令和4年度までの期間において、さらなる利便性の向上を図るため便数の増便と路線の見直しを行ったばかりです。したがって、まずは見直しを行った結果の検証を優先すべきと捉えており、その上で、新たな公共交通体系の確立に着手すべきか否か、判断していきたいと考えております。
吉田
見直しの効果の検証は、既にその前の改定に対して行われていなければいけないはずで、それを言っていたら、いつまでたっても新たなことはできないという流れになってしまいます。デマンド型乗合タクシーの導入について、先ほど紹介した山田司郎議員は恐らく市長と同一人物かと思うのですが、今のような御発言、御答弁を当時の山田議員に対して市長がしたとしたら、山田議員は納得すると思いますか。
議長
議題から大きく外れております。吉田 良議員。
吉田
では、実際に市長の選挙公報を振り返ってみたところ、その中に公共交通の充実、高齢者の日中の移動支援とありました。そして、市長の後援会のビラにもデマンド型乗合タクシーへの言及がありました。同じく公約の一つである仙台市営地下鉄の南進がありますが、どちらが実現性が高いと思いますか。
山田市長が議員時代の平成22年に茨城県神栖市の例を紹介されており、数字まで挙げていて非常に鋭い分析だと思います。総務消防常任委員会でも、平成29年5月に福岡県八女市を訪れて予約型乗合タクシーについて視察を行いました。これは電話予約によるドア・ツー・ドア方式で、土日、祝日を除き1日8便、10人乗りワゴン型タクシー12台を運行しています。公共交通分野の導入前と導入後、平成23年度の収支を示されまして、導入前の支出が約8,400万円であったのに対して導入後は約8,800万円と、それまで運行されていたコミュニティバスを廃止するなどいろいろな工夫を行ったことで、増額する経費を約400万円に抑えたと説明されました。
また、もう一つ、これはぜひ調べてもらいたいのですが、導入に当たって地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金、それから維持管理については地域公共交通確保維持改善事業費補助金を活用しています。こうした補助金がせっかくあるのですが、これらについて本市ではどこまで把握しているのか、現状をお伺いしたいと思います。
市長
私は現在の段階でデマンド交通そのものを否定しているわけではありません。ただ、バス路線については大幅な拡充を図って、その分お金も投資していますので、その検証はしっかりと行わなければいけないと思っているところです。 御質問の件については、担当より答弁をいたさせます。
政策企画課長
議員御紹介の補助制度について、現在資料を持ち合わせておらず、詳しい内容は承知していませんので、今後調査をしたいと考えております。
吉田
今申し上げた補助金は国のどの省庁が所管していると思いますか。
今の補助金は国土交通省の所管です。交通機関というと、本市では答弁にあったように総務部の防災安全課ですが、国では国土交通省の所管ということで、やはり専門とは違う国の機関が所管している補助金もあるわけです。そのようなことにもっと目を配っていくためにはやはり組織の改編が必要ではないかと思うので、今後の検討としていただければと思います。
デマンド型乗合タクシーの導入については、高齢ドライバーの運転免許自主返納につなげていくような視点も当然必要になってくると思います。先ほど例に挙げた福岡県八女市の予約型乗合タクシーは、導入以降、利用者数が減少傾向にあることも説明されました。ただ、これも自家用車を運転する高齢者の割合の増加が要因の一つではないかと説明に当たった職員は分析していました。
高齢ドライバーによる悲惨な事故をなくすと同時に、公共交通を持続可能なものにしていくため、運転資格を有しない方が使いやすく、親しみやすい新たな公共交通体系の確立を強く求めていきたいと考えております。以上で大項目1を終わります。
次に、大項目2 和装文化の振興についてお伺いいたします。
日常生活において和服を着用している人を見る機会はそれほど多くありません。日本人が洋服を最初に取り入れたきっかけは、江戸時代末期における軍制改革であったと考えられます。和服よりも動きやすいという理由で西洋式の軍服が採用されたようですが、明治期に進められた近代化政策により、軍ばかりでなく民間人にも少しずつ洋装が浸透してきました。しかし、当時はまだ洋服は和服に比べて非常に高価でしたので、一部の富裕層しか所有できなかったという歴史的な経緯があるようです。現在、歌舞伎俳優や相撲取り、料亭のおかみなど和服を日常的に着用する職業もありますが、そういった方を見かけることはごく少ないのが現状です。洋服は安価になった一方で和服は高価で、明治期とは現在逆転しています。
ただ、そのような現代の日本においても、国際化が進展していく中、固有の伝統文化を大切にしようという機運の高まりが感じられます。学習指導要領には、ゆとり教育から転換した平成23年の改訂で伝統文化の尊重が教育の目標として規定されました。そして、明くる平成24年度から使用された中学1年生の家庭科教科書には、和装に関する記述が掲載されました。このことについて、平成27年9月議会で星居敬子議員が一般質問で、中学校の技術・家庭科の時間に日本の伝統衣装である浴衣等の着物の着つけを学べるようにすべきと提案したのに対して、教育長は、平成26年度、市内の中学校の家庭科の時間では、5校中3校において外部の専門家にお願いして浴衣の着つけの教室を実施し、説明をお聞きした後、実際に着つけの体験をしていると答弁されております。それから約4年経過していますので、その後どのような進展があったのか確認をさせていただきたいと思います。
小項目1 中学校の技術・家庭科において、和服の基本的な着装についてどのような取り扱いが行われているのか、教育長にお伺いいたします。
教育長
中学校学習指導要領技術・家庭編では、家庭分野の衣生活・住生活と自立において「衣服の選択と手入れについて、次の事項を指導する」とあり、「衣服と社会生活とのかかわりを理解し、目的に応じた着用や個性を生かす着用を工夫できること」と示されております。また、内容の取り扱いには「和服の基本的な着装を扱うこともできること」とあります。
現在、市内の中学校で使用している教科書では、「伝統に息づく和服の文化」として、「ゆかたを着てみよう」「ゆかたのたたみ方」の2つの活動を取り上げています。
昨年度、幾つかの中学校では、地域の方々の協力をいただきながら実際に浴衣を着る活動に取り組みました。和服に関する指導において、必ずしも実際に着つけを行うことが求められているわけではないため、各学校の教育課程や実情に応じて行っているのが現状となっております。学校数で申し上げますと、昨年度は市内3校で行っております。
吉田
中学校3校でということで、前回の4年前と同じかと思いますが、大変協力していただける着つけの先生方がいらっしゃるということで、生徒たちの受けとめ方も非常に好意的だと伺っています。生徒たちが体験の教室を受けて感想を書いたものを借りてきたのですが、着物について理解が広まったとか、今後もっと大切にしていきたいといった生徒の反応があります。そして写真もお借りしてきましたが(写真を示す)、おじぎの仕方等の所作などについても学んで、いろいろな性格の生徒がいますが、やんちゃな少し落ちつきのない生徒でも本当に楽しんで授業に参加していたという経緯があったようです。教育長は、このような着つけの授業について御自身で視察されたことはあるでしょうか。
教育長
和服の着つけの授業そのものを視察したことはありません。
吉田
今年度も予定されているそうなので、現場を見ていただければ、本当にこの授業の効果として、単に和服の知識を身につける以上のものを得ていることを実感されると思います。
そして、次の質問に関係してしまいますが、指導に当たっている家庭科の教員はしっかりと着つけを指導できる知識と技能を持っているかどうか、現状でどのように捉えているかお伺いしたいと思います。
教育長
着つけ体験をした生徒の感想等の御紹介もありましたが、私は、学校の学習活動においていろいろな体験を行うことは非常に大事なことだと思っております。ただ、先ほどの答弁でも申し上げましたが、この学習は和服の着つけをすること自体を目的としているわけではなく、着つけを取り扱うこともできるという内容とされていて、狙いは別なところにあります。そういったことから考えても、家庭科の教員が必ずしも着つけのスキルを身につけていることが必須であるとは考えておりませんし、中学校の家庭科の全ての教員がそのような技能を身につけていることはないと認識しております。
吉田
次の質問に移りますが、来年度から新しい学習指導要領が実施されます。現行の中学校の学習指導要領では、教育長がおっしゃったように和服の基本的な着装を扱うこともできるとあり、これは「扱うこともできる」なので、扱わなくていいとも拡大解釈できると思うのですが、新しい学習指導要領によると、「日本の伝統的な衣服である和服について触れること」と義務的な取り扱いになっていると確認しました。「また、和服の基本的な着装を扱うこともできること」ということで、着装に関しては現行と同様ですが、触れることについては必ず触れなければならないと改訂されたと伺っています。ですから、家庭科の先生方にはやはり和服について授業で触れられるだけの知識と経験が必要になると考えます。
ただ、教育長がおっしゃったように、残念ながらそこは不十分な部分があるのかもしれないといいますのも、やはり今、日本の建築は徐々に和室が減っていったり、家庭科の先生でも着物を着る機会は多くないという方がほとんどかと思います。そこで、新学習指導要領の目標をしっかりと達成できるように、私は研修の機会を設ける必要があると考えております。 そこで、小項目2 家庭科教員への和服の着つけ研修を充実させるべきについて、教育長の御見解をお伺いいたします。
教育長
繰り返しになりますが、学習指導要領では、「和服の基本的な着装を扱うこともできること」と示されており、家庭科教員が地域や民間の方々の協力を得て実施している学校もあります。 着つけの仕方そのものは必須ではなく、また学習の狙いそのものではありませんので、家庭科教員への和服の着つけに限定した研修については考えておりません。
吉田
現状の学習指導要領ではおっしゃるとおりですが、新学習指導要領の解説を読めば、取り扱い方の重さがもう少し増していると感じられると思います。着つけの体験を行っているボランティアの方と、資料をお借りする際に直接お話しして、家庭科の先生方に教えるための研修もぜひ協力します、できますという言葉も伺いました。ですから、そのような方の協力を仰いで本市独自に家庭科の先生を対象にして研修を行ってはいかがかと思いますが、教育長の御見解をもう一度お伺いしたいと思います。
教育長
新しい学習指導要領ですが、令和2年度から完全実施されるのは小学校で、中学校は令和3年度からになります。家庭科の内容について、基本的には現行の学習指導要領と大きく変わっているとは認識しておりませんが、先ほども申し上げたように、今話題になっている和服について取り扱っている中学校の家庭科の衣生活・住生活と自立という大きな単元の中で、教科書でいうと11ページ分を5時間で取り扱う内容の一部に和服が登場します。それは、自分らしい生き方、衣服の働き、衣服の構成、衣服の選び方、環境に配慮した衣生活の中の衣服の構成において、和服と洋服の違いに着目しようというところで和服が登場してきます。
実際に和服の着つけを扱うと少なくとも2時間はかかります。この内容を5時間で指導することを考えたときに、先ほども申しましたが、和服の着つけを身につけることが目的ではなく、衣生活に対し目を向けて、その中で自立した衣生活ができるよう子供を育てるのが狙いです。当然、いろいろな団体の方が厚意で学校に出向いて指導してくださるのは大変ありがたいと思っておりますし、中学校の家庭科に限らず、さまざまな学校の教育活動の中でボランティアの方々の協力をいただいて大変ありがたいと思っております。ただ、だからといって、全ての方々の思いを学校が受けとめて教育活動に取り入れていくことは非常に困難だと思っていまして、繰り返しになりますが、各学校で全体的な教育課程の編成の中で考えて行っていますので、教育委員会として着つけに特化した研修の実施は考えておりません。
吉田
短い時間であるからこそ、その中でより内容の濃い授業を行うことが何よりも生徒たちのためになると思いますので、今すぐにとはなかなか言えないと思いますが、一つの選択肢として考えていただければと思います。
では、小項目3に移ります。
近年では小学校の卒業式に和服で臨む児童が増加しています。私も毎年地元の小学校の卒業式にお招きいただきますが、和服着用の児童が男女ともふえていると感じております。こうした風潮に対し、華美を競うべきではない、また、格差を助長するのではないかという批判的な意見がある一方で、伝統文化を尊重するのは大切なことであると前向きに捉える声もあると伺っています。
本市ではまだそのような論争にはなっていませんが、ただ、学習指導要領に定める卒業式の趣旨からもし大きく逸脱したり、着装の乱れによる式進行上の問題が発生したりすれば、教育委員会として何らかの対応をとらなければならなくなるかもしれません。ふだん和服を着たこともない児童が、ある日突然和服を着て、式が終わるまで過ごさなければならないとなると、通常の動作やトイレなどが原因で着崩れしてしまうことは十分にあり得ます。そうなれば児童本人が直すことはほぼ不可能で、周りの保護者や教師がサポートしなければ、せっかくの卒業式も笑いのエピソードに終わってしまいます。そこまで心配するなら和服など着なければよいと突き放すことは簡単ですが、和装文化のすばらしさがさらに多くの方に理解されることにつながれば、なお喜ばしいと私は捉えております。
そこで、小項目3 小学校卒業式に和装で臨む児童が増加傾向にある。着崩れ等に対応できるよう保護者と小学校教員向けの着つけ講習を実施すべきと考えますが、教育長の御見解をお伺いいたします。
教育長
市内の小学校10校に確認したところ、和装の児童がいた学校は7校、いなかった学校は3校です。増加する傾向が見られると回答があった学校は4校でした。
卒業式への和装での参加については、児童の体調面や安全面、保護者の経済的負担を考えると、課題も多いと捉えております。
小学校の卒業式での服装については、基本的に各家庭での判断と捉えていますので、保護者と小学校教員向けの着つけ講習の実施については考えておりません。
吉田
そのような点についても地域の方が協力してくれることもあり得ますので、ぜひ地域の力を使って取り組めればいいなと思いますが、どこまで教育委員会として行うべきかということについてはいろいろな議論があると思いますので、御答弁のとおりかと思います。
前回の冬季オリンピックで2連覇を果たした羽生結弦選手は、国民栄誉賞の授賞式に和装で臨み、袴の生地が仙台平であったことなども含めて大変話題になりました。また、和装の世界遺産登録を目指す運動、そして来年の東京オリンピック・パラリンピックを着物で飾ろうというプロジェクトも進められていると伺っています。和装文化が振興していく中で、見た目の美しさ以上に、着物文化とはもったいない精神の一部である、あるいは一体であるということこそが広く知られるべきであると私は思っております。
着物は染めかえができます。より濃い色に染め直して新しい色、新しいデザインにする、あるいは、縫い目をほどいて平らな生地に戻して、そして仕立て直しができるということで、親から子へ、子から孫へと大切に受け継がれてきました。こうした和服の精神的な文化を学ぶことで、子供たちの心に日本の文化への敬意と誇りが生まれてくる、さらに環境についても考えるという意識の醸成も期待されると思います。本市は特に着物の有名な産地ではありませんが、学校において一人一人の人格の完成を目指す過程で、着物に触れる機会を十分に生かしていただきたいと教育長にお願いしたいと思います。
最後の大項目3に移ります。通貨危機に対する備えについてお伺いいたします。
通貨危機とは、通貨の対外的な価値が急激に下がり、その通貨が流通する国や地域の経済に大きな混乱を与えることを意味します。近年では、南米のベネズエラでインフレ率が1000万%にも及ぼうとしている、通貨ボリバルの急激な下落があります。一日のうちで通貨の価値が大きく下がる場合もあるため、品物の価格の設定が難しくなり、国民は物々交換によって必要なものを手に入れることを強いられています。このベネズエラは、石油や天然の鉱物が豊富に産出されるため、南米でも特に裕福な国でした。しかし、チャベス政権期における価格統制など市場原理を無視した政策、また、その後のマドゥロ政権による政策などが原因で、ボリバル通貨は紙切れ同然の価値にまで落ちてしまい、国内の混乱はおさまる気配がありません。
仮に日本円の価値がこのボリバルのように大幅に下落すると、日本銀行が発行している紙幣はもちろん、円建ての債券なども価値が溶け落ちてしまいます。そのようなことはあるはずがないと信じたいのが国民としての心情ですが、現実の世界では、信じる者は救われるというよりは備える者のほうが救われます。この質問が行政もこうしたことに備えなければならないという意識の共有の第一歩になれば幸いです。
まずは現状確認からさせていただきます。小項目1 市が保有する金融資産の総額と外貨建て金融資産の額をお伺いいたします。
市長
市が保有する債権(災害援護資金貸付金)を除いた金融資産は、平成29年度決算において、有価証券が1,025万円、出資金が5億6,872万7,000円、積立基金が249億223万3,000円であり、外貨建て金融資産については保有していないところです。
吉田
平成31年2月定例会の総括質疑において市長から、低金利の状況の中、基金運用に係る収益増を図るため、安全かつ効率的な管理運用の方策について検討していきたいという御答弁があったと記憶しています。このことについて、外貨か日本円かどうかも含めて、基金の管理運用方針を市民に対して示さなければならないと思うのですが、その方針はどのように示していくべきと考えているか確認したいと思います。
日本の財政が非常に厳しい状況に置かれていることは指摘するまでもありません。国と地方を合わせた借金は1,100兆円に達したと報じられていました。これは対GDP比で236%です。アメリカは108%、イギリス86%など、主要先進国と比べて非常に高い水準であると言えます。こうした現状の中、日本政府には500兆円の資産がある、あるいは政府と日銀の資産を連結すると国債残高は相殺できるなどという論もあります。しかし、私にはこれは都合の悪い部分に目をつぶっているようにしか思えません。逆に、日銀そのものの破綻を危惧する識者の声も上がり始めております。私自身、金融や経済について詳しくはありませんが、この2つの考え方、政府と日銀はまだまだ大丈夫という考え方と、日銀は危険水域に入ったという考え方を比較した結果、私は後者により説得力があると捉えるに至りました。
日本政府は莫大な借金を抱えているとはいえ、お金を貸してくれる金融機関がある限り、財政破綻することはありません。しかし、そのお金を貸してくれる金融機関に問題が生じたら、これは大変なことになります。現状では、国債が起債されると、民間銀行や証券会社に入札で販売されるそうです。かつては、こうして購入された国債は銀行や機関投資家が満期まで保有していました。しかし、現在は、早ければ入札の翌日に銀行や機関投資家は日銀に転売するという状況になっています。その結果、日銀が年間国債発行額の約7割を買っているに等しい状態で、日銀の国債保有額は、1998年末時点で52兆円だったのが、2018年5月末時点では459.4兆円へと膨れ上がっています。また、民間銀行から預かっている日銀当座預金残高は、4.4兆円から384.2兆円と激増しています。
何を意味するのかということですが、もし日銀が国債の購入を絞れば、日本政府は資金繰りができなくなります。国債を売り始めてしまうと、国債は暴落して長期金利が暴騰するということで、政府の支払金利が急激に上がります。そして、これまでのように円を刷り続けていくと、ゼロ金利に苦しむ地方銀行が限界を迎えることになります。そして、短期金利をもし引き上げるとなると、日銀当座預金の付利金利の支払いが増加するので日銀の債務超過になるということで、どちらを見ても大変手詰まりの状況であり、異次元緩和というものには出口がなかったということです。
このような状態がいつまで続くかわかりませんが、1つ言えるとすれば、何事も起こらずに収束していくとは考えづらいのではないかということです。ここ最近の地方銀行の経営危機についての報道の多さ、非常に嫌な動きだと私は思います。もし1つきっかけがあると、円と日本国債と日本株、これらは世界中の投資家から売られるおそれがある。そして売りが売りを呼んで、紹介したベネズエラのようなハイパーインフレへと突き進んでいく可能性があることを指摘させていただきます。
そこで、小項目2 出口なき異次元緩和がハイパーインフレをもたらすとの指摘がある。最悪を想定し、金融危機に対応できる体制を整備すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
市民の財産である金融資産を守る対策は重要であると捉えております。平成14年4月1日よりペイオフが解禁となった際には、公金の保護のため、名取市公金管理及び運用基準を制定し、公金保護のための対応方策を検討する体制として名取市ペイオフ対策会議を設置しました。
また、現在、名取市資金運用会議を設置し、資金の安全かつ効率的な管理運用のあり方については、意を用いて研究しているところです。
吉田
日本でハイパーインフレなど起こるはずがないと考えている方がほとんどだと思います。日本円が溶けてしまうようなことはないだろうと。しかし、絶対起きるはずがないと思っていたことが起きた事例はここ最近でも幾つもあります。東日本大震災による大津波や福島第一原子力発電所の事故です。そして、このようなことは想定しておくことが必要ではないか。今、さまざまなリスクについてあらゆる事態を想定すべきレベルまで高まっていると思います。例えば、インフレがとまらなくなってしまうと、職員の給与の支給も大変難しい問題になりますし、上下水道、ごみ処理などが稼働できるかどうかも難しい問題になるわけですが、そういったことに対するシミュレーションの必要性はないと捉えているのでしょうか。
市長
できる限り市民の財産である金融資産を守る対策は自治体としてとっていきたいと考えていますが、基本的に金融危機への対策は国策で行われるべきものであり、基礎自治体が取り組める範囲は非常に限られていると思います。
吉田
市民のお金を預かっているのは名取市であり、日本には国の税があるわけですが、地方自治の観点から見ても、やはり市民の税金をしっかりと守るのは市の役割であることは当然で、いろいろなケースを想定しておくことは必要だと思います。
最後の質問に移りますが、税金、基金は全て円建てであり、仮の話ですが、もしハイパーインフレが起きて日本円が大暴落すると全て溶けてしまうことになります。しかし、ハイパーインフレから財産を守る方法もあります。これは円建ての金融資産の保有割合を下げることです。例えば金は大きく値動きすることはないと言われていますし、機軸通貨のアメリカドルはFRBでしっかりと管理されています。万一、日本円が暴落しても、これらの資産にかえていればダメージを最小限に食いとめることは可能と考えられます。
ただし、注意しなければならないのは、こうした資産は必ずしも元本が保証されるわけではないということであり、その部分を例えばある種の保険のように捉えて認めるかどうかとなれば、これは市民の判断であり、すなわち議会の判断になるものと思います。ただ、いずれにしましても、今そうしたことを考えるための材料が全く示されていないという現状には、私はいささか不安を覚えます。
そこで、小項目3 外貨建て金融資産や金などの貴金属に資産を分散するリスク管理を研究すべきについて、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
公金の管理運用については、地方自治法など法令の規定等によって、最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならないと定められており、貴金属による資産の保有は想定されていないところです。
しかしながら、資産管理におけるリスクマネジメントについては、他の自治体等を参考にしながら調査研究していきたいと考えています。
吉田
金については、私は地方自治法第239条の物品に位置づけることもできるかと思うのですが、先ほど申し上げたような基金管理運用の指針や方針といったものを市として策定してリスク管理を行うことについては今後いかが取り組んでいくのか、お考えをお伺いしたいと思います。
市長
先ほども御答弁申し上げましたが、名取市資金運用会議を設置して資金の安全かつ効率的な管理運用のあり方について意を用いているところで、そして、基本的には、最も確実かつ有利な方法で安全に保管しなければいけないという法令の趣旨に沿って運用すべきものと思っております。
吉田
通貨として円が一番安全かどうかもだんだん怪しくなってきている状況だと思いますので、資金の運用方針をしっかりと市民に示す形で策定していくことについても今後検討していただければと思います。
以上で私の一般質問を終わらせていただきます。
本会議
(議案第57号 令和元年度名取市一般会計補正予算)
吉田
10、11ページ、20款5項2目雑入の防災ラジオ売払収入とありまして、当初予算の時点で残り台数は約100台という御説明だったと記憶しているのですが、今回計上された金額の内訳についてお伺いします。
防災安全課長
防災ラジオ売払収入ですが、議員お話しのとおり3月の予算委員会で100台近く残っているという答弁をしました。補正をお願いする関係ですが、3月から5月までに売れて在庫が少なく、歳出の防災ラジオ導入委託料で新たに防災ラジオを追加製造をして、1台1,000円で有償配布します。それに伴って雑入での補正をお願いするわけですが、台数は月約20台ということで、残りの月数10カ月で200台の計算ですが、月がまたがっている部分もあって今回190台で補正をお願いしているところです。
吉田
きのうも大きい地震があって、防災ラジオが鳴りました、初めて聞きましたという声もいただきました。追加して使っていただける方がふえることに関しては、大変結構なことだと思います。
毎月20台で約10カ月ということでしたが、追加の分の製造については今回の予算の中で一緒に計上されているのでしょうか。
防災安全課長
新たに台数の追加ということで補正をお願いしているところです。
吉田
6、7ページ、14款2項7目災害復旧費国庫補助金の社会教育施設災害復旧費、補助基本額が3分の2ということですが、この内容を伺います。
生涯学習課長
こちらは被災前の閖上公民館の延べ床面積等を基本として、国と県が協議した上で補助基本額が決定されています。もともとの躯体や備品の一部を認めていただいたということで、こちらに計上されたものです。
吉田
10、11ページ、21款1項6目教育費に中学校建設事業に対する起債とありますが、確認ですが、増田中学校の大規模改修に充てられる分と考えてよろしいですか。
財政課長
議員お見込みのとおりです。
吉田
先ほどの7ページの14款2項6目教育費国庫補助金の額と、こちらを計算すると、実際にかかる現在の予算の工事費に少し足りないくらいかと思ったのですが、この起債の金額を今回の額に決めた根拠について伺います。
財政課長
今回の増田中学校の大規模改修は、工事費を2億4,000万円と見ております。その中で、国からの内示分の補助対象は2億円となっています。残りの4,000万円については、国算定等の単価差分ということで、いわゆる継ぎ足し単独分ということで4,000万円を見ております。国内示分の2億円については、防災・減災国土強靱化緊急対策事業債ということで、1億3,330万円ほど起債をしております。
もう一つ、この増田中学校の大規模改造は、学校教育施設等の整備事業ということで、工事費で足りない分4,000万円の75%の3,000万円、合わせて1億6,330万円と2つの起債を使っているということです。
吉田
13、14ページ、2款1項11目公共交通対策費の19節、乗合バス運行業務欠損補助金の内容をお伺いします。
防災安全課長
乗り合いバス運行業務については、平成30年度より新たに5年間の業務委託を契約しております。この乗合バス運行業務欠損補助金ですが、名取市公共交通計画に基づく乗合バス等運行業務に関する覚書の中で、欠損補助金について取り交わしておりまして、名取市が示した年間収入見込み額に満たない場合は、当該収入見込み額と収入実績額との差額について、5分の4の範囲を上限に欠損補助を行うものとしております。
また、あわせて障がい者運賃の無料化及び割引適用に伴い、年間運賃収入見込み額に著しい影響が生じた場合に、障がい者割引適用補助としてあわせた欠損補助金を算出しているところです。現在、株式会社桜交通、仙南交通株式会社の2社に業務委託を行っているわけですが、今回の欠損補助金については、仙南交通株式会社に当たり収入見込み額が400万円に対し、平成30年度実収入金額が374万7,355円でしたことから、その差額の欠損補助対象額25万2,645円を1,000円未満切り捨てた5分の4、20万1,600円に合わせて、障がい者割引適用補助金額5万1,000円を合計したもので、25万2,600円という額になるわけですが、予算書では25万3,000円ということで補正をお願いするものです。
吉田
今のお話ですと、平成30年度の1年間分の中の見込み額に達しなかったところということだと思います。実際に乗る方が少なかったということかと思いますが、具体的な路線の中で、特にこの路線は見込みよりも大幅に下がっていた等、捉えているところがあれば御説明いただければと思います。
防災安全課長
当該事業者、仙南交通株式会社の運行している路線ですが、路線の増便を図りながら、利用者増を目指したところですが、数字から分析しますと1路線、上余田線というのがありまして、それを廃止した影響があったのではないかと捉えているところです。
吉田
24、25ページ、10款6項5目復興ありがとうホストタウン推進費の復興ありがとうホストタウン推進実行委員会についてお聞きします。2020年東京オリンピックの関連ということですが、パラリンピックについてはホストタウン事業は関係ないのかどうか、そこは確認してもらいたいのですが、先ほど課長の答弁で、全事業費の100%に当たる分だということで今回240万円ということでした。実際にオリンピック・パラリンピックの開催まで、まだしばらく間があるわけですが、この240万円は今年度でその事業が完結し、次年度以降はこの実行委員会の活動はないという認識でよろしいのですか。
復興ありがとうホストタウン推進室長
先にオリンピック、そしてパラリンピックという流れで開催されるわけですが、本市としてはオリンピアンを対象として今取り組んでいるところです。 それと240万円の補助金について、これは実行委員会で主体的に事業に取り組んでいくことになるのですが、今年度の事業の経費として考えている予算です。新年度事業については、今想定はしているのですが、今回立ち上がっていく実行委員会の中で、さらに議論をしてその内容の精度を高めて、新年度の予算の中に反映させていただければと思っているところです。
吉田
100%というのはあくまでも今年度の事業費の分ということかと思いました。先ほど御答弁の中で、協賛金なども今後あり得るというお話でした。そういったさまざまな収入がこれから入ってくることになるのでしょうが、そういったものの会計の報告をしていく中で、もし収入が支出を上回った場合は、この補助金の部分については返還されるという規定になっているのですか。
教育部長
実行委員会については、今はまだ立ち上がっていませんので何ともお答えできませんが、基本的にはこの予算を使って事業を行っていくという考えです。ただ、協賛するとか、そういったところがもし出てくれば、また少し状況が変わってきますが、基本はこの予算を使って事業を執行していくという考え方です。
吉田
20、21ページ、9款1項4目防災費の防災ラジオ導入、販売委託料についてです。先ほど歳入で伺ったところですと、300台という御答弁だったと記憶していますが、およそ450万円として300台だと、1台当たり1万5,000円になるのかと思うのですが、最初にたしか1万台導入された際の当時の単価と比べると、今回どのくらい差が出ているのか、その違いについて伺います。
防災安全課長
防災ラジオの単価ですが、平成27年度には5,000台発注しているところですが、ラジオ自体の単価はその年とほとんど変わっておりません。
吉田
念のためラジオそのものの仕様などで、何か変更点がもしあれば教えてください。
防災安全課長
防災ラジオは、自動電源起動機能、自動同調、チューニング機能、あと内蔵ライト点灯という3大機能があります。これについては引き続き継続していく形で、新たなものは今のところ考えておりません。
吉田
先ほど歳入7ページ、14款2項7目災害復旧費国庫補助金の社会教育施設災害復旧費は、閖上公民館の備品などに充てられる費用という御説明でした。歳出ではどこに当たるのか伺います。
財政課長
先ほどの歳入の社会教育施設災害復旧費については、中身は閖上公民館の災害復旧分、これは平成30年度分で完了しなかったことから、平成31年度で受け入れようとするものです。ということで、事業を充てる分、歳出はありませんので、一般財源の振りかえになるものです。
吉田
22、23ページ、10款3項2目教育振興費の19節負担金補助及び交付金、(一財)自治体国際化協会事業会費とあります。当初予算は52万1,000円で、当初予算では前年度と同じだったのですが、これが増額になった理由について伺います。
学校教育課長
平成31年3月26日に成立した地方交付税法の一部を改正する法律において、JETの参加者の任用に係る負担交付措置の見直しが含まれておりまして、今年度、前年度から1万円値上げになったために、中学校に配置しているALT7名分、7万円を計上するものです。
吉田
24、25ページ、10款6項5目復興ありがとうホストタウン推進費です。首相官邸のホームページで確認したら、各自治体の取り組みの一覧表が出ていて、本市の事業を読むと、今執行部から説明があったことがそのまま書いてあって、その中に「東京大会期間中は市民応援団を結成し大会会場でカナダ選手団の応援を行う」とありました。大会会場で行うということは、もちろんその会場に入場するということだと思うのですが、オリンピックのチケットはたしかもう申し込み期間が過ぎて、販売されているかと思います。今年度の予算で大会会場に入るための措置をしなければ、この事業は行えないと思うのですが、どのようになっているのでしょうか。
復興ありがとうホストタウン推進室長
応援チケットについてですが、5月末現在で東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会からの説明会等々で提供されている情報によりますと、来年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会での参加国に対して、事前合宿を受け入れたり、大会前後に交流したりする全国のホストタウン自治体、私どもの復興ありがとうホストタウンも含みますが、そこに対しては両大会のチケットが30枚ずつ割り当てられると聞いております。それで応援チケットの申し込みの際は、競技や会場ごとに申し込みに枚数の制限がありますが、上限を設定された上で定価で委員会に申し込むならば、30枚の割り当てはあるものの、いずれ定価で購入していただくというお話を伺っております。ですので、新年度の予算に反映していくことになろうかと今は想定しております。
何分にもまだ各自治体でもいろいろと見解、考えがばらばらです。現地に行って応援したいというところもあれば、そうでないという自治体もあって、まだ不確定なところが多分にありますが、そこも含めて県のオリンピック・パラリンピック大会推進課と他自治体の取り組み、そして本元である組織委員会の情報をこれからも注視しながら、確認して進めていきたいと思います。
吉田
チケットが30枚ずつ買えるということで、どのようにしてそのチケットを市民に割り当てるかが、これからの検討課題になってくると思います。もちろん、30枚全部を抽せんなど、しっかり公平性が保たれた中で購入していただくということでいいのですね。例えば、何か特別な役職についている人は、優先的に30枚のうち1枚を割り当てるとか、そういうことはないということでよろしいですか。
復興ありがとうホストタウン推進室長
枚数も、もしかするとこれ以上になる可能性もありますし、また限られたチケットをどのように応援チケットとして運用していくかということも、誰がどんな形でということも現時点では未定です。ですので、今後進めていく中で、そこは明確にして不公平感のないよう、他自治体とも調査研究しながら進めていければと考えております。
(議案第60号 工事請負契約の締結)
吉田
資料2ページの平面図ですが、入り口から入って一番奥の駐車スペースが建物すれすれに車をとめるような形になっておりまして、バックして入れないのではないかと思います。少し先まで車の頭の部分を出してバックするのが普通で、これでは建物にぶつかってしまうと思うのですが、このあたりの考え方を伺います。
それから、身体障がい者用の駐車スペースは、普通は建物に一番近いところに設置されるのが基本かと思いますが、このように離れている理由について伺います。
都市計画課長
まず、身体障がい者用の駐車位置ですが、建物から右側の部分ですが、玄関ポーチが真ん中にあって、北側に着色しているところまでスロープになっております。その南側は壁になっておりまして、建物の近くにつくったとしても、車椅子を利用する場合、真ん中あたりが開口部になっているので、そちらに戻って入るようになってしまうためです。また、北側に駐輪場があるのですが、そちらの動線も考慮してスムーズに使い勝手がいいように、ちょうど真ん中あたりに身体障がい者用の駐車スペースと駐輪場を使う方、自転車利用の方も同じような動線で入っていただくように、この形にしております。
それから、一番建物に近い部分は駐車が難しいのではないかということですが、確かに限られたスペースの中で9台確保しておりますので、常にこの駐車場が満車になるかどうかわかりませんが、ここは切り返してバックで入っていただくようなことになります。
吉田
バックで入るというのは、道路からバックして、駐車場の入り口から既に後ろから入っていかないととめられないということだと思いますが、それは非常に危ないと思います。この施設には小さなお子さんがたくさんいるわけですから、バックを強いるようなことを初めから前提として設計されたとしたら、それは考え直さなければいけないのではないかと思います。この駐車場全体をもう少し東側に寄せることができるスペースが、道路際のところにあると思いますので、そのように駐車場全体を図でいうと右側のほうにずらしたほうが、奥のほうのスペースも前から入っていってとめることができるのではないかと思いますが、今後改善できるかどうか伺います。
それから、この図ではスロープがよく見えないのですが、もし道路側の黒い三角形の入り口のところからスロープが始まっているのだとすれば、駐輪場のあたりや車椅子の方がスロープに乗ろうとする部分は、もう既に段差ができてしまっているのではないかと思うのですが、このスロープの具体的な形を確認したいと思います。
都市計画課長
児童センターの入り口は、側溝等、また門扉もあるので、図面のとおり広いかというとそうでもないのですが、今後、外構工事を発注しますので、その中で検討したいと思います。
2点目のスロープの位置ですが、3ページ右側に通路の部分がありますが、この位置が2ページの着色している部分になりますので、ここからスロープが始まることになります。御理解いただきたいと思います。
吉田
3ページの平面図で伺います。男子トイレの中ですが、いわゆる大の便器が3台ということで、通常見かける小の便器がないのですが、学校なども全て個室にしようという動きが全国的に広がっていると聞いていますが、この設計についてもそのような考えでこのように決めたということでよろしいですか。
こども支援課長
家庭の男子トイレは洋式が大分普及していますので、家庭環境に近いつくりということで今回このようにしました。
吉田
それは大変結構なことですが、使う側として、家庭では例えば男の子も座って用を足させるという指導もしている家庭もふえているという調査結果を見たことがあるのですが、こういうタイプの便器は立って用を足そうとすると、飛び散って汚れがひどくなって、後から使う人が非常に不快な思いをするのですが、そういったところの配慮はどのようにお考えでしょうか。
こども支援課長
運営の中で考えていきたいと思います。
(議案第61号 工事請負契約の締結)
吉田
以前に中央公園の工事のときにもお聞きしたかと思うのですが、今回の街区公園やポケットパークについても、町内会等の活動で使えるような掃除用具、スポーツ用品などをしまっておく倉庫的なものは置けると考えてよろしいですか。
復興区画整理課長
今回の工事の中で、用具等の倉庫等の設置は考えておりません。
吉田
今回の工事でということではなく、今後この地域の方々がそういうものを置きたいというとき、ほかの町内会などでは多くの公園には防災倉庫という形で置いてあるかと思うのですが、そのようなものが置けるかどうかという確認です。そうなったとき、町内会の組織がどういう区域でどう形成されていくかよくわからないのですが、町内会の中に必ず1つはそういうものが置けるようなスペースが確保されているかどうか、今のところしっかり確認できているかどうか伺います。
都市計画課長
これまでのケースでは、町内会等から要望があって設置を認めています。今後どうなるかわかりませんが、町内会が発足して必要だと思えば、申請していただければ設置は可能だと考えております。 市内どこの公園も、特に倉庫の設置位置を決めているわけではないので、利用する方と公園を愛護していただける団体等に支障のないところに置いていただければと考えております。