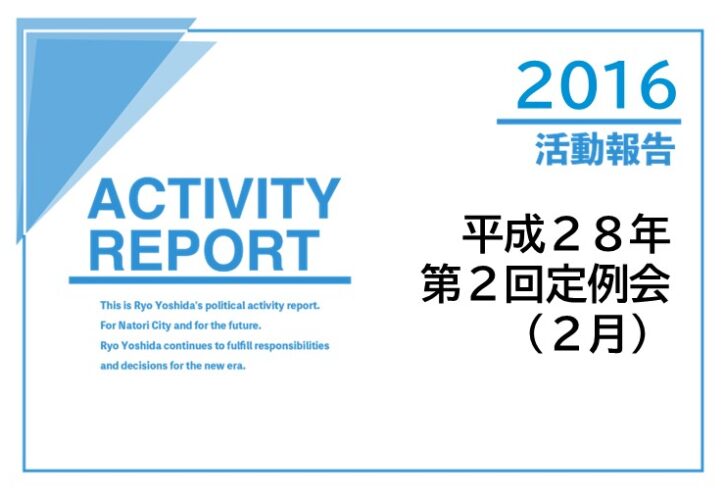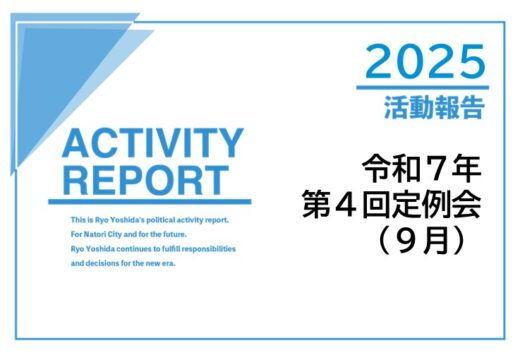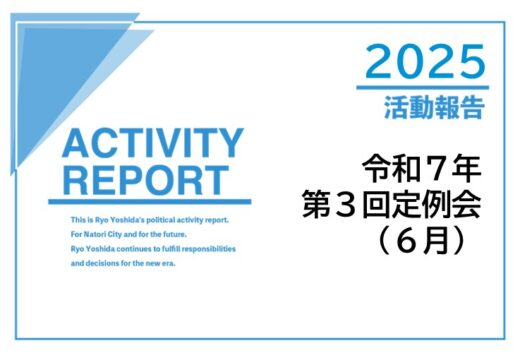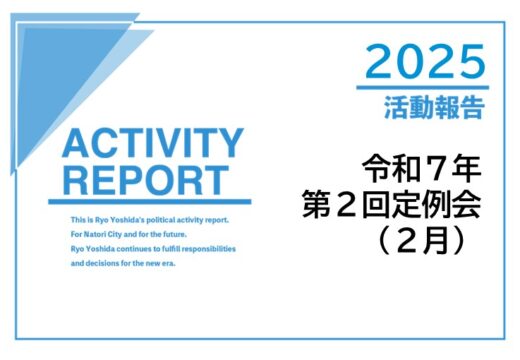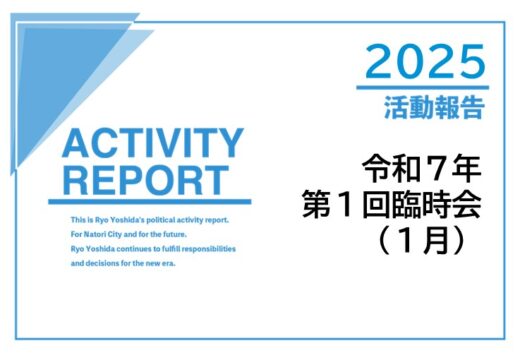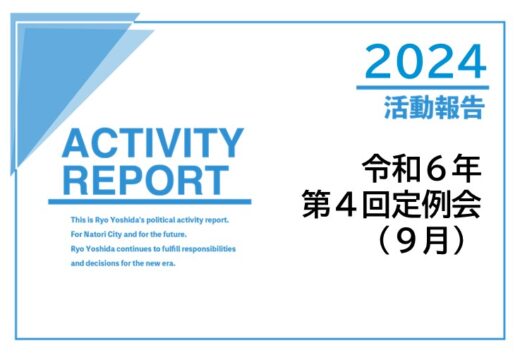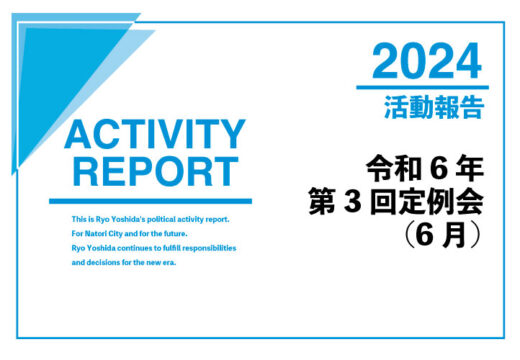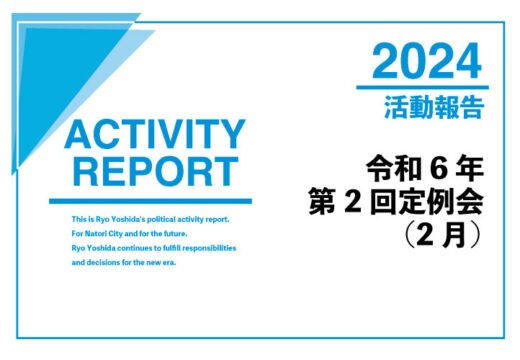一般質問
吉田
市は、地方創生総合戦略を策定し、合計特殊出生率を2030年までに1.80、2040年までに2.07に引き上げ、人口減少に歯どめをかけることを目標としています。しかし、少子高齢化は進むわけですから、税収の減少、社会保障負担などの増大は避けて通れない問題です。負担を求めるだけでは住民の理解は得られません。私たち議員の報酬を含む公務員人件費を初め、身を切る改革が必要です。
そこで、(1)人口減少や少子高齢化が国レベルで進む中、本市が今後も住みよい地域であり続けるためにも、仙台市を含む周辺自治体との広域連携を進め、将来的に合併すべきではないでしょうか。市長にお伺いします。
市長
まず、私自身、どのような形での合併も否定するものではありませんが、市町村合併は、地域の将来や住民生活に大きな影響を及ぼすものであり、市民の方々に自主的、主体的に判断していただくことが大変重要であると考えております。そのためには、市として、正しい判断をしていただくための情報提供や課題提起を行う必要があると考えておりますが、現在、私の耳に合併を望む声は聞こえてきていない状況であり、合併に関する情報提供などを行うべき状況ではないと捉えているところです。当面は、本市独自のまちづくりを推進していきたいと考えております。
その上で、広域連携については、これまでも、ごみ・し尿処理の一部事務組合、後期高齢者医療の広域連合、周辺自治体との広域行政協議会の設置、広域観光の連携など、積極的に取り組んできているところですので、今後とも、市民福祉の向上につながるものについては積極的に連携を図っていきたいと考えているところです。
吉田
ただいま市長から、住民から合併を望む声は聞こえてこないが、広域連携は必要なのでそちらは進めているという御答弁がありました。その広域連携ですが、少子高齢化の進展も含め、そのような人口構造の変化とともに、住民の社会生活圏は既に広域化していることはもう皆様御存じのとおりだと思います。住民は自治体間の境界線などは完全に越えて社会生活を行っています。例えば本市の文化会館や休日夜間急患センターの利用者の多くは、市外の住民の方です。そしてまた、名取市民も仙台市立病院や仙台市営地下鉄などを利用しています。これらインフラ利用の観点からも、住民にとって自治体の境界線はもはやないに等しいものであると言っても過言ではありません。また、仙台市営バスの乗り入れが実現すれば、交通の利便性は現在よりも高まります。さらに、水道事業が統合することによって水道料金のさらなる引き下げが可能となりますし、消防署の管轄区域の見直しによって、通報から到着までの時間短縮等の効果も見込まれます。しかし、これらのことは広域連携だけでは実現できません。やはり合併を行うことによって、住民負担の軽減、そして公的サービスの向上を続けることができるのではないでしょうか。お伺いいたします。
市長
自治体間の合併については、これまでも昭和の大合併、あるいはさきの平成の大合併ということで合併が進められてきた経緯があります。平成の大合併については、県南地区ではどこもなかった、ほとんどが仙台市より北のエリアだったということもあります。このような合併した市町村の抱えている現状での問題も、今大きくクローズアップされています。仙台市に戦後合併した本市の隣の太白区でも、合併当時約束されていた道路整備に今やっと取りかかっているという状況もあります。
この合併ということについては、それぞれにいいところもあれば、新たな課題が出てくるということもあります。そのようなさまざまな問題についてそこに住む人々がどう考えるか、合併を望むのか望まないのか、そのようなことで将来を決めていく必要があるだろうと考えています。現状では、直接的に合併を望む声が大きなうねりとなって起こっている状況ではないと捉えていますので、御理解をいただきたいと存じます。
吉田
直接合併を望む声が聞こえてきていないと市長はおっしゃいましたが、そのようなニーズを抱えている住民の方は確実にいらっしゃいます。そして、それ以前に、人口減少や少子高齢化が続いている今の日本の全国的な状況について、今後、20年30年先を見据えていかなければならない。そのときになってから対策をしようとしても、そのときでは遅いということも考えられます。現に今、仙台市の秋保地区の合併の問題に関してもやっと動き出したという話ですが、それだって以前に合併できたからこそ今動いているわけであり、合併そのものがなければ何も進んでいくことはありません。
今、本市の人口は増加していますが、今後、もし人口減少を抑えることができたとしても、全国で少子高齢化が進んでいき、国民負担は間違いなくふえていきます。本市においても、今後国民健康保険税の負担増が絶対にないとは言い切れない状況だと思います。そのようなことは、やはり広域連携だけで維持していくことは不可能だと言わざるを得ません。そして、そのような時代が到来しても、住民の負担の軽減、公的サービスの向上が行政の目標であることは間違いのない事実であると思いますが、合併をしないでこの人口減少、少子高齢化の時代をどうやって乗り越えていくおつもりなのか、お伺いします。
市長
議員から、少子高齢化や人口減少の問題などいろいろな懸念が示されましたが、これらは合併することによって解決できる問題でしょうか。全然視点がずれているだろうと考えております。
吉田
一番先に申し上げましたように、やはり人件費等の行政負担を減らすことによって住民の負担を減らすことを目指していくのが、今後の長い視点で見た上での行政の役割ではないかと認識しています。
先ほど市長からお話がありましたように、もし住民の方から具体的な声が上がってくれば合併も視野に入れていかざるを得ないと思いますが、実際このたびの市議会議員選挙で、私は仙台市との合併を施策に掲げて戦ってきました。そして、住民の方々からは暮らしをよくしてほしいということでさまざまな意見が寄せられましたが、仙台市との合併を望む声も数多く届いています。平成7年に名取市議会で合併協議会設置議案が否決されてから約20年が経過していますが、新たな団地の形成等もあり、社会情勢は大きく変わっているのが現状だと思います。住民の方々からは、あのとき合併していればよかったのにとか、今からでも合併を目指してほしいとか、そういう意見も決して少なくありません。では、今後、署名などによって合併を求める声がもし多く寄せられるようなことがあれば、当然市としては検討されるのでしょうか、お伺いいたします。
市長
合併については、手続について定めがありますので、その定めにのっとって進めていくことになろうかと思います。
吉田
その法律に定められている合併の手続を進めていくためには、多くの壁を越えていかなければなりません。目指すところの人件費を初めとする行政コストの削減までたどり着くには、相当多くの時間と労力がかかることは間違いないことだと思います。しかし、行政の無駄をなくして住民サービスを高めていくためにも、今、身近なところから、必要でないものに対する税金の投入をやめることを目指していかなければなりません。
そこで、必要のないものの一例として、選挙期間中に騒音をまき散らす選挙運動用自動車、いわゆる選挙カーをここで挙げたいと思います。平成28年1月に行われた市議会議員選挙の投票率を見ても、有権者の政治離れが進んでいることは明らかです。その要因の一つとして、有権者の政治不信が挙げられます。政治不信は政治家の不祥事ばかりが原因ではありません。一般市民と政治家との間にある意識の乖離こそが、誰を選んでも何も変わらないという政治への諦めを抱かせている大きな理由であるとも考えられます。
そこで、(2)公費で賄われる選挙運動用自動車は、住民福祉の増進に何ら資するところがない。選挙運動用自動車への公費負担を廃止すべきではないでしょうか。
市長と選挙管理委員会委員長の御見解をお伺いします。
市長
選挙運動用自動車への公費負担については、選挙管理員会が所管する事務となりますので、今後、選挙管理委員会と十分連携をとっていきたいと考えております。
選挙管理委員会委員長
選挙運動用自動車の使用の公費負担は、公職選挙法第141条第8項の規定に基づき、選挙運動用自動車使用について無料にできるように条例化したものです。その目的は、お金のかからない選挙の実現、候補者間の選挙運動の機会の均等化などを図るためです。
1月に行われた市議会議員選挙では、23名の候補者全員が選挙運動のために自動車を使用し、この制度を利用していることを踏まえると、立候補者が対等な条件で選挙運動をするに当たり必要な制度であると考えております。また、この制度を廃止することで立候補者の門戸を狭めてしまうおそれもあり、廃止することは現在のところ考えておりません。
吉田
また、この選挙カーの公費負担の問題に加えて、市議会議員選挙の際、選挙はがきや選挙公報を除き政策を書いたビラを一枚も配れないという規則が定められた公職選挙法の問題点について、指摘させていただきたいと思います。
選挙権が18歳からに引き下げられても、必要な活動は禁止され、選挙カーに関してだけ、候補者名を訴えることができると。討論会なども禁止されている。そのような選挙のあり方が有権者から遠いところにあるという事実は変わりありません。こうした状況を是正するためにも、他の市町村の選挙管理委員会と協力して問題提起を行い、国に制度の正常化を求めていただきたいと思います。
では、次に移ります。政治をより住民に近いものにするためにも、税金の使われ方の見える化を進めていくことは重要な課題です。汗水流して働いて得た給料から徴収される税金がどう使われているのかは、納税者にとっては最も関心の高い事項です。行政には、税金の使われ方について住民に説明責任を果たす義務があります。住民の多くは、税金の使われ方に関心を抱いたとしても、市役所に電話で問い合わせたり、あるいは決算書の細部にまで目を通したりする時間的な余裕はありません。
そこで、まず目を向けられるのが、広報なとりに掲載されている「名取市の家計簿」ではないかと思います。したがって、その表示方法については、あくまで住民の目線で常に改善に努める必要があります。しかし、平成27年12月号の広報なとりに掲載された平成26年度決算報告を見ると、改善を要する表示が見受けられます。
そこで、(3)広報なとりに掲載される決算報告「名取市の家計簿」が、納税者に対する説明責任を十分に果たしているとは言えない。より丁寧でわかりやすい表示方法に改めるべきではないでしょうか。市長にお伺いいたします。
市長
決算の状況については、数字ではわかりにくい区分ごとの割合はグラフを活用し、難しい行政用語には解説を入れるなど、丁寧でわかりやすい表示となるよう工夫を凝らしながら、広報によりお知らせをしているところです。
また、これまで市民の方々からわかりにくい等といった御指摘をいただいたことはありませんが、今後とも、より丁寧でわかりやすい表示方法を心がけていきたいと考えております。
吉田
市民の方から直接そのような要望が届いたことはないというお話でした。ただ、住民の方は、思ったとしても直接市役所に電話をかけて訴えることがなかなかできない方もいらっしゃると思います。そこで、住民の方と話し、そこで届けられた声を参考にして、もっと改善したほうがいいのではないかということを、今から具体的に要望させていただきたいと思います。
配付させていただいた資料1をごらんください。「名取市の家計簿~平成26年度決算報告~」のページの写しです。
まず、一般会計の目的別収支決算額の歳入の部について1点指摘させていただきます。この円グラフにあらわされている繰入金という言葉は一般的ではありません。繰入金という言葉は通常余り使われる言葉ではありませんので、それを理解できる住民の方はほとんどいらっしゃらないものと思います。また、市税や地方交付税などの項目には簡単な解説が載せられておりますが、地方譲与税と繰入金にはそれがありません。これらにも解説を表示するべきではないでしょうか。また、繰入金は歳入全体の3割にも上っていますので、その内訳もぜひ明らかにするべきではないでしょうか。お伺いいたします。
財政課長
まず、決算の広報への掲載については、議会の認定に付した決算の要領を住民の方に公表しなければならないという地方自治法の規定に基づいて公表しております。
先ほど議員から、繰入金や地方譲与税という用語が一般的ではないのでわかりにくいのではないかという御指摘がありましたが、ほかの項目については適宜用語の解説等を入れながら載せていますが、紙面の都合等もあり、余りに全ての項目を詳細に載せるとかえって見にくくなるというおそれもありますので、現状においてはこのような表記方法をとっています。県内の他市で出している広報等を見ても、それぞれに紙面のつくり方については工夫をされておりますが、どこも本市と同じような表記方法になっているのが現実ではないかと考えています。
なお、先ほど住民の方からのお問い合わせについてもお話がありましたが、この紙面においてさらに深く内容を知りたいという方からは、直接電話で相談をいただいたりお答えしたりするという機会もあります。ただ、そのような中では、この表記している中身そのものがわからないという御意見はいただいておりませんので、特にわかりにくい表現になっているという認識は今のところ持っていないところです。
吉田
わかりにくいと認識されていないということですが、説明責任というのは、一目でより深く理解できることを常に目指していかなければ果たせないのではないかと思います。
次に、歳出の部ですが、歳出全体の4分の1に及ぶ総務費の解説が「広報、住民票発行やコミュニティづくりなどに」となっています。しかし、その金額は、震災前の平成22年度よりも平成26年度は150億円も増額しています。しかし、150億円も増額しているにもかかわらず、内容については以前と変わらないまま「広報、住民票発行やコミュニティづくりなどに」となっています。それだけの増額された分が広報や住民票発行に使われているとは思えませんし、また、コミュニティーづくりというのも非常に難解な言葉だと考えます。この辺の総務費の解説なども含め、やはり額が大きく変わったところについてはより深く説明をするべきではないでしょうか。
財政課長
総務費については、種々さまざまな経費が入っている款です。そのようなことから、この限られた紙面の中に総務費だけを抽出して項目の説明を載せるということは、それ以外の費目に割くスペースが逆に限られてしまうことになり、総務費の中身よりも、それ以外のところに紙面を使うべきという判断からこのような表記になっています。
吉田
限られた紙面の中でより工夫をしていただき、金額が大きく変わったところについては、なぜそれが変わったのかをできるだけわかりやすく説明していただくことを願います。
次に、左側のページの名取市の財産の部分ですが、基金が約415億円となっています。前年度の平成25年度は468億円程度でしたので、これもやはり50億円近く変化しています。このような年度ごとに変化していく財産、特に基金は貯金のようなものですから、市の財産として非常に重要な部分だと思いますが、このようなものがふえている、減っているということが一目でわかるように示すべきではないかと思います。直近の数年間の年次比較を折れ線グラフなどで表示することができれば、それも可能ではないかと思いますが、御見解をお伺いします。
財政課長
年次比較まで含めてというお話もありました。先ほど来申し上げているように、限られた紙面の中で、まず決算の要領を全てくまなく書くことが第一義と捉えています。それ以上に詳しい情報については、市の情報公開のコーナーにも決算書等を備えておりますし、ホームページにはさらに詳しいデータを年次別に掲載しているところです。そこまでの情報が必要な方についてはホームページ等で情報をとっていただくことは可能な状況になっていますので、市民の皆様、全ての御家庭にお配りする紙面では、このような構成が今の状態では限界ではないかと考えています。
吉田
現在の紙面の構成が限界とおっしゃいますが、資料2をごらんいただきたいと思います。名取市の家計簿でいうと一般会計の性質別内訳ですが、資料1の一般会計性質別内訳の中で、その他の項目が全体の約4分の1を占めています。その他がこれだけの割合を占めているというのは、どこの企業の決算報告でもあり得ないと思いますし、ほかの自治体でも当然そうだと思います。資料2を見ますと、右側が広報いわぬまですが、性質別歳出にその他そのものが設けられておりません。また、左側の仙台市の家計簿を見ますと、相当大きな規模の予算ですが、その他は全体の3%しかありません。このように工夫次第で、その他も含めて、改善できるところは多々あると思います。本市の場合は、平成25年度ですと、その他が全体の42.8%を占めているという現状もあります。ホームページを見れば一目瞭然ですが、これは金額にすると約295億円という莫大な金額であり、震災前の平成22年度の一般会計当初予算に匹敵する金額です。それだけの金額が、その他として表示されているのは、やはり大きな問題だと思います。本市においても、このようにほかの自治体の決算報告の家計簿を参考にして、その他も含めて、わかりづらいところを改善していただきたいと思います。
次に、大項目2 教育についてお伺いします。
いまだに仮移転先や仮設の校舎で学ぶことを余儀なくされている閖上小学校・中学校の児童生徒はもちろん、市内全ての児童生徒が健やかに成長するための学びの場を整備することが行政の役割です。多様な活動を通して豊かな人間形成を行うために、学校には適正な数の生徒が在籍していることが望ましいと思います。しかし、平成27年4月時点で閖上小学校・中学校に通う児童生徒数は小学校84名、中学校87名で、普通学級は各学年1クラスずつしかありません。これでは、9年間の義務教育を通して一度もクラスがえを経験せずに学校に通い続けることとなってしまいます。そのような狭いコミュニティーの中で長期間の生活を送ることにより、健全な競争を経験できず、人間関係の固定化が懸念されます。年少人口が市の思惑どおりに増加しなければ、小中一貫校建設後にはますます状況が悪化することが考えられます。
そこで、(1)建設が予定される閖上小中一貫校は、児童生徒が充実した学校生活を送れるだけの人数確保が困難である。人口分布と児童生徒数の長期的見通しを踏まえた上で、計画を見直すべきではないでしょうか。市長、教育長にお伺いいたします。
市長
平成23年10月に策定した名取市震災復興計画において、閖上と下増田のまち再生プロジェクトの中で、まちの再生とともに、子供たちが元気に育つ環境をつくるための主要施策として、地区の復興を先導しコミュニティーの拠点となる閖上小・中学校の再建を位置づけております。
閖上小・中学校の再建については、既に平成25年1月28日に教育委員会が定めた名取市立閖上小・中学校再建の基本方針に基づき事業を進めているところであり、閖上地区のまちづくりに欠かせないものであることから、計画の見直しについては考えておりません。
教育長
平成30年度の閖上小中一貫校開校時における児童生徒数については、小学校では、1年生が10人、2年生が11人、3年生が6人、4年生が5人、5年生が4人、6年生が7人の合計43人、中学校は、1学年が19人、2学年が23人、3学年が18人の合計60人となり、小中学校合わせての児童生徒数については103人を見込んでいます。
ただし、震災前に閖上に住んでいて現在ほかの学校へ通っている児童生徒のうち、開校に合わせて戻ってくる正確な人数を把握することは困難であり、今述べた児童生徒数には含まれておりません。また、防災リーダーの育成や名取市として初めての小中一貫校で学びたいという声に応えるために、市内全域から児童生徒を受け入れる予定ですが、その正確な人数も現時点では把握できていません。
被災した閖上小学校と閖上中学校の再建に関しては、平成24年に閖上小中学校の保護者のアンケート調査を行ったほか、同じ年に設置された閖上小・中学校再建懇話会の提言などを受け、現地に小中一貫校の建設を決定しました。開校に当たっては、小規模な学校となることも想定されますが、小規模でも魅力ある学校を目指して校舎の設計や教育課程の検討を進めており、具体的な事業が進行中です。現在検討中の骨子が固まり次第、保護者や市民に対する説明を行い、PRにも努めていきたいと考えております。
復興する閖上のまちに小中学校は必要不可欠なものと考えており、教育委員会としても計画の見直しは考えておりません。
吉田
平成24年度に実施されたアンケートによると、小中一貫校でと答えた保護者の方は、多くても2割台にとどまっています。初めに小中一貫校ありきという考え方で進められてしまったのではないかという懸念があります。
また、今、見込まれる児童生徒の数が提示されました。今後それ以上の生徒数も見込まれるという説明もありましたが、小中一貫校のメリットについては、今はまだ小中一貫校そのものが進められているのはごく一部であり、本当に小中一貫校で子供が高いレベルの教育を受けられるのかどうか、あるいはデメリットもあるのではないかという懸念もあります。児童生徒数が今後ふえるかどうかという多くの保護者の方の心配を踏まえますと、閖上地区以外に住む住民の方があえて子供を閖上に通わせるということは考えづらいのではないかと思います。立派な建物をつくったのはいいけれども児童生徒がいないということは絶対避けなければならないと考えます。再建後にもし市の予測どおりに児童生徒数が確保できなかった場合は、結局は子供たちにその負担が回っていってしまう。後々、子供たちがその責任を負わなければならないことになってしまう。そうならないように、開校のときだけではなく、その後もずっと児童生徒数を確保していくために、どのような対策をとるつもりでしょうか、お伺いいたします。
教育長
まず、今の御質問の冒頭で、小中一貫校ありきで進めたのではないかという御質問がありましたが、決してそうではありません。まず、そのことについてお話しさせていただきたいと思います。
閖上の小中一貫校については、震災の前から、地域の方々から小中一貫校を望む声がありました。具体的に申し上げますと、震災でお亡くなりになった高橋史光議員から、議会の一般質問でも何度となく、小学校と中学校の学区が一緒だということから閖上小中一貫校を御提言いただいていましたが、その時点では、教育委員会としては時期尚早という考えを持っていました。そういった背景が震災前からあったということが一つです。
それから、震災直後の3月31日に、商工会館で閖上小・中学校の保護者の皆様を対象とした今後の閖上小・中学校のあり方について説明をする会を持たせていただきました。その時点で閖上小・中学校の保護者の方からいただいたのは、閖上小学校、閖上中学校はなくなるのですかという不安の声でした。その時点で教育委員会としては、閖上小学校・中学校はなくさないという基本的な考えは持っていました。
その後、平成24年2月にアンケートを実施しましたが、そこで、再建する閖上小・中学校の形について保護者の方々の御意見をお伺いしています。その結果、小学校、中学校を別々の場所に再建してほしいというお考えの方は15.1%、小学校、中学校は別々であっても同じ場所につくってほしいというお考えの方が57.8%、小中一貫校をつくってほしいという御意見の方は22.5%でした。そのことから、少なくとも再建する閖上小・中学校は同じ場所につくるという基本的な考えは当初から持っていました。
その後、地域の代表の方2名、保護者の代表の方2名を含む8名の委員から成る、名取市立閖上小・中学校再建懇話会を設置し、その中で、同じ場所に別々に再建するか、小中一貫校がいいかということも含めて議論をしていただきました。そして平成24年10月に、閖上小・中学校は小中一貫校として校舎一体型で再建するのが望ましいという提言をいただきました。その後、保護者の方、教職員、地域の方、児童生徒との意見交換などを行い、平成25年1月に教育委員会としての基本方針を決定し、その中で閖上小・中学校を一貫校として再建するという方針を決定させていただきました。ですから、小中一貫校ありきで当初から進んでいたということではありません。
次に、児童生徒数が非常に少なく、それで十分な教育が行えるのかという御質問でしたが、確かに学校の適正規模という考えがあります。学校教育法施行規則第41条で、小学校の標準として12学級から18学級ということが述べられています。しかし、これによりがたい場合はその限りではないというただし書きがあります。中学校も同様です。
では、今の本市において、あるいは全国的に見て、この適正規模がどうなっているかということですが、本市では、小学校の場合、適正規模に当てはまる学校は2校で、4校が大規模校、5校が小規模校、中学校では、適正規模に当てはまるのが3校、大規模校が1校、小規模校が1校となっています。全国的に見ても、宮城県もほぼ同じですが、適正規模に当てはまる学校は小学校で約30%、中学校でも30数%です。小規模校が小学校では約半数、中学校では半数を上回っています。
それでは、こういう小規模な学校や大規模な学校では十分な教育が行われていないのか、私は決してそうは思いません。確かに適正規模にはそれなりの理由があります。望ましい学級数だとは思いますが、では、小規模である半分近くの学校で手をこまねいて教育を行っているのかというと、決してそうではありません。例えば小規模校で適正かつ健全な競争が行えるかというと、切磋琢磨できないということは、一つのデメリットとして間違いなくあります。私も一学年一学級の学校で勤務した経験があります。また、児童数が1,120名を超す大規模校で勤務した経験もあります。ただ、小規模校で切磋琢磨ができないというデメリットを解消するために、小規模な学校ではいろいろな取り組みをしています。その中でどのように子供たちに向上心を持たせるか、目標を持って進ませるか、そのようなことに一生懸命取り組んでいます。仮に大規模校であっても、何もしなくても切磋琢磨ができるということではないと思います。
それから、小規模校のメリットとしてきめ細かな指導が行える、大規模校では一人一人に目が行き届かないとよく言われますが、大規模校でも組織をきちんとつくって見ていけば、むしろ一人の子供を複数の目で見るなど多様な見方ができます。決して大規模校できめ細かな指導が行えないということはないと思います。
ですから、私は、閖上小・中学校が少人数でスタートすることが見込まれるという、そのことをもって見直しをするということは考えておりません。もちろん適正規模が望ましいとは思います。ただ、小規模校であってもすばらしい学校をつくっていく、それは教育委員会、教職員の努力で、地域や保護者の方々の協力をいただきながら進めていけばできることではないかと考えています。当初、小規模な学校としてスタートするかもしれませんし、その後の児童生徒数の増加等については安易に見込むことはできませんけれども、将来、閖上に小中学校があってよかったと思われるような学校をこれからも目指して開校に向けて取り組んでいきたいと考えていますので、見直しをするということは考えておりません。
吉田
学校の適正な生徒数を確保できるかどうかに関しては、それ以外のことでカバーしていくという御答弁だったと認識しました。
実際に今、増田中学校の生徒数が急に膨れ上がっています。また、下増田小学校も児童数が増加傾向にあります。そのような生徒数がふえている学校の生徒も通えるようなところに例えば中学校だけでも再建するという形にすれば、その地区に住む生徒のためにもなりますし、閖上の中学校も今後ずっと長く生徒数を確保して存続していけるということにつながってくるのではないかと考えます。
それ以外にも、今市内の中学校では、徒歩や自転車で通学できず、バス通学をしている生徒も実際にいらっしゃいます。例えば相互台や愛島台などの生徒はバスで中学校に通学しています。こういう生徒は部活動を行う時間帯もほかの生徒に比べると制限があります。そのような問題がまだある中で小中一貫校を今の計画のまま進めていくより先に、まず全体のバランス、均衡を目指していくべきではないかと私は考えますが、教育長の御見解をお伺いします。
教育長
学校の適正規模という考え方は非常に大事な考え方であるという認識は持っております。今の議員の御提言をそのまま受けとめさせていただきますと、適正規模に向けて学校を見直して、もう少しバランスをとったらいいのではないかと受け取れました。例えば中学校ですが、2月1日現在、本市には2,326人の中学生がいます。中学校が5つありますので、単純に5で割れば465人になります。そうするとほぼ適正規模に全ての中学校がおさまります。小学校も11で割ればそうなりますが、ただ、私は適正規模よりも大事にしたいことがあります。学校はやはり地域との結びつきが大切です。学校は地域に浮かぶ船と言われることがあります。これは学校が地域を超越したところにあるということではなく、学校は地域に支えられ、地域とともに歩んでいく、ある意味では地域のコミュニティーの一つの核となるものだと考えています。そのような意味で、各学校では地域との連携を深めたり地域の力をおかりしながら学校運営を行っていますし、これはこれからますます大事になってくるのではないかと考えます。
学校の適正規模については、先ほどお話しいただいた下増田小学校、増田中学校については増築等で対応しています。可能であれば適正規模の学校ができれば望ましいとは思いますが、数を合わせるために児童生徒数を操作するために学区の変更を考えるということは、教育委員会としては現在考えておりません。
吉田
地域との結びつきを今後大事にしていくというお話がありましたので、そのことを今後も目指していただきたいと思います。
市内全ての児童生徒が公平な教育を受けられる成育環境が望まれます。
平成27年度の全国学力・学習状況調査結果の集計によると、朝食を余り食べていない、あるいは全く食べていない小学生の割合は4.4%、中学生の割合は6.6%に上ります。この数値は、当該生徒が各クラスに平均1名程度いることをあらわしています。
そこで、(2)核家族・共働き世帯がふえる中、市内には毎日の朝食を食べられない児童生徒が多数いるものと考えられます。朝食を食べられない児童生徒に対する支援を行うべきではないでしょうか。教育長の御見解をお願いいたします。
教育長
平成27年度全国学力・学習状況調査における学校質問紙による実態調査によると、小学校5年生と中学校2年生の毎日朝食を食べている子供の状況は、「食べている」と「どちらかといえば食べている」と回答した子供の数を合わせると、全国平均では小学校で95.6%、中学校で93.4%でした。本市における小中学生の朝食を食べる子供の割合は、この全国の数値を上回っており、経年変化においても増加しています。これは、県の教育委員会や各学校で呼びかけている「はやね,はやおき,あさごはん」推奨運動で保護者や家庭への働きかけを行っている一つの成果と考えております。
議員御指摘の朝食を食べられない子供に対しては、各学校において、健康観察等を通して食べていない子供がいる場合に家庭との連絡をとるなどの対策を行っています。御提案の朝食の提供などの支援については、現時点では考えておりません。
今後とも継続して、さまざまな機会を捉えながら、栄養面、体力面、心理面等の視点から朝食をとることの大切さを指導していきたいと考えております。
吉田
全国平均を上回る割合で本市の児童生徒が朝食をしっかり食べていることは、非常に喜ばしいことであると思います。皆様のお取り組みがその成果につながっていることと存じます。ただ、その中でも朝食を食べてこない生徒、御家庭で事情があって食べられない生徒は一定数いるわけです。このような事業を新たに始めるとなると、そこにも予算をつけなければならない状況になりますので難しいこととは存じますが、本市の場合は農業が盛んですし、市場に出てこないで廃棄されるような食材などもありますので、住民の力で、事情があって朝食を食べられない生徒の支援をして、市がその後押しをできないものでしょうか、お伺いいたします。
教育長
一口に朝御飯を食べていない子供といっても、いろいろなケースがあります。大きく分けて3つほどあろうかと思いますが、1つ目として、親がきちんと朝御飯を用意する環境にあるのに、子供自身が朝御飯を食べてこないというケースがあります。小学校の高学年や中学生になると、太ることを気にしてダイエットとして朝御飯を食べないという子供も出てきます。それから、夜遅くまでゲームや勉強で起きていて、朝、寝坊をして御飯を食べないで来る子供もいます。そのような子供たちに対しては、各学校で、3食バランスのよい食事をとることの大切さを食育の一環として本市の学校給食センターいただきスマイルかんの栄養職員などの協力もいただきながら指導をしています。これは、子供たちに、御飯をきちんと食べることが大切だという自覚を持たせることが大事ではないかと思っています。
それから、2つ目のケースとして、親の問題だと思いますが、親も朝食を用意する気持ちはあるのですが、例えば夜勤をしていて朝は寝ているなど、いろいろな事情で朝御飯が食べられないという子供もいます。そのような場合は、各学校で、家庭と連絡をとって朝御飯を用意するような働きかけを行っています。ただ、私も学校現場でいろいろな保護者の方とお話をしてきましたが、例えば母子家庭になって一生懸命子育てをして日中も夜も働いていて朝起きられないという御家庭もあります。ただ、そういう御家庭であっても、朝は仮に起きられないとしても、夜のうちに少なくともパンと牛乳ぐらい置いておいてあげれば朝御飯は食べてくることができる、そのような働きかけをどこの学校でも行っています。
それから、3つ目として、親が朝御飯を食べさせる意欲も気持ちもないようなケースもあります。働きかけは行いますが、どうしても改善しない場合は、児童相談所等の関係機関と連絡をとって、そのような力もかりて改善を図るという取り組みも行っています。
実際問題として朝御飯を食べてきていない子供がいる場合、本当に服装も汚れていて給食時間になるとがつがつと給食を食べる子供も私も何人か見ていますが、そのような子供を見て、現場の先生方は本当に心を痛めています。こっそり職員室に呼んで牛乳を飲ませたりというようなこともありますが、私は、基本的には家庭の問題、家庭を何とか変えていかなければだめではないかと思います。一時しのぎではなくてきちんと朝御飯を食べて学校に通える環境を整える、それは簡単にはできないこともありますが、まず子供たちの問題の場合は子供たちへの食育と指導、家庭的な問題で食べられない場合は家庭への働きかけを行っていくことがまず基本ではなかろうかと思っています。具体的に御提案のあった、教育委員会で後押しをして朝食の準備をすることについては、現時点では考えておりません。
吉田
教育長がおっしゃったように、家庭がそもそも責任を持って子供に食事をとらせることが大原則であることは当然のことだと思います。ただ、現状、家庭で朝食が用意されなくて困っている子供がいることに関して、何か手を差し伸べることができないかと考えたときに、もし仮に朝食を子供たちに準備できるような仕組みが民間から出てきた場合、例えば他の自治体ではフードバンクなどを利用して子供たちに食べさせようという活動があります。行政が関係していくのか民間でやっていくのかは各自治体によって違いますが、例えばNPOが進めているフードバンクを活用していくとか、あるいは地域の食材を子供に提供したいという地域の方が出てきた場合に、学校の校舎を利用して朝食を希望する子供に食べさせることは可能かどうかお聞きします。
教育長
全国の自治体あるいは公立の小中学校で、それほど多くはありませんが、今議員からお話があったような取り組みをかつて行ったこともあるとは聞いております。ただ、やはり学校でそこまでやるべきかについてはかなり議論があったと聞いています。現時点で、もし今議員からお話があったような申し出があった場合には、十分、教育委員会あるいは各学校とも検討した上で、受け入れるかどうかを判断する必要があろうかと思います。ただ、子供たちへの食育と保護者への働きかけを今後も引き続き行っていきたいというのが基本的な考え方です。
吉田
私も、今後も子供たちの食に関する問題提起、解決に向けて努めていきたいと思います。
では、次に移ります。さきにも触れましたが、若者の市外流出を食いとめることが今後重要な課題になってくると思います。市の地方創生総合戦略には、進学や就職を機に首都圏などに転出する若者が多いことが明記されています。地域で生まれ育った子供たちは、地域の文化を次の世代につなぐかけがえのない人材です。せっかく子供たちに手厚い教育を施したとしても、成長して市外に流れていってしまったのでは文化のバトンリレーは途切れてしまいます。
そこで、(3)若者の首都圏への流出を抑え、有形無形の文化財を次の世代に確実に受け渡すためにも、ふるさと教育を充実させるべきではないでしょうか。教育長の御見解をお願いいたします。
教育長
市内に所在する多くの有形・無形の文化財は、その保存・継承が地域に密接にかかわり、人々の手により現在まで守られてきておりましたが、地域社会の環境変化に伴い、担い手や後継者が少なくなっているのが現状となってきております。
このような中、教育委員会では、これまで有形文化財の所有者や無形民俗文化財保存団体の保存・継承活動に助成を行うほか、ふるさと名取の歴史展や歴史講座等を通し、地域の文化財への理解促進と愛護の心を学ぶ機会を提供するなど、文化財の保存・伝承に努めてきました。さらに、地域にある文化財を総合的に保存活用するための歴史文化基本構想の策定や(仮称)歴史民俗資料館整備事業に新たに取り組んでいきたいと考えています。
また、小学校においては、社会科副読本「わたしたちの名取市」等を活用した社会科や生活科の学習の中で、中学校においては、総合的な学習の中で地域の歴史や文化財等を取り込むことにより、その魅力や価値を認識し、伝統や文化財を大切にする心を培う学習を実施しております。
このような取り組みは、子供たちがふるさとへの愛着や誇りを持ち、地域社会の一員として貢献し地域を支える、次世代の育成にもつながるものです。今後も、地域の歴史や文化財等を生かしたふるさと教育に取り組んでいくことにより、有形無形文化財が次の世代へ継承され、少しでも若者の首都圏への流出の歯どめにつながっていければと考えているところです。
吉田
ただいま教育長がおっしゃった取り組みを今後もぜひとも進めていっていただきたいと思います。それと同時に、ふるさとを知り愛着を持つことももちろんですが、それ以上に自分自身がふるさとの文化の担い手であるという自覚を子供たちがしっかり心に持ち続けることが、この文化を次の世代に継承していくこと、また、子供たちが成長したときに本市にしっかり生活の拠点を置いて本市で生活していくことにもつながっていくのではないかと思います。
そういう意味においても、本市において市と県から指定を受けている9件の無形民俗文化財の保存にかかわる体験活動を通して、自分自身が文化の継承者であるという自覚を育てていければと考えますが、現時点でこの9件の無形民俗文化財の小学校、中学校における体験学習の現状をお聞きします。
文化・スポーツ課長
本市には9件の無形民俗文化財がありますが、その中で現在学校と関係を持って活動をしている団体が2つあります。まず1つは館腰にある花町神楽の保存団体ですが、この保存団体については、館腰小学校で神楽の実演と神楽の演技指導を実施しています。その成果については、小学校3年生が学校の発表会で発表しているところです。
もう一つは、手倉田地区、増田西小学校の学区ですが、そこに手倉田枡取り舞保存会があります。枡取り舞の保存会については、増田西小学校において、枡取り舞の演技の実演、また指導を行い、子供たちが発表会において発表しているという状況です。
吉田
全部で9件ある中で現在2件が実際に小学校で体験学習に用いられているということですが、今後これをぜひふやしていって、9件それぞれ、どこかの学校で取り組むような形に持っていっていただきたいと思います。
今回の総合戦略において、本市の観光振興が挙げられています。この観光振興に教育を結びつけていき、子供たちが自分たちで本市の文化を観光の一つの資源として観光客にアピールしていくという取り組みを行うことができれば、例えば子供や若者が体験活動によって身につけたその無形民俗文化財を観光客に実演していくとか、そのようなところにまで持っていくことができれば、本当の意味での子供たちのふるさと教育に結びついていくのではないかと思います。今後、地方創生総合戦略に書かれていることを実現していくためにも、この無形民俗文化財に限らず、子供や若者の感性や行動力をぜひ取り入れて進めていっていただければと思います。
もし本市が観光地としてにぎわいが得られれば、子供たちの学習している無形民俗文化財の保存活動にもつながります。また、それがふるさと教育の本当の意味での、自分自身がこの地域を守っていくと、未来にしっかり財産を受け継いでいくという気持ちにもつながっていくと思います。そういう意味でも、観光振興の面にもぜひつながりを持たせて、子供たちのふるさと教育を進めていっていただければと存じます。
以上をもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。
財務常任委員会
吉田
8ページ、9ページ、1款4項市町村たばこ税について伺います。旧3級品と旧3級品以外、いずれも本数の伸びを見込んでいるということですが、この伸びを見込んだ根拠は、1人当たりのたばこを吸う本数なのか、それともたばこを吸う方の人数なのか、どの辺でこの数字が出たのかお伺いします。
税務課長
伸びの見込みについては、主に決算額をもとに見込んでいるところです。決算額でいうと平成25年度の収入が5億9,000万円程度、平成26年度が5億8,000万円と下がっていましたので、平成27年度当初についても下がると見込んでいましたが、実際は伸びがあり、12月に増額補正をさせていただきました。そのような動向を見て、平成28年度についても伸びを見込んで調定を上げさせていただいたところです。
吉田
私はたばこを吸わないのでよくわかりませんが、今コンビニエンスストアなどでは電子たばこの売れ行きが随分伸びているようですが、そちらについても課税はされているのですか。
税務課長
それは課税の対象外です。
吉田
もう一度、たばこ税について質疑させてください。8ページ、9ページです。先ほどの私の質疑が少し曖昧な言葉になってしまいましたので具体的な商品名を挙げますが、コンビニエンスストアで売っているiQOSという商品で、加熱するたばこの本体にニコチンを含むたばこの葉を詰めて使用されるものですが、こちらにも課税はされていないのでしょうか。
税務課長
マルボロiQOSについては、葉たばこタイプですので、これはたばこ税の課税対象になります。
吉田
26、27ページ、14款1項1目10節生活保護費ですが、資料の2ページを見ると、平成28年度は年間で1万6,307人を見込んでいるということですが、この数字のあらわし方について御説明をお願いします。
社会福祉課長
歳入の基礎となっている人数ですが、歳出が絡んできますので157ページをごらんいただきますと、扶助別で、生活扶助費から次のページの葬祭扶助費まで扶助費がありますが、それぞれの延べ人数を合算した人数という形になっています。
吉田
そうすると、延べ人数の合算ということは、いろいろな保護の形がありますが、それを合わせてこの1万6,307人になるということでよろしいですか。
社会福祉課長
例えば生活扶助費、住宅扶助費をお一人の方が2カ月受けたとなると4人分と。1人が2つの項目で2カ月受けた場合は4人という計算の基礎で算定されています。
吉田
28、29ページの14款1項1目13節被保護者就労支援事業費となっているこの事業について、具体的にどのような活動をされるのかお聞きしたいと思います。
社会福祉課長
被保護者就労支援事業については、その上の12節生活困窮者自立支援事業費と関連しますが、生活困窮となっていてこれから就労をしようとする方に対して、ハローワークなどと連携して仕事を見つけ、あっせんをしていくという事業をしています。それが生活困窮者及び生活保護者ということで、両方にまたがっている事業となります。
吉田
資料を見ると、2ページの10節生活保護費で年間602人の増が見込まれていますが、その支援事業を行った上でもこれぐらい増が見込まれるということでしょうか。
社会福祉課長
就労と生活保護等というのは一概に自立には結びつかないところもありますが、昨今の報道でも御存じのとおり、最近は生活保護が最高水準まで達しているということがありますので、予算のほうでは602人を見込んで少し多目に確保しているところです。その中で就労ができそうな方やできる方に対しては就労支援を行っていくという内容になっています。
吉田
28、29ページ、14款1項3目2節教育施設災害復旧費の公立学校施設災害復旧費についてですが、昨日の御説明では、閖上小・中学校の再建に対する国からの支出金ということでしたが、こちらは市で今計画している小中一貫校としての計画に対する国からの支出金でしょうか。
庶務課長
委員お見込みのとおり小中一貫校の財源となるものです。
吉田
44、45ページ、15款1項1目10節、こちらは県負担金の生活保護費ですが、資料の7ページの一番下を見ると、見込み人数が3人となっています。先ほど国庫負担金の生活保護費については延べ人数ということでしたが、この違いについて内容を御説明いただきたいと思います。
社会福祉課長
この県支出金の生活保護費については、居住地がない方を保護した場合に、本市の支出する分の4分の1が県の支出になるという形の経費として3人分を見込んでいるということです。
吉田
52、53ページ、15款2項5目1節農業費ですが、その中の農地中間管理事業費交付金が大幅に増額されていますが、どのような事業なのか具体的に教えていただければと思います。
農林水産課長
農地中間管理事業費交付金については、農地中間管理機構へ農地を貸し出すことによって受け取ることができる経営転換協力金などの機構集積協力金及び推進事務費分として交付されるもので、補助金は10分の10となっています。
吉田
集約化とは全く関係ないのですか。農地の集約化はこの中には入っていないのですか。
農林水産課長
この事業は、例えば高齢化に伴って農業を継続することができないという農家さんが農地中間管理機構に農地を預けて、農地中間管理機構が今度は受け手の方にその農地の耕作をお願いするという形の事業となっています。
吉田
75ページの2款1項1目18節備品購入費の中で、公用自動車購入費となっていますが、購入に至るいきさつや自動車の車種等の情報についてお聞きします。
総務課長
公用自動車購入費は、現在29人乗りのバスを総務課で管理しておりますが、平成2年に取得しており26年が経過しているため経年劣化が著しく、その更新となります。今使っているのがトヨタのコースターという29人乗りのバスですが、今回想定しているのは同様の29人乗りのバスを考えております。
吉田
では、現在使っているバスは廃車ということですか。
総務課長
お見込みのとおりです。
吉田
81ページの2款1項4目12節役務費ですが、平成27年度の予算では郵送料は計上されていなかったようですが、今回の466万4,000円の郵送料の内容について御説明お願いします。
財政課長
この郵送料はふるさと寄附をいただいた方への寄附金の証明書を送るための費用と、それからワンストップ特例の申請をなされた方にその証明というか、ワンストップ特例を受けましたという書類を送付するための2回分の郵送料について措置しているものです。
吉田
全体で何件分くらいの郵送を見込んでいるのですか。
財政課長
平成28年度の寄附は、件数で4万件を見込んでおります。ワンストップ特例については、そのうち3割の方が申請されることを平成27年度の実績から見込んでおりまして、そちらは1万2,000件と見込んでおります。
吉田
83ページの2款1項6目8節報償費の名取マイレージ事業記念品の中身について、御説明をお願いします。
政策企画課長
名取マイレージ事業については、地方創生事業の一環で交流人口の拡大、市内の方のイベントへの参加を促すために今回企画したものです。ポイント制にして、イベントに参加していただくとポイントがもらえて、そのポイントの数に合わせて応募していただいて、地場産品の賞品を抽せんで贈るという形の事業を考えております。イベントについては、基本は市の主催事業になりますが、どのようなイベントを入れていくかは今検討している最中です。
吉田
多くの方に参加していただくことが、このマイレージ事業の一番の趣旨、目的とするところだと思うのですが、それを促すために抽せんとおっしゃいましたが、記念品を選定するための工夫といいますか、その点はどのようにお考えかお伺いします。
政策企画課長
地場産品を選んでいきたいということで、これも今後決めていくことになりますが、市内で製造されたものを優先して賞品として決めていきたいと考えております。
吉田
93ページの2款1項14目ふるさと振興費、先ほど大久保委員から質疑がありましたが、姉妹都市交流事業についてもう少し詳しくお聞きしたいと思います。新宮市主催のイベントへの小学生、中学生の参加ですが、どのような基準で参加する児童生徒を選んでいるのか、そこについて詳しくお伺いします。
総務課長
募集方法ですが、市の広報でお知らせして応募者を募っております。
吉田
選考はどのような形で、どのような基準で行っているのでしょうか。
総務課長
決定については抽せんで行っております。
吉田
143ページの3款3項2目12節役務費のピアノ調律料とありますが、これはピアノ何台分になるのでしょうか。
こども支援課長
公立保育所4施設分になっております。
吉田
そうすると、4施設で1年間に1回ずつという計算でよろしいでしょうか。
こども支援課長
委員お見込みのとおり1回ずつになっております。
吉田
145ページの3款3項3目7節賃金に臨時児童厚生員賃金とありますが、この臨時児童厚生員の仕事の内容についてお伺いします。
こども支援課長
臨時児童厚生員は、児童センターでの勤務をしていただくことになります。現在、児童センターは職員館長と嘱託職員、そして臨時児童厚生員といった職員構成になっており、基本的に平日であれば子供たちは午後から来ますので、その時間帯に合わせて出勤をしていただき、放課後児童クラブ、自由来館の子供たちの児童厚生面に当たっての対応をしていただいています。
吉田
平成27年度の当初予算に比べて増額になっているのは、どのような変化があってのことでしょうか。
こども支援課長
放課後児童クラブの利用希望の方がふえつつあることでの増員を図っております。また、一部賃金の単価改正もありましたので、それも増額の要因となっております。人数としては7人の増を見込んでおります。
吉田
149ページ、3款3項4目20節扶助費のひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金とありますが、この支援事業について対象者と支援の内容について伺います。
こども支援課長
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業は、まずひとり親家庭であるということで、その家庭の親の方が、高等学校を卒業していないということで就労等にハンデがある中で、高等学校卒業の資格を取ることで就労状況がよくなったり改善の道があるという場合には、この制度を使っていただいて対策講座を受けていただくといった場合に、受講料等の支給をするものになっております。
先日の歳入のときもこちらの内容に触れましたが、その対象講座を受講して修了した場合に、受講費用の20%相当額を支給します。上限10万円となっております。さらに合格時の給付金ということで、高卒認定試験に合格された場合には、受講修了日より2年以内という条件はありますが、受験費用の40%相当額、上限5万円になりますが、総額15万円までの支給をするといった内容になっております。
対象としては今2名を見込んでおります。
吉田
(5款)13節のものづくり企業等資格取得支援委託料についてお伺いします。ただいまの答弁で大学、高等専門学校、高等学校に対して委託をしているということで、その支援の中身といいますか、大学等の教育機関が学生に対して資格の取得等をできるように後押ししていくということだと思うのですが、どの時点でどのぐらいの支援が行われるのか、もう少し具体的にお伺いしたいと思います。
商工観光課長
まず最初に市で公募をかけるということで、ホームページでの広報や学校に直接御案内をします、4月以降となりますが。それから提案書をいただき、授業などいろいろと絡みがありますので、学校側で1年間の全体のスケジュールの中で資格取得支援事業を実施する工程を決めていただき、それに基づいて実施するものになります。
ちなみに、平成27年度においては尚絅学院大学、仙台高等専門学校、宮城県農業高等学校の3校が行っておりますが、内容は例えば電気工事の資格、フォトショップやイラストレーターの資格の取得といったことを行っております。
吉田
大学等になると、市外から通ってくる学生が割合としてもたくさんいらっしゃると思います。もちろんその方たちも本市在住の学生も分け隔てなく支援を受けられるという条件であるとは思うのですが、やはり市として取り組む以上、この取り組みが市にとってどれぐらいのメリットといいますか、例えば市外から来る学生に対して支援を行ったとして、その学生が市外に出ていって別なところで就職してしまったら、本市として支援した分は一体何だったのかということにもつながってしまうと思いますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
商工観光課長
今委員おっしゃるようなこともあるかと思いますが、やはり地元の学校ということもありますので、そちらに通って地元に就職し、そのまま働いていただいて地元に居住し続けるというようなことを一つの目的として実施しているものです。これだけではなく、そのほかにもインターンシップ事業、学生が直接企業にかかわっていくとか、そういった事業をあわせて人材流出を防いでいくことも含めて取り組んでいくものです。
吉田
195ページです。6款1項10目19節負担金補助及び交付金の岩沼藤曽根地区太陽光発電施設整備事業負担金について、その土地はもともとどのような土地で、今後この事業を進めるに当たってどのような土地改良をしていかなければいけないのか、また、その事業によって見込まれる効果もあわせて御説明をお願いします。
農林水産課長
この太陽光発電施設整備事業は復興交付金事業です。大型の圃場整備により新たに整備される農業用の排水施設等の維持管理経費や、震災による地盤沈下の影響によって排水経費がふえている状況です。そのために要するに土地改良区の賦課金が高くなって、被災農家の経営を一層圧迫するといったことが懸念されます。そのようなことに対する一つの解決策として、今回太陽光発電設備を設置し、そこで得られた電力を売電することによって先ほど申し上げた経費に充てて、かかり増し経費、農家負担の軽減を図るという目的で取り組む事業です。太陽光発電施設を整備するのは岩沼市の藤曽根地区ですが、この土地は岩沼市の藤曽根地区という集落があったところです。その集落については災害危険区域に指定され、集団移転をされているわけですが、その土地を活用し、県の事業によって太陽光発電施設を整備するという内容です。
吉田
太陽光パネルを設置したことによって、例えば昨年は、土地の性質は全く違いますが、茨城県常総市での堤防の決壊の要因になったことも考えられるという国土交通省の見解もありました。今回は堤防ではありませんが、自然災害がより威力を増している中で、例えば突風などで太陽光パネルが根こそぎ全て吹き飛ばされるようなことも実際に起きていまして、そのような対策についてはどのように講じていくのでしょうか。
農林水産課長
これから整備する太陽光発電施設ですが、特にほかと明らかに特別な仕様ではありません。一定の設置基準に基づいて設置し、施工されるものと考えています。したがって、極端な突風が吹いても必ず大丈夫なのかというところまで尋ねられるとなかなか答弁も難しいのですが、一般的にそういったものにも耐えられる施工と考えております。
吉田
201ページの7款1項2目商工振興費の中でふるさと寄附金についてお伺いいたします。8節報償費として計上されている金額と13節委託料、消防の点検委託料も入っていますが、これを合わせて歳入として見込んでいる3億円に近い額になっています。恐らく委託料には郵送料なども含まれているかと思うのですが、3億円見込んでいる寄附金はほとんど全て謝礼品としてお返しするような形で見込んでいるのかどうかお尋ねします。
財政課長
ふるさと寄附金については歳入で3億円計上させていただいております。歳出については、件数として4万件とお話ししていますが、経費としては5億円相当分を見込んでいます。その5億円に係る経費が、予算上は6割を少し超えますが、おおむね6割程度が御礼品の送付あるいは事務的な経費に要するということで、それと同等見合いの3億円を歳入で計上しています。ただ、歳出については、5億円相当の寄附を見込んだ中での支出ということで計上しています。
なお、ふるさと寄附金の謝礼品、報償費になりますが、寄附をいただいている中の47%を御礼品とそれを寄附していただいた方に送るための送料ということで見込んで計上しています。
それから、ふるさと寄附金特産品取扱委託料ですが、金額的には御容赦いただきたいと思いますが、内容としては、月額の基本料、1件当たりの取り扱い、それから金額ベースでのお支払いといった内容で構成する委託料ということで計上しております。
吉田
やはり謝礼をお送りするということで、市の側としては、その謝礼品をつくっているメーカーを初めとして地元の企業の方たちに広く恩恵が行き渡るようにという趣旨であることはもちろんだと思うのですが、委託先で決めることかもしれませんが、謝礼を準備する段階でどこからそれを仕入れるというか、卸なのか製造元なのか、あるいは小売なのか、その辺御説明をお願いします。
財政課長
御礼品の送付については、平成27年度においては観光物産協会に委託して進めています。年に2回、この事業に参加していただける事業者の方を公募という形でお願いしております。実際に事業者から応募いただいた中から市と観光物産協会でつくる選定委員会で選定して御礼品を決めています。
吉田
213ページの8款2項1目19節負担金補助及び交付金の中で国道4号拡幅改良(4車線)建設促進期成同盟会負担金とあります。具体的にどのような構成員で成り立つ同盟会でどのようなことを望んでいるのか、御説明いただければと思います。
土木課長
国道4号拡幅の件ですが、国道4号を通る白石市から仙北は栗原市、その6市4町1村の期成同盟会を発足しまして、4車線化を目標としている協議会です。
吉田
平成28年度、何か進展は見込めるのでしょうか。
土木課長
この路線は国土交通省管理ということで、今私の認識しているところでは、大河原町、蔵王町宮地区あたりの工事を進めていると捉えています。
吉田
先ほど貸し出し用のタブレット端末、生徒用40台というお話でしたが、40台というのは普通に考えると1学級分の生徒数にほぼ匹敵するのではないかと思いますが、それは生徒たちに継続して貸し出し続けるのでしょうか。それとも1時間目は1組で2時間目は2組というように持ち回りで使っていくのでしょうか。その辺の説明をお願いします。
学校教育課長
その学校の中で一つの授業時間での40台ですから、1時間目である学級で使ったら、2時間目は別の学級という形になると考えています。
吉田
そうすると、ある生徒が使った端末を別の生徒が次の時間に使うことになりますので、前に使った生徒は、そこに自分で何か教育の成果とか作品等を保存したりは恐らくできないことになると思いますが、その認識でよろしいでしょうか。
教育長
まず、モデル校として取り組むということもありますが、子供がどのような場面に使うかということも含めての研究となります。それで、子供がある時間に学習した成果がタブレットに残らないのではないかという御質疑ですが、残す必要がある場合は各学校のサーバー等に保存することもできます。インターネット回線、Wi-Fiも各学校で使えますので、そのような活用の仕方も含めて、平成28年度、モデル校でいろいろと調査研究をしてもらいたいと考えています。
吉田
249ページの2款1項2目14節の教育用コンピューター借上料について再度質疑させていただきます。こちらはモデル校を1校選んで進めていくというお話でしたが、その1校の決め方としては、このような授業をしていきたいのでコンピューターを使いたいという学校側からの申し出によるのでしょうか、それとも教育委員会で1校を指定するという形になるのでしょうか。その辺の選び方を教えてください。
学校教育課長
まず、平成28、29年度2年間でこのICT教育推進モデル事業という形で進めたいということでしたので、実施要項を教育委員会でつくり、それを各学校に示して、小中16校の中から1校を推進校として選んで実施するということで提案させていただきました。その上で、手を挙げた学校が実際は4校ありましたが、その中から、教育委員会でもいろいろと検討した上で、今回1校を決めさせていただいたという流れになります。
吉田
その1校はいつの段階で決定されるのでしょうか。
学校教育課長
1校ということで候補は挙げていますが、あくまでもこの予算が通ってから、その学校と具体的にお話をしながら進めていきたいと考えています。
吉田
もう一度、249ページの10款1項2目14節の教育用コンピューター借上料、いわゆるタブレット端末についてお伺いします。現在、小学校1校をモデル校にとおっしゃっていますので、今後、成果が出てきた場合、小学校全体に広げていくのか、あるいは中学校まで含めて広げていくのか、いろいろ見通しを持っておられると思います。その辺のところ、もし成果が出れば広げていくのか、成果が上がらなければどうなるのか、それとも成果のいかんにかかわらず今後その事業をどんどん進めていくのかについてお伺いします。
教育長
総括質疑の市長答弁にあったかと思いますが、現在の考え方としては、平成28、29年度にモデル校1校で調査研究に当たっていただくと。その後、平成30年4月開校の閖上小・中学校にも導入する考えでおります。具体的に何年計画というところまでは考えていませんが、順次市内の小中学校に拡大していきたいという考えは持っています。ただ、委員御指摘のように、仮に効果が全くないという研究結果になれば、その考え方自体を見直さざるを得ないということも想定しています。ただ、現時点ではほかの学校にも順次拡大していきたいという考えは持っています。
吉田
効果があるかないかという評価の仕方について、具体的にどのような観点で比較し、誰が主体となって評価をしていくのか、御説明をお願いします。
教育長
タブレットを初めICTについては、既に全国各地の先進校でかなり取り入れており、そのメリット・デメリットについてもいろいろな観点から議論されています。これまでの実績も参考にしながら、2年間の研究で、教師が教材提示等のために使用するという使い方と児童自身が学習に使用するという2つの観点から、モデル校で効果的な活用のあり方を研究してもらい、その成果をまとめて、教育委員会に報告をしていただくと。それを主として教育委員会で検証して、今後の方針を決めていきたいと考えています。
吉田
283ページ、10款5項5目8節報償費の資源調査指導・調査員謝礼ですが、こちらの調査員の方の具体的な仕事の内容や人数について御説明をお願いします。
文化・スポーツ課長
これは歴史文化基本構想に伴う資源調査です。これは平成26年度から進めている事業ですが、その3年目として、平成27年度で実施した資源調査について整理してまとめる作業を平成28年度に行うものです。作業員については154人を想定して進めていますが、歴史文化基本構想策定委員会の資源調査指導・調査員謝礼ということで、まず指導員として延べ130人、調査員として延べ140人、調査補助員として延べ60人を現在想定しているところです。
委員長
課長、最初の154人はどういう数字ですか。改めて文化・スポーツ課長。
文化・スポーツ課長
先ほど答弁した154人については、7節の作業賃金でした。8節については後から説明した人数です。
吉田
今の御答弁の内容ですと、指導員が延べ130人、調査員が延べ140人、調査補助員が延べ60人と。延べとおっしゃっていますが、これは兼務しているところがあるとか、そういう意味でしょうか。
文化・スポーツ課長
例えば2人で一日だったら2人ということで、その日によって作業する人数が変わってきますので、延べという表現を使っています。
吉田
295ページ、11款3項1目の15節工事請負費の閖上小・中学校改築工事についてお伺いします。現在見込まれている平成30年度の生徒数はかなり少ない人数になっていると思います。そこで、現在の学区をそのまま適用して閖上地区に住んでいる児童生徒が通った上で、それにあわせて市内全域から児童生徒を集めていくという方針でよろしいのでしょうか。
教育長
現在の通学区域を見直す考えはありませんので、現在の閖上小学校、閖上中学校の学区に居住する児童生徒が基本的に閖上小中一貫校に通うこととなります。それにあわせて通学区域を弾力化することを閖上小・中学校については考えていますので、市内全域から受け入れることもあわせて考えています。
吉田
市内全域というと面積的にはかなり広くなりますので、例えば西部の団地の児童生徒が通学を希望される場合、安心して毎日通学ができるように、また、長期休業中も学校に行くことがあると思いますが、そういうところについてのケアはどのようにお考えですか。
教育長
市内全域から受け入れるという考えを示している以上、できるだけ保護者、児童生徒に負担をかけないで閖上に再建する閖上小中一貫校に通うことができるような方策について、今、決定ではありませんが、具体的に検討を進めている段階です。
吉田
もう一度、295ページの11款3項1目15節、閖上小・中学校改築工事についてお伺いします。市内全域から生徒を集めることを今後目標としていくということですが、小中一貫校という学校のあり方以外の面で、保護者の方がぜひ自分の子供を通わせたいと思うようなほかの要素を今後検討していくお考えはないのでしょうか。
委員長
吉田委員に申し上げますが、予算の質疑で、これは工事費でついていますので、考え方についてはまた別のところで質問等をしていただきたいと思います。
吉田
355ページの11節需用費の医薬材料費の内容をお伺いします。
休日夜間急患センター事務長
これは今回新たな施設内に設けた院内薬局にかかわる医薬材料費です。
吉田
院内薬局となると患者さんがこの医薬材料費の中からつくられた医薬品を購入される形になると思いますが、患者さんの支払い分は歳入ではどこに計上されているのでしょうか。
休日夜間急患センター事務長
350ページ、351ページの1款1項1目の休日夜間急患センター使用料の増額分に含まれています。
吉田
351ページの歳入の1款1項1目の休日夜間急患センター使用料は先ほどの御答弁で薬品代も含むということで認識しましたが、どうしても使用料というと場所の使用料のように私は個人的に捉えてしまうのですが、薬品等のほかにどのようなものがあるのか、もう少し具体的な内容をお知らせいただきたいと思います。
休日夜間急患センター事務長
この使用料については、患者が急患センターに診療に来られた際にお支払いしていただくもの全てです。今回院内薬局を設置しましたので薬局については薬品の料金、それから診療の際に支払う金額等が含まれています。利用者負担金と診療報酬、それに今回薬品の分が加わったというのが主な内訳です。
吉田
377ページの4款1項3目任意事業の20節扶助費で在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業とありますが、平成27年度当初よりも減額となっている理由について御説明お願いいたします。
介護長寿課長
平成27年度当初予算では426人ということで計上していました。平成28年2月補正で減額補正ということで333人と見込んだところです。平成28年度については393人になるのではないかと見込んで予算を計上しております。
吉田
そうすると平成27年度当初から1年間で見込みとして30名ほど減っていることになると思いますが、それは必要とされている方が減っているのか、それとも申請の数が減っているのか、その辺の理由というか見込みはどのようにお考えでしょうか。
介護長寿課長
この紙おむつ支給事業の対象者の減ですが、担当課としてもはっきりとした要因は実は把握していません。今後も、広報、ホームページ、それから地域包括支援センター、ケアマネジャー等を通じて周知啓発をしていきたいと考えています。
名取市一般会計予算
吉田
議題となっております議案第3号 平成28年度名取市一般会計予算について、教育に関連する事業を中心に意見や要望などを加えた上で、賛成の立場から討論を行います。
平成28年度予算は、復興への思い、心からの笑顔を求めて、新たな未来の実現に向けて、復興の加速化を目指すという強い決意のもとに編成されたものと捉えております。被災された方々が再び安心して住み、働き、憩うことができる環境を取り戻すことは、我々名取市民はもとより全ての日本人が共有する願いです。
被災した閖上小中学校の復旧は、復興を進める上で欠かせない事業であり、新たなまちづくりが行われる閖上が再び多くの住民でにぎわう地域となるためにも、教育や地域コミュニティーの拠点である学校は必要不可欠な施設です。当面は被災された方々の生活再建が最も重要な課題ですが、やがて復興が進み、世代が交代したとしても、学校が地域住民の連帯を保持するための施設である事実は変わらないはずです。
児童生徒数の減少により、特に過疎化する地域において昨今学校が閉鎖されるケースがふえております。今年度をもって仙台市では中野小学校、荒浜小学校が閉校されます。他の自治体でも閉校する小学校が多数あります。私が最も恐れるのは、復興の夢を乗せて新たに歩む閖上小中一貫校が、生徒数の減少によって存続させることが困難となる事態を迎えることです。再建する場所を厳選することで、閉校のリスクを軽減することは可能であると思われます。しかし、閖上小中学校災害復旧の現計画に対して、国からの支出が決まっているとの答弁を受けまして、今の段階での計画見直しは復興のさらなるおくれを招くと理解するに至りました。
市内全域から児童生徒を受け入れるという目標を掲げる教育委員会が、今後どのようにしてそれを実現するのかを注視していきたいと思います。教育長は、小中一貫校の計画見直しを求める私の一般質問に対し、学校は地域に浮かぶ船と答弁されました。大小さまざまな船が将来にわたって安全に航海できるよう、市長を初め船を預かる執行部の皆様には住民の声が届けられるのを待つばかりではなく、風と波を正確に読むがごとく、みずから進んで市内全域の住民の声を聞き取られることを強く要望いたします。
さて、政府によって人口減少に歯どめをかけるという目的が提示されたことを受けまして、市の実情に応じた今後5年間の目標や講ずべき施策の基本的方向などが、名取市版地方創生総合戦略として策定されました。平成28年度予算には、総合戦略に基づいた事業が数多く盛り込まれており、未来を担う子供たちや子育て世代への支援が重視されていることについては、その方向性を評価したいと思います。
名取市地方創生総合戦略の基本目標3、基本的方向の3には、学校教育と社会教育の充実を図り、知の地域づくりを目指すことが明示されております。具体的な施策として、閖上小中一貫校による個性豊かで魅力ある学校づくりを進めることが上げられ、平成31年の児童生徒数を開校時よりふやすことが目標とされております。平成27年度は学びの場となる校舎改築の予算が措置されておりますが、教育課程については検討中とのことです。小中一貫校はことしの4月から制度化されるために、平成30年の開校時にはさまざまな課題が浮かんでいることが予想されます。全国各地の小中一貫校から頻繁に情報収集を行い、浮上した課題を本市の実情に照らしてシミュレーションし、本市で前例のない形の学校に対するさまざまな不安を可能な限り払拭することで、再建される学校がすばらしいスタートを切れるよう願います。
また、平成28年度はICTを活用した教育が、モデル校に指定される1つの小学校で始まります。私はかつて営んでおりました学習塾におきまして、ICTを活用して授業を行っておりました。初めこそは学習への関心を高める効果が見られましたものの、本当の学ぶ喜び、それから楽しさに気づかせるものは道具ではないという結論に至る経験をしました。ICTの導入で最も戸惑うことになるのは、恐らく現場で指導に当たる教員の方たちであると思われます。児童と向き合う時間や教師として必要な資質、能力を向上させるための時間が削られることのないよう、まして学校業務の効率化による教員数削減などという誤った方向へ進むことのないよう、留意していただきたいと思います。
それから、名取市地方創生総合戦略の基本目標1として、結婚、出産、育児に優しい環境づくりが掲げられております。平成28年度は子供医療対策や不妊治療、児童センターの運営委託などが予算措置されており、子育て世代にとって一定の負担軽減が見込まれると思われます。しかし、子供を保育所に預けたくてもあきがない待機児童の問題、学校の授業だけでは基礎学力がつかず、塾に通わせざるを得ない子供がいる実情、また高額な大学授業料、そして給付型奨学金の少なさなどは克服されておらず、結婚、出産、育児に優しい環境までの道のりは、まだまだ遠いと言わざるを得ません。住民が実感できるほどに優しい環境を整備するためには、さらなる努力が必要であろうと考えます。
最後に、名取マイレージ事業やチャレンジショップ事業、自主防災組織支援事業などの住民参加型の事業に予算がつけられていることを評価したいと思います。これらを行う上で、住民からさまざまなアイデアや要望が上げられると予想されますが、できない理由を見つけるのではなく、できない理由をともに克服する姿勢を見せることが、いつまでも住み続けたいまちとして選択されるための鍵になると考えます。住民と行政が一丸となって、持続可能なまちづくりが行われることを期待し、私の賛成討論といたします。