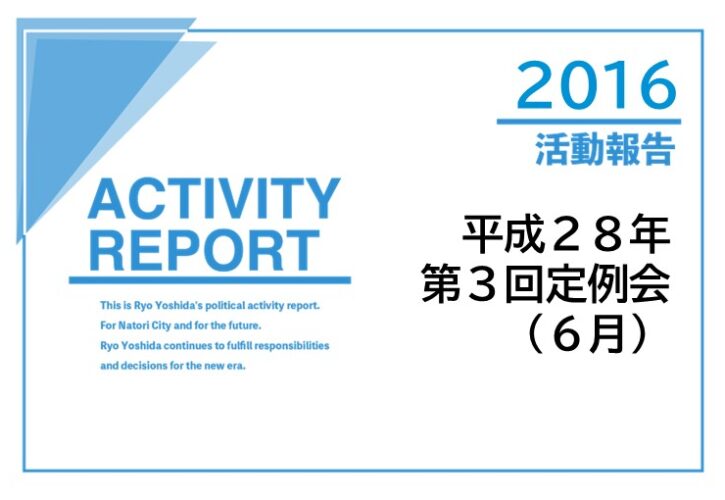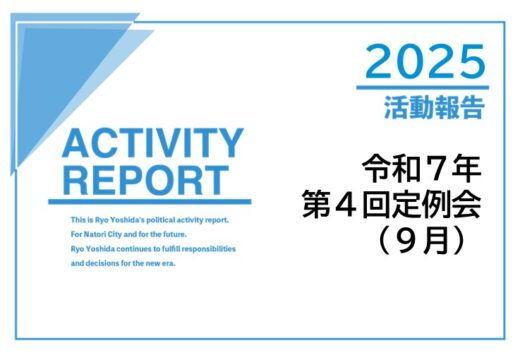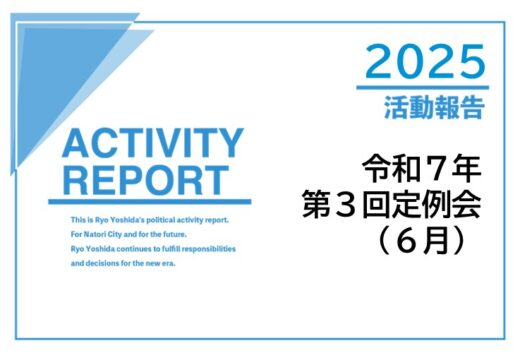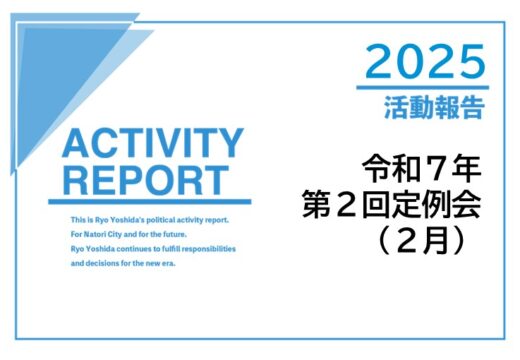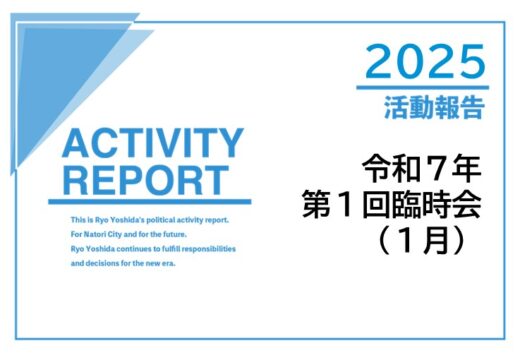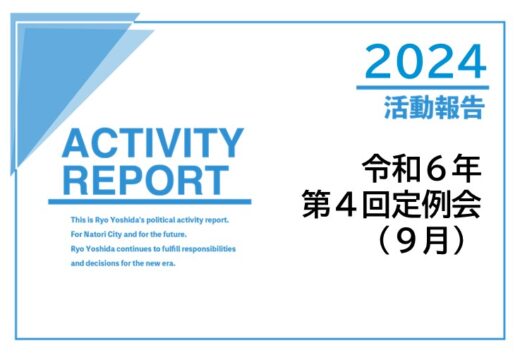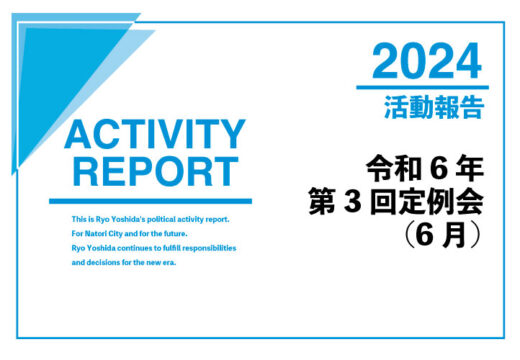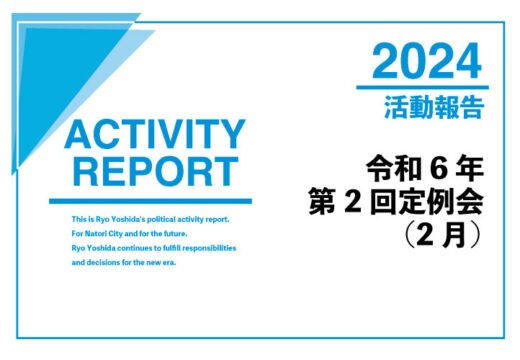本会議
(議案第54号 名取市議会議員及び名取市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例)
吉田
このたびの条例改正の背景には公職選挙法施行令の改正があるという説明がありましたが、公職選挙法施行令がこのような形で改正になった理由についての御説明をお願いします。
選挙管理委員会事務局長
このたびの改正については、公職選挙法施行令に規定する公営単価については国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律と人件費、物価の変動等を考慮する共通の考えによって、3年に一度、参議院議員通常選挙の年にその基準額の見直しを行うことを例としているところですが、その期間中、平成26年に消費税が5%から8%に引き上げられたことも踏まえ、国でこの経費の見直しを行ったものです。
吉田
国で経費の引き上げが決まったということですが、選挙運動に対して公費負担を行うことについてはどういう理由があるのか。平成28年2月の第2回定例会の私の一般質問では、お金のかからない選挙の実現や、候補者間の選挙運動の機会の均等化などの理由があるという御答弁がありました。このような形で公費負担の引き上げが行われなかったとしても、本市で今後行われる選挙において、お金のかからない選挙、あるいは選挙運動の機会の均等化などが特に害されることはないと思いますが、それでも、なぜあえて国に合わせて引き上げなければならないのか、お伺いします。
選挙管理委員会事務局長
ただいま吉田議員がおっしゃられたことももっともだと思いますが、市議会議員等に立候補する方においては、こういった公費負担の補助がないとなかなか出られない方がいらっしゃるという考え方も一つでありますので、本市としても引き上げを行いたいと考えております。
(議会案第4号 日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求める意見書)
吉田
この意見書の表題を見ると、まさにそのような決断と行動が必要なときであることは否定できないことかもしれません。しかし、今の世界情勢を見たときに、リスクを考えずにこのような意見書を提出することで、もし仮に政府でそういう動きが始まった際、どのようなことになっていくのかという不安も実際にあります。提出されている資料の3ページに日本政府に要望することが2項目ありますが、2つ目として、米国の核兵器による「拡大抑止」、いわゆる「核の傘」に依存した安全保障政策から脱却することと書かれています。この核の傘に依存した安全保障政策からの脱却という意味について、具体的に御説明をお願いしたいと思います。
大沼宗彦議員
今、核の数が1万5,000発あると言われていますが、その90%をアメリカとロシアが保有しているという中で、核廃絶のための行動を起こしていくことがどうしても必要だと。そして、核の傘を大義名分にして核廃絶に対する批判をしていくことは、必ずしも得策ではない。核の傘があるから守られているという考え方からは脱却する、抜け出すことがどうしても必要だということで、そうでなければ核廃絶の願いが実現していかないということです。また、中国の脅威、北朝鮮の脅威などいろいろなことが言われますが、そのようなことを言っていたのでは、全体の核廃絶の運動につながっていかないと思います。核廃絶のためには、どうしても今まで日本がとってきた核の傘という考え方から抜け出していかなければ、このような運動がさらに広まっていかないという考えからこの意見書(案)を出しています。
吉田
核の傘という言葉を具体的に考えてみると、もし万が一、日本が外国から核の攻撃を受けたと仮定したときに、アメリカがそれに反撃をするという意味で、反撃できる力があるからこそ、日本が攻撃を受けないと。そのような前提があるというのは理解できることだと思います。今の御説明は私にはちょっと理解できないのですが、核の傘にかわるような抑止力については、具体的に何かお考えなのでしょうか。
大沼宗彦
東南アジアにはASEANという話し合いで紛争を解決する機構がありますが、北東アジアにも話し合いで解決していくようなものをつくっていくと。まどろっこしいようにも思えますが、今までの歴史の中で、武力による威嚇や軍備によって平和が訪れてきたか。これは戦国時代から、また古代の歴史からも、繰り返されては悲劇が生まれてきたという歴史があるわけです。人間ですから、考えて平和友好条約を構築していくということが必要なのではないかと思います。それから、日米安全保障条約がありますが、これも平和友好条約、対等、平等の条約にしていくと。その中で話し合いが生まれるという方向を目指す必要があるのではないかと思います。誰かが守ってくれるという考え方をしていても、一発でもこの地球上で核が使われたならば、地球は滅亡しますので、話し合いをしていくことをまどろっこしいと考えないで、対等、平等な平和友好条約をつくっていく、それを世界中に張りめぐらせていくという方向が、平和に向けての着実な一歩になるのではないかと思います。
吉田
話し合いによって解決できればというのは、とてもすばらしい理想だと思います。それで解決できるのであれば、これまでの歴史を見ても、幾らでもそういう解決ができる局面はあったはずです。しかし、今、現に日本が曲がりなりにも戦禍に巻き込まれないでいるという現実の裏には、やはりアメリカによる日米安全保障条約があるという現実、これは否定できないことだと思います。アメリカの核の傘に依存した安全保障政策から脱却するというのは、いわば日米安全保障条約そのものを否定するというように捉えられるわけですし、そのことを日本政府に要求したところで、それは恐らく通るわけがないと。それはなぜかといえば、それにかわる抑止力として話し合いで解決しましょうというのは、抑止力でも何でもなく、理想でしかありませんので、それでは全く政府に通じるところはないと思います。ただ、この文章を読んで、提出者の方の大変強い気持ちは非常によく伝わってきます。気持ちとしてはとても理解できます。ただ、もしこのような意見書が仮に通って、政府がアメリカの核の傘への依存から脱却しましょうということを仮に決定した際、その後の、今おっしゃったアメリカ、ロシアを初めとする1万5,000発の核兵器の廃絶はどのように進んでいくと予想されるのでしょうか。
議長
吉田議員に申し上げます。議論の場ではありません。これは常任委員会に付託いたしますから、常任委員会でいろいろとお話をしていただきたいと思います。答弁は結構です。
一般質問
吉田
初めに、大項目1 JR名取駅西口広場の整備についてお伺いいたします。
JR東日本がまとめた統計によりますと、2014年度の名取駅の1日平均乗車人員は1万2,000人を超え、仙台駅とあおば通駅に次いで宮城県内で3番目の多さとなっております。
名取駅の出入り口は東口と西口の2つがあることは御承知のとおりですが、宮城県農業高等学校の仮設校舎の利用開始などの理由によってか、西口を利用する乗客が増加傾向にあるように思われます。朝の通学の時間帯、なとりん号の到着を待つ学生らでバスの乗車場に行列ができております。雨の日ともなると、生徒や一般の利用者は傘を差してバスを待ちます。混雑する車内では、傘についた水滴が服をぬらし、不快なひとときを過ごすことを余儀なくされていることと察せられます。また、降車場と駅舎が離れており、雨の日にはバスをおりた方が駅まで走って移動する姿も見られます。小さいお子さんの歩行もあるため、危険がないとは言えない状況です。両手で松葉づえをつき、ずぶぬれで移動する女子生徒の姿を目にしたこともあります。
一方で、東口には駅舎とバス停をつなぐ屋根が設置されております。東口のバス停に行列ができているところは余り見かけませんが、仮に行列ができても雨にぬれることなくバスを待つことが可能です。バスから駅、また駅からタクシーなどの移動にも一々傘を開閉する必要はありません。
今後、増田地区の再開発事業により複合施設が集約、再建されれば、西口も含めた名取駅利用者の増加が考えられます。
そこで、小項目(1)JR名取駅西口にも東口と同様に、駅舎とバス・タクシーの乗降場をつなぐ屋根を設置し、利便性の向上を図るべきについて市長にお伺いいたします。
市長
JR名取駅西口は、「自然の豊かさを感じさせる緑豊かな景観」をコンセプトとし、バス及びタクシー乗り場の屋根の設置については、木陰をイメージしたデザインとなっており、東口と比べ小規模ではありますが、議員御承知のとおりバス及びタクシー乗り場には屋根を設置しております。
近年では、仙台空港アクセス線の開通など駅全体の利用者は増加傾向にあり、また、東日本大震災による津波により甚大な被害を受けた宮城県農業高等学校が高舘地区に移転したことにより、名取駅西口の利用者も増加しているものと捉えております。
議員から御提案のありました駅舎とバス・タクシーの乗降場をつなぐ屋根の設置については、当初計画どおりの整備も完了していることから新たな整備をする予定はありません。
吉田
ただいまこれ以上の整備の御予定はないとの答弁ですが、状況は少しずつ変わっております。例えば7月には仙台空港が完全民営化されます。空港利用者の増加が見込まれます。本市の地方創生総合戦略の基本目標3には交流人口を100万人にまで増加させるとうたわれており、仙台空港の完全民営化を契機として観光客の増加を実現したいところです。仙台空港線の起点駅であるという立地を生かした施策を打てば、本市を目指して来る観光客の増加とそれに伴う駅周辺の活性化にも期待が膨らみます。
そこで、市単独で建設するのがもし難しいのであれば、周辺商業施設、企業、さらに仙台空港の運営者などを巻き込んだ形での建設を目指すべきではないでしょうか。市長にお伺いいたします。
市長
都市のインフラ整備はいろいろな種類がありますし、どこまで整備すべきかということはそれぞれの計画の中で取り組んでいく必要があるだろうと思います。今議員おっしゃるような駅前の利便性を向上させることも都市の魅力の一つになろうかと思います。ただ、西口については、当初の名取駅西土地区画整理事業の中での駅前の整備ということで基本的なコンセプトを持ち、最終の計画案に基づいてまちづくりがなされてきた経緯があります。もちろん屋根があったら便利なのは間違いありません。ただ、改めて整備を行うかどうかはやはり議論の余地があるだろうということです。つまり、都市全体が雨が降ってもぬれずに済むというまちづくりを目指しているのであれば別です。今、議員から一つの例としてお話しいただいた宮城県農業高等学校にしても、駅ではぬれずに済んでも、バス停に着いてそこから校舎に入るまでの間ぬれずに済むかというと、バス停からは相当離れているわけです。そういったことを考えれば、駅前だけぬれずに済むというのも、それは屋根があったにこしたことはありませんが、例えば仮に屋根をかけたとすると概算で2億円近くかかるわけで、これを改めて整備するかどうかとなるとやはり検討の余地があるだろうということです。
吉田
確かに市長がおっしゃられるように、まち全体に屋根をかけるなどということは当然不可能ですし、バスの利用者がバスをおりてからのことや、あるいは名取駅以外のバス停ではどうするのかなど、そのような問題は当然あると思います。ただ、駅全体をもっと利便性を高くするという意味でもう少し検討の余地はないものかと私は思っております。
6月2日に議員協議会が行われ、名取駅前地区市街地再開発事業の説明がありました。その中で名取駅から今度新たに名取駅東口につくられる複合施設までをつなぐ歩道橋の説明があり、それについては施行区域外にあるため別事業として市が発注すると執行部より御答弁があったと記憶しています。その歩道橋の完成した姿を想像してみると、恐らく駅2階の自由通路の東側に扉を設け、そこからもともと東口のバス停にかかっている屋根の上に歩道橋をかけて、そして複合施設の2階部分へとつなげるものになるかと思われます。確かにこの歩道橋もとても魅力的なものです。ただ、自動車の通行量がそれほど多くない車道に歩道橋をかけるわけですから、多額の予算を組んでの新たな整備以外にも、東口広場においてもとからあるバス停の屋根をさらに東へ延ばすことで、1階を通ることになりますが、複合施設の1階まで延長する整備が可能ではないか、そのような仕方もあるのではないかと考えたところです。
そして、もしこの方法で行えば、雨にぬれることなく駅から東口の複合施設への移動も可能となりますし、同時に歩道橋よりは建設費が大幅に削減されることが予想されます。この削減によって生じる具体的な金額は私にはわかりませんが、この削減分を回すことによって西口広場のバス停の屋根の設置が可能となれば、駅の西口から東口の複合施設まで一体的に雨にぬれない形の整備が可能になると思います。現行案と今申し上げた西口、東口両方での雨にぬれずに済む整備について、利用者の観点で比較検討すべきではないかと思います。市長にお伺いいたします。
市長
まちづくりにはいろいろな要素がありますし、いろいろな選択肢があります。そういった中で一度総合的に検討させていただいた上で取り組みたいと考えます。
吉田
前向きな御検討に期待しております。
次に、大項目2 教育の負担軽減と、費用対効果向上についてお伺いいたします。
毎年4月は、入学や進学などで新たなスタートを切る子供を持つ保護者にとって喜びの季節であるとともに悩みの季節でもあります。子供が学校で使用する学用品を購入しなければならず、家計への負担が重くなるからです。
義務教育を無償とすることは憲法第26条に規定されているとおりですが、公が負担するのは施設、人件費、教科書などにとどまり、制服、学用品、校外学習の費用などは原則として保護者が直接負担しているのが現状です。これらの費用は経済的に厳しい状況にある家庭には就学援助という形で支給されることとなっております。本市においては全児童生徒のうち1割近くが就学援助の認定を受けていますが、裕福ではないのに認定を受けられず、悩んでおられる保護者も多数存在しているものと思われます。これらの費用についてはそう簡単に公費で賄うことに踏み切れるものではないことは理解しておりますが、せめて負担の軽減や、負担に見合うさらなる効果の向上を目指すことは行政の責務ではないでしょうか。昨日、先輩議員や同僚議員からも子供の貧困について一般質問が行われましたが、子供の貧困問題にとどまらず、少子化の問題を少しでも改善に向かわせるためにも、教育に係る家計負担の軽減は自治体ごとに取り組まれるべき課題であると考えます。
とりわけ学校制服は、通常は3年間しか着ることがなく、しかも学校生活においては体育着で過ごす時間が長いことから、上下で3万円を超える現在の金額設定は高額であるとの声が一部で聞かれます。量販店に行けば成人用スーツが上下1万円で買える時代です。お父さんが1万円のスーツを着てせっせと働き、子供が3万円の制服を3年間で用済みにしてしまう。この漫画のような光景が現実に起こっているのです。
そこで、小項目(1)学校ごとに指定され、競争の原理が働きにくい制服の価格について、保護者の負担軽減策を講じるべきについて教育長にお伺いいたします。
教育長
まず、義務教育を無償とするという憲法の条文の御紹介がありましたが、私は基本的に保護者の教育に係る負担は極力軽減すべきだという思いは議員と同じくするものです。ただ、憲法の義務教育は無償とするということについては、国公立の義務教育諸学校においては授業料を徴収しないという意味と一般的には解釈されていると認識しております。そのことを踏まえてお答えいたします。
現在、本市においては中学校5校が制服を指定しております。5校それぞれが制服を統一することで、各校の生徒に一体感が生まれると考えます。制服の価格については、男子Mサイズの平均が約3万4,000円、女子Mサイズが約3万3,000円です。
中学校の制服は、3年間着ることができるようにするため、耐久性にすぐれた生地を使用しています。さらに、吸汗性、保温性においても改良が重ねられております。また、制服のデザインを一定期間変えないことで、型を新たにつくることなく製造ができたり在庫の生地を活用できるという点で価格が抑えられております。以上の点から適切な価格であると考えます。
吉田
食品、家電、日常品などさまざまな商品、およそ商売というものは価格の競争があることによって消費者に不当な不利益を負わせない仕組みとなっています。しかし、学校制服については、このような競争のプロセスをほとんど経ることなく価格が設定されていると捉えられます。確かに制服のメーカーは複数ありますが、価格がより低くなるからといって頻繁にメーカーを変更することは、先ほど教育長がおっしゃいましたように逆に負担がふえてしまうため考えにくいことですが、例えばデザインは変えないとしても、販売の価格は競争入札で決定すべきではないでしょうか。教育長にお伺いいたします。
教育長
制服の今の価格設定において不当な不利益を与えているという御指摘でしたが、私はそのようには考えておりません。現在、市内の5つの中学校の制服は名取衣料店会を通して制服メーカーから購入しています。この価格については、かなりの間ほぼ据え置きとしていただいておりました。私はそういった点では衣料店会や制服メーカーが非常に努力していただいているという認識を持っております。先ほど言われたように、確かに量販店で1万円のスーツもあります。ただ、制服については、私が申し上げるまでもなく、その学校独特のデザインで生産します。例えば生徒数の少ない学校であれば1年間に男女それぞれ二、三十着しかつくらないという中で制服を提供していただいております。ですから、大量生産できる大手の紳士服店などで販売されているものとの比較は一概にはできないのではないかと思います。
それから、制服の価格をもっと安くすることができないかということについては確かに検討の余地はあろうかと思います。ただ、私服にした場合、むしろ余計にお金がかかるという声もよく聞かれます。私の子供たちも、中学校に通っているとき制服を3年間着ました。それを私服にした場合、多分もっと費用がかかるのではないかと思います。それから、デザインについても子供たちが愛着を持っていますし、業者では材料として使う生地などを一定程度まとめて用意することで価格を抑えるなどといった努力もしていただいております。
そういったことから、安易に入札によって業者を選定する方法はなじまないのではないかと考えます。
吉田
文部科学省が掲げる確かな学力には「主体的に判断し、行動し」という文言が盛り込まれております。今教育長は否定的な立場だと思いますが、将来において、制服そのものの廃止、そして行き過ぎでないデザインを認める寛容化も、確かな学力に掲げられる主体的な判断力や行動力を養う点では意味がないとは思われません。ただ、おっしゃるように、制服があることで私服よりも全体的な費用が抑えられるというメリットも確かに小さくはありませんので、今後、保護者や生徒はもちろん、広く市民から意見を集めた上で今後の制服のあり方を検討する機会を設けていただきたいと期待します。
では、次に移ります。
ただいま取り上げた制服は中学校3年間を通して使用するものです。その一方で、毎年保護者が負担する費用として、教科ごとに必要となる参考書、問題集などの補助教材があります。これらにかかる費用も学校によって差がありますが、本市16の小中学校においてはそれぞれ1人当たり年間5,000円から2万円程度の幅で設定されています。今の時代、塾に通っている、あるいは通信教育を受けている児童生徒は非常に多くおられます。民間の教育業者が使う教材も、学校で購入する補助教材と内容的にはさほど差異はありません。保護者としては二重三重に教材を購入していることとなり、かさむ教育費の一因となっていると考えられます。補助教材は授業で使用するため、購入を任意とすることは難しいと思われます。それなら、せめてこの補助教材を最大限に活用して少しでも学力の向上につながるよう努力することが学校の役割ではないかと思います。
そこで、小項目(2)保護者が費用を負担する児童生徒用の参考書や問題集を授業時間内に極力活用し、基礎学力の向上につなげるべきについて教育長にお伺いいたします。
教育長
参考書や問題集は学校教育法第34条によるところの教科用図書以外の図書や教材に含まれるものであり、指導の効果を高めるため、児童生徒の実態に応じ有効に活用しております。
その活用については、御指摘をいただきましたとおり授業時間内に極力活用しておりますが、家庭学習において活用される場合もあります。家庭学習に使用された場合は、学校で答え合わせを行ったり、採点や評価を行ったりするなど、各学校において補助教材を有効に活用し、学力向上につながるよう努めているところです。
吉田
今教育長が御答弁されたように、現場の学校の先生方はそれぞれ指導に工夫を凝らしてよりよい授業となるように日々努力されていることと思います。補助教材をどのように指導に役立てるかということについても、教師によってさまざまな考え方があると思います。ただ、やはり保護者に負担を求めている以上は、年間の授業時間内に補助教材をくまなく使い、教師が勤務時間中に全生徒の取り組みを確認することが理想ではありますが、実際は学習指導要領が定める学習内容と授業時間数を考慮すれば非常に難しいと思われます。
ですから、補助教材の一つの使用例としておっしゃった内容と重複しますが、生徒に家庭学習の課題として取り組ませる、そして保護者の方に答え合わせにかかわっていただく、そのような保護者のかかわりをぜひとも市を挙げて働きかけてはいかがかと思います。これを学校と家庭をつなぐ一つの手段として活用する、そのことで保護者の関心の向上、児童生徒の家庭学習の習慣づけにつながり、基礎学力の向上という最も重要な課題が進展すると思われますが、家庭での保護者のかかわりについて教育長の御見解をお伺いいたします。
教育長
まず、補助教材について先生方によって使い方がまちまちという趣旨のお話がありました。学校で補助教材を選定する際には、年度初めに、学年が1学級の場合は主としてその学年の担任が選定いたしますが、学年を担当する先生方、それに教務主任等が入って、学年として1年間のカリキュラムを子供たちに指導していく上で何が必要か、どれが必要か選定し、どのような場面で活用するかということも含めて十分検討した上で購入計画を立てていると認識しております。
それから、家庭学習についてですが、私は、家庭学習に頼らないで学校の授業時間内で全ての子供に確かな学力を身につけさせることができれば、これにこしたことはないと考えております。ただ、子供たちが学習習慣を身につけたり、あるいは学校で学習したことを繰り返し学習することで教育効果が上がることも実際にあります。
今御指摘いただいた家庭学習についての考え方ですが、それぞれの学校では、家庭学習に関して一定のやり方について先生方で話し合って、保護者ともいろいろと話し合いをしながら家庭学習の手引等を作成しています。今年度以降の教育委員会の取り組みの一つとして、本市として家庭学習をどのように考えていくか、研究主任の先生方の集まりに今年度から配置していただきました学校教育指導専門員が入って検討を進めているところです。ただ、保護者の積極的なかかわりについては、各家庭の実情もありますのでそこまでは今具体的に方向性は考えておりませんが、家庭学習について教育委員会としても各学校の実情を踏まえて検討を進めております。
吉田
ただいまの御答弁で研究主任の方たちと学校教育指導専門員で家庭学習の進め方について検討していくということですので、大いに期待をいたしております。
今申し上げた補助教材については、費用は保護者に負担していただいている観点から、やはり何かの形で保護者の方に常に見ていただけるような環境をどこかでつくることが使い方の工夫という形で一つの方向性ではないかと考えます。
それでは、次に移ります。
新年度の入学・進学シーズンから、間もなくしますと多くの学校では遠足、野外活動、そして修学旅行など、いわゆる校外学習が行われます。特に修学旅行は最も楽しみにしている児童生徒が多い行事の一つで、大人になっても鮮明に記憶が残っている人は少なくありません。修学旅行は宿泊と長距離移動を伴うことから費用は決して安くありませんが、これもやはり保護者が直接負担することが原則となっております。
今年度は、本市11小学校における修学旅行の目的地の内訳を見ると山形方面が1校、岩手方面が5校、会津方面が5校で、日程はいずれも1泊2日、費用は1万6,000円から2万3,000円の間で設定されていると伺っています。一方で、中学校の修学旅行は5つの中学校全てが東京方面を目的地としており、2泊3日の日程で5万4,000円から6万円の費用が設定されております。東京方面という目的地は記録が残る範囲で一度も変更されたことがなく、費用は県立中学校の修学旅行費に合わせて設定しているとのことです。費用にしても目的地にしても改善の余地があるのではないかと考えます。
そこで、小項目(3)中学校の修学旅行のあり方を再検討し、入札に参加する業者に多様な選択肢を示すことを促して、内容の向上と費用の軽減を目指すべきについて教育長にお伺いいたします。
教育長
修学旅行を含めた教育課程の編成は校長の職務権限のもとに行われております。現在、各中学校では、業者選定委員会等において修学旅行に係る業者を検討し決定しております。安全を第一に考えるとともに、経費、学習の狙いの達成と、生徒の自主的な活動を通して互いの親交を深めることができる内容であるかなどを検討し、業者を決定しております。
多様な選択肢との御指摘ですが、安全性、学習の狙い等を示し、複数の業者から見積もりを提出いただいております。内容の向上は、学習の狙いが達成できるプランであるかが重要な観点になると考えますが、安全性を考慮しつつ費用の軽減に努めるよう今後指導していきたいと思います。
吉田
教育長の答弁のとおり、安全性は何よりも最大限に優先しなければならないことは申すまでもありません。ただ、学習の狙いも学校でそれぞれに設定されていると思いますが、やはり今の時代の変化を勘案した上で今後検討が必要かと思います。
現在、目的地として5校が例外なく定めている東京方面ですが、日本政府観光局の統計では、外国人観光客の総数は平成27年で1,974万人に達しております。宿泊旅行統計調査では、外国人宿泊者の延べ数のうち約4分の1が東京に集まっているという現状です。その影響もあってか、既存の宿泊施設は慢性的に空き部屋が不足しています。そのことが宿泊料金の高騰を招いているという指摘もあるほどです。その対策として民泊の推進が今目指されています。私はその是非についてこの場では申し上げませんが、2020年までに4,000万人の外国人観光客を迎えようという政府の方針を考えますと、宿泊施設は今後も不足傾向が続くことが予想されます。よって、東京方面を目指すという長年続いている慣例はそろそろ見直すべき時期に来ているのではないかと思います。
修学旅行の内容の決め方はただいま御答弁あったとおりで、目的地、金額の目安を先に設定することによって、複数の旅行業者がそれに見合ったプランを持ち寄って入札を行っていますが、やはり目的地、金額の大枠が決まっていると似通ったプランばかりの提案ということで、なかなか新しい風が吹きにくいと思います。当然、安全性、そして学習の狙いを前提とした上で、今後、目的地の指示を外す、あるいは金額を今の目安の形から上限額に改めることにより、業者のプラン設定の自由度を上げるべきではないかと思いますが、教育長にお伺いいたします。
教育長
修学旅行についてまず申し上げておきたいのは、ただいま外国人観光客を例にお話をいただきました。申し上げるまでもないかと思いますが、修学旅行は決して観光旅行ではありません。中学校の場合、2泊3日の中にグループごとの自主研修あるいはクラスごとのコース別研修なども盛り込んでいます。修学旅行にただ2泊3日行くということではなく、かなり前から総合的な学習の時間などでグループごとに目的地の検討や行き方を調べるといった事前の学習も行いますし、当然2泊3日もそういった意識で参加させます。戻ってきてからも、グループごとに研修の成果をまとめたり発表したりという取り組みを行っております。
目的地ですが、東京がベストかどうかは議論の余地があろうかと思います。ただ、多くの子供たちを受け入れる宿泊施設、それから子供たちが安全に自主研修を行う場所が複数あること、また本市からの距離や移動、そういったことを考えての選定と考えております。小学校については少し前まではほとんどが福島県会津若松市への修学旅行でした。それが現在、議員にお話しいただいたように岩手方面、山形方面と分かれております。これは、東日本大震災、福島第一原子力発電所の問題も若干影響していますが、小学校の場合、1泊2日という中で適切な場所ということでそれぞれの学校が選定しております。ただ、中学校の場合、2泊3日で東京と同じように目的を達成できるところがあるかということについては、検討の余地はあろうかと思いますが、そう簡単に見つかるものではないと思っております。
最初に申し上げましたように、修学旅行の方面等に関しては各学校で十分検討していますし、先輩やあるいは親が修学旅行で行った場所をまた訪れることにも一つの意味があろうかと考えております。
吉田
検討の余地があるとおっしゃったことについて私なりの考えを少し述べさせていただきたいと思います。
今、東京一極集中の是正と地方の活性化が我が国の課題であると言われているところです。地方創生総合戦略に交流人口の増加を目標として掲げているのは本市に限ったことではなく、多くの自治体が同じことを目指しています。このような時代の要請を受けるのであれば、修学旅行の東京一極集中も変えていくことが必要と考えるべきではないでしょうか。安全性、それから自主研修ができる場所、また移動時間等を考慮して修学旅行のプランが決められるということですが、本市にはほかの多くの自治体と違って空港があるという利点があると思います。そして、今仙台空港は以前とは異なり格安航空が就航しています。お乗りになったことがある方も非常に多いかと思いますが、この格安航空会社を使えば、日にちや時間によりますが、仙台と関西空港の間を安いプランですと2,000円から3,000円で飛べるような設定さえあります。現在のところ、私が調べた範囲で中学校の修学旅行に格安航空会社を利用したケースはまだありません。会社側が受けるかどうかという問題もありますし、運賃がどこまで安く抑えられるのか、また一番は欠航になってしまった際どう対応するか、いろいろな課題があることは確かですが、格安航空会社を利用した修学旅行の検討に取り組む価値は決して低くないと思います。
何よりも、私の個人的な思いではありますが、感性豊かな中学生に京都や奈良のような文化を味わっていただきたいという気持ちがあります。それはともかくとして、格安航空を利用した修学旅行の実施が可能となるように、関係機関との間で必要な調整に取りかかるべきではないかと思いますが、教育長の御見解をお伺いいたします。
教育長
先ほども申し上げましたとおり、修学旅行の方面、コース、内容については各学校で検討し、決定しています。教育委員会で一律に東京と決めているわけでもありません。それから、格安航空というお話もありましたが、現在、教育委員会として積極的に修学旅行に格安航空、飛行機を利用することは考えておりません。
吉田
仮に格安航空を利用できたとして、本市から飛行機でどこかの地域へ修学旅行に行けるということは、逆に考えると、その地域から本市へも修学旅行生を迎え入れることができる、つまり相互の行き来が可能であることを意味するのではないかと思います。それも本市が受け入れ体制をしっかり整えることが前提ですが、今後本市を目指してやってくる修学旅行生の増加も可能性が見えてくるのではないかと少しは思えるところです。どちらにしても修学旅行のあり方に一石を投じる意味で、教育委員会の今後の対応、関係機関との取り組みに期待したいと思います。
済みません、少し話がそれてしまいました。ここまで保護者が直接負担する教育費の一部について取り上げましたが、最後の質問に移ります。市が公費で賄う教育関係の備品についてです。
市が財産の買い入れを行う際、一定の金額を超えるものについては競争入札の手続が行われており、これは学校で使用されるものについても例外ではありません。小中学校と児童センターで使用される教育関係の備品については、平成22年7月までさかのぼって22件の記録を確認することができました。その範囲では、指名競争入札、指名を受けた業者4人で入札が行われたケースが10件ありました。ちなみに、5人以上の指名で行われたものが8件、4人未満の指名が4件でした。震災以前から震災直後にかけては5人以上の指名が多くありましたが、その後4人のケースがしばらく続き、それが平成27年6月から3人に減って今に至っています。本市の契約規則には、指名競争入札により契約を締結しようとするときは4人以上を指名しなければならないと定められております。
そこで、小項目(4)学校用品物品の競争入札に指名される名簿登録者は、平成27年から毎回3人となっている。名取市契約規則第21条に定めるとおり4人以上を指名するなど、競争性を確保し落札価格の低減を図るべきについて市長にお伺いいたします。
市長
予定価格が80万円を超える物品の購入については、原則として指名競争入札により購入先を決定、契約締結しておりますが、購入する物品の特殊性がなく、市内業者での調達が可能な場合は、市内業者育成の考え方から市内業者を優先して指名選定しております。特殊性が高く、市内業者では調達が難しいと判断される場合は、市外業者も含めた指名選定を行うなど、事案によって対応しているところです。
吉田議員御指摘のとおり、名取市契約規則第21条においては、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、4人以上を指名しなければならないとなっておりますが、平成27年度においては、1社の廃業を受け、特別な事情がある場合には4人未満とすることができるというただし書きを適用し、学校用品物品の受注実績のある市内業者3人の指名選定としてきたところです。
平成27年度に行われた学校用品の落札結果からは、市内業者3人の指名であっても競争性が確保されていたと考えており、今後とも市内業者育成とのバランスを踏まえながら、引き続き適正な入札執行に努めていきたいと考えております。
吉田
市内業者の育成は大変重要な観点であると思います。しかし、市内業者を優先する形で4人の指名を行いしばらく競争入札が行われていた上でも、そのうち1者が廃業してしまったという現状があります。市内業者を優先することが直ちに業者の育成につながっているとは言えないのではないかと思います。特別な事情として今市内には業者が3件しかないとおっしゃいましたが、以前には多くの業者、4者を超える業者による指名競争入札が行われていた経緯がありますし、特別な事情といっても、それが1年も続いているというのはどうしても納税者の理解を得ることは難しいかと思います。これらについてしっかり説明責任を果たした上で、やはり原則にのっとった形で運用していくべきではないかと思いますが、市長にお伺いいたします。
市長
いろいろな議論があろうかと思います。議会の中でもこれについては吉田議員のような考えをお持ちの方も中にはおられるかもしれませんが、そうではないと、市内業者を優先すべきだという議員も多くおられるだろうと思います。そういった中でどのような判断をしていくかということになりますので、今後とも、公平性あるいは地元業者の育成、そういった観点の中からバランスをとって判断していきたいと考えております。
吉田
市長がおっしゃいましたように、公平性や地元業者の育成は非常に大事な観点であることは先ほどから申し上げているとおりですが、1つ抜けているのは、備品に関してもそれを購入する原資はどこから来ているのかといえば、やはりそれは住民の皆様から広く集めている税金であると。その金額を少しでも下げていく努力をすることはやはり行政の役割の一つではないかと私は考えます。
ただ4人に戻せばそれでよいのかと言われれば、私はそれでも足りないと思います。このたびは、一般に公開されている落札等結果表だけでなく、開示請求によって契約それぞれの内訳書を入手しました。この内訳書に記載されている主な備品のメーカーを列挙しますと、ウチダ、ヒシエス、キハラ、プラス、コクヨ、ホウトク、アイリスチトセ、ライオン事務器、ジョインテックスなどがあります。聞きなれない業者がほとんどだと思います。しかし、調査したところ、これらのうちウチダ、ヒシエス、キハラ、プラスについては、代理店の契約を結んでいる販売業者しかそれを仕入れることができない仕組みになっています。代理店となっている業者は私が確認できただけで3社あり、それらの業者は震災以前の落札等結果表にその名前が見られます。ということは、当然指名されていたわけです。しかし、指名が4人になってからはほとんど見ることができません。もし代理店でない販売業者がこれらのメーカーの商品を落札した場合でも、結局は代理店を通して仕入れることとなっています。よって、当然ながら代理店が落札した場合に比べて価格が上乗せされます。そればかりではなく、これらのメーカーの備品が破損や故障した場合は、代理店ではない業者では対応できないことが多いとされています。正常な状態に戻すために余計な時間がかかり、学校の教育現場において時間的なロスが発生してしまうことにつながります。このような理由からも、指名を4人に戻すにとどまらず、震災前のように市外の業者も含めて4人以上にふやすべきではないでしょうか。市長にお伺いいたします。
市長
これらについてもさまざまな考え方があります。効率性、低価格での購入といったことも一つには公費負担の軽減につながるかもしれません。ただ、我々は、名取市という一つの自治体を運営していく、この名取市というコミュニティーをしっかりとつくっていく、そのような使命も担っているわけであります。例えば最近話題になっているように、新興住宅地において古くからあったスーパー、店舗などが撤退してしまっています。どこで買ってもいいではないか、買い物などどこでもできる。では地元になくなっていいのかと。なくなっては困る。同じようなことです。市内の事業者は、確かになりわいとしての仕事もしておりますが、本市の経済を支えるという大事な根幹を担ってもいただいているわけです。ですから、地元でそのような事業を展開している業者の方々には地域貢献もしていただいてということです。そういったものをみんな大手に委ねていけば、今日本の中で問題になっている首都圏一極集中といったものにつながりかねない。地方が疲弊していくことにもなりかねない。我々は、そうではない、それぞれのまちがそれぞれに生きられるようなまちづくりを目指しているのであり、この点に関しては議員と意見を異にするところであります。そのような判断の中で、これからもバランスをとりながらそれぞれの状況に応じて判断していくことが必要であろうと思っております。
吉田
地元で商売を行っている業者がいらっしゃって、社会的な活動に携わっていただいている方も多いと、そのような方を大事にしていくことも当然重要です。ただ、その一方で、いわゆる大手の業者にも、市内に営業所、事業所を置いていないだけであって、その中には本市の市民もいらっしゃるかもしれない。そのようなことも今後は考えていかなければいけないのではないかと考えます。
指名をふやすことによって競争性が強まり、落札価格の低減が見込まれる。その結果、クラブ活動、部活動などの道具の購入、修理、さらに、今後いろいろと課題が出てくると思いますが、一つの例として学校のトイレの洋式化、これらの施設整備の財源も生まれることになり得るのではないかと思います。現在、少子化の影響は教育関連の業者にとって大いなる脅威であることは間違いありません。既存の業者を守ることを否定するわけではありませんが、それも行き過ぎてしまえば結局は子供たちにしわ寄せが来てしまうことになりかねないと考えます。その一方で、先日の新聞報道で確認しましたが、例えば少子化の影響を最も受けやすいと言われている制服のメーカーにおいて、家庭のペットとして飼われている老犬用のハーネスの開発製造などを始め、ペット市場に活路を見出そうとしている業者があることもお聞きしました。このように時代の変化に合わせ努力する姿勢を応援することこそが、企業育成の本来のあり方ではないかと私は個人的に思っております。
いずれにしろ健全な競争が行われる環境の整備によって地方経済が活性化するよう、行政には常に中立の立場で社会情勢の変化を確実に捉え、子供たちのためにも不公平感のない社会の実現を目指していただくことを強く願いながら、私の一般質問を終わります。
本会議
(議案第54号 名取市議会議員及び名取市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について)
吉田
議題となっております議案第54号 名取市議会議員及び名取市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について、選挙運動の公費負担は段階的に縮小し、選挙運動の規制を時代の変化に即して見直すべきとの持論により、反対の立場から討論を行います。
平成4年12月の公職選挙法改正に伴い、本市においては平成7年6月に選挙運動の公費負担に関する条例が制定されました。選挙が民主主義の根幹をなすものであることは申すまでもありません。公費負担の制度は、選挙の機会が資産家に独占されることのないよう、お金のかからない選挙、候補者間の選挙運動の機会の均等化などを目指して定められたものであると伺っております。しかし、選挙の機会均等化のためとはいうものの、公費負担の範囲外である選挙事務所、看板、車上運動員の報酬などは個人が負担するものであり、資産のある者とない者とでは選挙運動の質、量ともに差が生じているのが現実です。インターネットによる選挙運動が解禁されたとはいえ、地方議会選挙においては候補者にビラ一つ配布が許されないなど、政策を訴える場の整備もまだまだ不足しています。機会均等は新たな形を模索するときに来ていると感じます。
公費負担の一部の限度額を引き上げる条例改正は平成15年にも行われており、平成9年に消費税率が3%から5%に引き上げられたことが関連していると考えられます。このたびの改正案も8%への消費税増税がその源流にあるとみなされます。各地の選挙管理委員会は他の自治体の委員会と情報交換を行い、足並みをそろえて公費負担の上限額引き上げを行っているようですが、時代に合わなくなっている制度の改正を中央に訴えるためにこそ連帯するべきではないでしょうか。
地方選挙における公費負担の上限額は条例により定められるものであり、国政選挙における上限額が引き上げられたからといって、必ずしもそれに合わせなければならないものではないはずです。本改正案の施行は直ちに多額の支出につながるものではなく、直近では7月の市長選挙のために組まれる補正は6万7,000円にとどまる見通しです。しかし、問われるのは金額の大小ではなく地方自治体としての自立心であると考えます。本市が他の自治体に合わせることなく、独自に公費負担引き上げを見送れば、新聞やテレビなど報道でも取り上げられ、市内の有権者は市や市議会の自主的で住民目線の判断を評価するものと期待されます。そもそも選挙費用の一部が税金で賄われている事実すら余り知られておりません。本市独自の取り組みが行政や選挙に対する関心に結びつけば、住民の政治参加という民主主義の最重要課題が前へ進むことになるのではないでしょうか。
舛添東京都知事の政治資金問題を挙げるまでもなく、納税者、有権者の税金の使われ方に対する関心は高まっております。消費税増税が公費負担の引き上げの根源的な理由であるという説明に市民の理解を得られるかどうか、いま一度熟考された上で採決に臨んでいただきますようお願い申し上げ、本案に対する私の反対討論とさせていただきます。
(議案第65号 和解について)
吉田
このような件が発生したときのために恐らく弁護士と契約しているかと思いますが、弁護士にはどの段階で相談したのでしょうか。
生涯学習課長
皆様に配付した資料に記載しているとおり、相手方からイラスト貸し出しの確認の文書が本市に届いたのは平成28年2月19日です。その後、すぐに当該公民館を調査し、確かに使用していることを確認した後に、2月25日に顧問弁護士とお会いいたしまして、いろいろな御意見、御指導をいただいております。その後、約10回ほどメールや電話で確認をさせていただき、最終的には4月21日にもう一度弁護士とお会いしてこの和解の合意案について御指導をいただきました。
吉田
弁護士からは、このような形での対応、和解金の支払い以外は何か御指導はなかったのでしょうか。
生涯学習課長
この和解案のほかにはありませんでした。
吉田
恐らくこのような事案は本市以外にも各地で相当起きているかと思いますが、ほかの自治体の情報についてどの程度把握していますか。
議長
吉田議員に申し上げますが、今の審査は名取市の和解の審査ですので、そこに絞ってください。吉田議員。
吉田
ほかの自治体で同じようなケースがあったときに、使用料のほかに調査料の名目で金額が求められている事例もあります。本市の場合は、この提示されている金額は消費税を除いて全て著作権使用料と認識してよろしいのでしょうか。
生涯学習課長
イラストを使用した使用料相当分となります。
吉田
議題となっております議案第65号 和解についてについて反対の立場から討論を行います。
インターネットの発達が生活の利便性を高めている反面、インターネットにかかわる種々のトラブルが増加しております。インターネット上に公開されている著作物の取り扱いに関するトラブルもその一つです。インターネット上にはさまざまな写真、イラスト、動画、音声等が公開されており、そのほとんどは誰もが簡単に接触することができます。そのため、インターネット上のデータは公共物であるとの誤解を招くことさえあります。本事案もその誤解が根底にあるトラブルと考えられますが、全ての職員に対しインターネットと著作権に関する研修を徹底していれば未然に防ぐことも可能ではなかったかと悔やまれます。
無料であると思い込んでイラストを使用し、しばらくして株式会社アートバンクから使用料の請求をされたという事例は、それこそインターネットを調べれば数多く見つけられます。株式会社アートバンクは、使用料の支払いに応じない団体等について「ソックリ広告博物館」と称するホームページで事例を紹介しています。私はそこに現時点で紹介されている全ての自治体に、イラスト使用の経緯や株式会社アートバンクによる請求への対応などの聞き取りを行いました。聞き取りを行ったのは奈良県王寺町、兵庫県高砂市、茨城県結城市、滋賀県野洲市、兵庫県尼崎市、北海道旭川市、鳥取県北栄町、奈良県御所市、福岡県小郡市、兵庫県三木市の10市町です。ただし、1つの自治体は個人に対してはノーコメントとのことで情報を得ることはできませんでした。
これらどの自治体にも共通するのは、イラストが無料であると思い込んで使用してしまったことです。初めに株式会社アートバンクからイラストの入手経路や使用開始時期などについて質問状が届きますが、その時点で対応しないことに決めた自治体は4つでした。そのうち1つの自治体は、国の機関が発行するパンフレットからの転載であったことを理由に返答を拒否しております。また、株式会社アートバンクから金額が提示されたものの、その支払いに応じないという対応の自治体が2つあり、使用料だけを支払い、調査費を支払わなかった自治体、広報紙作成の委託先が対応している自治体、和解金を支払った自治体がそれぞれ1つでした。なお、これらの自治体はいずれも株式会社アートバンクとの間で訴訟に発展してはおりませんが、以上のケースの中で最大の請求額は223万5,000円でした。
株式会社アートバンクと本市との間に著作物の使用に関する契約は結ばれておりません。確かに本市が著作物を無断で使用したことは事実ですが、それは過ちによるものであり、決して悪意あってのことではなかったはずです。公民館だよりは営利目的の発行物ではなく、掲載するイラストは素人による手描きのものでも全く問題ありません。1つのイラストに6万円も支払う妥当性はないため、本市としては、誠意を尽くして説明と謝罪を行いつつ、契約が締結していないことを理由に支払いに応ぜざるべきでありましょう。
本案では和解金を約103万円としておりますが、103万円の税金を納めるために1人の社会人がどれだけの労力を費やさなければならないか、行政側は深刻に受けとめていただくべきであると考えます。このような過ちが繰り返されることのないよう、本市においては職員や関係者に対する研修を徹底し、税金を狙ったさまざまな仕掛けについて自治体間で情報を共有できる仕組みを構築することを関係機関に強く望み、本案に対する私の反対討論といたします。
(議案第77号 工事請負契約の締結について)
吉田
資料2ページの全体図で、正門のところですが、体育館と校舎の東側の壁面に沿って実線と点線が交じっている二重線が描いてあると思いますが、これは一体何でしょうか。
庶務課長
体育館と校舎の東側の二重の点線は門扉となります。
吉田
そうなると階段が門扉の外についていると捉えられると思うのですが、鍵などなしにして門扉の外にある階段から外部の方が侵入できる範囲はどの辺までになるのでしょうか。
庶務課長
先ほどの部長の補足説明にもありましたが、こちらと正反対側にあるもう1カ所の階段は屋外避難階段です。したがって、この階段で4階と4階の屋上に上がれます。
吉田
今の御答弁ですと、鍵等はついていないということで、外部の方が直接校舎のテラス等に侵入することが可能と捉えていいのですか。
庶務課長
この屋外避難階段は、手でひねると開錠できるノブがついており、材質は今のところわかりませんが、それに仮にプラスチック製のカバーのようなものをつけて常にはさわれない状態になっているもので、非常の場合にそのカバーを壊して手で開錠して利用いただくという階段です。
吉田
そうなると先ほどの第2期の復興公営住宅と同じような形で、ついていてついていないような鍵であると思うのですが、学校が現場になるような痛ましい事件もこれまでに例がありますので、例えば悪意を持った外部の人が入ってこようとしたときに、鍵をあけたら職員室で警報が鳴るなどの仕組みの構築は考えていらっしゃるのでしょうか。
庶務課長
この校舎についても他の学校等と同じように機械警備を導入する計画です。屋外避難階段も、施錠をあけて通った場合は、夜間や学校側からの場合は警備のほうで感知するようになっています。
吉田
今の御答弁ですと夜間のみ警備会社が感知する仕組みでの利用ということですが、悪意を持った人は昼夜関係なしにやってくるわけです。昼に鍵をあけて中に入ろうとする。そして職員室がどこにあるかというと反対の西側にありますので、多くの先生方はここまで目が届かない状況であります。そして、図面を見ると2階から上に向かうところも全て屋外の階段でつながっていますので、死角となる部分が多くあるように見受けられます。また、更衣室などもありますので、侵入されたときに外からのぞかれるようなことも万が一のこととして考えておかなければいけません。以上のことから、何かしら昼間の対策もとることについて今後のお考えはないでしょうか。
教育部長
昼間等のセキュリティーの問題については、今後運営の中で検討していきたいと考えております。
(議会案第4号 日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求める意見書)
議長
ただいま議題となっております議会案1カ件につきましては、総務消防常任委員会に付託をしておりましたので、同委員会における審査の経過及び内容並びに審査結果について委員長の報告を求めます。総務消防常任委員会長南良彦委員長、登壇。
総務消防常任委員会委員長
ただいま議題となっております議会案第4号について、総務消防常任委員会における審査の経過及びその結果について御報告申し上げます。
本委員会は、去る6月9日の本会議において付託されました本件議会案1カ件について、同日及び6月13日に委員会を開催し、慎重に審査を進めてまいりました。
それでは、議会案第4号 日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求める意見書の審査内容について申し上げます。
審査において委員から出された意見といたしましては、核兵器の全面禁止を被爆国である日本から発信すべきとする意見、国際的な問題について話し合いによる解決は難しい。まずは、国と国民の生命、財産を守るための安全保障の枠組みを守っていくべきであり、核の傘から脱却するのは現実的ではないとする意見、核兵器の全面禁止の考えには賛同できるが、要望内容の「米国の核兵器による「拡大抑止」、いわゆる「核の傘」に依存した安全保障政策から脱却すること。」の部分について、現実的に厳しいのではないかとする意見などがありました。
その後、一部委員より修正案が提出されました。修正箇所につきましては、原案の案文中、アンダーラインで示した箇所を削除する内容となっております。
採決の結果、議会案第4号 日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求める意見書につきましては、賛成多数により修正案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、本委員会に付託されました案件についての審査経過並びに結果の報告といたします。
吉田
議題となっております議会案第4号「日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求める意見書」案について、反対の立場から討論を行います。反対の理由は3点ございます。
初めに1点目は、本案に明記されております固有名詞が、日本政府が正式に使用する呼称ではないからであります。例を挙げますと、4行目に「NPT(核不拡散条約)再検討会議」とありますが、外務省は「運用検討会議」と称しております。また本文13行目の「核兵器の禁止と廃絶に向けた人道の誓約」については、外務省は「核兵器の禁止及び廃絶のための人道の誓約」と称し、本文14行目の「核兵器のない世界のための倫理的至上命題」については、外務省は「倫理上の責務」と称しております。政府に意見書を届けるのであれば、政府が公式に使用する文言に合致させるよう調整することが、議会に求められる最低限のマナーであると考えます。
次に2点目は、本案が政府に要望する内容が独善的に遂行されれば、諸国間の関係を不安定なものにして、逆に核兵器の使用の危険性が高まることになりかねない恐れを含んでいるからであります。政府は、核軍縮は諸国間の安定的な関係の下で進められる必要があるとしており、平和で安全な世界に向け、核リスクを確実に最小化していくための実践的かつ具体的な核軍縮・不拡散措置を追及しております。我が国周辺地域には、依然として核戦力を含む大規模な軍事力が集中しており、このような状況下で政府は、自国の防衛力整備、日米安保体制の堅持とともに、周辺地域が国際環境の安定を確保するための外交努力により、自国の平和と安全を図るとの基本的な立場をとっております。本案の表題にあります「核兵器全面禁止」という理想と、アメリカの核の傘に守られているという現実のはざまで、政府は軍縮・不拡散外交を安全保障政策と整合する形で進める責任を負っています。本案は理想のみを見て政府への要望を並べておりますが、日米安保体制の堅持という現実的課題については一言も触れておりません。原案にあった「米国の核兵器による拡大抑止、いわゆる核の傘に依存した安全保障政策から脱却すること」の文言は削除されましたが、修正案においてもその本質は残されたままと見なされます。アメリカとの共同歩調を度外視した外交姿勢の変更を求めていると受け止められる、そのように感じます。
最後に3点目は、復興道半ばの本市が、このような内容の意見書を現時点で政府に提出することに大義があるとは思われないからであります。本市被災地域のインフラ整備については、他の被災自治体に比べて遅れているとの指摘はあるものの、着実に前進しております。しかしインフラ整備だけでは復興とは言えず、あくまで復旧の段階でしかありません。そこに住民が戻り、安心・安全の暮らしを取り戻し、地域コミュニティが形成されてはじめて、復興を成し遂げたと言えるものでありましょう。人口問題の深刻化は被災地域が直面する課題であり、インフラ整備だけで対応し切れるものではなく、地方分権をさらに加速させる大掛かりな制度改革が必要になるものと思われます。広島・長崎などの被爆地であればともかく、震災復興を最優先課題とする自治体の議会に求められる対応は、地域課題解消のための意見書の提出であり、本市議会が積極的に取り組むべきことは他にあると考えます。
唯一の戦争被爆国に生まれた一人の人間として、核兵器の廃絶を望む気持ちは、私も本案提出者と異なるものではございません。核兵器廃絶の実現に向け、世界的な潮流の変化が生まれつつあることも事実であり、大いに歓迎するところです。記憶に新しいところでは、5月27日にアメリカ大統領による初めての被爆地広島訪問が実現しました。このことは核廃絶に向けて大きな前進であり、日米両政府の核なき世界実現への努力は大いに評価すべきものでありましょう。このような友好ムードに水を差すことがあってはならないと考えます。
今後も政府には、日米間の強固なる信頼関係を維持しつつ、軍縮・不拡散イニシアティヴなど地域横断的な非核兵器国グループとの連携を強化して、これまで同様に現実的かつ実践的アプローチを国際社会に示すことを期待し、本案に対する私の反対討論とさせていただきます。
小野寺美穂議員
討論なので自分の意見を述べることは、委員会の姿勢でも反対ということだったのでそれは結構なことだと思いますが、委員会で審査に参加しているので、文言等の間違いということですが、私は、外務省が使っている言葉をそのまま使わなければ意見書にならない、また国に対して出すものではないなどということはあり得ないと考えます。また、そういった訂正箇所があるのであれば、委員会の審査のときに言うべきです。今言うことではありません。そして、復興とどう関係するのかわかりませんが、趣旨には賛同するという矛盾したことをおっしゃるのですが、それはそのようなスタンスだからいいでしょう。ですから、そのような点を指摘するなら、きちんと審査をしている場においてしていただきたいと思います。ここに来てお二人の方からもう修正案が提出され、我々はその修正案を審査しました。今さらどうしようもないわけです。ですから、そのようなことはきちんと委員会の審査の場で行っていただくようにお取り計らいをお願いいたします。
議長
ただいまの小野寺議員の議事進行に対して見解を申し上げます。
先ほど吉田議員の討論の中において矛盾する文言があったと私も考えておりました。そこで、その矛盾する文言を議長の職権において整理をして出したいと思います。
※閉会後、議長の諮問により議会運営委員会において吉田の討論における発言内容は議事手続上の討論と認められるかが協議されました。
具体的な疑義の内容
1、反対理由の1点目、「文言(字句)の誤り」については、自らが参加した委員会の審査において指摘すべき内容であって、仮に、その時点で気付かなかったとしても、所管常任委員会委員としての手落ちを本会議で指摘することはいかがか。
2、意見書の提出自体に「大義がない」との指摘であるが、住民世論の動向に常に関心を持ち、それを先取りする形で、議会自らの政策活動として、大所高所から住民の立場に立って、客観的にみて、社会公共の利益に関する内容であるか否かを積極的、自発的に取り上げ、検討・処理することは、議会に求められた責務であり、「大義がない」とする指摘は妥当か。
3、核兵器全面禁止を求める意見書に対する討論において、震災の復興状況に対する評価や地方分権の加速化に関する発言が、賛否の判断材料となり得るか疑義がある。
4、反対理由の3点目で「核兵器廃絶の実現に向け世界的な潮流の変化が生まれつつあることも事実であり、大いに歓迎する」と明言しており、意見書の趣旨に賛同しているとも受け取れる発言は意見書提出の反対討論とは相反するのではないか。
上記4点の疑義に対して、吉田の見解は次の通りです。
1、断じて通したくない内容の意見書であったからこそ、委員会で手の内を全て明かさずに本会議での否決を目指した。吉田の本案に対する態度は一貫しており、委員会と本会議ではそれぞれ状況に応じて異なる反対理由を述べたまでである。このような手法を「手落ち」と言い切る対応こそいかがなものか。
2、議員個人の主観による指摘であるが、討論は主観が入ることを許容すると認識している。
3、2に同じ。
4、吉田が歓迎するのは「核兵器廃絶の実現に向けた世界的な潮流の変化」であり、本意見書が求める趣旨「アメリカとの共同歩調の見直し」ではない。小学生でも読解可能なレベルの文法であるが、あえて意地悪な読み方をすれば、吉田が本意見書に賛成しているように読めないことも全くないわけではない。今後は表現に一層注意したい。
吉田は会派に属していないため、議会運営委員会の会議における発言権がなく、自らの見解を述べる機会を有しておりません。委員会の会議において、一部の委員から「吉田の意見も聞くべきだ」との趣旨の発言がありましたが、そのような手順がふまれることなく、討論の大部分が削除されることとなりました。
以下は最終的に会議録に収められることとなった内容です。
吉田
議題となっております議会案第4号 日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求める意見書について、反対の立場から討論を行います。
反対の理由は3点あります。
初めに1点目は、_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
次に2点目は、本案が政府に要望する内容が独善的に遂行されれば、諸国間の関係を不安定なものにして、逆に核兵器の使用の危険性が高まることになりかねないおそれを含んでいるからであります。政府は、核軍縮は諸国間の安定的な関係のもとで進められる必要があるとしており、平和で安全な世界に向け、核リスクを確実に最小化していくための実践的かつ具体的な核軍縮・不拡散措置を追求しております。我が国周辺地域には依然として核戦力を含む大規模な軍事力が集中しており、このような状況下で政府は、自国の防衛力整備、日米安保体制の堅持とともに、周辺地域が国際環境の安定を確保するための外交努力により、自国の平和と安全を図るとの基本的な立場をとっております。本案の表題にあります核兵器全面禁止という理想と、アメリカの核の傘に守られているという現実のはざまで、政府は軍縮・不拡散外交を安全保障政策と整合する形で進める責任を負っております。本案は理想のみを見て政府への要望を並べておりますが、日米安保体制の堅持という現実的課題については一言も触れておりません。原案にあった「米国の核兵器による「拡大抑止」、いわゆる「核の傘」に依存した安全保障政策から脱却すること。」の文言は削除されましたが、修正案においてもその本質は残されたままとみなされます。アメリカとの共同歩調を度外視した外交姿勢の変更を求めていると受けとめられる、そのように感じます。
最後に3点目、______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
今後も政府には、日米間の強固なる信頼関係を維持しつつ、軍縮・不拡散イニシアチブなど地域横断的な非核兵器国グループとの連携を強化して、これまで同様に現実的かつ実践的アプローチを国際社会に示すことを期待し、本案に対する私の反対討論といたします。