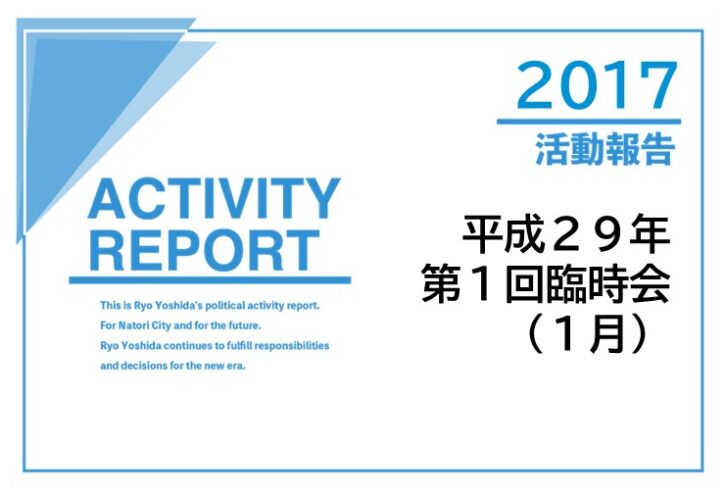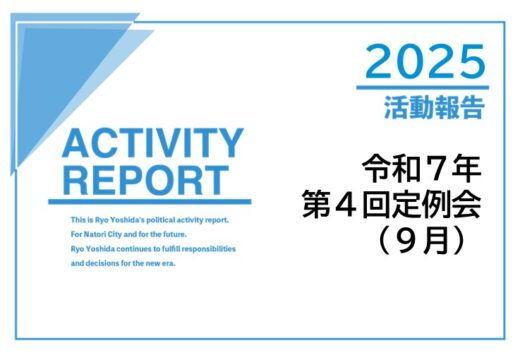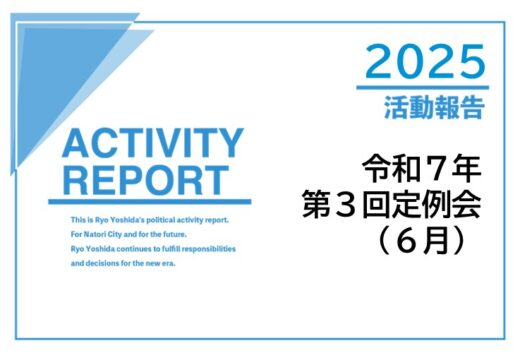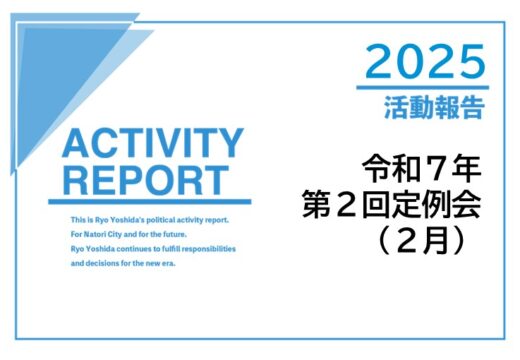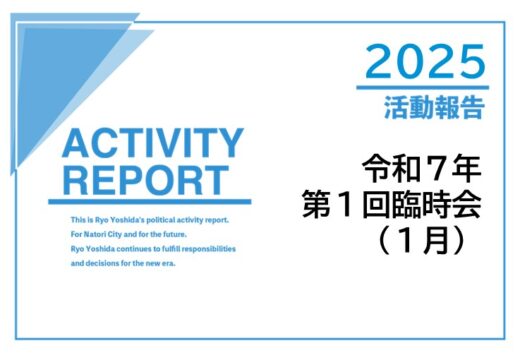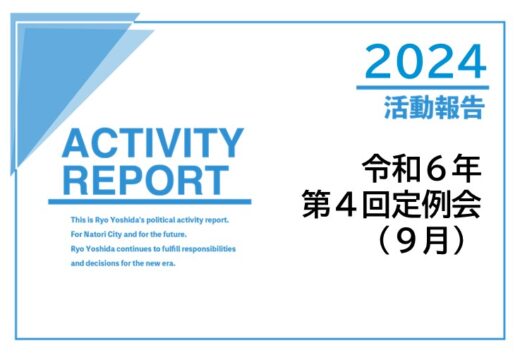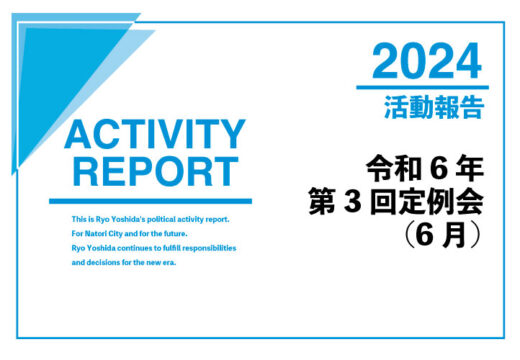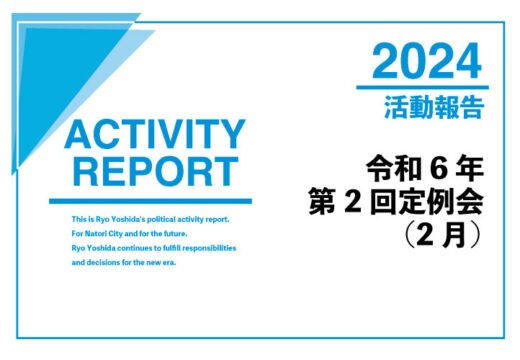本会議
(議案第2号 名取市震災復興計画の基本方針の一部変更について)
吉田
今回の基本方針の変更の中で、最も注目され市民の方たちの関心が集まっているのは、何といっても内陸部への復興公営住宅の一部整備という部分だと思います。その点について、市民の方から、待ち望んでいる声、あるいはそれによって閖上の復興がおくれるのではないかという懸念の声など、さまざまな声が上がっています。
そのような方たちに、今後どのような形で安心していただけるような手だてを打っていくのか、具体的に御説明をお願いします。
復興まちづくり課長
今回、内陸部への移転ということで、名取団地の一部に33戸を整備する計画としています。限られた戸数の中で入居希望者が多いという実態もある中で、抽せんで外れた世帯については、前回の議員協議会でもお話ししたとおり、平成29年度から新たに被災者自立支援事業を実施し、個々のニーズに沿った丁寧な対応を行って、住宅の再建、暮らしの再建ができるように取り組んでいきたいと考えています。
吉田
抽せんに漏れた方はもちろんですが、名取団地というと、今、交通の便についてもいろいろと声が上がっている現状があります。また、閖上地区についても、現在は復興支援バスが走っていますが、今後は交通の課題がますます深まってくるのではないかと思います。そのあたりについても今後の御検討の内容をお知らせいただきたいと思います。
市長
今回の内陸部移転については、当然抽せんに漏れる方もいらっしゃると思います。その方々も含めて、お一人お一人がきちんと生活再建できるまで、最後までしっかりケアをしていく必要があると考えております。もちろん閖上に戻れない方もそうですが、今御指摘があったように閖上に戻って現地で生活再建をする方もたくさんおられますので、そうした方々に対して、閖上のまちが持続可能なまちになるように、公共交通、商業施設、病院など基本的な生活インフラを張りつけていく、また定住を促進しながら交流人口を拡大していく策についてもさらに行っていきながら、閖上で生活再建される方についても、閖上に戻れないという方の生活再建についても、最後までやり切るという覚悟で臨みたいと思っております。
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長のお許しをいただきましたので、議題となっております議案第2号 名取市震災復興計画の基本方針の一部変更について、賛成の立場で討論を行います。
名取市震災復興計画の基本方針の改定案がこうして本会議にかけられるまで、4回の議員協議会を経てきたことは、議員の皆様もよく御記憶のことと思います。毎回、さまざまな角度から質疑の声が上がり、非常に長い時間をかけて協議が行われてきたことは、議員の皆様がそれぞれ被災者と本市の未来を真剣に考えていたことのあらわれであったと確信しております。
本案は、復興途上の本市における被災者の生活の問題点全てを直ちに解決するものではないかもしれません。しかし、東日本大震災から間もなく6年を迎えるともなれば、復興計画の策定当初とは状況も変化し、想定とは異なるニーズが生じてしまうことはいたし方なく、まして生活再建を目指す被災者の方たちにとって、課題が当時のままであるはずもありません。策定当時に想定し切れなかった新たな課題も生じていることから、それらの克服のためには基本方針の変更は必要であり、ただいま示されている改定案は、生活再建途上の被災者、特にどうしても海側の地域には帰れないという特別な事情を抱えた方にとって、希望となる内容を含んだものであると評価されるべきではないでしょうか。
平成28年10月に開かれた議員協議会において、名取が丘地区に33戸の復興公営住宅を整備する案が初めて示されました。内陸部には整備しないというこれまでの執行部の説明と食い違っていたために、議会側としては理解しかねるという雰囲気が充満していたように感じられました。私もまた、それとは違う理由によって、初めの案には疑問を抱いておりました。
11月の議員協議会で、その疑問点に対する回答を得たく、何度も質疑を繰り返しました。つまり入居者を抽せんで決定するという選定方法について、特別な事情を抱える被災者を救いたいという市長の思いの原点が、このままで本当に達せられるのかということでした。内陸に33戸を建設し、行政はそれで責任を果たしたと。応募に当たっては、皆さんに御配慮、御協力をお願いするというのでは、被災者側の運に全てを委ねることになり、行政側は責任逃れをしているとも捉えられるのではないかと思った次第です。この疑念に対する御答弁は優先枠のようなものは設けないという内容でしたので、賛成するのは難しいという認識でおりました。
12月の協議会で示された内容は11月とほとんど変わらないものでしたが、平成29年1月16日の議員協議会では、ついに7戸の優先枠を設ける最終案が示されました。それまでできないと言ってきたことができたわけです。何事にも慎重な執行部ができないと説明をすることはごく正常なことであると思いますが、できないをできるに変えるための働きかけを行っていくこともまた、議会に求められる重要な役割の一つではないかと考えています。
確かに計画をころころと変える朝令暮改の政治では住民が困惑するだけですが、住民の考え方の変化が反映されない行政が当たり前となってしまっては、民主主義の成熟はどんなに待っても訪れることはありません。しかし、本件に関する本市の経緯を振り返れば、内陸部に復興公営住宅を整備しないという初めの方針について、6年近くが経過し、見直しを求める住民世論が高まり、それを受けて執行部が大幅な改定の案を示し、議会の求めによってよりよい内容にと修正されました。このような経緯をたどった本市には、民主主義が確実に育っており、私はそのことを誇らしく思います。民意と議会の提言を受けてこのような最終案を示した執行部の努力と実行力には、心より敬意と感謝を申し上げます。
閖上の復興公営住宅に既に入居されている方や、これから閖上地域に戻ろう、あるいは住もうとされている方にとって、内陸部への復興公営住宅の整備に対し、さまざまな思いがあることも察せられます。被災地域の復興をおくらせないために定住促進と交流人口拡大に向けた施策の充実を検討していることについても、1月16日の議員協議会で説明がありました。人口問題に特効薬はなく、不安が完全に払拭されるわけではありませんが、今後も時代の変化と住民ニーズの変化に対応し、住みよさを実感できる魅力的なまちの形成に努めていただきたいと強く願います。
本改定案には、もう一つの利点として、老朽化した名取団地の建物の一部解体が実現し、地域の不安が軽減されることが挙げられます。解体や改築には非常に高額な経費がかかることから、これまでこの課題は先送りされてきました。復興交付金を活用できるこの機会を逃せば、解体はますます先送りされることになるでしょう。地域住民の不安を少しでも早く除去するために、この機会を逃すべきではないと考えます。
33戸では足りない、あるいは名取が丘ではなく平地に整備すべきだなどの考え方もありますが、どうしても海側へ帰れないという被災者にとって、本案はまさにあすへの希望となっております。私が直接個人的にお会いした被災者の中には、既に本案は決定したという前提でお話しされる方もいらっしゃいました。恐らくは報道の一部を聞いて勘違いされたものと思われます。誤解を改めるためにまだ決まっていないことを説明しましたが、その方は必ず実現するものと信じておられる様子でした。
行政側には、被災者が最後の一人まで生活再建を果たせるよう、必要な支援を必ず行っていただきますようお願いします。そして、これだけの時間を重ねて提示された最終案に対し、議会がどのような決定を示すかについても、多くの方が注目していることも確かです。本案を可決させることこそが本市のよりよい未来を実現するために今とるべき行動であることと御賛同いただきたく、お願い申し上げまして、私の賛成討論とさせていただきます。