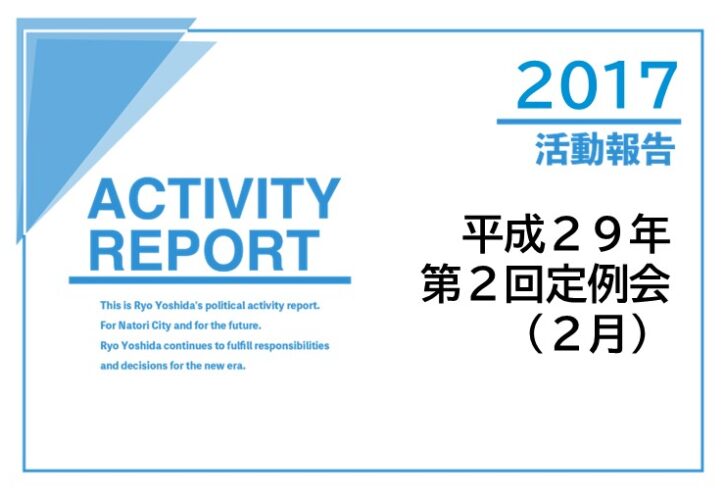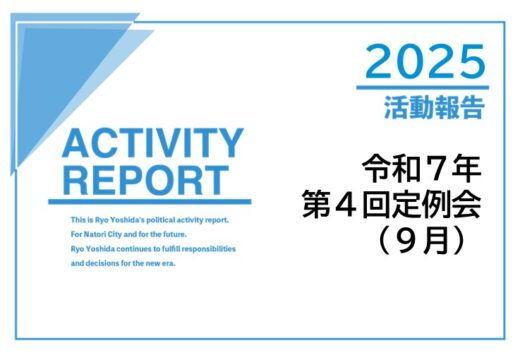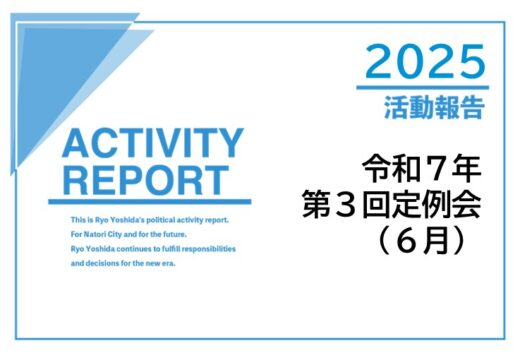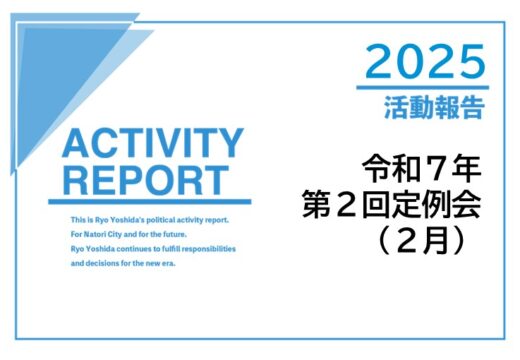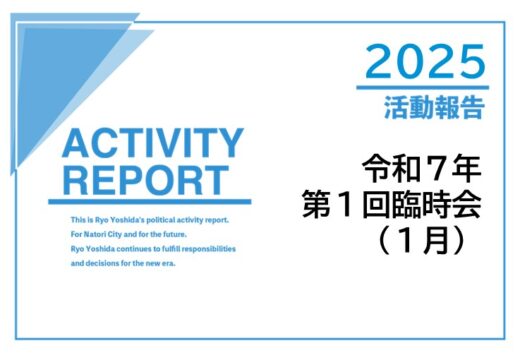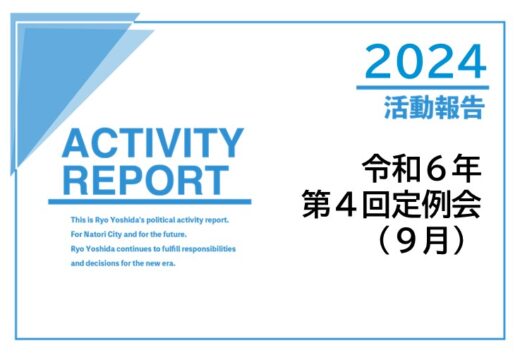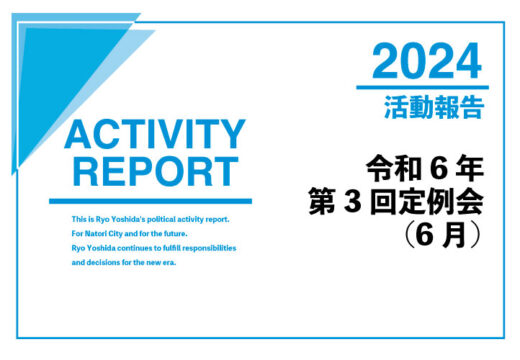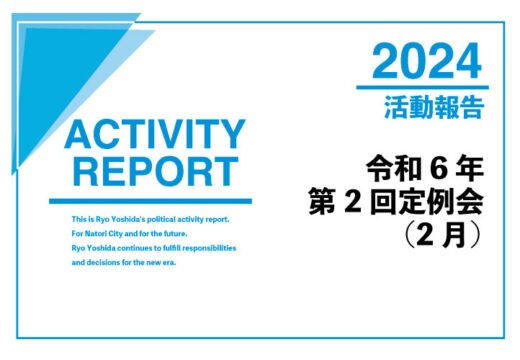一般質問
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長よりお許しをいただきましたので、通告に従い私の一般質問を行います。
まず、大項目1 税の手続の簡素化についてお伺いいたします。
いろいろな手続をとるため何かと役所を訪れる機会がふえる年度の変わり目ですが、役所まで足を運ばなくても身近なところで手続を行えることや窓口での待ち時間が短くなることは、多くの市民に共通する行政への願いであろうと推しはかれます。本市でも平成28年6月からコンビニエンスストアで住民票が取得できるようになり、多くの市民が助かっていることと思います。窓口業務を少なくすることは人件費の削減にもつながるため、情報流出などのリスクをゼロに近づける努力を継続しつつ、今後も可能な分野で機械化や自動化を進めていくべきであろうと思います。
また、交通弱者と位置づけられる層の市民にとっても、機械化や自動化による恩恵は大きなものがあることでしょう。高齢ドライバーによる交通事故が毎日のように報じられておりますが、役所を訪れなければならない人と回数を減らせば、事故の発生率を下げることにもつながるかもしれません。
機械化や自動化の流れが進む一方、本市では障がい者の軽自動車税減免の手続が毎年必要な状態が続いております。名取市市税条例第90条に、市長は、身体障がい者または精神障がい者が所有する軽自動車等に対し軽自動車税を減免できる旨が明記されていますが、続く第2項に減免を受けようとする者は納期限までに必要書類を提示して申請書を提出しなければならないとの規定があり、毎年の申請を求めています。しかも、申請期間は納期限である5月31日までの2週間しかなく、期間内に申請できなかった年は減免を受けることができません。少し調べた範囲では、徳島県鳴門市、山形県鶴岡市、佐賀県佐賀市などが自動継続を認めており、県内では石巻市や塩竈市が郵送による継続の申請を認めております。これらの自治体に住む障がい者やその方を介護する方には、手続に係る負担が軽く感じられていることでしょう。
そこで、小項目1 障がい者が所有する軽自動車に軽自動車税の減免を承認した場合、減免要件事項に変更がない限り、次年度以降は申請を不要とすべきについて市長にお伺いいたします。
市長
名取市市税条例では、障がい者等が軽自動車税の減免を受ける場合、議員御指摘のとおり市長に対し納期限までに申請書類を提出していただくよう定めております。
また、翌年度以降引き続き減免を受ける場合も、減免の対象が単年度の課税に対するもののみであることや、県税である自動車税の減免を二重で受けていないか、手帳を窓口において確認する必要があるため、改めて市長に対し納期限までに申請書類を提出していただくことになります。
しかしながら、継続申請の簡略化を実施している団体もあることから、先進事例の情報を収集し、実施に向け調査研究をしていきたいと考えております。
吉田
実施に向けて調査検討されていくということで、前向きな御答弁と受けとめさせていただきます。
自動継続については、認めている自治体によって異なる方法をとっているようです。先ほど例に挙げた塩竈市や石巻市では、納税通知書とともに現状報告書が送られてきて、状況が前年度と変わらないことを記入して郵送すればそのまま継続される仕組みになっています。また、県外には、障がいの等級や車両番号などに変更があった場合以外、届け出を必要としない自治体もあります。障がいを持つ方だけではなく、行政側にとっても事務の簡略化という効果があるのではないかと思います。早速新年度から導入すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長
先ほど御答弁申し上げたとおり、どのような形がいいのかということも含めて、なるべく早い段階に取り組めるよう近隣自治体等の先進事例を調査研究していきたいと思います。
吉田
市長がかわって、なるほど役所が変わったなと市民から評価されるチャンスであると思いますので、ぜひともできるだけ早く始めていただきたいと思います。
では、次に移ります。
平成29年1月から所得税や相続税などの国税をクレジットカードで納入できる仕組みが始まりました。自治体によっては、国より早く納付のチャンネルをふやすためにクレジットカード納税を導入したところもありました。手数料が納税者負担であることや決済が自動的に継続されないなどデメリットもありますが、国の将来を考えれば、お金の電子化を進めることは国民側にも行政側にもデメリットよりメリットのほうが大きいと私は個人的に思っております。
お金の電子化という遠い将来に向けた本市の第一歩として、小項目2 市民税等のクレジットカードによる納付を可能とする仕組みを導入すべきと思いますが、市長にお伺いいたします。
市長
市税を含む公金のクレジットカードによる収納については、平成23年度にコンビニエンスストア収納を導入した際、あわせて検討を行っております。
その際、収納のコストに関して、収納額に対して1%の手数料がかかることもあり、コスト負担が大きいことからコンビニエンスストア収納のみを採用した経緯があります。
このようなことから、現時点ではクレジットカードによる公金収納は採用していないところです。しかし、検討当時から5年以上経過していることや、他の自治体で採用されている事例もあることから、県内自治体の取り組み状況の把握に努めながら、収納率向上の効果や手数料の負担割合も含めてクレジット収納に関する情報収集を行い、調査研究を行っていきますので、御理解をいただきたいと思います。
吉田
取り入れている自治体も徐々にふえてきているということですので、ぜひ情報収集を進めていただきまして、制度導入に向けて前向きに動き始めていただきたいとお願いいたします。
それでは、次に大項目2 東日本大震災に係る義援金についてお伺いいたします。
東日本大震災の発生から間もなく丸6年となります。発生直後から今日までの間、たくさんの善意ある方から多くの義援金が寄せられてきました。本市のホームページによると、平成28年12月末時点で約6億円の義援金が寄せられております。非常に大きな金額ですが、平成28年9月末時点から3カ月で増加したのは約220万円であり、増加率は約0.6%にとどまっています。
東日本大震災以降も各地でさまざまな大規模災害が発生しており、本市に寄せられる義援金の大幅な増額は今後も見込めないものと思われます。復興は道半ばとはいえ、義援金の受け付けをどのように閉じるか、そろそろ考えるときに差しかかっているのではないでしょうか。なお、仙台市は平成28年3月に義援金の受け付けを終了しています。
また、義援金をいつまで受け付けるかと同時に、義援金の監査とその報告を行う時期についても市民に示すべきではないかと思います。災害発生直後の混乱の中で義援金の会計監査にまで手が回らない状況であったことは容易に想像できますが、さすがに丸6年が経過してなおそれが行われないままであるという状況は、市民に疑念を抱かせることにつながりかねないと考えます。大金を預かる組織ですから、監査報告の時期等の検討も進んでいることと思います。
そこで、小項目1 受け付けの期限、処理に係る監査と支給状況についての公表はいつになる見込みなのかを市長にお伺いいたします。
市長
東日本大震災に係る義援金については、義援金受付団体、宮城県、名取市へ義援金としていただいたものを、それぞれの配分委員会において決定した基準に基づき、被災された方々へ配分をしております。
義援金の受け入れ期限について、宮城県では平成29年3月末までとしており、毎年見直しを行っております。本市においては、復興がまだ途中であること、今後も被災された方々への支援が必要であることから、受け入れ期限は未定としています。
支給状況については、必要に応じて名取市災害義援金配分委員会を開催して配分額を決定し、その都度、復興だより及び市ホームページにおいて配分額をお知らせしています。
処理に係る監査については、義援金の配分が終了した段階で速やかに実施したいと考えております。
吉田
1点に絞りたいのですが、市長の御答弁では、名取市災害義援金配分委員会の開催の都度、復興だよりとホームページで配分額の公表を行っているということでしたが、私がホームページで確認したところ、財政課による義援金の状況のページ、生活再建支援課による配分額のページと、大きく2つのページで公表されていると思います。残念ながらそれぞれに説明の不十分な点があると見受けられました。
義援金の状況のページは、先ほど申し上げたように平成28年12月末時点で約6億円、正確には5億9,327万何がし円と表示されていますが、これが本市に直接寄せられた額なのか、それとも日本赤十字社等あるいは宮城県から配分された義援金も含んだ額であるのかが不明です。また、配分額のページでは対象件数と残額が不明です。市民には、寄せられた額と配分された額が釣り合っているのか確認するすべがありません。今申し上げた項目は既に数字がはっきりしているわけですから公表は容易であろうと思われますが、今後も現状の表示内容を続ける考えかどうか確認させてください。
市長
わかりにくい部分があれば当然見直すべきだろうと思いますが、現状の考え方について担当より答弁をいたさせます。
生活再建支援課長
今の議員の御指摘はもっともな部分もあります。現在のページに受け入れ額や配分額の総計等や支給率、全体の件数といった項目を速やかに開示したいと考えます。
会計管理者
収入の部のほうの公表ですが、この金額については本市に寄せられた義援金のみということでホームページに3カ月ごとに更新を行いながら公表しています。生活再建支援課長からも答弁したとおり、ホームページの内容について少しわかりにくい面もあるかと思いますので、今後、生活再建支援課と調整を図りもっと見やすい表示の仕方を検討していきたいと考えます。
吉田
市長の御答弁では受け付けの終了は未定ということで、まだしばらく時間がありそうですので、御担当からの答弁のとおりホームページの改修を早急に進めていただきたいと思います。
さて、仙台市や宮城県の配分委員会設置要綱には監事を置くことが明記されております。仙台市は銀行の常勤監査役と公認会計士、宮城県は銀行の監査役と社会福祉法人の理事、それぞれ行政の外部から2名を選任しています。チェックの目は外部の第三者によるものであることが理想と思いますが、本市の配分委員会設置要綱に監事の定めがなく、今のところ監事が置かれておりません。
そこで、小項目2 配分委員会に監事を置くことなどにより、会計監査の透明性を確保すべきについて市長にお伺いいたします。
市長
宮城県内外から寄せられた義援金を公正かつ効率的に配分するため、名取市災害義援金配分委員会を設置しております。この委員会は、社会福祉協議会会長、民生委員児童委員協議会会長、区長連合会会長などから委員を組織しております。
会計監査の透明性については、配分委員会の中で収入収支の内容、未振込額などを確認し、配分決定をしています。
また、該当被災者への配分金の振り込み、未振込者の追跡調査などは生活再建支援課で継続して行っており、会計事務を含め公正かつ透明性は確保できているものと認識しておりますが、より高い透明性を確保するために監事の設置について検討していきたいと考えております。
吉田
おっしゃるとおりより高い透明性が必要かと思います。監事の設置を検討していくという答弁でしたが、それは配分委員会内に置くということで配分委員会設置要綱の改正をお考えでしょうか、あるいは別な方法で監事を置くのでしょうか、そのあたりを詳しくお伺いいたします。
市長
議員御指摘の中では外部ということもありましたが、その点も含めて今後の検討になりまして、今の段階でそこまで至っておりませんので、御理解いただきたいと思います。
吉田
外部から置くのが、やはり透明性を高める意味でも市民からの信頼性の点でも適切かと思いますが、義援金の問題については、個人情報などの面で非常に神経質にならなければならない部分が多く出てくると思います。例えば、義援金の配分が始まってから間もなく6年となりますが、受け取る資格を持つ方が既に亡くなっていても振り込みが継続しているような事例もあるのではないかと思います。そのようなさまざまなケースに対して、内部に監査委員を置くことになれば透明性という面ではある程度下がってしまうわけですが、個人情報が外に漏れにくい。逆に、外部から呼ぶとなれば、その方に個人情報をある程度提供しなければならない部分が出てくると思うのですが、個人情報の考え方について再度お伺いいたします。
市長
御存じのとおり本市に監査委員がおりますので、それを内部と言うかどうかという捉えになると思うのですが、いずれ公正、中立に御判断いただけますので、内部であるか外部であるかも含めて検討していきたいということです。透明性を高めることが趣旨ですので、そこのところはもちろん曲げずに進めていきたいと思います。
吉田
監査委員で義援金の配分についての監査を行うのも一つの手段かと私も考えます。ただ、やはり組織としては別な組織であるわけですから、現状で配分委員会の中で扱っている個人情報を外に出さないという原則がありますが、その部分の監査委員の取り扱いについて現状では市長はどのようにお考えでしょうか。
市長
まだ内部か外部かも決めていませんので、今の段階ではお答えしかねます。
吉田
大金を扱っているわけですので非常に重要な問題です。いずれにしろ市民の皆様にしっかり納得していただけるような制度に改めていただきたいとお願いいたします。
では、次に移りまして、小項目1に対する御答弁の中で義援金の受け付け終了の時期は今のところで未定ということでした。また、監査の時期は配分が終了してからということでした。
受け付けを今後もしばらく継続せざるを得ないのであれば、最終的に監査事務が一時期に集中してしまうことにつながるのではないかという懸念もあり、できれば今から対策が必要なのではないかと思いました。確かに義援金には会計年度の考え方がありませんので、定期的に監査報告を行う必要はないという受けとめ方ができると思いますが、義援金を寄せてくださった方や市民に対する説明責任を果たすためには、定期的に報告することが望ましいことは申すまでもないと思います。
小項目3 個人情報に配慮した上で、なるべく早い時期から定期的に収支報告を公表すべきについて市長にお伺いいたします。
市長
義援金の定期的な収支報告について、収入の部の本市に寄せられた義援金は会計課で公表しており、支出の部の本市の配分額については、県より通知があった義援金受付団体分と宮城県分の配分額とあわせて生活再建支援課で公表しています。
今後、県や他自治体を参考にしながらよりわかりやすい形で公表していきたいと考えております。
吉田
義援金受け付け終了後、どのようなスケジュールで収支報告に至るのか、もう少し具体的にお伺いしたいと思います。配分委員会の解散の時期や、日本赤十字社、県などから配分された義援金に対する監査や収支報告は本市で行うのかどうか、そのような点も含めて流れについて御説明をいただきたいと思います。
生活再建支援課長
監査のタイミングは配分が終了してからで、そこからスケジュール等の調整があるため具体的な期間をお示しするのは難しいのですが、できるだけ早く行いたいと考えております。
それから、義援金受付団体、宮城県の監査については、被災地の市町村にきちんと配分したのかという点はそれぞれのところの監査の領域だと思います。本市としては、受けた分が確実に入っているのか、そして配分する分については、口座振替になっているのですが、対象の方々に、義援金受付団体、宮城県、本市の3者のものが全て確実に振り込まれているか監査する形になると考えます。
吉田
では、日赤等あるいは県からの被災者の方への配分が終わるまで支出という面では続くわけですから、そこまで監査の最終的な報告はできないという認識でよろしいですか。
生活再建支援課長
そのとおりです。
吉田
では、配分が終了するまでしっかり市民の方たちに説明できるような形でのスケジュールを今後検討していただきたいとお願いして、次の大項目3に移ります。仮設住宅の利活用についてお伺いいたします。
平成28年5月、本市に整備されている仮設住宅の供与期間が7年間に延長されました。この先、再延長がなければ、平成30年度上半期には原則として仮設住宅の供与が終わることになります。仮設住宅の建物は県が買い取り契約をしたものとリース契約を結んだものの2種類に分けられますが、買い取り契約をしたものについて県は、供与期間終了後の無償譲渡先を募集しております。仮設住宅の無償譲渡を受ける際は、解体、輸送、再組み立て等の移設費用が別途必要となりますが、進め方によっては新築よりも低額で建物を建てることが可能と思われます。本市の仮設住宅の供与終了まで残り約1年となった今、本市にとってメリットとなる具体的な利活用の方法を検討すべきではないでしょうか。
そこで、小項目1 仮設住宅の供与終了後、宿泊施設や小規模事業者向け賃貸物件、市民向け施設として利活用を図るべきについて市長にお伺いいたします。
市長
供与終了後のプレハブ応急仮設住宅の有効活用については、宮城県においてその取り組みを進めており、本市にも宮城県より有効活用の希望の有無について平成28年12月21日付で照会が来ております。
対象となるプレハブ応急仮設住宅は、県所有のプレハブ応急仮設住宅のうち、長期利用が可能で比較的容易に移築できるユニットタイプの物件となっており、本市の仮設住宅で対象となるのは愛島東部の仮設住宅のみとなっております。
愛島東部の仮設住宅については、議員も御承知のとおり、現在も被災者の皆様がお住まいになっておりますので、現時点において有効活用を希望するのは難しい状況にあります。
また、プレハブ応急仮設住宅の有効活用に当たっては、本体については無償譲渡となりますが、解体、輸送、再組み立て等の移設経費が別途必要であり、それらの経費は全て譲渡を受けた側の自己負担となりますので、新築の場合との費用対効果等の検証も必要になります。
そのような状況にありますことから、現時点において本市では有効活用の予定はない旨、宮城県へ回答させていただいているところです。
吉田
現在のところ有効活用の予定はないということで、非常に寂しい気持ちです。費用対効果とおっしゃいまして、確かに再組み立てまでいくと新築のほうが安くなるという計算結果が出た経緯がこれまであったことも伺っています。しかし、仮設住宅という特別な施設であることをもう一度考えていただきたい。それは、住む場所を奪われた方々が生活再建までの年月を過ごすことになった場所です。地震や津波の恐ろしさとともに、後世に伝えるべき記憶の一つではないかと私は思います。私自身は仮設住宅で寝泊まりをした経験もない立場ですから、このようなことを申し上げるのは僣越かもしれませんが、未曽有の大災害に見舞われて、なお人々が励まし合って生活してきた場が仮設住宅であったという記憶をぜひとも後世に伝えたい、これから本市を訪れる方に少しでも知っていただきたいという考えです。
具体的な提案になりますが、仙台空港が民営化されたことにより、今後は本市でも宿泊場所の需要の高まりが予想されます。また、市長の選挙公約であるナスパの再開が実現すれば、全国各地から大会や合宿のために多くの利用者が本市を訪れることになるでしょう。防災教育を兼ねた修学旅行や研修旅行の宿泊施設としてもうってつけであると思います。まちの活性化にもつながる可能性があることから、宿泊施設としての仮設住宅の活用をもう一度検討しておくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長
先ほど申し上げたとおり、対象が愛島東部のプレハブ応急仮設住宅のみで、そこに現在被災者の方がまだ暮らしておられることもありますので、今は仮設住宅の利活用を具体的に検討する段階ではないと捉えています。宿泊施設としての活用は非常に興味深い提案であると思いますが、今の段階で具体的に県にこのような形で使いたいと申し上げる状況ではないということです。
吉田
もちろん愛島東部の仮設住宅に今も住んでおられる方がたくさんいらっしゃいます。ただ、いずれは供与期間が終了するわけですから、終わってから検討を始めるのでは遅い。やはりそれに先立って市として方向性を示しておくことが必要ではないかと思います。
話題が少し離れるかもしれませんが、今申し上げた宿泊施設のほかにも、今回陳情として提出されている交番の問題なども、例えば設置基準や警察官の配置などいろいろと難しい課題があるかと思いますが、仮設住宅の集会所などを交番として再利用するというアイデアをもって県に改めてかけ合うことにより、先へ進められるのではないかという期待も持っているわけですが、その点について御答弁はいただけないでしょうか。
市長
交番となると宮城県警察が主体の話になりますのでなかなかお答えしづらいということと、プレハブですからあくまで仮設ということで、恒久的な施設への転用は難しいだろうと考えています。いずれプレハブ応急仮設住宅の活用策の是非も含めて今後検討していきたいと考えております。
吉田
交番は難しいとしましても、具体的に例は挙げませんでしたが、小規模事業者用の賃貸物件などいろいろな使い道があるかと思います。やはり本市の今後の発展のためと、そして震災の記憶を後世に残すというこの2つの課題のために有効に活用するすべをぜひ考えていただきたいとお願いいたします。
それでは、最後に大項目4 復旧・復興事業に係る予算についてお伺いいたします。
小項目1 平成28年度より震災復興特別交付税による措置の仕組みが変わり、自治体が実質的な負担を求められている。この影響により、全ての復興事業が完了するまでに本市が実質的に負担する総額はおおむねどの程度ふえる見込みなのか、市長にお伺いいたします。
市長
議員御指摘のとおり、国の復興推進会議において、復興の基幹的事業や原子力事故災害に由来する復興事業については、これまでと同様、被災自治体の実質的な負担をゼロとし、復興事業と整理されるものでも、地域振興策や将来の災害への備えといった全国に共通する課題への対応との性質をあわせ持つ事業については、被災自治体においても一定の負担を行うものとするとの整理がなされたところであり、負担する程度については、被災自治体の財政状況等も踏まえ、通常の災害時の復興事業における負担の程度と比べて十分に軽減されたものとし、被災自治体の財政負担に十分配慮された上で設定がなされたものであります。
これらの変更に伴う具体的な自治体負担の対象事業といたしまして、社会資本整備総合交付金の復興分や東日本大震災復興交付金のうち効果促進事業分等について、負担を求められることになったものです。その負担の程度については、事業費のうち、国庫補助金等を除いた地方負担分の5%であり、補助率等により異なりますが、各対象事業費の1から3%程度となっています。本市が該当する事業で具体例を申し上げますと、社会資本整備総合交付金の復興分ですが、補助率が55%で地方負担が45%となっておりますので、45%の5%分として実質負担は事業費の2.25%となります。
今年度の対象事業といたしましては、社会資本整備総合交付金の復興分の閖上小塚原線整備事業や飯野坂杉ケ袋線整備事業、県営事業の用排水施設整備事業など6事業となっており、12月補正予算後ベースで申し上げますと、事業費33億930万1,000円に対しまして、その2.4%に当たる7,926万2,000円が制度改正に伴う新たな実質的負担額となっております。
また、今後の見込みについてですが、今後の復興事業の事業費全体を見込むことが困難な状況にありますことから、市の負担額を精査するまでには至っておりませんので、御理解願います。
吉田
今年度、6事業、全体で33億930万1,000円の2.4%で7,926万2,000円が本市の実質負担になるという御答弁でした。また、今後の実質負担の合計は今のところ見通すことは困難という御答弁でしたが、困難なことは確かに理解できますが、やはり事業を進めていくためにはお金が必要です。それも、これまでのようには国が全て手当てしてくれないと事情が変わった以上は、本市としてもある程度の見通しをつけておかなければならないと思います。市長としては、今後の実質負担を最大限どの程度まで抑えたいというお考えでしょうか。
市長
基本的には復興をおくらせないこと、そして市全体の適正な財政運営に努める中で、どのような判断をしていくかということになろうかと思います。復興に関する全体の事業費の中で市の負担分の精査がまだできていない状況ですので、そういった視点を踏まえながら今後事業に当たっていきたいと考えます。
吉田
6事業で約8,000万円の実質負担で、今後これがさらに膨らむことが予想されるわけです。
そこで、小項目2 実質負担の資金を手当てするために地方債発行が認められているが、実質負担の財源をどこから確保する考えなのか市長にお伺いいたします。
市長
新たな地方負担分の財源の確保については、復興事業における地方負担の導入に伴い、資金手当債が新たに設けられましたが、後年度交付税措置がないため、将来的には一般財源で負担することに変わりがないことから、通常事業における市債の発行同様、収支のバランスを見ながら、財源として市債を充当するか、一般財源により手当てするかについて判断していきたいと考えております。
吉田
起債をするかそれともそれ以外で確保するか、方針がまだ決まっていないということかと思いますが、起債となればやはり将来にツケを残す、借金を次の世代に残してしまうことになりますから、できる限りその方向は避けて、現在の通常事業も含めて財源をどこから確保するか、削るべきところは削って確保していくという方向をぜひとも考えていただきたいとお願いいたします。
平成23年度に震災復興特別交付税の制度ができてから、平成28年9月までの間に本市へ交付された交付金の額を合計したところ、324億円に上るという結果が出ました。そのうち相当な額が既に支出されていると思いますが、今後行われる予定の事業に充てられる分として積み立てられている額はどの程度か把握しておきたいと思います。
小項目3 震災復興特別交付税からの交付金は財政調整基金として積み立てられていると伺っているが、平成27年度決算として認定された約73億円のうち復興財源の額を市長にお伺いいたします。
市長
財政調整基金の内訳についてでありますが、平成27年度末財政調整基金残高約73億円のうち、震災分として約51億円、通常分として約22億円と捉えております。
吉田
過去の決算の記録を確認しましたら、財政調整基金の残高は平成21年度が約11億円、平成22年度が7億円、そして特別交付税の交付が始まった平成23年度に30億円に膨らんでいる。その後は平成24年度が66億円、平成25年度が84億円、平成26年度が73億円としばらく高い水準が続いていますが、震災以降積み立てられている額のうち、現在、純粋な一般財源分は22億円という御答弁でした。
51億円の特別交付税の分、復興財源のほうは、今後の事業による支出が続きますからいずれ減っていきますが、ここで1つ確認させていただきたいのは、復興事業が全て終わった時点において剰余が出た場合、これは国庫に返還するのでしょうか。
財政課長
震災復興特別交付税については、通常の復旧・復興事業の補助の財源の裏に充当してもなお不足する分等を国で算定して交付を受けているものです。復旧・復興事業に充てることを前提に交付されていますが、市では一般財源として管理を行っているもので、復旧・復興事業の裏の財源として交付されている分については、事業の実績に応じて過大過少分が生じますので、その分については精算が入ると捉えております。
吉田
精算が入るということは国庫に返還するという考え方かと思います。やはりこれは国全体で新たに納税者に負担を求めた上での制度ですから、国に余った分を返還するのは当然の流れだと思います。
財政調整基金の話に戻りますが、純一般財源分の残高が平成27年度末時点で22億円と。これは震災前の規模に比べると少し大きい額ですが、だからこそ財布のひもをしっかりとかために締めて、復興事業が終了した後に財政調整基金が枯渇するようなことにならないよう備えておかなければならないと思います。復興事業は全て国が手当てするという原則が変更されるに至ったわけです。なおさら身を引き締めて事に当たっていただきたいと考えますが、さらにそれ以外の部分についてお伺いしたいと思います。
小項目4 復興財源では賄い切れない事業の内容は、負担額を縮小するため、復興をおくらせない前提で見直しの検討に入るべきについて市長にお伺いいたします。
市長
復興事業については、各種復興財源を最大限に活用するべく、復興庁などと調整を行いながら現在も取り組んでいるところです。 そういった中で、どうしても復興財源で賄い切れない事業が生じた場合については、議員御提案のとおり、復興をおくらせないよう配慮しつつ、本市の負担額の軽減に努めていきたいと考えております。
具体には、震災復興計画の実施計画において、本市の負担額について十分精査を行いながら、実施時期等も含め計画的に進めていきたいと考えております。
吉田
復興をおくらせないというのは大前提です。それを踏まえた上で今後の再検討が入るという市長の御答弁でした。
復興事業の中で交付金の対象とならない部分も当然ありますし、それ以外にも復興事業に付随する形の市の単独事業もいろいろとあるように見受けられます。仙台市の話になりますが、復興事業費に約70億円の不足が生じる見通しであることが、2月15日の代表質疑によって明らかになりました。仙台市と本市とでは、被災の実態や予算の規模、また復興事業の進め方などが異なりますから、同じ問題が生じることにはならないと思いますが、本市の財政は本当にこのままで大丈夫なのか、復興事業が終わると同時に苦しい局面に立たされることがないのかということについて、市長から現状における御認識をお示しいただきたいと思います。
市長
いずれ厳しい状況であることは申し上げておかなければいけないと思います。ただ、そのまま手をこまねいているのではなく、国、県とも相談しながら、また内部でも事業の精査を行い、復興をおくらせない前提と適正な財政運営の両方を考慮しながら、一つ一つの事業、そして復興事業の全体像もつかみながら事業を進めていきたいと考えております。
吉田
復興の目標として閖上の持続可能なまちづくりに一つの大きな焦点を置いていると思いますが、持続可能とはいろいろな捉え方ができるかと思います。やはり市全体の持続を考えていった上で、今後の少子化、高齢化、そして、人口減少に転じるのはまだ先の話ですが、いずれ本市もそのような時期が必ず来るということも頭の中に置きながら、今後の震災復興をおくらせないように努めつつ、よりよいまちにしていっていただきたいとお願いいたしまして、私の一般質問とさせていただきます。
本会議
吉田
5番、宮城維新の会、吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、通告に従い総括質疑を行います。
初めに、大項目1 一般会計予算について、中項目1 予算編成の基本方針についてお伺いします。
市長は新年度予算案の提案理由説明において、大幅な財源不足が解消されない状況であることを述べられました。一般会計の歳出を款別に前年度当初予算と比較すると、例として災害復旧費が約11億9,000万円の減、総務費が約5億7,000万円の減であるのに対し、土木費が約37億2,000万円の増、教育費が約8億5,000万円の増であり、総額では約29億2,000万円の増となっております。また、同様に性質別に比較すると、投資的経費が約25億6,000万円の増と非常に高い水準となっています。全ての被災者が一日も早く生活再建を果たし、被災地が再び安心とにぎわいを取り戻すために、公共事業に莫大な経費が必要となることは論をまちません。そのための財源は原則として国が全額手当てするという制度のもと、本市はこれまでの復興関連事業を進めてきたことと思います。
しかし、復興事業の一部に自治体の実質負担が求められる内容へと制度が変わった今、これまで以上に緊張感を持った財政運営が求められております。政府は、平成28年11月、平成29年度予算編成の基本方針を閣議決定し、地方財政に関しては、国同様厳しい財政状況を踏まえ、引き続き歳出全般にわたり聖域なき徹底した見直しを推進することとしました。この方針は地方の自主性を妨げるものではありませんが、本市は新年度予算編成に当たり歳出全般において自主的に徹底した見直しが行われたのか、特に市債の新規発行を前年度当初比約3億円増としたその経緯について、負担の先送りと批判を受けぬためにも丁寧な御説明を求めます。
小項目1 市債の新規発行額が相変わらず高い水準にあるが、将来への負担をできる限り軽減するためにどのような手だてを講じたのかお伺いします。
次に、大項目2 震災関連事業について、中項目1 生活再建支援事業についてお伺いします。
震災から間もなく丸6年を迎える今になってなお、本市には生活再建の見通しが立たない被災者が多数おられるのが実情です。自力で生活再建するのが困難な立場に置かれた被災者に対し、復興公営住宅を整備し、健康で文化的な生活を営めるよう支援することが行政の務めです。しかし、恐ろしい津波を経験した海のそばで暮らすことに恐怖を覚えるなどの理由により、閖上の復興公営住宅には住むことができない被災者もおられます。そのような被災者への対応として、市長はさきの臨時会において復興公営住宅の内陸部への整備を提案しましたが、それに先立つ平成28年12月15日に開催された議員協議会において、抽せんに外れた被災者への対応として、NPO法人と連携し仮設住宅からの転居について伴走型支援に取り組むことを検討するとの説明がありました。内陸部への復興公営住宅整備の提案は議会で否決されましたが、選に漏れた方のためとされた伴走型支援は新年度予算案に残り、提案理由の説明の中で事業に取り組むことが明言されました。
先ほど大沼宗彦議員と山口 實議員からの伴走型支援の具体的な計画についての質疑に対し、市長は、民間賃貸住宅への転居を支援するなどの住まいの再建と、医療・福祉機関と連携して支援するなどの暮らしの再建の2本柱から成るとの内容の答弁をされました。これが本当に被災者の生活再建のために求められる支援であるのか、被災者のニーズはこれとは異なるところにあるのではないか、支援の空回りを憂慮するところです。
行政側は、現状を的確に把握し、伴走型支援による効果の見通しを立てていると思いますので、小項目1 仮設住宅の供与の終了が迫るが、伴走型支援を必要とする方と支援によって平成29年度中に生活再建を果たせる方の見込み数をお伺いします。
続いて、大項目3 通常事業についてお伺いします。
まずは、中項目1 総務費についてです。
本市の乗合バスなとりん号の運行契約が切れるまで残り1年となりました。平成30年度に向けて新たなバス路線の見直しを行うスケジュールとなっており、市長は新年度予算案の提案理由の中でも、さらなる利便性の向上を図るために必要な公共交通調査を行うと述べられております。なとりん号の路線等を見直す声はこれまでも多くの市民から寄せられてきました。南部においては総合南東北病院までの路線延長、東部においては、復興支援バスの廃止後、復興公営住宅から商業施設や公共施設などへのアクセスが地域の願いとして捉えられます。また、市全域として見れば、通勤通学の時間帯に利用客が集中し、昼間は乗客がほとんど乗らないという時間差による食い違いを解消することが求められます。
市長はさきの選挙戦において、公共交通の充実、高齢者の日中の移動を支援という公約を掲げられました。また、市長の後援会が発行したパンフレットには、「通勤通学の大量輸送に適したバスと日中の移動の足を区分するなど、公共交通体系のあり方を見直す(乗合タクシーなど)」と記されていました。就任後も市長の耳にはなとりん号の路線改定を求める市民の声が多く寄せられていると思われます。これまでの行政側の説明は、平成30年度の路線改定まで大幅な変更はできないというものであったと記憶しています。これを逆に捉えれば、大幅な改定は平成30年度しか行えないということになります。いよいよそのときが迫る今、市長はどのように市民との約束を果たす考えであるのか、具体的な見通しを示していただきたいと思います。
そこで、小項目1 公共交通のさらなる利便性の向上のために、なとりん号の運行形態の変更や、ほかの交通手段の導入はどこまで可能であると考えるのかお伺いいたします。
次に、中項目2 商工費についてです。
本市の経済をより活性化していく中で、今後特に大きな伸びが期待されるのが観光に関連する分野の産業でありましょう。本市は仙台空港が立地するという地理的利点を有するだけでなく、歴史的・文化的資源にも大変恵まれ、非常に魅力的な観光地としての要素を備えておりますが、本市を通過する観光客こそ多いものの、本市を目指して来る観光客は少ないのが実情です。さらに、仙台空港が民営化したことで、本市の飛躍の可能性はますます高まっています。インバウンドの拡大によってまちを元気づけることは、復興の進展にもつながると思われます。
本市の総合戦略には、地域資源を生かした観光振興の項目が掲げられており、10の具体的な施策が計画されていますが、うち8の施策が市内に範囲を限定するものであり、近隣自治体と連携して取り組める施策は2つしかないように見受けられます。また、新年度予算案の提案理由の中で市長が述べられた観光事業の中身も、全てが市内に限定されたハード面の整備にとどまるように見てとれます。しかし、一般的に観光客は自治体の範囲の中だけを移動するわけではありませんから、文化圏や地理的・歴史的背景を同じくする自治体間での連携は観光による地域振興のために望ましいことであると考えます。
一方、観光は本来、民間で取り組むべき地域課題であるという考え方もあろうかと思います。行政の関与は住民による活動を円滑化するための最小限の範囲にとどめ、行政にしかできないことに限るという形が理想であるのかもしれません。そこで、主にソフト面における広域的な観光振興をどのように進めていくべきか、市長が描く今後の観光施策のあり方をお示しいただきたいと思います。
小項目1 交流人口の増加に向けて、沿岸部と丘陵地帯それぞれの隣接自治体との広域連携の可能性をどのように捉えているのかお伺いします。
次に、中項目3 教育費についてです。 県内には各自治体に郷土の歴史的資料を展示するミュージアムがありますが、公営、民営いずれも立地しない自治体は本市だけです。(仮称)歴史民俗資料館の整備は、ミュージアム空白地たる地位を返上する、本市にとって歴史的事件になるものと確信しております。しかも、高額な費用をかけて建物を新設するのではなく、既存の建物を再利用するという方針は、行政運営に係る経費削減を求められる今日、高く評価されるべきものと言えるでしょう。資料館が市内外を問わず多くの来館者でにぎわい、展示内容により高い水準を求める声が高まった段階で新築の検討に移ればよいことであります。
いずれにしろ、いかに多くの来館者を集めるかが重要です。幾ら収蔵品の質と量を充実させても、誰もいない展示室で係員が退屈そうにしているようでは宝の持ち腐れとなってしまいます。全国にはさまざまなミュージアムがありますが、東京都など大都市にある一部施設を除き、ほとんどの施設が特に平日は寂しい風景となっているのが現状です。(仮称)歴史民俗資料館も、他市町村に倣ったセオリーどおりの運用に終始すれば、いずれ似たような状況に置かれることは避けられないと思われます。まして、ほかの目的に使われていた既存の建物を再利用するという不利な条件を埋めるには、他の自治体が取り組まないような思い切った運用が求められると思います。
ここで振り返るに、平成28年9月定例会における私の無形民俗文化財についての一般質問に対し、市長から、無形民俗文化財が持つ歴史的な価値や特徴を市内外へ積極的に情報発信するとともに、他の文化財との一体的な観光資源としての活用について教育委員会と協議していきたい旨の御答弁がありました。無形民俗文化財の担い手は市民であることから、(仮称)歴史民俗資料館において市民が無形民俗文化財を発表することは、施設の趣旨からも当然進めるべき取り組みです。新年度予算案の提案理由において、当資料館は郷土の歴史・文化遺産を展示、公開、体験できる施設と位置づけられていますが、特に体験については市民の参画なくして実現不可能と思われます。資料館を人でにぎわう施設にするためには、今申し上げたことを初めとして民間の活力を最大限に発揮させる環境を整えることが重要です。その一方で、有形の歴史資料を扱うには専門的で高度な技術と知識が求められます。民間人と専門家との協力関係をどのように構築するかによって、資料館の未来は左右されることになるでしょう。
そこで、小項目1 (仮称)歴史民俗資料館を魅力的な施設にするために、有形無形の民俗文化財をどのように活用するのか、人材という市の財産をどのようにかかわらせていく考えなのかお伺いします。 以上、平成29年度予算案に対する総括質疑とさせていただきます。
市長
5番吉田 良議員の総括質疑に答弁をいたします。
まず、大項目1 一般会計予算について、中項目1 予算編成の基本方針について、小項目1 市債の新規発行額を軽減する手だてに関して御質疑をいただきました。
平成29年度予算における市債は38億3,270万円ですが、その内訳は、いわゆる建設債である普通債が27億850万円、臨時財政対策債が11億2,420万円となっております。
普通交付税の振替措置である臨時財政対策債については2億240万円の増額となっておりますが、その元利償還金相当額については全額を後年度に交付税措置されることから、将来の負担にはならないものであります。
普通債は、対前年度では1億310万円の増額となっておりますが、これは、新図書館施設整備事業や増田公民館災害復旧事業など前年度から既に予定されていた施設整備によるものが大半を占めております。
普通債の発行に当たっては、後年度交付税措置がある市債を優先して活用することで、将来の負担を軽減するよう努めているところですが、交付税措置のない市債以外に活用できる財源がない事業もあることから、住民負担の世代間の公平のための調整という市債の機能に着目し、事業の優先度などを勘案しながら発行せざるを得ない場合もあることについては御理解いただきたいと存じます。
次に、大項目2 震災関連事業について、中項目1 生活再建支援事業について、小項目1 伴走型支援を必要とする方及び平成29年度中に生活再建を果たせる方の見込み数についてお尋ねをいただきました。
仮設住宅の供与については、特定の理由により供与期間が延長となる特定延長対象世帯を除き、7年間の供与期間をもって終了となります。
供与期間終了に伴い、さまざまな理由から具体的な生活再建策を決めかねている方に対し、伴走型支援に取り組んでいきますが、その支援を必要とする世帯についてはおおむね100世帯程度と考えております。
また、再建を果たせる方の見込み世帯数については、具体的に捉えることはできませんが、支援を必要とする全ての方が一日も早く再建方針を決定し、生活再建が進められるよう支援を行っていきたいと考えております。
次に、大項目3 通常事業について、中項目1 総務費について、小項目1 なとりん号の運行形態の変更やほかの交通手段の導入の可能性についてお尋ねをいただきました。
なとりん号運行形態については、平成29年度は原則、現状を維持し運行するものとし、国より地域公共交通確保維持改善事業補助金を受けていることから、引き続き利用者へのアンケート調査を実施することとしています。
現在、平成28年度において平成30年度からのなとりん号運行路線等の見直しを行っている状況であり、素案ができましたら平成29年度中に議員の皆様に説明の場を設けたいと考えております。
現状の考え方といたしましては、現在のなとりん号による閖上の復興まちづくりへの対応や通勤通学、通院、買い物、金融機関等への移動手段としてよりきめ細かなサービスができるよう計画策定に取り組むものであります。
なお、新たな交通手段の導入については、平成29年度では検討する考えは持っておりません。
次に、中項目2 商工費について、小項目1 交流人口の増加に向けた隣接自治体との広域連携の可能性についてお尋ねをいただきました。
名取市、岩沼市、亘理町、山元町で構成する名亘地場産業振興協議会において、平成28年度は隣接自治体の観光資源を生かした広域周遊ルート策定やプロモーションなどの事業を進めてきたところです。平成29年度においても、引き続き平成28年度の成果をもとに旅行プランの商品化などの取り組みを続けていきます。
また、県南4市9町で構成する宮城インバウンドDMOの設立が平成29年3月に予定されており、加えて、宮城県及び名取市を含む関連6市3町による仙台・松島復興観光拠点都市圏においても平成29年度にDMOを設立する予定です。これらの枠組みに本市としても積極的に参画しながら、広域連携に取り組んでいきます。
次に、中項目3 教育費について、小項目1 (仮称)歴史民俗資料館についてお尋ねをいただきました。
(仮称)名取市歴史民俗資料館は、本市が有する歴史・民俗資料を調査、研究、保存するとともに、市民に総合的に公開し、屋内外での体験学習、各種歴史学習や文化財愛護活動の拠点となる施設を基本理念に、調査収集、資料保存、展示公開、学習交流、観光拠点の5つの機能を有する施設として整備を目指すものであります。
中心となる展示公開では、名取の特徴的な歴史に触れ、郷土の魅力を再発見していただくよう、埋蔵文化財などの歴史資料のほか、多様な民具などの有形民俗文化財を活用した展示コーナーや、情報・体験コーナーを施設内に設置することとしております。
また、学習交流では、歴史体験のほか、各地域の民俗芸能など無形民俗文化財の実演や交流もできる体験学習施設の整備も計画しています。
今後、施設運営に当たっては、市内の文化財関係団体等の人材活用についても検討していきます。
平成29年度では、こうした基本構想等をもとに、資料館の施設の配置や施設内のゾーニング、展示コーナーなどの構成等を取りまとめる基本設計の策定に取り組んでいきます。
財務常任委員会
吉田
8ページ、9ページ、1款3項軽自動車税についてお伺いします。昨日の御説明だと2万6,577台で156台の増ということでしたが、障がい者の方の減免となっている台数は何台を見込んでいますでしょうか。
税務課長
見込みというか平成28年度の実績という形になるのでしょうが、身体障がい者の方の減免の台数としては、平成28年度は152台が対象になっているところです。
吉田
そうすると、平成29年度も同じ台数を見込むということで、申請の漏れなどは特に考慮していないということですか。
税務課長
新規で申請される方はなかなか見込めませんので、平成28年度の実績をもとに予算編成をしているところです。
吉田
28、29ページ、14款1項1目11節中国残留邦人等支援給付事業費ですが、減額となっている要因についてお伺いします。
社会福祉課長
中国残留邦人等支援給付事業費については、平成28年度は1世帯2名という形で給付していました。これが平成29年度は1世帯1名ということになりますので、実質減額という形になっています。
吉田
クラウドファンディングについてお伺いしたいのですが、いろいろな取り組みで使われるようになってきている仕組みかと思いますが、このクラウドファンディングに寄附金を納めた方に対して、例えば温泉施設ができた後で招待券を贈るとか、そういう形で何か特典をお考えでしょうか。
商工観光課長
今、現状では具体的なことはありませんが、その辺も含みを持って、平成29年度の中でいろいろと内部で調整していきたいと考えています。
吉田
できるだけ多くの方にこの仕組みを使って協力を仰ぎたいところですが、どのような形でPR、周知をしていくお考えでしょうか。
財政課長
クラウドファンディングの募集の仕方については議決をいただいた後に検討に入ることになりますが、現在のふるさと寄附の募集に当たって活用しているサイトなどもありますので、そういったクラウドファンディングの取り扱いをしているポータルサイトの活用を考えています。そういったサイトも種々いろいろとある中で、手数料の額もさまざまですし、PRに対していろいろと支援をしていただけるサイトなどもあります。そういったところを総合的に判断しながらサイトについては選択をしていきますが、まずは何よりもPRをしていくことが大事かと思いますので、その辺も重点に置きながら、このクラウドファンディングについては行っていきたいと考えています。
吉田
58、59ページ、先ほどのクラウドファンディングの件についてです。ふるさと寄附金の場合だと寄附した額の何%かが税の控除の対象になると思いますが、このクラウドファンディングの場合はそのような税の控除はあるのでしょうか。
財政課長
ふるさと寄附とクラウドファンディングの区分けについては、こちらの内部での仕分けの処理の違いだけですので、ふるさと寄附と同様、税の控除の対象になるものと考えています。
吉田
そうすると、控除の仕組みというか率もふるさと寄附金と全く同じと考えてよろしいのでしょうか。
財政課長
委員お見込みのとおりです。
吉田
58、59ページ、もう一度一般寄附金でお聞きしたいのですが、ふるさと納税とクラウドファンディングは同じ仕組みということでしたが、本市の場合、市民の方が本市にふるさと納税をすることは受け付けているのでしょうか。
財政課長
もともとふるさと納税として始まったときには、市外にお住まいの方がふるさとである名取市に寄附という形で納税することが本来の趣旨でしたが、制度上、居住地によって寄附ができないという制限はありませんので、名取市民の方がお寄せいただくものについても受け入れをしているところです。
吉田
そうすると、返礼品についても他の自治体の方が納めた場合と同じような形で受け取れるという理解でよろしいでしょうか。
財政課長
本市ではそのような取り扱いとしております。
吉田
77ページの2款1項1目13節委託料ですが、人事管理システム保守委託料、人事評価システム保守委託料とありますが、この両者の違い、特に人事評価システム保守の内容について伺います。
総務課長
まず、人事管理システム保守委託料ですが、こちらは職員の人事異動や職員の給与の号俸などを管理するシステムです。そして、人事評価システム保守委託料は、平成27年度に試行という形で人事評価制度を始めましたが、平成28年度から本格稼働となっております。現在、人事評価については評価シートにより個人ごとに管理しているところですが、現在エクセルで管理していて、一次評価、二次評価、それから本人にメールでそのやりとりをするという煩雑な部分がありますので、こちらのシステムを採用して事務の効率化を図るために委託するものです。
吉田
今までのエクセルを使った内容から、この専用のシステムを導入するということで、事務がより簡略になっていくのかと思いますが、このシステムを利用するに当たって、それは全職員が同じシステムをそれぞれ新しく学び直して使っていくという形でよろしいのでしょうか。
総務課長
評価シートの形式はできるだけ変えないようにしたいところですが、どのシステムを採用するかによって若干差異は出てくると思います。なるべく職員の負担にならないように運用していきたいと考えております。
吉田
81ページの2款1項3目11節需用費について伺います。印刷製本費が平成28年度と比べますと増となっておりますが、その理由を伺います。
総務課長
印刷製本費の増の理由ですが、広報なとりの印刷製本費になります。主にページ数の増加と、平成29年度から表紙と一番後ろの2ページだけになりますが、カラーページを導入して対応するということで増になっているところです。
吉田
議会だよりも委員長のもと今一部カラー化と、内容をより見やすいものとして多くの市民に見ていただけるようにいろいろ工夫しているところですが、カラーページとページ数増以外に、工夫した取り組みをしている点があったらお伝えください。
総務課長
昨年の10月号からポイントを少し大きくしました。11月からは、さらにポイントを大きくしたところです。少し見やすくなっているのかなと考えているところですが、その分ページ数が増になっているところがあるので、費用は少しかさんでいるかもしれませんが、そういった工夫はしているところです。
吉田
93ページ、2款1項13目電算運営費の中で13節委託料、14節もできれば一緒にお聞きしたいのですが、市民の大切な情報を扱っているこのようなプログラムや委託というものについて、いずれかの業者に委託することになっていると思うのですが、その際の業者の選定の仕方は入札で行われているものでしょうか。次の14節は借上料となっていますが、そちらについてもある業者から毎年借り上げるという契約で進めるに当たって、これは入札で行われているのかについてお伺いします。
市政情報課長
電算機器関係ですが、これは毎年入札ではなくて、5年の長期継続契約で入札によって運用しているところです。
吉田
5年ごとに更新する、その都度入札が行われるということかと思いますが、このような大事な情報を業者が扱う上で、プログラムの中身を業者がいろいろ組んでいくと思うのですが、中にどういうプログラムが入っているか、行政でどこまで目が届いているかについて確認したいと思うのです。
といいますのは、やはりその業者に5年、次の5年でもし入札を行ったとしても、次の入札のとき、ほかの業者がそこで入札に参加できるかどうかという問題が出てくると思うのです。これまで構築してきたのは、その業者が手がけてきたものであって、それを引き継ぐのは相当大変な労力が発生するわけですから、そういうことも考えますと、どうしても同じ業者に非常に長い年月お願いするという形になってしまうのではないかと思います。そうすると、支出する先が一つの業者にずっと固定されてしまうことにもつながりますので、どのくらいまで市としては委託している中身について把握しているか、お伺いします。
市政情報課長
電算機器借り上げについては5年間の長期継続契約で運用しているわけですが、5年たったからすぐ新しくということでは、今までは行っていないところです。ただ、やはり電算機器関係、プログラム関係もそうですが、これについてもやはりいいものもあれば悪いものもあるということで、実際更新の時期、5年ごとになりますが、ある時期が来たときに当然ベンダーはいろいろありますので、そのときに事前に会って、システムにプロポーザルなりで本市に合ったものを取り入れていきたいと考えておりますし、今度の更新のときにも、更新する二、三年前から、どのような方向で行っていくかということで検討していきたいと考えております。
吉田
113ページ、2款4項選挙費の3目宮城県知事選挙に係る費用で、14節使用料及び賃借料ですが、投票所等借上料ということで計上されていますが、この選挙で期日前投票所はどのように行われるのでしょうか。
選挙管理委員会事務局長
期日前投票所は、従来どおり市役所1カ所です。
吉田
時間について伺います。
選挙管理委員会事務局長
午前8時30分から午後8時までとなっております。
吉田
3款4項生活保護費の2目20節扶助費について伺います。基本的な制度についてですが、保護を受けている方に臨時収入があった場合の扱いについて教えてください。
社会福祉課長
生活保護費については一定の基準がありまして、基準の中で収入、例えば年金収入があればそれを差し引いた形、年金収入と生活保護費を合計した金額が最低生活費になるという計算をし、全額を支給するわけではなく、年金収入分を除いた金額を生活保護から支給するという形になります。その最低基準額の範囲内で臨時収入があった場合には、その収入の内容を審査し、それがそれからの生活に必要なものであるかないか、その辺も踏まえて収入認定という形をとります。その臨時収入が生活保護を受けてから発生した、例えば年金が遡及されたというような臨時収入があった場合ですと、生活保護法第63条に基づき返還という形になります。
吉田
そのような臨時収入というのは、全て市役所で把握できるわけではなく、受けられる方から申請される部分が多いかと思うのです。今回国の予算委員会でも話題になったことですが、パチンコで勝った場合の臨時収入ということで、そのあたりについて考え方としては勝った分と負けた分の差し引きではなく、負けた分はあくまで消費として、勝った分があった場合は必ずそれは所得になるという捉え方がされるという答弁があったと記憶しています。そうなると、ほとんどのケースで所得として捉えられるのではないかと思いますが、その辺の把握の仕方はどのようにお考えなのでしょうか。
社会福祉課長
基本的にパチンコを生業としている方については、そういう方法もあろうかと思います。ただ、通常の就業形態の中で、就業する時間帯の中でパチンコをすることについては、就労指導という面からは本来は認められていない。その後の、例えば我々も勤務している時間以外に起きた部分については、よほどの金額があれば収入申告ということで御本人からの申告があろうかと思いますが、その辺の厳密な差し引きはなかなか難しいと捉えています。
吉田
159ページの3款5項災害救助費の2目13節委託料の伴走型支援について、もう少し具体的に、伴走型支援を受けようとする方がその支援を利用するときの手続や、あるいは市役所がこの人にはこの支援が必要だと、こちらから把握してそれを始めるのか、そのあたりのスタートの仕方についてお伺いします。
生活再建支援課長
現在考えている方法は、まず市で用意します対象者リストをつくりまして、それをもとにその団体に戸別訪問をしていただいて、そこで本当にそこから先の支援が必要であるかどうかというところを見きわめていただいて、そこから先に進むという形を考えております。
吉田
歳入でも質疑があったと思うのですが、全ての方の生活再建をできるだけ早期に目指すという形であったと思いますが、業者に委託をして一定の委託料をお支払いして、それで1年間行うという形になると、その業者の中でその事業に対して、例えば歩合のような形でうまく進んだらそれだけ報酬が得られるとなれば、そこに当たる方も一生懸命頑張ってくれると思います。結果が出ても出なくても同じような報酬となると、少し心配な点が出てくるのですが、業者の取り組みについてはどのように捉えていくのでしょうか。
生活再建支援課長
こちらで委託をお願いしたいと思っている団体は、実は仙台市、多賀城市、宮城県の伴走型の業務を実際に行っているという実績がありますので、委員御懸念のところについては発生しないのかなと考えております。
吉田
189ページ、6款1項7目の19節負担金補助及び交付金、下堀及び矢野目堀用排水施設整備事業負担金について伺います。まだ完成は少し先のことかと思いますが、工事の内容としては、堀の側面や底の部分をコンクリートで固めていくということで、一部その中でコンクリートでない部分も残す形で進められていると伺っていますが、この事業が行われて堀が完成することによる生態系など環境への影響についてはどのように捉えていらっしゃるのでしょうか。
農林水産課長
下堀及び矢野目堀の改修事業の関係の御質疑ですが、まさにこの下堀、矢野目堀については、下堀のほうが多いのですが、希少生物が生息している水路ということがわかり、今回の改修事業については、その辺のところにも十分重きを置いて工事を進めているところです。具体的に言うと、アカヒレタビラという小さい魚がいます。そういった希少生物を保護するために、通常であれば水路の改修は三面張りといって側面と底をコンクリート製などに施工するわけですが、今回は側面だけをコンクリート製にして底は土のままにするという二面張りという施工方法としています。また、水路の機能としては水の走りがある程度いいことが条件になるものだと思っていますが、実はこの下堀の改修については、ところどころ水路を蛇行させるような形につくったり、希少生物がすみやすい工夫なども取り入れながら現在事業を進めているところです。
吉田
配慮をされた上での工事が進められているということかと伺いましたが、堀の側面だけを固めて底の部分は土を残すという施工方法をとる部分が、全体の工区のうちのどの程度になるのか、その距離の割合についてと、それから、今おっしゃった一部で土の部分を残すという話ですが、例えば増田川も現状を見るとそういう土の部分が既に流れてしまっているところがあります。やはり水が常に流れているものですから、削られて流れていくことが考えられますが、そういうところについてどのような対策をとられるのかお伺いします。
農林水産課長
土の部分の割合ですが、全面的にその工法を採用すると伺っています。
それから、土砂の堆積の御質疑ですが、今回の下堀の改修についてはあくまでも環境配慮型の工事ということを第一として設計し、施工をしているところです。例えば土砂の堆積などについては、たまれば当然しゅんせつを行わなければ水路の機能を果たしませんので、具体的にはそういった対応になるのかなと思っています。
吉田
201ページの7款1項4目8節報償費の中で名取市写真コンクール入賞者記念品とあります。恐らく市役所1階のホールに展示されるコンクールのことかと思いますが、あの場における写真の展示のほかに、別な場での展示は行われているのでしょうか。
商工観光課長
まず、応募作品については、初めに秋祭りの会場内で展示しています。そのほか名取駅でも展示をしている状況です。
吉田
より多くの方に見ていただくことが今後の課題なのかなと個人的には思うのですが、今後、ホームページ等を使った展示などについては御検討されていないのでしょうか。
商工観光課長
もともとこの写真コンクールの事業の目的には、情報の発信、観光資源を知っていただくということもありますので、いい作品についてはホームページやパンフレットの中に組み入れていくような形で進めているところです。
吉田
223ページ、8款5項公園費1目の8節報償費についてお伺いします。公園等愛護協力報奨金ですが、愛護協力団体は平成29年度何団体と見込んでの予算なのか、平成28年度と比べての増減も含めてお知らせいただきたいと思います。
都市計画課長
公園等愛護協力団体は公園の除草や点検をお願いしている団体で、平成29年度については76団体、148公園を見込んでいます。平成28年度については73団体、138公園でしたので、3団体、10公園の増加となっています。
吉田
その数は、平成29年度については、見込みというかこれからふえるというよりも、今の段階で76団体、148公園ということでよろしいですか。
都市計画課長
10公園については、開発等で新しくできた公園の帰属を受ける形になっており、まだ帰属を受けていないところもありますが、いずれ平成29年度は148公園になるということです。それから、愛護団体については申請制をとっていますので、地元町内会に話をして愛護協力団体として登録申請をしていただくことになります。
吉田
241ページの9款1項4目防災費13節委託料の防災ラジオ販売委託料についてもう少し詳しくお聞きします。私も購入して防災安全課で手続をとって業者に設置していただきましたが、今回このように委託料となるとどのような手続で購入に至るのでしょうか。
防災安全課長
基本的にこれまでと購入の仕方は変わっておりません。市役所に来ていただいて申請用紙を書いていただき、1カ月分を取りまとめますので、翌月あたりに業者が持っていって1,000円を頂戴し、使用方法を説明するとともに、どこで電波が入るか確認して、置く場所を説明して有償配布しているものです。
吉田
そうすると、あえて委託料として計上しているのはどのように捉えるのか、これまでと大きな変更点は特にないと捉えてよろしいのでしょうか。
防災安全課長
先ほど申し上げたとおり基本的にはこれまでと同じで、市内の業者が申請した方の自宅に持って上がって配布するものです。
吉田
237ページの9款1項2目非常備消防費13節委託料と14節使用料及び賃借料にある消防団管理システムの内容を伺います。
消防本部総務課長
現在、現職消防団、退職消防団、965名の消防団の情報を管理しており、今後も消防団情報量は増加していくものと考えています。現状は複数のソフト、それからエクセルで作成したデータ、また紙ベースで別々に管理している状況です。今回の消防団管理システムの導入は、消防団情報を一括管理することで業務の効率性や正確性の向上、職員の負担軽減を図ることを目的に考えているところです。
吉田
人事評価で同じようにエクセルから一括管理になるという先日の御答弁を思い出したのですが、紙に書いてあることやこれまでエクセルに入力されていたデータを別のデータベースに移しかえるということだと思いますが、その移しかえの作業はどこで行うのでしょうか。
消防本部総務課長
消防団管理ということで住所や生年月日等はソフトに入っており、紙ベースでも消防団員台帳として管理しております。データをシステムに入力することについては現在担当職員が行っているところです。
吉田
消防費でお聞きします。241ページの9款1項4目防災費13節委託料、防災行政無線保守点検等委託料とありますが、平成29年度はどのような体制で保守点検を行っていく予定かお伺いいたします。
防災安全課長
これについては、同報系のデジタル無線と市役所にある車など移動系の無線、そして監視カメラとモーターサイレンの3種類についてこれまでどおり設置した業者に保守点検を委託するものです。基本的には、外観検査あるいは機器を開いて異常がないか点検し、システムについても点検して、何かあれば担当に異常が報告されます。
吉田
具体的にスケジュール等はもう決まっているのかどうかと回数をお伺いいたします。
防災安全課長
同報系無線と移動系無線は年2回です。監視カメラとモーターサイレンについては1回です。時期については上半期に1回、下半期に1回と考えています。
吉田
255ページの10款2項2目教育振興費18節備品購入費の学校図書購入費についてお伺いします。市内の図書についてはデータベース化されていくという話を伺いましたが、学校の図書についても、本市の場合は司書が配置されているということで、学校は図書室ではなく図書館という位置づけとお伺いしたこともありました。学校図書の貸し出しを行う際、例えばA小学校の児童がB小学校の図書をA小学校で受け取るなど、そのような仕組みは平成29年度はあるのでしょうか。
学校教育課長
ほかの学校間での貸し出しは今のところ考えておりません。
吉田
もし借りたいとなったときは、ほかの学校にわざわざ行って借りてくると。そこまでする人はいないのかもしれませんが、お伺いしたいのは、小学校が11校ある。その11校それぞれに図書館が設置され、学校で図書を購入するということで毎年蔵書がふえていくと思うのですが、学校ごとにそれぞれ同じような本を購入してあげたいという気持ちももちろんわかりますが、それよりも広くたくさんの種類の本を置いてあげたほうが、別な学校にしかないとなった場合そちらに借りに行くことになってしまうかもしれませんが、それでも市で所有する図書の質というか種類をふやしていくという意味ではそちらのほうがメリットがあるのではないかとも考えるのですが、図書の選定の基準についてお伺いいたします。
教育長
新年度予算で学校図書館のネットワーク化を図ることについては、委員からも御指摘がありましたように、それぞれ各学校の考えで本を購入しており、子供たちがどこの学校からも借りられるという体制はまず考えておりません。ただ、例えば授業の中で同じ本を40冊ぐらい欲しいというときには、名取市図書館やほかの学校に照会して、一定の期間ある学校でまとまった同じ本を使うこともあります。ただ、それを今までファクスや電話でのやりとりをしていましたが、今度ネットワーク化すると、どの学校にどのような本があるか、市の図書館にどのような本があるか、それぞれの学校で検索することができます。そういった意味でより効率的に本の活用ができると考えております。ただ、やはり各学校で子供たちの希望や読書傾向などを考えて蔵書計画を立てて本を購入していますので、どの学校からもどの子供も借りられるというところまでは現在は考えておりません。
吉田
私も昨年、東京の国立能楽堂で観劇してきた者の一人ですが、平成29年度中に開催されるということで、恐らく出演される方との調整はかなり詰まってきているとは思うのですが、日程等、例えば何日間にわたって行われるのか、また1日で行われるとしても午前の部、午後の部に分かれるなどいろいろな日程の組み方があると思います。そのようなことは今のところどこまで決定しているのかお伺いいたします。
文化・スポーツ課長
これについては、相手方もおりますことから、現在のところ、10月1日の文化会館の開館日に合わせまして1回開催する予定となっております。開催時間は午後を予定しています。
吉田
恐らく大ホールとなると思います。1回きりの非常に貴重な公演ということで、チケットが恐らく売り切れてしまうほど人気が出るのではないかと、そのように半分期待を込めているところでもありますが、東京で行われた公演で感じたことは、やはり聞くだけでは昔の日本語ですからよく聞き取れないというか、内容がよくわからない部分がありました。ただ、国立能楽堂には座席一つ一つに字幕がついており、これを見ながらですと内容をとてもよく把握できると。文化会館にはもちろんそのような設備はありませんので、例えば字幕をどこかに出すなどといったことについては何かお考えなのでしょうか。
文化・スポーツ課長
国立能楽堂では委員おっしゃるとおり自分の前の席の後ろ側で字幕が見られる形態をとっております。本市で開催する際はそういった各席で字幕で見るような設備は難しいと考えておりますが、わかりやすいような形、例えば両脇に字幕を流すとか、または前段で具体的な内容を誰かに語っていただくというようなことで、より理解を促進できるような取り組みも検討していきたいと考えています。
吉田
329ページ、8款2項1目1節報酬のレセプト点検員報酬ですが、平成28年度の当初は3名となっていて、先日の補正で1名分減って、今回の平成29年度当初で2名となったと思います。本来であれば補正でお聞きすればよかったのかもしれませんが、これを3名から2名に減らした理由についてお伺いします。
保険年金課長
平成28年度当初においては、確かに委員おっしゃるとおりレセプト点検員の嘱託は3名で予算をお願いし、実際4月から3名で点検をしていたところですが、3名のうち1名の方が平成28年6月に家庭の事情で退職されました。その時点で1名補充を検討しましたが、平成30年4月からの県単位化に向けてレセプト点検の共同実施が検討されていたところでしたので、その経過なども見据えながら、平成28年度中は1名補充をしていなかったところです。今回、平成29年度についても、レセプト点検の共同実施についてまだ結論が出ていませんので、それも見据えながら、今後、補充もしくは現状のままで点検を進めていこうと考えています。
吉田
ただいまの答弁ですと、まだ補充するかどうかの方針ははっきり定まっていないと捉えられますが、どのような状況になったら補充するとか、そういう明確な方針はお示しいただけないものでしょうか。
保険年金課長
今のところ、基本的な方向性はまだ見出していないところですが、平成30年4月からの国民健康保険の県単位化によるレセプト点検の共同実施がいつから始まるか、その辺をいろいろ見ながら、今後検討させていただきたいと思っています。