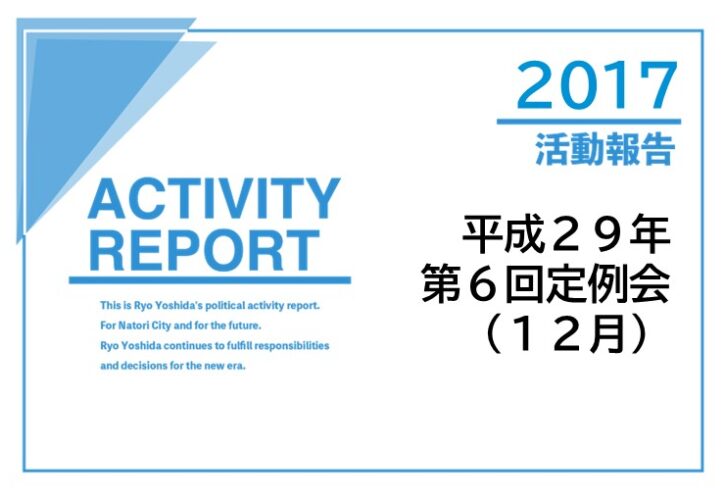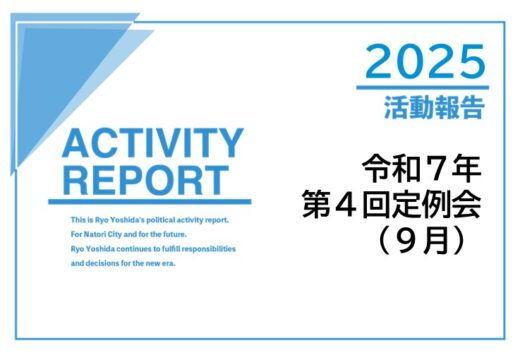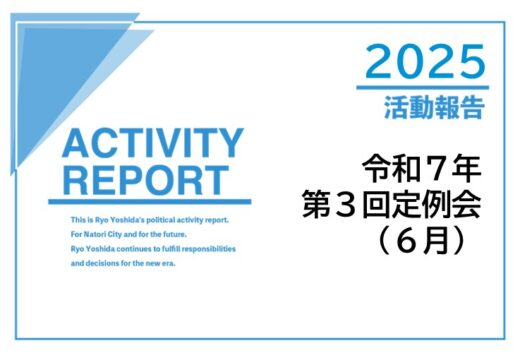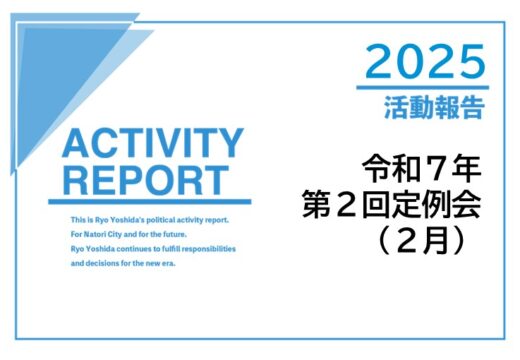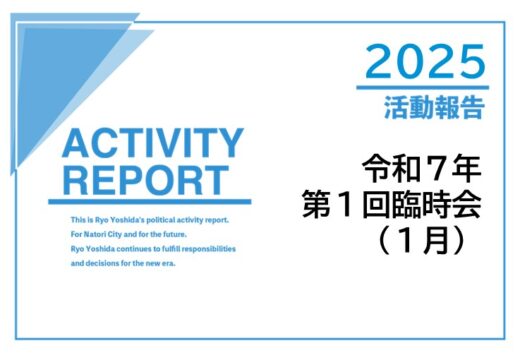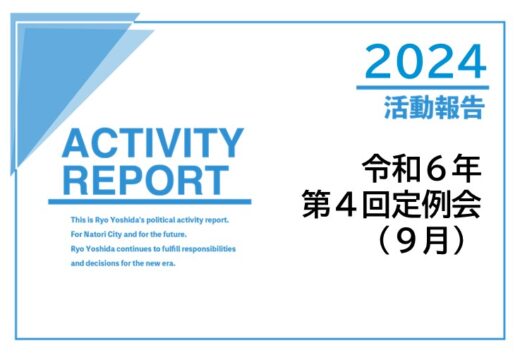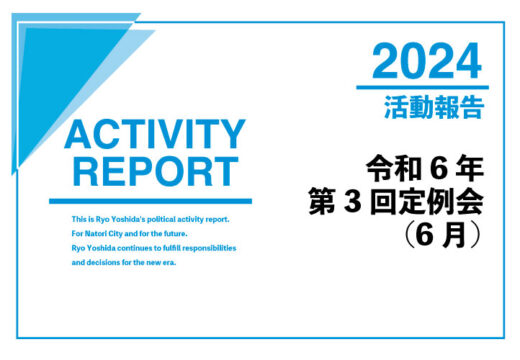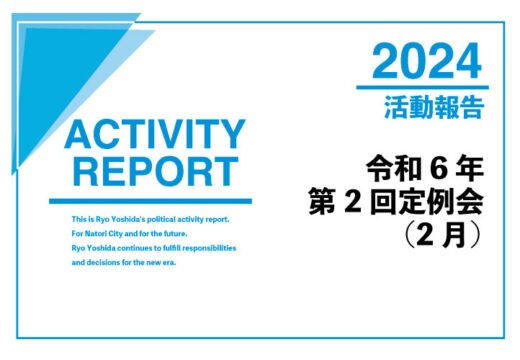一般質問
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、通告に従い私の一般質問を行います。
まず、大項目1 ICTやモバイル端末の普及拡大を受けた施策についてお伺いいたします。
近年、ICT技術の発達は目覚ましいものがあります。人工知能の機能を搭載したロボットは既に商品化されています。愛知県では無人の自動運転車の走行実験が公道で始められており、市販化される日もそう遠い未来のことではなくなってきました。これから日本では少子高齢化と人口減少が進むことが予想されております。私が大学を卒業した当時は就職氷河期でした。しかし、現在は逆に人手不足が深刻化してきています。人工知能や自動運転などの新しい技術は労働力不足の解消にも寄与するものと期待されております。
また、ICTの技術は人と人とのコミュニケーションのあり方も大きく変えました。人対人のコミュニケーションは、直接会って話さなければならなかった原始時代以降、手紙、電話、ファクス、電子メール、テレビ電話と時代とともに新たな技術が誕生、普及し、現在はモバイル端末さえあれば、ほとんど時間や場所を選ばずに好きな手段で世界中の人々とつながることが可能です。
ICTやモバイル端末の普及拡大という情勢の変化を受け、行政も新しいサービスの形を追い求めていくべきときに来ています。新たな技術を行政に生かす取り組みは既に一部の自治体で始められております。一例を挙げますと、長野県の教育委員会では平成29年9月、2週間だけ通信アプリケーションLINEを使い中高生の悩み相談を受け付けました。それまで電話による相談を行い、昨年1年間で259件であったのに対し、LINEには2週間で1,579件ものアクセスがあり、このうち547件の相談に乗ることができたとのことです。その内容はいじめや不登校についての悩み、また恋愛や進路の相談などもあったそうです。同様の取り組みは滋賀県大津市でも平成29年11月から始められております。本市もさまざまな相談事業を実施していますが、通信アプリによる相談はまだ行われておらず、庁舎や施設への訪問が原則です。しかし、ほとんどの相談は受け付け日時を平日の昼間に設定しており、学生や勤め人が利用しやすい環境とは言えません。悩み事については対話で相談することに抵抗を覚える方もいます。
そこで、小項目1 市が実施している相談事業の中から、直接の面談が難しい層を対象とするものを選び出し、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)上に相談窓口を開設すべきについて市長にお伺いいたします。
市長
各種相談事業の取り組みにおいて、議員御指摘の直接の面談が難しい層を、悩みを抱える青少年を初め、誰にも相談できずにさまざまな問題を抱えている方などが該当するものと捉えてお答えいたします。
現在、各種の相談事業は面談または電話による取り組みを進めているところですが、直接の面談が難しい方への対応として、コミュニケーションツールとして議員御紹介のとおりLINEを活用した取り組みを進めている自治体もあることから、このような先進事例などを参考として、その運用や費用、課題も含めて研究していきたいと考えております。
吉田
前向きな御答弁として受けとめさせていただきます。
その際、LINEとは1つの会社がつくっているサービスですが、それぞれの会社でいろいろなサービスが用意されています。それを選ぶときの基準はどのように考えているでしょうか。
市長
基準の前に検討に当たっての課題ですが、まず対象者をどのような方にするかということもありますし、業務に適した機能を持つどのようなSNSがあるのか、また初期費用とランニングコストの問題、どの相談メニューに絞るのか絞らないのか、相談に応じる専門相談員の配置などもありますので、こうした検討課題について研究していきたいと考えているところであります。
吉田
ぜひ研究を進めていただきたいと思います。
その際、やはり業者が用意するSNSなどはどうしても一度業者を通すことになるので、個人的な秘密の相談がそこに記録として残るわけです。業者はそれを適切に管理していることは恐らく疑いない事実だと思いますが、今情報化の中でセキュリティーの問題もあります。業者を通さず、独自に市でそのような仕組みをつくるという考えについてはいかがでしょうか。
市長
後段の質問にもかかわってくるかと思いますが、いわゆるシステムエンジニア、システムアナリストといった専門の職員は配置していませんので、市単独でそういった取り組みを進めることは現段階ではなかなか難しいのではないかと考えております。
吉田
まずはあるものから検討していただくということかと思います。
では、次に移ります。地域振興への活用についてお伺いいたします。
今どきの旅行者の間では、旅をさらに安心・安全、快適なものにするためだけでなく、より多くの楽しみに出会うきっかけを得るためにもモバイル端末の利用が広がっております。例えば、写真共有アプリ、インスタグラムを利用し、旅先での一こまを多数の利用者に見てもらおうという方がふえています。自治体によっては地域のイベントで撮影された写真を投稿した方へプレゼントを贈るような企画が行われたりしています。県内では、平成29年12月1日から始まったおおがわら桜イルミネーションでインスタグラムを利用したフォトキャンペーンが行われています。また、ゲームアプリ、非常に話題になったポケモンGOを利用した取り組みとしては、宮城県が石巻市で実施したイベントにおいて、約10万人の利用者が集まり20億円ほどの経済効果があったと試算されています。石巻市の人口はおよそ14万5,000人ですから、相当な集客効果があったと評価できるかと思います。
旅行者ばかりでなく住民にとっても、自治体がモバイル端末をうまく活用することで大きなメリットが生まれます。例えばカレンダーアプリの運営会社と連携して市内のイベント情報の登録者の携帯端末への配信なども実施されています。アプリはホームページと異なり情報の更新が簡単であるという特徴もあります。こうした既存のサービスの利用は、新たなものをつくるよりも費用、時間の両面で負担がより小さいというメリットがあります。
小項目2 既存のSNSやインターネットサービス等を利用し、地域のイベント情報や魅力の発信と、国内外からの誘客を図るべきについて市長にお伺いいたします。
市長
現在、本市では広報紙や市ホームページ、コミュニティFMのほか、報道機関等への積極的な情報提供により市政情報の発信に努めているところです。
また、議員御指摘のとおり、国内外からの誘客や交流人口の拡大につなげるには、ホームページのほか飛躍的に発展、普及しているソーシャルネットワーキングサービス、いわゆるSNSを活用して広く情報発信を行い、本市に関心を持っていただくことが重要であると認識しております。
このことから本市では、名取市観光物産協会と連携し、協会ホームページ上でフェイスブックを立ち上げ、きめ細かな観光や特産品情報を発信するとともに、市ホームページにおいても多言語化を図り、広く情報発信に取り組んでいるところです。
SNSの活用は、誘客促進のほか、さまざまな世代、特に若い方々に名取市をもっと知ってもらうためにも有効なPR媒体であると捉えています。今後は、広報なとり、ホームページを主とした充実を図りながら、SNSの活用について他自治体での活用事例も参考にしながら検討を進めていきたいと考えております。
吉田
本市のホームページは非常に充実していると私も感心しております。そのホームページと今申し上げたSNSなどのインターネットサービスは違うのです。ホームページはあくまでも市の、こちら側の情報を発信するツールですが、SNSなどは逆に利用者側が主体となって自分たちで情報を選んだりできる、より利便性の高いツールです。ですから、ホームページはもちろんですが、SNSの活用はやはりこれからの市の発展のためには欠かすことができない、できるだけ早く進めていただきたいものであると思っております。
他の自治体の先行事例などを参考にと御答弁にありましたが、市で検討するに当たり、このような新しいツールはどちらかというと若い世代の職員のほうがより多くの情報を持っていたり、いろいろなところにアンテナを立てていると思うので、そうしたより若い世代の職員の意見を十分取り入れられる環境をつくっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
市長
ただいま御提案いただきました体制づくりというところまで発展するかどうかはありますが、いずれ若い方々を含めてSNS等の知識を豊富に持っている方の御意見を聞く機会を設けるなど、今後検討していきたいと考えます。
吉田
新しい技術や情報についてはやはり若い方の間で流行がありますので、非常に大事なことだと思います。もちろんだからといって上の年代の方の話を全く聞くなということではありません。どの世代からもしっかり検討できる体制を庁内につくってほしいと思います。
次に、業務の効率化への活用についてお伺いします。
市役所の業務を効率化し、市民サービスの向上につなげるためにも、モバイル端末のアプリケーションの導入は有効であろうと思います。既にアプリの導入は一部の自治体で始まっています。多くの例がある中で特に私が興味を引かれたのは、千葉県千葉市が導入したパトレポアプリ、ちばレポというものです。これは、千葉市内で発生している地域の課題を市民と協働で解決するため千葉市が独自に開発したアプリです。市民から携帯端末を通して市役所へ送られるまちのふぐあいを画面にあらわれる地図上でシェア、共有し、地域の課題を一緒に解決する仕組みです。実際にちばレポをのぞいてみると、例えばごみが散乱している、区画線が薄くなっている、街灯が切れている、公園の砂が減って砂利ばかりになっている、こうしたさまざまな情報が寄せられています。そして、対応中のものと解決済みのものは地図上で色分けして表示されるので非常にわかりやすいわけです。また、市役所でどのような対応をとってきたか一つ一つ時系列順に記録が残っており、誰でも閲覧が可能です。市民は、簡単なコメント、それから画像を送信するだけですので、電話や来庁と違ってたらい回しにされるようなこともありません。職員にとっても、担当部署の職員だったらすぐにわかるので、現地に行かなくてもその場で優先順位をつけることが可能となり、職員の働き方を変えることにも大きな効果があると思われます。このようなアプリを使った自治体の取り組みはそれだけではありません。
小項目3 さまざまな自治体において、道路などの異常を写真と位置情報で通報する「パトレポアプリ」を初め、「健康づくりアプリ」、「母子手帳アプリ」、「見守りアプリ」、「ごみの分別アプリ」、「カレンダーアプリ」など、携帯端末用のアプリケーションを独自に開発したり、既存のアプリケーションを導入する取り組みが進められている。本市でも検討すべきについて市長にお伺いいたします。
市長
現在本市においては、市と市観光物産協会が連携して開発した、観光拠点や地場の特産品などの情報を発信する携帯端末用の名取市観光アプリが公開され、利用に供されているところであります。
携帯端末用アプリについては、パトレポアプリのように市民の皆さんから情報をお寄せいただく機能や、プッシュ通知など市からの情報を利用される方のライフスタイルに合わせた形で配信できる機能などを持ち、ホームページとはまた違った形で市民生活の利便性向上に有効な情報把握・発信のツールであるものと認識しております。
御指摘の各種携帯端末用アプリについては、市のさまざまな業務に関連し、その情報の授受のあり方についても多岐にわたりますことから、その有効性や整備・運用コストなどを念頭に置きつつ、全庁的な合意形成を図りながら研究を継続していきたいと考えております。
吉田
観光アプリものぞいてみたことがあります。これはどちらかというとホームページや広報に近いものかと思います。市長の御答弁にあったプッシュ通知はやはり非常に有効だと思うのです。例えばこのようなイベントに行きたいと自分で登録しておけば、時期が来ると自動的にお知らせが送られてきます。このような新しい仕組みはぜひとも早く導入してほしいと思います。
その際、開発費も含めて今おっしゃったランニングコストについての検討だけではなく、アプリを導入することによって職員の働き方がどのぐらい効率化されるのかといった検討は行わないのでしょうか。
市長
アプリの導入を検討する際、視点の一つとしては市民にとってということで、市民の皆さんが利用するに当たって利用しやすい使いやすさがあるのか、負託に応える十分な機能があるのかという観点があると思います。また、市にとって、職員にとってということで言えば、今おっしゃった業務の効率化や、逆に業務量が対応し得るものなのかといった視点も必要になってくると思います。そして、そもそも行政が取り組むべき課題かどうかといった点、また市のメリットも含めてさまざまな角度から検討していかなければならないと思います。いずれ市民生活の利便性が向上するといった視点から、条件が整えばアプリについて具体的に検討していければと思っております。
吉田
市民生活の利便性向上はもちろん一番大事な観点だと思います。ただ、パトレポアプリなどのアプリを導入することによって、職員が毎日現地に行ったり来たりしている現場の写真が送られてくることで一目でわかり、例えば土木課が行ったら実際は農林水産課だったなど別の部署の担当だったというケースは多くあると思うのですが、車で移動する時間を職員1人当たり1時間削減できたとすると、週5日間だったら1人当たり5時間削減でき、その時間を別な業務に回せると思うのです。そのようなことも検討の中に入れていただきたいと思います。
そこで、業務量に対応できるかどうかというお話も御答弁にありましたので、この大項目の最後の質問に移りたいと思います。
市長の御答弁からは、いずれ庁内で検討が進んだ結果、アプリ導入、そして開発までいければなおのこといいと思いますが、そのような流れになっていくのではないかと感じました。ただ、私が危惧しているのはその後のことです。各担当課でそれぞれアプリができたと、この縦割りがアプリの世界の中でも続いてしまえば、同じような機能が重複したり、それぞれ違う業者に委託すれば余計にお金がかかります。これからそういうものを一本化して、名取市には名取市のアプリと、ポケットの中に市役所がある、このようなほかの自治体で取り組んだことがないような新しい取り組みをぜひ進めていただきたいというのが私の願いなのです。既に北海道札幌市では7つのアプリを取り入れ、今8つ目の導入に向けて検討しているそうです。大きい自治体ですからそういったことができるのかと思いますが、本市はまだ1つも導入していません。観光物産協会に1つありますが、市としてこれから導入するとなったときに、やはり大きな設計図を描いて、パトレポの機能あるいは母子手帳的な機能もある、あるいは町内会のお知らせもごみの分別の日も知らせられる、いろいろな機能を備えた、本当に市役所を携帯端末の中に入れたようなものを検討するなら、導入を始める前の今だったらできるのです。通常出回っているアプリは最初から完成形で出てくるものは余りありません。スマートフォンなどで皆さんほとんど御利用かと思うのですが、出てきてふぐあいがあって更新されて、それを繰り返す中で順々に機能をふやしていくことができるのも特徴の一つだと思うのです。そういう意味では、本当に小さなところから始めたとしても、いずれは全体的にこのような大きな仕組みにしていきたいという設計図をあらかじめ描いていただきたい。
ただ、そこで問題となるのはやはり業務量だと思います。恐らくコンピューター、情報システムに関しては市政情報課で取り組むことになろうかと思いますし、もちろんそこに司令塔を一本化できることが理想かと思います。
そこで、小項目4 市政情報課を情報政策課などに改称し、システムエンジニアの増強など体制を強化するとともに、利便性の高いアプリケーションの開発、オープンデータの適切な運用、将来的な庁内ネットワーク刷新の検討を進め、ICTの利点を積極的に活用すべきについて市長にお伺いいたします。
市長
課名の見直し及び職員体制の強化について、現在、市にはシステムエンジニアを本務とする職員はおりませんが、市の行政事務職員には専門的な知識や発想の転換を行う能力が強く求められることから、業務の内容に応じてそのあり方を研究し、体制づくりに努めているところであります。
議員御指摘の利便性の高いアプリケーションの開発については、前段申し上げましたとおり、システムエンジニアがいないことから職員直営でのアプリケーション開発は困難であります。オープンデータの適切な運用については、現在、ホームページ等でさまざまな情報の発信はいたしておりますが、オープンデータとしての情報提供の形には至っておりません。
今後、国及び県の取り組みなどを踏まえつつ、個人及び法人の権利利益などが害されることのないよう意を用いながら、研究を継続していきたいと考えております。
また、庁内ネットワークの刷新については、現在の庁内ネットワークは通信障害の発生や職員の増加による通信速度の低下などの懸念はなく、セキュリティーも確保されていることから、現時点では刷新する考えは持っておりません。今後ともICT技術の進歩には注視し、その利点の活用には意を用いていきたいと考えております。
吉田
もちろん市の直営での開発は到底無理だと思います。外部に発注してつくってもらうことになろうかと思いますが、やはり司令塔を一つにまとめると。例えば土木課でもこども支援課でもつくるといったばらばらなことではなく、一本化の考え方については市長はどのようにお考えでしょうか。
市長
アプリケーションの導入に当たっては、やはり全庁的にまず意識を共有し、目的意識をしっかり持って取り組むことが大事だと思います。その中で、先ほど申し上げたようなさまざまな事項を全庁で検討しながら進めていくことが必要だろうと思っております。その意味では、一本化とは組織なのかどうかということはまた別になると思いますが、市民生活、そして庁舎内での業務の効率化や業務量の増大に対応し得る内容であるかということも含めて、五月雨式に導入していくやり方ではなくて、ある程度の方向性を持って取り組むという意味では議員と同じ考えであると思っております。
吉田
五月雨式という言葉の意味が捉え切れないのですが、順々に新しく更新していくというのは、新しいものがどんどんふえていくのですから、市民にとって逆にうれしいことだと思うのです。最初から立派なものを一つつくろう、100%完成形を求めようという気持ちももちろんわかりますが、できるところからやっていく。そして最終的に利便性の高いものを目指していく。ICTの時代は日々技術が進歩していますので、そのような方向性も必要かと思います。実際システムエンジニアリングの技能を持った方もいると思いますが、例えば申し上げたオープンデータはこれから総務省も推進していくようです。第五次名取市行財政改革大綱にあった他自治体との共同クラウドはとまってしまっているようですが、ICT化の時代の中で非常に有効だと思いますので、そうしたものを推進するような体制はぜひ検討していただきたいと考えます。
では、大項目2に移ります。市民協働の進展についてです。
個人的なことですが、私が加入している町内会は会員世帯数こそ300以上あるものの役員のなり手がなかなかあらわれず、私は平成29年度、副会長を仰せつかりました。そして、先月には会計を担当していた方が転居され、引き継ぐ方がまたまた見つからなかったために会計も兼務することになりました。町内会の役員になったことでいろいろと勉強になることはあります。ただ、議員は町内会の役員になるべきではないという声もありますので、早目に次の方に引き継いでほしいと考えております。
個人的なことはいいのですが、市内には多くの町内会や自治会があり、その取り組みの現状もさまざまであると思います。現在はアパートなどに賃貸で暮らす方が増加し、定住するとしてもオートロックつきのマンションがふえています。また、持ち家があっても町内会加入に積極的でない方もいます。もちろん町内会は任意団体ですから加入は個人の自由ですが、町内会が機能していることで地域の安心や安全が守られていることも事実であり、町内会が存続できなくなれば行政にとってもいろいろとぐあいの悪いことが出てくると考えられます。
まず、小項目1 名取市第五次長期総合計画では、平成27年度の「町内会・自治会への加入率」の目標が85%と設定されている。目標達成の成否と、現状に対する見解を市長にお伺いいたします。
市長
町内会、自治会への加入率については、震災以降、特に被災沿岸部において組織の再構築がなされている途上であることから、正確な数字は把握できない状況にありますので御理解いただきたいと思います。
以前にも一般質問において御答弁させていただいておりますとおり、町内会や自治会などの自治組織は住民同士の自由な意思によって結成されている任意の団体です。そのため、組織については住民の皆さんが十分話し合った上で運営方法や活動内容などを決めていくものであり、加入についても住民主体で促進を図るべきであると考えます。
一方、市が自主的、主体的なコミュニティー活動を側面から支援することが自治会活動を盛り上げ、町内会、自治会への加入促進に結果的につながるものとも捉えておりますので、今後も多岐にわたる活動への支援に努めていきたいと考えております。
吉田
もちろん加入は個人の自由です。ただ、長期総合計画に目標の数字が入っているということは、市としても目標は持っているということです。平成27年度で85%という目標を定めたのは行政です。ですから、震災の影響は大きくあるので把握できないということは確かに理解はできますが、それが目標であることは間違いないと思います。例えば、被災後新たにまちづくりが進んでいる閖上を除いたほかの地域、現在、直接新たな復興がないような地域について町内会のあり方をどのように捉えているか。加入率だけではなく、例えば年代別の加入状況や、加入はしているが実際の活動はどうなのか、80%加入しているがみんな活動しているのか、そのあたりの把握についてお伺いします。
男女共同・市民参画推進室長
第五次長期総合計画の策定時点で定めた当時の現状80%、それから平成27年度の85%の目標についての考え方ですが、当時、町内会があると市で把握している行政区の世帯数と町内会ごとの加入世帯数の情報から、おおむね80%の世帯が加入していると捉えていました。85%の目標については、長期総合計画にあるように、また議員からお話のあったように、地域の安心・安全の確保あるいはコミュニティーの醸成といった面もありますので、できるだけ加入してもらうことを目標として5%のプラスという設定をしているところです。ただ、現在の年代別の状況や活動している方の割合等については、先ほど市長も御答弁申し上げましたとおり運営は町内会、自治会の自主的なものと捉えていますので、そういった活動の詳細までは市として把握しておりません。
吉田
私も町内会に参加しておりまして、確実に若い方の参加は減っていると実感しています。市長も同じ名取市民ですので町内会の現状をよく感じているところはあると思うのです。恐らくどこの町内会も似たような状況ではないでしょうか。活動は一部の役員がしている、そうでないところも中にはあると思いますが、そして重要な役目のなり手はなかなか見つからないといった状況かと思います。一体いつまでそのような町内会のあり方がもつのか、非常に厳しい状況ではないかと私は捉えます。もっと活性化していくためにはまた違う観点で取り組まなくてはいけないのではないか。
そこで、行政区のお話も出てきましたので、行政区長制度に係る質問に移らせていただきます。
本市には行政区という単位があります。これは町内会の範囲と一致していないということでこれまでもさまざまな指摘がされてきましたが、行政区長は非常勤嘱託職員としての身分を持ち、条例に定められた額の報酬を受け取っています。一方で、町内会は行政から独立した団体ですから、役員へ市から報酬が払われることはもちろんありません。ただ、それぞれが今申し上げたように高齢化している状況にあり、区長の担い手もなかなか見つからない地域もあると伺っています。したがって、両者のあり方、そして関係を根本から見直さなければこの先の高齢化に対応していけないのではないかと思います。行政区長の制度については第四次名取市行財政改革大綱で見直しが図られましたが、震災の影響によって見送られました。私は平成28年12月定例会で区長の業務内容と報酬の見直しの検討を求め市長から御答弁をいただきましたので、今回はそれを受けての再度の質問とさせていただきます。
小項目2 区長制度の見直しは、震災復興業務が落ちついた時点において再度検討するとのことであった。新しい制度に移行するまでのスケジュールを示すべきについて市長にお伺いいたします。
市長
震災復興については、復興公営住宅は一部完成しているものの、いまだ整備途上であります。市内には仮設住宅もまだありまして、必要な手当てをすべく、仮設住宅にも行政区と同様に区長を置いています。このような意味において震災復興業務が落ちついたとはまだ捉えておりません。
震災前は、モデル地区を設けるなどして広報配布のポスティング化や一部業務の町内会への委託など試行の結果を見ながら、その後の全体のスケジュールを考えることとしておりました。震災復興業務が落ちついた時点において、区長業務の負担を軽減させるべく業務内容を再度見直し、それに見合った報酬を検討していきます。また、過去に区長制度そのものの廃止を含めた議論があったことは承知していますが、区長は地域と行政のパイプ役として重要な役割を果たしており、現状では区長制度を廃止する考えは持っておりません。
なお、区長業務の細かな内部基準については、震災復興の状況にかかわらず、必要に応じてその都度見直しをかけておりますので申し添えます。
吉田
スケジュールに関して震災復興業務が落ちついた時点と。何をもって落ちついた時点と捉えればよろしいのでしょうか。
市長
1つには平成30年12月の住まいの再建、また震災復興計画が平成31年度までであること、そして平成32年度には復興庁の解散もありますので、基本的には本市の状況の中でそれらも踏まえて判断することになると考えます。
吉田
今3つ出ましたので、どれをもって業務が落ちついた時点と言えるのか曖昧だと思いますが、そこからさらに検討を始めていくと。検討を進めていくのにはまた何年も時間がかかります。その辺で震災復興業務が落ちつくと今の時点で大体認識しているのでしたら、もう今から区長制度の見直しの検討を始められるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
市長
これまでも答弁していますとおり震災復興業務がある程度落ちついてからということです。現状まだ震災復興業務に多大な人と時間を労しているわけで、そこが落ちついてからということで御答弁申し上げてきたとおりです。区切りとしてどのようなことが考えられるかというお尋ねでしたので、住まいの再建や震災復興計画の期間といったことで申し上げたまでであります。
吉田
先ほど平成23年度の見直し案のお話がありました。一部見直しということで報酬の額の見直しが大きいかと思いますが、ポスティング業務の委託などいろいろとあると思います。ただ、その当時の状況から高齢化はより進んでいると思うのです。そして、報酬があのときの提案ではたしか月額1人当たり一律5,000円にすると。その金額でほかにもたくさんある区長の業務を全部の行政区できちんと確保できるとお考えなのでしょうか。
総務課長
議員御指摘のとおり、平成23年度、震災前については、広報配布はポスティングへ移行し、それに伴って区長報酬についても見直しを行う、それ以外の相談業務や募金業務、その他の充て職としての業務は従来どおりという考えでした。また、これは想定ですが、区長が推薦されない行政区については無理に区長は置かないというケースも検討していました。
吉田
そのことも書いてありました、区長のなり手がいないところはなしもあり得ると。だったら市内全体をなしとすることも不可能ではないと捉えるのです。例えば募金にしてもいろいろと言われていますが、1軒1軒回る区長は本当に大変なのです。今、平日の昼間いない家庭もあって、1軒に3回も往復してやっと募金してもらえたというお話もあります。やはりこうした中で今後高齢化していく区長が業務の中で倒れてしまうなど、実際にポスティングにおいてそういう事例も聞いていますが、このようなことを考えると、もう少し市内全体の区長制度のあり方と先ほどから申し上げている町内会について同時に整理していくことが必要ではないでしょうか。
そこで、1つ例を挙げますと、東松島市に会派で視察に行ってきたのですが、震災復興を待たずに、平成29年4月に行政区制度を完全に廃止して地区自治会制度に移行しました。行政区長を全て廃止し、それ以外の市の嘱託の地域担当も皆なくして町内会とし、そこに交付金を交付して、その中で総会を開いて使い道を決めてもらう。ですから、役員の報酬に幾ら充てようと、あるいは道路整備でどこかに委託しようと、自分たちでやってお金がかからなかった分はお祭りやイベントの開催など別なことに使う。そのようなことができる非常に裁量の広い仕組みになっていると伺ってきました。同じ沿岸部にある東松島市ができたということですが、本市では区長制度と町内会のあり方を再検討するというような連携させた考え方は持っていないのかどうかお伺いいたします。
市長
区長制度を廃止して、自治会、町内会に地域の運営というかその代替的な役割を担っていただく、交付金を交付するということも一つの考え方であろうかと思いますが、本市のこれまでの整理としては、区長制度については廃止は考えずに、業務の内容を見直し、報酬についてそれに見合ったものに変えていくことが一つ整理されております。また、町内会については先ほど申し上げたとおり、住民同士の自由な意思によって結成されている任意団体ですので、市としてはその運営等について側面から支援をしていきたいという考え方です。ただ、高齢化等によって地域がなかなか成り立たなくなってきているのではないか、行政と地域とをつなぐもの、そしてまた地域そのものの元気をしっかりとつないでいかなければいけないという思いは同じです。そのやり方、手法について、区長制度の見直しも含めて検討していきたいと考えております。
吉田
区長制度の見直しの中で、廃止はないと言い切ってしまうのは私は少し違和感がありまして、それも含めて次の検討に入るべき段階に来ているのではないかと思うのです。地域と行政との連携のあり方については後の質問で伺いたいと思いますが、町内会については側面的な支援という御答弁でした。確かに花を植えたときに助成金をもらうなど、いろいろとしていることはあります。ただ、自治会、町内会は育てていくことによって、今区長が市の嘱託職員として担っているようなことも町内会の自主的な活動の中でできるようになっていく、これこそが市民協働のまちづくりの根本的な考え方だと思うのです。できるだけ行政から市民に手渡していく。そして、自分のまちは自分たちでつくってください。行政は最低限の交付金の交付あるいは市役所との連絡調整などに限っていく、そのような捉え方が今主流になりつつあるのではないか。特に高齢化が進み過疎が進んでいる地域ではそういった地区自治会の話をたくさん聞きます。東松島市もその一つだと思います。本市はまだそこまで行っていないとおっしゃるかもしれませんが、地域によっては差があり、高齢化の進んでいるところや人口が減少している地域もあります。やはり市内全体で地区自治会をもっと育てていかなければいけないと私は捉えております。
小項目3 地域づくりのための人材を発掘・育成するとともに、区長制度の見直しによって地域と行政の連携が崩れぬよう、人材を活用できる新しい自治組織のあり方を早期に示すべきについて市長にお伺いいたします。
市長
先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、現状では区長制度を廃止する考えは持っておりませんので、区長制度を原因とする地域と行政の連携が崩れるような事態は特に想定していないところであります。
区長制度のいかんにかかわらず、議員御指摘のとおり市民協働は非常に重要な考え方であると認識しています。第五次長期総合計画においてお示ししていますとおり、公民館主催の地域力向上講座や市民活動団体の協力による地域リーダー養成講座の取り組みなど、地域づくりのための新たな人材発掘やコミュニティーリーダーの育成に努めているところであります。これらの取り組みによって愛島もりあげ隊、キラキラパルク増田西、高舘ハッスル隊など地域主体の団体が数多く立ち上がっており、地域の魅力を掘り起こすさまざまな活動を行っております。
また、町内会、自治会などの自治組織は、地域住民により自主的、自立的に組織された任意団体ですので、自治組織のあり方について市がお示しすることは難しいと考えます。
吉田
区長制度を見直すといっても廃止する考えはないということですが、先ほどの課長の御答弁の中で区長のなり手がいない場合は区長を置かないこともあり得ると、平成23年度の見直し案が今回そのとおり出てくるかどうかわかりませんが、もしそのように区長をやる方がいない地域が出たときに、それでも行政と地域との連携は崩れていないと言ってよろしいのでしょうか。
市長
前の御質問でもお答えしたとおり、行政と地域のパイプ役として区長が果たす役割は非常に大きいものがあると思っています。できるものならば、全地区に区長がいてそういった橋渡しをしていただく、行政の情報も伝えていただき、また地域からの声も届けていただくといった機能があったほうがいいとは考えております。
吉田
ですから、あったほうがいいはずの区長が置かれない地域が出てきてしまうおそれがあるわけです。今もそういう行政区が中にはあるとどこかで聞いたことがあるのですが、そこの区長のかわりに隣の区長がやるとなったら、その方は仕事が2倍にふえるわけです。しかも報酬が5,000円に減ると。これは一律5,000円ですよね。世帯割は完全になくして1人当たり5,000円と。その金額の中で地域と行政との橋渡しや募金集めの業務などをやっていただける区長をきちんと確保できるとはっきり今断言できるのかどうか、もう一度確認させてください。
市長
先ほどは平成23年度当時の整理のあり方について御説明を申し上げたわけでありまして、その後、震災があり、区長会に対する説明や地域の理解、そうしたことはこれからの手続になりますし、それらも含めて区長制度のあり方について見直しを進めていくということですので御理解をいただきたいと思います。
吉田
平成23年当時とは恐らく違う案が出てくるかと思います。その際に、今申し上げたとおり町内会のような自治組織との関係、区長のあり方との関係はやはり視野に入れていかなければなりません。完全に行政と切り離すのではなく、地域主体の団体に行政としては区長がそれまで担ってきた仕事をシフトしていく。業務もシフトしお金の部分もシフトするといういわゆる分権的な考え方です、地方自治体レベルで見れば。それを町内会レベルで進めることが高齢化の世の中において必要になるのではないか。先ほどの東松島市以外の例を申しますと、11月30日の読売新聞に載っていておもしろいなと思ったのですが、山形県川西町のある地区で町内会、自治会をNPO法人にして全世帯が加入したことで、今までそういうことに興味のなかった若い世代の人たちも参加するようになったそうです。そして、大項目1にも関連しますが、高齢者の買い物を支援するアプリをつくった。アプリで日にちを指定して注文すればその日に届けてくれると。そうしたものまで自治会の中で進めているという事例が山形県ではもう出てきているわけです。町内会はもう好きにやってくださいとまでは言っていないと思いますが、やはり行政としてもう少しいろいろなあり方を示して、今後の自分たちの地域を自分たちでつくっていくという気持ちにもっと導いていくべきではないかと思うのですが、それは考え過ぎでしょうか、お伺いいたします。
市長
高齢化する地域の運営をどうしていくかということは非常に大きな課題であり、市としても取り組んでいかなければならない課題であると捉えています。ただ、町内会については何度も申し上げるとおり地域の自主的、自立的な組織ですので、どこまで立ち入ることができるのか、逆に言えばどのような形で連携を図っていけばいいのかということについてはもちろん研究していきたいと思っております。ただ、町内会の課題としても、先ほど議員みずからもおっしゃったとおり、町内会のつながり自体が希薄化している地域もありますし、逆に言えば町内会と区長が非常に密接に連携している地域もあります。そうした地域ごとの実情も踏まえて今後のあり方について検討していきたいと考えております。
吉田
地区自治会の制度についてはぜひいろいろな事例を参考にして検討していただきたいと思います。
では、最後の質問に移ります。公民館についてです。公民館は社会教育を奨励するための施設ですが、現状では市役所の支所的な業務も一部で行われています。区長制度、町内会の今後を考えていく上で、社会福祉や防災などの機能もつけ加えていく、公民館のコミュニティーセンター化も同時に検討していく段階ではないかとも捉えられると思います。ただ、今回は公民館の中で事務長に絞って質問したいと思います。
教育委員会がさきに開催した公民館の将来像を考える市民ワークショップにおいて、参加した市民からたくさんの意見が寄せられたと伺いました。現在の公民館の運営を肯定的に評価する声が大部分であったと同時に、正規職員としての事務長はぜひ残すべきだという意見が強かったと伺っております。また、ワークショップに参加しなかった市民からも、事務長までも正職員でなくなってしまうのではないかという心配の声も聞こえてくるときがあります。
行政をよく知る職員が地域に1名置かれていることで多くの市民に安心をもたらしていることは事実であると思われます。特に災害発生などの非常時に市役所から発せられるさまざまな情報を的確に読み取ったり、ほかの施設との連携を円滑に進めることができる能力は市役所での職務経験を持つ職員ならではのものだと思います。もし事務長が行政職員の経験のない民間人であれば、非常時に市役所への対応の窓口として十分に機能しないおそれもあるかと考えます。区長制度を見直すとなれば公民館の事務長の存在はますます重要なものになっていくと考えられます。新しい自治組織、今後の町内会の組織運営、また町内会のいろいろな備品の管理や行事の開催など、行政のプロによる助言、支援は今後も欠かせません。もし事務長までも正職員でなくするとなれば、それは現在の課題ではなく、自治組織がしっかりと自立できて活動の実績を積んだそのさらに後のことになると考えます。
ただ、一方で、地域に1名配置される職員を必ず管理職とするかどうかは検討に値すると思います。私は、むしろ若手の職員にこそ、住民とともに地域づくりに取り組む経験をしてもらいたいと考えます。本庁舎から外へ出て地域に飛び込んでいくことは不安を覚えるかもしれませんが、担当する地域に密着し、サークルなどの育成や行事の開催などを住民とともに行うことで、より深く地域の課題を知ることができるようになると思います。そして、公民館で得た経験、つながり、こうしたものは本庁に戻ってからも職務に当たる上の大事な財産になると考えます。
そこで、小項目4 現在の公民館事務長のかわりに若手職員を地域担当として公民館に配置し、中長期的スパンで地域と向き合いながら、住民とともに地域課題を解決する経験の機会を持たせるべきについて市長にお伺いいたします。
市長
地域課題を解決するためには地域のことをよく知る必要がありますので、地域住民が集まる学びの場である公民館は若手職員の学びの場にもなり得る可能性があるものと考えられます。
しかし、そのためには地域住民にとっても若手職員にとっても、ともに学び協働することのプロセスや成果が共有できるシステムが必要です。
教育委員会では、公民館の将来像について市民ワークショップなどを開催し、その将来像について検討していると聞いていますので、その内容や結果について確認し、相談の上で研究していきたいと考えております。
吉田
若手職員を配置するという私の案はどうなるかわかりませんが、現状を維持するにしろ、可能な範囲で事務長をその地域に在住している方を充てるという考えについてはいかがでしょうか。
市長
地域をよく知る方を置いたらいいのではないかという意図だと思いますが、人事上そうしたことが必ずできるかどうかお約束いたしかねると考えます。
吉田
今回、大項目1と2でいろいろな提案をさせていただきました。中には今後検討していただけるという部分もありました。本市は現在人口は確かに増加していますが、高齢化が進んでいる地域、市長も認識されていますように、今後10年たったら非常に深刻化してくると思います。できるだけ早くそうしたところに手を打てるように取り組みを始めていただきたいとお願いさせていただきまして、私の一般質問を終わります。
本会議
(議案第119号 平成29年度名取市一般会計補正予算)
吉田
16、17ページの21款1項7目教育債の中で、公民館建設債で200万円計上されていますが、これはどこの公民館になるのですか。
財政課長
こちらの200万円は館腰公民館の耐震改修工事に係るもので、平成29年度当初予算のときには400万円で起債しておりましたが、今回600万円の起債ということで200万円の増となっています。
吉田
22、23ページ、2款1項26目諸費の8節報償費ですが、農業委員会委員候補者選考委員会委員謝礼ということで、先ほど審査した新しい条例の制定を受けてと捉えていますが、この農業委員会の委員を選ぶための選考の委員会ということかと思うのですが、この選考委員会の委員はどのように選ぶのでしょうか。
農業委員会事務局長
選考委員会の委員ですが、平成29年12月、名取市農業委員会委員候補者選考委員会の設置要綱を制定して、その中で選考委員を市長が委嘱するという形になります。今考えている選考委員は、農業協同組合の役員、農業共済組合の役員、土地改良区の役員、宮城県亘理農業改良普及センターの所長、農業委員会の委員経験者を1人、合計5人の方にお願いする形で考えております。
吉田
先ほど条例で、現行で18名、3つの選挙区から6名ずつと、そのほかに農業協同組合、農業共済組合、土地改良区から各1名ということで、何かそこに重なってくるように思うのですが、この選考委員会の委員になった方は、今度新しく選挙ではない形での農業委員になるということは考えられないのでしょうか。
農業委員会事務局長
こちらの規定上、兼務ができないという明記はされていないものですが、やはり社会通念上の観点から、選考委員の候補者になって、農業委員にも推薦なり公募することはできないということで、どちらかを取り下げてもらう必要があると考えております。
吉田
46、47ページ、8款7項2目防災集団移転促進事業費の閖上地区防災集団移転促進事業移転先団地集会所の場所や内容について伺います。
復興区画整理課長
まず集会所の場所ですが、閖上の防災集団移転促進事業の移転先団地の中央部にポケットパークがありまして、その南隣の敷地に集会所を建設するものです。建物は、平家建ての建物を予定しているところです。面積は、延べ床面積が約150平方メートルを予定しています。
吉田
完成後の維持管理はどのように進めていくことになっているのでしょうか。
復興区画整理課長
集会所の管理については、当分普通財産として市で管理しまして、処分制限期間満了後、これは24年間になりますが、それが完了した後に地元の自治会等に管理を譲渡したいと考えております。実際の管理については今、コミュニティー組織の立ち上げでいろいろとお話し合いをしていますが、そちらに管理をお願いしていく形で進めていきたいと思っているところです。
吉田
使用基準に沿った形になっているかどうかをいずれかのレベルで判断しなければならないわけです。ほとんどの場合は大丈夫ですということになると思いますが、ちょっとこれはいかがなものかというケースも必ず出てくるかと思います。そのような際の判断をしていくための、もっと細部にわたった捉え方を市がある程度準備をしておかなければ、先ほど申し上げたように、例えばもっと過激な思想の団体が、これは宣伝ではないとか、これは事実なのだとか、いろいろな理由をつけて展示することができるわけです。例えば写真にもそういうものを一部つけ加えて、自分たちはそういう思想ではないと言って宣伝することも、やり方によってはできることになります。非常に線引きが難しい中で、それを最終的に責任を持って行政は、これはちょっとまずいのではないか、これはいいと決めていかなければなりません。そういう責任を負っているわけです。そのあたりについて、市長として、これまでできるだけ市民に広く開放してきたということも維持しつつ、もう少し今までよりも確認のレベルを高くしていくべきではないかと思いますが、お考えを伺いたいと思います。
市長
先ほど担当からも答弁いたさせましたが、使用許可基準の中に政党または政治団体の使用は認めないという文言があります。ただ、今回の件については、大々的に全面的に特定の政党なり政治団体なりを宣伝しているのではなく、原爆の悲惨さを通じて世界の恒久平和を願うという趣旨で開催されたものと捉えており、その中の一部に、ちょっと確認はできていませんが、問題となる部分があったというだけをもって、例えば中止にしたり、以後貸さないという措置までとれるかというと、それは少し違うのではないかと思います。基本的には市民の方に広く利用していただきたいと考えております。
また、その確認についても、検閲をするというような考え方ではなく、庁舎内で行われる市民の方の活動について、こちらでも拝見させていただきながら、基準に沿った使われ方がされているかどうかという確認をできる限りしていきたいということです。
吉田
何も私は検閲を推進しているわけではありません。思想・信条の自由は誰にでも認められています。先ほどから申し上げています。ただ、それは例えば自分たちの活動資金などで行っていくことであって、市民全体の持ち物を使ってそのようなことが行われるということについて、果たしてどうなのかと申し上げているわけです。
この使用許可基準は平成19年に作成されたもので、10年間そのまま継続しているものです。一般の市民の表現活動をこれからも推進していく、どんどん進めていただく、それと同時に公平性を確保していくためには、今の使用基準では少しわかりづらいと思います。行政側の裁量に任される部分が非常に大きいと思うのです。例えば、政党はわかります、政治団体にも制限をかけるというのもわかりますが、その政治団体というのはどこまでを言うのかと。選挙管理委員会に申請されているものだけが政治団体なのか、あるいはそれよりもっと広い意味での政治団体があるのか、そういう部分についても曖昧なままです。そればかりではありませんが、こういった面も含めて、やはり今後改定を検討すべきかと思います。
小項目3 使用許可基準第5条(使用許可の制限)に政治や宗教の宣伝活動を追加し、違反した個人や団体に対して以後の使用を認めないなど罰則を設けるべきについて、市長にお伺いいたします。
市長
現行の使用の制限に関する規定の仕方については、本市においては一般的な規定の仕方であると考えておりますが、他の自治体では宗教活動等を制限している団体もありますことから、今後、実態を見きわめながら十分研究していきたいと考えております。
また、違反した個人や団体に対してのペナルティーについては、以後使用を認めないというペナルティーを検討する以前に、使用する方々へ、ポケットギャラリーの使用に当たってのルールを十分に御理解いただいて、そういった状況にならないように周知徹底を図っていきたいと考えております。
吉田
他市の議員とこの件について話したときに、その市ではこれはあり得ないことだと言われました。やはり政治にかかわっているからと。もちろんそういう線引きは自治体ごとに決めていくことだろうと思いますが、10年たって今の使用許可基準が見直しの時期に来ていることは市長も認識されているということですので、どうかこれについてはおっしゃったとおり進めていただいて、みんなが納得できる、そしてみんなで安心して使っていけるようにしていただきたいと思います。啓蒙活動にしても、市長からも原爆展というお話がありましたが、やはり原爆の恐ろしさ、悲惨さはしっかり次の世代に引き継いでいかなければならない、そういう気持ちについては全く同じです。そういう純粋な気持ちをそのような場で提示していただいて、その一方で公平性が疑われるようなことにならないように、そういう点について誰が見ても一目瞭然の判断基準を目指して、今後使用基準の改定を進めていただきたいと思います。
これをもって私の一般質問を終わらせていただきます。
本会議
(議案第92号 平成29年度名取市一般会計補正予算)
吉田
9ページの16款2項2目土地建物売払収入1節土地建物売払収入について、具体的な場所をお伺いいたします。
財政課長
今回の土地建物売払収入は名取駅前の市街地再開発に伴う代替地6区画分の売却収入です。
吉田
6区画の具体的な場所と金額の算定方法をできる限り詳しく御説明願います。
財政課長
6区画については、事業区域の東側、増田四丁目の5区画と旧増田公民館駐車場のところの1区画です。面積は、事業区域の東側5区画がトータルで1,263.65平方メートル、旧増田公民館駐車場が264.47平方メートルです。売却価格については、事業区域の東側5区画分で合計7,591万1,000円、旧増田公民館駐車場で1,904万1,840円です。
吉田
11ページ、18款2項7目1節ふるさと寄附基金繰入金について伺います。ふるさと寄附は6項目の寄附金の使い方の中から選択する形で今進められていると思うのですが、今回はどの項目に幾らなのか、繰入金の内訳をお伺いします。
財政課長
今回のふるさと寄附基金繰入金は、平成28年度で使用したふるさと寄附金特産品取扱事業の特産品代と送料、そして、観光物産協会への委託に係る委託費について、平成28年度においては一般財源で立てかえていたこともあり、平成28年度分の確定に伴って基金から繰り入れたもので、議員御質疑の目的に関しては特に想定していません。
吉田
ということは、用途が選択されて寄附されているわけですが、その部分については手をつけていないという解釈でよろしいのでしょうか。
財政課長
今回繰り入れているのは経費というか事務費の分で、強いて6つの項目のどこから充てているかと申しますと、「元気な都市(まち)づくり【市長にお任せ】」の項目から充てていると考えられるかと思います。
吉田
20、21ページの8款1項3目公共物管理費19節負担金補助及び交付金の私道等整備補助金についてお伺いします。当初予算で200万円が計上されたと思いますが、私道に関してはやはり多くの方からいろいろと整備の要望が上がっていると思います。今回追加された中で要望に対して適用されるのは何件分の補助になるのでしょうか。
土木課長
今回の補正ですが、補助金交付要綱の要件の緩和を行い、また、交通安全施設の設置を補助対象に追加したため、当初予算額では不足することから補助金の増額補正を計上しました。その内訳は、現在、申請予定件数は4件で、そのうち、舗装要件の緩和で1件、新たに補助対象になった交通安全施設の照明灯関係が2件、合計3件が今回の改正により追加されました。
吉田
要望している方からするとこのような形で補助がおりることはありがたいのかと思いますが、そもそもこの金額が小さいのではないかと思います。当初予算の200万円プラス今回73万2,000円ですが、金額について今後拡大していく必要性は感じていないのでしょうか。
土木課長
毎年200万円ずつ予算計上していますが、過去5年間で申請なしが2回、それから1件が2回で、それは舗装で約100万円ぐらいでした。今回改正したのは、申請がなかったり、あっても申請額が少ないということで、より多くの方に使っていただきたいということで利便性向上を図ったものです。舗装に関しては、当初予算200万円というのは、1件当たり100万円で、通常年2件分と考えています。ですから、今後改正によりふえると思われますが、その時々に合わせて補正等で対応していきたいと考えております。
吉田
22、23ページです。8款7項3目復興まちづくり事業費で13節委託料と15節工事請負費にある名取駅東口歩道橋整備工事についてお伺いします。資料を見ますと、まず橋脚を全部で4本設置して、その橋脚の上に歩道となる部分を載せるのかと思いますが、橋脚の場所を見ると、一番名取駅舎側とその次の橋脚が現状のアーケード、雨よけの屋根のかかっている部分に重なっていると思うのですが、現在のアーケードは設置したままで、そこに穴をあけるような形で橋脚を設置するのか、詳しい施工方法を説明願います。
増田復興再開発推進室長
歩道橋の工事で一番駅舎側と橋脚についてですが、ここには現在アーケードということで歩廊が設置されていて、橋にぶつかる部分は撤去となります。
吉田
ということは、歩道橋の下側にあるアーケードの部分は撤去するという考え方ですね。名取駅から南側におりてくるほうもバス停に現在アーケードがかかっていますが、それも撤去し、そこに橋脚を打ってその上を通すということで、その撤去費についても含まれていると思います。また、P3の橋脚は視覚障がい者のための点字ブロックにもかかっていると思うのですが、これらも全部含めた上での今回の工事の予算という考え方でよろしいのでしょうか。
増田復興再開発推進室長
平成29年度9月補正で計上している予算は橋脚の設置分となります。まず今年度において橋脚を敷設した後、一時的に舗装の撤去等もあります。そして、平成30年度に視覚障害者用誘導用ブロック等の復旧を行いたいと考えております。
吉田
今回の予算は橋脚のみでそれ以外は新年度でと聞いて少し驚いたのですが、幾らぐらいさらに必要になるのか。図面を見ただけではわかりませんが、橋脚を認めればその上の部分も認めなければならなくなると思いますので、全体の工事費の現在の見込みをお聞きしたいと思います。
増田復興再開発推進室長
全体の歩道橋の整備費は、現在のところ、上部工と下部工を合わせて2億8,000万円と見込んでおります。
吉田
次の48、49ページ、8款7項3目復興まちづくり事業費の22節補償補填及び賠償金のところで、名取駅東口歩道橋整備工事上水道移設補償費とありますが、この内容について伺います。
増田復興再開発推進室長
歩道橋整備の上水道の移転補償の内容について、まず歩道橋の再開発区域の接続部分の基礎部分に当たる部分ですが、この下に100ミリの水道管が埋設してありますので、この切り回しに要する工事に対する補償費ということです。
吉田
先ほどの歳入審査の中で歩道橋整備には復興交付金がついたということで、大変ありがたいことかと思いますが、こちらの今回の補償費の財源と金額についてお伺いします。
増田復興再開発推進室長
財源については全て一般財源です。金額については控えさせていただきたいと思います。
(議案第129号 名取市職員の給与に関する条例及び名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例)
吉田
年に一度の人事院勧告ということで、今回もこうした形で国家公務員の給与改定に準じるという形で御提案いただいているという御説明がありました。この人事院勧告に基づいての改定案ということですが、その改定案をつくっていく過程で、人事院勧告以外の分を何か検討の中に入れることはなかったのかどうか、伺います。
総務課長
人事院勧告以外の独自の内容があるかという御質疑と捉えてお答えしますが、基本的に本市の給与等については国家公務員に準じる、人事院勧告に準拠するというスタンスをとっております。これは上がるときも下がるときも同じです。ということで、今回も人事院勧告に準拠しているということです。
吉田
多くの自治体が同じような改定の仕組みになっていると思うのですが、私は上げることや下げることそのものに賛成反対ではなく、例えば今の本市の状況を見たときに、人口がふえている、税収も市税で上がっているというところもありますので、多分職員の仕事量もふえてきているのではないかと思います。ですから、上げることそのものに反対というのではなく、なぜ常に人事院勧告にだけ準拠していくのか。やはり地方自治という、独自に条例を決められるという、それだけの権限を与えられているわけです。 何が正しいかというのは大変な議論になるので決めることは難しいかと思うのですが、その中で総務省のホームページで拾ってきたのですが、国家公務員、地方公務員の中で都道府県と政令指定都市、特別区、それ以外の一般市と町村がそれぞれ違う手続で決められていくという中で、一つの考え方ですが、人事委員会が置かれていない団体、一般市町村においては、国の取り扱いや都道府県の勧告等を受けて具体的な給与改定方針が決定されるということで、都道府県の人事委員会で出たものを改定の中に盛り込んでいけることも示されているのですが、そのあたりの検討はしてこなかったのでしょうか。
総務課長
今、議員からお話のあったところについては特に検討はしておりません。あくまでも国の人事院勧告に準拠するというスタンスで取り組んでおります。
(議案第135号 平成29年度名取市一般会計補正予算)
吉田
不足が生じたと今お聞きしたのですが、9月の補正の時点では橋脚部分として約1億2,000万円で、その後平成30年度の当初予算で残りの上部工で、合わせて2億8,000万円ほどの合計額になるのではないかというお話だったと記憶しておりますが、そこにさらにこれが上乗せされて合計額は上がると考えてよろしいのでしょうか。
増田復興再開発推進室長
合計額については、議員お見込みのとおり上がるということです。
吉田
そうすると、単純計算して3億円を超えるぐらいになるのかなということですが、今度財源のほうで一般財源からも支出されておりますが、このあたりの考え方はどのように捉えればよろしいのでしょうか。
財政課長
先ほどの一般会計の補正6号でも御答弁しましたが、1億1,900万円については復興交付金基金繰入金と震災復興特別交付税に振りかわっています。今回お願いしている分についても、復興交付金基金繰入金と震災復興特別交付税で手当てをしているということで、一般財源としては震災復興特別交付税が該当するものと捉えているところです。
吉田
歳出全般ですが、先ほど給与等の引き上げについて条例改正になりましたのでそれを受けてということで、それぞれの部署ごとにこうした形になっているかと思うのですが、実際に支給されるタイミングはどのようになっているのでしょうか。
総務課長
後日、年内に支払いを予定しています。
吉田
どこかの月の分と一緒ということで、金融機関等の手数料が余計にかかったりするなどということではないと捉えてよろしいのですか。
総務課長
金融機関への手数料がかかるのかということですが、そこはかかりません。
(議会案第5号 小選挙区制度を廃止し、民意が反映される選挙制度へ見直すことを求める意見書)
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、議会案第5号 小選挙区制度を廃止し、民意が反映される選挙制度へ見直すことを求める意見書について、賛成の立場から討論を行います。
選挙とは何か。総務省のホームページに私たちの生活や社会をよりよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる代表者が必要であり、その代表者を決めるのが選挙なのですと示されております。
私たち市議会議員が、市民の代表者として議席を預からせていただいているのも、選挙というプロセスを経てきた結果によるものです。本市の市議会議員選挙は、本市における大選挙区制で議員を選ぶ仕組みとなっております。選挙人が投票できるのは1名の候補者に限りますが、地域に関係なく誰にでも投票できます。得票数が多い候補者から順に定数までの議員が当選となるため、選挙人の意思が反映されやすい制度であると言えます。なお、選挙人の数がより多くなる政令市や都道府県の議会議員選挙は、地域を複数の選挙区に分け、中選挙区制で行っております。ただし、選挙人の数が少ない選挙区は定数1の小選挙区制となります。
さて、衆議院選挙は、終戦後の昭和22年から中選挙区制で行われ、平成6年の選挙制度改正以来、現在に至るまで、小選挙区比例代表並立制で行われております。小選挙区制は、一つの選挙区から1名を選出する仕組みです。小選挙区制の問題はどこにあるのか。国を名取市に置きかえて考えてみたいと思います。
まず、選挙人の数にできるだけ差が生じないよう市内を21の選挙区に分けます。行政区でも小学校の学区でもない、選挙のためだけの区割りにおいて選挙が行われます。選挙人は、選挙区の候補者にしか投票できません。どんなに魅力的な候補者がいても、ほかの選挙区から立候補している候補者へ投票することはできないのです。裏を返せば立候補者は、選挙区の中でだけ強固な組織を持てば、めったなことで落選することはなくなります。当選後は、各議員の活動は専ら選挙区の代表として行われるようになり、地域への予算の引っ張り合いが起こると予想される。これでは市全体を考えられる議員などは育たないと思われます。
国政の規模になると、問題はさらに深刻です。選挙区当たりの候補者数が多くなり、得票率が低くても2位より1票でも多くとれば当選できます。国政選挙では、ほとんどの候補者が党の代表としても立候補するため、政党ごとの得票率と議席占有率に大きな差が出ます。大政党ほど有利な結果が出やすくなります。
平成29年10月に投票が行われた衆議院選挙を例にとれば、最も得票数の多かった自由民主党は、得票率が約48%であったのに対し、議席占有率が約74%、そして次に得票数の多かった希望の党は、得票数が約21%であるのに対し、議席占有率が約6%でした。選挙区で希望の党は自由民主党の半分近い票を得ていますが、議席数は自由民主党の1割にも満たない。もしこれを政党を選ぶ選挙として捉えるのであれば、総務省ホームページが示す、私たちの意見を反映しているとは言いがたい結果です。
さらに今後、郡部では人口が減少、都市部では人口は増加すると予想されます。衆議院議員選挙が行われるたび、1票の格差を是正するために、どこかの選挙区で区割りが変更されていきます。意見をどの候補者に向ければよいのか、選挙人を惑わせる事例が続くこととなります。
これだけ問題の多い制度であるにもかかわらず、平成28年1月の衆議院選挙制度に関する調査会による答申では、小選挙区比例代表並立制を維持するとし、新たな制度の導入を検討せざるを得ないほど深刻な事態にあるとは考えられないと理由づけられておりました。選挙制度もほかのさまざまな問題と同様、これが最善だ、これが百点満点だという回答はなかなか見つかりづらいものです。それでもその意義や目指すべきところを見失うことなく、問題解決へ向けた議論を続けていくことが重要であると思います。
民主主義の根幹である選挙をより民意が反映される制度に見直していくために、政党や主義主張の違いを乗り越え、地方からもしっかりと声を上げていくべきであろうと考えます。
本意見書に御賛同賜りたくお願い申し上げまして、私の賛成討論といたします。