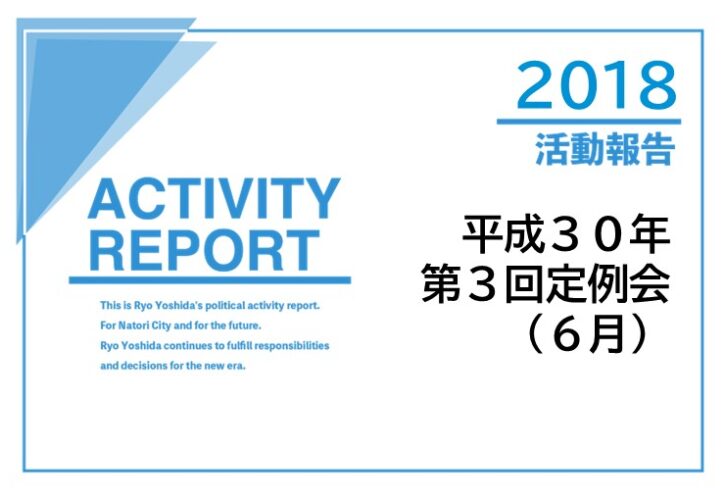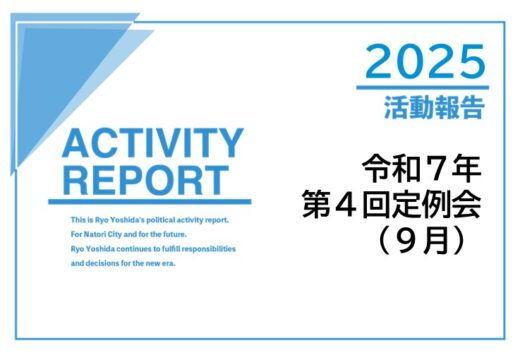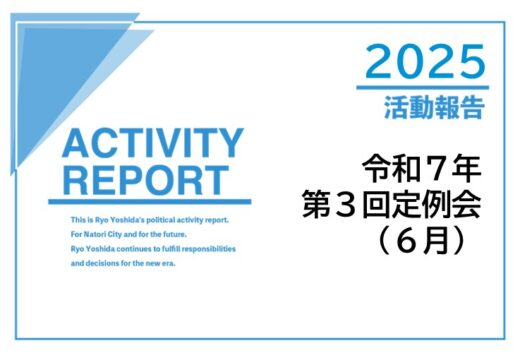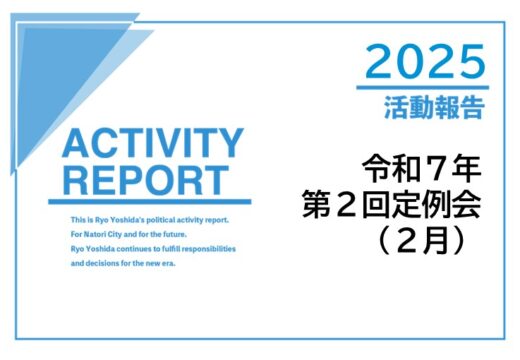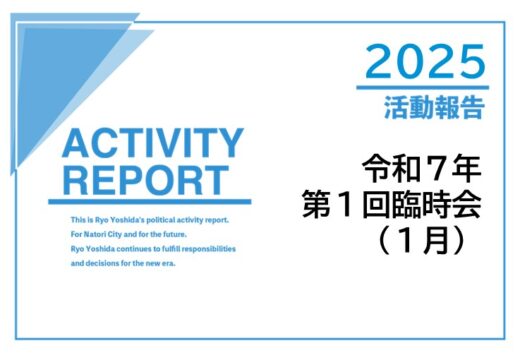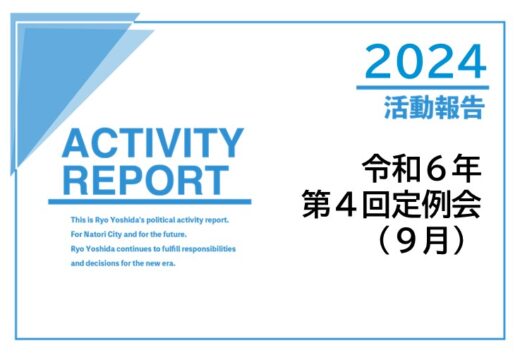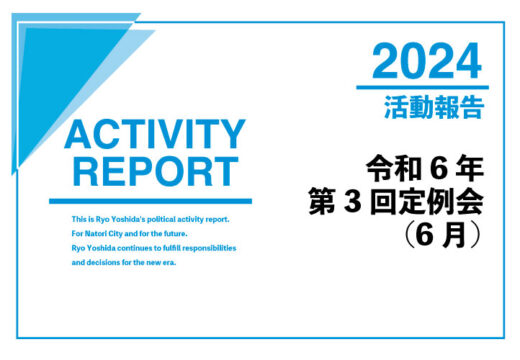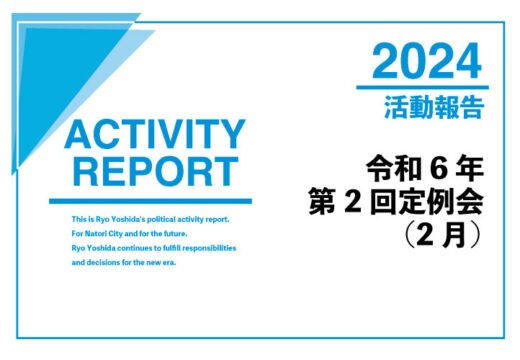本会議
(議案第68号 専決処分の承認)
吉田
6、7ページの増田中学校の改修について、もう少し詳しくお聞きしたいと思うのですが、国の全体の状況でと話されたのですが、国のほうから平成29年度の補正でいかがですかという話が来ておきながら、これが採択されなかったというのは本市としては非常に事業を進める上で、言い方は悪いかもしれませんが、余り適当ではないと捉えられるのですが、なぜ国のほうで認められなかったのかという、その報告されている部分をもう少し詳しくお願いします。
庶務課長
理由までは聞かされておりませんが、あくまでも市のほうで事業自体が該当するから、できれば平成30年度よりは平成29年度ということで、可能性が高まればということで申請をした次第です。
吉田
先ほどの御説明だと、国のほうからどうですかという提案だったように私は捉えたのですが、そうではなく、本市として平成29年度でできる、国の補助金がそこにつけられるのではないかという見込みで進めたと捉えられる御答弁です。このことによって学校を運営している現場の方たちの中で、どのぐらい影響が考えられるのか、その範囲についてお伺いしたいと思います。
庶務課長
あくまでも国、県を通して、ありきではなくて可能かどうかという調査の段階で、市としては少しでも補助事業の可能性が高まればということで申請したもので、国が確約したものではないと捉えているところです。
実際の工事ですが、当初平成30年度に予定していたところですが、現段階では増田中学校の全体の工事に支障があるとは考えておりません。
(議案第70号 名取市公民館条例の一部を改正する条例)
吉田
次の図書館にもかかってくるかと思うのですが、12月19日をもってということで今回期限が切られております。それは市民の利用者の方のための駐車場も、同じく12月19日から供用開始ということでよろしいのでしょうか。
生涯学習課長
公民館の入る北棟については、10月末に竣工、引き渡しを受ける予定となっております。駐車場については、南棟のマンション住人や店舗関係者も使用することになりますので、具体的な駐車場の供用開始は未定ですが、12月19日は使用可能と考えております。
今後、北棟、南棟の所有者で構成される駐車場管理組合の中で、詳細な運用ルールが決定されるものと思われます。
吉田
さきの議会で、管理組合で維持管理することについては御説明を受けていましたので、駐車場についてその中で決められていくことかと思いますが、駐車料金について、現状本市としてどのように把握されているのか、お伺いします。
生涯学習課長
駐車料金については、一定の無料サービスを行うこととしておりますが、その時間帯、その設定等についてはまだ決まっておりません。今後決定されると思われます。
(議案第75号 財産の取得)
吉田
ただいまの御説明で、今、全国的に図書館で問題になっています盗難、返却されないことについても十分対応可能なのかなと安心したところです。これだけの機械ですと、やはりそれなりにメンテナンス費がかかってこようかと思うのですが、今回の契約には将来的なメンテナンスは含まれず、あくまでもこの機械一式ということでよろしいのですか。
生涯学習課長
今回は備品の購入ということになっております。
吉田
先ほどの質疑の際に、今回の金額の中には維持管理費は含まれていないという答弁でしたが、維持管理の中にソフトウエアの更新も含んだつもりだったのです。それももしかからないとなると、ソフトウエアの更新は今後無料で行われるのか。それとも、ソフトウエアの更新そのものがない仕組みなのか。あるいは更新される際に、また別に料金を請求されるのか。そのあたりはどのようになっているのでしょうか。
生涯学習課長
今後、保守点検をしていく中で、ソフトウエアの更新等も含めて考えていく予定です。
吉田
先ほど別の議員からの質疑で、入札の際は先に仕様書が公告されるという話でしたが、今回その仕様書の中でも、システムのメンテナンスについては今後行われていくという中身だったのでしょうか。
教育部長
今回の機器購入に際しての仕様書の中には、メンテナンス部分については記載はしておりません。ただ、機械関係の保証期間としては1年間という決め方はしております。
(議会案第1号 日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書)
吉田
案文の5段落目のところで、「我が国は、広島と長崎で核の惨禍を経験しています。その経験から核兵器の禁止に賛同し、その先頭に立つことが強く求められています」とありますが、強く求めているのは一体誰であると認識されているのでしょうか。
齋 浩美議員
広島、長崎を初めとした日本国民の皆さんだと私は思っています。
吉田
そのように思っている方はもちろんいることは否定するわけではありませんが、地方自治法第99条、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件について意見書を提出することができるとなっておりまして、あくまで名取市民の公益を主に考えていかなければいけないというのが、この意見書の原則であろうと考えます。名取市民の中でこのように強く求めている方がどのぐらいいるのかについて、どのような形で意見を集めてこられたのか、そのあたりの経緯について御説明をお願いいたします。
齋 浩美議員
基本的に日本人であれば、広島、長崎の核兵器で起きた出来事を体験していて、そこについての考えがあって、核兵器を使うことは容認できないと考えていると思います。それは非核三原則という国是もあるものですから、そういうところで大変申しわけないのですが、そういう調査等はしていません。しかし、日本国民であるならば、広島、長崎という経験があって、実際見に行かれた方もいるかと思うのですが、そういったことで提出しています。
先ほど意見書についてお話がありましたが、少なくとも名取市民とか、名取の公益という話であれば、意見書については4月10日のデータでも、全国でも239議会で持っていると。全自治体の1割超がこのような意見書を出していることを否定しかねないのではないかと思うのです。そこで、自治体に公益という話があったのですが、これは基本的に一般的な意見書と私は捉えています。
一般質問
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、事前の通告に従いまして一般質問を行わせていただきます。
初めに、大項目1 改元に向けた準備についてお伺いいたします。
ことしは平成30年です。昭和から平成へと元号が変わったとき、私は卒業を間近に控えた小学6年生でした。昭和という時代の大半を体験したことのない私にとって、昭和に対するイメージは、初期は戦争の時代、中期は高度経済成長の時代、そして後期は繁栄の時代というものです。では、平成という時代はどうかといいますと、停滞から衰退、自然災害の脅威、そして国際的なテロリズムの拡散、個人的にはこうしたイメージが強くあります。将来、東日本大震災を語る際には、平成という時代のこととして説明される場面がふえるのではないかと考えます。元号は日本において、単なる数字や記号とは異なった、一つの時代を象徴する言葉として定着しております。
平成に変わって間もないころ、新しい元号になかなかなじめなかった記憶があります。企業や役所等の組織にとっても、なじめないどころの話ではなく、いっときに大量の仕事が降りかかってきたような感覚ではなかったかと察せられます。しかし、当時の関係者は、英知と努力を結集させ、改元という突然の出来事を乗り越えてきました。戦後初めて天皇陛下が御存命中に皇位を譲られる日付が、来年、平成31年4月30日と決まっております。平成は来年4月30日をもって終わり、5月1日から新しい元号になります。平成への改元から30年。市役所事務のコンピューター化が一層進んだこともあり、改元による影響が行政のさまざまな分野で生じるのではないかと危惧しております。まずは現状を確認したいと思います。
小項目1 各種事務や行政文書、住民からの届出等において、年の表示は元号と西暦のいずれを原則としているのか、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
行政文書等において元号を使用することについて法的な規定や国からの通知はありませんが、本市では慣行として元号を表示しております。一部の申請書類、パンフレット、チラシなどには、西暦のみを表示したものや西暦と元号を併記したものがありますが、これらは掲載する内容などその文書の性格によって必要な対応を行っております。
また、条例等に定めている様式については、日付については基本的に元号を使用せずに単に「年月日」と記載しています。市民の皆様から御提出いただく実際の申請書等については、元号、西暦のいずれの記入でも対応しているところです。
教育長
各種事務や行政文書、住民からの届け出等の年の表示の考えについては、教育委員会の対応もただいま市長が答弁したとおりとなっています。
具体的に、住民からの届け出等で、教育委員会が所管する公民館使用許可申請書や市民体育館使用許可申請書における年の表記について答弁させていただきますが、これら許可書の記載の年の表記は、あらかじめ「平成」の元号を印刷し使用しております。
吉田
市長からは、慣行として元号表記を原則としていると御答弁がありました。それ以外の情報システムの部分、目に見えない機械の中の処理についてはどのような処理を行っているのか、市長にお伺いしたいと思います。
また、教育長には、学校における生徒の通知表や、指導要録はわかりませんが、子供たちの成績の処理などで一部機械化が進んでいると思います。そこでの年の表示はどのようになっているのかお伺いします。
市政情報課長
市で運用している基幹系システムと内部情報系システムについて御説明いたします。
基幹系システムでは年を西暦で保持しています。それを和暦に変換する仕組みを用いて和暦を出力する形になっています。基幹系システムと関連して運用している一部のシステムにおいては、西暦でなく保持しているシステムもありますので、これについては対応方法についてシステムベンダーなどと協議しながら対応を考えていきます。
次に、内部情報系システムです。内部情報系システムの主な業務システムは財務会計システムで、これは、本年10月見込み以降、平成31年度の予算編成あるいは予算執行から新しいシステムを使うことにしています。ただし、これまで使用しているシステムは平成30年度の予算執行を決算まで行いますので、10月以降は2つのシステムを並行して使用することになります。
新しいシステムは新元号に対応できるようしますが、並行して使うこれまでのシステムについては、改元の時期がちょうど出納整理期間に当たりますので、金融機関との関係、あるいは、出納整理期間なので処理件数もかかわりますので、システム改修に費用を投じたほうがいいのか、あるいは別な対応方法があるのか、引き続き検討していきたいと考えています。
教育長
学校で使用している成績に関するいろいろな書類や、先ほど話があった通知表、卒業証書等は、私の知り得る範囲では元号表記となっていると思います。卒業証書でいえば、本人の生年月日と卒業年月日に現在であれば平成何年と。通知表については、公的な公簿ではありませんが、学校と家庭の連絡ということで保護者、児童生徒に配付しており、一番最初に平成何年度と、年の表記は元号表記です。修了証書の年月日等も元号で表記されていると認識しております。
情報処理の観点での御質問だと思いますが、学校において、最近は指導要録あるいは通知表を電子データとして作成していますが、先ほど申し上げたように、パソコン上で作成した元号をそのままプリントアウトするような形ですので、その中に使われているのも基本的には元号、あるいは、成績処理などについては、先生方が各自個人的にエクセル等で処理することもあると思いますが、その場合は西暦と和暦の表示の違いはさほど影響しないのではないかと考えます。
吉田
現状について確認させていただきましたので、次に移ります。
改元に向けたこれまでの経緯を振り返りますと、平成29年6月16日に天皇の退位等に関する皇室典範特例法が公布されました。そして、12月13日に天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令が制定されました。政府は、改元に先立って、新元号を発表するとしております。その時期として、まだ確定ではありませんが、御在位30年の記念式典が開かれる平成31年2月24日以降とすることを検討しているということです。このように短い期間ではありますが、準備の期間が全くなかった昭和から平成への改元時に比べれば、まだ恵まれた環境にあると言えると思います。
行政として、改元によって市民生活に影響が出ないよう、今いろいろと取り組みに関してまで御説明いただきましたが、改めて具体的な対策をどのようにとってきたのか、小項目2 次の改元を想定した対策の経過を市長と教育長にお伺いいたします。
市長
申請書等の様式の修正、条例等の一部改正、システム改修などが必要となりますが、新しい元号の施行に対応できるよう対策を行ってまいります。新元号の公表時期が平成31年4月とされていることから、具体的な作業はそれ以降とならざるを得ませんが、遅滞なく作業が進められるよう、対象となるもののリストアップなど、平成30年度中にも可能な限り準備を進めていきます。
国からの具体的な通知は示されておりませんが、今後とも国の動きを注視しながら、システム業者などの関係者と十分な連携を図り、必要な準備を進めてまいります。
教育長
改元に当たって、新しい元号が発表されていない状況ですので、具体的な対策を行う段階ではありませんが、ただいまの市長答弁にありましたとおり、今後、市長部局と足並みをそろえ、準備作業等の対応をしていきたいと考えております。
吉田
まだ新しい元号がわからない時点でできることは当然限られていますので、発表と同時に作業が進められるよう準備が行われていると今伺って、やはり市が責任を持って進めているのだなという感想を持ちました。
条例などに平成32年や平成33年と書かれているものがあります。契約書も同様です。こういったものが改元によって無効になることはあり得ないのは当然ですが、平成32年だったら新元号の2年と読みかえるなど、その根拠については市としてどのように考えているのか、市長にお伺いします。
それから、教育長には通告はしていませんので確認として、今後、学校において、卒業証書などを初めとして元号表記を続けていくということでよろしいのかどうか、もう一度お伺いしたいと思います。
総務課長
改元に伴う条例等の改正ですが、昭和から平成に変わるときに国や県から通知があり、条例等の規定の中で、改元の日以降の期日、いわゆる平成31年5月1日以降です、またはその期間が平成と用いてあらわされている部分については、改正を行わなければならない。要は平成31年5月1日以降での期日と読み取れる部分については、元号のところは改正しなければならないという通知が来ています。それ以外については、元号の改正をもって効力がなくなるわけではないという通知をいただいております。
教育長
先ほど答弁申し上げた卒業証書等の学校で使用している公簿あるいはいろいろな書類などについて、従来、元号で表記しているものを、平成から元号が変わったことによってあえて西暦にする考えは持っておりません。基本的な考え方として、学校現場においては併用することが今までもそうでしたし、例えば中学校の歴史の教科書では、歴史の中での年号表記については、江戸時代以前はほとんど西暦表示になっています。明治以降は、西暦表示の後に括弧書きで元号が表記されているのが通常の使い方で、学校現場では、卒業証書等は従来のままだと思いますが、場合によって西暦と和暦を使い分けていくことになろうかと思います。
吉田
平成から変わったときに条例の改正が必要だと課長の御答弁から読み取ったのですが、例えば今回、専決処分で製造たばこの区分に加熱式たばこが加わりましたが、段階的に税率を上げていくということで、一々それらの条例改正が必要になるということでよろしいのですか。
総務課長
繰り返しになりますが、平成31年5月1日以降を示すところが「平成」の表記になっているのであれば改正を行うことになります。
吉田
では、市の取り組みについては確認できましたので、次に移ります。
改元の際に、コンピューターの大規模なシステム改修が必要になることや、年数の計算に不便という理由などから、元号を使わずに西暦に一本化すべきという主張も一部であります。このように効率ばかり重視するのであれば、そのような結論に至るのも理解できますが、やはり効率だけでははかり切れないものもあります。多様性というものが世の中にはあり、それはもちろん今申し上げている暦や言語においても同じことが言えると思います。
歴史上、世界にはさまざまな暦がありました。その大部分が消えていった中で、世界のスタンダードとなったのが西暦です。これは紀元6世紀のローマでイエス・キリストが誕生した年を紀元とするということで考案されて採用されましたが、その後、実はキリストの誕生の年は違っていたという研究の成果もあるようです。そのほかにも、例えば中国大陸では、中華民国が樹立するまでは独自の元号が使われていた。ただ、中華民国ができて共和制の政体ということで元号を廃止し、現在、中華民国何年というあらわし方をしていると伺いました。そして、それは今は台湾において使われているということです。ちなみに、中華人民共和国は西暦を採用しています。
世界でさまざまな取り組みをしていますが、この私たちの日本においては、明治5年にそれまでの太陰太陽暦から太陽暦に移行し、月日のあらわし方は世界標準に変えました。その際、初代神武天皇が即位したと推定される年を紀元とする皇紀も定められましたが、戦後はほとんど使われなくなり、元号表記が今に続いているという経緯があります。なお、現在まで元号の数は全部で231と、かなり多い数です。全部暗記しようと思っても多分できないと思うのですが、いずれ挑戦してみたいと思っています。
さて、5月21日の読売新聞朝刊に、政府は、各省庁が運用する行政システムの日付データについて、元号を使わず西暦に一本化する方針であるとの記事が掲載されました。内容をよく確認すると、西暦で一元管理するのはあくまでコンピューター内の日付データの処理に限り、書類上は元号による表示を続けるということでした。このように政府としても、事務のコンピューター化が進む中で、今後もできるだけ元号を使用し続けていこうという苦心の跡が見られるように感じます。これはやはり自治体レベルでも歩調を合わせることが望ましいと思います。
そこで、小項目3 元号という日本古来の伝統を大切にしていくために、改元後も届出等の年の表示には元号を用いるよう市民の理解と協力を求めるべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
行政文書として統一性を確保すること、元号が市民生活に広く定着していること、さらに国の機関や他の地方公共団体の多くが元号を使用していることなどから、本市では改元後もこれまでどおりの対応としていきたいと考えております。
吉田
申請書等もそうですが、広報なとりのような市からの刊行物等についても同じように捉えてよろしいですか。
市長
基本的にはそのように考えております。
吉田
機械化されたシステムについてお伺いしたいと思いますが、今回元号が変わることが決まっています。そして、また次、何年後か何十年後かわかりませんが、元号が変わることになります。そのときのこともあらかじめ想定した中で新たなシステム構築を考えているのかどうか、お伺いしたいと思います。
市政情報課長
先ほども御説明申し上げましたが、市の基幹系システムについては年を西暦で保持しています。和暦をセットして変換する仕組みを用いていますので、将来また別な元号に変わっても、例えば基幹系システムであればその元号をセットして読みかえるシステムということで対応していきます。
吉田
コンピューターは相当優秀になってきていますので、そういうところもしっかり対応できる仕組みになっているという御答弁と捉えました。
では、次に、一般の出版物やメディアによる報道等には、元号のみ、あるいは西暦のみ、また元号と西暦の両方の併記と、さまざまな年の表示の方法が見られます。先ほど市でも同じようなケースがあると御紹介いただきました。今後も年の表示について市民の協力と理解を求めるべきと申し上げましたが、やはり個人の私生活あるいは学術面、経済活動などは自由に行われるものですから、年の表示をどうするかはそれぞれが決定すべきだと思います。ただ、このように日本国内で年の表記が全て一本化されているわけではありませんので、市のサービスを受ける方の中には、元号表記だけではどうしてもわかりづらい、西暦であらわしてほしいという方もいるかもしれません。ですから、今後も元号表記を原則としつつ、こうした方への配慮も忘れてはならないと思います。
そこで、小項目4 新しい元号が発表されたら速やかに、当面の間利用できる和暦西暦早見表を窓口等に設置すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
議員御指摘の和暦西暦の早見表について、市民課を初め1年を通じて来庁者が多く訪れる庁舎1階の課には、基本的に窓口に設置していますが、庁内全ての窓口で設置しているものではありませんでした。
市民の利便性向上のため、議員御提言のとおり、新元号の発表後、速やかに、窓口のある全ての課に早見表をわかりやすい形で窓口等に設置するよう周知徹底を図ります。今後とも市民の皆様にわかりやすい表記の工夫に努めていきます。
吉田
1階の窓口に設置していることは、私の勉強不足でそこまで確認できておりませんでした。
今の御答弁だと、設置するものの中身をこれからつくる段階になるかと思います。今の段階でどうとは言えないかもしれませんが、例えば年齢を組み合わせて何年に何歳とわかるものなど、行政の申請文書でそこまでは必要ないかもしれませんが、どの程度のものをつくっていくのか、今後の検討のスケジュールがもしあれば教えていただきたいと思います。
総務課長
改元については、先ほどからの答弁のとおり、システム改修や印刷されている申請書等の元号の訂正、また例規の改正などのほかに、いろいろと全庁的にやはり一度情報共有をしなければならないと思っておりまして、できれば夏ぐらいに一度全庁的な打ち合わせを持ちたいと思っています。その中で、今御提言の部分についても検討事項といいますか、調査事項としてのせたいと考えております。
吉田
新しい元号発表、そして改元まであと1年を切っています。市としてもそこを見越した対策をしっかりとっているということですので、これがスムーズに、順調に進んで、新しい元号を国民がこぞって新天皇の御即位ということでお祝いできたらと思います。これで大項目1は終わりたいと思います。
次に、大項目2 特別職礼遇者制度についてお伺いいたします。
特別職礼遇者制度と申しましたが、その根拠となっている条例の正式な名称は名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例です。昭和45年に公布、施行されました。「れいぐう」という言葉は冷たい待遇を想起する方のほうが多いのではないかと思いますが、本市の「礼遇」は礼儀「礼」の字です。その礼遇とはどのような内容かというと、条例の第3条で、礼遇者名簿に登録した上で、礼遇者記章の交付、市の重要な式典への参列、市政に関する重要な刊行物の配付、及びその他特に必要と認める事項としています。では、どのような人が礼遇者に該当するのかといいますと、第2条で、市長の職にあった者、8年以上副市長、助役、収入役または教育長の職にあった者及び4年以上市議会議員の職にあったものとされています。
この条例が成立するまでの経緯を追ってみました。まず、宮城県で昭和34年に県議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例が成立した。その明くる年に、倣うかのように名取市議会議員の職にあった者の礼遇に関する条例が成立した。そして、礼遇者の中に市長などを加える形で、昭和45年に名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例として成立しました。この昭和45年の会議録も調べましたが、補足説明の内容までは残っていませんでしたが、議会側からではなく、行政側から提案された議案であったことを確認しています。
ここから本題になりますが、第5条に礼遇の喪失についての規定があります。礼遇者が禁錮以上の刑に処せられたときのみ礼遇を喪失するとなっています。つまり、みずからの意思によって礼遇を辞退することは認められておりません。市において、特別職にあった者に礼遇者としての対応をとりたいという気持ちは大変ありがたいものですが、待遇を遠慮したいという人がいた場合、その意思を尊重することも必要ではないかと捉えます。
そこで、小項目1 礼遇を受ける要件に該当した者へ、礼遇者としての待遇の辞退を認めるべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
特別職礼遇者は、条例に定められた要件を満たした方が礼遇者名簿に登録され、礼遇者記章の交付、市の重要な式典への参列、市政に関する重要な刊行物の配付等について礼遇するほか、亡くなられたときに花輪や弔慰金を贈るなどして弔意を表することとしておりますが、これらの待遇について、これまで特に辞退するといった事例はありませんでした。
礼遇の辞退については、特段条例にうたわれてはいませんが、今後、特別職礼遇者からその待遇について辞退したい旨の話が出てきましたら、最大限その意思を尊重していきたいと考えております。
吉田
今の御答弁では、一度は礼遇者の名簿に登録されて、その上で辞退することになるかと思いますが、あくまでも条例の中に辞退の規定が入っていませんので、それが果たして解釈という形でできるのかどうか大変疑問があります。では、現段階で、私はまだそうではないのですが、もし辞退したいという方がいたら、それはできると捉えてよろしいのですか。
政策企画課長
市長から答弁したとおり、辞退の申し出があった場合、そのお考えについては最大限尊重するという取り扱いで進めたいと考えております。ただ、先ほど議員から御指摘があったとおり、条例上、礼遇者については、条例にのっとって、その要件に該当する方を全て名簿に登載することになっており、辞退の取り扱いは特にうたっていないわけです。この運用上の取り扱いについては、名簿に自動的に登載することに処分性があるのかどうかということについて、確たる考えといいますか、解釈を持ち合わせていないところです。処分性があるとなれば、条例上に辞退の条文の追記などを行わないと、辞退は受けられないものと捉えておりますので、その解釈について今後研究をしていきたいということで、現時点では確たる取り扱いは持ち合わせていないことを御理解いただきたいと思います。
吉田
処分性の有無ということでしたので、現職は礼遇者名簿から外れますが、今は4年の議員の任期を務めれば自動的に礼遇者になります。私のような新人が、あと1年少しすると4年になるわけです。その間に礼遇の辞退がしっかり条例上認められるという結論を出すことは可能ですか。
政策企画課長
先ほどの市長の御答弁でも申し上げているとおり、現在、具体的な辞退の申し出を受けた経過がありませんので、条文への追加、あるいはそれによらずして辞退の申し出を受けられるのかといった具体的な検討は行っていません。今後、そういったケースが出てくれば、市長が御答弁したとおり、そのお考えを最大限尊重する方向で具体的な検討に入りたいと考えております。
吉田
ということは、礼遇者にならなければ辞退ができないと、あらかじめ辞退することができないということかと思いました。
そこで次に移りますが、今度はもう少し広げて、これは、今礼遇者の方やこれからなる方のそれぞれのお考えがあると思いますので、あくまで私個人の考えです。また、名取市特別職礼遇者会がありますが、それはあくまでも任意の団体ですので、そことは切り離して、本市の礼遇者制度の中でお聞きしたいと思います。
先ほど条例の第3条を御紹介しましたが、礼遇者の待遇とはいっても、予算としては大した額ではありません。礼遇者制度があることによる弊害は全くありません。それがこれまで余りこのことが取り上げられなかった、半世紀以上続いてきた要因ではないかと捉えています。しかし、礼遇者という身分を必要とする時代ではそろそろないのではないか。やはり現在は市民協働が重視されていて、さまざまな分野で市民の方が本当に奉仕の気持ちで活動しています。礼遇者は議員を4年務めればなりますが、市民の中には何十年もボランティア活動をしている方がたくさんいるという中で、やはり今の線引きの仕方は時代の流れに合っていないのではないかという印象を私は持っております。
そこで、小項目2 礼遇者制度の廃止を視野に入れた検討を行うべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
特別職礼遇者制度の条例は、議員御指摘のとおり昭和45年に議会の議決をもって制定されました。
この条例に規定されている、先ほど御答弁申し上げました礼遇者に対する待遇については、これまで市民の方々から御意見等をいただいた経緯はありません。また、社会通念上、一般的に認められる範囲のものと解しておりますので、現時点において礼遇者制度の廃止を検討する考えはありません。
吉田
いきなり廃止はかなり難しいと思うのですが、例えば、礼遇者制度そのものがない自治体も県外にはたくさんあり、県内でも仙台市では、特別職礼遇者ではなく議員待遇者というくくりで行っています。これは市議会議員の職を3期か4期だったと思うのですが、確かでなくて済みません。ただ、1期ではなく、相当長く務めていると。そして、やはり名称が礼遇者ではなく議員待遇者と。通常の現職の議員とほぼ同じ待遇ということで、発行物の配付や式典への参加等をあらわしているのかと思いますが、そういう部分です。それから、例えば現在礼遇者にある方はそのままとして、今後なる方にはそれこそ選択制にしていくなど、そのような形で制度を緩やかに変更していくことは可能かと思うのですが、そういった御検討についてはどのようなお考えでしょうか。
市長
これまで昭和45年から長い歴史の中で積み重ねてきた制度だと思っております。また、市勢発展、市民福祉の向上に十分貢献されてきた方々であり、礼をもって遇されるにふさわしい方々であろうと思います。したがいまして、廃止、もしくは変更については、これは例えば対象の方々、さらには市民からそうした機運が醸成されてきた場合にはまた別ですが、現時点においてはそのような検討をする考えはありません。
吉田
ちょうどきょう会派室のポストに特別職礼遇者会の会報が入っていて、すごくタイミングがいいなと思いました。現在の会長や会員、礼遇者の方々の寄稿や御挨拶文を読みまして、本当に見識が高い、大変本市に対する愛情が深いことも受けとめております。
市民から議論が起こるのを待つのも一つかと思いますが、市長御自身も、市議会議員を2期務められ、その後、市議会議員を引退して一度礼遇者になったわけです。そのときに、御自身、50代という年齢で礼遇者となることについて、率直にどのような感想をお持ちだったのか教えていただきたいと思います。
市長
個人的なお話ですが、私は、特段の理由がありまして、そうしたことを考えるいとまはなかったということであります。
吉田
大変忙しいときだったので、おっしゃるとおりかと思います。これから年齢の若い議員がふえてくるかと思います。そしてまた、1期、2期務めただけで、5期、6期続けるとは限らないかもしれない。時代の変化はそのようなところにもこれからあらわれてくると思いますので、何かしら今後機会があったら、市でも御検討いただきたいとお願いします。
では、最後の大項目3 人の終末に関する施策についてお伺いいたします。
本市議会の一般質問では、人生における節目に関して、結婚や出産などどちらかというとおめでたい内容が取り上げられるほうが多い気がいたします。今回はあえて人の終末、つまり死を取り上げたいと思います。
どのような人でも、必ず一度は誕生と死を経験します。新しい命とそれを迎える家族へのケアと同様に、この世を去っていく人とその遺族へのケアも行政の重要な課題として位置づけられます。 近年、誰にもみとられず、場合によっては死後数日間気づいてもらえない孤独死という社会問題がクローズアップされています。最近では余り報じられませんが、それはこうした問題がなくなったからではなく、珍しくなくなったことが原因ではないかと思います。みとりから埋葬まで家族や親戚が行うものであるという原則はこれからも変わるものではありませんが、全く身寄りのない境遇の方がいることも事実です。しかも、現在の日本は、高齢化の坂道をかなりのスピードで駆け上がっています。そして、その先には多死社会が到来すると言われています。単身者や所得の少ない高齢者の割合が高まっていくことが予想されており、こうした方々にとってみずからの最期を頼ることができる存在は行政しかありません。
こうした課題に対して対策をとり始めた自治体もあります。例えば神奈川県横須賀市では、平成27年7月から、高齢者自身が市の仲介で葬儀業者と生前契約を結ぶ「エンディングプラン・サポート事業」を行っています。葬儀の希望を伝えて、最低限の費用を預ける仕組みで、市は納骨まで見守るとしています。また、同じ神奈川県大和市では、平成28年度から葬儀生前契約支援事業を行っています。主に身寄りがなく経済的に困窮している市民は、生活保護の葬祭扶助基準と同じ20万6,000円を上限に、葬儀の内容や納骨する寺を決めておく生前契約を結ぶことができるとされています。これは、市による定期的な安否確認も行われています。
本市も含めて日本全体が、多死社会到来を見据えた対策に取りかかる段階に来ていると言えると思います。そこで、小項目1 ひとり暮らしで身寄りがなく生活にゆとりのない高齢市民を対象とするエンディングサポート事業に取り組むべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
超少子高齢化社会となった昨今、御自身が亡くなった後のために、生前から葬儀や墓などの準備や身の回りの整理、あるいは財産分与や延命治療などの意向を家族に伝えておくなどの人生の終わりに向けた活動、いわゆる「終活」を行う方もふえております。
エンディングサポート事業は、その終活の一部を支援する事業であり、近年、事業に取り組む市町村も少しずつふえてきていると認識しています。
本市において、ここ数年における高齢者からの、御自身が亡くなった後のいわゆる終活についての相談実績については、四、五件となっております。内容はさまざまですが、高齢者御自身のお墓の問題であったり相続問題などです。
今回、御質問のあったエンディングサポート事業は、高齢者の人生の終わりに向けた不安を少しでも解消することができる事業として考えられることから、今後、情報収集を行い、調査研究していきたいと考えております。
吉田
現状で、何年間か確かではありませんが、四、五件相談があったという御答弁でした。
この「終活」という言葉は、市長の御発言にもありましたが、やはり御自身の終末期を不安視するのと同時に、みずからのお子さんやお孫さんに対してできるだけ負担を残さずに自分はこの世を去りたいという思いを持っている方がふえているあらわれの一つかと思われます。私の質問では、高齢の方、特に社会的弱者ということで取り上げましたが、横須賀市のエンディングサポート事業については、実際は、相談に訪れた市民の大半が所得面などでその対象外であったと伺いました。そこで、平成30年5月からは「わたしの終活登録」という新しい事業を始めたということです。今度は、かかりつけの医師、また遺言状や御自分でつけているエンディングノートの保管先などを登録できるということで、もう少し幅を広げました。
そのようなことを踏まえながら、より多くの方に利用してもらえる形に検討を進めていただきたいと思いますが、市長としてはどのぐらいまで検討の範囲を広げられるとお考えか、お伺いいたします。
市長
今後、先進事例を含めて調査研究していきたいと考えておりますが、例えば葬儀会社に御本人が事前にお支払いする仕組みになっており、その葬儀会社が万が一倒産等したときにどうなるか。また、議員御指摘のとおり、対象者について、当初は低所得者を対象としていましたが、実際はもっと違う所得の方がお一人で来られる場合が多かったということもありますので、いわゆる整理すべき課題がまだあるだろうと思っています。また、今すぐ取り組むべき事業なのかということについても検討の一つに加えて、調査研究をしていきたいと考えております。
吉田
では、次は残された遺族に対するケアについてお伺いしたいと思います。
人が亡くなると、市町村に提出する死亡届を初めとして、さまざまな手続を行わなければなりません。さらに民間会社との契約の解除などを含めると、多い方では20件を超える手続を行わなければならないケースも出てきます。こうした手続を代行する葬儀業者がふえてきていますが、中には葬儀業者を使わないという方もいて、その遺族の方は、幾つもの手続を行うために、書類を書いたり窓口を回らなければならない。大切な人を亡くした悲しみにさらに追い打ちをかけるようなことになっている部分もあると伺っております。
こうした負担を減らすために、死亡に関する手続を1カ所の窓口で全て行えるワンストップサービスを始めた自治体があります。特に早くから取り組んでいる大分県別府市では、死亡に関する手続が必要な各課の窓口のほかに、おくやみコーナーを設けて、亡くなった方についての情報を聞き取り、死亡に関する申請書を一括して作成できます。同時に各課にこの情報を提供することで、必要な手続を選別し、その後、手続の必要な課へ案内する、あるいは担当職員が順次そのコーナーに出向いて手続を完了してくれる仕組みとなっているようです。また、三重県松阪市でも、平成29年11月、おくやみコーナーを新設しました。これは、銀行預金などの相続や生命保険、土地相続登記など、市役所以外の手続についても案内しているということです。
このような先行事例を参考として、小項目2 親族の死去に際し、さまざまな申請や手続をより分かりやすく簡単に済ませられるワンストップサービスの窓口を設置すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
御質問に対しまして、まず現状を御説明させていただきます。
通常、死亡届は御遺族の方にかわって葬祭事業者から窓口へ提出されます。届け出を受け、即日、埋葬火葬許可証を交付し、御遺族の方宛てには必要な諸手続についての御案内文をお渡ししており、実際の手続については、後日、御遺族の方が来庁された際、担当部署に窓口において対応しているところです。
御提案のありましたワンストップサービスの窓口については、1つの窓口において申請や手続ができるというメリットはあるものの、具体的な内容となれば、担当部署が対応せざるを得ない場合もあることから、他の申請手続と同様に、専門的な説明ができる現在の対応を継続していきたいと考えております。
なお、複数にまたがる手続については、担当部署間の連携を図り、必要な申請や手続をよりわかりやすくお伝えするように努めてまいります。
吉田
1カ所の窓口でできればそれにこしたことはありませんが、市長の御説明ですと、できるだけ負担を少なくする方向として、市としての努力が十分認められるのかなという印象も受けました。そうした中で、先ほど紹介したように、市役所業務以外の手続も本当にたくさんあると思うのです。携帯電話の契約もそうですし、それらの御案内などは今の仕組みの中で行っていますか。
市長
本市でもまとめてお知らせするような書類をつくっていますが、今回の御提言を受けていろいろと調べた結果、群馬県前橋市では「ご遺族の方へ」という、本当に多岐にわたる諸手続の内容と窓口が掲載され、それから手続が終わったかどうかチェックリストになっています。そのようにして取り組んでいることがわかりましたので、よりわかりやすく、そして優しく丁寧な対応になるように考えていきたいと思います。
吉田
前橋市でも出しているのですね。私は松阪市のものです。かなり多岐にわたる案内ですが、本市としてもこのようなものを将来的に検討していただければと思います。
次に移ります。家族が亡くなった際に葬儀の日程や会場などを知らせる手段として、近所の方に対しては町内会の協力で回覧を回すこともありますが、町内会以外の方に知らせる手段としては、新聞に訃報広告を掲載する方法があります。例えば地元紙の河北新報の場合、朝刊は15万2,000円から、夕刊で11万6,000円から、広告の大きさに応じた金額となっています。商業広告に比べると金額は低く設定されていますが、決して安いものではありません。中には、やはり訃報広告を出したくても諦めた方がいるのではないかと思います。自治体によっては、自治体の広報紙で訃報情報を出しているところがあったようですが、現在はほとんど目にすることはありません。これはやはり発行の間が長くあいてしまうことや紙面に限りがあって、自治体の広報紙は訃報情報には向いていないということではないかと思います。
しかし、現在、市の広報の媒体として本市では広報紙のほかにホームページがあります。ホームページであれば更新も早く、掲載スペースの確保もそれほど難しくないため、無料に近い形で掲載できるのではないかと思います。もちろん対象は希望者のみとし、掲載内容も葬儀の日程や会場など必要最低限のものに限る。そうすれば個人情報保護の観点からも問題はないと思います。そのことによって、新聞を講読していない方を中心にホームページの閲覧者数がふえ、そしてバナー広告の効果も上がるという期待も持てるのではないかと思います。
小項目3 市のホームページに訃報情報のページを設けるべきに対する市長の御見解をお伺いいたします。
市長
本市のホームページでは、各課の担当する事業に関する情報やその他の行政情報など、さまざまな情報をサイトポリシーや個人情報の取り扱いなどに配慮しながら掲載しているところです。
御提案のあった訃報情報については、市民にとってお互いのつながりを確認する重要な情報ではありますが、個人情報を悪用したトラブルや犯罪に巻き込まれるおそれがあること、また、正確な情報を早急に掲載することは市側の事務的負担も多いことから、慎重に対応すべきものと考えております。
吉田
個人情報については、先ほど申し上げましたが、家族の方の住所などは載せず、葬儀の情報だけであれば……、もちろん希望者です。希望しない方の名前まで載せる必要はありませんが、希望する方であれば可能ではないかと思います。事務的な負担ともおっしゃいますが、先ほどあったように、亡くなったときの対応としてそこまでできているのであれば、葬儀業者を通して市にそのような情報というか申し出があれば、ホームページの更新はさほど大きな作業ではないと思いますので、それは今の体制でも可能性はあるのではないかと思うのですが、ホームページの更新についてのあたりで、できない理由をなぜそこまでおっしゃるのかお聞きしたいと思います。
市長
まず前提として、現在も弔意事務に関しては相当な事務量となっております。また、連絡先等を入れないともありましたが、トラブルや犯罪という部分については、例えば空き巣、仏壇のセールスに巻き込まれるといったことも考えられますし、何より御遺族の意向の意思確認を正確にしなければいけない、名前などもちろん間違えられない、そして葬儀等の時間に絶対におくれられないといったことがあります。現在、私まで死亡の届け出の報告が上がってくるのですが、期日を過ぎて上がってくることもしばしばあります。そうしたことを踏まえると、なかなか難しい事業ではないかと考えているところです。
吉田
私、これは自分自身でオリジナルの案かなと思ったのですが、調べてみたらほかの自治体で既に導入しているところがありました。新潟県見附市ともう1カ所ぐらいあったようです。やってできないことではありませんので、いずれ機会を捉えて御検討いただければと思います。
最後の質問です。現在、本市で、平成31年度の供用開始に向けて被災者等市民墓地公園の工事が進められています。また、一般市民墓地の用地取得は今議会の議決をもって全て完了し、平成30年度下半期には着工となる予定です。これまでも市民墓地を待ち望む声は非常に多くあったと思いますが、ようやくその実現が近づいてきたのではないかと思います。
先ほども申し上げましたが、日本はこれから多死社会に突入していきます。死者は多くなる一方で、墓を管理する側の生きた人間、つまり人口は減っていく。さらに、都市部への人口の集中が続くことにより、地方の墓を守る人がいなくなっていくことが懸念されます。現在でも、花や供物もなく荒れ放題の墓があちこちで見られます。誰も管理していないのか、それとも管理する人がいなくなってしまったのか、事情はそれぞれだと思いますが、こうした社会情勢の中で墓そのものの新しいスタイルが求められていることも事実ではないかと思います。家族単位ではなく共同に利用する合葬墓や、樹木葬、自然葬、こうしたもののニーズが高まっていると言われています。
本市の市民墓地公園には合葬墓や樹木葬の計画はありません。しかし、名取市民にとっても、潜在的なニーズは決して少なくないと考えます。そこで、小項目4 市民墓地公園に合葬墓及び樹木葬の空間を整備すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
一般の市民墓地については、小塚原地区で造成工事に入っている被災者等市民墓地公園の西側隣接地に、約2ヘクタールの規模で2,000基程度の基数を整備する計画となっています。 現在、墓地区画の実施設計を進めているところですが、平成28年度に実施した市民墓地に関するアンケート調査の結果を踏まえ、墓地のタイプとして希望する割合の多かった、一般的な和風の墓地及び芝生洋風の墓地の区画を整備することとしております。
議員御質問の合葬墓及び樹木葬ですが、アンケート調査において、少子化や核家族化により墓を継いでくれる家族がいないといった理由や、墓の購入に多額の費用がかかるといった経済的な理由により、墓の承継を前提としないタイプの墓地を求めたいとの意見もあったことから、他自治体で運営している公営墓地の事例等も参考としながら調査研究を行いたいと考えております。
吉田
一般の市民墓地の実施設計も始まっているということでした。そちらは資料を見るとスペースはないと思いますが、被災者等市民墓地公園は、250基と300基の墓所以外に、芝生広場と樹木が生えている大変大きなスペースがあります。現在は復興事業として進めていると思いますが、今後、法律的なこととして、墓地、埋葬等に関する法律に基づいて、市長が墓地として新たに使用用途というか許可することは、被災者等市民墓地公園では可能かどうかお伺いしたいと思います。
市長
被災者墓所のお話でしたが、市民墓地については、今後2,000基といいましても段階的に整備していきたいと考えておりまして、その中で、将来的に例えば納骨堂のような形で合葬墓をつくることについては調査研究をしていきたいと考えているところです。樹木葬については、市民の皆さんが集う弔いの場であるという観点を考えると、なかなか難しいのではないかというのが今の見解です。
吉田
樹木葬にもいろいろなものがあり、御遺骨を埋めるのは墓地でなければだめだと。自宅の庭などには埋めてはいけない。ただ、パウダー状にするとどうやらグレーらしくて、これは自宅にまいたり山の中にまいたりできるらしいです。ただ、やはりそうではなく、墓地公園の中でそのようなスペースをしっかり墓地として市で指定する、許可すれば、そこでは自然葬ができると、法律はそのように解釈されているようですので、現在はそこまでの計画はありませんが、今後自然葬も検討の中に入れるべきではないかと思いますが、もう一度市長の御見解をお伺いしたいと思います。
市長
調査研究はさせていただきたいと思いますが、現段階での見解は先ほど申し上げたとおりです。
吉田
アンケートもとって、その結果を踏まえて検討したと思いますが、市民のニーズは日に日に変わっていくものでもありますので、いずれ何かの機会を持って、新たな検討に向けての情報収集を行っていただきたいと思います。
これにて私の一般質問を終わらせていただきます。
本会議
(議案第74号 工事請負契約の締結)
吉田
橋脚を打ち込む本数ですが、この赤い部分で示しているところは橋脚が全部で6本ありまして、西側の黒であらわしているところは8本あるようですが、6本と8本でなぜ違いが出てきたのかについて伺います。
土木課長
くいについては、橋梁や自動車等の荷重に対し、地盤から決定される支持力等により、くいの本数が決定されます。本工事においても、荷重や地質調査から得られた地盤状況を踏まえ、決定しました。A1とA2では地盤状況が異なるため、くいの本数が異なります。また、橋梁の設計において、A1の名取インター方面が固定端になり、A2が自由端ということですので、地震時の水平力は固定端であるA1に大きくかかります。そのため橋台のフーチング幅が広く、基礎ぐいの本数がA2より多くなっています。
吉田
今の御説明で、実際地震などが起きたときの揺れも考慮されているようですが、私のような素人が考えると、東側と西側でバランスが悪いので、揺れたときにかなりゆがむのではないかという気がするのですが、そういうこともないように、こういう設計をしたということでよろしいですか。
土木課長
A1が固定端で、上部工と下部工が固定される箇所になります。A2のほうが自由端で、地震のときに動くような形です。揺れを防ぐということで、このような構造になっております。
(議案第79号 平成30年度名取市一般会計補正予算)
吉田
8、9ページ、16款2項2目1節の土地売払収入の内容について伺います。
財政課長
こちらは名取市社会福祉協議会の移転に伴いまして、市が普通財産として管理している増田五丁目の土地、面積で2,001.29平方メートルのうち、共有分も含めて市が所有している1,942.29平方メートル分を売り払おうとするものです。
吉田
今後の社会福祉協議会の建物の建設予定で伺っているものがあれば、日程などについてお知らせいただきたいと思います。
社会福祉課長
この後、歳出のほうにもありますが、社会福祉協議会は現在、基本設計に取り組んでいると伺っています。補助金等のめどがつけば、平成30年9月ごろには着工したいという考えを持っていると聞いております。いずれ平成30年度内には建物ができ、平成31年度当初から新しい建物での事業を行いたいという考えでいると伺っております。
吉田
14、15ページ、3款5項2目生活再建支援費の23節、被災者支援総合交付金返還金とありますが、こちらの内容を伺います。
生活再建支援課長
こちらの返還金ですが、国庫補助金による平成29年度事業実施分の返還金になります。3つの事業を実施したところですが、ことし4月に精算して額が固まりましたので、その差額を返還するものです。
吉田
精算ということは、もうその事業は無事に完了して、交付された中から実際に使われなかった分をお返しするというように捉えてよろしいですか。
生活再建支援課長
議員お見込みのとおりです。
吉田
18、19ページ、8款7項3目復興まちづくり事業費の中で、原停車場線の改良について幾つか上がっていますが、この詳しい場所や範囲について伺います。
増田復興再開発推進室長
原停車場線の補償調査等委託料の場所ですが、名取駅東口で現在再開発の工事をしておりますが、その北側に位置する原停車場線、延長が160メートルの部分について調査を行うものです。
吉田
調査を行うということですが、道路の一部が狭くなっている部分を拡幅するということで今後進めていくのかと考えていますが、今後の住民への説明会なども含めたスケジュールについて、決まっているところを伺います。
増田復興再開発推進室長
今後のスケジュールですが、現在用地取得に向けて地権者の方と交渉を行っております。交渉がまとまり次第、復興交付金事業の申請を行いまして、工事に入っていくスケジュールとなっております。
(議案第85号 工事請負契約の締結)
吉田
資料3ページの平面図ですが、どこにどのようにドアがつくのか、この図からははっきりしないので確認します。和室や事務室のところに倉庫があります。それから、アリーナのところにも体育館倉庫とありますが、この倉庫は外から入る入り口は設置されるのでしょうか。
教育部長
まず、公民館のほうの倉庫ですが、廊下側に入り口があります。体育館の倉庫は、体育館の器具等を保管する倉庫になりますので、体育館のほうから、この図面では右側に出入り口があるということです。
吉田
2ページの全体的な図のほうで見ると、屋外にも倉庫らしきものがないのです。南側に公園があるということで、公園でいろいろスポーツ競技をする際に、屋外の競技用の道具を使うこともあろうかと思いますが、屋外用の道具類を収納しておく倉庫はどのようにお考えでしょうか。
教育部長
南側の公園は、例えばグラウンドゴルフなどもできるように考えているところですが、そういった用具類は基本的には利用団体が外に設置していただくことになります。公民館の外の倉庫については、今のところ考えておりません。