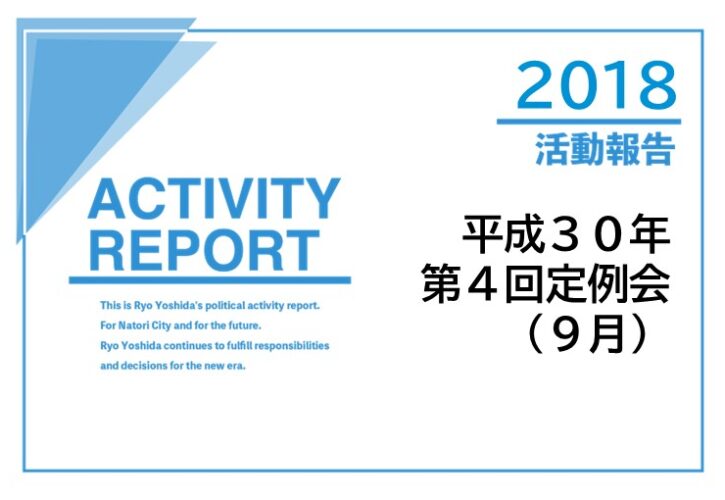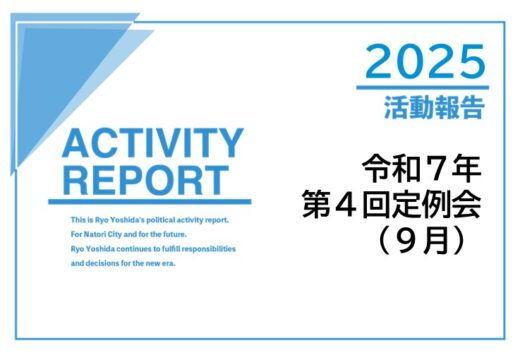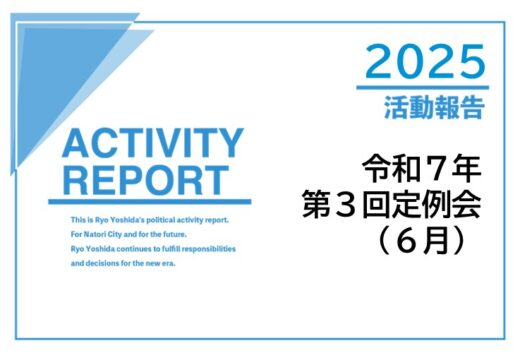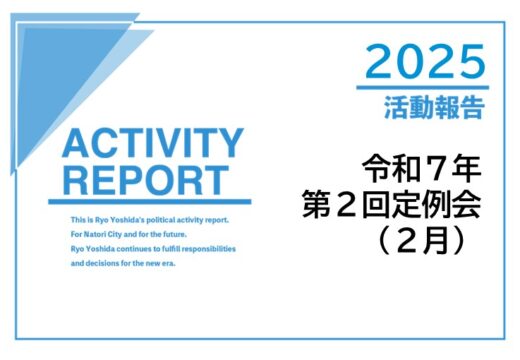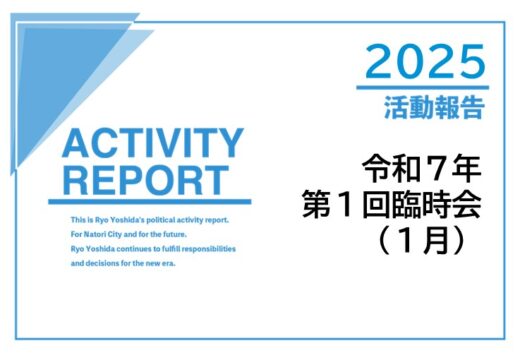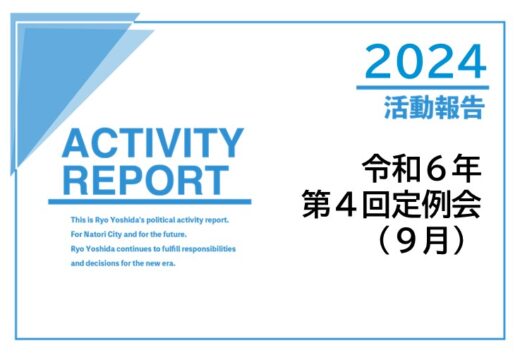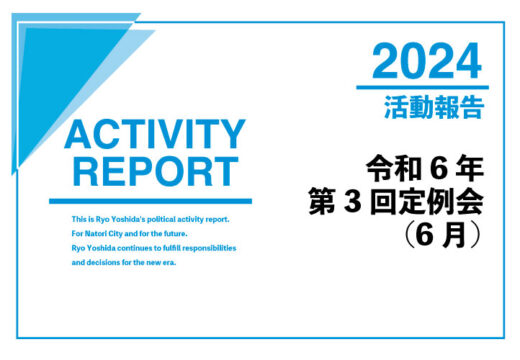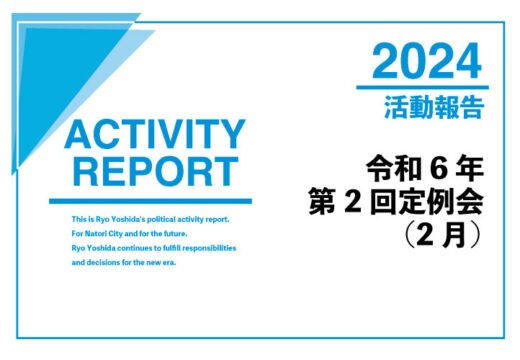本会議
(議案第99号 名取市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例)
吉田
今回の改正によって資格の要件が学校教育法の規定から教育職員免許法の規定に変わりましたが、具体的に要件がどのように変わるのか、その変化によって資格を失うなど影響を受ける方は市内にいるのかどうか確認したいと思います。
こども支援課長
今回の改正は資格要件をはっきりさせたということになります。今までは、免許状を更新していない場合、放課後児童支援員に採用できるかどうか判断が難しかったのですが、要件が明確になったことで放課後児童支援員として採用しやすくなりました。
また、市内に影響を受ける方がいるかどうかということですが、ほとんどいないのではないかと考えております。
吉田
ほとんどいないということですが、要件が明確になったということは、今後募集においてはグレーなところがなくなって、よりわかりやすく募集を行えるため、事業そのものは進みやすくなると捉えてよろしいのでしょうか。
こども支援課長
お見込みのとおりです。
一般質問
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長より発言のお許しをいただきましたので、通告に従いまして私の一般質問を行わせていただきます。
初めに、大項目1 異常高温への対策についてお伺いいたします。
ことしの夏はこれまでに経験したことのない異常な暑さでした。気象庁のまとめによると、35度以上の猛暑日となった地点は全国で延べ6,479カ所に上り、全国202地点で史上最高気温を観測したとのことです。東日本では、6月から8月までの平均気温が平年差プラス1.7度で、過去最高となりました。気温の上昇は地球規模で進んでいると見られ、根本的な問題解決のためには国際社会の強い連携が不可欠であると言われています。そうした広い視野で問題を捉えることも必要ですが、現に市民の健康にとって大きな脅威となっている異常高温に対し、行政として取り組んでいかなければならない課題があると考えます。
総務省消防庁のまとめによりますと、平成30年の全国における熱中症による救急搬送人員数は、6月が5,269人で前の年より1,788人の増、7月が5万4,220人で同じく2万7,518人の増となっています。また、死亡者数は6月が5名、7月が133名で、7月は調査開始以来最多となりました。
そこで、本市の状況を確認したいと思います。小項目1 今夏の本市における、熱中症が原因と見られる搬送者、重症者及び死亡者の数を市長にお伺いいたします。
市長
今夏の本市での熱中症またはその疑いのある傷病者の救急搬送人員数は、8月31日現在91名で、搬送医療機関の医師による初診時診断結果にあっては、軽症60名、中等症29名、重症2名です。
吉田
8月31日までに91名という人数でした。この数は、前年度の数値や前年度までの平均値などに比べてどのような変化があると言えるでしょうか。
市長
平成29年の5月1日から8月31日までで搬送人員が17名ですから、非常にふえており、災害レベルの暑さであったと捉えております。
吉田
約5倍と非常にふえていて、市長から災害レベルという言葉がありました。それについては後で触れますが、次に移りまして、指定避難所の高温対策についてお伺いいたします。
本市には33カ所の指定避難所があり、その大部分が市で所有、管理する建物です。名取市地域防災計画には、大規模災害が発生した際の避難収容対策が盛り込まれており、市は避難所において暑さ寒さ対策としての空調の整備に努めると明記されています。通常の暑さ寒さであれば、扇風機やストーブなどで対応できます。しかし、ことしの夏のような異常な猛暑であれば、例えば公民館のホールや体育館で避難生活を送ることは命にかかわると思われます。30度を超えるような日は、直射日光の当たらない体育館の屋内でさえ、1時間も居続けると危険を感じます。大規模災害はいつ発生するかわかりません。東日本大震災は寒さが厳しい時期でしたが、もしあのような大災害が猛暑の季節に重なっていたとすると、避難所で熱中症が重症化する方や熱中症によって命を落とす方が出てもおかしくなかったはずです。
そこで、小項目2 避難所に指定されている市の施設に空調機器の設置を拡充すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
指定避難所に指定されている市の施設については、学校の保健室や公民館の研修室など、施設内の一部に空調機器が設置されていますが、学校の屋内体育施設や公民館のホールなど、避難場所として主に使用される箇所については現状では空調機器が設置されておりません。
以上のことから、現状での猛暑時の避難所での対応といたしましては、乳幼児や高齢者の方々を中心とした空調機器が必要とされる方々に空調機器が設置された箇所を使用していただき、災害による二次的な健康被害を防止したいと考えているところです。
また、今後の屋内体育施設等への空調機器の設置については、避難所での生活を想定すると、設置が望ましいものとは捉えていますが、施設内の他の箇所についても空調機器が設置されていない中、それら施設内のどの箇所に優先的に空調機器を設置していくかについては、主に平時の利用を想定しながら拡充の検討を行わざるを得ないものと捉えております。
吉田
市長の昨日の御答弁がきょうの新聞に載っていまして、市内の全小中学校の普通教室へ、来年夏までに10億円以上かけて空調設備を設置するということでした。学校の普通教室も、本当に極限状態の中では避難所として使われる場合もあると思いますが、そういったことも含めて、学校における避難所としての考え方の中で、空調設備をそれ以外のところにもう少し拡充することについては全く検討しないということでよろしいのですか。
市長
まず避難所として避難者を受け入れること、そしていろいろと工夫しながら二次的な健康被害を防ぐことが大切です。同時に、学校としての機能を一日も早く復帰させることも重要だと思います。
特に屋内体育施設への空調設備の設置となれば、それはそれでまた非常に大きな財源が必要になりますので、やはり市単独で取り組める状況ではないのではないかと思います。そうしたことについては、後ほど出てくる質問にもあると思いますが、やはり国レベルで対応を一緒に考えていただかなければいけない事態だと思っております。
吉田
もちろん、子供たちの学習環境に支障を来さないようできる限り心がけなければなりませんので、災害が起きた場合でも、エアコンがついている部屋を避難場所とすることは非常に難しいと思います。ただ、これは次の補正予算の審議の中で恐らく進めていくと思いますが、教室に設置して体育館に設置しないということは、子供たちが教室の中で快適な授業を行い、体育館に移動して運動するとなったときに、温度差によって体調を崩す子供が出てくることも考えられます。冷房症や冷房病と言われると思いますが、そのようなことも考えると、体育館こそ運動で非常に熱が上がる施設ですので、お金がかかるのはわかりますが、今回10億円の予算を措置するということですから、その流れの中で検討していただきたいと思います。
次に移ります。今度は異常高温そのものへの対処についてです。
ことしは天気予報で、猛暑への対策として、水分や塩分を小まめにとることや、エアコンのある室内で過ごすことなどの呼びかけをたびたび耳にいたしました。水分や塩分の補給は自宅でもできますが、エアコンは費用が高額であり、また特定の季節にしか使わないので、家庭での設置は後回しにされがちです。また、エアコンの設置工事は業者が1日に施工できる件数に限りがあるため、繁忙期ともなれば購入から設置まで1カ月も待たされることで、断念するケースもあります。これらの理由から、エアコンの設置を見送ったり設置できない状況にある世帯、また、エアコンがあっても、電気代を心配して使用を避ける世帯は決して少なくないと思われます。
気象庁はことしの7月23日、連日の猛暑を受けて異例の会見を開きました。40度前後の暑さは、これまで経験したことのない、命に危険があるような暑さ、そしてまた一つの災害と認識していると伝えております。この発信は、国や自治体に対し、異常高温を災害として捉え、必要な対策を求めているものと受けとめられると私は思います。災害対策基本法には、災害の定義として、防風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りが挙げられています。そして、その他の異常な自然現象という文言もありますが、ことしのような猛暑はまさにこの異常な自然現象に当たると考えるべきではないでしょうか。
名取市地域防災計画に目を向けると、地震災害対策、津波災害対策、風水害等災害対策の3編で構成されており、異常高温は対策を講ずべき災害としては位置づけられていません。これは本市に限ったことではなく、恐らくほとんど全ての自治体で同様であると思います。災害対策基本法第24条には、市町村防災会議は、毎年、市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときはこれを修正しなければならないとの規定があります。
そこで、小項目3 名取市地域防災計画に、高温に対する対策を盛り込む修正を検討すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
市町村が定める地域防災計画については、災害対策基本法第42条の規定において、内閣府に置かれた中央防災会議が作成する防災基本計画に基づき作成することと定められています。
また、中央防災会議が定める防災基本計画は、我が国において防災上必要と思料される諸施策の基本を、国、公共機関、地方公共団体、事業者、住民それぞれの役割を明らかにしながら定めるとともに、防災業務計画及び地域防災計画において重点を置くべき事項の指針を示すことにより、我が国の災害に対処する能力の増強を図ることを目的として作成されている計画です。
議員御質問の高温対策については、この防災基本計画上に記載がなく、国において、高温を災害対策基本法上の災害として捉えた計画が定められていないことから、これまで名取市地域防災計画にも盛り込んできませんでしたが、今後、市長会等を通じ、国にそのような視点も盛り込むよう働きかけていきたいと考えております。
吉田
国への働きかけはもちろんできますが、国の取り組みを待って、国が決めたら市町村がやるのでは地方自治ではないと思います。ことし、本市で実際にこのような異常高温、今までで最高気温を記録したわけで、救急車で運ばれた方も非常にふえて、もしかするとその中に亡くなった方もいるかもしれない。このような状況を見れば、国の動きを待っているだけでは遅いと思います。
市長がおっしゃったように、災害対策基本法には防災基本計画に基づきとありますが、大事なのはそこではなく、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画または当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであってはならないという部分ではないかと思います。本市で独自の猛暑に対する対策、避難計画等をつくったとして、それが県の防災計画に抵触するものでなければ、これはその不足を補完するということで、かえって進めていくべきものと思うのですが、それはできないのですか。
市長
まさに、今、議員御指摘の災害対策基本法第42条で、「防災基本計画に基づき」という部分、そして「都道府県地域防災計画に抵触するものであってはならない」という文言をどう読むかということになるわけですが、基本的には、この部分があるので、まず国から指針も含めて示してもらう必要がある。ただ、こうした動きについてはやはり急を要すると思いますので、早速、さまざまな機会を通じて働きかけをしていきたいと考えております。
ただ、本市としての計画にのらなければ対応しないのかということはまた別だと思います。教育委員会でも指針をつくり、温度と湿度と輻射熱をはかる機械を現場に配備していますし、そうした基本的にとれる対応を行いながら、計画の整備についても、国、県に働きかけながら同時進行で進めていきたいと考えております。
吉田
熱中症にかかるのは温度計があるところだけではありません。御自宅で、特に夜間、熱帯夜のときに体調を崩して運ばれる方がふえているわけです。ですから、エアコンがない家庭はまだたくさんあるわけで、どこにその人たちの逃げ場があるのかといったときに、夜中はショッピングセンターも開いていませんし、まさかコンビニに夜中に入り浸るわけにいきませんから、逃げ場がないのです。
しかし、市には、和室などにエアコンが設置されている公民館があります。そのような場所に避難できるように、名取市地域防災業務計画の今申し上げた3編の中から応用できる部分を抜粋して、異常高温や猛暑に対するものとしてつくることは、皆さんの力だったら十分できると考えますが、いかがでしょうか。
市長
具体的な対応の中身について進めていくことはそのとおりですが、第42条の防災基本計画に基づきと、抵触してはならないということもありますので、そうした文言を具体的に盛り込むことについては、まず、やはり国が災害レベルの暑さに対してこのようなスタンスで臨むという部分を示すべきだろうと考えておりまして、そのことについてはしっかりと働きかけをしていきたいと考えています。
吉田
国がそれをつくるのにまた一、二年かかり、それをもとに市で検討して一、二年かかる。そうしている間にも失われる命があるかもしれません。やはり私は、そこは国の動きを待つのではなく、進んで自主的に動くべきだと思いますが、認識が違うようですので、この点については以上にしたいと思います。
次に移ります。大項目2 隣接自治体との連携についてお伺いいたします。
山田市長が就任されてから2年が経過しました。市長選の前後、多くの市民が山田司郎さんなら名取を変えてくれるのではないかという期待感を抱いていたことは、私も個人的な政治活動において何度も実感させられました。選挙公約とされた復興公営住宅の内陸部での建設、ナスパの再開、学校給食の無償化、そして仙台市地下鉄の南進などは、どれ一つとっても実現は困難をきわめるものですが、山田司郎さんならやってくれるかもしれないと多くの市民が希望を託したわけです。
復興住宅の件で市長が努力された経緯については、結果は残念ではありましたが、市民もしっかりと受けとめてくれているものと私は捉えております。しかし、それ以外の公約については、ごみの最終処分場の引き受け以外、ほとんど進展が見えません。進展しているのかいないのか、その経緯が表に出てこない状況です。市長の選挙公約について、これまでに質問を行った議員もいます。その際の市長の御答弁から、実現への展望、ビジョンが見えた方はいなかったと思います。私にも見えませんでした。就任から2年間、市長は公約の実現に向けて必死に駆け回ってこられたと思います。任期4年の折り返し地点に到達した今、闇の中にあって見えていない経過を市民に対し説明していただきたいと思います。
本日は仙台市地下鉄の延伸について取り上げます。お断りしておきますが、私は、地下鉄延伸に賛成か反対か以前に、非常に難しい、ほぼ不可能であろうという認識です。しかし、市長が公約実現のために本気で働きたいと思っているのであれば、それを議論の土俵に上げるために提案していきたいと考えます。
まずは小項目1 市長就任から2年間、仙台市地下鉄の名取延伸という選挙公約を実現するために、仙台市の前市長及び現市長との間で行ってきた情報交流や協議の経過を市長にお伺いいたします。
市長
仙台市地下鉄の名取延伸という選挙公約を実現するため、仙台市の現市長に対し、事務レベルでの意見交換の場を設けていただけないか打診をしております。
現在、宮城県と仙台市が中心となって、仙台都市圏のパーソントリップ調査の分析を進めているところであり、この成果を踏まえながら、まずは本市と仙台市との交通体系のあり方について、事務レベルによる情報交換、意見交換の場を設定し、調査、研究を進めていきたいと考えております。
吉田
仙台市長に対して事務レベルでの情報交換を打診しているという話ですが、実際にいつごろから打診は始まっているのか。そして、その後、現在に至るまでの仙台市側からの回答、あるいはいつまでに回答するという見通しがありましたら、お聞かせいただきたいと思います。
市長
事務レベルによる情報交換の場は、パーソントリップ調査検討会の前後で設定することとして打ち合わせは終了しています。先日、仙台市側から連絡があり、近々情報交換を行う予定となっております。
吉田
パーソントリップ調査とは、私も不勉強で今初めて耳にしたのですが、宮城県も入っての調査となると、仙台市地下鉄については、今後、宮城県、仙台市、そして名取市の3者の協議の中で市長の公約が進んでいくと捉えてよろしいのですか。
市長
仙台都市圏のパーソントリップ調査は、仙台市の広域の交通体系のあり方について調査するものであり、必ずしも地下鉄だけを対象とした調査ではありません。
吉田
仙台都市圏の広域の交通体系とすると、本市も含まれると思います。実際に都市圏ということで調査がこれから進んでいくということですが、パーソントリップ調査そのものはどのような過程で今後進んでいくのか。例えばどのぐらいの頻度で開かれるのか、また結果はいつごろ出るのかなど、現時点でわかっていることがあればお聞きしたいと思います。
政策企画課長
パーソントリップ調査については、現時点では平成32年度末を目途に分析を進めていくと伺っています。その分析を進める中で調査結果についての知見が得られるものですから、そういったタイミングを捉えて、まずは仙台都市圏ということではありますが、仙台市と名取市間の人の動きの調査結果を踏まえて、総合的な交通体系としてどのような取り組みが可能かといった意見交換から始めていきたいと考えております。
吉田
市長が先ほどおっしゃったように、このパーソントリップ調査は地下鉄だけを対象にしたものではなく、その結果については、平成31年度までに分析等を行うので少し先になりますが、見通すことは難しいと思います。もちろんこうした取り組みは仙台市の協力なしには進めていけないと思いますが、仙台市とどのような形で連携していくのか、どこまで本市が管理し、どこまでが仙台市という具体的な線引きは非常に難しいと思うのです。そのことも考えていかなければならないのですが、その前に過去の御答弁の真意についてここで確認させていただきたいと思います。
平成28年9月定例会の一般質問で、私は市長に対して自主的な市町村合併に移るべきだ、つまり仙台市との合併をもう一度検討すべきであると申し上げました。その質問に対し市長は、当面は本市独自により持続・発展し続けるまちづくりを目指していきたい、自主的な市町村合併の検討ではなく、広域連携の強化で対応していきたいと答弁されました。この独自でのまちづくりとはどこまでを独自というのかまずお聞きしたいのですが、本当に純粋な意味で独自といえば、本市が全て単独で地下鉄をつくるとも捉えられ、それは予算上非常に厳しく難しいのではないか、無理ではないかと思います。そのあたりの整理をしていきたいと思います。
小項目2 平成28年第5回定例会における、本市が独自により持続・発展し続けるまちづくりを目指すという市長の答弁は、地下鉄の名取延伸という公約に矛盾すると捉えるが、市長の真意をお伺いいたします。
市長
本市独自により持続・発展し続けるまちづくりを目指すことが、地下鉄の名取延伸という公約に矛盾するのではないかという御指摘ですが、私はそのようには捉えておりません。
そもそも公約に掲げました地下鉄の名取延伸については、これまでも答弁申し上げてきましたとおり、大都市仙台市に隣接しているという本市にとっての大きなメリットを生かすためにも、仙台市との交通面での連携は重要であり、その実現に向けては、広域連携の強化により取り組んでいきたいと考えたものでありまして、仙台市との合併を前提に掲げたものではありません。
吉田
相変わらず同じ内容の答弁で、そのようにおっしゃるということはわかっております。ただ、独自にというところにやはりこだわるとすれば、広域連携のレベルがどの程度なのか、もう少し市長としてはっきりしておかなければならないと思います。パーソントリップ調査の結果が出て、さらに先にどうつなげていくかということになります。仙台市が名取市と強力に連携して地下鉄を共有していく、そのような流れになるのだったら、本市としても大変ありがたいと思いますが、もし仙台市が、地下鉄を延ばしたところで採算はとれないでしょう、それはやはり無理ですとなったとき、市長はどのような判断をしようと考えておられますか。
市長
仮定の話で非常にお答えしづらいのですが、大事なことは、名取市民にとって例えば仙台市に行きやすくなることだけではなく、仙台市民にとっても名取市に来るのに便利であるなど、仙台市側にとってのメリットをどのように生み出し、お伝えしていくかということに尽きると思います。
吉田
観光客の話も先ほどありました。本市に観光客が来ないというのも同じかと思いますが、やはり人の流れはどうしても大都市に向かっていく。そして、本市はベッドタウンとしての利便性をもっと深めていく。さまざまな仕事があって、いろいろと考え方はありますが、最大公約数的に市民の生活をより豊かにしていくためには、ベッドタウンという視点は決して度外視できないと思うのです。ですから、仙台市からどう流れてくるかということももちろん一つの考え方としてあると思いますが、私が聞きたかったのはそのことではなく、あくまで想定ですが、仙台市の回答がもし厳しいものだったときに、市長はそれでもやはり連携しましょうと呼びかけるのか、あるいは、では本市単独で行うという立場をとるのか、お考えをお聞きしたいと思います。
市長
まず、いつの時点でどのような状況の延伸はお断りという仮説の話なのかわかりませんが、仙台市の地下鉄ですので、名取市が単独で整備をすることは不可能だと思っております。
吉田
もちろんそのとおりです。ですから、私が申し上げたいのは、いずれにしても地下鉄を延ばすためには連携しなければならない。連携するといっても、仙台市が調査の結果を踏まえて、本市との人の交流は確かにあるが、今後、地下鉄の本市までの延伸が採算性の点で厳しいという判断になった場合、本市に対して、ごめんなさい、やはり難しいですよとなることは考えられると思うのです。そのときに、本市は連携をどのような形で仙台市に呼びかけるのか、このことを市長は次の一手として今どのように捉えているのか。今、目の前のこととしてはもちろん仙台市と協議していくというのはわかりますが、その結果によってもしだめだった場合、仙台市との連携の形をどのように変えて深めていくのか、そのあたりのビジョンをお示しいただきたいと思います。
市長
まちづくりは非常に長い時間をかけて取り組んでいく部分もあるかと思います。早急に対応しなければいけない部分と、時間をかけてじっくりつくっていくまちづくりがあると思うのですが、私はこの問題については後者だろうと思っています。ですので、今回、パーソントリップ調査を一つの土台にしての意見交換の場の設置は一つのアプローチであり、このことがだめだったから全てだめだということではないと思っています。したがって、いわゆるアプローチの一つとして今回それに取り組む。ただ、遠い先の名取市と仙台都市圏を考えたときには、やはり地下鉄の延伸も含めた、広域での、圏域での交通体系のあり方を見直す必要がいずれあるだろうということで、そのことをお互いに理解を深めながら、徐々に近づいていければいいのではないかと思っております。
吉田
長い時間がかかるのは当然です。まだ議論すら始まっていないのですから、長い時間がかかるのはわかりますが、その長い時間、市長はよく20年後、50年後という話を出しますが、そのころにこの地域はどうなっているのか、それは後ほど議論したいと思います。
今飛ばしそうになってしまったのですが、小項目3を確認させていただきたいと思います。地下鉄延伸を実現するためにはどのような手法があるのか、これまでに進めてきた調査の成果を市民に示すべきについて市長の御見解をお伺いいたします。
市長
先ほどの答弁でも触れているとおり、仙台市側と事務レベルによる意見交換の場の設定について打診を行っている段階ですので、地下鉄延伸を実現するための手法について具体的な調査は行っていないところです。仙台市側との事務レベルの意見交換を踏まえ、必要となる調査について検討を行っていきたいと考えております。
吉田
結局、進んでいるのですか。市長としては進んでいるという認識と捉えてよろしいのかどうか、この2年間の地下鉄に関する御自身の評価をお聞きしたいと思います。
市長
長期的な視点で取り組んでいくべき課題で、ただ本市には絶対に必要な課題だと思っており、それに向けて、一歩ずつではありますが、歩みを進めていると捉えております。
吉田
広域連携とよく言われますが、広域連携で公営企業の事業ができるのかどうか。第三セクターという方法もあるかもしれませんが、その点についての研究等は庁内ではどの程度行っているのか、そのあたりをもう少し聞きたかったのですが、もしあればで結構です。
市長
まず、例えば地下鉄を延伸した際、本市がその運営にかかわるかというと、そういった形ではないと捉えていますし、公共交通も含めて全体の交通体系のあり方について検討を始めようというところで、その意味では、議員御指摘のような具体の中身についてはまだ検討を進めておりません。
吉田
例えば大阪市の場合は、地下鉄は民営化されて、市外まで線路が延びています。一方、名古屋市や札幌市などの地下鉄はその自治体の中だけで完結しています。市外にまで出ていこうとなったとき、国土交通省の認可か許可かわかりませんが、本当に認められるかどうか、それに対して本市としてきちんと用意しておかなければ仙台市と議論すら始められません。こちらから求めているわけですから、仙台市側が調べることではありません。したがって、本当に実現性があるのかどうか、市の境界を越えて地下鉄を呼ぶことができるかどうか、それらの検討は庁内で行わないのですか。
市長
議員御指摘の点についてはまさに必要だろうと思っています。ただ、今、手法としてはまずパーソントリップ調査での意見交換からアプローチを行うということで、まだ緒につくところです。必要な調査については、議員御指摘の面も含めて進めていきたいと考えております。
吉田
平成31年度にはパーソントリップ調査が終わるという話でしたから、それほど時間はないわけです。やはり本市としてすぐ次の議論に移れるような万全の体制をとっておかないと、せっかくのチャンスも逃してしまうかもしれません。お願いしたいと思います。
次に移りまして、今後20年先、50年先の日本がどうなっているのか。地下鉄の議論から離れますが、通告書にも書きましたように、総務省の自治体戦略2040構想研究会が報告書を出しました。この報告書を受けて総理大臣から第32次地方制度調査会に諮問が行われたわけですが、これを読んで本市の未来を考えていきたいと思います。先ほど取り上げた議員もおられましたが、この中には西暦2040年ごろには自治体の職員を半分にまで減らすというビジョンも書かれています。恐らく市長も読んでおられると思いますので、その前提で話を進めたいと思います。
この自治体戦略2040構想研究会が4月と7月の2回に分けて出した報告書は、人口減少下において満足度の高い人生と人間を尊重する社会をどう構築するかというテーマについて、自治体戦略の必要性、個別分野と自治体行政の課題、我が国の内政上の危機とその対応、自治体戦略の基本的考え方の4つの柱で構成されています。この中で、2040年ころにかけて迫り来る我が国の内政上の危機として、若者を吸収しながら老いていく東京圏と支え手を失う地方圏、標準的な人生設計の消滅による雇用・教育の機能不全、スポンジ化する都市と朽ち果てるインフラの3点が挙げられています。非常に衝撃的な内容です。人口減少が進み、我が国を取り巻く環境に不確実さが増す中でも、地方自治体が安定して持続可能な形で住民サービスを提供し続けることが必要と説かれております。
特に自治体の将来に大きくかかわる内容としては、第2次報告における新たな自治体行政の基本的考え方の中に、個々の市町村が行政のフルセット主義を排し、圏域単位での行政をスタンダードにし、戦略的に圏域内の都市機能等を守る必要があると示されています。さらに、都道府県と市町村の二層制を柔軟化し、それぞれの地域に応じ、都道府県と市町村の機能を結集した共通基盤の構築が必要などとも書かれております。これを要約すれば、たくさんある道路も橋も減らしましょう、インフラをどんどん縮小して、戦略的に縮んでいく、そのような内容を総務省では研究会で報告したということで、今後の地方制度調査会の議論が待たれますが、広域連携が公共施設の共同利用など緩やかな連携にとどまるのに対して、この研究会が提唱する圏域は、法律によって位置づけられた行政単位と見られています。医療施設や学校等の共同運営などを想定し、合理化のために統廃合を行うことも視野に入れています。研究会による報告の後、第32次地方制度調査会が平成30年7月5日に発足しました。急速に進む人口減少に対応した行政サービスのあり方についての調査、審議が進められていく中で、圏域を新行政単位とするかどうかが議論の柱の一つとなると見込まれています。
私自身はこの研究会の報告内容について、地方自治の充実に逆行するものであり、満足度の高い人生にも、人間を尊重する社会の構築にも結びつかないものと捉えております。いずれにしても、国によるこうした流れに一方的にのみ込まれるのではなく、自主的かつ主体的に将来のあり方を研究していくべきであると考えます。
小項目4 総務省の自治体戦略2040構想研究会による報告書には、日本が直面する未曾有の危機が示されている。本市でも、西暦2040年ごろに想定される課題について、隣接自治体との連携のあり方を中心に議論を始めるべきについて市長に御見解をお伺いいたします。
市長
総務省の自治体戦略2040構想研究会の報告書によれば、2040年には、団塊の世代及び団塊ジュニア世代が高齢者となる一方、20代の若者が年間100万人にも満たない状況となり、人口が集中する首都圏の高齢化、支え手を失う地方圏、インフラ維持の困難化などといった状況に直面する可能性があるとしています。
その上で、2040年ごろを見据えた新たな自治戦略の基本的な方向性として、スマート自治体への転換や新しい公共私の協力関係の構築、地方圏の圏域マネジメントと都道府県・市町村の二層制の柔軟化など、人口減少時代に即した枠組みへの転換が必要とされております。
このことについては、既に人口減少時代に突入している現状を踏まえると、予想できる将来像の一つであると捉えていますが、本市のみの課題というよりは隣接自治体も含めた国全体の課題ですので、それらの動きについて情報収集に努めていきたいと考えております。
吉田
先ほども申し上げましたが、本市が主体的に動くことが大事だと私は申し上げているのです。もちろん周辺自治体との連携などを全く度外視するということまで言っているわけではありませんが、本市が今置かれている地理的な環境、仙台市のベッドタウンであること、沿岸部にあること、そして仙台以南の地域自治体がいずれも人口減少、高齢化が進んでいる。その中で本市がどのような未来をこれから歩んでいくべきか、今議論しなければもう遅いわけです。
本市が広域で取り組んでいる亘理名取共立衛生処理組合、この2市2町の枠組みも、私は非常にメリットもあればデメリットもあると思います。特に、16議席の組合議会の議席を2市2町で4議席ずつ振り分けています。これまで組合の立ち上げからそのような経緯で来ていると伺っていますが、本市は人口が7万8,000人、一番小さい山元町は1万2,000人で、1票の格差で考えると6倍以上になります。つまり、単純計算で、ごみ処理、し尿処理については名取市民6人以上の声でやっと山元町民1人の声と等しいという考え方もできるわけです。また、分担金については本市は全体の4割以上を負担しています。
このような広域連携のあり方の現状、そして、本市は2040年ごろまで人口が増加すると見られていますが、岩沼市、亘理町、山元町は今後人口がますます減少していきます。そうした中でこの議会の構成等を市長は管理者としてどのように捉えているのか、お伺いしたいと思います。
議長
吉田議員、通告より広がっておりますので、注意して質問してください。別の角度でお願いします。
吉田
そのような県南の自治体とも今後連携をさらに深めなければならないかもしれないと申し上げているのです。圏域を国が法で定めたら、そこに本市が入るということ、そして、これは事実上の市町村の廃止ですから、それらを考えた場合、これから20年先に向かって、この枠組みが今後本当にこのままでいいのかどうか、やはり本市が主体的に今もう一度検討し直す。これは市長が判断するべきことではなく、議会の中の問題とも捉えられますが、やはりそこは名取市としての立場もあると思いますので、市長としても一つの考え方といったものを発信していく必要はあると捉えております。
では、最後の質問に移ります。本市の将来に関する具体的な選択肢についてお伺いいたします。
総務省の報告書からもわかるように、過疎化していく自治体を国はもはやお荷物としか見ていない。民間のシンクタンクの日本創成会議で示した消滅可能性自治体は全国に896あります。うち523の自治体は、2040年時点の人口が1万人未満で、消滅可能性が高いと言われています。こうしたお荷物を整理していかなければならない。しかし、市町村合併という言葉にはアレルギー反応を示す人がいる。だから、実質的に同じことを圏域という言葉に置きかえて、さらに法律による強制力まで持たせよう、今の国の姿勢は私にはそのように見えるわけです。
現在、政府が自治体に取り組ませている地方創生も、根本的な解決策にはなりません。自治体の間で人口を奪い合っても、全体の総数はふえるわけではありません。近年では、地方でも海外からの人材に労働力を依存する傾向は高まってきています。平成27年、外国人移住者の日本への流入は約39万人で、世界で4番目に多くなりました。外国人の移住に反対するわけではありませんが、人口問題によって今後活力がそがれていくと考えられている日本は、高度人材にとっては魅力の少ない国となっていきます。経済を移民に頼ることにより、余り望ましくない層の移民を大量に入れなければならないことにもなりかねないと思います。よって、人口が減少し少子高齢化が進んでも自立できるコンパクトな国を目指していかない限り、国民の幸せを守ることは難しいと思われます。
このように人口問題を国のレベルで俯瞰すれば、人口微増という状況で本市だけが安泰でいられるわけがありません。総務省の圏域構想については、本市も部外者でいられるわけではないことをしっかりと認識しておく必要があります。2040年ころに向けた選択肢は限られてきていると考えるべきです。
そこで、小項目5 急激な人口減少と高齢化への対処として、国は市町村に対し、圏域単位における行政へ転換を促していくものと思われる。将来も単独で市政運営を続けるのか、仙南地域の圏域に参加するのか、あるいは仙台市との合併を目指すのか、あらゆる可能性を排除せず、国の動向を注視しながら、本市が進むべき方向について比較検討を重ねるべきについて市長にお伺いいたします。
市長
先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、この問題に関しては、本市のみならず国全体の課題として捉えていますので、御指摘のとおり国の動向等を注視していきたいと考えておりますが、現時点において、圏域単位における行政がどのように進められるのかについては不透明なところが多く、構想段階にとどまるものと捉えていますので、比較検討を行うことまでは考えていないところです。
吉田
構想で終わればいいのです。しかし、ではほかにどのような手があるのか。2040年ごろ、日本の人口がどうなっているのか。先ほど市長も答弁されましたが、人口の予測はほとんど外れることがないのです。逆に、地方から都市への人口の流出の度合いは予測を上回るペースで速まっています。地方がますます人が減っている状況です。
こうした中で国が何もしないでいるということはあり得ませんし、一度総務省で時間をかけて一つの今後の戦略を立てた以上は、総理大臣に諮問はしますが、やはりその方向に進むということは前提として持っておかなければ、またその分余計に時間を無駄にしてしまう。地方制度調査会から最終的に答申が出るのは2020年ごろと言われていますから、あと2年かかります。この2年間に何もしないで現在の広域連携を続けていくのでしょうが、2020年にやはり圏域にしますよ、市も決断しなさいということになって、そこから検討を始めるのですか。それでは遅いのです。本市は自治体であって、国の下部組織ではありませんので、名取市として国の動きをしっかりと見きわめて、そしてあらゆる可能性を想定し、もちろん国が圏域を制度化することも想定に入れながら、このまま自治体単独でいいのか、圏域に入るのか、それとも別な道があるのか判断すべきだと思いますが、市長はそのような危機感は持っていないのでしょうか。
市長
自治体戦略2040構想研究会の報告書の捉え方だと思うのですが、構想として考え方が示された段階であり、これに対して国としての具体的な法整備の方向性も全く示されていない段階です。構想としては発表されましたが、では法整備をどうするか、具体の内容はまだ何もない状況ですので、これがもう少し具体化してくれば当然検討を始めなければいけない、そういう選択肢もあるかと思います。先ほども申し上げたとおり、一つの方向性としてそうしたことは考え得るものと考えています。ただ、具体的な法整備の手法や段取りなどが示されない現在において具体な検討を進めることについては、まだ時期尚早と考えております。
吉田
非常に悠長だと思います。刻一刻とこの日本の危機的な状況は迫っているのです。本市も決して部外者ではありません。例えば、今後、2040年に向けて本市が単独で市政運営を続けていくと考えても、地方交付税交付金も含めた国からの交付金が恐らくは今後減額されていく。そして、国庫負担金もありますが、使い道が決まっている国庫負担金でさえ今後縮小していく。なぜなら、2040年ごろには社会保障関連の費用が国全体で190兆円かかるという試算もあるのです。そうした中で、今の借金まみれの国の財政がどこまでもつかわからない。途中で多分だめになるのでしょうが、ならなかったとしても、地方に対する手当てがどんどん下げられていくのは避けられない状況にある。私のような素人でもそんなことはわかります。市役所にいるプロの皆さんなら当然危機感を持っていると思うのですが、市長はそういった危機感はないのですか。
市長
草刈りの話題もありましたが、少子高齢化によって行政が担うべき守備範囲が広くなり、逆に言うと行政としての負担がふえていくわけです。本市は人口がふえていますが、全体としては人口が減って税収が減ってくるであろう。その中で行政が果たすべき役割は割合としてふえてくることに関して、危機感を持っていない首長は誰もいないと思います。
ただ、この問題については、先ほどお話ししたとおりまだ構想段階ですので、具体の検討は差し控えたいと思いますが、将来にわたってどのように持続可能なまちをつくっていくのかということは、これはもう私に与えられた至上命題ですので、常にその視点は持っていきたい。今一番大事なことは、やはり変化にきちんと対応できる組織をつくっていくことだろうと思っております。この先どうなるかわからないというのは議員おっしゃったとおりで、その変化に具体的に的確に対応できる組織をつくっていくことも一つの方策だろうと思っております。また、まちづくりについては、平成32年度から11年間の長期総合計画、それは20年先、ちょうど2040年を見据えて計画を策定します。その第六次長期総合計画の中で、今考えられる独自のまちづくりについて方向性を示していきたいと考えております。
吉田
行政が担う役割がふえていくとおっしゃいましたが、構想の中では逆のことを言っています。公共私のベストミックスと言っていて、共とはほかのいろいろな団体、私とは個人で、いかにして公だけではなくそれらを活用していくのかということなのです。変化に対応できる組織とは、そもそもいろいろな前提を持つことができる組織だと思います。
そこでまた、申しわけありませんが、地下鉄の議論に戻りますが、仙台市の2040年ごろの人口はどうなっているかというと、100万人を割っているだろうという見込みが立てられています。恐らくそのとおりになるのではないか。宮城県内で富谷市と本市だけは人口増加が見込まれていますが、仙台市は100万人を割る。仙台市単独でも地下鉄の利用者が今後縮小すると考えられる中で、本市は、地下鉄を利用するだけではなく、それこそ一緒に運営していくという形で、仙台市との合併を一つの想定に入れておく。市長がおっしゃった変化に対応できる組織は、みずから変化に対応して行政の体制を大きく変え得るもので、仙台市という自治体と一緒になることもその変化の一つと考えられますが、これは変化と捉えてよろしいでしょうか。
市長
これは何度も答弁申し上げているとおり、本市としては、現状は独自のまちづくり、名取市として主体的にまちをつくっていきたいと考えているところです。この先、世の中がどう変化するかわからないということで言えば、例えばAIやロボティクスなど、今、地下鉄は運転手が運転していますが、そうした部分ももしかしたら変わってくるかもしれない。そのようなこともまだ予測がつかない未来があるわけなので、それらに対して的確に対応できるような組織づくりを行っていきたいと考えております。
吉田
鉄道などの自動運転は既に始まっていますので、現在のことではなくもっと先を見てもらいたいと思いますが、組織なのです。今申し上げたように、人口問題や財政問題については、今後国で市町村をがんじがらめにするようなことが見込まれますので、そうしたとき、20年後、誰もが幸せを感じられるようなまちにしていくためには、やはり日本にとって、そして地方自治にとっての非常に重要な分岐点ということで御理解いただきたいと思います。以上で終わります。
本会議
(議案第92号 名取市名誉市民条例)
吉田
第1条において、対象者を「郷土の誇りとして市民から深く尊敬されているもの」としていますが、この「もの」という部分には、個人はもちろんだと思いますが、団体も含まれるのかどうか。もし含まれるとしたら、どういう団体を想定されているのかお伺いいたします。
政策企画課長
法令の用語として、単純に「もの」と平仮名で表記して指した場合は、今議員御指摘のように自然人と法人とを含むとされているところです。ただ、この第1条における「もの」の使い方については、いわゆる英語の関係代名詞的な用法となっており、「公共の福祉」というところから「尊敬されている」というところまでが、最初にある「市民又は市に縁の深い者」というところにかかるということで、この「市民又は市に縁の深い者」の中でそういった方に限定するという用法として使っているものと御理解いただければと思います。
吉田
今回この条例を制定するに当たって、宮城県内の各自治体について調査を行い、名取市以外は皆この条例を定めているというような御説明をいただきました。本市で今回、市制施行60周年を一つの契機としてということでしたが、これまで市内で、こういう条例があったほうがいいとか、あるいはここに書かれているような非常に顕著な功績を残した方がいたのに、そういう方を名誉市民にすることができなくて市が非常に残念な思いをしたというような経緯はあったのでしょうか。
政策企画課長
議会においても、これまで幾度か議員から名誉市民条例を制定してはどうかといった御質問をいただいているところです。そういったことから、一般的には名誉市民条例を制定すべきではないかという議論があると捉えているところです。
ただ、一般の市民の方から、この方を名誉市民に推戴してはどうかといった具体的な話はいただいていないところですし、これまでの議会答弁においても、そういった方が出れば条例を制定するというお答えをしているところですので、現時点における認識としては、具体的な提案という形ではいただいていないものと捉えております。
吉田
「公共の福祉の増進又は学術、技芸その他の文化の振興に著しく貢献し」ということですが、表彰条例のような具体的な基準は設けないということで、ここで大事になってくるのが「郷土の誇りとして市民から深く尊敬されている」という部分かと思います。ただ、尊敬というのは心の問題ですので、これこそ数値などではかることができないものかと思いますが、ここにあえて「深く尊敬される」という、尊敬という言葉を盛り込んだ理由をお伺いしたいと思います。
政策企画課長
尊敬の念というのは確かに内面のことですので、具体的に基準を設けるのは難しいことかと思いますし、それを評価するのもなかなか難しいかと思います。ただ、名誉市民条例については、市民の方からも広く尊敬される方こそが贈られるにふさわしい方というような理念をもって定めているところですので、具体的に尊敬されるということがどういうことかについては捉えていない、理念の中での話と御理解いただければと思います。
吉田
こういう各自治体の名誉市民や県民栄誉賞のようなもの、あるいは国でも国民栄誉賞などがありますが、人によっては、自分自身がこれまで一生懸命取り組んできたこととはまた別に、政治に利用されると捉える方もいて、辞退する方も実際にいるわけです。この名誉市民条例の条文の中には辞退の規定がありませんが、もし名誉市民の称号を贈りたいといったときに辞退をしたいという場合、どのようにそれを扱われるのかお伺いしたいと思います。
政策企画課長
実際に議会に議案を出す際にあらかじめ内部の表彰審査会での審査を経ると、先ほど御説明申し上げました。その際には、該当する方にあらかじめ受ける意思があるかどうかも含めて確認させていただいた上で、表彰審査会での審査に付したいと考えております。提案する前に御本人の意思は確認させていただいて、それを尊重したいということです。
吉田
この条例が可決されたと仮定して、大変功績のある方が市から出たと。いざ条例に基づいて名誉市民の称号を授与すると。そこまで仮定したとします。その際、名取市でこういう方が名誉市民に選ばれたということで、マスコミなども大変盛り上がるかと思いますが、実際に名誉市民になった方がマスコミにいろいろ報じられたりしていくことについては、市としては特に問題ないのか、逆にどんどん報じてもらいたいのか、どのような態度でお考えでしょうか。
政策企画課長
マスコミ等での報道に対して、市から御意見を申し上げる立場にはないのではないかと捉えております。ただ、こういった功績については、条例の中でも、広く市民にお伝えするということにしておりますので、そういったことについてこちらが積極的に制限をすることは特に考えていないところです。
吉田
きのうも、西田敏行さんが福島県の県民栄誉賞を受賞して大々的に報じられていました。そのテレビに映る場面では、必ず、県だったら知事、市だったら市長の姿があります。言ってみればそういう首長の出番が多くなって露出度がふえてくる、そのことに名誉市民などが利用されているのではないかと捉えると少しうがち過ぎかもしれませんが、ただ、やり方としては、実際にそういう形で利用することも可能なわけです。ですから、例えばこういう名誉市民を本当に市民全体で祝っていくのであれば、市長としては一緒にテレビに映るのを自粛するとか、そういうところの名取市としての遠慮深さも必要ではないかと思いますが、そのあたりは何かお考えではないのでしょうか。
政策企画課長
私の立場として今お答えする立場にはないと考えていますが、今御質疑にあったようなことや先ほどの政治的、宗教的というところも含めて、当然ながら審査等の過程で配慮していきたいと考えております。ただ、そういった方については事前に報道されて市民の方が広く知るところになると思いますので、それとの関係の中でそういった露出がふえることについてはある意味避けられないところもあるかと思いますし、あくまで名誉市民の称号を贈ることを決定するのは市長ということにしておりますので、市長からその名誉市民の方に顕彰状を贈る場面で一緒に報道されることについては十分考えられることと捉えております。
(議案第93号 名取市子育て支援拠点施設条例)
吉田
本当は小さい子供連れの保護者の方が子供を預けて買い物ができれば一番よいのでしょうが、先ほどの御答弁では、採光がとれないということで、そういう規制がネックになって一時預かりができないということでした。第4条第1号から第5号で挙げられている業務で、この施設を市内の大型ショッピングモールに置くことの一番の目玉についてはどのように捉えていらっしゃるのでしょうか。
こども支援課長
今回、商業施設の中に設置するということで、市内外からの利用が相当見込まれます。その中で、保護者同士、乳幼児同士が交流できることが大きな目玉かなと考えております。
吉田
もちろん多くの不特定の方が交流して、そこからお互いに子育てのことについて悩みを話したりとか、そういう効果も出てくるかと思いますが、それは何もこの子育て支援拠点施設に限ったことでもなく、いろいろなレベルで行われていると思います。それを目玉としてこの施設を設置していくことについては、少し薄いというか、もう少し何か、ここだからこそ来てよかったとか利用したいというものをつけていくことが必要ではないかと思います。何かそのあたり、指定管理ということもあろうかと思いますが、今後施設の運用を始めてからより魅力を高めていくために、何か今後の方向性のようなものを考えていればお聞きしたいと思います。
こども支援課長
中心となるのは交流ということで先ほど申し上げましたが、その中で情報の収集・発信、相談も業務の中に設けております。この場所でさまざまな情報を発信し、そして市内のほかの子育て支援拠点施設と連携して事業を進めていきたいと考えております。
吉田
市長からの先ほどの答弁の中で、市内の子育てをしている方から、こういう気軽に相談できる施設が市内にないという話があったということでしたが、保護者の方同士が交流するとなれば、別にそこら辺のファミリーレストランに行ってだって、交流だけと見ればできると思います。ただ、そこで、なぜイオンモール名取につくらなければいけないかといったときに、いろいろな方が集まってくるというのが1つかと思います。また、第4条第2号には子育てに係る相談に関する業務と載っていますが、相談を受ける以上は、その内容に対して的確にアドバイスをしていく必要があろうかと思います。実際にこの相談を受ける方、相談に応じる方は何か特殊な知識や資格を持っている人ということでお考えでしょうか。
こども支援課長
相談を受ける方の資格ですが、施設には子育て等に精通した方を配置することになっておりますので、その方がまず相談を受けることになります。 なお、専門的または援助が必要な相談となった場合には、専門機関につないでいきたいと考えております。
吉田
子育てに精通しているということで、かなり経験豊富な方を配置することになろうかと思います。専門的なことになれば別の機関につなぐともおっしゃいましたが、その場でできるだけ的確なアドバイスができるにこしたことはありませんので、そうしたことを考えたときに、もう少し具体的に、どのような経歴や資格を持っている方が相談に応じる方になるのがよいと捉えていらっしゃるのでしょうか。
こども支援課長
職員配置に当たっての具体的な資格ですが、保育士や幼稚園教諭の資格等が考えられますが、今後、募集要項の中で具体的に規定していきたいと考えております。
(議案第103号 工事請負契約の締結)
吉田
同じく資料3のトイレのことでお聞きします。管理についてですが、冬場は気温が下がって、海風などもある地域ですから非常に寒くなろうかと思いますが、そういう冬場のトイレの水道の凍結対策についてはどのようにお考えなのでしょうか。
復興区画整理課長
屋外のトイレですので、凍結防止の対策として配管周りに電熱線を設置して対応しております。
吉田
もう1点ですが、この周辺は居住が制限されている地域なので、夜になると人通りがほとんどなくなるかと思います。そういう夜間の防犯対策の面でも、トイレは死角にもなるわけなので、そこに誰かが住みついたりすることはないと思いますが、夜間も開放したままでおくのか、あるいは施錠するのかという検討などがあるのかどうか、お伺いしたいと思います。
復興区画整理課長
夜間については、施錠するのではなく、開放するような形をとらせていただきます。
(議案第106号 平成30年度名取市一般会計補正予算)
吉田
12、13ページ、2款1項1目一般管理費の旅費が317万5,000円ということで少し金額が大きいと感じたのですが、この内容についてお伺いいたします。
総務課長
317万5,000円のうち、総務課として263万9,000円分を計上しております。中身については、6月18日に発生した大阪府北部地震で被害を受けた大阪府高槻市への応援職員の派遣に係る旅費となっております。
政策企画課長
政策企画課で残る53万6,000円を計上しております。内容としては、大阪府北部地震、西日本豪雨に係る二役の見舞金持参に係る旅費、それから、宮城インバウンドDMO推進協議会における台湾のトップセールスの旅費ということで3点上げております。
吉田
そのそれぞれの応援や派遣の人数についてお伺いいたします。
総務課長
大阪府高槻市への応援の職員数ですが、1班4人編成で4班、計16名を派遣しております。
政策企画課長
大阪府北部地震並びに西日本豪雨については、二役1名と随行1名の合わせて2名ずつ、それから、宮城インバウンドDMOについては市長1名の旅費となっております。
吉田
16、17ページ、3款5項1目災害救助費の応急仮設住宅用地借地料ですが、増額になっている理由についてお伺いいたします。
生活再建支援課長
まず、場所については美田園第1仮設住宅の用地になります。増額補正の理由ですが、平成30年度、固定資産の評価がえがあり、この評価がえに伴って評価額が上昇したことから、今回、差額分の増額補正をお願いするものです。
吉田
固定資産の評価がえということですが、全体の面積と、こういう増額になった計算の仕方についてお伺いしたいと思います。
生活再建支援課長
まず、敷地の面積は1万2,449.13平方メートルです。それから、算定については、固定資産評価額に対して6%を掛けて算出したものが借地料となっております。
吉田
22、23ページ、8款7項3節復興まちづくり事業費の工事請負費の中で、一番下の皇太子同妃行啓碑等設置工事の内容についてお伺いいたします。
復興調整課長
平成29年11月に皇太子御夫妻が閖上においでになり、復興公営住宅を訪問され、慰霊碑に献花を行っていただきました。そのときの思いをことしの歌会で詠んでいただきましたので、そういった歌碑を慰霊碑の近くに設置したいということです。
吉田
慰霊碑の近くということで、大変結構なことだと思います。それで、この碑の正式な名称ですが、名取市として設置する以上はこれが正式な名称かと思いますが、この皇太子同妃行啓碑ということでよろしいですか。両殿下という敬称は入らない形になるのですか。
復興調整課長
皇太子が訪問などをされた場合は行啓ということになって、まず1つは、皇太子御夫妻が閖上においでになったことを示す碑が行啓碑。それから、その隣に、そのときにお詠みいただいた歌碑を建てると。さらに、そういった歌碑をどういったことから建てているかということを説明する説明板を建てたいということで、全部で3つのものを建てたいと考えております。
殿下という敬称を入れるかどうかという御質疑ですが、今は歌碑を建てることについて宮内庁と相談中ですので、その碑にどういった文言を刻むのかも含めて、これから宮内庁と相談して調整していきたいと考えております。
吉田
その碑の銘文についてではなくて、こういう碑を建てたときは、例えば案内板をつけたり、あるいは地図上にここに碑があるということを示したり、インターネット上に表示したりもするかと思いますが、そうすると、そういう場合の正式な名称はまだ決まっていないということでよろしいですか。
復興調整課長
先ほどの繰り返しになりますが、宮内庁と相談をしていきたいと思います。既に同じように碑を建てている先進地においては、両陛下行啓碑という形で刻んでいる石碑がありますが、どういった文字を刻むかも含めて宮内庁と相談していきたいと思っております。
吉田
22、23ページ、8款7項3目復興まちづくり事業費の22節補償補填及び賠償金、原停車場線物件移転補償費とあります。今回のこの補正をもって土地の取得率は全体のどのぐらいになりますか。
増田復興再開発推進室長
補償協議については現在進めておりますが、まだ契約にまでは至っておりません。
全部で件数が11件あります。その中で、今はまだ補償協議をしている段階で、契約には至っていない状況です。
吉田
契約のために今交渉されているということですが、ここに計上されているということは契約が成り立つという前提ではないかと思います。そういう前提に立ったときに、本市として必要な分の土地、今民地となっている土地を市が取得しなければならないと。その取得しなければならない総面積が何平方メートルとかあると思いますが、今回のこの補正が通って契約ができたとして、その全体のうちどのぐらいの進捗という形になるのか、土地の取得という面での進捗率をお伺いしたいと思います。
増田復興再開発推進室長
用地については全件数で11件となっています。そのうち、現在交渉中でまだ契約に至っておりませんので、進捗率としてはゼロ%となります。
吉田
24、25ページ、10款5項4目図書館費ですが、委託料として備品等廃棄委託料とあります。今、図書館の駅前の再開発ビルへの引っ越し作業が急ピッチで進んでいるかと思いますが、書籍、図書などの資料についてはこの備品等廃棄委託料には入っていないということで、備品ですから棚などのようなものだけと捉えてよろしいですか。
生涯学習課長
議員お見込みのとおり、書棚、黒板その他のものを今回廃棄するものです。
吉田
移転に当たって、現在の蔵書や資料については全て新しい図書館に移すということでよろしいですか。
生涯学習課長
本等については新しい図書館に移転する予定になっております。
(議案第116号 工事請負契約の締結)
吉田
ただいまの御説明ですと、その別途工事というのが資料では黒い文字であらわされている部分なのかと思いますが、被災者墓地は1区画が3平方メートルと4平方メートルで、それぞれ302基と200基となっていて、この数が今回の最終的な決定かと思いますが、その数はどのような理由で決定されたのかお伺いいたします。
クリーン対策課長
被災者墓地の区画数については、平成24年に遺族にとったアンケートに基づく基数と、津波で浸水被害を受けた閖上地区の共同墓地や個人墓地の基数から見込み、当初は550基としていたところです。その後、こちらの墓所の設計をするに当たり区画の検討を行ったところで、資料の図面にも記載しておりますが、無縁合葬墓を今回新たにつくることになり、その分の区画数を差し引き、また、区画についても、当初は4平方メートルの区画だけで構成しておりましたが、その後、区画の見直しで3平方メートルの区画もつくることとし、その結果、502区画と見直して設計したところです。基数の見直しの主な部分については、1区画の面積が小さくなった部分があることと、無縁合葬墓の予定の分を考慮したことによるものです。
吉田
当初の計画から48基分が減り、無縁合葬墓に埋葬される方もいるということかと思いますが、この無縁合葬墓はあくまでも無縁の方だけが対象となるということでよろしいですか。例えばお墓の管理が大変だという方が希望した場合は、お断りすることになっているのでしょうか。
クリーン対策課長
今回設ける無縁合葬墓については、みとる人がいない方を対象としております。議員御質疑の例えばお墓を持たない方などについては、今後、一般市民墓地などで検討していくということで、今回の無縁合葬墓についてはそういった方は対象としていないところです。
吉田
お墓参りに行くとお供え物をすると思います。それで、お線香のように火をつけて消えるものはいいのですが、花は枯れてしまいますし、お菓子なども処理に困ります。こういう公営墓地の場合、使用料をいただいているのですから、サービスの一環として、市が業者に委託してお供え物を回収してきれいにするとか、ごみ箱を設置しておくとか、そういうことも考えられると思いますが、この墓地公園の場合はそのあたりをどのようにお考えでしょうか。
クリーン対策課長
お墓の清掃関係については、議員がおっしゃったようにいろいろなやり方があるかと思います。ごみを捨てる場所を設置して、お参りに来た方にそこに置いていってもらう形もあれば、委託業者などが定期的に清掃して片づける方法もあります。具体的な対応については運営部分の一部となりますが、そこについては現在細部を検討中ですので、今の段階では具体的なところまでまだ固まっていないところです。検討中であるということで御理解願います。
財務常任委員会
吉田
9、10ページ、1款3項1目軽自動車税について伺います。収入未済額と収入済額のところで、それぞれ百の位以下に数字があります。それは合わせると28と72なので100になるのですが、これは収入未済の方が分割で納めたと捉えてよろしいですか。
税務課長
軽自動車税の収入未済額の819万9,872円という端数については、納税者から端数を持った状態での納付がありましたので、繰越金である収入未済額が端数を持った状態で繰り越しになったため、収入未済額に端数がついているということです。
吉田
恐らく何千何百28円という形で納めて、何千何百72円が足りなかったということかと捉えました。例えば財布をあけてみたら持ってきた額が足りなかったのかと思いますが、市役所の窓口では足りない場合でも受け付けるという対応なのでしょうか。実際どうしてこのような納め方ができたのか、非常に疑問なのですが、詳しく御説明をお願いします。
税務課長
軽自動車税の未納者に対しては、預貯金の差し押さえをいたしました。その金額が1万6,828円、口座からこれを押さえたということで、この差し押さえ納付による端数が収入未済額に100円以下の端数が生じた理由です。また、完納したわけではないので、この影響で繰り越しに端数を生じたということです。
吉田
差し押さえた際に、金額が不足してこの端数が出たということでした。最終的に差し押さえで対応されたということですが、平成29年度内に差し押さえという形で支払っていただいた件数は全体で何件ありましたか。
税務課長
平成29年度は給料差し押さえ52件、預貯金の差し押さえ33件、その他の差し押さえとして63件、合計148件で、これによって換価できた金額は1,865万4,170円です。
吉田
17、18ページ、10款1項1目地方交付税について伺います。今回の額の中で、普通交付税の分が20億何がしということで、前年度比で12.80%の減という御説明がありました。この地方交付税は、国が地方自治体の状況に応じて配分されると伺っています。非常に難しい計算式で、そこまで説明していただく必要はないのですが、国全体の普通交付税の中の本市の分は一体どのくらいの割合、何%になるかというのは押さえているでしょうか。
財政課長
普通交付税の御質疑ですが、臨時財政対策債も含めての実質的地方交付税ということで答弁します。本市の実質的地方交付税については、普通交付税が19億4,595万9,000円、臨時財政対策債が10億676万6,000円で、実質的地方交付税が30億5,275万5,000円となっています。国の実質的地方交付税と地方交付税の臨時財政対策債の合計が19兆9,950億円ですので、計算しますと、本市分は0.015%前後になるものと捉えております。
吉田
19、20ページ、13款1項1目総務使用料の行政財産目的外使用料、こちらは自動販売機の収入を含むと伺いましたが、平成29年度、自動販売機の数の変化について伺います。
財政課長
自動販売機についての増減はありません。
吉田
増減はないということですが、同じ自販機でももっと充実したAEDつきのものにするとか、そういう変更もなかったということでよろしいですか。
財政課長
行政財産の目的外使用ということですので、事業者の方からこういった自動販売機を置かせてくださいという申請があります。その際、自動販売機の機種の選定はこちらで統一するわけではありませんので、どういう自動販売機を設置するかについては事業者の意向で行われています。
吉田
今の菅原委員と同じ21、22ページ、13款1項4目土木使用料の4節住宅使用料です。きのうの総括質疑でも説明があったと記憶しておりまして、連帯保証人にも催告書を送っているということですが、連帯保証人に催告書を送った後、その後支払いにつながったケースは、平成29年度ではどのくらいあったのでしょうか。
都市計画課長
支払いの方法としては、コンビニ納付や銀行振り込みがあるのですが、どなたがお支払いになったかまではわからないので、そこまでは把握できていません。
吉田
例えば、滞納している方が10人いたとして、10人に連帯保証人がついている。その方々それぞれに催告書を送ったとして、実際にはその10人以外から振り込まれたのか、その10人から振り込まれたか、わからないということですか。
そうではなく、連帯保証人の方に催告書を送ったのは、どの方かというのは全部把握されていると思います。その中から実際その後支払いにつながったケースの件数、あるいは人数についてお伺いしたかったのです。
都市計画課長
支払いについては割賦が借りている方のお名前なので、そこまではわからないということです。
委員長
今の質疑は、連帯保証人に連絡した後に振り込みがあった件数は何件かと聞いていると思われますが、それでよろしいですか。
吉田
今、委員長がおっしゃったように、契約している方は本市との間で契約している。その世帯ごとに滞納されているかどうかは把握されているわけですね。その中で滞納が積み重なっていったときには、連帯保証人に催告状を送る。そこまでは全部つながっていると思うのですが、世帯主の名前で振り込まれる、あるいは現金で支払うときに、その方は連帯保証人なのか、実質的に払った方か、そこの色分けはできると思うのですが、難しいですか。
都市計画課長
あくまでも割賦が借りている方の名前になっています。連帯保証人の方には、こういうことになっているので何とか納めてもらえるようにという文面を送りますが、連帯保証人が払っているかどうかはわかりません。
吉田
わかりました。ですから、連帯保証人に催告書を送ったとしても、そのことを直接契約者に伝えているかどうかはわからないということですね。お互いのやりとりですから、伝えているかもしれないし、連帯保証人でとまっているかもしれない。だから、そこで把握できないということだと、今そう捉えたのですが、連帯保証人が全員そのことをお知らせしたと仮定して、連帯保証人に催告状を送った契約者から支払いにつながった件数は押さえていないのでしょうか。
都市計画課長
契約者と連帯保証人の両方に催告状を出しており、連帯保証人から契約者に言っていただいていると信じているのですが、それを連帯保証人が払っているかどうかは把握できません。割賦が契約者の名前ですので。
建設部長
吉田委員からの御質疑ですが、滞納があった場合、まずは本人に督促状、催告状を送ります。それでも納入されていない場合は、連帯保証人に催告状なり監護指導なりをするのですが、その後、本人が支払ったか、連帯保証人が支払ったかは捉えておりません。また、連帯保証人に催告状をお渡しして、それが支払いに結びついたかどうかまでは捉えていないところです。
吉田
29、30ページ、14款2項2目民生費国庫補助金7節臨時福祉給付金について伺います。昨日の説明で、今回9,342名の方に給付されたということですが、母数といいますか、全体の対象者の数は何名だったのでしょうか。
社会福祉課長
申請書を発送した人数でお答えしますと、1万126人に申請書を送りました。
吉田
600人くらい受け取っていない方がいるということだと思いますが、受け取らなかった理由、要因はどのように分析されたのですか。
社会福祉課長
申請書を送って、申請がなかったことに関して個々に理由をお尋ねしたことはありませんが、9,356人から申請がありました。その中で9,342人の方に支給しましたが、不支給の方もいます。申請された後お亡くなりになったり、あるいは親族に扶養されている等、要件を満たさなかった方が14人いたということです。申請がなかった方については、最初から要件を満たしていないとか、そういったことも考慮されたのかと捉えているところです。
吉田
33、34ページ、14款2項6目消防費国庫補助金の1節消防施設費で伺います。こちらは緊急消防援助隊の装備の充実のための補助金と伺いましたが、平成29年度の緊急消防援助隊としての出動の実績を伺います。
消防本部総務課長
平成29年度、災害による緊急消防援助隊の出動はありません。
吉田
今、災害のと言いましたが、災害以外の部分や訓練等も含まれていくのですか。平成29年度は災害はゼロだったということですが、これからより大きな災害が起きて、いずれ要請が来ることもあろうかと思いますが、そのあたりの備えに市の消防としてはどのように取り組まれたのか、伺います。
消防本部総務課長
まず、基本的に災害での緊急消防援助隊の出動はないということを先ほどお答えしました。1年に1回、9月1日防災の日に、前日の8月31日から9月1日にかけて、緊急消防援助隊宮城県ブロック訓練ということで野営訓練、大規模な火災の救助事案に対応する訓練を毎年実施しております。
あともちろん全国で大規模な災害がありましたら、消防庁長官の求め、指示等によりまして、緊急消防援助隊が出動することになります。それに備えて、当然消防本部のほうも訓練を実施しているということです。
吉田
51、52ページ、17款1項1目一般寄附金のクラウドファンディングについてもう少し伺います。今回、募集したのが1,000万円であったと記憶していますが、クラウドファンディングを始めてから最初の数字を見て、なかなか厳しいなと思いまして、ある1週でぽんと一気に上がったような記憶があります。寄附者の方は額はそれぞれ決めるわけですが、今回の1人当たりの最高額は幾らだったのでしょうか。
財政課長
最高額は100万円となっています。100万円が2件ありました。そのほかに50万円が4件ありましたが、これらの件数がほぼ11月上旬に固まっておりまして、短い期間で金額が上がったのはそのためかと考えております。
吉田
ただいまの御説明で、1,000万円の目標額に対して、その1割に当たる100万円が2件あったと。かなりありがたい、救世主のような寄附です。このような大口の方がいらっしゃればそれにこしたことはないのですが、全体から見れば、大口の方が必ず出てくれるとは限らない。そういうことで、これからクラウドファンディングを行うかどうか、いろいろ検討されていると思いますが、平成29年度の額も含めたクラウドファンディングの取り組みについての評価を伺います。
財政課長
きのうの総括質疑でもお話ししましたが、全国的にサイクルスポーツセンターの復旧ということでプロジェクトを組んで情報発信をし、温かい寄附をいただいたところです。そういった意味で、今後、温泉券などをさらに利用していただければ、将来につながるような本市の魅力の発信につながっていくのかなと考えています。
吉田
61、62ページ、20款5項2目雑入の12節返還金について伺います。こちらの返還金は、説明の中で生活保護法の第63条、それから第78条と、平成28年度の負担金の精算など説明がありましたが、生活保護分としてお聞きしますが、今回の収入済額と収入未済額、その中の生活保護の部分に当たるものは、件数は一部お聞きしましたが、収入済額のできれば第63条と第78条の条項ごとの違いを、もしデータがあればお伺いします。
社会福祉課長
先ほど委員から第63条と第78条と分けてという御質疑でしたが、こちらの集計は、第63条の現年分、過年度分という捉え方、あわせて第78条も同じような捉え方をしているところです。
第63条の分は、現年分として216万7,773円が返還を受けています。過年度分が159万4,110円、返還を受けております。
第78条の分ですが、現年度、平成29年度分が43万1,187円、過年度分が57万8,000円です。
したがって、第63条、第78条を合わせて現年度分が259万8,960円、過年度分が217万2,110円で、合計して477万1,070円が返還となっている金額です。
吉田
生活保護を受給できる資格に当たらない部分でこのようなものが生じてくると思うのですが、具体的にこれがわかるケース、どのようにして返還金が生じることがわかるのか、あるいは自己申告するのか、そのあたりの平成29年度の状況について伺います。
社会福祉課長
まず返還金に関しては、生活保護法の第63条と第78条と2つの種類があります。
第63条については、被保護者が資力がありながら保護を受けたときに、その資力に応じて支給した保護費を上限として返還するもの。いわば年金などが後になって遡及して受給できるようになった、そういったケースのときに第63条を適用して返還を求める場合があります。
第78条については、不実の申請その他不正な手段により保護費を受け取った場合。働いているにもかかわらず、収入申告をしなかったケースです。この収入申告については、収入があったときは申告してくださいということは、保護の開始時点、説明の段階でもお願いしているところです。それをしないで就労して収入を得ていた、それを黙っていたということが発覚した場合に、この第78条で返還を求めるものです。収入があったにもかかわらず黙っていた場合は、ケースワーカーが収入に関しての課税状況など収入の調査を行いますが、その中で発覚する場合があります。また、第29条で資産の調査をする権限もありますので、預金通帳などの確認を求めた中で、何らかの形で収入を得て、それを黙っていたという場合もあります。
その状況に応じて法を使い分けて、返還が生じた場合には回収をお願いするという形をとっています。主にはそのような形で返還を求めるものです。
吉田
63、64ページ、21款市債の全体的なことで伺います。総括質疑で市債の総額が増加していると指摘したところ、答弁では、当年度の使用料収入や交付税措置を見込んでいることが増額になっている主な要因として捉えているということでした。交付税措置を見込んでいるということですが、現段階で、平成29年度の全体の中のどのくらいの割合を交付税措置として見込んでいるのでしょうか。
財政課長
平成29年度の市債全体については44本、総額40億5,894万円となっています。そのうち交付税措置の起債については26本、総額で26億1,860万円となっています。本数では59%、額では64.5%が今年度交付税措置のある起債となっています。
なお、平成29年度に借りた起債の後年度に交付税措置される総額ですが、14億3,973万5,000円となっています。ただ、この中では臨時財政対策債、10億60万円が入っています。その分を差し引くと、現実的な実際のところは4億3,900万円程度となっています。
吉田
せっかく今御説明いただいたので、交付税措置される事業の主な事業名、大きなものだけで結構ですので、幾つか御紹介いただきたいと思います。
財政課長
額の大きなところですが、図書館整備債が平成29年度で11億6,100万円の借り入れとなっています。
財務常任委員会第一分科会
吉田
市政の成果136ページ、常備消防費の消防事務の1の(2)危険物施設、防火対象物の査察指導についてお伺いします。施設数が、危険物施設は前年度と変わらないのですが、防火対象物が70棟ほどふえています。この防火対象物がふえた中身についてお伺いしたいと思います。
予防課建築設備係長
防火対象物数は、まず建築確認がおりてふえた数の中から、消防法施行令別表第1に定められている防火対象物としての用途1項から16項までに含まれていると思われるものを繰り入れています。建築確認がおりて建てられたもの全てが防火対象物になるわけではなく、一般的には集会所、店舗、飲食店、アパートなどになっています。
吉田
ふえた70棟の用途ごとの内訳は把握されているのでしょうか。
予防課建築設備係長
防火対象物は、その業態や機能をもとに項別に分けられています。その中で、建物は存続しているがその業態や機能が変わったとなるとその項を移動したり、あるいは廃業するところや、さらに新築でできるところもあって、その比較増減の中でトータルで70件という数字が出ています。その中で前年度と比較して特に顕著にふえたところとしては、15項のその他の事業所というところで、事務所的なもの、サービス業的なところが前年度と比較して58件の増、それから、2つ以上の用途が組み合わされている建物などを複合用途の防火対象物と言っていますが、もともとは単一の用途だったところに後から別の用途の店が開業すると複合用途となり、建物自体は単一の用途だったものが複合用途という項に含まれることになってふえていったりということもあります。間違いのないように説明したいのは、もちろん新規でできたものもありますが、単純に70件の建物が新たにできたのではなく、項の中を移動したりしているものもあるということです。
吉田
大変わかりやすい答弁ありがとうございました。単純にその建物がふえただけではないということでしたが、検査をしていく段階でやはり対象となるものがふえているということですので、現在の検査の体制について、平成29年度内で対象物がふえたことによって見えた課題などがあれば教えていただきたいと思います。
消防署指導係長
対象物がふえたことによって、管区をふやし、立入検査数をふやす状況にあります。毎年、1管区ぐらいずつふえる状況にあります。
吉田
市政の成果137ページ、常備消防費の消防事務の5 消防活動力の充実・強化の委託料の多言語通訳コールセンターの業務委託です。これも毎年お聞きしていますが、平成29年度はどのくらい利用されたのか、その状況についてお伺いいたします。
警防課通信指令係長
平成29年度は、多言語通訳コールセンターについては使用はありませんでした。
吉田
使用がなかったというのは、日本語が通じない方が通報しなかったのか、それとも、もともと通報する人がいなかったのか。そして、使用されないのに継続していくかどうか、今後のあり方についての検討というところもお伺いしたいと思います。
警防課通信指令係長
なぜゼロ件だったのかという理由ですが、ホームページ等で119番のかけ方などを外国語を使って掲示してアピールしているつもりですが、まだまだ浸透していないのかなと思います。実際に外国人の方からの119番通報は何回かあるのですが、日本語が話せる方でしたので特に通訳まで必要なかったところです。
ゼロ件なのになぜ継続するのかということもありますが、全国的に東京オリンピック・パラリンピック等に向けて国際化が叫ばれている昨今でもあり、ふえる可能性もゼロではありませんので、今後とも継続していきたいと思っています。
吉田
同じく市政の成果の137ページ、常備消防費、消防事務の5 消防活動力の充実・強化で、緊急消防援助隊用ポータブル冷凍・冷蔵庫等とあります。このポータブル冷凍・冷蔵庫がどういうものかについてお伺いしたいと思います。
警防課消防係長
これは、緊急消防援助隊として活動する際に、屋外での活動が続きますが、夏場の活動のときに保冷剤を防火衣の中に入れて使ったりしますので、そういうものを現場に行って準備するということでそろえております。その際に飲料水などもそうですが、緊急消防援助隊は外で野営して活動しますので、そちらで準備するものということで、持ち出しで、そちらの災害場所に行って使用するものとなっております。
吉田
緊急消防援助隊として派遣されてということだと思いますので、市内での活動には活用されていないのかと思いますが、市内での消防の活動の中でこれが何か活用されるようなことはあるのか。あるいは、これは完全に緊急消防援助隊の中でしか使用しないと決められているのでしょうか。
警防課消防係長
市内での活動については、もともと消防本部にある冷蔵庫、冷凍庫で保冷剤などを常時準備していますので、災害があった場合にはそちらを持ち出して使うようになっております。この緊急消防援助隊用のものについては、緊急消防援助隊出動のときに持ち出す形にしております。
吉田
市政の成果139ページの常備消防費、消防活動の成果の3の救助活動で、風水害、自然災害が出動件数3件で人員が22人ということで顕著に大きくなっていますが、こちらがどういう内容だったのかお伺いしたいと思います。
消防署救急救助係長
10月22日の台風21号の襲来の際に、閖上地区において道路が冠水しました。そのときに救助隊が出動して19名をゴムボートで救出したということで、自然災害の件数と人数がふえております。そのほか、同じく台風21号襲来の際に、下増田地区と閖上地区で、もう1回同じような事例で救助活動を実施しております。
吉田
今、答弁を受けて思い出しました。この災害の際の出動件数が3件となっていますが、このように同じ災害であっても件数が別にカウントされるのはどのような考え方なのでしょうか。
消防署救急救助係長
要請が3度ありましたので、その都度カウントして、3件で救助人員が22人となっております。
吉田
同じ144ページ、防災費の防災対策事業、委託料の(7)の防災ラジオ販売業務委託ですが、平成28年度末の時点で残り503台と御説明いただいた記憶がありますが、平成29年度末の残り台数をお伺いしたいと思います。
防災安全課長補佐
平成29年度末では305台となっております。
吉田
順調に在庫がなくなってきていると思いますが、この追加などについて平成29年度内に何か検討等はされなかったのでしょうか。
防災安全課長補佐
追加発注については検討しておりませんでした。
吉田
同じく市政の成果144ページの防災費です。防災対策事業の9 県総合防災訓練で、これは大変意義のある訓練だったと受けとめておりますが、こちらは全体的な費用が400万円を超える額ですが、財源として県からは200万円ということで、それ以外は市の単費ということでよろしいでしょうか。
防災安全課防災係長
委員お見込みのとおり、単費での負担となっております。
吉田
市政の成果145ページ、防災費の12 国民保護事務で、国民保護研修会への参加とあります。毎年参加されていると思いますが、平成29年度の研修会の内容についてお伺いいたします。
防災安全課防災係長
こちらについては、東京都にある消防大学校で講習会があり、約1週間、国民保護、危機管理のセミナーに参加しているところです。
吉田
その研修会に参加してきて、それを受けての市の取り組みとか、その取り組みによってどのような成果があったのかをお伺いしたいと思います。
防災安全課防災係長
平成29年度については、北朝鮮のミサイル発射に関する情報だけで国からの情報が12件ありました。平成30年度は大分落ちついていますが、国民保護の関係での危機感がかなり高まっていたところですので、そういった研修内容なども踏まえて、そういう災害が起きた場合の対応等についてもう一度見直したり、自衛隊の東北方面隊で実施している防災訓練に参加したり、危機意識を高く持つことで、市としては避難誘導等の業務が主になり、消防については救助活動などいろいろな業務がありますが、そういったときに必要になる物品等についても改めて確認したりということで、平成29年度は取り組んでいたところです。
吉田
市政の成果146ページ、水防費についてお伺いいたします。2番の水防用資機材の整備で土のう用川砂等とありますが、この土のう用の川砂は訓練用だけのものなのでしょうか。それとも災害時に使えるようにどこかにストックされているものなのでしょうか。お伺いいたします。
警防課消防係長
この土のう用の川砂については、平成29年度、東北水防技術競技大会に伴い、訓練用として川砂を購入しました。それで、その後の土のうについては、砂だけでなく土のう袋に入れた状態で消防本部に持ってきて保管しております。
吉田
全体の川砂の量がよくわかりませんが、その全部が土のうに入れられて消防本部に保管されているのか、もし余った分があったらそれは有効活用されなかったのか、お伺いしたいと思います。
警防課消防係長
訓練は十三塚公園の多目的グラウンドで実施し、そちらで訓練が終わってから、残りの砂を全て土のう袋に入れて消防本部に持ち帰ってきております。
吉田
市政の成果の1ページ、企画費からお伺いしたいと思います。地方創生事業の中で、1 報償費の(2)名取マイレージ事業記念品ですが、平成29年度の記念品の中身をもう1回確認したいと思います。それから、応募された件数についてもお伺いいたします。
政策企画課政策係長
まず、記念品ですが、5ポイントコースと3ポイントコースとあり、5ポイントコースについては10本、3ポイントコースについては40本出しております。内訳としては、5ポイントコースについては全て上山市宿泊券、3ポイントコースについては名取の地酒が6本、真がれいの閖上干しが6本、笹かまぼこの詰め合わせ16本、北釜チンゲン菜入り米粉パスタが6本、米が6本となっております。
それから、応募の数ですが、応募の有効総数については97件となっております。
吉田
全部で50本の商品で97件の応募ということは、倍率が2倍ぐらいなのでしょうか。思ったよりも当たりやすいのかなと思ったのですが、例えば上山市の宿泊券については、たしかこれはペアではなかったのでしたか。そのあたりで何か、全体的にはいいのですが、記念品について、この事業を1年間行った成果なども踏まえて、今後どのように進めていくのか、もし御検討されたのであればお聞きしたいと思います。
政策企画課政策係長
まず、宿泊券については、ペアという形ではなく、応募に対して純粋に抽せんをし、当せんさせている状況です。お配りする商品の状況、中身についての配慮をということですが、応募するときに既にはがきに応募者の方からこういうものが欲しいという形で要望があるということで、当然それを踏まえて抽せんをする形ですので、応募する方の気持ちについては配慮させていただいているものと捉えております。
吉田
市政の成果の2ページです。財産管理費の財産管理事務、2 財産保険加入で、公営住宅火災共済の保険対象物の面積が前年度に比べて非常に大きくなっています。これは復興公営住宅が完成したことによるものかと思いますが、この保険が掛けられる対象となるのはあくまで建物の延べ床面積なのか。もしそれ以外の方法であれば、そのあたりの説明をお聞きしたいと思います。
財政課管財係長
公営住宅火災共済については、分担金という形で支出しており、基本的には建物の面積によって算出されたものについて負担しています。
吉田
建物がふえれば、それだけ火災が起きるリスクが高まってくるのかと思いますが、契約者の方が自分で火を出してしまったり、それ以外の要因であったり、実際に火災が起きるケースはいろいろとあろうかと思います。その燃えてしまうものについても公営住宅の建物そのものとか、そこに附属している市が貸し出しているものとか、いろいろとありますが、どの部分まで火災保険が適用されて保険金が支払われるのか、そのあたりをお聞きしたいと思います。
財政課管財係長
火災共済事業適用の範囲については、地方公共団体が管理する公共賃貸住宅とその附帯する集会所等の共同施設が対象となっております。その附帯施設については、今、手元に内容の詳細なものはありませんが、住宅及びその附帯施設が対象となるということです。
吉田
事項別明細書の77、78ページ、2款1項3目広報費です。ホームページ作成が委託料に計上されているかと思いますが、平成29年度のホームページの閲覧者数が前年度に比べてどのような変化があったのか、もしデータがあればお願いしたいと思います。
総務課広報広聴係長
市のホームページのアクセス件数、セッション数になります。セッション数というのはユーザーがホームページを訪問した回数ですが、平成29年度は92万8,202回、月平均で7万7,350回となっております。前年度比で1万6,408回の増、率で101.8%となっております。
吉田
市のホームページは大変充実した中身で見やすいものであると、いつも感心して拝見しています。平成29年度にホームページの中身を改修したとか、いろいろとあるかと思いますが、重点的に力を入れた部分がもしあればお伝えいただきたいと思います。
総務課広報広聴係長
平成29年度における市のホームページの新たな取り組みとして、ホームページのトップページにスライド画像を使用したり、一つ一つの情報発信において画像を多用し、利用者の視覚に訴えるような情報発信に努めたところです。それから、もう一つ、市のホームページの多言語化表示と音声読み上げ機能の導入を図ったところです。
吉田
市政の成果の7ページ、交通防犯対策費で、防犯事業の1 (2)岩沼地区防犯協会連合会補助金は、名取市内の各町内会ごとに置かれている防犯協会に対する補助金の合計と捉えてよろしいですか。
防災安全課生活安全係長
岩沼地区防犯協会連合会というのは、事務局は岩沼警察署の生活安全課となっており、そちらに対して、名取岩沼両市から、世帯数に70円を掛けた金額を補助金として支出しているところです。
吉田
1世帯70円で、名取市内の世帯数3万何千世帯掛ける70円ということだと捉えましたが、実際に岩沼地区防犯協会連合会においてこの補助金はどのようなことに使われているのですか。
防災安全課生活安全係長
名取市内には旧字の各地区に防犯協会がありますが、そちらの補助を連合会から支出したり、名取岩沼両市の合同で防犯運動にかけての出発式をしたり、そういった共同で岩沼署管内の防犯に関する行動を行っているものです。
吉田
同じく市政の成果9ページ、公共交通対策費です。なとりん号の時刻表、路線の改定が平成30年4月からということで、平成29年度はその改定に向けての最後の年度だったわけですが、その改定の際に、新設だけでなく、実際にそれまで置かれていた既存のバス停の移設など、交通状況等も含めて、そのあたりの検討をされた経緯についてお伺いしたいと思います。
防災安全課生活安全係長
既存のバス停の移設については、なかったと思います。路線の廃止によって撤去する場所はありましたが、既存のバス停を移設したところはありません。
吉田
交通事情の悪いところとか危険を感じるとか、市にいろいろとバス停の要望などがあったかと思いますが、既存のバス停の移設についての要望が市になかったために、移設はしなかったというか、検討をしなかったということでよろしいですか。
防災安全課生活安全係長
平成29年度においては、そういった要望はありませんでした。
吉田
市政の成果13ページ、市民活動促進費の市民活動支援センター管理運営事業です。指定管理がされた最初の年度ということですが、前年度の決算と比較すると、指定管理料となったことで、維持管理費だけで比較すると金額的には大きくなっているのですが、結局その分、市の直営ではなくなったので職員の数が必要なくなったとか、いろいろな計算の仕方があろうかと思いますが、指定管理にしたことによるコスト面での成果をどのように捉えていらっしゃるのかお伺いいたします。
男女共同・市民参画推進室推進係長
市で、共同提案事業について例えば受け付けや指導についても、市民活動支援センターの職員に丁寧に指導いただいています。また、情報交換会やフォーラムなど、市民活動支援センターでいろいろな事業を行っておりますが、そういったところで大変成果があったと捉えているところです。
吉田
こういう市民活動を促進するための施設は、NPOプラザなど名前はいろいろとありますが、各自治体で設置が進んでいる状況だと思います。ただ、公民館などとの違いがよくわからないということで、公民館を利用するのと同じ感覚で行ったときに、制限が非常に厳しくて、登録もできなかったとか、そういうことをいろいろとお伺いしています。そういったことで、この市民活動支援センターはこういう施設だよということを市民に周知して理解を広げていただいて、もちろん利用を促進していくということもありますが、そのあたりの平成29年度の取り組みはいかがだったのでしょうか。
男女共同・市民参画推進室推進係長
先ほど御答弁申し上げた情報交換会やフォーラムなどいろいろなときに市の広報を通して、またホームページを通して、より多くの市民に広げていくように周知をしたところです。今後もそういった活動を通して市民の方に広げていきたいと考えているところです。
吉田
事項別明細書の96ページ、2款1項26目諸費の行政区長事務の中身ですが、行政区長の研修会が地域ごとに開催されているかと思います。この研修会の実施の状況についてどの程度把握されているのかお伺いしたいと思います。
総務課総務係長
1日5,000円、宿泊の場合は1泊2日になりますので掛ける2で1万円ということで申請いただいて、地区ごとに旅行という形で研修に参加するところが多いのですが、このように算定して支給しております。
吉田
区長の方々もいろいろな研究を行って地域のためにより貢献したいという気持ちでそういう研修会に参加しているのかと思いますが、その研修の一部を公費で負担しているとなると、その研修の成果がどうだったのか、ある程度見える形で示していただきたいということがあろうかと思います。そういった点でこの公開の仕方についてどのように取り組んでこられたのか、お伺いしたいと思います。
総務課総務係長
地区ごとに研修して、報告は上げていただいております。報告いただいた中で多いのが地熱発電所とか岩手・宮城の自然関係のところをめぐったりというものですが、そのように本市で一部負担して研修を積んできたものについて御報告いただいている形が多いと捉えております。
現状では、こちらに報告はいただいておりますが、さらにこの旨を公開等はしていないところです。
吉田
事項別明細書の100ページ、2款2項1目税務総務費ですが、昨日の歳入の審査でも、納入の方法についてコンビニ納付とか窓口納付とかいろいろとありましたが、平成29年度内にクレジットカード納付についての検討は進められたのでしょうか。
税務課収納管理係長
平成29年度に関しては、クレジットカード収納の検討のため、システム会社の研修会に参加して研究をさせていただいた状況です。
吉田
もう1点、これも私の一般質問で取り上げたのですが、障がい者の方の軽自動車税の減免の自動更新を行っている自治体がありますが、そちらについての御検討は平成29年度はいかがだったでしょうか。
税務課市民税係長
軽自動車税の障がい者の減免の関係については、自動更新ではないのですが、直接窓口に来なくても郵便でのやりとりで更新できるよう平成29年度に検討をして、平成30年度から実施しております。
本会議
(議案第119号 平成30年度名取市一般会計補正予算)
吉田
6月上旬までということでまだ半年以上期間が残っていますが、この空調設備を設置していくに当たって、設置された後、学校で実際に使用していく際にそのエアコンの機械そのものの管理は各教室ごとに行うのか、それとも一括して職員室や事務室などで行うのか、そのあたりの検討はどのように進んでいるのでしょうか。
庶務課長
エアコンについては各教室ごとに管理するものとしているところです。
吉田
例えばストーブなどですと、火元についての責任者が必ず位置づけられていると思います。エアコンはそういう危険性などがないという利点もありますが、各教室での管理となると、実際に使う際にスイッチを入れたりとめたり、あるいは温度調節などについては教室ごとにそれぞれ決めていくことになるかと思います。そういう考え方でよろしいでしょうか。
教育長
エアコン設置後の具体的な使用については、これから学校とも相談しながら検討していきたいと思います。ただいま吉田議員御指摘のようにストーブの場合ですと火気取締責任者、教室の場合は学級担任になりますが、消火の確認をして、さらに日直、最後に教頭が確認をするという段取りとなっています。基本的にエアコンのスイッチを消したかどうかの確認はそのような流れになると思いますが、ただ、どのくらいの状態で使用するのか、どういうときにスイッチを切るのかといったところについては、各教室の担任判断ではなくて、教育委員会としても使用についてのガイドラインを来年の夏までには考えていきたいと思っております。
吉田
今回、このように補正予算に計上されているということで、対応がとても早かったと思います。下増田小学校の熱中症の件などもあり、恐らく急ピッチで検討されて、このようなところにまで至ったのかと思います。
こういう子供たちの学習環境をしっかり整備していく、より学びやすい安全な教育空間を整備していくというのは非常に大事なことですし、誰も反対する人はいないと思います。ただ、その一方で、ことしのような異常な暑さ、猛暑がそもそも何から始まっているかというと、これは科学の世界でもいろいろな説があるようですが、やはり地球が温暖化している、その原因として温室効果ガスの排出量が地球規模でふえているという話があるわけです。結局、子供たちの安全な学習環境を奪っているのが、今のこの経済社会……
議長
吉田議員、簡潔にお願いいたします。
吉田
そういう観点からすると、この環境というものをいかに子供たちに考えてもらうかという一つの大きなきっかけになっていくかと思います。再生可能エネルギーなどもありますので、そうしたものをこれをきっかけに何か授業の中で取り組んでいくとか、そのような検討は全くなかったのでしょうか。
議長
吉田議員、議題外ですので、別の角度から質疑をしていただきたいと思います。
吉田
別の角度といいましても、あくまで電気代とか、そういうことで言っているのではなくて、もっと広い視野で見ていきたいのですが、わかりやすく言えば、例えば環境に負荷がこれだけかかることになるわけですから、その分、各学校にソーラー発電を設置するとか、そういう形で何か代替的な電力の供給などについての検討はなかったのでしょうか。
教育長
まず、今回のエアコン設置については、御指摘がありましたように、下増田小学校での熱中症事故なども当然背景としてあります。教育委員会単独で判断できる問題ではありませんので、市長を初め市長部局とも調整をしながら、速やかな対応ができたと思っております。
エアコン設置については、今回これだけの猛暑の中でということはそれはそれとして、やはり子供の学習環境の整備のために必要だろうと思っております。それと環境教育を直接結びつけて学校で取り組むことまでは考えておりませんが、これまでもさまざまな角度で小学校、中学校の発達段階に応じて環境教育には取り組んでおりますし、また、太陽光発電なども非常用電源等として学校に設置しておりますので、今回のエアコンと結びつけてということではありませんが、これからも環境教育には意を用いて各学校で取り組むように声がけをしていきたいと思っております。