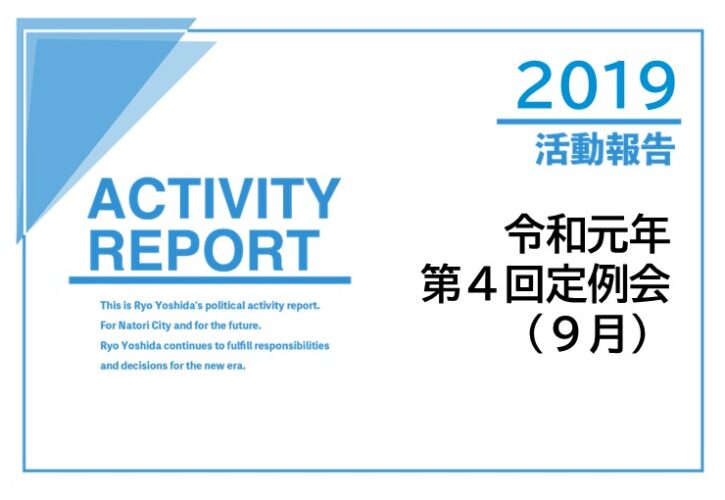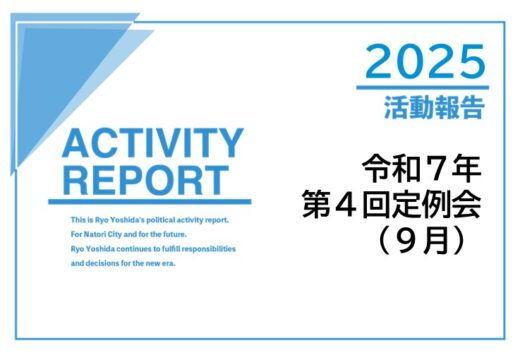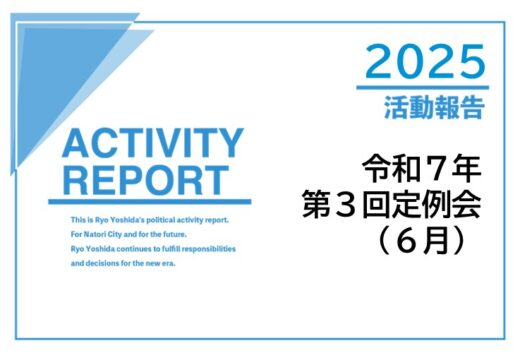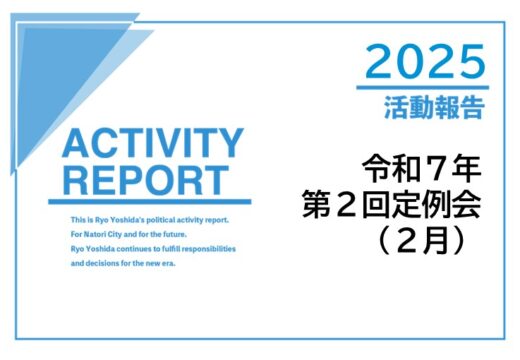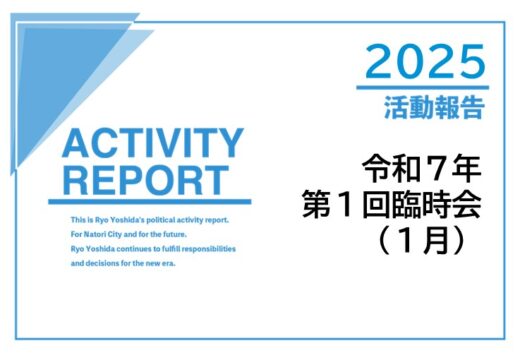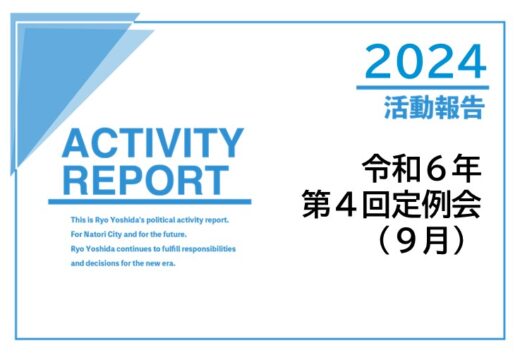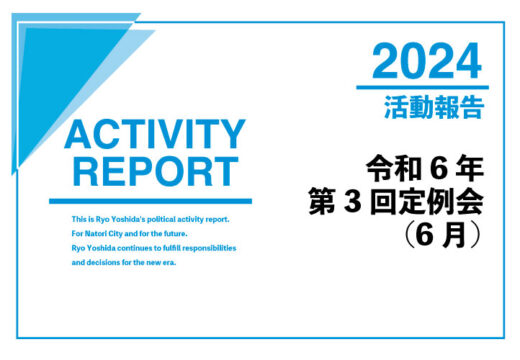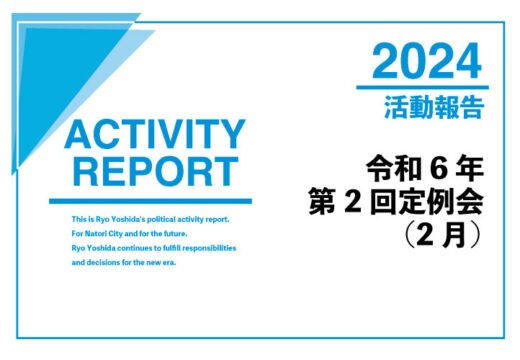本会議
(議案第72号 名取市市税条例の一部を改正する条例)
吉田
日帰り入浴客の入湯税50円という金額ですが、別の自治体では、仙台市70円などのケースもあるようです。これを50円と決めた理由について伺います。
税務課長
これまで本市の入湯税は150円で、宿泊施設に泊まる際の入湯税として規定していたところです。今回、日帰りの入湯税ですが、他市においては今回当方で考えた50円でないところはあります。入湯税はいわゆるぜいたく税としての性格も有しますが、奢侈性が希薄であることから金額は低く定めたいと考えました。入浴の回数を考えるならば、日帰りの場合は1回程度ですが、泊まる場合はチェックイン後、夕食後、翌朝など複数回と見込まれるため、今回日帰りは50円と定めたいということで提案したものです。
吉田
多い方では3回ぐらい入る方もいるかと思います。この金額は、サイクルスポーツセンター条例の審議の際にお聞きすることかもしれませんが、回数券を設ける際に、入湯税50円は無料分のところでも本来であれば徴収しなければならないのではないかと思うのですが、そのあたりの整理について今まとまっていればお聞きします。
総務部長
一般的に回数券、例えば10回分の料金で11回入れるという場合ですが、11回分の入湯税については納めていただくという方向です。
一般質問
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長より発言のお許しをいただきましたので、事前の通告に従い一般質問を行います。
初めに、大項目1 名取駅東西自由通路と駅前広場等の施設整備についてお伺いいたします。
JR東日本のまとめによりますと、平成30年の名取駅の1日平均乗車人員は1万2,927人で、県内のJRの駅としては仙台駅、青葉通駅に次ぐ第3位となっております。なお、秋田駅は1万773人、山形駅は1万728人、青森駅は5,397人で、新幹線がとまる県庁所在地の駅より利用者数でまさっているのが実情です。昨年12月には名取駅東口に図書館と増田公民館が入る複合ビルが完成しました。駅利用圏内では新たな住宅建設も進んでおり、名取駅の利用者は今後ますますふえると予想されます。今回は、より親しみやすく、使いやすい駅にするための提案を行いたいと思います。
まずは西口のバス停についてです。
西口には、東口のような駅舎とバス、タクシーの乗降場をつなぐ雨よけがないことは平成28年6月定例会の一般質問で取り上げました。その際、当初計画どおりの整備も完了していることから、新たな整備をする予定はないと前市長から答弁をいただいた経緯があります。駅前広場道路沿線を屋根で囲んだ場合、概算で2億円近くかかるとの試算もいただきました。確かに大きな金額であると思います。ただ、その後、通勤通学の時間帯に西口でバスを待つ人の数はさらに多くなったように感じます。雨にぬれず待つことができるよう、せめて駅舎とバス停の間の10メートルほどばかりでも改めて要望したいと思います。
それでは、小項目1 西口のバス停と駅舎との間に雨よけを設置すべきについて、市長にお伺いいたします。
市長
名取駅西口駅前広場には、現在、なとりん号が平日で83便、休日で43便が乗り入れており、バスの利用を促進するためには、駅前広場やバス停を快適に利用できる環境づくりも重要と捉えております。
現在もバス停にはバスシェルターとベンチは設置していますが、議員御提案の駅舎とバス停を結ぶ雨よけの設置についても、今後のバス利用の促進が期待されるため検討を進めていきたいと考えております。
吉田
今後具体的に設置に向けた検討となると、どのようなスケジュールを現在考えているか、現状でお知らせいただける部分を伺いたいと思います。
土木課長
現在、市長答弁のように、検討をしていくということでまだ始まったばかりです。現地を見た限り、駅舎とバス停間で、間口が駅舎側で3メートルあいています。そしてバス停に向かうような形で、その区間として8メートルほどシェルターを設置する形になると思います。そして、シェルターも両方に柱があるタイプや片支持などどのような形状にするか、その辺も含めて現地を見ながら設置に向けて検討したいと考えているところです。
吉田
やはり名取駅の東西口の整備は、さらによい環境の創出につながると思いますので、早目に進めていただきたいとお願いを申し上げます。
では、次に移ります。案内表示についてです。
新しい図書館は令和元年8月2日に来館者数が20万人を超えたということです。現時点で23万人にまで達しているとも伺いました。市外からの来館者も少なくなく、その中には電車を利用して来館する方もいます。しかし、駅構内に図書館の方向を示す表示がありません。夏休み中は名取駅の清掃員の方が図書館の場所を尋ねられることがしばしばあったと伺っております。東口方面の表示には市役所、市民体育館、文化会館、閖上、下増田、増田と書かれていますが、図書館と増田公民館の文字はありません。また、東口バス停付近にある総合案内板の地図には、震災前の増田公民館の場所がそのまま示されています。完成から半年以上が経過しており、早急に改めるべきだろうと思います。
小項目2 行き先案内板を新しい図書館と増田公民館の位置が記載されたものに更新すべきについて、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
議員御指摘の行き先案内板ですが、名取駅東口の総合案内板や東西自由通路の案内板と捉えて答弁させていただきます。
この案内板の更新については、平成31年2月議会において、平成31年度名取市一般会計補正予算にて復興まちづくり事業費に予算措置した名取駅東口駅前広場案内板等設置工事に含まれており、今後更新を行っていきたいと考えております。
吉田
予算化はされているのですが、一切更新するのではなく、まだ工事が始まらないうちに、今あるものに例えばシールや紙を張って、完成するまでにわかりやすく示しておくことはきょうすぐにでもできるかと思いますが、そういった対応は行わず、あくまでも工事が終わるのを待つということでよろしいですか。
復興区画整理課長
総合案内板については修正に時間を要するところがあります。発注はこれからですので、細かい図面や形態などを詰めていかなければなりません。議員御指摘のとおり、東西自由通路の東口方面と西口方面の案内板についてはカッティングシートなりで応急措置等もできますので、早目に対応したいと考えております。
吉田
やはりこのままですと、ビルの完成からもう1年たってしまい、なぜそんなに遅いのかということでさらに指摘があるかと思いますので、できるところから工夫をして進めていただきたいとお願いを申し上げます。
次に移ります。東西駅前広場の安全面について、4項目質問いたします。
まずは自転車の走行についてです。
西口バス停の利用者が多い時間帯は駅舎に向かって行列が発生しています。この行列が駅舎とバス停の間の壁となるため、自転車で横切ろうとする人がバス待ちの人と接触しそうになることが少なくありません。東口は西口に比べて駅舎とバス停の間のスペースが狭く、閖上小中学校のスクールバスを待つ児童生徒を初め、危険性を感じることがあります。自転車は車道を走るのが原則ですが、通勤通学の時間帯は車道に駐停車する車やバスも多く、自転車の走行は大変危険です。まして、ここはロータリーですので一方向にしか進むことができません。重大な事故が発生する前に対策を講じる必要があると思います。
そこで、小項目3 バスを待つ人に危険が及ばないよう、自転車走路を整備すべきについて、市長にお伺いいたします。
市長
自転車走路については、車道の路側に設ける方法と歩道内に走路を指定する方法があります。
駅前広場の車道路側はバス停やタクシー乗り場があるため走路の設置は不可能であり、歩道内は点字ブロックのために走路の指定が困難な状況であり、歩道全体を改修する必要がある自転車走路の整備については、今後の課題と捉えています。当面は自転車の誘導方策について検討してまいります。
なお、バスを待つ人への危険回避については、バスシェルターへ反射テープの設置やバス停前後に注意喚起のための施設を設置し、安全の向上に努めたいと考えております。
吉田
安全のための施設とは看板のことかと思うのですが、看板という形ではなくて、もっとしっかりとした対策を講じていただきたいと思います。
そして、スペースの件ですが、私も少し研究しましたところ、バス停付近の自転車走行空間における設計方法として、交通島設計型、停車場所混在型、停留所混在型、バス停分離型の4つに分類されるそうで、名取駅の特性と費用面から考えると、停留所混在型が最もハードルが低いと思いました。例えば仙台市の電力ビル前のバス停は、バス停で待つ人とバスがとまるところの間を自転車が通る。バスが来たら自転車走路をまたいでバスに乗るという方法をとっていますが、こういった研究については今後のお考えはいかがでしょうか。
市長
自転車走路の整備については、先ほど申し上げたとおり今後の課題と捉えていますので、その課題を整理、研究する中で調べていきたいと考えております。
吉田
名取市自転車利用環境整備計画の中にも、自転車ネットワーク路線として市道名取駅西線、そして一般県道名取停車場線が選定されています。それはロータリー内も含むと考えてよろしいのか、確認したいと思います。
土木課長
駅前広場まで含まれると考えております。
吉田
ぜひ自転車の走路もしっかり検討の中に入れて、より快適な空間をつくっていただきたいと思います。
次は点字ブロックについてです。
西口の電話ボックス付近、そして東口のタクシー乗り場前方付近に点状警告ブロックが敷かれている場所があります。この点状警告ブロックは、進路が交差、湾曲、行きどまるなどの場合に注意喚起・警告を促すために敷き詰められるものです。しかし、今申し上げた場所はそのような状況ではありません。
小項目4 視覚障がい者の混乱を招かないよう、西口における点字ブロックの敷設進路を適正化すべきについて、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
点字ブロックは視覚障がい者の安全確保と歩行情報を提供する重要な施設として捉えていますが、名取駅西口駅前広場と駐輪場前の歩道において、双方を連絡する点字ブロックが欠落していることを確認しました。視覚障がい者の安全が保たれるよう、早急に適正な場所に点字ブロックを設置したいと考えております。
吉田
済みません、東口のほうは通告しておりませんでした。東口も今申し上げた一部分ありますので、ぜひ御確認いただいた上で同様の対応をとっていただきたいとお願いいたします。
次は自動車の路上駐車についてです。
朝夕の通勤通学の時間帯は多くの自家用車がロータリー部分を通行します。家族などの送迎のために駐停車する車もあり、混み合う時間帯は危険な二重駐車を見かけることもあります。西口の場合は、自家用車約1台分少々の一般車おり場がありますが、おりるための一時的な利用ばかりではありません。乗る人を待っているのか、決して短くない時間、駐車しているケースもよく見かけます。運転手がおりてどこかへ行ってしまい、長時間とめられたままのケースもあります。近くには30分間無料で利用できる駐車場がありますが、路上駐車が多いのは、料金体系のわかりにくさと看板の書き方に原因があると考えます。案内看板を見ても、無料であることが瞬間的に伝わりにくい。また、30分は無料でも、31分たつと1時間と同様200円になる。そして、1時間は200円でも、1時間を少し超えると400円になってしまう。このような料金体系が利用をためらわせる原因になっていると私は分析しています。ロータリー内における事故を防ぐため、駐車場の利用が進むような取り組みが必要です。
小項目5 駐車料金を1時間200円から30分100円に改めるとともに、30分以内の利用は無料であることを目立つように示し、道路上に駐車しないよう注意喚起すべきについて、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
駅前広場と一体的に整備した駐車場は、本来、駅への送迎や切符の購入等短時間での利用を想定しており、料金は無料としておりました。しかし、名取駅西口駅前広場の整備直後に終日駐車する車がふえたため、やむを得ず料金を徴収することにした経緯があります。
現在の料金体系を30分以内は無料とし、その後1時間200円としておりますのは、駅前駐車場はあくまで短時間での利用が目的であることを踏襲しており、議員御提案の30分100円に料金体系を改めますと、駐車場利用者の利便性向上にはつながりますが、目的外の利用が増加する懸念があることから、改定については、駅周辺駐車場の料金体系や駐車場利用動向を見定めながら、今後の検討課題としてまいります。
なお、道路上への駐車対策としては、駐車場の30分以内無料の掲示を見やすく工夫すると同時に、路上駐車をしないよう注意看板や路面標示を設置し、定期的に広報なとりやホームページで周知していきたいと考えております。
吉田
また看板が出てきました。一体幾つ看板を立てればいいのか非常に疑問に思います。そのような形ではなく、もう少し根本的に運用方法を変えていっていただきたいと思います。
今、目的外の使用がふえることが懸念されるという答弁がありましたが、30分100円は30分刻みでメーターが上がるという考え方で、結局1時間とめたら200円になるので、1時間200円とほとんど変わりません。それほど大きな影響はないと思います。逆に適切に使う方がふえると思うので、もう少しその辺丁寧に検討されたらいかがかと思いますが、どのような検討で今の御答弁に至ったのかお伺いいたします。
市長
あくまで駅の利用を前提とした駐車場ということで御理解いただきたいのですが、目的外の利用については、例えば近くで買い物をしたり近くのマンションへの来客と、極端な話、無料であれば宿泊も可能になってしまいます。飲食をする施設も近くにありますので、そういった部分で目的外の利用が広がらないような配慮もしているということです。
吉田
路上駐車の点でもう1点お伺いしたいのですが、横断歩道の直前に一般車のおり場が設けられていますが、道路交通法第44条第3項では、横断歩道の端から前後5メートル以内の部分は駐停車が禁止されています。メジャーではかったわけではありませんが、現状では恐らくぎりぎり5メートル手前かと思うのですが、実際には横断歩道の直前といったところにとめている車もあって、横断歩道を渡る方が非常に危険なケースがあるので、そこに停車場を設けることについては検討が必要ではないかと思います。
最近、仙台市の長町駅のロータリー内の駐車を制限する新たな取り組みが始まっています。そういった周辺の自治体あるいは主要な駅の状況なども含めて、おり場について検討をもう少し行ってはいかがかと思うのですが、市長の御見解がもしあればお伺いしたいと思います。
市長
これまでもバス利用者、タクシー利用者、また送迎の方、そしてロータリーの中央を渡る歩行者など、ロータリーの中だけでもいろいろな課題がある中で現在の位置に落ちついたという状況だと思っております。議員御指摘の点についても今後の課題として検討させていただきたいと思います。
吉田
よろしくお願いいたします。
次は自動二輪車による歩道の走行について取り上げます。
西口の駐輪場は車道から離れた場所にあります。自動二輪車が利用する場合、必ず歩道を通ることになります。本来であればエンジンを切って押して移動しなければなりませんが、そのまま走行している自動二輪車も見かけ、非常に危険な状態と感じております。
小項目6 西口駐輪場を利用する自動二輪車に歩道を走行させないための対策をとるべきについて、市長の御見解を伺います。
市長
名取駅西口駐輪場周辺の歩道には、ベビーカーや車椅子利用者が通りやすい間隔で部分的に車どめを設置し、歩道であることを認知させています。しかし、車どめに一定の間隔があるため、自動二輪車が走行したまま通り抜けすることを確認しております。
緊急の対策として注意喚起の看板を設置しますが、注意喚起で効果がない場合は、車どめの間隔を狭めて互い違いに設置することや、歩道の中間にも車どめをふやすなど、自動二輪車が走行したまま通り抜けができない方法を検討していきたいと考えております。
吉田
また看板ですね。看板もわかるのですが、例えば道路交通法をよくわかっていない方がいるかもしれません。だから、今はシルバー人材センターに管理委託しているかと思いますが、例えば、駐輪場の中で二輪車、バイクをとめた方全員に注意を促すチラシなど印刷物を「皆さんこれ見てくださいね」と渡すなど、そこからまず注意喚起を図っていってはどうかと思うのですが、いかがでしょうか。
市長
道路交通法を余りよく知らないドライバーがいるということはあり得ないと思っております。基本的にはモラルの問題ですので、市としてできる対応としては先ほど申し上げたような中身だろうと思っているところです。
吉田
看板は景観を損ねる側面もあります。そして、車どめも、それ以外の走行あるいは歩行する方に危険が及ぶ可能性もゼロとは言えません。あの辺は広場といって公園でもあり子供たちが遊んだりもしていますので、そういった部分も総合的に考えて、今モラルとおっしゃいましたが、ではモラルの部分に問いかけるような対策からまず一つ一つ進めていただきたいとお願いをいたします。
それでは、次の質問です。ごみについてです。
東口のペデストリアンデッキに出るあたりのドアの手前、また西口のエスカレーター乗り場付近に飲み物の自動販売機が設置されています。そして、名取市環境美化の促進に関する条例に基づき、空き缶等回収容器も置かれています。販売業者によって定期的に容器の中身が回収されていますが、時々中をのぞいてみると、缶、瓶、ペットボトル以外の一般ごみまで捨てられております。先日、ちょうど回収作業中の業者の方がいましたので、一般ごみがどのぐらい入っているのか尋ねたところ、3分の1ほどは弁当のパックなど外部のプラスチックごみだと嘆いておりました。
小項目7 空き缶等回収容器に一般ごみが投入されている。ごみ箱を設置すべきについて、市長にお伺いいたします。
市長
名取駅東西自由通路内には、施設利用者の利便を図る目的で、清涼飲料自動販売機を東側と西側の2カ所にそれぞれ1台、合計2台を設置しています。空き缶等回収容器は、清涼飲料自動販売機2カ所と同一箇所にそれぞれ3台、合計6台を設置しており、これらは全て空き缶やペットボトル等専用の回収容器となっております。
御指摘の一般ごみが投入されているとのことについては、少量の一般ごみが日常的に投入されていることは確認をしていますが、これらの行為はマナーの問題と捉えており、空き缶等回収容器に張り紙を貼付し、一般ごみ投入防止の啓発を行ってきたところです。今後も引き続き一般ごみ投入防止の啓発活動に努めていきたいと考えておりますので、ごみ箱設置については現段階では考えておりません。
吉田
空き缶等を回収するのは、清涼飲料自動販売機を設置している業者の責任であると伺ったと思うのですが、それは間違いないのですよね。そうなりますと、飲料水のメーカーの業務に当たっている方は、あくまでも缶と瓶とペットボトルを回収するのが義務であって、一般ごみまで持ち帰る義務はないと思うのですが、そこの整理についてお伺いしたいと思います。
市長
清涼飲料水の自動販売機で販売された分を回収しているということであり、現状、一般ごみについては業者の厚意で持っていっていただいているのだろうと思います。御指摘の件については今後話し合いをさせていただきたいと思っておりますが、基本的には、仮に一般ごみは回収できないとなれば、いわゆる施設利用者の利便性を図る意味で置いている自動販売機そのものが置けないことになってしまいますので、そこについてはやはりマナーを守っていただくよう啓発していくことが市としてまず行うべき取り組みだろうと私は考えております。
吉田
当然、マナーの啓発は今までも行っているはずですし、これからも必要だと思いますが、やはりこれだけ交流人口、交流人口と言っていますと、市民にマナーを啓発しても、市外から来る人も大勢いますから限界があります。そうなると例えば、一般ごみを空き缶等回収容器に捨てるだけまだましで、もしそれがなかったら路上等にポイ捨てされてしまってもおかしくないと思うのです。ですから、今は単純に市が清涼飲料水の業者に依存してというか頼ってというか甘えている状況であって、やはりごみについて市として責任を持っていただきたいと思います。
それはどういうことかといいますと、最近のニュースで気仙沼市が海洋プラスチックごみ対策の行動計画を取りまとめたとありました。新聞にも載っていましたが、これについては、家庭のごみが捨てられるというリスクも予想していますが、それでも海を守るという気持ちから、行政が責任を持ってごみの回収のためのごみ箱の設置を決めたそうです。
本市には本市の事情があるかと思いますが、まず実験的に名取駅という一番人が通るところに試験的にごみ箱を置いてみて、どのような利用状況かといった課題等を検討していただきたいと思いますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
世の中の流れは、ごみを減らす、リデュースの方向でありまして、ごみ箱は徐々に減らしていく方向にあると。ごみは持ち帰ることが基本だと私は考えております。
吉田
ポイ捨てされたごみはどこかに消えて存在しなくなるのではありません。みんなそれが川に流れ、海に流れ、汚染しているのです。それを防ぐのは本来であれば行政の責任だと私は思います。これはこれからも一切譲りませんので、今後また改めて申し上げたいと思います。
次に、大項目2に移ります。一般家庭用の除草剤の危険性についてお伺いいたします。
除草剤とは何か確認したところ、主に雑草を枯らすために用いられる農薬の一種で、全ての植物を枯らす非選択的除草剤と、対象となる植物だけを枯らす選択的除草剤に分類されるそうです。そして、農薬や除草剤とは薬のような表現ですが、除草剤を英語に訳すとハービサイドという単語で、ハーブは草、サイドは殺す、草を殺すという意味で使われています。除草剤は草だけではなく人体への影響もあると疑われており、特にグリホサートという成分が世界的に今問題となっています。それについては最後の小項目で詳しく説明させていただきます。それ以外の成分についても、人体に完全に無害というものはありません。使用方法を守って、適切に管理、利用すれば人体に影響はないとされていますが、体が小さく成長過程にある乳幼児や子供への影響が心配されます。また、化学物質過敏症を患う原因の一つとしても除草剤の成分が疑われています。 土地を所有している人にとって、毎日が雑草との闘いです。私自身も現在一軒家を借りていますが、やはり雑草を取り除くのには大変骨が折れます。最近の新築の一軒家は、敷地全体をコンクリートで覆って庭がない物件もふえているようです。個人の敷地でもこのような状況ですから、広大な土地を所有する行政であればなおのこと、雑草を取り除くために人手と費用を要していると思います。まずは現状を確認させてください。
小項目1 市が管理する施設における除草剤の使用状況と、使用されている除草剤の品名について、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
市が管理する施設の除草作業において除草剤を使用している施設等は、東日本大震災慰霊碑、児童センター1カ所、愛島老人憩の家、6地区の農道や用水路、実方の墓、共同墓地2カ所、雨水ポンプ場2カ所、愛島東部仮設住宅、消防署です。
また、使用した除草剤の品名については、草退治Z粒剤、みんなにやさしい除草剤おうちの草ころり、ラウンドアップ、カソロン粒剤2.5、MCPソーダ塩、デゾレートAZ粒剤、タッチダウン、バスタ液剤、はや効き、グリホサートエースになります。
教育長
教育委員会が所管する施設において平成30年度に除草剤の使用実績があった施設は、学校教育施設が16施設中8施設、社会教育施設が12施設中2施設、文化・スポーツ施設が16施設中2施設となっております。
また、使用した除草剤の品名については、グリホエキス液剤、クサクリーン液剤、ビスマターJ、クサクリア、グリホアップ、ラウンドアップ、グリホサート41%、ラウンドアップマックスロード、デゾレートAZ粒剤になります。
吉田
答弁に児童センターや学校施設とあったので、ぞっとしたところです。さまざまな除草剤が販売されていて、その都度選んで購入していると思いますが、どこにどのようなものを使うかといったことについてはどのように検討して決定しているのか、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
これまでは施設ごとの判断によって市販の除草剤を購入して使用していると思っていますが、今後については、今回指摘いただいたことも含めて、薬剤、それから発注先の統一について検討していきたいと考えております。
教育長
現状におきましては、各施設の判断で購入して使用しているのが実情です。
吉田
どの薬剤にどのような成分が含まれているかまで詳しく確認していないのが現状だと思うのです。人体や環境へのリスクについての研究、使用のためのガイドラインの策定に関しこれまでに協議が行われた経過があったのかどうか、市長と教育長にお伺いしておきたいと思います。
市長
そもそも市でどこまでそういった研究ができるかということもあるわけですが、これまではそういった経過はありません。
教育長
教育委員会としましても、市長答弁と同様に特に調査研究した実績はありません。
吉田
では、次に移ります。まず、子供への配慮についてです。
ある量の化学物質が成人にとって影響が少ないとしても、体の小さい子供にとっては影響が大きくなるものです。例えば薬の服用量は子供と大人では異なります。成人よりも子供のほうが、そして子供よりも胎児のほうがより影響を受けやすいと考えられています。先ほどの御答弁では、学校教育施設、児童センター、そしてまた多くの方が利用する施設にも除草剤が使用されている現状でした。こうした公共施設の中でやはり特に子供が活動する施設については、これから除草剤を使わないことをはっきりと文書で示して、そして子供たちが安全に育つことができる環境を確実に守っていかなければなりません。
小項目2 学校や児童センター、保育所、公園など、子供が活動する公共施設において除草剤を使用しないことを明文化すべきと思いますが、市長と教育長の御見解をお伺いいたします。
市長
市長部局が所管する施設のうち、保育所では除草剤を使用しておりませんが、1カ所の児童センターにおいて、子供の立ち入りを禁止している箇所に限り除草剤を使用しております。また、子供の利用が多く見込まれる公園では除草剤を使用しておりません。
散布に際しては場所を限定するなど安全に留意して行われており、現在のところ、除草剤を使用しないことを明文化することは考えておりません。
教育長
教育委員会が所管する施設においては職員、学校においては職員に加え児童生徒と保護者による除草を基本とし、除草剤の使用は除草作業が困難な場所に限定されており、子供が日常的に活動する場所では使用しておりません。このような実情を踏まえ、現在のところ、除草剤を使用しないことを明文化することは考えておりません。
吉田
現時点でそのように市長部局も教育委員会も除草剤を使用できる場所と使用しない場所がほぼ定められていると思うのですが、改めてそれをしっかりと明文化して、保護者、利用者にきちんと示したほうが、より市としてこれだけ責任を持って対応していることを理解していただけると思うのですが、今後、明文化についての検討はやはり必要ないということでよろしいのか、市長と教育長にお伺いいたします。
市長
国の基準を満たして一般の小売店で販売されている除草剤について、確かにいろいろと心配する声はあると思いますが、正しい使い方をして、そしてまた手作業で除草できない箇所もありまして、いわゆる除草剤の使用全般を否定するような形での明文化は考えていないということです。
教育長
先ほども答弁申し上げたように、特に学校においては職員、先生方、そして子供たち、またPTAの奉仕作業等で保護者の方の協力をいただいて行うのが基本的な除草のあり方だと考えております。ただ、学校によって実情が違い、除草が非常に困難な箇所等もありますし、除草のために必要な労力が十分ではない状況もあります。そういった中で、子供たちが日常的に活動しないような場所、あるいは除草作業自体が危険な場所等においては除草剤を使用しているのが現状です。それぞれの除草剤の使用上の注意等については各施設で遵守して使用していると判断していますが、あえてそれを使用しないようにと明文化することについては考えておりません。
吉田
自分自身の経験も申し上げましたように、やはり除草は非常に大変であることは理解しています。ただ、生徒が立ち入らない場所であっても、すぐ近くの敷地であれば風で飛んでくるわけで、生徒が余り使用しない場所だから薬を散布していいということではありません。生徒が活動する場所もしない場所も、レベルは違うかもしれませんが、いずれ体に吸収されれば同じだということはわかっていただきたいと思うのです。ですからそういった意味で、除草剤の成分がいろいろとある中で、これから深く掘り下げていきますが、この成分は使用しないということを明文化して、ぜひ市長部局でも教育委員会でもはっきりと示していただきたいと思います。
次に移ります。今度は外部で管理している施設についてです。
本市でも幾つかの公共施設において管理を外部に行わせる指定管理者制度が導入されており、今後も名取市サイクルスポーツセンターなど拡大していく見込みです。指定管理の場合、管理権限は指定管理者が有することとなっており、屋外の管理において除草の方法については現場任せになっているのが現状ではないかと思います。また、指定管理者制度を導入していない施設であっても、民間の力をかりて管理されているものがあります。そのような場所でも除草剤が使用されていないと言い切ることはできないと思います。
除草剤の危険性に対する認識は管理する団体ごとにさまざまではないかと思いますが、安全を確保するため、特に小さいお子さんや妊婦の方が利用する施設については除草剤の使用を制限することが必要だろうと思います。
小項目3 管理を外部に委ねている施設における除草剤の使用制限について指針を設けるべきについて、市長と教育長の御見解をお伺いいたします。
市長
市長部局が所管する施設のうち、管理を外部に委ねている施設においては、除草作業において除草剤を使用しておりません。現在のところ、除草剤の使用制限について指針を設けることは特に考えておりません。
教育長
教育委員会の所管で管理を外部に委ねている施設におきましても使用は限定的であり、現在のところ、除草剤の使用制限について指針を設けることは特に考えておりません。
吉田
市長部局にお伺いしたいのですが、小項目2で公園では除草剤をまいていないという答弁でしたが、今の御答弁ですと除草作業は市が直接業者に依頼しているのだろうと思いますが、それは年に1回か2回だと思います。その間に管理団体は公園で除草剤を全く使っていないと全て把握されているのですか。
クリーン対策課長
市内の施設の管理をお願いしている各団体に照会をかけたところ、市長が答弁した調査結果の報告が上がってきましたので、そのように御答弁申し上げた次第です。
吉田
細かいことになりますが、公園愛護協力団体はたくさんあるのですが、全てに当たったということでよろしいのですか。
都市計画課長
公園愛護協力団体も草取りに除草剤は使っていないことを一応確認しております。
吉田
一応という言葉がありましたが、一つ一つ聞いて回って、そして自分たちの公園愛護活動の中で除草剤は使っていないと、どの団体も使っていないという回答を得たということでよろしいのですね。
都市計画課長
曖昧な言葉を使って申しわけありませんでした。公園愛護協力団体では除草剤は使っておりません。
吉田
除草剤は確かに便利ではあります。しかし万能ではなく、耐性を持つ別の種類の雑草が発生することもあります。そのようなことになるとより強い毒性を持つ薬剤への依存を招きますから、土壌汚染の意味も含めてやはり科学的根拠に基づいて市民に示すべきではないかと思います。その点については余り前向きではないようでしたので少しがっかりしましたが、次に市民への周知についてお伺いいたします。
除草剤は先ほど申したように風に乗って隣に飛んでいってしまうことがありますので、自分の家で使用していなくても、隣の家で使用していれば同じようなことになってしまう。特に小さな子供がいる家庭でどんなに気をつけても、周囲で散布されることによって、結局子供の健康を危険にさらすことにつながってしまうのではないかと懸念されるわけです。これはやはり市民全体で除草剤の危険性に対する認識を共有することが必要だと思います。
行政は、市民の安全な生活を確保するために、自然災害に対するハザードマップや野焼きの禁止などいろいろな広報を行っています。これらは法律や条例に基づくものもありますが、防犯、防災、それから健康に関する情報など、独自の判断で呼びかけているものもあるはずです。除草剤についても同様に、人体に有害な成分を含む商品があること、不適切な使用によって健康や環境を害することなどについて市民に知っていただく取り組みを行っていただきたいと思います。
小項目4 除草剤の使用による健康や環境へのリスクを市民に周知すべきについて、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
一般家庭用に販売されている除草剤は、国で定めた基準を満たした上で認可を得ています。しかしながら、除草を目的とした薬剤ですので、その使用に際しては安全に留意し、希釈濃度や使用量といった使用方法を正しく守らなくては人や環境に悪影響を与える可能性があります。
基本的には使用者の責任において取り扱われるものですが、事故や被害防止のため、市としてもホームページ等を通して使用に当たっての注意喚起に努めていきたいと考えております。
吉田
ホームページ等いろいろな媒体を使ってぜひ周知を図っていただきたいと思います。
市長答弁に国の認可基準などの話もありましたが、この認可基準が日本では非常に緩くなっているという点についてお話をしますので、どうぞお聞きいただきたいと思います。
先ほどのグリホサートについてです。このグリホサートを主成分とする除草剤がラウンドアップという商品ですが、これは1974年から販売が開始されました。このラウンドアップを開発したのはモンサント社という会社で、ベトナム戦争で使用された枯葉剤を製造していた会社として知られております。その後、1996年にはラウンドアップだけに耐性を持つ遺伝子組み換え大豆を開発しました。この大豆畑にラウンドアップを散布すれば、大豆だけが生き残り、その他の雑草は全て死滅するという、大変生産性につながる夢のような農業が実現しました。生産性が飛躍的に向上したため、農薬と大豆のセット販売により世界中でシェアを伸ばしました。大豆のほかにトウモロコシ、菜種、綿なども、ラウンドアップに耐性を持つ品種が遺伝子組み換えによって開発されています。そのようにしてモンサント社は世界の遺伝子組み換え作物の種子について最大で9割までシェアを伸ばしました。世界で最も影響力のある10社に選ばれるまでに成長したという経緯があります。
このモンサント社はグリホサートは安全であるという説明をずっと続けていました。しかし、2013年ごろから、がん細胞の増殖を誘発するなどの危険性を指摘する研究結果があらわれ始めます。そして、2015年、WHO(世界保健機関)の外部研究機関である国際がん研究機関が、グリホサートについて人に対して恐らく発がん性があるとするグループ2Aに指定したことを発表しました。これは発がん性があるとするグループ1に次いで高いレベルです。この発表を受けて世界の国々で動きがありました。例えばスリランカはグリホサートの輸入を禁止、デンマークはグリホサートを発がん性物質に指定、イギリスのエジンバラ市議会は段階的なグリホサートの排除を決定、ドイツやスイスなどでは民間の事業者がグリホサートの販売を自主的に中止するなどの対応に至りました。そして、グリホサート排除の動きは次第に広まり、フランス、イギリス、イタリア、オーストリアで3年以内に禁止、スウェーデンは個人使用を禁止、中東・湾岸協力会議加盟6カ国が禁止、オーストラリアのビクトリア州が公共用地における使用の見直し、インドでは5つの州が販売を禁止、ベトナムは輸入を禁止、このように世界中で規制が強化されました。そして、民間事業者でも同じように販売や使用の自主的な中止が広がっております。一方、モンサント社はドイツのバイエル社に結局買収されたわけですが、そのドイツについては使用延長をめぐって政府内で意見が割れたという経緯があります。
このような世界の動きの中、日本政府は何をしたかといいますと、2017年12月、グリホサートの残留基準を緩和しました。例としてトウモロコシは5倍、小麦は6倍、ソバ150倍、ヒマワリの種400倍という引き上げ幅です。これは除草剤とセットで販売され、当然それらの作物にはグリホサートが多く残留していることになります。そして、遺伝子組み換え作物そのものと残留農薬について、人体への影響に対する懸念から多くの国が排除に向けた取り組みを始めていますが、行き場を失った遺伝子組み換え作物とグリホサートは世界でトップクラスに規制が緩い日本へと流れ込んできている、このように推定されています。この遺伝子組み換え作物については、機会をいただけましたら改めて取り上げたいと思いますが、今回は、市内でもホームセンターやドラッグストア、100円ショップなどで簡単に手に入る、そして市でも使用実績のあるグリホサート系除草剤に焦点を絞りたいと思います。
小項目5 グリホサートを含有する一般家庭用除草剤の市内での売買及び使用を条例で規制すべきについて、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
現在、グリホサートについては、平成28年7月に内閣府食品安全委員会にて「発がん性、繁殖能に対する影響、遺伝毒性は認められない」との評価をしており、使用することは禁止されておりません。
薬剤の規制については、国で判断、対応すべき事柄であると認識しておりますので、条例での売買及び使用の規制については考えておりません。今後、グリホサートの取り扱いに関しては、国の動向を注視していきたいと考えております。
吉田
日本はそのように、世界の評価と違って、なぜか問題がないという結論を出しているのです。これは実は日本だけではありません。モンサント社がバイエル社に吸収されるまでに本社を置いていたアメリカでも、同じように一部の州を除いてグリホサートに対する規制がほとんど進んでいませんでした。そして、政府は危険性について否定し続けてきました。そうした中で、2018年、グリホサートを長年使用し続けてきた学校用務員の男性が、重いがんを患った原因はグリホサート系除草剤であるとしてモンサント社を提訴し、結果、被告は日本円で約320億円の賠償金を支払うべきとの判決を勝ち取りました。そして、その後もアメリカではモンサント社やバイエル社の敗訴が続いています。現在までにグリホサートをめぐる訴訟は1万件を超え、バイエル社が支払う賠償金の額は日本円で1兆円を超えることが見込まれています。
グリホサートの発がん性はこれでもう確定したと言っても過言ではないと私は思います。それが今この瞬間も私たちの身の回りで使われている。子供たちの体内に少しずつ吸収されていっていると思われる。こうした未来を担う子供たちの体がむしばまれている現状を市の決断で変えていただきたい。市長にそのことをお願いしたいと思います。もう一度御見解をお伺いいたします。
市長
グリホサートに関する評価については、例えばFAO/WHO合同残留農薬専門家会議で2016年5月に、食を通じてグリホサートが人に対して発がん性のリスクとなるとは考えにくいと発表しております。また、欧州食品安全機関(EFSA)も2015年11月に、グリホサートは発がん性または変異原性を示さず、受精能、生殖等に影響する毒性を持たないと発表し、米国環境保護庁では2017年12月に、グリホサートは人に対して発がん性があるとは考えにくいと結論づけた評価をしていることも情報として入っています。カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの規制当局についても同様の判断をしていると、発がん性のリスクは低いと結論づけていることもあり、いずれこのことについては本市単独で判断できる状況ではないと考えております。国の基準で、国において判断、対応すべき事柄だということで御答弁申し上げたとおりです。
吉田
その国が、今、異常な状態にあるということなのです。なぜグリホサートの規制が日本だけ緩いのか。余り結びつけたくはないのですが、結びつくかどうかわかりませんが、グリホサートを製造している大企業が政権与党に対して非常に多額の献金をしているという収支報告も確認しております。そんなことは直接関係ないと信じたいわけですが、市長答弁でカナダも取り上げられたので、これは原典まで確認できていないのですが、ブログの記事に掲載されていたカナダのある村での事例を紹介したいと思います。ハドソン村というところですが、議会で除草剤などの使用に許可を必要とする罰則つきの条例を制定したことに対して、芝生の管理会社が、国の許可を理由に、条例は越権行為であり、無効であると裁判所に訴えたそうです。しかし、最高裁は自治体の規制の正当性を認めるという判決を出しました。
自治体は国の下部組織ではありません。自治体には自治体なりの規制を設けることができる。それは国の規制を最低限としてです。国の規制より甘いものはできません。国の規制を最低限として、それよりも厳しい規制を設けることができる。これが日本の地方自治なのです。それが認められている。この地方自治とは、地方分権一括法の施行によって大分変わってきていますが、それでもまだまだ国、県の補助金に頼らなければ多くのことはできない今の制限された自治の中でこうした規制を設けることは、ほとんど珍しい例外的な自治体の権限であると私は思います。昭和44年に東京都が制定した東京都公害防止条例が、全国的な環境保全や反公害の機運を高めることにつながり、そしてついに国を動かして公害関係法令の大幅な整備を実現したということもあります。
もしグリホサートの売買、使用を規制する条例を本市で制定すれば、まだ全国に例がありませんので、全国から注目され、そして本市を前提としていろいろな自治体が研究検討を進めていく。そのようにしていつか国を動かすことにつながると思うのです。先日、議員協議会での名取市第六次長期総合計画基本構想案の説明で、キャッチフレーズ「なとりプライド」とありましたが、本当に地域にプライド、誇りを持つというのは、そういう意味で自分たちの権限をしっかりと守って、使って、そして国に対して言うべきことは言っていく、守るべきものは守っていくというのが自治体のあるべき姿ではないかと私は思います。
市長の個人的なお気持ちをお聞きしたいと思います。市長はグリホサートを市として規制したいですか、したくないですか、市長の本心をお伺いします。
市長
本心と言われたので一般論と言ってはまずいのかもしれませんが、基本的に、例えば名取市発でそれこそひいては日本全体を変えられるような条例が制定できれば、それはそれですばらしいだろうと思いますが、そもそもこのグリホサートに対する危険性も含めて世界の中でもいろいろと議論が分かれている。日本は国の基準でそれを認めている中で、本市がそれを規制する条例を制定するだけの根拠が情報としてまるでないわけです。今後それを調べるのに、例えばどのような実験をして検証を行うのか。逆に言えば、条例ですから、議会に上程したときに説明する根拠は何もない状況になるわけです。したがって、現段階でというよりも、これは恐らくそういった部分について本市として独自の情報を持って、独自の判断をすることは至難だろうと思っております。そういう気持ちでおります。
吉田
結局規制はしたくないということですね。そのように捉えました。わかりました。 今回は一般家庭用の農薬だけ取り上げて、農業経営者が使用する農薬については取り上げませんでした。ただ、これも今非常に世界的に問題になっているネオニコチノイドという農薬などがあり、子供の脳や神経などへの発達性神経毒性が指摘されています。これについても、日本は平成23年に残留基準を最大で2,000倍引き上げているという経過があります。国として考えることはもちろんですが、市としてできることがあれば、より自主的に主体的に取り組んでいただきたい。この件に限らず今後もそのことを強くお願い申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきたいと思います。
本会議
(議案第66号 名取市震災復興伝承館条例)
吉田
第4条で、指定管理者制度をとるということが書かれております。施設の展示品などの内容については、管理者のほうで例えば内容を変えたり、つけ加えたり、撤去したりするのか、それともそれは市のほうで行うのか、そこの部分についての役割分担をお伺いしたいと思います。
復興調整課長
展示スペースは施設の中に大体100平方メートルほどありまして、東西に2カ所設定しております。海に近いほうの東側の部分については、復興の歩み、防災の備えとか、そういう意識啓発のパネルなど、ある程度固定したものを考えております。西側については、指定管理者のみならず、いろいろな団体の皆さんが企画展等で使えるよう、使用許可という形で使っていただくスペースとして考えているところです。
吉田
東側のほうがある程度固定ということであれば、市が、もうこの展示と決めたら、指定管理者側ではその内容については手を入れることができないということでしょうか。現場のいろいろな運用の中でもっとこうしたほうがいいなということや、利用者からの意見などを受けてもっとこういう展示があったらいいなということがあったとしても、指定管理者にはそこまでの権限はないということでよろしいですか。
復興調整課長
今御説明させていただいた東西の考え方は基本的な考えで、固定で置くところもずっとそれを動かさないということではありませんので、内容を変えたり、そこに新たな展示を加えたり、そこは柔軟に進めていきたいと考えています。
(議案第67号 名取市こどもまちづくり基金条例)
吉田
今年度初めてこの事業がこどもファンド事業として行われているということかと思います。当初の予算の中で、それまで行われていた民間企業の事業を名取市として引き継いだという御説明がありました。それで今度こうやって基金まで設立するということですが、この事業が民間の企業でなぜ取りやめになったのか、引き継いだ本市としてはその辺の事情もいろいろと把握されていると思いますので、わかる範囲でそのあたりの経緯についてお聞きしたいと思います。
男女共同・市民参画推進室長
民間企業の事業を引き継いだということで、その民間企業の事業の経過ですが、民間企業としては5カ年分の事業費を一括してNPO法人に寄託をして、その中で事業が行われてきました。その5年間の事業の最後の2カ年間についてこどもファンド事業といったものが実証されたということで、当初から5カ年の期間で区切って引き継いだという経過です。
吉田
今、いろいろな事業というかお金の使い道として、民間でできることは行政から民間にどんどん任せているという流れが全国で進んでいるかと思います。民間事業者が5年と先に決めていたとしても、それがもしより有効なものであれば引き続き行われていたかと思いますが、あえて5年でやめたものを本市が引き継ぐという判断に至った理由をお伺いしたいと思います。
男女共同・市民参画推進室長
企業が5カ年間を区切って、その後の事業費について措置しないことについては、民間企業それぞれの御判断があると思いますので、市としてその判断について意見を申し上げる立場にはないかと考えます。
名取市としては、その事業を運営しておりましたNPO法人からの依頼を受けて、その2カ年間行われた事業にアドバイザー的な立場で協力してきたところです。そういった中で、初年度は5団体5事業、2カ年目は8団体8事業が採択され、事業的には非常に広がりを見せてきていること、また、子供の人材育成という観点からは市の考え方と一致するところもありますので、これを一企業の事業としてそのまま終了させてしまうことについては、行政としても非常にもったいないところがあるのではないかということで、市としてこの事業を引き継いで実施していきたいと考えたところです。
吉田
第2条で「子どもが主体となって取り組む」とあります。先ほどの男女共同・市民参画推進室長の答弁の中にも、子供の主体性、人材の育成ということがありました。こういった観点は教育活動ではないかと思います。教育活動であれば教育委員会が所管するべきかと思いますが、なぜそれを教育委員会でなく市長部局でとお考えなのでしょうか。
男女共同・市民参画推進室長
一つにはそういった教育的観点もあるかとは思いますが、こどもファンド事業の中で目的としていることとして、一つは先ほど申し上げた人材育成もありますが、子供たちがみずからまちづくりに取り組むといったところもその大きな柱の一つと考えているところです。そういった意味では、学校教育等で行われる教育活動ではなく、まちづくりといった観点が入ってきますので、これは市長部局のほうで所管すべき事業であるということで、我々男女共同・市民参画推進室が施行させていただいているところです。
吉田
まちづくりに関しても教育活動の中で、その重要性というか、将来のまちづくりに参画していける人材を育てるための活動は教育課程の中でしています。なぜ教育委員会という機関が置かれているのかは、言うまでもなく、市長から独立した第三者的な合議機関として、教育に政治を持ち込まないためです。このように子供たちにという一つの名目で補助金を出すという形は、ともすれば、子供たちに審査会をさせる、その担当までも子供たちがといっても、結局導いていくのは市の職員であると。であれば、政治的に完全な中立性というものを確保することは難しいのではないかと。やはり教育委員会として実施するべきではないかと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。
男女共同・市民参画推進室長
今、議員がおっしゃられたような政治的な中立性といった観点というところはあるのかもしれませんが、例えば市民活動等においても、そういった社会教育の部分は公民館で行って、その後、具体的に活動するといったような段階になれば市長部局が所管しております市民活動支援センターがそのサポート等を行うなどといったようなところで役割分担を行いながら事業展開をしているところもあります。この事業については、そういった教育的な観点ではなく、その後にあるまちづくりといったような具体的な活動の中での助成ということで整理をしているところです。
吉田
もう一度お伺いしますが、子供に教育的な部分が含まれる活動を行う際に、どのようにして政治的中立性を担保するのか。一定の方向に導いていないことをどのように説明されていくのかについてお伺いいたします。
男女共同・市民参画推進室長
こちらから事業を指定するなり、あるいは提案の内容を改変するような作業をこちらで行ったりするのであれば、議員御指摘のようなことに抵触する場合もあるのかもしれませんが、あくまで子供たちの自主性に基づいた提案を受けて、それを子供たち自身が審査をするといった流れで行っていますので、今議員から御指摘されたようなことについては、この事業を行う中では当たらないと考えております。
吉田
審査という手続が途中に入ってきますので、実際の定数というか定員というか、決められた枠をはみ出してしまう部分があろうかと思います。そもそもこの事業は子供も審査に当たるということですが、その審査に当たる子供たちがどういう事業を選んでいくのか、審査をする際の観点というか採点の仕方については、やはりどこかで大人の導きが入っていようかと思います。そういうのも全て排除して、全部子供に任せるとなれば、男女共同・市民参画推進室長のおっしゃるとおりなのかもしれませんが、それでは事業そのものも成り立たないと思いますし、子供が主体となって審査をするとはいっても、そういう事情までわからなければ、やはりこれは本当に中立なのかなと。そこではじかれたものは何か市にとって都合のよくないもので、選ばれたものだけが都合のいいものではないかなと思う人が出てしまう。みんなが思っているというのではなく、そのように思われかねないということで、外形的公正性という意味で、そういうものを確保していかなければいけないと思いますが、その辺のより丁寧な説明については今後どのようにお考えなのかお伺いいたします。
男女共同・市民参画推進室長
この事業を行うに当たって、我々男女共同・市民参画推進室は、あくまで事業の裏方としてサポートに回っております。そういったことから、直接子供が提案する事業の中身に口を出して、これはやってはいけないとか、これをやってほしいといったような趣旨でお話をすることはありません。
それから、審査会の審査基準を5つ定めて今年度は実施していると先ほど紹介しましたが、この基準は、チーフアドバイザーとして就任いただいている早稲田大学の先生が、子供たちの研修会の中で子供たちと直接話し合いをして決めているものであり、この話し合いの中にも我々は裏方として入るだけで、その内容について口を挟むということはしておりません。そういう意味では、行政的な関与はサポートのみに限られるということで御理解いただければと思います。
吉田
5番吉田 良です。ただいま議題となっております議案第67号 名取市こどもまちづくり基金条例について、意見を申し述べながら賛成の立場で討論させていただきたいと思います。
そもそもこの条例の基金の支出先であるこどもファンド事業について、令和元年度の予算の中で既に事業化されておりますし、本来であれば、そこでより深く自分自身考えて発言するべきだったと、まずは反省の気持ちをここで申し上げたいと思います。
今ほど執行部にいろいろと質疑をさせていただいた中で、やはりどうしてもこの事業には子供の教育という側面があることは事実であろうと思います。そして、教育的な部分とまちづくりの観点という部分と、どちらが多い、どちらが少ないということで比較するのではなく、やはり教育的な活動に含まれるのであれば、それは第三者的な立場である教育委員会の所管として進めていくべきだろうと私は思います。
チーフアドバイザーという立場の方に入っていただいて、市長部局のさまざまな関与はないように努めているという御発言でありましたので、それはそのように今後もしていただければと思いますが、チーフアドバイザーの選出に関しても本当に中立・公正な立場で選ばれたかどうか、それは教育委員会ではないわけですので、そのあたりにはどうしても私自身は疑問が残ります。
しかし、こどもファンド事業という、子供たちが主体となって将来のまちづくりに携わり、そして人材を育成していくというこの事業そのものについては、決して否定するわけではありません。運用に関して、次年度以降、教育委員会に移すなり、しっかりと市民に説明できる体制をとっていただけるようにお願いいたしまして、このたびはこの条例に関しては賛成させていただきたいと思います。
(議案第68号 名取市森林環境譲与税基金条例)
吉田
先ほど郷内議員からの御質疑に、民有地についても管理できるという御答弁でしたが、その根拠となるのは森林経営管理法ということでよろしいですか。
農林水産課長
今回の新しい森林の経営管理の制度については、この名取市森林環境譲与税基金条例の補足説明等であらかじめ説明しているとおり、森林経営管理法に基づいて行われるということです。
吉田
面積などの要件はないということでしたが、森林経営管理法によると、市町村で管理計画のようなものを策定しなければならない、それも土地ごとにだったと思います。そうしたものについて、今回この名取市森林環境譲与税基金条例が成立した後どういう形で進めていくのか、スケジュールがもしあればお知らせいただきたいと思います。
農林水産課長
今後の進め方については、経営管理が不十分な森林のうち、林業経営が成立する可能性の高い森林を特定して、年度内には森林所有者に対する意向調査を実施したいと考えております。その関係予算については、またしかるべき時期に予算措置をお願いしたいと考えているところです。それを踏まえて、次年度以降、具体的な取り組みを進めるということで考えております。
(議案第69号 名取市サイクルスポーツセンター条例)
吉田
名取市サイクルスポーツセンターの再建まで残り1年というところかと思います。今回も指定管理者制度をとるということですが、宿泊施設、温泉施設、食堂、運動施設と非常にさまざまな分野にわたっての管理になってくると思います。そういったものについて、例えば指定管理を受けた団体が自分のところの専門外の部分について再委託をすることは認められているのでしょうか。
政策企画課長
指定管理者制度の担当ということで、政策企画課から答弁を申し上げます。 指定管理者制度においても、事実上の行為、例えば清掃業務などといった指定管理の許可等の管理業務に直接かかわらない業務等については、包括的な委託でない場合については再委託も制度上は認められているところです。
吉田
今の政策企画課長の御答弁で少し理解できなかったのですが、その認められる部分と認められない部分は明確な線引きがあるのでしょうか。そして、今回のこの名取市サイクルスポーツセンターに当てはまる部分がもしあるのであれば、お知らせいただきたいと思います。
政策企画課長
前段の部分について答弁申し上げます。明確な基準があるかということですが、これについて、例えば何%以上の事業費といったような明確な線引きがあるわけではありません。先ほど申し上げたように、そもそも指定管理の業務として条例で規定している業務の内容が包括的に再委託をされない範囲ということで、これについては個別の事案ごとに判断すべきものと考えております。
吉田
先ほど質疑した指定管理者の再委託ですが、この名取市サイクルスポーツセンターの施設の中で再委託ができると見込まれる部分、例えば1階の売店とか食堂とか細かくいろいろと分かれるかと思いますが、見込まれる部分についてお伺いしたいと思います。
生活経済部長
名取市サイクルスポーツセンターの指定管理の関係ですが、今後、募集要項等を定めて公募することになりますが、事業者については単独で事業者として応募する場合もありますし、それぞれのノウハウをもって事業体で応募する場合もありますので、包括的に委託されるかどうかについては公募の申請の内容を見て判断するようになるかと思います。
吉田
でしたら、主体となる団体に対して委託を大きくお任せして、その中から小さな事務について再委託をする際に、考え方としては孫請のようになるのでしょうが、そういう団体は収支の報告や指定管理者のモニタリングの報告などについては、やはり一体となって指定管理者の枠の中で処理されるのか、それともそちらはまた別に何か示さなければいけないようになっているのか、そのあたりの整理は今どうなっているのでしょうか。
生活経済部長
指定管理については、事業者側で事業報告や、あるいはモニタリングの調査もありますので、その中で包括的に中身を確認していくことになろうかと思います。
吉田
施設で温泉に入る宿泊の方、そして日帰りの方がいて、先ほど名取市市税条例の改正で日帰りの入湯税についても決まったところですが、そちらの免除をされる範囲に12歳未満という部分がありました。12歳未満というのは小学校6年生のあたりで、小学校6年生は11歳から12歳までだと思いますが、これは小学校6年生が施設を利用する際に12歳になっていたとしても、なっていなくて11歳だったとしても、同じ料金を徴収するということでよろしいのですか。
商工観光課長
名取市サイクルスポーツセンターは入浴料として一般と小学生ということで条例に定めており、「「小学生」とは、小学校の児童その他これに準ずる者をいう」と備考に記載させていただいております。以前にも、入浴料については券売機で徴収したいとお話を申し上げました。一般と小学生の表示をする予定でおりますが、小学生の方は多分小学生のボタンを押すのではないかと思っております。ただ、そこに12歳未満の方とか12歳以上の方はこちらとかと表示するかどうかは、今後検討していきたいと思っております。今のところは、まだ決めていないところです。
吉田
入浴料の設定がこちらでは小学生となっていますが、名取市市税条例では12歳未満が入湯税が免除される年齢となっていて、そこにずれが生じるために、生まれた月によって、生まれた月が来ていれば入湯税の対象となって、来ていなければ免除となります。今の御答弁ですと、券売機のボタンをどうするか、まだそこまで詳しく決まっていないということでしたが、同じ金額をもし納めていただいた際に、指定管理者としては入湯税の対象となっている分だけもちろん市に入湯税を納めることになると思います。それはやはり11歳か12歳かということを、ボタンの部分もそうですし、あるいは宿泊の方もそうだと思いますが、どのように確認をしていくのか、そしてどのように適切に徴収していくのか、そのお考えをもう一度確認したいと思います。
商工観光課長
宿泊については課税免除は行いませんので150円です。日帰り入浴のみが50円ということで、条例改正が出ているものです。
以前も申し上げましたが、例えば市外の方、市内の方についても、ボタンを押されてしまえば、その人が市外の方なのか市内の方なのかは、わざわざ聞き取りをするわけではないので、そこは自己判断に任せたいと思っております。同じく一般と小学生についても、一般を押していただいた人について、その数を数えて入湯税を納めたいと考えております。
吉田
実際は小学生も課税免除は宿泊の場合もあるということで、12歳未満の場合は宿泊でも150円課税免除になるということでよろしいかと思いますが、であれば、宿泊者の場合の小学校6年生、11歳か12歳かというところの確認、その適切な徴収という点に関してはどのように進めていくのか、改めてお伺いいたします。
生活経済部長
年齢の確認等も含めて、入湯税の徴収の仕方については、今後、指定管理者も含めて開業前までにはふぐあいのないように調整をしていきたいと考えております。
(議案第75号 工事請負契約の締結)
吉田
資料2の左側の図ですが、今までの工事の経緯を全部追っていけば多分わかることだと思いますが、この赤の実線と水色の実線を見ると、微妙に赤だけの部分がありますが、そこは既に下水道管が敷かれているのですか。
復興区画整理課長
この貞山堀沿いの下水道管ですが、赤の実線だけの部分については既に下水道管を埋設しているところです。今回、その上に舗装をするということです。
(議案第76号 工事請負契約の変更)
吉田
資料の地図を見ると、たくさんの線が引いてあって、どの部分が何になっているのかよくわからないのですが、例えば南側となっている閖上港線のところですが、赤い着色部分が今回施工する部分ということで、ここはこの図があるのでわかるのですが、その1つ内側というか、道路側の細い線が引いてある部分、ここはもともと歩道としてのスペースではないのでしょうか。
復興区画整理課長
こちらの赤い着色部分と閖上港線という文字の間の細い部分については、歩道ということになります。
吉田
では、歩道が並行してつくられることになると認識したのですが、きちんとした広い歩道になるのか、それとも間にブロックのようなものが入ってしまうのか。この2つ並行する歩道の関係についてどのようになっているのか確認させてください。
復興区画整理課長
閖上港線はもともと歩車道境界ブロックで縁切りされている歩道です。こちらは道路附帯施設ということになりますので、歩道の外側の施設になります。これはあくまでも歩行空間というイメージで、今回は植栽がメーンのところと考えていただきたいと思います。ただ、そこを歩くこともできるという形で歩行空間とするということです。
(議案第77号 工事請負契約の変更)
吉田
資料1にも資料2にも平面図が載っています。今回、園路整備と駐車場整備等については別途発注となっていますが、一応示されているのでお聞きしたいと思います。先ほどの御説明の中で、車の出入り口は南北2カ所ということでしたが、常時開放して、どんな車でもいつでも通れる状態にしておくという考え方でよろしいですか。
文化・スポーツ課長
コミュニティー広場、多目的広場ですので、利便性を考慮して、北と南の両道路から入れるように対応している駐車場です。施錠するのではなく、24時間開放した状態で使っていただくということです。
吉田
この地図上、2つの道路をつなぐような場所にありますので、実際は一般の道路のような形で通行する車がふえてしまうという懸念はないのでしょうか。それから、先ほど防犯のことでトイレやあずまやの話も出ましたが、夜間などに車で乗り入れてきて駐車場でドリフト運転をするなど、そういう使い方をされてしまうのではないかという懸念があるのですが、そういうところの対策は今のところはまだ何も考えていらっしゃらないのでしょうか。
教育部長
まだここには図示しておりませんが、今後、車どめ等を設置して、グラウンドの中に入れないようにとか、あるいは必要があれば車どめを外して中の整備をするとか、そういったことができるように今打ち合わせをしているところです。
吉田
主に資料1のほうですが、災害復旧グラウンドとコミュニティー広場と、そして全体の中で、排水施設整備という水色の線が引いてあります。グラウンドにももちろん雨が降って、その水がスムーズに流れるような設計になっているかと思いますが、コミュニティー広場の南側の部分とか、南側の駐車場の出入り口の部分が一部途切れているようです。主な部分で、水の流れというのはどういう方向に考えているのか。グラウンドから雨水施設に流れて、その雨水施設からどちらのほうに流していくという設計なのかお伺いいたします。
復興区画整理課長
まず、災害復旧グラウンドについては、グラウンドの周りをU字溝でぐるっと回します。図面の水色の部分ですが、こういった形でぐるっと回します。それで、暗渠排水管、これは直径100ミリメートルの有孔管ですが、これをグラウンドの中に設置して、それぞれ側溝に排水できるような形とします。大きく分けると、災害復旧グラウンドとコミュニティー広場の貞山堀側にも南北に排水施設、水色の線がずっと来ています。この右側の水色の線がずっと来て、閖上小塚原線のところの水路に排水するような形になります。
それから、コミュニティー広場については、これも災害復旧グラウンドと同じように暗渠排水管、100ミリメートルの有孔管を埋設します。この管を今言った貞山堀側の水色の線のところ、ここのU字溝に排水するような形になります。
北側の駐車場と西側からの排水も、水色の側溝がありますので、主にここの水路を排水が通るという形になっております。水色の線を見ていただくと、この施設の西側のところに水路がありますが、そちらのほうに5カ所、水路から横断してそちらの水路に排水するようになっています。
系統としてはそういった形で、全体の排水は、南側には閖上小塚原線の排水路、西側については閖上のメーンの排水路がありますので、そちらに排水するというような系統で考えております。
吉田
暗渠の部分とU字溝の部分と別の形状かと思いますが、このような土でできたグラウンドの、その土がやはり流れ込んでいって、結局は土が堆積してU字溝そのものがだんだん浅くなっていくかと思います。そのあたりの対策はどのように考えていらっしゃるのかお伺いいたします。
復興区画整理課長
暗渠排水についてですが、これはただ穴のあいている暗渠管を埋設するということではなく、その周りに砕石をまいて、そこから水が浸透するような排水構造になっております。
それから、水路については、接合部分にますなどもありますので、維持管理上は、土がたまった場合はそのますの部分を清掃するという形になろうかと考えております。
(議案第78号 令和元年度名取市一般会計補正予算)
吉田
14、15ページ、20款5項2目雑入で保育所副食費実費徴収金とあります。こちらについても制度が変更されて、今度は実費で負担することになったようですが、この金額を算定した根拠をどのようにお考えだったのかについてお伺いいたします。
こども支援課長
10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、副食費の実費徴収分が出てきます。実費徴収の算定ですが、1人当たり月額4,500円に公立保育所の人数160人を見込み、その6カ月分で432万円と計算したところです。
吉田
議案第78号の資料を見ると、副食費の部分は施設で徴収ということになっていますので、利用者の保護者が施設に払って、その分が市に収入として入ってくるのかと思いますが、もしその際、副食費の部分が何らかの事情で支払いが滞ったり支払いが行われなかったりした方がいた場合は、市の歳入としてはどういう扱いになるのかお伺いします。
こども支援課長
副食費の徴収については、私立保育所や認定こども園については施設で徴収することとなりますが、公立の保育所については市が徴収することになります。私立保育所や認定こども園の分で滞納額が出れば、その分は園の収入不足になります。公立保育所で未納額が出れば、その分については市が収入不足となってくると考えています。
吉田
22、23ページ、3款3項2目保育所費の委託料で、幼児教育無償化例規整備情報提供委託料とありますが、こちらの内容についてお伺いいたします。
こども支援課長
今後、幼児教育の無償化関係で、名取市の特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、規則等の改正を予定しております。その情報を得ながら改正の事務を進めていきたいというのが1点と、今後、施設等利用給付と令和2年度の入所事務が重なることから、この部分については委託したいと考えております。
吉田
無償化というと、全国的に恐らく同じような制度になっているのではないかと思いますが、これはやはり国からある程度ひな形のようなものが示されて、そして例規整備が進められていくということなのか、それとも、あくまでも名取市独自のものとして整備していくのか、その部分の確認をお願いしたいと思います。
こども支援課長
国から内容的なものが示されますので、本市もそれに合わせてつくっていきますが、この条例の部分とほかの条例、規則等に影響がある部分についてどうなるか、その辺の情報を取得しながら進めていきたいと考えております。
吉田
24、25ページ、6款3項2目水産業振興費のろ過海水供給施設保守点検委託料です。これは当初予算でも盛り込まれておりますが、通常の保守点検なのか、それ以外の何かふぐあいが起きているのか、そのあたりの内容をお伺いいたします。
農林水産課長
ろ過海水供給施設保守点検委託の内容ですが、今回お願いしているのは2つの業務となっています。1つは、ろ過海水取水管砂排出業務委託、これは当初予算でもお願いしておりましたが、これについては増額補正をお願いしているという内容です。もう一つは、今後施設の改善を検討していくために、取水ポンプと取水口の距離を短くして、取水ポンプを仮に取水口のほうに移設をして取水ポンプの稼働テストを実施する、海水取水ポンプ移設稼働試験業務委託となっています。
吉田
砂の排出については、砂がたまってきているということだと思います。改善も同じ理由によるのかなと思いますが、当初ではなく補正で計上することについては、よほど緊急のことが起きているのかと思いますが、現状どのようになっているのか、御説明をいただきたいと思います。
農林水産課長
これまでもろ過海水供給施設の補正をお願いしている中で、なかなか海水取水の状況が思わしくない場合もあると。例えば取水管の中に空気だまりが生じて、水中ポンプを設置して空気だまりの空気を抜く作業が必要になると。そういったことで工夫をしながら取水をしているということをこの議会の中でも答弁しておりましたが、現在の施設の課題として、やはり取水口から取水ポンプまで約820メートルの距離がありますが、その距離が長いことがこの施設の一つの課題になっているのではないかと捉えております。その試験をどういった形で実施すればいいのかということでこれまでも検討してきましたが、具体的な方法を今回ある程度固めて実施したいということで、補正ではありますが、今回お願いしたいという内容です。
吉田
26、27ページ、8款6項1目住宅管理費の柳田団地空家解体工事の今後のスケジュールについてお伺いいたします。
都市計画課長
年度内に完了を見込んでおります。
吉田
先ほど歳入の土木費についての質疑で今回は解体だけという説明があったと思いますが、解体をした後の土地の活用などについて、今何か検討されている内容があればお伺いしておきたいと思います。
都市計画課長
今のところ、都市計画課としては何も考えておりませんが、関係部署といろいろと協議、検討していくと思われます。
吉田
これは以前も質疑した記憶がありますが、30枚という限られた枚数をどういう形で市民に割り当てるのか。誰の手にどういう手続でどう行き渡るのかということについて、そろそろ何か検討が始まっているのではないかと思いますが、そのあたりの経過についてお伺いいたします。
復興ありがとうホストタウン推進室長
先ほども言ったように、まだ確定していない段階です。最大30枚ということですが、私どもは自転車競技を想定していますが、会場の都合もあって最大30枚を申し込める枠組みがなく、今、最大応募できる20枚について進めているところです。それで、あと10枚追加ということも考えていますが、最大30枚として、それをどのように誰が行くかということは、市民団体等を巻き込んだ実行委員会がありますので、その実行委員会の中で検討していきたいと考えています。ですから、今のところ、誰がということについてはまだ具体的なところには至っていませんので、検討していきたいと思っています。
教育部長
対象者をどのように決めるかということですが、まだ具体的な内容には至っておりません。これからどういった方々にということは具体的に検討していくことになりますので、今の時点ではまだ決定しておりません。
それから、先ほど復興ありがとうホストタウン推進室長から申し上げた20名という発言については、30名の枠があったり、20名の枠があったり、10名の枠があったり、いろいろと種目によって違っていまして、そういう事情がありますが、市としては30名の枠をなるべく最大限当たるように進めていく予定でおります。
吉田
30枚当たったとして、市民が応援団を結成して行くことになると思います。この東京オリンピックの期間は東京都内や周辺の宿泊施設が満室になっていたり、通常安いところでも金額が何倍にも上がっていたり、大変な状況が起きていると伺っています。チケットが当たった一般の市民の方が、そういうことにきちんと対応して、みんなで応援を必ずできる体制をどのように整えるのか。あるいは日帰りで行って帰ってくる、そういうスケジュールを何とか組むのか、そのあたりの検討はどのように進んでいるのかお伺いいたします。
復興ありがとうホストタウン推進室長
まだチケットも確定していないということもあって、日にちについても確定していませんので、詳細についてはこれからということです。先ほど宿がなかなかとれないという御指摘もありましたが、宿泊を伴うかとか、そういう日程的なことについても、今、県や旅行会社に確認しながら、情報の収集に努めているところです。
財務常任委員会
吉田
7、8ページ、1款1項1目市民税の個人分ですが、納税義務者数を捉えていると思いますので、その数と全人口に占める割合を伺います。
税務課長
個人の市民税の納税義務者は総数で3万8,136人、このうち均等割のみの納税義務者は2,219人、均等割と所得割の納税者は3万5,917人です。
吉田
納税義務者は所得があることで納税の義務が課せられるわけですが、生活困窮者からは出てこないと、納税の義務が課せられないと思います。本当に働けないような方ではなく、所得に応じての納税額だと思いますが、働いていても所得が上がらずに納税義務が課せられていない人数を捉える方法はあるのですか。
税務課長
働いても収入が少ない場合には非課税となります。ただ、申告をした総数から課税者数を引いた数字は捉えておりません。
吉田
1款2項1目固定資産税でお聞きします。土地と家屋と償却資産ということで昨日御説明を受けましたが、家屋の部分で、平成29年度から平成30年度にかけて家屋の解体という形で減った数は捉えていらっしゃいますか。
税務課長
実務上、滅失家屋となりますと異動処理を行います。例えば住宅が滅失した場合には、住宅用地の特例と異動処理を組み合わせるということで、直接的に滅失棟数が何棟あったという捉え方ではなく、特に課税に関しては滅失しても当該年度もしくは翌年度に新築住宅が建てられるということがありますので、特に捉えておりません。
吉田
9ページ、10ページの1款3項1目軽自動車税でお伺いします。昨年も同じような質疑をしましたが、今回も調定額も含めて十の位以下の端数が出ていて、どういうことなのか疑問に思いました。昨年の決算審査の際は、口座振替で未納額を差し押さえたら端数が生じたという説明だったと記憶していますが、今回は調定額から872円と端数が生じているのは何か理由があるのでしょうか。
税務課長
平成29年度において収入未済額になっている金額が滞納繰越分の調定額になっています。72円の端数が生じていますが、これは、前年度、預貯金差押等により一円単位まで差し押さえを行いまして、滞納額からその差し押さえた金額を差し引いたので、一円単位の端数がそのまま残っているということです。
吉田
では、その支払いは完納したということで、収入済額でも端数が出ているのは別な対象者から全額徴収できなかったためということでよろしいのですか。
税務課長
調定額で72円、収入未済額で最終的に9円の端数がありますが、例えば一円単位までの預貯金の差し押さえを行ったことでまた一円単位の金額が残っているということです。税額としての百円単位に限らず徴収する滞納整理の方法をとっているため、端数が存在しています。
吉田
13、14ページ、2款3項1目航空機燃料譲与税の金額の内容についてお伺いいたします。
財政課長
航空機燃料譲与税については、原資となる航空機燃料税の9分の2の額が、着陸料収入や騒音世帯数によって案分されて都道府県及び指定市に譲与されるものです。平成30年度当初予算の編成段階では詳細な地方財政計画が示されていませんでしたので、前年度の収入見込み額から4,500万円と見込みましたが、9月の交付金が少し多かったことから年度総額を5,500万円と見込み、2月の補正において1,000万円の増額補正を行いました。決算額としましては、対前年度比で5.6%の増、5,821万7,000円となりました。国税からの関係都道府県、市町村への譲与金の総額についても対前年度比100.4%となっていますので、結果としては本市に対する譲与税額は全国的な傾向を上回るような水準で推移しました。
吉田
飛行機の離着陸の回数がふえたのが大きな増額の要因ではないかと思います。
今、宮城県は仙台空港の運用時間延長を目指して地域の理解を得るためにさまざまな取り組みを行っているようですが、飛行機の離着陸の増加は、やはり地域にとってはそれだけ飛行機の音が聞こえる状況がふえることにつながると思いますが、航空機燃料譲与税はあくまでも一般の税であって、これを財源としてそれらの問題に対策を講じるなど目的が決まっているものではないということでよろしいのですか。
財政課長
航空機燃料譲与税の使途は航空機燃料譲与税法で規定されており、航空機の騒音により生ずる障害の防止、空港及びその周辺の整備、その他政令で定める空港対策に関する費用に充てなければならないとされております。これを受けまして本市においては、航空機燃料譲与税額を空港対策費や公害対策費、航空機騒音関係、道路新設改良費、そのほかに消防費に充当していると整理しております。
吉田
21、22ページ、13款1項4目土木使用料の2節駐車場利用料です。市内の公営駐車場は名取駅東西と館腰駅の3カ所だったと思いますが、使用料の区分というか、200円は何件、400円は何件と施設ごとにもし捉えていればお知らせいただきたいと思います。
土木課長
市政の成果115ページの駅前広場等管理費の中で、平成30年度の館腰駅西口自動車駐車場、名取駅東口自動車駐車場、名取駅西口自動車駐車場の3自動車駐車場の利用状況が載っております。一つの参考として、館腰駅西口自動車駐車場の30分以内ですと101件、1時間以内は193件、2時間以内は330件など1時間単位で載っています。
吉田
45、46ページ、16款1項1目財産貸付収入1節土地建物貸付収入の収入未済額ですが、昨日の補足説明で仮設工場が3件ということでした。平成29年度で2件とありましたが、また新たに3件ということでよろしいのでしょうか。
商工観光課長
今回の収入未済額50万4,900円は、2つの事業者の仮設工場3件分になります、1事業者は、平成28年度、平成29年度からの滞納分が35万1,000円あります。もう1業者は、平成29年度、平成30年度分として15万3,900円の滞納がありましたが、令和元年度になり一部納入がありました。
吉田
では、これは平成28年度分から積算してというか合わせてこの金額かと思いますが、支払いが滞っている状況については、市としてこれからどのように返済、納入していただくように考えているのでしょうか。
商工観光課長
今までもですが、引き続き今後も納入の依頼、督促を行っていきたいと考えております。個別訪問も行っていますし、何度かお会いしてお話もしていますので、今後引き続き納入について協力を求めたいと思います。
吉田
49、50ページの16款2項2目土地建物売払収入です。平成30年度2月の10号補正で予算現額である3億6,514万9,000円になっていますが、調定額で金額が少し減少したのはどのような要因だったのでしょうか。
財政課長
まず、財政課担当分から御説明させていただきます。
財政課担当分の金額は9,321万円ほどで、件数は15件です。中身の主なものとしては、社会福祉協議会への事務所用地としての払い下げが5,120万円、仙台土木事務所で行っている災害復旧に係る払い下げが1,756万7,000円、ほかに市道買収用地の代替地として払い下げるものが1,477万8,000円となっております。
復興区画整理課長
閖上地区の区画整理事業地内の土地の売り払い収入は、32件で2億2,394万8,241円です。
復興まちづくり課長
復興まちづくり課では2件取り扱っております。1つ目が美田園北団地内の1区画、1,455万3,000円、それから下増田防災集団移転の移転元地で1件、3,200万1,807円という実績です。
吉田
予算の額から最終的な額が下がっているのは、今の説明の全てに満遍なく要因があるということでよろしいのですか。
財政課長
売り払いという性格の収入ですので、予算も一致させればよろしいのかと思いますが、当初では見込めないような払い下げなど執行上動きがあろうかと思いますので、その点で予算は少し多目に計上しています。
吉田
61、62ページの20款5項2目雑入3節広告料収入で伺います。昨日の総括質疑でも新たな財源等による歳入確保とありましたが、この広告料収入の中で答弁いただいた新たな取り組みの部分がありましたら、金額とあわせてお伺いしたいと思います。
政策企画課長
総括質疑でお答えした新たな取り組みとしては、平成30年度にネーミングライツの導入に関するガイドラインを政策企画課で制定しました。ただ、これについては、募集をしましたが残念ながら応募者がいなかったこともあり、歳入としては入っておりません。
それからもう1件、総括質疑で答弁した図書館の雑誌スポンサーについては、歳入として入ってくるのではなく現物の支給を受けるものであり、結果として市の財政負担を減らすという意味で、歳入として入ってくるのと同じような効果がありますが、今回の広告料収入の中に新たな取り組みの財源分は入っていないところです。
吉田
61、62ページの20款5項2目雑入9節学校給食費実費徴収金です。これも収入未済額が出ていて、昨日565件という説明でした。この徴収方法はたしか振り込みだけだったかと思いますが、565件の徴収できなかった理由をお伺いいたします。
学校教育課長
収入未済額ですが、現年度分については口座振替ができなかったということ、過年度分については、教育委員会等から未納の御家庭に連絡を差し上げていますが、まだ納めていただいていない分になっております。
吉田
件数で出ていますが、世帯数では捉えていますか。
学校教育課長
世帯数では捉えておりません。
本財務常任委員会第一分科会
吉田
市政の成果135ページ、常備消防費の消防事務の1の予防活動です。内容は前年度と比較してさほど大きな違いが見られないように思いますが、決算の額が10万円ほど減になっています。どういった要因で減になったのかお伺いいたします。
予防課長
例年、仙台市と東北各地の持ち回りで開催している東北消防長会予防担当者会議というものがありますが、平成30年度は仙台市で開催されたために旅費、宿泊費等がなかったため、少なくなっているところです。
吉田
今おっしゃったのは、市政の成果でいうとどの部分に書かれているものでしょうか。
予防課長
市政の成果にはあらわれていないところです。
吉田
市政の成果135ページの常備消防費の消防事務、1 予防活動で、防火チラシを全世帯に配布、広報なとり年2回掲載ということです。これは毎年同じ事業かと思いますが、確認のために、その年2回というのは何月と何月なのかを教えていただきたいと思います。
予防課長補佐
広報なとりについては、春と秋の火災予防運動の実施時期に合わせて掲載しています。そのほか、7月号に住宅用火災警報器についても、重要性、交換時期、点検方法などについて掲載しております。防火チラシについては、秋の火災予防運動に合わせて配布している状況です。
予防課長
掲載月日としては11月1日号と3月1日号に掲載しているところです。
吉田
毎年同じような内容かと思いますが、何か目につくような工夫を新たに平成30年度に取り組んだ部分がありましたら、お知らせいただきたいと思います。
予防課長補佐
住宅用火災警報器の交換時期の広報を重点的に行っているのと、消火器、住宅用火災警報器の悪質販売等に対する注意喚起と、高齢者に多い出火原因について掲載しております。ここが新しい取り組みです。
吉田
多言語通訳コールセンターですが、利用が1件ということでした。その1件の状況をお聞きしたいと思います。本当にこの多言語通訳コールセンターを使わなければ救助できなかったケースなのか、そして到着するまでにかかった時間など、詳細に把握されていたらお知らせいただきたいと思います。
警防課通信指令係長
平成30年度に多言語通訳コールセンターを利用したのは、通報段階ではなく、現場で、傷病者が外国の方ということで、その方と意思疎通を図るために携帯電話によって多言語通訳コールセンターを利用して通訳をしていただきました。ですから、到着時間などは今把握しておりませんが、ふだんの救急と同様の対応ということで、やはり有効であったと思っています。
吉田
以前も保健センターの話でそのようなことが出たことがありましたが、今、スマートフォン端末をほとんどの人が持っていて、無料のアプリで通訳ができるものがあります。そこに言語を指定すれば、本当に一般の人でも海外旅行などで自由に使っているようなものがありますが、そういうものに切りかえていく形でもう少し使いやすいものにしていくという検討に移ることは考えていらっしゃらないのでしょうか。
警防課通信指令係長
救急隊でもスマートフォンを使っていますので、そういうアプリとして、国の救急ボイストラという多言語音声翻訳アプリを導入しています。ただ、119番通報時には、そういうアプリを使うとかえって手間がかかります。現在の多言語通訳コールセンターでは、119番をかけていただいたその電話に直に介入して、通訳の方と3者同時通話ができますので、現在はそれが一番有効な手段ではないかと思っています。
吉田
市政の成果137ページ、常備消防費の救急・救助事務の3 備品購入費(流水救助対策用胴付長靴)とあります。こちらの数量や仕様についてお伺いいたします。
警防課消防係長
購入数量は8着となっています。この胴付長靴については、最近多発している土砂崩れ、それから、今後予想される津波災害、南海トラフ地震などで出動する際に、現場で活動する隊員が着用するものとなっております。
吉田
胸まである長靴だと思います。私も川に入るときに使ったことがありますが、実際に履いて水の中を移動すると、結構体をとられてしまって難しいのですが、これを着た訓練はどのぐらいの頻度でどういう内容で行われたのでしょうか。
警防課消防係長
実際に水の中に入っての訓練は実施しておりません。流水救助対策用ということで、胸のところにベルトがついていて縛れるようになっていて、余裕のあるぶかぶかしているものではありません。そういうものを着て、深く水の中に入っての活動ではなく、水たまりとか、少し汚れた水がある場所などに入る場合に使用することを目的としております。
吉田
どこに含まれているのかよくわからなくて、消防事務かなと思うのですが、市の消防本部にもホームページがあります。名取市のホームページとデザインなども少し違うようですが、このホームページは消防本部独自でデザインとか更新とかそういう日々の管理を行っているということでよろしいでしょうか。
警防課通信指令係長
そのとおりです。消防本部独自で行っております。
吉田
これは市全体のこととしても考えていかなければいけないことだと思います。ホームページも一つの有効な広告の手段ですが、やはり今、それ以上にいろいろなソーシャルネットワークサービスなどが進んでいく中で、防災安全課でもツイッターのアカウントを持っていますが、そのように、よりいろいろな方にアクセスしていただけるような環境をネット上でつくっていくことに関して、平成30年度に何か御検討されたことがありましたらお知らせいただきたいと思います。
警防課通信指令係長
特に新たに始めることは考えておりませんでした。名取市のフェイスブックなどに消防本部の情報も上げられますので、そちらを活用していきたいと思っています。
吉田
常備消防費に含まれると思いますが、平成30年度に名取市立第二中学校で仕事博覧会があって、そこに消防としてもブースを設置して協力されたと思います。そのことについて全体としてどのように評価されているのか、お聞きしておきたいと思います。
消防署長
仕事博覧会については、2年ほど前から依頼があって、2年間参加させていただきました。その前から、小学校4年生の段階では全員が消防署の仕事を見学に来ております。それから、中学生に関してはインターンの受け入れも行っており、何名か受け入れております。仕事博覧会については、消防の仕事のみならず、ほかの企業でもこのような仕事をしていて世の中が成り立っているということを学ぶ名取市立第二中学校独自の行事ですので、それに参加させていただいている現状です。
吉田
特に平成30年度はドローンを管理している民間の団体の協力もあったと伺っております。それもとても好評だったということですが、今後そういった民間との連携をしていくことについては、消防として何か御検討はあったのかどうかをお伺いしたいと思います。
消防署長
ドローンという話がありましたが、6・12の総合防災訓練などでも使用させていただいたドローンの業者と、何かのときの協定も含めて考えているところです。
吉田
市政の成果139ページの非常備消防費でお伺いいたします。消防団の学生団員が2名在籍していたと思いますが、消防概要を見ますと、年度が明けて1名になっております。2名のうちの1名の方は平成30年度が活動の最後の年度だったと捉えてよろしいのでしょうか。
消防本部総務課長補佐
平成31年2月28日付で1名退団しております。
吉田
学生団員の制度ができて、1期生というか、最初に入ってきてくれた非常にありがたい存在の方なので、消防団員として参加してよかったとか、そういう感想などを受け取っていればお聞きしたいと思います。また、恐らく大学の卒業とか、いろいろとその方の事情があってのことかと思いますが、もし把握されていれば、その後、消防団の一般の団員として加入しているかどうかについてもお伺いしたいと思います。
消防本部総務課長補佐
退団した学生消防団員1名については、就職に伴い退団しました。それで、他市の企業に就職したものですから、現在、一般団員としては活動しておりません。なお、学生消防団に参加してよかったということは聞いております。
吉田
市政の成果139ページの非常備消防費でお伺いいたします。消防団運営事業の2 訓練・行事の実施の中で、10月から12月の宮城県消防学校教育のところに現地教育という形で23名とあります。平成29年度にはそういった実績はなかったようですが、この現地教育はどういう方を対象としたもので、どういった内容だったかについてお伺いいたします。
消防本部総務課総務係長
この現地教育については、初任消防団、消防団に入ってからまだ教育を受けていない方を対象とする教育です。上のほうに基礎教育とありますが、内容は同じで、初任消防団に対する教育です。現地教育については、2年に一度、名取市を会場として、宮城県消防学校の教官に来ていただいて教育をしていただくということで行っている教育です。ですので、平成29年度の市政の成果には出ていないところです。
吉田
そうすると、初任の方が少なくとも23名はいるということかと思いますが、開催される日時や曜日などは、初任の方に配慮した形で決められているのかについてお伺いいたします。
消防本部総務課総務係長
今、消防団の方は勤めている方がほとんどですので、この現地教育も含めて消防団の学校教育については、入校、講習にあっては土日で実施されているところです。
吉田
市政の成果142ページ、消防施設費の救急高度化事業の1 救急救命士の養成1名と書いてあります。平成29年度の決算の際には、全部で20名の方が救急救命士として在籍ということでしたが、1名ふえて21名になったということでよろしいでしょうか。
消防本部総務課長補佐
平成30年度は救急救命東京研修所に1名出向しています。
吉田
詳しい仕組みがよくわからないのですが、実際には救急救命士の資格を持つ方は平成30年度は何人になったということですか。
消防本部総務課長補佐
平成30年度については、資格取得者は21名です。
吉田
市政の成果143ページの防災費の防災対策事業の9の(1)全国瞬時警報システム新型受信機等改修工事です。これについては先日の総括質疑でも大変具体的な丁寧な御答弁をいただきましたが、こちらは国のシステム改修に伴ってということですので、このための工事の費用は全額国庫からということでよろしいのでしょうか。
防災安全課長
こちらは緊急防災・減災事業債の対象となっておりまして、充当率が100%となっております。そのうち70%が交付税の措置ということです。
吉田
音声出力といった形で伝達される情報がより詳細になったということですが、このシステムが具体的に運用されるケースとして、どういった場合が想定されるのでしょうか。
防災安全課防災係長
瞬時に警報を発令する必要があるような、大規模災害が起きたときですので、主に津波や国民保護事案の場合などに作動する形になります。それ以外に、先日の総括質疑の中で6種類の災害種別を説明させていただきましたが、そういった場合に、さまざまな情報が全国瞬時警報システムを通じて届くようになっています。ただ、国が直接エリアメール、緊急速報メール等で発信する場合については、名取市の自動起動機を使った発信ではなく、直接国からエリアメール等に行く場合などもありますので、その中で市として単独でしなければいけないものなどについて、Jアラートを受信した後に対応するという形で運用を行っているところです。
吉田
今の御答弁で、津波とか国民保護事案という話がありましたが、6つの区分の中にはこの2つが入っておりません。このようにシステムを変えるのであればその辺も反映させたほうがいいのではないかと思いますが、それは国の仕事だと思うので、本市としては何ともしがたいことだと思います。Jアラートもあり、このシステムもありで、実際にそういう大規模災害等が発生した場合に、1つの情報として総合的に配信されてくるのでしょうか。それとも、端末ごとに違うところから違う経路で情報が入ってくることになるのでしょうか。
防災安全課防災係長
衛星回線と地上系の回線の2種類がありますが、情報発信側としては1種類です。 先ほどの津波と国民保護事案については、今回の対応の前に既に分かれていましたので、今回の改修の部分にはなっていないという内容です。
吉田
気象等の特別警報に係る音声出力という部分では、その他というのがこれまであったのが、その他がなくなるということになるのですか。
防災安全課防災係長
委員お見込みのとおりです。
吉田
市政の成果143ページの防災費、防災対策事業の11 国民保護事務です。これも毎年確認させていただいておりますが、平成30年度の国民保護研修会の内容についてお伺いいたします。
防災安全課防災係長
平成30年度は危機管理・国民保護コースという消防大学校のメニューを受講しております。内容的には、国民保護に限らず、本市の災害等に対する危機管理に関する内容や、国民保護事案があった場合の対応等について、具体的に自治体でどんなことをするのかとか、そういったことについての研修を受けてきているところです。
吉田
毎年、内容としてはそんなに大きな変わりはないのかなと思いますが、名取市国民保護計画の策定から時間がたっておりますので、こういった研修会の内容なども踏まえて、平成30年度は国民保護計画の改定についてどの程度取り組みが進んだのかお伺いいたします。
防災安全課長
平成30年度の名取市国民保護計画についての取り組みですが、先ほど防災係長が申し上げたとおり、平成30年度は消防大学校で講習会を受講し、職員の国民保護なり危機管理の勉強を行ったところです。
吉田
市政の成果144ページの防災費の自主防災組織支援事業でお伺いいたします。前年度に比較するとこちらも減少していますが、減少した要因として考えられるところを伺います。
それから、自主防災組織支援事業の2 自主防災組織連絡協議会運営補助金ですが、この運営補助は毎年得られるものではないのでしょうか。そこの確認もお願いいたします。
防災安全課防災係長
委員御指摘のとおり組織数が減っております。従来どおり防災講話や研修などにおいて、自主防災組織の重要性や補助事業についての説明をしてきたところです。先ほど総務部長から組織率78%という説明もありましたが、やはり従来のやり方では、なかなか組織率の向上が図られなかったのかなと考えております。今年度については、地域に出向く回数などをふやしながら、なるべく対策をしていくということで現在とり行っているところです。
また、自主防災組織連絡協議会運営補助金についても、例年3万円を上限として、申請があれば交付する形になっております。平成29年度は4団体あったものですので、こちらも積極的な働きかけが少し足りなかった部分があります。今年度についてはきちんと声がけをしながら、自主防災組織連絡協議会に対して、補助申請していただけるように取り組みたいと考えているところです。
吉田
ただいまの御説明ですと、自主防災組織連絡協議会が申請をしなかったために件数が減ったということかと思いますが、自主防災組織連絡協議会そのものは現在でも4団体存在しているということでよろしいですか。
防災安全課防災係長
委員お見込みのとおりです。
吉田
市政の成果1ページ、企画費の第六次長期総合計画等策定事務で伺います。第六次長期総合計画は議員協議会などでもこれまで何回か御説明をいただいておりますが、改めて平成30年度の策定に係る経緯をお伺いしたいと思います。
政策企画課政策係長
第六次長期総合計画については、平成30年度と平成31年度の2カ年で策定を進めていくということで作業を進めているところです。平成30年度の実施内容としては、まず、各種統計、基礎データの調査ということで、例えば市民アンケート調査や市民懇談会といった形で、市民、団体などからいろいろな御意見をいただきながら、市民の意見を取りまとめるという形で行っております。平成30年度の到達点としては、中間報告という形で、その辺の基礎データの分析の結果を取りまとめている状況です。
吉田
アンケートや懇談会でいただいた市民の意見は、どういう市にしていきたいのかという思いが込められているものですから、それを反映させていくのはもちろんですが、行政の側として今後の市を背負っていく市職員の方々、特に若手の職員の方々の意見はどのように反映させていったのでしょうか。
政策企画課政策係長
若手職員ということですが、策定に当たっては、庁内において策定本部、各課長で構成する幹事会、係長級で構成する部会という3つの組織があります。したがって、まず、部会の中で、中堅職員というか若手職員から意見をもらっているという状況です。
吉田
これは毎年聞いていますが、市政の成果1ページの企画費の地方創生事業の1の(2)名取マイレージ事業記念品です。名取マイレージ事業への応募者の数を前年度との比較もあわせてお伺いいたします。
政策企画課政策係長
平成30年度の応募数は141件となっております。平成29年度が97件でしたので、44件の増となっております。
吉田
さまざまな記念品があったと思いますが、記念品の中身の検討について、平成30年度、何かありましたらお伺いしたいと思います。
政策企画課政策係長
平成30年度の記念品ですが、基本的に平成29年度と同じ内容で設定させてもらっております。5ポイント賞については、姉妹都市である上山市の温泉宿泊券、3ポイント賞については、ふるさと寄附金を5,000円いただいた方の相当分ということで設定しております。なお、平成30年度については、市制施行60周年記念と絡めて、それにプラスして60周年記念賞を10本追加しております。そういったところで工夫をしているところです。
吉田
事項別明細書79、80ページ、2款1項3目広報費の広報広聴事業でお伺いします。広報としては広報なとりを初めとしていろいろとお知らせをしていますが、この広聴のほうの事業としてはどういったことを進めてこられたのか、お伺いしたいと思います。
総務課広報広聴係長
広聴の部分については、例えば目安箱の設置をしておりまして、そちらで市民の御意見を伺ったり、ホームページにおいても意見を聴取するコーナーがありますので、そちらで広く御意見を伺ったりしております。
吉田
庁舎1階に目安箱に寄せられた意見に対する回答が掲示されていますが、目安箱やホームページに寄せられた意見の平成30年度の実数についてお伺いします。 それから、それらの意見に対して市役所として何かしらの回答をしなければならないと思いますが、回答を見ると、そういう回答しかないのかなというような諦めの部分もありながら、もう少し丁寧に回答したほうがいいのではないかと思われる部分も個人的には感じるところがあります。あの回答はどういう手続で書かれているのか、最終的に誰がチェックして確認をしているのかをお伺いしたいと思います。
総務課広報広聴係長
まず、件数については、目安箱への投函件数は29件、ホームページへの御意見、御質問については278件いただいております。
こちらについて受け付け後どのような処理をしているのかというと、まず総務課で受け付けをし、その後、担当課へ内容をお伝えして、担当課において、対応できる、できないも含めて内容を検討して、御意見をいただいた方への回答をしております。目安箱にいただいた御意見については全て市長に報告させていただいているところです。
吉田
市政の成果の3ページ、庁舎管理費の庁舎管理事務でお伺いいたします。1番の庁舎の維持管理で、表の真ん中の段にある庁舎警備業務、先ほどの御説明では委託料が増になったというお話でしたが、具体的に大きく増になった委託料の部分についてお聞きしたいと思います。
財政課管財係長
庁舎警備業務については、5年間の長期継続契約を締結して業務を発注しております。平成30年度において、平成25年9月から平成30年8月までの契約が一旦切れまして、平成30年9月に新たに競争入札を執行し、契約締結をし直しました。その際に、新たな契約について前回の5カ年に比べて増が発生したため、委託料が増になったということです。
吉田
5年契約ということですが、5年間の金額がこれではないと思います。これからの5年間、毎年同じぐらいの金額が契約の内容によってかかってくるのではないかと思われます。今の御説明ではどの部分がふえたかわからないのですが、平成29年度までと警備の内容はほとんど変わらずに金額だけ上がったということなのでしょうか。それとも警備の内容についても変わった部分があるのでしょうか。
財政課管財係長
警備の内容そのものについては、仕様等で大きく変わったところはありませんので、金額だけの変更です。
吉田
市政の成果の5ページ、市民相談費の市民生活相談事業でお伺いいたします。2番の消費生活相談事業ですが、受け付け件数が全体的にかなりふえております。平成30年度の体制でこれだけの件数にしっかり対応できたという評価でよろしいのでしょうか。
防災安全課生活安全係長
平成29年度に比べて、平成30年度の相談件数が81件ほどふえているところです。それについては、増加の主な原因として、架空請求のはがきが市内の各家庭に無差別に送られたことが平成30年度当初にありまして、それについての相談や情報提供が多くありました。相談全体については、もちろん繰り返しの相談もありますので実件数以上に実際相談員は相談者の方と対面しているところですが、平成30年度についても対応できたと捉えているところです。
吉田
今おっしゃった架空請求のはがきという内容のものについては、この2番の表でいうと一番上の商品一般というところに計上されてしまうのですか。それでは少しわかりにくいような気がしますが、そういった整理の仕方も何か検討はされなかったのでしょうか。
防災安全課生活安全係長
市政の成果のこちらの表については、国民生活センターや宮城県消費生活センターに報告する分類をそのまま掲載させていただいておりますので、確かに一見わかりづらいところがあったかと思います。それで、これについては、架空請求ということだけでなく、その内容によってそれぞれの分類にしているところです。例えば、インターネットの有料サイトを閲覧したので料金が発生するという形ですと、右側の役務のほうの真ん中にある運輸・通信サービスという形になったりするのですが、今回の架空請求のはがきの内容が、総合消費料金の購入に関するという書き方で、商品の具体的な名称などが書かれておらず、ただ何らかの商品を買ったのだという内容でしたので、国民生活センターとも相談しながら、左側の商品の欄の商品一般という項目の中に組み込ませていただいたところです。
吉田
市政の成果の6ページ、交通防犯対策費の交通安全事業、2番の交通指導隊の活動です。隊員数は2名増加ということで先ほど御説明がありました。出動延べ回数は平成30年度は3,330.5回ということですが、1人当たりで、最高の回数の方が何回であったか、一番少ない方が何回であったかを把握されていればお願いしたいと思います。
防災安全課生活安全係長
交通指導隊の出動回数の多い方と少ない方ということですが、最高の回数の方は278回という方がいました。ただ、こちらの出動回数については、1回当たり4時間を超える行事については2回とカウントしたり、1日において例えば朝と夕方とか2つの行事に出た場合は2回ではなく1.5回とカウントしたり、そういった形もあるところです。一番少ない方は11回という方もいましたが、仕事などでなかなか都合がつかないとか、月に1回ぐらいなら出られるとか、そういった方もどうしてもいるところです。
吉田
もちろんそれぞれの生活のサイクルといったことで回数は皆一緒になるわけがないのですが、それにしても随分差が開いているという印象です。そういった部分で、市として、例えば全体の回数を人数で割れば平均の回数が出てくると思いますが、大体何回から何回が適正な回数でないかとか、そういう目安は特に設けられなかったのでしょうか。
防災安全課生活安全係長
平成30年度の出動回数を全隊員数で単純に割りますと、平均は75.7回となります。ボリュームゾーンといったらおかしいですが、多くの隊員は大体そこの部分に当てはまるのですが、交通指導隊の中で幼児交通教室とか高齢者の交通教室の講師を担当する教育班というものがあり、主に女性の隊員4人の方々が平成30年度は教育班で活動していました。どうしてもその方々が、いろいろな学校や幼稚園に出向いての教室もあるということで、やはり多くなってしまうというところがあります。また、先ほど、市で年間のカレンダーを定めてというお話をさせていただきました。その数だけで申しますと五、六十回程度になりますが、そのほかにも地域の夏祭りとか、各地区の行事での歩行者の誘導などの業務もありますので、どうしてもお祭りの多い地域の方などは出動が多くなるといった傾向も出てきます。
吉田
市政の成果の7ページ、交通防犯対策費の防犯事業の1の(2)岩沼地区防犯協会連合会補助金です。これは前年度の決算の際にも御説明いただきまして、世帯当たり70円という計算で納めているという話でしたが、実際に使われるのが岩沼署の出発式など岩沼署の主催で実施する事業とか、あとは各地区の防犯協会におりてくる補助金の部分もあると記憶しております。このように一旦岩沼地区防犯協会連合会に名取市として納めるということですが、こうした防犯事業を各町内会や各地区で行っていて、防犯パトロールカーのふぐあいというか故障した部分があったりしても、そうしたものに対しての助成や補助は市では担当していないということでもありますし、警察でもすぐに対応できるメニューはないということです。こういう補助金を出している以上は、名取市としても何らかのそういうものを求めていく必要があるのではないかと思いますが、その辺の考え方は平成30年度どのように検討されたのでしょうか。
防災安全課生活安全係長
今、委員からのお話にもありましたとおり、主に本市における防犯活動の事業においては、市政の成果7ページの1の(2)の岩沼地区防犯協会連合会が名取市内、岩沼市内の各防犯協会の連合体となっておりますので、こちらとのタイアップ、並びに、その下の(3)にある名取市防犯協議会が名取市内の各地区の防犯協会の集まりという形ですので、こういったところとのタイアップで進めているところが多くあります。各地区のそういった活動の中で困っているという話でしたが、どうしても防犯パトロールカーの関係、広報資材の関係については基本的には岩沼地区防犯協会連合会の事務局である岩沼警察署で整備してきた経過がありますので、本市としても、このように困っている地区があるようだという声を事務局である岩沼警察署に届けていきたいと思っております。
吉田
市が窓口になって、ぜひそのように今後も進めていただきたいと思います。
この70円というのは、岩沼市も同じ金額で岩沼地区防犯協会連合会に納めているかと思いますが、その内訳として、実際に連合会として主催している行事の中で、やはり岩沼署は岩沼市内にありますので、どうしてもそこを中心としていろいろな事業が実施されているとすると、名取市としては距離感があって、どういうことを行っているのかがいま一つ伝わりにくい部分があると思います。実際この岩沼地区防犯協会連合会で行われている事業をいろいろと把握していると思いますが、連合会の予算の配分の中で、名取市のほうにどのくらい恩恵があるのかということについてはどのように捉えていらっしゃいますか。
防災安全課生活安全係長
予算の配分の中でどのくらいの恩恵かと言われると、なかなか答弁が難しいところですが、警察署が岩沼市にあることでの距離感ということでお話しさせていただきますと、こちらの連合会の会長は名取市長と岩沼市長が2年交代で務める形になっており、平成29年度、平成30年度は名取市長が会長を務めていました。それから、名取、岩沼合同での出発式についても、名取市役所の正面玄関で行っております。とはいえ、各地区の防犯協会の皆様からすると、どうしても岩沼警察署との距離感もあるということで、先ほど、市政の成果の7ページの1の(3)のところで名取市防犯協議会というものがあるというお話をさせていただきましたが、名取市内の防犯協会の方々については、こちらの防犯協議会という形で名取市独自で連合組織をつくりながら、市とタイアップしながら一体的な活動も行っているところです。
吉田
市政の成果8ページの公共交通対策費でお伺いいたします。なとりん号の委託先として現在契約している会社は2社だと思いますが、平成30年度なとりん号の路線等の見直しが行われたことによって、バスの台数はどのように変化したのかをお伺いいたします。
防災安全課生活安全係長
バスの委託先の会社ですが、株式会社桜交通と仙南交通株式会社の2社となっております。
それで、平成29年度から平成30年度の新たな契約にかけての台数の変化について答弁いたします。まず、株式会社桜交通については、平成29年度までは小型バスが2台、中型バスが7台、合計9台で運行していたところですが、平成30年度の新たな契約の中では小型バスが4台、中型バスが8台、合計12台ということで、3台増加で運行しております。それから、仙南交通株式会社については、平成29年度までは10人乗りのワゴン車が2台、小型バスが1台、合計3台での運行でしたが、平成30年度からの契約では14人乗りのワゴン車5台という形で運行しているところです。
吉田
そうすると、平成30年度は2社合わせて全部で17台ということになるのですか。思ったよりも台数が少ない気がしますが、それらのバスの中で、アイドリングストップに対応しているバスがあるのかどうか、あるいは普通のバスであっても電源を切った際に表示が消えずに使用できるというか、乗る方が迷わずにバスの行き先などをきちんと把握できるような仕組みになっているバスが何台あるかということについて、市では把握されていますでしょうか。
防災安全課生活安全係長
まことに申しわけありませんが、アイドリングストップの車両が導入されているかどうかまでは、こちらでは把握しておりませんでした。
吉田
市政の成果の9ページ、電算運営費の電子情報化推進事業の3番、地図情報システム管理運営費、平成29年度の質疑に対しては、利用者数は延べ3,373人と答弁されたと記憶しておりますが、平成30年度の実績として利用者数の延べ人数をお伺いいたします。
市政情報課長
延べ人数は3,004人です。
吉田
数だけ見ると減っているように見えますが、このサービスは本当にいろいろなことに使えてとても有益だと私は個人的には思います。平成30年度中に取り組んだ新しい内容というか機能が何かありましたら御紹介いただきたいと思います。
市政情報課長
平成30年度においては、道路の除融雪路線の表示ができるように機能強化をいたしました。それから、公共施設の公衆無線LANを備えている施設の表示ができるように機能強化をいたしております。
吉田
市政の成果15ページの市制施行60周年記念事業費についてお伺いいたします。これも総括質疑で御答弁をいただきましたが、3 委託料の中で一番大きなボリュームを持っているウォークイベント連動型ラジオ特別番組作成・放送等業務ですが、視聴率とか、実際にウォークイベントに参加した方の数を捉えていらっしゃいましたらお知らせいただきたいと思います。
政策企画課政策係長
こちらのウォークイベント連動型ラジオ特別番組作成・放送等業務の委託料ですが、ラジオウォークについては約550名の参加でありました。それから、特別番組の視聴率ですが、東北放送から提供いただいた内容ですと、9月29日の午前10時55分から午前11時25分まで放送しておりますが、その際における世帯視聴率については4.9%という形で報告をいただいております。
吉田
550名という数を多いと捉えるか少ないと捉えるかは私はわかりません。これだけ大きな予算をかけて行った事業ですが、この番組を制作する放送局をどのようにして決定したのか、それについて経緯をお伺いしたいと思います。
政策企画課政策係長
今回の市制施行60周年記念事業をどういったラインアップで進めるかについては、庁内で組織している策定本部会議で調整をしてきております。その中で今回どういった内容でいくかといったときに、このウォークラリーと番組をタイアップさせた形でできないかと考えました。そうなりますと、ウォークラリーはほかの自治体でも行っておりますが、ウォークイベントについては東北放送が実施していると。かつ、番組制作も行っているということもあり、そこを連動させて実施するということで東北放送を一者指名させていただきまして、委託をして進めてきたという経過です。
吉田
市政の成果15ページ、もう一度、市制施行60周年記念事業費についてですが、記念式典も、毎年行われている市制施行記念日の式典と同じような内容で、名取市文化会館の大ホールで行われました。あの式典で通常のさまざまな功労賞などとあわせて、つながりナトリ市民賞という、功績のあった市民の方を広く紹介していただいて市が賞を差し上げるという60周年独自のものがありましたが、実際にどういう形で該当者を選定したのか。私もそうですが、誰か該当する人はいませんかと紹介を求められたことがありましたが、それをどの範囲まで広げてやっていたのか。そして、その中から実際に選考した際に、落選した方はいたのでしょうか。
政策企画課秘書係長
つながりナトリ市民賞を平成30年度の式典で差し上げたわけですが、まず、周知に関しては、名取市民の皆様で市制施行50周年から60周年までの10年間さまざまな方面で活躍した方を広く褒賞するということで募集をしたところです。そこに関して、例えばホームページであるとか、あとは区長などにお願いして募集をしたところです。実際に紹介された方々に関しては、今回表彰審査を行いました。こちらについては、市政功労表彰についても表彰審査会がありますので、そのメンバーによって1人ずつ内申が上がってきたものを名簿のほうで処理して、これまでに例えば同じ項目で功労表彰を受賞した方を外していこうということで見てきたところです。それで、今回、表彰の該当から外れた方がいるかということですが、その辺に関しては若干いまして、例えば市の職員が業務のお褒めによって推薦をいただいたという大変ありがたいお話もあったのですが、残念ながらそういった方は除外したという経緯もありました。
吉田
今さらこんなことを言ってはいけないのかもしれませんが、あの人が選ばれたのに、同じような、あるいはそれ以上の働きをしている誰々さんはなぜ選ばれなかったのかとか、そういういろいろな意見が恐らく市のほうにもあったかと思いますし、私も聞いています。そういった部分の反省点を次にぜひ生かしてもらいたいと思います。
もう1点が、これは会場でも思ったのですが、これは通常の市制施行記念日の式典でもそうですが、ステージ上に並んでいるのはあくまでも来賓とか主催者だけであって、功労者の方も含めて、本来主役となるような受賞者の方々が壇上に上がらないで代表者だけにして、あとは客席で起立をして、代表者が賞状を授与されるという形式をとっています。ほかの自治体の例などを見ますと、全員上がって客席のほうを向いてもらうような取り組みをしているところもありますので、今後そうしたことを取り入れていただきたい。市制施行60周年記念事業もやはり市民のためのイベントであって、盛り上げるのは市役所ですが、市役所の中だけの盛り上がりではいけないわけです。どうやったら市民のために本当によりよいイベントになるかということをぜひ御検討を重ねて次につなげていただきたいと思ったところですが、その点について何か御意見がありましたらお伺いしたいと思います。
政策企画課秘書係長
今、委員おっしゃったとおり、今回もやはりさまざまな反省点はありました。その辺に関しては、きちんと資料に残しておりますので、今後、市制施行70周年の記念事業が行われるということであれば、きょう委員からお話しいただいたこともつけ加えて、次の会がよりよいものになるように努めていきたいと思います。
吉田
事項別明細書99、100ページ、2款1項27目諸費で、行政区長事務についてお伺いいたします。区長業務がいろいろとある中で、広報の配布が大きなものかと思いますが、平成30年度中、広報の配布を区長が行えずに別の形で配布したケースがありましたら、その件数等についてお伺いいたします。
総務課総務係長
平成30年度はちょうど区長の改選の時期に当たっておりまして、1つの行政区で推薦自体が1カ月おくれたということがありまして、そちらの1つの行政区において町内会等への配布をお願いした経緯があります。
吉田
1つというのは、1カ月ということでしょうか。その分は職員が手分けをして配布したのか、それとも別の業者を使ったのか。その町内会にどうやって配布したのかをお伺いいたします。
総務課総務係長
総務課の職員が手分けをして行ったところです。
本会議
(議案第63号 平成30年度名取市歳入歳出決算の認定)
吉田
5番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、名和会を代表しまして、議案第63号 平成30年度名取市歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から討論をさせていただきます。
一般会計・特別会計の歳入歳出決算額は、歳入が836億9,523万6,343円、歳出が715億1,346万6,404円で、昨年度に比べそれぞれ減少しました。
歳入では、現年度未納者を中心とした催告書の発送や納税相談等の早期対応などを実施したことにより、市税全体における収納率は前年度と比べ0.33ポイント高い97.38%となり、収入未済額の縮減が進んでいること、宮城県地方税滞納整理機構との連携により任意納付と滞納処分を行ったことで、約1,625万円の徴収に結びついたこと、さらに、納税誓約や滞納処分による給与差押等を継続していることなどについて、取り組みを評価すべきと考えます。
また、寄附金の総額は、前年度に比べて約1億9,656万円、86.58%の大幅な増となりました。当初の見込みを大幅に上回る寄附金が寄せられたことは大変にありがたいことですが、生まれ育った地域やゆかりのある自治体に共感し、応援するというこの制度の本来の目的から外れ、特産品の好みや返礼率の高さなどで選ばれているケースも多く、官製通販との批判の声も聞かれます。返礼品のラインアップの充実もさることながら、物品とは違う独創的なサービス型返礼を加えることについても調査研究を進められるよう望むところです。
ほかに、新たな財源等による歳入確保に取り組んだことは評価すべきと考えますが、新図書館を命名権の対象施設としたことについては、検討過程に慎重さと丁寧さが欠けていたのではないか、省みるべきであろうと思います。応募がなかったため、結果として企業名などがつくことにならなかったのは幸運でした。図書館は調査研究のための学術施設でもあり、安易に財源確保の種にするべきではないと考えます。自治体の品格をみずから損なうことのないよう、慎重な対応をとられることを望みます。
歳出に移ります。総務費では、市制施行60周年記念事業が開催されました。特に市民提案事業は、その後の自立と継続につながった活動もあり、効果的な取り組みであったと評価したいと思います。新しいイベントの実施に対しては、非常に意欲的に取り組んでおられるという印象を得ました。イベントは市のPRにつながる利点もありますが、行政主導で行われることには疑問を感じざるを得ません。行政とは政を行うと書きます。政の本質とは、天つちの恵みに感謝をささげ、国と民の安寧を願う深い祈りであり、お祭り騒ぎとは異なるものです。例えばラジオ特別番組は聴取率4.9%、参加者数は550名とのことでしたが、今も記憶にとどめている人は果たしてどのくらいいるのでしょうか。多額の費用をかけたことにより得られた効果について、納得できるレベルの説明ではありませんでした。次の10年に向けて、親しみやすさの中にも品位の光る行政であることを願います。
土木費では、市営住宅名取団地の解体が当初の計画を前倒しして進められていることを評価すべきと考えます。跡地活用について、住民アンケート調査の回答と市内部の意見との間には共通する部分と乖離する部分とがあるように感じられました。市の未来を見据え、地域の実情に合った計画となることを望みます。
消防費では、婦人防火クラブ会員数の増加や消防力強化のための備品整備等が進められた一方で、自主防災組織の年度内における新組織設立が2組織にとどまりました。自主防災組織の重要性を今後も粘り強く広報し、組織率の向上に努められることを望みます。
教育費では、市内小中学校で暑さ指数を計測する機器を導入し、熱中症予防指針のもとで活動が行われたことを評価すべきと考えます。しかし、プールや運動などが中止された回数が詳細に把握されておらず、運用面に課題が残りました。収集されたデータを整理、蓄積し、危機管理の徹底のため次年度以降へ引き継いでいただきますよう望むところです。
以上で賛成討論を終わります。
(議案第92号 工事請負契約の締結)
吉田
先ほどの御答弁の中で、歩道は非常時には車も通れると御説明があったと思いますが、歩道と車道と分ける縁石のようなものが図に描いてあります。これは取り外し可能なものですか、どのような形状かお聞きしたいと思います。
復興まちづくり課長
通常施工されている歩車道境界ブロックで、取り外し等はできません。あくまでも非常時、緊急時のみの利用と考えていますので、その幅の中を通れる車両、緊急車両に通っていただければという考えです。
吉田
緊急事態が起きないのが一番望ましいわけですが、いざ起きたときには歩道を通るという前提での緊急的な行動になると思います。その場合、実際にどのようなケースを想定しているのか、また、車の向かう方向はどちらからどちらに行けるのかとか、現時点で想定していることがもしあったらお伺いいたします。
復興まちづくり課長
通常は歩道としての利用です。緊急時としては、今回のような大震災や、また大地震などいろいろとあると思いますが、その時点でどのような活動が必要になるかによってさまざまに変わってくると思います。ですから、そこまで限定した考えはとっておりません。とにかく今は、通常時は歩道使い、緊急時には車両も使えるような形態につくり上げるという考えです。