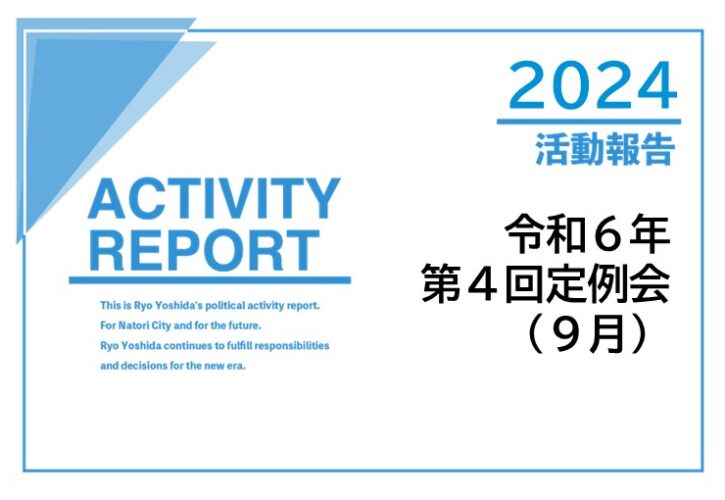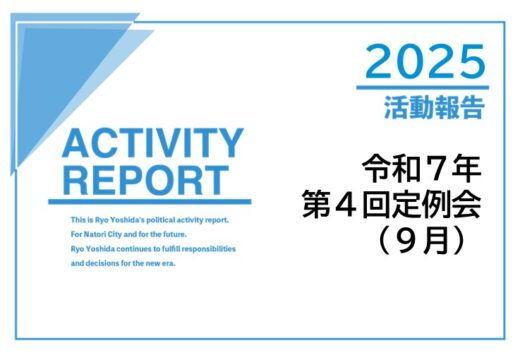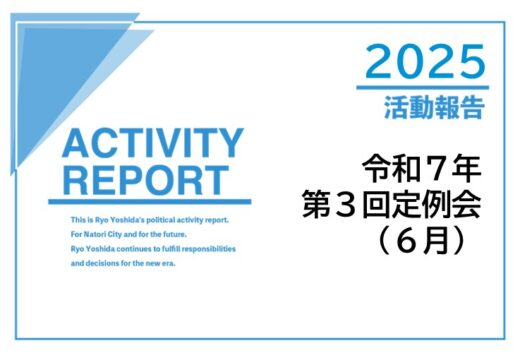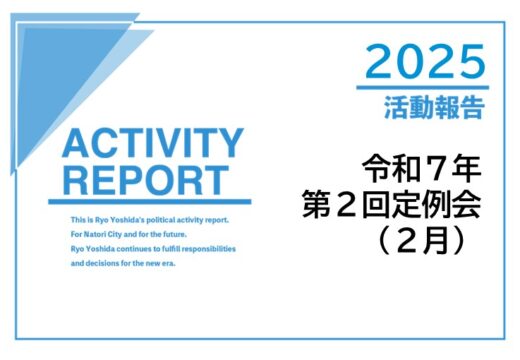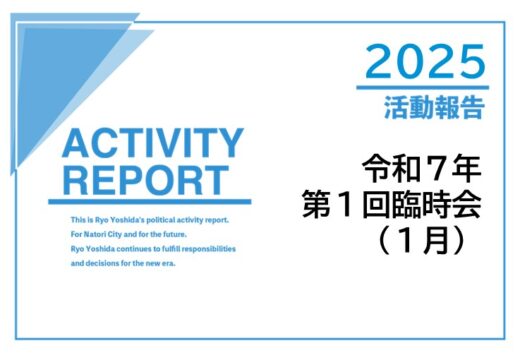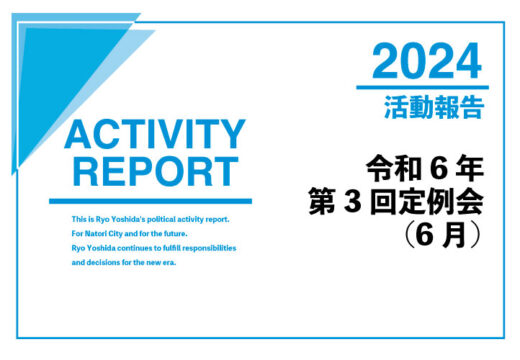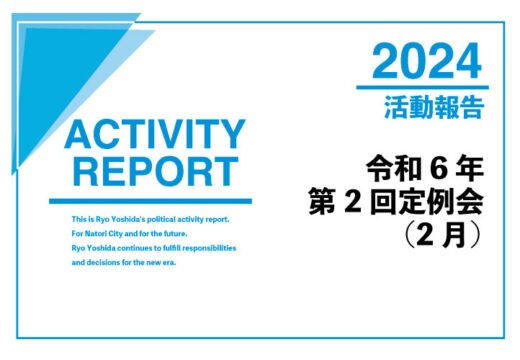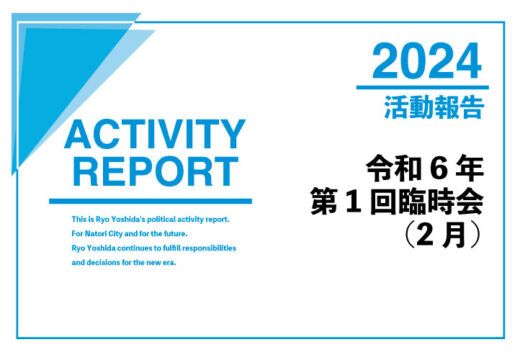本会議
(議案第102号 名取市教育委員会委員の任命)
吉田
議案書の31ページ、議案第102号の提案理由のところで、今回任期満了となる委員の浅野かほるさんの名前が書いてありますが、名取市の教育要覧や名取市教育委員会の会議録を見ると、かほるさんの名前が「ほ」ではなく「お」になっています。どちらが正確なのか、確認したほうがいいと思います。
総務課長
議案第102号の提案理由中、現教育委員会委員氏名を「浅野かほる」と記載しておりますが、こちらを「浅野かおる」に訂正をお願いしたいと思います。
一般質問
吉田
14番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、事前の通告に従って一般質問を行います。
初めに、大項目1 良好な景観の形成及び保全についてお伺いします。
景観については、令和3年9月定例会で取り上げました。そのときは景観を形成または保全すべき対象を具体的には指摘しませんでした。今回は具体的に3点について対応を求めていきたいと思います。
その前に、まず、これまでの取組について確認したいと思います。
小項目1 景観条例や景観計画など、景観に関する施策について、令和3年9月定例会における一般質問以後に進められた取組を市長にお伺いします。
市長
令和3年9月以後の景観に関する施策の取組につきましては、令和3年12月以降、毎年度、国土交通省主催の景観行政セミナーに参加しているほか、令和5年8月28日には、閖上公民館を会場に宮城県主催で開催された仙台湾沿岸地域の広域景観に関する勉強会に岩沼市、亘理町、山元町とともに参加し、この中で、景観資源・田園型景観等に関する紹介や洞口家住宅周辺の現地視察などを行ったところであります。
吉田
令和3年の9月定例会のときにいろいろな提案をしたのですが、検討するという答弁がありましたので、一つ一つ確認していきたいと思います。
まず、名取市都市計画マスタープランの中で「心地良い市街地・田園景観の形成」と基本的な方向性が挙げられており、それらに沿ってまちづくりを進めていきたいという答弁がありましたが、これらについては具体的にどのようなことをされたのかお伺いします。
都市計画課長
都市計画マスタープランには景観について述べている部分があり、「景観計画や地区計画等による美しい調和のとれた街並み形成の促進」としています。その中で、地区計画等で景観法を促進していたり、無電柱化等、そういった形で景観を維持保全してきたということです。
吉田
今、具体的に心地よい市街地や田園景観の形成という部分でお聞きしたのですが、特にそういった部分についてはなかったということでしょうか。
都市計画課長
特に具体的な景観計画の策定はありません。
吉田
また、景観法の第5条及び第6条に、事業者と住民が市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならないということ。そして、その協力の仕組みの構築について、今後の検討課題という答弁がありました。その検討についてはあったのかどうか、もしあったとすればどのような検討だったのかお伺いします。
都市計画課長
民間業者と住民が協力するような仕組みづくりは行いませんでした。
吉田
検討とあったのですが、3年あったのでいろいろと検討が進んでいるのかと思って期待していたのですが、残念です。
次は、景観条例の制定や景観計画を視野に入れながらという答弁もありました。本市における景観行政の在り方を検討していきたいと答弁がありましたが、こちらについての検討はいかがでしょうか。
都市計画課長
先ほど答弁にもありましたように、景観セミナーや研修等でいろいろ職員が学んできました。自然、歴史、文化、人々の生活、経済活動が調和することによって形成されるのが景観ですが、研修やセミナーで勉強しながら今後検討していかなければならないと感じています。
吉田
セミナーもせっかく時間と労力をかけて行くものですから、その後、何をつくるか、何を行うかが大事だと思います。
そしてもう一つ、景観行政団体への移行についても、先進事例を踏まえて十分に検討していきたいという御答弁がありましたが、十分に行われてきたのか確認させてください。
都市計画課長
景観行政団体については、景観計画を視野に入れながら考えるべきもので、景観計画の具体的な施策はこれから検討していくものですので、それと併せて景観行政団体についても考えていくものだと思っています。
吉田
これから検討というのは3年前におっしゃっていますので、その3年間一体どうだったかとお聞きした次第です。
その3年間の間に、こういうことが起きました。これは今日取り上げる1点目のテーマですが、大手町四丁目に予期せぬ開発行為ということで、9階建てのマンションの建築計画が今回明らかになりました。これについて、市の把握状況を確認したいと思います。
小項目2 大手町四丁目において、周辺では前例のない9階建てマンションの建築が計画されている。市で把握しているこれまでの経過と、今後見込まれるスケジュールを市長にお伺いします。
市長
大手町四丁目のマンション建築計画の経過につきましては、名取市中高層の建築物の建築に関する指導要綱に基づき、令和6年6月28日に建築主から建築計画事前確認書が提出され、7月8日には近隣説明会開催についての事前報告、7月9日には標識設置報告書の提出があったところです。
その後、8月21日には、7月21日に開催された近隣関係住民への建築計画の説明会の説明結果報告書及び建築計画等の提出がありましたが、説明会時に住民に対し回答保留とした項目があったことから、市としては、再度説明会を開催する必要がある旨の指導を8月29日付で行ったところであります。
このことに対し建築主からは、説明会時の未回答事項について、改めて近隣関係住民に回答する説明会を本日9月11日に開催すると伺っております。
なお、今後のスケジュールについては、建築主からの提出書類によると、令和6年12月下旬に建築工事着手、令和8年7月下旬に完成予定であることを確認しております。
吉田
まず、住民説明会の報告書が一部内容に不足があって、その部分の補正を求めたということについては、この建築指導要綱がしっかり機能しているということで認めたいと思います。
8月21日に報告書があったというのは7月21日の近隣住民を対象とする建築計画説明会なのですが、これも本市の中高層の建築物の建築に関する指導要綱に基づいて開催されたものであります。私自身は近隣というほど近いわけではありませんので、建築主から案内はありませんでしたが、近隣住民の方から情報の提供があり参加をさせていただきました。見たところで40名ほどの方が出席をされていて、質疑応答も活発に行われました。市長は、この説明会における近隣住民の反応がどのような雰囲気だったか御存じでしょうか。
市長
説明結果報告書並びに私たまたまその近くを歩いたときに近隣住民の方からお話を伺って、やはり子供たちの出入り、通学路、通行の問題であるとか車の出入りの問題、それから、高い建物が建つことに対して日陰になってしまうのではないか、それに対する補償はどうなんだということで心配する声が多くあったと捉えています。
吉田
住民の方々にとっては急に持ち上がった話でして、そもそも想定をしていなかったことですから、どうなっているのかということで非常に不安、不信感が高まっていると私も見受けられました。こういうことが起こらないように、先ほど申し上げたように事前に景観計画などしっかり策定しておくべきだったのではないかということなのですが、3年前の一般質問で私、地域政策プランナーの田村 明さんによる「美しい都市景観づくりのための19原則」を紹介しています。振り返りますと、その5番目に「都市の上空は市民総有の空間としてコントロールする」とあったのを覚えていらっしゃるでしょうか。3年前のこの一般質問の指摘を受けて検討から実施へと進めていれば、今般のマンションが計画される前に高さを制限する都市計画を定めることができていたのではないかと思いますが、今になって思われることがもしあればお伺いしたいと思います。
市長
当然、景観計画の中には市街地も含まれるわけではありますが、基本的には、自然であるとか歴史、文化、こうしたところの景観の在り方について考えていくものであると思っています。
それから、この当該の地区について、いわゆる市民の私権をある程度制限をしていくものになりますので、そういったことを進めていくにはやはり慎重な議論が必要だと思っています。
吉田
慎重な議論するために、3年ぐらいあれば十分にできたと思うのですが、それを行っていなかった、スタートしていなかったことが私は問題だと思っています。
それから、景観についても、もちろん歴史とか自然、そして人の暮らしとの融合、そうしたものを一体として捉えるのが景観だと前回も話しましたが、マスタープランの中には美しい街並みの形成ということもしっかり書いてあります。それも景観なんですよ。人が住んで、建物を建てて、その統一感ということも。ですから、これが当たらないと今聞こえたのですが、そうではないと私は思います。
それでは、次に移ります。地域住民による対応についてです。
マンション建築計画地の近隣住民はもとより、大手町四丁目、そして、増田西の町内会連合会に至るまで、このたびの計画の見直しを求める声が広がりつつあります。近隣住民としては、居住環境の悪化の懸念が一番の理由でありますが、それ以外の方からは、例えば、一体何のためにマスタープランの策定時に意見を聴取したのかと。せっかく意見を出しても意味がなかったのではないかという声も聞こえてきています。
そこで、小項目3 大手町四丁目におけるマンション建築計画は、美しい街並みの形成を図る都市計画マスタープランに適合しないのではないかと考える。地域住民による計画変更を求める署名活動及び地区まちづくりルールの策定に関する勉強会の開催計画がある事実について、当該計画の事業主との間で情報共有すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
当該建築主とは、既に名取市中高層の建築物の建築に関する指導要綱に基づき、手続を進めているところであり、御指摘の地域住民による計画変更を求める署名活動及び地区まちづくりルールの策定に関する勉強会の開催計画につきましても、当該建築主に情報提供を行ってまいります。
吉田
ぜひ情報提供を行っていただきたい。それは最低限だと思います。
そして、私、この署名の表題について伺わせていただいたのですが、建築計画見直しに関する要望書とありまして、実施主体は大手町四丁目の町内会、宛先は建築主の仙台支店となっています。計画そのものを白紙とかそういう過激なことではなくて、あくまでも地域住民の声を聞いてほしいと、一部変更を求める内容と理解しています。この要望書、私も趣旨に賛同していますので署名したいと思いますが、市長にも、もし趣旨に賛同できるのであれば、個人として署名していただくことはできないでしょうか。
市長
行政の長の立場でありますので、確かに私個人の権利も義務もありますが、そのことについては適切ではないのではないかと思います。
吉田
分かりました。
もう一つお聞きします。勉強会について、都市計画課から講師を派遣していただいて開催する出前講座ということで、9月29日に行われると伺っています。出前講座で説明される内容、既にいろいろ要望が来ていると思いますが、特にその中で地区まちづくりルールにはどのようなものがあるかということを中心に、簡潔にお考えの内容について御紹介いただきたいと思います。
都市計画課長
9月29日日曜日13時30分から、地元で地域のまちづくりのルールや地区計画について学びたいとあります。
今回、まず主題であります地区計画についての説明をしたいと思っていますし、まちづくりルールについても、様々なルールがありますので、その種類等々を説明していきながら、当日は皆様と勉強会を一緒にしていって理解を深めていければと思っています。
吉田
地区計画は非常に難易度が高い都市計画なので、実現可能な範囲でのものを特にお話しいただきたいという私の勝手な思いですが、そうした流れをしっかり受け取って、今度は行政としても、このマンション建築計画がこれだけ住民の方々にとって非常に不安が高いということをどういう形で事業者に理解していただけるかという検討につなげていきたいという思いです。
それでは、次に移りたいと思います。マンションの建築主は、法的に問題があるわけでもないのに、まさかこれほどまで住民が強く反発するとは恐らく予想もしていなかったと思います。ある意味でこれは建築主も被害者のようなものではないかと思います。
名取市都市計画マスタープラン改訂版の58ページ、地域住民の意見の6番目には「戸建て住宅を主体とした安全で住みよい環境の充実」とあります。この意見が出されたときに現状の用途地域では中高層マンションの建築を制限できない事実がもし説明されていれば、住民が主体となって地区まちづくりルールの策定に動いたかもしれません。そうすれば中高層マンションの建築を制限することが可能になったわけです。その意味で当時の市の対応はやはり不十分だったのではないかと思います。
大手町地区の住民のほとんどは、開発以来3階建て程度の建築物しか建てられないと認識をしてきました。このことは町内会による要望書にも書かれております。知らないほうが悪いと突き放すような行政であってはならないと思います。何とか大手町地区の居住環境、街並みの景観を保全したい。そのために地域住民の間で半世紀にわたり守られてきた不文律を尊重すべきと考えます。
そこで、小項目4 大手町地区に地区計画は定められていないものの、市街地の形成から約半世紀にわたり3階建てを超える建築物はほとんど建築されてきませんでした。住民によるこのような自主的な高さ制限は、不文法たる慣習として、成文による地区計画等の策定までの間効力を有すると考えますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
大手町地区については、高層の建築物は建築されてきませんでしたが、そのことが既存の法律をも規制する強い拘束力を有する慣習によるものであるとは考えておりません。
市としては、引き続き、法令等を適切に運用してまいります。
吉田
やはり法令に違反していることはないというのが一番の建築主の強みといいますか、地域住民としてはなかなかそこは規制がかけられない、非常に難しいというのは分かります。
ただ、やはり、この建築主の方も、これまで相当な期間、土地を所有していたならまだ理解できるのですが、今回は土地を取得されたのが非常に最近ということで、地域との縁が大変薄いと言えるかもしれません。約半世紀という長い年月、大手町地区の1,000を超える世帯が、このように例外はありますが、ほとんどが2階、高くても3階という理解の下で守ってきた地域の不文律というものを、つい最近土地を所有したばかりのたった1社の企業に覆されてしまうのは、やはり地域住民にとっては非常に納得し難いものがあるのではないかと私は思います。
やはりこうした事態を招いてしまった理由の中に、この地区計画等の策定が、住民のほうできちんと把握できていなかった、市のほうからもっと積極的にお知らせを本来すべきだったのではないかと私は思いますが、そういう意味で対応の不足があると少しでも理解されるのであれば、この建築主の方に、地域住民に寄り添うように申入れ等をしていただきたいと思いますが、そのあたりの考え方はいかがでしょうか。
市長
説明会で住民の方から不安視する声が寄せられ、それに対して一部保留したところ、回答されていないところもあり、指導した経過があります。やはりできる限り地域住民の方の不安また意見等については答えていただきたいという思いはあります。
一方で、建築確認申請が出される前の段階でありまして、行政としては、行政手続法に基づいてできるだけ遅滞なく手続、申請について確認していかなければいけないということもあります。そのはざまの中で、できることについてはできる限り地域に寄り添っていきたいと思っています。
吉田
建築確認申請は、土木事務所あるいは民間の認可を受けた機関ということで、どのように進むのか本市で把握するのは、地区計画が定められていませんので、難しくなってしまうということですから、そうなる前にあらかじめ事業者のほうには何らかの形で、こうした多くの市民の方、今日これだけ傍聴の方もいらっしゃっていますので、もちろん強制力はないので任意ではあるのですが、そうした懸念ということ、より善処してもらえるように申入れをしていただきたいと思います。
次に移ります。同様の問題が起こらないための対策についてです。
これから日本の人口減少、少子高齢化はますます深刻化すると予想されますが、本市は仙台市に隣接していることもあり、その減少は緩やかに進むと考えられます。したがって、住宅の投資の対象とされることにより、地域住民が望まない形で中高層マンションが建築されるケースは続いていくおそれがあります。未然に防ぐためのルールづくりが必要だと思います。
そこで、小項目5 地区計画が定められていない市街化区域に、住民主体により地区計画等の地区まちづくりルールを定めるための支援の在り方について検討すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
地区計画は、住民の私権の制限を伴う計画であることから、地権者による合意形成が不可欠であり、そのためには、規制の内容はもとより、まちの将来像について、住民の方々に共通の理解が得られるよう十分に議論していただくことが重要と考えております。
市といたしましては、今後とも地区の求めに応じ、勉強会に出向くなど、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
吉田
先ほどの地区計画だと非常にハードルが高いということですが、やはり地域の特性や必要性に応じて建物の高さが一番多く議論になる要素だと思います。となると、これは高度地区という都市計画あるいは合意形成が最も易しい任意のルールも定めることが可能ということで、こうした制度がもっと広く周知されることが必要だと思いますが、そのような方策について、今度こそ検討を進めるということ、本当に検討に向かうように約束していただきたいのですが、市長、いかがでしょうか。
市長
それぞれの地区、地域の方々が、やはり自分たちの地域をこのようにしていきたいというビジョンやまちづくりについて考えていくという機運については、大変すばらしいことであります。現に今、ゆりが丘地区において、そうしたことの取組を進めていただいている地域もあります。
一方で、やはり私権の制限を伴うことは大変難しいことになりますし、先ほど議員がおっしゃった、任意のルールということであれば、逆にその縛りのほうも自主的に担保していかなければいけないといったようなこともあります。
そういうことも含めて、まちづくりについて、地域づくりについて、地域の方が考えていきたいということについては、今後とも積極的に行政として支援をしていきたいと考えています。
吉田
様々な方法があるということがまず知られていませんので、それを知らせる方法から考えていただきたいと思います。
それでは、次に移りたいと思います。小項目6に入ります。具体的な内容の2つ目です。サッポロビール仙台工場ビオトープ園が令和6年12月に閉園となる予定である。なとり百選にも選ばれた、市を代表する景観の存続を求める姿勢を市として表明するとともに、所有者の考えを確認すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
平成19年3月に発行したなとり百選においては、緑豊かな水辺のビオトープ園を含め「サッポロビール仙台工場とビール園」として選定されておりました。
先ほどの二階堂 充議員の質問に対する答弁でも申し上げましたが、跡地利用につきましては、引き続きサッポロビール側と本市との意見交換をお願いし、望ましい方向性を検討してまいります。
吉田
本市としてはどう考えているのかというのが気になるんですね。もちろんこれは持ち主の意向が一番ですが、やはりこれだけ住民、そして住民に限らず駅の利用者にも利用されて愛されてきたものですから、まず本市の考え方をまとめるべきではないかと思います。ビオトープ園について、ぜひ存続してもらいたいのか、それとも、なくなっても仕方がないという捉え方なのか。そのあたりを決めてから希望を出すべきだと思いますが、どのようにこれから考え方をまとめていけばいいと思われるでしょうか。
市長
まず、ビオトープ園につきましては、ビール製造に当たり使用していた水の一部を水源として活用してきたために、現在ビールが造られていないということで、ビオトープ園の存在が水の問題で困難だと伺っています。
いずれサッポロビールの敷地も含めて、名取駅を中心とした東西のにぎわい交流のエリアになると思いますので、そうしたことについては本市としてどういうふうに考えていくか、都市計画マスタープランにも載ってはいますが、もう少し具体化したようなビジョンをできればお示しをしていきたい。その上で意見交換をしていければと思っています。
吉田
水に関するものはこれまで大体廃止されてきたのが多いので、非常にお金もかかりますし管理が大変というのは分かりますけど、もし存続するとなり、所有権を移すための手続に入るとなったときに、一つは市で買い取るのも選択肢だと思います。企業版ふるさと納税で不動産の寄附という形で法人住民税などの9割控除もあり得るということです。そういった制度上の優遇策などについてしっかりまとめて提示することはできると思いますが、そのあたりの考え方はいかがでしょうか。
市長
まず、サッポロビールが全体の開発についてどう考えるかというところ、それから、本市として、先ほど申し上げたような考え方、意見を申し上げて、サッポロビールについては民間ですので、最終的にはどうしても経済性というところが出てくるのかなと思います。そうした中で、ビール園が担ってきたにぎわい性やビオトープ園が担ってきた市民の憩いの場といったようなところを、どの程度、どういう形で継続できるのかということも含めて意見交換をしていきたいと思います。
吉田
そのように意見交換を続けていただきたいと思います。
それでは、次に移ります。具体的な内容の3番目です。小項目7 名取駅東西自由通路からの眺望を確保するため、北側の窓を覆うように設置されている横断幕を移設すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。
市長
名取駅東西自由通路は、通勤や通学等で利用する方が多いことから、市のプロモーション及び情報発信をする広告媒体として有効と考え、通路北側に市の情報や魅力に関する横断幕を設置しております。
設置場所については眺望の観点から、通路北側窓の上部に設置することも検討いたしましたが、排煙窓があることから現在の位置になった経緯があります。
今後、名取駅東西自由通路における情報発信については、デジタルサイネージに移行する予定であることから、横断幕の移設について検討を行ってまいります。
吉田
この間ある方から指摘がありました。夜中にあの辺に座ってる人がいた。しかし、横断幕つけたことで、夜中に座る人がいなくなった、かえってよかったのではないかという意見もありました。そうした経緯は検討の段階でお聞きになっていましたか。
市長
私も朝、通りますが、恐らく海外の方々だと思います。横断幕がどう影響したかについては、その検討の中には含めていません。
吉田
分かりました。横断幕そのもの、テント幕は今後移設ということだと思います。
私は名取駅を様々な情報発信の拠点にするという考え方にはもちろん賛同しています。それで、あのような形で市のPRをするとしたら、景観の観点から何ができるかというと、名取駅の改札口を出て真っ正面の窓のところに衣笠の松のステンドグラスがあります。あれは増田町内会で寄贈されたものと表示されています。あのようなアートとして将来に残るものを景観の中で取り入れていくと。これは先ほどから申し上げている美しい都市景観づくりのための19原則の中で12番目に「まちに優れたアートを置く」とありますので、そうしたことでも検討していただけたらいいのではないかと思います。作品としてずっと残るものとして、デジタルに限らずそれも検討してもらいたいと思いますが、お考えはいかがでしょうか。
市長
御答弁申し上げたとおり、今はデジタルサイネージということで議会でもお認めいただいておりまして、このことをしっかりと進めていきたいと思います。
景観について、名取駅の活用も含めてどういった方向があるかについては、調査研究していきたいと思います。
吉田
以上で大項目1を終わります。
続いて、大項目2 令和5年12月に市立学校で発生した重大事態についてお伺いします。
非常に痛ましいことに令和5年の年末、本市の公立学校で生徒が校舎の3階から転落する事案が起きてしまいました。当時、学校の保護者を対象に説明会が開かれたという情報を得ておりましたが、内容は転落事故であったと伺っていたため、特に疑問を持つことはありませんでした。ところが、令和6年に入り、7月18日の報道で、この件がいじめを苦とする自殺未遂であったことを知りました。それだけでも驚きでしたが、飛び降りた生徒は特別支援学級に通っていたこと、いじめ防止対策調査委員会がいじめを受けた本人やその保護者への連絡や聞き取りを一度も行っていなかったことなどが報じられ、とんでもないことが起きているとの認識に変わりました。その後の報道で、保護者からの申入れに基づいて調査のやり直しが決まるとともに、飛び降りた生徒が脳挫傷に伴う急性循環不全で亡くなっていた事実が明らかになりました。報道によると、けがの療養をしながら高校受験のために塾に通っていたそうです。彼は、本当は生きたかった、死にたくなどなかったはずなのに、自殺に追い込まれてしまったのです。学校でどんなに苦しい目に遭っていたのか。地面に体をたたきつけられた衝撃はどんなに痛かったか。そして、大事なお子さんを失った保護者はどんなに悲しいことか。想像すればするほど胸が締めつけられます。
今最も大事なことは真実の解明です。もう二度とこのような悲しい出来事が起こらないように、全ての事実を明らかにし、彼を自殺に追い込んだ者がいるのであれば、その全員に心から反省と被害者側へのおわびをさせなければなりません。また、教育委員会と学校が事実に向き合うことは、このたびの重大事態への対処や同種の事態の発生防止を図るためにも、決して欠かすことができないものと思います。
まずは、これまでの対応を確認してまいります。
小項目1 重大事態の発生からこれまでの対応の経過を、市長と教育長にお伺いします。
市長
令和5年12月19日に教育委員会から市内の中学生による飛び降り事案が発生したとの報告を受けました。
私からは、当該生徒及び保護者に寄り添った対応を行うこと、学校の生徒の心のケアを行うことなどについて話をしました。
その後、7月に保護者及び代理人弁護士から調査委員を一新し、調査をやり直すよう教育委員会に対して申入れがあり、教育委員会としては、背景調査と再発防止について早急に取り組んでいくためには、調査をやり直すことも必要との考えをお聞きしました。
今後は、新しい調査委員会において、国の指針やガイドラインにのっとって調査が進められていくものと考えております。
教育長
令和5年12月19日に市内の中学生による飛び降り事案が発生し、教育委員会では、直ちにいじめが疑われる重大事態と判断し、県を通じて文部科学省に報告するとともに第三者委員会の立ち上げに着手しました。
12月27日にはいじめ防止対策調査委員会の臨時会を開き、重大事態の概要説明を行いました。そして、令和6年1月24日に第1回の調査委員会を開き、重大事態に係る背景調査及び再発防止について、教育委員会から調査委員会へ諮問しました。
その後、2月27日に第2回、4月23日に第3回の調査委員会が行われましたが、7月に代理人弁護士から委員を一新し調査をやり直すよう申入れ書が届いたことから、調査委員会の委員の意見を聞いた上で、8月に調査委員会として調査のやり直しを決定し、代理人弁護士にその旨を報告いたしました。
吉田
まずはお二人にお伺いしていきたいと思います。このいじめた者、それから、いじめの疑いが濃厚な者の特定の状況については把握されているでしょうか。また、報道によると教師もいじめに関わっていたということがありますが、その部分の把握についても状況をお伺いします。
市長
教育委員会で調査委員会を設置して調査を進めているということはお聞きしていましたが、その内容についてはお伺いをしていないところです。
教育長
いじめの有無についてですが、まず、調査の過程等でいじめがあったという事実は何件か確認はされています。ただ、以前の調査委員会の中で今回の重大事態の背景調査をお願いしていたわけですが、今回の飛び降り事案の背景として、いじめがどのように関わっていたかという判断についてはまだ調査の途中ですし、今後、新しい調査委員会においてその因果関係を明らかにしていただくことをお願いしていきたいと考えていますので、現時点では、いじめの事実があったということはありますが、具体的な内容、それから、今回の事案との関係等については、これからの調査を待つということになると思います。
吉田
こういう事案が起きると、大体どこの教育委員会もそういう対応を取るのですが、もう一つお二人にお聞きしたいのは、中学校3年生ということで、事情を知っている生徒たちは卒業ということです。また、教員の中でも異動があったと思います。異動や卒業等によって聞き取りに応じることが難しくなることや、また、事実解明につながる文書等の物品が散逸することも考えられるということで、これらのことを想定した上でお二人はどのように対応されてきたのかお伺いします。
市長
先ほども御答弁申し上げましたが、教育委員会で調査委員会を立ち上げて進めているということの報告のみ受けています。
教育長
議員御指摘のように卒業を控えた時期でしたので、12月に当該事態が発生した後、該当する学年の生徒からの聞き取りは速やかに学校を中心として行って、記録も残しています。今後、調査の中で再度の聞き取りが必要だということも出てくるかもしれませんが、その場合においては、保護者の了解を得た上で聞き取りを実施することもあるかと思います。
それから、その当時、調査委員会で収集したり、あるいは学校で確認した資料等については、教育委員会としても全て保管しており、そういった資料が散逸することはないものと思っています。
吉田
匿名のインターネット掲示板に、伏字ではあっても学校名が特定できる書き込みがありますが、この事実についてお二人は把握されているでしょうか。
市長
把握をしていないところです。
教育長
その書き込みについては把握しておりません。
吉田
それでは、次は、お二人にそれぞれ質問していきます。
まず、市長です。先ほど、12月19日、学校からすぐに報告があったということですが、こちらの報告が、いわゆるいじめ防止対策推進法第30条に規定される重大事態が発生した旨の報告と受け止めてよろしいかお聞きします。
教育長には、生徒が校舎から転落した際に学校は救急出動の要請をしたと思われますが、警察への通報をされたかどうか確認させてください。
市長
重大事態と認識しています。
教育長
警察にも通報したと伺っています。
吉田
それでは、市長には、今の重大事態の報告を受けてから現在までに総合教育会議が1月29日の第18回と5月30日の第19回、合計2回開かれたとホームページに記録されています。まず、この事実について間違いないか。それから、これは市長が招集したものか、教育委員会が招集したものか、それぞれ回ごとの別を伺います。
教育長には、12月26日に保護者説明会を開催されたことについて、本件重大事態を転落事故という形で説明したと、事情を知っている方から伺ったのですが、このことも含めて保護者説明会の詳細をお伺いします。
市長
私、市長が招集をして総合教育会議を行いました。日程については、今議員おっしゃったとおりかどうかについてはこの場では分かりかねます。
教育長
当該校で該当学年の保護者を対象に説明会を開催したという報告は受けています。12月19日に生徒が飛び降りた、転落して大けがをしたということについて、時間帯からいって見ている子供たちもいました。不安に感じている子供もいました。そういったことも含めて、今後の子供たちの心のケアなどについて学校から説明したと聞いています。
吉田
まず市長には、総合教育会議は市長の招集ということですが、本件重大事態について協議されなかったのかどうかお伺いします。
それから、教育長に対しては、被害者生徒以外の生徒対象の個人面談、それから、事案発生後、本来速やかに着手すべき全件を対象とする基本となる調査、それぞれが行われた日付についてお伺いします。
市長
総合教育会議において、この事案そのものについてのお話合いはしていません。
教育長
学校では事案のあった翌日12月20日に当該学年の生徒へのアンケートを行っています。何かその生徒のことで気になることはなかったか、その子が知っている情報とかを取得するためのアンケートを翌日に実施しています。その後、保護者に連絡をして、保護者の了解を得られた生徒については、12月末から1月初めにかけて3回に分けて個人面談を実施し、詳しく話を聞いています。希望する場合は、保護者も同席の下、面談を行っています。
吉田
まず市長に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に、地方公共団体の長は、児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議を行うために総合教育会議を設けることが規定されています。具体的には逐条解説に、いじめ問題により児童、生徒等の自殺が発生した場合とあります。この本件重大事態がこれに当たるとの認識がなかったのかどうかお伺いします。
それから、教育長には、いじめ防止対策推進法第28条第2項で、調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとされます。また、文部科学省が平成29年3月に示したいじめの重大事態の調査に関するガイドラインに、調査実施前に被害児童生徒、保護者に対して以下の1から6の事項について説明すること。説明を行う主体は、学校の設置者及び学校が行う場合と第三者調査委員会等の調査組織が行う場合が考えられる。状況に応じて適切に主体を判断することとあります。先ほどの経緯の中で、このガイドラインが守られずに被害者生徒保護者にはそういった説明が一切なかったと思うのですが、なぜ守られなかったと捉えているのかお伺いします。
市長
総合教育会議は一つの手段であると思いますが、総合教育会議を開催する段階において、まだ教育委員会で調査委員会を立ち上げて調査をしている段階でありますので、そちらのほうでまずは事実解明をしっかりとしていただいて進めていくべき事案と捉えていたところであります。
教育長
今議員から御紹介のありましたガイドラインに沿った進め方ということに関して、まず、調査委員会での調査が始まる前の説明については、1月18日に教育委員会において、当該生徒の母親と代理人弁護士が来庁しまして、私と担当指導主事から、まず、いじめ防止対策調査委員会において調査を進めること、いじめ防止対策調査委員の委員の構成、それから、当該学年の生徒から、あるいは先生からの聞き取りを行うことなどをお話をして、一応の了解はいただいています。ただ、その後、調査委員会を何回か開催してきたわけですけれども、その後の経過等については、代理人弁護士、母親からも御指摘いただきましたが、十分な説明が行われなかったことは事実でありますし、その辺については大変申し訳なく反省をしているところです。
吉田
まず市長にですが、そもそもこの総合教育会議というものが、今の運用として、本当に協議調整すべき事務に当たらないものが議題とされることが多いのではないかということが多く見受けられています。その一方で、なぜこの総合教育会議が設けられたかというのは、それこそまさに市長がリーダーシップを発揮して、いじめ問題にしっかり取り組んでいくというその趣旨の下に新たに設けられた制度ですから、こうした重大事態が発生したときに、真っ先に開いて、すぐに開いて、そして協議していかなければならないはずだったと思います。そうしたことについては、きちんと規定を分かった上で運用していたのか、それとも抜けていたのか、一体どちらだったのか、お伺いしたいと思います。
それから、教育長に対しては、今おっしゃった内容でもう1回確認です。一番最初に母親と代理弁護士に説明した際に、ガイドラインの1から6が全て満たされていたかどうか、もう一度確認させてください。
市長
やはり議員がおっしゃっている事実関係がまず明確にならなければいけませんし、そのためには調査委員会を通じて様々な方々への聞き取りや証拠を踏まえて判断されるべきものであります。総合教育会議を開いても、まだ調査委員会で調査中ということでありますので、ある程度資料がそろってきた段階であれば、判断として総合教育会議にかけて、一番の主眼としてはなぜこういうことが起きたのか、二度と起きないようにするためには、いじめを防止するためにはどうすればいいのかということを話し合っていくべきだと思っています。
考え方については、担当より答弁をいたさせます。
総務部長
一般的な話になりますが、いじめ防止対策推進法第30条第2項については、教育委員会から報告を受けた地方公共団体の長、市長については、第28条第1項の規定の調査の結果について調査を行うことができるということで、まず調査が行われて、学校の設置者として報告を受けて、その後にどういった措置を取る必要があるのかにつながるものだと考えています。先ほど市長が御答弁申し上げましたとおり、総合教育会議で協議する材料がまだそろっていなかったため、そのような対応がなされたものと認識しています。
教育長
6項目について、1番目の調査の目的・目標について、口頭ですので、どこまで具体的に説明したかは、はっきりしないところもありますが、調査を始めると。目的としては、今回の飛び降り事案についての背景調査と再発防止策、それから、学校の対応、教育委員会の対応等について検証をしていただくと。2番目の調査主体ついては、組織の構成として10人で構成され、どういう職業の方が構成メンバーに入っているかについてもお話はしています。3番目の調査時期・期間については、これから調査を行うことはお話をしていますが、期間については、見通せないこともあったので具体的にはお話はしていません。4番目、調査事項については、先ほどと繰り返しになりますが、背景調査、学校の対応、教育委員会の対応、再発防止策について調査をしていただくことはお話をしています。5番目、調査方法ですが、当該学年の生徒や職員からの聞き取りをすることはお話をしていますが、具体的にどういうアンケートをして、いつ聞き取りをするというところまでの具体はお話はしていないと思います。6番目の調査結果の提供については、その後の経過の説明が抜けていたところとも関わりますが、十分な説明はなされていなかったと思っています。
吉田
まず、市長には、総合教育会議の中で調査の具体的内容まで踏み込むのではなくて、今まさに教育長がおっしゃったようなガイドラインにしっかり沿った調査が行われているのかなど、その仕組みのほうを確認し、調整して、そして、協議するのが総合教育会議の役割だと思いますが、それが行われなかったのは、やはり私は対応が足りなかったのではないかと思います。そのあたりの考え方をもう一度お伺いしたいと思います。
それから、教育長には、今おっしゃったように1から6まで、当時説明されたことが今どれに当てはまるかと考えている時点で、当時このガイドラインに沿っていなかったことは事実ではないかと受け止めさせていただきました。ほかに、例えば子供の自殺が起きたときの背景調査の指針というものもありまして、その総論の中に非常に重要なことが書いてあります。学校及び学校の設置者が、たとえ自らに不都合なことがあったとしても事実にしっかりと向き合おうとする姿勢が何よりも重要であるということです。この事実にしっかり向き合うという姿勢については、しっかり確保されていたということでよろしいでしょうか。
総務部長
先ほどの答弁と重なるところがあるかと思いますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律上の第1条の4総合教育会議の中で総合教育会議が行う第2号だと思いますが、児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置について所掌していると認識しています。そうなりますと被害が生じるおそれもしくは生じるおそれがあると見込まれる場合ということで、緊急に措置しなければならないことについて協議することはあるかと思いますが、既に起きてしまったことについては、細かく言ってしまえば対象外になると思います。
教育長
先ほど申し上げましたように、いじめ防止対策調査委員会において、教育委員会で諮問した内容が、今回の事案の背景調査、学校の対応、教育委員会の対応の検証ということも含んでいました。当然、都合の悪いことと向き合わないということは全く私自身も考えていませんし、調査委員会の委員の方々も、私から申し上げましたし、そのような認識、考えは全くなかったものと思います。ということから、私も、教育委員会も、いじめ防止対策調査委員会も、きちんと事実と向き合って調査を進めるという考え方は持っていたと認識しています。
吉田
分かりました。
それでは、次に移ります。8月24日の新聞報道から得た情報に基づいてです。
小項目2 報道によると、調査委員会の委員を一新し、調査をやり直すとのことである。委員の交代の根拠と、従前の調査からの引継ぎの方法を教育長にお伺いします。
教育長
当該保護者及び代理人弁護士からの申入れや、それまでの経緯について、10人の調査委員へ説明を行ったところ、全ての調査委員から、委員を一新し、調査をやり直したほうがよいという意見をいただきました。任期の途中ではありますが、委員の皆さんは辞職され、新たな委員を選び直すことになります。
これまでの調査の引継ぎにつきましては、新しい調査委員会ができてから、新しい調査委員の意見を聞き、その取扱いについて決めていくことになります。
吉田
ある報道によりますと、1月に開始した旧調査委員会の調査については、8月の下旬の段階で報告書の策定段階に入っていたと報じられています。このことについて事実確認をさせていただきたいと思います。
教育長
当然いじめ防止対策調査委員会で調査をすれば、報告書は作成します。報告書を作成する作業、話合いは確かに行われていました。ただ、どの段階まで進んだかについては、途中のことでありますので、具体的な進捗状況については控えさせていただきます。
吉田
この8月下旬というのが、もしかしてミスリードなのかどうかははっきりと分からないのですが、そうすると交代前に行われた調査委員会の調査は、今後その内容を公表するものではなく、非公表という考えになっていくのでしょうか。
教育長
現時点では、これまでの調査委員会が調査をしてきた内容は全て非公表と考えています。
質問にもありました引継ぎに関しては、これまでの調査委員会の調査の進め方については当然報告します。新たな調査委員会で、この資料については新しい調査委員会でも資料として活用していきたいという話も出ると思います。客観的な資料や聞き取った内容等の資料については引継ぎも必要かなと思いますが、具体的な背景についての議論内容やいじめの認定、それと、今回の事案の関連性などについての議論等については、先入観を与えてしまうこともあるので、引き継ぐことはどうなのかという感じを持っています。
吉田
先ほど総合教育会議について市長に質問しましたが、教育委員会としても市長に対して招集を求めることができることになっていますし、運用上、逐条解説によると、緊急の場合には首長と教育長のみで開くことも可能と解されています。この総合教育会議は原則公開になっていまして、議事録の作成と公表が努力義務とされていますが、本市はそのように透明性をしっかり維持して確保しています。この調査委員の一新や調査のやり直しというような重要な案件を、本来は総合教育会議でしっかり過程が分かるような形で協議すべきであったと思うのですが、この点について教育長はいかがお考えでしょうか。
教育長
まず、いじめ防止対策調査委員会の調査そのものについては、原則非公開で進めていますし、そのこと自体は問題はなかったと考えています。
総合教育会議については、市長が主催するものです。確かに今議員御指摘のように私のほうから申し上げることも可能だとは思います。
この間の8月末に文部科学省でいじめの重大事態に関するガイドラインを改訂しまして、その中でも重大事態について取り上げることも触れています。ただ、その場合、当然内容が内容なだけに非公開とすることも考えられるということも書いてあります。都合が悪いから公開しないということではなく、プライバシーの問題や十分な解釈や判断ができてない段階で、途中段階での話合いの状況などを公開することが果たしていいのかどうかという問題もあります。
報告書ができた段階では原則として公表することが求められるとガイドラインにもありますので、基本的には報告書については何らかの形で公表すべきものだと思っています。
吉田
私はその内容云々ではなくて、手続上のことです。今混乱と言っていいと思います。委員が一新するというのは、本当に全国的にもきっと例がないのではないかと思います。そういうことに関して、もっと透明性を図るべきではなかったかと思いますし、それから、引継ぎの部分に関しても、メンバーが一新してしまえば、一人でも残るわけではないですから、新しい調査委員会に全て情報がしっかり引き継がれるかどうかが非常に疑問です。ということで、全ての情報が正確に引き継がれることを担保できる仕組みが何か必要なのではないかと。第三者ではなくて第四者によるチェックなど、そういったことについて何か検討されていないのでしょうか。
教育長
第四者までは現在考えていません。これまで調査委員会で収集してきた、要望によって学校等から集めた資料については全て、先ほどお話ししたように教育委員会できちんと保管してあります。前の調査委員会でこういう資料を集めて議論してきたということは、当然新しい調査委員会の委員の皆様にもお示しをします。必要となれば当然それを全て新たな委員会の資料として引き継ぐことになると思います。ただ、新しい調査委員会の委員のお考えを尊重しながら、教育委員会の下に置く第三者委員会ではありますが、調査については独立性のあるものだと思っていますので、最大限、新しい調査委員会委員の皆さんの考えを尊重しながら進めていきたいと考えています。
吉田
分かりました。
では、次に移りたいと思います。小項目3 再発防止への対策の方向性を示すべきと考えますが、市長と教育長の御見解をお伺いします。
市長
いじめはあってはならないものです。命の大切さや貴さ、いじめは絶対許さないという心情を子供たちに育てていくことが何より大切だと考えます。いじめの早期発見に努め対応していくことも含め、教育委員会と連携して取り組んでまいります。
その際、名取市自死対策計画に基づき、若い世代の自死対策についても教育委員会と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。
教育長
先ほど来申し上げておりますが、調査委員会において再発防止についての提言もいただきたいと思っていますが、当然それを受けてさらに取り組むということは考えています。今回の事案発生後、教育委員会としても、いじめの重大事態の再発防止のため、いじめの未然防止、いじめの早期発見、いじめが起きたときの組織的対応・関係機関との連携に取り組んでまいりました。
いじめの未然防止のためには、児童生徒が、安心して自己有用感や充実感を感じられる学校生活を送っていけるような学校づくりが重要だと考えます。
また、いじめの早期発見では、毎月のアンケート調査や教育相談の実施、生涯学習課で作成し、毎年児童生徒に配付しているこども相談カードを活用した電話相談窓口の周知等により、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整えてまいります。
いじめへの対処につきましては、組織的な対応、必要に応じた関係機関との連携が重要だと考えます。
これまでも学校では以上のような取組を行ってまいりましたが、さらに徹底していくよう、教育委員会として指導してまいります。
また、宮城県立精神医療センターの吉田弘和先生を講師とし、「死にたいと話している子供がいたときの対応」をテーマとした心のケアに関する研修会を毎年実施することで、児童生徒の心のケアの充実を図ってまいります。
吉田
再発防止のために、外部への取組はもちろんですが、組織の中の今回の対応に対する反省、振り返り、総括がどうなるのか一番気になります。まだ報告書が出ていない段階なので、これからになってくると思いますが、その見通しについてお伺いしたいと思います。
特別支援学級に通う生徒、特別支援学級ですよ。普通学級の生徒も命の重さは同じですが、特別支援学級に入ることを望んで、そして、そこで勉強していた生徒をいじめから守ることができなかったこと。そして、自殺未遂によるけがが原因で貴い命が失われたこと。また、保護者の不信感を招いたこと。これは事実であります。生徒を預かる学校関係者、また、その設置者としての教育委員会が何も責任を取らないということは、私は考えられないと思います。この責任の所在と重さについて、教育長どのようにお考えなのかお伺いします。
教育長
今冒頭でお話があった点について、教育委員会として確認できていないところもあります。特別支援学級に在籍をしていたことがいじめの要因だったのかについても調査委員会において、いろいろ検証していただいております。また、亡くなられた原因についても今言及されていましたが、それについては教育委員会では、12月の事案との因果関係を知る具体的な情報は持っていませんので、そこは何とも申し上げられません。
ただ、今回のような重大事態を招いたこと、それから、その調査の過程で保護者、生徒、代理人弁護士等の信頼を得ることができなかったことについては、私の十分な説明が不足していたことが大きな要因だろうと考えています。当然今回の事態が起きたこと、それから、こういう混乱を招いたことについては、私の責任は重いものと認識をしています。
吉田
また、いじめを行った者がいるはずですね。遺書にも書かれていたと思います。その事実関係もこれから明らかになっていくと思いますが、いじめを行った人が何もなかったように生きていくというのは、これは教育上一番悪い効果ではないかと私は思います。他人を傷つけるような悪事を働いておいて何の報いも受けないということが当たり前となったら、倫理や道徳は崩壊してしまいます。いじめに加わった者がもしいるのであれば、刑事責任や賠償責任は、これは今回の議題とは別です。それとは別に、良心として、お墓や仏壇の前で手を合わせるなどして、自らの言葉で償うべきだと思います。それが本来の本人たちのため、将来のためになると私は思います。これを促すのが教育の役割ではないかと思いますが、教育長どう思いますか。
教育長
いじめは絶対に許されないものであるという点、それから、いじめた側が心の痛みを感じていないとしたら、それは非常に大きな問題だと思います。
今回の件については、先ほどもいじめがあったことは学校でも把握をしていたということは申し上げましたが、様々ないじめについての当事者側からの訴え、それから、学校による生徒からの聞き取り、教員からの聞き取りなど、かみ合わない部分があるのも事実です。そういった点も含めて、今後、調査委員会において、因果関係、いじめの有無、それとの背景としてどういうふうに関わりがあったかということについて議論をしていただき、背景を明らかにしていただくことになると思いますので、具体的にいじめた側がどういった対応ということまでは、現時点ではまだ考えることができない状況です。
吉田
私は、いじめた側に対する懲罰という観点からではなくて、あくまでも教育上の観点から申し上げているつもりです。もし本当にいじめが原因であったと、いじめそのものがあったということ自体が非常に重大なことで、残念なことですけど、絶対にうやむやにしてもらいたくはないので、しっかり調査を完遂してもらいたいと思います。やはり気になるのは、この事実の解明が、被害者生徒が亡くなったこと、そして、この調査委員会が1回解散となって一新されてメンバー全部入れ替わったということで、真相を完全に解明するのは今非常に困難な状態に置かれているのではないかと思います。おまけに同級生は皆卒業していると。教師の中には異動した人もいると思います。関係者への一斉の調査は今後不可能となっています。この新しい調査委員会は、よほどの手腕がなければ真相にたどり着くことはできないと思われますが、どのようにサポートされていくつもりでしょうか。
教育長
御指摘のように、今回の事案について、卒業学年であったこと、それから、調査委員会のメンバーを入れ替えるという要因もありますが、一般論として申し上げると、他の自治体の同様の重大事態の調査においても、年単位での調査であり、はっきりとした因果関係等を結論づけられないようなケースもあると承知をしています。今回の件がそうだということではありませんが、文部科学省のガイドラインにも、この調査は決して警察組織とか裁判のために行うものではなく、背景をできる限り明らかにし、再発防止に役立てていくということがあります。当然捜査権もありませんので、事実関係をどこまで明らかにできるか、断定的なことは申し上げられませんが、現時点で申し上げられるのは、今まで蓄積してきた資料、それから、今後、新しい調査委員会で必要とされる聞き取り調査などを通して、できる限り事実関係、背景を明らかにし、今後の本市の学校において、再発防止のためにこんなことをしていく必要があるという提言をいただき、教育委員会として全力でそれに取り組んでいくということです。具体的な答弁にはなっていないかもしれませんが、今後そういった考え方で取り組んでいきたいと思っています。
吉田
いじめによる自殺、痛ましい事件、全国で起きている中で、滋賀県大津市で起きた大津いじめ自殺事件というのがありました。こちらについても非常に調査委員会や教育委員会の対応がよくなかったということで、調査の過程でいろいろと国民全体から高まった声に応える形で対応されてきたという経緯がありました。今回の本件事案については、私は名取市教育委員会の対応は、全体としてどうだったのかなと、本当にこれを検証しないことには、また同じようなことが起きてしまうのではないか。それはいじめに限らず、ガイドラインに沿った形での行動が一部できていなかったりして、大変憂慮しているところです。
また、一番最初の小項目で申し上げたのですが、大津の事件は学校名が公表されています。これはもう明らかになっています。今回の事案について、今後、学校名の公表についての考え方はどのようなものをお持ちなのかお伺いします。
教育長
教育委員会として積極的に公表する考えはありません。
吉田
公表することがいいのか悪いのかといったら、もちろん公表しないでおいたほうが学校関係者の方々にとっては平穏が保たれるのだと思います。一方で、先ほど申し上げたようなインターネット上でもう既に名前が特定できるような書き込みがあったり、あるいは、一般人がこの件を報道で知って、あの学校ではないか、あそこで自殺あったみたいだよというように複数の学校の名前が挙がっていて、事実でない事柄が流布されているといった現状もあります。そういう意味では何かしら対応を取らなければいけないのではないかと思いますが、教育長、いかがお考えですか。
教育長
先ほど申し上げましたのは、教育委員会として積極的に公表する考えはないということですが、保護者あるいは代理人弁護士が公表を望むのであれば、公表されるのかなと思います。ただ、教育委員会のほうから積極的に公表する考えはないということで先ほどは申し上げたつもりです。
吉田
分かりました。
最後に、執行部の皆さんではなく、全国で現にいじめられている方、いじめを受けたことがある方にメッセージとして残させていただきたいと思いますが、いじめに負けてはいけないと思います。いじめに勝つというのは、いじめられている本人がいじめた人よりも幸せに生きていくことだと、それしかないと思います。そして、必ず幸せになれると思います。いじめは絶対いけないことだと、このことを強調して、今日の一般質問を終わらせていただきたいと思います。
本会議
(議案第91号 名取市歯と口腔の健康づくり推進条例)
吉田
条例の第4条市民の役割の2行目に「自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努める」とあります。努力義務ということだと思いますが、この「自ら」というのは、一般的に小さいお子さんには難しいのではないかと思います。ここにある市民の定義の年齢的な考え方はあるのでしょうか。本当に小さいお子さんは、この市民の中に含めるのは無理があるのではないかと思いますが、その年齢の考え方をお伺いします。
保健センター所長
市民の役割の中の知識及び理解を深めるというところについては、なかなか小児、幼児は難しいかとは思いますが、大体乳歯が生えそろってぶくぶくうがいができる、歯磨きができる年齢が3歳ぐらいになりますので、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むという意味では、幼児も対象にした考え方をしています。
吉田
第9条第2号には乳幼児期及び学齢期における虫歯の予防対策に関することが載っています。これは市の基本施策の推進ということです。もちろん小さいお子さんでぶくぶくうがいができるのは自ら努めることになると思いますが、それと同時に、家庭の中において食生活や歯磨きを習慣づけることが必要ではないかと思います。この条例の中に保護者、家庭の役割が書かれていませんが、なぜでしょうか。
保健センター所長
家庭としての役割や保護者としての役割という形では記載していませんが、今回条例の中ではライフステージに応じた対策という分け方をしています。家庭での内容については、乳幼児期、学齢期における対策として、7か月児相談や乳幼児健診、保育所や幼稚園での歯科指導の中で対応していきたいと考えています。
吉田
歯を大事にしていく習慣は小さいときに家庭で身につけていくことが非常に大きな要素で、この条例をつくるに当たって家庭の役割を盛り込まないのは、一番大事な部分が欠けているのではないかと思います。例えば、経験上、だんだん年を取ってくると、歯の健康を保つには歯磨きだけでは駄目で、デンタルフロスを使うといいのです。そういう具体的な歯の健康を保つ方法などは、条例に基づいての基本計画あるいはいろいろな講習会で教えてもらえばいいと思いますが、子供の頃に家庭で歯を大事にする習慣をつけていくということをなぜ載せないのかと思います。県の条例にも載っていないようですが、県と必ずしも同じものをつくらなければいけないということではなくて、本市は本市でそういうところをもっとより幅広く課題として捉えてもらったらいいのではないかと思ったのですが、そうした検討はなかったのですか。家庭の役割を載せない何か大きな理由があるのでしょうか。
保健センター所長
議員がおっしゃるとおり、家庭での役割は大変大事だと思っています。乳幼児においても保護者の仕上げ磨きが大切であるとか、歯ブラシだけではなくデンタルフロスの使用も大変重要なことと考えています。ただ、今回の条例については、ライフステージごとという区分けをさせていただいていますので、詳しい内容については基本計画に記載していきたいと考えます。
吉田
小さい子供の歯の状況を見ると、家庭で育児放棄されていないかということも見えてくるというぐらい子供の歯の状態はいろいろなことを示すもので、私はここに保護者あるいは家庭の役割が書かれていないのは、一番大事な部分が欠けているのではないかと感じます。
今回はせっかくの提案なのでこの形でいいと思いますが、今後、いろいろな機会を捉えて条例改正など、もっと内容を良いものにしていくべきだと思いますが、その際にこの家庭の役割など盛り込めるような余地は残っているのでしょうか。可能性があるかどうか伺います。
保健センター所長
現段階で可能性についてお答えすることはできませんが、今後検討していきたいと思います。
(議案第94号 令和6年度名取市一般会計補正予算)
吉田
事項別明細書の6、7ページ、15款2項1目総務費国庫補助金2節デジタル田園都市国家構想交付金は、具体的にどの事業に充てられるのかと、それぞれの内訳をお伺いします。
政策企画課長
今回補正をさせていただきますデジタル田園都市国家構想交付金については、歳出では2款1項6目企画費12節委託料の増に伴い増加するものです。具体的な事業としては、デジタル地域通貨なとりコインの取組にかかる増額に対応するものです。
吉田
地域通貨はDXの推進の枠組みだと思いますが、今回増となった部分の割合はどのようになっているのでしょうか。
企画部長
先ほど政策企画課長が申し上げました歳出の委託料727万6,000円のうち、175万円分が補助の対象外となっています。残りの552万6,000円の2分の1が補助として措置されるものとなります。
吉田
12、13ページ、22款1項9目諸支出金債1節普通財産取得債について、先ほどの財政課長の答弁ですと、実際にこれがお金となって入ってくるのはもう少し先になるのかなと受け止めました。令和6年11月から12月頃に計画書提出ということですが、今、額面上予算措置をするわけですが、実際にこの額は本市の財布の中にはないわけですよね。実際お金が入ることがもっと確実になってからでないと予算として計上するのは早いのではないかという単純な疑問です。なぜ今なのでしょうか。
財政課長
実際起債を予算化しても資金が入ってくるのは、議員からお話ありましたとおり令和6年度末もしくは出納閉鎖期間中となります。ただ、起債協議をしていく上で、予算の計上をしているものという条件がありますので、事前に予算を計上させていただいて協議に当たっていきます。
吉田
県に対して提出する計画書に予算措置がされているという記述がなければ県には受け取ってもらえないと理解しました。以前、病院の用地買上げに関する一般質問をしたときに、県から融資を受けて、その返済の仕方は有期限、無期限という2種類が大きく分けてあるということでしたが、今回の起債について、計画書の中ではどういう形で県に要望されていくのかお伺いします。
財政課長
返済の期間や各種条件などについては、起債計画書の中に含めるものではありません。一般的に起債のメニューによって償還期間や起債の借入れ条件が決まってきますので、実際どういったメニュー、どこから起債を借りられるのか、そういったことは起債協議以降に、決まってくるという取扱いになっています。
吉田
14、15ページ、2款1項6目企画費デジタル地域通貨システム運用事業全体でお伺いします。先ほど歳入でもお伺いしましたが、まず、今回の補正の内容についてお伺いします。
DX推進室長
7節報償費は、デジタル地域通貨アンケート結果分析謝礼で、現状や課題を分析して、今後の利用促進の方法やシステム見直し等の検討材料とするために利用者と加盟店それぞれを対象に各1回実施するアンケートの分析に対する謝礼となっています。
12節委託料は、1点目のデジタル地域通貨システム運用委託料です。こちらはシステム業者に対する委託料になっていまして、主な増額の内容としては、令和5年に予定していた加盟店説明会、利用者説明会等を令和6年度開催へ変更したことに伴う増額になっています。
2点目のデジタル地域通貨管理委託料は事務局業務を担当する名取市商工会に対する委託料になっていまして、今回の主な増額の内容としては、4月から6月9日までに行ったモニター実証実験を受けて、商工会から加盟店への振込作業が複雑でヒューマンエラーが発生するおそれがあるといった相談を受けたことに伴い、今後の加盟店の増加や決済金額が増加した場合でも安定的に対応できるように、銀行指定のフォーマットにて振込データを作成するシステムを構築するものの増額になっています。
吉田
先ほど国の交付金が認められるものと対象外のものがあるという御説明でしたが、具体的にはどこの部分で認められなかったのでしょうか。
DX推進室長
補助金の交付対象外と捉えているものは、利用者がクレジットカードを使ってチャージする際のクレジットカード手数料、また、商工会で紙のカードを販売する際に市が商工会に支払う手数料などです。
吉田
14、15ページ、2款1項14目ふるさと振興費18節負担金補助及び交付金の国際交流実行委員会補助金について伺います。当初予算で令和6年度1,400万円、前年度比で300万円の増だったと記憶しています。その際の説明ですと、コロナ禍前よりも個人負担も増え、いろいろな燃料費などが増額していることが要因だと伺ったはずですが、今回さらに350万円増額となる理由をお伺いします。
なとりの魅力創生課長
議員御指摘のとおり、令和6年度の当初予算では、物価高や資材高騰、燃料費高騰を受けて増額して予算措置をしたところですが、いよいよ派遣事業の準備で旅行業者から見積りを徴収したところ、その増額以上の経費がかかるとのことから、今回さらに追加での増額補正を要求するものです。
吉田
時期がいつなのかという私の知識にはないので、時期がこれからやってくると思うのですが、あまりにも金額が大きく膨らみ過ぎているのではないでしょうか。人数や日程、実際参加者負担も負担金が7万円に上がったということで2万円増加していますが、そういった部分の変更点というものがあればお伺いします。
なとりの魅力創生課長
今回その見積りをいただいた段階で、どういった形で削減できるのか、課でも検討した経緯があります。その中で、令和6年度は令和7年3月にカナダに派遣しますが、これまでは直行便でカナダに派遣をしていたものを経由便を活用することで経費が圧縮できるといった提案もありまして、令和6年度についてはそういった形を採用しながら少しでも経費圧縮に努めてきたところです。
なお、自己負担金の兼ね合いも検討はさせていただきましたが、できる限り多くの方に参加していただきたいという思いから、今はお一人当たり自己負担金7万円をいただいていますが、これについては上げずに据置きでいきたいと。派遣団員数についても、より多くの方に経験を積んでいただきたいという観点から、例年どおり22名を予定しています。
吉田
16、17ページ、3款1項6目精神障害者福祉費14節工事請負費、友愛作業所改修工事でお伺いします。令和6年度当初予算でも措置されていまして、その際にしっかり質疑していなかったので、改めてこの工事の内容、そして今回の増額の内容についてお伺いします。
社会福祉課長
友愛作業所の大規模修繕を今行っていまして、令和5年度に外回りの工事を終えました。令和6年度については、中のひび割れの補修や古くなった部分の補修をしています。あわせて、2階の調理をするところが大分古くなっていましたので、そこの改装を行いました。
今回追加させていただくのは、階段の手すりの設置です。当初予定はしていなかったのですが、2階に上がる階段には今片側しか手すりがなく、利用者が高齢化してきたため危ないと思う瞬間が増えてきたそうで、施設側から反対側にも手すりをつけてほしいという要望があり、今回増額させていただく内容となっています。
吉田
内装工事となると利用者の方にいろいろと影響が出ると思いますが、どういう対策を取っているか。そして、工事の終了見込みをお伺いします。
社会福祉課長
主に精神障がいの方が通われているので、大きい音などに敏感な方が多いと思います。そのため、工事はできるだけ利用者のいない週末に集中するようにして対応しています。年度内には全ての工事を完了する予定となっています。
吉田
18、19ページ、3款3項5目児童措置費19節扶助費の母子生活支援施設入所措置費について伺います。施設は県内、県外合わせて3施設利用されていて、現状と今後増える見込みについて世帯数と人数の御説明がありましたが、実際は利用者の方が利用する日数によっても金額が変わってくると思います。そのあたりはどのように今回の増額に反映されているのか、考え方をお伺いしたいと思います。
こども支援課長
当初予算で計上した方は令和5年度から既に入所されていますので、令和6年度1年間の利用で2世帯4名の方は見込んでいました。このたび実績としてさらに4世帯9名の方が年度当初から入りまして、その方々も生活の立て直しの見込みが立てば自立に向けて退所しますので、当面の間、令和6年度中は利用される形で見込んでいます。さらにほかに3世帯11名の方について相談を受けているのですが、その方は、順次9月、10月程度の利用を見込んでいまして、令和7年3月まで入所の形で所要額を見込んでいます。
吉田
しっかり自立できるまで保護してあげることが大事だと思います。今の御説明ですと、今回見込まれている全世帯、全ての方たちは、令和7年3月いっぱいまで利用できるだけの分の額を今回措置したということでよろしいですか。
こども支援課長
議員お見込みのとおり、今回見込んでいる方については令和7年3月まで入所できる所要額を見込ませていただいています。
吉田
22、23ページ、6款3項2目水産業振興費のろ過海水供給事業について伺います。11節役務費のインターネット通信料は今までに見当たらなかった項目だと思います。実際に機械が稼働している状況など制御しているところと連絡取り合うものかと思いますが、この内容、期間、台数、上限データ量など契約の内容の確認をしたいと思います。
農林水産課長
現在、送水ポンプ室内に制御盤や炉圧計などがあり、貯留槽の残水量、稼働状況を確認していますが、今回新たに稼働状況や残量の確認など施設の維持管理の利便性を図るためにカメラを導入します。その通信料となっています。17節備品購入費ではカメラの購入を予定しています。
吉田
カメラを設置することによって稼働状況の確認がより正確にできるということだったら本当にいいことだと思います。しかし、カメラに録画されるのではなくて、常時それをインターネットにつないで通信を行うということであれば、通信されてきたその状況を常に24時間チェックしなければいけないと思いますが、それは事実無理ですよね。なぜカメラをつけるだけではなく、そこにインターネットの通信まで常時接続が必要になるのかが今の御説明では理解できないのですが、なぜなのでしょうか。
農林水産課長
設置したカメラをインターネット回線を通じての確認ということで、そのインターネット通信料としてお願いしています。
吉田
インターネット通信は分かりますが、何のためのインターネット通信なのか。カメラを設置して、その映像を24時間常時接続をして、それを誰かがチェックする体制をつくっていくということになるのでしょうか。
農林水産課長
非常停止の関係で、今まで送水ポンプ室の外にあるランプで停止状況を確認し、目視で確認していましたが、カメラを通して確認したほうが状況を詳しく確認できるということで、今回お願いしたものです。
吉田
カメラで常時接続しておいて、何か不具合があったときにすぐそれをモニターで確認できるような体制を整えるための通信料の措置ということになるのでしょうか。
農林水産課長
議員お見込みのとおりです。
吉田
22、23ページ、6款3項2目水産業振興費11節役務費のインターネット通信料について伺います。インターネットで通信をしてカメラから送られてきた映像をいつでも確認できるということですが、実際に管理をする管理者はどこに置かれているのか。先ほどコンサルタント会社に委託をしているということでしたが、その管理も委託先が決まっていて、今回その委託料も含めて措置されているということなのでしょうか。
農林水産課長
この通信料及び備品も市の属するものということで、市で管理するものとなっています。
吉田
では、今回のカメラ、今もしかすると農林水産課の中で画面がすぐに開けて、今こういう状況で動いているということが確認できる。これからカメラの通信料の補正が認められればそういう運用になっていくのだと思いますが、実際に不具合が発生していることを認識した際、どういう手順で不具合を直すことになっていくのか。そのときにまた予算措置を新たにしなければいけないのだとすると、カメラまでつけて、すぐに知らなければいけないということまですることなのかなと思うのですが、実際に不具合が起きたときの対応の進め方についてお伺いします。
農林水産課長
カメラ等でろ過海水の水中ポンプ等が止まっているのを確認した場合は、随時市の職員が現場に向かって対応しています。また、この保守点検の関係で、業者にも随時連絡をしながら、こちらの運用を図っています。
吉田
26、27ページ、10款1項2目事務局費1節報酬、いじめ防止対策調査委員会委員報酬の内容についてお伺いします。
学校教育課長
いじめ防止対策調査委員会は、いじめの重大事態発生により調査を実施してきたところですが、例年に比べ実施回数が増加する見込みであるため補正をお願いするものです。委員10名について、当初予算では年4回を計画していましたが、年10回を見込み、その差の6回分について、報酬、費用弁償についてお願いをするものです。
吉田
このたび委員の一新が決まって、これまでの方たちは自発的にお辞めになる形と伺っていましたが、当初予算措置された部分から今回お辞めになる方たちの分は一旦引いて、新しい10名の方にまた新たに報酬をお支払いしていくことになっていくのでしょうか。払ったものを返してもらうわけではなくて。例えば、臨時会などのとき、急遽開いたために全員集まれなかったなど今後もあり得ると思いますが、全て回数に応じて支払うということでしょうか。
学校教育課長
回数に応じてとなっています。令和6年度、既に4月23日、7月25日、8月22日の3回実施していますが、その後、月1回の開催が必要だと見込みまして、残りの分、補正でお願いするということです。
吉田
30、31ページ、13款2項1目土地取得費16節公有財産購入費の病院用使用貸借用地取得費です。今企画部長からも御説明あったように、市からもかつて3病院の富谷市移転という際に要望書を出したと。それは本市議会としても決議を行っています。当時、まだ議席に就いていなかった方もいるので確認したいのですが、令和2年第7回定例会、2020年9月29日に、議会全会一致で決議が可決しています。一つとしては、県立がんセンターの市内での存続と、もう一つは医療機能の充実と2つの内容でした。これは多分市長と同じだと思いますが、これに対して本市議会として全力を傾注して取り組むことを表明すると全会一致で可決されています。どうも今のこの状況で、全力を傾注するということについて、まず、県立がんセンターに焦点を当てますが、がんセンターが県立ではなくなると、県立がんセンターが閉院されると、まずこの部分、機能云々ではなくて、県立がんセンターが閉院されるということについての事実確認をお願いします。
企画部長
今回の基本合意においては、県立がんセンターと日本赤十字社の仙台赤十字病院を統合した上で、運営主体を日本赤十字社が担うということで基本合意がされていますので、基本的にはがんセンターそのものが残るというものではないと認識しています。
吉田
県立がんセンターの市内存続はあり得ないと、市内どころか県内から消えてしまうということが、このことからも、まずは確実にこれから起こってくるわけですね。そして、機能の部分で見たときに、これが一部新しい病院に引き継がれないおそれがあるということで、村井知事からは、東北大学病院に引き継いでもらえるように交渉しているということでしたが、それを、機能が存続すると、存置すると捉えるのは早いのではないかと。まだ今の段階では何もそれを担保するものはありません。もし本当にそれが実現するのであれば、基本合意の中にも東北大学病院が入っていなければおかしいわけです。東北大学病院も含めての再編ということであればまだ納得はできますが、基本合意に入っていない東北大学病院に県立がんセンターの機能の一部を移すというのは、実現できるかどうかは非常に不安定だと考えていますが、そうした部分についての新しい情報をどのように把握されているのかお伺いします。
企画部長
県立がんセンター機能のうちのどの部分が残ってどの部分が東北大学病院に引継ぎをされるというところについて、明確な内容については存じ上げていません。
ただ、県立がんセンターの機能の部分については、先ほど来、話題となっています研究機能のほか診療機能等についても、そのマインドについては引き継ぐという発言もされているということです。具体的にどういった機能が残って、どういった機能が移管をされるのかについては、今後の協議の推移を見ていかなければはっきりとしないところはあるかと思います。ただ、少なくとも診療機能については、統合される新病院に引き継がれることは確実ではないのかなと捉えています。
吉田
同じく13款2項1目土地取得費について伺います。先ほどの御答弁だと、県立がんセンターの機能が、何が残って何が残らないのかがまだ分からない。分からないということで、ここで土地の取得を決めてしまえば、あとはどのような結果になろうとそのまま進んでいくことは明らかです。この議会の決議、私は重いと思います。全員賛成したわけです。そのときにいなかった方は別ですけど、その場で一緒に起立をした方たちにとっては非常に重いものだと。全力を傾注して県立がんセンターの市内存続に向けて取り組んでいくと、全力で取り組みますと言っているんですね。全力で取り組みますといったことだったら、今全力でやるべきことは、県立がんセンターもしっかり残してもらう、そして、病院ももう一つ本市に来てもらうと、これが私たちが全力でやるべきことだと思うのです。それが、県立がんセンターはなくなるわ、新しい病院の規模は小さくなるわで、何も一つの全力を尽くしたことになりません。これから市民に対して全力でやりますと言ったって、またうそ言っているなと思われるだけですよ。市長からどういう要望書があったのか、その内容を見たことはありませんが、少なくとも県立がんセンターのどのぐらい機能が残るか、そして、あるいはもう一つ、県立がんセンターは今、都道府県がん診療連携拠点病院に指定されています。こちらも基本合意には、その連携拠点病院の機能を東北大学と補完、連携を進めと書いていますが、せっかく県内に2つある連携拠点病院の1つを日本赤十字社で新しい病院で担えるのですか。担えないで1つになってしまうおそれのほうが非常に高いと思いますが、そういうことを何も分からないまま土地を購入するということに対して、その正当性というのはあるのでしょうか。その部分をどう捉えていらっしゃるのかお伺いします。
企画部長
先ほど申し上げたように、県立がんセンターの機能のどの部分が存置をされて、どの部分が移管をされるのかについては、現時点ではっきりとした情報をつかんでいるわけではありません。ただ、少なくとも、県立がんセンターの診療機能については、引き続き、統合される新病院の中でも引継ぎをされると認識をしています。そういった意味では、当初要望していました県立がんセンター機能の存置という部分について、直接市民が受益を受ける診療の部分は確保されるのではないのかと捉えています。
吉田
県立がんセンターの診療が新しい病院に引き継がれるのはそのとおりだと思いますが、ただ、今の県立がんセンターは、希少がん、難治がんという主要がんよりもっと珍しいがんの治療、研究をしていると。実際に何を希少がん、難治がんというかという定義ははっきりしていませんが、一つの見方からいって、五大がんを除いた部分として捉えたときに、大体県立がんセンターでは5割程度、そうした難治がん、希少がんを治療しているといったことも県議会である議員から紹介がありました。ただ、今回の基本合意の中には難治がん、希少がんの部分について引き継がれるということははっきり明記していませんので、企画部長がおっしゃるような県立がんセンターの機能が診療科として残るというのは楽観的な考え方ではないのかなと。もっとはっきりと、少なくとも基本合意の次の基本計画ぐらいまで、これが公表されるまでは、まだ私たちはもっとよりよいものにしていくために要望を続けていくべきではないかと思いますが、お考えはいかがでしょうか。
企画部長
要望ということについて申し上げますと、まず、県立がんセンター機能の存置と医療機能の充実について、また、機能の全てが残るのかどうかというところははっきりしないところはありますが、少なくとも医療機能の充実については拡充されるものと考えています。病床数自体が2つを合わせたものから少なくなることについては、病院の統合をそもそも議論する病院の在り方の検討会議の中で議論されている内容でありますので、ここの部分については、そういうことを前提として3病院あるいは4病院の移転が進められているものと捉えています。
吉田
同じく30、31ページ、13款2項1目土地取得費について伺います。県立がんセンターの機能の部分で見ても、市内の存置は100%できていないということは先ほどの企画部長の答弁からも明らかになりました。
もう一つ、私たちが市議会として全力を傾注して取り組むことを表明した医療機能の充実。確かに本市に総合病院が来ることは私も大歓迎です。もちろんです。それは安心感増します。いざというときに近くなると運んでもらえるし。遠くなってしまう方はそういう思いがありますので、そういう人がいないようになるべくしたいのですが、どこかに置かなければいけない。そういうことでどうしても起きてしまうのは理解します。ただ、もう少し広い視野で見たときに、この間の一般質問の市長の答弁の中で、何もかも全部の市に置かなければいけないのかみたいな発言があったような記憶をしていまして、具体的に何のことだったかは思い出せないのですが、警察署も本市にはないと。ただ大事なのは、地域の治安が維持されて、そして、いざというときにすぐに駆けつけてもらえる体制が確保されることであって、近いところに警察署があるかないかではないと思うんですよ。近くにあったとしても機能していないのでは意味がないですし、使えないのでは意味がない。病院も同じで、大事なのは、病院にアクセスできる環境ではないかと思います。本市にもし今の400床というベッド数で新しい病院が来たとして、もちろん仙台市からは二次救急医療の補助金は取らないと言っていますが、仙台市の患者さんも受け入れなければいけない。そこがいっぱいだったら本市の患者は、結局はまた遠くのところに運ばれなければいけないということになってしまって、必ず近い病院に運ばれるという確証はないわけですよ。だから、そういう意味で、これを医療機能の充実とすなわちすぐにつなげてしまうというのは、見方が一方的なのではないか、偏っているのではないかなという印象があります。仙台市では今度、仙台市立病院までの搬送時間、今、篭ノ瀬交差点、それから鹿の又交差点の立体工事がこれから始まっていきますが、工事が完了すれば、名取市方面からのアクセスが大体13分ほど短縮されると仙台市では見込みを立てています。あと本市は消防の人員も増やしました。ずっと増やしてくれなかったのを、令和6年11名新たに採用して、そして、救急車が手倉田出張所に配備されるということも決まっています。そうやってソフトの部分でも一生懸命取り組んできているわけですから、このことによって本当に医療が今まで受けられた以上の拡大になっているかどうかというところが、今の御説明だとどうも一方的なのですが、それ以上に県からもっと情報はないのでしょうか。全く何も情報がないので、これが本当に機能充実なのか、縮小なのかが見えない不安、そういう状況です。少なくとも今の情報量では簡単に判断はできない。何せ1回決めてしまったら後戻りできなくなりますから。だから、もっと県のほうの情報をしっかり取ってもらいたいと思うのですが、現時点での最新の情報をお伺いしたいと思います。
企画部長
現時点での最新の情報ですと、基本合意書に明記されています5つの診療機能が、植松入生に新しく建設をされる病院に入るということかと思います。
医療機能の充実という面でいいますと、少なくとも周産期医療や災害医療といったこれまで市内になかった医療機能が入ることは明記されていますので、少なくとも、規模は別としても、医療機能そのものが充実することについては、基本合意のとおりではないかと考えています。
吉田
ですので、基本合意というのは一番外側の枠の部分でしかなくて、これからもっと具体的な基本計画が恐らく今策定されている途中だと思います。そういうものまで見ないと、これを1回認めてしまえば、今度計画の中でこんなはずではなかったのにといったことが起きたときに、取り返しのつかないことになってしまうのではないかということを一番懸念するのです。先ほど今回の土地は年間で大体8%ほど値上がり傾向だということで、早いほうがいいという御説明でしたが、もう少し、基本計画が少なくとも示されるまで、そちらのほうが後々いいと思います。なぜそこまでしっかり見極めようとしないでこんなに焦っているのか。そこが理解できないのですが、御説明お願いします。
企画部長
まず、先ほど来申し上げていますように、市で3病院の誘致の条件として提案していることですので、立地を決めていただいたのであれば、市の責務として土地は用意をしなければならないと思っています。
なぜ急ぐのかということですが、先ほど担当の病院立地環境整備推進室長が申し上げましたように、市内の地価が非常に上がっている傾向がありまして、さきの土地の鑑定評価においても直近では7.9%の上昇となっています。これが1年、2年と取得が遅れますと、当然その取得に要する費用が毎年1億5,000万円程度ずつ上がっていくことになりまして、取得に要する費用も多額に上っていくことも実際出てくるかと思います。また、その間、地権者のNTT東日本様も土地の有効活用ができない状況で迷惑をおかけすることになります。基本合意を受けて市内に立地することが決定されましたので、早急に土地を確保するほうが市にとっても得策であると考えています。
吉田
30、31ページ、13款2項1目土地取得費についてです。令和6年6月17日に一般質問した際に最後に指摘させていただいたのですが、この土地の買上げをもってこのことについては後戻りができなくなる一つの大きな通過点だと思います。実際に病院が来ることによって、二次救急医療の運営費補助やそれ以外の道路の改良工事などいろいろな部分でお金がかかるということ、そしてまた将来的に仮に病院が赤字経営になったときに、これだけいろいろな機能をつければつけるほど病院の経営は大変になっていくでしょうから、公立であれば税金投入できますが、民間でもし賄えなければ最悪撤退しかないので、そうならないためには赤字補填もあり得ると思いますが、どの範囲まで本市としてするつもりなのかをある程度示してもらいたいと6月の時点で申し上げていました。その点に関しての検討はあったのかどうかお伺いします。
企画部長
その際にもお答えを申し上げていると思いますが、現在、総合南東北病院に2市2町協調して病院の運営補助を行っています。これは国の特別交付税制度の枠組みを使って補助をしているわけですが、新しくできる病院から支援についての要請があれば、そういった枠組みの中で支援については考えていきたいと思っています。
吉田
二次救急に限らず、道路の改良、それに伴っての土地のまた新たな買上げなども含めての総額としてどのぐらいの規模になっていくのかがとても気になるところですが、その点の検討はいかがでしょうか。
企画部長
今後どういった環境整備が必要になってくるかについては、今まさに全庁的な体制の中でどういったことが考えられるのかの検討に着手したところです。いずれ病院周辺については、病院に限らず、東側の市道関下植松線の整備と、これとは別にまた進められる部分もあるかと思いますが、例えば国道関係の右折、左折レーンなどについては、国にお願いをしていくことも出てくるかと思います。ただ、具体的な病院の配置計画が決まっていませんので、どこから進入をするのかというようなことについて、まだ何も検討する材料がないということもあります。そういったことが決まってくるのに従って、市としてどこまで対応していくべきなのか、周辺にお住まいの方の生活環境の保全も含めて検討していきたいと考えていますが、現時点で具体的な金額等の想定はありません。
財務常任委員会
(議案第88号 令和5年度名取市歳入歳出決算の認定)
吉田
7、8ページ、1款市税全体でお伺いいたします。市税の納税の対象となる要件があると思いますが、最近やはり国外から入ってきて経済活動を行う外国人の方が増えていて、令和5年度内で110人増えたと成果表に載っています。そういった外国人による市税の件数や額は捉えているのかどうかお伺いします。
税務課長
特には捉えていないところです。
吉田
外国人の方が働いていたとしても、例えばその企業で源泉徴収する場合は1つの固まりとして納付されるので、件数や額を押さえるのは現状では難しいということになるのでしょうか。
税務課長
御指摘のとおりです。
吉田
7、8ページの1款2項1目固定資産税です。地方税法第348条第2項第9号に基づいて非課税とされている学校法人について、令和5年度決算時点の法人数と筆数、また、学校法人が所有する固定資産で課税対象となっているものについても法人数と件数をお伺いします。
税務課長
非課税適用法人の法人数は7法人で、件数としては54筆です。課税となっている学校法人については捉えていないところです。
吉田
令和5年12月の一般質問の際にはあると伺ったのですが、捉えていない理由は何でしょうか。令和5年度決算時点では課税されている学校法人はなくなったということでしょうか。
税務課長
課税対象となった学校法人は令和5年度では1件でした。
吉田
7、8ページ、1款2項1目固定資産税です。課税されている学校法人は1件という御答弁でしたが、この1件については、土地や建物全てか、それとも、例えば学校内に設置されている商業用スペースの部分だけなど、区分を区切った形での課税か、詳細をお伺いいたします。
税務課長
敷地の詳細な利用状況は捉えていませんが、一部を賃貸に使用しているため課税対象となっています。
吉田
賃貸とは、学校法人として貸出しをして、それが収入源になっているという経済活動ということになるのでしょうか。となると、例えば学校内の自動販売機を設置しているスペースだけを貸しているといった形なのか、1件の面積はどのぐらいですか。
税務課長
詳しい面積は把握していませんが、理由としては賃貸アパートの経営のために課税されている状況です。
吉田
7、8ページ、1款2項1目固定資産税、学校法人の非課税措置についてです。これはさきに一般質問で取り上げた際に、非課税の適用について疑義が生じた場合は聞き取りや実地調査を行うと答弁がありました。大体どこか分かると思いますが、令和5年度中、令和6年度分の賦課期日である令和6年1月1日の時点でも結構ですが、常態的に学校教育活動が行われていないのではないかという疑義がある件数についてお伺いいたします。
税務課長
令和5年12月定例会において一般質問があったことから、それを踏まえて確認が必要となる学校法人はあるものと捉えております。
吉田
当然だと思います。そのとおりだと思います。非常に問題があると思います。令和6年度に入ってからのことではなく、令和5年度中に12月定例会で一般質問を行い、直近の賦課期日は令和6年1月1日ですが、その時点ではなかなか決定までに至らないとは理解できていましたが、1月から3月までの間、次年度に向けて聞き取りや現地調査の進め方、スケジュール等の検討は行われたのか、もし行っていればその概要をお伺いいたします。
税務課長
令和5年度内に現地の確認は実施しております。また、聞き取り確認等については、今後のこととして内部で検討を進めているところです。
吉田
7、8ページ、1款2項1目固定資産税です。保留事項の御答弁をいただきました。周辺住民からの情報などを聞くと、まず当該固定資産は学校教育に使われている形跡が見られないということです。税務課長の答弁で令和5年度中にも現地調査を行ったという御説明でしたが、回数、そしてその現地調査でどのような状況を把握したかお伺いいたします。
税務課長
今の御質疑については税務調査の範囲になりますので、個別の案件ということでお答えは差し控えさせていただきます。
吉田
税務調査が既に始まっているということですか。ではいつから始まったのか。答弁保留で随分長い時間がかかりましたが、だったらもう少し早く税務調査が行われていると説明があってしかるべきではないかと思います。今、なぜ急に税務調査という言葉が出てきたのか理解できません。これは、現在の措置が適正か不適当か、速やかに決定しなければいけない。そうしなければ、まさに違法、不当な、公金の賦課徴収を怠る事実と言われかねないですし、そのようにもう見えてきていますので、速やかに調査を行わなければいけないと思うのですが、まず今の税務調査の根拠についてお伺いいたします。
総務部長
当該学校法人の施設に対する調査というか確認については、令和5年のうちから始めています。突然税務調査と出てきたという話ですが、既に始まっていますので、どこまで進んでいるのかといった点については、申し訳ありませんが、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
吉田
9、10ページ、1款6項1目入湯税です。入湯税特別徴収の手引きをまとめて対象施設間で格差が生じないように統一化を図ったということですが、令和5年度中でこの手引が反映されたのは何か月分になるのでしょうか。
税務課長
入湯税特別徴収の手引きについては、令和5年10月に特別徴収納税義務者である各事業者をお伺いして、適切に徴収するよう説明した上で配付しておりますが、もとより各事業者は制度の趣旨を理解した上で適正に申告納付しているものと捉えております。
月数については、10月分ということで11月以降の申告納付なので5か月分と捉えております。
吉田
取扱いの考え方について、手引を作成する以前の事業者にある程度お任せしていた状況から市でどのような部分を統一したのか、大まかでいいので手引の概要をお伺いしたいと思います。
税務課長
手引の内容ですが、制度の概要、また課税対象として入湯しているかどうかの考え方や申告書等の記載例、関係法令などについてまとめました。
吉田
9、10ページでもう一度1款6項1目入湯税についてです。収入済額も同様ですが、令和4年度の調定額と比較して多少増額になっていて、手引を5か月間反映させたにしては変化は大きくないのかと思うのです。施設ごとの金額はなかなかお示しできないことは理解していますが、その中で増減が施設ごとにあると思うので、手引作成後に大きく増額あるいは減額になった施設はあったのでしょうか。
税務課長
手引配付後に大きな増減があった施設は令和5年度ではありませんでした。
吉田
手引を作成して説明に回ったのは税務課の仕事として評価したいと思いますが、やはりどのぐらい反映したかという実際の影響のほうが重要だと思うのです。不公平感がないように1回の入湯の数え方といいますか、ホテルの大浴場を利用すれば日帰りではなく宿泊と捉えるはずですが、宿泊しても使わない人がいるので、そこで考え方に差が出てしまうのだと思います。手引では1回分として入湯税を課税する基準はどのように示されているのですか。
税務課長
課税対象者については、あくまで入湯行為をした方ということで手引には明記しています。
吉田
19、20ページ、11款1項1目地方交付税の中の特別交付税でお伺いします。輪番制の事業ということで本市から総合南東北病院に対して二次救急医療運営補助金を支出し、その財源となっているのがこの交付税だと思うのですが、交付税中の補助金分の金額とその算定の根拠についてお伺いいたします。
財政課長
二次救急医療運営補助金に対する特別交付税の措置の内容です。令和5年度では、二次救急医療運営補助金として本市では1,676万2,000円を支出しております。2市2町で令和3年10月から令和4年9月までの受診者数の実績で案分した結果、本市については27.914%でこの金額になっております。特別交付税措置については、この補助金1,676万2,000円の40%として670万5,000円が措置されています。
吉田
その根拠というところで、名取市公的病院等による二次救急医療運営補助金交付要綱の第4条第2項には、特別交付税に関する省令第3条第1項第3号の表第52号2の規定により算出した額を上限とありますが、岩沼市と亘理町の交付要綱では同じ省令の第3条第1項第3号イの表第43号となっていて本市とは違うので、本市の算定の根拠法令が間違っていると思うのですが、いかがでしょうか。
保健センター所長
根拠については岩沼市、亘理町と同一で、本市の要綱の修正が遅れていましたので現在修正をかけているところです。大変申し訳ありません。
吉田
29、30ページ、15款2項1目総務費国庫補助金の2節デジタル田園都市国家構想推進交付金についてです。説明資料では主に3つの項目ということで、新公共交通体系となとりスーパーキッズ育成プロジェクト、そして名取市地域DX推進事業とありますが、それぞれの金額をお伺いいたします。
政策企画課長
デジタル田園都市国家構想推進交付金を充当している事業の内訳です。名取市地域公共交通DX導入事業については、調定額が3,429万1,260円、収入済額も同額です。なとりスーパーキッズ育成プロジェクトは、調定額が832万4,380円、収入済額も同額です。名取市地域DX推進事業は、調定額が3,301万2,172円、収入済額が2,462万4,672円、差引き、収入未済額、繰越分になりますが、838万7,500円となっております。
吉田
繰越しについては全て名取市地域DX推進事業の分だと思いますが、どういった内容で繰越しになったのでしょうか。
政策企画課長
繰越しの内容については、名取市地域DX推進事業において実施することとしているナトぽた及びなとりコインの2つのシステムについて、ログインIDを共通化し、シングルサインオンの実現に向けたシステム構築について令和6年度に繰越しをしております。
吉田
31、32ページ、15款2項4目土木費国庫補助金の3節住宅費については、補足説明では復興公営住宅の東日本大震災特別家賃低減事業及び災害公営住宅家賃低廉化事業に対する補助金ということですが、今回措置された補助金全額を市営住宅建設基金に積み立てるという理解でよろしいでしょうか。
財政課長
積立金については、事項別明細書209、210ページの歳出8款6項2目市営住宅建設基金費の9億4,822万9,000円となっております。災害公営住宅家賃低廉化事業と東日本大震災特別家賃低減事業の分については、こちらに積立てをして、必要なときに基金から繰入れをしている状況です。
吉田
補助金については積立金のうちの何分の幾つというルールがあると思いますが、そのあたりの算定方法についてお聞きしたいと思います。
財政課長
災害公営住宅家賃低廉化事業と東日本大震災特別家賃低減事業の補助金については、一度積み立てることになるわけですが、年度によって8分の7や8分の6など補助率が変わりますので、収入としては差異が出てくることになります。
吉田
49、50ページ、18款1項1目一般寄附金です。内訳については補足説明の資料に書かれていますし、具体的に企業版ふるさと納税が280万円と総括質疑で御答弁いただきました。この企業版ふるさと納税280万円が充てられた事業の内訳をお伺いいたします。
財政課長
企業版ふるさと納税については、収入280万円のうち180万円を令和5年度に充当しております。内訳としては、なとりこどもファンド事業に140万円、なとりスーパーキッズ育成事業に40万円となっております。
吉田
一般のふるさと納税でも同様だと思いますが、企業版ふるさと納税を納める企業はこのような使途に使ってほしいと何項目かの中から指定するわけで、積み立てられることについて果たして想定していたのかどうか少し疑問があるわけです。この140万円、40万円という内訳ですが、今回寄附した企業については、どのような効果を市民のために見込んでというか、企業版ふるさと納税を募る際に、計画等を策定して、そこに幾つか項目があると思うのですが、どの項目に対しての御寄附だったのかお伺いします。
政策企画課長
本市で企業版ふるさと納税を募集する際には、基本的には地方創生総合戦略の趣旨にのっとった事業ということである程度広く募集しております。ただ、実際に企業とお話をする際には、市から例えばなとりスーパーキッズ育成事業やなとりこどもファンド事業など事業を例示して個別に打合せを行って、企業に寄附金の使途を選んでいただいています。企業によっては、当該年度に予算化していない事業でも、例えば実施計画に載っていて、次の年度に実施する予定の事業に対して充てることを希望される場合もあって、その都度お話を聞きながら進めているところです。
吉田
49、50ページ、19款2項1目財政調整基金繰入金です。これも総括質疑でお伺いして、主な内訳として3項目お示しいただきました。その中の震災復興特別交付税の国への返還に充てられたのが令和5年12月補正で計上された2億8,555万7,000円かと思います。これが、これまで財政調整基金の中で運用してきた、通常分ではなく震災分に当たるのかどうかですが、まず令和5年度末時点での財政調整基金の通常分と震災分の内訳をお伺いいたします。
財政課長
繰入金の残高については、通常分が31億2,338万1,000円、震災分が8億9,698万1,000円となっております。
吉田
今回返還に充てられた分は震災分からでしょうか、それとも通常分からでしょうか。
財政課長
国への返還金2億8,555万7,000円については震災分で整理している部分から取り崩しており、先ほど申し上げたのは取崩し後の金額となっております。
吉田
49、50ページ、19款2項1目財政調整基金繰入金でお伺いいたします。内訳として、子ども医療費の助成の増額で今回繰入れになったと総括質疑で御説明がありました。総括質疑ではもう一つ、予算の流用の質疑でも子ども医療費が説明に出てきました。約3,500万円を流用して、その後、令和5年度第11号補正で子ども医療費の増額が認められたので、一旦借りていたような扱いの分を流用し直して戻したということですが、この財政調整基金の繰入金が第11号補正の財源と理解してよろしいですか。
財政課長
子ども医療費助成に係る流用については、支払い時期のタイミングに応じて、不足が生じる場合に一度流用している格好です。
財政調整基金繰入金の増加の主な要因として子ども医療費助成と説明していますが、令和4年10月から子ども医療費助成の拡大を行っております。令和4年度は半年分、令和5年度については通年分、その拡大の影響を受け、医療費助成の総額が多くなったため、一般財源ベースとして約1億5,000万円程度令和4年度より増えている状況で、それに伴って財政調整基金の繰入れを行ったという経緯です。
吉田
流用については財政調整基金繰入金には全く関わりがないのですか。そうすると、流用は歳入ではないので質疑できないのかもしれませんが、あくまでも名取市予算の編成及び執行に関する規則の第26条の柱書きに次の節の金額は流用することはできないという原則が示されて、その中に扶助費があるのですが、これはまさに扶助費が流用されています。流用ではなく、第11号補正ということは年度の大分後のほうの補正ですので、もう少し早い段階で措置しておくべきだったのではないかと思いますが、なぜ遅れてしまったのでしょうか。
財政課長
流用するタイミングですが、実際の所要額と不足額を見込んで行っております。補正予算を組むタイミングの前に予算の不足が見込まれたものですから、一度ほかの科目から流用しました。
扶助費については、一般的には禁止科目とされていますが、内部決裁を踏まえて、款項目節の項の間であれば流用が可能という取扱いになっていますので、その制度にのっとって流用しております。逆に流用元のほうが不足しますので、総額の不足額については、補正ができるタイミングで補正予算を組んで戻したということになっております。
財務常任委員会第1分科会
(議案第88号 令和5年度名取市歳入歳出決算の認定)
吉田
市政の成果134ページ、常備消防費、消防事務の1 予防活動の(2)危険物施設、防火対象物の査察指導についてです。立入検査実施状況の防火対象物数が令和4年度に比べると結構な増になっていますが、この状況の査察は施設ごとに何年に一度というサイクルがあって、その中で令和5年度は814件ということでよろしいでしょうか。
消防署指導係長
名取市予防査察規程の中で査察対象物は1種と2種に分かれており、2種については2年に1回以上実施すると定められています。そのため、件数の増加が認められたということになります。
吉田
消防職員の数がまだ少ない中で、これだけの件数を1年間で回るのは結構大変だと思いますが、この査察というのは、何人で1グループとなって1日何件とか、どういう体制を組んで行ったのかお伺いします。
消防署指導係長
一般的には2名で実施します。1名で実施するところもありますが、そこは簡易にできるような査察ということです。また、大規模な大型店舗などは係員の人数も増やして、5名から10名程度で実施する場合もあります。
吉田
市政の成果134ページの常備消防費でお伺いします。令和5年度全国消防救助技術大会への出場の状況と成績についてお伺いいたします。
消防署救急救助係長
宮城県消防救助技術指導会という予選があり、令和5年度は、ロープブリッジ救出、はしご登はん、ほふく救出、あとは個人競技のロープブリッジ渡過、そういったもので出ておりまして、はしご登はんで、県大会を1位で通過して全国大会に進出しております。全国の結果としては、規定タイムはクリアしましたが、入賞はできなかったという状況でした。
吉田
規定タイムに入ったということで、成績としては大変優秀だと思います。こうした結果を受けて、訓練の今後の在り方などへの活用はどのように行われたのかお伺いします。
消防署救急救助係長
結果を踏まえ、はしごを渡ったりロープを渡過したり、そういったことを現場に生かせるように、ほかの隊員にも周知するということで、毎月とか毎週とか、現場の訓練を継続しております。
吉田
市政の成果138ページ、非常備消防費、消防団運営事業の2 訓練・行事の実施の中で、令和5年度は消防操法指導会の項目が見当たらないのですが、これは実施されなかったということなのか、それとも他の行事の中に組み込まれていたのか、そのあたりをお伺いします。
消防本部総務課総務係長
委員御質疑の操法指導会に関しては、団員から負担になっているという意見があったことから、消防団員の処遇改善を図るために、令和5年度から競技性をなくして講習会形式として運営の方法を変更したものです。なくしたのではなく、運営方法を変更したということです。
吉田
もともと消防団で操法指導会が負担になっているという声が全国的に上がっていることは認識していました。令和5年度から競技ではなくて講習会形式になったということですと、この令和5年10月8日に行われた応用小型ポンプ操法講習会ということですか。では、これはどういう講習だったのか、具体的な内容をお伺いします。
警防課警防係長
応用小型ポンプ操法講習会ですが、名取市消防団に配備している資機材を有効活用した操法として新たに改良して実施したところです。
改良した点については、無反動管鎗という反動を少なくするための管鎗がありますが、それを名取市消防団独自で配備しているのと、あとは二又分水器といって、それを使うことによってホース1本から2栓に分けることができますので、消防団員の疲労や負担の軽減、あとは有効消火範囲を広げることができます。
もう1点、消防団に簡易無線機を支給しております。今までの消防操法は、隊長が現場から放水始めと指示したら、隊員が走ってポンプのところまで戻って、放水始めという伝令を行っていましたが、それを無線で行うことにより、早期の消火活動の実施と疲労軽減につながります。そのように新たに名取市消防団に即した操法に改良して令和5年度から実施したところです。
吉田
市政の成果134ページからの常備消防費の中でお伺いします。以前はホームページの運営費がどこかに書かれていたような気がするのですが見当たらないので、ページ数が分からないのですが、令和5年度、市のホームページが大幅リニューアルされて、以前の非常に手作り感のあった消防のホームページが、市のホームページに一体化されました。そのときにいろいろ聞き取りをされたということは総括質疑で答弁があったのですが、実際、消防本部のほうから、新しくこういう機能をつけてもらいたいとか、何か要望された項目はあったのでしょうか。
警防課通信指令係長
名取市消防本部のホームページが市のホームページに移ったときに、火災件数等の件数の表示を週に1回更新するということで、そこの部分は付け加えさせていただきました。
吉田
そうした消防ホームページの部分の情報を更新しますよね。情報の更新は、市役所のほうはもちろん市の広報の担当がすると思いますが、消防本部のホームページの中の情報は消防のほうで更新ができるような仕様になっていますか。
警防課通信指令係長
今度の新しいシステムは、各職員のパソコンからも更新できることになっていますので、令和6年4月から各係からの発信という形に見直しました。
吉田
市政の成果139ページ、非常備消防費、消防団運営事業の7 団体負担金です。令和4年度までは宮城県消防協会名取・亘理地区支部だけが記載されていましたが、今回、宮城県消防協会と名取・亘理地区支部と2つに分けて記載されています。全体の金額としては多少減っているものの大きな変化はないのですが、2つに分けてここに記載するようになった何か特別な理由があるのでしょうか。
消防本部総務課総務係長
団体負担金について、宮城県消防協会と名取・亘理地区支部の2つに分けて令和5年度から記載するようになった理由としては、令和5年度から負担金の納め方に変更があったということです。以前は、宮城県消防協会という大本の団体があって、その下部組織として宮城県消防協会名取・亘理地区支部という団体が存在していました。名取市消防団、本市はその名取・亘理地区支部に属しているのですが、そこに地区支部分の負担金と宮城県消防協会分の負担金をお支払いするということで、2つの負担金を地区支部を経由してお支払いしていました。そういったことから、令和4年度市政の成果では宮城県消防協会名取・亘理地区支部負担金のみの記載でよかったのですが、令和5年度から別々に負担金をお支払いするという流れに変わっておりますので、その流れに沿った形で、今回、市政の成果への記載も変更したものです。
吉田
その金額について、どういう取決めでこういう金額になっているのか、そして、その額の決め方についても令和4年度までとの違いというか、変更した部分はないのかお伺いいたします。
消防本部総務課総務係長
団体負担金の金額の内訳ですが、まず、宮城県消防協会負担金に関しても、名取・亘理地区支部の負担金に関しても、基本的には、まず会員数と呼ばれる団員数と消防本部の職員数を基礎数値とします。さらに市内の世帯数も基礎数値とします。さらには、宮城県消防協会と宮城県消防協会名取・亘理地区支部で算定された平等割も示されて、そういった形で、毎年、負担金の請求が来ているものです。
吉田
市政の成果140ページ、消防施設費、消防施設整備事業の2 消防施設設備の整備等の(3)小型動力ポンプ付積載車で、3台とあります。これはこの3台の更新ということだと思いますが、その内容についてお伺いいたします。
警防課警防係長
更新した車両3台については、増田分団第1部、館腰分団第2部、愛島分団第4部の車両となっております。
吉田
それは耐用年数が来てしまったとか、何年使用した車両を更新したかとか、そういうことを聞きたかったのですが。それで、令和4年度のメモで残り4台と書いてあったので、ここで3台ということは、更新されていない車両が残り1台ということになるかと思いますが、それも併せてお伺いします。
警防課警防係長
まず、増田分団第1部に関しては24年間使用した車両です。続いて館腰分団第2部についてですが、同じく24年間使用しております。愛島分団第4部については25年使用しております。
委員からお話のあった4台のうち3台を更新しておりますので、残りの1台は令和6年度に増田分団第3部の車両を更新する予定となっております。この車両については25年使用中のものです。
吉田
市政の成果143ページの水防費、水防事務の2 水防用資機材の整備、(1)カゴ台車等とありますが、こちらの内容についてお伺いいたします。
警防課警防係長
水防資機材を運搬しやすいように大量の資機材を運ぶためのカゴ台車を購入しております。ほかには、水防倉庫に配備しているチェーンソーのオイル交換のためのツーサイクルオイル等を購入しております。
吉田
水防倉庫と今おっしゃいましたが、その倉庫はどちらにあるのですか。
警防課警防係長
本市の消防団は6分団ありまして、6分団に1か所ずつ水防倉庫があります。代表的なものですと高舘の水防倉庫でして、高舘の河川敷のグラウンドの堤防を挟んで南側にあります。そこに水防に関する資機材等を収納しているところです。
吉田
事項別明細書71、72ページ、2款総務費全体でお伺いします。総括質疑では消防職員に限って質疑させていただきましたが、総務部の所管ということで、市長部局の職員の育児休業の取得率を、全体と男女別でお伺いします。
総務課長補佐
消防部局を除くということですと、男性については、16名のうち15名が取得しており、率にしますと約94%です。ちなみに、取得しなかった1名については、令和6年3月に子供が生まれており、令和6年度には取得していますので、実質的には100%と捉えております。
女性については、9名中9名取得しており、100%となっております。
吉田
総務部では、教育委員会部局については捉えていませんでしたか。もし分かればお願いします。
総務課長補佐
今、答弁させていただいた中に教育委員会の部分も含まれております。
吉田
事項別明細書71、72ページ、2款総務費全体でお伺いいたします。総括質疑でもお伺いした内部公益通報についてです。件数はゼロで、受理・不受理はなかったということですが、この制度ができてまだそんなに日もたっていないということで、実際、確認すると、内部というくくりの中には、市の職員だけではなく、市から事業を請け負った事業者やその従業員なども含まれていて、例えば入札の不正などがもしあったら、そういうことにも対応できるような制度になっていると思います。そうしたものの周知は令和5年度しっかり進んだと捉えられているかどうかお伺いします。
総務部長
内部公益通報について、どこまでが内部かという話になるかと思いますが、名取市内部公益通報等の処理に関する要綱としては、職員等ということで、地方公務員法に規定される一般職と特別職、あとは市から業務を受託し、また請け負った事業者の従業員であってその業務に従事する者、それから市の施設の管理を行う指定管理者の従業員であって当該施設の管理業務に従事する者、そのほか市の法令遵守を確保する上で必要と認められる者と規定されております。上位法として公益通報者保護法がありまして、そちらのほうで通報できる範囲はかなり限定的にされておりますので、ただいま申し上げたとおりの方々に該当すれば通報できるということです。
吉田
もちろん制度上はそうなっているのは分かるのですが、こういう内部公益通報の制度があるということが本当に知れ渡っているのかなと。そして、その制度に基づいて厳格に運用していけば、通報者の人権というか、その立場、身分も含めて守られなければいけないと思います。そのことなども含めて、本当に通報すべき案件がもしあった際に、ちゅうちょすることなく通報に至るようなものになっているか、そもそもそれが知られているのかどうかをどう捉えているかなのですが、よろしいでしょうか。
総務部長
名取市内部公益通報等の処理に関する要綱については、令和4年6月から施行されており、告示をしているので、周知はしているところです。
通報した者が不利益を被らないようにというのは上位法にもありますし、本市の要綱で申し上げますと第12条、不利益取扱いの禁止として規定されております。
吉田
事項別明細書75、76ページ、2款1項4目財政管理費10節需用費でお伺いします。この需用費には予算書、決算書の印刷業務等も含まれていると思いますが、その印刷の業務委託の仕様の内容についてお伺いします。
財政課財政係長
令和5年度に印刷製本した決算書、令和4年度の決算書の仕様ですが、決算書及び事項別明細書、そして市政の成果3点についての印刷製本に関する物品購入契約締結伺ということで、その仕様については、校正予定回数を2回とすること、ページ番号を付番すること、電子データ、PDFデータも併せて納品すること、確定原稿のページ数が見本の品のページ数と比して全体で3%以上の増減が発生した場合は別途協議可能とすることが、この3点の共通の仕様です。決算書ですが、印刷用原稿は会計課が作成し、紙原稿をお渡しします。事項別明細書も、印刷用原稿は会計課が作成し、紙原稿をお渡しします。市政の成果は、印刷用原稿は財政課が作成し、紙原稿をお渡しします。市政の成果のページ中央及び余白部分を調整することというのが、まず決算書の仕様です。
予算書について、こちらは予算書、予算に関する説明書、そして予算資料の3点です。令和5年度に行った印刷に関する物品購入契約ですが、令和6年度の予算書となります。その条件ということでお示ししているのが、市で作成した原稿を各部数、複写印刷し、冊子として製本する。ただし、以下の点に注意すること。1番、表紙及び裏表紙については厚紙を使用する。2番、ページ番号を付番する。3番、仮製本後、2回程度の校正あり。4番、電子データ、PDFファイルも併せて納品する。5番、確定原稿のページ数が見本の品のページ数と比して全体で3%以上の増減が発生した場合は別途協議可能とするというのが、予算書の仕様です。
吉田
聞き逃したのかもしれないのですが、印刷業務は外部に再委託はできない仕様だったと思います。そういった部分が守られているかどうかについては、令和5年度中、実際に立入り等の確認はされているでしょうか。
財政課契約係長
今回の予算書、決算書の請負業務については、外部委託禁止の仕様は定めておりませんので、現場確認も行っておりません。
吉田
市政の成果9ページ、交通防犯対策費、防犯事業の3 傷病一時支援金とありますが、こちらの内容についてお伺いいたします。
防災安全課交通防犯係長
こちらは名取市犯罪被害者支援条例施行規則に基づいてお支払いしたものです。中身については、犯罪によってけがをされた方に対してお支払いをしたというものです。
吉田
その条例の制定もたしかつい最近でしたよね。早速その支援金が出たということですが、これは1件ということでしょうか。この1件のケースについては、どのタイミングで支援金がその方の手元に渡ったのかをお伺いいたします。
防災安全課交通防犯係長
こちらについては、犯罪被害者の方から申請をいただきます。その後、警察でそちらが間違いなく犯罪被害者であるかどうかの確認作業を終えた後に御本人にお渡しするということですので、通常、数週間というよりは1か月2か月の単位でお時間をいただくような形になっております。
吉田
市政の成果10ページの公共交通対策費、公共交通対策事業の2 委託料、(1)乗合バス等運行委託料の乗合バスなとりん号についてです。令和5年度に大分大きく路線も変わり、もちろん事業者も替わったわけですが、令和4年度の実績と比較すると、乗車人数は大きく増加していると見ていいと思います。令和5年度は年度内を前半と後半の6か月ずつで区切られており、そこだけ見ても、改定後のほうが乗車人数が多少増えているのですが、これはやはり改定の効果と受け止めてよろしいでしょうか。
防災安全課交通防犯係長
主な要因として、朝夕の通勤通学時間帯の乗車人数が増えているということですので、効果があったものと捉えているところです。
吉田
令和5年度末時点で、遅延がよく起きる傾向があった路線をもし把握されていればお伺いいたします。
防災安全課交通防犯係長
主に10分から15分程度遅延しているという部分で捉えているのが、令和5年度においては、まちなか循環線、相互台線、愛島線となっております。
吉田
市政の成果10ページ、公共交通対策費、先ほどと同じ2 委託料の(1)乗合バス等運行委託料で、次はデマンド交通なとりんくるについてお伺いします。令和5年度末時点で登録されている方の数をお伺いします。
防災安全課交通防犯係長
令和5年度末時点での登録者数は2,673人となっております。
吉田
登録の仕方として、インターネットで申し込むとか、運転手の方に申込票を渡すとか、いろいろな方法があったと思いますが、そういった内訳を捉えていればお伺いしたいと思います。
防災安全課交通防犯係長
登録については、紙の登録票を提出いただく方法と、どうしてもそういったことができない方はお電話で、さらに、アプリで登録をしていただくという3つの方法があります。今、登録票と電話を合わせた形で集計をしておりまして、現状、アプリでの登録が54%で、それ以外、登録票がベースになりますが、そちらが46%という状況になっております。
吉田
同じく市政の成果10ページの公共交通対策費のなとりんくるについてです。利用のルールがあって、乗る場所と降りる場所、どこからどこまででもいいというわけではなくて、中心部から東側と西側と大きくエリアを分けているわけですが、その利用の地区別の内訳というのは、この全体の件数の中で何%ずつみたいなものは取っていますか。
防災安全課交通防犯係長
なとりんくるのエリア間の移動の内訳ですが、エリア間移動については出発地点と到着地点がありますので、出発地点ベースでお答えいたします。東エリアを出発した便については2,348件、中心エリアから出発した件数が1,645件、西エリアから出発した件数が2,884件、合計6,877件となっているところです。
吉田
人数との違いというのは、乗り合いだった場合がカウントされないという理解でよろしいですか。
防災安全課交通防犯係長
こちらについては、車が動いた件数として今お答えをいたしましたので、乗車人数とはまた別な件数ということになります。
吉田
事項別明細書75、76ページ、2款1項3目広報費の中で、広報なとりについてお伺いします。先ほどは総務部に予算書、決算書について伺いましたが、広報なとりでは、自社内での印刷ということが令和5年度の契約の中で仕様書に定められていましたか。
なとりの魅力創生課国際交流・広報係長
自社内での印刷ということですが、契約自体、再委託は禁止されているところなので、自社内での制作ということで委託しております。
吉田
制作というか印刷の業務の中で、私は、自社内で行わずに外部に出すことがそんなに悪いことなのかなという疑問も少しあって、あまり意味のないような仕様だったら変更してもいいのではないかと思います。令和5年度、そういう部分での検討はなかったのでしょうか。
なとりの魅力創生課国際交流・広報係長
令和5年度については、そういった検討はありませんでした。
吉田
市政の成果1ページ、企画費の地方創生事業、1 委託料の(2)なとりスーパーキッズ育成事業委託についてです。こちらは、総括質疑で、それぞれ3種類の事業の金額の内訳をお伺いしました。確認すると、選考会経費が195万2,000円、Natori Cupの開催経費が533万3,000円、自転車競技体験会経費が80万円ということでしたが、これを全部合計しても800万円余りで、こちらに書かれている約1,600万円という金額には届いていません。この差額はどういうことになっているのでしょうか。
なとりの魅力創生課魅力創生係長
選考会経費、Natori Cup開催経費、自転車競技体験会経費以外に、育成プログラムの構築経費、マネジメント経費が含まれており、育成プログラム構築経費は330万円、マネジメント経費は495万円となっております。
吉田
なとりスーパーキッズをこれから長年育成していく中で、例えば次の年度に大きな大会があるとか、そういうことを想定しておいて、この令和5年度中に措置された補助金を次の年度に使うということが受託された企業の中で可能な仕様になっているのでしょうか。
なとりの魅力創生課魅力創生係長
認定されたキッズの遠征などと捉えて答弁させていただきますが、遠征に関しても令和6年度の予算の中に入っております。そちらはキッズの成長具合といったところも含めて、どういうものが適切なのかということをコーチ陣とも整理しながら、遠征については検討していきたいと考えております。
吉田
市政の成果1ページ、先ほどと同じ企画費の地方創生事業の1 委託料の(2)なとりスーパーキッズ育成事業委託ですが、私が聞きたかったのは、今回ここで事業者に支払ったお金が、次年度以降に例えば大きな世界大会などがあったときに、そちらに回すことができるかどうかということも含めてだったのです。というのは、育成プログラム構築経費が330万円と先ほど説明がありましたが、330万円かけてつくったにしては、その育成プログラムがきちんと保護者に伝わっていなかったのではないかということで、どういうプログラムを示して、しっかりそれを保護者の方にお伝えできたのかというところをまず1つ確認しておきたいと思いますので、その部分の事実関係についてお伺いします。
なとりの魅力創生課魅力創生係長
育成プログラム構築経費の中身ですが、こちらは、プロライダーやトレーナーなどとプログラムの内容の調整、利用するクラブとの調整などにかかった必要な経費となっております。保護者への説明というところですが、実際に来た児童のスキルなどを見ながら、構築したプログラムにプラスアルファをしたりとか、そういった調整をした上で提供するというところで整理しております。
吉田
育成をするためのコーチの方たちは、恐らく採択した事業者が選定するということになってくると思います。その考え方として、コーチが月に1回、宮城県外、結構遠くから来るというよりは、県内に住んでいるオリンピック経験者などにお願いしたほうが、育成環境としてはよりよいものになるのではないかと思います。コーチを選ぶ際にそういった部分が反映されたのかどうかをお伺いしたいと思います。
なとりの魅力創生課魅力創生係長
地元の方のコーチというところですが、そちらの検討には至っておりません。
吉田
市政の成果2ページ、企画費、地域振興事業の1 報酬の(1)空家等対策協議会委員報酬についてです。総括質疑では管理不全空家等の指定はゼロということでしたが、私が確認している範囲で特定空家等もゼロだと思います。その特定空家等のための審議会が開かれていないと思うのですが、それ以外の区分ごとの令和5年度内での管理不全的な空き家の状況をお伺いします。
なとりの魅力創生課魅力創生係長
管理が適切にされていない空き家ということで、令和5年度、近隣の方の迷惑になっているかどうかという視点で区長と町内会長にアンケート調査を実施し、168件の空き家の報告をいただいています。その168件について全戸調査をし、将来的に特定空家の候補となるものについては11件、迷惑空き家になっているものについては18件となっております。
吉田
特定空家候補は11件あるということで、それも改善した部分があったりとか、そういうことも伺っていますが、大分前から議会としても委員会で現地調査などを頼まれたような、誰がどう見てもこれは特定空家等だというような物件もいまだにそのままという状態です。令和5年度中に特定空家等に指定するための会議を開かなかった理由が何かあるのかなと思って、以前にその会議を傍聴させていただいたときは、時期がまだ来ていないというか、もう少し時期を見てというような発言が委員あるいは事務局からあったような気がします。では、一体いつになったら時期が来たという判断になるのか、それがなぜ令和5年度ではなかったのかをお伺いします。
なとりの魅力創生課魅力創生係長
特定空家等の認定の協議会のテーブルにのらなかった理由ですが、所有者の動きなどがあった場合については、やはり基本的には所有者の責務というところもありますので、所有者のほうで対応いただきたいと思っております。そういったところから、令和5年度については協議会に提出しなかったところです。
吉田
市政の成果2ページ、企画費、地域振興事業の4 委託料の(2)シティプロモーション用番組制作委託でお伺いいたします。まず、このシティプロモーション用の番組の内容、どういう動画になったのか、お伺いします。
なとりの魅力創生課魅力創生係長
こちらのシティプロモーション用番組制作委託については、関西圏において放映している「TOKIO城島 ほのぼの茂」という番組の制作を委託したものとなっております。
吉田
あまり聞いたことのない番組名ですが、それは東北では見ることができないものなのでしょうか。東北の人というよりは、関西から来てもらう人をターゲットにしているということが恐らくあるのでしょうが、誰かが行って番組に出演したのではなく、そうした番組の枠の中でこの動画を放映してもらうというようなものなのですか。
なとりの魅力創生課魅力創生係長
こちらは番組をつくっていただく委託となっておりまして、実際にTOKIOの城島 茂さんが本市に来て、セリの収穫体験とか、かわまちてらす閖上で来場されている方と触れ合ったりとか、そういった名取の魅力を城島さんが自ら体験して、それを番組として放映するという取組となっております。こちらは毎週月曜日に30分ほどの番組として放映しているのですが、3週間放映していただいたところでして、実際にその放映を見てかわまちてらす閖上に来たという声も現地から聞いておりましたので、一定の効果はあったと捉えております。
申し訳ありませんが、こちらでの番組の放映はないところです。
また、城島さんが実際に本市にお越しになったのは令和5年10月2日となっております。
吉田
市政の成果2、3ページ、企画費の情報発信プラットフォーム基盤構築・運用事業の中で、2 委託料の(1)情報発信プラットフォーム基盤構築・運用委託ですが、構築するのに結構な額がかかっています。このプラットフォームそのものは、構築されたことによってDXが推進されたなということで評価をしているところですが、中身の充実度からいうと少し物足りない、あの内容でこの金額は少し大きいのではないかと思うのですが、これは工数とか、そういう部分で何か捉えていますか。この金額の根拠はどういう部分にあるのかお伺いします。
DX推進室長補佐
情報発信プラットフォーム基盤構築・運用委託の委託料、1,758万3,500円となっているところですが、DX推進室としては、工数については把握しておりません。
吉田
本当にDXを進めるとすれば、こういう基盤ができたものを市役所の職員の手で利便性を高めていけるぐらいにまでしていかなければいけないと思います。例えばコンテンツを追加したりということを一々外部に委託したら、そのたびに委託料を取られて、何のためのDXか分からなくなってしまいます。今回のこのプラットフォームについては、庁内で一体どのぐらい変更というか中身の運用を変えていくというか、例えば今アプリケーションにつなぐための項目が幾つか出ていますが、そういうものを庁内で自由に変えたりできるようなシステムになっているのか、それも含めてお伺いします。
DX推進室長補佐
アプリの中身の変更ですが、市役所職員が直接システムを変更することはできないようになっておりまして、全てこちら側の意向を受託業者にお願いして変更している状況です。
吉田
市政の成果3ページ、先ほどの企画費の情報発信プラットフォーム基盤構築・運用事業、2 委託料の(1)情報発信プラットフォーム基盤構築・運用委託について、もう1回確認ですが、今、事業者との契約では、庁内でのシステム変更はできないので、必要が生じたらその都度事業者に依頼をするということだと思います。その際の費用は、この最初の委託料の中に年度分という形で含まれているのか、それともその都度発生するものなのか、契約の在り方についてお伺いします。
DX推進室長補佐
軽微な変更については、費用はかからずに受託事業者で修正していただけますが、大規模なものについては追加で費用が発生するものと認識しております。
吉田
こういう情報ICTというか、デジタル関係のソフトウエアというのは、1回そうやって契約を結ぶと半永久的に同じ事業者にお願いし続けて、しかも変更が必要になったときに、向こうの言い分にほとんど合わせる形でお支払いをしていかなければいけないような関係ががっちり築かれてしまうので、それも考え方としてはどうなのかなと思うところがあります。今、ナトぽたで幾つかのお知らせの仕方、通知の仕方とかがありますが、令和5年度に構築した際に、もう少しこういう機能がついていればよかったなとか、業者とのやり取りの中で、今回のプラットフォームを1,700万円の金額で本当に認めてしまっていいのかなという部分で、もう少し検討はなかったのでしょうか。
DX推進室長補佐
ナトぽたを導入するに至っては、必要な機能を5つほど設定させていただき、それに見合うものとして、プレゼンテーション審査によって事業者を選定したところです。そういったことから、今回初めて導入するシステムでもありますので、今のところは現存のシステムを使いやすいように構築していくのがメインと考えておりまして、新たな機能については今のところ考えていないところです。
吉田
市政の成果12ページ、電算運営費、電子情報化推進事業の5 デジタル化推進費、(1)RPA導入・運用業務です。こちらも総括質疑で御答弁いただきました。確認ですが、宮城県電子自治体推進協議会AI・RPA専門部会で、本市はたしか部会長を務めておられたと思いますが、令和5年度も引き続き部会長としてどのような活動をされたのかお伺いします。
AIシステム推進課AI推進係長
県のAI・RPA専門部会の中では、本市は副部会長という立場で関わらせていただいておりました。令和5年度も、令和4年度に引き続き副部会長として参画しておりました。
令和5年度は、共同利用の参加意向の市町村で協議を重ねて、共同利用するRPAのソフトウエアの選定ですとか運用ルールの策定について協議していたところ、そのあたりのなお継続した議論が必要となったことから、令和5年度末時点での共同利用の導入には至っていない状況になっておりました。
吉田
その検討の中でいろいろな課題が見えてきたと思いますが、令和6年度以降への展望という部分ではどういった手応えがあったのかお伺いします。
AIシステム推進課AI推進係長
市町村ごとでRPAですとかAI、またはOCRなども含め、デジタル技術への取組には少し温度差というか、進み具合、取組具合にも差があることが顕在化してきた部分もありまして、議論がまとまるまでにはまだ幾らか整理が必要な部分が出てきたというところがあります。一方で、共同利用以外にも何かしらRPAの導入・普及に向けての方策がないかというところも、併せて議論を進めていた状況です。
本会議
吉田
本市に整備が計画される新病院の開院時期の延期について緊急質問を行うための動議を提出したいと思いますので、お取り計らいをお願いいたします。
議長
ただいま14番吉田 良議員から「本市に整備が計画される新病院の開院時期の延期について」に係る緊急質問の動議がありました。
お諮りいたします。この動議を議題とすることに賛同する議員の起立を求めます。
起立多数であります。よって、会議規則第15条の規定に定める所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
よって、本動議「本市に整備が計画される新病院の開院時期の延期について」に係る緊急質問についてを直ちに議題とし、採決いたします。
お諮りいたします。本動議のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
起立全員であります。よって、本動議「本市に整備が計画される新病院の開院時期の延期について」に係る緊急質問の動議は可決されました。
休憩をいたします。
再開は追って予鈴でお知らせいたします。
再開いたします。
この際、お諮りいたします。吉田 良議員の緊急質問に同意の上、日程第1の次に追加日程第1とし、発言を許すことに御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。よって、吉田 良議員の緊急質問に同意の上、日程第1の次に追加日程第1とし、発言を許すことに決しました。
緊急質問
吉田
14番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しがありましたので、通告に従って緊急質問を行います。
大項目1 本市に整備が計画される新病院の開院時期の延期についてお伺いいたします。
9月19日、新病院に無償貸与する用地を購入するための19億9,000万円を含む補正予算が可決されたことはまだ記憶に新しいところです。採決では賛否が分かれましたが、それぞれの議員が自らの信念に基づいて表決したことに変わりはありません。また、判断の材料として執行部からの説明によったことも事実であり、執行部は、県から得た情報を基に、議会側からの疑問に対し、できる限り丁寧にかつ誠実に答えるよう努められたことを承知しています。
ところが、補正予算が可決して間もない9月26日、村井知事は県議会9月定例会の代表質問に答える形で、新病院の開院時期が当初の予定から2年ほど遅れる見込みである旨の発言をされました。1週間前の19日の時点で代表質問への答弁は準備されていたことは容易に想像できます。計画の遅れが公表されないまま、本市議会で用地取得費用を可決させられたことは誠に遺憾です。計画の遅れについて、県は本市に知らせていなかったのか、知らせはしたものの、本市の執行部がその事実を議会に説明しなかったのか、いずれにしても非常に残念な対応だと思います。まずは事実を確認したいと思います。
小項目1 宮城県知事が9月26日に県議会で答弁した新病院の開院時期が2年程度遅れる見込みとされたことについて、本市に対する説明の状況を市長にお伺いいたします。
市長
開院が2年延期となったことについては、県議会で代表質問のあった9月26日当日の朝、県から副市長を経由し私に報告があったところです。
吉田
では、9月19日の補正予算の審議の際にはまだ御存じなかったということですね。それでは、確認をさせていただきたいと思います。まず、県知事からの突然のこうした発言、議会での御答弁について、市長として率直にどのような感想をお持ちかお伺いいたします。
市長
開院時期が遅れることにはなりますが、新病院が立地することについては変わりがなく、大変大きな事業であり、しっかりと協議を行っている結果であると受け止めており、やむを得ないと感じております。一方で、周辺環境の整備について、市としてある程度余裕を持って行えることもあるのではないかとも思っております。
吉田
やむを得ないという捉え方についてはそれぞれかと思います。
なぜこれほど重大な事実が予算審議の前に本市へ伝えらなかったのか、そのあたりはどのように捉えていらっしゃるでしょうか。
市長
情報については初めに議会で公表するのが原則であり、4病院の再編については県が主導する事業であることから、議会軽視とならぬよう、県議会へ報告するまでは事前にほかの団体に情報は出せなかったものと捉えております。県議会の代表質問が市の補正審議の後であったこともあり、双方の会期の都合上、このようなタイミングでの公表になったものと捉えております。
吉田
順番として県議会への説明を先に行わなければいけないのは理解できます。一方で、この計画の遅れがもし公表されていれば、本市の補正予算の成立に何かしらの影響が出かねないと恐れてこうした時期になったのではないかと想像されますが、そのようなことではないというお考えでよろしいでしょうか。
市長
先ほど申し上げたとおりです。
吉田
それでは、県から副市長を通して9日26日に市長の下へ延期の事実についてお知らせがあったと。ただ、その時点では県議会の本会議の開議前だったわけですね。県議会の本会議が開かれた後ではなく、その前に市長に情報が来ていたことが分かりました。
では、現時点で県から伝わっている情報のより詳細な内容をお伺いいたします。
企画部長
今回の建設予定の時期については、基本合意の中で、目途として進めるということのほかに、双方協議をして今後決定するとされており、そういったことを受けて3者に東北大学も加えていろいろと協議を行っていると思います。非常に規模が大きく、また官民共同で行う事業で、調整する内容については多岐にわたると思います。改めて慎重に検討をなされた中で、具体的な時期としてそういった協議を踏まえて決定したものと捉えております。
吉田
今回は長くても2年程度の延期という県からの説明ですが、例えば今後10年以内の開院など、県としてもう少し余裕を持たせておけば、急に延期の話が出て市民の不安につながるような事態にならずに済んだのではないかと思います。今回このように2年遅れるということは、またこの先、3年、5年と遅れるようなことになりかねないのではないかと非常に心配です。
このように様々想定すれば、9月19日に予算は成立しましたが、土地の購入については、2年遅れるということで、現時点ではもう少し様子を見たほうがいいのではないかという想定もできると思いますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。
副市長
9月26日、業務開始前に県の担当者から私に連絡がありました。内容は、本日の本会議で本市に建設する統合病院についての代表質問があり、その答弁として知事から2年程度遅れると回答するということでした。私から、遅れる理由は検討に時間を要しているためか、また、その検討の内容に何か問題があるのか県に確認いたしましたが、県はむしろ、しっかりと今検討している。だからより確実に開院のスケジュールが明らかになったと申しておりました。
私はその内容についてしっかり理解をさせていただきました。といいますのは、病院再編事業計画の内容については、これまで市長も答弁させていただいておりますが、やはり我々がコミットすべきものではありません。我々は県が出せる情報についてできるだけ早く情報提供してほしいとこれまでも述べてきましたが、あくまでも県が公表できる範囲の内容について我々は知り得るという状況下にあると理解しております。
市長
土地の取得の時期に関するお尋ねでした。まず、当該土地というかインターチェンジ周辺については、現在、物流機能を中心に土地活用の需要が非常に大きく高まってきている地区で、土地の値段が年々上昇している実態にあります。そのような中で、土地の所有者からは市から相談があれば協力したいということはいただいているものの、2年後それがどうなるか、保証はありません。民民の取引の中で本市より高くいい条件で買い求めたいと言われた場合に、それでも協力してくれるかというところまでは保証はないわけです。今回3者による法的拘束力を持つ基本合意が締結されたこと。それから確実に土地を取得しておくこと。そしてできる限りコストを抑えて取得するといった観点から今回の判断に至ったということです。
吉田
今の市長の御答弁については後で改めて確認したいことがあるのですが、まず副市長の御答弁についてです。
県からの説明でまだはっきりしないところがありますが、メディアの報道では建設工事に時間を要すると受け止められる内容が見られましたが、今回2年遅れる理由については、工事の遅れというよりは、基本構想をよりよいものにするために時間を要しているとの説明であったということでよろしいですか。
副市長
1つは工事の点もあろうかと思いますが、全体的にしっかり検討を進めていて、その中でいろいろなことが見えてきたということで、工事に限ってということではないのではないかと考えております。
吉田
今回の基本合意は3者による締結でした。その合意には含まれていない東北大学病院にも、一部がんセンターの機能の移転ということで協力をいただくという構図になっていると思うのですが、基本構想をこれから策定していくに当たって、2年の延期については一体どの部分の協議に時間を要しているのか。診療科をどうするかなど、まだまだ基本合意から見えない詳細な部分がたくさんあって、これから少しずつ明らかになっていくと思いますが、特にどの部分に時間を要しているのか説明がもしあったら内容をお知らせください。
市長
今おっしゃった内容については、現在、基本構想の中で、具体の病床数や診療科目、従業員数などを含めて、年内に結論を出したいという考えで協議されているものと捉えております。その進捗状況等について、これまでもそうでしたが、今後も議会軽視につながらない範囲でできる限り情報提供していただくよう申し上げていきたいと思っております。
吉田
市長に確認ですが、年内とは年内に基本構想が示される計画で進んでいるということでしょうか。だとすると、2年遅れるとは、基本構想ができた後、それを具現化していくために予定よりも2年時間がかかるということでしょうか。
市長
年内を目指して基本構想の策定を急いでおられると認識しております。
吉田
それから、土地の取得についてです。先ほど市長から御答弁があったように、確かに現在市の土地の値段が上昇傾向にあると。さきの補正予算の審議でもそのような御答弁、御説明があり、やはり早く手に入れたほうが積み上がってしまう差額の分の支出が必要なくなるので、お気持ちはよく分かります。一方で、企画部長の答弁の中では、固定資産と流動資産の間でやりくりされるため、実質的に市の資産を減らすことにはならないとありまして、土地を買って、その後、新しく病院ができて、その病院が古くなって移転する50年、60年先には資産価値がもっと上がっているかもしれないので、そこは焦る必要はないのではないかと思います。
そのほかに相手方の話もあるということですが、今回、場所については4か所から選定されて、当該土地についてほかと比較できる材料を私たちは持ち合わせていませんので、本当は別な場所のほうがいいのではないかと根拠を持って言うことはできません。しかし、少なくとも病院の立地が可能な土地が市内に4か所あるならば、それらも想定に入れておいても、2年延期されるのであれば大きな支障にはならないのではないか、むしろ災い転じてということもあると思います。そして、民間での売買によってさらに経済が活性化すると。公が関与するよりも、民間における経済活動によってもっと人が集まる施設が建つかもしれませんので、そこはやはり自由経済の原則に従ってもいいのではないか、無理して慌てて購入する理由には当たらないのではないかと思うのですが、その点の御見解はいかがでしょうか。
市長
今回の基本合意に至ったその前提となるものは、本市の植松入生の当該土地を前提として病院を立地するということで、病院側も、経営、商圏やマーケット、交通など様々なことについてコンサルタントも交えて試算を行った結果で基本合意に至ったと思っておりますので、単純にこの場所から別の場所にしたらどうかという問題ではありません。あの場所を前提として、しかも本市から無償貸与することを前提として様々な試算がなされて基本合意に至ったと思っておりますし、逆に、違う場所でもいいとなれば、本市ではなくてもいいという話になりますので、基本合意の前まで話を戻すことはあり得ないですし、市としてはあってはならないと思っております。
吉田
民間がもし先に買ってしまえば、基本合意の中身をそれこそ変更するしかなくなりますので、そこは経済の自由競争の原理に基づくことも一つの選択肢ではないかと思うのです。もちろんそうするとさらなる遅れもあり得るので、できればそうしたくはありませんが、現在の場所で計画を進めていくためには、県に対してより一層の情報の公開が求められると思います。ということで次に移ります。
県に対する本市の姿勢についてです。
統合される新病院の具体的な機能については、基本合意書に記載された内容以上のものはまだ分からないままです。県立がんセンターの機能の何が残るのかについても同様です。このように中身が分からないものを19億9,000万円という市民の税金によって購入することは非常にリスクが高い。中身の分からない福袋を買うのではないので、どのような病院になるのかより明確に示された上でなければ、そのような税金の執行は後々住民に大きな負担を残してしまうのではないかという意味で私は恐ろしさを感じております。
あるいは、今おっしゃったように、病院の中身に関して市が何か言える立場ではないことはもちろんですが、土地を提供する以上、原資となるのは市民の税金ですから、やはりある一定の県に対して物を言う立場、申し立てる立場は認められるのではないかと個人的には思います。受け身でひたすら従順な態度を取るのではなく、市からも積極的に情報を求め、そして、もし情報提供の要望が認められない場合は、こちらもその強みを生かして駆け引きすることも必要ではないか、そうやってよりよい病院を引き出していくことも税金を使う以上は必要ではないかと思います。
そこで、小項目2 整備地を無償貸与する自治体として、宮城県に対し、基本構想の協議状況を含む情報の逐次提供を強く求めるべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
情報については、これまでも提供をお願いしてきたところではありますが、県が主導する事業であり、議会軽視とならぬよう、最初に県議会に報告することが原則と捉えているところです。
一方、そのことと、立地する本市としてはできるだけ早い段階で情報をいただきたいということがありますので、その2つが両立できる範囲で情報をいただきたいということは引き続き県に申し入れていきたいと考えております。
吉田
もちろん議会軽視にならないことは非常に大事です。しかし、先に議会に説明しなければいけないのは全てのことに当たるわけではなく、地方自治法や条例等で定められる議決事件については当然議会が先だと思いますが、病院の構想について立地自治体への説明が後回しになるのは、逆に当該地域、本市を軽視していることにならないかと私は思います。もちろん県議会も大事ですが、実際にお金を出すのは県議会議員ではなく、本市の市民からの税金ですから、本市を軽視しないでほしいということは知事に対して市長からもっと強く訴えてもいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
市長
そもそも新病院の立地については、3病院の統合、そして市外、富谷市への移転というところから始まっております。ただでさえ救急については病床の空白地帯と呼べる状況であった中で、700床以上の病床がなくなってしまい、さらに状況が悪化してしまうということで危機感を覚えて、本市のいわゆる主体的な判断として、土地の提供と公共交通の充実をお約束して誘致をしたという経緯がまずあります。
また、今回の土地の取得についても、先ほど申し上げた、法的拘束力がある基本合意に至ったこと、それから土地を確実に取得しておく必要があると考えること、またできる限りコストを抑えて取得したいということから、本市が主体的に判断をして取得するということです。
病院の再編そのものは県が主体となって進める事業です。ただ、先ほど申し上げた基本構想の中身等については本市に直接関わる部分ですので、そういった情報についてはできるだけ早く提供いただけるようにこれからも働きかけをしていきたいと考えております。
吉田
情報提供していただくのは非常に大事なことです。決まってからではもう動かせません。それも県議会で説明したらもう動かせなくなることは恐らく間違いないのではないかと思うのです。だからこそ、県議会も大事ですが、立地する自治体としては、まず県知事に対して物を言えるのは市長しかいないわけですから、市長が言ってくれないと。県立精神医療センターに関しては、患者の団体などが一生懸命働きかけて今回大きく動こうとしていますが、やはり新病院の本市への立地については市長から県知事というルートしかないわけです。やろうと思えば意見書などもありますが、何といっても一番は市長だと思います。
同時に、構想をこれから進めていくに当たって、議会としても、もちろん本市に病院が来てくれるのは非常にありがたいことですから、それに対して反対するものではありませんが、やはり市民の税金からお金が出ていく、これはよりレベルの高い説明が当然必要ではないかと思います。
今回、このように開院の延期が県議会で明らかになりましたが、仮に市長に早く情報が来ていたとしても、なかなかこの場で言えないということもあるかもしれませんし、非常に苦しい立場であることは理解したいと思うのですが、本市の未来に非常に大きく影響する事業ですから、職員の方々からもたくさん知恵を集めて、そしてこの事業が確実に市民のプラスになる病院の設置へとつながるよう強く願います。この点について市長の御見解をお伺いしたいと思います。
市長
今回の新病院については、周産期医療や断らない二次救急、災害拠点病院など、感染症対応も含めて様々な機能を有するいわゆる総合病院の立地という非常に大きな市民の安心・安全につながる話ですので、事業が確実に、できるだけ早期に進むように、市として準備や必要な協力を行っていきたいと思っております。また、立地自治体の考え方として、必要なことについてはできるだけ情報を共有していただけるようにということについても、県に対して機会を捉えてこれからも申し上げていきたいと思っております。
吉田
私の感想ですが、村井知事は県知事のキャリアも長くなり、とてもしたたかな性格で交渉も非常に上手ではないかと思います。ただ、時々強引に進め過ぎてうまくいかなかったりすることもありますが、はっきり言ってしまいますが、県としては県立がんセンターを廃止したいのです。統合される病院がなければそれができないわけですから、そこはある意味県の弱みかもしれない。一緒によりよい医療にしていくために、そうした点も本市として駆け引きの材料にして県と渡り合って、一方で情報を県からしっかり収集しながら進めることが一番望ましいのではないか。最後にうまくいけばいいわけです。ただ、本市がここで19億9,000万円を出して用地を買ってしまうと、今度何か別の不都合が起きたときに、もう何も口を出せなくなってしまう。これが一番怖いことで、県知事のしたたかな性格からいうと、これはあながち私の勝手な悪い予感ではなく、あっても驚かないぐらいの想定はできるのではないかと思うのです。
ですから、基本構想の中身が見えてくるタイミングをしっかり見計らってでなければ、土地の購入に至るのは大変リスクが高いと考えます。かといって、あまり遅らせて計画がますますずれ込んでもよくないので、微妙なところだと思いますが、公表される情報だけではなく、どうしても市長の段階で止めなければいけない表に出せない情報もあります。見えないところで県知事とお互いに意思疎通を図りながら、言うべきことを市民の代表として言っていただいて、そして、この計画がどの住民にとっても今まで以上に医療にアクセスできる環境につながることを切に願っておりますので、ぜひそうした方向へ進めていただきたいと思います。
以上で私の緊急質問を終わります。