吉田良が所属する会派「名和会」で九州地方3市を視察しました。
初日の8月6日、6:20に名取駅に集合し、仙台空港に向かいました。
福岡空港へ向かう飛行機は7:35のフライトでしたが、急病人が出て飛行機を降りるとになり、荷物を降ろしたり重量を再計算するなどして離陸が30分ほど遅れてしまいました。
それでも定刻より10分程度の遅れで福岡空港へ到着しました。
地下鉄空港線で博多駅へ向かい、特急リレーかもめ21号で新鳥栖駅まで行き、JR長崎本線に乗り換えて目的地の神崎駅へ到着したのは11:39でした。
ありがたいことに神崎市議会事務局の職員が公用車で迎えにきてくれました。
神崎市役所から最も近い飲食店で昼食をとり、市役所本庁舎まで徒歩で移動しました。
視察が始まる13:30まで少し時間に余裕があるので、庁舎1階を見学しました。

入口には公告などが次々に表示されるデジタルサイネージが置かれており、本日の予定として会派の視察研修も表示されました。

また、地元で生産された農産物や工業製品などが展示されるスペースがあります。
視察の開始時刻が迫ってきたので、会場となる4階の委員会室へと移動しました。
まだ早かったため、議場を見学させていただきました。

庁舎は令和2年度に落成されたばかりの新しい建物で、議場は自然光が入る明るい雰囲気の造りです。
13:30から研修が始まりました。
調査事項は「日の隈公園キッズパークの整備」についてです。
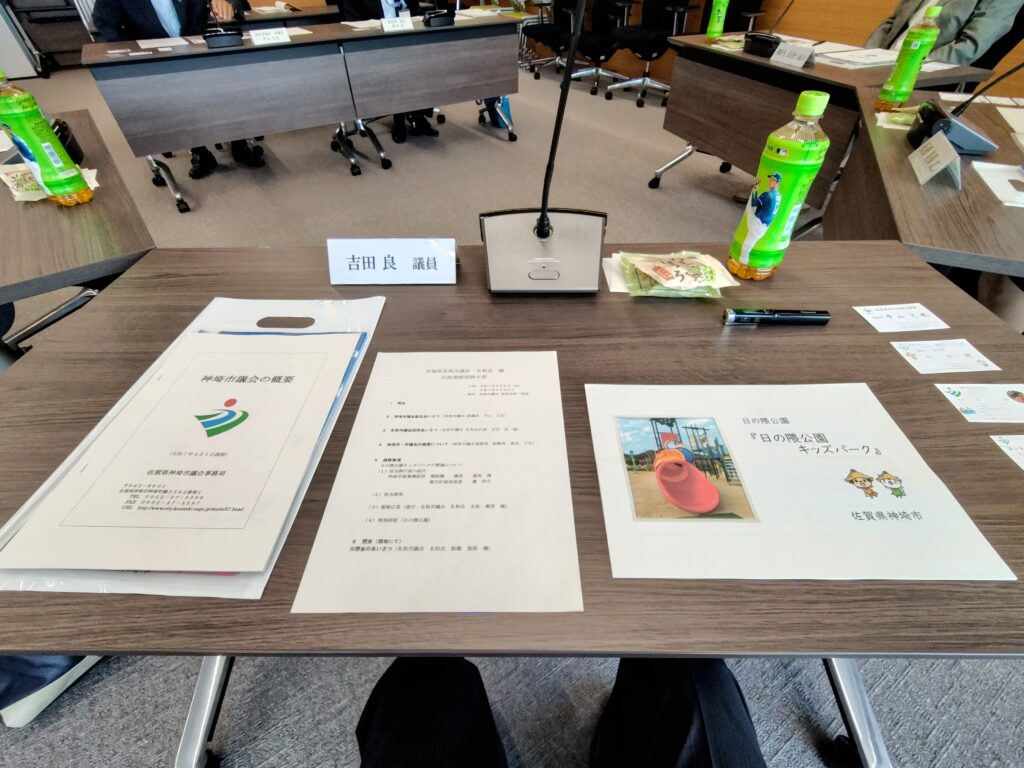
神埼市第二次総合計画に「幸せを感じられる、誰もが安心して暮らせる環境の充実」と、コロナ禍でステイホームを強いられている状況において、三密を避けた公園環境において、心身ともにリフレッシュできる場所が求められていたことから、安全に楽しんでいただける公園環境整備を目的として日の隈公園の再整備が行われました。
公園内に、大人向けの健康遊具、複合遊具、「九州初」と思われるインクルーシブ遊具を導入することで、年齢、性別、文化、個性を気にせずに誰もが安心して利用することができる公園になること、また子供たちが様々な利用者と遊びを通して関わることで、人との接し方、思考力、想像力など様々なことを学ぶことができる公園になることを目的としているとのことです。
公園の名称は「日の隈公園」で、公園全体の面積は39,000㎡あり、うち整備面積はおよそ1,831㎡です。
また事業費は総額で6,700万円で、うち地方創生臨時交付金が6,000万円とのことです。
なお、施工期間は令和3年10月29日から令和4年3月31日まででした。
公園エリアは、①健康遊具エリア、②インクルーシブ遊具エリア、③大型複合遊具エリアの3つのエリアに分かれます。
遊具類の点検は、年1回の法定点検が行われ、点検を含む公園全体の年間の維持管理費は280万円であるとのことです。
市民の利用状況として、キッズパーク整備後、利用者数の増加から駐車場が満車になることが多くなり、利用者への聞き取りによると好意的な意見が多いそうです。
整備の効果として、市内外を問わず多くの個人や、近隣の保育園等の方に来場いただき、大変喜ばれているそうです。
今後の課題として、情報発信の必要性、遊具のメンテナンスなど維持管理の重要性、利便性の向上などがあるとのことです。
市役所での座学が終わり、現地を案内していただけることになりました。
駐車場に停めた車を降りると、モニュメントが見えました。

吉野ケ里遺跡の時代、日の隈山に置かれていた狼煙をイメージしたものであるということです。

駐車場に最も近いエリアが、③大型複合遊具エリアです。
ツリーハウスをイメージした外観となっており、チューブスライダー、吊橋わたり、ろくぼく、フクロウパネル、リングわたり、ワイドスライダー、スパイダークライム、ロープクライム、アクティブパネル、パイプアクセス、スロープブリッジ、ダブルスライダー、イノシシパネル、きのこクライム、ブリッジ、タイヤステップ、梯子、スパイラルスライダーなどの遊具で構成されます。
死角をなくした見守りやすさ、大人も歩ける幅広いデッキ、ゴムチップマットの装備、ゴム舗装で衝撃を吸収など、安全に対する様々な配慮がされています。
少し先に進むと、②インクルーシブ遊具エリアがあります。

人口内耳を着用している子供たちも安心して滑れるスライダー、車いすでも通ることができるADA規準のスロープ、遊具に登らなくても遊びやすいパネルプレイ、日光アレルギーや光線過敏症などを想定し、日光が当たらないためのシェードなど、ビックフォレストには様々な配慮がされています。

ブランコにセーフティタイプの座面を備えることで、姿勢の維持が難しい子供たちでもブランコ遊びを楽しむことができます。

体幹のコントロールが苦手な子供でも遊べるよう、回転遊具は座部に腰をかけたり、インクルーシブシートが埋め込まれたりされています。
また、2種類の高さのスタンドによる砂場で、車いすに乗ったまま砂場遊びを楽しむことができます。
これらインクルーシブ遊具により、子供の成長を助ける「ゆらゆら」「高低差」「ぐるぐる」「加速度で楽しむ」「ふれあい」の5つの遊びを体験できます。
さらに先へと進むと、③の健康遊具エリアがあります。

こちらは主に高齢者向けに、ぶらさがり、バランスシーソー、ストレッチベンチの3つの遊具が置かれています。
日の隈山登山道の入口にも近く、これから登山をする方の準備運動にも利用されます。
3つのエリアを現地視察し、視察研修は終了となりました。
公用車で神崎駅まで送っていただく途中、電車の時刻まで余裕があったため、行程にはない市の施設1か所を見せていただきました。
王仁博士顕彰公園です。

王仁博士は応神天皇の時代、日本に漢字と論語を伝えた百済人として知られます。

施設内には、王仁博士が伝えたとされる漢字の一文字一文字を著名人がタイルに揮毫し、それらを集めた「鍾繇千字文」が置かれています。
中には「・」と書かれたタイルもあり、どういう理由か尋ねたところ、縁起が悪いなどの理由で揮毫を依頼できないのだそうです。
裏手にある鰐神社(王仁神社)を参拝し、神埼駅まで送っていただきました。
15:55発の長崎本線に乗り、佐賀駅で特急みどり39号に乗り換え、さらに武雄温泉駅で西九州新幹線のかもめ41号に乗り換えました。
宿泊地である長崎駅には17:22に到着しました。
2日目は6:40にホテルからタクシーに乗り、長崎港へ向かいました。
7:40発のジェットフォイルで福江港へ向かう予定でしたが、時化のため休航となってしまいました。
幸いフェリーは通常運行するということで、券売所で乗船券を変更してもらい、8:05発のフェリーへ乗り込みました。
ジェットフォイル休航の影響で船内は混み合い、さらに波が高く揺れがひどいため、船酔い状態になってしまいました。
11:15に福江港に到着し、五島に上陸しました。
海上は時化ていましたが、五島市内は時折小雨がぱらつく程度の穏やかな天気で、船酔いも解消しました。
福江港から徒歩数分の飲食店で昼食をとり、時間調整のため五島観光歴史資料館を見学しました。

五島市の歴史と文化を知ることができる20分強の映像を視聴しました。
五島ばらもん凧をめぐる、男の子を主人公としたドラマは、昭和の香りが残るノスタルジックな内容でした。
五島観光歴史資料館は福江城(石田城)跡に建てられており、堀には蓮の花が満開に咲き誇っていました。

そのまま徒歩で五島市役所へ向かいました。

五島市役所は観光歴史資料館から徒歩10分ほどの場所にあります。
雨がぱらついていたのでアーケードが設置された道を選んで歩いていると、新しい庁舎が見えてきました。
令和2年に竣工したばかりの建物です。
調査事項「モバイルクリニック」について、13:30から研修が始まりました。
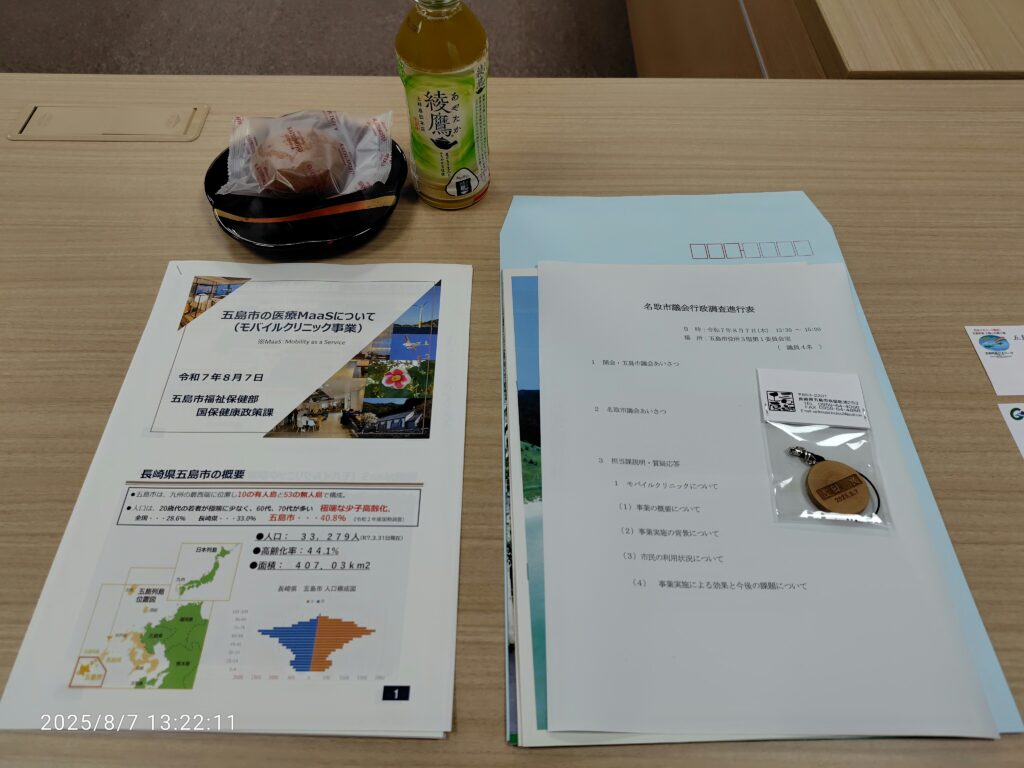
五島市は10の有人島と53の無人島で構成され、極端な少子高齢化に直面しています。
市域の面積は名取市の約4倍の407.03㎡ある一方、人口は半分以下の33,279人です(令和7年度末時点)。
市内の医療機関は31ありますが、うち14が市の中心部に集中しているため、令和5年1月からモバイルカーの運行を開始し、モバイルクリニック事業を始めました。
高齢化率が60~70%の二次離島もある中、路線バスの減便や運転免許の返納などで移動手段を失った高齢者が増加し、定期受診が困難になることで高齢者の病気が重症化するなどの課題があります。
過疎地域を支える医療体制が必要とされることから、医療MaaSによるモバイルクリニックが始められたのでした。
モバイルクリニックを使ったオンライン診療は原則1か月に1回で、3か月に1回は対面診療としています。
モバイルカーには看護師が乗り込み、自宅近くまで配車して患者が乗車することで、オンラインで担当の医師や管理栄養士からの診察を受けられます。
また処方箋を調剤薬局に送付することで、患者の自宅へ薬を配送する仕組みとなっています。
モバイルクリニックを導入したことにより、医師の拘束時間は57分から15分へ、診察患者数は1人から5人へと効率化が実現したということです。
医師からは「画像が鮮明。心雑音等もはっきり聞こえる」「看護師がいることで患者への説明がスムーズで、非常に心強く安心できる」という声が寄せられているそうです。
なお、受信した方の97%が満足と回答しています。
今後は国の特区制度を利用し、ドローンを活用した薬のオンデマンド配送を計画しているということです。
課題として、年間約2,000万円のランニングコストがかかっていることが挙げられますが、住み慣れた地域で安心して暮らせることを目指して今後も取り組んでいくとのことです。
名取市でもゆるやかな少子高齢化が進み、地域によっては医療難民が生じることが予想されます。
高齢者の健康寿命をのばすための対策の一つとして、医師など医療関係者の負担軽減の対策を検討していくことが必要だと思います。
15:00に研修を終え、議場を見学させていただきました。

庁舎を出て、商店街でおみやげなどを買いながら福江港へ向けて徒歩で移動しました。
幸い波が穏やかになったためにジェットフォイルは運航を再開しました。

16:30に福江港を出発し、18:15に長崎港に到着しました。
3日目、視察最終日は宿泊施設で朝食をとり、9:30に長崎市役所へタクシーで向かいました。
長崎市役所は令和5年1月に供用開始されたばかりです。

研修会場は庁舎5階です。
10:00から「長崎まちぶらプロジェクト」について、研修が始まりました。
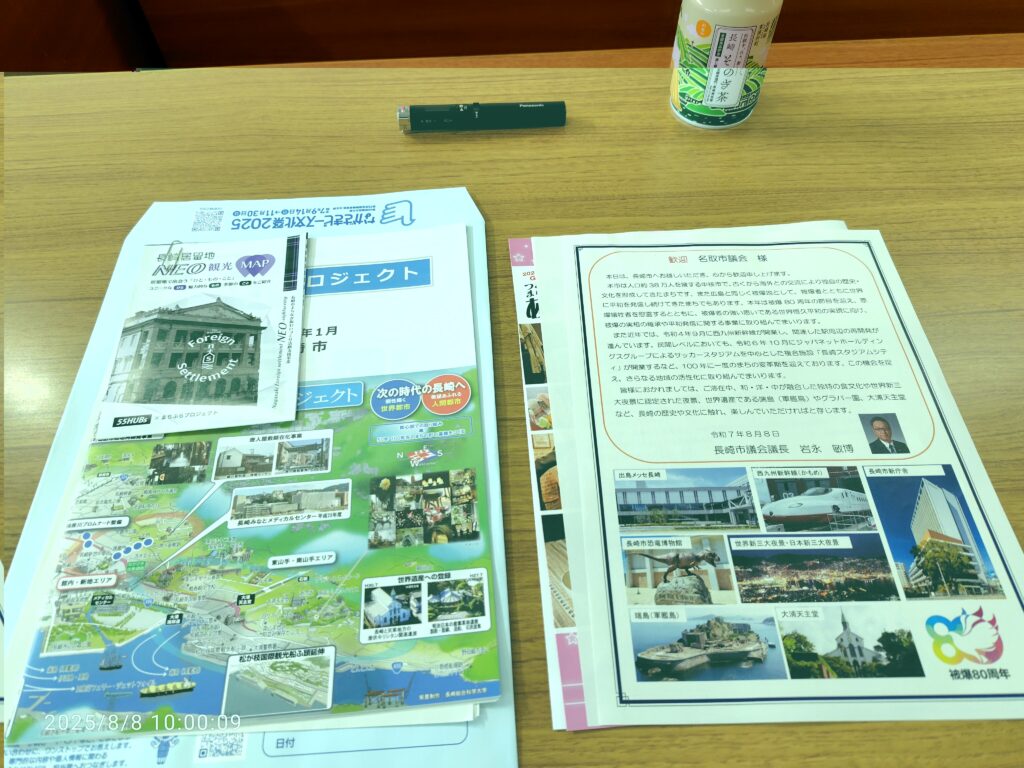
長崎原爆犠牲者追悼平和祈念式典の直前の日程であるにもかかわらず視察を受け入れていただいたことに感謝申し上げます。
研修の内容については、学んだ内容の量と質が圧倒的に大きいことから、後日名取市議会ホームページで公開される報告書をご覧いただきたいと思います。
座学の終了後、庁舎19階の展望フロアから、説明のあったエリアの位置関係などについて、実際に見てご説明いただきました。


実際の位置関係を確認し、改めて綿密に練られた計画に感心しました。
予定の終了時刻である11:30を過ぎて、長崎市での視察研修は終わりました。
路面電車で長崎駅まで移動し、駅ビルで昼食をとりました。
13:14長崎駅発のかもめ84号に乗り、武雄温泉駅で特急リレーかもめ84号に乗り換え、14:53に博多駅に到着しました。
西九州新幹線が博多駅へ直接接続される日は来るのでしょうか。
地下鉄空港線で福岡空港へ移動し、16:30発の飛行機に乗り、ほぼ定刻で仙台空港に到着しました。
視察行程のほとんどは乗り物での移動時間でしたが、3市それぞれで新たな学びがありました。
名取市の市民福祉向上のために、持ち帰った知見を生かして、会派として提言していきたいと思います。














